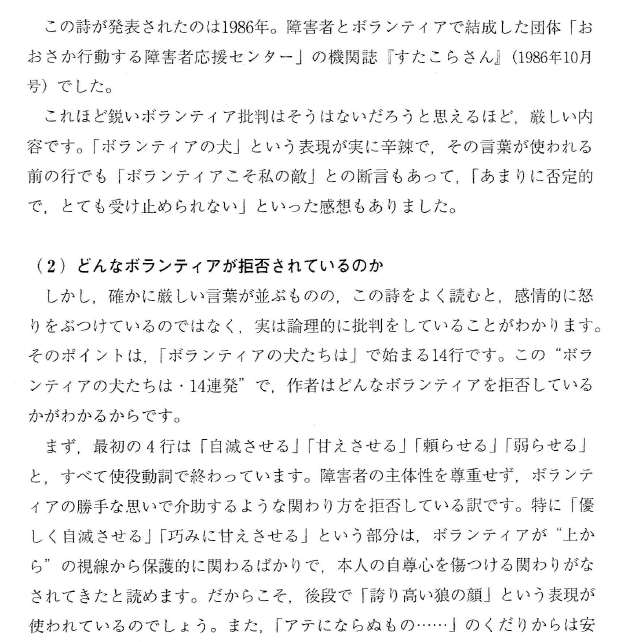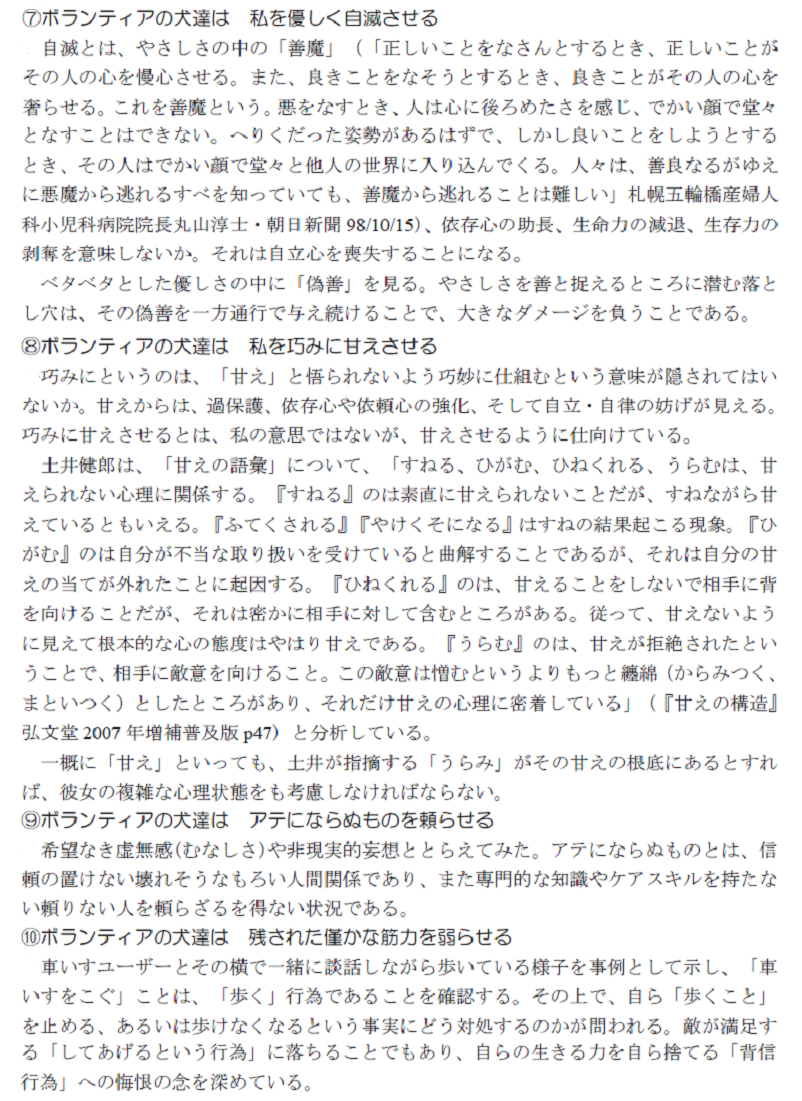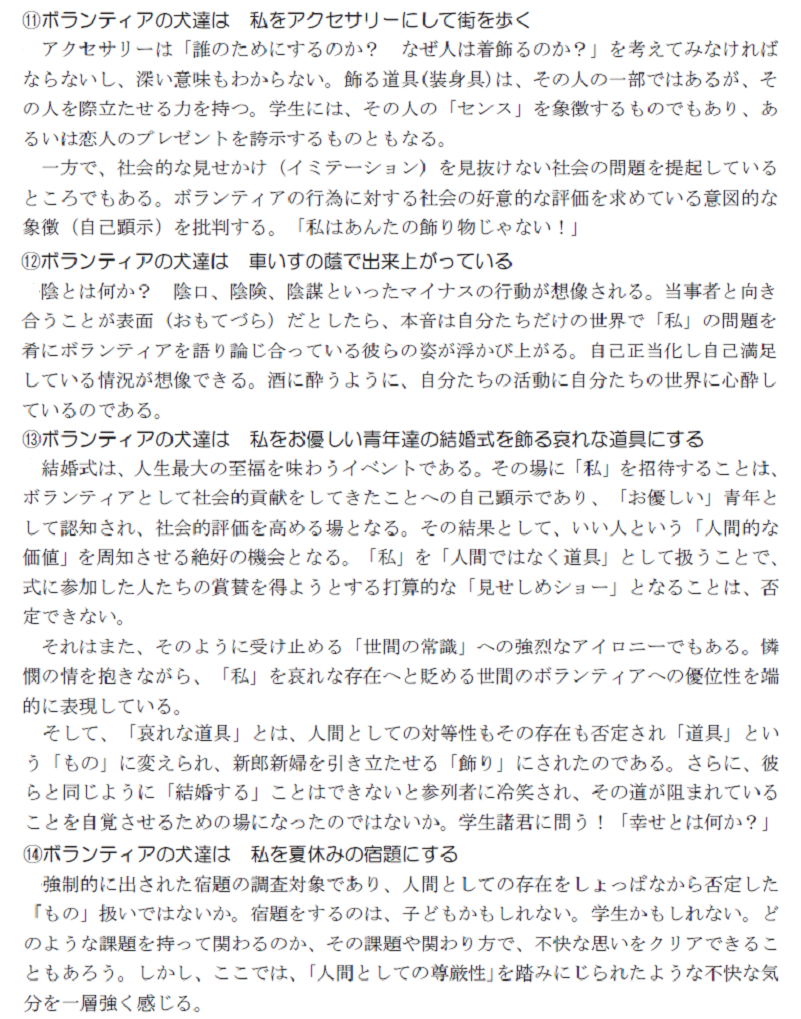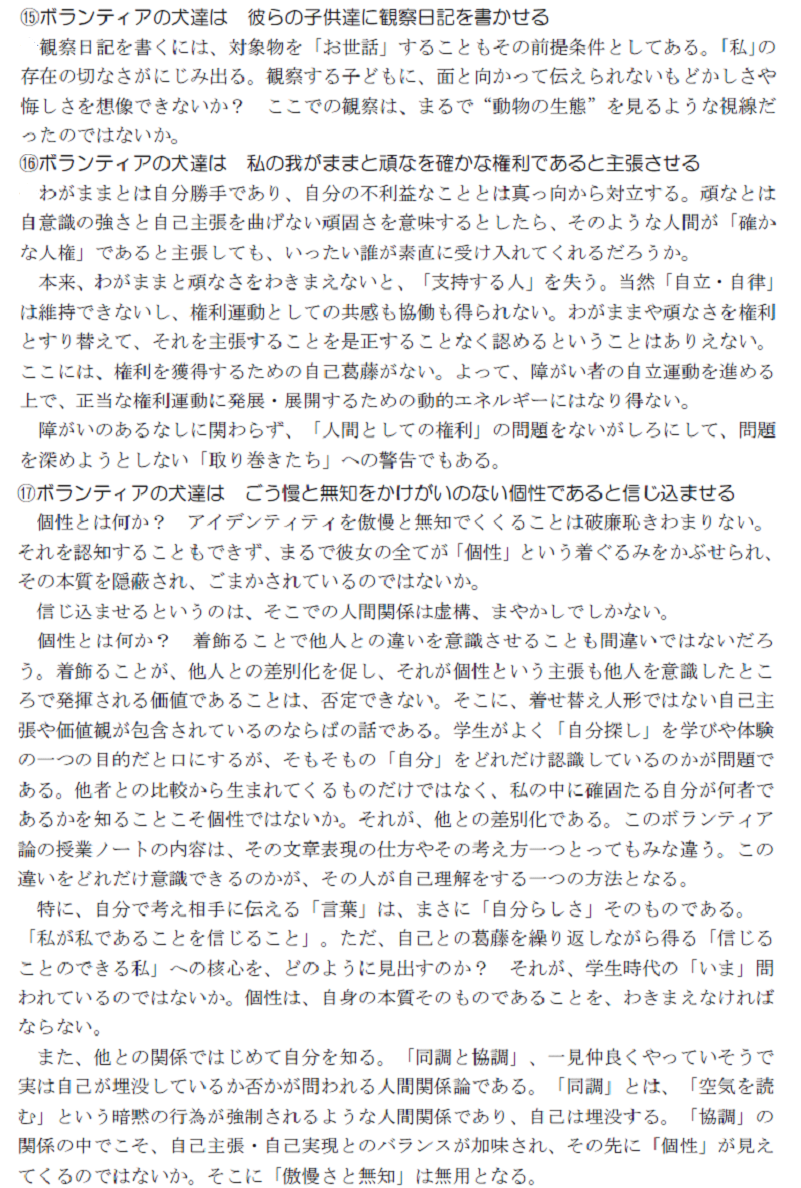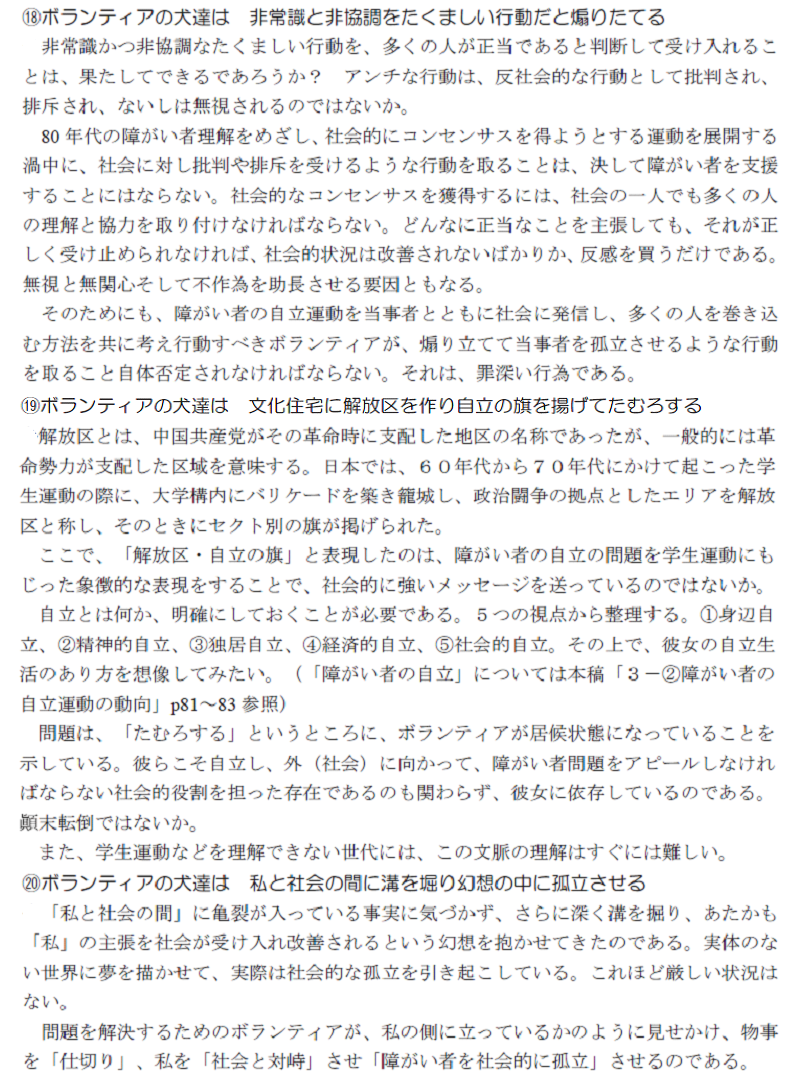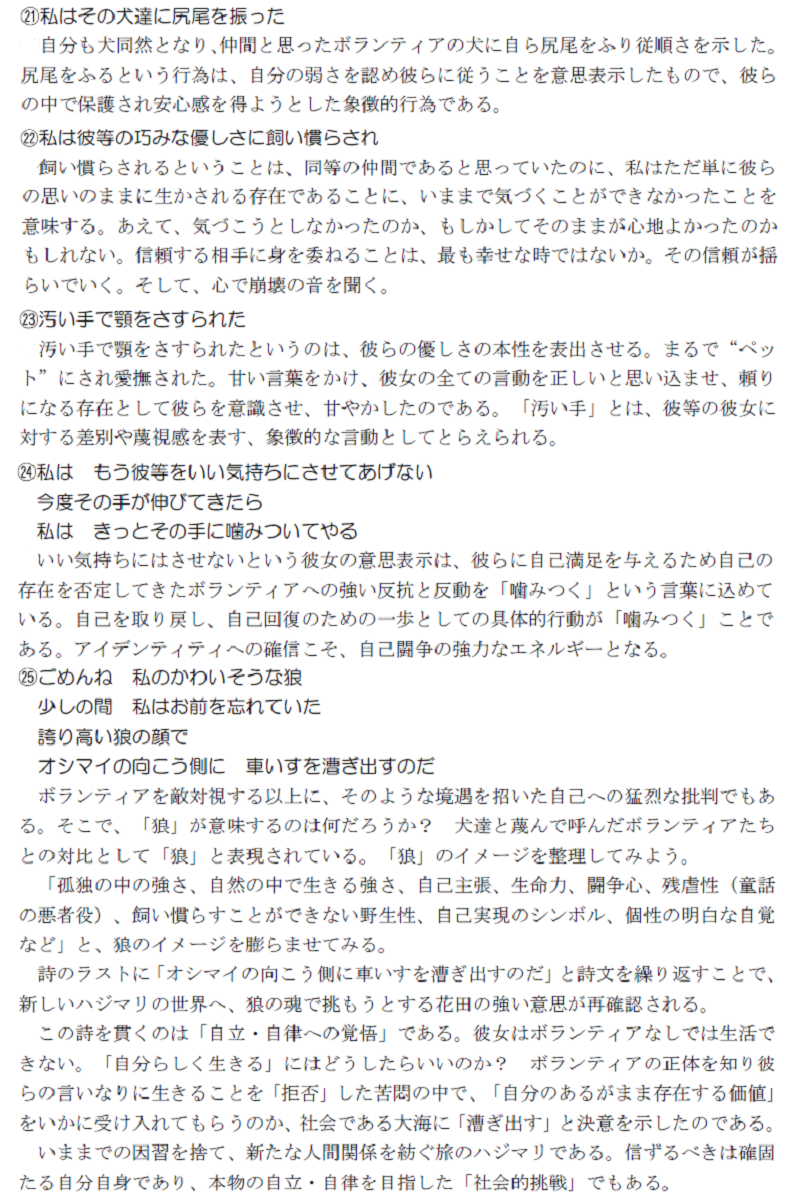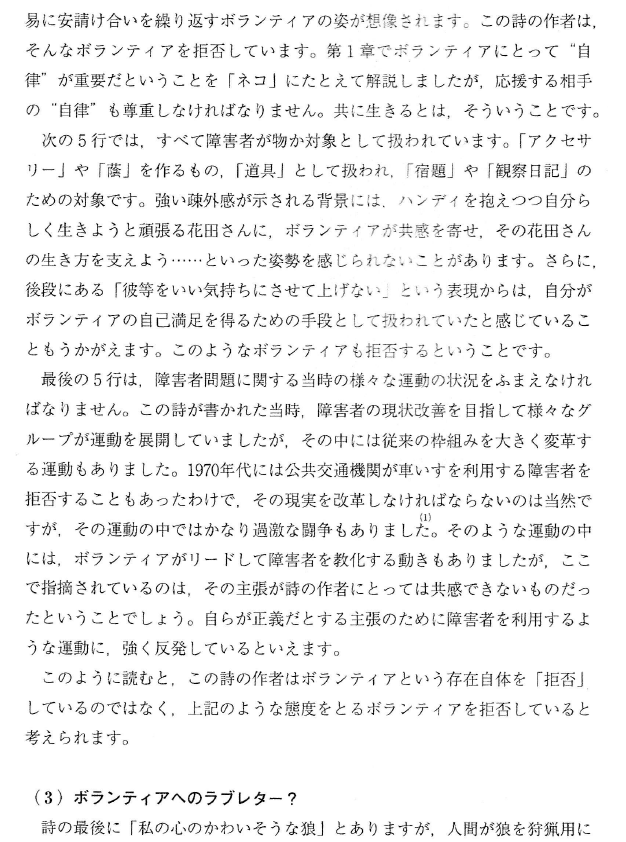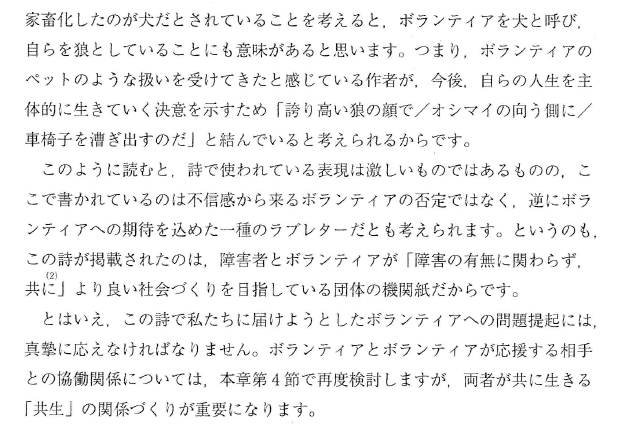〇筆者(阪野)が住むS市では、2018年7月に豪雨による浸水被害が発生した。社協は早速に災害ボランティアセンターを立ち上げ、ボランティアの募集と被災者(被災地区)への支援活動を始めた。2週間で、「予想をはるかに超える」およそ6,500人のボランティアが活動に参加した。そんななか、活動現場での次のような“やりとり”や“思い”が耳朶(じだ)に触れる。「遠くからわざわざ来ているので、弁当くらい出したらどうだ」(すべて手弁当でお願いしています)。「あちこちの被災地での活動経験について、その話を聞いてくれ」(いまは床下の泥だし作業が最優先です)。「持参した道具が壊れたので弁償しろ」(自己責任・自己負担でお願いしたいのですが)。「今日のボランティアの数とその内訳について情報提供しろ」(スコップをもってきて作業に加わってもらいたいものだ)。災害ボランティア活動現場のひとつの実相である。
〇8月、行方不明の子どもを発見したことを契機に、「スーパーボランティア」(尾畑春夫)が世間の耳目を集めた。尾畑は「無償」のボランティア精神を貫いている。9月からは、2020年東京オリンピック・パラリンピックの大会運営を支える「大会ボランティア」(8万人)と「都市ボランティア」(3万人)の募集が始まった。「上から目線」で、「安易にボランティア=労働力を集めようとしている」という批判の声も聞こえる。筆者が購読する地元新聞の「社説」は、最近のボランティア事情について次のように説いている(9月27日)。「これまでのような奉仕活動にとどまらず、災害からの復興援助、イベントの運営補助などボランティアの活動範囲は広がりを見せており、活躍の機会が増えるとともに期待も増しつつある。ボランティアは、かつてのような裏方ではなく、主役を支える名脇役へ役割を変えつつある」。
〇日本社会では、民主主義が後退し、右傾化・全体主義化が進んでいる。また、「災害多発時代」や「無縁社会」「共生社会」「管理社会」などについて云々される。ボランティアに関しては、「動員」「派遣」「活用」「タダ働き」「有償」「感動体験」「やりがい詐欺」等々の言葉が躍っている。『戦争ボランティア』(高部正樹著、並木書店、1995年2月)や『ブラックボランティア』(本間龍著、株式会社KADOKAWA、2018年7月)というタイトルの本も出ている。そういうなかでいま、ボランティアや市民活動の新たな展開を図るために、「ボランティア」や「市民活動」についての本質的な議論が求められている。
〇その時宜にかなった本が刊行された。早瀬昇著『「参加の力」が創る共生社会―市民の共感・主体性をどう醸成するか―』(ミネルヴァ書房、2018年6月)がそれである。筆者は早瀬の「ボランティア」言説にすべて首肯するものではないが、この本では、市民による「自治と共生の社会」を構築するための基礎的知識や、市民参加(市民活動)の視点や考え方についてわかりやすく解説されている。そのなかで早瀬は、花田えくぼの詩「ボランティア拒否宣言」(おおさか・行動する障害者応援センターの機関誌『すたこらさん』1986年10月号)を紹介している。筆者がこの詩に最初に出会ったのは、岡本栄一「ボランティア活動の分水嶺」大阪ボランティア協会監修/小田兼三・松原一郎編『変革期の福祉とボランティア』(ミネルヴァ書房、1987年7月、251~252ページ)においてである。鋭く厳しい表現(「犬」)や言葉によるボランティア批判は、衝撃的であった。およそ30年前のことである。以下にその詩を記しておく(ルビは筆者)。
ボランティア拒否宣言/花田えくぼ
それを言ったらオシマイと言う前に
一体私に何が始まっていたと言うの
何時だってオシマイの向うにしかハジマリは無い
その向う側に私は車椅子を漕(こ)ぎ出すのだ
ボランティアこそ私の敵
私はボランティアの犬達を拒否する
ボランティアの犬達は 私を優しく自滅させる
ボランティアの犬達は 私を巧(たく)みに甘えさせる
ボランティアの犬達は アテにならぬものを頼らせる
ボランティアの犬達は 残された僅(わず)かな筋力を弱らせる
ボランティアの犬達は 私をアクセサリーにして街を歩く
ボランティアの犬達は 車椅子の蔭で出来上っている
ボランティアの犬達は 私をお優しい青年達の結婚式を飾る哀(あわ)れな道具にする
ボランティアの犬達は 私を夏休みの宿題にする
ボランティアの犬達は 彼等の子供達に観察日記を書かせる
ボランティアの犬達は 私の我がままと頑(かたく)なさを確かな権利であると主張させる
ボランティアの犬達は ごう慢と無知をかけがえのない個性であると信じ込ませる
ボランティアの犬達は 非常識と非協調をたくましい行動だと煽(あお)りたてる
ボランティアの犬達は 文化住宅に解放区を作り自立の旗を掲げてたむろする
ボランティアの犬達は 私と社会の間に溝を掘り幻想の中に孤立させる
私はその犬達に尻尾を振った
私は彼らの巧みな優しさに飼い慣らされ
汚い手で顎(あご)をさすられた
私は もう彼等をいい気持ちにさせて上げない
今度その手が伸びてきたら
私は きっとその手に噛(か)みついてやる
ごめんね
私の心のかわいそうな狼
少しの間 私はお前を忘れていた
誇り高い狼の顔で
オシマイの向こう側に
車椅子を漕ぎ出すのだ
〇この詩については、複数のヒトがその内容を読み解いている。ここでは、筆者の手もとにある論考のうちから、岡本栄一、筒井のり子、仁平典宏、鳥居一頼、そして早瀬昇の解釈(総括)を紹介しておくことにする。
岡本栄一
この詩はいろいろな解釈を私たちに迫る。「障害者の自立」の問題、「一人よがりの独善的なボランティア活動」、あるいは「活動の手段化」等々。
いずれにしても、ボランティア活動を先験的、アプリオリ(自明的:筆者)に「社会的善」であるとみなしている人達には大変ショッキングな詩であろう。車イスを押したなら、どんな押し方でも障害者は「ありがとう」というべきものだ、と考えている人達は、きっと「傲慢」な障害者の詩だと思うだろう。私はこんな詩を書かせたこれまでのボランティア活動の「あり方」を悲しいと思う。ここには健常者と障害者とを二つに分けたままで成立するボランティア活動の姿がある。そこではお互いが成長せず、また変わりもしない、といったことがある。ともあれ、私はボランティアの側だけで「自己回転」する活動が、どんなに罪が大きいか、この詩を読んでハッとさせられたことは事実である。(岡本栄一『前掲書』252~253ページ)
筒井のり子
「かわいそう」という言葉自体は、もちろん差別語ではないが、その使われ方、使う人の気持ちいかんで、きわめて差別的な響きをもってくる。優越感の裏返しの同情は、その受け手にとって屈辱である。
次の詩はある障害者団体の機関誌に投稿されたものだが、“優しさ”から出発した援助が、結果的に相手の自立を損なってしまうことを、鋭く告発している。
「何もできない人」「かわいそうな人」「常に誰かの助けが必要な人」という決めつけは、ボランティア活動の本質をゆがめる。
たしかに現在、彼らは援助を必要としている。しかし、「援助を受ける側」という固定的なとらえ方をすべきではない。(筒井のり子『ボランティア・コーディネーター―その理論と実際―』大阪ボランティア協会、1990年3月、52、54ページ)
仁平典宏
1970年代以降、「ボランティア」は障害者から、抑圧者として尖鋭な批判を突きつけられることになった。この中で〈犬〉の記号も反復される。次の詩は、障害者運動――親や周囲の「善意」によって障害者の可能性が縮減されていく事態に対する根底的な異議申し立て――の系譜に位置づくものである。「ボランティアの犬達は」と何度もくり返されるこの詩は、それが〈贈与〉の対価として何を奪うかを、雄弁に告発している。
無償の、愛情に満ちた〈贈与〉行為こそが、「障害者」を障害者役割にとどめ、その可能性を根こそぎ奪っていく――言うまでもなくこれは、障害者運動が提起した最も重要な論点の一つであった。同時にボランティア言説の歴史も、決してナイーブなものではなく、絶えずこのような否定的なまなざしとの緊張のもとにあった。その中で、ボランティア言説は展開し鍛えられ、それなりに首肯性をもつ答えも生み出されてきた。(仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉―〈贈与のパラドックス〉の知識社会学―』名古屋大学出版会、2011年2月、32、34ページ)
鳥居一頼
この詩は、たしかに衝撃が強いメッセージである。デフォルメ(歪曲:筆者)された表現であるが、そこに潜むボランティアの問題の核心を鋭く突いていることは、間違いない。このくらい痛烈に批判しない限り、お互いに覚醒はできないかもしれない。彼女のボランティア批判は、そこに安住した自身への憤りと悔悟(かいご:筆者)でもあり、その批判の矢は“自らに”放ったものでもあるといえよう。
その批判を裏読みすると、そこにボランティアの本質が見えてくる。逆説的に見るとボランティアとの信頼関係をどのように構築するのか、その関わり方を見事に表現しているのである。
もう一つ、ケアのあり方について問題を提起している。(中略)
この「ボランティア拒否宣言」は、まさに地域包括ケアが本格化する「ケア時代」に生きる多くの高齢者や闘病者の意思表明や自己選択・決定にかかる問題をも包含していることに気づかされる。花田の「頑固に意志を通す」生き方を考え真摯に受け止めなければ、障がい者や高齢者、そして闘病者にも、自己喪失の道を彷徨する悲劇となるであろう。(鳥居一頼「詩『ボランティア拒否宣言』に学ぶ“自立”と歪んだボランティア観~覚醒と受容そして意識変革を促す教材としての価値を探る~」『人間生活学研究』第22号、藤女子大学人間生活学部人間生活学科、2015年3月、103ページ)
早瀬昇
詩で使われている表現は激しいものではあるものの、ここで書かれているのは不信感から来るボランティアの拒否ではなく、逆にボランティアへの期待を込めた一種のラブレターだとも考えられます。というのも、この詩が掲載されたのは、障害者とボランティアが「障害の有無に関わらず、共に」より良い社会づくりを目指している団体の機関紙だからです。
とはいえ、この詩で私たちに届けようとしたボランティアへの問題提起には、真摯に応えなければなりません。ボランティアとボランティアが応援する相手との協働関係については、(中略)両者が共に生きる「共生」の関係づくりが重要になります。(早瀬昇『前掲書』93ページ)
〇いずれにしろ、この詩が発表された1980年代半ば以降は、1981年の「国際障害者年」、1983年から1992年までの「国連・障害者の10年」の取り組みや「障害者生活圏拡大運動」とともに、「障害者自立生活運動」が展開された時期である。「優生思想」「自立と自己決定」「障害文化」などについて激しく議論された。「青い芝の会」(横塚晃一、横田弘)や「札幌いちご会」(小山内美智子、沢口京子)などによる社会的差別・偏見に対する糾弾闘争が思い出される。それにしても、横塚晃一の『母よ! 殺すな』(すずさわ書店、1975年2月)はあまりにもインパクトの強い本であった。
〇そしていま、この詩の主語(「主役」)を「政府や行政」、「ボランティアの犬達」を「ボランティアの私達」に置き換えると、例えば、「国や行政は、ボランティアの私達をアテにならないものに頼らせ、巧みに甘えさせ、優しく自滅させる」などとなろうか。そこにあるのは政府・行政主導の「地域共生社会」「地方創生」「一億総活躍社会」の実現や、ボランティアによる国民保護活動の展開(「国民保護法」)にむけた「篭絡」(ろうらく。巧みにいいくるめて人を自由に操ること)である。気がつくと、恣意的に解釈されている「積極的平和」のために「戦争ボランティア」が動員・派遣される、ということが一番怖い。
〇筆者は、ボランティア活動については大まかには、「人権意識や正義感覚に基づく主体的・自律的な住民による・住民のための市民活動」である。「主体的」とは「他のものによって導かれるのでなく、自己の純粋な立場において行うさま」であり、「自律的」とは「外部からの支配や制御から脱して、自身の立てた規範に従って行動すること」をいう(『広辞苑』第7版)。すなわち、市民活動は、「言われなくてもするけれど、言われてもしない」(早瀬『前掲書』231ページ)活動である。ボランティア活動は、原則的に「無償」であり、「有償ボランティア」という言葉は矛盾した使用法である。「市民活動」は、(無償の)ボランティア活動と非営利・有償活動の両者を包含するものである。そして、ボランティア活動は、「ボランティアのいない地域・社会」づくりをめさず活動であり、そこにあるのは主体的権利と社会的責務としての市民活動である、と考えている。
〇なお、ボランティアの基本的な「原則」や「性格」、「最も重要な要件」や「一番の核にある要素」は「自発性」であるといわれる。『広辞苑』によると、「自発性」は「他からの教示や影響によるのでなく、内部の原因・力によって思考・行為がなされること」、「自発的」は「自分から進んでするさま」である。類似用語の「自主性」は「他者に依存せず、自分で行動することができる性質」、「自主的」は「他からの干渉などを受けないで、自分で決定して事を行うさま」をいう。
〇ここで、高島巌の「ボランティアは活動ではない。生活なのだ」「ボランティアは人間にだけあたえられた楽しき権利なのである」、木谷宜弘の「ボランティアは自由である。だから楽しい」「共生から共働、そして共創の社会づくりへ」という言葉が思い起こされる。
補遺
① 鳥居一頼の「『ボランティア拒否宣言』(花田えくぼ)を読み解く」について、鳥居の「解釈」の部分(「学生の意見をまとめた」部分もある)を紹介しておくことにする(「前掲論文」95~103ページ)。
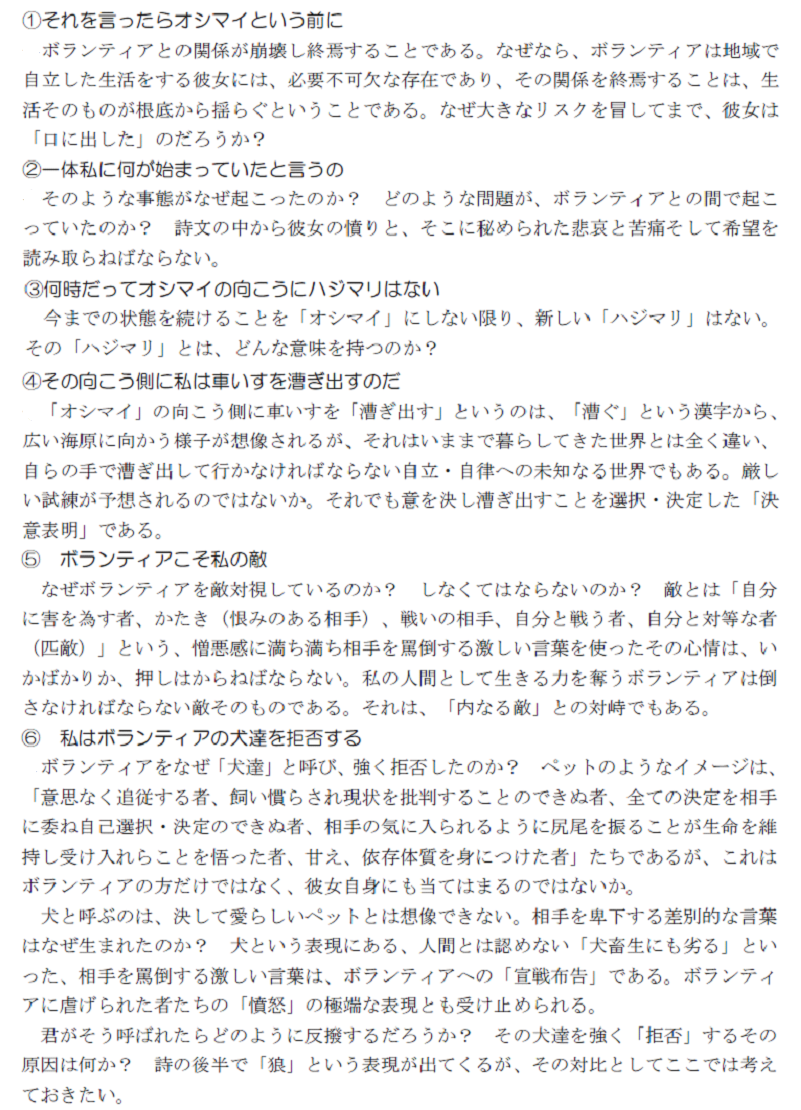
② 早瀬昇の「『ボランティア拒否宣言』から学ぶ」について、上記の本文で引用した部分と一部重複するが、紹介しておくことにする(『前掲書』91~93ページ)。