「老爺心お節介情報」第54号
地域福祉研究者の皆様
社会福祉協議会関係者の皆様
皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。
「老爺心お節介情報」第54号を送ります。
2024年3月8日 大橋 謙策
〇皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。
〇能登半島地震の被害状況の報道を見るたびに胸が痛みます。災害の状況、規模によっても違いがありますが、人口減少、超高齢化地域における大きな地殻変動、液状化現象を伴う災害支援、災害復旧の難しさを改めて突き付けられている能登半島地震災害です。
Ⅰ 人口減少時代における地域福祉研究を考える
〇私は、去る2月20日に、長野市、長野市社会福祉協議会、長野県社会福祉協議会共催の「人口減少時代の地域づくり」をテーマにした「地域福祉ネットワーク会議」に招聘され、行ってきました。
〇その際の講演のレジュメの抜粋は以下の通りです。
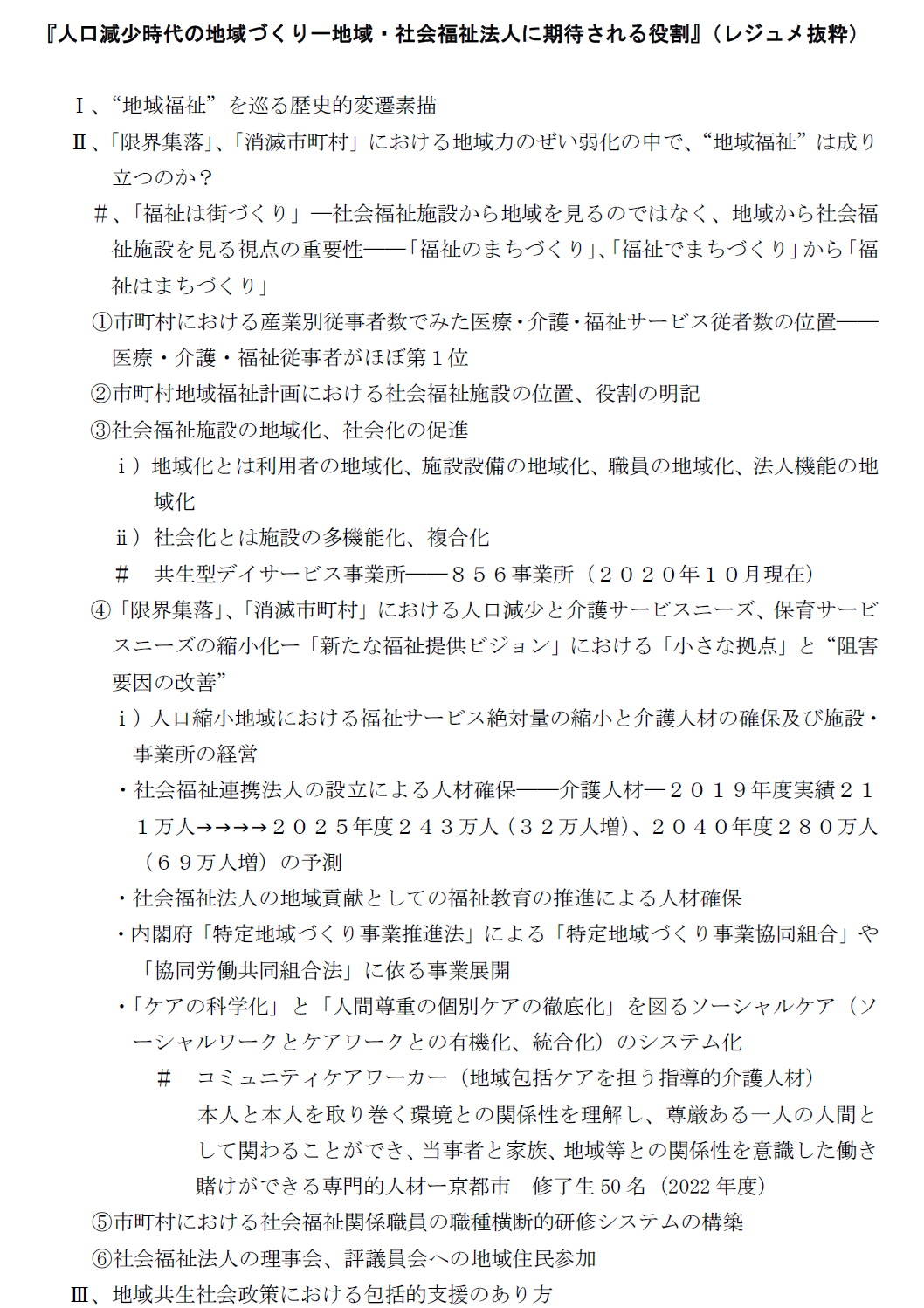
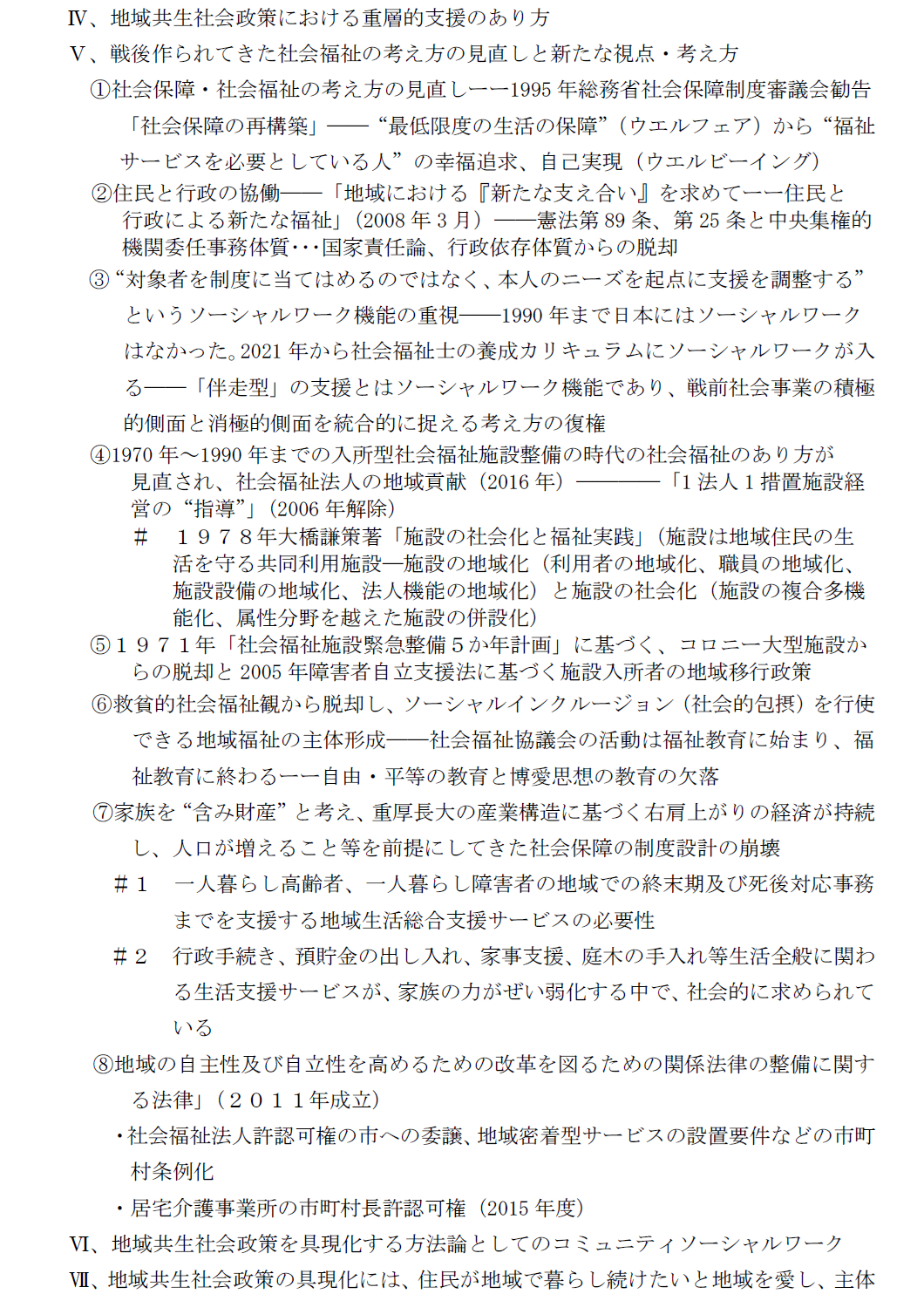
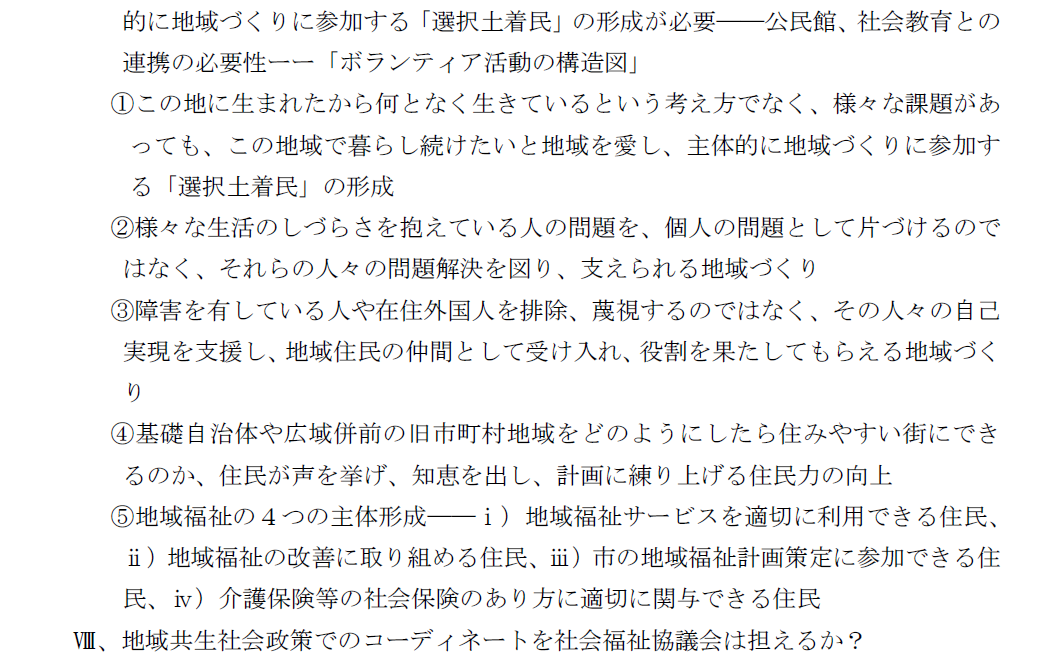
〇筆者がこの講演を通して言いたかったことは、日本の社会福祉政策において、「地域福祉」がメインストリームになり、地域共生社会政策が展開されるときに、「地域福祉」の“地域”が“危急存亡”に陥っている。このような状況の中で、地域福祉実践、地域福祉研究はどうあるべきかを問い直すという視点で話をしたいと思った。
〇その講演で訴えたかった点は3点である。
〇第1点目は、地域の住民力、地域の力を向上させる支援を行う「触媒機能を持つ職員論」が重要であるという点である。
〇地域の住民が自然発生的に力を付け、地域の自治力を高めることは単純ではない。地域づくりに関わる公民館や社会教育の職員、あるいは社会福祉協議会の職員などが触媒機能を発揮して、働き掛ける重要性を述べた。今日のように、人口減少、高齢化が急速に進んでいる状況の中で、住民の負担感を減らし、一緒に地域づくりをしていく「職員論」が重要になる。
〇1984年に書いた論文「公民館職員の原点を問う」(『月刊社会教育』1984年6月号所収)はまさにそのことを述べたのである。地域福祉論の泰斗と言われる岡村重夫には「職員論」がない。
〇その「職員論」はどのような触媒機能を持つかである。一般的に触媒とはⅰ)触媒する物質を入れることによって、従来の物質が活性化する、ⅱ)触媒する物質を入れることによって、従来の物質が安定する、ⅲ)触媒する物質を入れることによって、新しい物質に変質すると言われている。
〇人口減少、高齢化における地域づくりには、この触媒機能を発揮できる職員の機能、能力と配置が重要であることを述べた。
〇この住民のエネルギーを向上させる触媒機能としては、公民館、社会教育による住民の主体形成と相通ずるものがある。
〇長野県は、戦後公民館活動と社会教育が非常に活発な地域であった。それは、ある意味戦前の「上田自由大学」に代表される住民の活発な自己教育活動の歴史ともつながる伝統、実践といえる(『大正デモクラシーと地域民衆の自己教育運動』(山野晴雄著、自費出版、申し込み先 東京都三鷹市牟礼5-6-10、山野晴雄、TEL0422-42-6558、定価3000円)参照)。
〇静岡県掛川市の市長であった榛村純一は1970年代に、地域づくりには住民一人一人が「選択的土着民」になれるよう生涯学習を推進することが肝要であると実践された地域づくりの思想と共通する。
〇筆者は、1980年代から地域福祉実践には「地域福祉の主体形成」が重要であり、それを促進する福祉教育が重要であると述べてきた。その福祉教育は、福祉サービスを受給している人と切り結びを通して獲得される意識、人間観であると述べてきた。
〇この考え方は、地域共生社会政策の基点になった1995年9月の報告書「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現――新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンーー」の中で、“対象者を制度に当てはめるのではなく、本人のニーズを起点に支援を調整することである。制度ではなく、地域というフィールド上に展開する営みであり、個人のニーズに合わせて地域を変えていくという「地域づくり」に他ならない。個別の取組の積み重ねが大きな潮流になって地域を変えていくという考え方と同じである。
〇第2点目は、現在進められている重層的支援体制整備事業に見られるように、地域共生社会政策は「住民と行政の協働」が重要になるが、その住民と行政の車の両輪の車軸を誰が担うのかという問題である。
〇これは第1点目と関わる問題であるが、この車軸の機能を担う機関を筆者は市町村社会福祉協議会ではないかと考えている。
〇重層的支援体制整備事業の要は、第2層レベルの専門多機関、専門職多職種連携による困難事例への総合的支援活動と第3層レベルの小学校区における近隣住民、民生児童委員、自治会、地区社会福祉協議会の方々によるインフォーマルな支援、見守り、声掛けとが有機化することが重要で、だからこそ福祉サービスを必要としている人を地域から排除することなく、受け入れる地域づくりにつながるわけで、この第2層と第3層の機能をコーディネートできるのは、地域を基盤としている社会福祉協議会ではないかと考えている。
〇第3点目は、今までややもすると市町村や地域との関りが豊かにあったとは言えない社会福祉施設やそれを経営している社会福祉法人であったが、人口減少、超高齢社会、福祉サービス利用者の減少の時代にあっては、全国の約2万の社会福祉法人、全国に10万か所ある社会福祉施設が、地域住民の生活を守る拠点、住民の共同利用施設の機能を持てるようになるかである。
〇筆者は、1978年の日本社会福祉学会の機関誌『社会福祉学』に書いた「施設の社会化と福祉実践」で社会福祉施設は地域住民の拠り所になるための社会福祉施設の社会化と地域化を推進するべきだと述べてきたが、今や、社会福祉施設、社会福祉法人の地域貢献が2016年以降法的に位置づけられ、求められるようになってきている。
〇人口減少、超高齢社会時代において、社会福祉施設は地域住民の生活を守る、かつ地域づくりの拠点となるよう意識改革をしていかなければならない。また、それをしないと社会福祉施設、社会福祉法人自体の存続も難しくなってきている。これからは、社会福祉法人の連携化や合併問題を含めて、地域の維持・存続に社会福祉施設はどういう役割を担えるかを考える時代であると述べた。
〇社会福祉施設、社会福祉法人の地域貢献活動を考える際に、大阪府社協「しあわせネットワーク事業」、香川県社会福祉協議会「おもいやりネットワーク事業」を参考にして欲しい。
(2024年3月8日記)
(備考)
「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(「阪野貢 市民福祉教育研究所」で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。
この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。




