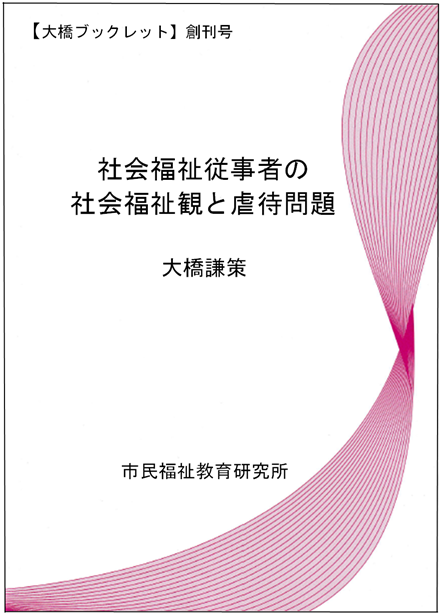
はじめに
〇日本社会事業大学同窓会北海道支部より、「北海道において保育所、高齢者福祉施設、障害者福祉施設等で虐待問題が起きている。ついては、同窓会支部の機関紙である『アガペ』において、『社会福祉と人権』というテーマで特集を組み、取り組みたい」ので、私にも「社会福祉と人権―社会福祉の今後―」と題して寄稿してほしい、との要請があった。
とても大事な課題であり、私なりに思うところを書かせて頂きたいと思った。しかしながら、大学教員退任後、社会福祉に関わる事象、事案、研究を網羅的に、かつ継続的にウオッチングしていないので、十分ご期待に沿えるかわからないが、本稿を書かせていただいている。そういう意味では、学術論文というより、エッセイ風な論考と捉えて頂きたい。
〇社会福祉実践現場などにおける虐待の問題は、法的には、①身体的虐待、②性的虐待、 ③経済的虐待、④ネグレクト、⑤心理的虐待に分類される。その虐待は現象的には職員一人一人の資質の問題として捉えられる。しかしながら、その背景にある社会構造としては、ケアの考え方、日本人の人権感覚、社会福祉従事者の人権感覚、社会福祉法人の経営・運営の在り方等、その背景と構造の分析は単純ではない。
〇筆者としては、それらの背景も含めて、以下のように論稿を構成したいと思っている。1回の寄稿では終わらないので、その旨ご了承頂きたい。
① 日本国民の文化と福祉文化――私が50年間闘ってきた「社会福祉通説」の問題
② 憲法第25条に基づくケア観と憲法第13条に基づくケア観の相違
③ 福祉サービスを必要としている人の「社会生活モデル」に基づくアセスメントと医学モデルに基づくアセスメント
④ 福祉サービスを必要としている人のナラティブ(物語)を基底とした「求めと必要と合意」に基づく支援方針の作成(ICFの視点と福祉機器の利活用)
⑤ 入所型施設の運営・経営理念、方針と提供されるサービス
⑥ 勤務先の“劣悪な労働環境”とキャリアパス等の職員資質向上の取り組み
Ⅰ 日本国民の文化と福祉文化――筆者が50年間闘ってきた「社会福祉通説」の問題
〇筆者は、高校時代に島木健作の『生活の探求』を読んで、日本社会事業大学への進学を決めた。高校の教師や親類縁者からは、なぜ日本社会事業大学のようなところを選択するのかと“奇人・変人”扱いであった。
〇そのような環境の下での日本社会事業大学での学習であったが、授業内容は必ずしも筆者が望んでいたこととは違っていた。その大きな要因が、アメリカからの“直輸入”的社会福祉方法論を“金科玉条”のごとく位置づけることと、「福祉六法」に基づくサービスの提供であった。
〇その当時の社会福祉方法論は、アメリカで1930年代に確立した考え方であり、WASP(ホワイト、アングロサクソン、プロテスタント)の文化を基底として成立してきた考え方、方法論であり、精神医学、心理学にかなり影響された考え方であった。
〇そのような中、筆者は日本の文化、風土に即した社会福祉の考え方、方法論があるのではないかと考え呻吟する。
〇当時、一番ケ瀬康子先生が「福祉文化」という用語を使用していくつか論文を書いており、自分の研究の方向もその方向ではないかと考え、“文化論”について研究したが、奥が深く、かつ掴まえ所がなく、その研究を中断した。
註1:一番ケ瀬康子先生は、1989年に「福祉文化学会」を創立している。
註2:筆者は、2005年に「わが国におけるソーシャルワークの理論化を求めて」(『ソーシャルワーク研究』31巻第1号)を書き、中根千枝の「タテ社会論」、
阿部謹也の「世間体文化論」等を援用して、日本のソーシャルワークの理論化を論証した。
〇この日本文化は根が深く、簡単に因果関係を証明できないので、研究は中断したが、常に頭にこびりついて離れない。
〇日本では、子育てする際の文化として、“禁止と命令”によって、枠にはめようとする文化がある。常に、集団的価値観が尊重され、同調志向が強く、“逸脱”したものを排除、蔑視する傾向が強い。これは、学校教育における画一的教育方法であるベル・ランカスター方式の影響でもある。是非、『6か国転校生―ナージャの発見』(集英社)を読んでほしい。
〇そのような中、筆者は、戦前の社会事業理論における精神性と物質性に関する研究を行い、そのあり方を問うことが日本の社会福祉実践、研究を変えることになると確信していく。
〇結果として、筆者は地域福祉と社会教育の連携、学際研究に関心を寄せるようになり、その実践のフィールドを公民館や社会福祉協議会に求めていくことになる。
〇ところで、筆者は自分自身としては社会福祉の研究者であり、それを岡村重夫が提唱した “社会福祉の新しい考え方としての地域福祉“(岡村重夫説・1970年)という考え方に依拠して展開しようと考えていたが、そのような筆者の研究姿勢は、多くの社会福祉学研究者には理解されず、日本社会事業大学の教員からも、”大橋謙策は社会福祉研究のプロパーではない“という批判、評価を受けた。また、日本社会事業大学の清瀬移転に際し、大学院創設の文部省への申請書を審査した某有名大学の某教授も”あなたの論文は社会福祉の論文ではない“という評価を下した。
〇そのような中、筆者は、従来の社会福祉通説とは異なる新しい社会福祉実践、社会福祉学研究を求めて、社会福祉学界への抵抗の地域福祉研究50年を送ることになる。
〇その既存の社会福祉通説への批判と新たな社会福祉実践、社会福祉研究の論題は以下の通りであった。
ⅰ) 大河内一男の労働経済学(「我が国における社会事業の現状と将来について」昭和13年論文)を基盤とする社会福祉研究への批判
ⅱ) 社会権的生存権保障としての憲法第25条の「ウエルフェアー」から、憲法第13条に基づく幸福追求、自己実現支援の「ウエルビーイング」への転換(1973年論文)――障害者の学習・文化・スポーツの保障、「快・不快」を基底としたケア観、
ⅲ) 属性分野で細分化された福祉サービス、福祉行政の再編成と地域自立生活支援
ⅳ) 社会福祉施設中心主義と施設の社会化、地域化論(「施設の社会化と福祉実践」(日本社会福祉学会紀要『社会福祉学』第19号所収、1978年論文)
ⅴ)社会福祉の国家責任論オンリーではなく、社会保険の国家責任論と対人福祉サービスの市町村責任論との分離
ⅵ) 社会福祉の行政責任論ではなく、経済的給付、システムづくりにおける行政責任と地域自立生活支援における住民との協働による対人援助――べヴァリッジの第3レポートの位置、1601年「Statute Charitable Uses」研究、憲法第89条の桎梏からの脱却、2008年「地域における「新たな支えあい」を求めて」(厚労省研究会報告書―2016年地域共生社会政策の前史になる報告書)
ⅶ)社会事業における精神性と物質性――戦後の社会福祉は物質的対応で解決できると考えてきたことの誤謬――「救済の精神は精神の救済」(小河滋次郎、戦前方面委員の理念)
〇筆者は、1984年に書いた論文で、社会福祉研究者、社会教育研究者は“出されてきた政策には敏感であるが、政策を出さざるを得ない背景には鈍感である“と述べ、住民のニーズに即応したサービスの提供、地域づくりの必要性を説いている。
〇それは、対人援助として社会福祉を提供する際に、かつ地域づくりを展開する際における住民参加と住民のニーズを基点に考えるということである。
〇従来の社会福祉行政には、住民参加の規定もなければ、住民の相談、ニーズを「社会福祉六法体制」の基準に該当するかどうかで判定することや、措置行政の枠組みの中でサービスを提供すれば良いという考え方に対する批判でもあった。
〇そのような中、1970年代に、なぜ市町村社会福祉行政は計画行政でないのか、また、地方自治体の社会福祉施設整備計画がないのかを問い、市町村ごとに社会福祉計画を立案する必要性を説いた。
〇1980年には「ボランティア活動の構造」という図を示し、一般的隣近所の紐帯を強める地域づくり活動、地域にいる福祉サービス利用者を支える地域づくり、それらを社会福祉計画策定により解決していくという「自立と連帯に基づく社会・地域づくりのボランティア活動の構造」という図を作成した。
〇児童福祉法には市町村に児童福祉審議会を設置することが「できる」規定があり、かつ、民生委員法第24条に規定される意見具申権という規定、考え方を基に、当時、いくつかの自治体において、住民参加を保証する「社会福祉審議会」、「地域福祉審議会」の設置を求める提案をしている。
註3:東京都狛江市は、住民参加を規定した「市民福祉委員会」を条例で1994年に設置している。同じ頃、東京都目黒区でも「地域保健福祉審議会」が設置された。筆者の地元の稲城市では1980年代初めに「社会福祉委員会」を設置するが行政による要綱設置であった。東京都豊島区でも要綱設置であった。
〇このような住民参加による、住民のニーズに対応したサービスの提供という考え方が、多くの社会福祉行政、社会福祉従事者に共有されていれば、少なくとも“虐待”が起きる社会的背景、構造は違ってくる。
〇しかしながら、現実は、そのような住民のニーズに応えて、住民参加で社会福祉施設が作られたわけでなく、かつ、その社会福祉施設は措置行政によって、長らくサービス利用者を“収容保護する”という構造のなかで、“閉ざされた空間”に置いて福祉サービスが提供されるという構造の中で“虐待”事案として発生する。
〇社会福祉施設が、1978年に書いた論文のように、地域に開かれ、地域住民の共同利用施設として位置づけられ、運営、経営されているならば、“虐待”という事案は少しは防げるのではないだろうか。
Ⅱ 憲法第13条及び「快・不快」を基底としたケア観と「社会福祉観の貧困」、「人間観の貧困」「貧困観の貧困」「生活観の貧困」
〇筆者は、日本社会事業大学の講義で、よく「社会福祉観の貧困」「人間観の貧困」「貧困観の貧困」「生活観の貧困」という用語を使用して講義をしてきた。
〇それは、社会福祉を志している学生が陥り易い社会福祉観を問い直す作業過程として、その用語を使ってきた。
〇筆者は、社会福祉を憲法第25条からだけ説き起こすのではなく、それとともに憲法第13条からも説き起こすべきだと1960年代末から言ってきたし、論文にも書いてきた。
〇憲法第25条の社会権的生存権の規定は、人類が歴史的に獲得してきた権利であり、国民のセーフティネット機能として重要であることは重々分かったうえで、それだけだと提供される社会福祉サービスがちまちました“最低限度の生活保障”の域を出ないことになるし、その反動として、社会福祉サービスを提供する側のパターナリズムが避けられないと考えてきたからである。
〇それらのことを実感する機会はいくつもあるが、その一つは1970年に女子栄養大学に助手として採用され、勤務し始めて改めて痛感したし、同じく1970年から始めた聖心女子大学の非常勤講師の勤務からも痛感させられた。
〇女子栄養大学では、昼食を大学の食堂で摂るのだけれど、その食堂はキャフェテリア方式で、自分の好み、自分の懐具合、自分が食べたい分量を自分で考えるという“主体性”が常に求められる。
〇当時の社会福祉施設の食事は盛っ切りで、自分(福祉サービス利用者)の主体的選択の余地はなく、かつ食器も割れない食器で供されていた。日常生活における食事の持つ意味、食事に伴う生活文化などを女子栄養大学でいろいろ教わった。
〇当時、島根県出雲市の長浜和光園がバイキング方式の食事を提供し始めていて、社会福祉施設における食事に関わる問題の重要性を随分と学ばせてもらった。食事を通して学ぶ食文化、食事の場における会話、食事を作る生活技術など日常生活における食事の持つ意味は大きい。女子栄養大学では、当時核家族化が進む中での“子どもの孤食”の問題が大きく取り上げられていた。
〇筆者は、当時の女子栄養大学で社会福祉の科目を受講している学生に、夏休みの宿題として、社会福祉施設を訪問し、その施設の食事の実態を分析するレポート課題を出した。そのレポートに書かれた当時の分析と今日とを比較出来たらとても良かったと思うのだけれど、そのレポートは女子栄養大学を退職した際に、廃棄処分してしまったことが残念である。
〇他方、聖心女子大学でも社会福祉の科目を教えていたが、同じように夏休みの宿題として、社会福祉施設を訪問してボランティア活動を行い、学生なりの社会福祉施設の評価を求めるレポートを課した。その際、学生から質問があった。訪ねる社会福祉施設は日本の社会福祉施設でなければ駄目かという質問である。その学生は、夏休みに入ると同時に、父母がいる海外へ行くという。その海外の社会福祉施設の訪問記でもいいのかという質問であった。そのような境遇の学生が数人いた。日本と海外の社会福祉施設との比較が図らずも行うことができた。社会福祉施設を取り巻く福祉文化の違いを期せずして学生同士で論議できたことはおもしろかった。
〇1992年、筆者は日本社会事業大学の長期在外研究が認められ、イギリスに半年間滞在した。それも、筆者はロンドン大学などへの派遣ではなく、自由にさせて頂いた。
〇筆者は、ロンドンのケンジントン&チェルシー区に滞在し、区内にあるホスピスやボランティアセンターなどに出入りさせてもらった。ホスピスでは、余命いくばくもない人々が、私が訪問する度に、私に向かって“エンジョイしているか”と尋ねられる日々であった。そのホスピスでは、余命いくばくもないのに、ドリンキングパーティもあり、かつ犬のボランティアも登録されていて連れてこられたり、浴室にはカラフルな壁画が描かれていたりという福祉文化の違いを様々な形で私に問いかけてきた。
〇筆者は、憲法第13条に基づく社会福祉観を考える場合、生活上の様々な事象に対し「快・不快」を基底として、生活を楽しむ、生活を再創造するというリクリエーションが大切ではないかと考え、1980年代後半に、日本社会事業大学の故垣内芳子先生や日本レクリエーション協会の園田碩哉さん、千葉和夫さん(のちに日本社会事業大学の教員)、淑徳短期大学の木谷宜弘先生(元全社協ボランティア活動振興センター長)等と“社会福祉における文化の問題、レクリエーションの位置”について研究を行った。社会福祉施設の食事、社会福祉施設のインテリア、社会福祉施設職員のユニフォーム、行動規範などについて調査研究を行った。その結果は、1989年4月に『福祉レクリエーションの実践』(ぎょうせい)として上梓された。その『福祉レクリエーションの実践』には、筆者が日本社会事業大学研究紀要第34集に寄稿した「社会福祉思想・法理念にみるレクリエーションの位置」と題する論文が収録されている。
〇その論文では、ⅰ)社会福祉とレクリエーション、ⅱ)レクリエーションの捉え方の視角、ⅲ)西洋の社会福祉思想とレクリエーション及び娯楽、ⅳ)日本における社会福祉思想にみるレクリエーション及び娯楽、ⅴ)社会福祉六法の目的と生活観、ⅵ)施設最低基準にみる生活観、ⅶ)在宅生活自立援助ネットワークの構成要件、ⅷ)在宅福祉サービスの供給方法と施設整備の在り方について論述している。
〇この論文では、権田保之助の社会事業や娯楽の捉え方を踏まえつつ、如何に社会福祉法の目的が狭隘であるかを論述した。と同時に、入所型社会福祉施設のサービスを分解して、地域で住民の必要と求めに応じてサービスパッケージをすれば、社会福祉施設の位置と役割が変わることを指摘している(当時はケアマネジメントという用語は使われてなく、筆者は必要なサービスをパッケージして提供するという意味でサービスパッケージという用語を使用していた)。
〇1996年に総理府の社会保障審議会が社会保障の捉え方を見直し、事実上福祉サービスを必要としている人のその人らしさを支えるサービスに転換させる勧告を出す。憲法第25条に基づく“最低限度の生活保障”への偏りを反省し、事実上憲法第13条を法源とする社会保障、社会福祉への転換が求められた。
〇しかしながら、相も変わらず社会福祉分野では、“上から目線のサービスを提供してあげる”という考え方や姿勢が蔓延っているし、生活を楽しく、明るく、楽しむ自立生活支援にはなっていない。
〇社会福祉分野では、故一番ケ瀬康子先生等が「福祉文化学会」を設立し、社会福祉サービスの考え方や社会福祉における文化性について研究を推進してきたが、その研究枠組みは必ずしも私の先の論文の枠組みとは同じではない。
〇他方、1970年代から播磨靖男さんたちのわたぼうしコンサートを始めとして、社会福祉の枠にとらわれない障害者文化の向上に貢献する実践があるが、それらがどれだけ社会福祉分野に影響を与えて、社会福祉の質を変えたかは定かでない。
〇個々人の福祉サービスを必要としている人の「快・不快」を基にしたケアの提供を考えたならば、従来の入所型社会福祉施設で行ってきたケアが、いかにケアする側の論理、都合で提供されているかが分かるであろう。
〇日本人の文化と社会福祉との関りについては、本連載第1回でも書いたが、社会福祉関係者もケア提供者も、福祉サービスを必要としている人を「枠組み」に当てはめ、その「枠組み」の中の人間は同じだという“錯覚”にも似た“思い入れ”で対応し、「枠組み」の中の人、一人ひとりを丁寧に見て、その人の“思い”や“願い”をきちんとアセスメントしようとしない「文化」を持っている。
〇障害者といっても、障害の状態、障害の種類によっては全然違うし、障害者の中の発達障害者を見ても、その行動様式、“こだわり”は全部違うといってよい。なのに、それらの人々を一括りにして対応しようとするケア観が蔓延っている。
〇人間を見るのに、「枠組み」からのみ見たり、レッテルを貼ってみる人間観を変え、一人ひとり異なる存在であり、その異なる存在を受容し、関係性を豊かに持てるようにしていかないとケアの現場だけで問題を解決できると思うのは誤りだとさえいえる。
〇虐待の背景、深層心理には、日本人が陥っているその人のおかれている属性や枠組みから人間を捉える抜きがたい文化がある。
〇このような日本人が“身に着けている文化”を払しょくし、新しい人間観の基でのケア観を構築していくことが“急げば回れ”の諺ではないが重要である。そのため、小さい時からの、多分化を学び、一人一人のナラティブを尊重する福祉教育の実践の推進が求められている。
Ⅲ 情感的ケア観からアセスメントに基づく科学的ケア観への転換―「求めと必要と合意」に基づく支援
〇日本の医療の発展の要因の一つは、症状、病変の事象から、それがどこに起因するのかを診断する検査技術の発展が大きく貢献してきたと筆者は考えている。かつては、脈を取ったり、へらで舌の状態を観察したり、聴診器で心臓の鼓動や呼吸を確認するといった診断法が、今ではレントゲン、尿検査、血液検査、MRI、CTスキャナーといった検査機器の開発により、症状、病変の診断は特段に向上してきている。それらの検査を担う検査技師の養成、資格まで確立してきている。
〇かつて、巷で言い交された“あのやぶ医者は!”といった言葉は今日では死語になっている。
〇それに比して、社会福祉分野では、長らく中央集権的機関委任事務体制のもとで、サービス利用者が行政により認定され、その人たちが行政の委任を受けた措置施設で生活を送ることを前提に、その人のADL(日常自立生活能力)が低くければ、それを補完する“世話”として三大介護と呼ばれる排せつ介助支援、食事摂取支援、入浴介助支援が展開されてきた。
〇そこでは、措置されたサービスを必要としている人の生活を向上させるために、何をするべきか、何に気を付けるべきかの診断という発想は事実上なかったといっても過言ではない。
〇1971年の「社会福祉施設緊急整備計画」の中では、それら福祉サービスを必要としている人々を施設に“収容保護”し、いわゆる“最低限度の生活を保障すればいい”という考えで貫かれていたといっても過言ではないであろう。
〇1971年以降の「入所型社会福祉施設中心の時代」においては、ある意味、措置された福祉サービスを必要としている人の生活を“丸ごと抱え込んで支援する”という発想のもとに、その利用者の個々の差異には着目せず、同じ生活リズムで、集団的に生活を“させる”というケアを提供する職員側の立場、視点からの対応の仕方で済まされてきた。
〇しかしながら、1990年の社会福祉八法改正“により、在宅福祉サービスが法定化され、かつ地方分権の下で中央集権的機関委任事務体制の改革が求められるようになると、状況は変わる。
〇在宅福祉サービスを利用している人は、一人ひとり生活環境も違うし、行動様式も異なるし、同一空間で集団生活をしているわけではない。それだけに、在宅福祉サービスを利用している人の支援には個々人の生活状況や本人の希望を尊重したサービスの提供が求められるようになる。
〇筆者は、1987年に書いた論文「社会福祉思想・法理念におけるレクリエーションの位置」(日本社会事業大学研究紀要第34集所収、1988年刊)において、入所型施設で提供しているサービスの分節化と構造化の必要性を提起した。それは福祉サービスを必要としている人の状況に応じて分節化させたサービスの中から必要なものを選択し、パッケージ化(当時、ケアマネジメントという用語はなかった)させれば画一的なサービス提供にもならず、かつ在宅福祉サービスの個々人の状況に対応できるということを提起した。
註1: 拙著『地域福祉とは何か――哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク』(中央法規出版、2022年4月刊、P32参照)
〇このことを進めるためには、福祉サービスを必要としている人は何を望んでいるのかその人の希望、願い、思いをきちんと受け止めなければならないし、同時に福祉サービスを必要としている人にケア・支援を行う専門職が、その人にはどういうサービスが必要であるかを診断したうえで支援する必要があることも提起した。
〇筆者の言い方で言えば、福祉サービスを必要としている人の求め、希望と専門職が生活支援上必要と考えることを出し合い、両者の合意で在宅福祉サービスの提供を考えていくという「求めと必要と合意」に基づく支援のあり方である。
〇ところで、福祉サービスを必要としている人々への支援において、よほど気を付けないと無意識のうちに“上から目線”の世話をしてあげるというパターナリズムになりがちになる。
〇福祉サービスを必要としている人はさまざまな心身機能の障害や生活上の機能障害において要介護、要支援の状態に陥っているので、ついつい福祉サービス従事者はその機能障害を改善、補完するために“いいことをしてあげる”という意識になりがちである。それは、一見“善意”に満ちた行為として考えられがちであるが、福祉サービスを必要としている人の意思や主体性を尊重しての“誠意”ある行為といえるのであろうか。
〇また、福祉サービスを必要としている人で家族と同居している場合には、福祉サービスを必要としている人本人の意思よりも、同居している家族が家族自身の“思い”、“願い”を福祉サービス従事者に話され、その家族の希望が優先され、ややもすると福祉サービスを必要としている本人の意向や意思は無視されがちになる。
〇ましてや、福祉サービスを必要としている人は、日常的に同居している家族に普段から迷惑をかけているからという“負い目”もあり、家族に遠慮して、自分の意向、意思を表明しない場合が多々ある。
〇日本の戦後の社会保障・社会福祉制度設計は、家族がおり、家族が“助け合う”ことを当たり前のように前提として設計されてきたために、福祉サービスを必要としている人本人の意思や希望は家族の前では搔き消されてしまいがちであった。
〇イギリスのブラッドショウは1970年代に、住民の抱える生活上のニーズを4つに類型化(①本人から表明されたニーズ、②住民は生活上の不安や不満、生活のしづらさを抱えているが表明されていないニーズ、③住民自身は気が付いていないし、表明もしていないが専門職が気づき、必要だと考えられるニーズ、④社会的にすでにニーズとして把握され、対応策が考えられているニーズ)した。
〇この類型化されたニーズにおいて、日本の社会福祉分野において気を付けなければならないニーズ把握の問題は、②の住民が生活上様々なニーズがあるにも関わらず気が付いていないか、自覚しておらず、表明されていないニーズである。
〇日本の“世間体の文化”、“忖度の文化”、”もの言わぬ文化”に馴染んで生活してきた国民は、自らの意思を表明することや自らの希望や願いを表明することに多くの人が躊躇してしまう。したがって、本人が自分の意見や気持ちを表明しないのだからニーズがないのだろうと解釈するととんでもない間違いを起こすことにもなりかねない。それらのニーズは潜在化しがちで、対応が遅れることになる。
〇一方、専門職が気づき、必要と判断するニーズにおいても、社会生活モデルに基づくアセスメントやナラティブに基づく支援方針の立案が的確に行われていればいいが、上記したようなパターナリズムでのアプローチをしている場合には専門職の判断が必ずしも妥当であると言えない場合が生じてくる。
〇イギリスでは、1990年の法律により、福祉サービスを提供する際には、その援助方針やケアプラン及び日常生活のスケジュール等を事前に本人に提示し、本人の理解を踏まえて提供することが求められるようになったが、2005年の「意思決定能力法」ではよりその考え方を重視するように法定化された。
〇日本の民法の成年後見制度や社会福祉法の日常生活自立支援事業が福祉サービスを必要としている人が自ら意思決定できないことを判定するということを前提にして制度設計されているのと違い、イギリスの「意思決定能力法」は日本と逆の立場を取っている。
〇「意思決定能力法」は①知的障害者、精神障害者、認知症を有する高齢者、高次脳機能障害を負った人々を問わず、すべての人には判断能力があるとする「判断能力存在の推定」原則を出発としており、②この法律は他者の意思決定に関与する人々の権限について定める法律ではなく、意思決定に困難を有する人々の支援のされ方について定める法律であるとしている。その上で、③「意思決定」とは、(イ)自分の置かれた状況を客観的に認識して意思決定を行う必要性を理解し、(ロ)そうした状況に関連する情報を理解、保持、比較、活用して 、(ハ)何をどうしたいか、どうすべきかについて、自分の意思を決めることを意味する。したがって、結果としての「決定」ではなく、「決定するという行為」そのものが着目される。意思決定を他者の支援を借りながら「支援された意思決定」の概念であるとしている。
〇日本だと、“安易に”、あの人は判断能力がないから、脆弱だから“その意思を代行してあげる”ということになりかねない。言語表現能力や他の意思表明方法を十分に駆使できない障害児・者の方でも、自分の気持ちの良い状態には〟“快”の表情を示すし、気持ち悪ければ“不快”の表現ができる。福祉サービス従事者は安易に“意思決定の代行”をするのではなく、常に福祉サービスを必要としている人本人の意思、求めていることを把握することに努める必要がある。
〇その上で、本人が自覚できていない人、食わず嫌いでサービス利用の意向を持てていない人に対し、専門職としてはニーズを科学的に分析・診断・評価し、必要と判断したサービスを説明し、その上で、両者の考え方、プランのあり方を出し合って、両者の合意に基づいて援助方針、ケアプランを作成することが求められている。
註2:菅冨美枝「自己決定を支援する法制度・支援者を支援する法制度――イギリス2005年意思決定能力法からの示唆―」法政大学大原社会問題研究所雑誌No822、2010年8月所収)参照
Ⅳ ナラティブ(人生の物語)を大切にした支援―福祉サービスを必要としている人のアセスメントを「医学モデル」から「社会生活モデル」へー
〇筆者は、1970年頃から、社会福祉学研究、社会福祉実践において労働経済学を理論的支柱にした経済的貧困に対する金銭給付と憲法第25条に基づく最低限度の生活保障の考え方では国民が抱える生活問題の解決ができず、新たな社会福祉の考え方が必要であると考え、提唱してきた。
〇筆者が考える社会福祉とは、その人が願うその人らしさの自立生活が何らかの事由によって阻害、停滞、不足、欠損している状況に対して関わり、その阻害、停滞、不足、欠損の要因を除去し、その人の幸福追求、自己実現を図れるように対人援助することだと考えた。
〇その場合の“自立生活”とは、古来から“人間とは何か?”と問われてきた課題を基に6つの要件(ⅰ)労働的・経済的自立、ⅱ)精神的・文化的自立、ⅲ)身体的・健康的自立、ⅳ)生活技術的・家政管理的自立、ⅴ)社会関係的・人間関係的自立、ⅵ)政治的・契約的自立)があると考えた。
〇と同時に、それらの6つの「自立生活」の要件の根底ともいえる、その人の生きる意欲、生きる希望を尊重し、その人に寄り添いながら、その人が望むナラティブ(人生の物語)を一緒に紡ぐ支援だと考えてきた。
〇戦前の生活困窮者を支援する用語に「社会事業」という用語がある。この「社会事業」には、積極的側面と消極的側面とがあるといわれており、その両者を統合的に提供することの重要性が指摘されていた。積極的側面とは、その人の生きる意欲、希望を引き出し支えることで、消極的側面は生活の困窮を軽減するための物質的援助のことを指していた。消極的側面は、気を付けないと“人間をスポイルする”危険性があることも懸念されていた。
〇現在の民生委員制度の原型である大阪府の方面委員制度を1918年に大阪で創設した小河滋次郎は、“その人を救済する精神は、その人の精神を救済することである“として、「社会事業」における積極的側面を重視した。しかしながら、戦後の生活困窮者を支援する「社会福祉」は積極的側面を実質的に“忘却”してしまい、物質的援助をすれば問題解決ができると考えてきた。
〇憲法第25条の最低限度の生活保障では消極的側面の対応でよかったのかもしれないが、憲法第13条に基づく幸福追求の支援ということでは、高齢者のケアであれ、障害者のケアであれ、生活困窮者の支援であれ、その人が送りたい“人生”、その人が願う希望をいかに聞き出し、その人の生きる意欲、生きる希望を支え、伴走的に支援していくことが求められる。
〇従来の社会福祉学研究や社会福祉実践では、「療育」、「家族療法」、「機能回復訓練」などの用語が使われており、その人らしさの生活を尊重し、支援するということよりも、ややもすると専門職的立場からのパターナリズム的に“治療・療”し、“問題解決”を図るという目線に陥りがちであった。
〇また 従来の社会福祉学や社会福祉実践では、よくアブラハム・マズローの「欲求階梯説」が使われが、この考え方も気を付けないといけない。
〇アブラハム・マズローがいう生理的欲求、安全の欲求、愛情と所属の欲求、自尊と承認の欲求、自己実現の欲求の6つの欲求の項目の意味は重要であるが、それらの項目において、下位の欲求が満たされたら上位の欲求が生じるという“欲求階梯説”はどうみてもおかしい。人間には、自ら身体的自立がままならず、他人のケアを必要としている人であっても、当然その人が願うナラティブ(人生の物語)があり、それを自己実現したいはずである。
〇その際、福祉サービスを必要としている人自らが自分の希望、欲求を表出できるとは限らない。福祉サービスを必要としている人の中には、さまざまなヴァルネラビリティ(社会生活上のさまざまな脆弱性)を抱えている人がおり、自らの願いや希望を表出できない人がいる。更には、障害を持って生まれてきたことで、多様な社会体験の機会に恵まれず、一種の“食わず嫌い”の状況で、何を望んだらいいのかも分からない人という生活上の“第2次障害”ともいえる状況に陥っている人もいる。このような人々の場合には、その人の“意思を形成する”ことに関わる支援も必要になってくる。
〇日本の社会福祉関係者の中には、1981年に世界保健機関で制定されたICIDH(国際障害分類)に基づくアセスメントを無意識に、いまだ利活用している人がいる。
〇ICIDHは、その人の心身機能に障害があるかどうかを診断し、その人の心身機能の障害がその人の能力不全をもたらし、ひいてはそのことがその人の社会生活上において不利をもたらすというImpairment――Disability――Handicapの関係を直線的に描くもので、心身機能の不全を診断することを基底とする「医学モデル」と呼ばれるものである。
〇この「医学モデル」は、ある意味わかりやすい構造になっているので、今でも多くの社会福祉関係の底層の心理として位置づいてしまっているが、これによる支援は機能障害を直すか、直せないまでもそれを補完するというレベルの支援になってしまう。
〇WHOは2001年にICF(国際生活機能分類)を発出し、ICIDHからICFへの転換を求めた。
〇ICFは、福祉サービスを必要としている人の生活環境を変えれば、従来のICIDHでは機能障害によりできないと思われていたことができるかもしれないので、その福祉サービスを必要としている人の“最低限度の生活保障”という考え方でなく、福祉サービスを必要としている人の生活環境を変えて、その人の自己実現を図る支援への転換を求めたものである。
〇ICFの考え方と昨今の急速な福祉機器の開発により、福祉現場は急速に変わらざるを得ない。介護ロボットや障害者のコミュニケーションを保障する福祉機器の導入如何では、従来の障害児・者、高齢者などの福祉サービスを必要としている人への支援のあり方は全く違うものになってしまう。
〇このような背景も踏まえて、筆者は従来の「医学モデル」に基づく診断(アセスメント)ではなく、社会生活上に必要な機能があるかないかを基に診断する「社会生活モデル」に基づくアセスメントの必要性を提起している。
〇「社会生活モデルに基づくアセスメントシート」の図の表頭の大項目に基づきアセスメントを行うことが、ケアの科学化には必須である。
〇今日のように、福祉機器の開発やICT、IoTが急速に進展している状況の下では、福祉サービスを必要としている本人は福祉機器を使ったら自分の生活がどのように変容するのかのイマジネーション(想像性)をもてない人がいる。そのような人々に対し、イマジネーションがもてるようにし、新たな人生を作り出すクリエーション(創造性)機能も重要な支援となる。
〇従来の社会福祉実践は、福祉サービスを必要としている人の「できないことに着目し、できないことを補完・補填する目的で、してあげるケア観」に陥りがちであった。幸福追求、自己実現を図るケア観に立つと、福祉サービスを必要とする人の「できることを発見し、それを励ますケア観」が重要になる。
〇今の社会福祉実践には、その人の生育歴におけるナラティブ(narrative:身の上話、経験などに関する物語)に着目し、その人が望む人生を創り上げることに寄り添い、支援することが求められている。
〇今まで3回に亘り、「虐待問題」が起きる根源的背景として、あるいは深層心理として持っている日本国民が有している文化的要因と社会福祉観、人間観について論述したうえで、ケア観の検討並びに画一的ケア観から個別支援におけるアセスメントとそれに基づくケアの必要性について述べてきた。
〇今回は、それらを踏まえて、虐待の定義、現状について整理した上で、今後の「虐待問題」の検討すべき課題を提示したい。
Ⅴ 虐待防止の法的定義と類型及び現状
〇虐待の問題は、子ども分野、障害者分野、高齢者分野において、共通する部分もあれば、異なる部分もあるので、虐待の法的定義とその類型及び状況については分野ごとに整理することとしたい。
① 高齢者分野における法的定義と虐待の類型及び現状
〇高齢者分野における虐待に関する法律は、2005年に制定された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という)がある。
〇その法律では、高齢者虐待の類型及び養護の定義を以下のように定めている。
ⅰ 虐待の種類 身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐
待、経済的虐待
ⅱ)高齢者とは65歳以上の者をいう
ⅲ 「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外
の者をいう
ⅳ)養介護施設従事者とは、介護保険法、老人福祉法等における業務に従事する者
〇高齢者虐待の状況は、厚生労働省が公表した令和4年度(2021年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況などに関する調査結果」を基にした。ここでは、気になる項目を中心に抜粋しているので、詳しくはその調査を参照願いたい。
〇養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の推移ば、2022年度において相談件数は2795件(虐待と判断された件数は856件)で、前年度比16・9%の増となっている。
〇「高齢者虐待防止法」が制定された翌年の通報件数が273件(虐待と判断された件数54件)であったことを考えるとその増加件数は約10倍で、高齢化率の増加を考えたとしても、かつ「高齢者虐待防止法」の周知度が高まったとしても大幅な伸びとなっている。
〇他方、養護者による虐待についてみると、2022年度の通報件数は38291件(虐待と判断された件数16669件)で、前年度比5・3%の増となっている。
〇「高齢者虐待防止法」が制定された翌年の通報件数が18390件(虐待と判断された件数12569件)と比較しても増大している。
〇ただし、養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の増大が約10倍なのに対し、養護者による虐待の通報件数では約2倍(虐待と判断された件数では約1・3倍)なので、如何に養介護施設従事者等による高齢者虐待が増大していることが見て取れる。
〇虐待が起きた養介護施設の種類別では、「特別養護老人ホーム」が最も多く、274件(32・0%)、次いで「有料老人ホーム」が221件(25・8%)、「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」が102件(11・9%)、「介護老人保健施設」が90件(10・5%)となっている。
〇虐待の内容は、養介護施設従事者によるものでは、「身体的虐待」が810人(57・6%)、次いで「心理的虐待」が464人(33・0%)、「介護等放棄」が326人(23・2%)であった。
〇虐待を受けた高齢者像では、認知症高齢者で身体的虐待を受けている人が多い。
〇養護者による虐待では、虐待の発生要因(複数回答)としては「認知症の症状」が9430件(56・6%)、虐待者の「介護疲れ・介護ストレス」が9038件(54・%)、「理解力の不足や低下」が7983件(47・9%)、「知識や情報の不足」が7949件(47・7%)、「精神状態が安定していない」が7840件(47・0%)、「被虐待者との虐待発生までの人間関係」が7748件(46・5%)であった。
〇養護者の虐待の内容(複数回答)は、「身体的虐待」が11167人(65・3%)、次いで「心理的虐待」が6660人(39・0%)、「介護等放棄」が3370人(19・7%)、「経済的虐待」が2540人(14・9%)であった。
〇被虐待高齢者の「認知症の程度」と「虐待種別」との関係では、被虐待高齢者に重度の認知症がある場合には「介護等放棄」、「経済的虐待」をうける割合が高く、軽度の認知症の場合には「身体的虐待」、「心理的虐待」が高い傾向がみられた。
② 障害者分野における法的定義と虐待の類型及び現状
〇障害者分野における虐待に関する法律は、2011年に制定された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という)がある。
〇と同時に、国連が制定した「障害者権利条約」(2008年発効)を日本政府が2014年に批准したことを受けて、2011年に障害者基本法が改正され、「障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止」が盛り込まれたことを受けて、その規定を具現化する「障害者差別解消法」が制定されていることも併行的に考えなければならない。
〇「障害者虐待防止法」では、障害者虐待の類型及び養護の定義を以下のように定めている。
ⅰ)「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身機能の障害がある者であ
って、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるものをいう。
ⅱ)「障害者虐待」とは、ⅰ)養護者による障害者虐待、ⅱ)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、ⅲ)使用者による障害者虐待をいう。
ⅲ)障害者虐待の類型は、イ)身体的虐待、ロ)放棄・放置、ハ)心理的虐待、
ニ)性的虐待、ホ)経済的虐待の5つとしている。
〇障害者虐待の現状については2024年3月5日に行われた第140回の社会保障審議会障害者部会に報告された「障害者虐待事例への対応状況調査結果等について」に基づき明らかにしたい。
〇2022年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は8650件で、2021年度より約1300件増加している。
〇「障害者虐待防止法」は2011年に成立しているが、その翌年の2012年度の相談・通報件数が3260件なので、約10年間で約2・6倍に増加している。
〇相談・通報件数のうち、虐待と判断された件数は2022年度で2123件、これも2012年度に比べると1・6倍になっている。
〇相談・通報者は、警察が51%、本人13%、施設・事業所の職員が11%、相談支援専門員が11%である。
〇虐待行為の類型では、身体的虐待が69%、心理的虐待が32%、経済的虐待が17%、放棄・放置が11%、性的虐待が3%である。
〇障害者福祉施設従事者等による障害者虐待は、2022年度が4104件で、前年度より1・28倍増加している。
〇そのうち、虐待判断件数は956件で、前年度比1・37倍である。
〇相談・通報者は、当該施設・事業所その他の職員が16%、設置者・管理者が15%、本人が16%、家族・親族が11%となっている。
〇虐待行為の類型は、身体的虐待52%、心理的虐待46%、性的虐待14%、放棄・放置が10%、経済的虐待が5%である。
〇被虐待者の障害種別では、知的障害が73%、身体障害が21%、精神障害が16%で、行動障害を伴うものでは34%になっている。
〇障害者分野の虐待問題では、他の高齢者や児童とは異なる“障害者を雇用している使用者”による虐待問題がある。
〇障害者虐待との通報・届け出があった事業所は、厚生労働省雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室の調査報告によれば、2021年度で1230件(都道府県からの報告197件、労働局などへの相談880件、その他労働局等の発見153件)であった。
〇通報・届出の対象となった障害者数は1431人であり、障害種別では、精神障害が37・8%、知的障害が32・3%、身体障害が19・1%、発達障害が7・1%となっている。
〇虐待行為の類型では、経済的虐待が47・5%、心理的虐待が37・8%、身体的虐待が8・3%、放置等による虐待が4・4%、性的虐待が1・9%となっている。
〇虐待の相談・通報があった件数のうち、虐待と認められた障害者数は、2021年度502人であった。
〇就労形態別では、パート等が46・4%、正社員32・9%、期間契約社員3・8%などとなっている。
〇障害者虐待を行った使用者の内訳では、事業主85・8%、所属の上司12・2%となっている。
〇虐待が認められた事業所の業種では、製造業25・5%、医療・福祉が22・7%、卸売業・小売業が11・2%、宿泊業・飲食サービス業が6・6%、建設業が5・9%となっている。
〇事業所の規模別では、5~29人規模の事業所が49・2%、30~49人規模が16・8%、5人未満が13.5%で、50~99人規模で6・9%、100~299人規模で3・8%となっている
③ 児童分野における法的定義と虐待の類型及び現状
〇児童分野における虐待に関する法律は、2000年に制定された「児童虐待の防止等に関する法律」(以下「児童虐待防止法」という)がある。
〇児童分野における虐待については、1933年に「旧児童虐待防止法」が制定されていたが、これは戦後1947年に児童福祉法が制定されたことに伴い廃止されている。しかしながら、1990年代に入り、急速に児童虐待が増加したことに伴い、新しく「児童虐待防止法が」が制定されることになった。
〇「児童虐待防止法」では、児童の虐待の定義及び類型について以下のように定めている。
ⅰ)児童虐待の定義――「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの
ⅱ)児童虐待の類型――身体的虐待、性的虐待、保護者としての監護の放棄・放任、心理的虐待
〇令和4年度(2022年度)中に、全国232か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は219170件だった。
〇筆者が日本社会事業大学の在外研究制度で、長期にイギリスに滞在したのは1992年であったが、当時イギリスの虐待件数は1990年当時約36000件だった。
〇しかしながら、イギリスの児童虐待の状況から考えて、日本でも家族形態の変容、地域における児童健全育成力の低下等から、急速に児童問題が深刻化し、児童虐待が増えると考え、筆者は全社協の全国民生児童委員協議会の企画委員会の委員長として、民生委員が児童委員を兼ねるだけでは対応できないと考えて、児童問題を主管、主務とする児童委員制度を創設すべきとの提案をした。その提案は厚生省に受け入れられ、1994年度から「主任児童委員制度」が始まる。
〇と同時に、筆者は東京都児童福祉審議会の専門部会長として、当時東京都にある12か所の児童相談所とは別に、都内各区市町村に最低1か所の「子ども家庭支援センター」を設置し、保健師、保育士、社会福祉士を配置して、子ども・家庭への相談支援を行うこと、しかもそれはアウトリーチ型の地域組織化を想定して行うことなどの提案をし、専門部会で承認され、東京都に建議した。その建議は受け入れられ、東京都全区市町村に58か所の「子ども家庭支援センター」が設置された。
〇この二つの提案は、イギリスでの在外研究制度の成果であり、日本でも急速に児童虐待への対応を図るべきとの提案であったが、当時の児童福祉研究者や児童福祉行政の関係者たちの反応は、従来の児童相談所体制でいいとする反応であった。
〇児童虐待は、筆者の想定した通り、1990年度には1101件で、その後2000年度には17725件、2010年度には56384件、2020年度では205044件と急増している。
〇2022年度の児童虐待の219170件の内容別件数は、「身体的虐待」が51679件(23・6%)、「ネグレクト」が35556件(16・2%)、「性的虐待」が2451件(1・1%)、「心理的虐待」が129484件(59・1%)となっている。
〇児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、2022年度では警察等が最も多く、112965件(51・5%)、次いで近隣・知人が24174件(11・0%)、家族・親戚が18436件(8・4%)、学校が14987件(6・8%)となっている。
〇児童虐待による死亡事件も2022年度では45件、51人が亡くなっている。子どもを巻き込んだ心中事件も37件、47人が亡くなっている。
〇虐待を行っている人の類型では、実母が38224件(57・3%)、実父が19311件(29・0%)、実父以外の父が4140件(6・2%)となっている。
〇虐待を受けた子どもの年齢別では、小学生が最も多く、23488件(35・2%)、次いで3歳~学齢前が16505件(24・7%)、0歳~3歳未満12503件(18・8%)、中学生9404件(14・1%)となっている。
〇児童分野における虐待発生の要因として、厚生労働省はⅰ)子どもの状況――発達・発育、健康状態・身体状況、情緒の安定性、問題行動、基本的な生活習慣、関係性、ⅱ)養育者の状況――健康状態等、性格的傾向、日常的世話の状況、養育能力等、子どもへの思い・態度、問題認識・問題対処能力、ⅲ)養育環境――夫婦・家族関係、家族形態の変化を挙げている。
Ⅵ 虐待の現状から抽出して論議すべき課題
〇このように「虐待問題」と一言で言っても、高齢者分野、障害者分野、児童分野といった多岐に亘っており、それを総括りして論議することは困難である。
〇強いて言えば、日本の「家」意識、画一的集団生活からの“逸脱者”への罰の意識、上意下達の命令体質がもたらす“複合的表出”の結果としての「虐待」と言えるのではないか。
〇とりわけ、日本の戦後の社会保障、社会福祉は、戦前の「家」制度の名残をとどめており、家族の扶養、家族の介護を家族間の情愛の感情、親密圏域の自然発生的ケア観を前提として構築されている。
〇社会福祉従事者もその呪縛から解放されておらず、家族を前提としたケア方針の立案をしがちであり、福祉サービス利用者を一個の独立した個人として捉え、その個人の幸福追求、自己実現を支援する役割を社会福祉関係者が担うという崇高な理念、人間像を描けないままに業務に従事していること、それらの職員を雇用する社会福祉法人などの組織自体も上記の理念を明確に持たないままの経営、運営に陥っているのではないかと思っている。
〇上記した虐待の現状について、再度まとめるとともに、今後検討する論議すべき課題との関係で、重要だと思われることを再掲しておきたい。
① 養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の増大が約10倍なのに対し、養護者による虐待の通報件数では約2倍(虐待と判断された件数では約1・3倍)なので、如何に養介護施設従事者等による高齢者虐待が増大していることが見て取れる。
② 虐待を受けた高齢者像では、認知症高齢者で身体的虐待を受けている人が多い。
③ 高齢者の養護者による虐待では、虐待の発生要因(複数回答)としては「認知症の症状」が9430件(56・6%)、虐待者の「介護疲れ・介護ストレス」が9038件(54・“%)、「理解力の不足や低下」が7983件(47・9%)、「知識や情報の不足」が7949件(47・7%)、「精神状態が安定していない」が7840件(47・0%)、「被虐待者との虐待発生までの人間関係」が7748件(46・5%)であった。
④ 2022年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は8650件で、2021年度より約1300件増加している。「障害者虐待防止法」は2011年に成立しているが、その翌年の2012年度の相談・通報件数が3260件なので、約10年間で約2・6倍に増加している。
⑤ 被虐待者の障害種別では、知的障害が73%、身体障害が21%、精神障害が16%で、行動障害を伴うものでは34%になっている。
⑥ 障害者分野の虐待問題では、他の高齢者や児童とは異なる“障害者を雇用している使用者”による虐待問題がある。
就労形態別では、パート等が46・4%、正社員32・9%、期間契約社員3・8%などとなっている。
事業所の規模別では、5~29人規模の事業所が49・2%、30~49人規模が16・8%、5人未満が13.5%で、50~99人規模で6・9%、100~299人規模で3・8%となっている
⑦ 児童虐待による死亡事件も2022年度では45件、51人が亡くなっている。子どもを巻き込んだ心中事件も37件、47人が亡くなっている。
虐待を行っている人の類型では、実母が38224件(57・3%)、実父が19
311件(29・0%)、実父以外の父が4140件(6・2%)となっている。
日本では、いまだ「子どもの発見」が不十分で、子どもは親の付属物として捉え、
子どもを親の意向に従わせる「命令と禁止」での子育てが払しょくできていない。
〇これらの「虐待の現状」から考えて、検討すべき課題は以下の通りである。
ⅰ)家族による親密圏域のケアを当たり前の前提として、公共圏域のケアの整備が十分でない問題。
この問題の中には、相談できる「福祉アクセシビリティ」の問題や介護支援専門員、障害者相談支援員のケア観の問題がある。
また、ケアをしている家族の社会福祉制度を活用する受援力、地域福祉サービス利用主体の形成が不十分の問題もある。
ⅱ)養介護者が集積している社会福祉法人などのサービス供給組織の経営理念、運営方針等にケアのあり方、サービス利用者の尊厳の保持が具体的に明記され、それが常に研修等を通じて確認できているかどうかの問題―社会福祉現場に関わる動機、モチベーションとその内省、外化の機会の有無とアンガーマネジメントの研修。
ⅲ)機関委任事務体制下では行政による措置施設職員の研修がおこなわれていたが、2000年以降は、社会福祉職員の研修は行政的には対応できておらず、個々のサービス供給組織により行われている。
しかも、メンター制度やOJTの機能はほとんどなく、入職後から独任官的に職務を任せられ、体系的な研修を通して、自らの実践を振り返り、検証する機会を持てていない。
とりわけ小規模のサービス供給事業組織がそうである。
ⅳ)上記ⅱ)の問題とも関わるが、従事者が安心してケアに従事できるかどうか、職場環境の整備との関係の問題と同時に、きちんとしたケア観を有している人を採用し、キャリアップについて見通しがもてる人事政策があるかどうかの問題。
ⅴ)日常的に地域で障害者等とふれあい、その人の人格を尊重する機会である福祉教育の実践が地域、学校において行われているかの問題―人間の理解は頭での言語能力での理解だけでなく、福祉サービスを必要としている人との切り結びが重要。
〇虐待が起きている現場の状況は様々であり、その「違い」を捨象して、共通の統一的見解を示すことは容易ではない。
〇しかも、今までも述べてきたように、日本人が有している国民的文化がもたらす人権感覚の低さ、多様性を認める認識の低さ等の、国民の深層心理、底流にある意識との関りを抜きにして語れない部分が多分にあるが、ここではそれを踏まえた上で、今後虐待問題を検討するに際しての課題について論述しておきたい。
〇筆者は、連載の第4回の最後において、下記のような問題があることを指摘した。
〇それは、以下の通りである。最終回の今号では、これらについて論述したい。
ⅰ)家族による親密圏域のケアを当たり前の前提として、公共圏域のケアの整備が十分でない問題。
この問題の中には、相談できる「福祉アクセシビリティ」の問題や介護支援専門員、障害者相談支援員のケア観の問題がある。
また、ケアをしている家族の社会福祉制度を活用する受援力、地域福祉サービス利用主体の形成が不十分という問題もある。
ⅱ)養介護者が集積している社会福祉法人などのサービス供給組織の経営理念、運営方針等においてケアのあり方、サービス利用者の尊厳の保持が具体的に明記され、それが常に研修等を通じて確認できているかどうかの問題―社会福祉現場に関わる動機、モチベーションとその内省、外化の機会の有無とアンガーマネジメントの研修。
ⅲ)機関委任事務体制下では行政による措置施設職員の研修がおこなわれていたが、2000年以降は、社会福祉職員の研修は行政的には対応できておらず、個々のサービス供給組織により行われている。
しかも、メンター制度やOJTの機能はほとんどなく、入職後から独任官的に職務を任せられ、体系的な研修を通して、自らの実践を振り返り、検証する機会を持てていない。とりわけ小規模のサービス供給事業組織がそうである。
ⅳ)上記ⅱ)の問題とも関わるが、従事者が安心してケアに従事できるかどうか、職場環境の整備との関係の問題と同時に、きちんとしたケア観を有している人を採用し、キャリアアップについて見通しがもてる人事政策があるかどうかの問題。
ⅴ)日常的に地域で障害者等とふれあい、その人の人格を尊重する機会である福祉教育の実践が地域、学校において行われているかの問題―人間の理解は頭での言語能力での理解だけでなく、福祉サービスを必要としている人との切り結びを通して体感的に学ぶことが重要。
Ⅶ 家族を“含み財産”とする社会福祉制度の破綻と「福祉アクセシビリティ」のいい「総合相談窓口」、「まるごと相談窓口」の設置及び福祉教育の推進
〇戦後日本の社会福祉制度は、家族を“含み財産”として位置づけ、家族の介護、養育を前提にして制度設計されてきた。
〇しかしながら、1960年代の高度経済成長政策の下、急速に産業構造の転換が行われ、工業化、都市化、核家族化が進み、家族の、地域の介護力、養育力はぜい弱化していった。
〇そのことについては、拙稿「高度成長と地域福祉問題―地域福祉の主体形成と住民参加」(吉田久一編『社会福祉の形成と課題』19811年、所収)に論述してあるので参照して欲しい。
〇ところで、筆者が地域福祉と社会教育との学際的研究において、より明確に地方自治体における地域福祉とそれを可能ならしめる地域づくりを社会教育と地域福祉の有機的関りのもとで行おうと考えるようになったのは、江口英一先生が1986年に書いた「日本における社会保障の課題」という論文に触発されてからである。
〇社会教育はもともと地方分権を前提にして理論構築や実践が展開されていたが、社会福祉の分野における地方自治体の位置というものは必ずしも明確でなく、“福祉国家体制”という名のもとに、常に中央集権的機関委任事務の下で社会福祉行政は進められてきた。社会保障の一環である社会保険は国レベルで検討される政策であることは理解できるが、社会保障の一環である対人援助としての社会福祉は地域で生活している住民の身近な地方自治体の政策として論議されるものだと筆者は考えてきた。
〇それは経済的給付とちがって、対人援助としての社会福祉は、地域性、地域の生活環境に左右される部分が多く、全国一律のサービス提供、対人援助にはなじまないと考えてきたからである。
〇江口英一先生は、先の論文で、地域住民の生活は大変不安定で、生活上のちょっとした事故でも住民の25%が生活保護世帯に転落する可能性を有していて、それを防ぐためには地方自治体ごとの福祉サービスの整備が必要であるとその論文で説かれていた。
〇筆者はこの論文に勇気づけられ、この論文に依拠しながら、どうしたら地域住民の生活を守り、安定させる福祉サービスの整備のあり方、提供のシステムができるかを考えてきたのが筆者の地域福祉研究60年であった。
〇その中の理論的、実践的課題の一つが「福祉アクセシビリティ」の問題である。それは住民の生活の安定を守る地方自治体の福祉サービスの整備量もさることながら、住民からみた「福祉アクセシビリティ」が大きな問題だと考えたからである。
〇「福祉アクセシビリティ」とは、距離的に近いという問題、公共交通機関の利便性、たらい回しをされない、ワンストップの相談の総合性、心理的、手続き面での受容性などが大きいと考えたからである。
〇1970年ごろ、国民の社会福祉認識は、社会福祉を利用する人、必要としている人は、ある意味で「自業自得」であり、福祉サービスを利用することは個人にとっても、家族・親類縁者にとっても”恥”とする意識が強かった。
〇このような福祉サービスを必要としていながら、福祉サービスの相談窓口が“縁遠かった“住民は、誰にも相談できず、ストレスを貯めこみ、ネグレクトするとか、心理的虐待、身体的虐待に走っていったことは想像に難くない。
〇住民の身近なところで、心理的負担もなく、相談しやすい環境があったならば、利用できる福祉サービスがある、なしに関わらず、住民は自ら抱える辛さ、悩み等を「外化」でき、虐待に走る度合いが減ったのではないだろうか。
〇今、地域共生社会政策の下で、包括的支援体制、重層的支援体制整備の必要性が謳われているが、1990年までの中央集権的機関委任事務体制の下では、「社会福祉六法体制」に基づく縦割り福祉行政が行われていて、「福祉アクセシビリティ」のいい世帯・家族全体を支援する総合相談窓口はなかった。
〇筆者は1990年に東京都狛江市、東京都目黒区、岩手県遠野市などにおいて、縦割り福祉行政の弊害を除去し、住民にとって「福祉アクセシビリティ」のいい福祉行政システムを構築してきた。
〇このような「福祉アクセシビリティ」の良さに加えて、職員によるアウトリーチ型問題発見と支援とが行われたならば、養護者の虐待の動向は違っていたのではないだろうか。
〇日本の社会福祉・社会保障は、相も変わらず“家族の介護力、養育力”に依存する“家族”を含み財産とする発想が色濃く残っている。
〇今こそ、市町村において包括的・重層的支援システムを構築し、コミュニティソーシャルワーク機能を発揮できるシステムの構築とそれを担当できる職員の養成が喫緊の課題である。
〇今や、単身者社会であり、家族に頼らない、「福祉アクセシビリティ」のいい、生活に関わる「総合相談窓口」や「まるごと相談窓口」を地域に構築することが必要である。
〇と同時に、住民の社会福祉に関する知識の向上、社会福祉制度の理解を深め、国民が戦前からの「家制度」に基づく「家意識」を変容させ、家族に頼らない、公共圏域の社会サービスを利用するのが当たり前と思える住民の福祉サービス利用の受援力を高める福祉教育の推進がますます重要になってきている。
Ⅷ 介護問題が集積している社会福祉法人の理念、経営方針と虐待問題
〇連載の第4回目で述べたが、厚生労働省の調査によれば、障害者施設や通所サービ
スなどの従事者から障害者が虐待を受けた件数は、2023年度、5618件で前年度比約37%増加している(ちなみに、家族などの養護者から虐待を受けた障害者は2285件、前年比7・8%増であった)。
〇介護施設の職員らによる高齢者への虐待は1123件(前年度比31・2%増)で、2006年度調査開始以来の最多となった。家族などの養護者による虐待は17100件(前年度比2・6%増)であった。
〇このような状況を踏まえ、社会福祉施設、福祉サービス事業所での虐待をなくすためには以下のような取り組みが必要ではないか。
ⅰ)社会福祉法人の設立理念、経営方針における人間性、個人の尊厳を謳う個別ケアが明確化されているか
〇日本の社会福祉施設は、中央集権的機関委任事務が少なくとも1990年まで、あるいは2000年まで続いていたこともあり、福祉サービスを必要としている人、福祉サービスを利用している人のアセスメントが事実上できていなかった。
〇福祉サービスを必要としている人を行政がサービス利用の要件に合致しているかどうかを判断し、社会福祉施設・社会福祉法人はその行政に措置された人を受け入れ、サービスを提供していたために、入所型施設などにおいては、三大介護と言われる食事、排せつ、入浴がどれだけ“自立”しているかというADLの評価が中心であった。
〇医療の世界では、ついこの間まで“やぶ医者”という言葉が住民の間で使われていたが、いまやその用語は“死語”になっている。それは、医療の世界では、聴診器だけでなく、レントゲン、MRI、CTスキャナー、血液検査などの診断技法が格段に進展し、患者の病変の診断と治療との関係性が格段に向上したからである。
〇ところが、社会福祉界は未だ福祉サービスを必要としている人が何につまずき、何が生活のしづらさを生み出す要因なのか、本人は何を希望し、どういう生活を送りたいと願っているのかなどの「社会生活モデル」に基づくアセスメント技法が確立していない。何となく社会福祉士、介護福祉士などの資格を有している人が“情感的に”判断しているという“やぶソーシャルワーカー”が沢山いる。
〇それは、福祉サービスを必要としている人が現に制度化されているサービスを利用できる要件に合致するかどうかという仕事の仕方をしてきた中央集権的機関委任事務体質の福祉文化を見直すことなく、無意識のうちにそれを引きずってきているからである。
〇また、社会福祉法人は行政から措置された人に対する“最低限度の生活保障”をしてあげるという目線になりがちで、結果として法令による措置施設の施設最低基準に基づき集団的、画一的ケアを実施してきたのではないだろうか。
〇2000年以降、福祉サービス利用が契約で行われるようになった際に、従来の支援方針、ケア観を見直し、福祉サービスを必要としている人、利用している人と福祉サービスを提供する側とが相対契約をする制度に変わったことに伴い、その際に、どれだけの社会福祉法人、社会福祉施設がその相対契約に相応しい福祉サービス利用者、福祉サービスを必要としている人の個々の状況に見合ったアセスメントと援助方針を確立することを明確にできたであろうか。
〇筆者が考えるのに、現象的には社会福祉法人も社会福祉施設も個人の尊厳、人間性の尊重を謡いながら、実質的には個々人の状況を丁寧にアセスメントするという福祉文化が確立できていなかったのではないか。
〇その点で、筆者が注目しているのは、2002年の老人福祉施設最低基準が改訂され、ユニットケアが出されてくる中で、一般社団法人日本ユニットケア推進センターが進めている、限りなく個別ケアの具現化の取り組みである(拙編著『ユニットケアの哲学と実践』日本医療企画、2019年)。
〇一般社団法人日本ユニットケア推進センターが進めている個別ケアの実践は、同じ厚生労働省が定めた基準である老人福祉施設最低基準に則りながら、個別ケアを確立できており、かつ職員の離職率も低く、利用者からの評価も高いことを考えると全国的に展開できないことではない。要は、社会福祉法人の経営理念、実践哲学がそのことを明かにできているかどうかの問題である。
ⅱ)市町村における福祉サービス事業所職員の研修の体系化はされているだろうか
〇中央集権的機関委任事務体制時代にあっては、行政がサービス提供を社会福祉法人に委託していたこともあって、各都道府県が社会福祉研修センターを設置し、社会福祉法人、社会福祉施設の職員に対する研修がそれなりに整えられていた。
〇しかしながら、2000年の介護保険、2005年の障害者総合支援法以降、福祉サービス利用は行政の措置から、福祉サービスを必要としている人と福祉サービス事業者との間の契約に変わったこともあり、各都道府県の社会福祉研修センターの役割は大きく変わり、筆者が観る限りにおいて各都道府県の社会福祉職員に対する研修機能は大幅に低下していると言わざるを得ない。
〇ある意味、職員の研修は、各福祉サービス事業者の任意となり、行政は各サービス事業者のサービス管理者の資格、研修を規制化させることで、職員のサービスの質の担保を図る仕組みへと変更した。
〇したがって、福祉サービス事業所で働く職員、社会福祉法人、社会福祉施設で働く職員の研修は、いわば無秩序状態になっている。
〇このような状況のなかで、小さな規模の事業所の職員はほとんど研修を受けることもできなければ、自前で研修をすると言うことも容易ではなくなってきている
〇先に挙げた事業所の虐待件数についても、事業所の規模や事業所内での研修の有無などについて丁寧に分析する必要があるが、ここでは触れない。ただし、福祉サービス事業所の規模別・虐待種別事業所数の調査によれば、規模が5~29人の規模の事業所が虐待件数全体の49・2%、30~49人規模が16・8%、5人未満が13・5%であり、逆に300人以上の規模では1・0%であることを考えると事業所の規模ごとにおける職員研修のあり方との関係があることは想像に難くない(「令和3年度使用者による障害者虐待の状況」調査)。
〇他方、1990年以降、地方分権化が進み、国や県は市町村への指導を直接的にはできず、専門的助言の域を超えることができなくなった。その上に、市町村は各分野ごとの福祉計画の“上位計画”として「地域福祉計画」を位置づけている。しかしながら、この市町村ごとの「地域福祉計画」を見る限り、市町村内の福祉サービスに従事する職員の研修の必要性を掲げている「地域福祉計画」は皆無に近い。
〇今や、一部の大手を除くと福祉サービス事業所、社会福祉法人の職員の研修システムはとても不十分だと言わざるを得ない。
〇しかしながら、福祉サービスは国民にとって欠かせないサービスであり、かつサービス利用費がいわば公定価格で縛られてはいるものの、逆の意味では“安定”していることもあり、いわゆる市場ベースの“競争原理”は働きにくい状況である。
〇ならば、サービス管理者の資格、研修のみならず、市町村福祉行政による市町村内の社会福祉職員の研修を整備し、職員の資質向上を図るべきなのではないだろうか。
〇2011年の「地方分権一括法」で、市域内だけの住民を対象に福祉サービスを提供している社会福祉法人の許認可権は市長が有することになったし、その後介護保険サービスの許認可権も町村長にまで移譲されたことを考えると、市町村レベルでの域内の福祉サービス従事者への研修システムの構築は市町村行政が責任をもって行うべきではないだろうか。
〇このような職員の研修システムの構築をしないでおいて、事業所における虐待を取り締まるという姿勢だけでは問題解決につながらない。
ⅲ)社会福祉学の構造と国家資格養成課程における実践力習得の課題
〇社会福祉学の構造は、①社会福祉の目的、理念に関わる哲学、②福祉サービスを必要としている人の生活のしづらさ、生活問題をアセスメントし、構造的に分析する分析科学、③福祉サービスを必要としている人の問題を解決するための援助方針の立案、活用できる福祉サービスの利用計画、活用できる福祉サービスがなければ、新しい問題解決プログラムを作成するとか、新しい福祉サービスを開発するなどの設計科学、④立案された援助方針、ケアプランに基づき具体的な対人援助の実践を展開する実践科学。この実践科学は、設計されたプラン通りに実施すればいいというものではなく、福祉サービスを必要としている人の日々の変化を見据え、実践者がその状況に合わせ、設計されたプラン、対人援助を微調整していく必要性がある。⑤実践を展開した後、福祉サービス利用者の「快・不快」を基底とした満足度や設計されたケアプランの妥当性などについての評価、振り返りを図る評価科学の5つの要素からなる統合科学である。
〇この統合科学という考え方は、戦前に確立されてき旧帝国大学の講座制の学問体系にはない、新しい学問の考え方であり、日本学術会議が2003年以降打ち出している考え方である。
〇社会福祉分野は、従来「学問」ではなく、「論」の域を出ていないと学術界では言われてきたが、日本学術会議の提案による「統合科学」という視点、枠組みを考えるならば、社会福祉はまさにぴったりの「統合科学」である。この「統合科学」という考え方の提唱もあって、社会福祉学は2003年度から日本学術振興会の科学研究費の細目として「社会福祉学」が位置づけられ、文字通り日本の学問体系において「社会福祉学」が認証された。
〇しかしながら、統合科学としての「社会福祉学」における個々の要因、要素の実践、研究の科学化は未だ道遠しの状況である。
〇第1には、援助方針を立てる基になるアセスメントが十分確立されていない。相も変わらず医学モデルに基づく“治療”、“療育”という考え方が強く、「社会生活モデル」に基づく、その人の自己実現を図るという発想が十分でない。そのことは先に述べた中央集権的機関委任事務体制の文化的名残りであり、かつ憲法第25条に基づく最低限度の生活保障を保証してあげるというパターナリズムを払しょくできていないからである。
〇今や、ICF(国際生活機能分類)の考え方に基づき、福祉機器等を活用してその人の生活環境を改善したらどうなるかという視点からのアセスメントも重要になってきている。
〇第2には、社会福祉の実践現場は、施設最低基準などの制約があり、ややもすると新人職員と言えども“一人前”の扱いを受けて、勤務シフトに配属され、事実上OJT―オン・ザ・ジョブ・トレーニング(職場での実務を通じて知識やスキルを習得させる育成方法)が実施されてない。
〇また、同じような理由から職員の資質を向上させる一つの方法であるメンター制度(経験豊富な先輩社員・メンター・が後輩シャインのキャリア形成や悩み解決法をサポートする社内制度)なども導入されていないのが大方である。
〇今日では、社会福祉士、介護福祉士の国家資格が出来てから約40年近くの歴史を経て、多くの社会福祉従事者が資格を有する時代になってきている。
〇先に述べた虐待事案において、国家資格の有資格者が虐待を起こしているのか、それとも資格を有していない人が虐待を起こしているのかの分析まではしきれていない(障害者分野では、虐待を起こした職員の就労形態別調査では、正社員、パート等において虐待がおこされていて、派遣労働者等の件数は少ない。しかしながら、国家資格の有無による虐待件数の調査は見当たらなかった。高齢者分野においてもこの項目は見当たらなかった)。
〇資格を有していない人が虐待問題を起こしていてもしょうがないという訳ではないが、資格を有している人でも虐待を起こしているかもしれないという問題点をここでは指摘しておきたい。
〇つまり、現在の国家資格は、社会福祉制度などに関わる座学で学べる部分と実習によって習得できる部分で教育課程は構成されているが、筆者は圧倒的に実習が少ないと考えている。
〇社会福祉士の国家資格の受験資格を得られる通信制の養成機関では、出題科目である講義科目についての履修は求められず、相談援助に関する演習と実習が課せられている。
〇この考え方は、講義科目は当然国家試験に出題されるので、その理解の程度を計ることは国家試験で行えばいいのであり、その国家試験をクリアできなければ合格できないので、それで一種のスクリーニングが行われているという考え方である。
〇しかしながら、相談援助に関する技術は演習で身に着けなければ習得できないので、必修にすると言う考え方だった。当時の厚生労働省の高官はそのことを明言していた。
〇そうだとすると、社会福祉系大学などの養成校の通学生の講義科目についても同じことがいえるので、もっと選択の幅を増やして、負担を軽減し、その分演習や実習によって、座学で得られない実践力の取得に努めるべきではないか。
〇同じようなことは、社会福祉職員研修においてもいえることで、知識の量を増やす、新しい知見を身に着けることを目的とした講義を聞くという承り研修はe-ラーニングでも行うことができるので、対面での座学研修は少なくし、その分事例に基づき、その事例で起きた現象がどのような要因から出されてきたのかをアセスメントし、其の問題を解決する援助方針を立て、どのようなサービス、どのような支援を行うべきかのケアプランを作成するアクティブラーニングを質量ともに増やすことが必要ではないか。それを行わない限り、“知識はあるけれど、対応ができない”という状況はなくならないし、国家資格を有していても虐待事案を起こすことになる。
〇ただ、このような事例に基づきコンサルテーションを行える大学の教員がどれだけいるかが大きな問題である。
〇第3には、医学部の入試において面接が重要な位置と役割を担ってきていることが評価されている。
〇社会福祉系大学において、社会福祉従事者の個人的資質を問う受験生の面接を行って、ソーシャルワーカー、ケアワーカーとしての適性を弁えるという取り組みをしている大学がどれだけあるのだろうか。
〇日本社会事業大学でも、面接を実施して社会福祉従事者としての資質を見抜くという課題は大きな問題であった。かつては、受験生全員の面接が行われていたが、大学経営と受験生の増大という課題の前に面接は受験科目から姿を消した。今、思い起せば、対人に関わることは受験における面接が無くなっただけでなく、新入生のオリエンテーションキャンプ、3年次進学時のインテグレーションキャンプといい、対人関係を培う行事はカリキュラムから姿を消している。ソーシャルワーク関係の教員がその重要性を指摘し、順守することができず、教員の負担軽減という名の下で姿を消している。このような状況で、学生はソーシャルワーク機能に必要な実践力を高めることができるのであろうか。
〇職員の個人的資質の面で言えば、怒りやすい、すぐ切れるとか言った問題は、全体の問題でもあると同時に、すぐれて個人的資質の問題でもあるので、アンガーマネージメントの研修を受けるとか、コーチングを受ける機会を増やすとかして、職員本人の思ったこと、感じたこと、悩んだことを「外化」する機会や「内省」の機会を持つことも重要である。
ⅳ)社会福祉施設最低基準等の見直しと福祉機器を利活用した職員の負担軽減、利用者のQOLの向上
〇虐待の問題は、福祉サービス利用者に対するケアワーカーやソーシャルワーカーの配置基準が劣悪であるからとか、労働条件が悪いから起きるというという労働環境劣悪説を唱える人もいるが、事柄はそう単純なものではない。
〇しかしながら、十分な労働環境が保障されず、気持ちの余裕もなくなり、身体的にも疲労が蓄積されている時に、虐待が起きやすいことは想像するのに難くない。
〇虐待案件の調査でそのような視点での分析が今後必要になるのではないか。しかし、ここではそれについては触れない。
〇虐待の問題と職員の労働環境の悪さとの直接的相関性をいうことは簡単にはできないが、先に述べたように「ユニットケア」で「個別ケア」を徹底している社会福祉施設ではサービス利用者も家族も大変評価していること、並びにその「ユニットケア」で働いている職員の離職率が全介護事業所や全国社会福祉施設経営者協議会に加盟している事業所と比較して、離職率が特段に低い事を考えると、それは社会福祉施設最低基準に問題があるというより、先述したような施設の経営方針等に由来していると考えるのが妥当であろう。
〇とはいうものの、社会福祉施設最低基準が見直され、福祉サービス利用者の空間的生活環境の整備が整えられ、集団的、画一的ケアの提供ではなく、サービス利用者の生活リズムに合わせた支援が可能となるような社会福祉施設最低基準の見直しは確かに今後必要であろう。
〇現在、厚生労働省は高齢者分野での介護ロボット、見守りセンサー等のICTや福祉機器を活用しての「介護労働生産性向上センター」を設置する政策を進めていると同時に、「LIFE」といった介護現場のデータ化によるケアの科学化を進めている。
〇他方、障害者分野でもICTを活用した「障害者ICTサポートセンター」を設置して、障害者本人の生活の利便性を高めると同時に、社会福祉職員の負担軽減を図っている。
〇これら福祉機器の利活用は、職員の負担軽減のみならず、利用者のQOLの向上にも連動している重要な取り組みである。
〇しかし、それ以上に重要なのは、介護ロボットの利活用もさることながら、介護現場に介護リフトを導入することである。人力による抱え上げをするのではなく、介護リフトを利活用することによって、福祉サービス利用者の不安感は軽減するし、職員の腰痛予防にもなる。結果的に利用者と職員との会話の時間も増えるということも考えると、社会福祉施設最低基準の人員配置基準の見直しのみならず、従来の人力による介護をするという福祉文化を変えることが、今最も重要な取り組み課題である。
(注記)
本連載は、日本社会事業大学同窓会北海道支部の求めに応じて執筆したものである。連載は、「老爺心お節介情報」第51号、第52号、第59号、第61号、第66号が初出である。
大橋ブックレット 創刊号
社会福祉従事者の社会福祉観と虐待問題
発 行:2025年5月8日
著 者:大橋謙策
発行者:田村禎章、三ツ石行宏
発行所:市民福祉教育研究所




