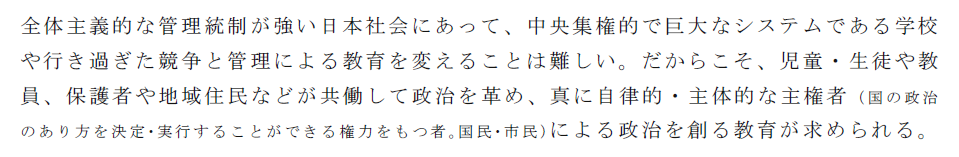
〇教育基本法(2006年12月22日公布・施行)の第14条(政治教育)は、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と謳(うた)っている。まず、この条文を押さえておきたい。
〇日本において「主権者教育」の必要性が声高に叫ばれるようになるのは、2000年代以降である。その政策化のひとつの重要な契機は、総務省が2011年4月に設置した「常時啓発事業のあり方等研究会」(座長:佐々木毅)の報告である。その「最終報告書」(2011年12月)では、子ども・若者に対する新たなステージとしての「主権者教育」の必要性と重要性を説き、現代に求められる新しい主権者像のキーワードは「社会参加」の促進と「政治的リテラシー(政治的判断力や批判力)」の向上である、とした。そして、「主権者教育」を次のように規定する。「欧米においては、コミュニティ機能の低下、政治的無関心の増加、投票率の低下、若者の問題行動の増加等、我が国と同様の問題を背景に1990年代から、シティズンシップ教育が注目されるようになった。それは、社会の構成員としての市民が備えるべき市民性を育成するために行われる教育であり、集団への所属意識、権利の享受や責任・義務の履行、公的な事柄への関心や関与などを開発し、社会参加に必要な知識、技能、価値観を習得させる教育である。その中心をなすのは、市民と政治との関わりであり、本研究会は、それを『主権者教育』と呼ぶことにする」(7ページ)。
〇いまひとつ注目すべきは、文部科学省が2015年10月、1969年10月の文部省初等中等教育局長通達「高等学校における政治的教養と政治的活動について」を廃止し、それに代わって同通知「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」を発出したことである。1969年通達では、「国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請している」。「生徒が政治的活動を行なうことは、学校が将来国家・社会の有為な形成者として必要な資質を養うために行なっている政治的教養の教育の目的の実現を阻害するおそれがあり、教育上望ましくない」などとして、学校内外における政治的活動を「禁止」した。そのねらいは、1960年代後半にベトナム反戦運動等を契機に多発・激化した学生運動(大学闘争)やその高校・高校生への波及(高校紛争)を阻止しようとするところにあった。
〇2015年通知では、「今後は、高等学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待される」。「現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一層具体的かつ実践的な指導を行う」などとした。その背景には、「18歳が世界標準」というなかで、選挙権年齢が「満18歳以上」(2016年6月施行)、成年年齢が「18歳」(2022年4月施行)にそれぞれ引き下げられたことがある。それに伴って、「主権者教育」の重要性が強調されることになる。
〇しかし、2015年通知の内実は、「高等学校等の生徒による政治的活動等は、無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲内で制約を受ける」などと、学校や教員の「指導」等による、学校内外における政治的活動の規制を求めるものとなっている。すなわちそれは、基本的には政治的活動の自由化を促したり、容認したりするものではない。
〇2015年9月、総務省と文部科学省は、高等学校等の生徒向け副教材として『私たちが拓く日本の未来―有権者として求められる力を身に付けるために―』の<解説編><実践編><参考篇>と教師用の<活用のための指導資料>を作成・公表した。それは、政府主導の「主権者教育」の展開をこと細かく指示するものとなっている。また、選挙権年齢の引き下げによる「主権者教育」の強調は、「有権者教育」に縮小・限定される恐れなしとしない。そこで、民主主義を成り立たせる前提である「人権」や「思想・良心(信条)の自由」などに基づく議論が必要かつ重要となる。
〇2017年3月に小・中学校、2018年3月に高等学校の「新学習指導要領」が告示された(小学校では2020年度、中学校では2021年度から全面実施、高等学校では2022年度から年次進行で実施)。それに基づいて、小・中学校と高等学校では、児童・生徒の発達段階に応じた「主権者教育」を実施し、主権者として必要な資質・能力を教科等横断的な視点で育成することとされている。高等学校では、従来の「現代社会」に代わって、「公民」科の新しい必修科目「公共」が設けられている。
〇また、文部科学省は2018年8月、新学習指導要領の下での学校・家庭・地域における「主権者教育」の推進方策について検討するために、「主権者教育推進会議」(座長:篠原文也)を設置した。そして、2021年3月に「今後の主権者教育の推進に向けて」最終報告を公表した。そこでは、主権者教育をめぐる課題と今後の推進方策に関し、(1)(小・中学校、高等学校、大学、教師養成・研修等)各学校段階等における取り組みの充実、(2)家庭、地域における取り組みの充実、(3)主権者教育の充実に向けたメディアリテラシー(メディアからの情報を批判的・創造的に読み解く能力)の育成、などについて提言する。そして、その提言を実現するために、(4)社会総がかりでの「国民運動」としての主権者教育推進の重要性を説く。こうした文部科学省の取り組みは、前述の2015年通知や『私たちが拓く日本の未来<活用のための指導資料>』に示された考え方の周知を図ろうとするものであり、内容的には新味に欠ける。
〇ところで、3月13日、新藤宗幸(しんどう・むねゆき。行政学・地方自治論専攻)が亡くなった(享年75)。4月1日、「18歳、きょうから成人」である。そんななかで、新藤の著作の一冊である『「主権者教育」を問う』(〈岩波ブックレット No.953〉岩波書店、2016年6月。以下[1])を再読することにした。
〇[1]における議論・言説の要点のひとつは、こうである(抜き書きと要約)。「主権者教育」は、現実の政治の実態を棚にあげ、単に新有権者に「政治的な教養を育む教育」を説くのではない(10ページ)。「主権者教育」は、まず現実の政治が生み出している社会的問題事象の中身を学習し、政治にどのような利害が反映されているのかを学ぶことから始めるべきである(15ページ)。「主権者教育」に求められているのは、日々生起する政治的事象の内実をみる眼を養うことであり、また政治権力の行動の意味を洞察する能力を高めることである(7ページ)。「主権者教育」は、政治権力に従順な人間を育てることではない(21ページ)。
〇「主権者教育」と表裏一体で強調されるものに、「教育における政治的中立性」がある。続けて新藤はいう。政権の言説やそれを忖度した同調の「政治性」は不問に付され、それらに対する批判的言説が「政治的中立性」に反するとされる傾向にある(23ページ)。「教育における政治的中立性」という場合の「政治」とは、「政治」一般をさしているのではなく、あくまで「政党政治」を意味する(30ページ)。「教育における政治的中立性」とは、政党政治の介入を排除する規範としての意味をもつものである(30ページ)。しかも、それだけではなく、教員にあっては自らの思想・信条や専門的知識にもとづいて、物事には社会的にも学問的にも多様な見解があることを示しつつ、自らの見解を説かねばならない(31ページ)。こうした能動的な教育と教員による「政治的中立性」を保障するためには、文部科学省から校長にいたる「タテの行政系列」を改革する必要がある。同時に、首長のもとの教育行政への市民参画を徹底するとともに、学校ごとに生徒・教員・市民が参画する運営組織をつくるなどして、「教育行政の政治的中立性」が実現されなければならない(43ページ)。
〇日本においては、国家による統一的・画一的な管理主義教育や教育行政が、学校現場や教育委員会を「思考停止」状態に追いやり、生徒の自主的・主体的な活動を制約あるいは否定してきた。そういうなかで、真の「主権者教育」の推進を図るためには、如何にして生徒の政治的関心を高め、政治的教養を豊かにするか。そして、学校内外における多様な政治的問題状況に異議申し立てをし、政治的活動への参加を促すか、が問われることになる。そのためには例えば次のようなことが求められる、と新藤はいう。政治的教養を培うにあたって、若者に限らず大人たちが生活の場に生じているさまざまな市民運動や社会運動との接点をもつ(61ページ)。学校は地域の多様な集団と生徒の交流の場を用意し、生徒たちが地域の課題を通じて政治のあり方を考える機会とする(63ページ)。地方自治体の首長や各行政セクションの職員、教育委員会や教育長・教育委員、自治体の議会や議員などと交流し、地域政治や地域行政の役割やあり方などについて議論する(64、65ページ)。学校を「地域に開かれた学校」「民主的な学校」にするために教員は、市民としての感性を磨きつつ、教育のプロフェッション(専門職)として、市民の支援を得ながら、学校改革や教育改革に立ち上がる(59、60ページ)、などがそれである。
〇日本における「主権者教育」のモデルのひとつは、イギリスの「シティズンシップ教育(Citizenship Education)」である。それを方向づけたのは、政治学者のバーナード・クリック(Bernard Crick)らが中心となってまとめた1998年9月の政府答申「シティズンシップのための教育と学校でのデモクラシーの指導(Education for citizenship and the teaching of democracy in schools)」(「クリック・レポート」)である。イギリスでは、この答申に基づいて2002年から、中等教育段階(第7学年~第11学年。日本の小学校1年~高校1年)でシティズンシップ教育が必修化された。
〇クリック・レポートでは、シティズンシップを構成する要素として、「社会的・道徳的責任(social and moral responsibility)」「コミュニティへの関与(community involvement)」「政治的リテラシー(political literacy)」の3つが挙げられている。この3つの事柄は、相互に関連性を有し、依存関係にある。クリックによればシティズンシップ教育は、ボランティア活動の促進に偏りがちであるが、「能動的な市民(active citizen)」の育成こそがその中心に位置づけられるべきである。そのためには、「政治的リテラシー」(政治的判断力や批判力)を中核的な内容とするシティズンシップ教育が肝要となる。なお、この「3つの柱」について、クリック・レポートは次のように述べている(下記「参考文献」(3)122、123、124ページ)。
社会的・道徳的責任
子どもたちが、権威のある者ならびにお互いに対して、幼少からの自信や社会的・道徳的な責任ある態度を教室の内外で見につけることです。このような学習は学校の内外を問わず、子どもたちが集団で行動したり遊んだりするときあるいは自分たちの地域における活動に参加するときに、時と場所を選ばずに展開されるべきです。
コミュニティーへの関与
自分たちの社会における生活や課題について学び、それらに有意義な形で関われるようになることです。社会参加・社会奉仕活動を通じた学習もここに含まれます。
政治的リテラシー
児童・生徒が知識・技能・価値観といったものを通じて、市民生活(public life)について、更には自身が市民生活において有用な存在となるための手段について学ぶことです。
〇シティズンシップ教育の一環として考える「まちづくりと市民福祉教育」についても、同じことが言える。すなわち、「市民福祉教育」が「まちづくり」のための地域貢献活動やボランティア活動、あるいはサービスラーニングなどとの関連性を問うとき、主権者・政治主体としての子ども・青年から大人までの「市民」に求められる政治的リテラシーの育成にとりわけ留意する必要がある。別の著作で述べているクリックの次の一節を引いておく(下記「参考文献」(2)199~200ページ)。留意したい。
イギリスでも合衆国でも、多くの指導的政治家たちはシティズンシップを、イギリスでは「ボランティア活動」に、合衆国では「公共奉仕学習」(サービス・ラーニング)に切り詰めようとしている。しかし、ここには難しさがある。ボランティア活動一辺倒になってしまうと、善意あふれる年寄りたちが若者に何をすべきかを言って聞かせるだけに終わってしまいかねないのだ。ボランティアに与えられた任務の目的や方法を誤っていると思ったり、つまらないことのよう思ったりしたときに、その改善策を提案してゆく責任を与えないでおいて、それを全うする責任だけを引き受けさせるということになれば、ボランティアたちは市民として扱われていないことになる。こうなれば、ボランティアは単なる使い捨ての要員にされかねないし、また彼らを幻滅させることになるだろう。
補遺
〇日本における「シティズンシップ教育」の政策化に関しては、経済産業省(委託先:三菱総合研究所)が「シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会」(委員長:宮本みち子)を設置し、2006年3月に「報告書」、同年5月に「シティズンシップ教育宣言」(パンフレット)をそれぞれ発表している。「報告書」では、「シティズンシップ」について、「多様な価値観や文化で構成される社会において、個人が自己を守り、自己実現を図るとともに、よりよい社会の実現に寄与するという目的のために、社会の意思決定や運営の過程において、個人としての権利と義務を行使し、多様な関係者と積極的に(アクティブに)関わろうとする資質」(20ページ)と定義している。
〇また、「シティズンシップ教育宣言」では、「シティズンシップ教育の必要性」について、「報告書」中の説述(9ページ)を次のようにまとめている(3ページ)。
私たち研究会では、成熟した市民社会が形成されていくためには、市民一人ひとりが、社会の一員として、地域や社会での課題を見つけ、その解決やサービス提供に関する企画・検討、決定、実施、評価の過程に関わることによって、急速に変革する社会の中でも、自分を守ると同時に他者との適切な関係を築き、職に就いて豊かな生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、さらによりよい社会づくりに関わるために必要な能力を身につけることが大切だと考えます。
一方で、こうした能力を身につけることは、いかなる人々にとっても、個々人の力では達成できないものであり、家庭、地域、学校、企業、団体など、様々な場での学びや参画を通じてはじめて体得されうるものであると考えます。
上記のような能力を身につけるための教育、すなわちシティズンシップ教育を普及して、市民一人ひとりの権利や個性が尊重され、自立・自律した個人が自分の意思に基づいて多様な能力を発揮し、成熟した市民社会が形成されることを期待しています。
なお、私たち研究会の提言は、市民に奉仕活動などを義務付けたり、国家や社会にとって都合のよい市民を育成しようという目的のものではありません。
参考文献
(1)新藤宗幸『「主権者教育」を問う』(岩波ブックレット No.953)岩波書店、2016年6月。
(2)バーナード・クリック、添谷育志・金田耕一訳『デモクラシー』(<一冊でわかる>シリーズ)岩波書店、2004年9月。
(3)長沼豊・大久保正弘編、バーナード・クリックほか著、鈴木崇弘・由井一成訳『社会を変える教育 Citizenship Education ~英国のシティズンシップ教育とクリック・レポートから~』キーステージ21、2012年10月。
(4)蒔田純『政治をいかに教えるか―知識と行動をつなぐ主権者教育―』弘前大学出版会、2019年6月。
(5)日本学術会議政治学委員会政治過程分科会『報告 主権者教育の理論と実践』日本学術会議、2020年8月。
(6)全国民主主義教育研究会編『「公共」で主権者を育てる教育を』(民主主義教育21 Vol.15)同時代社、2021年7月。




