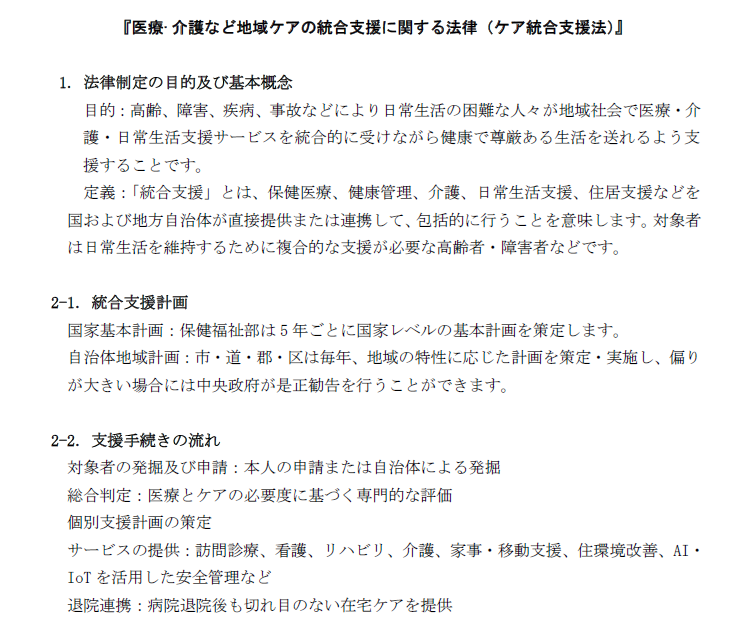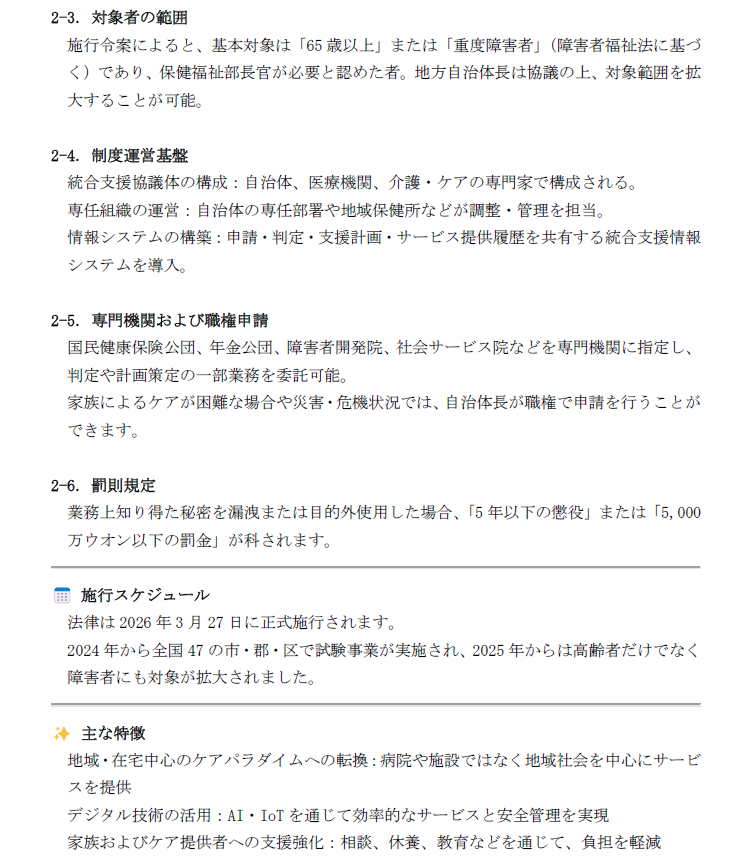「老爺心お節介情報」第73号
地域福祉研究者の皆様
社会福祉協議会関係者の皆様
暑い日がまた戻ってきましたが、皆様お変わりありませんか。
「老爺心お節介情報」第73号をお届けします。ご活用ください。
2025年8月15日 大橋 謙策
〇立秋が過ぎたというのに、いまだ酷暑が続きます。皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。
〇私の方は、7月は各地のCSW研修で東奔西走しましたが、8月に入り、お盆までのんびりと過ごせ、英気を養うことができました。毎日の家庭菜園、庭木への水やりをする他には、週2回ほど地域の囲碁クラブに出かけ、対局を楽しみました。
〇また、このところ筋力の衰えを実感していましたので、8月より近くの民間のスポーツジムNASの会員になり、機器を使って筋力トレーニングを始めました。80歳の筋力は、20歳代の半分だといわれていますので、“年寄りの冷や水”かもしれませんが、チャレンジしたいと思っています。通うのが楽しい日々になりました。
〇8月20日から22日まで、ソウル特別市社会福祉協議会の金玄勲会長(日本社会事業大学の学部、大学院での教え子)の招聘により、韓国・ソウル市を訪問することになりました。
〇当初は、拙著『地域福祉とは何か』を金玄勲さんがハングル語に翻訳してくれ、その出版記念会への招聘でしたが、20年振りくらいに日韓地域福祉学術交流をしようということになり、日本地域福祉研究所からも田中英樹副理事長や原田正樹日本福祉大学学長なども参加されることになりました。
〇学術交流としての訪韓は久しぶりなので、今回の訪問では、金成垣・金圓景・呉世雄編著『現代韓国の福祉事情』(法律文化社、5700円)を読んで、学習していきました。その本を読んでの私の韓国理解の概要を下記にまとめてみましたのでご参照ください。
〇今日は、終戦後80年の節目の日です。今、日本では「排外主義」の主張が高まっていますが、今年は「日韓国交正常化50周年」ですし、「村山談話」発出30周年です。
〇改めて、日本が戦前の軍国主義の時代に行った様々な蛮行に思いを致し、蹂躙された国の方々の辛い、悲しい思いに心を寄せ、二度とあのような蛮行の過ちを繰り返さないためにも国民レベルの平和友好交流を強めたいとしみじみと思いますし、誓いました。
(2025年8月15日、終戦の日に平和共生を祈念して)
Ⅰ 韓国の社会福祉の現状
〇筆者が韓国と学術交流していたのは、1990年代後半のアジア通貨危機の時代から2008年の韓国の介護保険である長期療養保険制導入時代である。
〇1990年代後半に、日本地域福祉研究所を中心に「韓日地域福祉実践研究セミナー」をソウル市、大邱市、釜山市、光州市などで開催してきた。
〇また、日本社会福祉学会会長、日本地域福祉学会会長時代の2000年初頭には学会の学術交流協定や日本介護保険制度に関わる学術交流をしてきた。
〇今回の訪韓は、学術交流としては久しぶりで、この20年間近い期間に韓国の福祉事情が大きく変化してきていることを『現代韓国の福祉事情』を読んで実感した。
〇『現代韓国の福祉事情』の編著者である、東大教授の金成垣先生の論文は大変参考になった。
〇金成垣先生の学説は、韓国の社会福祉・社会保障は、資本主義先進国で確立した従来の「福祉国家」体制ではなく、新しい「社会サービス国家」ともいえるもので、「社会保険でない制度」、「準普遍主義」に基づく政策が展開されているのだと指摘している。それを可能にさせているのが、「総合社会福祉館」、「老人福祉館」、「障害者福祉館」で、そこを拠点に地域福祉活動が展開されているのが特色だとも指摘している。
〇筆者は、日本地域福祉学会会長の時代(2000年代初頭)に「地域福祉実践・研究に関する日本と韓国の学術交流協定」を締結したが、相手の韓国の学会名は「韓国地域社会福祉学会」である。
〇韓国は、その当時、市町村の権限、役割も弱く、市町村社会福祉協議会の位置づけも法的にはない状態だった(韓国の市町村社会福祉協議会が法制化されたのは、確か2021年?)。
〇筆者は、地域福祉における日本との比較研究をする枠組の要は、「総合社会福祉館」等のセツルメント実践の流れである地域福祉施設が重要なのではないかと指摘してきた(ただし、「総合社会福祉館」の設置は人口10万人に1か所が目安)。
〇日本でも、近年の「地域共生社会政策」の中で、子ども、障害者、高齢者を問わず誰もが通い、集い、時には泊まれる全世代対応型の「小さな拠点」の設置の必要性がうたわれ、既に高知県などにおいて「ふれあいあったかセンター」の実践が、限界集落、人口減少地域で大きな成果を上げていることを考えると、韓国の「総合社会福祉館」や農村部の「マウル館」等と日本の「小さな拠点」施設との比較をしつつ、地域住民のインフォーマルケアをどう位置付けるかの比較研究をする必要性がある。
〇いずれにせよ、金成垣論文を読んで、日韓地域福祉比較研究の枠組みが大変明確になった。
〇ただ、金成垣先生は、従来の社会保障関係の学説である“現金給付とサービス給付は代替関係にある”という学説に囚われず、韓国では現金給付とサービス給付との関係は代替関係ではなく、補完関係にあると考え、新しい「社会サービス国家」という考え方を打ち出した。その在宅福祉サービス(韓国では在家老人福祉事業)を「総合社会福祉館」等で現物給付する形で提供しているのが特色だと指摘している。
〇金成垣先生の学説は、日本の在宅福祉サービスの開発、研究を牽引してきた三浦文夫先生がイギリスのティトマス等に学び、貨幣的ニーズでは対応できない非貨幣的ニーズの必要性が都市化、工業化、核家族化の中で生活ニーズとして登場してきており、その対応が必要であると論述してきたことや江口英一先生が1960年代の不安定就業層に対する地方自治体での福祉サービスの整備が必要であると論述した考え方との関りや整合性を改めて検討する必要があるのではないかとの感想を持った。
〇日本では、現在、1960年代末から指摘されてきている「新しい貧困」の問題がより深刻化し、生活のしづらさを抱えている家庭の生活技術能力や家政管理能力などへの支援の必要性が増大してきているし、かつ、「ひきこもり」と称される人が246万人にいると推計され、孤立・孤独問題が深刻化している。更には、一人暮らし高齢者、一人暮らし障害者の増大に伴うそれらの人々の身元保証問題、入退院支援、終末期支援、死後対応サービスの必要性が喫緊の大きな課題になってきている。
〇これらの問題も含めて、韓国の「社会サービス国家」論と日本の「地域共生社会政策」との比較研究が必要だと思った。
〇『現代韓国の福祉事情』に基づき、日本との比較の視点も入れて韓国の福祉事情の特色、特徴を述べるとすれば、以下の点を挙げることができる(概要で述べる内容は、『現代韓国の福祉事情』の中に書かれていることで、一つ一つ引用個所を明示するのは煩瑣になるので省略させて頂いた。ご了承頂きたい。なお、日本の記述は筆者の考えである)。
➀韓国は、人口が2022年時点で5169万2000人、2000年に高齢者人口比率が7%になり、高齢化社会になった。2017年には高齢者人口が14%を超え、高齢社会になっている。日本以上に速いスピード(日本は24年で到達)で高齢化が進んでいる。
子どもの合計特殊出生率は、OECD諸国の中で最低の0・78(2022年)で、日本の1・26よりはるかに低い。
韓国では、高学歴化における受験戦争の激化、ソウル一極集中における住宅難、不安定就業による生活の見通し不安等の要因が影響して少子化が改善されていない。
➁韓国では、就業形態別の雇用保険の加入率が、正規労働者で78・1%、非正規労働者で44・4(2019年)と低い。かつ、不安定就業層が多く、臨時雇用者の割合が2019年で24・4%、かつ自営業者の割合が24・9%と多く、「福祉国家体制」の下になる正規の常用雇用者による社会保険制度の成熟度が進んでいない。
韓国では、1999年に「国民皆保険・皆年金」体制が実現したが、2015年時点で、非正規労働者の年金加入率は37・0%、医療保険は43・9%、雇用保険は42・1%である。
日本では、高齢化社会に入った1970年前後に、急激な都市化、工業化、核家族化の中で、家族が高齢者を経済的に扶養できず、かつ年金も未だ成熟していていない時代であったこともあり、国が低所得層の高齢者に「老人福祉手当」を支給したことと同じように、韓国でも社会保険だけでカバーできない部分を国が税金によってサービスを現物給付する形態で賄っている。
➂日本の公的扶助制度である生活保護制度に該当するのが、現行の韓国では2000年10月に施行された「国民基礎生活保障制度」である。
韓国では2022年までは、「扶養義務者基準」が厳しく(扶養義務者の所得(年収1億ウオン以上)、および資産(保有不動産価格9億ウオン以上)があれば扶養義務基準を適用)、適用されていた。
他方、勤労能力のある貧困者には、多様な働く場としての自活事業が用意されているし、創業教育、機能訓練及び技術・経営指導等の創業支援、自活に必要な資産形成支援等が展開されている。
この自活事業の多様なプログラムは、韓国で2007年に制定された「社会的企業育成法」に基づき育成支援されている「社会的企業」、「協働組合」、「マウル企業」、「ソーシャルベンチャー企業」の取組とも関わっていて、「自活企業」だけでも2021年時点で997企業が経営されている。
日本では、生活困窮者などに対する支援で、“一般就労”支援が中心になっているが、韓国のように、新しいプログラムを開発しながらの支援は日本でも大いに参考にすべきである。
韓国では、このような状況もあり、社会福祉士養成カリキュラムに「プログラムの開発及び評価」、「社会福祉資料分析論」が取り入れられている。かつ、「総合社会福祉館」には、社会福祉士が義務設置化されていて、外部資金の獲得や地域資源の開発・連携に取り組んでいる。
筆者、コミュニティソーシャルワーク研修において、「問題解決プログラムの企画立案」や「地域福祉・地域包括ケア基本情報シート」の作成を取り入れているが、考え方は全く同じである。日本の社会福祉士の養成カリキュラムが“時代錯誤”なのである。
➃韓国では、「長期療養保険制度」がドイツ、日本に学び2008年7月から導入された。
しかしながら、日本で2006年に始められた介護予防事業は制度化されていない。
韓国の介護予防事業は、全国に357か所あり、300万人の会員を擁している「老人福祉会館」で展開されている。その活動を支える従事者が14000人配置されている。
日本では、1990年代に全国社会福祉協議会が主導して全国各地の市町村社会福祉協議会が「住民参加型福祉サロン」を創設し、活発な活動を展開していた。
しかしながら、2000年の介護保険制度の実施の際に、国民の理解を得るためか、福祉サロンに通う高齢者も介護保険制度のデイサービスを利用できるようにしたことにより、「住民参加型福祉サロン」は衰退していく。
ところが、介護保険財政が厳しくなると、2006年に介護予防事業制度を導入し、再度「住民参加型福祉サロン」を推奨させるようなシステムを作り出す。
韓国では、一貫して介護予防は老人福祉館で行われている。老人福祉館は、1989年にモデル事業として取り組み始められた。
老人福祉館の基本事業は、「生涯教育支援事業」、「趣味余暇支援事業」、「相談事業」、「情緒生活支援事業」、「健康生活支援事業」、「社会参加支援事業」、「危機および独居高齢者支援事業」、「脆弱老人保護連携網構築事業」の7つである。
選択事業としては、「敬老堂革新プログラム」、「高齢者住居改善事業」、「雇用および所得支援事業」、「家族機能支援および統合支援事業」、「地域資源の開発と連携、高齢者権益増進事業」の5つがある。
この老人福祉館は「地域食堂」の機能も持っており、安価な3000ウオン程度で利用でき、かつ生活困窮者には無料で昼食が支給されている。
老人福祉館の個人の利用料は3か月で2万ウオンから4万ウオン程度である。老人福祉館の運営費は、市区町村からの補助金の他、共同募金、協賛会費などで賄われている。
➄日本でも「離別によるひとり親世帯における非養育者の養育費不払い問題」は深刻で、母子家庭における養育費を支払っている非養育者の比率は28%と言われている。
韓国でも同じような問題を抱えており、2014年に「養育費履行確保法」が制定され、かつ2020年からはそれがより強化され、「行政制裁として、運転免許停止処分及び出国禁止、身元公開(氏名、年齢、職業、住所、養育費債務不履行期間、養育費債務額)」が規定され、かつ刑事罰まで法制化された。
日本でも、行政が代執行して養育費を支払わせる制度の確立が望まれている。
➅日本では、2023年5月に「孤独・孤立対策推進法」が制定され、孤独問題担当大臣を設置するほど孤立・孤独問題は深刻化している。
筆者が、孤立・孤独問題に関心を寄せたのは、旧自治省系の自治行政センターの依頼を受けて、「行政とボランティア活動との関係に関する調査研究」で、三浦文夫先生とヨーロッパ諸国を訪問した1982年である。
その際、スウエーデンを訪問したが、スウエーデンのソーシャルワーカーが日本の老人クラブの実践を学びたいと話をした。その理由が、スウエーデンではその当時、高齢者の孤立・孤独問題が深刻で、日本の老人クラブ活動に学びたいということであった。
当時の日本の老人クラブへの加入率は75%程度(現在は17%程度)あり、地域の老人たちがクラブ活動をすると同時に、地域の一人暮らし老人たちへの友愛訪問活動をしていることを参考にしたいという話であった。
その後、イギリスでは2018年に孤独担当大臣を設ける等、ヨーロッパ諸国での孤立・孤独問題は深刻化していった。
韓国では、2020年3月に「孤独死予防法」が制定された。これに先立つ対策として、2007年に「老人福祉法」が改正され、独居高齢者支援が法定化された。
2020年には、「老人個別型統合サービス」に統合整理され、安全支援、社会参加、生活教育、日常生活支援という「直接サービス」、生活用品支援、住居改善、健康支援等の「連携サービス」、孤立型グループ、抑うつ型グループへの「特化サービス」の業務が展開されるようになった。
「老人個別型統合サービス」の実施機関は2023年時点で全国681か所あり、その中で「特化サービス」を実施している機関は191か所である。
「老人個別型統合サービス」の実施機関には、専担社会福祉士と生活支援士が配置され、対象者選定とケアマネジメント及びソーシャルワーク機能を担当している。
➆韓国では、日本以上に少子化が進んでおり、労働力をカバーするために、日本以上に外国人労働者を受け入れている。2022年末現在で、韓国の在留外国人は224万59912人で、全人口の4・37%を占めている。
これらの在留外国人の生活支援のために、韓国では2007年に「在韓外国人処遇基本法」を制定している。また、2008年には「多文化家族支援法」を制定し、韓国の社会福祉事業による福祉的支援に法的根拠を持たせることになった。
「多文化家族支援法」では、多文化家族に対する理解促進、生活情報の提供および教育支援、家庭内暴力被害者に対する保護・支援、医療および健康管理のための支援、多言語によるサービス提供および「多文化家族向け総合情報コールセンター」の設置・運営、外国人支援を行っている民間団体への支援等が定められている。
これらの法律でいう「在韓外国人」とは、韓国の国籍を持たないもので、韓国に居住する目的で合法的に滞在している者、「結婚移民者」とは、韓国の国民と婚姻したことがある者または婚姻関係にある在韓外国人である。
一方、「多文化家族」とは、「結婚移民者または韓国の国籍を取得した者からなる家族」のことで、外国人夫婦のみの世帯、外国人労働者、留学生は含まれていない。しかし、近年では、多分化家族の定義を広く適用しているという。
韓国での在留外国人への政策は、日本でも学ばなければならない課題である。
➇韓国は、国連の世界デジタル政府ランキングで、1位、2位を競うレベルのデジタル化が進んでいて、日本の比ではない。
韓国のデジタル政府を推進する根拠法は、1995年制定の「情報化促進基本法」、2000年の「デジタル政府法」、2009年の「国家情報化基本法」によるところが大きい。
福祉業務に特化した情報システムとしては、2010年に「社会福祉統合電算網」によるところが大きい。
それは、社会保障基本法の中で、「社会保障の受給者の決定や給付管理などに関する情報を統合・連携して処理する情報システム」であり、それは保健福祉部(日本の厚生労働省に該当)の福祉事業の業務を電子処理する「幸福eウム」と各省庁の福祉事業業務の電子処理を支援する「凡政府」との2種類がある。
「幸福eウム」は、地方自治体福祉業務と連繋して、各種社会福祉サービスの給付や受給資格、受給履歴の情報を統合管理している。
この2つの情報管理により、国税庁や国民健康保険公団、国土交通部(日本の国土交通省に該当)等の公共機関の所得及び財産情報を活用して不正受給や死亡届の提出遅延、未提出による“受給の不正”を防止している。
また、この情報システムを活用して、申請主義のために、本来受給できるにもかかわらず申請できない人を発見・把握し、支援につなげられるようになった。
更には、2014年12月に「社会保障給付の利用、・提供及び受給権者の発掘に関する法律」が制定され、電気料金や水道料金の滞納等公共料金の滞納にも関わらず、社会福祉関係者がアウトリーチできていない世帯を発見・把握し、職員を家庭訪問させ、申請につなげられるようになった。
一般的に、ICT化は低所得者や低学歴の人の生活に及ぼす影響・効果は限定的で、ややもするとのその利活用から疎外されがちであるが、韓国では逆にそれらの人々へのアプローチの手段として活用できていることは注目に値する。
いまや、福祉サービスへの福祉アクセシビリティがぜい弱な人々を発見・把握するために活用する情報は、通信費滞納、金融債務滞納、健康保険料滞納等にまで広がり、44種類にも上っている。
➈「マウル館」は、“地域社会の中心地として機能し、街の集まり、地域の市場、祭りなどの各種活動ができるように一定の設備を備えた建物で、一般的に多目的ホール、小さな会議室、演劇場、キッチン、トイレ、駐車場などの設備が含まれる”施設である。
「マウル館」(韓国語辞書では、マウルとは主に田舎でいくつもの家が集まって住むところと定義されている)は、1970年代のセマウル運動のセマウル会館として全国的に設置されていったが、現在は行政上の明確な管理主体がない状態である。
現在、「マウル館」は、全国に36792か所設置されており、自宅から「マウル館」まで10分以内の距離に設置されている村が95・5%である。距離的アクセシビリティはすこぶるいい。
「マウル館」は、1階建ての単独建物が多く、「敬労堂」と複合的に運営されているところが多い。
「マウル館」でも「地域食堂」としての機能を有しており、一日1回の食事提供が最も多く、69・3%、一日に2回の食事提供するところが22・3%である。
「マウル館」の運営は、里長(自治会長)が最も多く68%、老人会長が運営するところが24・1%である。
食事の提供に関わる経費は、住民たちが分担するが30・6%、「マウル運営資金の支援」が28・3%、「政府と自治体の支援金」が19・8%である。
農村地域の高齢化率は2020年時点で46・8%となっており、冬の期間、各自の自宅で暖房をつけるのには経費が掛かるが、「マウル館」に居ればそれも節約できることから、暖房施設のある「マウル館」の冬の期間における存在意義は大きい。
韓国の228自治体のうち、113の自治体が消滅危機にあるなかで、「マウル館」を拠点にしての地域づくりは、日本の限界集落との比較研究をする上で重要である。高知県の「ふれあいあったかセンター」がその比較研究する上で最適である。
➉「総合社会福祉館」は、韓国・社会福祉事業法第2条で「地域社会を基盤に一定の施設と専門人材を備え、地域住民の参加と協力を通じて地域社会の福祉問題を予防または解決するために総合的な福祉サービスを提供する施設」と規定されている。
「総合社会福祉館」は、2023年現在、全国に479か所設置されており、人口10万人当り1か所の目安で設置されている。
当初、「総合社会福祉館」は、低所得者が密集している永久賃貸住宅団地を中心に設置が進められたが、その後戸別の住宅面積が狭い住宅団地住民の生活福利のための共同の福利施設として住宅法が改正されて、設置、利用が少し変容していく。
「総合社会福祉館」は、「地域社会の特性や地域住民のニーズを踏まえた事業」、「官民の福祉サービスを連携した事例管理事業」、「地域の福祉共同体の活性化を目指した福祉関連の資源管理や住民教育」、「住民組織化等に関する事業」等が社会福祉事業法第34条の5に規定されている。
利用対象者は、社会福祉館の位置する地域のすべての地域住民となっているが、特に国民基礎生活保障の受給者や生活困窮者、障害者、高齢者、一人親家庭、多文化家庭、保護と教育が必要な幼児・児童・青少年、その他緊急支援が必要と認められるものが優先されると社会福祉事業法34条の5で規定されている。
全国の社会福祉館479巻のうち、社会福祉法人運営が約7割(338か所)、次いで財団法人、社団法人は都築、地方自治体の運営もある。
社会福祉館は、その建物の大きさにより「ガ型」、「ナ型」、「ダ型」に分けられている。
その運営費はおおむね年間予算が10~30億ウオンである。
社会福祉館の専門人財の配置は、「事例管理」、「サービス提供」、「地域組織化」、「行政及び管理」を実施しているかどうかと、その設置されている地域が「特別市」、「広域市」、「特例自治市・道・特例自治道」の違いによっても配置される人材数が異なる。
韓国の「総合社会福祉館」の源流は、1906年アメリカの宣教師・メソジスト教会の女子宣教師であったメリー・ノールズが始めた元山での隣保館運動で、その拠点が「班列房(バンヨルバン)」であった。その後、キリスト教関係者や大学関係者によって「社会福祉館」は作られていく。
「総合社会福祉館」としての制度化は、1983年に社会福祉事業法が改正され、社会福祉館への財政支援と地域住民の利用施設としての位置づけが規定されてからである。
韓国では、1998年に社会福祉士1級国家試験制度が実施され、今では社会福祉館の採用条件に社会福祉1級を条件としているところがほとんどである。
Ⅱ 韓国で2026年3月から実施される『医療·介護など地域ケアの統合支援に関する法律(ケア統合支援法)』の概要――韓国・崔太子さん提供資料