「老爺心お節介情報」第76号
地域福祉研究者の皆様
社会福祉協議会関係者の皆様
「老爺心お節介情報」第76号を送ります。
本文に張り付けができなかったので、添付ファイルでの(註)が3つあります。
皆様、ご自愛の上ご活躍下さい。
2025年10月1日 大橋 謙策
そのときの出逢いが
出逢い そして感動
人間を動かし 人間を変えてゆくものは
むずかしい理論や理屈じゃないんだなあ
感動が人間を動かし
出逢いが人間を変えてゆくんだなあ・・・
(相田 みつお)
『「そのときの出逢いが」――私の生き方、考え方に影響を与えた人との出逢い』➁
Ⅱ 日本社会事業大学卒業後から大学院修士課程修了を経て、日本社会事業大学専任講師就任までの時代―主に社会教育活動での出逢い
➀東大大学院修士課程入学から1970年
〇筆者は、1967年に日本社会事業大学を卒業し、東大教育学部宮原誠一研究室の研究生になる。
〇大学院に進学して、できれば研究者の道に進みたいと決意した日本社会事業大学の4年生の時には、おぼろげながら「社会教育と社会福祉の学際研究」をしたいと考えるようになった。
〇研究者の道への選択と研究テーマに大きな影響を与えてくれたのが、小川利夫先生が1962年、37歳の時に書かれた論文「わが国社会事業理論における社会教育観の系譜―その『位置づけ』に関する一考察」(日本社会事業大学研究紀要『社会事業の諸問題』第10集)であった。奇しくも、私も小川先生と同じようなテーマで修士論文を書くことになる(修士論文テーマ「戦前社会事業における『教育』の位置」)。
〇大学院研究者への進学を志した日本社会事業大学の4年時は、相変わらず教育科学研究会などに出入りし、群馬県島小学校での実践で一世を風靡した斎藤喜博先生の研究会にも出入りし、教育実践の考え方、方法などについても学んだ(後に発刊された『斎藤喜博全集』を購入したが読み切れなかった。『島小の実践』等単行本の幾冊かは読んだ)。
〇他方、社会福祉論(当時は「社会福祉学」とは言えず、「社会福祉論」であり、体系化された「社会福祉学」への構築を目指した。筆者が、「社会福祉学」を躊躇なく使用するようになったのは、2003度から日本学術会議において日本学術振興会の科学研究費の細目として「社会福祉学」が認められ、「社会学」から独立した時からである)については、当時労働経済学を学ばなければ駄目だと言われていた時代でもあり、大河内一男、氏原正治郎、隅谷三喜男、戸塚秀夫等の著作を読んだ(後日談になるが、日本社会事業大学の専任講師になった際、日本社会政策学会に入会しろと言われた。日本社会政策学会は日本社会福祉学会の親学会だから入会しろと言われたが、私は入らなかった。また、当時は、大河内一男の昭和13年論文「我國に於ける社会事業の現在及び将来―社会事業と社』第22巻5号、昭和13年8月)は社会福祉論を学ぶ者の必読文献と言われ読んだが、なぜ社会事業が労働経済学の社会政策の“補充・代替”の位置にあるのか疑問に思い、納得しなかった。仲村優一先生の『社会福祉概論』は“補充・代替説に立脚している)。
〇そのような経緯もあり、社会福祉論を憲法第25条を法源とする社会的生存権の位置づけだけでいいのかと疑問を持つようになるし、当時の社会福祉学界の通説である「狭義の社会福祉と広義の社会福祉」という言い方には幻滅を感じることになる。
〇そんな折、1967年に『経済学全集22「福祉国家論」』(小谷義次編著)の別冊に収録された江口英一先生の論文「日本における社会保障の課題」を読み、これこそが「社会教育と社会福祉の学際研究」をする際の道しるべだと思った。
〇その当時は、何故か別冊という方式が出版界で流行っていた。少年雑誌などの付録付き雑誌と同じ感覚だったのか分からないが、紙の装丁箱に入っている『福祉国家論』に江口論文は柴山幸治著「福祉国家と経済計画」という論文とともに別冊として入っていた。筆者にとっては、本体の本よりも別冊の江口論文の方が面白かった。
〇この江口論文に示唆されて、対人援助としての社会福祉は国家レベルの政策ではなく、市町村自治体レベルで整備され、システム化されるべきだとの確信を得た。
〇筆者の地域福祉研究は、江口英一学説と岡村重夫学説を乗り越えようとするところから始まった。
➁1970年は筆者の人生の大きな節目
〇1970年は筆者にとって、「人生の大きな節目」であった。
〇「第1の節目」は、1970年3月に東京大学大学院修士課程を修了したことである。「東大紛争」等があり、必ずしも全力で取り組めたとはいえないまでも、東大の中央図書館の地下に個室閲覧室を借りられて、資料を必要なだけ借りて読み、書けたことは自分にとって大きな財産になった(後日談になるが、日本社会事業大学の清瀬移転に伴い、図書館棟を建設できたので、そこに教員や大学院生が研究できるように個室の閲覧室を設けたが、利用者は少なく、後日廃止された。日本社会事業大学大学院の院生の研究能力、研究姿勢に正直落胆した)。
〇修士論文の審査は、宮原誠一教授、碓井正久教授、裏田武夫教授(図書館学)、藤岡貞彦助手などの教員の列席の他、多数の院生にも公開される修士論文公開審査会であった。
〇修士論文のテーマは、拙著『地域福祉の展開と福祉教育』、『地域福祉とは何か』にも収録させて頂いたが、「戦前社会事業における『教育』の位置」である。
〇その審査結果は、宮原誠一先生から良い評価を頂いたが、宮原先生から今度は「社会教育における社会事業の位置を」を研究する必要があるのではないかとの指摘を受けた。
〇宮原誠一先生は1970年3月で退官されたので、最後の指導を受けた院生だった。修士課程を修了し、かつ博士課程への進学も認められた。博士課程での指導教授は碓井正久先生にかわった。
〇1970年の「第2の節目」は、1970年4月26日に日本社会事業大学の同級生の渡部貴恵と結婚したことである。
〇渡部貴恵とは日本社会事業大学1年時の夏休みに一緒に神奈川県立中里学園のボランティア活動を行った。3年次の社会調査実習では、同じ小川利夫班(助手 高澤武司先生、後に岩手県立大学ソーシャルワーク学部学部長)で「中卒青年の集団就職調査」を行い、かつ3年次からは「教育科学研究会」で一緒に雑誌「教育」の勝田守一論文を輪読した仲であった。
〇日本社会事業大学卒業時には、将来一緒になろうと結婚の約束はしたものの、渡部貴恵は東京都職員、私は研究生で将来が見通せない状況だったので、東大大学院の修士課程を修了したら結婚しようということで、1970年4月26日に結婚式を挙げた。新婚旅行の費用は全て渡部貴恵が負担してくれた。結婚のお祝いに夫婦茶碗を2組頂いた(一組は煎茶用の九谷焼で、仲村優一先生から頂いた。もう一組は栃木の方で益子焼のほうじ茶を飲む夫婦茶碗である。その二組の夫婦茶碗は壊れることなく、結婚後55年の現在も毎日使われている)。
〇1970年の「第3の節目」は、女子栄養大学の助手に採用されたことであった。
〇女子栄養大学で教育学を教えていた柴田義松先生から小川利夫先生に話があり、私が女子栄養大学の社会福祉論を担当する助手として採用された。
〇柴田義松先生は、教育科学研究会のメンバーで斎藤喜博先生と教授学部会を作って活躍していた先生で、旧ソ連のレフ・ヴィゴツキーの『思考と言語』の翻訳者でもあった(柴田義松先生は1985年に東大教育学部助教授に転出、のちに教授。日本教育方法学会会長。柴田義松先生の影響もあって、スイスの心理学者・ピアジェの『言語と思考』を齧ったりした)。
〇女子栄養大学の助手の話があった際、私は東大大学院の博士課程に在籍したまま、助手になれるなら受諾しますと生意気にも条件を出し、それが認められて大学院との2重籍で就職した。
〇女子栄養大学の助手の待遇は、一般事務職員と同じように朝から夕方まで勤務する形態で、朝出勤すると出勤簿に押印しなければならなかった。授業を担当する助手なのに、一般教養科目を担当する教室(教授3人)の掃除、お茶くみ、雑務を命じられた。他の実験系教室の助手は助手とは名前が付いているものの、副手か事務職員のような扱いであった。
〇東大紛争を見てきたものにとって、これは看過できないので、まず助手会を組織化した。心ある助手たちと話をし、助手会を作り、助手の地位向上のために助手会の機関誌『あしすたんと』を1971年に創刊した。創刊号の巻頭言を筆者は書いており、そこで助手会結成の目的を“女子栄養大学は「食」にかかわる研究をする単科大学であり、その栄養大学における研究等はどうあるべきかを志向しつつ、助手の研究体制を向上させるところにある”と述べている。
〇助手会の滑動もあって、①出勤体制を教授たちと同じフレックスタイム制にできた、②主任助手制度を創設してもらい、待遇改善を図った、③教授会に助手会の代表を出席させることなどの改善が図れた。
〇このような活動を助手会会長として主導したので、講座制の強い実験系の教授に睨まれ、大学院博士課程と女子栄養大学の2重籍は認めないといわれ、3年半で女子栄養大学助手を退職した。いまとなっては、給料をもらえる助手を継続し、博士課程を退学する道を選べばよかったと後悔しているが、その当時は研究者の道を選んだ以上博士課程を全うしたいと考えていた。
〇助手の籍を失ったので、1973年1月から日本社会事業大学の専任講師に採用される期間、東京都職員であった妻の扶養家族になった。当時、男が妻の扶養家族になるという発想がなく、随分もめたそうだが、結果として認めてもらった。収入の面は、三鷹市勤労青年学級の講師をしていたので、それなりにあったが、健康保険面で扶養家族にならざるを得なかった。
➂稲城市社会教育委員と「社会教育推進全国協議会」、「社会教育学会」の活動
〇1970年4月、我々夫婦は東京都南多摩郡稲城町に移住した。稲城町は、1971年に3万人特例市として稲城市に昇格した。
〇稲城市に昇格することもあってか、稲城市教育委員会に社会教育主事が設置されることになった。東京都教育庁からの依頼もあって、小川利夫先生は日本社会事業大学で筆者の2年後輩の川廷宗之さん(後の大妻女子大学教授)を紹介した。当時、日本社会事業大学には社会教育主事養成課程があった。
〇川廷さんとは、顔見知りだったこともあり、かつ筆者が東大大学院で社会教育を専門に学んだ人ということで、弱冠26歳の若さなのにいろいろな機会を与えて頂いた。1969年に設置していた稲城市社会教育委員の会議の委員に筆者を推薦してくれた。
〇早速、稲城市社会教育の礎になる稲城市社会教育委員の会議で、稲城の社会教育の将来像を論議し、1972年に「公民館及び図書館の運営について」と題する答申を出し、①公民館7館構想、②社会教育主事等の専門職の採用、③公民館運営審議会、図書館運営協議会等の住民参加の手立ての保障、④後述する「公民館3階建て構想」の実現を提言する。
〇稲城市においては、それまで公民館や図書館はなかったが、婦人会や青少年委員会による活動が活発で、東京都内でも一目置かれる活動をしていた。
〇稲城に戦前移住してきて、いろいろ生活改善などの活動をしていた当時の社会教育委員の会議の議長の勝山道子さんや稲城市で最初の女性議員になる富永ヨシ子さん等、外部からの移住者がある意味婦人会の活動を活性化させていた。
〇一方、青少年委員活動としては、長坂泰寛さんや川島実さん等の地主層が頑張ってくれていた。
〇社会教育委員の会議は、移住組の人々と地元の土着民である、地主層の白井威さん(後の東京都議会議長、東京都社会福祉審議会でも筆者と同席)等が混在して、“新しい稲城のまちづくり”をしようと活気に満ちた論議をしていた。この時期は、稲城市の公民館の整備計画等これからの稲城市の社会教育のあり方、プランを立てるという楽しい時期であった。
〇社会教育主事も川廷宗之さん以降、毎年のように採用され、浜住治郎さん(現、被団協事務局長)、向山千代さん、霧生久夫(?)さん、霜島義和さんなどが採用され、研究会を作り、稲城の社会教育の楽しい夢を語った。
〇稲城村は明治22年(当時人口3600人、現在9万5千人)に7つの村が合併して発足するが、社会教育委員の会議はその合併した旧村(稲城市の大字単位)毎に一つの公民館を立てるという7館構想という画期的な答申を社会教育委員の会議はした。その構想は現在実現している。新しく大規模開発された地域にも必ずコミュニティセンターか文化センターが設置された。
〇1973年に最初に建てられた公民館は、1960年代に東京都三多摩で論議された「公民館3階建て論」に基づき、1階はロビー及び軽食が摂れるコーナーとホール、2階は社会教育団体事務室(共同使用の印刷機器やロッカーなどを整備)及び集会室、3階は図書館、4階は学習・研修室といった、当時の最先端の考え方を反映したものになった。この公民館には市役所の職員が常駐する保育室を設置した(1947年に制定された児童福祉法の保育所の目的の一つに、女性の社会参加と地位向上のために保育所が必要と考えられていたことを援用)。
〇筆者は、新しくできた中央公民館において、1974年に「住みよい稲城を創る会」(代表大橋謙策)主催の「稲城の福祉を考える集い」を開催した。公民館に約400名近くが集まり、「父子家庭の子育て」、「学校拒否児の課題」、「嫁の立場での舅、姑の介護」の体験発表を聞いて頂き、その後分科会に分かれてグループワークが行われた。体験発表者を探すのには苦労したが、大成功を収めた。「学校拒否児」の親御さんが15名も来られていて、急遽その分科会を作らざるを得なかったことがとても印象的であった。
〇この頃、筆者は江口英一先生が指摘されたように、住民の暮らしを守るためには市町村の社会福祉サービスを充実させることが重要だと考え、稲城市の社会福祉問題にも関心を寄せ、保育所づくり運動や就学援助制度の改善を図っていた。就学援助制度は、文部省(当時)基準でいくと生活保護基準の1・5倍であったが、筆者は1・8倍まで引き上げるべきだと陳情し、結果的に1・6倍になった(当時、長崎県香焼町が1・8倍で、筆者は長崎まで視察に行った)。
〇保育所づくりでは、公民館保育室は設立できたが、保育所の増設はなかなか進まなかった。そうこうするうち、我が家に子どもが産まれ、保育所入所を申請したが、市役所は“保育に欠けることは認めるが、保育所に空きがない”と申請却下の措置決定通知書を寄越した。ご丁寧に、その決定通知書には、“この決定に不服がある場合には、児童福祉法、行政不服審査法に基づき、不服申し立てができます”と書いてあった。
〇筆者は、不服申立制度があることは当然知っており、福祉事務所に電話をして、あれだけ保育所増設の必要性を言ってきたのに、”保育所に空きがない“から措置できないというのなら不服申し立て制度を活用して不服申し立てをします。1週間後に不服申し立て書を提出しますと福祉事務所に通告をした。1週間後、福祉事務所から電話があり、”保育所に空きがでましたので、入所してください“ということで、”不服申し立て騒ぎ“は終わった。
〇筆者は、その後も保育所増設運動や保育料の適正化運動を行い、稲城市保育問題審議会や稲城市社会福祉委員会等を行政に設置させ、住民参加の社会福祉行政のあり方を追求してきた。
〇稲城市では1975年4月に統一地方選挙があり、筆者が代表を務めていた「住みよい稲城を創る会」からも候補者(須恵淳さん。稲城市市議会議員、コマクサ幼稚園園長)がでて、現職の森直兄候補と争ったが、敗退する。そのような敵対行為をした筆者を森直兄市長は、干すことなく、社会教育委員も保育問題審議会の会長も続投させてくれた。のちには、「稲城市地方自治功労賞」まで授与された。
〇敗れた須恵淳さんには、コマクサ幼稚園の副園長として手伝えと言われ、それから10年間、非常勤で副園長を務めることになる。この時は、教育科学研究会で学んだことが大いに生かされた。
〇1970年前後の筆者の滑動は、「社会教育と社会福祉の学際研究」とはいうものの、圧倒的に社会教育分野での活動が中心であった。
〇東大の宮原研究室の研究生にも関わらず、「社会教育推進全国協議会」(国土社の「月刊社会教育」の読者が中心に、1963年に設立され、民主的社会教育推進の全国セミナーを毎年8月各地持ち回りで行っていた。その活動に筆者は参加していた)や修士課程に入学した際には、小川利夫先生の推薦を頂き、日本社会教育学会の会員になった。
〇また、筆者が日本社会事業大学の卒業生で、それなりに社会福祉分野が分る人として認識されていたのか、1960年代末からの東京都立三多摩社会教育会館での障害者の青年学級の調査研究や1970年に東京都教育庁が始めた「市民の自主企画による市民講座」のあり方プロジェクトの「社会福祉コース」の講師を命じられた。
〇立教大学の室俊司先生(東大宮原研究室出身)ともども、都内各地から選ばれた、各地の婦人(当時の使用語)の地域活動のリーダーたちと「自主企画による市民講座」のあり方を論議した。「社会福祉コース」には、練馬区から世良田さん、杉並区から杉山さん、文京区から若林さん、品川区から山口さん、板橋区から手嶋さん、世田谷区から植村さん等、各地域の若手の女性リーダーたちが地域づくりに燃えて参加してくれていた。
〇「社会福祉コース」では、当時出版された「自分たちで命を守った村」(岩波新書)を読んで学習していることもあって、「社会福祉コース」のメンバーで、岩手県沢内村を1970年に訪ねた。
〇当時の、大田祖電村長や、深沢正雄元村長の奥様(当時、沢内村社会福祉協議会の事務局長)、高橋典茂さんらに深沢村政が始めた「自分たちで命を守った村」の理念、活動について話を聞き、感動した(沢内村には、その後もたびたび訪問し、1990年には沢内村地域福祉活動計画「コーリムプラン」を作成し、「コーリム大学」を開催した)。
〇コースの人々とは、東京都教育庁の事業が終わった後も、月1回女子栄養大学の松柏軒で食事を取りながら勉強会を続けた。
〇そんな経緯も作用したのか、1971年の第8回社会教育全国集会では「権利としての社会教育とはなにか」のテーマで基調講演を任された。このテーマは、日本社会事業大学の小川政亮先生の著作『権利としての社会保障』をもじったものであった。その縁で、1972年に、雑誌『都政』に「権利としての社会教育と社会教育行政」という論文が掲載された。
〇1969年には、日本社会教育学会紀要第5号に「社会教育主事の「専門職化」に関する一考察」を書いたし、1971年には『日本の社会教育 第15集 社会教育法の成立と展開』(日本社会教育学会編、東洋館)に「社会教育法制と社会事業―地域福祉を巡る隣保館と公民館」という論文が採択され、収録されている。
➃「社会教育と社会福祉の学際研究」の萌芽と『月刊福祉』への登場
〇1970年に大学院修士課程を修了して、研究者への道が見通せるようになったので、本来研究テーマにしていた「社会教育と社会福祉の学際研究」を隣保館や地域福祉との関りで深めようと考えた。
〇この頃、小川利夫先生、永井憲一先生(法政大学教授)、平原春好先生(東大教育学部教育行政専攻)らと日本教育法学会の設立と研究会が持たれていた。筆者は、その研究会の事務局を担っていたということもあり、1972年に勁草書房より刊行された教育法学叢書第2巻の『教育と福祉の権利』に執筆の機会が与えられた。「へき地教育・夜間中学――貧困の世代継承と「教育福祉」」と題して執筆した。小川先生、永井先生からは「貧困の世代継承」という表現はどうなのだろうかと疑問が出たが、筆者は“貧困が世代を超えて継承されてしまっていることが問題であり、それを断ち切る教育と社会福祉にならなければならない”と言い張り、この表現を認めて頂いた。
〇この論文を書くに当たって、糀谷中学や小松川第4中学(?)等の夜間中学を訪問調査し、夜間中学の先生方との交流や高野実(?)さんが書いた「夜間中学」という本を読んだりした。
〇また、それの延長で、時期は少々後になるが、一粒社から1978年に刊行された『教育と福祉の理論』(小川利夫・土井洋一編)の編集実務を担当し、「社会問題対応策としての教育と福祉―戦前の歴史的構造の一考察―」を書かせて頂いた。
〇そのような研究生活を送っていた折、日本社会事業大学の1年先輩の和田敏明さん(筆者は、和田さんを「ミスター社協」と呼んでいる。全社協の地域福祉部を主に歩き、最後は事務局長、その後ルーテル学院大学教授、『和田敏明 地域福祉実践・研究のライフヒストリー・社会福祉協議会の変遷とこれからへの期待及び提言』(香川県社会福祉協議会刊、2024年3月参照))が全国社会福祉協議会の地域福祉部に勤務していたことや、東大教育学部社会教育学科出身の根本嘉昭さん(後の厚生省専門官、立正大学教授)が全社協に就職したということもあり、全社協地域福祉部に出入りするようになる。
〇丁度その頃は、1969年に「コミュニティー生活の場における人間性の回復」(国民生活審議会報告)がだされ、文部省も厚生省も含めて各省庁挙げてコミュニティ政策に取り組んでいた時代である。
〇同じように、全社協も、1971年5月に「地域福祉センター研究委員会報告案」を出す。また、1971年6月には「福祉事務所の将来はいかにあるべきかー昭和60年を目標とする福祉センター構想」(社会福祉事業法改正研究作業委員会報告)が出され、戦前のセツルメントや隣保館の“再生”が謳われたことに感動し、自分が行おうとしている「社会教育と社会福祉の学際研究」はまさに、この地域福祉センター構想を拠点に展開できるのではないかと喜んだ。
〇1971年7月に行われた全社協、神奈川県隣保事業協会主催の「全国地域福祉センター研究協議会」に胸躍らせて参加した。しかしながら、論議の中心は、その当時の隣保館の経営、運営をどうするかということに終始していて、筆者はいたたまれず、隣保館の今後のあり方とその実現のあり方を論議する場ではないのかと質問した。横須賀キリスト教会館の阿部志郎先生が、後日“大橋君はあの時発言したね”と覚えていてくださった。
〇当時の全社協職員の中には、日本社会事業大学卒業生が沢山いた。学部だけでなく、研究科、専修科、短大の卒業生が多くいた。それは、戦後初期に、戦前の海軍博物館の跡地利用で、日本社会事業大学のみならず全社協等の社会福祉団体が一緒に事務所を構えていたことも影響していたのかもしれない。
〇多分、そんなことも影響しているのだと思うが、全社協職員には「社会教育と社会福祉の学際研究」をしている筆者をある意味使い勝手がよかったのかもしれない。1973年11月には、『月刊福祉』に「新しい貧困と住民の教育・学習活動」を書かせてもらっている。また、1977年1月号の『月刊福祉』に「社会福祉のための社会教育―その三つの枠組み・試論―」、1977年10月号の『月刊福祉』に「地域福祉の主体形成と社会教育」という論文を書いている。
〇そのような縁があったからか、全社協出版部の矢口雄三さん(日本社会事業大学の同窓生)の薦めもあって、1978年2月には全社協出版部から『社会教育と地域福祉』を編著として刊行出来た。
〇この編著では、実践編では1960年代から取り組んできた「障害者の社会教育」(西宮市の肢体不自由者の生活学習と町田市の大石洋子(東大教育学部出身の社会教育主事)さんの心身障害者の青年学級の実践を取り上げた)や体系的高齢者の生涯学習を推進していた兵庫県の「いなみ野学園」等を取り上げた。
〇また、地域福祉分野の実践では、山形県社会福祉協議会が推進していた地域保健活動である「かあちゃんの病気をなくす運動」を渡部剛士先生に、ノーマライゼーション思想に基づくまちづくりとして、田代国次郎先生(当時東北福祉大学教授)に「福祉モデル都市」第1号になった「仙台・福祉のまちづくり」について書いて頂いた。
〇理論編としては、「教育と福祉」の理念・構造や「教育と福祉」の歴史的系譜等筆者が書き留めてきた論文を収録させて頂いた。
〇1972年から日本社会事業大学の非常勤講師を務めていたこともあり、日本社会事業大学の小川政亮先生には『扶助と福祉』(至誠堂、1973年刊)に「『世帯保護』の原則と「教育を受ける権利」、「入院助産制度―子どもの私有性と社会性」、「母子家庭と世帯の自立助長―母子福祉資金問題」を書かせて頂いた。
〇また、鷲谷善教先生には、1973年刊の『社会福祉労働論』(鳩の森書房)で「児童指導員解雇事件に内在する課題」という論文を書かせて頂いた。この論文は、児童養護施設に根強くあった、模擬家庭観に基づく実践と“滅私奉公的職員論”の在り方を批判し、科学的支援論の必要性を問うたものであった。
➄1974年4月に母校の日本社会事業大学の専任講師に就任
〇小川利夫先生が「教育制度検討委員会」の事務局長に就任されるなど忙しくなり、かつ名古屋大学への転出も決まっていたので、日本社会事業大学には、1972度から非常勤講師として勤めていた。
〇この当時は、聖心女子大学(橋口菊先生、東大教育学部社会教育専攻)、千葉大学(福尾武彦先生・社会教育学、中島紀恵子先生・看護学)、成蹊大学で社会福祉論を教えると同時に、和光大学で社会教育を教えた。和光大学では、講義の他に、非常勤にも関わらずゼミナールも担当し、12年間教えた。
〇1974年4月、母校の日本社会事業大学の専任講師に就職できた。実は、この時、東京学芸大学の小林文人先生(九州大学教育学部出身、社会教育推進全国協議会のメンバー)から、社会教育担当の講師で来ないかと言われていたが、小林先生には、申し訳ないが、もし日本社会事業大学で採用されなかったら東京学芸大学にお世話になりますといって、正式決定を待って頂いた。結果として、東京学芸大学をお断りして、母校の日本社会事業大学に専任講師として就職した。その選択には、母校というだけでなく、「社会教育と社会福祉の学際研究」をするのには、日本社会事業大学の方が研究環境的にいいと考えたからである。
〇1974年4月、正式に日本社会事業大学専任講師として就職できた。仲村優一先生から辞令を交付されたが、その折、仲村先生に、”先生、この給料の額は、準保護世帯の基準ではありませんか。何とかならないのですか”と聞いたら、”この基準は国家公務員の給料表に準じているのでどうにもならない”といわれ、給与の低さを実感した。
〇就職に当たって、仲村優一先生と五味百合子先生(戦前の日本女子大学社会事業学科卒業、戦前の社会事業講習会の修了者、日本社会事業大学では研究生活をせず、学生課長として一貫して学生指導(学生を守る)に従事した)から言われたことは、”日本社会事業大学の教員は、研究者として日本の社会福祉界に貢献することは大切であるが、それ以上に学生の教育・指導をしっかりして欲しい。日本の社会福祉界を向上させるために、学生をしっかり育てて、卒業させることを重んじてほしい”と説かれた。
〇この考え方を筆者は守り通したと自負している。2年次、3年次のゼミナールで、学生の興味・関心に即して、いくつもの「小ゼミ」を作り、「小ゼミ」のテーマを共同研究させ、親ゼミで報告させるとともに、「小ゼミ」毎にテーマに即したゼミ論文集を書かせ、それを持って”温泉付き、お酒付き、スキー付きのゼミ合宿“を毎年行ってきた。
〇後日談になるが、1989年には、当時の平田富太郎学長の提案を受けて、日本社会事業大学「大橋ゼミ」開設15周年を記念して、第1回の「大橋ゼミ」卒業生の「ホームカミングデー」を開催した。
〇それ以降、5年おきに行ってきた。教員としての筆者も5年間の研究業績を印刷し、参加者に配布するし、卒業生とともに学ぶ機会を作ってきた。
〇2023年10月に第8回目の「ホームカミングデー」を開催し、「ホームカミングデー」の行事は終了させて頂いた。筆者が80歳になったということと、筆者が社会福祉界の実践、研究に目配りをして情報を集め、それに関して論文を書き、その5年間の論文を「ホームカミングー」で配布することが辛くなってきたからである(筆者の情報発信は、その後「老爺心お節介情報」として、現在74号まで発信している)。
〇この「ホームカミングデー」という考え方は、筆者が日本社会事業大学の清瀬移転の際に打ち出した、今後の大学の在り方の一つとして「卒業生のリカレント教育」の場になるべきだという考え方とマッチしていた。
(註1)
「我が師を語る(1)仲村優一先生とソーシャルワーク」
(『ソーシャルワーク研究』115号・2003年秋号所収、相川書房)
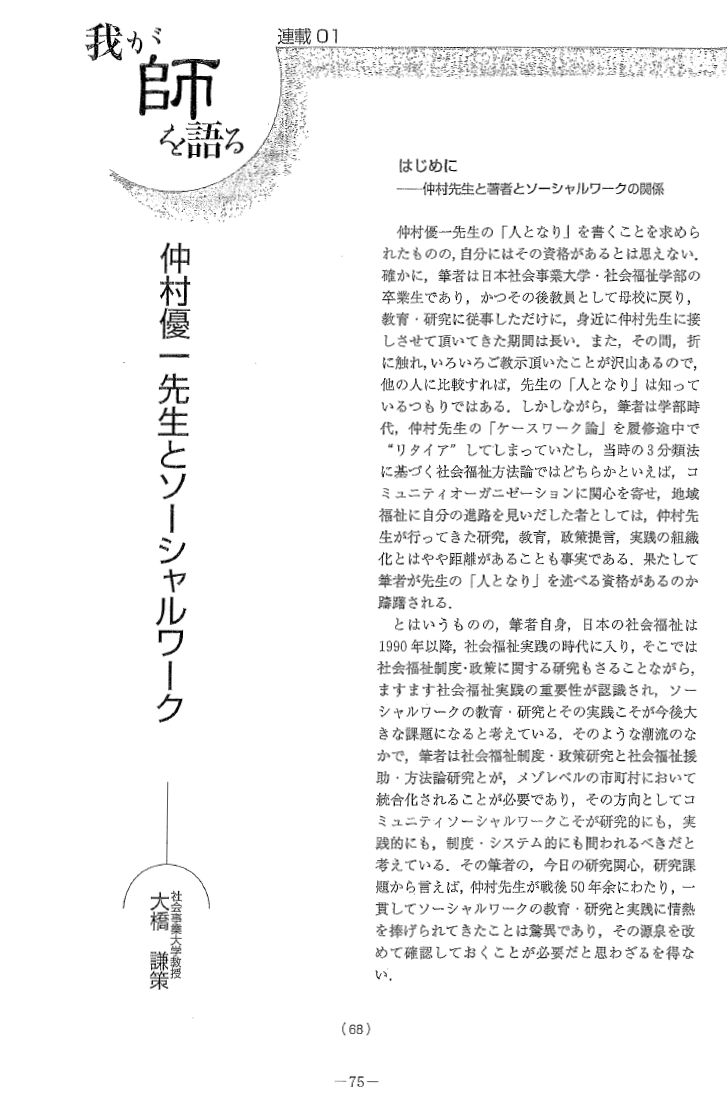
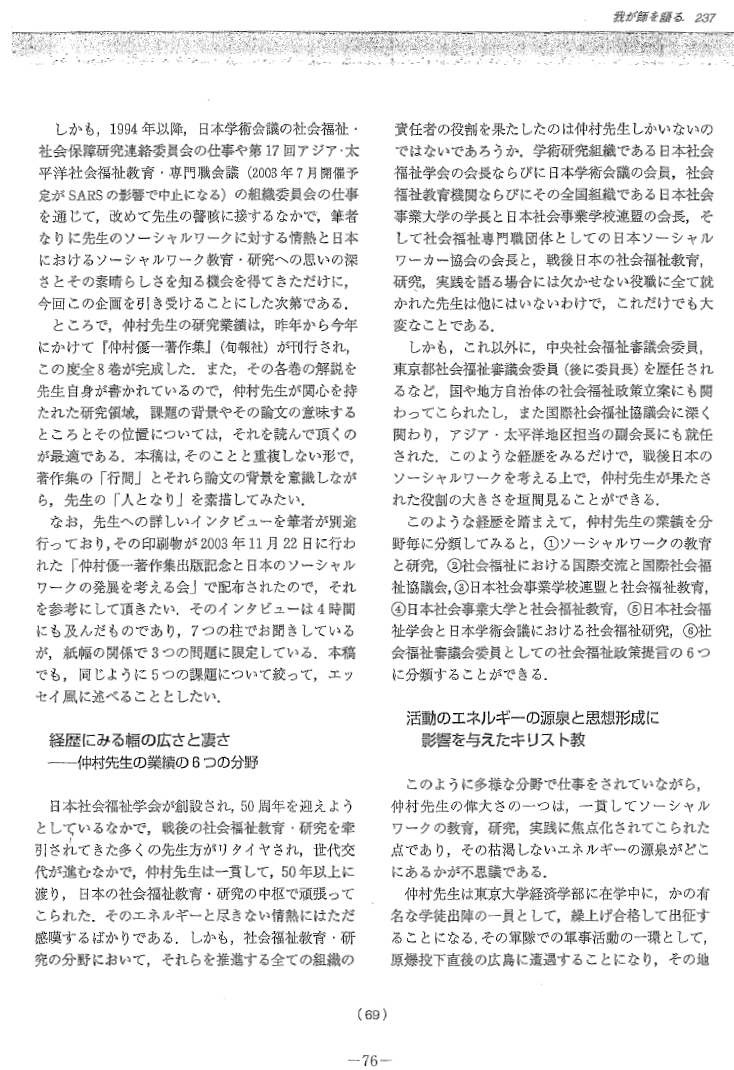
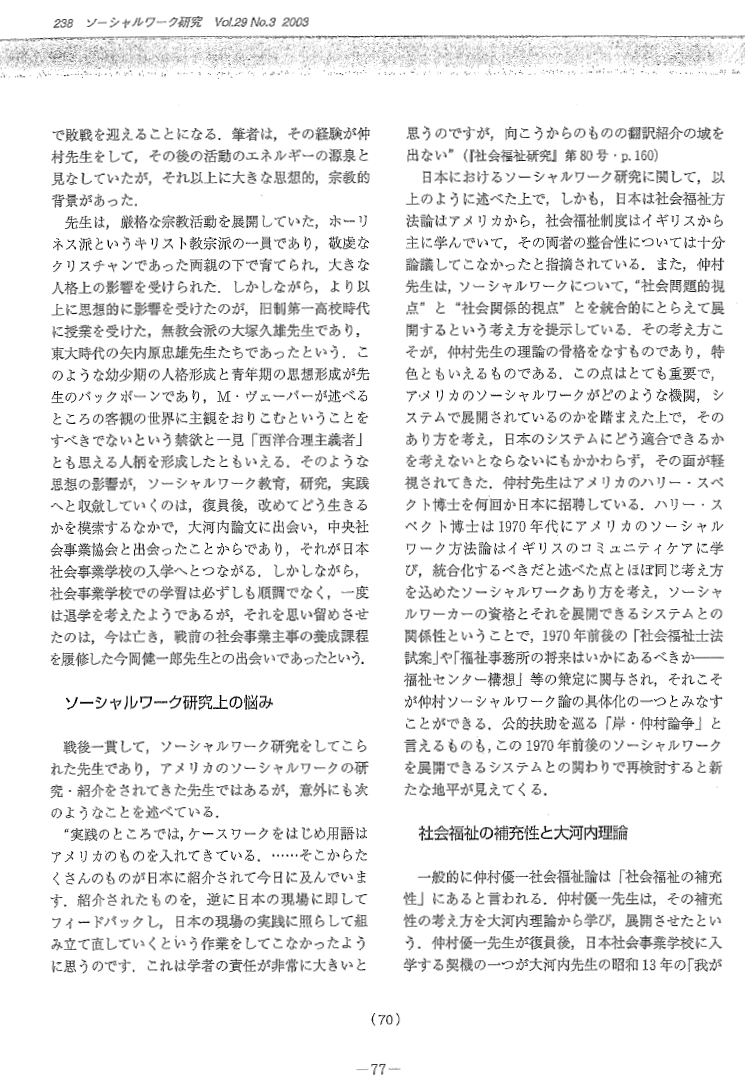
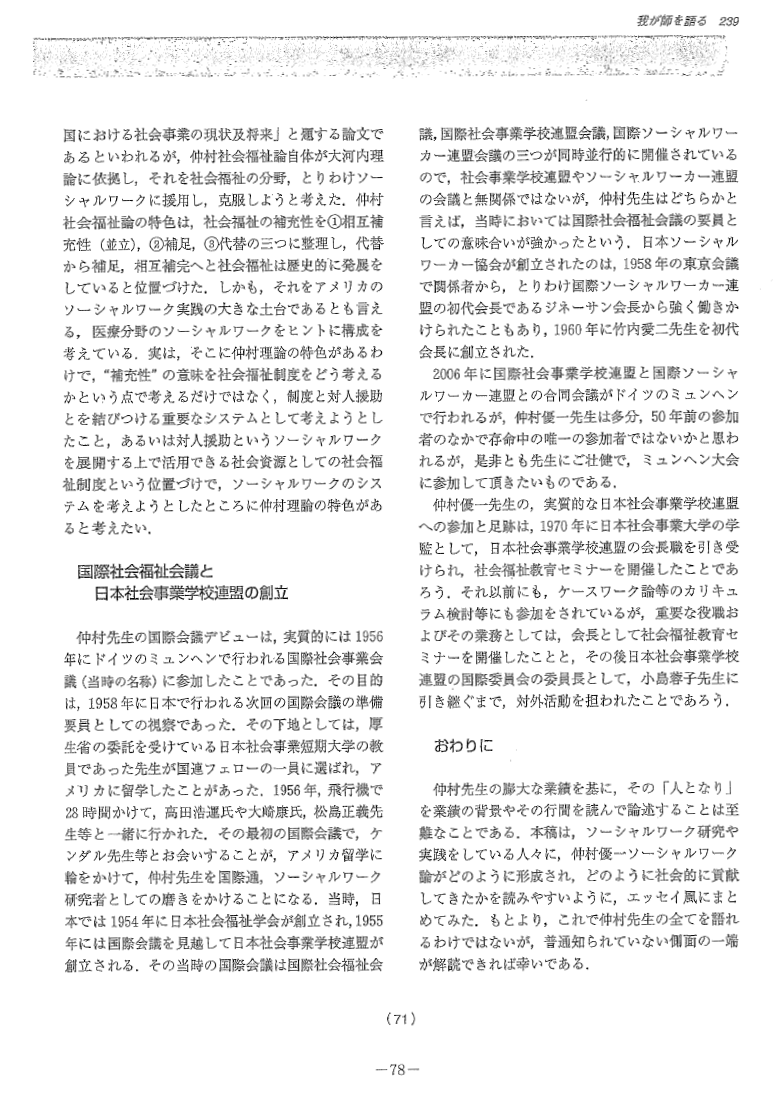
(註2)
『故仲村優一先生偲び草―研究業績・社会活動の功績』刊行にあたって(2016年2月14日)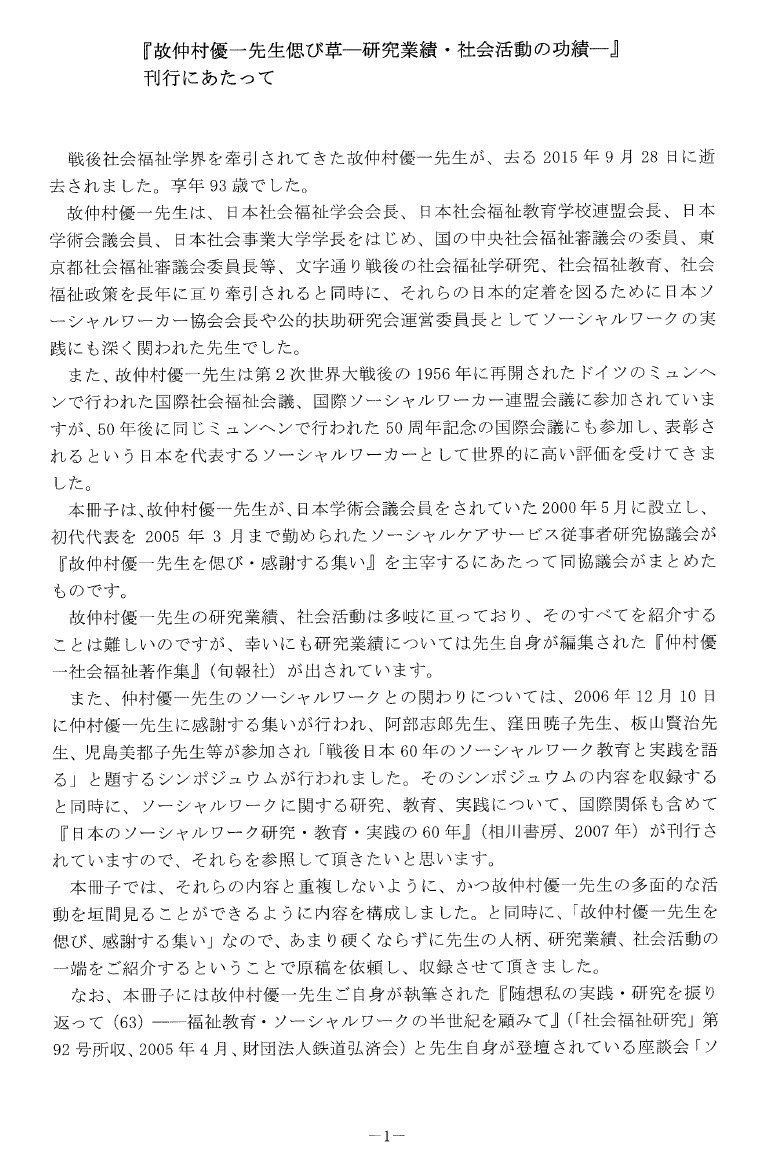
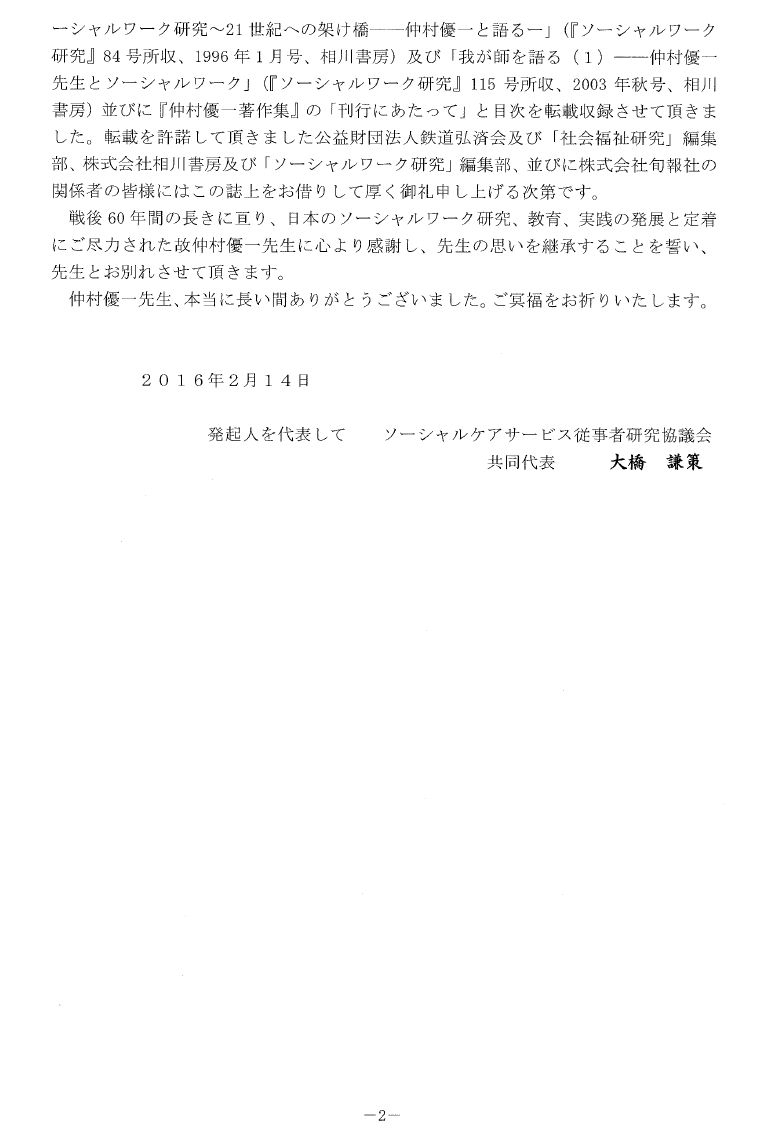
(註3)
「日本社会事業大学名誉教授五味百合子先生お別れの会弔辞」(2009年4月5日)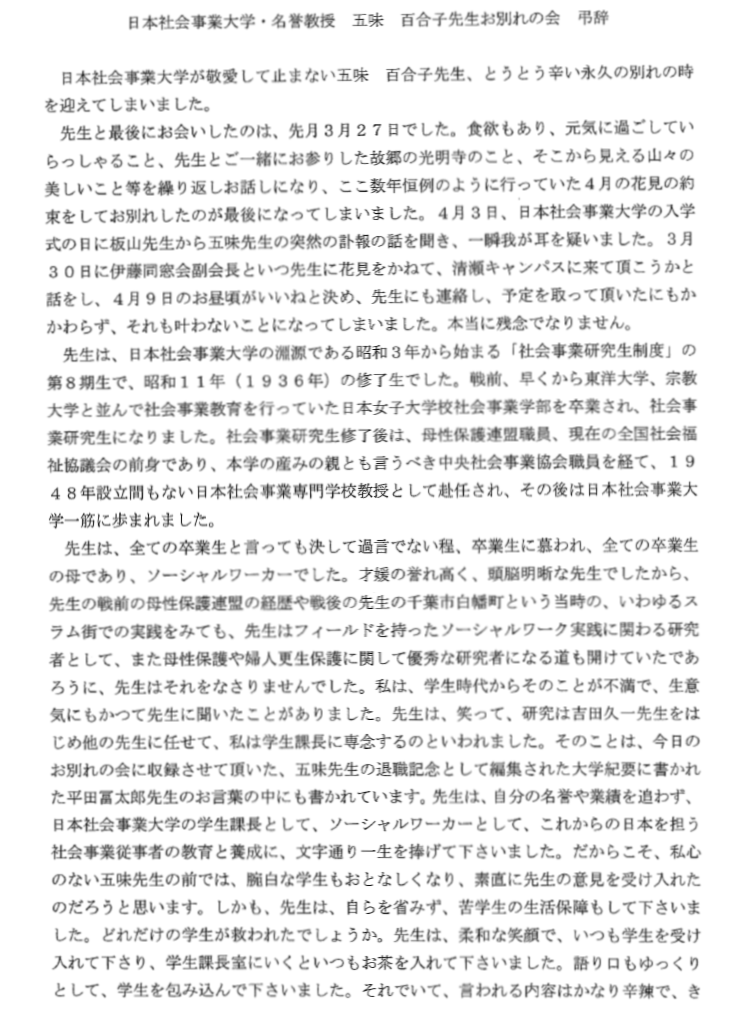
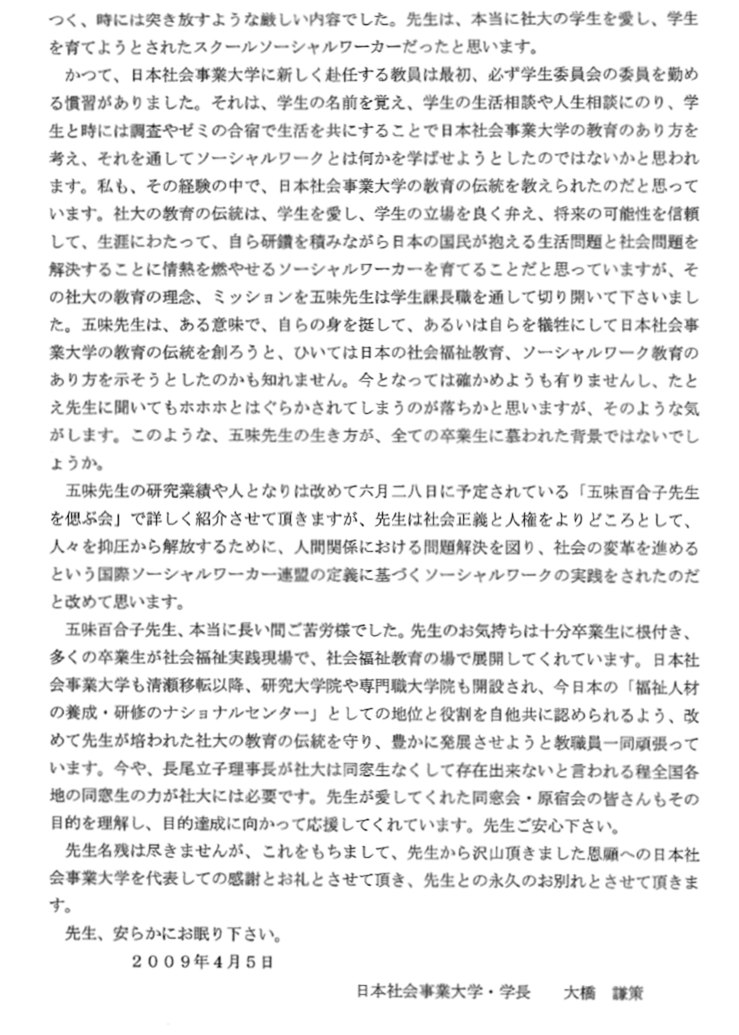
(2025年10月1日記)




