
目 次
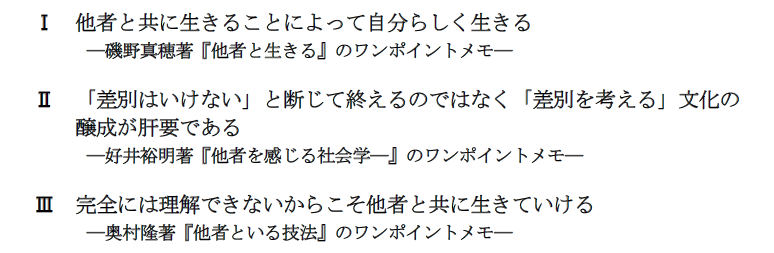
Ⅰ
他者と共に生きることによって自分らしく生きる
―磯野真穂著『他者と生きる』のワンポイントメモ―
******************************************************************
〇人は、2020年1月に始まるコロナ禍において、疫学理論や統計解析手法などを用いた新型コロナウイルスの感染予測(流行予測)に一喜一憂し、罹患のリスクを避けようとした。そんななかで、普段の暮らしにおいて如何に「自分らしく」生きるかを問い、それができる社会システムを求めたのは、昨日のことのようである。筆者(阪野)の手もとに、磯野真穂著『他者と生きる』(講談社新書、2022年1月。以下[1])がある。[1]において磯野は、前者の概念を「統計学的人間観」、後者のそれを「個人主義的人間観」と呼び、また「生の手ざわり」(生きていることの実感や経験)を求めて、前者に関して「“正しさ”は病を治せるか?」、後者に関して「“自分らしさ”はあなたを救うか?」([1]帯)と問う。
〇磯野は、現代社会における人間観、すなわち「人とは何か」「人とはどのような存在であるか」という問いに対して、3種類の人間観を措定する。統計学的人間観、個人主義的人間観、そして「関係論的人間観」がそれである。[1]におけるひとつのキーワードである。本稿では限定的になるが、それに関する一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
〇磯野はいう。「人間の病いと生き死に、及びそれをいかに避けるか、引き受けるかをめぐる問題の諸相の根底には、この3つの人間観の錯綜(さくそう)があると捉えるべきである。つまりあるひとりの人間の病気や死をめぐって、本人とその人を取り巻く人々の間で行き違いが起こる時、その問題に関わる人それぞれが、思考の根底で異なる人間観を前提としながら、同じ人、同じ問題について語っている可能性がある。ある問題に複数の関係者が存在する時、関係者それぞれがどのような人間観を持っているかで、立ち上がる価値と倫理は異なる。したがって、そこのすり合わせが意識的にも、無意識的にも起こらない話し合いは、どこまでも平行線を辿るだろう」(180~181ページ)。
統計学的人間観――病気の事前予測や予防的介入に価値を与える人間観
統計学的人間観は、主に疫学の文脈で提示されるが、例えば50代以上の男性は高血圧だと脳梗塞に罹患する確率が高いというように、統計学的にある集団を数量化することによって導かれた、社会のなかの平均的な人間像(「平均人」:アドルフ・ケトレ)に基づく人間観をいう(150ページ)。その「平均人」は、ある集団の特徴を客観的に表すとみなされながらも、実体としてそれはどこにも存在しない。複雑な計算式を通して現れる架空の物言わぬ人である。それはどこにでもいることにされているが、どこにもいない。誰でもあるが、誰でもない(153ページ)。統計学的人間観は、計算式の上に成り立つ極めて抽象度の高い人間観であり、その最大の特徴は、ある集団の行く末を予想することが可能になるという点にある(184ページ)。
個人主義的人間観――「自分らしさ」(=「私たちらしさ」)を礼賛する素地となる人間観
個人主義的人間観は、自分の内発的な選択や動機によって、社会規範や世間の当たり前に逆らって自分の望みを実現する・表明するといった意味の「自分らしさ」や個性という価値によって支えられる人間観をいう(162、163ページ)。しかし、その「自分らしさ」は、ある選択や行動が「自分らしい」と認められるためには、その選択や行動に社会的承認が伴う必要がある(165ページ)。すなわち、「自分らしさ」が達成されたと思われる時、実際そこで起こっているのは「私たちらしさ」の発現であり(212ページ)、「自分らしさ」はその響きとは裏腹に、合意の形成に他ならない。その点を捉え損ねると、「自分らしさ」は、「それはあなたが決めたこと」という過度の自己責任論や責任回避の機能を生み出したり、「異なる他者といかに生きるか」という共生への省察を欠くことになる(176ページ)。
統計学的人間観と個人主義的人間観の協働と相互支援
統計学的人間観は個々人の価値を棄却する冷たい人間観であり、個人主義的人間観は個々人の価値を大切にする温かい人間観であるように思える。しかし、このふたつの人間観は、一見相反するように見えながら、実は背後(裏)で手を結び協働しあいながら、互いの存在を支え合っている(186ページ)。それはそこに、「生物的な命が存続することが何よりも素晴らしい」という絶対性を帯びた倫理が存在することによる(226ページ)。すなわち、統計学的人間観は、個人のかけがえのなさに絶対的な価値を置く個人主義的人間観に基づいて立ち上がっている(支えられている)のである(193ページ)。
関係論的人間観――自分と他者との「関係性」の生成や変化に価値を見出す人間観
関係論的人間観は、個人主義的人間観の特殊性を浮き立たせるために措定されたカテゴリであるが、他者との関わりのなかではじめて生まれる者として「自分」(個人)を捉える人間観をいう(212ページ)。そこにおいて、この人間観は、自分と他者との関係性の生成や変化に注目することになり、「他者とは何か」「出会いとは何か」「他者と生きるとはどういうことか」などを問うことになる。「他者」とは、分かり合えるかもしれないという存在であり、同時に分かり合えないかもしれないという両義的な存在である(232ページ)。そういう他者との関わり(つまり出会い)は、不安や恐れなどをもたらすが、他者との言動の相互行為を通してどのように他者と共に在るか、共に在り続けるかについて互いの間に規則性が生成される。この相互行為の場や規則(「共在の枠」:磯野)を前提に出会いは進展するが、未来に向かって共に在り続けるためにはその「共在の枠」を変化させていく身構えと身振り(「投射」:磯野)が必要となる(238~241ページ)。その意味において、「他者と生きる」とは、「共在の枠」を共有する自分と他者が、「投射」(相互行為の姿勢や態度)によってその関係性を維持し、新たな関係性を生み出すことによって、出会った他者と共に生きていく「私」/「あなた」が存在することをいう(251ページ)。
〇要するに、一見相反するかのように見える統計学的人間観と個人主義的人間観は実は、一緒になって「生物的な命が存続することが何よりも素晴らしい」という絶対的な倫理観や価値観を創り出す。そしてそれは、絶対性を帯びているがゆえに、人々の営みを制約する。そこにおいて磯野は、両者の人間観を二項対立的な図式で措定するのではなく、両者は協働関係にあるという。そして(そのうえで)、3つ目の人間観として、自分と他者との関係性の生成や変化に注目する関係論的人間観を考えるべきである、という。それが、「他者とともに生きる」すなわち「自分らしく生きる」ことに繋がる。これが磯野の言説であり、視座である。
〇磯野は[1]の最後でいう。「ひとつの尺度で他者の生の長さ(人生の長さ:阪野)を測り、それを価値付け、生き方に介入する際には、唯一の生への畏怖(いふ)を宿した慎み深さが求められる」(269ページ)。留意したい。
〇この指摘から、例によって唐突であるが、これまでの福祉教育の実践や研究は真に「唯一の生への畏怖を宿した慎み深さ」をもってきたか。さまざまな人間観をすり合わせる地道な・丁寧な作業を行ってきたか。特定の人間観を強要し(押し付け)てはこなかったか。そんな疑問が頭をよぎる。
Ⅱ
「差別はいけない」と断じて終えるのではなく
「差別を考える」文化の醸成が肝要である
―好井裕明著『他者を感じる社会学』のワンポイントメモ―
******************************************************************
〇筆者(阪野)の手もとに、好井裕明著『他者を感じる社会学―差別から考える―』(ちくまプリマ―新書、筑摩書房、2020年11月。以下[1])がある。[1]における言説を理解するに際しては例えば、好井自身による「他者性」についての次の一節が役立つ。
社会学とは「他者の学」だ。私たちが社会を構成するメンバーとして生きるとき、他者といかに交信でき、繋がれるのかが “ 解くべき重要な問題 ” となるだろう。ただ私たちは他者を本当に理解しきることなどできるのだろうか。他者理解がいかにして可能かと問うことは、翻って他者を理解することがいかに困難であるのかを確認することとなる。さまざまな「ちがい」をもつ他者が出会い、せめぎあう。この出会いやせめぎあいの様相を克明に見つめていけば、他者理解を邪魔しているさまざまなものが見えてくる。そしてさまざまなものをさらに考えていくとき、道徳や倫理の次元で差別や排除を否定するのではなく、世の中で起きてしまう必然として、社会学的考察の対象として、差別や排除を考えることができるようになる。/「他者理解の学」というよりむしろ「いかに他者理解が困難であるのかを考える学」としての社会学の「面白さ」。差別を考える社会学の魅力。『他者を感じる社会学』(2020年)で私が伝えたかったことの一つだ。(好井裕明「社会学的想像力をいかにしたら伝え得るのか―私が新書を書き続ける理由(わけ)―」『フォーラム現代社会学』第21号、関西社会学会、2022年5月、76ページ)
〇この記述をより広く深く理解するために、[1]のなかから次の一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換)。
・差別は、他者理解――あるいは他者理解の難しさ――という深遠なコミュニケーションの過程で生じてしまう “ 必然 ” であり、私たちが他者を理解しようとし、他者と何かを共有し、伝え合おうとするときに(すなわち、他者とつながろうとする過程で)生じてしまう “ 摩擦熱 ” のようなものである。(20ページ)
・私たちは普段、人間として「素晴らしい」「豊かな」存在がいるし「つまらない」「貧しい」存在もいると考えるが、それはあくまで、そのような評価の対象となる人間の営みやその人が表明する価値観や思想に由来するものであり、その人の存在自体に張り付いている属性ではない。(81ページ)/また、「貴(とうと)い―賤(いや)しい」「浄(きよ)い―穢(けが)れている」という伝統的で因習的な人間の見方があるが、廃棄すべきである。(82ページ)
・(性別や年齢、人種や民族、障害、被差別地域など)ある人々や集団、地域や状況を「きめつける」さまざまなカテゴリー化が「あたりまえ」のこととして、その時々の支配的社会や文化に息づいている。(70ページ)/文化や社会の「あたりまえ」や「普通」に息づいているものの見方や価値観こそが差別や排除をうみだす原因なのである。(208ページ)
・多様なセクシュアリティを生きる人々が性的少数者という「カテゴリー」を生き、独自に歴史を創造していく主体であるという事実を見失うことなく、私たちは、常に支配的文化や価値を相対化する「くせ」を身につけていくべきである。(128ページ)
・部落差別は、身分差別や職業賤視(せんし)、地域への偏見が密接に絡み合っており、日本の中世以前からの歴史や文化に根ざした奥の深い問題である。(88ページ)/部落差別は、本当に「不条理で」「理屈にあわない」営みである。それを背後から支えているのが、「貴(き)―賤(せん)」という人間を “ 分け隔てていく ” 見方であり考え方なのである。(90ページ)
・「差別を考える」とは、「あたりまえ」や「普通」のことと見逃している「決めつけ」や「思い込み」をあらためて洗い出し、自分自身がより優しい気持ちで他者と出会い、つながり、気持ちよく生きていくために自分の「あたりまえ」や「普通」をつくりかえていく、ということである。(246ページ)
・日常生活に生起する偏見や差別をなくすためには、まずは自分自身で「差別を考える」 “ くせ ” を身につけることが必要であり、それによって “ 差別などしない自分らしさ ” を身につけることになる。さらに「みんな」で「差別を考える」ことを模索し、そうした営みの延長に、しなやかでタフな「差別を考える」文化が息づく日常が私たちの前に立ち現れてくる。(252ページ)
・差別を受ける人々の「リアル」に対する想像力の圧倒的な欠如、貧困がある。/他者への想像力が枯渇するとき、差別は繁殖する。今、まさに「他者へのより深く豊かで、しなやかでタフな想像力」が必要とされている。(255ページ)
〇こんにち、ネット時代におけるコミュニケーションの変化や社会の分断化・個別化が指摘されるなかで、多様な存在としての「他者」と向き合う対面の人間関係(つながり)が希薄化している。そんななかでまた、自分と向き合う機会も少なくなっている。それは好井にあっては、他者を尊厳あるひとりの「人間として感じない」ゆゆしき事態であり、そこから日常生活における差別や排除が生起する。その改善や改革を図るためには、「他者を感じる」「差別を考える」ことが必要不可欠となる(11ページ)。また、「差別はいけない」と断じて終えるのではなく、「今、ここ」(現在進行形)で「差別を考える」ことによって私が「かわり」、「みんな」が「かわる」のである(252ページ)。好井からのメッセージである。
〇この点を福祉教育の実践や研究に引き寄せて言えば、例えば障がい者差別についてその歴史や現状(実態)、原因や背景などをしっかりと押さえてきたか。障がい者は憐憫(れんびん)や同情の対象ではないとしても(いまだにそうであることが多い)、「あたりまえ」のように「思いやり」の対象として直截的に認識させてきたのではないか。障がい者差別はよくないこととして、反省すべき問題であり、反省すれば「それはそれでよし」としてこなかったか。
〇また、福祉教育実践や研究は、上述の「貴―賤」に関する部落問題(さらには天皇制)について、「家柄」や「血筋」といった人間の地位や場所、属性だけで評価するという “ 偏った ” 他者理解の仕方に言及してきたか。間違っても「寝た子を起こすな」という考えはないと思うが、どうだろうか。「浄(じょう)―穢(え)」に関して言えば、伝統的で因習的なジェンダーをめぐる知識や規範、性的少数者( LGBTQ)というカテゴリーを生きる人たちの理解について関心を持ってきたか(持っているか)。福祉教育実践や研究において、「他者を感じる」「差別を考える」問題は山積している。
Ⅲ
完全には理解できないからこそ他者と共に生きていける
―奥村隆著『他者といる技法』のワンポイントメモ―
******************************************************************
〇筆者(阪野)の手もとに、奥村隆著『他者といる技法―コミュニケーションの社会学―』(筑摩書房、2024年2月。以下[1])がある。人は、多くの他者といっしょにいながら(その場を「社会」と呼ぶ)、そのためのさまざまな「技法」を用いて暮らしている。[1]は、そのさまざまな技法(「他者といる技法」)について体系的に論じたものである。ここでは、それらのうちから、「理解」できない(わかりあえない)「他者」とともにいるための技法の一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。なお、[1]は、単行本(日本評論社、1998年3月)を文庫化したものである。
〇その点に関する奥村のひとつのメッセージはこうである。「私たちは、『わからない他者』と『いっしょにいる』技法を、ていねいに考えていかなければならない」。「そこにはたくさんの居心地が悪い世界があるかもしれないが、どうやらそもそも他者といるということはそういうことなのだ。そして、それができることは、他者といるということを、もっとずっとゆたかなものにしてくれるように、私は思う」(298ページ)。
①「わかってくれない」ことと「わからないこと」は、他者といるときによく起こる問題である
「理解」は、他者と共存するためのひとつの有力な「技法」である。私たちは、これをよく知っており、じっさいにいつも行っている。また、それと関係するある苦しさも知っている。私たちは、よく「私のことを理解してくれない!」と嘆いたり、「私はあの人を理解できない!」と叫んだりする。わかってくれないこととわからないこと、このふたつは、他者といるときによく起こる問題である。そして、わかられたいこと、わかりたいことが、私たちがしばしば望むことである。(254ページ)
② 他者に「理解」されない「私だけ」の領域があるとき、そこに「自由」や「私」が存在する
これはありえない想定であるが、完全に他者の「こころ」(思いや考え:阪野)が「理解」できたとしたら、どうなるだろう。完全に私の「こころ」が他者によって「理解」されたとしたら、なにが起きるのだろう。(272ページ)/なにもかも「理解」されてしまうとき、私たちは「こころ」を自由に働かせることはできないだろう。むしろ、私たちの「自由」は、他者に「理解」されないことを条件にするようだ。もちろん、他者に「理解」されることと両立する「自由」もある。しかし、両立しない「自由」もたくさんある。たとえば、「まちがえる自由」。他者に「こころ」をすべて「理解」されるとき、私たちは決して「まちがえる」ことはできない。しかし、「理解」されない領域があるとき、私たちは「こころのなか」でいくらも「まちがえる」ことができる。「まちがえる」ことが、私たちにたくさんの「自由」を、可能性を与えてくれる。完全に理解されてしまうとき、私たちはその可能性をもちえない。/また、完全に理解されてしまうとき、「私」など存在しない。「私」のこころのすみずみまで他者によって「理解」されるとき、「私」のなかに「私だけ」の場所などどこにもないことになる。(中略)私は、他者の理解によって、どんどん蒸発していってしまう。逆にいえば、他者に「理解」されない場所をもつことによって、「私」は「私」でありはじめる。(274ページ)
③「理解」の素晴らしさ(「理解の過少」)には敏感であるが、「理解」の苦しさ(「理解の過剰」)には鈍感である
私たちは「理解」のすばらしさはよく知っているが、「理解」が生む苦しみは(感じていても)あまり論じないのではないか。「理解の過少」という事態には敏感だが、「理解の過剰」という事態にはひどく鈍感なのではないか。人がわかりすぎてしまったり、わかられすぎて苦しんでいるときにも(他者の「こころ」が全てわかってしまったと感じたり、他者に自分の「こころ」が全てわかってしまったと感じたりして苦しんでいるときにも:阪野)、もっとわからなければ、もっとわかられなければと思い込み、かえって「理解の過剰」の苦しみを増幅するということが頻繁にあるのではないか。そして、「理解」を断ち切って別の技法を探すことをあまりせず、「理解」の技法が有効でない場面においてもこの技法を使用しているのではないだろうか。(284~285ページ)
④「理解の過少」と「理解の過剰」の苦しみと、「完全な理解」と「適切な理解」の基準はそれぞれ異なる
「理解」にはふたつの異なる基準がある。ひとつは、「完全な理解」という、原理的な基準である。ここから見れば現実に存在するすべての「理解」は「過少」である。もうひとつは、それよりも「理解」が「過少」でも「過剰」でも苦しみを感じる、ある実践的な基準――「適切な理解」とでも呼ぼう――である。そして、このふたつの基準はまったく異なる。(中略)私たちはときに、「完全な理解」が「適切な理解」であると取り違える。「完全な理解」が達成されたら(それは原理的に絶対に経験できないから確かめようがないのだが)どれだけすばらしいだろう、と思い込む。しかし、これはと取り違えである。原理的な「完全な理解」を誤って実践的な「適切な理解」とするとき、私たちはいつも「理解の過少」だけを発見し、「理解の過剰」は絶対に発見できないことになる。/私は、「理解の過少」の苦しみと「理解の過剰」のそれをしっかりと区別しなければならないと考える。また、「完全な理解」という基準と「適切な理解」という基準が異なることを明確に自覚しなければならないと考える。これができないとき、私たちは、それでは解決できなかったりかえって苦しみを増す問題までも「より多くの理解」という技法で解決できると思い込み、それを使用してしまう。(286~287ページ)
⑤「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法、すなわち「理解」とは異なるかたちで他者と「共存」するための技法が必要である
私たちがよく知っているのは、「わかりあう」から「いっしょにいられる」という状態だ。だから、「わかりあえない」とき、「いっしょにいる」ために「もっとわかりあおう」とする。それは、おそらく「社会」という領域のある部分では、必要なことだし大切な成果を生むだろう。しかし、この技法しかもたないとき、「わかりあえない」と私たちは「いっしょにいられなく」なってしまう。おそらくもうひとつの技法があるのだ。「わかりあえない」とき「もっとわかりあおう」とするのではなく、「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法、「わかりあえない」ままでひとつの「社会」を作っていく技法。私は、「他者」といること、「社会」を形成することの少なくともある領域において、このような技法を探すことが必要だと思う。「わかりあわない」と「いっしょにいられない」、「社会」がつくれない、という技法は、私たちの「社会」の可能性を大きく限定する。「理解」は「他者」との「共存」のためのひとつの技法でしかなく、このふたつは別のことなのだ。私たちはときに、他者との「共存」よりも「理解」のほうを目的として設定してしまう。しかし、「理解」できない他者と「社会」を作る場面はあり、そのとき「理解」に囚われることは、私たちを「共存」できなくさせてしまう。私たちは「理解」を断ち切り、それ以外の「共存」のための技法を開発し始めなければならない。(290~291ページ)
⑥「話しあう」技法を身につけているとき、人は「わかりあわない」ときにも「いっしょにいる」ことができる
「他者はわからない」という想定を出発点として、他者といることを模索する技法、そのひとつは、ごく素朴でありふれているが、「話しあう」ということである。/「話しあう」ということは、次のふたつからなりたつ。ひとつは、「尋ねる」「質問する」ということ。これは、いうまでもなく、「わからない」とき、その「わからなさ」につきあっていこうとするときにのみ、開かれる。もうひとつは、「答える」「説明する」ということ。これも、相手が私を「わかっていない」と感じるときにしか、始まらないことだ。(294ページ)/「話しあう」こと。「質問しあい」「説明しあう」こと。――これは、じつに居心地の悪い時間を私たちに開いてしまう。(中略)このことは「わからない!」と相手にはっきり伝えることからしか始まらず、ひとつひとつ「質問し」「声明する」ことは双方にこころの負担をかけることだし、「わかりあっていない」ことを自覚しながらいっしょにいる時間をずいぶん長く共有することになる。しかし、この「話しあう」技法を身につけているとき、人は「わかりあわない」ときにも「いっしょにいる」ことができる。(294~295ページ)
⑦ 早く「わかる」ための技法よりも、「わからない」でもゆっくりとしていられる技法が大切である
私たちは、「わかりあおう」とするがゆえに、ときどき少し急ぎすぎてしまう。しかし、「わからない」時間をできるだけ引き延ばして、その居心地の悪さのなかに少しでも長くいられるようにしよう。その間に、「わかりあう」ことが自然に開かれる場合も、「話しあう」ことを意識的に開く場合も、「わかりあわないまま」ただいっしょにいるだけという場合もあるだろう。しかし、「わかる」ことを急ぎすぎ、その時間を稼げないと、私たちは多くの可能性を閉ざしてしまう。私たちは「わかる」ことにすぐに着地したがる。しかし、より困難で大切なのは、「わかる」ための技法よりも、「わからないでいられる」ようにする技法であるように私は思う。(中略)これをもたないとき、「わからない」とすぐに「なぐりあう」=「暴力」を振るうことをしてしまったり、すぐに「わかろう」として乱暴な「類型」に他者をひきつけるような「理解」に着地する=「差別」することをしてしまったりする(すぐに「わかろう」として高齢者や障がい者、女性などの「類型」によって他者を理解することは、独自性を欠いた部分的な理解にとどまり、差別することになる:阪野、259ページ)。しかし、「わからないでいる」のが常態であり、そこにゆっくりといられるのなら、私たちは「なぐりあう」ことも「差別」することもずっとしなくてすむだろう。(296ページ)
〇人は、他者を理解したい・わかりたい、他者から理解されたい・わかってもらいたいと望む。しかし、他者を完全に理解すること・わかること、他者から完全に理解されること・わかってもらうことは、原理的には不可能である。そこで人は、他者を「ああいう人」「こういう人」や「高齢者」「障がい者」などの「類型」(常識的な思考の構成概念:259ページ)にはめ込むことによって、他者を理解しようとする。しかし、それも部分的・表層的なものにとどまり、他者を完全に理解すること・わかることにはつながらない。むしろ「類型」を利用することによって、他者から離れたり、他者を排除したりする。あるいは、苦しい思いをしながらも他者と共にいることによって、他者への偏見や差別を引き起こすことにもなる。
〇しかし人は、他者と共にいることによって、「生」(生命、生活、人生)の営みを続けることができる。それによってしか、できない。そこで奥村は、理解できない・わからない他者といっしょにいるための技法について考える。理解できなくても・わからなくても、異なるかたちで他者とともにいっしょにいるための技法について言及するのである。
〇上記の見出しを再掲する。
①「わかってくれない」ことと「わからないこと」は、他者といるときによく起こる問題である。
② 他者に「理解」されない「私だけ」の領域があるとき、そこに「自由」や「私」が存在する。
③「理解」の素晴らしさ(「理解の過少」)には敏感であるが、「理解」の苦しさ(「理解の過剰」)には鈍感である。
④「理解の過少」と「理解の過剰」の苦しみと、「完全な理解」と「適切な理解」の基準はそれぞれ異なる。
⑤「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法、すなわち「理解」とは異なるかたちで他者と「共存」するための技法が必要である。
⑥「話しあう」技法を身につけているとき、人は「わかりあわない」ときにも「いっしょにいる」ことができる。
⑦ 早く「わかる」ための技法よりも、「わからない」でもゆっくりとしていられる技法が大切である。
〇以上のうちとりわけ、②の、他者に「理解」されない「私だけ」の領域があるとき、そこにたくさんの「自由」や可能性があり、「私は(が)私である」ことの自己理解(認知)がすすむ。⑤の、「わかりあわない」と「いっしょにいられない」、「社会」がつくれないという技法は、私たちの「社会」の可能性を大きく限定する。「理解」は「他者」との「共存」のためのひとつの技法でしかない。そして⑦の、早く「わかる」ための技法よりも、「わからない」でもゆっくりとしていられる技法が大切である、という指摘に注目したい。それが、他者といるということを、もっと、ずっと、きっと豊かなものにしてくれるのであろう。
〇福祉教育実践における高齢や障害の疑似体験は、高齢・障害理解や高齢者・障がい者理解を通して、共存や共生、共存社会や共生社会のあり方を問う。その際の高齢・障害「理解」や高齢者・障がい者「理解」に関して、奥村の議論に留意したい。例によって唐突であるが、付記しておく。
【一言】
―「まちづくりと市民福祉教育」の視点から―
******************************************************************
〇「まちづくり」において「共感」は不可欠な要素である。それは、単なる感情的な同調ではなく、地域に生きる主体の多様性を前提とする。そして、それらを排除せずに「共働」(協働)するための関係形成の基盤である。
〇そのため「まちづくり」においては、効率的な課題解決や安易な合意形成を目的化するのではない。互いの「わからなさ」を尊重し合い、「差別を考える“くせ”」(好井裕明)を身に付け、その文化化を図って地域に根付かせることが重要となる。
〇「市民福祉教育」は、他者を「わかる」ためではなく、他者との差異を抱えたまま、それでも共に生きるための知識や技法、価値観を育む営みである。この教育は、「まちづくり」の前提条件であり、その過程そのものである。
「他者」考
他者と生きる、差別と共生
発 行:2025年12月25日
著 者:阪野 貢
発行者:田村禎章、三ツ石行宏
発行所:市民福祉教育研究所




