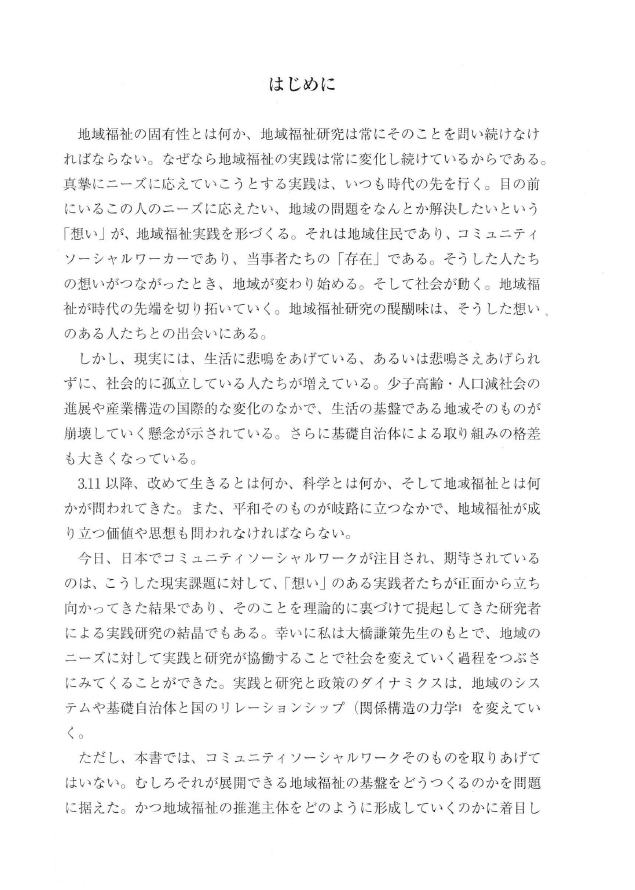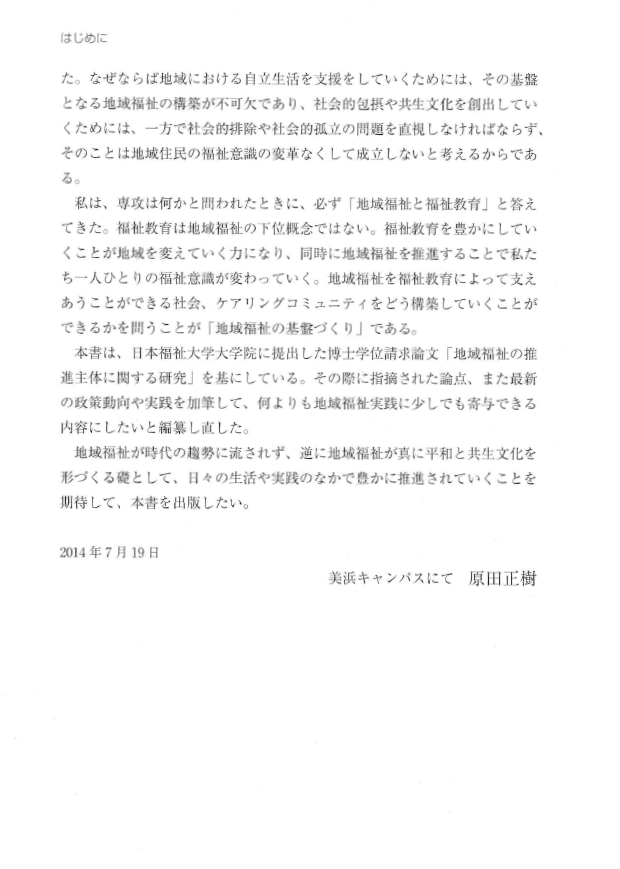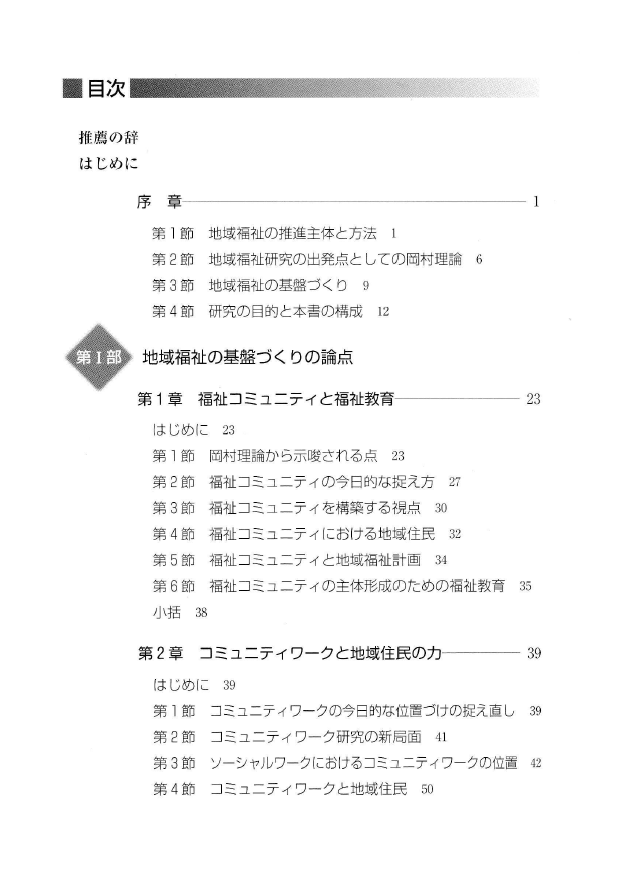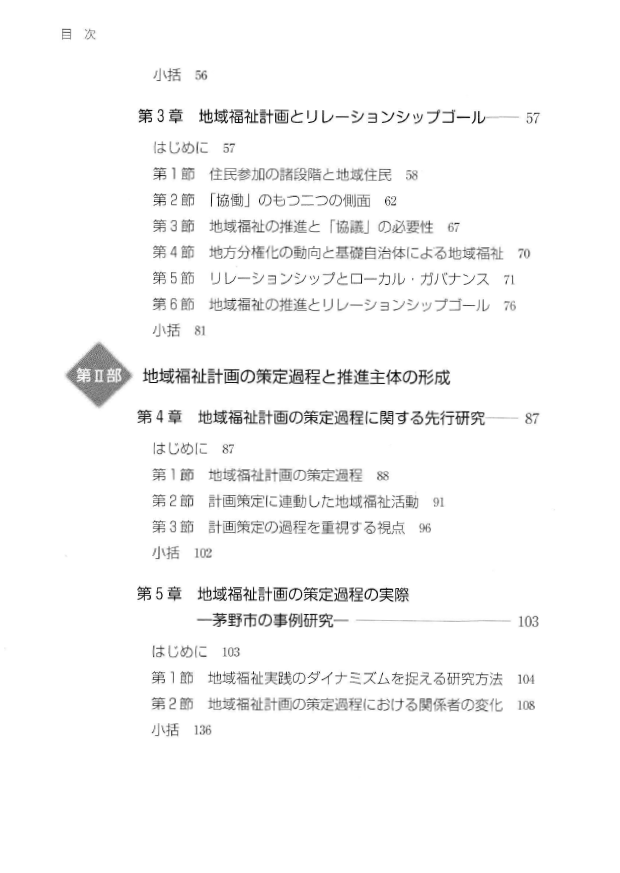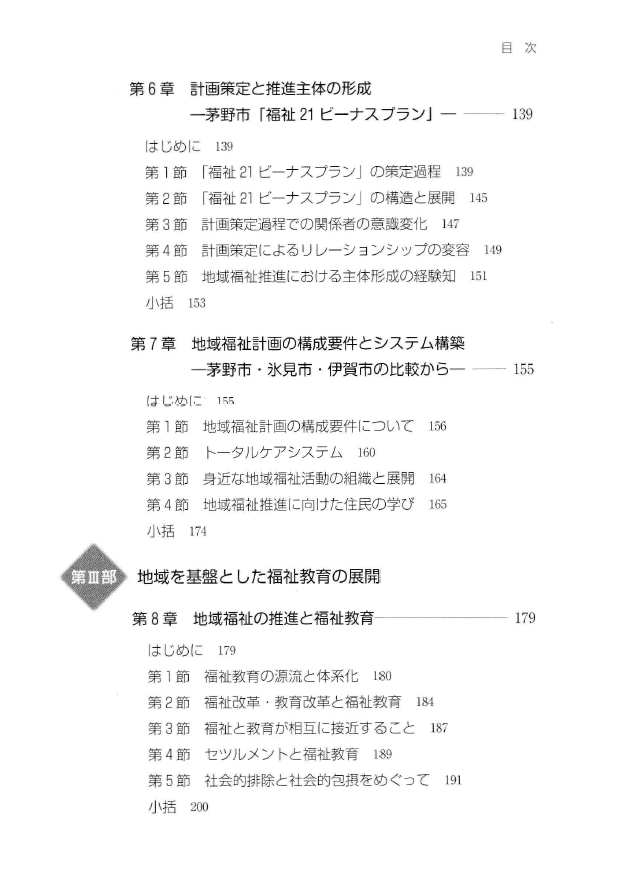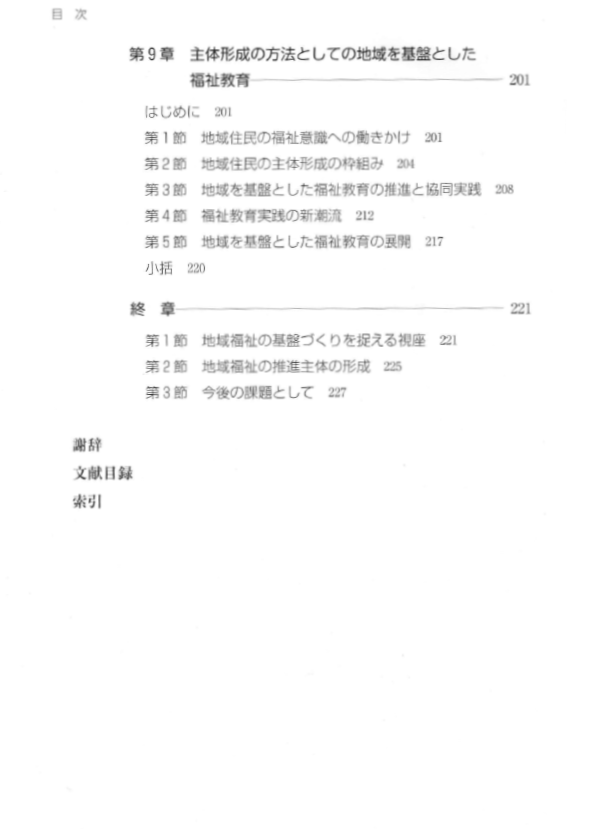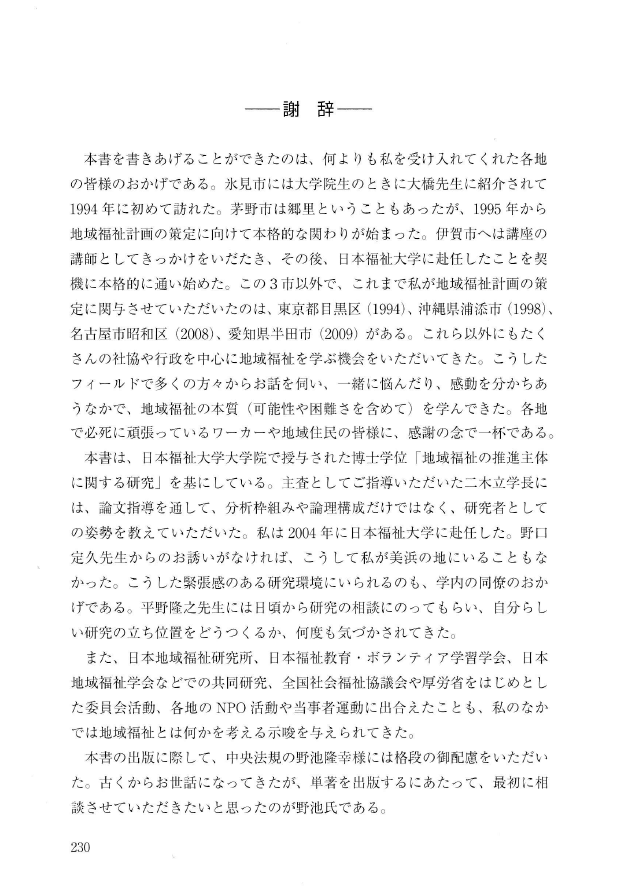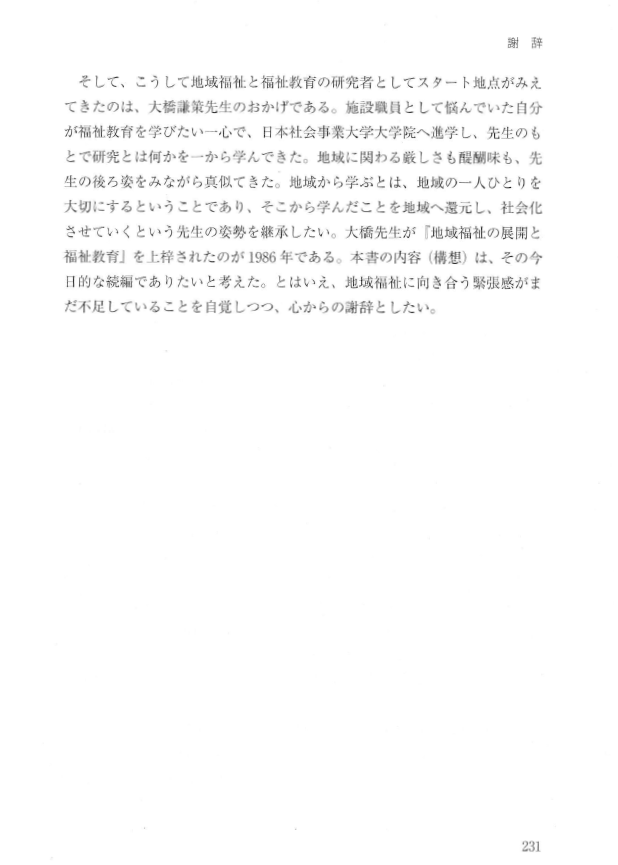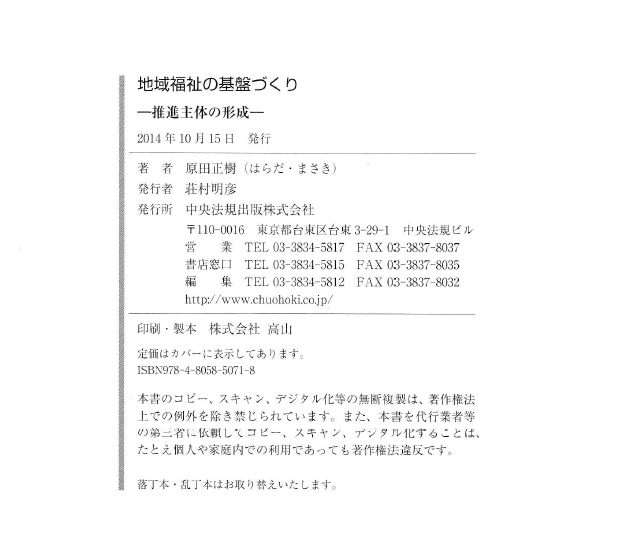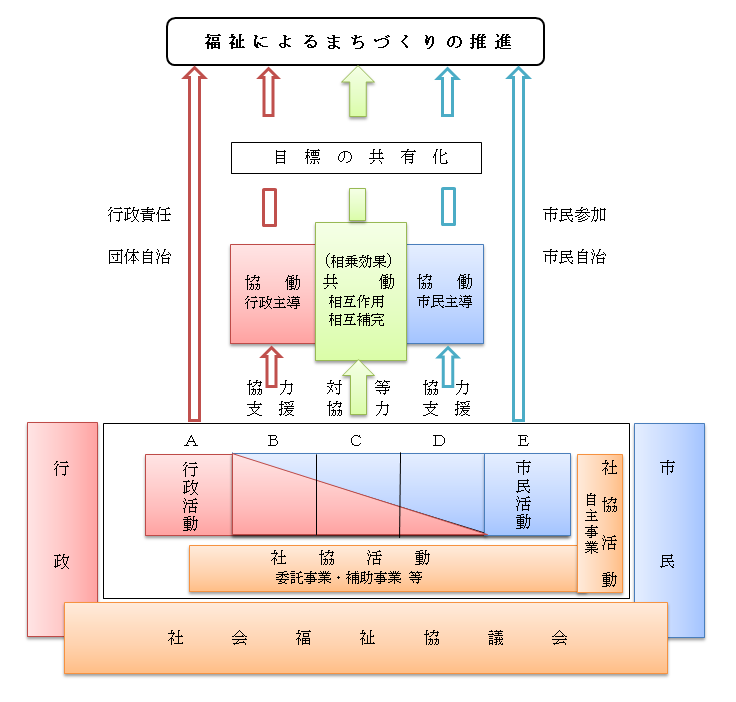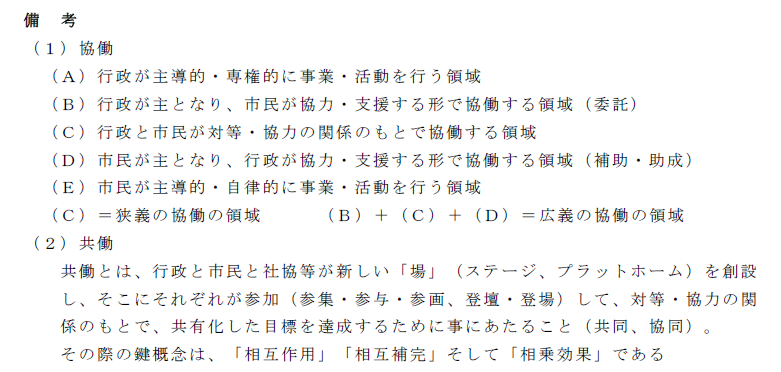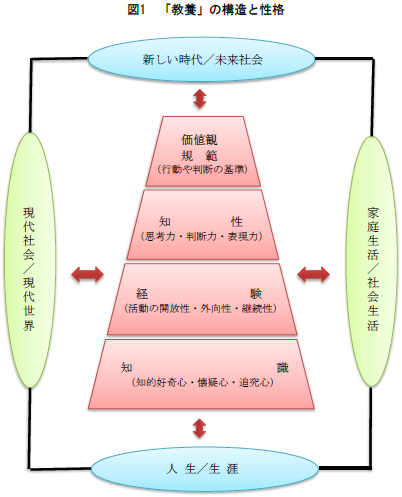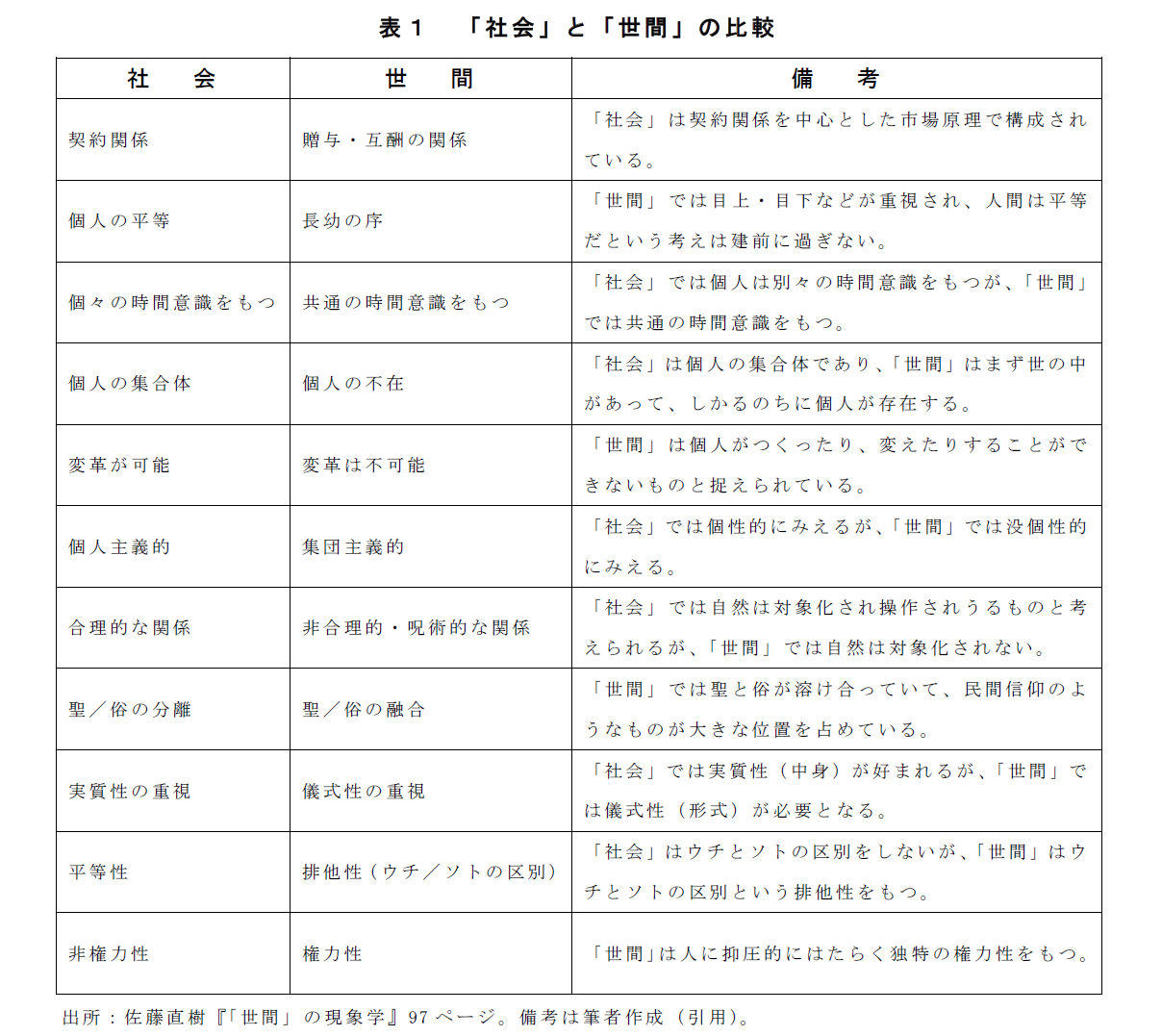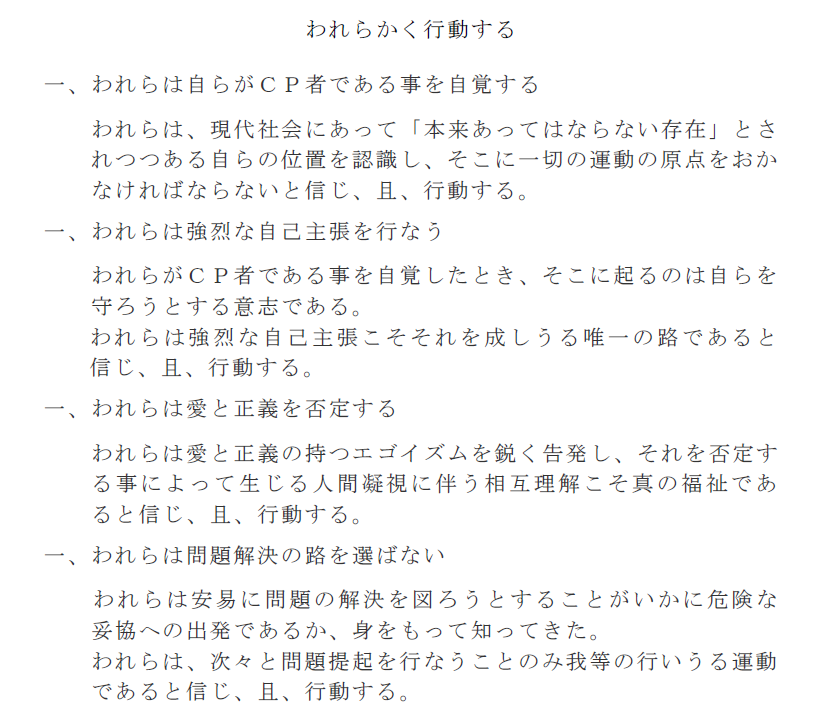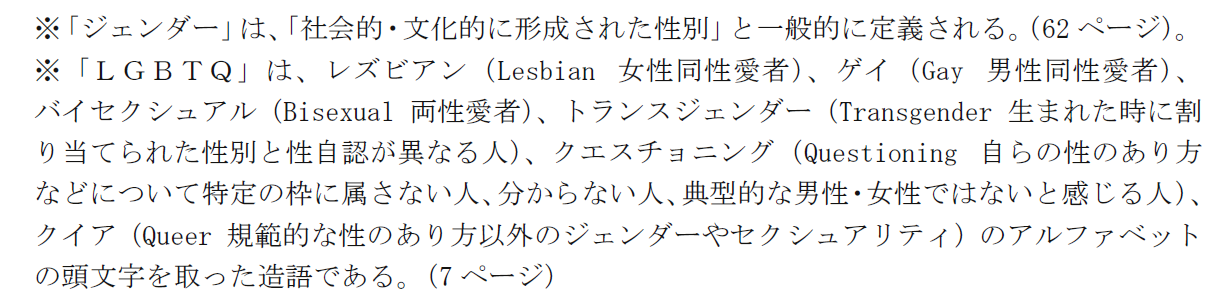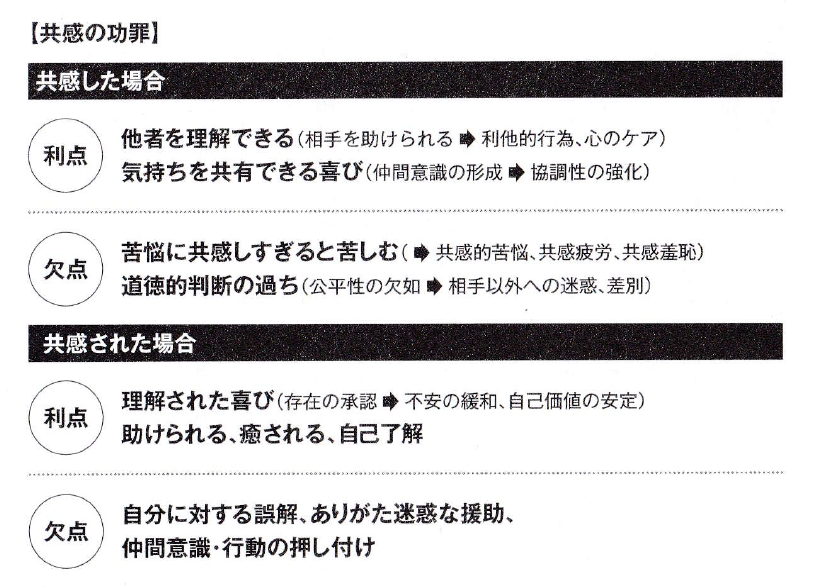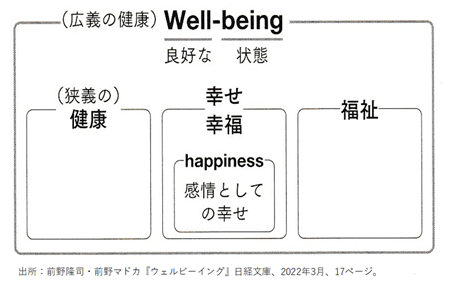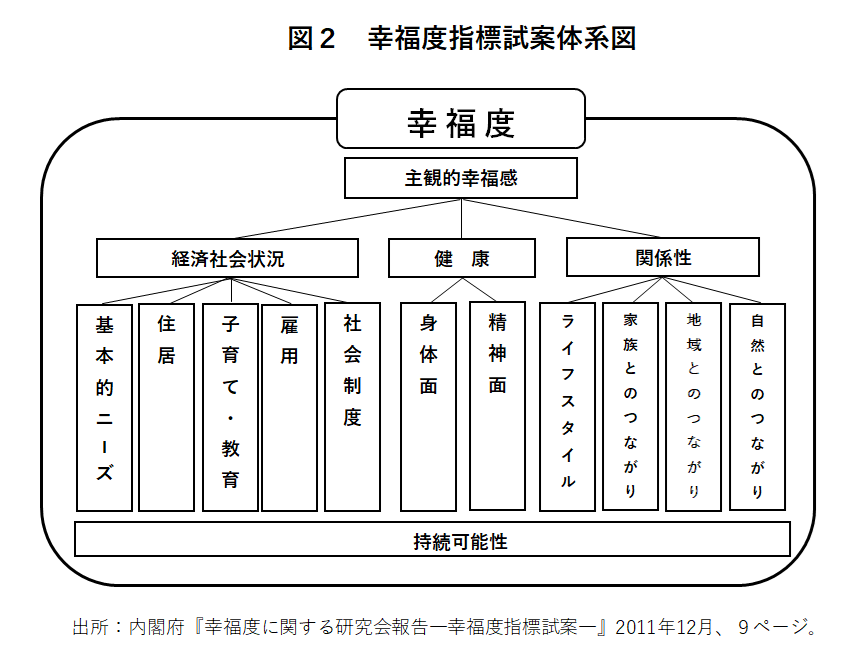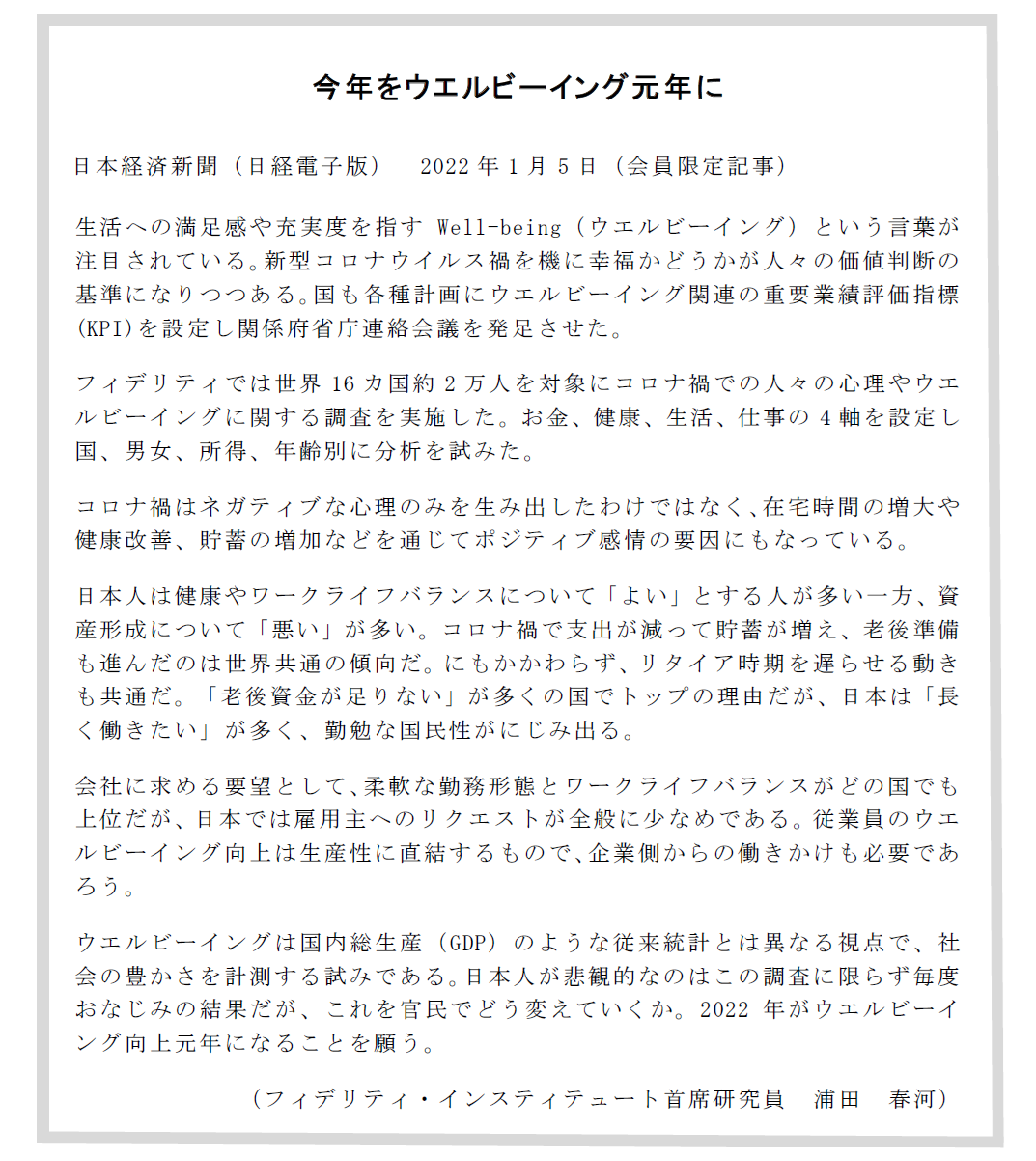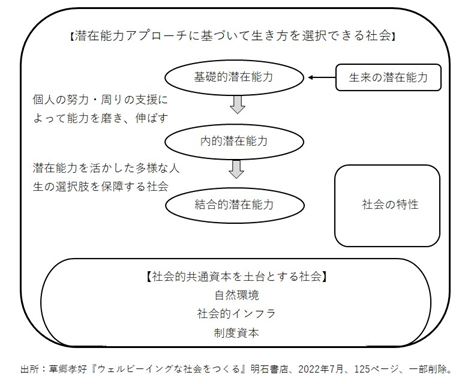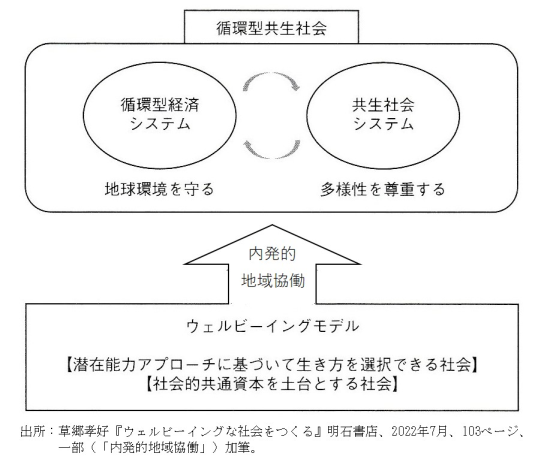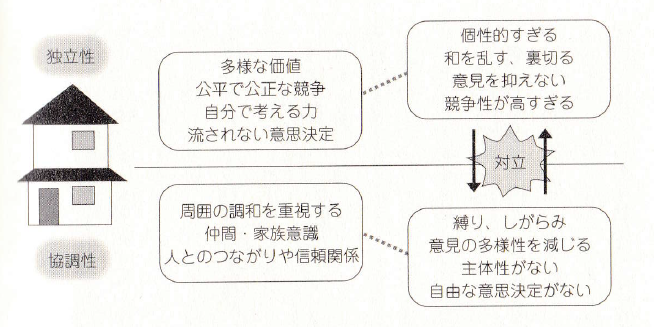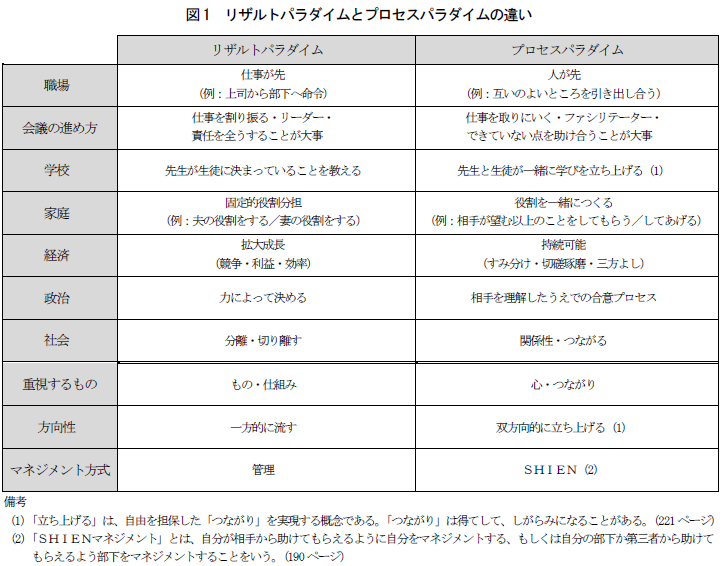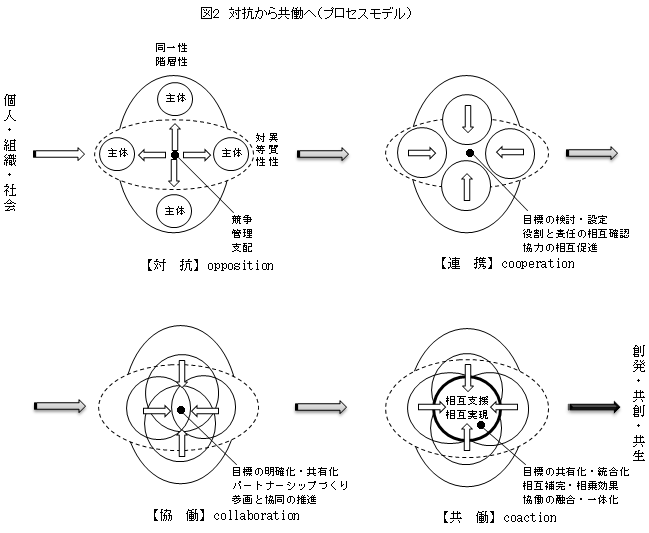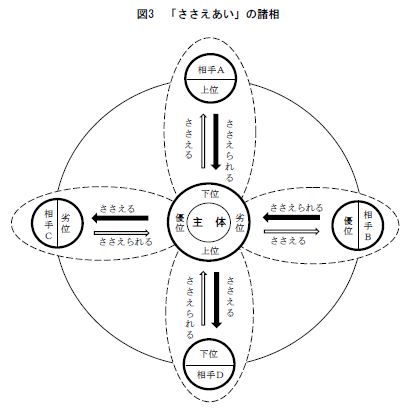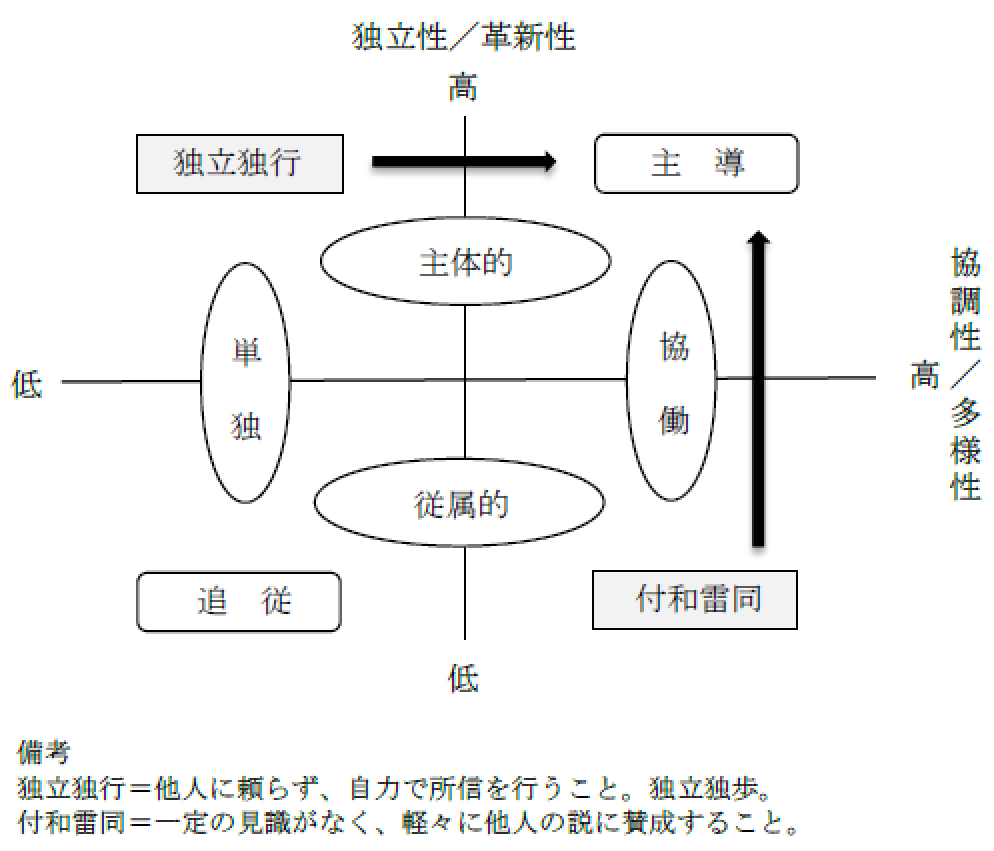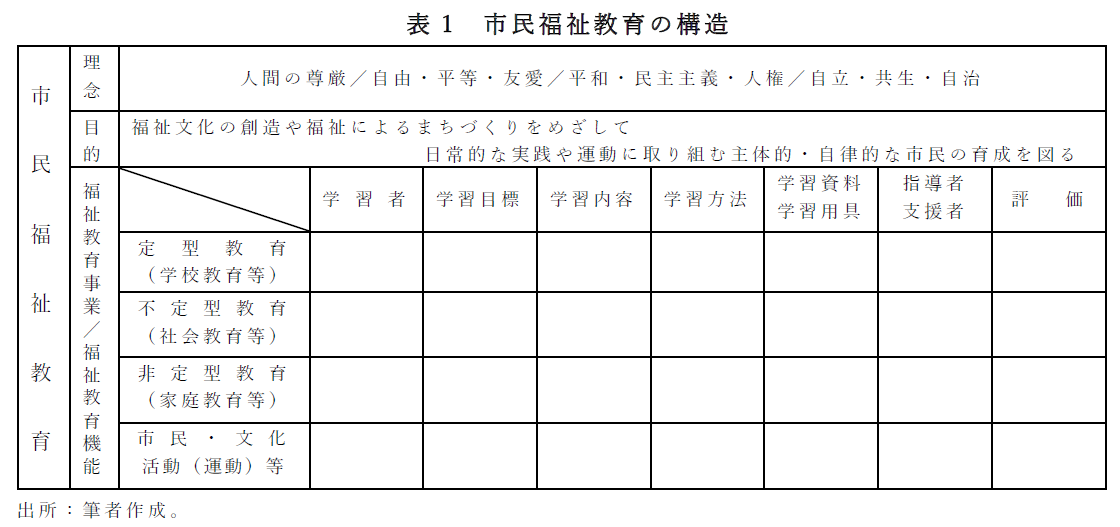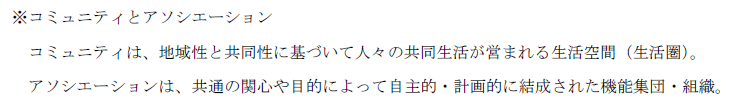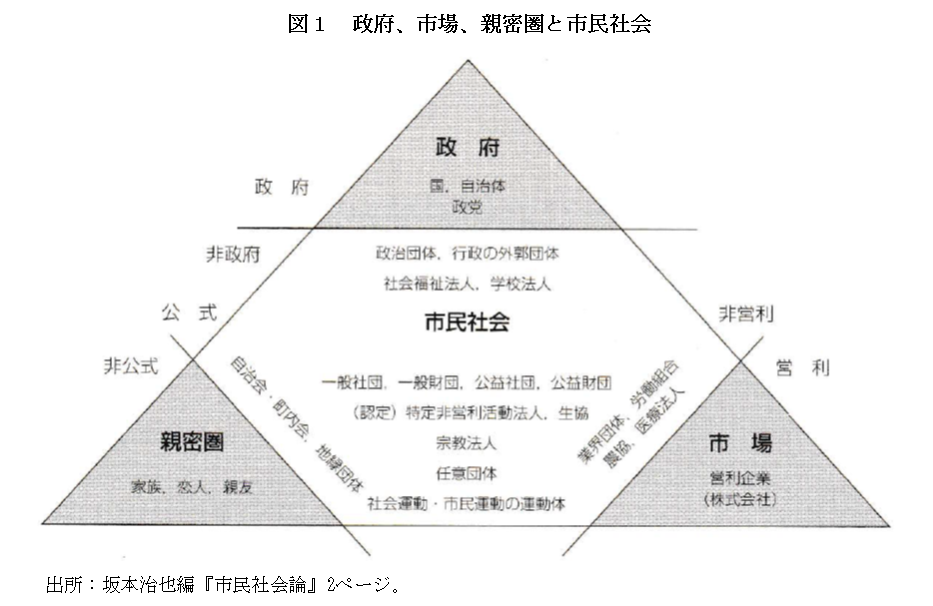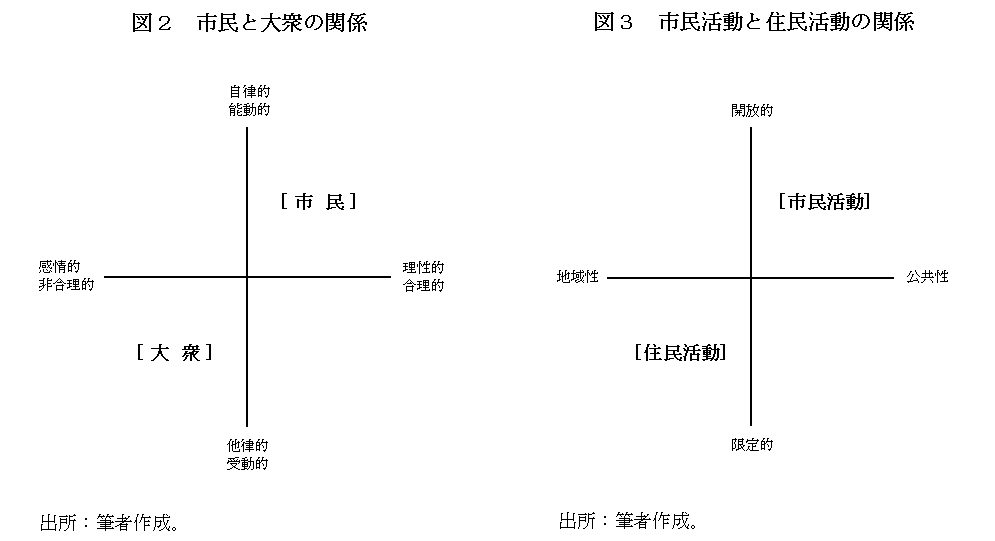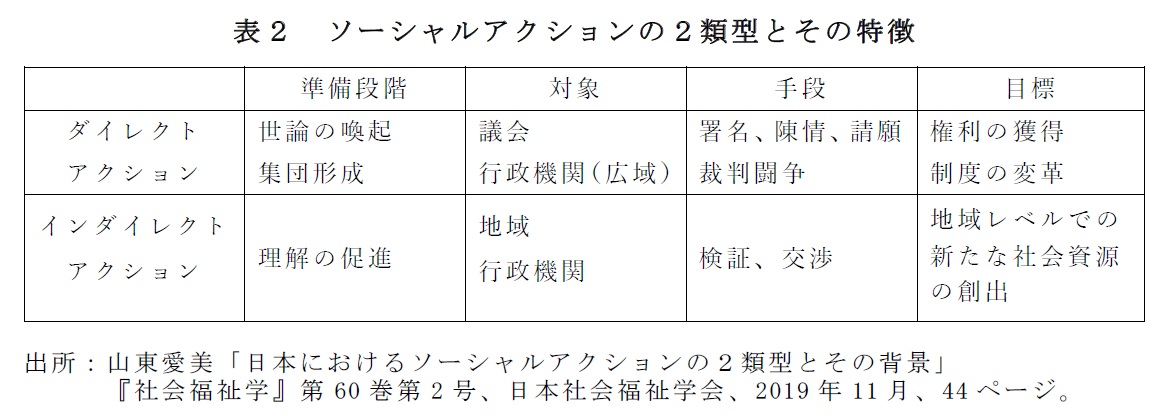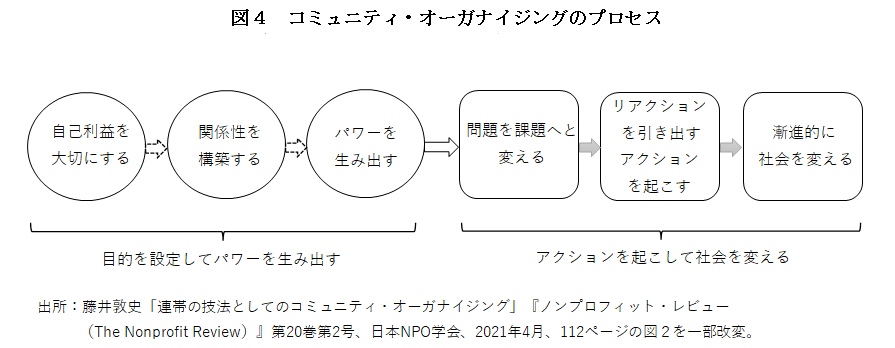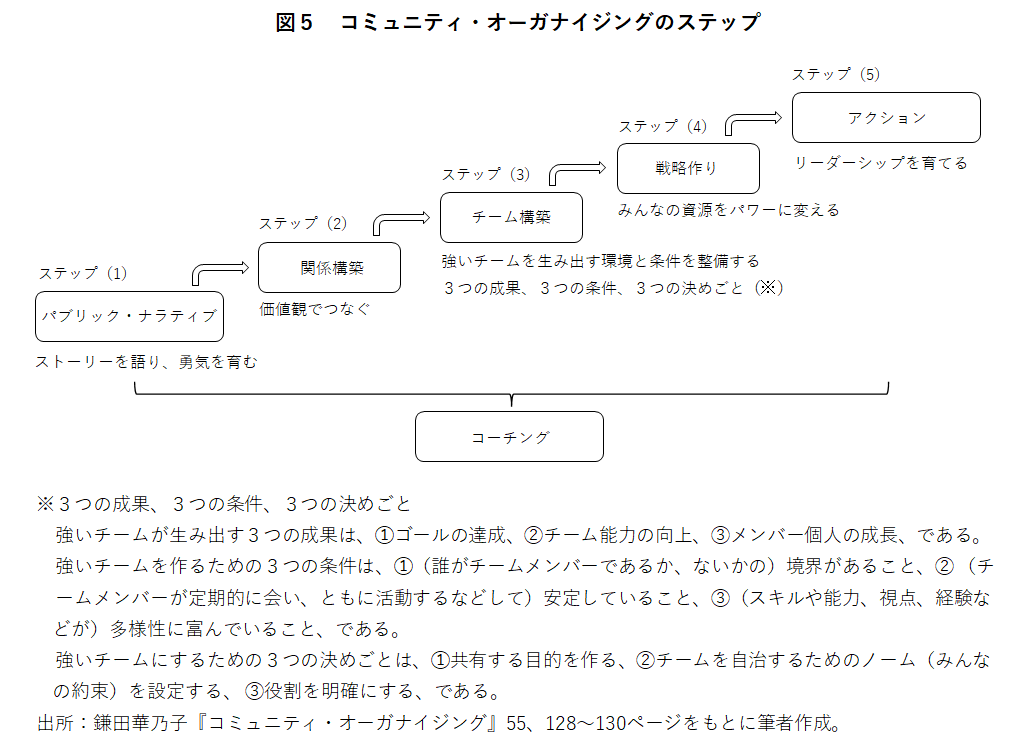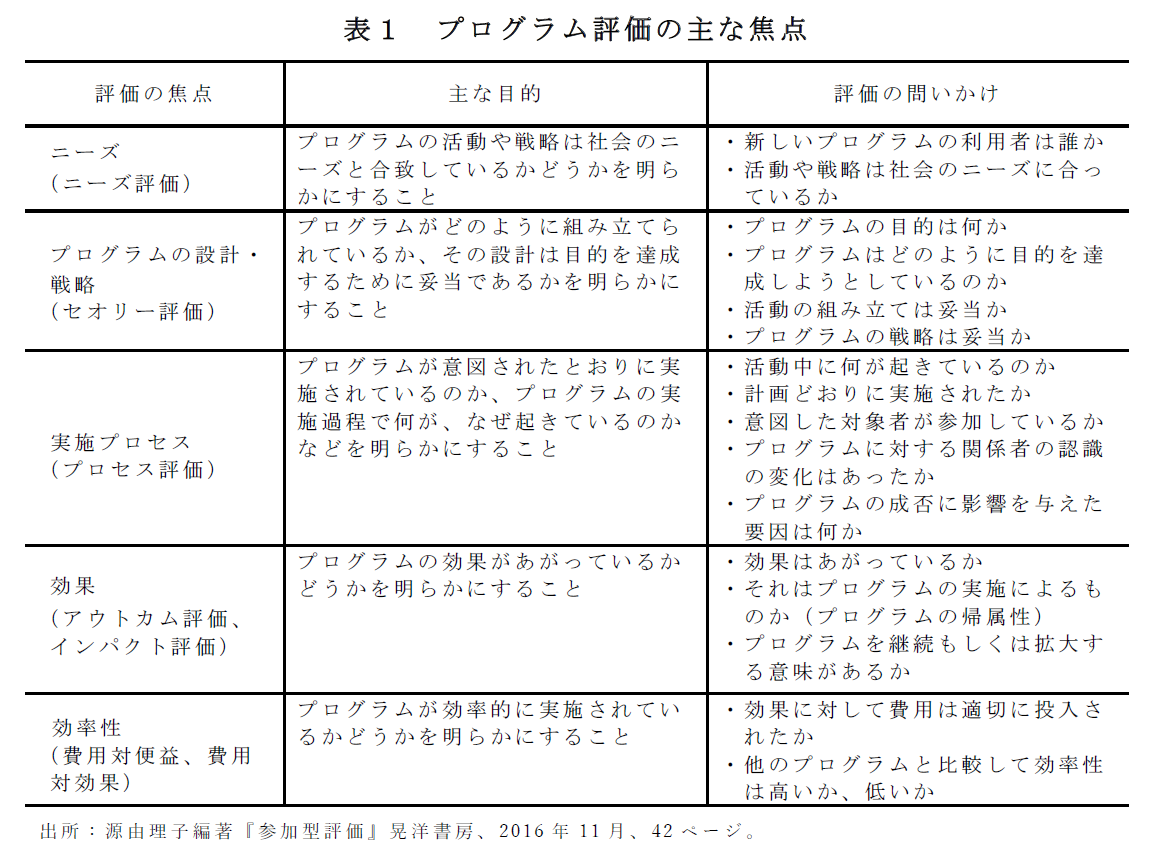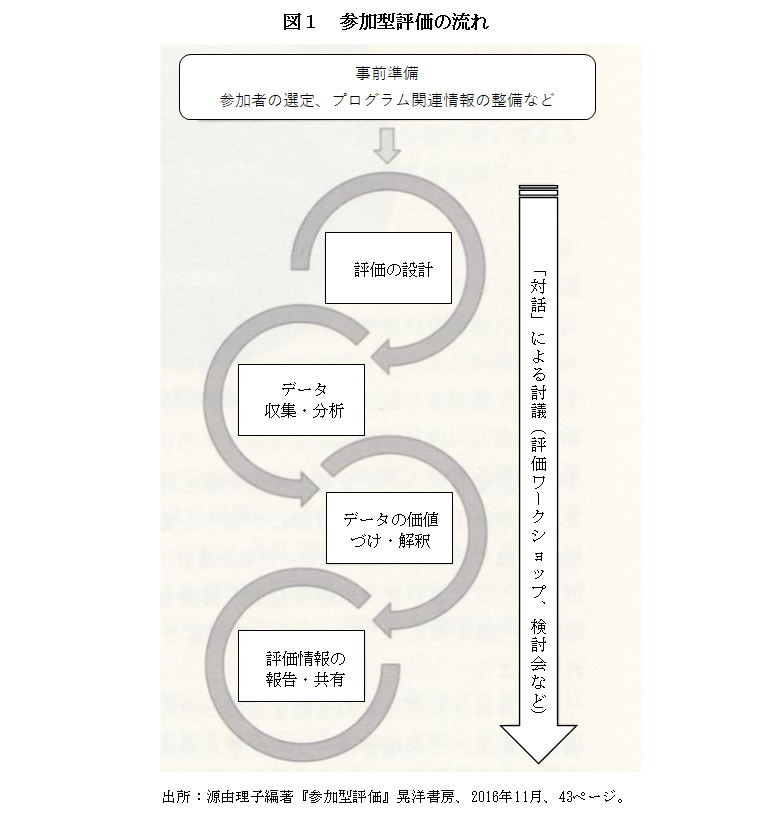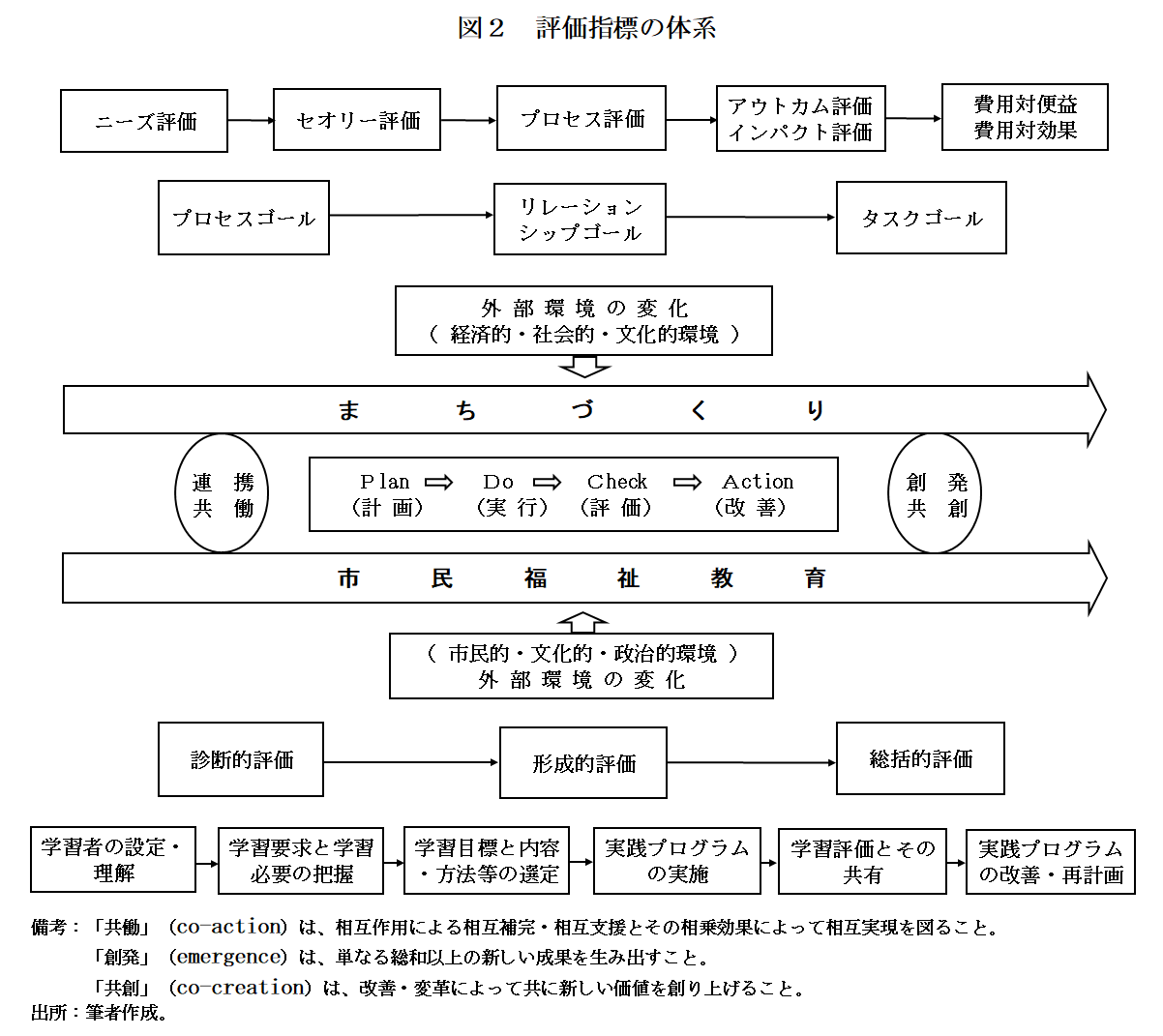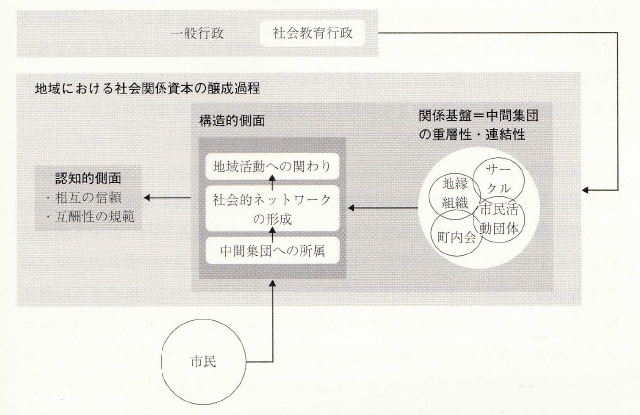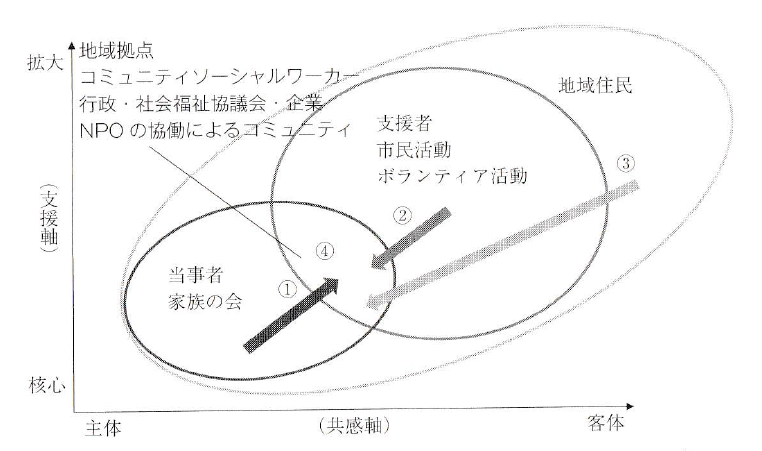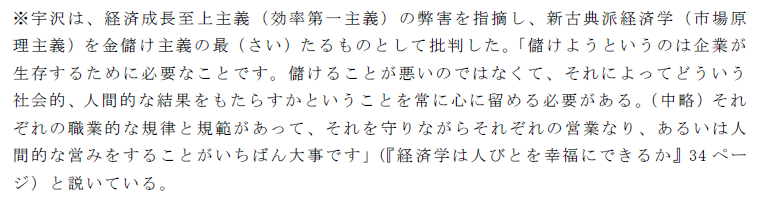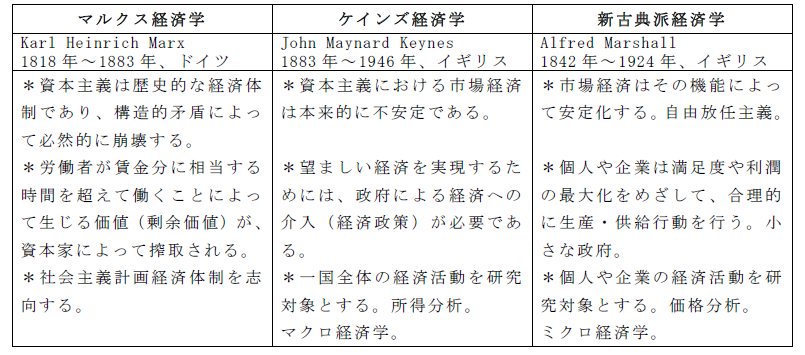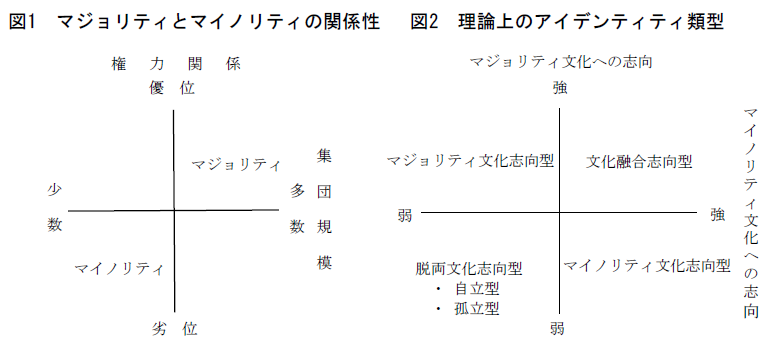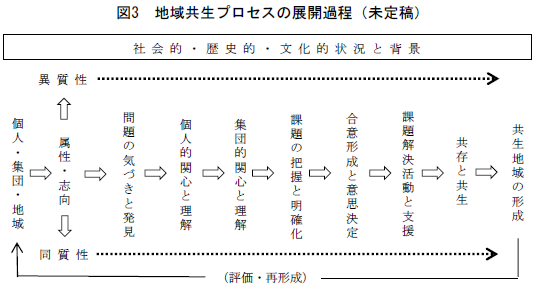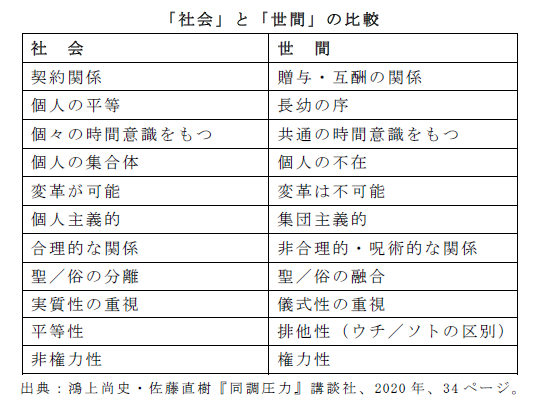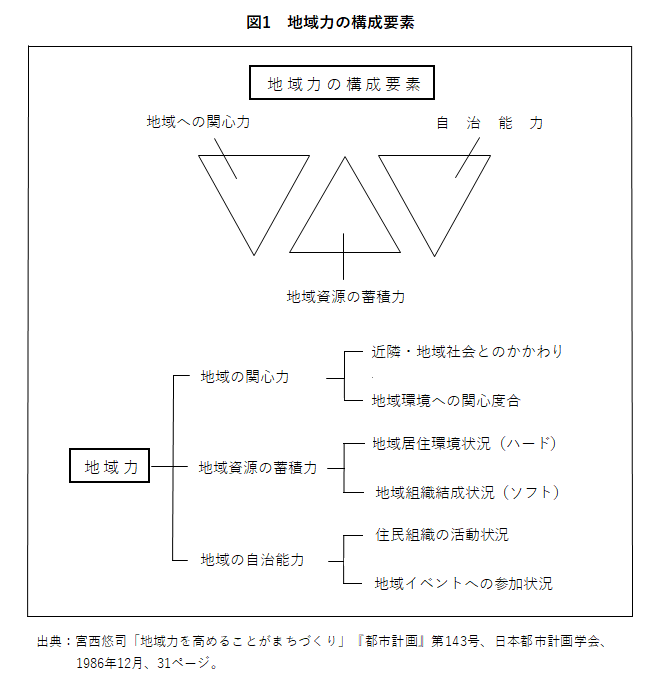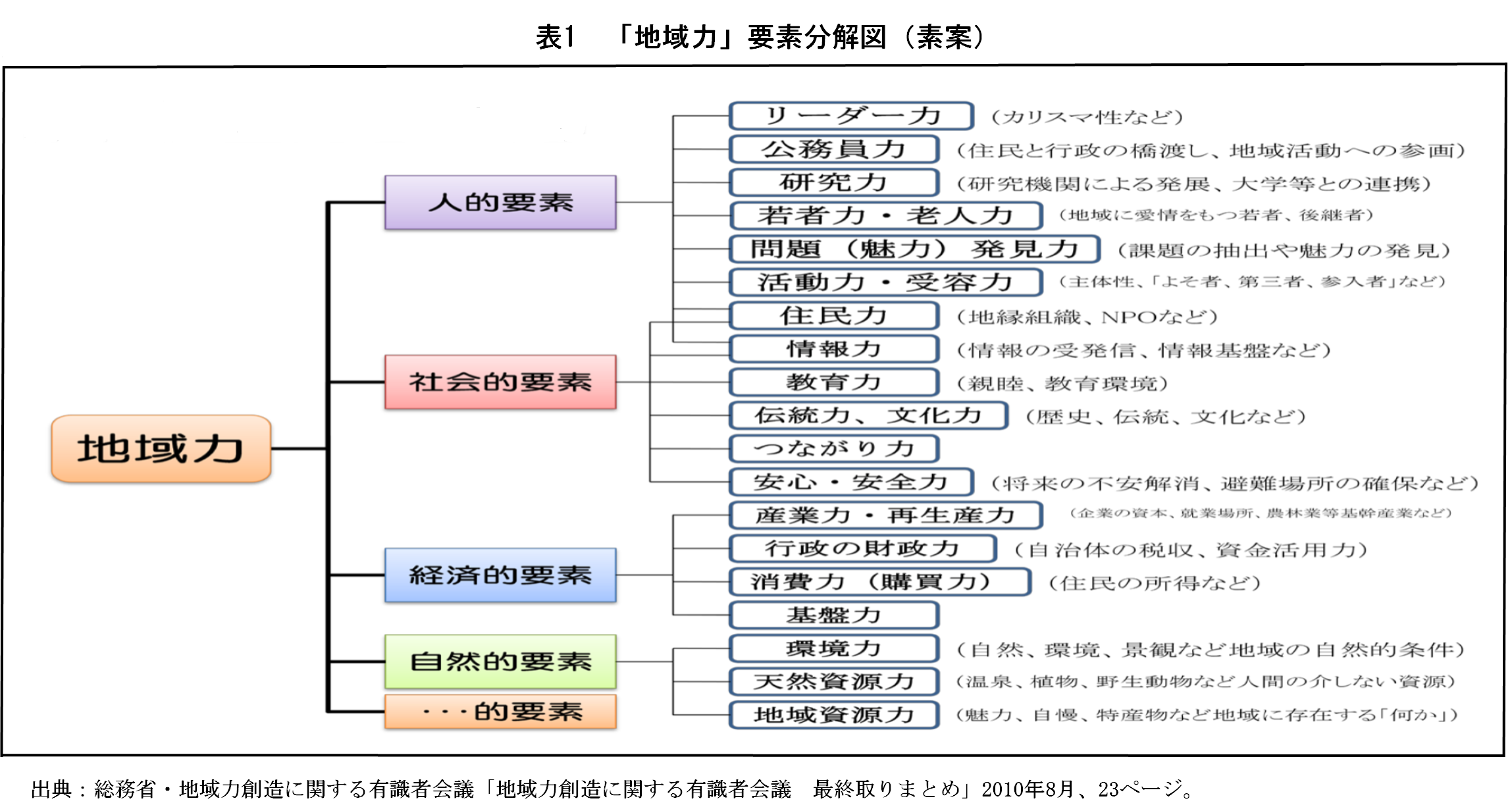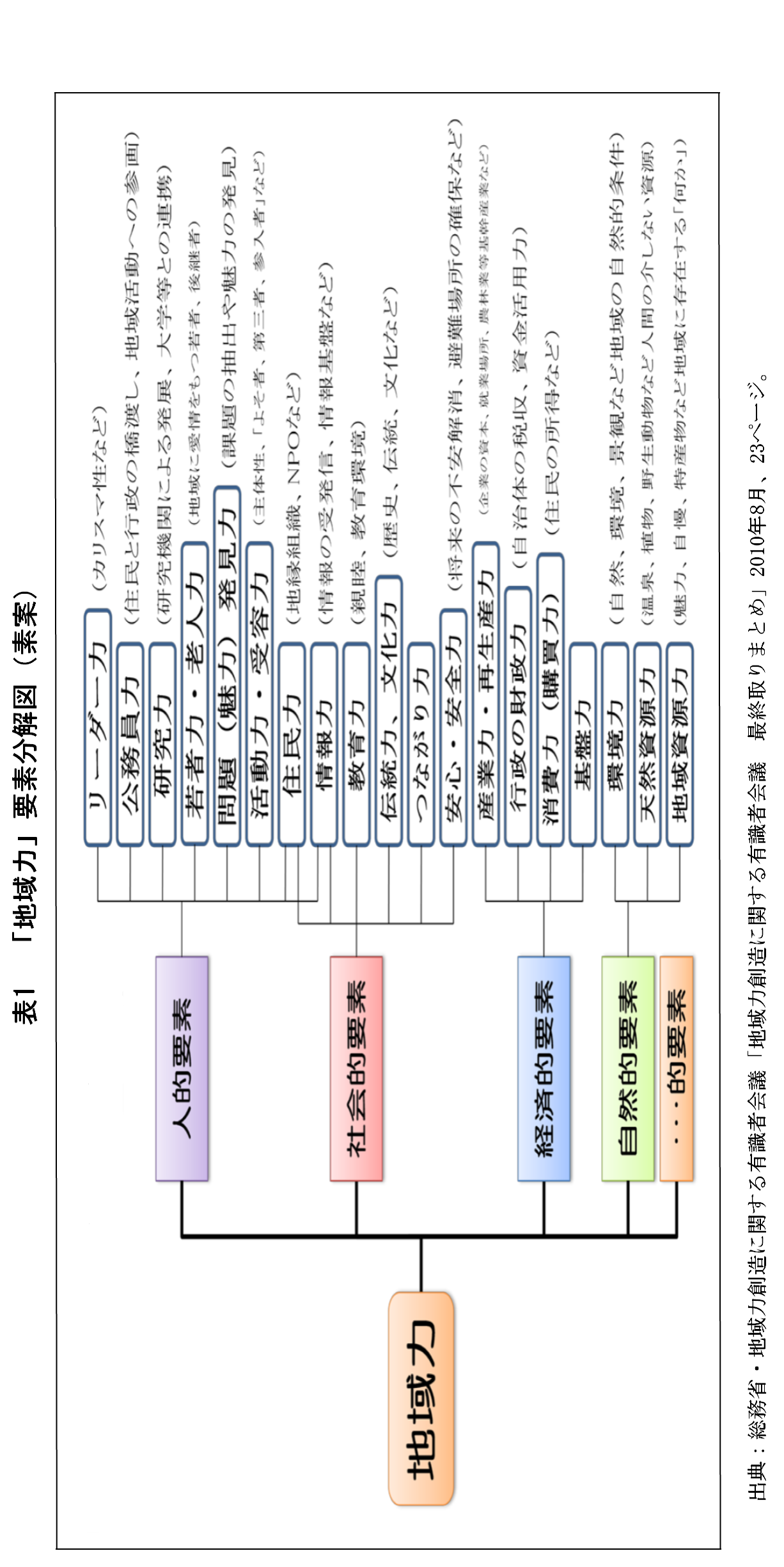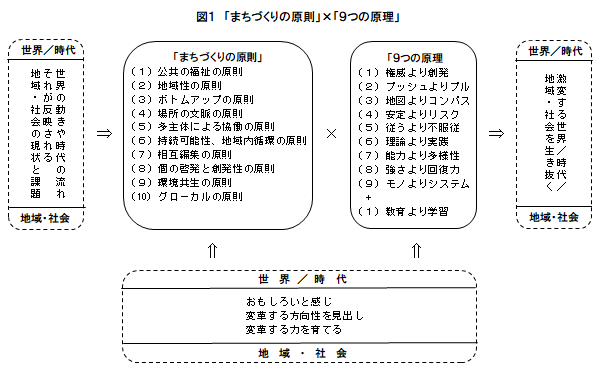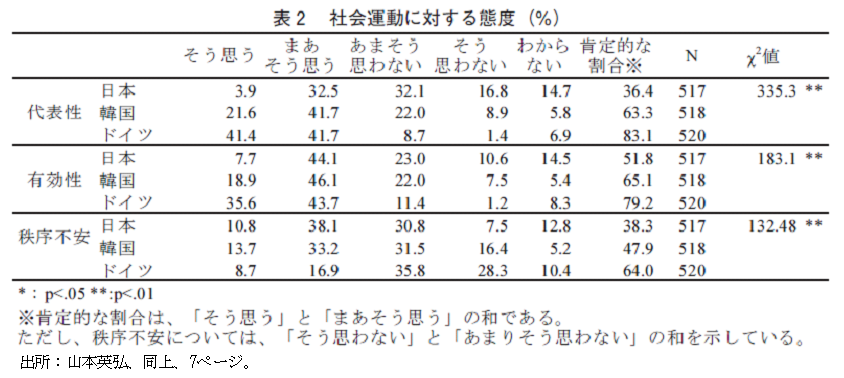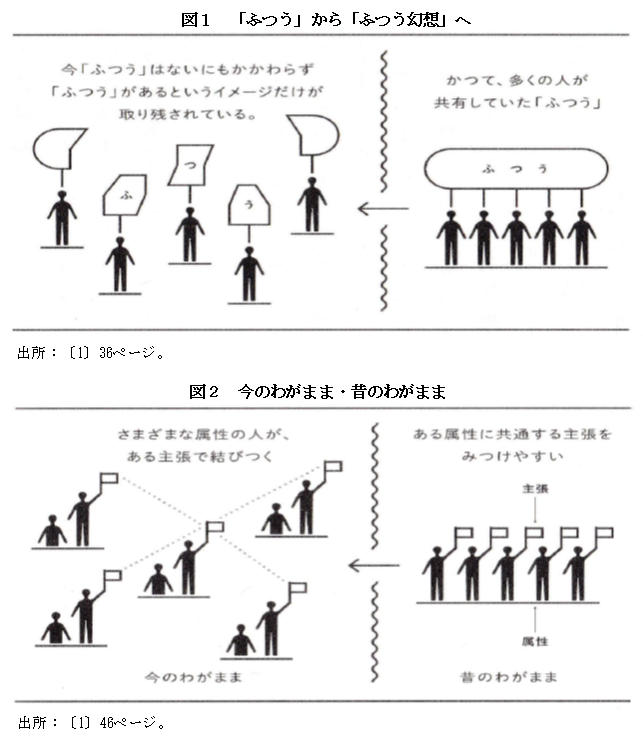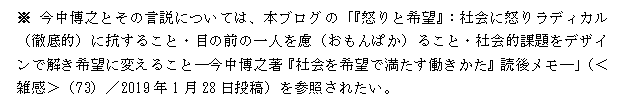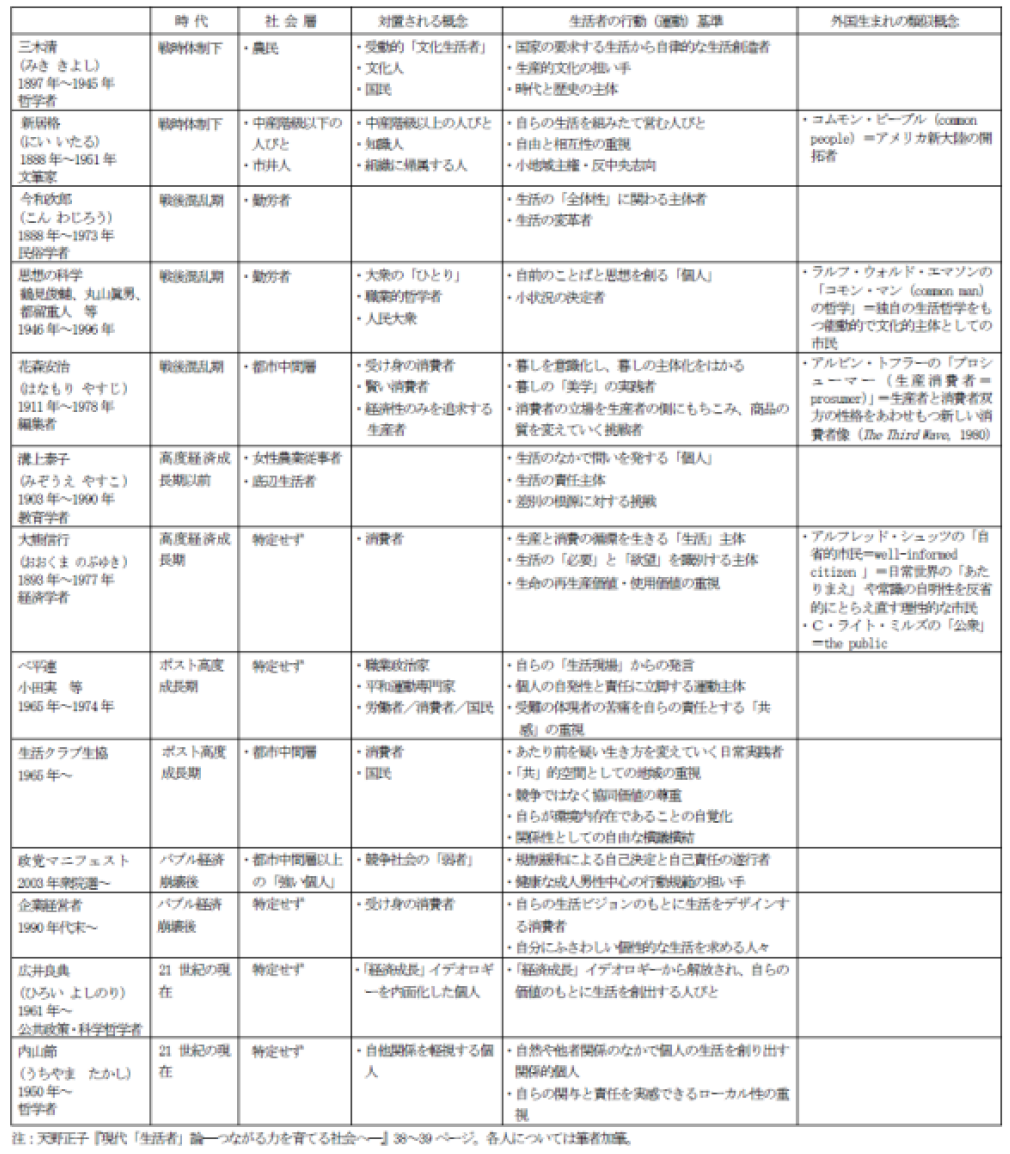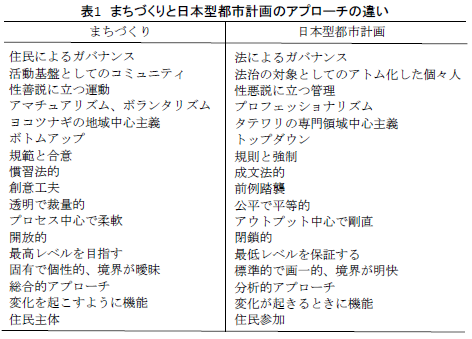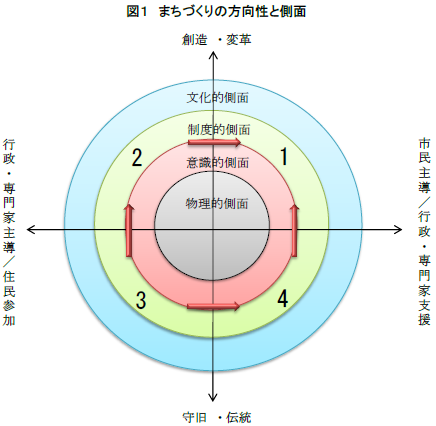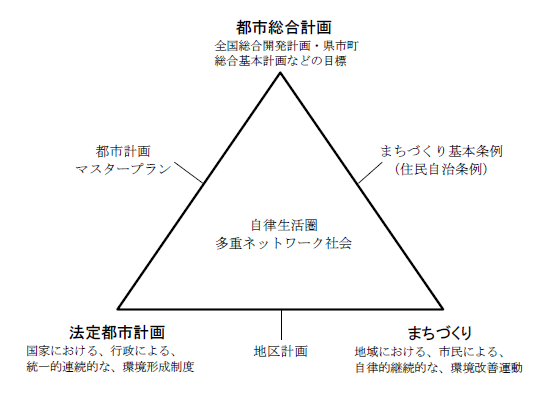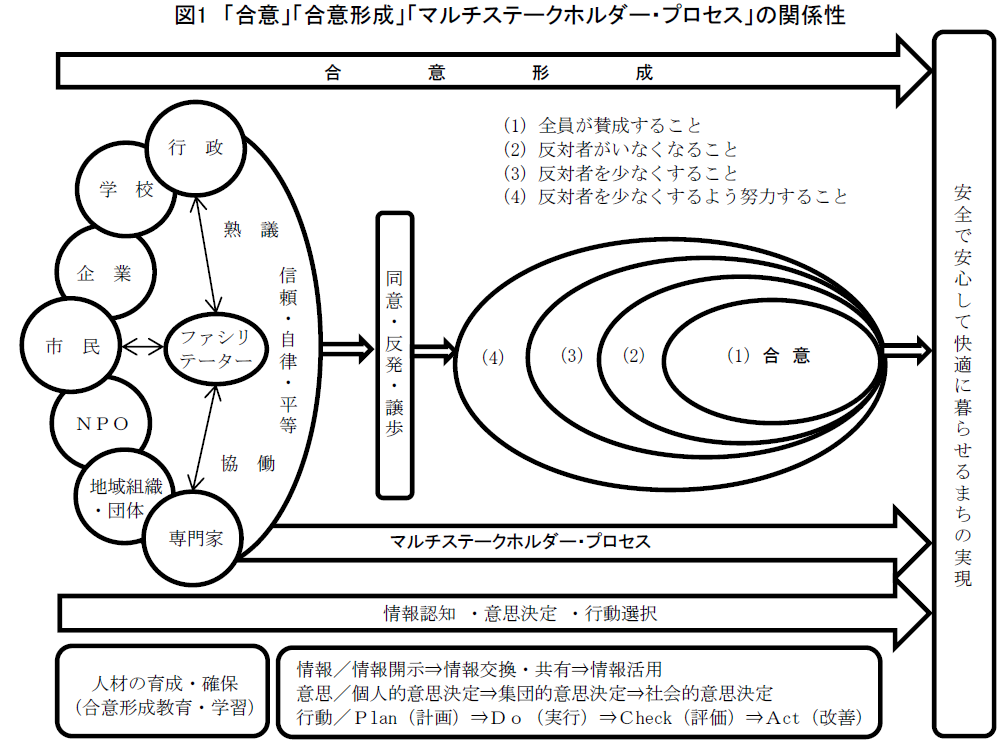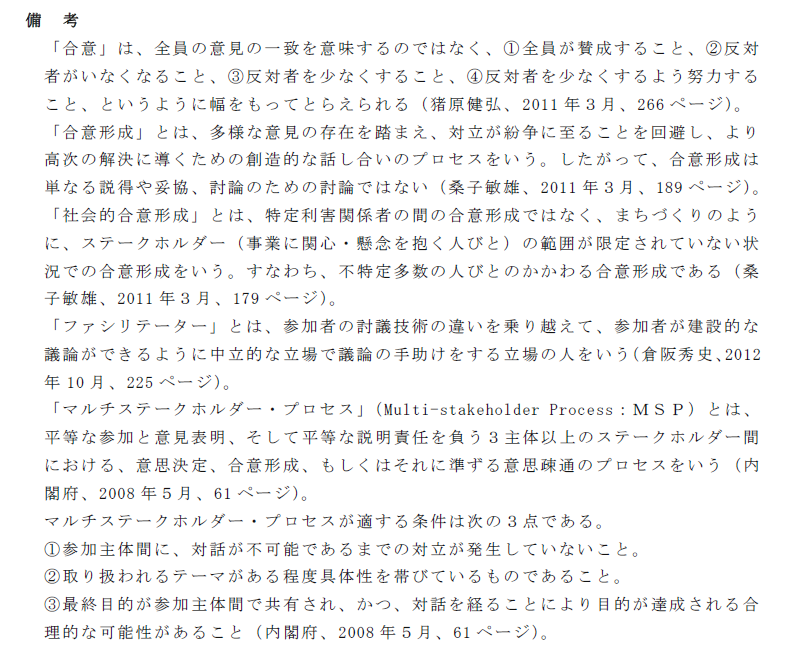新訂「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けて
―その哲学的思考に関する研究メモ―
阪野 貢/市民福祉教育研究所
はじめに―哲学のある教育実践―
01 「ふくし」の哲学
02 「正義感覚」の育成
03 「人間的連帯」の言説
04 「自己決定」の実相
05 「世間」からの解放
06 「しょうがい」と疑似体験の陥穽
07 「生」の倫理
08 「しんがり」の姿勢
09 「助けて」の表明
10 「愛郷心」の相克
11 「差別」の本質
12 「共感」の功罪
13 「利他」の学問
14 “Well-being” の視点
15 「自前」の思想
16 「生きづらさ」の正体
17 「相互支援」の人間学
18 「ふつう」の功罪
19 「批判的教育」の使命
20 「対話」の技術
21 「 弱さ」のデザイン
22 「 共同体」の教育的営為
23 「贈与」の意義
24 「共事者」の実践的態度
25 「思いやり」の暴力
26 「哲学対話」の方法
27 「地域共生社会」の模索
28 「まちづくりの哲学」の構築
むすびにかえて―支配に抗する思想―
はじめに―哲学のある教育実践―
<文献>
(1)高久清吉『哲学のある教育実践―「総合的な学習」は大丈夫か―』教育出版、2000年4月、以下[1]。
〇2019年11月、日本福祉教育・ボランティア学習学会第25回北海道大会が北星学園大学(札幌市)で開催された。大会テーマは、「未来へつなぐ、みんなでつなぐ。~多文化共生社会を育む福祉教育とボランティア学習~」であった。圧巻で感動的だったのは、本田優子による「アイヌ文化からみる多文化共生社会の創造」と題する「基調講演」であった。アイヌ語に「ヤイコシラㇺスイェ」という言葉がある。「ヤイ」は「自分」、「コ」は「に対して」、「シ」は「自分」、「ラㇺ」は「心」、「スイェ」は「を揺らす」、「ヤイコシラㇺスイェ」で「自分に対して自分の心を揺らす」となる。それは日本語の「考える」という意味である。「考える」とは「心を揺らす」こと、筆者にとって目から鱗(うろこ)が落ちる一言であった。
〇「自由研究発表」や「課題別研究」報告などでは、ひとえに筆者の浅学菲才によるものであるが、「心を揺らす」報告はさほど多くはなかった。新味のない(使い古された)テーマについて、場所や組織、人を替えただけの、あるいは横文字や権威づけられた(古めかしい)過去の言説を多用した議論では、福祉教育実践や研究の推進は望むべくもない。歴史的・社会的・文化的実践であるはずの福祉教育実践をめぐって、その現場から乖離(かいり)した抽象的な言葉・概念や思考をこねくり回すのも、然りである。そこからは、原理や理論のない、視野が狭く定型化され、矮小化された実践が生み出されるだけである。そうした福祉教育実践さえも、厳しい時代状況に押しつぶされようとしている(されている)。意図的にか無意識的にか、それを理解・認識しない実践者(あるいは実務家)や研究者がいる。また、そうした状況に抗することなく早々に諦め、受け入れ、慰め合っている人たちもいる。そこからは、福祉教育実践や研究の「展望」や「未来」は見出せない。
〇そこで、いま求められるのは、歴史的視点や哲学的思考を重視しながら、福祉教育とは「そもそも何か」、それは「いかにあるべきか」「いかに取り組むべきか」を、危機的な現場や生々しい実践とのかかわりのなかで本質的・根源的に問い直すことである。「理論と実践」の関係性について探究することなく、単なる「実践(事例)」研究にとどまりがちな福祉教育研究の現状も気にかかる。
〇そんな思いのなかで、高久清吉の[1]で、筆者なりに再確認・再認識しておきたい論点と言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「哲学のある教育実践」という言葉
「哲学のある教育実践」という言葉に接した時、ある人は、教育についての確固とした信念や信条をもった教師による実践とか、教育の理念や理想に基づく明確な思想に貫かれた実践を思い浮かべるかも知れない。また、人によっては、考え方や判断の筋道がすっきりとした実践、教師の体系的な見方や考え方が際立っているような実践をイメージするかも知れない。いずれにしても、「哲学のある教育実践」が意味するものは、だれにも共通一様に理解されるというのはあり得ないようである。(108~109ページ)
「哲学」の意味
「哲学」の意味は、通常、大きく次のような二つに分けられる。一つは、「哲学すること」(Philosophieren)、もう一つは、「哲学」(Philosophie)である。
「哲学すること」とは筋道の通った知的活動そのもの、この活動の「過程」にこそ哲学の本質があると見る立場である。それに対し、「哲学」とは知的活動の「結果」または「所産」として導き出された内容の体系、それが本来の哲学であるとする立場である。この二つの意味は、よく「過程としての哲学」と「結果としての哲学」という言葉で表現されている。この二つを切り離して別々のものと見なすことはできないが、「哲学」の意味を、一応、この二つに分けるのは妥当である。(109~110ページ)
「哲学のある教育実践」の意味
「哲学」の意味を二つに分けるとすると、これに対応して、「哲学のある教育実践」の意味も二つに分けられる。「哲学のある教育実践」の「哲学」を「過程としての哲学」と理解すれば、「哲学のある教育実践」とは、哲学的な見方や考え方が大きく作用する教育の実践、言い換えれば、教育実践上のさまざまな問題や事柄が哲学的な見方や考え方に基づいて吟味され、判断され、構想される実践ということになる。これに対し、「哲学」を「結果としての哲学」と理解すれば、「哲学のある教育実践」とは、哲学的な思考から生まれた内容、つまり、教育に関する明確な「思想」に基づく実践ということになる。
「哲学のある教育実践」のこのような二つの意味は、実は、一方がなければ、他方も成り立たないという表裏の関係にある。哲学的な考え方によって明確な思想が導き出されるし、明確な思想が前提となって、実践上のさまざまな問題や事柄についての哲学的な考え方も行われることになるわけである。(110ページ)
〇以上を簡潔に言えば、高久にあっては、「哲学」とは「いわゆる学問領域としての哲学やその学説内容ではない。いつでも、全体的・根本的なものを踏まえながら、実践や実際上の個々の問題を筋道立てて主体的・構造的にとらえていこうとする思考の働きそのもの」(まえがき、ⅵページ)をいう。そして、「哲学のある教育実践」は、「教育の理論または哲学と結び付き、これによって支えられ、方向づけられた教育実践」(97ページ)と定義づけられる。
〇そのうえで高久は、教育現場と教師について、次のように指摘する。「哲学をもたないで教育の実際の仕事に従事している教師たちに共通して認められる欠点は、本質と現象、全体と部分、本と末、重と軽との間の区別がはっきりせず、これらを簡単に混同してしまうことである」。「さまざまな問題や事柄への対応に追いまくられる教育現場において、教師のものの見方や考え方は強力に狭められてしまい、現象に振り回される本末軽重の見分けもできなくなってしまう」(112ページ)。そこで、現場教師に求められるのは、「教育の理論または哲学と、教育実践との生きた結び付きを求める問題意識」である(97ページ)。「教育現場にとって何よりも必要なのは、『普遍的理念』、つまり、教育の本質的・原理的なものをしっかりと踏まえ、これに基づく哲学的な考え方を展開していくことである」(112ページ)。
〇こうした指摘は、学校現場を含めた地域・社会における福祉教育(「市民福祉教育」)にも通底する。福祉教育学界(学会)が探究すべきものは、福祉教育の場当たり的な、対処療法的な方法・技術ではない。哲学的思考によって生み出される「福祉教育思想」(「福祉教育哲学」)と、それに貫(つらぬ)かれた福祉教育の「理論と実践」である。その際の哲学的思考は言うまでもなく、自律的で理性的、批判的な思考であり、その論理化と体系化が「哲学する」ということでもある。
〇今日、行政主体のまちづくりや福祉の公的責任の縮減、教育の国家統制の強化などが進むなかで、市民の要求や構想に基づく「まちづくり改革」や高齢者や障がい者などの真のニーズに基づく「福祉改革」、子ども・青年から出発する下からの「教育改革」が強く求められている。そこで何にもまして必要なのは、それらに関する思想と哲学である。筆者は、「まちづくりと市民福祉教育」について思考する際、歴史的視点とともに哲学的思考が必要かつ重要であることを指摘してきた。その際とりあえず、大雑把であるが、「思想」を物事についてのまとまった思考、「哲学」を物事の根源のあり方についての探究、そして「倫理」を社会において人が守るべき物事の規範、と考えてきた。本稿は、その点に多少なりとも留意しながら草してきた拙稿(論点や言説についてのメモ)の一部を集成したものである。
【初出】
<雑感>(98)阪野 貢/歴史的視点や哲学的思考を欠いた福祉教育:「福祉教育哲学」の必要性を問う―高久清吉著『哲学のある教育実践』再読メモ―/2019年12月12日/本文
01 「ふくし」の哲学
<文献>
(1)三谷尚澄『哲学しててもいいですか? ―文系学部不要論へのささやかな反論―』ナカニシヤ出版、2017年3月、以下[1]。
(2)広井良典『福祉の哲学とは何か―ポスト成長時代の幸福・価値・社会構想―』ミネルヴァ書房、2017年3月、以下[2]。
(3)糸賀一雄『福祉の思想』日本放送出版協会、1968年2月、以下[3]。
(4)阿部志郎『福祉の哲学』誠信書房、1997年4月、以下[4]。
(5)伊藤隆二『この子らは世の光なり』樹心社、1988年9月、以下[5]。
(6)仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉―<贈与のパラドックス>の知識社会学―』名古屋大学出版会、2011年2月、以下[6]。
(7)大橋謙策『社会福祉入門』放送大学教育振興会、2008年3月、以下[7]。
〇文部科学省によって、「大学改革」という名のもとで、教員養成系・人文社会科学系「学問」の「不要論」が謳(うた)われている。また、「学問」ではなく、「実践力」の養成に特化した職業訓練機関(「専門職大学」)や資格取得機関への転換が図られている。それは、「社会」的要請によるものであるというが、その際の「社会」は(政治に大きな影響力を持つ)「財界」のことを意味する。ちなみに、2023年度開学予定を含む専門職大学・短期大学は22校(大学19校、短期大学3校)、専門職学科は1学科を数えている。
〇こうした潮流に対して、[1]で三谷尚澄はいう。「頼るもののない時代のただなかに、拠って立つべき足場をもたないままに放り出された人間は、どうやって日々をしのいでいけばよいのだろう。(中略)そんなときだからこそ、それほど立派でも力強くもない人間にも届くことのできる倫理の言葉を探しておく必要があるのではないか。そして、その点において、(中略)哲学と呼ばれてきた知的営みがきわめて大きな知的貢献を行なうことができるのではないか」(81~82ページ)。「論理的・批判的に思考する」能力と「箱の外に出て思考する」能力の育成(120、151ページ)、「市民的器量(civic virtue)」すなわち「哲学の器量を備えた市民」の育成(105、195ページ)などを目的とする教育がこの国の大学から姿を消すことがあってはならない、と。「まちづくりと市民福祉教育」のあり方を問う際の根源的な問題のひとつでもある。強く認識したい。なお、「箱の外に出て思考する」能力とは、「異質なもの」や「自分とは違った考え方や意見」に対する「感受性」や「耐性」、さまざまな状況に柔軟に対応するために必要とされる「器量」をいう(151ページ)。
〇政治と社会の右傾化、福祉の私事化と教育の国家統制が進んでいる。こうした現在の社会情勢のなかで、「いつか来た道」論が唱導される。しかし、その「危機」は、「時代の繰り返し」であり、歴史の繰り返しではない(吉田久一『日本社会事業思想小史―社会事業の成立と挫折―』勁草書房、2015年10月、はしがき、ⅴページ)。新しい歴史をつくるのは、草の根の民主主義であり、歴史的で社会的な内容を失うことのない「市民」による組織的・体系的な実践(援助・支援、活動)や運動である。
〇[2]の広井良典にあっては、「ポスト成長時代」の日本社会は、(1)政府の借金の際限なき累積と将来世代へのツケ回し、(2)人々の「社会的孤立」の高さ(「無言社会」)、の “危機” 状況にある。と同時に、「新たなつながり」やネットワーク化を志向する動き(「関係性の進化」「関係性の組み換え」)がみられる。このような状況においてこそ、「人々の行動や判断の導きの糸となるような、新たな価値原理や社会構想が求められている」。いま、「福祉の哲学とは何か」が問われるところである(まえがき、ⅱ~ⅲページ)。
〇なお、[2]では、「福祉」を積極的ないしポジティブな営みとしてとらえ、「幸福」や「公共性」「宗教」「コミュニティ」「生命」などとのかかわりについて多面的・多角的な思考を展開している。それは、これまでの「福祉思想」や「福祉思想研究」とは異なる「新たな視点」からのアプローチであり、「独自の考察と構想」を提起するものでもある。
〇ところで、「福祉の思想や哲学」といえば筆者はまず、「この子らを世の光に」「発達保障」の糸賀一雄と、「ボランティアの互酬性」「コミュニティ重視志向の地域福祉」の阿部志郎を思い出す。糸賀は、「福祉の実現は、その根底に、福祉の思想をもっている。実現の過程でその思想は常に吟味(ぎんみ)される。(中略)福祉の思想は行動的な実践のなかで、常に吟味され、育つのである」([3]64ページ)という。阿部は、「福祉の哲学は、机上の理屈や観念ではなく、ニードに直面する人の苦しみを共有し、悩みを分ちあいながら、その人びとのもつ「呻き」(うめき)への応答として深い思索を生みだす努力であるところに特徴がある」([4]9ページ)と主張する。二人はともに「実践的思想家」であり、それは、先駆的な現場実践(キリスト教福祉実践)を通して形成された幅の広い、奥行きの深い「福祉の思想」であり「福祉の哲学」である。なお、周知のように、「世の光」とは新約聖書(「マタイによる福音書」)の「山上の垂訓(説教)」のひとつである(「あなたがたは世の光である」)。「互酬」とは「贈与と返礼」の社会的相互行為を意味する。
〇ここでは、糸賀の「この子らを世の光に」と阿部の「ボランティアの互酬性」について、その論点と言説を改めて[3]と[4]から確認することにする(抜き書きと要約)。
糸賀一雄:「この子らを世の光に」([3])
(精神薄弱児の教育は)彼らについて何を知っているか、彼らにたいして、また、彼らのために何をしてやったかということが問われるのでなく、彼らとともにどういう生きかたをしたかが問われてくるような世界である。(51ページ)
この子らはどんなに重い障害をもっていても、だれととりかえることもできない個性的な自己実現をしているものなのである。人間とうまれて、その人なりの人間となっていくのである。その自己実現こそが創造であり、生産である。私たちのねがいは、重症な障害をもったこの子たちも、立派な生産者であるということを、認めあえる社会をつくろうということである。「この子らに世の光を」あててやろうというあわれみの政策を求めているのではなく、この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよいよみがきをかけて輝かそうというのである。「この子らを世の光に」である。この子らが、うまれながらにしてもっている人格発達の権利を徹底的に保障せねばならぬということなのである。障害をもった子どもたちは、その障害と戦い、障害を克服していく努力のなかに、その人格がゆたかに伸びていく。3才の精神発達でとまっているように見えるひとも、その3才という発達段階の中味が無限に豊かに充実していく生きかたがあると思う。生涯かかっても、その3才を充実させていく値打ちがじゅうぶんにあると思う。(177ページ)
この子たちは、自己実現という生産活動ばかりではなく、もうひとつ別な新しい生産活動をしている。心身障害をもつすべてのひとたちの生産的生活がそこにあるというそのことによって、社会が開眼され、思想の変革までが生産されようとしているということである。ひとがひとを理解するということの深い意味を探究し、その価値にめざめ、理解を中核とした社会形成の理念をめざすならば、それはどんなにありがたいことであろうか。(178ページ)
阿部志郎:「ボランティアの互酬性」([4])
哲学という言葉は、「知恵の探求」という意味である。哲学は、答えそのものによってよりも、むしろ問いによって性格づけられる。哲学は学問の一分野であるが、「学問」が「問いを学ぶ」「問われて学ぶ」という字で構成されているのは興味深い。(9ページ)
福祉の哲学とは、福祉とはなにか、福祉はなにを目的とするか、さらに人間の生きる意味はなにか、その生の営みにとって福祉の果たすべき役割はなにかを、根源的かつ総体的に理解することであるが、それには、福祉が投げかける問いを学び、考えることである。それはニードの発する問いかけに耳を傾けることからはじまる。(9ページ)
互酬は、親族・地域共同体を維持するための不可欠な行為で、今でもアジアの共同体は互酬で成り立っている。戦後の日本社会では、共同体は封建遺制として否定され崩壊の途をたどったのに、目標とするコミュニティは未だつくられていない。でも、互酬は生き続ける。香典、
香典返し、結婚祝い金、引き出物、中元、歳暮の風習は、ヨーロッパ社会ではまったくみられない。しかし、共同体を維持する機能としての互酬は失われ、かつアジアの互酬を支える宗教性も日本社会にはないのが実態だ。(92ページ)
互酬制と近代型福祉、さらに伝統的ボランティアと有償型サービスとのあいだに深いギャップがあり、ときおり、雑音が聞こえぬわけでもない。アジアの共同体のなかにたくましく息づいている互酬制――分かち合いの相互扶助――に今ひとたび目を向け、そして日本の地域社会の現実を見直したうえで、自立と連帯の福祉社会を創出する発想に切り換えるのが望ましいのではないか。時代とともにニードが変わるから対応が多様化するのは当然である。その態様はどうであれ、住民が福祉を学習し、理解し、実践に参加するまちづくりを推進する必要を痛感せずにはいられない。(126~127ページ)
〇「福祉の思想や哲学」の探究は、実証的・実践的なものでなければならない。それによってその思想や哲学は広め、深められ、また新たな思想や哲学の形成が図られることになる。ここでは、筆者の姿勢が評論家的なそれであることを承知のうえで、糸賀の「この子らを世の光に」に対して伊藤隆二の「この子らは世の光なり」、阿部の「ボランティアの互酬性」に対して仁平典宏の「贈与のパラドックス」についての言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
伊藤隆二:「この子らは世の光なり」([5])
糸賀一雄氏は戦後、最初の公立福祉施設「近江学園」をつくり、この子らの教育福祉に邁進(まいしん)し、ついに「この子らに世の光を」を「この子らを世の光に」に転回させたのである。「この子らを」というとき、われ(または、われわれ)は主体で、「この子ら」は客体になる。主体が客体に働きかけ(あるいは操作し)、「世の光に」まで高めてやるのだという発想には、ある種の傲慢(ごうまん)さがあるし、「この子ら」の本質への誤解がある。また、「この子らを世の光に」というとき、まだこの子らが「世の光」であることを認めていない。そこで教育し、きたえ、みがきをかけて、やっと世の光になりうるのだという見方である。わたくしは、この子らと長く深くかかわっているが、この子らは生まれながらにして「世の光」だと知った。正確にいうと、生まれたときから死ぬときまで、いや死んでもなお世の光でありつづける。「この子らは(そのままで)世の光である」。「この子ら」は主体であって、世を照らしつづけているのである。(223~224ページ)
仁平典宏:「贈与のパラドックス」([6])
阿部志郎も「互酬性」を基盤に据えたボランティア論の担い手の一人である。阿部は1973年の時点では、ボランティアの報酬性を明確に否定していたが、1994年には態度を180度と言ってもいいほど「軟化」させている。彼はまず、共同体や地域社会において不可欠な行為として「互酬性」を取り上げ、「香典―香典返し、結婚祝い金―引き出物、中元、歳暮の風習」を例示する反面、その基盤は失われてきているという。その一方で、新たに登場してきた「相互に有料で利用し、有償でサービスを提供する」「市民参加型福祉サービス」に、「互酬の近代化・組織化」を見る。彼によると、これらは「(1)会員の自主性にもとづく、(2)友愛・協同の思想にたつ、(3)有償とはいえ実費弁償的性質のもので収益を目的としない、(4)グループとして、ボランタリー・アソシエーションの性格を保つ」ことから「広義のボランティアの原則からはずれていない」と述べる。このように、ここで「互酬性」という思想財を獲得することによって、「ボランティア」という言葉は高い汎用可能性を配備することが可能になった。担い手にとって効用があると言えるなら、経験・楽しさ・友達づくり・評価・金銭的対価などを、区別なく堂々と「ボランティア」として肯定できる。<贈与のパラドックス>は、このような形で「解決」されるべきこととなった。(381~382ページ)
〇仁平の「贈与のパラドックス」(paradox、逆説・矛盾)とは、贈与は行為者の真の意図とは別に、交換や見返り、偽善や自己満足などとして外部観察されがちである、という意味であろう。平易に言えば、「贈与の偽善性」「贈与の疑わしさ・怪しさ」である。ボランティアについての言説の歴史は、こうした「贈与のパラドックス」を如何に解決するかの歴史であった、と言ってよい。
〇いま改めて「福祉の哲学」の必要性を強調する一人に、「実践的研究者」である大橋謙策がいる(注①)。大橋は[7]で、「住民と行政との関係を上下の関係で捉えるのではなく、住民の自立と連帯を前提にし、対等の立場で問題解決を図る新たな社会哲学、社会システムが求められ、社会福祉のような歴史的に国の『社会の制度』として発展してきたものも従来にない発想が求められている」(30ページ)として、次の3つの「思想」を取りあげる。(1)フランスの近代市民革命の際にうたわれた「博愛」の思想(自由と平等を担保する「博愛」)。(2)ノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンといった思想(「社会的包摂」)。(3)自分たちで相互扶助組織をつくり、対応しようとする考え方(「協同組合方式」)、がそれである(28~30ページ)。そして大橋はいう。「ソーシャルワークを展開する際の価値の1つは、人間性を尊重し、社会正義と公正を守ることであり、人々の自由と平等を保障することであるが、それらを標榜すればするほど、人々が社会的にも、個人的にも “博愛” という社会の神聖な責務を遂行することが求められる。(そのためには)伝統的な意識と行動を尊重しつつも、新たな社会システムに必要な価値、意識として “博愛” の精神の涵養とそれを推進する福祉教育が求められる」(227ページ)。再認識したい。
〇なお、大橋は、全国各地における草の根の地域福祉実践の向上と「バッテリー型研究」に取り組んでいるが、最近の政策動向に関して、「地域福祉が“我が事”になり、その危険性を警鐘すべきである。戦前の歴史を忘れた政策は恐ろしい」という(筆者への書簡)。地域共生社会が「上から」の押しつけ(「教化」)によるものであってはならない、という指摘である。「バッテリー型研究」については、大橋謙策『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク―』中央法規出版、2022年4月、ⅱページを参照されたい。
〇また、「博愛」に関しては、次の諸点にも留意しておきたい。(1)フランス革命は、新興の「ブルジョワジー」(有産階級、中産階級)による革命である。(2)その理念は、「自由、平等、友愛」であり、「自由、平等、博愛」ではない。(3)「自由」は、多様性を保障するが、不平等を生むことにもなる。(4)「平等」は、突き詰めれば全体主義や不自由を生む。(5)「友愛」とは、他者を自分の本当の兄弟のように愛すること(社会秩序)を意味する。(6)「博愛」には、「慈善」と同様に、階級差別的な意味合いがある、などである(注②)
注
①「福祉を哲学する」ひとりに秋山智久がいる。秋山は、「福祉哲学の必要性」を次の8点に要約している。(1)平和・人権・安全の希求、(2)人間尊重の確認、(3)社会福祉の進む方向の示唆、(4)社会福祉的人間観の確立、(5)「倫理綱領」の検討、(6)実践の価値観の探求、(7)社会福祉利用者の人間としての不幸、人生の不条理の解明、(8)実践の拠り所としての価値観・人生観の提供。これらの必要性は、秋山にあっては、将来より広義の「福祉哲学」が体系化されるときに、その主要な「構成要素」ともなるものである(秋山智久・平塚良子・横山穫『人間福祉の哲学』ミネルヴァ書房、2004年6月、45~47ページ)。
②フランス革命の理念は「自由、平等、友愛」である。「自由」は放置すればアナーキズム(無政府主義)に行き着く。「平等」は突き詰めたら全体主義や共産主義になる。「友愛」は友を愛するであり、他の宗教や民族は除外される。「博愛」とは違う(中川淳一郎・適菜収『博愛のすすめ』講談社、2017年6月、35、98ページ)。
【初出】
<雑感>(59)阪野 貢/引き続き「福祉教育」してもいいですか?―“福祉を哲学する”はじめの一歩:「世の光」(糸賀一雄)と「互酬性」(阿部志郎)、そして「博愛」(大橋謙策)/補遺:大橋謙策「最終講義」(レジュメ)(2010年3月13日)―/2018年1月25日/本文
02 「正義感覚」の育成
<文献>
(1)伊藤恭彦『さもしい人間―正義をさがす哲学―』新潮新書、2012年7月、以下[1]。
さもしい:①見苦しい。みすぼらしい。②いやしい。卑劣である。心がきたない。
正義:①正しいすじみち。人がふみ行うべき正しい道。②正しい意義または注解。③(justice)㋐社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。現代ではロールズが社会契約説に基づき、基本的自由と不平等の是正とを軸とした「公正としての正義」を提唱。 ㋑社会の正義にかなった行為をなしうるような個人の徳性。(新村出編『広辞苑』(第六版)岩波書店、2008年1月)
〇周知のように、2015年6月、選挙権年齢を満18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立した(施行は2016年6月)。そしていま、高校生らの政治や選挙への関心を高め、政治的教養を育む教育のあり方が問われている。
〇「まちづくりと市民福祉教育」について考えてきた筆者は、これまで、「政治」(とりわけ地方政治)を重要な検討課題のひとつとして位置づけてきた。また、各地のまちづくりにかかわるなかで、地域における政治的・社会的権力や地元住民(「有力者」)の言動に戸惑ったこともあった。そのとき、正義感をひけらかすわけではないが、「さもしい」や「正義」という言葉が脳裏に浮かんだのも偽らざる事実である。
〇[1]で伊藤恭彦は、政治「哲学的思考を思い切り『低空飛行』させ」(18ページ)、わかりやすく、ユーモアを交え、ときには自虐ネタをふりかけながら「さもしさ」の正体を追う。そして、伊藤の主張(結論)は、シンプルでクリアである。「私はいろいろな考え方や生き方をする人々が、ゆるやかに共存している社会が望ましいと思う。正義という言葉を使って一人一人をお説教するのではなく、最低限の正しい制度についてみんなで考え、合意し、それを形作ることを目指した方がいい。正義は制度を通して実現される。制度とは、すべての人間を架け橋でつなぐ最低限の絆でもある」(205ページ)、というのがそれである。
〇以下に、(1)「さもしさ」と「正しさ」、(2)「お互い様」の倫理と制度化、(2)「私憤」と「公憤」、という項目を設けて、伊藤の論点や言説の要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
(1)「さもしさ」と「正しさ」
私たちは既に十分豊かであるにもかかわらず、他の人をさしおいて貪欲に利益を追求しているかもしれない。さらには誰かの不幸の上に自分の豊かな生活を作り上げているかもしれない。こうした態度を「さもしい」と呼びたい。(14ページ)
「さもしさ」が人と人との関係を意味しているとするならば、その反対語は「正しさ」になる。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは倫理の体系の中に「正しさ」(正義)を位置付け、それが人間関係においてとても重要であることを説いた。「不正な人と思われているのは、(1)法律に反する人と、(2)貪欲な人、すなわち、不平等な人である」という。(57ページ)
「さもしい」とは倫理的に言うと不正な人間関係を意味している。不正だと言う理由は、自分の「分」を超えて何かを得ようとするからである。一人一人が「分」を超えて欲望を追求すると、すごく不平等な人間関係ができあがってしまう。これを押さえ込むためには、一人一人の「分」を確定する基準が必要だ。しかし、この基準を確定できるほど、私たちの社会は単純ではない。そこで生きている人間はみな違い、おかれた環境もみな違うからである。(71~72ページ)
「分」とは、ある人がもっている価値であり、その人の必要性や功績や長所などにあったその人にふさわしいものをいう。不正とは自分の「分」を守らないことであり、正義とは「その人にふさわしいものを与える」ことを意味する。各人の「分」を決めるにあたり、分かりやすい基準は、自由な行動と自己責任である。(59~62、72ページ)
自由社会(市場社会)は、競争社会である。市場社会の競争は全員に参加を強制する。競争である以上、順位がつく。かくして市場競争は必然的に不平等を生み出す。不平等の発生を必然と捉えた上で、問題を含んでいない不平等とは何か。別の言い方をすれば、許される(倫理的に許される)不平等とは何か。これが不平等と格差(不平等が、ある限度を超し、問題を含んでいる場合の表現)を検討するときに中心に据えられなければならない問いだ。不平等に対してこうした問いを『正義論』の著者ジョン・ロールズも立てている。ロールズは現代社会にふさわしい正義として、①「基本的な自由を全員に保障すること」、②「機会(ライフチャンス)の実質的平等をはかること」、そして、③「それでも残る不平等は社会の最も不利な人々の利益になること」、という三点を指摘している。不平等はあってもよいが、社会で最も不遇な人々の状況改善に役立たなくてはならないというわけだ。
不平等や格差を捉えるときには、視点を不平等の底辺にいる人々に定めなければならない。もし、不平等の底辺にいる人々が過酷な状態に放置されているならば、その不平等は問題だと言える。(98~99、101~102ページ)
(2)「お互い様」の倫理と制度化
共同体社会の名残として、私たちの社会には「お互い様」という考えが残っている。「困った時はお互い様」である。(106ページ)
「お互い様」は、日本的共同体関係に源をもつ言葉だと思われる。共同体的なもたれ合いという互酬性がここには含まれている。ただ、同時に「お互い様」には、相手の立場になってみるという大切な洞察が含まれている。つまり、自分の視点と他人の視点を入れ替えてみるわけだ。共同体的な倫理と正義は異なるかもしれないが、「お互い様」の倫理には公平さや正義につながる視点が含まれている。そう考えてみると、「お互い様」という美しい発想を、制度の中に組み込んでいくことは正義を満たす一つのルートになるだろう。できることなら困っている人を助けたいとほとんどの人は思うだろう。ただ、助けることを個人に任せると、同じ苦境に立ちながらも、助けられる人と助けられない人という不公平が生じる。だから、市場社会の底辺で苦しむ人々を助けるための基本的な仕組みは、社会制度にした方がよい。(113~114ページ)
お互いに助け合うという制度は、自己責任を曖昧にするものではない。不運な人を助けることは、その人がまた自己責任に基づいて行動していく途を確保することでもある。つまり、自由な選択とか自己責任とかいった価値を、助け合いの制度は損なうのではなく、逆に輝かすことになるのだ。(123ページ)
不平等の底辺で苦しむ人々を助けることは、最低限の正義だと思う。私たちはこのような正義感を制度にきちんと組み込む必要がある。そして、そんな制度をつくり、制度の維持に貢献したならば、後は自由に自分の欲望を追求しても「さもしい」とは言われない。(137ページ)
(3)「私憤」と「公憤」
正義は、人を苦しめる構造、人を食い物にして利益を得てしまう構造、この構造を改革することである。正義が求めるのは、構造を規制する制度の形成や制度の改革である。(159~160ページ)
社会の中で苦しんでいる人を助けることが、正義の優先課題である。正義という規範に従って社会を構想してみること、これが今、私たちに求められることだ。正義はそれを支える感情も必要としている。それは「むかつき」といった私憤ではない。「私が公平に扱われていない」という怒りを、同じように社会で不公平に扱われている人々の境遇と重ねあわせることで生じる「これはおかしいだろう」という感情だ。私的なむかつきではなく、社会の不正を訴える怒りである。それは私憤ではなく、またバラバラな私憤の寄せ集めとしての興奮でもない。社会全体の不公平や不正義に対する憤り、つまり公憤だ。不公平に対する公憤を紡ぎ合わせ、それを社会的な公平感に高めていくこと、これが現実社会に生きる私たちの正義感になる。そしてそれが制度改革を導くだろう。(197~198ページ)
〇以上から分かるように、伊藤は、社会の不公平や不平等の「さもしい」問題を解決するのは、「正しさ」(正義)にかなった公平な「制度」である。先ずは政治による制度の形成が肝要である、と説いている。そういうなかで、次の一節は大いに首肯するところである。それに関して、福祉教育の実践・研究における似たような姿勢・態度を律したい。
政治家の中にもやたら道徳的お説教をしたがる人がいる。「親を敬え」「郷土を愛せ」「公共心をもて」などと。そのメッセージ自体には問題がないとしても(本当は問題の多い道徳を語っている場合も多いが)、お説教は政治家の仕事ではない。政治家は全身全霊をかけて制度の再構築に取り組むべきだ。そのために税金で雇われている。上から目線で道徳を語るヒマがあったら、制度構築のために政治学、政治哲学、公共政策学などを学ぶべきだ。(205~206ページ)
〇ただ、制度の構築は政治(政治家)の役割であるが、そのすべてを政治に任せておけばよいというものではない。国政であれ地方政治であれ、政治をつくるのは国民・市民の一人ひとりである。すなわち、制度(法規、仕組み、きまり)の形成や運営、またその改革に直接的あるいは間接的に参加(参画)して公平・公正で平等な社会を創り、それを保持するのは、国民・市民一人ひとりである。その際、「私憤」や「公憤」を感じる能力、「正」や「不正」を判断する能力、すなわち「正義感覚(the sense of justice)」が問われることになる。
〇人は、親子の愛情や信頼関係に基づく親の指示や命令、禁止などを通して、道徳的な感情や態度を習得する。また、自分の身の回りや日常生活における仲間との関係で、正義や不公平(不正義)の感覚や感情を持ったり、表出したりする。それはより広い地域・社会における正義を求め、さらには政治的あるいは法的な正義を求める感覚や感情を醸成することになる。そして社会での正義感覚は、制度を遵守することに向けられ、また必要に応じてそれを改革することによってより一層の「秩序だった社会」が形成・保持されることを要請する。
〇このように、社会における正義や制度による秩序は、家庭での親子関係や集団での仲間関係における正義感覚によって基礎づけられる。そして、その正義感覚は、子ども・青年が地域・社会のなかで成長するにつれて徐々に習得されていく。
〇そうだとすれば、子ども・青年から大人までの正義感覚をいかに育成し、発達させるかが重要な問題となる。それを「まちづくりと市民福祉教育」に引き寄せて言うとすれば、市民福祉教育を通じた正義感覚の育成が、(子ども・青年から大人までの)市民の人権意識や地域における助け合いの意識を高め、市民的資質や能力(シティズンシップ)を形成し、それに基づいたまちづくりの社会的実践(援助・支援、活動)や運動を促すことになる。別言すれば、正義感覚は、市民的資質や能力の重要な構成要素であり、市民によるまちづくりはそうした正義感覚に基づいた理解力と判断力、実践力を欠いては機能しない、ということである。その意味では、市民福祉教育における正義感覚の育成という課題は、シティズンシップやその教育のあり方を追求するなかでより明確なものとなる。筆者が市民福祉教育の基本的概念として「シティズンシップ教育」を重視する所以である。
〇「まちづくりと市民福祉教育」はこれまで、「共生」の理念のもとで、政治や社会への参加(参画)や協働(共働)を重視してきた。しかし、「正」「不正」を判断するのに必要な正義感覚の育成・形成については、必ずしも十分に関心を払ってきたとは言えない。まちづくりの実践や運動に向けた、またその実践や運動における(子ども・青年から大人までの)市民の正義感覚の育成・醸成が大きな課題になる。
補遺
〇 不平等や格差を肯定する立場に立つと、不平等や格差そのものを解消するための取り組みは消極的なものにならざるを得ない。その際の取り組みは、いわゆる勝ち組と負け組のうち、負け組の人びとに「再チャレンジ」の機会を用意することになるが、結果的には勝ち組と負け組の入れ替えをするだけに過ぎない。しかも、その機会をとらえて努力する限りでは支援(「助け合いの制度」)の対象とされるが、努力の質量によって支援の対象から外されることになる。そこにあるのは排除の論理(排除の正当化)である。
〇そこで求められるのは、個人の「意欲」「能力」「努力」などの有無や質量を個人的・内面的なものに押しとどめるのではなく、それを下支えする多面的・重層的な社会システムをどう構築するかということである。すべての人が、その属性や帰属にかかわりなく、「自立と連帯」「自律と共生」の社会的な互恵的信頼関係のなかで平等に扱われ、共に支え合い、それを通して社会への完全参加を果たすことが強く求められる。
【初出】
<ディスカッションルーム>(53)阪野 貢/「正義感覚」とまちづくり:伊藤恭彦著『さもしい人間』を読む―資料紹介―/2015年12月11日/本文
03 「人間的連帯」の言説
<文献>
(1)馬淵浩二『連帯論―分かち合いの論理と倫理―』筑摩書房、2021年7月、以下[1]。
(2)齋藤純一『不平等を考える―政治理論入門―』ちくま新書、2017年3月、以下[2]。
「人間の尊厳と存在意義―生の無条件の肯定と豊かに生きるということ―」について筆者は、次のように考えている。すなわち、人がそれぞれ、みんなと豊かに生きるためには、「 “ただ生きる” ことの保障」と「 “よく生きる” ことの実現」、そして「 “つながりのなかに生きる” ことの持続」が必要かつ重要となる。
「 “ただ生きる” ことの保障」は、人はそれぞれ、いま、ここに生きているというそのことに本源的な価値がある、という考えに基づいている。
「 “よく生きる” ことの実現」は、人にはそれぞれ、やりたいこと・やれること・やらなければならないことがある、という考えに基づいている。
「 “つながりのなかに生きる” ことの持続」は、人はそれぞれ、社会や歴史・文化・環境などとのつながりのなかに生きている、という考えに基づいている。
〇馬淵浩二は[1]でまず、(1970年代以降の)新自由主義の影響のもとで消費主義をはじめ個人主義や能力主義が強化され、多元化や多様化が進み、格差や分断が拡大した現代社会にあって、「連帯」という言葉はすでに「賞味期限」が切れているのだろうか、と問う。その答えは「否」である。そのうえで馬淵は、「連帯(solidarity)」概念の類型化と最大公約数的な定義を試みる。具体的には、代表的な「社会的連帯(social solidarity)」、「政治的連帯(political solidarity)」、「市民的連帯(civic solidarity)」、「人間的連帯(human solidarity)」についての主要な論者の連帯論を辿り、自身の「人間的連帯論」を構想する。その基底にあるのは、人間は連帯的存在であり、相互扶助的な関係のなかでしか生きられないという人間観である。すなわち、[1]の基調を成すのは「連帯は人間存在の基本構造である」(313ページ)というテーゼである。
〇馬淵は「連帯」を次のように定義する。
連帯とは、共通の性質・利益・目的を共有する複数の者たちが、あるいは他者の利益・目的の実現に関与する複数の者たちが、協働や扶助(の責任)を引き受けることで成立する結合のことである。この結合は、自然発生的であったり、目的意識的であったり、制度的であったりする。この結合には、一体感の感情が伴うことが少なくない。(50ページ)
〇連帯とは、人々が結合し、互いに協力し支え合うことであるが、それは様々な場面や文脈において成立する。この定義には上述した連帯の代表的な類型が包摂されている。「社会的連帯」は、「接着剤のように人々を繋ぎ止め、社会の成立に資する結合関係」、「同じ社会の成員であるという条件のもとで成立する連帯」を意味する。「政治的連帯」は、「政治的大義(共通の目標)の実現をめざす者たちのあいだに成立する協力関係」、「同じ政治的大義に関与しているという条件のもとで成立する連帯」を意味する。「市民的連帯」は、「福祉国家の制度を介して市民のあいだに成立する相互扶助関係」、「同じ福祉制度を支えているという条件のもとで成立する連帯」を意味する。「人間的連帯」は、「人類の一員である個人のあいだに成立する普遍的な道徳的関係」、「人間であるという理由で成立する連帯」を意味する(42、280ページ)。
〇馬淵が構想する「人間的連帯」について加筆すれば、それは「国家、社会、政治集団といった特定の集団のなかで成立する連帯ではなく、人間あるいは人類という集団の内部で成立する連帯」(281ページ)である。それは、「全人類が結合している」ということを意味し、「人間は本来的に連帯的存在であるという人間の存在様式を表現するもの」(296ページ)である。別言すれば、「人間の存在構造」を指し示す・形容する言葉(302ページ)である。その意味において、馬淵にあっては、「人間的連帯」は他の様々な種類の連帯に通底する共通の「分母」(303ページ)であり、「母体」(312ページ)となる。
〇ここでは、馬淵の論点や言説のうちから、市民福祉教育の実践・研究に「使える」あるいは「使いたい」次の5点に限ってメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。それは、冒頭に記した管見に新たな視点や思考を加味したいという思いによる。
人間は本来的に「連帯的存在」である/人間の生は相互扶助や連帯によって成立している
新自由主義の過去数十年にわたる影響のもとで、自助努力や自己責任という発想が持て囃(はや)されてきた。自助努力や自己責任の主張は一面では正しい。しかし、この主張を不当に全面化することは避けなければならない。なぜなら、そのことによって、人間に関する一個の真理が覆い隠されてしまうからである。それは、他者たちに支えられなければ、人は生きられないという真理である。新自由主義は、この連帯の真理を抑圧し隠蔽(いんぺい)してきた。だが、自助努力や自己責任という発想が妥当する領域など高が知れている。それは、人間の生という氷山の一角にすぎず、その下には分厚い連帯の層が存在し、その山頂を支えているのである。新自由主義の狭隘(きょうあい)なイデオロギーに抗して、人間は連帯的存在として見出され、思考されなければならない。(15ページ)
連帯はそれ自体では「正当性」を保証しない/連帯は「共同性」以外の価値や尺度を必要とする
連帯は、ある集団に属する者たちを結合させ、支え合いを実現する。だが、連帯はそれが働く集団の性格に応じて、「悪のための連帯」として実現される可能性も残される。その意味で、連帯が成立しているという事実だけで連帯の正当性や倫理的正しさが保証されるわけではない。(318ページ)連帯論には人間の共同性や利他性を強調する傾向があるが、人間はいつも共同性や利他主義にもとづいて生きているわけではない。(211ページ)
個々の連帯が正当化されうるものであるためには、連帯が帯びる共同性の価値とは別の価値や別の尺度が必要になるだろう。たとえば正義という尺度が必要になるかもしれない。連帯する者たちの一部に犠牲が強いられ、一部が特権を享受する事態が生み出される場合、その連帯は正義に悖(もと)る可能性がある。あるいは、連帯がどのような目的を実現しているのか、どのような価値を促進しているのか、集団の外部に悪しき影響を及ぼしてはいないか――そうした事柄についての思考が連帯論には必要となる。そのような事柄を思考するためには、正義以外にも自由、平等、差異、人権といった他の価値や尺度が考慮されなければならないかもしれない。(318~319ページ)
しかし他方で、連帯が他の価値を支えているという一面を忘れてはならない。人々の自由や平等が毀損(きそん)された状況を変えようとするとき連帯が生起する。自由を行使する人物の生存が危ういとき、それを支えるのも連帯である。(325ページ)
連帯は「排除の論理」を内包する/連帯は包摂と排除という両義性を持っている
連帯が連帯であるがゆえに自身の内部に生み出してしまう負の要素のひとつとして、「排除」が挙げられる。(319ページ)
集団は、集団に属する者たちと、そうでない者たちとのあいだに境界線を引くことによって成り立つ。あるいは、境界線が引かれることによって、集団が立ち上がる。「彼ら」とは異なるものとして、「われわれ」集団が生み出されるのである。その集団の連帯が機能するとき、それは一方で当該の集団の結合を強化するが、その結合の強化が他方で排除を生み出すことに貢献する。すなわち、集団の外部に敵を作り出してそれを攻撃したり、集団の内部から「不純」な分子を排除して外部に放逐(ほうちく)する。(319、320ページ)
そうであるなら、連帯をめぐって次のような論点が浮上する。誰が連帯によって結合するのか、誰がその結合から排除されるのか、包摂されたり排除されたりする場合の条件はどのようなものか。その線引きは正当なものか。これらの問いは、連帯の「正しさ」を判定するうえで、欠かすことのできない参照事項となるだろう。いずれにせよ、ある場面で連帯を主張するとき、かならずそこから排除される者たちが存在するという構造的事実に、連帯論は敏感でなければならない。(320、321ページ)
連帯は「感情」によって成立する/連帯は人間の感情の及ぶ範囲や程度に左右される
連帯感という言葉が存在することからも分かるように、連帯の成立にとって感情は重要な要素である。集団の成員たちによってある種の感情が共有されていなければ、連帯が成立し持続することは困難だろう。連帯と親和的な感情は、共感や親近感や一体感といったものであろう。こうした感情が共有されず、成員たちが憎しみ合っていたり、利己主義が支配的であったりするような集団においては、連帯は成立し難いはずである。(321ページ)
だが、感情は、連帯にとって諸刃の剣である。ひとつには、感情が及ぶ範囲の問題がある。人間の感情の及ぶ範囲は狭い。規模が比較的小さな集団の内部でなら連帯は容易に成立するだろう。だが、感情が及ぶ領域を超えたところに存在する者たちとのあいだに連帯が成立することは困難になる。(321、322ページ)
人は、感情の及ぶ範囲にいる者たちだけと結び付いているわけではない。このような世界にあっては、見知らぬ者たちとの連帯がひとつの焦点となる。そのような連帯はいかにして可能になるのか。感情の広がりと関係の広がりが大きくずれてしまう世界にあって、感情の広がりの外部に存在する者たちとのあいだに、どのようにして連帯を立ち上げることができるのだろうか。連帯に刻まれた包摂と排除の問題、「われわれ」と「彼ら」を分かつ境界線の問題は、感情という問題の地平においても未決の問題なのである。(322ページ)
連帯には「水平的連帯」と「垂直的連帯」がある/連帯は権力性・階層性を排除できない
連帯の現象形態として、水平的連帯と垂直的連帯がある。水平的連帯では、(相互依存関係にある)個人が横に連なる。これに対して、連帯する個人のあいだに、垂直的な位階秩序が生み出されることがあるかもしれない。そのような垂直的な権力関係によって規制されている連帯が、垂直的連帯である。たとえば、一国の指導者が危機を乗り越えるためだと称して、国民に団結や自己犠牲を訴えることがある。それは、権力者によって組織され、動員される連帯である。(323ページ)
連帯をひとつの理念として捉え、階層性が廃棄され平等性によって特徴づけられる結合だけを連帯と呼ぶこともできる。ただし、そこでは、階層性が廃棄され、あまねく平等性によって特徴づけられる連帯が現実にどれほど存在するかという疑問が生じる。また、連帯から階層性を完全に排除できるかという問題も存在する。(323、324ページ)
かりに垂直的権力が連帯に伴うことが避けがたいことなのだとすれば、その事態にどのように対処すべきかを考えなければならない。その場合、許容される権力とそうでない権力とを識別すること、つまり、垂直的権力の許容される範囲を確定することが、ひとつの論点となる。(324ページ)
〇人間は身体と不可分な「身体的存在」(297ページ)であり、人間はその生(生存や生活)を自足できない「非自足的存在」(299ページ)である。それゆえに人間は、外部の物質(とりわけ自然)や他者に依存せざるを得ない。すなわち、人間は本来的に、他者との相互扶助や連帯の関係のなかでしか生きられない存在である。これが、馬淵が説く人間観の核心のひとつである。そして、(社会福祉における)自助努力や自己責任を前提とした「自立生活支援」や「依存的自立」などの言説とは異なる評価を得るところである。自助努力も自己責任も社会的レベルの連帯を通じてなされ、果たされるのである。馬淵が[1]の「あとがき」で、「私が述べたかったのは、連帯によって私たちの生が成立しているという、その事実だけである」(376ページ)という意味はここにある。
〇「人間の存在構造」に刻まれた支え合いと「分かち合いの論理と倫理」(333ページ)は、人々が連帯するときに立ち上がる。その連帯は、私と他者との相互依存関係を重視する際、「自律」や「自由」の価値を不可欠とする。人間は自律し、自由であることによって「相互に排他的であるのではなく、むしろ相互に結び付き連帯する」(108ページ)。私だけの自律や自由は、他者を支配したり、他者からの信頼や承認が得られなくなったりする。すなわち、連帯は、単なる道徳的規範や国家などの介入(強制)によるのではなく、個々人の主体的・能動的な思考や行動による自律や自由によって支えられる。同時に連帯は、個々人の自律や自由を実質化し、その実現を図るのである。さらにそれを支えるのは「平等」という価値である。
〇齋藤純一は[2]で、格差や分断、不平等が拡大・深化する現代社会にあって、人々の「平等な関係」とは何かを根底から問いなおし、その関係を再構築するための「制度」について考える。すなわち、市民の間に平等な関係を維持するための生活条件を保障する(広義の)社会保障制度と、市民を政治的に平等な者として尊重する(熟議)デモクラシーの制度のあり方等について考察する。その際、「不平等」とは、その人に「値しない」(「ふさわしくない」「不当である」)「有利-不利が社会の制度や慣行のもとで生じ、再生産されつづけている事態」(17ページ)をいう。「熟議デモクラシー」とは、「数の力」(「選挙デモクラシー」)ではなく、「理由の力」を重んじ、「質的に異なった意見や観点を、たとえそれがごく少数の者が示すにすぎないとしても、尊重すること」(175ページ)をいう。
〇齋藤にあっては、社会保障の目的は、「たんに貧困に対処し、すべての人が人間らしいまともな(decent)暮らしが送れるようにする(事後的な保護・救済:筆者)だけではなく、深刻な社会的・経済的不平等をも規制し、平等な自由を享受しうる条件をすべての市民に保障すること(事前の支援:筆者)にある」(134ページ)。こうした「社会保障の制度を支持し、それを介して互いの生活条件を保障しようとする市民間の連帯」が「社会的連帯」である(94ページ)。その社会的連帯は、次のような理由によって必要とされ、市民によって受容されなければならない。①国力(戦力・生産力等)を増強するための「生の動員」、②人生に起こりうる病気や事故などの「生のリスク」の回避、③生まれ持った能力や境遇の「生の偶然性」がもたらす不当な格差の改善、④生・育・老・病・死という「生の脆弱性」によって生まれる支配-被支配関係の阻止、⑤人々の多様な生き方を促す「生の複数性」の尊重、がそれである(98~104ページ)。
〇そして齋藤はいう。「生の動員」を除く4つの理由はいずれも、「生きていくために人々が他者の意思に依存せざるをえない状態に陥るのを避け、市民の間に平等な関係を保つことを重視している。他者に依存しながらも、その意思に服することを強いられない自律が可能となるのは、依存とそれへの対応が人々の間に支配-被支配を生みださないようにする制度化された保障が確立されているときである」(105ページ)。すなわち、齋藤にあっては、誰もが避けられない「他者に依存すること」と、「他者の意思に依存すること」を区別し、特定の他者の意思に依存せずに生きることすなわち「自律」を可能にするための制度が(「事前の支援」としての)社会保障である(107ページ)。「私たちの生において依存関係が避けられないからこそ、『自律』が価値をもつのである」(107~108ページ)。留意したい。
【初出】
<雑感>(145)阪野 貢/「連帯」再考―馬淵浩二著『連帯論』のワンポイントメモ―/2021年10月10日/本文
04 「自己決定」の実相
<文献>
(1)小松美彦『「自己決定権」という罠―ナチスから相模原障害者殺傷事件まで―』言視舎、2018年8月、以下[1]。
(2) 吉崎祥司『「自己責任論」をのりこえる―連帯と「社会的責任」の哲学―』学習の友社、2014年12月、以下[2]。
(3) 高橋隆雄・八幡英幸編『自己決定論のゆくえ―哲学・法学・医学の現場から―』九州大学出版会、2008年5月、以下[3]。
(4) 湯浅誠『どんとこい、貧困!』イースト・プレス、2011年7月、以下[4]。
〇1990年代後半以降、財界の要望に応える「小さな政府」を実現するために、「措置から契約へ」という社会福祉基礎構造改革の推進が図られた(1998年6月:中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」等)。そのなかで、「自己選択」「自己決定」すなわち「自己責任」が声高に叫ばれるようになった。また、「市場原理の導入」などの新自由主義的教育改革の推進が図られた(1996年7月:中央教育審議会「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について(第一次答申)」等)。そこでは、子ども・青年が抱える困難や不利益を、「自己責任」として個々人が引き受ける「生きる力」の育成が強調されるようになった。周知の通りである。
〇「自己決定」と「自己責任」は口当たりのよい言葉である。しかし、その言葉に関して、「自己」すなわち「個人」「ひとり」については曖昧であり、「共に」決定する、「共に」責任を取るなどとはあまり言わない。また、「自己決定」と「自己責任」の実相は、外見だけを飾り(虚飾)、人目をあざむき、だます(欺瞞)という危険性がある。
〇小松美彦の[1]は、『自己決定権は幻想である』(洋泉社新書、2004年7月)の増補改訂版である。旧版では、「自己決定権」の概念それ自体や「自己決定権」への無条件の信頼は非常に危ういことを論じている。旧版のインタビュー(2003年)から15年後のこんにちでは、主に医療や福祉の分野において「自己決定権」「自己決定」という言葉と概念は当たり前のものになっている。しかし、その問題性は見えにくい形でますます拡がっている。「自己決定権」に加えて、「人間の尊厳」という言葉と概念も巧妙に作用し、差し迫った状況にある(3~4ページ)。小松は、その問題状況をダイナミックに論考する。
〇[2]で吉崎祥司はいう。小泉政権(2001年4月~2006年9月)によって、競争原理を基本理念とする規制緩和の推進が図られた。そのなかで、1990年代以降の「自己責任論」が、政財界においてより一層強調されるようになった。また、経済の低成長下における社会保障費の削減を理由づける考え方として、「自立・自助論」が展開された。ヨーロッパなどと比べて、日本では、社会的責任の観念が必ずしも十分に定着しているわけではない(6~13ページ)。こうした特殊「日本型自己責任論」(13ページ)について吉崎は、その内容と特質を批判的に検討し、それを克服するための課題と道筋を明らかにする。
〇高橋隆雄・八幡英幸らは[3]で、生命倫理における基本的概念のひとつである「自己決定」をめぐって、その歴史的由来や概念の意味、法的観点からの問題、医師や看護師の専門職の自律性とのかかわり、等々について多面的に論考する。そのなかで、小柳正弘は、「『自己決定』の系譜と展開」(22~42ページ)において、「『私たち』の自己決定」について次のように述べている。自己決定の主体である「自己」は、理念としては「強い個人」が前提とされている。しかし、現実には「弱い個人」が主体として困難を引き受けているのが現状である。それでも「私」が自己決定しなければならないとすれば、私は他者によって支えられなければならない。すなわち、私が他者とともに「私たち」として決定することが必要となる。「自己が自己のことを決定する」という自己決定には、もうひとつ、「私たちが私たちのことを決定する」という自己決定の理念型が存在することを思い起さなければならない、と(38~40ページ)。
〇[4]は、現代日本の貧困問題を現場から訴え続け、社会的包摂を説く湯浅誠が子どもたちに書き下ろした自己責任論である。そこでのキーワードのひとつに、「溜め(ため)」がある。湯浅にあってはそれは、「がんばるための条件」「その人が持っている条件」を意味するが、基本的な「溜め」となるのは「お金」「人間関係(親や友達など)」「精神(的なもの)」の3つである。「家にお金がなくて、人間関係に恵まれないなら、社会がその人の “ 溜め ” になればいい」(49ページ)。また、自己責任論をふりかざす人たちに共通しているのは、「上から目線」である。自己責任論は「問い」を外に、社会に出てこないように封じ込めること、自己責任論の一番の目的、最大の効果は、相手を黙らせることである。自己責任論は、弱いものイジメが横行し、生きづらい、誰も幸せでない、満ち足りない社会をつくる(153~157ページ)。
〇さて、ここではまず、[1]において留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
自己責任論と「自己決定」「自己決定権」
政府の言う自己責任論は、国家や支配権力が、基本的に人々を強制したいと考えている事実の裏返しの表現にすぎない。自己決定をするのなら自分で責任をとれという、身の蓋もない態度の裏側には、文句を言わずに言うことを聞けという、国家の冷徹で傲慢な態度が透けて見える。(18ページ)
自己決定と自己決定権とはまったく違うものである。自己決定イコール自己決定権だと単純に考えていると、権利という制度的な思弁の土俵の上で、思わぬ落とし穴にはまってしまう危険がある。(19~20ページ)
私たちの行動には、「思わず~する」という無意識の行動、すなわち言葉で考えるというよりも身体全体で考えると言ったほうがよいようなものがあり、自己決定には、そういった具体的な生の実相が、まるごと含まれている。これに対して、自己決定権にはこのような自ずからなる要素はない。自己決定権は、言葉によって普遍化された人為的な権利であり、思弁によって客観化された制度であり、さらには個別の実相を他人事に変えてしまう装置であり、したがって、いつでも政治的な恣意によって道具にされるという危険性をもったものである。(20ページ)
自己決定権批判の根拠
自己決定権という考え方には、根本的に問題がある。
①人が生きていくすべての場面において、個人が何かを決めるということは、決して個人の問題にとどまらない。自己決定権という言葉によって、人間関係の尊重すべき貴重な機微(微妙な事情・おもむき)が覆い隠されてしまっている。
②「本人の意思による」という自己決定権という言葉が謳(うた)われ、その美しい響きが無為に受け入れられてしまったことによって、(政府や政治に対する)人々の抵抗が鈍ってしまった。
③いったん自己決定権を盾(たて)にしてしまうと、さまざまなことに関して、自分のことは自分で決めればよいのだから、他人には口を出してほしくないという壁ができてしまう。その結果として、自己決定権が他者同士のコミュニケーションを遮断・排除する道具として機能する危惧がある。
④死は果たして自己決定できるのか。死は一個人に閉じ込められたものではなく、家族や医師、看護師など実に多くの人がかかわる。死は、周囲の人々すべてにまたがる、人間関係のなかでおきる事柄である。(40~49ページ)
自己決定・自己決定権と「共決定」
自己決定とは、起こっている事柄それ自体のことである。あるいは生の具体的な局面で私たちが絶えず行っている個々の判断や選択や行為そのもののことである。その意味では、人間が自己決定なしに通常の社会生活を送ることは、とてもできないと言ってよい。自己決定権とは、自己決定することを社会や国家が、個人の権利として認めるということである。「する」あるいは「せざるをえない」のが自己決定であるのに対して、「認められる」あるいは「するために使う」のが自己決定権であると言ってよい。(98ページ)
私たちは、いつも他者とのかかわりのなかで自分の行動を決定している。同じように、自分が決定した行動は、いつもまわりの他者たちに少なからぬ影響を及ぼしている。決定すればそれで終わりということは本来的にない。自己決定とは、他者との複雑な網の目のなかで行われるしかないものであり、そういう意味では、純粋な自己決定はない。私たちの行う決定は、好むと好まざるとにかかわらず、いつも本質的に「共決定」であることを強いられているといえる。(98ページ)
「共決定」と関係性・共同性
共決定とは、猶予のある場合にそうすべきだというモデルである。そのモデルを不毛なものにしないためには、それぞれがそれぞれの立場から努力し、徹底的に話し合いながら決めていくことである。(102ページ)
関係性を大切にする立場は、まず内と外を区別しない。個々の人間的な交渉から目をそらさないことを原則として、これを守ることができるのであれば、どこまでも外に広がっていこうとする態度のことである。(103ページ)
共同性を重視する立場は、私たちは私たち、あなたたちはあなたたちというように、そもそも内と外に縁取りをこしらえておいて、二つを区分けし固定していこうとする態度のことである。(103~104ページ)
だから、関係性を重視する立場は相互の異質性を厭(いと)わないし、共同性を重視する立場では自分たちのなかにある同質性に、まず目を向けるということになる。(104ページ)
個々の人間の具体的な実存を前にすれば、抽象的な同質性などというものは、はじめからどこにもない。共同体の掲げる同質性は、いつも避けがたい抽象性を帯びてしまい、個々人の具体的な個別性にあるかけがえのなさを、共同体の意思の名をもって、裏切っていくことになる。(105ページ)
「人権」と「存在」
「人権」とは、結局、国家や社会によって与えられる人為的なものである。しかし、それ以前に、障害者にせよ健常者にせよ、その人がいるということ、「存在」していること自体が第一次的なもののはずである。これ自体は絶対に否定できない。(311ページ)
仮に、心や意識が本当に絶無のまま生きている人がいるとして、それをどう考えたらよいのか。それでもその人が “ そこにいる ” という厳然たる事実が、その人から被(こうむ)る迷惑と呼ばれることまで含めて、私たち自身が “ いる ” ことを何らかの形で支えてくれているのである。「迷惑をかける―かけられる」という関係をもてることは、実は人間の豊かさに思われる。(316ページ)
「自己決定権」にせよ、「人間の尊厳」にせよ、検討にあたって必須のことは、型どおりの「人権」的な思考ではなく、誰々がいた、あるいは誰々がいるという「存在」ベースで考え直すことである。(319ページ)
〇次に、[2]において留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「自己責任論」の機能
「自己責任論」の機能とは、さしあたり、①競争を当然のこととし、②競争での敗北を自己責任として受容させ(自らの貧困や不遇を納得させ)、③社会的な問題の責任をすべて個人に押しつけ(苦境に立たされた “ お前が悪い ” )、④しかもそうした押しつけには理由がある(不当なものではない)と人びとに思い込ませることによって、⑤抗議の意思と行動を封殺する( “ だまらせる ” )、というものである。そのようなものとして、「自己責任論」は、新自由主義的支配の合理化・正当化のためのイデオロギー(支配層の思想形態)であることを本質としている。(11ページ)
「自己責任論」の特徴
「自己責任論」は、次のような特徴をもっている。
①「自己責任論」は、「社会的責任」と「個人的責任」を意図的に混同したうえで、「社会的責任」を否定する、あるいは相対化する。
②「自己責任論」は、社会的責任の否定にとどまらず、社会的な問題をすべて「個人」のうちに押し込め、個人的な解決を迫る。
③「自己責任論」は、個人が抱える困難は、誰のせいでもなく、当の本人の努力や能力の不足によるもので、その事実を受け入れよと強く迫る。一生懸命努力していても報われない場合は、そもそも「能力」が不足しているからだ、と個々人の「能力」の有無・高低をあげつらう。
④「自己責任論」は、本質的に「社会問題」であるのにもかかわらず、社会的責任に蓋(ふた)をして、問題をもっぱら個人的なものに還元し、しかも困難の最終的な原因を個人の能力に求めることで、「責任」を自認させ、抗議の意思も封じる。
⑤「自己責任論」は、それが流布しやすい理由の一つに、「一人前」の人間は、他人に頼らずに自立すべきもの・自ら助けるべきもの、という「自立・自助」の世間的常識がある。誰にも頼らずにちゃんと生活をたてていけないような人間は一人前ではない、といった「自立」観を前提としている。
⑥「自己責任論」では、何にせよ、自分で決定し、選択したことの結果について自分で責任をとるのは当然であり、ある人がおかれた状況・境遇は、そうした決定・選択の結果なのだから「自己責任」であるという一見もっともらしい理屈のもとで、「自己決定=自己責任」が説かれる。
⑦それらの結果として、「自己責任論」は、人びとの間に、多重的な分断をもたらし、個人を孤立化させるにとどまらず、たがいを敵視するように仕向ける。
これらの諸特徴をもつ「自己責任論」が通用しやすい特有の土壌(「社会文化」)が日本社会にはある。(16~17ページ)
自己決定の前提と条件
自己決定には、それを簡単に許さない前提や条件(困難性)がある。①自己決定は、社会制度や時代の支配的な社会的観念や意識、社会の風潮や趨勢、慣習や風俗などの「状況」の「圧力」や「傾向性」のもとで行われる。②「状況」の圧力や傾向性に対して自覚的・批判的であるためには、十分な情報の獲得と、「選択」の結果についての適切な判断が必要とされるが、それが困難である。③「状況」や「選択」にかかわる基本的な情報が獲得されているとしても、従属的位置にある労働者に、その特定の社会関係において自由な選択を行うことは許されない。(55~58ページ)
こうして、「自己決定」は多くの場合、疑似的で、決定者の「自己責任」を問えるようなものではない。つまり、「自己決定」は、個人の「自己責任」に直結させることができるようなものではない。真に自由な自己決定・選択が可能になる前提・条件の周到な吟味なしに、自己決定を自己責任に直結させるような「自己決定論」は、多く欺瞞をかかえるものである。(58ページ)
そこで、労働者が自己決定する際の鍵になるのは、個人が他者と「共にする決定」の場と仲間、連帯する組織を作り出すことである。(60ページ)
〇筆者はかつて、『みんなのなかにわたしがいる みんなとともにわたしがいる』(三重県社会福祉協議会、2004年3月)というタイトルの「小学生からの福祉読本」の作成にかかわったことがある。そこでの根本的な考え方は「実存」「自立」「共生」「まちづくり」「参画」「共働」などであった。
〇そのことを思い出しながら、改めて[1]における小松の言説を要約する。「自己決定」は、実際には、社会的広がりや他者との関係性(「関係としての私」「われわれのわれ」198ページ)のなかで行われる。「自己決定権は、個人主義を擬装しながら、実際には抽象化され、普遍化されることによって、いつでも国家共同体に転化・悪用されかねない危険性をもったもの」である。その意味で、「自己決定権を個々人の具体的な実存の側から見てみれば、そんなものは、はじめからないのだと極論してもよい。それをあるのだとなお言い募るのであれば、幻想としてあるのだと言うしかない」(106ページ)。これが、小松が最も強く主張する「自己決定権の欺瞞性」、すなわち「自己決定権という罠」である。加えて、小松の「共決定」(「相互決定」:筆者)という言説にも留意したい。
【初出】
<雑感>(85)阪野 貢/「自己決定」と「自己責任」:いま改めてその虚飾と欺瞞について考える―小松美彦著『「自己決定権」という罠』と吉崎祥司著『「自己責任論」をのりこえる』の読後メモ―/2019年6月22日/本文
補遺
〇小気味よい本に出会うと楽しいものである。筆者の手もとにある、桜井智恵子(さくらい・ちえこ、教育社会学)の『教育は社会をどう変えたのか―個人化がもたらすリベラリズムの暴力―』(明石書店、2021年9月。以下[1])もその一冊である。タイトルからも興味をそそられる。(小気味よさはしばしば、一元論的な思考やそれに基づく思考停止状態のなかにあることに留意しておきたい。)
〇生存のための「自立」を必要条件とする資本主義社会は、能力と所有の論理に基づいている。現代社会のルールであるリベラリズム(自由主義)は、個人の尊厳や自由、多様性、自己決定(自己責任)などを最も重要な価値とみなしている。そういう社会の政治経済的構造が生み出す排除や差別などの諸困難に対する桜井の主張は、明快である。能力主義の価値観を是認し、それを国家や社会の支配層と共有している限り、排除や差別は助長され正当化される。すなわち、個人が「自立」能力で生き延びるために自己中心的に生きることは、排除や差別する社会を自分自身が支えていることになる。そこで考えるべきは、現代社会の根底にある能力主義=業績承認の解体、である。
〇[1]におけるキーワードは、「個人化」、「能力の共同性」、「存在承認」である。それぞれの定義とそれに関する言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部語尾変換)。
個人化
私たちは、個人で稼いで個人で満たすという「勤労」概念に基づく個人化社会をつくった。生きていくためのニーズを満たすために、がんばって働き自分で稼ぐスタイルが前提となり、皆で分かち合う共同性は縮減した。環境や状況の劣悪は横に置き、「生きる上での困難」を乗り越えられないことを個人の問題に矮小化する傾向を「個人化」と呼ぶ(16ページ)。
能力の共同性
能力は個人が有する固有(単独)のものではない(私的所有物ではない:阪野)。能力は、他者や社会・文化によって、個のなかに共同的に培われているものであり、他者や環境とのかかわりという相互関係自体(能力の共同性)である(188ページ)。すなわち、能力とは、分かちもたれて現れたもの(互いに分かち合って共有するもの:阪野)であり、それゆえその力は関係的であり共同のものである。能力は個に還元できない(190ページ)。「共同」とは、個が「力を合わせる」「互いに助け合う」というものではなく、「いっしょにある」という意味合いであり、「私のなかにみんながいる」(189ページ)のである。
存在承認
現代社会を覆う能力主義は、「できること」(成果や業績)を承認する「業績承認」を意味する。それに対していま必要とされるのは、「在ること」(ありのまま)を承認する「存在承認」である。それは、自分自身を自分で承認し得る、「社会的状態」の構想である(187ページ)。すなわち、存在承認とは、「共同的なものを基底に、自分を自分で承認しうる所得配分を前提にした状態」(251ページ)をいう。
●現代の学校現場で、子どもは批判的に物事を考える機会を奪われている。必要なときに他者を頼ることは「依存」と見なされ、自助努力で生きることが大事だという価値観が教え込まれる。教育現場は、学力やコミュニケーション能力で人の価値が計られる能力主義によって貫かれ、自己責任という考え方を刷り込む場となっている。そこには、共に生きる社会や国の在り方を考えたり、能力主義によって正当化される経済格差をもたらす資本主義に疑問を持ったりする余地はない(12~13ページ)。
●学校や社会には「能力の高い人ほど優秀」というソフトな優生思想が浸透している(15ページ)。それによって生きづらさが生じ、社会的弱者がつくられ、自責他害が強まっている(206ページ)。また、凄惨(せいさん)な相模原障害者施設殺傷事件(2016年7月)を受けてもなお、自己責任や排除を生み出す能力主義に基づく教育を問い直す機運は高まらず、グローバル人材の育成という形でむしろ強化されている。他方で、子どもの状況に応じた多様な教育機会を確保するとして個別支援の流れが強まっている。それは、学校のありようを問い直さずに子どもの分断を正当化する(15ページ)。
●個別救済は、トラブルが起きてからの救済システムであり、それらを生み出す社会的なあり方をこそ、問う必要がある。個別救済だけでは、逆に現在の排除的な社会の原理や個人化を補完することになる(19ページ)。
●資本主義経済を基調とする日本の公教育制度は、教育を受けることを権利として保障し、その保障を通して教育における国家支配を実現していくような体制である。いいかえれば、「保障」を通して「支配」を実現し、「支配」を実現するために「保障」を行う教育体制である(岡村達雄)(111ページ)。
●リベラリズムは近代個人の自由や多様性を尊重するために、政治権力や世間から干渉されない個人の自由を重視した。すなわち、個人の自由が、個人化された自由に矮小化されてしまった。個人の自由にとって大切なのは、個人化されない自由である(20、21ページ)。
●能力主義が導く自己責任論は、本人の能力や努力に問題を矮小化し、社会が協働する意味や契機を奪っている。すなわち、能力が個に分断されることで、人々には共同性が見えにくくなっている。「地域との連携」がお題目のように叫ばれているが、連携をすればよいというわけではない。自己責任論を広げるような連携ならしない方がずっとましだ。また、自己責任論は、「自立支援」という名の下に「自立するなら支援する」という脅迫めいたメッセージを発している(60~63ページ)。「支援」は支配的要素を含む言葉でもある(59ページ)。
●「能力の共同性」は、多様な人々が力を合わせるという意味合いとは異なり、個に還元できない能力論である。「依存先を増やす」というような個人化された共同性は、いともたやすくネオリベラリズム(新自由主義。個人の選択や市場原理の重視)に利用される。「存在承認」は、あなたの存在を認めるよといった承認論ではない(261ページ)。共同的なものでしかありえない、個人化されていない存在のあり方である(251ページ。)
〇繰り返しになるが、桜井の主張は脱個人化と能力主義の解体である。それによって、「自由で平等な社会への書き換え」(257ページ)が可能となる。その際、桜井にあっては、新しいしくみを構築するのではなく、現在の社会を覆う個人化や能力主義に基づく仕組みや制度を「脱構築」(既存のものを問い直して一度解体し、新たなものに再構成)し、非資本主義的な生活様式による社会を構想することが肝要となる。そこに求められるのは、「能力が個人のものではなく、いつも共同ではたらいていて、競争をしなくても必要に応じて分かち合う論理」(252ページ)である。それは、「(存在承認の基で)生きていくための所得分配がフェアで、それぞれが自由に生き合うという世界」(262ページ)、「アナキズム(国家や市場の支配権力に向き合いながら、自分たちの問題を自分たちで解決す知恵・思想:阪野)のようなもので教育や福祉の世界を包囲する」(252ページ)社会をめざす。要するに、個々人の「能力に応じて」から「必要に応じて」への転換である。
〇なお、[1]のタイトルを「市民福祉教育は地域・社会をどう変えたのか」と読み替えると、汗顔の至りである。福祉教育は、子どもが自主的に、そして自由かつ平等に学ぶ場としての学校や学校教育の根源的・社会構造的な問題状況やその要因を厳しく問うてきたか。支配的な価値観のままに物事を承認し提案することは現状肯定につながるが、人間・社会の現実を主導する価値観やその枠組みにあてはめることに終始し、枠組みそのものを問うてこなかったのではないか。仮に桜井の言説に依拠するとすれば、個人化や能力主義、業績承認や存在承認などについて深く問うことなく、自立(自律)や連帯(共生)、まちづくりなどについて理念的・表層的に言及するだけではなかったか。それらを問うてこなかった「成果」は、資本主義システムにおける教育や福祉を下支えし、補完することにある。個人化や能力主義に基づく教育や福祉の拡大再生産(個人の自由と分断と多様化による管理・統治)である。
〇筆者はかつて、『みんなのなかにわたしがいる みんなとともにわたしがいる』(三重県社会福祉協議会、2004年3月)というタイトルの「小学生からの福祉読本」の作成にかかわったことがある。そのタイトルの意味するところは、「よりよくある」ための人間の「自立と連帯」「自律と共生」である。それは、桜井の言説によると、個人化に基づくものであり、個人モデルのそれであることになる。そこで筆者には、「自立と連帯」「自律と共生」を「個のもの」のままではなく、「共同のもの」「分かち合うもの」としていかに展望するかが問われることになる。その意味で、「私のなかにみんながいる」という桜井の言葉は重い。
〇「私のなかにみんながいる」は、「みんなのなかに私がいる みんなとともに私がいる」の基底あるいは前提に位置づくのであろうか。そう考える場合、それは、(必ずしも力を合わせるという要素はない)一緒に行う「共同」と相互作用の「共働」を含意する(分かち合う)ことになる。「共同と共働」に基づく「自立と連帯」「自律と共生」である。そしてそこには、アナキズムやコミュニズム(共同体主義)に基礎をおく社会像が構想される。
〇筆者の手もとに、桜井智恵子の『教育は社会をどう変えたのか―個人化がもたらすリベラリズムの暴力―』(明石書店、2021年9月)という本がある。
〇生存のための「自立」を必要条件とする資本主義社会は、能力と所有の論理に基づいている。現代社会のルールであるリベラリズム(自由主義)は、個人の尊厳や自由、多様性、自己決定(自己責任)などを最も重要な価値とみなしている。そこでは、環境や状況の劣悪は横に置いて、「生きる上での困難」を乗り越えられないことが個人の問題に矮小化される。その傾向を桜井は「個人化」という。そういう社会の政治経済的構造が生み出す排除や差別などの諸困難に対する桜井の主張は、明快である。「能力主義」の価値観を是認し、それを国家や社会の支配層と共有している限り、排除や差別は助長され正当化される。すなわち、個人が「自立」能力で生き延びるために自己中心的に生きることは、排除や差別する社会を自分自身が支えていることになる。そこで考えるべきは、現代社会の根底にある能力主義=業績承認の解体、である。
〇桜井の主張は脱個人化と能力主義の解体である。それによって、「自由で平等な社会への書き換え」(257ページ)が可能となる。その際、桜井にあっては、新しいしくみを構築するのではなく、現在の社会を覆う個人化や能力主義に基づく仕組みや制度を「脱構築」(既存のものを問い直して一度解体し、新たなものに再構成)し、非資本主義的な生活様式による社会を構想することが肝要となる。そこに求められるのは、「能力が個人のものではなく、いつも共同ではたらいていて、競争をしなくても必要に応じて分かち合う論理」(252ページ)である。それは、「私のなかにみんながいる」ことを意味し、個々人の「能力に応じて」から「必要に応じて」への転換である。
〇桜井の言説を「市民福祉教育は地域・社会をどう変えたのか」と読み替えると、汗顔の至りである。福祉教育は、子どもが自主的に、そして自由かつ平等に学ぶ場としての学校や学校教育の根源的・社会構造的な問題状況やその要因を厳しく問うてきたか。支配的な価値観のままに物事を承認し提案することは現状肯定につながるが、人間・社会の現実を主導する価値観やその枠組みにあてはめることに終始し、枠組みそのものを問うてこなかったのではないか。仮に桜井の言説に依拠するとすれば、個人化や能力主義、「業績承認」や「存在承認」などについて深く問うことなく、自立(自律)や連帯(共生)、まちづくりなどについて理念的・表層的に言及するだけではなかったか。その際の業績承認は、「できること」(成果や業績)を承認することをいい、存在承認は「在ること」をありのままに承認することをいう。それらを問うてこなかった「成果」は、資本主義システムにおける教育や福祉を下支えし、補完することにある。個人化や能力主義に基づく教育や福祉の拡大再生産(個人の自由と分断と多様化による管理・統治)である。
【初出】
<雑感>(155)阪野 貢/「私のなかにみんながいる」ということ―桜井智恵子著『教育は社会をどう変えたのか』読後メモ―/2022年7月18日/本文
05 「世間」からの解放
<文献>
(1)阿部謹也『「世間」とは何か』講談社現代新書、1995年7月、以下[1]。
(2)阿部謹也『学問と「世間」』岩波新書、2001年6月、以下[2]。
(3)佐藤直樹『「世間」の現象学』青弓社、2001年12月、以下[3]。
(4)山本七平『「空気」の研究』文藝春秋、1983年10月、以下[4]。
(5)鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力―日本社会はなぜ息苦しいのか―』講談社現代新書、2020年8月、以下[5]。
(6)岡檀『生き心地の良い町―この自殺率の低さには理由がある―』講談社、2013年7月、以下[6]。
〇筆者はこれまで、いくつかの地域で、「まちづくり」や「市民福祉教育」の実践「活動」にかかわってきた。正直に言えば、自分が現に居住する地域での取り組みには、ある種の“息苦しさ”や閉塞感を感じてきた。その息苦しさを和らげるためには“酸素”を吸入し、いま一度呼吸を整えることが必要である。以下の[1]から[4]の「世間」と「空気」に関する抜き書きは、過去に吸ったことのある空気よりも高濃度の酸素である。筆者には、いま所属する世間で、その流量や濃度、吸入方法を如何に考えるかが問われることになる(抜き書きと要約)。
[1]阿部謹也『「世間」とは何か』
西欧では社会というとき、個人が前提となる。個人は譲り渡すことのできない尊厳をもっているとされており、その個人が集まって社会をつくるとみなされている。したがって個人の意思に基づいてその社会のあり方も決まるのであって、社会をつくりあげている最終的な単位として個人があると理解されている。日本ではいまだ個人に尊厳があるということは十分に認められているわけではない。しかも世間は個人の意思によってつくられ、個人の意思でそのあり方も決まるとは考えられていない。世間は所与とみなされているのである。(13~14ページ)
私達は世間という枠組の中で生きているのであって、誰もが世間を常に意識しながら生きているのである。いわば世間は日本人の生活の枠組となっている。敢(あ)えていえば日本人は皆世間から相手にされなくなることを恐れており、世間から排除されないように常に言動に気をつけているのである。(14、15ページ)
世間とは個人個人を結ぶ関係の環であり、会則や定款はないが、個人個人を強固な絆で結び付けている。しかし、個人が自分からすすんで世間をつくるわけではない。何となく、自分の位置がそこにあるものとして生きている。世間には、形をもつものと形をもたないものがある。形をもつ世間とは、同窓会や会社、政党の派閥、短歌や俳句の会、文壇、囲碁や将棋の会、スポーツクラブ、大学の学部、学会などであり、形をもたない世間とは、隣近所や、年賀状を交換したり贈答を行う人の関係をさす。(16、17ページ)
世間には厳しい掟がある。それは特に葬祭への参加に示される。その背後には世間を構成する二つの原理がある。一つは長幼の序であり、もう一つは贈与・互酬の原理である。世間の掟にはもう一つ重要なものがある。それは世間の名誉を汚さないということである。(17、18ページ)
「世間」の構造に関連して注目すべきことがある。西欧人なら、自分が無実であるならば人々が自分の無実を納得するまで闘うということになるが、日本人の場合は、自分は無罪であるが、自分が疑われたというだけで、世間を騒がせたことについて謝罪することになる。このようなことは、世間を社会と考えている限り理解できない。世間は社会ではなく、自分が加わっている比較的小さな人間関係の環なのである。(20~21ページ)
[2]阿部謹也『学問と「世間」』
「世間」と社会の違いは、「世間」が日本人にとっては変えられないものとされ、所与とされている点である。社会は改革が可能であり、変革しうるものとされているが、「世間」を変えるという発想はない。明治以降わが国に導入された社会という概念においては、西欧ですでに個人との関係が確立されていたから、個人の意志が結集されれば社会を変えることができるという道筋は示されていた。しかし「世間」については、そのような道筋は全く示されたことがなく、「世間」は天から与えられたもののごとく個人の意志ではどうにもならないものと受けとめられていた。したがって「世間」を変えるという発想は生まれず、改革や革命という発想も生まれえなかった。(111~112ページ)
「世間」は差別的で排他的な性格をもっている。仲間以外の者に対しては厳しいのである。「世間」には序列があり、その序列を守らない者は厳しい対応を受ける。それは表立っての処遇ではないが、隠微な形で排除される。「世間」の中では個性的な生き方はできない。常に「世間」の枠を意識していなければならないからである。自分と「世間」とは一体として意識されている。自分が落ちこぼれないように努力している反面で、「世間」の外に特定の対象を設定して、その対象に対して自分の優位を確認しようとする。「世間」の外にそのような対象を設定することによって、自分自身の恐れや不安を転嫁するのであり、「世間」に対する恐怖を和らげるのである。私たち自身が「世間」の中で生きている不安を転嫁する過程で差別意識が発生してくるのである。その意味で差別意識は「世間」の産物である。(151~152ページ)
[3]佐藤直樹『「世間」の現象学』
社会という言葉はわが国の「近代化」と一体となったかたちで、つまり「近代化」のシステムとして展開された。ジャーナリズムや学問の世界では、あたかも西欧流の社会が実在するかのように、社会という言葉があたりを席巻した。しかしそれは、蜃気楼のようなものだった。おおかたの見方に反して、「世間」は消滅するどころか、実際に明治以降私たちの<生活世界>に実在したのは、「近代化」のシステムとしての社会ではなく歴史的・伝統的システムとしての「世間」のほうであった。(98ページ)
西欧流の「社会」と日本の「世間」のちがいを簡単にまとめると表1のようになる。(97ページ)
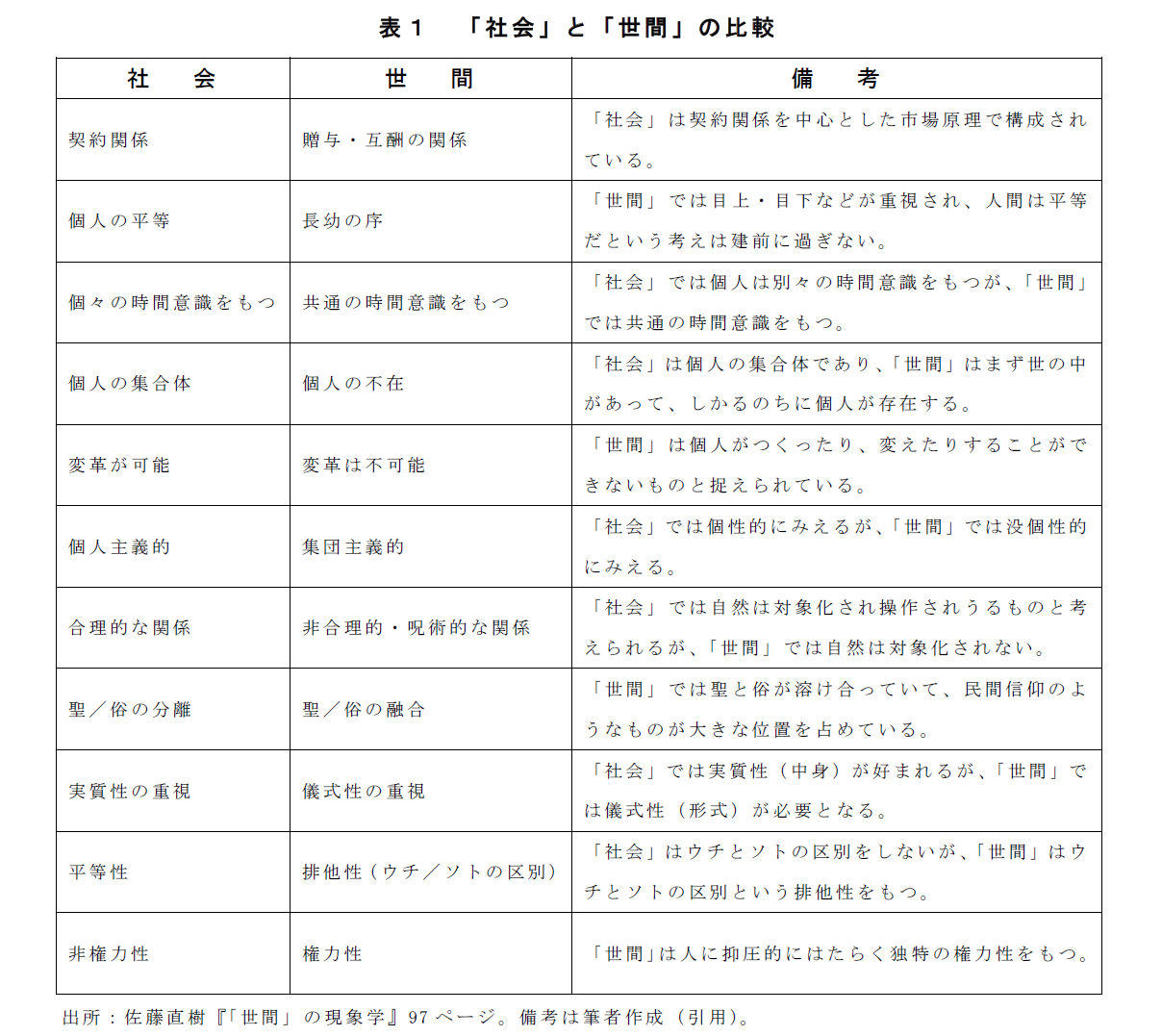
[4]山本七平『「空気」の研究』
「空気」は非常に強固でほぼ絶対的な支配力をもつ「判断の基準」であり、それに抵抗する者を異端として、「抗空気罪」で社会的に葬るほどの力をもつ超能力である。われわれは「空気」に順応して判断し決断しており、総合された客観情勢の論理的検討の下に判断を下して決断しているのではない。だが通常この基準は口にされない。それは当然であり、論理の積み重ねで説明することができないから「空気」と呼ばれているのだから。従ってわれわれは常に、論理的判断の基準と、空気的判断の基準という、一種の二重基準(ダブルスタンダード)のもとに生きているわけである。そしてわれわれが通常口にするのは論理的判断の基準だが、本当の決断の基準となっているのは、「空気が許さない」という空気的判断の基準である。(22ページ)
「空気」の基本にあるのは臨在感的把握である。それは、物質から何らかの心理的・宗教的影響をうける、言いかえれば物質の背後に何かが臨在していると感じ、知らず知らずのうちにその何かの影響を受けることをいう。(32、33ページ)
臨在感の支配により人間が言論・行動等を規定される第一歩は、対象の臨在感的な把握にはじまり、これは感情移入を前提とする。感情移入はすべての民族にあるが、この把握が成り立つには、感情移入を絶対化して、それを感情移入だと考えない状態にならねばならない。従ってその前提となるのは、感情移入の日常化・無意識化乃至は生活化であり、一言でいえば、それをしないと、「生きている」という実感がなくなる世界、すなわち日本的世界であらねばならないのである。(38ページ)
臨在感は当然の歴史的所産であり、その存在はその存在なりに意義を持つが、それは歴史観的把握で再把握しないと絶対化される。そして絶対化されると、自分が逆に対象に支配されてしまう、いわば「空気」の支配が起ってしまうのである。(40ページ)
われわれは、「空気」を排除するため、現実という名の「水」を差す。「水」とはいわば「現実」であり、現実とはわれわれが生きている「通常性」であり、この通常性がまた「空気」醸成の基である。そして日本の通常性とは、実は、個人の自由という概念を許さない。(129、172ページ)
ある一言が「水を差す」と、一瞬にしてその場の「空気」が崩壊するが、その場合の「水」は通常、最も具体的な目前の障害を意味し、それを口にすることによって、即座に人びとを現実に引きもどすことを意味している。われわれの通常性とは、一言でいえばこの「水」の連続、すなわち一種の「雨」なのであり、この「雨」がいわば「現実」であって、しとしとと降りつづく “ 現実雨 ” に、「水を差し」つづけられることによって、現実を保持しているわけである。従ってこれが口にできないと “ 空気 ” 決定だけになる。(91、92ページ)
〇「世間」と「空気」は過去の遺物ではない。「世間」は今日も、解体・消滅することなく、そこに所属する人々の行動原理として働いている。そこで醸成される「空気」は、人々を支配し、ときには議論を否定し、思考を停止させる。日本の現代社会においては一面では、「世間」が膨張し、「空気」が意思決定の主役のようにもなっている。
〇「まちづくり」や「市民福祉教育」の世界ではこれまで、「世間」と「空気」の存在を前提にした議論が十分に行われてきたとは言えない。もっぱら、「地域社会」「市民社会」「共生社会」などの、翻訳語としての「社会」(society)を舞台にした議論が行われてきた。「社会」は観念的な世界であり、人はそのなかで生きているとはいえ、一定の心理的距離を置くこともできる。「世間」は日常生活における具体的な人間関係であり、一面では本音(ほんね)の世界でもある。右傾社会や格差社会、そして監視社会すなわち管理社会が進展するなかでいま、その趨勢を押しとどめ、真の市民社会や共生社会の実現を図るために、日常語としての「世間」と「空気」について探究する必要がある。「世間」と「空気」を対象化し議論することは、「社会」について論究する際のひとつの前提である。それはまた、自分の存在を意識し思考することであり、「社会」や「世間」の「息苦しさ」から自分や他の人々を解放することに通じる。
〇[5]は、鴻上尚史(作家・演出家)と佐藤直樹(評論家)の対談本である。「人を苦しめているものは『同調圧力』と呼ばれるもので、それは『世間』が作り出しているもの」である。新型コロナウイルスの感染拡大によって、日本特有の「世間」が強化され、「同調圧力」が狂暴化・巨大化している。自粛の強制や監視、感染者に対するバッシングなどがそれである。「世間」の特徴は、「所与性」(変わらないこと・現状を肯定すること)にあり、「今の状態を続ける」「変化を嫌う」ことにある(鴻上:6、7ページ)。[5]は、新型コロナがあぶり出した「世間」のカラクリや弊害について追求する。
〇[5]で筆者が留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
[5]鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力』
「同調圧力」を生む「世間」:鴻上
「同調圧力」とは、「みんな同じに」という命令である。同調する対象は、その時の一番強い集団である。多数派や主流派の集団の「空気」に従えという命令が「同調圧力」である。数人の小さなグループや集団のレベルで、職場や学校、PTAや近所の公園での人間関係にも生まれる。日本は「同調圧力」が世界で突出して高い国なのである。そして、この「同調圧力」を生む根本に「世間」と呼ばれる日本特有のシステムがある。(5ページ)
「世間」と「社会」の違い:鴻上
「世間」というのは、現在及び将来、自分に関係がある人たちだけで形成される世界のことである。分かりやすく言えば、会社とか学校、隣近所といった、身近な人びとによってつくられた世界のことである。「社会」というのは、現在または将来においてまったく自分と関係のない人たち、例えば同じ電車に乗り合わせた人とか、すれ違っただけの人とか、知らない人たちで形成された世界である。つまり、「あなたと関係のある人たち」で成り立っているのが「世間」、「あなたと何も関係がない人たちがいる世界」が「社会」である。日本人は「世間」に住んでいるけれど、「社会」には住んでいない。(31、32ページ)
「世間」と「社会」の二重構造:佐藤
「社会」というのは、「ばらばらの個人から成り立っていて、個人の結びつきが法律で定められているような人間関係」である。法律で定められている人間関係が「社会」である。「世間」というのは、「日本人が集団となったときに発生する力学」である。「力学」とはそこに同調圧力などの権力的な関係が生まれることを意味する。日本人は「世間」にがんじがらめに縛られてきたために、「世間」がホンネで「社会」がタテマエという二重構造ができあがっている。おそらく現在の日本の社会問題のほとんどは、この二重構造に発していると言ってもいい。(33~35ページ)
「世間」を構成するルール:佐藤
「世間」を構成するルールは四つある。①お返しのルール/毎年のお中元・お歳暮に代表されるが、モノをもらったら必ず返さなければならない。②身分制のルール/年上・年下、目上・目下、格上・格下などの「身分」がその関係の力学を決めてしまう。③人間平等主義のルール/「みんな同じ時間を生きている」、すなわち「みんな同じ仲間である」と考えている。そこから、「出る杭は打たれる」ことになり、「個人がいない」ということになる。④呪術性のルール/「友引の日には葬式をしない」といったように、俗信・迷信に逆らうことができない。こうした四つのルールからできあがったのが「世間」である。そうした人間関係のつくり方をしている国は日本しかないのではないか。(35~50ページ)
「世間」の特徴:鴻上
「世間」には五つの特徴がある。①「贈り物は大切」、②「年上が偉い」、③「『同じ時間を生きること』が大切」、④「神秘性」(佐藤がいう「呪術性」)、佐藤の言説と同じである。加えて⑤「仲間外れをつくる」がある。それは「排他性」を意味し、仲間外れをつくることが、自分たちの「世間」を意識し、強固にすることになる。この五つの特徴(ルール)のうち、一つでも欠けた場合に表れるのが「空気」である。「世間」が流動化したものが「空気」である。「空気」に支配されるのは、それが「世間」の一種だからである。(50~53ページ)
〇要するに、「世間」の本質は、その暗黙のルールに従うこと、みんなと同じことをすることにある。「世間」のルール(その強さ)が、「みんな同じ」すなわち「違う人にならない」という同調圧力を生み出し、個人の行動を抑制するのである。
〇「同調圧力」とは、「少数意見を持つ人、あるいは異論を唱える人に対して、暗黙のうちに周囲の多くの人と同じように行動するよう強制すること」である。すなわち、「何かを強いられること」「異論が許されない(封じられる)状況」(16ページ)をいう。こうした同調圧力や相互監視を生み出す、別言すればそれによって支えられるのが「世間」である。この「世間」と「同調圧力」が、いまの日本社会の「息苦しさ」や「生きづらさ」の正体である。それを緩和あるいは除去するためには、「世間のルール」を漸進的に変革するしかない。そのためのひとつのヒントを与えてくれるのが岡檀の[6]である。
〇[6]は、「地域の社会文化的特性が住民の精神衛生にあたえる影響、特に、コミュニティの特性と自殺率との関係」(10ページ)を明らかにしている。徳島県南部に位置する旧・海部町(現・海陽町)は、太平洋に臨む、人口3000人前後で推移してきた小規模な町である。その町は、全国でも極めて自殺率の低い「自殺 “最” 稀少地域」である。[6]は、そこに暮らす町民たちの、「生きづらさを取り除く」ユニークな人生観や処世術を、2008年から4年にわたる現地調査によって解き明かす(「帯」)。
〇[6]で筆者が注目したいひとつの言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
[6]岡檀『生き心地の良い町』
5つの自殺予防因子
旧・海部町ではなぜ、自殺者が少ないのか。「自殺予防因子」として次の5つが考えられる。
① いろんな人がいてもよい、いろんな人がいたほうがよい
多様性を尊重し、異質や異端なものに対する偏見が小さく、「いろんな人がいてもよい」と考えるコミュニティの特性がある。それだけではなく、「いろんな人がいたほうがよい」という考え方が町に浸透している。
② 人物本位主義をつらぬく
職業上の地位や学歴、家柄や財力などにとらわれることなく、その人の問題解決能力や人柄によって判断するという考え方が重んじられている。
③ どうせ自分なんて、と考えない
町民には、自分たちが暮らす世界を自分たちの手によって良くしようという、基本姿勢がある。「どうせ自分なんて」と考える人が少なく、主体的に社会にかかわる人が多い。
④ 「病(やまい)」は市(いち)に出せ
病気のみならず、生きていく上でのあらゆる問題をひとりで抱えるのではなく、みんなで解決しようという考え方がある。町民の、援助を求める行為への心理的抵抗が小さい。
⑤ ゆるやかにつながる
人間関係が固定していない。町民はそれぞれが、息苦しさを感じない距離感を保ちながら、「ゆるやかな絆」のもとで連携している。(29~92ページ)
〇岡はいう。旧・海部町は江戸時代の初期、材木の集積地として飛躍的に隆盛し、「多くの移住者によって発展してきた、いわば地縁血縁の薄いコミュニティだった」(88ページ)。「人の出入りの多い土地柄であったことから、人間関係が膠着(こうちゃく)することなくゆるやかな絆が常態化したと想像できる」(90ページ)。こうした歴史的背景のもとで培われ維持されてきた「ゆるやかな絆」が、自殺予防を促している。「ゆるやかな絆」という住民気質に注目しておきたい。
〇ここで、世論がどのようなメカニズムで形成されるかを検討したE.ノエル=ノイマン(1916年~2010年、ドイツの政治学者)の「沈黙の螺旋理論」についてメモって(紹介して)おきたい。その概要はこうである。人間はその社会的天性として、仲間と仲たがいして孤立することを恐れる(「孤立への恐怖」)。人間には意見分布の状況(「意見(の)風土」)を認知する能力がある(「準統計的感覚(能力)」)。そこで、自分の意見が多数派であると判断したときは、自分の意見を公然と表明する。逆に自分の意見が少数派であると認識した場合は、孤立を恐れて沈黙を促す(守る)。この循環過程によって意見の表明と沈黙が螺旋状に増幅し、多数派意見への「なだれ現象」(同調)が引き起こされ、多数派意見が「世論」(「論争的な争点に関して自分自身が孤立することなく公然と表明できる意見」)として公認されるようになる。そして、少数派はますます孤立の度を深めていく。なお、ノエル=ノイマンは、少数派でありながら、孤立の脅威をものともしないで意見表明する、「ハードコア(固い核)」と名付ける活動層についても言及する。「沈黙の螺旋研究」の詳細については、E.ノエル=ノイマン、池田謙一・安野智子訳『沈黙の螺旋理論―世論形成過程の社会心理学―』(改訂復刻版、北大路書房、2013年3月)と、たとえば時野谷浩の『世論と沈黙―沈黙の螺旋理論の研究―』(芦書房、2008年3月)を参照されたい。
補遺
・歩いて2、3分の所に住むおじいちゃんが入院された。「にわか百姓」の私に、いつも優しくまた丁寧に、農作業を指南してくれた方である。早速お見舞いに伺ったが、一週間ほどたってご子息からお礼の連絡が入った。電話で、である。
・我が家には2002年3月生まれの犬(柴犬)がいた。目が見えず、耳も聞こえず、認知症の症状が顕著にみられた。ある夜、大きな声で鳴き始めた。すぐに対応したが、近所からお叱りの連絡が入った。深夜23時30分、無言電話で、であ。
・私は数年前、地元の老人クラブの役員を仰せつかった。ある役員との連絡は、時にはメールで行うことがあった。いま思えば、その時の話題は少々厄介なものばかりであった。メールは、お互いの「繋がり」を深化させない、「摩擦」を避けるためのツールとして活用されたのだろうか。
・3年前、隣の家が火事になり、大騒ぎになった。翌日、お見舞いと後片付けにお邪魔したが、その作業に参加したのは私だけであった(2日目には丁重に断られている)。今年になって、近所に住む二人のおばあちゃんが他界された。それを知ったのは1か月後のことである。「村八分」の二分はどこへやら、である。
【初出】
<雑感>(46)阪野 貢/「世間」の膨張と「空気」の支配―その「息苦しさ」からの解放―/2017年4月24日/本文
<雑感>(120)阪野 貢/同調圧力の強い世間を生き抜くということ―鴻上尚史・佐藤直樹著『同調圧力』と岡檀著『生き心地の良い町』のワンポイントメモ―/2020年10月2日/本文
06 「しょうがい」と疑似体験の陥穽
「しょうがい」と疑似体験の陥穽【その1】
<文献>
(1)荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』柏書房、2021年5月、以下[1]。
(2)荒井裕樹『車椅子の横に立つ人―障害から見つめる「生きにくさ」―』青土社、2020年8月、以下[2]。
(3)荒井裕樹『障害者差別を問いなおす』ちくま新書、2020年4月、以下[3]。
(4)荒井裕樹『障害と文学―「しののめ」から「青い芝の会」へ―』現代書館、2011年2月、以下[4]。
(5)荒井裕樹『差別されてる自覚はあるか―横田弘と青い芝の会「行動綱領」―』現代書館、2017年1月、以下[5]。
〇1970年代から80年代にかけて、日本脳性マヒ者協会「青い芝の会」神奈川県連合会の横田弘や横塚晃一らは、「障害者は不幸」「障害者は施設で生きるしかない」「障害者は殺されてもやむを得ない」といった固定的な価値観(常識)と闘った([3]134ページ。注①、②)。その後、「完全参加と平等」(1981年の「国際障害者年」)をはじめ「バリアフリー社会」「自立生活」「地域生活支援」「地域共生社会」、あるいは「共生共育」(インクルーシブ教育)などの実現をめざした障がい者運動が展開された。2016年4月に「障害者差別解消法」(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が施行され、同年7月にはその対極に位置する「相模原障害者施設殺傷事件」が起きた。「差別を解消するための法律を作れば、そのうち差別は克服される」といってしまえるほど、この社会は単純な仕組みにはなっていない([3]13ページ)。元施設職員の犯人・植松聖は「重度障害者は不幸をばらまく存在であり、絶対に安楽死させなければいけない」と断言した。そして早々に、事件の風化が進んだ。ここに障がい者差別の「現在」があり、青い芝の会の「過去」の闘争やその思想が浮かび上がる。
〇荒井裕樹は、「この社会に存在する数々の問題について『言葉という視点』から考えること」を仕事にする気鋭の「文学者」である。専門は、厳しい境遇に追いやられている「被抑圧者の自己表現活動」([1]20ページ)である。主な研究対象(テ―マ)は、障害や病気と共に生きる人たちの「言葉」であり、障がい者運動や患者運動にかかわる(かかわった)人たちの表現活動である。荒井はいう。1970年代に、障がい者の苦労をわかってもらうのではなく、世間の障がい者差別と闘った「青い芝の会」神奈川県連合会の横田は、「障害者は不幸」「障害は努力して克服すべき」という考えが常識だった時代に「なんで障害者のまま生きてちゃいけないんだ?!」と言った([1]151ページ)。障がい者運動家たちからもらった最大のものは、「『正しい』とか『立派』とか『役に立つ』といった価値観自体を疑う感覚」([1]244ページ)である。「ある人の『生きる気力』を削(そ)ぐ言葉が飛び交う社会は、誰にとっても『生きようとする意欲』が湧(わ)かない社会になる。そんな社会を次の世代には引き継ぎたくない」([1]29ページ)。荒井が依拠する基本的な視点や認識のひとつであり、ひとりの「学者」としての覚悟(姿勢)である。
〇[1]は、「言葉」に潜む暴力性を明らかにし、その息苦しさ(「言葉の壊れ」)に抗(あらが)うための18本のエッセイ集である。荒井は、「言葉の殺傷力」、特に2010年代以降に顕著になった「言葉が壊されている」現実に、猛烈な危機感を持つ。「言葉というものが、偉い人たちが責任を逃れるために、自分の虚像を膨らませるために、敵を作り上げて憂(う)さを晴らすために、誰かを威圧して黙らせるために、そんなことのためばかりに使われ続けていったら、どうなるのだろう」(247ページ)。これが[1]の各エッセイに通底する問題意識である。空虚なスローガンやキャッチフレーズとともに、質疑や質問に向き合わず、討論やコミュニケーションを遮断した安倍政権の汚く卑劣な言葉やフレーズを思い出す。
〇[2]は、学術誌に掲載した論文と文芸誌やネットジャーナルに寄稿したエッセイの14本の論考から成っている。荒井の研究者人生「最初の10年間の総括」(222ページ)である。ほとんどの人が「車椅子の横に立つ人」を障がい者の「身内」か「介護者(福祉職)」と決めつけてしまう。障害や障がい者をめぐるある種の固定観念や思い込み(ステレオタイプ)にとらわれ、それを定型的・限定的に捉えてしまう狭い範囲での想像力は、何から生み出されるのか。障がい者が経験する現代社会における「生きにくさ(生きづらさ)」や、それをめぐる「語りにくさ(語られにくさ)」を言葉でどうとらえるのか。こうした「にくさ」が交錯(こうさく)する問題について考える端緒を開こうとするのが[2]である。そして荒井はいう。「いつか(その)正体を見極めて、ぶち壊したいと思う」(34ページ)。
〇[3]は、1970年代から80年代にかけてさまざまな抗議行動(闘争)を繰り広げた「青い芝の会」神奈川県連合会の問題提起を、その運動に参加した障がい者たちの言葉やフレーズ、思想や価値観などを通して丹念に振り返り、「障害者差別を問い直す」。たとえば、青い芝の会が「障害者と対立関係にある健康な者」「障害者を差別する立場にいる健康な者」を「健全者」(73ページ)と呼んだ。あるいは、憲法第25条に規定された「生存権」を「生きる権利」「この世に存在する権利」(194ページ)という意味で使ったことなどに言及し、そこに青い芝の会の思想をみる。そして荒井はいう。「障害者本人たちが、障害者抜きに作られた『常識』に対して、異議申し立てを行なってきた経緯」(22ページ)について、その具体的な事例を一つひとつ調べていくことが重要である。障がい者差別についてあまりにも早急にあるいは短絡的に「解決」を求める発想は、「弱い立場の人に我慢や沈黙を強いたり、そうした『解決』に馴染(なじ)めない人たちを排除したりする方向へと進みかねない」(252ページ)。複雑に入り組んだ障がい者差別の問題について考える荒井のスタンス(立場)である。
〇ここでは、福祉教育(とりわけその実践)に関してしばしば見聞きする言葉やフレーズのいくつかを[1][2][3]から抜き出し、荒井のその論点や言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「障害」という言葉と定義([2])
これまで「障害」は「不幸の代名詞」「生きにくさの象徴」のように考えられてきた側面がある。「障害」は立場や見方によって定義がさまざまに変化し得る相対的なものである。(189、192ページ)
人は程度の差こそあれ、何らかの障害を抱えながら生きていると考えた方がよい。
自分には何ができて、何ができないのか。どこからが自分の手に負えない状況になってしまうのか。何かできないことに直面した際、誰に、どれだけのサポートを求めれば良いのか。自分のなかに「障害」を見出すというのは、こうした点について考えることでもある。ここでいう「障害」とは、「ある特定の文脈や状況のなかで、他の多くの人がそれほど苦労せずにできることができず、そのことで日常生活に支障をきたすこと」という意味である。人は誰しも「障害的要素」や「障害者的側面」をもっているはずであり、そうした内省(リフレクション、reflection)を通じて、社会を捉え返すことが大切である。(190~195ページ)
「障がい者」に対する紋切り型の表現([2])
障害者に対する紋切り型の表現は、これまでも繰り返し批判されてきた。記憶に新しい例で言えば、Eテレの情報バラエティ番組「バリバラ(Barrierfee Variety Show)」が、日本テレビ系列の有名チャリティ番組「24時間テレビ」にぶつけて「障害者×感動の方程式」と題した番組を組み、障害者が感動や勇気を与える存在として描かれることを「感動ポルノ」(Inspiration porn)と批判したことが話題になった。(24ページ)
もともと「感動ポルノ」という言葉は、豪州(オーストラリア)のジャーナリスト、ステラ・ヤング(Stellar Young)のものとされている。Eテレの同企画を詳細に報じた『朝日新聞』(2016年9月3日)の記事は、当日の番組の様子を次のように伝えている。<番組では冒頭、豪州のジャーナリストで障害者の故ステラ・ヤングさんのスピーチ映像を流した。ステラさんは、感動や勇気をかき立てるための道具として障害者が使われ、描かれることを、「感動ポルノ」と表現。「障害者が乗り越えなければならないのは自分たちの体や病気ではなく、障害者を特別視し、モノとして扱う社会だ」と指摘した。>(27ページ)
「不幸」や「悲劇」を健気(けなげ)な努力によって乗り越える障害者の姿が涙とともに「消費」されることは珍しくない。(113ページ)
障がい者の「役に立たない」という烙印([1])
戦時中の障害者たちは、「お国の役に立たない」ということで、ものすごく迫害された。「国家の恥」「米食い虫」という言葉で罵(ののし)られた。そうした迫害に苦しんだ人たちだからこそ、「障害者を苦しめる戦争反対!」とはならない。むしろ、なれないのだ。迫害されている人は、これ以上迫害されないように、世間の空気を必死に感じ取ろうとする。どういった言動をとればいじめられずに済むか、自分をムチ打つ手をゆるめてもらえるかを必死になって考える。(104~105ページ)
誰かに対して「役に立たない」という烙印を押したがる人は、誰かに対して「役に立たないという烙印」を押すことによって、「自分は何かの役に立っている」という勘違いをしていることがある。特に、その「何か」が、(「国家」「世界」「人類」などの)漠然とした大きなものの場合には注意が必要だ。「誰かの役に立つこと」が、「役に立たない人を見つけて吊るし上げること」だとしたら、断然、何の役にも立ちたくない。(107ページ)
「障がい者はもっと遠慮するべきだ」という暴力([1])
老若男女、障害や病気の有無にかかわらず、「遠慮」をまったく感じないでいられる人は現実的にはほとんどいない。だから、みんなが、どこかで、誰かに「遠慮」している。それでも、障害や病気がある人の「遠慮」は、場合によっては命に関わる。(178ページ)
日本の障害者運動が最初に闘ったのは、「遠慮圧力」だった。<生きるに遠慮が要るものか>というフレーズは、障害者運動の神髄だとさえ言える。「みんな、それなりに遠慮しているのだから、障害者も弱者なんていう言葉にあぐらをかかず、もっと遠慮するべきだ」。いまでも、こうした意見を持つ人がいる。でも、この世の「遠慮圧力」は、みんなに等しく均一にかかっているわけではない。やはり、どこかで、誰かに、重くのしかかっている。自分たちが生きる社会のなかで、「生きること」そのものに「遠慮」を強いられている人がいることを想像してみてほしい。「遠慮圧力」が、ときには人を殺しかねないことを想像してみてほしい。確かに、ある程度の「遠慮」は美徳かもしれないけれど、誰かに「命に関わる遠慮を強いる」のは暴力だ。(183~184ページ)
「障害は個性」「みんな違ってみんないい」という言葉([3])
1990年代以降、「障害は個性」や「みんな違ってみんないい」といった言葉が、障害者との共生をめざす文脈でしばしば見かけられるようになった。しかし、これらの言葉は、どちらかというと「障害者と仲良くするための言葉」であり、障害者差別という人権侵害を抑止したり糾弾したりする「闘う言葉」ではないようである。(231~232ページ)
ある差別について語る言葉がない(少ない)ことは、その社会に差別が存在しないことを意味しない。むしろ、差別について語る言葉が少ないほど、その社会が差別に対して鈍感であることを意味している。(232ページ)
「障がい者も同じ人間である」というフレーズ([3])
障害の有無にかかわらず、人は皆、等しくかけがえのない存在であり、等しい尊厳を有した存在であるという意味において、「障害者も同じ人間」というフレーズはまったく間違ってもいなければ、無力なきれいごとでもない。(235ページ)
「人間」とは極めて普遍的で抽象的な言葉だからこそ、ともすると、個々人の抱えた事情を一切無視して、少数者を多数者の論理に従わせたり、多数者の価値観を少数者に受け入れさせたりする抑圧的な言葉として、いかようにも転用できてしまう。つまり、「障害者も同じ人間なのだから」という表現は、障害者に対して我慢や自制を強いる表現としても使われかねないのである。(236ページ)
障害者たちが障害者運動のなかで叫んできた「障害者も同じ人間」というフレーズは、「障害者も生物学上『人間』に分類される存在である」などといった意味ではない。運動の蓄積に鑑(かんが)みるならば、この言葉は「障害者も社会のなかで共に生活する者である」といったメッセージとして育て上げられてきたフレーズである。「障害者も同じ人間」というフレーズは、「他の人々に認められている社会参加への機会や権利は、障害者にも等しく認められるべきである」といった意味内容で使われなければならない。(239ページ)
障がい者の「差別と区別は違う」という定型句([1])
「差別と区別は違う」というのは、障害者差別が起きたときにも出てくる定型句である。「差別」は不当に「されるもの」であり、「区別」は不利益が生じないように「してもらうもの」である。「不利益の生じる区別」は「差別」だし、そもそも属性を理由に「不利益」を押しつけることは許されない。「差別と区別は違う」というフレーズは、「それは差別だ!」と批判された側が思わず口走るというパターンが多かったように思う。(124~125ページ)
この社会は「権利」という概念に鈍(にぶ)いけど、それと対になって「差別」への感性も鈍い。「差別」への感性を鈍らせないためにも、「権利」に敏感でなければならない。(126ページ)
「隣近所」で生きる障がい者との「闘争(ふれあい)」([2])
障害者が排除されるのは抽象的な「地域」ではなく、具体的な「隣近所」であることから、横田は「障害者は隣近所で生きなければならない」と言った。これは、「障害者は、目に見えて、声が聞こえる距離で生きなければならない」ということだ。障害者が身近にいない社会では、障害者はどんな人なのかといった想像力が希薄になる。逆に、障害者にとっても、様々な人たちが混在している社会のなかで生きなければ、「自分とは何者か」「自分と社会はどのような関係にあるか」について考える機会を失う。「障害者が遠い社会」や「障害者にとって遠い社会」では、障害者について語る言葉も、障害者と語らう言葉も貧困になる。言葉が貧困なところに想像力は育まれない。(77~78ページ)
横田は、障害者は周囲の人々と軋轢を起こしながら・起こしてでも(「隣近所」で)生きなければならないと言った。小さな諍(いさか)いは、相手と言葉を交わし、相手が何者なのかを考える契機になる。横田が「闘争」という言葉に「ふれあい」というルビを振ったことは有名なエピソードだ。(78ページ)
「自己責任」という言葉とその不気味さ([1])
「自己責任」という言葉に、おおむね次の三点において不気味さを覚えている。
一つ目は、2004年の「イラク邦人人質事件」で騒がれた時から、「自己責任の意味が拡大し過ぎている」という点だ。これまでも、病気・貧困・育児・不安な雇用などで生活の困難を訴える人が、「甘え」「怠(なま)け」といった言葉でバッシングされることはあった。近年では、こうした場面にも「自己責任」が食い込んできた。二つ目は、「自己責任」が「人を黙らせるための言葉」になりつつある、という点だ。社会の歪みを痛感した人が、「ここに問題がある!」と声を上げようとした時、「それはあなたの努力や能力の問題だ」と、その声を封殺(ふうさつ)するようなかたちで「自己責任」が湧き出してくる。三つ目は、この言葉が「他人の痛みへの想像力を削(そ)いでしまう」という点だ。「自己責任」という言葉には「自らの行ないの結果そうなったのだから、起きた事柄については自力でなんとかするべき」「他人が心を痛めたり、思い悩んだりする必要はない」という意味が込められている。(189~191ページ)
「自己責任」というのは、声を上げる人を孤立させる言葉だ。「従順でない国民の面倒など見たくない」という考えを持った権力者は、今後も「自己責任」という言葉を使い続けていくだろう。国民が分断されていることほど、権力者にとって好都合なことはないからだ。(195ページ)
人が「生きる意味」について議論すること([3])
人が「生きる意味」について、軽々に議論などできない。障害があろうとなかろうと、人は誰しも「自分が生きている意味」を簡潔に説明することなどできない。「自分が生きる意味」も、「自分が生きてきたことの意味」も、簡潔な言葉でまとめられるような、浅薄なものではないからである。私が「生きる意味」について、第三者から説明を求められる筋合いはない。また、社会に対して、それを論証しなければならない義務も負っていない。もしも私が第三者から「生きる意味」についての説明を求められ、それに対して説得力のある説明が展開できなかった場合、私には「生きる意味」がないことになるのか。だとしたら、それはあまりにも理不尽な暴力だとしか言えない。(234ページ)
この社会のなかで、誰かに対し、「生きる意味」の証明作業を求めたり、そうした努力を課すこと自体、深刻な暴力であることを認識する必要がある。重度障害者に対し「生きる意味」の証明作業を求めるような価値観は、必ず、重度障害者以外に対しても牙(きば)を剥(む)く。(235ページ)
〇[4]は、「障害者によって描かれた文学」作品を研究対象に、それらの作品が生み出された文学活動の歴史と意義について考察する。具体的には、俳人で運動家の花田春兆と文芸同人団体「しののめ」、詩人で運動家の横田と「青い芝の会」神奈川県連合会をとり上げる。そして、「障害者自身がいかに自己の存在意義について悩み、いかに自己と社会との関係性について折り合いをつけてきたのか、その内省的な思索の変遷過程を、可能な限り同時代の障害者自身の文学表現から読み解いていく」(8ページ)作業を行う。それは、障がい者や障がい者運動の「内面史」を語ることでもある。荒井はいう。戦後日本の障がい者運動のなかでは、「文学は決して周縁的・副次的な存在ではなく、人脈を繋ぎ、思想を練磨していく上で、むしろ中心的な役割を果たしていたとさえ言える」(8ページ)。
〇[5]は、横田が1970年5月に書き上げた「青い芝の会」の「行動綱領 われらかく行動する」(「補遺」参照)の解釈を通して、その歴史や思想、その意義について考察する。「行動綱領」は、「一人の重度脳性マヒ者が、この社会に厳然と存在する障害者差別に頽(くずお)れてしまわないために、自分を鼓舞し支えようとして綴った言葉」(299ページ)である。「青い芝の会」の活動には、「『自分たちの苦労と悲しみをわかってもらいたい』という迎合的な姿勢や、『障害のある人もない人も、共に手を取り合ってがんばろう』といった朗(ほが)らかな雰囲気は微塵もなかった」(14ページ)。彼らは、差別者を容赦なく徹底的に糾弾し、非妥協的で戦闘的な姿勢を貫き通した。荒井によると横田は、差別者と対峙して自覚的あるいは無自覚な差別を問いただし、その壁を乗り越えて明日を切り拓き、自分自身を解き放つためには「差別されてる側の自覚から湧き上がる怒りが必要だ」(299ページ)とした。障がい者(被差別者、被抑圧者)の「自覚」がキーワードである。ここに、「差別されている自覚はあるか」というタイトルの意味をみる。
社会のすべてが、障害者と共生する時が来るとは私には考えられない。/私たち障害者が生きるということは、それ自体、たえることのない優生思想との闘いであり、健全者との闘いなのである。(横田:[4]225ページ)
私達は生きたいのです。/人間として生きる事を認めて欲しいのです。/ただ、それだけなのです。(横田:[5]103ページ)
注
①1970年5月に起きた実母による障がい児殺害事件に対する減刑嘆願反対運動をはじめ、優生保護法改悪反対運動および「胎児チェック」反対運動(1972年から1974年)、川崎バス闘争(1977年から1978年)、養護学校義務化阻止闘争(1975年から1979年)などがそれである。その概要と詳細は[3](41~47、128~145、150~176、188~220ページ)を参照されたい。
②横田と横塚の言説(思想)については、次の著作を参照されたい。
横田弘『障害者殺しの思想』JCA出版、1979年1月。
横田弘、立岩真也解説『障害者殺しの思想(増補新装版)』現代書館、2015年6月。
横塚晃一『母よ!殺すな』すずさわ書店、1975年1月。
横塚晃一、立岩真也解説『母よ!殺すな(増補復刻版)』生活書院、2007年9月。
補遺
横田の手になる「行動綱領 われらかく行動する」は、次の通りである([5]29~30ページ)。
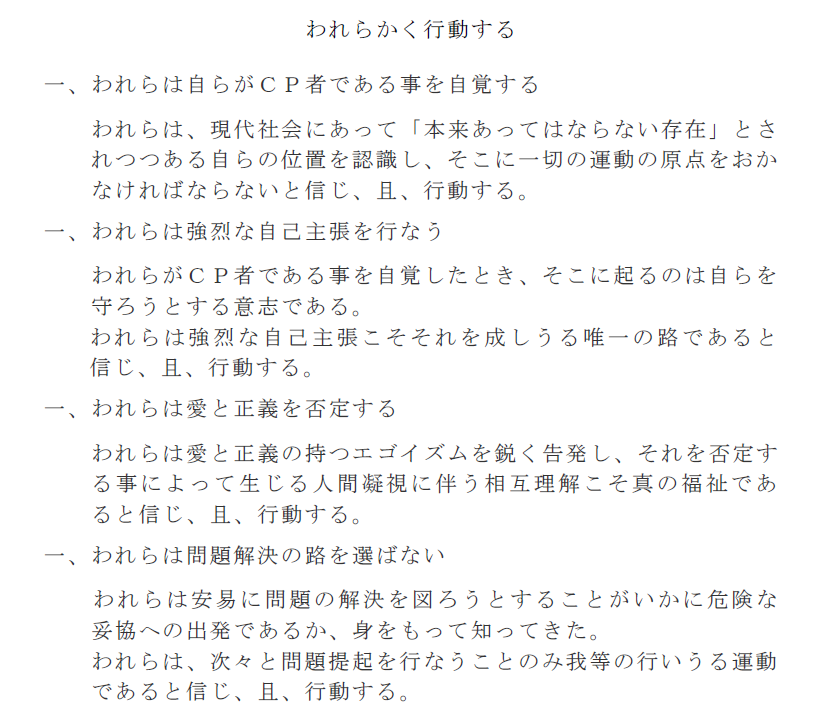
荒井による各項目の解説文(「注釈めいたもの」)をメモっておくことにする([5]121~142ページの抜き書きと要約)。
一、われらは自らがCP者である事を自覚する
障害者運動は障害者が主体となり、障害者の主体性が発揮されるかたちでなされなければならない。そのためには自分がCP者(脳性マヒ者)であることを自覚し、CP者としての思考や考え方がなければならない。それがすべての原点である。
一、われらは強烈な自己主張を行なう
障害者が障害者のまま生きていくために、障害者としてしか生きられない自分の存在を「自己主張」すべきである。この社会の常識自体が障害者の存在を否定的に捉えている。そんな常識を<健全者エゴイズム>として捉え直さない限り、障害者は<自己解放>の道を歩むことはできない。
一、われらは愛と正義を否定する
母親がわが子を愛するが故に障害児を殺した事件が起きた。その愛を圧倒的多数の人たちが支持すれば、それは正義になる。その「愛と正義」の名のもとに、障害児は殺され、あるいは施設へと送られた(送られている)。「障害者のためを思って」という健全者だけに都合のよい「愛と正義」について、人間の心を凝視しなければならない。「福祉は思いやり」という発想も怖い。非常時に真っ先に犠牲になるのは障害者である。
一、われらは問題解決の路を選ばない
障害者が成し得ることは、「不満があるなら何か具体的な対案や代替案を示せ」という発想に応えることではなく、次々と問題提起を起こす以外にない。安易な問題解決は<安易な妥協>を生む。安易な妥協は、「正義」として受け止められ、「誰」が「何」を考えなければならないのかという点を曖昧にしてしまう。妥協は、弱い立場の者がしぶしぶ折れる(折られる)ことになる。
【初出】
<雑感>(144)阪野 貢/言葉とフレーズと福祉教育 :福祉教育は障がい者から感動や勇気をもらい、自分を演じるための教育的営為か? ―荒井裕樹を読む―/2021年9月19日/本文
「しょうがい」と疑似体験の陥穽【その2】
<文献>
(1)佐藤貴宣・栗田季佳編『障害理解のリフレクション―行為と言葉が描く〈他者〉と共にある世界―』ちとせプレス、2023年3月、以下[1]。
〇福祉教育実践ではこれまで、「訪問・交流活動」「収集・募金活動」「清掃・美化活動」の“3大活動”や「疑似体験」「技術・技能の習得」「施設訪問(慰問)」の“3大プログラム”を中心にした体験活動が実施・展開されてきた(されている)。圧倒的に多いのは、障害や高齢の疑似体験、なかでも車いす体験やアイマスク体験、インスタントシニア体験である。相変わらず「慰問」という施設訪問も多い。これらの体験活動は場合によっては、誤解や思い込み、偏見を助長し、「貧困的な福祉観の再生産」(原田正樹)を促すことになる。
〇ここで、障害疑似体験の陥穽(かんせい。落とし穴)について、村田観弥の論考[1]――「障害疑似体験を『身体』から再考する」佐藤貴宣・栗田季佳編『障害理解のリフレクション―行為と言葉が描く〈他者〉と共にある世界―』ちとせプレス、2023年3月、123~153ページ。――から先行研究と村田の言説の一部をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
西舘有沙らは、できないことに目が行き過ぎて事実誤認やミスリードを引き起こし、障害者へのネガティブな態度を植えつける点、障害者の能力を特別視する傾向が強まる点など、障害者の姿を誤って捉え、障害に対する認識のゆがみを強固にする側面を挙げ、この検討をせずに教育方法としての疑似体験を採用すべきでないと指摘する。そして改善策として、➀体験の目的を具体的かつ明確に定める、②できないことばかりを体験させない、④事後指導の時間を設ける、④指導者の指導技術を高める、を提案する。(124ページ)
松原崇と佐藤貴宣は、障害学や障害当事者からの視点として、➀政治・社会的構造の要因の看過(個人にばかり焦点を当てる)、②差別的な見方の強化(障害者の無力さが強調され、障害者や障害にネガティブな価値づけが生じる)、③体験の精度の低さ(疑似体験できるのは、個人が突然身体機能の障害を負ったときの状態やそのときの感情のみで、症状の不安定さや症状の進行などの可変的状態がシミュレートできない)、④障害者への倫理的問題(試しにちょっとやってみる程度に扱われ、しばしば楽しい遊びやゲームのように行われる)、を批判として挙げる。そこで対策として、障害者自身がファシリテーターとなる手法や、注意深くブログムムをデザインすることでネガティブな効果を回避する事例など、学習を始める参加者が「現実」を対象化するきっかけとして、プログラムの一部や出発点として位置づけることを提案する。そして、社会構成主義的な協働体験として再構成し(体験は人々の間のコミュニケーションを通じて協働的に構成されると考える社会構成主義の観点に依拠し)、①問題を障害者個人でなく、外部環境へと問題帰属する文脈を用意する、②障害者が企画者として参加する、③障害者を含む参加者間での対話を喚起する、の3点の「仕掛け」を挙げている。(124~125ページ)
障害当事者である鈴木治郎は、体験し経験して知ることはけっして無駄ではないとしながらも、「その場限りの経験」になることや、企画者が「役に立つことだから善いこと」だと押しつける点を指摘する。そして、誰もが「当たり前」を共有化できる場づくりのための「互いの差異を認め共に出会う教育」が必要だと述べる。それを受け谷内孝行は、障害理解プログラムは、障害を理解することに重きを置くのではなく、障害から個性の尊重、共生の重要性、社会変革などを学び、新たな価値を創造する場であるとする。(128ページ)
細馬宏通は、アイマスク体験の主役は、アイマスクをつくる人ではなく、ナビゲーター(ガイドヘルパー)側だと述べている。(148ページ)
村田観弥はいう。
● 操作的に経験された疑似体験は、障害者への偏見をもってはいけないとする常識的な規範意識に囚われ、障害/健康の枠組みを強固にし、特別な存在とする見方を先鋭化することにもなりうる。また場合によっては、その経験は個々に異なるにもかかわらず、障害当事者の発言があたかも正解のように伝わることもある。(126~127ページ)
● 障害を疑似的に体験する活動をたんに問題とするよりも、その経験を自分自身の「日常」や「身体」について考えるきっかけとしての「学びの契機」(「障害者理解」でなく「自己理解」の体験)とする論を試みる。(130ページ)
● 他人の経験を生きるという試みは困難である。であるならば、体験が疑似(似て非なるもの)であることを問題にするよりも、疑似であることの可能性(誰かの立場になって考えたことによる意味の変化や視野の広がり等)に視点をずらすことで、思い込みや誤解が生じるプロセスに気づき、みずからの問題として考える教育的契機にできるのではないか。(144ページ)
● 体験活動は、「意図的に制限した身体を生きる」という体験を、「まずは実践してみる」ことに重点を置く。特定の障壁を感じることなく生きてきた同質性の高い日常から外へ出て、そうでない世界に身を投じる。「健常者」として規格化された身体を崩すことで、「差異化」の体験過程が言語化され、新たな「私」が再構成される。体験は「他人の身体を生きる」ということとは程遠いけれど、何かが生まれるきっかけにはなる。疑似体験では誤解や思い込み、偏見が生起しやすい。あえて誤解や偏見が顕在化する「場」として提示することで、それが我々の日常に遍在し、気づきにくく、見えない壁をつくっており、そこへ意識を向けることで壁を動かすことには有効かもしれないと考える。(151ページ)
● まず己の身体を通した困惑や不安、違和感といった感覚に向き合ってみる経験こそが、「私も同情や特別視をしているのではないか」との気づきにつながり、誤解や偏見と生きる自分自身に向き合うことになるのではないだろうか。(152ページ)
〇疑似体験には「有効論」と「有害論」がある(杉野昭博)。前者は、疑似体験は障がい者への配慮や支援の仕方について理解することを通して、障がい者への共感性を高めることになる、というものである。後者は、疑似体験は障がい者個人の機能障害(インペアメント)が強調され、社会の偏見や差別についての理解が進まず、障害や障がい者に対するネガティブな価値づけがなされてしまう、といものである。いずれもそこでは、一面的なあるいは一時(いっとき)の障害理解や障がい者体験にとどまり、計画的・継続的なまちづくりや社会変革への視点が弱いと言わざるをえない。再認識したい。
07 「生」の倫理
<文献>
(1)野崎泰伸『生を肯定する倫理へ―障害学の視点から―』白澤社、2011年6月、以下[1]。
(2)野崎泰伸『「共倒れ」社会を超えて―生の無条件の肯定へ!―』筑摩書房、2015年3月、以下[2]。
〇[1]は、「障害学」の視点から、障がい者にとって「正義」とは何かを問い、生を肯定する「倫理」を新たに構想しようとしたものである。野崎泰伸はいう。この社会で障がい者が「生きづらい」のは、軽減・克服すべき個人の身体(障害)に問題があるのではなく、健常者を「正常」とする価値観にとらわれている社会に責任がある。したがって、その「生きづらさ」を解消するためには、障がい者を分断・排除している社会が負担を負わなければならない。また、「障害はないほうがよい」という言説がある。その多くは「障害者は存在しないほうがよい」という議論にすりかわってしまう。その「すりかえ」は、社会的負担の拒否を表明するものである。1970年代の「青い芝の会」などの障がい者運動は、「障害からの解放」ではなく(障害によってこうむる)「差別からの解放」を求めた。それらの運動は、「障害者の生存を無条件に肯定する」という「当たり前のことを当たり前に」要求したものであり、その主張に「学問」は学ぶべきである。改めて確認しておきたい野崎の言説のひとつである。
〇[2]は、「犠牲」という視点から、障がい者が抱える諸問題(「生きづらさ」)を検討することによって、「生の無条件の肯定」という思想の構築を図ろうとしたものである。野崎はいう。この社会では、経済成長至上主義や功利主義(「最大多数の最大幸福」)の考え方のもとで、貧富の格差や少数者の犠牲が前提・容認されている。そうしたなかで、障がい者が抱える「生きづらさ」の問題が私事化・矮小化され、障がい者やその家族、支援現場は犠牲を強いられ、追い詰められる。そして、閉鎖的な関係性が形づけられ、そこでのみ「生きづらさ」が共有されることになり、「共倒れ」が引き起こされていく。そしてまた、「何を言っても」「どうせ」この社会は変わらないという諦(あきら)めが、自分の暮らしを守ることに傾注させ、異質な存在(他者)を排除することを促す。こうした「犠牲の構造」のもとに障がい者を差別・抑圧し、捨て置くこの社会に抗するには、「生の無条件の肯定」という正義が問われ、倫理が求められなければならない。改めて押さえておきたい野崎の言説のひとつである。
〇ここでは、福祉教育実践や研究に思いをいたしながら、留意したい論点や言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
[1]『生を肯定する倫理へ』
障がい者問題の本質と「障害をもつ者ともたざる者との断絶」
障害者問題は特殊な問題ではなく、みんなの問題である。そのことを説明するために、次のようなことが言われる。みんな老いていくし、不慮の事故で障害者になったりする。あるいは、昨今では精神的な病になってしまう者も多い。このことから、誰もが障害や老いによっていつしか自分の身に社会的なハンディを背負わされるようになる。(8ページ)
こうした理解は「いま障害をもっていない者への説明」としては適切だ。だが、現に障害を有する者にとっては、こうした言われ方が生ぬるいと感じられるのもまた事実である。実際に「明日障害をもつかもしれない人」にとって「いままで障害を有してきた身体/精神がこの瞬間感じるもの」を感じ取ることは不可能である。障害をもつ者ともたざる者との間のこの断絶は、あなたと私が違う人間である以上、けっして完全に埋めることなどできないはずである。まずは、この断絶の存在を深く認識しなければ、なにも始まらない。それでは「どのように」障害者の問題は〈私たち〉の問題であるということができるのであろうか。それは次のように考えることができる。現在の私たちの社会が、障害者を生きにくくさせていること、障害があるだけで人間扱いされないような社会に、あなた自身も、私も住んでいることを、あなたや私はどう考えるのか、を問わなければならないのである。そして、これこそが、障害者問題が〈私たち〉の問題であるという理由のもっとも基本的な部分なのである。(9ページ)
障害者を排除する社会にあなたや私が住むということ、そしてそのことをあなたや私はどう考えるのか、というところに問題の本質があると述べた。この問題には、2つの側面があると思われる。1つは、社会の正しさの問題、つまり正義の問題であり、もう1つは、こうした問題を自身から引き離さず、棚上げすることなく考えるという要素である。(10ページ)
障害学と「障害はないほうがよい」という言説
障害学は、多くの健常者が考えるような発想、すなわち障害はなおしたり、克服すべきものだという視点を基本的にはもたない。そうした視点は、障害を「異常なもの」と考える発想であり、この社会で生活したければ、健常者のように「正常」になるように努力しなさい(障害の医学モデル・個人モデル)、という結論を導きやすい。なぜならば、この社会が健常者中心で回っているからである。これに対して、障害学の視点とは、まず「この社会で障害者が〈人間らしく〉生きていくためには、(障害者のほうではなく)社会はどのようにあるべきか」を考えるのである(障害の社会モデル)。(19ページ)
障害を社会的文脈において理解するということは、障害者の〈生きづらさ〉を誰が負担すべきか、つまり「帰責性の問題」が中核的な議論となる。(26ページ)
「障害はないほうがよい」という言説は、その多くが「障害者は存在しないほうがよい」という議論にすりかわってしまうことに注目すべきである。社会モデル的に考えれば、「障害はないほうがよい」という問いに対する答えは定まらないはずである。「障害はないほうがよい」が「障害者は存在しない方がよい」にすりかわってしまう背景には、社会的負担の問題がある。つまり、「障害はないほうがよい」を「障害者は存在しないほうがよい」にすりかえるのは社会的負担の拒否を表明しているのである。そのように考えたとき、「障害はないほうがよい」を問わせる場自体が、「すりかえ」も含めて、私たちが構築したものにすぎないとも言えるはずである。(27ページ)
障がい者運動と「障がい者の生存を無条件に肯定すること」
1970年前後に、重度障害者が個々の場面において声をあげ始めた。(中略)(そうしたなかで)特に注目されるのが、脳性マヒ者の団体である「青い芝の会」の活動であろう。(「青い芝の会」の)障害者本人が訴え、求め続ける障害者解放とは、障害からの解放ではなく、(障害によってこうむる)差別からの解放なのである。これは障害学でいうところの「医学モデルから社会モデルへ」というパラダイムシフト(支配的な考え方の劇的な変化:筆者)に符号している。(36、37ページ)
日本における戦後障害者運動を(中略)思想的に見ていけば、とりわけここ40年間の障害者本人による運動に胚胎(はいたい。芽生え)するのは、障害者の生存を無条件に肯定することであると言える。私は、この運動が面白いのは、当たり前のことを当たり前に言っていることにあると思っている。彼らの主張はしばしば非論理的であると言われたりもするが、私は明快な筋が通っていると考えている。障害者によって主張されたから意味があるのではなく、障害者によって主張された数々の主張が、社会において普遍性を帯びるからこそ、この運動には意味があると私は考えている。まず学問がなすべきことは、障害者運動の主張を学ぶことであり、それによって学問自身をとらえ返すことにあると、私は考える。(45~46ページ)
「当事者研究」と当事者が語ること
近年、「当事者研究」というものがなされている。それは、当事者自身の手によって、当事者が直面する問題を、当事者内部にとどまらず、当事者と(当事者を捨て置く)社会との関係によって考察していこうとするものである。(166ページ)
当事者が語り出すとき、さまざまな点で考えるべきことがある。まずは、そこに行きつくまでにその当事者がいかなる困難を経験してきているかは、想像すべきであろう。語り出した当事者を勇気があると賞賛することも問題である。まず、誰が、何がそこまで当事者を語れなくさせてきたのかが問われるべきである。(中略)語り出す当事者を英雄化してしまうのは、「語ることのできる主体」を期待するだけの非当事者であると言わずに、他になんと言えようか。それはまた、いまだ沈黙せざるを得ない当事者たちへ向けた無言の圧力でもあるのだ。(167ページ)
そもそも、語り出す当事者の主張が、当事者一般の意見を代表するわけでもない。また、いったん語り出した当事者の主張の内容が、当事者であるというだけで正しさを担保されるわけでもない。ではなぜ、当事者の主張が大切になってくるのか。ここまでの理路をたどってくれば、当事者の(生きづらさ)を捨て置く学問体系や私たちの社会が不正義であるからだ、ということができる。それを正すためには、これまでの学問体系や私たちの社会に、ただ単に当事者の主張をつけくわえたもので満足してはならない。それだけでは語る主体の物語で終わってしまう。(167~168ページ)
正義と倫理的命令としての「生の無条件の肯定」
正義というものが存在するのであれば、それはどのような生が生きることをも無条件に肯定しなければならない。生の無条件の肯定が、倫理的命令である。(193ページ)
(1)「生の無条件の肯定」は、感情や気持ちの問題ではない。「生の無条件の肯定」は、広く社会構造の問題をも問うものであり、条件をつけながら特定の存在だけを「生きる価値がある」とする社会構造に反対するものだと言える。(2)「生の無条件の肯定」は、生命の神聖性原理ではない。生命の価値を、他の価値と比べて絶対で最高の価値であるとする「生命の神聖性」という原理とも一線を画し、それがなければ他の、自由や平等などといった価値が実現しないという意味で、基本的かつ原初的な価値であると言える。(3)「生の無条件の肯定」は、スティグマを与えるものではない。当事者にスティグマを与えたり、スティグマを黙認する社会のようなものが、「生の無条件の肯定」を体現するはずもない。(4)「生の無条件の肯定」は、現前するものではない。「生の無条件の肯定」は、いまだ達成されたものでもないし、将来達成されるものでもないからこそ、正義なのである。(194~198ページ)
[2]『「共倒れ」社会を超えて』
「生きづらさ」と共依存による「共倒れ」の社会
困っているとき、弱っているときに、誰かに何かをお願いしたり頼ったりすることを妨げてはならず、誰かにSOSを発信すること自体はけっして悪いことではない。(中略)〈生きづらさ〉をひとりで抱え込む必要などないからである。他方で、ある特定の相手と閉じた関係性が形づくられ、そこでのみ〈生きづらさ〉が共有されるような場合、「共倒れ」の危険性が出てくる。というのも、弱っている相手、支えが必要な相手を支えたくても支えきれなくなった場合、もはやそれは「共に生きる」状態ではなく、「共倒れ」と呼ぶにふさわしい状態だからである。(75ページ)
Xという条件を満たしていなければ生きる価値などないと思わせるような構造や価値観がこの社会に存在しているからこそ、共依存による「共倒れ」が起こってしまうのだと私は考えている。(中略)であるから私は、共依存による「共倒れ」を防ぐには、家族や近親者だけに責任を負わせてはならないと考えている。誰もが無条件に生きてよいというメッセージを社会が発し、それを可能にするような制度を整えることが、より根本的な解決法であろうと思うのである。(76~77ページ)
「犠牲のシステム」と「豊かに」生きられる社会
犠牲とは、交換や譲渡ができないもの、しないものを、その社会において、それができるようにする力のことである、と言ってよいのではないか。そして、真の「豊かさ」とは、交換不可能性、譲渡不可能性を源泉とする価値のことなのである。であるなら、交換不可能性、譲渡不可能性に基づく価値を、自発的にせよ強制的にせよ、社会に差し出してはならないのであり、それらの価値を守るために、交換可能な価値は存在すると考えることもできるのではないか。ここで私は、(中略)交換不可能な価値を差し出さなくてもすむような社会を創出するためにこそ、交換可能な価値を使う必要があると述べているのである。交換可能な価値の代表が貨幣であり、交換不可能な価値の代表が身体や生命、環境、尊厳である。交換可能な価値は、使用することによって価値が生まれ、交換不可能な価値は、そこに存(あ)るだけで本源的な価値を有していると言えるかもしれない。(96ページ)
「豊かに生きる」とは、すべての生が、先述のような意味において犠牲にならないことであると私は考えている。人の生命や尊厳など交換不可能なものを、貨幣など交換可能なものに「交換」させ、それを「美談」に仕立て上げ、そうした「交換」を社会に埋め込んでいく装置が、「犠牲のシステム」なのである。他者を犠牲にしない、そして私という存在も犠牲にされない社会(「犠牲のない社会」:筆者)こそが、他者と共に「豊かに」生きられる社会であると言えるのではないか。(96~97ページ)
障がい者の「生そのもの」を選別する「教育」と「観念」
日本の道徳教育においては、「生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重する」(中学校学習指導要領)などと、生きることや生命を尊重することの大切さを児童・生徒に理解させることが重視されている。(190ページ)
(分離教育を前提とするこの国の:筆者)学校教育においては、障害のある「生そのもの」が、「学校教育に順応できる(順応させるに値する)」かどうかが、当人および家族の意向よりも優先的に問われることになるのである。つまり、障害のある「生そのもの」は、「この社会で生きるに値する/生きさせるに値する」かどうかが問われることになるわけである。こうして、障害をもつ子どもの「生そのもの」は、一般化・抽象化された「生命」観に基づく価値序列によって選別の対象となっていくのである。こうした動きを、根本のところで推し進めているのは、政治や法律であるというよりはむしろ、「障害者の『生そのもの』は、生きるに値する/生きさせるに値するかどうかが問われても仕方がない」という、広く私たちを覆う観念なのではないか。そして、そのような観念は、世論によって強化され押し広げられ、私たちを、障害をもつ人を、「犠牲の構造」へと巻き込んでいくのである。(194~195ページ)
「生の無条件の肯定」と「権力に抗する倫理の姿」
一般化・抽象化された「生命」ではなく、個別・具体的な「生命」に目を凝らしてみると、ただそこに存在しているだけで、それは絶対的なのである。個別・具体的な「生命」は、ある空間と時間において間違いなく存在している。だからこそ、それは比類がないのであって、絶対的なのである。(中略)この「生きているということそのもの」(「生そのもの」)こそ、あらゆる生の原形であって、私たちはこうした「生そのもの」を無条件に肯定しなければならないのではないか。なぜなら、「生そのもの」の否定は、原理的な水準において、すべての生の否定を意味するからである。こうした理由によって「生命の価値」「生命の尊厳」といった一般的・抽象的な次元よりもいっそう深い水準において、「生そのもの」を無条件に肯定する必要があるのではないかと私は考えているのである。(191~192ページ)
権力は「生そのもの」を、一般化・抽象化された「生命」に基づく価値序列に当てはめ、「生きるに値する生/生きさせるに値する生」であるかどうか選別していく。その過程で権力は、「生そのもの」に「尊厳」を付与することで、「生そのもの」を肯定する回路を絶ってしまう。だからこそ私たちは、そうした力に抵抗しなければならないのである。「生そのもの」を、それ自体として受け取ること、したがって、一般化・抽象化された「生命」として受け取ってはならないということ、「生そのもの」を無条件に肯定すること。それこそが、「生の無条件の肯定」が指し示す倫理の地平なのである。(200ページ)
社会運動と「民主的アプローチ」
多くの社会運動は、「他者と共に豊かに生きられる社会」の実現を目指している。裏を返せばそれは、この社会が、まだそうなっていないことを意味している。(中略)現安倍政権は、異質な人間を排除し、同質な人間をのみ成員とする社会を作ろうとしているように思えてならない。異質な人間を異質なまま、この社会のメンバーとして受け入れようとせず、同質化を強要し、それに従わない人は構成員とみなさず、放遂しようとしているのである。それによってこの社会は、他者と出会う機会を失っていき、同質な人間だけで完結した、閉じた社会になっていくのではないか。(180ペジ)
社会運動にかかわる上で肝要なのは、ある属性をもつ人びとを差別し、見殺しにするこの社会を、「犠牲の構造」の上に成り立つこの社会を絶対に許さないという思いと、いつの日か、そうした社会を変革することができるという信念ではないかと私は思うのである。(215~216ページ)
いくら「来るべき社会」について議論をしても、その基底に「正しさ」がなければ、何の意味もない。人びとがもし、「政治的な力による調整」によって多数派を形成することこそ民主主義の実践だと考えているとすれば、端的に言ってそれは誤りである。結局のところそれは、政治的に力の強いものこそが「正しい」と言っているのと同じである。複数あるプランのうち、もっとも論拠が確かで妥当性が高いのは何かをめぐって、意見交換をしながら合意を形成し、それに基づいて社会を運営していくというのが、あるべき民主主義の姿ではないか。(222ページ)
〇野崎の言説の核心は、「『生の無条件の肯定』は正義であり、倫理的命令である」という点にある。それを[1]では「障害者」の視点に立って、[2]では「犠牲」という視角から論究するのであるが、その主張を際立たせようとするあまり、論理の飛躍や混乱、不整合が散見される。例えば、野崎は「負け惜しみではなく、障害がないほうがよい、とは思わない障害当事者も存在する」ことから「『障害はないほうがよい』という問いに対する答えは定まらない」([1]27ページ)という。その意見については、筆者にも「自分がCP(Cerebral Palsy:脳性マヒ)であることを誇りに思っている」という知人がいるが、一般論としては全面的には首肯しかねる。「障害はないほうがよい」。ただし、それが即、障がい者の存在を否定することにつながらない論理の展開が強く求められる。そこでは、障がい者に対する意識・態度や個別具体的な支援のあり方などが厳しく問われることになる。多言を要しない。
〇野崎の言説は必ずしも新味性があるとは言えないが、そこから福祉教育実践や研究が学ぶべき論点や主張も多い。例えば、「身体や生命は、そこに在るだけで本源的・絶対的な価値を有している」。「一般化・抽象化された『生命』ではなく、個別・具体的な『生命』に目を凝らすことが重要である」。「学校教育においても、障害のある『生そのもの』は価値序列によって選別の対象となっている」。「生きる・生きさせるに値するかどうかを問うという考え方は、世論によって強化・拡大されていく」。「これまでの学問体系や私たちの社会に、ただ単に当事者(障がい者)の主張をつけくわえるもので満足してはならない。それだけでは語る主体の物語で終わってしまう」、などがそれである。
補遺
野崎泰伸は、「倫理」と「倫理学」そして「哲学」について次のように述べている。
「倫理」とは、「人としてあるべき道についての掟」のようなものである。「倫理学」とは、「いかに生きるべきか」について考える学問である。「哲学」とは、人生のあらゆる出来事について、その根源にさかのぼって探究する学問である。倫理学は哲学のひとつの領域である([2]49ページ)。「障害とは何かを問うていく営為は哲学的であり、障害者とともに生きる社会はどうあるべきかを考える営為は倫理学的でもある」([1]21ページ)。
【初出】
<雑感>(67)阪野 貢/障がい者差別と生の思想:「自分の存在意義を問う」(「“ただ生きる”ことの保障」×「“よく生きる”ことの実現」×「“つながりのなかに生きる”ことの持続」)―野崎泰伸「生の無条件の肯定」思想についての福祉教育的視点からのメモ―/2018年11月3日/本文
08 「しんがり」の姿勢
<文献>
(1)鷲田清一『しんがりの思想―反リーダーシップ論―』角川新書、2015年4月、以下[1]。
(2)駒村康平編『社会のしんがり』新泉社、2020年3月、以下[2]。
〇[1]で鷲田清一はいう。「縮小社会・日本に必要なのは強いリーダーではない。求められているのは、つねに人びとを後ろから支えていける人であり、いつでもその役割を担えるよう誰もが準備しておくことである」。いま、「新しい市民のかたち」「自由と責任の新しいかたち」が問われている(カバー「そで」「帯」)。
〇鷲田の論はこうである。日本は、高度経済成長の「右肩上がり」の時代から「右肩下がり」の時代に移行し、人口減少や少子高齢化などによる「縮小社会」が進行している。しかしいまだに、この国の政治・経済は「成長」を至上命題として考え、多くの人は拡大思考から解放されないでいる。
〇かつて出産から子育て・教育、看護や介護、看取りと葬送(そうそう)、もめ事解決、防犯・防災などの基本的な生活活動(生命に深く関わる「いのちの世話」)は、地域社会で住民が共同で担ってきた。しかし、高度消費社会の進展が図られるなかで、それらの活動も、納税やサービス料を支払うことによって、行政や専門家、サービス企業に責任放棄・転嫁(「押しつけ」)され、委託(「おまかせ」)されている。別言すれば、市民が「顧客」や「消費者」という受け身の存在に成りさがっている(「市民の受動化」)。それは、「責任を負う」ということをめぐっての、この社会の「劣化」であり、市民の「無能力化」を意味する。
〇いま、こうした「右肩下がり」の時代を見据えて、いかにダウンサイジング(downsizing、縮小化)していくかが問われている。そこで求められるのは、人や組織を引っ張っていく強いリーダーシップ(リーダー)ではなく、社会全体への気遣い・目配りや周到な判断ができ、「退却戦」もいとわないフォロワーシップ(フォロワー)である。それが「しんがりの思想」である。これこそが、市民が受動性から脱して「市民性」(シティズンシップ)を回復させ、それを成熟させる前提になる。「市民性」とは、「地域社会のなかで、みなの暮らしにかかわる公共的なことがらについてともに考える、そしてそれぞれの事情に応じて公共の務めを引き受ける、そんな市民・公民としての基礎的な能力」(88ページ)をいう。
〇そして、鷲田にあっては、「市民性の回復」すなわち(対抗的な)「押し返し」の活動は、たとえばボランティアやNPOの活動、Uターン、Iターンの動きなどに見ることができる。リーダーや市民にはいま、「しんがり」の務めと「押し返し」のアクションを行なうことが求められている。その際に重要なのは、リーダーシップではなくフォロワーシップである。
〇鷲田は[1]で、民俗学者の梅棹忠夫の「請(こ)われれば一差し舞える人物になれ」(215ページ)という一言を引いて本文を閉じる。「成熟した市民」「賢いフォロワーとなる市民」の姿である。
〇[2]は、2014年度から2018年度まで慶應義塾大学で行われた全労済協会寄附講座「生活保障の再構築―自ら選択する福祉社会」をもとに、さまざまな分野や地域で、変化する社会経済が引き起こす諸課題を克服すべく格闘している「しんがり」たちの活動をまとめたものである(8ページ)。
〇[2]での駒村康平の思い・願いは、すなわちこうである。「しんがり(殿軍:でんぐん)」とは、戦いに敗れて撤退する本隊を守るために最後まで戦場に残り、敵を食い止める部隊のことである。社会や地域が大きく変化し、その対応に既存の諸制度が対応できないときに、起きている問題に格闘する人や組織は必ず必要である。そうした人々や組織を「しんがり」と呼び、「先駆け(先駆者)」だけが褒(ほ)めそやされる時代に、「しんがり」の活躍にも光を当てたい(8~9ページ)。
〇駒村はいう。今日の日本社会は、人口減少や格差の拡大などによる社会の劣化が進んでいる。また、戦前・戦中の適者生存や優生思想が強まり、再び危機の時代を迎えている。LGBT(性的少数者)をめぐる生産性の議論や相模原障害者施設殺傷事件(2016年7月)などがそれである。そんななかで、地域社会を維持するために自ら社会問題を考え、構想し、地域の問題は住民自身で解決するという意識のもとで行動できる市民を育てる。また、平和のために時代や場所を超えて他者の困窮(困りごと)を想像し、共感できる市民を増やす、それが強く求められる。駒村が期待する「市民」は次のようなものである。
(1)充実した熟議ができるような市民になってほしい
社会や国に影響を及ぼす大きな政治的な諸問題について、伝統にも権威にも屈従することなく、よく考え、検証し、省察し、議論を闘わせる市民になってほしい。
(2)他者への敬意を払うような市民になってほしい
自分たちとは人種、宗教、ジェンダー、セクシュアリティが異なっていたとしても、他の市民を自分と同等の権利を持った人間と考え、敬意を持って接するようになってほしい。
(3)他者、他国の人の気持ちを想像、共感できる市民になってほしい
さまざまな政策が自分そして自国民のみならず他国の人々にとってどのような意味、影響を持つかを想像、理解できるようになってほしい。
(4)人の「物語」を聞くことにより、人生の意義を広く、深く理解できる市民になってほしい
幼年期、思春期、家族関係、病気、死、その他、さまざまな人生の出来事について、単に統計・データとして見るのではなく、一人ひとりの人生の「物語」として、理解することによって、多様な生き方に共感できるようになってほしい。
(5)政治的に難しい問題でも自ら考え、判断できる市民になってほしい
政治的な指導者たちを批判的に、しかし同時に彼らの手にある選択肢を詳細にかつ現実的に理解したうえで、判断するようになってほしい。
(6)世界市民として自覚し、社会全体の「善」に想いをはせてほしい
自分の属する集団にとってだけではなく、社会、人類全体にとっての「善」について考えてほしい。複雑な世界秩序の一部として自分、自国の役割を理解し、人類が抱えている国境を超えた、複雑で知的な熟議が必要とされる多様な諸問題の解決を考えてほしい。(23~24ページ)
〇言うまでもなく、地域の問題は地域住民の問題であり、住民自身で解決するという意識が重要である。その地域社会(まち)のありようを最終的に決めるのは、「市民」でなければならない。その点で市民には、鷲田がいう「市民性の回復と成熟」、駒村がいう(1)から(6)の「市民性」(市民としての資質・能力)の形成が求められる。地域の問題はまた、複雑化・複合化し、多様化、困難化している。その点で市民には、多領域の専門家や「関係人口」などとの「共働」が肝要となる。先ずは問題把握や解決に向けて「熟議」する公共的な “場” の構築であろう。さらに市民には、政治や行政に対する一辺倒な批判だけでなく、まちの将来展望を踏まえた課題解決活動や運動の取り組みが求められる。これらは、筆者がいう「市民福祉教育」に通底する。
〇なお、鷲田は[1]で、福澤諭吉の『学問のすゝめ』の一節、「一人にて主客二様の職を勤むべき者なり」(岩波文庫、1978年1月、64ページ)を引く。それは、「ふだんは公共のことがらを、市民のいわば代理として担う議会や役所にまかせておいてもいいが、そのシステムに致命的な不具合が露呈したとき、あるいはサービスが決定的に劣化したときには、いつでも、対案を示す、あるいはその業務をじぶんたちで引き取るというかたちで、人民が『主』に戻れる可能性を担保しておかなければならないということである」(197~198ページ)。これは、「顧客」「消費者」としての市民の、鷲田がいう「押し返し」である。世間から押しつけられるものではなく、地べたから立ち上がる、「責任」の新しいかたち(感覚)である。得意げに口汚くののしるだけの市民(クレーマー)や専門家は無用であり、ときに有害でもある。付記しておきたい。
【初出】
<雑感>(114)阪野 貢/社会劣化の時代における「しんがり」の思想と闘い―鷲田清一著『しんがりの思想』と駒村康平編著『社会のしんがり』のワンポイントメモ―/2020年8月1日/本文
09 「助けて」の表明
<文献>
(1)奥田知志『もう、ひとりにさせない―わが父の家にはすみか多し―』いのちのことば社、2011年6月、以下[1]。
(2)奥田知志『「助けて」と言おう―3・11後を生きる―』日本キリスト教団出版局、2012年8月、以下[2]。
(3)奥田知志・茂木健一郎『「助けて」と言える国へ―人と社会をつなぐ―』集英社新書、2013年8月、以下[3]。
(4)佐藤彰・奥田知志・宋富子、明治学院150周年委員会編『灯を輝かし、闇を照らす―21世紀を生きる若い人たちへのメッセージ―』いのちのことば社、2014年3月、以下[4]。
(5)奥田知志・稲月正・垣田裕介・堤圭史郎『生活困窮者への伴走型支援―経済的困窮と社会的孤立に対応するトータルサポート―』明石書店、2014年3月、以下[5]。
(6)埋橋孝文、同志社大学社会福祉教育・研究支援センター編『貧困と生活困窮者支援―ソーシャルワークの新展開―』法律文化社、2018年9月、以下[6]。
〇2018年11月、日本福祉教育・ボランティア学習学会第24回大会(「あいち・なごや大会」)が日本福祉大学(愛知県東海市)で開催された。大会テーマは、「共生文化創造への途―福祉教育・ボランティア学習の新たな展開を探る―」であった。奥田知志の記念講演――「共に生きる意味」と、それを受けて行われた大橋謙策との対談――「共生文化の創造にむけた学び」は圧巻であった。宗教や実践・研究の体系を持つヒトは強くて深い。聞き手は感銘を受け、心が揺さぶられる。
〇周知のように、奥田は、生活困窮者(ホームレス等)に対して、信仰(神学)に支えられた深い洞察とそれに基づく個別的で包括的かつ持続的な「人生支援」を行っている。奥田はいう。「自己責任論の社会が私たちから奪ったものがある。それは『助けて』という一言である」(「2」37ページ)。大橋は、地域福祉の理論と思想、方法(コミュニティソーシャルワーク)、そして福祉教育について実践的研究を進めている。大橋はいう。「新たな社会システムに必要な価値、意識として“博愛”の精神の涵養とそれを推進する福祉教育が求められる」(大橋謙策『新訂 社会福祉入門』放送大学教育振興会、2008年3月、227ページ)。
〇[1]:本書の内容をあえて言えば、「絆の神学」とも言うべきであろうか。しかし、それは空論ではなく、具体的な「ホームレス」との出会いの中から紡(つむ)ぎだされた「絆の物語の神学」である。この時代に「だれ」と、どのような「絆」を結んで生きるのかと、この本は問いかけている。(関田寛雄「推薦の言葉」6ページ)
〇[2]:震災以来声高に叫ばれ続ける「絆」という言葉。しかし多くの場合、そこで意味しているのは自分に都合のよい絆のこと。ホームレス支援の現場と震災支援の中で見えてきた、傷つくことを恐れて自己責任論の中に逃げ込む現代人の心のあり方を問う。(「帯」)
〇[3]:ホームレスが路上死し、老人が孤独死し、若者がブラック企業で働かされる日本社会。人々のつながりが失われて無縁社会が広がり、格差が拡大し、非正規雇用が常態化しようとする中で、私たちはどう生きればよいのか? 本当の“絆”とは何か? いま最も必要とされている人々の連帯とその倫理について、社会的に発信を続ける茂木健一郎と、長きにわたり困窮者支援を実践している奥田が論じる。対談本。(カバー「そで」)
〇[4]:本書は、明治学院150周年記念連続講演会(2013年11月、明治学院高校主催)を再録したものである。奥田の講演「その日、あなたはどこに帰るか?―誇り高き大人になるために」が収録されている。メッセージは、「誇り高い人類として生きたいのならば、『助けて!』と言ってください。『助けて!』は、新しい社会を創造するために欠かせない言葉です」。(77ページ)
〇[5]:奥田によって名づけられた「伴走型支援」の思想・理念・仕組みを確認するとともに、その成果と課題を実証的に明らかにしたうえで、これからの生活困窮者支援の方向性を示す必要があると考えた。それが本書である。(稲月正「はじめに」4ページ)
〇[6]:本書は、①「伴走型支援」の内容、②家計相談支援の意味と方法、③学校ソーシャルワークの背景と機能、④保育ソーシャルワークの今後の方向性など、生活困窮者および(子どもの)貧困に関するホットイシューズを取り上げている。講演記録集。(埋橋孝文「序」3ページ)
〇筆者が奥田を知ったのは、NHKクローズアップ現代取材班編著『助けてと言えない―いま30代に何が―』(文藝春秋、2010年10月)である。その本の「帯」の一文、「言えない/孤独死した39歳の男性が便箋に残した最後の言葉は『たすけて』だった」に衝撃を受けたことを覚えている。ここでは、[1]から[6]のうちから、[1]の論考について筆者が留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「一人称」で語られる「安心・安全」は人を無縁へと押しやる
「安全、安心の街づくり」とは、いったい何であったのか。そもそもホームレス状態の人々を「タイプの違う人」と呼び、「治安や秩序が乱れる」と決めつけているのは差別である。「安全、安心の街づくり」が人を排除し、その人たちを死へと向かわせている。「安心・安全」が、人を無縁へと押しやっているのである。あえて問いたい。「安心・安全はそんなに大事か」と。自分たちの「安心・安全」を追求する地域社会が、「自分の安心・安全」を守るために他者との出会いのチャンスを自ら閉ざし、敵対心を燃やす。あるいは、それを理由に無関係を装う。(92ページ)
実際の「安心・安全」は、常に「一人称」で語られる。私の安心・安全、我が町の安心・安全、我が国の安心・安全、我が家の‥‥‥。そこには、あなたの安心・安全や彼らの安心・安全は存在しない。全部が「我がこと(一人称)」なのだ。そもそも人が出会い、共に生きようとする時、人は多少なりとも自分のスタイルやあり様を変えざるを得なくなる。すなわち、自らの都合を一部断念せざるを得なくなる。出会いというものは、その意味で自分の「安心・安全」のみを願う私たちにとって、「危険」だと言わざるを得ない。出会いによって人は学ぶ。そして学ぶと、人は変えられ、新たにされる。(93ページ)
「自己責任論」は社会の無責任を肯定し人を分断・排除する
自己責任論社会とは、困窮状態に陥ったその原因も、またそこから脱することも、すべては本人次第、本人の責任であるという考え方である。現在の社会は、この自己責任論に席巻された感がある。(162~163ページ)
自己責任論の構造は、ある人に関する責任を、ある一定の範囲に押しとどめて理解するというものである。自己責任、あるいは身内の責任は、自分自身、あるいは家族という一定の範囲に責任を押しとどめた。その結果、周囲は無責任を装えたのだ。「自己責任論」は、社会の無責任を肯定するための理屈だった。自己責任論的な構造は、日本社会においては以前からあったと思う。しかし、当時成長を続ける社会というものが前提として存在していたゆえに、がんばればチャンスを手に入れられるという時代でもあった。すなわち、個人のがんばりが効く時代であった。自己責任という言葉は、教育的な面も含め、ある程度の意味があったのだ。しかし、現在のような低成長期において、企業社会や家族的経営と呼ばれたものは崩壊し、終身雇用制は原則ではなくなった(賃金労働者の4割が非正規雇用である:阪野)。公の行う社会保障も先細るなかで、自己責任は「励まし」ではなく、人を分断、排除するための用語となった。(168ページ)
「孤族」の時代は「何が必要か」とともに「だれが必要か」を問う
ホームレス支援において重要なのは、「ハウスレス」と「ホームレス」という、2つの困窮という視点である。ハウスレスは家に象徴される、食糧、衣料、医療、職などあらゆる物理的(・経済的:阪野)困窮を示す。もうひとつは、ホームレス。それは、家族に象徴されてきた関係を失っている、すなわち関係的困窮(無縁:筆者)を言う。税制と社会保障の一体的改革は、ハウスレス問題にとって重要な課題である。経済の動向がこの先どのようになるのか。労働者の権利がどのように守るのかなど、課題は山積である。しかし一方で、たとえ食べられるようになったとしても、だれと食べるのかという問題は、さらに重要な事柄なのだ。この視点に立ち、野宿者支援をしてきた私たちが考え続けたことは、この人には今何が必要か、ということとともに、この人に今だれが必要か、ということであった。そして今日、このホームレス問題は、野宿状態という物理的困窮の有無にかかわらず、多くの人々が抱えている問題となっている。(171ページ)
「無縁社会」や「孤族」の時代は、ホームレス問題がもはや路上の問題ではないことを明示している。このホームレス化を促進したもの、その最大の要因が「自己責任論」であったと思っている。(172ページ)
「傷」つくことなしにだれかと出会い「絆」を結ぶことはできない
自己責任社会は、自分たちの「安心・安全」を最優先することで、リスクを回避した。そのために「自己責任」という言葉を巧妙に用い、他者との関わりを回避し続けた。そして、私たちは安全になったが、だれかのために傷つくことをしなくなり、そして無縁化した。長年支援の現場で確認し続けたことは、絆には「傷」が含まれているという事実だ。(209ページ)
傷つくことなしにだれかと出会い、絆を結ぶことはできない。出会ったら「出会った責任」が発生する。だれかが自分のために傷ついてくれる時、私たちは自分は生きていてよいのだと確認する。同様に、自分が傷つくことによってだれかがいやされるなら、自分が生きる意味を見いだせる。自己有用感(自分は人の役に立っているという意識:阪野)や自己尊重意識にとって、他者性と「きず」は欠くべからざるものなのだ。(210~211ページ)
「傷つくという恵み」――国家によって犠牲的精神が吹聴された歴史を戒(いまし)めつつ、今こそ他者を生かし、自分を生かすための傷が必要であることを確認したい。(211ページ)
〇日本社会はいま、福祉や教育の世界においても、規制緩和や市民参加(「我が事・丸ごと」等)が声高に叫ばれるなかで、民主主義の崩壊が進み、国家権力による管理・統制が強化されている。「地域参加による学校づくりのすすめ」(「コミュニティ・スクール」等)や市民によるまちづくり(「地域福祉計画」等)の「主体性」や「自律性」も所詮は、規制緩和と同時並行的に管理・統制の変更や強化が図られるなかでのものに過ぎないのか。こうした社会認識のもとで改めて[1]を読むと、奥田らの地べたを這いずり回り、血がにじむ取り組みにただただ頭が下がる。とともに、日本社会の危うさを痛感する。
〇福祉教育についての議論は、「学会」の界隈だけにあるのではない。個別具体的な実践や研究が展開されている「いま」(現在進行形)の福祉教育現場こそが重視されなければならない。「学会」は、最新の福祉教育実践や研究の成果を持ち寄り、多面的・多角的な視点から議論し、実践・研究の深化や発展を図る“現場”である。その“現場”ではいまだに、これまでの権威ある学説を無条件に受け入れたり、眼前の地域・社会や新たな社会福祉問題に向き合おうとしない「報告」が散見される。高齢者や障がい者、生活困窮者、外国籍住民などを福祉教育実践や研究の「共働者」ではなく、言い古された「当事者」として位置づけるモノも多い。また、気鋭の実践家や研究者による実践・研究の学際的・総合的、歴史的・哲学的視点(視座)からの掘り起こしやブラッシュアップ(磨き上げること)も、必ずしも十分であるとは言えない。学会の「あいち・なごや大会」に参加し、また[1]から[6]を読み返して思ったことのひとつである。
補遺
奥田の言説のキーワード、キーコンセプトのひとつに「伴走型支援」がある。奥田によるとそれは、「1988年にホームレス支援が始まり、以来、路上での生活やその後の看取りまで続く営みのなかで生まれた支援論である。学者が豊富な知識を駆使して構築した体系ではない。日々の経験が積み重ねられ、何よりも当事者から学ぶなかで澱(おり。液体の底に沈んだカス:阪野)が沈殿していくようにできた支援論である」([6]27ページ)。奥田は、生活困窮者支援における「伴走型支援の7つの理念」について次のように整理している。([5]56~72ページ抜き書き)
(1)家族(家庭)機能をモデルとした支援
家族(家庭)が持っていたと想定される機能に、①包括的、横断的、持続的なサービス提供機能、②記憶の蓄積と記憶に基づくサポートプラン策定機能、③持続性のあるコーディネート機能、④役割の担い合いによる自己有用感提供機能、がある。伴走型支援は、これらの家族(家庭)機能をひとつのモデルとした支援である。
(2)早期的、個別的、包括的、持続的な人生支援
伴走型支援は、生活困窮者が社会的に孤立状態にあり、しかも多様で複合的な課題を抱えているとの認識に立つがゆえに、早期的、個別的、包括的、持続的な支援でなければならない。それは「自立支援」にとどまらず、「人生支援」である。
(3)存在の支援
伴走型支援は、従来の問題解決型の「対処・処遇の支援」に加えて、「伴走そのもの」を支援とする。伴走者と当事者が、向き合うこと、関係すること自体が支援である。
(4)参加包摂型の社会を創造する支援
伴走型支援は、徹底して個人に寄り添うことから始まる。当然の帰結として、社会や地域を問うことになる。困窮者支援は、経済的困窮状態にあり、社会的に孤立した「個人の社会復帰を支援する」といわれるが、問題の本質は「そもそも復帰したい社会であるかどうか」というところにある。
(5)多様な自立概念を持つ相互的、可変的な支援
伴走型支援は、生活自立や社会参加を基軸とした社会的自立、経済的自立など多様な自立概念から構成される。伴走は、助けられたり助けたりという相互的な関係である。また、助けられた者が助ける側に変われる可変性が担保されなければならない。
(6)当事者の主体性を重視する支援
伴走型支援は、当事者が自分で自分を助ける力を得ることである。当事者は「できない人」ではなく、「自分を助けることができる人(になる)」との認識に立つ。「まず自助、次に共助、最後に公助」という順番が重視されるが、自助は、公助や共助が適正に機能している状況において成立する。
(7)日常を支える支援
伴走型支援は、人生支援である。そして人生の大半は、なにげない日常である。伴走型支援は、この日常を支える支援である。伴走型支援は、「日常は問題が起こる場所である」という認識に立ち、日常を支える参加包摂型社会の構築をめざす。
【初出】
<雑感>(70)阪野 貢/「“助けて”と言えない無縁社会」×「“違った意見”が言えない統制社会」:気がつけば民主主義が民主的な手続きによって内側から壊れている―奥田知志を読む―/2018年12月25日/本文
10 「愛郷心」の相克
<文献>
(1)将基面貴巳『反「暴君」の思想史』平凡社新書、2002年3月、以下[1]。
(2)将基面貴巳『日本国民のための愛国の教科書』百万年書房、2019年8月、以下[2]。
(3)将基面貴巳『愛国の構造』岩波書店、2019年7月、以下[3]。
(4)姜尚中『愛国の作法』(朝日新書)朝日新聞出版、2006年10月、以下[4]。
(5)佐伯啓思『日本の愛国心―序説的考察―』中公文庫、2015年6月、以下[5]。(6)市川昭午『愛国心―国家・国民・教育をめぐって―』学術出版会、2011年9月、以下[6]。
(7)鈴木邦男『〈愛国心〉に気をつけろ!』岩波ブックレット、2016年6月、以下[7]。
最近、戦争が始まる “臭い” がする / あんた、戦争を知ってるか / 気をつけなよ / もうこりごりだからな。
最近、“里” の夢をよく見る / 人っ子一人いない / おかしな空模様だ / なぜか、いつもそこで夢は終わる。
〇筆者が、「愛国」や「愛国心」についていま改めて考えなければならないと思ったきっかけは、上記の、要介護高齢者(女性)の痛みに耐えるような“うめき声”である。そして、彼女はいつも、自分が生まれ育った「里」のことを心配している。
〇将基面貴巳は[1]を、「現代日本は『暴政』への道を歩んでいるのではないか。そんな想念がこのごろしきりに脳裏をよぎる」(10ページ)と書き出す。「このごろ」とは、バブル崩壊(1991年3月~1993年10月)後10年余が経過し、小泉純一郎内閣(2001年4月~2006年9月)によって「規制緩和」や「構造改革」という名の新自由主義的政策が推進された時代であろう。
〇[1]は、「危機的様相を日ごとに深める祖国(日本)を念頭におきつつ、政治をいかに監視すべきか。不正な権力にはどのように抵抗すべきか」(232ページ)について真正面からとり上げたものである。そこにおいて、将基面は、「共通善」思想に立脚する「国民社会」の建設の必要性を説く。「共通善」(common good)とは、「社会や国家など政治共同体全体にとっての善のことを指し、ある特定の個人や集団にとっての善とは明確に区別されるものである」(10ページ)。その「共通善」の実現に国民は、直接的な責任を持たない。「それは権力担当者が引き受けるべき責務である」(35ページ)。「暴政」とは、「ある一部の権力者や権力がひいきにする特定の集団が利益を享受することを目的とする政治のことである」(10ページ)。
〇将基面はいう。「共通善思想が浸透した社会では、国民一人ひとりが、国民全体の理想と利益に対して責任を負っていることを自覚し、そうした共通の理想と利益を一人ひとりがおのおのの立場から不断に探求する。また、権力が不正を働いていることを知るならば、これを公の場ではっきりと批判し、たとえ一人であっても不正権力に立ち向かう個人がいれば、その人を『社会』」(特に社会の木鐸〈ぼくたく。指導者〉たるジャーナリズム)が援護する。権力に擦(す)り寄り、既得権益にしがみ付いてはなれようとしない者や、反社会的なビジネスを行う者や組織を公の場で批判し、たとえそうした行為が自らの目的にかない、自分の利益になるとしても、自らは手を出さないよう、自身をコントロールする」(232~233ページ)。このような倫理的感覚・態度をもつ人々が、日本という国家権力に対峙する存在としての「国民社会」を探求し創出することが、現代日本に求められる。将基面の主張のひとつである。
〇国家権力は、被治者を統制・強制する。「いざとなれば、自国民に対してさえ銃口を向け、私有財産を没収し、個人のあらゆる権利と自由を侵害しうる存在である」(39ページ)。国民はこのことを十分に認識し、国民社会の理想像の創出を権力担当者に一切任せてはならない。国民は、一人ひとりが「共通善」を不断に追求し、政治に対する関心を強め、権力を厳重に監視する。そして、正当性や妥当性を欠く場合には、権力に抵抗の意思を明示しなければならない。それは、「国民各自が自分の良心の問題として、悩み、決断すべき問題」(39ページ)であり、国民の倫理的義務である、と将基面はいう。
〇こうした将基面の言説は、「反時代的」(234ページ)なものであり、その底流に流れるのは以下に述べる「共和主義的パトリオティズム」の思想である。
〇[2]は、「日本人なら日本を愛するのは当然であり、自然である」という単純な社会通念に対して歴史的・哲学的に批判する、中学生でも理解できる平易な「教科書」である。内容的には、通俗的な「愛国心」や「愛国心教育」に関する言説への「解毒剤」(将基面)としての効能が期待される。別言すれば、日本の長所ばかりを見て欠点を見ようとしない「日本バカ」(65ページ)にならないための、日本の若者へのエールである。なお、[2]は[3]の「副産物」(将基面)でもある。
〇[2]における論点や言説のひとつの要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
批判的愛国者のすすめ
日本語の「愛国」「愛国心」は、英語で言うとパトリオティズム(patriotism)である。(33ページ)
現代の日本では、「愛国」「愛国心」=ナショナリズムという理解が一般的である。日本語の「愛国」は、「ナショナリズム的パトリオティズム」の意味で理解されている。しかし、ヨーロッパで「愛国」という場合、「共和主義的パトリオティズム」を指す。この考え方が世界的・歴史的には本来のものである。(44、51ページ)
ナショナリズムとは、自らのネイション(nation.国民、民族)の独自性にこだわり、それに忠実であることを求める思想である。(42ページ)
共和主義とは、市民の自治を通じて、市民にとっての共通善(特に自由や平等、そしてそうした価値の実現を保証する政治制度)を守ることを重視する思想である。(35ページ)
「ナショナリズム的パトリオティズム」は、自国を盲目的に溺愛し、自国の失敗や過ちの経験から学ぶことなく、ひたすら自国の歴史や文化を誇りに思う自画自賛(自国礼賛)である。(116、117ページ)
政治的・経済的に権力を持つ人たちは、批判の対象とならざるを得ない。なぜなら、権力を持たない人々にはできないことをその政治的・経済的権限で可能にできる人々は、大きな責任を背負っているからである。(120ページ)
本来の「愛国」「愛国心」とは、常に政治権力に対して批判的なまなざしを注ぎ、市民の自由や平等を守る「共和主義的パトリオティズム」である。権力に対して批判的な態度をとることが愛国的(patriotic)なのである。(123ページ)
「報道の中立性」という犯罪
報道機関の重要な役目は、強制力や影響力を持っている人たちを監視することである。ところが、昨今ではマスメディアが「報道の中立性」という名目で権力批判をしないことが当たり前になっている。これほど甚(はなは)だしい勘違いはない。勘違いどころかほとんど犯罪的な過ちである。報道機関は、権力を持たない人々を代弁するためにあるのである。事実を客観的に報道するだけではなく、権力を持つ人々の仕事内容を、権力を持たない人々の立場から批判するためにあるのである。それをして初めて、報道機関は仕事を立派に成し遂げたということができるのである。(121~122ページ)
〇「現代世界で静かに進行する変化の一つは、『愛国』が政治を語る言葉として復活していることである」([3]2ページ)。「愛国という問題が今日ますます徹底的な思考を要する課題として急浮上している」([3]322ページ)。そういうなかで、[3]は、欧米と日本の多様な現代パトリオティズム論を歴史的観点から批判的に検討し、その固有の性格をあぶり出し、その問題性の一端を明らかにする。約言すれば、愛国=パトリオティズムについての歴史的・哲学的な構造の解明が[3]の目的である(12ページ)。
〇[3]における論点や言説のひとつの要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「愛のまなざし」と愛国
愛国的であることを「祖国への愛」と読み換えるならば、その「愛」は盲目なものであってはならず「愛のまなざし」という観点が重要である。自国に「愛のまなざし」を注ぐということは、「私の国」に対してあらゆる規範的な判断を停止することではない。誇るべ長所だけでなく、恥ずべき欠点も含めて正確に「私の国」を理解することが、「愛のまなざし」に含まれる。一方で、愛する自国に長所を見出すことを喜ぶが、他方で、様々な過失や過誤を見出して、そのことに悩み苦しみ、欠点を改めようと努力するのである。このような「愛のまなざし」に基礎づけられた愛国的態度であってはじめて、それは道徳的義務ではないにせよ、望ましいものでありうると結論づけられるであろう。(222ページ)
「愛のまなざし」(loving attention,loving gaze)において重要なのは、愛の対象を可能な限り明瞭に理解しようとする点である。「愛のまなざし」の下にある対象は、「あばたもえくぼ」ではなく、「あばた」は「あばた」として認識される。「愛のまなざし」は、まなざしの対象に、良いところを見ようと心がけつつも、長所も短所も同様に、正確に理解する。すなわち、そのまなざしが「愛」に発するために、対象に好意的に接するが、しかし、その対象を正確に理解するという意味で、対象を分析し評価することも怠らないのである。共和主義的パトリオティズムを胸に抱く市民は、祖国に対してこのような「愛のまなざし」を持っている。祖国への愛は盲目ではなく、むしろ「祖国を鋭く見つめることを要求する」のである。(170ページ)
愛国と排除の論理
愛国的であるということは、無条件に道徳的正当性を主張できるものではない。にもかかわらず、愛国的であることが国民としての当然の義務であるかのような主張を巷間(こうかん。世間)で目にすることも少なくない。愛国的であることが義務であるとする認識が広く共有されるならば、それはどのような帰結をもたらすのか。(222~223ページ)
自国のアイデンティティに基礎づけられた愛国は、極端な場合、排外的で外国人を忌み嫌ったり見下(みくだ)したりする態度に結びつきやすい。他方、自国民であっても、愛国的ではないと判定される人々は、愛国者たちによって公的な避難や攻撃にさらされることが少なくない。愛国が熱狂化すればするほど、文化や人種、宗教的背景を共有する同一国民の間においてさえ、思想信条を異にする一部の人々を「非国民」「売国奴」であると排撃する傾向が増大することは広く認識されている。(226ページ)
国家の聖性と愛国
国家は、正統な義務を独占する「聖なる」存在である(国家は国民に様々なサービスを提供する組織、神社のように国民にとってありがたい・尊いもの、正当な暴力を独占・行使する存在である)。愛国的であることを義務として承認することは、国家という「聖なる」存在の忠実な信徒であることを意味する。国家の聖性への信仰は、当然、国家を尊崇(そんすう)することを必要とし、国家のための犠牲を要求する。国家のために死ぬことを拒否するのは、国家の聖性を認める限り、極めて難しい。(282ページ)
現代という歴史的地点において愛国的であるということが道徳的義務であると主張しうるとすれば、それは国家の聖性を認める限りにおいてにすぎない。「国家の聖性を認める限りにおいて」という限定条件は極めて重要である。(283ページ)
現代において当然視されているが必ずしも自覚されていない国家信仰を掘り崩(くず)すには、政府(さらには国家)を批判する市民たちが、非国民や国賊などと罵(ののし)られても動じないことが必要である。現代日本の文脈では、「反日」などと非難罵倒(ひなんばとう)されても、これに対して、自分たちこそが愛国的なのだと応答すべきではない。なぜなら、そうした自己弁護は、すなわち「お前は反日だ」という非難を支える国家への崇拝感情を裏書きする(実証する)ことになるからである。(283~284ページ)
〇[4]の姜尚中にあっては、愛国とは、自然な感情の発露としての妄信などではなく、「理にかなった信念」「自分自身の思考や感情の経験に基づいた確信」(54ページ)による行為である。愛郷は、自分が生まれ育った故郷への愛、情緒や感情によるものである。[5]の佐伯啓思にあっては、「戦後日本の愛国心をめぐる感情は、(「あの戦争」によって)ある『負い目』を背負い、その『負い目』をめぐって展開している」。そういった認識に立って「日本的精神の行方」を探求するなかで、「もうひとつの愛国心」(388ページ)を描き出そうとする。
〇将基面は、[4][5]について、「平成時代を代表する日本の愛国心論」である。しかし、いずれも「基本的には啓蒙書」であり、「愛国=パタリオティズムの包括的・体系的議論を必ずしも指向するものではない」([3]9ページ)と評している。
〇ここでは、[4][5]で言及している「愛郷と愛国」「愛郷心と愛国心」について、その一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
姜尚中―「愛郷と愛国」、その微妙な共棲関係
「愛郷」と「愛国」の関係は、「微妙な共棲(きょうせい)関係」にある。つまり、一方では、「愛郷」は、ナショナリズムという特定の歴史的段階において形成された一定の教義によって利用され、時として排斥される関係にある。例えば、上からの「郷土教育」が説かれるのは、画一的な「愛国心」などを強制する場合に、空洞化した実感的な部分を補完する必要があるためである。『美しい国へ』の著者(安倍晋三)が「国を自然に愛する気持ちをもつ」ために、「郷土愛をはぐくむことが必要だ」と述べているのは、そうした「郷土教育」の効用を意識しているからであろう。つまり、「愛郷」は「愛国」に「自然な」感情の装いをほどこす補完的な役割を果たしていることになるのである。(154~155ページ)
佐伯啓思―愛郷心は愛国心の換喩的表現
「愛郷心」とは「愛国心」のいわば換喩(かんゆ。比喩)的表現にすぎない。「郷」は「国」の象徴的な代理になっており、換喩的に「国」を表現している。この二つの概念を変換すれば「パトリオティズム」が二重性を帯びていることは別に不思議ではなかろう。「愛郷心」は結構だが「愛国心」は危険だ、という議論は説得力がない。そして、「愛郷心」と「愛国心」が重なり合うという意味での「パトリオティズム」にある種の強い情緒が伴うのは、「郷」にせよ「国」にせよ、その何か大事なものが失われつつあるからではなかろうか。そこにはあの種の喪失感が付着するのではないだろうか。繰り返すが、ある国の歴史的な伝統や文化や風土がそのままそこにあり、それらに自明のものとして囲まれているとき、人は、わざわざ「愛郷心」や「愛国心」を感じる必要もないであろう。ほとんど無自覚にそれらに囲まれて生活しているだけである。それらが失われつつあるという喪失感に囚(とら)われたとき、もしくは、たとえば外地にあってそこにどうしようもない距離感をもったときにこそ、「愛郷心」や「愛国心」を感じるというべきなのであろう。近代社会は、人々の流動性を高め、急激に都市化を行い、なつかしい風景を破壊していった。このことが近代の人々にパトリオティズムを抱(いだ)かせるのである。(132~133ページ)
〇[6]と[7]について将基面は、次のように評している。[6]は、「戦後の愛国心論では『忠誠問題が無視されてきた』と指摘し、そこに戦後日本における愛国心論の一つの特徴を見ている」([3]121ページ)。[7]は、「72ページの小冊子(岩波ブックレット)ながら、充実した作品である。愛国心の旗印のもと現代日本で広がりつつある排外主義を的確に批判している」([2]193ページ)。それぞれの一節をメモっておくことにする。
市川昭午―愛国は究極的には殉国を求める
愛国心や愛国心教育の問題が敬遠されたり嫌われたりするのは、それが究極において国家に対する忠誠の問題となるからであろう。国民国家は国民を保護し、その権利を保障する代わりに、国民に法律を守らせ、国民の自由を制約する。国家が国民の安全と国の独立を守るための共同防衛装置である以上、国民の側も国を大切に思うだけでは足りず、国防の義務に従うことが要求される。それは一旦緩急(かんきゅう。危急)ある場合には愛国だけでは不十分であり、究極的には殉国(じゅんこく。国のために命をなげだすこと)が求められるということである。(87ページ)
鈴木邦男―〈愛国心〉を汚れた義務にしてはならない
「同じ日本人なんだから」「日本を愛する愛国心をもっているのだから」という視野の狭い仲間意識のもと、排他的な傾向が強まっている。政権を批判したり、日本の問題点などを指摘したりすると「反日!」とののしられる。「他国に学んで、日本のここを良くしよう」などと言っても、「お前は外国の肩をもつのか」と怒鳴られる。その結果、「日本はすばらしい」「日本人は最高」といった自画自賛の言葉が氾濫し、そしてその足下で排外主義が跋扈(ばっこ。強くわがままに振る舞うこと)しているのが現状ではないのか。(52ページ)
〇「まちづくりと市民福祉教育」について語るとき、否が応でも、「自然に育まれた歴史や伝統・文化」の継承や「地域を愛する豊かな心」「郷土を愛する子ども」の育成などに関して語ることになる。しかも、愛郷心とその延長戦上にあるものとして扱われる愛国心が、学校現場においては道徳教育とのかかわりで言及されることにもなる。福祉教育はこれまで、その点を避けてきた。
〇周知の通り政府や文部科学省は、道徳教育と愛国心教育を強化する法律や施策を重ねてきた(いる)。その頂点は、「我が国と郷土を愛する」の文言(愛国心教育規定)が盛り込まれた2006年12月の教育基本法改正と、2018年4月からの道徳の教科化である。
〇2015年3月に「学校教育法施行規則」と道徳に係る「学習指導要領」が一部改正・改訂された。そして、それに基づいて小学校では2018年4月から、中学校では2019年4月から「特別の教科 道徳」(道徳科)が全面実施されている。注目すべきは、検定「教科書」の使用と新たな教育方法と評価の導入である。前者は、「日本の伝統や文化の尊重」「愛国心や郷土愛の態度」などをめぐって、一定の価値観や規範意識を国が上から押し付けることになる。それは、多様性や人権の尊重が声高に叫ばれる時代・社会にあって、極めて憂慮すべきことである。後者については、いわゆる「読み物道徳」「押し付け道徳」から「考え、議論する道徳教育」への質的転換である。しかしそれは、学習指導要領にあらかじめ提示された「道徳的価値」(「内容項目」)に限って「考え、議論する」にとどまる。したがって、それはまた、一定の価値観の押し付けに他ならない。加えて、道徳教育の評価については、「数値による評価」ではなく「個人内評価」として行うとされるが、一人ひとりの児童・生徒の道徳的心情や態度を評価することは憲法が保障する「思想・信条の自由」を侵害する以外の何物でもない。
〇愛国心教育の拡充の背景には、1990年代以降の経済のグローバル化が進展するなかで世界に通用する、「高い倫理観」や「多様な価値観」をもつパワフルな日本人の育成を図る必要があった。と同時に、社会格差が急速に拡大するなかで、国民統合の強化を図ることが要請された(市川昭午『教育基本法改正論争史―改正で教育はどうなる』教育開発研究所、2009年4月、29ページ)。すなわち、グローバル人材の育成・確保(エリート教育)が強く求められるなかで、一般の子ども(ノンエリート)に対する道徳教育の推進が図られ、その中心に位置づけられた(られる)のが愛国心教育である。要するに、「グローバル人材養成の道徳教育」と「ノンエリートへの愛国心教育」、すなわち「国家(財界)のための道徳教育」である。
〇こうした背景を押さえたうえで、大森直樹の言説に留意したい。大森にあっては、道徳教育には2つの重要な領域がある。ひとつは、「道徳は人々が生活と仕事のなかで自然に身につけるものであり、子どもにとっては学校が生活の場であることに対応した領域である」。すなわち、「無意図的な道徳教育」である。いまひとつは、「歴史と社会のなかで人々はどのように道徳を形成してきたか、社会現象としての倫理や道徳について認識をふかめる」領域である。すなわち、「道徳事実についての学習」である。そして大森は、こうした教育・学習は、「社会科をはじめとする教科学習や人権を主題とする総合学習でおこなうべき」である、とする。(大森直樹『道徳教育と愛国心―「道徳」の教科化にどう向き合うか―』岩波書店、』320、321ページ)。「まちづくりと市民福祉教育」について考える際の、ひとつの重要な視点でもある。
〇なお、ここで、愛郷心は生まれ育った地域・郷土の歴史や風土、文化を愛する心(感情や態度)で、地域への帰属意識を醸成する。愛国心は政治共同体としての国家を愛する心(感情や態度)で、国家への忠誠を求める、という愛郷心と愛国心の違いについて改めて確認しておきたい。
【初出】
<雑感>(96)阪野 貢/戦争が始まる“臭い”がする:「愛国」「愛国心」に関するワンポイントメモ―将基面貴巳を読む―/2019年10月8日/本文
11 「差別」の本質
<文献>
(1)キム・ジへ、 尹怡景訳『差別はたいてい悪意のない人がする―見えない排除に気づくための10章―』大月書店、2021年8月、以下[1]。
(2)神谷悠一『差別は思いやりでは解決しない―ジェンダーやLGBTQから考える―』集英社新書、2022年8月、以下[2]。
〇[1]は、韓国で16万部超のベストセラーとなったキム・ジへ(김지혜、Kim Ji-hye)著『善良な差別主義者』(선량한 차별주의자、2019)の日本語訳版である。筆者の差別や人権についての稚拙な考えや思い・願いに変革を迫る、強烈なメッセージを発する本である。内容的には、事例を交えながら、女性や障がい者、セクシュアル・マイノリティ、移民などに対する差別や人権の諸問題が取り扱われる。
〇「本書が注目されたのは、差別に関する既存の考え方に新たな問いを投げかけたからと考えられる。一般に、差別に対する認識は、差別をする加害者と、それを受ける被害者という構造の中で議論される。本書でも指摘されているように、だれもが差別は悪いことだと思う一方、自分が持つ特権には気づかないので、みずからが加害者となる可能性は考えない傾向が強い。こうした考え方に、本書は『善良な』という表現を用いて、『私も差別に加担している』『私も加害者になりうる』という可能性に気づかせる。つまり、平凡な私たちは知らず知らず差別意識に染まっていて、いつでも意図せずに差別行為を犯しうるという、挑発的なメッセージを著者は投げかけている」(金美珍、[1]229~230ページ)。
〇[1]では「トークニズム」、「特権」、「優越理論」、「間接差別」、「差異の政治」などの理論に基づき、「多様性と普遍性」(「多様性をふくむ普遍性」)や「形式的平等と実質的平等」の観点から、また個人的レベルと構造的レベルの差別などをめぐって論究する。「差別禁止法」についての言及も注目される。それぞれの理論と差別禁止法に関する言説の一部をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
トークニズム―名ばかりの差別是正措置:お茶を濁す―
トークニズムtokenismとは、歴史的に排除された集団の構成員のうち、少数だけを受け入れる、名ばかりの差別是正措置をさす。/トークニズムは、被差別集団の構成員のごくわずかを受け入れるだけで、差別に対する怒りを和らげる効果があることが知られている。それによって、すべての人に機会が開かれているように見え、努力し能力を備えてさえいれば、だれもが成功できるという希望を与えるからである。結局、現実の状況は理想的な平等とは雲泥の差があるにもかかわらず、平等な社会がすでに達成されているかのような錯覚を引き起こす。(25ページ)
特権―「持てる者の余裕」:意識にのぼらない恩恵―
特権とは、一部の人だけが享受するものではない。特権とは、与えられた社会的条件が自分にとって有利であったために得られた、あらゆる恩恵のことをさす。/不平等と差別に関する研究が進むにつれ、学者たちは平凡な人が持つ特権を発見しはじめた。ここで「発見」という言葉を使ったのには理由がある。このように日常的に享受する特権の多くは、意識的に努力して得たものではなく、すでに備えている条件であるため、たいていの人は気づかない。特権というのは、いわば「持てる者の余裕」であり、自分が持てる側だという事実にさえ気づいていない、自然で穏やかな状態である。(30ページ)/自分には何の不便もない構造物や制度が、だれかにとっては障壁(バリア)になる瞬間、私たちは自分が享受する特権を発見する。(31ページ)/ほとんどの人は平等という大原則に共感しており、差別に反対している。(中略)しかし、相対的に特権を持った集団は、差別をあまり認識していないだけでなく、平等を実現するための措置に反対する理由や動機を持つようになる。(38ページ)
優越理論―嘲弄(あざけり、からかうこと):他人の不幸は蜜の味―
プラトンやアリストテレスなど、古代ギリシアの哲学者たちは、人は他人の弱さ、不幸、欠点、不器用さを見ると喜ぶと述べた。笑いは、かれらに対する一種の嘲弄(ちょうろう)の表現だと考えたのだ。このような観点を優越理論superiority theoryという。トマス・ホッブズは、人は他人と比べて自分のほうが優れていると思うとき、プライドが高まり、気分がよくなって笑うようになると説明する。だれかを侮蔑(ぶべつ)するユーモアがおもしろい理由は、その対象より自分が優れているという優越感を感じられるからである。/優越理論によれば、自分の立ち位置によって、同じシーンでもおもしろいときと、そうでないときがある。そのシーンから自分の優越性を感じる際にはおもしろいけれど、逆に自分がけなされたと感じればおもしろくない。(92ページ)/集団間の関係においても、同じような現象があらわれてくる。人は自分を同一視する集団に優越感を持たせる冗談、すなわち自分とは同一視しない集団をこき下ろす冗談を楽しむ。もしも相手の集団に感情移入してしまうと、その冗談はもはやおもしろくなくなる。(中略)相手の集団に対してネガティブな偏見を持っている場合はどうだろうか。決して自分とは同一視せず、むしろ距離を置こうとする集団に対する侮蔑は、みずからの属する集団の優越性を確認できる、楽しい経験になる。(93ページ)
間接差別―一見の平等と実際の差別:同じようで違う―
だれに対しても同じ基準を適用することのほうが公正だと思われるかもしれないが、実際は、結果的に差別になる。司法書士試験で、問題用紙・答案用紙と試験時間をすべての人に同一に設定すれば、視覚障害者には不利になる。製菓・製パンの実技試験において、すべての参加者に同じように手話通訳を提供しない場合、聴覚障害者に不利である。公務員試験の筆記試験で、他の受験生と同様、代筆を許可しない場合、高次脳機能障害の人に不利である。これらは、全員に同一の基準を適用することが、だれかを不利にさせる間接差別indirect discriminationの例である。(117ページ)
差異の政治―多様性を含む普遍性:みんな違う、みんな同じ―
承認とは、たんに人であるという普遍性についての認定ではなく、人が多様性をもつ存在であること、すなわち、差異を受け入れることをふくむ。集団間の違いを無視する「中立」的なアプローチは、一部の集団に対する排除を持続させる。「中立」と見せかけている立場は、実は主流の集団を「正常」と想定し、他の集団を「逸脱」と規定して抑圧する、偏った基準であるからだ。アイリス・マリオン・ヤングが述べる「差異の政治politics of difference」は、このように「中立性」で隠蔽(いんぺい)された排除と抑圧のメカニズムに挑むために「差異」を強調する。(194ページ)/アイリス・ヤングは、抑圧的な意味を持つ「差異」という言葉を再定義する必要があると述べる。「主流集団を普遍的なものとみなし、非主流だけを『異なる』と表現するのではなく、違いを関係的に理解し相対化すること」である。女性が違うように、男性も違うことができ、障害者が違うように、非障害者も違うと見る、相対的な観点だ。したがって、差異とは本質的に固定されたものではなく、文脈によって流動的なものである。車いすに乗っている人が「つねに」異なるわけではなく、運動競技のような特定の文脈では差異があっても、他の脈略では差異がなくなるようなものだ。(196~197ページ)/私たちはみな同じであり、またみな異なる。私たちを本質的に分ける差異はないという点で、私たちは人間としての普遍性を共有するが、世の中に差別が存在するかぎり、差異は実在するため、私たちはその差異について話しあいつづけなければならない。(197ページ)
差別禁止法―平等を実現するための方策:文化の改善か、政治改革か―
私たちが生涯にわたって努力し磨かなければならない内容を、「差別されないための努力」から「差別しないための努力」に変えるのだ。これらすべての変化は、市民の自発的な努力によって、一種の文化的な革命としておこなうこともできる。平等な社会をつくる責任のある市民として生きる方法を、市民運動に学ぶのだ。しかし同時に、平等の価値を共同体の原則として明らかにし、新しい秩序を社会の随所に根づかせるための法律や制度も必要だ。日常における省察とともに、平等を実現するための法律や制度に関する議論が必要なのだ。(202ページ)/差別撤廃という目的には同意するが、国が介入する問題なのかという疑問を抱く人々もいる。かれらは、国が介入するかわりに、自発的な文化の改善を通じて社会の変化をつくりだせると考える。これは、たしかに理想的で望ましく、法の制定とは無関係に、根本的な社会変化のために必要なアプローチではある。しかし、すでに差別が蔓延している社会で、法律で定められた規範ないし実質的な変化を期待することは難しい。(208ページ)
〇以上に加えて、キム・ジヘの言説の理解を深めるために、文章のいくつかを抜き書きする。
● 私をとりまく社会を理解し、自己を省察しながら平等へのプロセスを歩みつづけることは、自分は差別をしていないという偽りの信仰よりも、はるかに貴重だということだけは明らかである。(プロローグ:13ページ)
● 私たちが権利や機会を要求するとき、結果として求めるのは、ただ楽な人生ではない。私たちは、施設に閉じ込められ、他人から与えられたものだけを食べて寝て、何の労働もせず生涯を送る人生を、人間らしい生き方とは思わない。(中略)不平等な立場にいる人が平等な権利と機会を求めるのは、他の人と同じように、リスクを覚悟して冒険し、自分なりの人生を生きていくための権利と機会という意味なのである。(1章:36ページ)
● 立ち位置が変われば、風景も変わる。/風景全体を眺(なが)めるためには、世の中から一歩外に出てみなければならない。(中略)私たちの社会がユートピアに到達したとは思えない。私たちはまだ、差別の存在を否定するのではなく、もっと差別を発見しなければならない時代を生きているのだ。(1章:41ページ)
● 固定観念は、自分の「頭の中にある絵」にすぎない。(中略)固定観念は、自分の価値体系をあらわす、ある種の自己告白になる。(51、52ページ)/固定観念は一種の錯覚だが、その影響力は相当強い。(中略)人々は、自分の固定観念に合致する事実にだけ注目し、そのような事実をより記憶し、結果的に、ますます固定観念を強固にしていくサイクルが作られる。一方で、固定観念に合致しない事実にはあまり注意を払わない。固定観念を覆すような事例を見かけたとしても、なかなか考えを変えようとしない。かわりに、その事例を典型的ではない特異なケースとみなし、例外として取りあつかうのである。(2章:52~53ページ)
● 差別を眺めるとき、性別や人種という軸に加えて国籍、宗教、出身国・地域、社会経済的地位などの軸を加えると、状況はさらに複雑になる。(62~63ページ)(中略)差別の経験をひとつの軸だけで説明することはできない(中略)。/さまざまな理由で幾重にも重なった差別を受ける人、差別を受ける集団の中でさらに差別を受ける人もいる。差別とは、二つの集団を比較する二分法に見えるが、その二分法を複数の次元に重ねて立体的に見てこそ、差別の現実を多少なりと理解することができるのだ。(2章:63ページ)
● 差別は私たちが思うよりも平凡で日常的なものである。固定観念を持つことも、他の集団に敵愾心(てきがいしん)を持つことも、きわめて容易なことだ。だれかを差別しない可能性なんて、実はほとんど存在しない。(2章:65ページ)
● (差別について)考察する時間を設けるようにしないかぎり、私たちは慣れ親しんだ社会秩序にただ無意識的に従い、差別に加担することになるだろう。何ごともそうであるように、平等もまた、ある日突然に実現されるわけではない。(3章:85ページ)
● 「からかってもいい」とされる特定の人々(中略)だけに同じようなこと(揶揄、蔑視)が集中してくりかえされる。私たちは、だれを踏みにじって笑っているのかと、真剣に問いかけるべきなのだ。(96ページ)/だれかを差別し嘲弄するような冗談に笑わないだけでも、「その行動は許されない」というメッセージを送れる。(中略)少なくとも無表情で、消極的な抵抗をしなければならないときがあるのだ。(4章:105~106ページ)
● 私たちはたちは教育を通じて、不公正な能力主義を学んでいるのではないだろうか。そのことによって、何ごとも不合理に区分しようとする、不平等な社会をつくっているのではないか。いまさらながら怖くなる。(5章:124ページ)
● 「差別は(中略)人種や肌の色を理由に、だれかを社会の構成員として受け入れないとするとき、その人が感じる侮蔑感、挫折感、羞恥心の問題である」。すなわち、人間の尊厳に関する問題なのである。(6章:143ページ)
● 民主主義が実現するには、基本的な前提として、社会のすべての構成員が平等な関係をもち、対等な立場で討論できなければならない。(中略)私たちは、同じ空間を共有しながら生きていくための倫理について考えなければならない。そうしてこそ、隠蔽された不平等を前提として平等を享受していた、古代ギリシアのポリスとは違う、真の民主主義をつくることができるだろう。(7章:162ページ)
● 正義とは、真に批判する相手がだれなのかを知ることである。だれが、または何が変わるべきなのかを正確に知る必要があるということだ。世界はまだ十分に正義に満ちあふれているわけではなく、社会の不正義を訴える人々の話は、依然として有効である。(8章:182ページ)
● 平等に向けた運動に参加できるのはだれだろうか。全員の賛同を期待することはできないだろう。歴史上、何の抵抗もなく達成された平等はなかったからだ。しかし同度に、一部の人々は、自分の立場や地位に関係なく、正義の側に立ち、マイノリティと連帯した。結局は、私たちだれもがマイノリティであり、「私たちはつながるほどに強くなる」という精神が世の中を変化させてきた。あなたがいる場所で、あなたはどんな選択をしたいだろうか。(9章:202~203ページ)
● だれもが平等を望んでいるが、善良な心だけでは平等を実現することはできない。不平等な世界で「悪意なき差別主義者」にならないためには、慣れ親しんだ秩序の向こうの世界を想像しなければならない。そういう意味で、差別禁止法の制定は、私たちがどのような社会をつくりたいかを示す象徴であり宣言なのだ。(10章:219ページ)
● 閉鎖されたひとつの集団としての「私たち」ではなく、数多くの「私たち」たちが交差して出会う、連帯の関係としての「私たち」も可能ではないだろうか。だれかに近づき、「線を踏んだでしょう」「出て行け!」と叫ぶのではなく、みんなを歓迎し、一緒に生きる、開かれた共同体としての「私たち」をつくりたい。(エピローグ:224ページ)
〇[2]は、「差別」を「心の問題」として捉え、善意の「思いやり」や「優しさ」で解決しようとする「思いやり」万能主義からの脱却を説く。そして、権利保障と差別を解消・禁止するための法制度の整備や施策の推進の必要性と重要性について論究する。そこで取りあげる差別は、主に女性差別と性的少数者差別である。
〇神谷はこういう。「思いやり」はあくまでも、個人の資質や感情に基づくものである。その「思いやり」に基づかなくても人は守られる、というのが「人権」の考え方である。差別のひとつに「アンコンシャスバイアス」(無意識の偏見)があり、「思いやり」と同じ匂いがするフレーズに、現状の取り組みを是認する(新規性がない)意味の「周知を徹底する」や、他人事の象徴としての「何も気にしない」といったものがある。セクシュアルハラスメントに関して、「防止」法制(規定)はあるが「禁止」法制(規定)はない。また、男女の雇用機会の均等に関しても差別は禁止されているが、罰則の規定はない。ともに実効性が低く、「思いやり」に留まっているのが日本の現状である。
〇そこで神谷にあっては、制度や法律を整備することによって、一定の水準で権利を担保することが重要である。差別の防止・解消や禁止についての「啓発」の制度化や、差別禁止の法制度の導入が必要であり、「これが一番の近道」(93ページ)となる。
〇[2]における神谷の主張は要するに、「差別は権利の問題であり、思いやりは人権尊重の理念を持たない」、「差別は思いやりではなく、制度で解決すべきである」というものである。その言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換)。
● 人権問題、特に「ジェンダー」や「LGBTQ」の問題を考えたり語ったりする際に、突然「思いやり」が幅を利かせ始め、万能の力を持つかのように信奉されてしまう。(中略)何をするにしても「思いやり」が靄(もや)のように現れ、実際には何も進んでいないにもかかわらず、何かを「やった感」「やっている感」だけが残るというのが長年の日本の状況(である)。(4~5ページ)
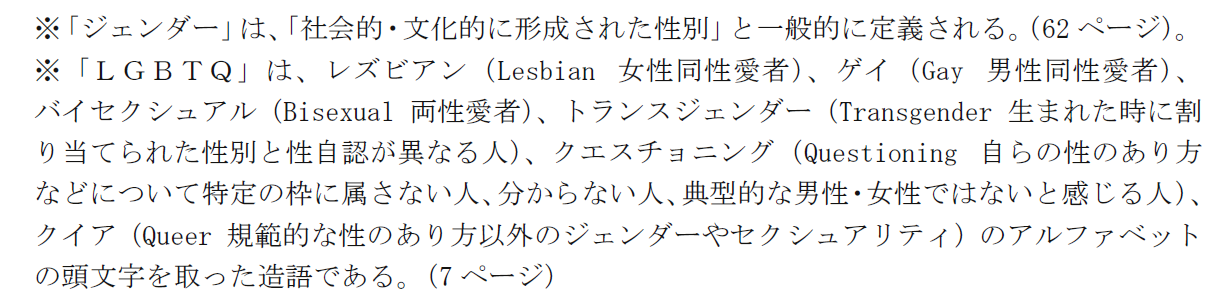
● 「思いやり」は、個々人の「気に入る」「気に入らない」といった恣意性に左右されやすいものであり、不具合が起きてしまうものである。思いやりも人それぞれ、ということになると、そこで保障されることも人それぞれであろう。そんな普遍性のないものを「人権」と呼べるだろうか。(49ページ)
● ジェンダー規範からの逸脱は、排除を引き起こし、差別やハラスメント、仲間外れや無視といった事象が、逸脱したマイノリティ(女性、性的マイノリティはもちろん、これらの人たちに限らない)自ら、自分を制約する方向に力を加える。それが差別に対する異議申し立てを封印し、「男らしさ」を優遇する。だから、性的マイノリティに対する個別の差別や暴力根絶とともに、大元の性差別撤廃(女性差別を含むが、より広い意味で)にも力を入れるべきだ、ということである。(112ページ)
● 思いやり「だけ」では、多岐にわたる複雑な問題を解決することはできない。仮に思いやる心があったとして、それを持続的に、習慣的に、社会的な背景や構造にアプローチできる何らかの方法で実行しない限り、社会はもとより、身の回りを変えることも難しいが実情である。/関心のない人も含めて、より多くの人がジェンダーの領域に一定程度の水準まで取り組みを進めるためには、オーダーメイド的な(職人的なと言ってもいいかもしれません)取り組みだけではなく、ある種の「量産型」的な、誰にでも取り組め、扱うことのできる手法(研修・講習による定期的な周知・啓発:筆者)も、同時に求められている。(133~134ページ)
● 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(略称「人権教育・啓発推進法」。2000年12 月 公布・施行)は、人権一般を扱うほとんど唯一の法律であるが、教育・啓発を実施するための行政の体制整備以外のことは規定がなく、実際の権利の保障には至っていないという致命的な課題がある。(52ページ)/この法制度に基づく取り組みは、「心がけとか思いやりとか、私人間の関係性のレベルにとどまっている」という指摘もある。(50ページ)
● イギリスでは、「性別」や「障がい」など各分野の差別禁止法を統合したものを、通称「平等法」と呼び、両者はほぼ同じ内容として見られているようである。イギリスの場合、各分野の差別禁止法を統合した「平等法」のほうが、差別禁止法よりも積極的に平等を目指すために「公的機関の平等義務」などを規定しているとの指摘もある。(187ページ)
〇以上の言説を「福祉教育」に引き寄せて一言する(問う)。福祉教育(実践と研究)はこれまで、ジェンダーやLGBTQの問題について見て見ぬ振りを決め込んできたのではないか。また、福祉教育(実践と研究)はどれほどに、外国籍の子どもだけでなく外国人労働者や移民などの人権や差別について体系的に言及してきたか。厳しい差別や排除の現場に立ってその実態から気づき・学びを深める教育(体験学習)に積極的に取り組んできたか。差別の背景や構成要素(直接差別、間接差別、合理的配慮の否定など)について加害者と被害者を構造化して考えてきたか。不公正な能力主義や不合理な選別主義に対峙する批判的な福祉・教育理論の構築や実践に関心を払ってきたか。社会通念の変革とともに、差別を禁止・根絶するための政策の立案や関係法律・制度の改善・整備について思考し行動(運動)を起こしてきたか。そして何よりも、「思いやり」はこれらについての「思考停止」を促してきたのではないか。自責の念に駆られる。
【初出】
<雑感>(168)阪野 貢/「差別」再考―「差別はたいてい悪意のない人がする」「差別は思いやりでは解決しない」のワンポイントメモ―/2023年2月4日/本文
12 「共感」の功罪
「共感」の功罪【その1】
<文献>
(1)山竹伸二『共感の正体―つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか―』河出書房新社、2022年3月、以下[1]。
〇「共感論」について活発な議論が展開されるなかでこんにち、「反共感論」の主張が少なからずみられる。[1]において山竹伸二はいう。「共感は本当に相互理解と協調、平和をもたらす自然の恩恵なのだろうか? それとも、不安や自由の喪失、憎しみ、差別をもたらす、悪魔のささやきなのか‥‥‥?」(21~22ページ)。「共感が生み出す助け合いが集団を強化し、文化を築く礎になったこと、その一方で、共感による集団の排他性が紛争や差別、迫害を生んできた歴史がある」(24ページ)。
〇山竹は、多角的な視点に立って、また科学的・哲学的な考察を通して「共感」の本質を解明しようとする。とともに、心のケアの領域や日常の対人関係における共感の有効性や応用可能性を明らかにし、共生社会における共感の重要性を指摘する。山竹は説く。「共感のメリットはリスクを大きく超える可能性がある」(204ページ)。「大事なのは共感に頼らないことではなく、共感のデメリットを減らし、よりよい形で共感を活かせるようにすること」(205ページ)である。
〇[1]で注目すべきポイントは、現象学(自分の意識・主観に現われていることを出発点にして、誰もが共通して了解できる意味(「本質」)を解明するための哲学的思考法)の観点から共感の本質にアプローチし、その問い直しを試みるところにある。山竹はそれを次のように整理する(7. 8. 以外の丸括弧内の解説は別頁より引用。126~129ページ)。
- 共感が生じる経験は、①「情動的共感」(相手と同じ感情であると感じる共感)と②「認知的共感」(相手と同じ考え方、感受性、価値観であると感じる共感)の2つに分けられる。
- 共感の質は心の発達、特に自己の確立と認知の発達にともなって変化する。
- 他者の共感によって得られる自己了解(自分の感情に対する気づき・自覚)と「存在の承認」(「ありのままの自分」が受け容れられていること)。
- 心理的距離、空間的距離の近い人間ほど共感が生じやすい。
- 共感力(相手の考えや気持ちを察することができ、その気持ちに寄り添うことができる力)には個人差がある。
- 共感は感情の共有であり、自己了解と同時に他者了解(他者の感情に対する気づき・自覚)が生じている。
- 共感は他者理解をとおして他者のためになる行動(利他的行為)を生む。
- 共感は喜びだけでなく、苦しみを生む場合もある(共感的苦悩)。
- 共感はお互いを理解し、協力し合う基盤となり、文化・社会を形成する。
〇以上の「共感の本質」(「共感の原理」)に続いて山竹は、「共感の功罪」について次のように整理する(130ページ)。
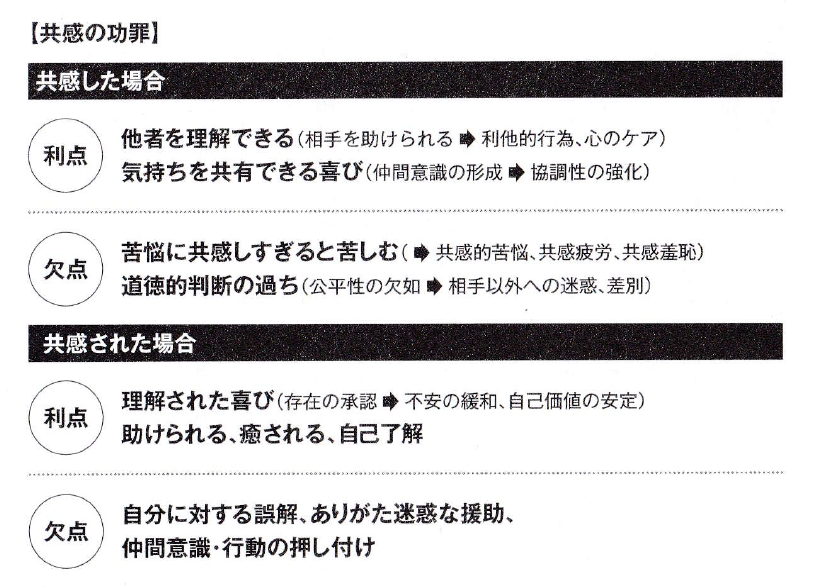
〇ここで、[1]のうちから、「共感」をめぐる論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
共感と利他的行為
共感という経験は対人関係における感情共有の確信であり、共感が生じると多くの場合、相手に対して親和的な感情(親しみ)が生じ、他人事ではないと感じられる。/この時、自己了解(自己の感情への気づき)と同時に、他者の感情了解が生じている。自己了解が「自分がどうしたいのか」という欲望を告げ知らせる以上、共感は「他者がどうしてほしいのか」を理解し、相手が望む行為の選択を、つまり利他的行為を可能にするのである。/もちろん、自分の感情と相手の感情が同じである、という保証はない。だが、私たちは共感を手がかりにして、相手に気持ちや望みを言葉で確認することができるし、それによって適切な対応を取ろうとする。そうやって経験を何度も積み重ねるほど、次第に的を外すことなく相手の感情を理解できるようになり、適切な対応が可能になる。/こうした理解力を培うには、言葉と想像力、推論する理性の力を身につけることが必要である。(110ページ)
排他的共感と差別
共感はすべてにおいてよいことが起きるわけではない。/誰かの悲しみや苦しみに共感し、助けたいと思う場合でも、必ずしもよい結果、正しい行動につながるとは限らない。共感から、目の前にいる人を手助けしてしまい、結果的に大勢の人を苦しめたり、困らせてしまうこともある。助けたつもりでいても、相手にとっては迷惑だったり、かえって悪い結果を招く場合も少なくない。/また、共感は憎悪や怒りのような感情にも共振するため、憎しみや怒りを増幅させる危険性がある。/仲間への共感から、仲間以外の人々を敵視したり、憎悪や軽蔑の眼差しを向けたりすることを、「排他的共感」と呼ぶことにしよう。/共感は文化を形成し、集団の結束を強めるのだが、それは半面、共感できない文化や自分の所属する集団以外の人々に対して、排除する傾向を生みやすい。共感による民族や国との一体感は、外国への差別意識、敵対意識につながりやすいのだ。繰り返される戦争、少数民族への迫害、異質な文化への差別などは、排他的共感が拍車をかけている。(116~117ページ)
協調的共感と共同性意識
多様な価値観を学び、様々な立場の人の身になって考えることで、偏った行動ではなく、より公正で適切な共感と利他的行為ができるようになる。/多様な価値観に寛容になるには、人間は集団の属性や価値観によらず、存在そのものが尊重されるべきだ、という感覚が必要になる。/この感覚を養うものこそ、親密な人々による共感なのだ。それは「ありのままの自分」が受容される経験、無条件の承認を感じる経験であり、だからこそ、「ありのままの他者」を受け容れ、共感できるようになるのである。/こうした対応を各々の人間ができるようになれば、他者との間に良好な関係性が形成され、よりよい協調が生まれ、お互いに助け合えるような社会を築くことができる。異なる考え方や価値観の人々の間にも、差異を認め合いながらも共感できるものを見出せるようになる。私はこれを「協調的共感」と呼び、共感の成熟したものとして捉えておきたい。(123~124ページ)/共感は人間同士の心のつながりを感じさせ、同じ人間であるという意識、共に生きているという意識をもたらすのだ。/しかし、この共同性の意識においても、適度な距離感、公正な判断力がなければ、容易に集団心理に呑み込まれてしまうだろう。/したがって、共感が人間の道徳性や共同性の意識において重要だとしても、そこに潜んでいるリスクを十分に自覚し、その対処法を考えなければならない。排他的共感に陥らず、協調的共感に至る道を考える必要があるのだ。(124~125ページ)
共感のリスクとその回避
共感には様々なリスクが付きまとっている。/まず第1に、共感しやすい人は、相手の感情に巻き込まれ、自分自身の感情を制御することが難しくなりやすい。/第2に、思い込みの強い人、自己中心的な人の場合、共感は相手と自分を同一視し、相手の他者性、固有性を無視してしまう傾向がある。/そして第3に、自分の所属集団、立場、価値観を過剰評価している人が共感すると、自分が共感できない人々に対して無関心になったり、敵視する傾向がある。/こうした共感のリスクを回避するためには、自己了解ができていること、感情の制御ができることが必要になる。自己了解の力があり、感情のコントロールができる人は、過度に相手の感情に巻き込まれたりしないし、相手と自分を同一視したりもしない。また、多様性に寛容で、他者との差異や他者性を認められる人は、排他的にもなりにくい。だから自分とは経験も立場も異なる相手であっても、先入観なしに対話し、相手との差異を認めつつも、自分と共通するものを見出すことができる。そうやって相手の感情に近づき、共感する可能性が高いのである。(166~167ページ)
良心と共感
「良心」は善悪を判断し、「人として正しくありたい」という思いが含まれているが、この判断の基準は内面にある価値観や行動規範、人としての理想などである。それは多くの人が認める価値観や社会規範とほぼ重なるため、共感や同情に公平性、公正さをもたらしている。しかし、そうした個人の内面にある価値観や行動規範は、何らかの状況で取り込まれ、身につけたはずなので、成長にともなって変化し、良心も変わってくることになる。(184~185ページ)/完全に「他者のため」という動機だけで良心が生じるわけではない。他者に承認されたい、他者と共に生きたい、という「自己のため」の動機も当然あるだろう。そうでなければ、自己犠牲を美徳と考えるような偏った義務論になりかねない。(188ページ)/共感によって他者の苦しみを知れば、自己の欲望を超えて、心から他者を助けたいという思いも強くなる。承認欲望と救済欲望が重なりあい、「自己のため」の行為が「他者のため」の行為になるのだ。そして共感の経験を繰り返し、理性的な思考が深まるにつれ、多様な他者の身になって考える力もついてくる。/こうして、成熟した良心は自己の欲望を自覚した上で、他者を心から助けたいと感じ、より普遍性のある判断を求めるようになるのである。(189~190ページ)
〇山竹にあっては、現代社会は、異なった文化や立場、多世代の「多様な人々が交流するようになり、共感が拡大する可能性のある時代である」(201ページ)。その一方で、現代社会では「絶対的な価値基準が見失われ、どうすれば周囲に認められるのか、自分の価値を確信できるのか、という承認不安が蔓延している」(202ページ)。そこで、上述の「共感の本質」を認識し、「心のケアの原理」に基づいて子育て、教育を実践すれば、「共感は私たちの未来を切り開く上で、とても重要な役割をはたすはず」(202ページ)である。「共感」への期待と展望である。山竹はいう。「楽観的と思う人もいるかもしれないが、私はそうした未来の可能性を信じたい」(205ページ)。
〇「まちづくりと市民福祉教育」(とりわけ学校福祉教育)においてはこれまで、抽象的な理念やひとつのスローガンとして「共感」が声高に叫ばれてきた感なきにしも非ずである。「共感の本質」についての理解・認識と、それに裏付けられた共感力を高めるための取り組みや教育プログラムの開発を如何に進めるかが問われよう。例によって唐突であるが、指摘しておきたい。
〇なお、上記の「心のケアの原理」とは、「共感は『ありのままの自分』が受け容れられている(認められている)という実感を与えることで、相手の不安を緩和する。また、共感によって相手の苦しみの根底にある感情を理解し、それを相手に伝えることで、相手に自己了解を促すことができる。すると、相手は自分を見つめなおすことができるようになり、考え方を修正したり、自分がどうしたいのか、どうすべきなのか、納得のいく判断ができるようになる」(194ページ)ということを指す。
【初出】
<雑感>(185)阪野 貢/「共感」再考:共感のメリットとデメリット ―山竹伸二著『共感の正体』のワンポイントメモ―/2023年8月23日/本文
「共感」の功罪【その2】
「共感には善玉と悪玉がある」
「共感は道徳的指針としては不適切である」
「私たちは(共感の時代ではなく)理性の時代に生きている」(ブルーム)
<文献>
(1)ポール・ブルーム、高橋洋訳『反共感論―社会はいかに判断を誤るか―』白揚社、2018年2月、以下[1]。
(2)永井陽右『共感という病―いきすぎた同調圧力とどう向き合うべきか?―』かんき出版、2021年7月、以下[2]。
〇筆者(阪野)は、1989(昭和64)年1月7日(土)と1989(平成元)年1月8日(日)は韓国・ソウルにいた。1月5日~10日の5泊6日、学生を引率しての研修旅行であった。ソウルの学生たちと「アリラン」(民謡)を合唱する機会にめぐまれた。また、7日から9日までのいずれかに、臨津江(イムジンガン)を渡って38度線・板門店を訪ねている。「イムジン河 水清く とうとうと流る‥‥‥」ではじまるザ・フォーク・クルセダーズ(学生フォークグループ)の「イムジン河」を思い出していた。
〇2019(平成31)年4月30日(火)と2019(令和元)年5月1日(水)は鹿児島にいた。4月28日~5月2日の4泊5日、福岡(大宰府天満宮と九州国立博物館)と鹿児島への観光旅行である。4月30日には川辺郡知覧町(現・南九州市)にある知覧特攻平和会館を訪ねた。そこに展示されている遺影と遺書・遺品などに圧倒され、多くの観光客がいるなかで筆者は、ただ立ち尽くすだけだった。何通かの遺書を読んだとき、脳裏をかすめたのは「検閲」「虚飾」そして「殺された」(「国家による殺人」)の三つの言葉である。
〇特攻隊員の全戦死者は1036人、そのうち知覧基地から出撃した者は402名。また、戦死した朝鮮人特攻隊員は17人、知覧特攻平和会館に祀(まつ)られている者は11人である。そのうちのひとりに、卓庚鉉(タク・キョンヒョン)がいる。「アリラン特攻」卓庚鉉と「特攻の母」鳥濱(とりはま)トメとの感動の物語は有名である。卓は、その前日に鳥濱が経営する富屋食堂で「アリラン」を歌い、1945(昭和20)年5月11日に出撃する。24歳の若さであった。「アリラン アリラン アラリヨ アリラン ゴゲロ ノモガンダ(アリラン アリラン アラリよ アリラン峠を越えて行く)‥‥‥」。
〇朝鮮人特攻隊員に関する最近の論文に、権学俊(クオン・ハクジュン)「韓国における朝鮮人特攻隊員像の変容」『立命館産業社会論集』第52巻第4号、立命館大学産業社会学会、2017年3月、67~81ページ、がある。そこに次の叙述がある。
植民地支配された朝鮮人青年が、自らを支配する国のために死を選択した、また、差別を受けた朝鮮人青年を、基地があった町で食堂を営んでいた日本人女性が自分の子どものように世話をし、その青年が出撃に前夜に朝鮮のアリランを歌ったという物語は、日本の都合に合わせた解釈がなされ、「悲劇の主人公」として同情を集めるだけでなく、一部からは「朝鮮人であるのに日本のために命を捧げた人物」と賞賛され、「アリラン特攻」としての物語性が評価された一方で、アリランを歌う以外の彼の心の声は全く聞こえてこなかった。(75ページ)
〇17人の朝鮮人特攻隊員は、植民地支配と民族的差別の被害者である。権はいう。朝鮮人「特攻隊員は日本のために死んだ『対日協力者』であり、民族の『裏切り者』だという認識・見方から脱することは非常に難しい」(76ページ)。「彼らの魂は依然として、軍神として賞賛された日本でも、祖国である韓国でも受け入れられずに、日韓の失われた歴史の空白の狭間でひたすら漂流している」(78ページ)。この一節に触れたとき筆者は、目頭を押さえる人がいた知覧特攻平和会館の時空ではあまり感じなかった怒りや悲しみを覚える。とともに、歴史的・理性的思考の重要性を再認識する。そして、30年前の平成元年早々に、ソウルで合唱した「アリラン」の哀愁や板門店の軍事停戦委員会本会議場の緊張を思い出した。なお、筆者には戦死した伯父(おじ)がいる。その長男(筆者の従兄)は70年以上もたったいまも、戦争の呪縛や国家不信から抜け出すことができないでいる。悲惨である。
〇こうした感情やわずかな理性をきっかけに、「積読」(つんどく)本のなかにあった、ポール・ブルーム(Paul Bloom、アメリカ・イェール大学心理学教授)著/高橋洋訳『反共感論―社会はいかに判断を誤るか―』(白揚社、2018年2月。以下[1])を読むことにした。それはまた、いま社会的風潮として(福祉教育の世界において)「共感」や「共生」、とくにその「心」が強調されるなかで、いかにして「感情」(「共感」)と「理性」のバランスをとるかが問われている、という認識に基づいてもいる。さらに一言すれば、筆者は、「共感」と「理性」にはそれぞれ限界があり、その両者の漸進的な共働によってよりよい“まちづくり”を進めることができる(進めなければならない)、と考えている。
〇ブルームによると、「共感」(empathy)は「情動的共感」と「認知的共感」に分けられる。「情動的共感」は、「他者が感じていると思しきことを自分でも感じること」すなわち「他者の経験を経験する」(10ページ)という意味での共感(感情的な働き)である。「認知的共感」は、「他者の心のなかで起こっている事象を、感情を挟まずに評価する能力に結びつけてとらえる」(25ページ)という意味での共感(理性的な働き)である。ブルームは、前者の情動的共感に反対し、後者の認知的共感を評価する。「共感には善玉と悪玉がある」(20ページ)。「共感(情動的共感)は愚かな判断を導き、無関心や残虐な行為を動機づけることも多い」(9ページ)。「共感は道徳的指針としては不適切である」(9ページ)。「私たちは(共感の時代ではなく)理性の時代に生きている」(19ページ)、別言すれば“他者を思いやる善き人になりたいのなら、あるいは世界をもっとよい場所にしたいのなら、理性を行使すること(理性に基づく判断や行動)が重要である”(9ページ、第6章)、などがブルームの主張である。
〇ブルームは、[1]の要点について次のように簡潔に述べている。
共感とは、スポットライトのごとく今ここにいる特定の人々に焦点を絞る。だから私たちは身内を優先して気づかうのだ。その一方、共感は私たちを、自己の行動の長期的な影響に無関心になるよう誘導し、共感の対象にならない人々、なり得ない人々の苦難に対して盲目にする。つまり共感は偏向しており、郷党性(きょうとうせい。同郷のよしみ)や人種差別をもたらす。また近視眼的で、短期的には状況を改善したとしても、将来悲劇的な結果を招く場合がある。さらに言えば数的感覚を欠き、多数より一人を優先する。かくして暴力の引き金になる。身内に対する共感は、戦争の肯定、他者に向けられた残虐性の触発などの強力な要因になる。人間関係を損(そこ)ない、心を消耗させ、親切心や愛情を減退させる。(17ページ)
〇この「要点」の理解を深めるために、ブルームの「反共感論」の論点や言説について、その一部をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
共感のスポットライト的な特質――共感はその射程が限定的であり、数的感覚を欠いている
●私たち人間にとって、共感はスポットライトのようなものである。つまり、焦点が絞られ、自分が大切に思っている人々は明るく照らし出し、見知らぬ人々や、自分とは違う人々や、脅威を感じる人々はほとんど照らし出さないスポットライトなのだ。
共感は、大勢の人々が関わる問題に直面すると黙して語らず、共感は大勢よりたった一人を重視するよう私たちを仕向ける。
共感は、特定の個人ではなく統計的に見出される結果に対しては反応を示さない。(45ページ)
スターリンは、「一人の死は悲劇的だが、100万人の死は統計的だ」と述べたと言われている。またマザー・テレサは、「大衆を見ても、私は決して行動しないでしょう。でも、一人を見れば行動します」と言った。道徳的判断において数の重要性が認められるのなら、それは理性のゆえであって感情のゆえではない。(112ページ)
●共感を含めた他者に対する反応は、既存の偏見、嗜好(しこう)、判断を反映するものである。この事実は、共感が無条件に私たちを道徳的にするわけではないことを示す。(88ページ)
●スポットライトの問題の一つは、焦点の狭さだ。またもう一つの問題は、向けた場所しか照らし出さないことである。だからバイアス(偏った見方)の影響を受けやすい。(112~113ページ)
●スポットライト的な性質のゆえに、共感はバイアスの影響を受けやすい。また、焦点の狭さ、特定性、数的感覚の欠如という特質を持つがゆえに、自分の注意を惹くもの、人種の好みなどの影響をつねに受けている。私たちが少なくともある程度の公平さや公正さを保てるのは、共感の作用から免(まぬか)れ、規則や原理、あるいは費用対効果の計算に依拠した場合に限られる。(119ページ)
共感と思いやり――共感と思いやりは独立しており、ときには対立することさえある
●心理学者のヴィッキー・ヘルゲソンとハイディ・フリッツは、「他者に過剰に配慮し、自分のニーズより他者のニーズを優先する」ことを「過度の共同性」(unmitigated communion)と呼んだ。(165ページ)
「共同性」(過度なタイプではなく適切な共同性)が高い人と、「過度の共同性」が高い人の違いはどこにあるのか? どちらのタイプの人々も、他者を気づかう。しかし「共同性」が、配慮や思いやりとも呼べるものに対応するのに対し、「過度の共同性」は共感、もっと正確に言えば共感的苦痛(empathic distress)、つまり他者の苦しみに苦しむことにより強く結びついている。
私は、「過度の共同性」の高さが、共感力の高さとまったく同じであるとは思っていない。とはいえそれらのいずれも、他者との関わりという点では、同じ根本的な脆弱性をもたらす。自身の生活を阻害する過剰な苦痛を本人に引き起こす。(167~168ページ)
●共感と思いやり(compassion)の区別は、非常に重要である。(中略)あるレビュー論文のなかで、神経科学者のタニア・シンガーと認知科学者のオルガ・クリメッキは、この区別について次のように述べている。「共感とは対照的に、思いやりは他者の苦しみの共有を意味しない。そうではなく、それは他者に対する温かさ、配慮、気づかい、そして他者の福祉を向上させようとする強い動機によって特徴づけられる。思いやりは他者に向けられた感情であり、他者とともに感じることではない」。(170ページ)
「感情的な共感は、思いやりの前駆である」「最初に情動的共感を覚えない限り、思いやりを感じることはできない」と主張される。
私たちは一般に、日常生活で情動的共感を特に覚えなくても他者を気づかったり手助けしたりしていることを考えてれば、これらの主張は理解しがたい。(中略)思いやりや親切心は共感から独立しているばかりでなく、それと対立することさえあり、共感感情を抑えたほうが人はより適切に振舞える場合がある。(174ページ)
暴力・残虐性と共感――暴力と残虐性の要因は必ずしも「共感の欠如」ではない
●暴力行為にはさまざまな原因があり、私は犠牲者の苦難に対する共感が、それ以外の原因より重要であると言い張るつもりはない。しかし共感は暴力と無関係ではない。ヒトラーがポーランドに侵攻したとき、彼を支持したドイツ人は、ポーランド人による同胞のドイツ人の殺害や虐待のストーリーに激怒していた。(234ページ)
私は平和主義者ではない。無実の人々の苦難は、アメリカが第二次世界大戦に参戦したときのように、場合によっては軍事介入を正当化すると、私は考えている。それでもやはり、共感は暴力行為を選好する方向へと、あまりにも強く人々を傾(かたむ)かせると言わざるを得ない。共感は私たちが戦争の恩恵を考慮するよう仕向ける。それを通じて被害者のために復讐し、危機に直面している人々を救い出させようとする。(235ページ)
感じることと考えること――「共感」に代わる道徳的指針・行動基準は「理性」である
●情動の本性が過大評価されている。私たちは直観力を備える一方、それを克服する能力(理性的熟慮の能力)を持つ。道徳問題を含めものごとを考え抜き、意外な結論を引き出すことができるのだ。ここにこそ人間の真の価値が存在する。この能力は、人間を人間たらしめ、互いに適正に振舞い合えるよう私たちを導いてくれる。そして苦難が少なく幸福に満ちた社会の実現を可能にする。(14~15ページ)
善き行ないには、あらゆる種類の動機が存在する。それには、より包括的な関心、思いやりなどがある。(中略)また、名声に対する関心、怒りの感情、プライド、罪悪感、信仰、世俗的な信念体系などがある。私たちには、正しい行ないを動機づける要因として、あまりにも性急に共感をあげる傾向があるようだ。(126~127ページ)
善き人であるためには、他者への気づかい、すなわち他者の苦しみを緩和し、世界をよりよい場所にしようとする心構えと、何が最善かを見極められる理性的な能力の組み合わせが必要である。(127ページ)
●「私たちは共感をはじめとする直感の影響を受けても、その奴隷ではない」。開戦するか否かを決定する際に費用対効果分析に依存する、あるいは自分の子どもに愛情を注ぎ、赤の他人には特に何も感じなくても、彼らの命も自分の子どもの命と同じく重要であることを認識するなど、私たちはもっとよいことができる。(258ページ)
〇[1]の原題は、“Against Empathy”(2016)である。一瞬ギョッとするが、ブルームは、“Empathy Is Not Everything”(「共感がすべてではない」)、“Empathy Plus Reason Make a Great Combination”(「共感と理性は偉大な組み合わせをなす」)などといったタイトルでも構わなかった、という。「自立」やそのための「自己決定」「自己責任」が強調される現代社会において、“共感の欠如”、したがって“共感性の強化”“共感力の育成”こそが最大の課題である、と言われる。それは、「共感」が無条件に肯定されていることにもよる。しかし、ことはそれほど単純ではない。「私は共感に反対する」というブルームの「具体的な見解に賛成するにせよ反対するにせよ、情動的に反応するのではなく、それについて理性的に考察し皆で議論することが肝要である」(「訳者あとがき」302ページ)。まさにそれが本書でブルームが説くところである。ブルームの「反共感論は理性の存在を前提とする」(258ページ)。留意したい。
補遺
〇[2]の永井にあっては、「共感」とは「他者の感情経験に直面した人が、認知的および感情的に反応すること」。その「反応に至るまでのプロセス」(33ページ)、である。永井はいう。「共感は、全員ではなく特定の誰かしか照らさない『スポットライト的性質』と、自分にとって照らすべきだと思えた相手しか照らさない『指向性』を持つ」(17ページ)。「共感とは誰かの困難に対してではなく、困難に陥っている自分側(同じグループの仲間)の誰かに作用している。まさに共感は差別主義者なのである」(18ページ)。「共感は一般的に、理性的な『認知的共感』と感情的な『情動的共感』の2つに、機能的に分けられている」(28ページ)。
〇永井は続ける。「多様性とは、自分にとって都合の悪い人の存在を認めることである。『多様性を受け入れることは難しい』という心構えを持つべきである」(161、162ページ)。「共感できない・共感されにくい人をなおざりにしないために、共感に代わるものが必要となる。共感ではなく、地に足のついたリアルな、実体の伴った、権利に対する理性的な眼差し(理性的に、自分の権利と同時に他者の権利を見つめること)こそが、憎悪が渦巻く現代の世界を良くする鍵である」(167~169ページ)。
〇要するに永井にあっては、「共感」とそれに代わるものとして、「理性」と「人権」、人権に対する理性的な理解と反応が重要である。「感情に任せるのではなく、共感の良いところをうまく使いながらも、同時に理性も働かせてその手綱(たづな)をしっかりと持ち、取り残されている人がいないか、対立や分断をどう乗り越えることができるか、などを常々考えることが社会と世界を良くしていくことに繋がる」(180ページ)のである。
〇なお、[2]には、永井と内田樹(うちだ・たつる、思想家)との対談が収録されている。そこで内田はいう。いまの日本社会は、「共感過剰」な社会になっている。共感できる人間だけで固まって、同質的な、集合的共感のようなものを作って、外部の人とのコミュニケーションができなくなってきている。共感や理解をベースにして人間関係を構築するのは危険である。それよりは、「共感も理解もできないけど、目の前に困ってる人がいたらとにかく助ける」(「惻隠の情」)というルールの方が汎用性が高いし、間違いが少ない。惻隠の情が発動するためには、「自分から見て弱者である」こと、「自分の力の範囲内で救うことができると思える」ことの2つの条件がある(191、218、222ページ要約)。参考までに付記しておくことにする。
【初出】
<雑感>(81)阪野 貢/共感≠善:共感は道徳的指針としては不適切である―ポール・ブルーム著『反共感論』読後メモ―/2019年5月15日/本文
13 「利他」の学問
<文献>
(1)伊藤亜紗編、・中島岳志・若松英輔・國分功一郎・磯崎憲一郎『「利他」とは何か』集英社新書、2021年3月、以下[1]。
(2)中島岳志『思いがけず利他』ミシマ社、2021年10月、以下[2]。
(3)若松英輔『はじめての利他学』NHK出版、2022年5月、以下[3]。
〇伊藤亜紗は美学者、中島岳志は政治学者、若松英輔は批評家・随筆家、國分功一郎は哲学者、そして磯崎憲一郎は小説家である。分野も背景も異なるこの5名の研究者が、東京工業大学の「未来の人類研究センター」(2020年2月設立)のメンバーとして取り組んでいるのが、「利他」をめぐる問題である。[1]は、「全員ではぐくんできた利他をめぐる思考の、5通りの変奏」であり、いまだその「出発点であり、思考の『種』にすぎない」という(8ページ)。
〇[1]におけるひとつのキーワードは、「うつわ」――「うつわになること」「『うつわ』的利他」である。伊藤は次のようにいう。
利他とは「うつわ」のようなものではないか。相手のために何かをしているときであっても、自分で立てた計画に固執せず、常に相手が入り込めるような余白を持っていること。それは同時に、自分が変わる可能性としての余白でもある。この何もない余白が利他であるとするならば、それはまさにさまざまな料理や品物をうけとめ、その可能性を引き出すうつわのようである。(58ページ。語尾変換)
〇人間は「うつわ」のような存在として生きることによって、「利他」が宿る。こうした人間観を生み出す伊藤の言説は、こうである。利他的な行動には本質的に、「これをしてあげたら相手にとって利になるだろう」という、「私の思い」が含まれている。その「私の思い」は私の思い込みでしかなく、「自分の(利他的な)行為の結果はコントロールできない」、すなわち見返りは期待できない(「利他の不確実性」)。自分の利他的な行為は、相手は「喜ぶはずだ」「喜ぶべきだ」という押しつけが始まるとき、人は利他を自己犠牲と捉えており、その見返りを相手に求めていることになる。その点において、利他的な「思い」や「行為」は、相手をコントロールしたり、支配することにつながる危険をはらんでいる。そうならないためには、相手を「信頼」してその自律性を尊重し、相手の言葉や反応を「聞く」ことを通じて相手の潜在的な可能性を引き出すこと、すなわち相手の力を信じることが必要不可欠となる。それは、「こちらには見えていない部分がこの人にはあるんだ」という距離と敬意を持って、相手を気づかうこと(「ケア」)である。この他者への気づかい、すなわち「ケアとしての利他」は、相手の隠れた可能性を引き出すこと(「他者の発見」)になり、それは同時に自分が変わること(「自分の変化」)になる。そのためには、こちらから善意を押しつけるのではなく、相手を信頼し、利他の結果の可能性や意外性を受け入れる、うつわのような「余白」を持つことが必要となる。この自由な余白、スペースは、とくに複数の人が「ともにいる」ことをかなえる場面で重要な意味を持つ(50~56、59ページ)。
〇筆者の手もとに、中島岳志著『思いがけず利他』(ミシマ社、2021年10月。以下[2])という本がある。中島は[1]の著者のひとりである。[2]において中島は、「利他の本質に『思いがけなさ』ということがある。利他は人間の意思を超えたものとして存在している」(6ページ)と説く。具体的にはこうである。「利他は自己を超えた力の働きによって動き出す(「縁起による業」:私はさまざまな縁によって(縁起的現象として)存在している)。利他はオートマティカルなもの(意思を超えたもの)。利他はやって来るもの(利他の与格性)。利他は受け手によって起動する(利他は事後的)。そして、利他の根底には偶然性の問題がある(利他の偶然性)」(174ページ。括弧内は筆者)。
〇[2]のうちから、中島の言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「共感」が利他的行為の条件となったとき、「別の規範」が起動し「共感される人間」になることが求められる
通常、利他的行為の源泉は、「共感」にあると思われている。/他者への共感、そして贈与(利他)。この両者のつながりは非常に重要である。(21ページ)/しかし、共感が利他的行為の条件となったとき、例えば重い障害のある人たちのような日常的に他者からの援助・ケアが必要な人は、「共感されるような人間でなければ、助けてもらえない」といった思いに駆(か)られる。/他者に自分の苦境を伝えることが苦手な人、笑顔を作ることが苦手な人、人付き合いが苦手な人。人間は多様で、複雑である。だから「共感」を得るための言動を強(し)いられると、そのことがプレッシャーとなり、精神的に苦しくなる人は大勢いる。/そもそも「共感される人間」にならなければならないとしたら、自分の思いや感情、個性を抑制しなければならない場面が多く出てくる。(22ページ)/「共感」されるために我慢を続ける。自分の思いを押し殺し続ける。むりやり笑顔を作る。そうしないと助けてもらえない。そんな状況に追い込むことが「利他」の影で起きているとすれば、問題は深刻である。(23ページ)/さらに、「より深い共感」を利他の条件にしてしまうと、今度は自分の思っていることや感情を露わにしなければならないという「別の規範」が起動してしまう。そうすると、「自分をさらけ出さないと助けてもらえない」という新たな恐怖が湧き起こってくる。(24ページ)
利他の主体はどこまでも受け手側にあり、その意味において私たちは利他的なことを行うことはできないのである
特定の行為が利他的になるか否かは、事後的にしかわからない。いくら相手のことを思ってやったことでも、それが相手にとって「利他的」であるかはわからない。与え手が「利他」だと思った行為であっても、受け手にとってネガティブな行為であれば、それは「利他」とは言えない。むしろ、暴力的なことになる可能性もある。いわゆる「ありがた迷惑」というものである。/つまり、「利他」は与えられたときに発生するのではなく、それが受け取られたときにこそ発生するのである。自分の行為の結果は、所有できない。あらゆる未来は不確実である。そのため、「与え手」の側は、その行為が利他的であるか否かを決定することができない。あくまでも、その行為が「利他的なもの」として受け取られたときにこそ、「利他」が生まれるのである。(122ページ)/受け手が相手の行為を「利他」として認識するのは、その言葉(や行為など)のありがたさに気づいたときであり、発信と受信の間には長いタイムラグがある。(128ページ)/つまり、発信者にとって、利他は未来からやって来るものである。また、発信者を利他の主体にするのは、どこまでも、受け手の側であるということである。この意味において、私たちは利他的なことを行うことができないのである。/発信者にとって、利他は未来からやって来るものであり、受信者にとっては、「あのときの一言」(や「あのときの行為」)のように、過去からやって来るもの。これが利他の時制である。(132ページ)
利他的になるためには「偶然の自覚」に基づいて器(うつわ)のような存在になり、与格的主体を取り戻すことが必要である
私という存在は、突然、根拠なく与えられたものである。あらゆる存在は、自己の意志によって誕生したのではなく、意志の外部の力によってもたらされたものである(与格的な存在)。ここに存在の被贈与性という原理がある。/そして、誕生以降も私という存在の奇跡は続く。今の私は、様々な偶然性の奇跡的な組み合わせによって成立している。私という個性は、単純な因果関係では説明できない天文学的な縁起によって構成されている。(150ページ)/この「私が私であることの偶然性」についての自覚が、「自分が現在の自分ではなかった可能性」「私がその人であった可能性」へと自己を開くことになる。(143ページ)/この「偶然の自覚」が他者への共感や寛容へとつながり、連帯意識を醸成し、「利他」が共有される土台を築くことになる。(143、145ページ)/ここで重要なのは、私たちが偶然を呼び込む器(うつわ)になることである。偶然そのものをコントロールすることはできない。しかし、偶然が宿る器になることは可能である。(176ページ)/そして、この器にやって来るものが「利他」である。器に盛られた不定形の「利他」は、いずれ誰かの手に取られる。その受け手の潜在的な力が引き出されたとき、「利他」は姿を現し、起動し始める。/このような世界観のなかに生きることが、「利他」なのである。/だから、利他的であろうとして、特別のことを行う必要はない。毎日を精一杯生きることである。私に与えられた時間を丁寧に生き、自分が自分の場所で為(な)すべきことを為す。能力の過信を諫(いさ)め、自己を超えた力に謙虚になる。その静かな繰り返しが、自分という器を形成し、利他の種を呼び込むことになるのである。(177ページ)
〇筆者の手もとに、若松英輔著『はじめての利他学』(NHK出版、2022年5月。以下[3])という本がある。若松も[1]の著者のひとりである。若松はいう。人と人との「つながり」が問われている今日、「私たちがもう一度、他者とともに生きるために『つながり』を持続的に深めるには何が必要か。この問題を解く鍵語(キーワード)として考えてみたいのが『利他』である」(6ページ)。そして若松は、[3]において、日本仏教の視座から最澄や空海、儒教のそれから孔子や孟子、西洋哲学からフランスのオーギュスト・コント(1798年~1857年)やアラン(本名:エミール=オーギュスト・シャルティエ、1868年~1951年)らの「利他」の思想を取りあげる。とともに、「利他を生きた人たち」として吉田松陰や西郷隆盛、二宮尊徳、中江藤樹らの「利他」の哲学を紹介し、論述する。そのうえで若松は、ドイツの心理学者・哲学者であったエーリッヒ・フロム(1900年~1980年)の『愛するということ』(1956年)を読み解き、「自分を愛すること」、すなわち「自分を深く信頼すること」が「利他」につながる、と主張する。次の一節が若松の結論である。
自分で自分のことを愛することができれば、その人は自分を固有なものにできる。そして、そのうえで誰かのことを愛することができれば、その人は他人のことを固有な存在として認めることができる。自分自身が固有であると知ることは、他者が固有であると知ることである。それはすなわち自他ともに等しい存在であることを経験するということでもある。/愛を通して利他を考えるとき、私たちは愛の前で等しくなければならない。Aさんのことは愛せて、Bさんのことは愛せないのであれば、それは利他がうまく働いている状態とはいえないのである。/利他には等しさが必要である。そして、そのためにはまず、他者を愛するように、自分を愛し、信じることが大切なのである。/(人は唯一無二の存在であることを認め、自他を愛するという)真の意味の「愛」があるとき、そこに在るものはすべて等しくなる。ただ人間であるというそのことにおいて、等しく貴い存在になる、のである。(118~119ページ。語尾変換)
〇前述の[1]で伊藤は、障がい者へのインタビューを通じて、こう語る。晴眼者が視覚障がい者に先回りしてことこまかに道案内をするとき、それはしばしば「善意の押しつけ」になってしまう。それは、視覚障がい者にとっては、「障がい者を演じること」が求められることになり、自分の聴覚や触覚を使って自分なりに世界を感じることができなくなってしまう。それはまた、障がい者が「健常者の思う『正義』を実行するための道具にさせられてしまう」(47ページ)ことになる。さらに伊藤は、認知症当事者の言として、こういう。認知症の当事者がイライラし怒りっぽいのは、支援や援助を求めていないのに周りの人が助けすぎるからではないか(46~48ページ)。福祉教育の実践・研究において、深く留意したい点である。
〇なお、筆者はしばしば、とりわけ福祉教育実践をめぐって「思いやり」と「思い違い」「思い上がり」はときとして紙一重(かみひとえ)であり表裏一体である、と語ってきた。ここで改めて強く認識したい。
〇加えて、次のことを付言しておきたい。人間は日常生活や社会生活を営むうえで何らかの支援や援助を受けるに際して、「たすけられ上手・たすけ上手に生きる」ことが問われることがある。その際の「たすけられ上手」とは、 甘え上手や集(たか)り上手ではないのは当然のことながら、社会(世間、財界)や支援者・援助者が期待し求める「たすけられ上手を演じる(あるいは演じさせられる)こと」(演じるさまや人)であってもならない。
【初出】
<雑感>(181)阪野 貢/「利他」再考の3冊:利他は事後的であり、利他的になろうとする作為は利他を遠ざける ―中島岳志著『思いがけず利他』等のワンポイントメモ―/2023年7月15日/本文
14 “Well-being” の視点
“Well-being” の視点【その1】
<文献>
(1)マーティン・セリグマン、宇野カオリ監訳『ポジティブ心理学の挑戦―“幸福”から“持続的幸福”へ―』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2014年10月、以下[1]。
(2)前野隆司『幸せのメカニズム―実践・幸福学入門―』講談社現代新書、2013年12月、以下[2]。
(3)前野隆司『実践・脳を活かす幸福学 無意識の力を伸ばす8つの講義』講談社、2017年9月、以下[3]。
(4)前野隆司・前野マドカ『ウェルビーイング』日経文庫、2022年3月、以下[4]。
(5)前野隆司『ディストピア禍の新・幸福論』プレジデント社、2022年5月、以下[5]。
(6)渡邊淳司・ドミニク=チェン監修・編著『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために―その思想、実践、技術』ビー・エヌ・エヌ、2020年3月、以下[6]。
(7)石川善樹・吉田尚記『むかしむかし あるところに ウェルビーイングがありました―日本文化から読み解く幸せのカタチ―』KADOKAWA、2022年1月、以下[7]。
「ウェル・ビーイングとは、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」である(厚生労働省『雇用政策研究会報告書』、2019年7月、1ページ)
「ウェルビーイングとは『健康』と『幸せ』と『福祉』のすべてを包む概念」である(前野隆司・前マドカ:下記[2]18ページ。注①)
「持続的ウェルビーイングは、人間が心身の潜在能力を発揮し、意義を感じ、周囲の人との関係のなかでいきいきと活動している状態」を示す包括的な概念である(渡邊淳司・ドミニク=チェンほか:下記[6]30ページ)
〇筆者(阪野)はかねてより、「福祉」を、キャッチフレーズ的に「ふだんの くらしの しあわせ」について「みんなで考え、みんなで汗を流すこと」を意味する言葉として、「ふくし」と表記してきた。その際、「しあわせ」についても簡潔に、「みんなが 満足していて 楽しいこと」と言ってきた。それは、個人のひと時の気分や感情に留まるものではなく、人生という長い期間にわたる「しあわせ」であり、しかも「みんなが」社会的に「良好な状態」にあることを含意するものとして考えてきた。近年、いろいろな分野で多用さ、注目を集めている “ Well-being”「ウェルビーイング」に通じる。(注②)
〇ウェルビーイングという言葉は、1946年7月に設立された世界保健機関(WHO)の世界保健憲章(1948年4月発効)のなかで使われたのが最初であると言われている。“ Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ”「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいう」がそれである。ここでは、“ well-being ”は「満たされた状態」と訳される。また、1946年11月に公布、翌1947年5月に施行された日本国憲法は、その第13条で幸福追求権について謳っている。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」がそれである。ここでは、「幸福追求」は公式には、“ pursuit of happiness ”と訳される。すべて国民は、第25条に基づく健康で文化的な最低限度の生活保障とともに、第13条が謳う幸福を追求し自己実現を図る基本的権利を有するのである。
〇時を経て、2015年9月、国連サミットで2030年を目標年次とする「持続可能な開発目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)が採択された。SDGs には、17のゴールと169のターゲットがある。3番目のゴールとして、“ Good Health and Well-Being ”「すべての人に健康と福祉を」が明記されている。ちなみに、1番目のゴールは“No Poverty”「貧困をなくそう」、2番目のそれは“Zero Hunger”「飢餓をゼロに」である。
〇このように、ウェルビーイングは古くて新しい言葉である。とりわけここ数年来のコロナ禍によって、改めて「健康」(health)や「幸せ」(happiness)、「福祉」(welfare)や「豊かさ」(richness)などに対する意識や価値観が変化し、働き方(雇用形態)や企業経営(健康経営)のあり方が問われることになる。それをひとつの要因や背景として、ウェルビーイングへの注目が拡大し、研究が進展している。ちなみに、2021年12月に「ウェルビーイング学会」が発足し、2022年1月に新聞紙上に「今年をウェルビーイング元年に」(注③)という記事が載った。そして、2024年4月には武蔵野大学に日本初(世界初)となる「ウェルビーイング学部」が開設される。「ウェルフェア(Welfare)からウェルビーイング(Well-being)へ」という新しい時代の幕開けであろうか。なお、このフレーズは、1994年3月に上梓された高橋重宏の著作『ウェルフェアからウェルビーイングへ―子どもと親のウェルビーイングの促進:カナダの取り組みに学ぶ』(川島書店)にみられる。
〇筆者(阪野)の手もとに、ポジティブ心理学(ウェルビーイングの実現を志向する心理学)の創始者と評されるアメリカの心理学者マーティン・セリグマン(Martin E. P. Seligman)の本――『ポジティブ心理学の挑戦―“幸福”から“持続的幸福”へ―』(宇野カオリ監訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2014年10月。以下[1])がある。[1]でセリグマンは、「ウェルビーイングの5つの要素」として有名な「PERMA(パーマ)」という指標について論述する(33~53ページ)。P:ポジティブ感情(Positive Emotion)、E:エンゲージメント(Engagement)、R:関係性(Relationships)、M:意味・意義(Meaning)、A:達成(Achievement)、がそれである。
〇「PERMA」すなわちウェルビーイングの状態について平易・簡潔に言えばこうであろう。次のような人は幸せである、という。(下記[4]参照)。
マーティン・セリグマン/「ウェルビーイングの5つ要素」
P:「ポジティブ感情」 嬉しい、楽しいなど、ポジティブな感情を持つ人。
E:「エンゲージメント」 物事に関わり、それに没頭したり夢中になる人。
R:「関係性」 援助や協力など、他者とのつながりやよい関係性を持つ人。
M:「意味・意義」 人生の意味・意義について自覚したり社会貢献する人。
A:「達成」 何かを達成(成功)するとともに、達成のために努力する人。
〇そして、セリグマンはいう。「幸せとは自分が気持ちよく感じることであり、人生の方向性はその気持ちよさを最大限にしようとすることで決まるとする。/ウェルビーイングとは、自分の頭の中だけで存在するわけにはいかないものだ。ウェルビーイングは、気持ちよさと同時に、実際には意味・意義、良好な関係性、および達成を得ることが組み合わさったものなのだ。人生の選択は、これら5つの要素すべてを最大化することで決まる」(50ページ)。
〇筆者の手もとに、日本における幸福学研究の第一人者と評される前野隆司の「ウェルビーイング」に関する本が4冊ある(しかない)。(1)『幸せのメカニズム―実践・幸福学入門―』(講談社現代新書、2013年12月。以下[2])、(2)『実践・脳を活かす幸福学 無意識の力を伸ばす8つの講義』(講談社、2017年9月。以下[3])、(3)前野マドカとの共著『ウェルビーイング』(日経文庫、2022年3月。以下[4])、(4)『ディストピア禍の新・幸福論』(プレジデント社、2022年5月。以下[5])、がそれである。
〇前野によると、ウェルビーイング(幸福)研究には、各人の主観的な幸福感を統計的・客観的に計測する「主観的幸福研究」と、収入や学歴、生活状況や健康状態などの客観的なデータを使って間接的に幸福を計測する「客観的幸福研究」がある([2]33~34ページ)。
〇前野は、主観的幸福研究をベースに、ウェルビーイングな状態でいるために必要な因子――「幸せの4つの因子」について探究する。次がそれである([2]96~113ページ、[3]98~113ページ、[4]72~75、87~92ページ、[5]119~140ページ)。
前野隆司/「幸せの4つの因子」
第1因子:「やってみよう」因子(自己実現と成長の因子)
やりがいや強みを持ち、主体性の高い人は幸せである。
・コンピテンス(私は有能である)
・社会の要請(私は社会の要請に応えている)
・個人的成長(私のこれまでの人生は、変化、学習、成長に満ちていた)
・自己実現(今の自分は「本当になりたかった自分」である)
第2因子:「ありがとう」因子(つながりと感謝の因子)
つながりや感謝、あるいは利他性や思いやりを持つ人は幸せである。
・人を喜ばせる(人の喜ぶ顔が見たい)
・愛情(私を大切に思ってくれる人たちがいる)
・感謝(私は、人生において感謝することがたくさんある)
・親切(私は日々の生活において、他者に親切にし、手助けしたいと思っている)
第3因子:「なんとかなる」因子(前向きと楽観の因子)
前向きかつ楽観的で、何事もなんとかなると思える、ポジティブな人は幸せである。
・楽観性(私はものごとが思い通りにいくと思う)
・気持ちの切り替え(私は学校や仕事での失敗や不安な感情をあまり引きずらない)
・積極的な他者関係(私は他者との近しい関係を維持することができる)
・自己受容(自分は人生で多くのことを達成してきた)
第4因子:「ありのまま」因子(独立とマイペースの因子)
自分を他者と比べすぎず、しっかりとした自分らしさを持っている人は幸せである。
・社会的比較志向のなさ(私は自分のすることと他者がすることをあまり比較しない)
・制約の知覚のなさ(私に何ができて何ができないかは外部の制約のせいではない)
・自己概念の明確傾向(自分自身についての信念はあまり変化しない)
・最大効果の追求のなさ(テレビを見るときはあまり頻繁にチャンネルを切り替えない)
〇そして、前野はいう。これらの4つの因子(第1因子:主体的に生きる、第2因子:共に生きる、第3因子:未来を信じる、第4因子:他人と自分を比べない)を意識しながら行動していけば、どんな人でも自分らしい幸せを掴むことができる。しかし、現代社会・世界は、利己主義から利他主義まで、民主主義から専制主義まで、個人主義から全体主義まで、経済成長から脱成長まで両極化しつつあり、バラバラのカオス(混沌)になりつつある。こうした混迷と分断の「ディストピア禍」において、多様な価値観を持つ人々がつながり合い、利他の精神を築き、より調和的な社会・世界をめざすためには、他者を「想像し、許し、信じ、対話する」ことからはじめる以外に解決策はない([5]141~147ページ)。
〇筆者の手もとにもう1冊、渡邊淳司・ドミニク=チェン監修・編著の『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために―その思想、実践、技術』(ビー・エヌ・エヌ、2020年3月。以下[6])という本がある。「ウェルビーイングとは、『わたし』が一人でつくりだすものではなく、『わたしたち』が共につくりあうものである」(2ページ)というのが、[6]のシンプルなメッセージである。すなわち、「個でありながらに共」という日本的なウェルビーイングのあり方について探究する([6]帯)。
〇[6]では、単数形の「わたし」ではなく、複数形の「わたしたち」のウェルビーイングを想定する。そして、「『わたしたち』のウェルビーイングとは『競争』するものではなく、『共創』するものなのだ。(中略)『わたし』のウェルビーイングを追い求めつつ、『わたしたち』のウェルビーイングを共につくりあう、重層的な認識によってウェルビーイングを捉えていく必要がある」(4ページ)と説く。渡邊・チェンらにあっては、「効率性」や「経済性」といった既存の「ものさし」にとらわれた個人主義的(individualistic)な「わたし(個)のウェルビーイング」だけでなく、人と人とのあいだにウェルビーイングが生じると考える集産主義的(collectivistic)な「わたしたち(共)のウェルビーイング」(32ページ)も、「人それぞれの心を起点とした新しい発想の『コンパス』となる」(3ページ)。それによって、「コミュニティと公共」というより広い視点からのウェルビーイングについても論じることになる。そして、ウェルビーイングに配慮した新しい社会像をめざすことができるのである(3~6ページ)。
〇渡邊・チェンらによると、ウェルビーイング(心身がよい状態)には3つの側面・領域がある。心身の機能が不全でないか、病気でないかを問う医学の領域である「医学的ウェルビーイング」、その時の気分の良し悪しや快・不快など、一時的かつ主観的な感情に関する領域である「快楽主義的ウェルビーイング」、心身の潜在能力を発揮し、周囲の人との関係のなかで意義を感じている「いきいきとした状態」を指す「持続的ウェルビーイング」がそれである(20、30ページ)。すなわち、健康で、心地よく、周囲の人との関係のなかで意義を感じいきいきと活動している状態をウェルビーイングというのである。そして「近年は、医学的もしくは快楽主義的なものではなく、ウェルビーイングを持続的かつ包括的に捉えようとする考えが主流となっている」(20ページ)。
〇次いで[6]では、持続的ウェルビーイングを生み出しその向上を図るためには、他者との関係性のなかでどのような働きかけ(「配慮」)をすべきか(「ウェルビーイング向上のために他者が介入する際、留意すべき点」45ページ)、について説く。以下がその要点である(45~49ページ)。
渡邊淳司・ドミニク=チェン/「ウェルビーイングを生み出すための6つの配慮」
個別性への配慮
何よりも意識すべきは、「私とあなたは違う」という点である。ウェルビーイングの要因の重要度は、個人によってやその人のライフステージによっても変化する。
自律性への配慮
ウェルビーイングは誰かに与えるものではなく、自身で気づき、行動するものである。他者に働きかける際には、いくつかの選択肢を用意し、相手に一定の自律性を担保することが望まれる。
潜在性への配慮
「ふとした瞬間に感じる気持ち良さ」や「ちょっとした違和感」など、潜在的には存在しているが自覚されていない情報や感覚体験をすくい上げ、それらに目を向ける。
共同性への配慮
人間は他者との関係性のなかで生きている。当事者間に深い共感や価値観の共有をもたらすものに取り組んだり、体験したりする。
親和性への配慮
ポジティブ感情には、興奮を伴うポジティブ感情と、平穏や思いやり、愛といったリラックスするそれがある。現代社会は前者に偏っており、両方のポジティブ感情のバランスを取ることが望まれる。
持続性への配慮
ウェルビーイングは、短期的あるいは長期的な目標設定をすることだけでなく、その過程の充実によって持続性を作り出すことが重要になる。
〇そして、渡邊・チェンらは「コミュニティと公共のウェルビーイング」についていう。インターネットの普及などによって、コミュニティのあり方が揺れ動いている。そんななかで、「公共のウェルビーイング」について考える際、「存在論的安心」「公共性」「社会創造ビジョン」という3つの要因が重要となる。「存在論的安心」とは、自身や自分を取り巻く環境や世界が安定的・継続的に存在し、それに対する確信や信頼のことを指す。「公共性」とは、多様な人々が共に生きられる公共の場(空間)を、一人ひとりのボトムアップな動きによって創り出すことをいう。そしてこの2つを前提に、自分たちが自律的に活動することによって新たなイノベーションが生まれ、社会創造が実現する(「社会創造ビジョン」)。それは自己効力感や達成感を得る機会になり、一人ひとりのウェルビーイングを高めていく。要するに、「コミュニティと公共のウェルビーイング」を実践していくことは、新たな社会や未来を構想し創造することそのものなのである(63~75ページ)。
〇この点(地域コミュニティにおけるウェルビーイング)は、住民個々人のウェルビーイングと集合的なウェルビーイング(コミュニティ・ウェルビーイング)を実現していく「まちづくり」や、そのための教育(「市民福祉教育」)に通じることになる。例によって唐突であるが、指摘しておく。
〇さらに筆者の手もとにもう1冊、石川善樹・吉田尚記の『むかしむかし あるところに ウェルビーイングがありました―日本文化から読み解く幸せのカタチ―』(KADOKAWA、2022年1月。以下[7])という本がある。[7]では、「日本の文化と風土を前提にしたウェルビーイングへの道とは何か」について、「古事記」や「日本昔ばなし」などから読み解く。そこから得られた「教訓」は次の5つである。
石川善樹・吉田尚記/「昔話と古典から学ぶウェルビーイング5つの教訓」
(1)上より奥を見る:上ばかりを見て焦るのではなく、あえて視点を外してみる。
(2)ハプニングを素直に受け入れてみる:突発的なトラブルや出来事と楽しみながら向き合ってみる。
(3)人間は多面体であることが当然という認識に立ち戻る:人間は本来、多面的な顔、矛盾した性質を持っていることを再認識する。
(4)自己肯定感の低さにとらわれすぎない:日本人には謙遜の精神が根付いているが、自己肯定感への執着を手放す。
(5)他者の愚かさを許し、寛容に受け入れる姿勢を身につける:自分と他者に寛容になる。
〇石川・吉田は、この5つの教訓が「現代人のウェルビーイングの素地になる」という(156~159ページ)。
〇なお、上述の[6]では、日本的ウェルビーイングの特徴として、次の3点を指摘している。(1)自律性(自分の周りの環境に対し主体能動性を感得できる)、(2)思いやり(自己のウェルビーイングのみならず周りの他者のそれにも寄与できる)、(3)受け容れ(自律性と他者の存在が調和し現在のポジティブ・ネガティブの双方を含む状況を受け容れられる)、がそれである(56~57ページ)。
〇冒頭で記したように、ウェルビーイングは、身体的、精神的、社会的に満たされている良好な状態にあることを意味する。すなわち、ウェルビーイングは、「豊かさ」を考えるためのキーワードである。その点をめぐって、筆者はこれまで、「豊かさ」を獲得・実現するための条件について言及してきた。ここでそれを再認識(再確認)しておくことにする。
阪野 貢/「豊かさ」を獲得・実現するための5つの条件
(1)基本的人権の尊重や自由・平等と民主主義の確保を前提に、人々の個別具体的な発達保障と生活保障の具現化と共生や支え合いの創出が図られること。
(2)すべての人が個性的・創造的に自分を生きる(生き抜く)ために多様な選択肢が準備され、その選択の自己決定やそのための支援がなされること。
(3)自分の生きがいや自己実現のための活動にとどまらず、他者や地域・社会のための、社会変革を進める社会貢献活動(共働活動)に参加できること。
(4)そのための個人的な尊敬と信頼に基づく熟議やさまざまな知識や経験による想像力と創造力によって、明るい社会と未来(希望)が開拓・共創されること。
(5)以上のことを可能にし、相互支援と相互実現、地域・まちづくり、社会変革と社会創造を推進するための教育・学習(市民福祉教育)が、すべての人の生涯にわたって自律的・主体的に行われること。
注
➀ 図1は、前野隆司・前野マドカの「ウェルビーイングの定義」を図示したものである。図2は、2010年12月に内閣府に設けられた「幸福度に関する研究会」(2010年~2013年)が、「幸福度指標試案」の構成要素を体系図として描いたものである。参考に供しておく。図2では、「幸福度」指標を「主観的幸福感」と、それを支える3つの柱として「経済社会状況」「(心身の)健康」「関係性」を含めて考えている。また、地球温暖化や大気汚染などの環境面の「持続可能性」についても重視している。
図1 ウェルビーイングとは何か
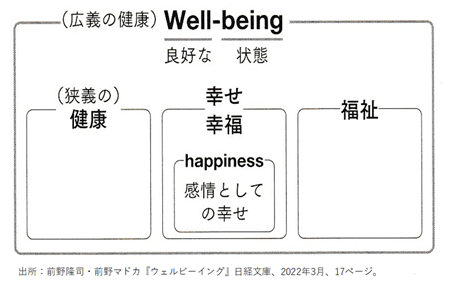
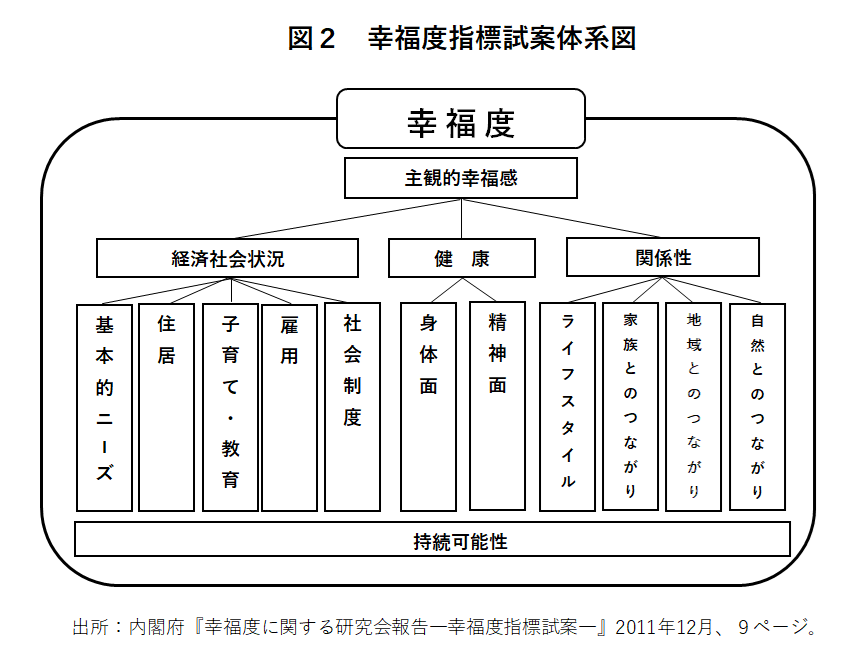
② 平仮名表記の「ふくし」については、例えば、松岡広路の論考「<ふくし>を実質化する福祉教育・ボランティア学習とは」『ふくとし教育』通巻36号、大学図書出版、2023年9月、62~63ページ、が興味深い。松岡はいう。<ふくし>とは、「あらゆる人が、多元的課題を内包する日常生活を基点に、臨床的かつ集合的に幸福を追求するとともに、マジョリティ文化のなかで当たり前とされてきた社会の在り方・生き方およびその根底の価値を、生活者としての視点で疑い、その変容を促す主体となるような総合的な営為」(64ページ)である。簡潔に言えば、「あらゆる人が、幸福や命をめぐる学びの中で、現代の生き方・ライフスタイルを批判的に再構築し社会を変えるという、人間らしさの本源を問う営みである」(6ページ)。
③ 「今年をウェルビーイング元年に」(日経電子版/2022年1月5日)
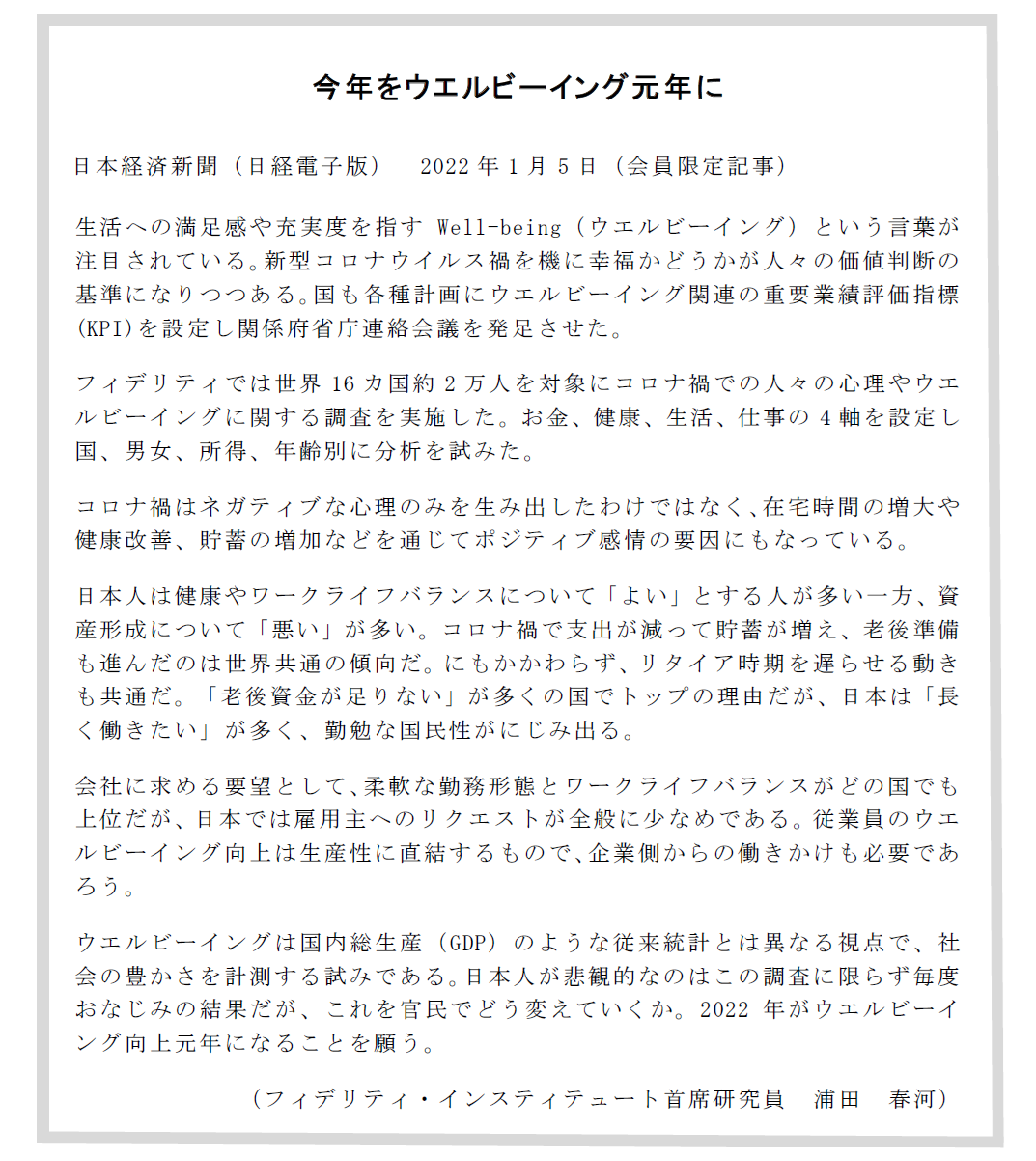
【初出】
<雑感>(193)阪野 貢/“ Well-being ” 考―「しあわせ」の構成要因に関するワンポイントメモ―/2023年12月12日/本文
“Well-being” の視点【その2】
<文献>
(1)草郷孝好『ウェルビーイングな社会をつくる―循環型共生社会をめざす実践』明石書店、2022年7月、以下[1]。
〇2015年9月、ニューヨークの国連本部で開催された「国連持続可能な開発サミット」(United Nations Sustainable Development Summit)で、2030年を目標年次とする「持続可能な開発目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)が採択された。それは、「誰一人取り残さない(no one will be left behind)」持続可能な社会の実現をめざす世界共通の目標である。
〇筆者(阪野)の手もとに、草郷孝好著『ウェルビーイングな社会をつくる―循環型共生社会をめざす実践』(明石書店、2022年7月。以下[1])という本がある。
〇[1]で草郷は、「誰一人取り残さない」持続可能な社会を実現するためには、社会発展モデル(経済・社会システム)を従来の「経済成長モデル」から「ウェルビーイングモデル」へ転換して「循環型共生社会」を切り拓くことが必要かつ重要であるとする。そして、そのためには、労働・教育・医療・環境・経済・社会に関する政策をウェルビーイングモデルに基づいたものに転換する必要があるとし、その処方箋を提示する。例えば、経済効率をあげる人材育成のための競争教育(偏差値教育)から、主体的に物事に取り組む力や他者に共感し協働する力を涵養していく「共創・共修学習」への転換や(152ページ)、地域づくりについて「行政が企画して、住民が参加する」という「市民参加」から、「住民の主体的活動を柱にして、行政がそれを支援する」という「行政参加」への転換(183ページ)、などがそれである。
〇「経済成長モデル」は一般的に、人間の物質的な豊かさを追求する経済成長のために生産活動の維持・拡大を図り、経済的利益を最優先する社会発展モデルをいう(大量生産、大量消費、大量破棄によって維持されてきた経済システム)。草郷にあっては、「ウェルビーイングモデル」とは、一人ひとりの人間が身体的・精神的・社会的に良好な状態を維持するために、自身が持っている「潜在能力」を活かし、充足度の高い生き方を選択し、追求できる社会発展モデルをいう(114ページ)。そして、「循環型共生社会」とは、ウェルビーイングを大切にし、経済の持続的成長と環境の持続的保全を図る循環型経済と、誰もが人間らしく生活でき、多様性と人権を認め合う思いやりのある共生社会の持続的発展がバランスよく保たれる社会像(99ページ)、循環型経済と共生社会の2つを併せ持つ社会像(15ページ)をいう。
〇以下では例によって、「まちづくりと市民福祉教育」を射程に入れながら、[1]における草郷の「ウェルビーイングを大切にする循環型共生社会」に関する言説や論点のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
SDGsと循環型共生社会
SDGsが掲げる「誰一人取り残さない持続的な社会」とは、
(1)誰もが安心して人間らしい生活のできる社会(人間らしい生活)
(2)お互いを認め合い多様性を大切にする共生社会(多様性重視)
(3)循環型経済によって環境と共存する持続可能な社会(環境との共存)
この3つの条件をすべて備えた「循環型共生社会」である。(26ページ)/別言すれば、循環型共生社会は、環境と調和し、経済と環境の両立をめざす循環型経済システムと、すべての人に基本的な生活と人権の保障(憲法25条の生存権)をめざす共生社会システムを両輪とする。(103ページ)
ウェルビーイングモデルと社会的共通資本
循環型共生社会を実現するためには、社会発展モデルを従来の「経済成長モデル」から「ウェルビーイングモデル」に転換する必要がある。(103ページ)/ウェルビーイングモデルは、日本の経済学者である宇沢弘文が提起した「社会的共通資本」(Social Overhead Capital)を土台として成り立つ。(123ページ)/宇沢がいう社会的共通資本は、一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置を意味する。それは、大気、森林、河川、水、土壌などの「自然環」、道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなどの「社会的インフラストラクチャ―」、教育、医療、司法、金融制度などの「制度資本」の3つの大きな範疇にわけて考えることができる。(124ページ、図1参照)
ウェルビーイングモデルと潜在能力アプローチ
ウェルビーイングモデルは、インドの経済学者であるアマルティア・セン(Amartya Sen)が提唱した「潜在能力アプローチ」(capability approach、ケイパビリティ・アプローチ)を大黒柱として成り立つ。(116ページ)/センは、誰もが真の自由を保障される社会こそ、よりよい生き方を選択できるウェルビーイングの高い社会であると考える。“真の自由”とは、誰もが自分の持っている素質や可能性に気づき、それを伸ばしていくことによって、充足度の高い生き方を自ら選択できる自由のことである。(116ページ)/潜在能力アプローチのもう一人の提唱者であるアメリカの哲学者マーサ・ヌスバウム(Martha Craven. Nussbaum)は、「善く生きる」ためには、安定した経済基盤を持つだけではなく、社会的包摂、政治的参加の保障、多様な文化を認め合う社会での暮らしが欠かせない。善く生きて、幸せな人生を送るには、個人と社会の両方が密接に関係し合っていると考える。(118~119ページ)/ヌスバウムにあっては、人間は、生まれた時から備わっている生来の潜在能力(基礎的潜在能力)と、その潜在能力を個人の努力や周りの支援によって磨き・伸ばす(内的潜在能力)とともに、それを発揮できる多様な選択肢を保障する社会を実現すること(結合的潜在能力)によって「善く生きる」ことができるのである。(118~120ページ、図1参照)
内発的地域協働と地域づくり
地域の社会変革には、地域住民が社会のあり方を思い描き、未来ビジョンを構想することが大きな力になる。そして、未来ビジョンの実現には、地域に関わるさまざまな当事者(stakeholder、ステークホルダー)の主体的な地域協働が欠かせない。(169ページ)/地域のステークホルダーが主体的に地域協働していくことを「内発的地域協働」という。(171ページ)/イギリスの国際開発省(DFID:Department for International Development、1997年~2020年)は、持続的に生活改善を図るためには地域協働が不可欠とし、地域協働を醸成するために、「当事者主体の地域協働を醸成するための6つのポイント」に集約し、実行に移した。
(1)当事者目線で問題に向き合う
(2)当事者自身が問題解決に動く
(3)当該地域と地域外との関係を意識する
(4)行政と市民の協働
(5)制度、社会、経済、環境の持続性
(6)柔軟で長期的な視点を持つ
がそれである。/これらからいえるのは、当事者目線と当事者行動が重要であること、地域間の連携が大切であること、地域の当事者同士の協働が必要であること、中長期の視点を持って地域協働に取り組むことである。地域社会を変えていくためには、長期的視点に立ち、当事者目線、当事者協働、地域間連携という形で地域協働を推し進めていくことが重要なのである。(171~172ページ)
循環型共生社会への変革のポイント
地域レベルで、ウェルビーイングを大切にする循環型共生社会に舵取りしていくためのポイントは、次の2点である。
(1)変革の方向性を打ち出すリーダーの存在
地域社会の変革に欠かせないのは、どのような社会を構想し、当事者である住民の参画意識を引き出し、協働をリードする優れたリーダーの存在である。
(2)当事者の地域協働と行政参加への切り替え
行政は、まちづくりの主役である住民のアイデアや動きにアンテナを張り、それらのパートナーとして参加していく行政参加に切り替えていくことが必要である。(205~207ページ)
ウェルビーイングを大切にする循環型共生社会に変革していくために、私たちが取り組むべき重要なポイントは、次の3点である。
(1)循環型共生社会への地域変革ビジョンを構想し、推進する
地域の当事者が、地域社会の将来ビジョンを描き、それを実現するために行動していけるかどうかがカギを握る。
(2)地域独自の文化、歴史、智慧を活かし個性ある循環型共生社会をつくる
循環型共生社会は、地域固有の環境、生活文化、地域の歴史、そして、地域住民がつくりだしてきたさまざまな智慧を活かして、持続的な社会の実現をめざしていく。
(3)循環型共生社会の暮らしを日常生活に取り込んでいく工夫と協働を楽しむ
循環型共生社会の実現には、日頃の生活を見直して、自ら生活を変えていくことが必要であり、そのために、住民同士が対話し、協働することで、生活の拠点である地元をかけがえのない共通の場(コモンズ)として育てていく。(213~215ページ)
〇草郷は、「社会的関係資本」と「潜在能力アプローチ」そして「内発的発展論」(内発的地域協働)を援用して、経済成長モデルからウェルビーイングモデルへの転換を図り循環型経済システムと共生社会システムを併せ持つ循環型共生社会の実現を提唱する(図2参照)。そして草郷はいう。「私たち自身が社会を変えていく当事者であることを自覚し、小さなことから協働、対話、共創によって自分事として何かを変えていくことが、後々、大きく社会を変えていくことにつながる」。「ウェルビーイングを大切にする地域が増えていけば、循環型共生社会に向かって社会は動き出していく」(222ページ)。そのためには、「主体性と共感力を磨く教育政策」への転換が求められる(150~153ページ)。これが草郷からのシンブルで強いメッセージである。それは、筆者が言ってきた「まちづくりと市民福祉教育」に通底する。
図1 ウェルビーイングを大切にする社会の特徴
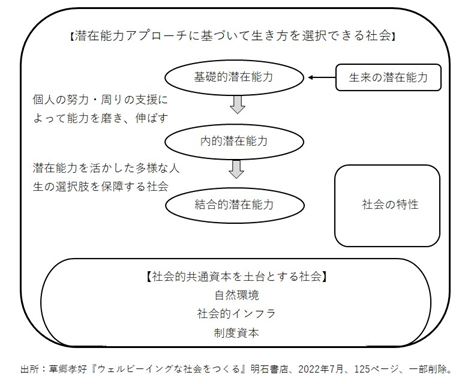

図2 循環型共生社会の構想
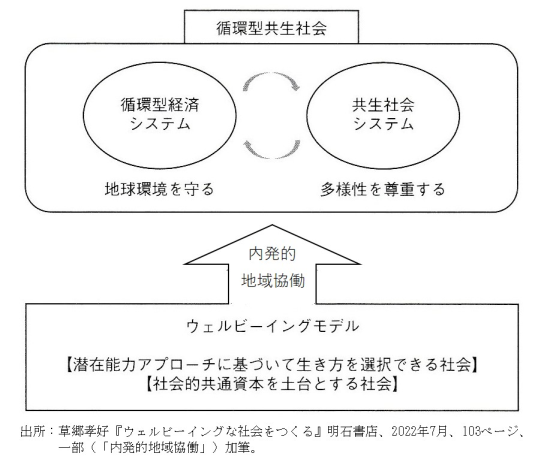
【初出】
<雑感>(194)阪野 貢/“ Well-being ” 再考―「ウェルビーイングを大切にする循環型共生社会」に関するワンポイントメモ―/2023年12月22日/本文
“Well-being” の視点【その3】
<文献>
内田由紀子『これからの幸福について―文化的幸福観のすすめ―』新曜社、2020年5月、以下[1]。
〇筆者(阪野)の手もとに、内田由紀子著『これからの幸福について―文化的幸福観のすすめ―』(新曜社、2020年5月。以下[1])という本がある。内田にあっては、主観的な幸福感(Happiness、subjective well-being)は、「喜びや満足などを含んだ、ポジティブな感情・感覚」として定義することができる。それは、一時的な感情状態だけではなく、持続的な、自分の状態や人生に対する評価や心理的安寧(well-being)も含んだ概念である(1ページ)。また、幸福は、個人の性格特性や志向性などの価値観を反映するものであるが、その個人が暮らす環境や文化社会的要因についての状態を示すものである。つまり公共の政策や意思決定にも関わるものである(20ページ)。国レベルの幸福については、経済的な豊かさが重要視されるが、経済自体が直接的に幸せをもたらすわけではなく、GDP(国内総生産)に代表される経済状態は幸福を高める要因のひとつに過ぎない(13ページ)。こうした考えのもとで内田は、専門とする文化心理学の視点・視座から、「幸福とは何か」「幸福とはどのように私たちが暮らす文化と関わっているのか」について客観的・実証的に探究する。内田はいう。[1]において「『幸せになりましょう』というキラキラ輝くメッセージではなく、『幸せとは何かをシリアスに考えましょう』というメッセージを発信したい」と(151ページ)。
〇[1]のキーワードのひとつに「文化的幸福観」がある。その一文をメモっておくことにする(抜き書き)。
幸福と文化的幸福観
幸福は個人が感じるものでありながら、何を幸福と感じるかは実はその人が生きる時代や文化(傍点筆者)の精神、価値観、地理的な特徴を反映している。たとえば自然のなかで過ごすことで感じる幸福、消費のなかで感じる幸福は、どちらも幸せをもたらすものでありながら、前者はより自然豊かな地域で、後者はより都市的地域で感じられるものであり、農村部と都市部では幸せに関する考え方が違っているかもしれない。幸福はどのような状況に暮らす人もある程度理想とする感情状態でありながら、「どのように幸福を得るのか」はやはり文化によって異なっているだろう。/このような幸福についての考えは「文化的幸福観」と呼ぶことができる。文化的幸福観は、文化を構成する価値観や人生観を反映して成立している。社会生態学的環境(生業あるいは気候など)や宗教・倫理的背景などにより、人々が実際に追求する幸福の内容は異なっている可能性がある。文化・思想的背景がいったんできあがれば、人々は「幸福とは〇〇なものである」という文化的幸福観を教育などにより意識的・無意識的に再生産し、その文化内の他者の幸福の感じ方にも違いを与えるかもしれない。そしてどのようにして幸福を得ようとするか、どの程度の幸福を求めようとするかなどの幸福への動機づけのあり方も異なってくるであろう。(ⅴページ)
〇ここでいう「文化」とは、「ある集団内に社会・集団の歴史を通じて築かれ、共有された、価値あるいは思考・反応のパターン」をいう。すなわち、習慣やルール・価値観など、一定の集団(国家、民族、地域、家族など)のなかで共有され、伝達される有形無形の枠組みが文化である。それはまた、生活のなかに多層的に重なって存在しており、集団を構成する人々が変化すれば文化自体も変化することになる(73、74ページ)。
〇いまひとつのキーワードは「集合的幸福」である。その一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
個人の幸福と集合的幸福
個人の幸福は、個々人の「心の持ち方」だけではなかなかうまくいかず、いろいろな社会の相互作用のなかで実現されている。これまでの個人の幸福モデルでは、一人ひとりの幸福の実現をめざすことが、組織や地域全体の集合的な幸福を高めることになるという視点で捉えられてきた。しかし、個人の幸福の追求は、誰かの幸福を搾取したり、誰もが利己的になることで「共貧状態」に陥ったりすることもあり得る。この視点に立てば、個人の幸福の追求だけでは集合的な幸福は実現せず、集合での持続可能な幸福モデルを考えることも必要になる。つまり、これからの幸福については、組織や地域全体における「個人の幸福」と「集合的幸福」の良きバランスを考えることが重要になる。(105、106ページ)
個人の幸せが、他者の幸せを搾取せずに協調的に成立することも大事な要件である。おそらく日本の協調的な幸福(傍点筆者)は、他者との調和を重視することで、天災などの困難を乗り越え、周囲と助け合うために自分を律する、そういう機能をもって受け継がれてきた。個人ばかりに目を向けてそれが競争的な形で相手を打ち負かし、自らが多くの取り分を得ようとするようなものでは、社会は過度に競争的になり、安定した幸福は得られない。個人の幸せの行きつく先が、足りない部分を満たし続けようとしてしまう快楽主義的なものになってしまっては持続的な幸福は見込めない。個人が生きる意味や価値を感じられるような幸福を実感しながら、それを支える社会・集合とバランスを持っていくことは、現在日本における幸福について考えるうえで極めて重要なことなのではないだろうか。(143ページ)
〇日本の「協調的な幸福」については、内田は「文化的自己観」(Markus & Kitayama)――「相互独立的自己観」と「相互協調的自己観」をめぐって、こう説述する。相互独立的自己観は、人は他者や周囲の状況から区別されて独立に存在するものであり、人の行動はその人の内部にある属性(能力、性格など)による、という考え方(自己観)である。相互協調的自己観は、人は他者や周囲の状況などによって左右されるものであり、人の行動は周囲からの要求に合わせて行われる、という考え方(自己観)である(77~79ページ)。狩猟採集に依存する経済体系を歴史的にもってきたアメリカでは、前者の「個人の自立」が優先されやすく、定住型の農耕に依存する経済体系を歴史的にもってきた日本では、後者の「社会の協調」が優先されやすい(84ページ)。それゆえに、日本人は、自分だけが周囲から飛び抜けて幸福であったりすることよりは、「人並みの日常的幸せ」「ほどほどの幸せ」が大切にされる(68ページ)。
〇なお、内田は、「個人の自由」を重んじる価値観が形成されるなかで、日本人の心のあり方は今、一階が協調性、二階が独立性という、二階建ての家のようになっているのではないか、と指摘する(123ページ。図1:124ページ)。そして、「一階部分の協調性を、保守的で階層的なものではなく、互いの信頼関係を構築し、維持するためのシステムとして活用すれば、(増設された)二階部分の独立性とは両立する可能性がある」(125ページ)という。
図1 現代日本の自己における独立性と協調性の二階建てモデル
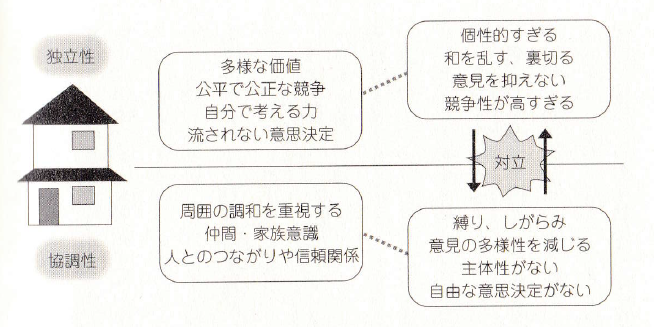
〇もうひとつのキーワードとして、「地域の幸福」に関する内田らの調査結果の概要をメモっておくことにする(抜き書き)。
地域内の「つながり」と幸福
地域内のつながりは住人の幸福度を上げている傾向がある。また、つながりは地域内部だけではなく、外の人とも広がっているほうがより良いようである。分析の結果、地域の幸福(傍点筆者)には社会関係資本(信頼関係)や地域内でのサポートのやり取りなどが重要な要素となっていることなどが見いだされた。また「閉鎖的」と思われがちな日本の地域内のつながりは、意外にも逆に「開放性」につながっていた。地域内信頼関係があれば、移住者についても受け入れる気持ちが強く、世代が異なる人など、多様な人の意見を聴こうとする雰囲気が醸成されていることなどがわかったのである。/このようなことから、地域内の「つながり」や「共有されている価値」を維持することに貢献するような活動(お祭りなど)や、地域間を橋渡しする制度設計(プロのコーディネート機能の活用)、そして地域外からの評価によって、自分たちが生きる社会・自然・文化的環境を再評価し、誇りをもてるような指針をつくることが重要なのではないかと考えている。(110~111ページ)
〇内田は、「地域の幸福」(地域内の集合的幸福)を高める試みの一例として、農村コミュニティにおける「普及指導員」の果たす役割について紹介する。普及指導員は、農業者や農業コミュニティを対象に、技術指導や経営指導を行う都道府県の職員である。内田らの研究の結論はこうである。農業コミュニティ内部の信頼関係(つながり)である「ソーシャル・キャピタルを形成することは農業コミュニティの幸福につながっていること、そしてそれは内部住民任せの自発的な部分だけではなく、普及指導員による外部からの働きかけによって支えることができるということが示された」(116ページ)。例によって唐突ながら、「まちづくり」や関係人口、コミュニティソーシャルワーカーなどにも通底する言説であろう。留意しておきたい。
〇[1]における内田の主張のひとつは、「幸福は『ごく個人的な』ものと考えられがちであるが、実は社会や文化の影響を大きく受ける、『集合的な現象』でもある」(146ページ)というものである。個人の幸福と集合的幸福の関係は、個人の幸福の追求は集合的幸福度を高め、集合的幸福の追求は個人の幸福度を高めるという相互性・不可分性にある。そこで内田は、個人の幸福と集合的幸福のバランスを保つことが重要であると言う。その際のバランスには、前述した日本人の相互協調的自己観、すなわち「人並み」「ほどほど」といった感覚を大切にするバランス思考が反映されているのであろう。
〇ここでは、個人の幸福度と集合的幸福度を高めるためには、個人に対する働きかけと組織や地域・社会に対する働きかけが必要かつ重要となることに留意したい。その際、ステレオタイプの幸福(「これが幸せなんだ」)や社会的に強制された幸福(「幸せだと思いなさい」)ではなく、それぞれの幸福とそれを支える要件を個々人が、地域・社会全体が思考し追求することが肝要となる(21ページ)。そこで問われるのが、内田が紹介する農業者(個人の幸福)や農業コミュニティ(集合的幸福)に対する「普及指導員」(生産技術に関連する技術力・活動と地域のつながりに関連するコーディネート力・活動が求められる:116ページ)のような役割や機能であろう。「まちづくり」(住民と地域コミュニティ)における重要な視点・視座でもある。
〇なお、筆者が本稿のタイトルを「“Well-being”再々考」としたのは、内田と同様に、「幸福」は個人的な感情状態をさす「幸せ」(happy、happiness)ではなく、地域・社会や環境などを含めた包括的な「幸福」(Well-being)概念として表示すべきであるという思考によるものである。そして、その根底には(またまた唐突であるが)、「困っている人を助ける」という「福祉」(welfare)観ではなく、「みんなの必要を満たす」という「ふくし」(Well-being)観がある。
【初出】
<雑感>(204)阪野 貢/“ Well-being ”再々考:文化的幸福観と集合的幸福をめぐって ―内田由紀子著『これからの幸福について』のワンポイントメモ―/2024年4月24日/本文
15 「自前」の思想
<文献>
(1)清水展・飯嶋秀治編『自前の思想―時代と社会に応答するフィールドワーク』京都大学学術出版会、2020年10月、以下[1]。
(2)佐高信・田中優子『池波正太郎「自前」の思想』集英社新書、2012年5月、以下[2]。
(3)伊藤幹治『柳田国男と梅棹忠夫―自前の学問を求めて』岩波書店、2011年5月、以下[3]。
〇筆者(阪野)の手もとに、清水展・飯嶋秀治編『自前の思想―時代と社会に応答するフィールドワーク』(京都大学学術出版会、2020年10月。以下[1])という本がある。[1]は、これからフィールドワークとそれに基づいて発信しようとする人たちが、「かつてそれぞれの時代の喫緊課題に積極的に関わり、発言し、行動していったフィールドワークの先達」(18ページ)の人生と仕事ぶり(技法や作法など)を学ぶことを通して、「示唆や励ましを得ること」(1ページ)を目的に編まれたものである。
〇「取り上げる先人たちは、自身のフィールドワークでの体験や知見にもとづき、それをじっくりと熟成させながら自前の思想を紡ぎ出し」(1ページ)、時代と社会の現場と現実に関与し、応答し、さらには積極的に介入していった人たちである。中村哲(医師・土木技師)、波平恵美子(文化人類学・医療人類学)、本多勝一(新聞記者・ルポライター)、石牟礼道子(詩人・小説家)、鶴見良行(東南アジア海域世界研究)、中根千枝(社会人類学)、梅棹忠夫(生態学・民族学)、川喜田二郎(地理学・文化人類学)、宮本常一(日本民俗学)、岡正雄(民俗学)の10人がそれである。
〇[1]の編者のひとりである清水は、「はじめに―現場と社会のつなぎ方」において、「10人の先達」の略歴と業績を紹介する。そして、それぞれがフィールドワークから「自前の思想」を編み上げていった、その方法や意義について言及する。それを通して清水は、読者・フィールドワーカーに対して、「時代状況への介入を含めた過激な応答実践」(18ページ)を呼びかける。次の一節をメモっておくことにする(見出しは筆者)。
フィールドワークと「自前の思想」の編成
フィールドワークとは、人々の暮らしの営みやそこで生ずる諸問題を、暮らしの場(生活世界)のなかで理解し、逆に個々人の暮らしの営みを見つめ丁寧に描くことをとおして、その喜びや悲しみ、日々の生活の背景や基層にある意味世界、つまり文化というコンテクスト(社会的脈略・状況や背景)を明らかにしようとする企てと言えるでしょう。そして(本書で取り上げるフィールドワーカーたちは:阪野)その総体を丸ごと描き考察するために、欧米の偉大な思想家の言説や流行りの理論を安易に借用(乱用/誤用?)したりしませんでした。人々の生活の場に身を置き、腰を低くして同じ高さ(低さ)の目線で話し、その説明に謙虚に耳を傾け、彼らが生きる社会文化や政治経済のコンテクストに即して粘り強く考え続けました。けっして虎の威を借る狐(とらのいをかるきつね)になろうとせず、かといって井の中の蛙(いのなかのかわず)になることも避けて身体と思索の運動を続け、具体的で手触りのある現場から的確な言葉を自ら紡ぎ出し、自前の思想を編みあげてゆきました。さらにその先には、人々の暮らしに直接に関わるような政治社会状況に積極的に関与し、問題の解決や状況の改善に寄与するために積極的な介入を行ったりしました。(17ページ)
思想―「応答」的行動を支える姿勢や信条
(本書でいう)思想とは、学術の理論や哲学というよりも、社会に対する身の処し方や律し方、広くは自らが生きる社会、狭くはフィールドワークでお世話になった人たちとの関係の作り方や応答の仕方などを支える姿勢や信条を意味しています。(1ページ)/下から・現地現場から社会の成り立ちを見据え理解し対応するための姿勢や信条とほぼ同義です。(2ページ)
〇もうひとりの編者である飯嶋は、「自前の思想」の本質を「時代と社会に応答する」3つの側面――「遭遇」「動員」「共鳴」からまとめている。それぞれの要点をメモっておくことにする(見出しは飯嶋)。
遭遇/自前の思想は遭遇したものへの応答から「はじまる」
人により、それがより劇的な場合と、より漸次的な場合との違いはありこそすれ、そののちインパクトをあたえる仕事が、自らの仕事の延長線上に出てくるという以上に、ある人物やある主題、ある状況に「遭遇」してしまい、そこから好むと好まざるとに関わらず、その状況に巻き込まれ、そのひとと仕事が大きく動いていくことになる。つまり自前の思想を生みだす応答は、こうした遭遇から「はじめる」というよりも「はじまる」のである。(422ページ)
動員/自前の思想の応答はあらゆるものを「資源化する」
予期せぬ「遭遇」から始まってしまう自前の思想の応答は、それゆえにこそ、応答する者がもてる全てを動員してそれに応答せざるを得なくなる。遭遇した事態に対して出来合いの方法論や便利なアプローチ法があるわけではない。まずは徒手空拳(としゅくうけん)のまま向き合い、それから手持ちの札と技をなんとかやりくり活用して応答する。(中略)それはきれいごとではなく、応答が遭遇から「はじまってしま」ったら、あらゆる契機を「資源」として動員して臨まざるを得なくなるのである。(425~426ページ)
共鳴/自前の思想は「徒弟化しない」
喫緊の課題との「遭遇」に始まり、あらゆる契機を資源として「動員」する必要が生じた自前の思想は、「徒弟化しない」という点がきわめて特徴的である。徒弟的に見える面があったとしても、それは学問的な技法の習得に限られている。(426ページ)/遭遇する事態や人々が異なり、動員できる資源が異なっている私たちが、先人の方法だけを模倣することに意味があるはずもない。徒弟化せずに自前の思想でやるしかないのは、かつても今も変わらないであろう。(429ページ)/(本書で取り上げたひとびと・応答者たちは:阪野)それぞれの現場(フィールド)で、他の現場で応答するひとびとのあり方に励まされ、自らの糧ともしていったのである。なので、自前の思想の応答者は徒弟化しない。ただ異なる状況にある応答者同士で共鳴するのである。(430ページ)
〇筆者は人類学や民俗学については全くの門外漢である。「10人の先達」に関しても、石牟礼道子の『苦海浄土―わが水俣病』(講談社、1969年1月)、中根千枝の『タテ社会の人間関係―単一社会の理論』(講談社現代新書、1967年2月)、『タテ社会の力学』(講談社学術文庫、2009年7月)、『タテ社会と現代日本』(講談社現代新書、2019年11月)、梅棹忠夫の『知的生産の技術』(岩波新書、1969年7月)、川喜田二郎の『発想法―創造性開発のために』(中公新書、1967年6月)、『続・発想法―KJ法の展開と応用』(中公新書、1970年2月)、宮本常一の『忘れられた日本人』(未来社、1960年1月。岩波文庫、1984年5月)、などのベストセラーとなっている本を読んだだけである。また、[1]に描かれている10人の人生と仕事については、スケールがあまりにも違いすぎ、想像だにできない。そんななかで、あるいはそれゆえに自分の浅学菲才さを恥じるのみであるが、「まちづくりと市民福祉教育」のフィールドワークに多少とも関わってきたものとして、[1]から認識を新たにする点は実に多い。
〇ここでは、宮本常一に関する次の一節だけをメモっておくことにする。そこには、「強い『地域主義』『反中央集権』『反官僚主義』の姿勢があり、(宮本は)現地と協働しながら生活改善と経済振興を図るという点でまさしく応答するフィールドワークの実践者」(11ページ)であった。
「外国の文化を受け入れるような素地を国の中へ作っていかなきゃならないんじゃないか。(中略)つまり外国の人たちがやってきて、安(やす)んじておられる場所だろう。それじゃあ、向こうの習俗をすてないで、日本人の生活の中に入り込み、ともに生活できるような場があったかっていうと、ないだろう。これが、やはり、君たちのやらなきゃならん仕事の一つだ。」
「僕の夢は、はっきり言うとね、地域主義なんだよ。それが昔から夢だったんだ。百姓のせがれだったからね。大事なことは、地域社会というのは立派に成長してゆかなければならないんだ。地域社会が充実してくると、世の中がにぎやかになるんだね。それぞれの地域社会が生き生きしてくることが、世の中で一番おもしろいんで、もういっぺん地方が中央に向かって、反乱をおこさなきゃいけないと思うんだ。世の中が変わってゆくのは、いつも、田舎侍が町に向かって反乱を起こすことなんだよね。」
「それが無くなったらね、国っていうのは滅びるんだろう。今はもう、完全な中央集権時代。しかしそれをもういっぺん、ぶっこわしてね、人間が生きるっていうことはどういうことなんだっていうことを問いつめていく。どうじゃろうそれを君たち、やってみないかね。なあ、やろうや。」(鼓童文化財団2011:62-63)(358ページ)
〇この一節にあるのは、「地域が大きなものの力に組み込まれ、それへの従属を余儀なくされ、自主性が削(そ)がれ挑戦へのエネルギーが失われていくことへの危機感であろう。こうした社会の動きに対して(宮本の)その姿勢は戦闘的であり、(中略)アナーキーさを感じさせる」(359ページ)。留意しておきたい。
〇また、宮本がいう「君たち」とは、若いフィールドワーカーのことである。宮本は、フィールド(現地・現場)でワーク(仕事・作業)する人に対して、「地域のよどみや人びとのしがらみに風穴をあけていく存在や力」(368ページ)として期待したのである。
〇なお、筆者の手もとに、佐高信・田中優子の対談本『池波正太郎「自前」の思想』(集英社新書、2012年5月。以下[2])という本がある。[2]は、「辛口評論家と江戸研究家の最強コンビが、『鬼平犯科帳』『剣客商売』『仕掛人・藤枝梅安』など池波正太郎のヒット作はもちろん、池波自身の人生をも読み解きながら、これからの日本人に相応しい生き方を共に考える」(カバーそで)本である。佐高と田中は次のようにいう。参考に供しておく。
自前の思想とは、つまり、迷ったり、遊んだりしながら、一人前になることをめざす思想ということである。(佐高、191ページ)
「自前」という言葉は「手前」と同様に空間を表現している。畳に手をついて頭を下げる。その手の身体側が自分、つまり自らの「分」であり、手前である。その自らの空間に全てを引き受けるのが、「自前で生きる」ことだ。(田中、192~193ページ)/自前の思想で重要なのは「他人と比較しない」ことなのである。比較するには比較の基準が必要だが、自前という空間には、共通の基準がない。(193ページ)/自前が、ありとあらゆることを引き受けつつ、社会における己の姿勢を練り上げていく楽屋空間(プライベートの空間:阪野)だとすると、そこは「あそび」の空間(童心にかえる、楽しい空間:阪野)でもあるはずなのだ。(193ページ)
〇筆者の手もとにもう一冊、伊藤幹治著『柳田国男と梅棹忠夫―自前の学問を求めて』(岩波書店、2011年5月。以下[3])という本がある。[3]は、「ミンゾク」学者で「一国民俗学」を構築した柳田国男と「比較文明学」を開拓した梅棹忠夫を比較しながら、ふたりの知の営み(業績とその特色など)を数々のエピソードをまじえて回想・整理した「柳田・梅棹論」である。「ふたりの知のスタイルは、幅広く多くの文献を参照しつつ、西洋の学問に依存するのではなく、自らの頭で仮説を構築して思考することだった」(カバーそで)。その点(「自前の学問」)をめぐって、次の一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。
柳田国男と梅棹忠夫のふたりの知のあり方には共通した点がいくつかある。
ひとつは、柳田国男も梅棹忠夫も、欧米の学問をまるごと輸入し、その理論を日本の社会や文化の研究にそのままあてはめるのを忌避したことである。/ふたりは欧米からの借りものでない、「自前の学問」を構築しようとしていたのである。柳田が「明日の学問」とよんだ民間伝承論(一国民俗学)(中略)の特徴は、この国の農山漁村に埋もれているさまざまな民間の伝承を文字に記録し、その記録をとおして「自前の学問」を構築しようとした点にある。/梅棹もまた、(中略)柳田と同じように、自分の目で見、自分の耳で聴き、自分のからだで感じ、自分の頭でたしかめた経験的事実にもとづいて構築した「自前の学問」を高く評価したのである。そして、これを「土着の学」とよんでいた。/こうした「自前の学問」を求めた柳田と梅棹の一貫した姿勢は、いずれも揺るぎない実証的精神に支えられたものと思うが、このことはややもすれば欧米の人類諸科学の理論に魅せわれるわかい世代の研究者に警鐘を鳴らしているとみてよかろう。
いまひとつは、柳田国男も梅棹忠夫もひろい視野に立って「日本とはなにか」という重い課題と真摯(しんし)に向きあっていたことである。/柳田は一国民俗学を構築するために、他者としての世界の諸民族の文化を視野に入れ、自己としてのこの国の民俗文化(フォークロア)を手がかりにして、「日本とはなにか」という問い対する答え求めたが、梅棹もまた日本文明論を開拓するために、他者としての世界の諸文明と対比して自己としての日本文明を相対化し、「日本とはなにか」という問いに対する答えを求めている。/ふたりの日本研究は、(中略)視野のせまい「一国完結型」の日本研究に再考を迫っている。
もうひとつは、柳田が構築した一国民俗学も梅棹が開拓した日本文明論も、ひとしく仮説の構築を特徴としていることである。/梅棹が(は)科学には実証的事実の蓄積(実証性)、その内的関係をみやぶる洞察力、発想力(仮説性)、全体をおおう論理的体系化(体系性)という三つの要素があると述べ、柳田の学問には仮説の構築とその検証が繰り返されている。(中略)自分の学問を実証性と仮説性のまんなかに位置づけた。(中略)柳田が膨大なデータを駆使して綿密な実証と仮説の構築につとめたことはよく知られているが、梅棹もまた(中略)洞察力に富んださまざまな仮説を提出している。/興味深いのは、柳田も梅棹が提起した仮説のほとんどが、いずれも個々の短い論文のなかに提示されていることである。ふたりは仮説を提示するために、さまざまな論文を書きつづけていたことになる。(180~183ページ)
柳田国男と梅棹忠夫には、一国民俗学と日本文明論以外の知の営みにも共通した点がいくつかある。
ひとつは、柳田と梅棹が後進の研究者やわかものたちと積極的に交流し、自宅の一部を開放して彼らと自由に議論する「私的な場」を提供したことである。
いまひとつは、柳田も梅棹も後進の研究者やわかものと「対等な関係」を結んでいたことである。
もうひとつは、柳田も梅棹もわかりやすい文章を書くことに精力を傾注していたことである。(中略)(それを)ひとことでいえば読者と「密度のあるコミュニケーション」を大事にしたからであろう。
最後に、柳田国男と梅棹忠夫が国際共通語のエスペラントに関心を寄せていたことを指摘しておこう。(183~185ページ)
〇この一節ではとりわけ、①人々の生活はその人が生まれ育った時代と社会のなかで営まれ、生活の主体性はそれを生み出す歴史的背景や社会的・文化的基盤の枠内で形成される。借り物理論ではなく、「自前の理論」が重視されるべき根拠がここにある。②フィールド(現場)での実践的研究には仮説探索型の研究と仮説検証型のそれがあるが、この両者を循環的に組み合わせて相互作用を引き起こすことによって、研究の科学性を担保することができる。その実践が科学的であるかどうかはこの仮説性が重要となる、この2点を押さえておきたい。
【初出】
<雑感>(173)阪野 貢/フィールドワークと「自前の思想」、そして「自前の学問」:時代と社会に「応答」すること ―清水展・飯嶋秀治編『自前の思想』のワンポイントメモ―/2023年3月24日/本文
16 「生きづらさ」の正体
<文献>
(1) 中西新太郎『〈生きにくさ〉の根はどこにあるのか―格差社会と若者のいま―』(前夜セミナーBOOK)特定非営利活動法人 前夜、2007年3月、以下[1]。
(2) 湯浅誠・川添誠編『「生きづらさ」の臨界―“溜め”のある社会へ―』旬報社、2008年11月、以下[2]。
(3) 香山リカ・上野千鶴子・嶋根克己『「生きづらさ」の時代―香山リカ×上野千鶴子+専大生―』専修大学出版局、2010年11月、以下[3]。
(4) 岡田尊司『「生きづらさ」を超える哲学』(PHP新書)PHP研究所、2008年12月、以下[4]。
(5)小山真紀・相原征代・舩越高樹編『生きづらさへの処方箋』ナカニシヤ出版、2019年2月、以下[5]。
〇「生きづらさ」という言葉や概念が使われるようになって久しい。藤野友紀(教育学)によると、「生きづらさ」という言葉が用いられたのは、雑誌記事検索で調べてみると、1981年の日本精神神経学会総会において「主体的社会関係形成の障害と抑制」として語られたのが最初である。2000年以降、「生きづらさ」などをタイトルに掲げる論考は一挙に増え、その学問的・実践的分野や領域も確実に拡がっている(藤野友紀「『支援』研究のはじまりにあたって―生きづらさと障害の起源―」『子ども発達臨床研究』創刊号、北海道大学、2007年3月、46ページ)。
〇「生きづらさ」の近接・関連用語に「障害」や「バリア(障壁)」がある。「障害」についてWHO(世界保健機関)は、2001年5月、ICIDH(国際障害分類)に変えて人間の生活機能と障害の分類法としてICF(国際生活機能分類)の考え方を提唱した。それは、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元と「環境因子」「個人因子」の2つの因子によって構成されている。「バリア(障壁)」は、一般的には「物理的バリア」「社会的バリア」「制度的バリア」「心理的バリア」の4つに分類される。周知の通りである。
〇「生きづらさ」という用語や概念は曖昧である。しかもそれは、子ども・青年や貧困者、高齢者、障がい者などに固有のものとして、個人的・主観的な心情や問題・課題として捉えられることが多い。しかしそれは、モラルハザード(道徳性や倫理観の混乱・欠如)によるものではなく、現代日本の社会構造(現代資本主義)の政治的・経済的・社会的そして歴史的な欠陥や矛盾によるものである。その欠陥や矛盾は、1990年代、2000年代以降、なんら解決・解消されることなく、むしろ多様化・多層化・多元化が進んでいる。2016年3月に施行された安全保障関連法や2018年12月に発効した環太平洋パートナーシップ(TPP)協定(経済連携協定)などによる現代版「富国強兵」政策が推進される“いま”においても、である。
〇「生きづらさ」とは、社会や組織のなかに自分の「居場所」(「要場所」)が見つからず、将来(あす)への希望や展望をもつことができない生活上の困難や不利益を被(こうむ)っている社会的排除の状態をいう。
〇「生きづらさ」は、一人ひとりが抱える困難・不利益や不安・不満を自己責任に「内閉化した問題」や「他者との関係性」の歪(ゆが)みなどとして、複雑で多面的な様相を呈している。貧困のなかで思考や意欲までも奪われる人(湯浅誠「意欲の貧困」)や、社会や組織・集団における人間関係をうまくつくれない人などが思い起こされる。そうした人たちは、社会(財界)が求める制度やシステムによって選別・分断され、排除されている。
〇“いま”求められるのは、「生きづらさ」の正体を暴(あば)き、その今日的現状をあぶり出し、その解決策(社会参加支援や居場所支援などの社会的包摂支援)を探求することである。それは、対症療法的な単なる処方箋ではなく、「下から」のまちづくりや地域・社会改革を志向するものでなければならない。その担い手は言うまでもなく、「生きづらさ」のなかにいる一人ひとりの住民・市民であり、社会的・政治的アプローチを行う支援者や組織・団体である。そこでは、表面的な同情や共感ではなく、真の連携や共働のあり方が厳しく問われる。
〇「生きづらさ」や「生きにくさ」をタイトルにした本は、筆者(阪野)の手もとには5冊しかない。以下がそれである。
(1) 中西新太郎『〈生きにくさ〉の根はどこにあるのか―格差社会と若者のいま―』(前夜セミナーBOOK)特定非営利活動法人 前夜
「苦しいけれど声が出せない日常を生きるのが若い世代の状態である」(5ページ)。本書は、その「生きづらさ」や「現代日本の抑圧構造」を確かめ、検証するために行われたセミナーの記録を中心に編まれたものである。国家主義と新自由主義とを合体させた政治体制のなかで、「まさか生存権が保障されないはずはない、という思いこみは通用しない。生きづらいと思うことさえ許されない抑圧状況はいっそう深く、広く、この社会に進行している」(6ページ)と中西新太郎(社会哲学)は説く。
(2) 湯浅誠・川添誠編『「生きづらさ」の臨界―“溜め”のある社会へ―』旬報社
本書は、社会活動家である湯浅誠と川添誠が「現代日本の生きづらさ」をテーマに、本田由紀(教育社会学)、中西新太郎(社会哲学)、後藤道夫(社会哲学)の研究者と行った鼎談を纏(まと)めたものである。湯浅は言う。「結局、私たちは『NOと言える市民・労働者・消費者になろう』と呼びかけたいんだ、と最近よく思います。こんな政治家はいらない、そんな非人間的な労働はしない、そんな商品は買わない、と個々の場面で人間(生)・労働・商品のダンピングに否をつきつけられる社会にしたい。それが言えるなら、そしてそれを言っても孤立しない、大丈夫だと感じられるようになれば、この社会の『生きづらさ』は相当程度軽減するだろう、というのがわたしの見通しです」(9ページ)。
(3) 香山リカ・上野千鶴子・嶋根克己『「生きづらさ」の時代―香山リカ×上野千鶴子+専大生―』専修大学出版局
「現在確かに『生きづらい』状況が、人間の内側(こころ)にも外側(社会)にも蔓延している」(荒木敏夫、8ページ)。本書は、「生きづらさのゆくえ」をテーマにした講演とシンポジュウ、それを聞いた学生たちの座談会の記録である。講演では、香山リカ(精神科医)が「生きるのがしんどい、と言う若者たち」、上野千鶴子(社会学)が「ネオリベ改革がもたらしたもの」について「こころ」や「社会」の問題を解きほぐす。
(4) 岡田尊司『「生きづらさ」を超える哲学』(PHP新書)PHP研究所
親と折り合いが悪い人、いわれのない不安に悩む人、心に空虚感を抱えている人、「絆」に縛られている人、自分が何者かわからない人、生きる意味が見つからない人。「生きづらさ」を抱える人が増えている。アルツール・ショーペンハウァー(ドイツの哲学者)、ヘルマン・ヘッセ(ドイツの詩人・小説家)、サマセット・モーム(イギリスの小説家・劇作家)らの生き方や岡田尊司(精神科医)自身の豊富な臨床経験を通して、「生きづらさ」を乗り越え、自分らしく生き抜くための哲学を描き出す。それが本書である。岡田は最後に言う。「生きるための哲学は、生きようとする営みのなかにこそある」(253ページ)。
(5) 小山真紀・相原征代・舩越高樹編『生きづらさへの処方箋』ナカニシヤ出版
本書は、京都大学のメンバーを中心に2014年に立ち上げた共同研究による、「生きづらさ学」からの実践的アドバイスの本である。そこでは、「過保護,性差、外国人差別、発達障害など、学生生活をメインに想定した種々の『生きづらさ』を分野横断的に分析し、克服の具体的方法を提示する」(「帯」より)。その際の「処方箋」(ヒント)は、臨床現象学をはじめ、社会学、法哲学、文化人類学、防災学、障害学生支援、精神医学、環境分析など、まさに分野横断的・俯瞰的視点に基づいている。「生きづらさ学」は「生きづらさの横軸」を探す学問であり、「生きづらさの共通性」や「他者との関係性」に留意する必要がある、と言う。
〇さて、本稿ではまず、[1]において留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
困難の内閉化と「自己責任論」
被害を被(こうむ)っている側に「自分に責任がある」と感じさせてしまう、つまり困難を内閉化させる抑圧様式は日本社会にいたるところで蔓延(まんえん)している。(中略)一人ひとりが抱える困難をその人の内側へと閉じこめる強烈な力がはたらいている。私には異議を申し立てる権利があると言わせない、封殺する力である。責任を偽装すると言ったほうが正確であるが、これは、きわめて深い抑圧の姿である。(58ページ)
このようなレトリック(表現の仕方)や自分に責任があるという感じ方を導く有力な言説として「自己責任論」がある。(中略)抑圧された者たちを徹底的に無力にしていく思想的回路として、自己責任論をとらえる必要がある。(59ページ)
自立支援と「生存権」の損壊
(近年の「自立支援型政策」にいう)政策言語としての「自立」は、公的・社会的な支援に頼らずに自己責任で生きていくという意味である。(128ページ)
「権力」と「社会的無力」という不平等な関係を含んだ(自立―依存関係)が「自立」のあるべき姿として押しつけられている。(128ページ)
生存権を保障する政策は、事情があって自立できない人たちが対象であるが、自立支援型の政策では、「自立」の見込みや「意欲」の有無という新たな尺度で対象者を再分類する。(129ページ)
生存権を平等に保障するという考え方が崩れると、どのような結果が表れるか。意欲や見込みのあるなしは、権力者によって認定・選別されるから、保障を得るには、自分は意欲も自立の見込みもない「真の弱者」だと認めなければならない。(129ページ)
つまり、自立できない存在は完全に無力であるとされ、自立できぬ以上他の人よりも低い処遇に甘んじるよう社会的に強制される。「国家の慈悲によってはじめて人権を保護される」存在になる。19世紀に福祉国家の観念が出てくるまで通用してきた「残余的福祉」という考え方である。(129ページ)
「自立支援」は、「真の弱者」をあぶり出し、同時に、自立してがんばろうと思う者を「貧困な自立」の状態に固定していく、という結果を招くのである。(中略)「自立支援」という政策を使って絶対的な貧困を受け入れさせる、生存権損壊(そんかい)のスパイラル(螺旋〈らせん〉)が出現するのである。(130ページ)
〇次に、[2]において留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「自己責任論」と「生きづらさ」
「生きづらさ」の問題をつねに社会的次元で捉えようとするわたしたちの立場からすると、どうしても必要になるのは、現状を丁寧にあぶり出していくことで、自己責任論からの転換を図ることである。(湯浅、6ページ)
大きなレベルで自己責任論を批判することは、ある意味では易(やさ)しい。構造改革や新自由主義といった用語をもち出せば、何かが言われ、何かがわかったような気がしてくる。しかしそのことと、目の前にいる一人ひとりと向き合い、対応することが切り離されていたら、総論としては自己責任論を大いに批判する人が、各論ではその子・親族・友人にたいして自己責任論を振り回す、という悲喜劇が起こらないとはかぎらない。残念ながらそれは随所で起こっている。そうなると、現実には貧困状態に追い込まれていく人たちの数は減らない。自己責任論批判が増えていったとしても、現実の場面では、個々に切り捨てられていくからである。(湯浅、6~7ページ)
「自立」が強いる「生きづらさ」
貧困者(貧困のなかにいる若者)にとって、「自立」は存在しえない。ところが、(中略)(彼らは)つねに“社会”から“家族”から「自立」を迫られている。「いつまでもフラフラしていないで、まともな仕事について早く一人暮らしをしなさい」と。彼ら自身の仕事は、本人の選択によるものとされ、彼らが抱える困難は「自己責任」によるものとされる。彼らにとっては、「自立」は目標でありながら、自分自身を締め付ける抑圧の言葉である。(河添、19ページ)
「自立」をめざせばめざすほど、彼らは非人間的な労働環境への順応を要請される。しかしながら破壊された労働環境は、彼ら自身を安定的に「自立」させるようなものではないから、破壊された労働環境によって今度は労働者の精神状態が不安定になっていく。貧困と「自立」は両立しえない。(河添、19ページ)
このように、貧困のなかにいる若者は、「自立」しようにも「自立」しようがない。貧困を根絶していくことなく、「自立」を促すことはありえない。(河添、19ページ)
「強い市民社会」と“居場所”づくり
「強い市民社会」というのは、弱肉強食の市場原理にたいしてきちんと歯止めをかけられる社会、人間の弱さを認めて受け止められる社会、弱さの認識から相互扶助・社会連帯の必要性の認識を通じて、「市場」とは異なる「社会」を構想できる社会、を言う。そういう「強い市民社会」が確立していれば、社会制度はおのずと変わっていくはずである。(湯浅、174~175ページ)
「意義申し立てする社会連帯」というのは、「これはおかしい」ということを話し、数人なり、数十人のグループができれば、それでもって社会的に訴えていく、それが当たり前に行なわれるような、そういう社会的な雰囲気をつくっていきたい。(湯浅、175ページ)
「強い市民社会」をつくるうえでの(労働)運動論的なポイントは、(中略)究極的には“居場所”である。つまり、不満を言い合って、「おかしい」と思ったことをかたちにできる場所である。(河添・湯浅、177ページ)
社会に向けて発言ができたり、ただその場にいるだけでもお互いが尊重される安心感・信頼感を感じられる空間としての“居場所”が大事だと思う。(湯浅、178ページ)
「たたかうためには、たたかわなくていい“居場所”が必要である」。(中略)たたかわなくていい“居場所”は、たたかうための必要条件みたいなものである。(中略)そういう“居場所”が社会のなかから減ってきている。(湯浅、179ページ)
〇いまひとつ、[3]において留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「非行から自傷へ」と「ネオリベ改革」
社会学では社会というのは、個人の集まりではなく、ふるまいの集合である。(中略)人々のふるまいの集合に一定の規則があるから、その行動がなにを意味しているかがお互いにわかるおかげで成りたっているのが社会というものである。(上野、57~58ページ)
(1980年代から90年代頃から)いわゆる青年期の逸脱といわれるものが(中略)変化してきた。それを簡単に言うと、非行から自傷へ、である。他人を傷つけることから、自分を傷つけることへの変化である。(中略)攻撃衝動というものが、他者から自己へ向かっているのではないか。何か困ったことが起きたときになんでこんなことが起きたのか、誰が悪いのかと思ったときに「私が悪い」というしかないから、生きづらい思いをするのである。これを、「私が悪い」という代わりに「貧乏が悪い」、「社会が悪い」、「学校が悪い」、「先生が悪い」、それから「資本家が悪い」とか言えたらラクである。(上野、64~65ページ)
それなのに、誰も自分以外の人を悪いと言えず、責めることができないために、自分自身を責めるほかない。それで攻撃衝動が我と我が身(われとわがみ)に向かう。なぜそういうことが起きたのか? (それは社会学者によると)「社会が変わったから」(中略)社会環境やルールが変わったからである。(上野、65ページ)
(その一つが)いわゆる「ネオリベ改革」(「ネオリベラリズム」つまり「新自由主義」改革)と言われるものである。(上野、66ページ)
ネオリベこと新自由主義とは、ごく簡単に言うと市場万能主義のことである。公平な競争のもとで勝ち負けを争って、勝ったら勝者の能力と努力のおかげ、負けたら敗者の無能と怠惰のせい。そういう「自己決定・自己責任」の原理をさす。規制緩和をして勝者が残り敗者は退出する市場の原理に委(ゆだ)ねたほうが、財の最適配分ができるようになるという考え方のことである。(上野、67ページ)
「生きづらさ」と不安
「生きづらさ」の精神構造は、不安と似ているのである。あるいは「生きづらさ」の原因は漠然とした不安感なのではないかとさえ思う。自分自身が何者であるかの不安、自分の将来や可能性にたいする不安、人が自分をどう見ているのかについての不安、この社会の先行きに関する不安、そうしたもろもろの不安が、私たちの精神や生活を脅かし、「生きづらい」感覚をもたらしているように思えてならない。(嶋根、209ページ)
不安そのものを完全になくすことはできない。しかし不安に直面したとき、その原因が何に由来しているかを知れば、不安はやわらぐものである。同じように、私たちが何となく感じている「生きづらさ」も、他の人や他の社会と引き比べてみたり、その原因が私たちの外部にあることを知ったりすることで、「生きづらさ」の感覚を多少なりとも乗り越えていくことができるかもしれない。(嶋根、209~210ページ)
〇以上の諸言説のなかで、河添の「貧困者にとって、『自立』は存在しえない」「貧困と『自立』は両立しえない」([2]19ページ)という言葉から思い出すことがある。1956年11月から1963年7月にかけて、岸勇(当時・日本福祉大学)と仲村優一(当時・日本社会事業大学)との間で、公的扶助とケースワークの位置づけをめぐって展開されたいわゆる「岸・仲村論争」である。ここでは、その論争に関する加藤園子(当時・立命館大学)の一文を紹介しておくことにする。「今は昔」ではなく、「今も昔(も変わらない)」である。
岸説では「最低生活保障」と「自立助長」をあいいれるものとしてではなく、本来分離、対立したものとして位置づけている。そこでは、公的扶助にケースワークが導入される根拠となった「自立の助長」の意味について、自立の基本的要素は経済的自立であり、自立の喪失が社会的原因にもとづくものである以上、自立は国家の雇用政策によってはじめて助長されるものであること、そして、これに反して公的扶助の目的である最低生活保障それ自体は決して自立を助長するものではありえず、そこではむしろ「自立」という概念が似而非(えせ)なる意味にすりかえられ、その強調は、実は保護の制限と引きしめの意図がその背後に政策的に存在することを厳しくとらえねばならないとしている。そして「自立の助長」と関連して公的扶助にケースワークが導入された目的もまさにその民主主義的体裁によるにすぎず、保護引き締め強化による対象者の人権侵害の事実や公的扶助のもつ救貧法的本性をそれによって隠蔽・合理化することに役立てられてきているとして、仲村説と真っ向から対立することとなった。
(加藤園子「仲村・岸論争」真田是編『戦後日本社会福祉論争』法律文化社、1979年9月、91~92ページ)
【初出】
<雑感>(87)阪野 貢/「生きづらさ」再考―一昔前と変わらぬ“いま”を考えるためのメモ―/2019年7月7日/本文
17 「相互支援」の人間学
<文献>
(1)支援基礎論研究会編『支援学―管理社会をこえて―』東方出版、2000年7月、以下[1]。
(2)舘岡康雄『利他性の経済学―支援が必然となる時代へ―』新曜社、2006年4月、以下[2]。
(3)舘岡康雄『世界を変えるSHIEN学―力を引き出し合う働きかた―』フィルムアート社、2012年11月、以下[3]。
(4)森岡正博編著『「ささえあい」の人間学―私たちすべてが「老人」+「障害者」+「末期患者」となる時代の社会原理の探究―』法藏館、1994年1月、以下[4]。
ケアリングコミュニティとは、「共に生き、相互に支え合うことができる地域」のことである。筆者はそれを地域福祉の基盤づくりであると考えている。/そのためには、共に生きるという価値を大切にし、実際に地域で相互に支え合うという行為が営まれ、必要なシステムが構築されていかなければならない。こうしたケアリングコミュニティは、①ケアの当事者性(エンパワメント)、②地域自立生活支援(トータルケアシステム)、③参加・協働(ローカルガバナンス)、④共生社会のケア制度政策(ソーシャルインクルージョン)、⑤地域経営(ローカルマネジメント)といった5つの構成要素により成立している。(原田正樹「ケアリングコミュニティの構築に向けた地域福祉―地域福祉計画の可能性と展開―」大橋謙策編著『ケアとコミュニティ―福祉・地域・まちづくり―』ミネルヴァ書房、2014年4月、100ページ)
〇いま、その問題意識は必ずしも目新しいものではないが、「我が事・丸ごと」の「地域共生社会」の実現について声高に叫ばれている。それを単なるスローガンに終わらせないためには、またあるべき「地域共生社会」を実現するためには、「相互支援」と「相互実現」についての基本的理解が必要かつ重要となる。
〇筆者(阪野)は、管見ながら、しかもその一部に過ぎないが、人と人が共に生き、共に支え合うこと(「相互依存」interdependence)によって自己成長と相互成長、自己実現と相互実現を促す地域社会、すなわち「ケアリングコミュニティ」(caring community)に関して次のように考えている。(1)地域のあらゆる住民が「安心」して暮らせるまちは、「安全」と「信頼」と「責任」のまちである。安心=安全×信頼×責任、である。(2)まちづくりは、そこに暮らす住民が相互に支援し合う(「相互支援」の)地域コミュニティを創造するために、意識と思考と行動の変革を図ることから始まる。まちづくりは相互支援であり福祉教育である。(3)「自立」(「依存的自立」)は、自己選択と自己決定、そして自己責任に基づく自己実現の過程を通して達成される。それは、個人的なものにとどまらず、歴史的・社会的・文化的状況や背景によって規定される。自立は自己実現のための手段であり、歴史的社会的性格(特徴)を持つ。(4) 自己決定と自己実現は、個人的営為ではなく、自分と他者との相互の認識と行動に基づいた自己成長と相互成長を通じて初めて可能となる。自己実現は「相互実現」である。(5)現在の日本社会では、格差社会や管理社会が進展するなかで、持続可能な相互支援型社会を如何に形成するかが問われている。管理は画一化や受動化を促進し、支援は多様性や能動性を尊重する。地域共生社会は相互支援型社会である。なお、これらとともに、またこれらを可能にするためには、まちづくりや地域福祉についての多様な政策・制度的対応や専門機関・専門家による対応などが必要かつ重要であることは言うまでもない。
〇上記のように、筆者の手もとには、そのタイトルやサブタイトルに「支援」などの文言が含まれている本が4冊ある。本稿では、それぞれの本のなかで論じられている「支援」に関する言説について、筆者なりにいま一度押さえておきたい一節を、抜き書きあるいは要約することにする(見出しは筆者)。それは、「支援」に関する基本的な文献や考え方について知りたいという、熱心なブログ読者からの依頼に不十分ながらも応えるためである。
(1) 支援基礎論研究会編『支援学』東方出版
〇「支援学」(Supportology)は、1993年に発足した「支援基礎論研究会」(オフィス・オートメーション学会〈現・日本情報経営学会〉の研究部会)が7年余にわたる研究活動を通して新しく開拓した学問分野である。「本書は、ハウツーを教える入門書ではなく、広く支援現象、支援行為一般の研究の指針を与えることを目的にした見取り図である」(2ページ)。ここでは、本書に収録されている今田高俊(現在は東京工業大学名誉教授)の論稿「支援型の社会システムへ」における言説について紹介する。
管理型社会システムから支援型社会システムへ
現在、行き過ぎた管理機構のひずみや亀裂が集中的にあらわれ、管理の限界がいたるところで露呈するようになっている。管理を中心とする運営法では、もはや活力ある社会を確保できない状態である。/意義のある人生や生活を築き上げるためには、管理に代わる社会の仕組みが必要である。管理に代わる新しい社会編成の在り方としてもっとも有望なものは支援である。支援型の社会システムへの構造転換をはかることが、現在、さまざまな形であらわれている社会問題を解決するために不可欠である。/1990年代以降、ボランティア活動やNPO(非営利組織)、NGO(非政府組織)による活動活動が高まった。これらの活動は、管理ではなく支援を、市民自身の自発的な意志によっておこなおうとする動きである。(9~10ページ)
支援の定義
支援とは、何らかの意図を持った他者の行為に対する働きかけであり、その意図を理解しつつ、行為の質を維持・改善する一連のアクションのことをいい、最終的に他者のエンパワーメントをはかる(ことがらをなす力をつける)ことである。(11ページ)
支援と自省的フィードバック
支援は、自分で勝手に目標を立てて効率よくそれを達成するという、従来の私的利益の追求行為からは区別される。被支援者がどういう状況に置かれており、支援行為がどう受け止められているかを常にフィードバックして、被支援者の意図に沿うように自分の行為を変える必要がある。これができない支援は本当の意味での支援ではない。(12ページ)
支援と配慮とエンパワーメント
支援をおこなう当事者は、あくまでも自分の生き甲斐や自己実現を得るという動機が前提になっている。この意味では、私的なものである。ただし、この私的性格は、被支援者の行為の質が改善され、被支援者がことがらをなす力を高めることを前提としており、いわゆる利己的な行為ではない。私的な自己実現が、直接、他者に対する気遣い、配慮へとつながっている。要するに、支援には、他者への「配慮 care」と「エンパワーメント」が決定的に重要である。(12ページ)
支援と支援システム
実際に支援が成立するためには、一連の支援行為がばらばらになされるのではなく、それらがまとまりをもったシステムを形成することが必要である。また、支援は固定したシステムではうまくいかない。被支援者が置かれている状況変化にあわせて、システムを変えていく必要がある。/支援システムは、人的・物的・情報的資源を関係づけ、それらが支援を効果的に実現できるようなモデル(ノウハウ)を備えることが重要である。(12~13ページ)
支援学の体系化
20世紀が管理の世紀であるとすれば21世紀は支援の世紀である。今後、管理が消滅することはありえないが、少なくても支援の発想が社会のなかに組み込まれ、肥大化した管理の仕組みを縮小する方向に進まざるをえないだろう。弱肉強食型の競争主義とそのグローバル化が進みつつあるが、これがアナーキー(無秩序)な社会あるいはその反動として管理主義の強化につながってはますます住みにくい世界になる。そうならないためにも今後、支援学を深め体系化していくことが重要である。管理に代わる支援の発想を持って、グローバル時代の共生原理をつくりあげていくことが、われわれの責任である。(234ページ)
〇管理型社会から支援型社会への転換が求められている。支援は、支援者(支援主体)と被支援者(被支援主体)というセットで意味をなす行為であり、①「他者への働きかけ」を前提にして、②「他者の意図の理解」、③「行為の質の維持・改善」、④「エンパワーメント」を構成要素とする。支援には、支援者の「自省的フィードバック」と、被支援者への「配慮」と「エンパワーメント」が重要である。支援の実質化を図るためには、「ヒト、モノ、カネ、情報」などの資源を効果的・効率的に活用し、またそのためのモデル(ノウハウ)を備えることが必要となる。とともに、支援システムを形成し、しかもそのシステムは被支援者の置かれた状況に応じて柔軟・自在に変化・対応する(「自己組織化」する)ことができるものでなければならない。
〇支援学は管理学に対置される。支援学は、社会生活上の諸問題を解決し、被支援者の「エンパワーメント」を図ることによって自己実現が達成され、それを通じて共生社会の創造に貢献することを使命とする。
〇以上が今田の言説、その一部である。注目されるのは、支援の概念に「エンパワーメント」が含意されていることである。そこから、支援が成立するためには、被支援者の意図が優先され、支援者の支援が自己目的化してはならないことになる。今田にあっては、「自分の意思を前面にださない」「相手への押しつけにならない」「相手の自助努力を損なわない」が、「支援に要請される条件」(15ページ)となる。
(2) 舘岡康雄著『利他性の経済学』新曜社
〇本書は、とりわけその前半は、舘岡康雄(現在は静岡大学大学院)の博士論文「”支援”の理論化と実証化に関する研究―利他的なビジネスモデルがもたらす経済合理性―」(東京工業大学社会理工学研究科)がベースになっている。舘岡は1996年から「プロセスパラダイム」の概念を提唱するが、「支援」と「プロセスパラダイム」に関する言説のみを抜き書き(要約)する。
自己中心の「管理」と相手中心の「支援」
管理は、自分から出発して相手を変える、相手をコントロールする行動様式である。それに対して支援は、相手から出発して相手との関わりにおいて自分を変える、自分で(自由意志で)自分をコントロールする行動様式である。/すなわち、管理は自己中心の行動様式であり、支援は相手中心の行動様式である。/したがって、管理の被行為者は「させられている」のであり、支援の被行為者は「してもらっている」のである。(86~87ページ)
リザルトパラダイムからプロセスパラダイムへ
いま時代は、あらゆる分野で「リザルトパラダイムからプロセスパラダイムへ」と動いている。パラダイム(paradigm)とは、その時代に共通するものの見方や捉え方(価値観、枠組み、考え方)をいう。/管理行動では、管理者は計画を提示し、その計画と被管理者の結果とのズレが重要とされる。そこでは、「結果」(リザルト、result)が重視され、管理者と被管理者の関係は「させる/させられる」の一方向の関係にある。管理行動はリザルトパラダイムにおける行動様式である。/支援行動では、支援者は相手の刻々変わる状況を知り、それに合わせて被支援者と相互作用を行ないながら支援を達成していく。そこでは、「過程」(プロセス、process)が重視され、支援者と被支援者の関係は「してもらう/してあげる」の双方向の関係にある。支援行動はプロセスパラダイムにおける行動様式である。(87、88、93~94ページ)
〇以上が舘岡の言説、その一部である。舘岡にあっては、支援はあくまでも支援者の自由意志で行われものであり、支援をするかしないかは支援者に委ねられる。「動員による支援」「支援の管理」「支援の制度化」などは想定されていない。また、舘岡の言説で重要なのは、「プロセスパラダイム」についての提言である(91~97ページ)。相手(被支援者)の動きに合わせて自分(支援者)も動きを変える。また、相手(被支援者)にも自分(支援者)の動きに合わせて動きを変えてもらう。両者が寄り添ってこうした動き(動的な活動)をするとき、その過程(プロセス)で問題解決能力が高まり、両者は「合一の方向に向かう」(100ページ)、とされる。留意しておきたい点である。
(3) 舘岡康雄著『世界を変えるSHIEN学』フィルムアート社
〇舘岡は、民間企業の人事部での経験を踏まえて、2001年から「SHIEN学」を提唱する。本書は、学生やビジネスマンが気軽に読める「SHIEN学の入門書」である。「支援」をあえて「SHIEN」とローマ字表記する意義、「管理」「支援」「SHIEN」あるいは「協働」などの概念の相互関連、SHIEN「学」の学問としての成立要件や理論的枠組みと体系性、などについての言及は必ずしも十分なものであるとは言えないが、要点を紹介する。
SHIENと「お互いの力を引き出し合う能力」
「支援」は上位者が下位者に、力のあるものが力のないものに、施すという概念である。/SHIENは、互いに助け合うことで、重なり(つながり、関係性)のなかったところに重なりをつくり、「してもらう/してあげる」を交換するという、新しい時代の問題解決法のひとつである。/SHIEN学では、相手の力を引き出したり、逆に相手からも自分の力を引き出してもらったりする能力を「してもらう/してあげる能力」と呼ぶ。/SHIENの原理というのは厳密なシステムではなくて、重なりがなかったところに重なりをつくったり、相手からしてもらうことと、こちらがしてあげることを、相互に交換したりすること。ただそれだけである。(13、35、58、155ページ)
「してもらうこと」と「豊かな関係性」とSHIEN学
「してもらう」能力を高めるためには、自分の「弱みを相手に見せること」が非常に大切であり、「相手によい質問をすること」「相手を褒(ほ)めること」も有効である。それによって自分と相手との豊かな関係性を深めることができる。/「してもらう/してあげる」というのはテクニックではなく、非常にいい関係性があるからこそ生まれるものである。志が同じで、ひとつの目標に向かっていく集団があったならば、惜しみなくお互いの能力を出し合っていって、一緒につくるよろこびを感じることが、お互いが幸せになる、何よりの方法である。/「してもらうこと」がSHIEN学のスタートであり、本質である。(60~65ページ)
プロセスパラダイムの時代と競争的共存の時代
これからの、「動いているものを動くままに」捉えるプロセスパラダイムの時代は、今までのリザルトパラダイムの時代の、「善か悪か」「有か無か」「量か質か」「ハードかソフトか」といった二項対立を越えて、新しい解へジャンプすることができる自由な社会である。/そういう時に大切になってくるのは、「してもらう能力」である。新しい時代には「してもらう」ことは必須となる。/苦手なことはしてもらってよいのである。そして自分は、自分の得意なことで相手をSHIENする。また今、競争的共存の時代が来たともいえる。競争しているのだけど、同時に共存してもいるわけで、ひとり勝ちの時代はすでに終わっているのである。/人間関係でいえば、「関係をつくることに積極的」(「関係積極性」)であることが大切な時代である。(82~83、119ページ)
リザルトパラダイムとプロセスパラダイムの違い
20世紀型のリザルトパラダイムと21世紀型のプロセスパラダイムの違いは、図1の通りである。(43ページ)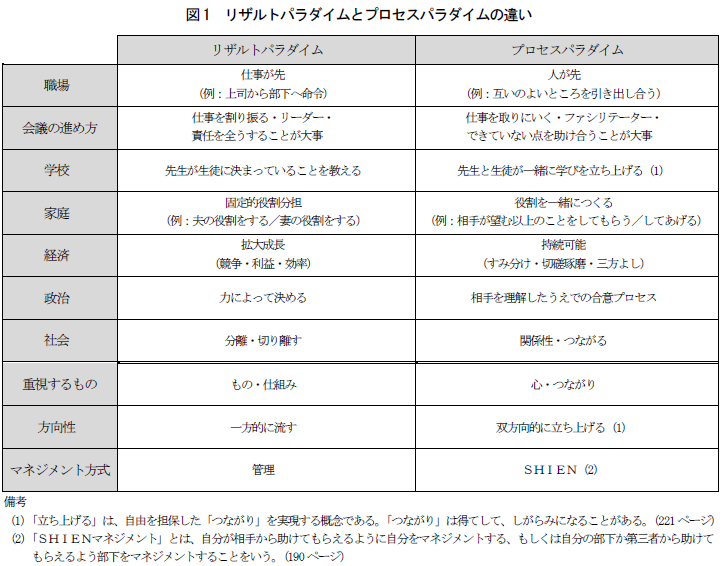
〇以上が舘岡の言説、その一部である。舘岡は、上下関係のなかでの一方向の支援(「施し」)を「支援」、対等な関係のなかでの双方向の支援を「SHIEN」とする。そして、「SHIEN」は、新しい時代(プロセスパラダイムの時代)における、「新しい働きかたを実現する行動原理」(15ページ)となる、という。
〇舘岡にあっては、「SHIEN学」でいう「SHIEN」とは、「自分よりも他人を大事にしたり、助けたりする考え方(=利他性)を軸に、行動を起こすこと全般」(18ページ)を指す。「SHIEN学の本質」「SHIENの神髄」は、「してもらう/してあげる能力」であり、お互いの力を引き出し合うことである。そこで重要になるのが、自分と相手を「つなぐ」こと、「関係性を高め合う」ことであり、舘岡はそれを「重なりをつくる」という。
(4) 森岡正博編著『「ささえあい」の人間学』法藏館
〇本書は、生命倫理や法哲学、仏教哲学などを研究する5人の共同研究のプロセスを纏めたものである。読み応えのある包括的で深淵(しんえん)なテーマ設定がなされているとともに、一般にありがちな共同研究の成果報告でないところがユニークで興味深い。本書の「ささえあいの人間学」とは、人と人が互いに「ささえあって」生きるという形の社会原理を探究し、人々にささえられながら生まれ死んでいく人間の「いのち」のあり方について議論する枠組み(学問)である。ここでは、本書に収録されている土屋貴志(現在は大阪市立大学)の論稿「『ささえる』とはどういうことか」等における言説について紹介する。
「ささえ」と「ささえあい」
人間同士の「ささえ」は、すべて「ささえあい」にほかならないのではないか。というのは、人間は必ず何らかの「他者」を必要とする存在であり、その意味で、完全に自分の力で自立しているわけではないからである。現実の「ささえ」の場面においては、一方向的な「ささえ」(「ささえる」側は自立しており「ささえられる」側は依存するだけであるような状況)が成立しているわけではなく、必ず両方向的な「ささえあい」(双方が「ささえ」「ささえられ」合っているような状況)になっているのである。/人間は何らかの他者を「ささえる」ことによってよろこびを得る存在であり、他者が何も返すことができなくてもその他者によって「ささえられている」ことになるのである。(105ページ)
「ささえる」と「ともにいる」
「ささえる」ことは、「相手にかかわっていこうとする」ことである。/「かかわり」こそ「ささえ」の基盤であり、かかわりのないところには相手もなく、したがって相手への働きかけもあり得ないからである。その意味で、かかわりを保っていこうとする姿勢こそ何にもまして必要なものであり、なくてはならないものである。/しかも、時間を惜しまず、傍に共にいるということ、この「ともにいる」ということこそ、かかわりの本質を表すことである。/「ともにいる」ということ、かかわっていく姿勢によって「ともにいる」ということを示すことが、「ささえる」ということの最も基本的な事項になるのである。(57~58、60~61ページ)
「かかわり」と「受容」
相手にかかわっていくとは、相手を受け容れていくことである。相手を受け容れる余裕がなければ、かかわっていくことはできない。もしその余裕がないまま無理にかかわろうとするなら、必ずひとりよがりに終わることになる。相手を受け容れるということは、結局のところ、相手に対していろいろな気持ちを抱く自分自身を受け容れることに他ならない。その意味で、いつでも、どんな相手にも、求めに応じてかかわってゆけるようにするには、つねに自分自身をみつめて、あらゆる自分を受け容れる用意が必要である。相手を受け容れる余裕は、実は自分自身を受け容れる余裕から生まれるからである。(59~60ページ)
「ささえ」と「共感」
「ささえ」の根底にあるべき考え方は、「共感」が達成されるように努めるべきである、ということである。/「ささえ」の場面では、「共感」が必然的な前提になっている。/「共感」とは、相手の私的な世界を、あたかも自分自身のものであるかのように感じとり、しかもこの「あたかも‥‥‥のように」という性格を失わないことである。いいかえれば、①相手の体験を、その本人が感じているままに感じ取ること、②相手の体験はあくまでその人自身の体験であり、私自身の体験とは別であるとわきまえていること、この二つの条件を同時に満たすことである。/ただし、「共感」だけで相手を「ささえた」ことにはならない。「こころのささえ」の場面を離れて、相手が具体的な介助や援助や治療を要求している場合には、「共感」の達成だけでは「ささえあい」の達成は不十分なものとなる。(281、290~291、296、299ページ)
〇土屋にあっては、「ささえる」ということについての原則的な考え方のひとつは、「どんな事実であれ、その人に関する事実は第一義的にその人本人のことであって、他の人のことではない」(52ページ)。「事実に直面しそれを受け容れなければならないのはその人自身なのであって、他の人が代わってやることは決してできない」(50~51ページ)ということである。ある事実についての当事者性(「自分のこと」である度合い)について言えば、本人が最も「当事者」であり、身近な人ほど「当事者性」が高く(つまり、より「自分のこと」であり)、身近でない人ほど低い(逆に言えば、「第三者性」すなわち「ひとごと」である度合いが高い)ということになる。しかし、具体的な「ささえ」の場面では、問題になるのはつねにいま現在目の前にいる相手であり、「当事者性の序列」は問題にならない(51~53ページ)。土屋の基本的な言説として押さえておきたい点である。
〇以上の叙述を踏まえて、ここではひとまず、「支援」とは、自分・支援者(支援主体)と相手・被支援者(被支援主体)の「要求と必要と合意」「受容と共感とエンパワメント」に基づいて、「相互支援と相互作用」「相乗作用と相乗効果」「自己実現と相互実現」を図る活動(行動様式)でありプロセスである、と理解しておくことにする。その際、支援者や被支援者は、個人だけでなく、集団や組織、コミュニティ、社会などを含む。「支援主体」や「被支援主体」の意味するところである。
〇ところで、筆者はこれまで、「まちづくりと市民福祉教育」について論考する際に、「共働」(coaction)の概念を重視してきた。また、その構成要素として、①多様な個人や集団・組織・コミュニティ・社会、②目標や価値観の共有化と統合化、③新しい場(ステージ、プラットホーム)の創設、④その場への主体的・自律的な参加(参集、参与、参画)、⑤多面的な相互作用による相互補完や相乗効果、⑥社会的統合や融合の達成、などを考えてきた。
〇図2は、「支援」に留意しながら、多様な主体による「対抗」から「共働」への過程を、ひとつのモデルとして図示したものである。例えば、「対抗」段階では、内部(当事者間)における上下関係や外部(第三者)との対等(並立)な関係における競争、管理、支配を意味している。「連携」段階では、役割と責任の相互確認や協力の相互促進に向けた行動を起こす。「協働」段階では、目標の明確化を図り、舘岡がいう「重なりのなかったところに重なりをつくる」即ち「関係づくり」(パートナーシップづくり)を進め、協同することを意味する。そして、新しく設けられた「場」における相互補完やそれによる相乗効果によって協働の融合・一体化が図られ、相互支援や相互実現が成立する。それが「共働」の段階である。こうした段階の過程を通して、「創発」(単なる総和以上の成果が生み出されること)や「共創」(イノベーションによって共に新しい価値を創り上げること)、「共生」(すべての人の人格と個性を尊重し、共に支え合いながら共に生きること)が実現することになる。
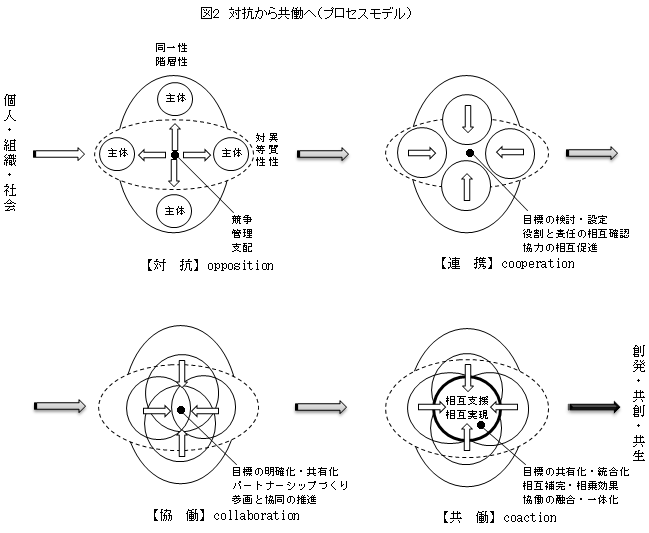
〇筆者が本稿で言いたいのは、「相互支援」と「相互実現」、そのための「共働」が「地域共生社会」の神髄である、ということである。
注
上野谷加代子(同志社大学)は、人が共に支え合って生きていくためには「助け上手と助けられ上手」になることが大切である、と説く(『たすけられ上手 たすけ上手に生きる』全国コミュニティライフサポートセンター、2015年8月)。森岡正博(早稲田大学)は、人間は他からささえられてはじめて生活でき、自己決定できる存在であり、「他からささえられ、他をささえてゆく」ことこそが「人間」の本質である、と言う(森岡正博「序 方法としての『ささえあい』」森岡正博編著『「ささえあい」の人間学』20ページ)。あえて可視化するほどのことでもないが、「ささえあい」(「ささえる」ことと「ささえられる」こと)の諸相について、例示的(上位と下位、優位と劣位)に図3に示しておく。
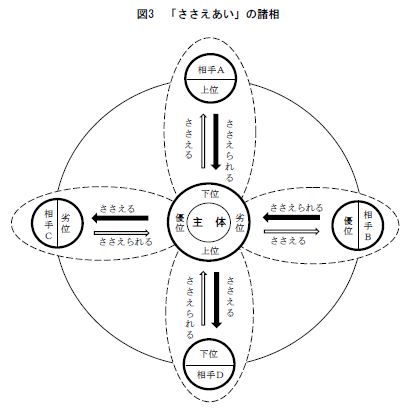
【初出】
<ディスカッションルーム>(68)阪野 貢/「支援学」ノート―「相互支援」「相互実現」に関する基本的な視点/追補:大橋謙策「『我が事・丸ごと地域共生社会』とコミュニティソーシャルワーク機能」―/2017年6月1日/本文
18 「ふつう」の功罪
<文献>
(1)深澤直人『ふつう』D&DEPARTMENT PROJECT、2020年7月、以下[1]。
(2)佐野洋子『ふつうがえらい』(新潮文庫)、新潮社、1995年3月、以下[2]。
(3)泉谷閑示『「普通がいい」という病』(講談社現代新書)、講談社、2006年10月、以下[3]。
(4)キリーロバ・ナージャ『6ヵ国転校生・ナージャの発見』集英社インターナショナル、2022年7月、以下[4]。
(1)「ふつう」は私とあなたの「あいだ」にある
私は、周りのあなたとの類似性を重視し、そこに安寧や安心を感じる。
私は、周りのあなたとの相異性に緊張し、そこに不安や劣等感を感じる。
(2)「ふつう」は私とあなたの「ふだん」にある
私が「ふつう」を意識するのは、日常の生活場面においてである。
しかもその現実の場面は、生活と人生のひとコマに過ぎず、常に変化する。
(3)「ふつう」の隣に「特別」がある
私には社会的に許容される独自性欲求があり、それが自尊感情を高める。
その一方で、社会意識である孤独感や差別意識・偏見を生む。
(4)- ➀ 私は「ふつう」を求め、あなたを「ふつう」にさせる
私は、人並みを求め、周りから目立つあなたを攻撃する。
それが窮屈で、生きづらい地域・社会をつくる。
(4)-➁ 私は「ふつう」を捨て、あなたと「わがまま」をいう
私は、生き方や価値観を変え、あなたと権利や不満を主張する。
それが地域・社会を革め、豊かな未来を切り拓く。
〇上記のようなことを思いながら、深澤直人(ふかさわなおと)の『ふつう』(D&DEPARTMENT PROJECT)と佐野洋子の『ふつうがえらい』(新潮文庫)を読んだ。深澤は世界的に有名な(身の回りにあるさまざまな製品をデザインする)プロダクトデザイナーである。深澤のデザイナー活動のテーマや哲学は、「ふつう」という概念にある。それは、「ふつう」という価値が日本人の生活の根底をなすことによる。[1]は、その「ふつう」について雑誌に15年間にわたって連載したコラムを書籍化したものである。佐野(1938年~2010年)は、絵本作家、エッセイストであり、代表作に絵本『100万回生きたねこ』(講談社、1977年10月)がある。[2]には、佐野が自分を「生きる」ことの思いや行動を装飾のない「なま」の文章に乗せた73篇のエッセイ(「世間話」)が収められている。それらは単純明快で、歯に衣着せぬストレートなところが面白い。
〇[1]では、「ふつう」の良さに気づき、「ふつう」は「日常のあたりまえに通り過ぎる出来事を自覚したときに感じるもの」(26ページ)であるという思いに至る。そんななかから、筆者が留意したい一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
知識の世界とリアルな世界の「ふつう」 ―経験に基づくリアルな世界の「ふつう」が人間を幸せにする―
頭で勝手に思い込んでいるものと、目で見ているものの形は違う。人間は実際にそのものを目の前にして見ているときでさえも、思い込んだ形をしているように捉えてしまう。極端な言い方をすれば目に見えるすべてはその人の概念であって先入観が成す世界なのかもしれない。先入観を成すものは経験なしに得た情報である場合が多い。デザインをしていると二つの世界の存在が見えてくる。一つは他から得た情報とその集積の知識が成す世界。これを「常識」とか「ふつう」とか言うのかもしれない。もう一つは先入観なく見た、あるいは感じたそのままの世界。経験から得た情報とその集積としてのリアルな世界である。これも言ってみれば「ふつう」である。人間はこの二つの世界観と二つの「ふつう」を持ち合わせ、そこを頻繁に行き来している。人は後者のようなリアルな「ふつう」に出会ったとき、自己の思い込みや先入観に気付き、「あ~、な~んだ、これもふつうなんだ」などと安心したり、驚いたりしていい気持ちになる。身体は常にリアルに触れているのに、思考は与えられた情報を信じている。だから既に触れていた感触を何かによって自覚させられたとき、はっとするのだ。(中略)リアルな世界の「ふつう」に触れたとき人間は幸せになる。(52~54ページ)
「変える」ことと「変えない」デザイン ―デザインはしっくりいっていないことを正し、改善することである―
長く使われてきたものは、もう生活の分子になっているから簡単に変えようとしてはいけない。「保守的」といわれるかもしれないが、「保守」ということばには二つの意味がある。一つは、「正常な状態を保つこと」。もう一つは、「旧来の風習・伝統・考え方などを重んじて守っていこうとすること」。それは、まさしく長い年月を経て「ふつう」になってきたことを「ふつう」のままにしておこう(と)することだと思った。保守の反対は革新で、その意味は旧来の制度を改めて新しく変えることである。制度を改革するのであって、よいものを新しく作ることとは違う。変えるのではなく、しっくりいっていないことを正し、改善すること。デザインは「変える」こととか「新しく」作ることだと思い込んでいる人は少なくない。そういったデザインの一般論に反抗して「変えない」ということは易(やさ)しくない。「自分のデザイン」というような気持ちを捨てなければならない。でも、そうやっていいものを継承して現在の生活に合わせて少しずつ直していこうとすれば、いつか自然に新しいものがぽろっと生まれる時がある。新しいのに、ずっといいものと繋がっているようなものができる時がある。(201~203ページ)
「美しい」と「いい雰囲気」をつくるデザイン ―デザインは暮らしという全体の「雰囲気」をつくることである―
椅子や家具をデザインする時も、心がけるのは、もはや「形」とか「自己表現」などでは、毛頭ない。いい雰囲気を醸(かも)し出す物かどうか、を問いながら、私はデザインする。(中略)いい雰囲気とは、調和の事かもしれない。(中略)「綺麗」とか「美しい」という事は、それがよい物かどうかを決める、最も重要な事ではない。「雰囲気がいい」事のほうが上である。物が、単一で美しい、などという事など、ないのだ。雰囲気を醸し出す物でなければ、「いいデザイン」とは言えない。新しければいい、などという事はデザインの基準ではない。/「いい感じ」を醸し出す物が、「いい雰囲気」をつくる。デザイナーは、物だけをデザインしてはいられない。暮らしという全体の「雰囲気」をつくらなければいけない。結局は、空気をつくるのだ。(310~312ページ)
〇以上を要するに、①事実(本物)に触れる経験、②「ふつう」になったものを「変えない」デザイン、③空気(意識)を醸成するデザインが重要であるというのであろう。唐突ながら、これらは「まちづくりと市民福祉教育」にも通底する。誤解を恐れずにそれを別言すれば、まちづくりはそのまちの歴史や文化によって生み出された「ふつう」を磨くことである、と言えようか。
〇[2]では、「ふつう」はシンプルであり、「えらい」は生まれてから死ぬまでの、誰もが行う人間の野性的な、普段の営みにこそあるという思いに至る。ここでは、河合隼雄(1928年~2007年。臨床心理学)の「解説」文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
ふつうの人とえらい人 ―「ふつう」は「生き物であれば、誰でも持っているもの」であり、「よくいきている」ふつうの人のほうがえらい―
「正しいというのは正義というのではない。」(192ページ)/「正義」の方は必ず理由をもっている。「かくかくしかじか」という理由によって正しいという。それは理由によって支えられており、その理由はイデオロギーとかによって支えられている。つまり、それは正しい理論、正しい認識、などというものによって支えられ、立派に見えるけれど、そこから知らぬ間に生きた人間が消え去ってしまう。それに対して、佐野洋子のいう「正しい」は、まず生きた人間が先行している。生きた人間の存在を通して、正しいという叫びがとびだしてくる。「私は野性の中にある知性こそが、本当の知性だ、そして、それは人間が生き物であれば、誰もが持っているものだと思う。」(193ページ)と書かれている。/「誰でも持っているもの」を言いかえると「ふつう」になる。その「ふつうがえらい」のだ。(中略)現代人は自分が「生き物」であることを忘れているのだ。うまくやったり、努力したりすれば何でもできる、と思いすぎている。今世紀になってテクノロジーが異常に発達したので、うまくやれば何でも可能と思いすぎているのだ。「えらい」人を見ると、自分も同じように「えらく」なろうとする。そのことによって無理をしすぎて、「生き物」である自分を見失ってしまうのだ。そのような偽物の「えらさ」ではなく、「生き物であれば、誰でも持っているもの」としての「ふつう」のところに、でんと腰をすえると、世間の評価と関係のない「えらさ」を獲得できる。しかし、そのためには、人はひとりひとり個人差があり、自分ではどうしようもない欠点が沢山あることをはっきりと認識する必要がある。(285~286ページ)
〇筆者の手もとにもう一冊、精神科医である泉谷閑示(いずみやかんじ)の『「普通がいい」という病』(講談社現代新書)という本がある。[3]にこういう一文がある。
ある親御さんが、「私は、息子に普通の子になって欲しかった。ある時、息子は『普通って何!』と言った。私は、何でもいいから普通に、みんなと足並みを揃えて欲しいって思って育ててきた。普通じゃないと他人に説明できないから、ただ分かりやすい人になって欲しいという気持ちだった」と、話されたことがありました(中略)。/しかし、どんな人も、決して最初から「普通」を求めていたはずはありません。/この親御さんの場合は、ご自身が幼い頃から周囲の視線や言葉によって傷ついてきた歴史があって、「普通」でないことはこんなにもまずいことなのかと考えるようになった。それで、どこか窮屈さを感じながらも、「普通」におびえ、「普通」に憧(あこが)れ、「普通」を演じるようになった。そして、わが子もそうやって生きるべきだと考えるようになったのです。(41、42ページ)
〇この一文から、「普通」は「考えや行動が同じ」であり、「他人に説明しなくても分かる状態」をいうのであろう。また、「普通」は、「一般的」「標準的」「多数派」といった意味をもち、自分が所属する「世間」(集団や組織)との関係性の調和を重視する日本文化(日本人)の伝統的な価値観である。「普通」の認知領域や設定基準によって、積極的・肯定的、消極的・否定的、あるいは好意的・非好意的な感情や思考・行動を生む。そして、周りの人への気配りが共有され、周りの人と調和したときのポジティブな感情や思考が、幸福感や満足感(well-being)として意味づけられる。上の一文から、こうした言説を想起する。
【初出】
<雑感>(122)阪野 貢/「ふつう」別考―深澤直人著『ふつう』と佐野洋子著『ふつうがえらい』等のワンポイントメモ―/2020年10月30日/本文
付記
「ふつう」こそ「個性」の原料
〇キリーロバ・ナージャ著『6ヵ国転校生・ナージャの発見』(集英社インターナショナル、2022年7月)という本がある([4])。6ヵ国転校生のナージャが1990年代にロシア、日本、イギリス、フランス、アメリカ、カナダで実際に通っていた学校での体験や発見を綴ったものである。「イギリスの学校では、よく書くために、消しゴムを使って書き直せるエンピツを使っていた。ロシアでは、よく考えるために、書いたものは直せないペンを使っていた」。「ロシアの学校では、体育で整列するとき背が高い人が前だった」。「フランスの学校では、多くの人が家に帰ってお昼をたべていた」。「カナダの中学校では、計算機を使いながら答えを解答用紙に書いていた」等々、興味深い。そこからは、多文化理解や多文化共生には、生活様式や文化の皮相的なものではなく、その内奥の思考方法などの違いに注目しなければならないことが分かる。
〇ナージャは、大人になって次の5つを発見したという。(1)「ふつう」が最大の個性だった。(2)苦手なことは、克服しなくてもいい。(3)人見知りでも大丈夫、しゃべらなくても大丈夫。(4)どんな場所にも、必ずいいところがある。(5)6ヵ国の先生からもらったステキなヒントたち(①すべてに理由、そして面白さがある。②分からないことがあるから、仲間がいる。③人生に完璧はなかなかない。④わたしも、答えを知らない。⑤目標を立てるのも、達成するのも自分だ。⑥前例を覆(くつがえ)すからこそ、進化がある)、がそれである。
〇ここで、(1)「ふつう」が最大の個性だった、について付言しておきたい(114~118ページ抜粋)。
「環境が変わると、ガラッと変わるものは?」
答えは、「ふつう」だ。転校するたびに今まで「ふつう」だと思っていたことが、急に通用しなくなる。転校生なら少なからずみんな経験している気がする。
絶対的な「ふつう」がないんだとしたら、自分の「ふつう」ってなんだろう? 今まで考えたことはなかったけれど、誰かの「ふつう」を真似する限り、二番煎じにしかならないし、自分の本当のよさが生きてこない気がした。
子どものころはなかなか気づけないけれど、まわりと違う自分の「ふつう」こそが、「個性」の原料だ。そう気づいてから、今まで嫌いだった自分の「ふつう」がなんだか少しだけかわいく見えた。
そう、みんな「ふつう」でいいし、「ふつう」に対するコンプレックスをもっともっと捨てられるといいなと。
「ふつう」を磨いていくことが、「個性」を磨くことよりずっと早いという発見をしてから、ずっとそう思っている。
〇そしてナージャは、「ふつう」を「個性」として考えるためのヒント、についていう(118ページ)。
(1)意識して、違う「ふつう」の環境に身を置いてみる。
(2)自分の「ふつう」に他の「ふつう」を少し混ぜてみる。
(3)どちらにとっても新しい「ふつう」が生まれる。
(4)みんながそれを「個性」として重宝するようになる。
19 「批判的教育」の使命
<文献>
(1)マイケル・W・アップル、ジェフ・ウィッティ、長尾彰夫編著『批判的教育学と公教育の再生―格差を広げる新自由主義改革を問い直す―』明石書店、2009年5月、以下[1]。
(2)ヘンリ―・A・ジルー、渡部竜也訳『変革的知識人としての教師―批判的教授法の学びに向けて―』春風社、2014年1月、以下[2]。
〇筆者の手もとに、「批判的教育学」(Critical Pedagogy)の必読書であるマイケル・W・アップル、ジェフ・ウィッティ、長尾彰夫編著『批判的教育学と公教育の再生―格差を広げる新自由主義改革を問い直す―』(明石書店、2009年5月。以下[1])がある。そこには長尾の論稿「教育改革のポリティックス分析―新たな『教師論』の構築に向けて」が収録されている。
〇本稿では、長尾彰夫(ながお・あきお)の言説のなかから、筆者なりにいま一度認識しておきたいいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
(1)新自由主義・新保守主義と公教育の破壊
自由経済と強い国家を追求する新自由主義と新保守主義(注②)の勢力は、一方で「民主主義」を口にしつつ、他方では民主主義の意味そのものを根底から変え、さらなる格差や不平等を作り出している。また、「伝統」を声高に叫びつつ、それに異を唱えるものは徹底的に排除する。こうした「改革」がもたらす最大の問題は、公教育の破壊である。(3ページ)
(2)批判的教育学・批判的教育学者の使命
批判的教育学は、新自由主義と新保守主義による政策と実践が子どもや教師に与える影響(問題状況)を明らかにする。究極的には、非民主的な「改革」を押し戻し、真の「民主主義と市民性」に基づく「改革」を推し進める。そのために、進歩主義的な社会運動と協力しながら行動する。それが批判的教育学や批判的教育学者の使命である。(3~4ページ)
(3)現代の教育改革の特徴
教育改革はしばしば、官邸・内閣を中心とした時の政治的権力によって推進される(中曽根内閣が1984年8月に設置した「臨時教育審議会」や安倍内閣が2006年10月に設置した「教育再生会議」等)。それは、従来型の、文部科学省の官僚的・行政的権力による教育改革とは異なる。しかも、その両者の間には、共通性(点)と異質性(点)が存在する。現代における教育改革は、こうした微妙にして深刻な矛盾と対立を含んだ権力構造の分析なしには、その実像と特徴を捉えることはできない。(151ページ)
(4)ポリティックスの意味
ポリティックス(politics、政治学)とは、政党や政治が行っているような狭い意味での「政治的な事柄」「政治活動」を意味するのではない。ある事態や事柄をめぐって、それに関わる様々な人々や集団が、それぞれの利益と被害に関わるパワー(権力)を行使していく過程、およびそれによって生み出されていく(権力的な)諸関係をいう。(152ページ)
(5)教育改革のポリティックス分析
教育改革のポリティックス分析では、教育改革に関わるさまざまな集団や組織の利害や権力(パワー)が、どのように複雑に作用しているかというその状態(権力作用の関係)を具体的・現実的に分析する。その際、何のためにポリティックス分析を行うのかという、ポリティックス分析のめざすべきところをどこに設定するのかを明らかにしておくことが重要となる。(154ページ)
(6)教育改革と教師の「批判的権力」
教師は、教師としての視点と立場に基づくパワー(権力)を行使しながら、教育改革に関わっていくことが求められる。そのパワーの根底に据えられるべきは、教師が実際的な教育現場に関わっていくという専門性であり、それを基礎に、教育政策を批判的に捉え対象化していくいわば「批判的権力」である。教育改革のポリティックス分析では、教師が「批判的権力」をいかに獲得していくか、それを可能にする「教師論」とはいかなるものかが重要な課題となる。(163~164ページ)
〇「学校における福祉教育」は、歴史的・客観的な評価・分析を行わないまま、「指定校制度」を過去のものにしつつある。それに代わって登場した「地域を基盤とした福祉教育」は、ただ時流に乗ることを優先し、曖昧な「地域指定」や「実践主体」のもとで進められている。その当然の帰結として、一部の社協(職員)や学校(教師)を除いて、社協と学校の関係が表層化・限定化し希薄化している。そしていま、福祉教育関係者は、文部科学省が進める「コミュニティ・スクール(Community School)」や「アクティブ・ラーニング(Active learning)」に何の躊躇もなく、無邪気に秋波を送っている。
〇こうした動向や実態(課題)を生み出したその時々の福祉・教育政策に対して、福祉教育の実践(実践者)や研究(研究者)は、十分な関心を持って臨んできたであろうか。それぞれの福祉・教育政策の真の狙いを抉(えぐ)り出すことなく、それらを無批判的・盲従的に是認し受容する。そのうえで福祉・教育政策に適応(適合)する福祉教育実践のあり方を探究してきたのではないか。長尾の言説から、福祉教育の実践や研究のあり方を厳しく問ういくつかの示唆を得ることができる。
〇筆者の手もとには、もう1冊、ヘンリ―・A・ジルー著、渡部竜也訳『変革的知識人としての教師―批判的教授法の学びに向けて―』(春風社、2014年1月。以下[2])がある。[2]は、アメリカの批判的教育学者であるジルー(Henry A. Giroux)が1970年代から80年代にかけて発表した論文を集録し刊行(1988年)したものの全訳である。
〇訳者の渡部によると、ジルーの教育論は「二部構成」から成っている。そのひとつは、「生徒(特にこの場合、被抑圧者たちの子どもたち)が日頃慣れ親しんでいる文化的経験に結びつく仕方で自分たちの社会的ポジションを力動的に捉えていけるような知の枠組みを提供していくアプローチ」即ち「批判の言説」である。いまひとつは、「必要ならばその社会的ポジションの変革に向けて文化的経験の読み替えを行い(既存の社会体制に疑問を呈するような新たな解釈可能性の発見)、同じ問題意識に立つ外部の団体などと協力して実際に変革への力をつけていくためのアプローチ」即ち「可能性の言説」である。この二つの言説を換言して要約すれば、「日常言説の自明性を疑うための批判的分析と新たな可能性の提言」となる。(383ページ)
〇ジルーの批判的教育学については原典に当たっていただくことにして、ここでは、[2]のタイトルでもある「変革的知識人」(transformative intellectuals)に関する次の一節を付記するにとどめる。
(1)学校は論争的領域である
学校は実際のところ、政治や権力から隔離された客観中立の装置などではなく、権威の諸形態、知識の型、道徳的規則の諸形態、過去の見方や未来の展望などのうちのどれを正当化して子どもに伝えていくべきかという問題をめぐる闘争を具体化して表現した論争的領域である。学校は決して中立的な場ではなく、教師も同じく中立的な立場にいることなど不可能である。(237ページ)
(2)教師は教育改革の主体である
教師は教育改革の主体である。教師は学校の官僚的組織のなかで、専門職化された技術職ではない。即ち、教師は単に、前もって定められた目標を効果的に達成するために職業的に準備をするパフォーマーとして見なされるようなことはあってはならない。教師は、知への価値に対して特別に貢献し、また若者の批判的パワーを高めること(思慮のある能動的な市民を育成すること)に自由でなければならない。(230、235ページ)
(3)教員養成の変革が求められる
教師が生徒を活動的・批判的市民に育てるためには、教師が変革的な知識人となるべきである。現在の大学や教員養成ではしばしば「ハウ・ツー」が優先され、そのような仕事をどのようにこなすのか、与えられた知識体系を教授するのに最善の手法をどのようにマスターするのか、といったところに力点が置かれている。「変革的知識人」としての教員養成のあり方を問う必要がある。(232、237ページ)
〇ジルーの言説に関しては、教育は本質的に政治であり、権力である。学校は現実的にも、政治や権力の構造と機能を持っており、それゆえに子どもの批判的主体性の育成や能動的市民性の形成を図る場として存在する。学校教育は「政治的中立性を確保しなければならない」「権力と結びつくことがあってはならない」というのは、幻想である。学校教育では、学校外部の地域・社会におけるそれ(政治や権力)との関わりで、どのような理念や目的や価値観を有する政治や権力の場として学校を位置づけるかが問われることになる。これらの点を再認識しておきたい。
〇ジルーがいう「変革的知識人としての教師」については、少なくとも社会科教師にはそのあり方が問われることになるが、全ての教師にその素養や能力が求められるとは言い難い。この点を「市民福祉教育」に引き寄せて言えば、先ずは、福祉教育担当の学校教員や社協職員、そして「活動する市民」「市民エリート」(坂本治也)などが福祉・教育政策を批判し変革する知識や能力を身につける必要があろう。その際の福祉教育は、「思いやり」などの特定の価値観を押し付ける道徳主義や、「共に生きる」などの口当たりの良い言葉を唱えるスローガン主義に基づくものでないことは言うまでもない。
〇福祉教育は、人権尊重や社会正義の価値を基盤に、福祉・教育政策を批判し変革するソーシャルアクションやアドボカシー(註➀)についての思考(批判的思考)と実践(変革能力)を要件とする。本稿で再認識したいのはこの点である。
注
①アドボカシー(advocacy)は、元々は「擁護」や「支持」「唱道」などを意味する言葉である。やがて、「政策提言」や「権利擁護」など、特定の政策を実現するために社会的な働きかけを行う活動を示すようになった。また、「政府や自治体に対して影響をもたらし、公共政策の形成及び変容を促すことで、社会的弱者、マイノリティー等の権利擁護、代弁の他、その運動や政策提言、特定の問題に対する様々な社会問題などへの対処を目的とした活動」とも定義される(「日本アドボカシー協会」ホームページより)。
【初出】
<雑感>(43)阪野 貢/福祉教育は「批判」と「変革」を必要要件とする:「福祉教育と批判的教育研究」に関するメモ―日本福祉教育・ボランティア学習学会の新体制に寄せて―/2017年1月4日/本文
20 「対話」の技術
<文献>
(1)山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室―3つのステップ―』新曜社、2013年7月、以下[1]。
(2)山口裕之『「大学改革」という病―学問の自由・財産基盤・競争主義から検証する―』明石書店、2017年7月、以下[2]。
(3)山口裕之『人をつなぐ 対話の技術』日本実業出版社、2016年4月、以下[3]。
〇筆者が最近読んだ本のなかで“面白い”と思ったものに、山口裕之(やまぐち・ひろゆき、徳島大学、哲学研究者)のそれがある。『コピペと言われないレポートの書き方教室―3つのステップ―』(新曜社、2013年7月。以下[1])、『「大学改革」という病―学問の自由・財産基盤・競争主義から検証する―』(明石書店、2017年7月。以下[2])、『人をつなぐ 対話の技術』(日本実業出版社、2016年4月。以下[3])、である。
〇[1]は、「レポート」を書くにあたって、「コピペ」と言われないためには具体的にどうすればよいのかを、「最重要ポイント」のみに絞って解説したものである。その根底には、学部学生らに「自分の意見を根拠づけて主張する力」を身につけてもらいたい、という願い(「思い」)がある。「おわりに―民主主義とレポート」(93~98ページ)は深く、読む意義は大きい。
〇[2]は、政財界主導で進められている「大学改革」(国家権力の過度の介入、学長トップダウン体制の構築、競争主義や成果主義の強化、研究予算の削減や組織の統廃合、等々)の単なる反対論ではない。いわんや「潰(つぶ)れる大学」「大学の生き残り策」といった類の「読み物」ではない。[2]は、大学改革における論点を整理し、あるべき姿を追求するための見取り図を提示する、総合的で本格的な「大学論」である。「教育は、消費者が欲するものを提供するサービスではなく、何を欲するべきかを考える力を与えるための営みである」(248ページ)。大学に求められる機能(大学の存在意義)は、民主主義的な市民社会を支えるために、「さまざまな問題について、その背景を知り、前提を疑い、合理的な解決を考察し、反対する立場の他人と意見のすり合わせや共有を行う能力」(148ページ)、「正しく考え、議論し、他人と意見を共有する技能」(221ページ)を育成する(習得させる)ことである。留意すべき言説である。
〇[3]は、そのタイトルから「マニュアル本」と思われるが、民主主義の思想や歴史、民主主義国家の形成やあり方などにも言及する学術書(「人文書」)である。そこでは、人々の対話を阻(はば)み、人々を分断させている日本社会の現状分析を通して、「対話による合意形成」の重要性が一貫して主張される。その論述に関して山口は自らを、「意地の悪い揚げ足取り」(159ページ)「へそ曲がり」(161ページ)などと言うが、そこに批判性やオリジナリティがあり、また[3]の魅力(“面白い”)のひとつがある。
〇本稿では、「まちづくりと市民福祉教育」にも通底する(使える)、[3]における山口の論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
対話のねらいは合意形成と妥当な結論の発見にある
対話は、立場や意見を異にする人と話しあい、互いに納得できる合意点を見つけることである。対話は、相手の立場を理解し、多面的な見方を知ることで、妥当な結論を出すための方法である。対話は、憶測や思いつきではなく、客観的な根拠にもとづいて進めなくてはならない。対話は、自分と相手を成長させ、人と人とをつなぎ、ひいては民主的な社会全体を支えるのである。(はじめに、263ページ)
民主主義の本質は対話であり多数決ではない
民主主義とは対話である。民主主義の本質は多数決でなく、すべての人が対等な立場で自分の意見を根拠づけて主張し、討議し、お互いに納得できる合意点を探るところにある。多数決は、合意を形成するための手段の一つに過ぎない。無造作な多数決は、「多数派の専制」とほとんど同義である。それは、少数者の権利を侵害することになる。民主主義は、共同体のメンバーの人権を保障するための制度である。(40、51、116ページ)
民主主義はすべての市民が賢くなることを要求する
民主主義を支える一般市民は、対話に先立ってあるいは対話の過程で、普段から自分の思考力を鍛えるべく、努力する必要がある。それは、一面的な感情にとらわれない、多面的なものの見方や論理的な思考(「人間の日常生活における論理的思考」「日常的思考」)である。民主主義とは、すべての市民が賢くならなければならないという、無茶苦茶を要求する制度である。大学やその他の教育機関は、その無茶苦茶を実現するために存在しているのである(47、117、146ページ)
一般意思は多数派の意思ではなく理性によるものである
「一般意思」とは、「多数派の意思」ではなく、「実際にメンバー全員が持っている意思」でさえない。それは、「論理的に考えて共同体を設立し維持するために必要な条件」であり、各人に理性(論理的思考力)があれば、メンバー全員がこれを意思するはずのもの(「論理的思考力がある人間なら誰しも納得するはずのもの」)である。その点で、「一般意思」は基本的人権と表裏一体であり、それをお互いに守ることが「一般意思」である。(65、67、107ページ)
権利は義務の対価ではなく義務を伴わない
基本的人権(自由権、平等権、社会権、参政権など)とは、人間が人間らしく生きていくために不可欠のものであり、義務を伴うものではない。「権利」(ライツ:rights)の対義語としての「義務」(デューティ:duty)は、「誰かから要求されたわけではなく、人として当然果たすべきこと」である。「ライツ・アンド・デューティズ」と言えば、「人間として当然要求できることと、人間として当然果たすべきこと」という意味であり、「権利は義務の対価」という意味ではない。ライツとデューティは、表裏一体の「人間として当然のもの」である。人権とは、国家権力が課した「義務」(オブリゲーション:obligation)を果たしたことの対価として、国家権力から恵与されるものではない。(76、77、78ページ)
「人それぞれ」は対話を拒み連帯を妨げる
最近の風潮として、「人それぞれ」が蔓延(まんえん)している。「人それぞれ」という言葉は、相手(個性)を尊重するかのようであるが、他人の意見をよく聞かずに切り捨てる言葉である。それは、人々に対話を拒否させて合意形成をしない、人々の連帯を妨げるものであり、民主主義社会の根幹を掘り崩してしまいかねない。民主主義の理念とは、他人と協力することで、一人で生きていくよりも安全で快適に生きていくことである。そのために、自分たち自身で妥当なルールを決め、それを共有することである。(137、155、156ページ)
個性の尊重は微妙な差異の競い合いにすぎない
「個性重視」をめぐって、「みんなちがって、みんないい」(金子みすず:私と小鳥と鈴と)というフレーズや、「NO.1にならなくてもいい もともと特別なOnly one」(槇原敬之:世界に一つだけの花)という歌詞を見聞きする。多様性を尊重することは重要である。「個性」や「その人らしさ」は、個人の属性ではなく、個人間の関係性である。また、それは、成長する過程で、社会に流通している既存の価値観を選択することで形成されるものである。「もともと特別」などということはない。「個性」や「その人らしさ」は千差万別というよりは、社会的に許容可能な範囲内での変異に収まる。それゆえ、「個性」や「その人らしさ」の尊重とは、ある許された範囲内での微妙な差異の競い合いということになる。(162、163
ページ)
真の道徳教育は対話の教育である
現在、社会全体が「感情」や「思い」を尊重し、「心」を重視する方向に進んでいる。感情は個人的で、その人の立場に依存するものであり、誰しもが認める「正しさ」の根拠とはならない。共有できる「正しさ」は、感情ではなく、客観的な事実と合理的な予測にもとづいた対話によって作っていかなければならない。また、「思い」は、強いことが評価される傾向にあるが、強ければよいというわけではない。「何を思うか」のほうが大切である。そして、「心」が重視されるなかで、(内発的な動機が無視され)特定の徳目(道徳内容)を押しつけ、刷りこむ道徳教育が推進されている。徳目を覚えたからといって、その徳目を実践できるとは限らない。徳目の一方的な刷りこみそのものが、非道徳的である。道徳教育にとって重要なことは、「正しさ」(何が正しいことか)を判断する能力や技術を身につけることである。それは対話の能力であり、「対話の技術」である。(173、264、267、274ページ)
〇ところで、[3]で山口は、「ネットで一番ヒットするのは『普通の人』の意見」という見出しの一節で、次のように述べている。「ネットで情報発信するためには何の資格も学識もいらないので、ネット上のサイトや掲示板には、憶測や妄想にもとづくいい加減な記述があふれかえっている。パソコンの画面に表示されたからといって、それは権威あるものではなく、その辺の居酒屋での世間話や、個人の思いをつらねた日記などと同等の信用性しかないものが大部分なのである」(237~238ページ)。
〇また、社会学者の宮台真司(みやだい・しんじ)も、『まちづくりの哲学―都市計画が語らなかった「場所」と「世界」―』(ミネルヴァ書房、2016年6月)という本のなかで次のように述べている。 「ネットが同じ穴のムジナだけが集う<劣化空間>を提供する。<劣化空間>でつけあがる輩(やから)が、電子掲示板や、ブログのコメント欄や、ツイッターなどのSNSを、炎上させる。<劣化空間>は『馬鹿にとっては逃避先』であるが、『馬鹿でない人々にとっては真っ先にそこから逃げ出したい場所』である。ネット上では、見識の深い作家や批評家の発言と、劣化した人々の発言とが、等価になる。そうしたコミュニケーション空間では、見識の深い作家や批評家から順番に退却していく道理である」(51ページ、要約)。
〇筆者はこれまで、ブログ(「市民福祉教育研究所」)を通して、「まちづくりと市民福祉教育」に関する議論のための素材や情報の提供によるひとつの「問いかけ」を行なってきた。その際、「知識は体系になって、はじめて力を発揮するのであって、断片の寄せ集めは単なる雑学である」([3]228ページ)こと、すなわち知識や情報の構造化・体系化が厳しく問われることについては、多少なりとも留意してきた。しかし、“多少”では困るのである。ここで改めて、肝に銘じておきたい。
補遺
山口は[3]で、「対話の技術」(どのように対話すればよいのか)について、その要点を次のように「まとめ」ている(259~260ページ)。
①自分から見て、どんなに不正だと思える相手についても、その人なりの立場や感情があるはずなので、まずはそれを理解しようとすることが大切である。
②それから、問題となる事態を具体的に特定し、それが事実に反する思いこみや、中身のない言葉だけのものではないかを検討する。
③人間の思考にはバイアス(偏り)がかかっていることを自覚する。
④自他の要求を明確化することで、争点を明確化する。
⑤要求が、事態の改善につながる因果関係を持っているかどうかを検討する。
⑥相手の思考の体系を理解したうえで、その問題点を指摘し改善策を提示するような建設的な質問をする。
⑦自分自身の立場を反省する。
⑧事実認識を共有する。そのためには、ネット情報に頼らず、学術的な研究や一次資料を確認する。
⑨共有されている価値観を確認し、価値観同士が両立しえない場合には、どの程度のところまでが許容範囲なのかについて合意形成する。現実をその許容範囲に収束させるための適切な手段を検討する。
【初出】
<雑感>(56)阪野 貢/続・「対話」考:山口裕之を読む―「みんなちがって、みんないい」はどこまで許容できるのか―/2017年12月1日/本文
21 「 弱さ」のデザイン
<文献>
(1)天畠大輔『<弱さ>を<強み>に―突然複数の障がいをもった僕ができること』岩波書店、2021年10月、以下[1]。
(2)澤田智洋『マイノリティデザイン―「弱さ」を生かせる社会をつくろう―』ライツ社、2021年1月、以下[2]。
(3)高橋源一郎・辻信一『弱さの思想―たそがれを抱きしめる―』大月書店、2014年2月、以下[3]。
(4)鷲田清一『<弱さ>のちから―ホスピタブルな光景―』講談社、2014年11月、以下[4]。
「ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、 それは弱くもろい社会なのである。障害者は、その社会の他の異なったニーズを持つ特別な集団と考えられるべきではなく、その通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ普通の市民と考えられるべきなのである。」(国連総会決議「国際障害者年行動計画」1980年1月30日採択)
〇筆者(阪野)の手もとにいま、天畠大輔(てんばた・だいすけ)の『<弱さ>を<強み>に―突然複数の障がいをもった僕ができること』(岩波書店、2021年10月。以下[1])と、澤田智洋(さわだ・ともひろ)の『マイノリティデザイン―「弱さ」を生かせる社会をつくろう―』(ライツ社、2021年1月。以下[2])という本がある。天畠は、四肢マヒ、発話障害、嚥下(えんげ)障害、視覚障害などの重複障害を抱える、「世界でもっとも障害の重い研究者のひとり」である。澤田は、「息子に視覚障害があるとわかってから、『強さ』だけで戦うことをやめた」コピーライターであり、「言葉とスポーツと福祉」が専門の広告クリエイターである。ともに1981年生まれの気鋭のヒトである。
〇[1]で天畠は、生活上の困難(「弱さ」)と徹底的に向き合いながら、独自のコミュニケーション法(「あ、か、さ、た、な話法」)を創り、24時間介助による一人暮らし、大学進学、会社の設立(介護者派遣事業所)、大学院での当事者研究(博士号取得)、全国各地の重度障がい者と介助者の相談支援活動など、自身の人生の軌跡と生き様を紹介する。その際のキーワードのひとつは「当事者力」「当事者研究」である。天畠はいう。「当事者力」とは、「自身の抱える困難<弱さ>を自覚し、社会にその困難<弱さ>と解決の方法を訴えていく力」(182ページ)である。「当事者研究」は、障がい者の生活が制度によって “ 囲われた生活 ” になっている状況を打開し、「個人的なこと」を「政治的なこと・社会的なこと」に結びつける。すなわち当事者研究には、障害の「個人モデル」を「社会モデル」に転換し、社会規範を変える・社会変革を促す障がい者運動を再び活性化させる可能性がある(212ページ)。
〇いまひとつのキーワードは「合理的配慮」であろう。合理的配慮とは、「障がいのある人が、過度な負担を伴わず社会参加の機会を得られるように社会の障壁を取り除き、障がい者に配慮すること」(69ページ)をいう。2016年4月の障害者差別解消法の施行をきっかけに社会で大きく注目を集めるようになった。
〇天畠の「合理的配慮」に関する論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「弱さ」を「強み」にする「合理的配慮」
介助者の介入ありきで論文を書きあげるという、一般的に考えられている規範(かくあるべきもの)からは外れてしまう自分の「弱い」部分にあえてスポットを当て、逆にそのことの合理性の証明を(個人的なことを徹底的に深堀りする)当事者研究によって実践してきた。そしてそれを発信することで、社会の見方を変え、すでにある合理性の考え方やその境界線を変化させること、ひいては合理的配慮の範囲を広げていくことにも繋がる、という可能性を実感した。/合理的配慮は「与えられるもの」ではない。「でき上がっているもの」でもない。当事者が自分のニーズを発信して、何が合理的であるかを社会と対話しながら、つくり上げていくものなのである。/障がい者が合理的配慮を受けるのは権利であるが、配慮を受けるためには相応の「責任を負う」。(73~74ページ)/「当事者が制度の上にあぐらをかいてはいけない」(74ページ)
介助者と協働で書いた論文は「自分の論文」と言えるのだろうか‥‥‥。介助者の能力に「依存」して、僕は自分の能力を水増しさせているのではないか‥‥‥。僕は論文執筆における「能力の水増し問題」に長く苦しめられることになった。(130ページ)/僕は「介助者と協働で論文執筆する研究方法」にみずから疑問を持ちながら、介助者と協働で博士論文を書き上げた。しかし、ある意味自分の<弱さ>と徹底的に向き合っていく作業ともいえるその過程で、誰しもが自分一人の能力で生きているわけではない、ということに気がついた。ちなみに僕は<弱さ>という言葉を、社会的規範からはみ出てしまうこと、それに付随する生きづらさという意味で使っている。(131ページ)
僕は常に介助者との関係性のなかで自己決定をしている。(204ページ)/一見すると僕の自己決定のあり方はとても特殊なように思えるが、他者とかかわりながら生きていく以上、「健常者」であっても発話が可能な障がい者であっても、基本はみんな同じである。誰もが、自分以外の他者の影響を受け、ときに〝妥協〟しながら、日々自己決定をしていると言えるのではないか。(204~205ページ)/研究の結果たどり着いたのが、「<弱い>主体としてのあり方を受け入れる」という思いである。他者の意見に左右されながら、そして協働しながら、モノを生み出していくことは、障がいがあるゆえの特別なことではなく、人間誰もがそういった側面を持っている。そのことへの気づきによって、僕の持つ生きづらさは軽減された。さらに、それがいかに合理的であるかということを論理的に分析していくことで、逆に自分の<弱さ>が<強み>になることもある、という発見に至った。(205ページ)
今の社会で能力主義から自由に生きられる人はほとんどいないのではないか。(225ページ)/能力主義は、個人の努力や責任を求めるあり方である。しかし、重度障がい者の置かれている現状をみれば、個人の努力や責任ではどうにもならないことのほうが多いのである。/僕は介助なしでは何もできない。しかし、だから多くの人とかかわり、深く繋がり、ともに創りあげる関係性を築いていける。それが僕の<強み>になっている。能力がないことが<強み>なのである。自分だけで何もできないことは、無能力と同義ではない。(226ページ)
〇[2]で澤田はいう。だれもが持つマイノリティ性である「苦手」や「できないこと」、「障害」、「コンプレックス」は、克服しなければならないものではなく、生かせるものである。だれかの弱さは、だれかの強さを引き出す力である(12ページ)。人はみな、なにかの弱者・マイノリティであり(42ページ)、人はみな、クリエイターである。(324ページ)。そこに「マイノリティデザイン」という新して言葉と考え方を見出す。
〇澤田は「運動音痴」すなわち「スポーツ弱者」である。そこで、「スポーツ弱者を、世界からなくす」ことをミッションに、90競技以上の「ゆるスポーツ」を発案する。粘り気のあるハンドソープを手につける「ハンドソープボール」、イモムシをモチーフにした衣装を着てコート内を這う「イモムシラグビー」、穴の開いたラケットを使う「ブラックホール卓球」等々である。勝利至上主義や強者にハンデをつけるスポーツではなく、「勝ったらうれしい、負けても楽しい」「健常者と障がい者の垣根をなくした」スポーツである。その競技場には、「弱さを強さに変える」仕事をする、「(目の見えない息子の)弱さを生かせる社会」を(息子に)残したいという澤田の姿がある。
〇澤田の「マイノリティデザイン」に関する論点や言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
マイノリティデザインは「弱さを生かせる社会」を創る
「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」。トルストイの言葉である。/「弱さ」のなかにこそ多様性がある。(51ページ)/だからこそ、強さだけではなく、その人らしい「弱さ」を交換し合ったり、磨き合ったり、補完し合ったりできたら、社会はより豊かになっていく。/息子が目に見えないという「弱さ」と、自分のコピーを書けるという「強さ」をかけ合わせる。自分がスポーツが苦手という「弱さ」と、いろいろな人の「強さ」をかけ合わせる。/今、僕は「強さ」も「弱さ」も、自分や大切な人のすべてをフル活用して仕事をしている。弱さは無理に克服しなくていい。あなたの弱さは、だれかの強さを引き出す力だから。/弱さを受け入れ、社会に投じ、だれかの強さと組み合わせる――これがマイノリティデザインの考え方である。そして、ここからしか生まれない未来がある。(52ページ)/マイノリティとは、「社会的弱者」ではなく、「今はまだ社会のメインストリームには乗っていない、次なる未来の主役」である。(42ページ)
すべての「弱さ」は社会の「伸びしろ」
「迷惑かけて、ありがとう」。昭和のプロボクサーでありコメディアンのたこ八郎さんの言葉である。(326ページ)/迷惑とは、あるいは弱さとは、周りにいる人の本気や強さを引き出す、大切なもの。/だからこそ、お互い迷惑をかけあって、それでも「ありがとう」と言い合える関係をつくれたなら、これ以上の幸せはない。/すべての弱さは、社会の伸びしろ。(327ページ)
〇筆者(阪野)の手もとにいま、上記の2冊のほかに、「弱さ」をテーマにした本が2冊ある。高橋源一郎(たかはし・げんいちろう)・辻信一(つじ・しんいち)の『弱さの思想―たそがれを抱きしめる―』(大月書店、2014年2月。以下[3])と、鷲田清一(わしだ・きよかず)の『<弱さ>のちから―ホスピタブルな光景―』(講談社、2014年11月。以下[4])がそれである。
〇[3]は、2010年から2013年にかけて行われた「弱さの研究」(共同研究)に基づく、高橋(作家、社会批評家)と辻(文化人類学者、環境運動家)の対談本である。その研究の「目的と意義」は次の通りである。
「弱さの研究」の目的と意義
社会的弱者と呼ばれる存在がある。たとえば、「精神障害者」、「身体障害者」、介護を必要とする老人、難病にかかっている人、等々である。あるいは、財産や身寄りのない老人、寡婦、母子家庭の親子も、多くは、その範疇(はんちゅう)に入るかもしれない。自立して生きることができない、という点なら、子どもはすべてそうであるし、「老い」てゆく人びともすべて「弱者」にカウントされるだろう。さまざまな「差別」に悩む人びと、国籍の問題で悩まなければならない人びと、移民や海外からの出稼ぎ、といった社会の構造によって作りだされた「弱者」も存在する。それら、あらゆる「弱者」に共通するのは、社会が、その「弱者」という存在を、厄介なものであると考えていることだ。そして、社会は、彼を「弱者」を目障りであって、できるならば、消してしまいたいなあ、そうでなければ、隠蔽(いんぺい)するべきだと考えるのである。/だが、ほんとうに、そうだろうか。「弱者」は、社会にとって、不必要な、害毒なのだろうか。彼らの「弱さ」は、実は、この社会にとって、なくてはならないものなのではないだろうか(かつて、老人たちは、豊かな「智慧」の持ち主として、所属する共同体から敬愛されていた。それは、決して遠い過去の話ではない)。/効率的な社会、均質な社会、「弱さ」を排除し、「強さ」と「競争」を至上原理とする社会は、本質的な脆(もろ)さを抱えている。精密な機械には、実際には必要のない「可動部分」、いわゆる「遊び」がある。「遊び」の部分があるからこそ、機械は、突発的な、予想もしえない変化に対処しうるのだ。社会的「弱者」、彼らの持つ「弱さ」の中に、効率至上主義ではない、新しい社会の可能性を探ってみたい。(高橋:11~12ページ)
〇[3]では、“ 大きいこと ” や “速いこと ” などを良しとする「強さ」の思想と “ 小さいこと ” や “ 遅いこと ” などに価値を見出す「弱さ」の思想を対比するなかで、「弱さの再発見」を説き、「弱さの思想」の必要性が打ち出される。
〇要するにこうである。人間は、身体をもつ存在(身体的存在)であり、必ず死を迎える有限性がある、本質的に「弱い」存在である(有限性=弱さ)。それゆえに人間は、家族やコミュニティを形成し、支え合い・分かち合い・補い合うという「内なる力(パワー:Power)」によって生きている。そしてそこに、やさしさや思いやり、明るさや楽しさなどの人間的な価値や意味が見出されることになる。政府や法律などによる強制力をもつ「外なる力(フォース:Force)」ではなく、この「内なる力」こそが真の強さである(7ページ)。すなわち人間には、「弱さ」のなかに多様な可能性があり、「強さ」が潜んでいる。「弱さの強さ」である(71ページ)。
〇現代社会は、経済成長をひとつのゴールとする競争社会である。競争は、多様性を犠牲にし、均質性や効率性を重視する。そこでは「強さ」が追求され、「弱さ」が排除される。その意味で、現代社会は強者に向けて設計されている社会である(74ページ)。現実世界では、社会的・経済的・(自然)環境的な破綻が露わになり、「強さ」と信じられてきたものの「弱さ」が明らかになっている。「強さの弱さ」である。そしていま、「強さ」をめぐる競争ではなく、多様な者たち同士がお互いの「弱さ」を補い合いながら如何に豊かに生きるか、すなわち多様性を如何にとりもどすか、人間に根源的に備わっていた「弱さの思想」を如何に育てるかが問われている。それは、「弱さ」を中心とした共同体を形成すること、弱者に向けて社会を設計し直すことを意味する(95ページ)。そこでは、「弱さの思想」の入口として、競争の「勝ち」「負け」や、人間の「弱さ」や「強さ」という二元論から自由になることが求められる(203ページ)。
〇次の一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「弱さの思想」と社会改革
この社会は、弱いとか強いとかというふうに二元論的にできていて、強さを上に、弱さを下にした固定的なヒエラルキーでオーガナイズされている。弱さの思想とは、その「強さ・弱さ」の二元論そのものを超えていくことである。この二項対立を溶かしていく、あるいは無効化していく。それが、社会を支配・被支配のない、よりよい場所へと変えていくのに役立つことになる。社会について言えることはそのまま自分にも言えるわけで、まずは内なる二元論やヒエラルキーからいかに自らを解き放つか、である。(辻:203~204ページ)
〇なお、高橋と辻は、「勝ち」「負け」や「弱さ」「強さ」の二元論から自由になるための方策、すなわち「弱さの思想」(「勝たないし、負けない」、「勝ち負け」そのものを超えるという考え方(161ページ) ) に基づく社会を実現するための具体的方策については言及しない。ここでは、そのひとつとして、社会的に弱い立場に置かれている人々の「内なる力」を育成・強化し、社会改革に向けた下からの草の根運動としてその力を臨機応変に発揮する、そのための教育的営為が必要かつ重要となる、と言っておきたい。
〇[4]で鷲田(哲学者)は、僧侶をはじめ教師、建築家、ゲイバーのマスター、性感マッサージ嬢、精神科医、医療シーシャルワーカーなど、人を「温かくもてなす」(hospitable) 仕事をする13人へのフィールドワーク(聞き書き)を通して、ケア(世話)する人がケアを必要としている人に逆にケアされるという反転(「ケアの反転」)の意味を追い、ケア関係の本質に迫る。そこでは、自分と他者の弱さを受け入れ、その存在を認め合い、信頼して他者に身をあずける関係(「存在を贈りあう関係」)が必要かつ重要となる。鷲田はいう。「『弱さ』は『強さ』の欠如ではない(松岡正剛)」(226ページ)。「弱い者には強い者を揺さぶるような力(弱さの力)がある」(210ページ)。「〈弱さ〉はそれを前にしたひとの関心を引きだす。弱さが、あるいは脆(もろ)さが、他者の力を吸い込むブラックホールのようものとしてある」(212ページ)。「ケアを、『支える』という視点からだけではなく、『力をもらう』という視点からも考える必要がある」(221ページ)。
〇鷲田による “ まとめ ” のエッセイ(「めいわくかけて、ありがとう」:たこ八郎)から、次の一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「存在を贈りあう関係」と生きる力
じぶんがここにいることがだれかある他人にとってなんらかの意味をもっていること、そのことを感じることができれば、ひとはなんとかじぶんを支えることができる。(231ページ)/じぶんの存在が、「ふつうのひと」としてではなく、看護され、介護されるべきひとという規定を受けることが、病院や施設のなかでひとをいかに生きづらくしているかは、しばしば語られてきたことである。ひとは世話をしてもらう、聴いてもらうばかりでなく、じぶんだってひとの世話ができる、じぶんだって聴いてあげられる、じふんだってここにいる意味があるのだ、という想いが閑(しず)かに湧いてくるとき、ちょっとばかり元気になるものだ。/じぶんのしていることが、あるいはじぶんの存在が、だれか別のひとのなかである意味をもっていると確認できること、そのことが生きる意味をもはやじぶんのなかに見いだせなくなっているひとがなおもかろうじて生きつづけるその力をあたえるということとともに、その逆のこと、つまり他者に関心をもたれている、身守られているのではなく他者への関心をもちえているということもまた、ひとに生きる力というものをあたえてきたのではないだろうか。(232ページ)
【初出】
<雑感>(146)阪野 貢/「弱さ」考―「弱さの強さ」と「強さの弱さ」―/2021年11月24日/本文
22 「 共同体」の教育的営為
<文献>
(1)内田樹『サル化する世界』文藝春秋、2020年2月、以下[1]。
(2)内田樹・平川克己『沈黙する知性』夜間飛行、2019年11月、以下[2]。
〇筆者は「内田樹の世界」への旅を重ねてきた。今回は内田の新刊書『サル化する世界』(文藝春秋、2020年2月。以下[1])を旅することにした。[1]は、雑誌のコラムや講演録、対談やインタビューなどを加筆修正し、再構成したものである。内田にあっては、挑発的なタイトルの「サル化」とは、「今さえよければ、自分さえよければ、それでいい」という時間意識の縮減や自己同一性の委縮した人たちが主人公になっている歴史的趨勢(過程)のことを言う。「サル」は、中国の「朝三暮四」(ちょうさんぼし)という説話に由来する(補遺① 参照)。
〇日本社会ではいま、「身の丈(たけ)にあった」「期待される」「自分らしい」生き方が推奨あるいは強制されている。それは、生き方の定型化・固定化を促すものである。「成熟」とは多様に「変化」し「複雑化」することであるが、それを認めないのが現代社会である。人びとが感じている「生きづらさ」や「息苦しさ」の原因のひとつは、ここにある。そのような視点から、内田は[1]で、自分の身の丈を超えて自由に多様に生きることを提案する。人間は、成長するにつれて、「考え方が深まり、感情の分節がきめ細かくなり、語彙(ごい)が豊かになり、判断が変わり、ふるまいが変わる」(8ページ)。それが「成熟」である(「なんだかよくわからないまえがき」)。
〇以下に、[1]で筆者が「共感」する2つの視点・言説に限ってメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
教育の主体は集団であり、「共同体の存続」をめざす営為である
教育する主体は集団である。そして、教育の受益者も集団である。教育は集団の義務である。教育の受益者は子どもたち個人ではなく、共同体そのものである。共同体がこれからも継続して、人々が健康で文化的な生活ができるように、われわれは子どもを教育する。(216ページ)。
「教師団」には、今この学校で一緒に働いている人々だけではなく、過去の教師たちも未来の教師たちも含まれている。そういう広々とした時間と空間の中で、教育活動は行われている。そして、そういうような時代を超えた集団的活動が可能なのは、教育事業の究極の目的が「われわれの共同体の存続」をめざすものだからである。(219ページ)
教育政策の適否を計る基準は一つしかない。それはその政策を実行することが子どもたちの市民的成熟に資するかどうか、それだけである。市民的成熟に関係のないこと、それを阻(はば)むものは教育の場に入り込ませてはいけない。そういう基準で教育政策の適否を判定する習慣をわれわれは失って久しい。それが現在の日本の教育の混乱と退廃をもたらしている。(219ページ)
相互扶助的な共同体は「持ち出し」覚悟の私人から立ち上がる
地域社会の相互扶助的なマインドは簡単に無くなってしまった。共同体は簡単に崩れてしまう。これから先、日本社会はゆるやかに定常経済に移行してゆく。そんななかで、相互扶助的な共同体を再生する必要がある。(260、261ページ)
相互支援の共同体を立ち上げるというのは、基本的には行政の支援を当てにするのではなく、私人が身銭を切って、自分で手作りする事業である。「持ち出し」である。私人たちが持ち寄った「持ち出し」の総和から「公共」が立ち上がる。はじめから「公的なもの」が自存するわけではない。公的なものは私人が作り出すのである。(269、270ページ)
今、市民たちはどうやって「公的なもの」から私権・私物を取り出すことができるかを競っている。政府は、国民に対して「私権を抑制しろ、私有財産を差し出せ」とうるさく命令している。逆である。国民が自発的に私権を抑制し、私有財産を贈与するときに、そこに公共が立ち上がる。(270ページ。補遺② 参照)
〇内田の新刊書に、平川克己との対談本『沈黙する知性』(夜間飛行、2019年11月。以下[2])がある。対談のテーマや内容は、言葉や世論にはじまり、日本社会の衰退やグローバリズムの終焉、そして村上春樹や吉本隆明等々、多面的かつ多層的である。ここでは、[2]における次の3つの言説だけを再認識しておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
言葉に対する怯えや覚悟
何かを語ろうとしてる人間はみな「自分が発信している言葉は、誰かの言葉をパラフレーズ(言い換え、置き換え)しているだけかもしれない」ということを自覚しておく必要がある。その自覚がないから、自分たちの思考がパターン化した思考の枠組みをなぞっているだけだという自覚もないし、逆に、お気楽に傲慢で攻撃的な言葉を発することができるとも言える。言葉に対して、怯(おび)えや覚悟というものがあってもよい。(平川:35ページ)
身体感覚と生活実感のある言葉
「ほんとうのこと」「本音」を言うためには、命を賭けなければならない。生身の身体(身体性)や現実生活の常識から乖離した言葉には、説得力がない。一方で、身体感覚に裏付けられた言葉だけではなく、抽象度の高い言葉を使っていかないと思想は形成できない。そこで、抽象度の高い言葉を、生活実感のある言葉で裏打ちしていく作業(「伝わる言葉」への変換)が必要になる。(平川:57、58、305ページ)
孤独な沈黙のなかでの知性
見聞の狭い人間は、目の前の現実を見てすぐに「前代未聞」だと浮き足立ったり、有頂天になったりする。知識人は逆に、何を見ても「これはどこかで見たことがあるんじゃないかな」というところから吟味(ぎんみ)をする。そして、どういう文脈で「こういうこと」が起きたのか、過去の事例を参照しながら理解しようとする。知識人の、この孤独な沈黙のなかでの営為が、未来を切り拓く。これが本物の知性である。(内田:106、109ページ)
〇なお、筆者はかつて、「まちづくり」のための市民性形成(市民的資質・能力の育成)と市民運動に関して、次のように述べたことがある。「市民運動は通常、自らの、あるいは他者の尊厳や生命・生活が脅かされるときに、多くの市民が集合し、集合行為として展開される。その際、その運動は、必ずしも環境や立場を同じにする人びとが集まって展開されるものではない。運動に参加する人びと(運動主体)は多様であり、運動の目的も直接的に自らの利益や地位向上などのための利己的なものではない。運動主体の多くは、利己主義を超える人間観や社会観をもっており、社会的な事象や出来事に積極的に関与し、自己決定し、共通認識のもとに連帯して行動する自発的で能動的かつ自律的な個人である。また、その個々人は、運動展開の過程で他者理解を深め、自己を再発見し、自己変容・変革を促す。それを通して、他者との相互連携がより深化・発展するのである。」(<まちづくりと市民福祉教育>(3)福祉のまちづくり運動と市民福祉教育/2012年7月4日投稿)。これは、まちづくりのための市民運動や市民福祉教育についての理念的な管見である。本稿のサブタイトルに関して付記しておくことにする。
補遺 ①
中国の春秋時代の宗(の国)にサルを飼う人がいた。朝夕四粒ずつのトチの実をサルたちに給餌(きゅうじ)していたが、手元不如意(てもとふにょい。家計が苦しく金がないこと)になって、コストカットを迫られた。そこでサルたちに「朝は三粒、夕に四粒ではどうか」と提案した。するとサルたちは激怒した。「では、朝は四粒、夕に三粒ではどうか」と提案するとサルたちは大喜びした。
このサルたちは、未来の自分が抱え込むことになる損失やリスクは「他人ごと」だと思っている。その点ではわが「当期利益至上主義」者に酷似している。「こんなことを続けていると、いつか大変なことになる」とわかっていながら、「大変なこと」が起きた後の未来の自分に自己同一性を感じることができない人間だけが「こんなこと」をだらだら続けることができる。その意味では、データをごまかしたり、仕様を変えたり、決算を粉飾したり、統計をごまかしたり、年金を溶かしたりしている人たちは「朝三暮四」のサルとよく似ている。([1]22ページ)
補遺 ②
スモールサイズの「顔の見える共同体」で、地域・住民自らが医療や福祉・介護などに関するサービスや事業活動を相互支援的に手作り・手売り・手渡しし、自律的なコミュニティをつくることが肝要である。「こんなところで小さくやったって社会は変わらないよ」ではなく、逆に「小さくやるから変われる」のである([1]324~325、326ページ)。
【初出】
<雑感>(110)阪野 貢/共感の世界:「教育は集団的営為であり、市民的成熟に資することである」ということ―内田樹著『サル化する世界』のワンポイントメモ―/2020年6月22日/本文
23 「 贈与」の意義
<文献>
(1)白井聡『武器としての「資本論」』東洋経済新報社、2020年4月、以下[1]。
(2)斎藤幸平『人新世の「資本論」』集英社、2020年9月、以下[2]。
(3)内田樹『コモンの再生』文藝春秋、2020年11月、以下[3]。
(4)マルセル・モース、森山工訳『贈与論 他二篇』岩波文庫、2014年7月、以下[4]。
(5)仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉――〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』名古屋大学出版会、2011年2月、以下[5]。
(6)山田広昭『可能なるアナキズム――マルセル・モースと贈与のモラル』インスクリプト、2020年9月、以下[6]。
「贈与」の概念を初めて体系的な社会分析のために用いた研究は、マルセル・モースの『贈与論』である。その主要な問いは、贈物の中に潜むいかなる力が、貰い手に返礼させるのかというものである。これに対するモースの答は神秘性を帯びている。つまり、マオリ族が用いる「ハウ」という観念それ自体に原因を求めた。「ハウ」とは、「物の霊、とくに森の霊や森の獲物の霊」とされ、返礼されずにいると――もち主を殺してでも――元の場所に戻りたがる「贈与の霊」である。贈与者は、贈物をハウと共に送ることで、貰い手に対して神秘的で危険な力を行使していることになる。この観念を媒介として、富、貢納、贈与の義務的循環と、それを通じた社会的結合関係の維持機能を説明するというのが、かの古典的名著の主旨であった。([5]28ページ)
〇筆者(阪野)の手もとにいま、3冊の本がある。白井聡(しらい さとし)著『武器としての「資本論」』(東洋経済新報社、2020年4月。以下[1])、斎藤幸平(さいとう こうへい)著『人新世の「資本論」』(集英社、2020年9月。以下[2])、内田樹(うちだ たつる)著『コモンの再生』(文藝春秋、2020年11月。以下[3])がそれである。現代の日本社会は、「格差」「分断」「貧困」、そして「コロナ禍」などの言葉で語られる。その現状は、「グローバル資本主義末期における、市民の原子化・砂粒化、血縁・地縁共同体の瓦解、相互扶助システムの不在という索漠(さくばく)たる」([3]6ページ)ものである。この3冊の本は、こうした行き詰まる資本主義社会の「いま」と、向こう側の新たな「社会像」について思考する際に役立つ。
〇[1]にあっては、自立が強制され、自己決定(自己責任)が追及される現代資本主義社会を生き延びるための「武器」になるのは、カール・マルクスの『資本論』である。1980年代以降の新自由主義(ネオリベラリズム)は、「小さな政府」「規制緩和」「市場原理主義」などをキーワードに、社会の仕組みだけではなく、人間の魂や感性、センスを変えてしまった。資本による生産・労働過程のそれのみならず、労働者の魂、人間の全存在(身体・心理・文化・社会的諸側面の全体。人間の「全体性」)の「包摂」である(66、67ページ)。[1]は、『資本論』のキモを平易に解説した画期的な入門書であるが、裏にあるテーマは「新自由主義の打倒」(222ページ)である。別言すれば、「資本主義を内面化した人生から脱却するための思考法」(「帯」)である。
〇[2]において斎藤は、「マルクスが求めていたのは、無限の経済成長ではなく、大地=地球を〈コモン〉として持続可能に管理することであった」(190ページ)として、「資本主義の転換」を迫る。その際の〈コモン〉とは、「社会的に人々に共有され、管理されるべき富のことを指す」。それは、資本主義(新自由主義)でも社会主義(国有化)でもない「社会像」(「脱成長コミュニズム」)であり、「水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主義的に管理する」(141ページ)ことをめざす。
〇[3]で内田はいう。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)によって、グローバル資本主義と新自由主義は大規模な修正を余儀なくされることになる。その先に取り得る選択肢のひとつが「コモンの再生」である。それは「いま」、世界各地で、共同・協働のネットワークの再評価が始まっていることからもうかがい知ることができる(270ページ)。内田にあっては、国民国家がより小さな政治単位に分割されてゆく「『地域主義』がこれからの流れ」(261ページ)になるなかで、「コモン(共有地)」とは(「私」ではなく)「私たち」による「ご近所」共同体(6ページ)である。
〇私事にわたるが、2020年9月、「PSA:4.43」が筆者のその後の生活を決することになった。同年12月、「グリソンスコア:9」によって奈落の底に突き落とされる。そして、コロナ禍のなかの2021年4月、手術のために12日間の入院生活を強いられた。入院中のある日、(本当に)何故かふと、40年以上も前のことであるが、他界した伯父の「献体」のことを思い出した。身体の「贈与」である。なお、伯父は晩年、百姓仕事などのすべてを娘婿に渡し、近くの寺院(真宗高田派本山 専修寺)で奉仕活動に没入している。
〇いま、資本主義社会の行き詰まりについて批判する文脈で、またコミュニティの再興が叫ばれ、「コモンズ」(共有資源)や「コミュニズム」(共同体主義)について論じられるなかで、「贈与」が注目されている。「贈与」は多義的で、多用あるいは乱用されている感があるが、その言葉で思い出すのはマルセル・モースの『贈与論』である。モース(1872年~1950年)は、フランスの社会学者・文化人類学者であり、協同組合運動を中心とする社会主義思想への共感・共鳴を示していた。1925年に出版された『贈与論』は、「バイブル的存在」(小林修一)、「現代贈与論の原点」(平尾昌宏)などと評される。周知の通りである。
〇以下では、モース著・森山工(もりやま たくみ)訳『贈与論 他二篇』(岩波文庫、2014年7月。以下[4])におけるモースの基本的な議論・主張のうちから、(1)「贈与の3つの義務」と(2)「全体的社会的事象」についてのみ再確認しておくことにする。それは例によって、「市民福祉教育」実践・研究に「使える」であろう理論や方法に関する筆者の個人的な関心による。
〇モースにあっては、伝統的な「贈与」は、「贈り物をおこなう義務」「贈り物を受け取る義務」、そして「受け取った贈り物に対してお返しをする義務」の3つの義務から成っている。この「贈与」「受領」「返礼」という義務のうち、その根幹に位置づけられるのは第3の義務すなわち「返礼」である。それは、「贈与」と「受領」の義務を前提としている(101ページ)。要するに、モースがいう「贈与」は、相互性(互酬性)に基づく義務的な「贈与交換」(「贈与と交換」「贈与=交換」「贈与という名の交換」)である。そして、モースによると、「贈与」「受領」「返礼」は「気前よく」(60ページ)なされねばならず、「借りを返さないままでいる」(395ページ)と劣位に置かれたり、対抗関係を生み出すことになる。この点は現代社会においても然りである。「ギフト(gift)という一つの単語が『贈り物』という意味と『毒』という意味」(37ページ)の両義性を持つといわれる所以でもある。物の贈与には悪意や敵対といった感情的要素(感情的価値)が備わっているのである。モースはいう。「物には依然として情緒的な価値(精神的価値:筆者)が備わっているのであって、貨幣価値に換算される価値(金銭的価値:筆者)だけが備わっているわけではない」(393ページ)。
〇「返礼」の義務の特徴は、「贈与の恩恵に浴した人には、もらったものと等価のものに、さらに何かを上乗せしてお返しすることが義務づけられるようになること」(15ページ)にある。そして、「贈与」「受領」「返礼」が果たす機能は、物の交換や流通それ自体ではなく、「贈り物を受け取るということ、さらには何であれ物を受け取るということは、呪術的にも宗教的にも、倫理的にも法的にも、物を贈る側と贈られる側とにある縛りを課し、両者を結びつける」(43ページ)ことにある。すなわち、「贈与」「受領」「返礼」の循環・体系は、個人や集団などの間に友好的な関係(紐帯)を生み出し、その維持・強化を促すのである。モースはいう。「社会が発展してきたのは、当のその社会が、そしてその社会に含まれる諸々の下位集団が、さらにその社会を構成している個々人が、さまざまな社会関係を安定化させることができたからである。すなわち、与え、受け取り、そしてお返しをすることができたからである」(450ページ)。
〇ところでモースは、「贈与」は、「社会生活をかたちづくるあらゆることが、ここで混ざり合っている」という。それは、「宗教的な制度であり、法的な制度であり、倫理的な制度である――この場合、それは同時に政治的な制度でもあり、家族関係にかかわる制度でもある。それはまた、経済的な制度である」。それゆえにモースは、これを「『全体的な』社会的現象」(「全体的社会的事象」)と呼ぶことを提唱する(59ページ)。これは、「『全体』への強い志向性にもとづいて学術的探究に臨む」(「訳者解説」476ページ)モースの社会学・文化人類学の特徴を示すものである。ここで、次の一文を引いておくことにする。「全体を丸ごと考察すること、これによって、本質的なことがら、全体の動き、生き生きとした様相を把捉(はそく)することができたのであり、(中略)社会生活を具体的に観察することのうちに、新しい諸事象を見いだす手段がある。(中略)全体的社会的事象を考究すること以上に差し迫ったものはないし、また実り多いものもない」(442ページ)。
〇上述したように、モースは[4]で、「贈与の3つの義務」に基づく贈り物が循環することによって、社会的連帯・紐帯が生み出されることを指摘した。その点に関して、私事ながら本稿の冒頭に記した伯父の「献体」の贈与行為についてはどう考えるのか。公益財団法人・日本篤志献体協会によると、「献体の最大の意義は、みずからの遺体を提供することによって医学教育に参加し、学識・人格ともに優れた医師・歯科医師を養成するための礎となり、医療を通じて次の世代の人達のために役立とうとすること」(同ホームページより)にある。現在、わが国には献体篤志家団体が62団体あり、献体登録者の総数はおよそ30万5000人を越え、そのうちすでに献体した人は約14万人に達している(2019年3月31日現在)。
〇伯父の献体行為は、宗教的な動機も考えられるが、見返りを求めない、利他主義に基づく不特定の匿名他者への自発的な贈与であった。また、伯父が普段所属していたアソシエーション(機能集団)やコミュニティ(共同体)に対する個人的な感情(正義、責任、義務、感謝、愛、自己実現など)の発露であったろう。しかもそれは、医学教育に参加し、医療を通じて次世代の人達に役立とうとする公的な贈与であったといってよい。さらに言えば、医学や医療技術、生命科学や生命倫理などの発展をもたらし、回りまわって伯父の家族の自己利益にもつながることが想定される。いずれにしろ、伯父の献体行為は何らかの個人的・社会的な連帯意識に基づくものであり、またその行為の結果として人々の個人的・社会(文化)的な連帯意識の形成が促される。あえて指摘するほどに目新しいものではないが、ひとつの論点として再確認しておきたい。
〇筆者の手もとにいま、2冊の本がある。仁平典宏(にへい のりひろ)著『「ボランティア」の誕生と終焉――〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』(名古屋大学出版会、2011年2月。以下[5])と山田広昭(やまだ ひろあき)著『可能なるアナキズム――マルセル・モースと贈与のモラル』(インスクリプト、2020年9月。以下[6])がそれである。そこに見いだされるひとつの論点([5]]の〈贈与のパラドックス〉、[6]の「支配への抵抗」)について留意したい。
〇[5]において仁平は、「ボランティアをはじめとする参加型の市民社会の諸カテゴリーは、『善意』や『他者のため』と解釈される契機を不可避的に含むことになる。(中略)この『他者のため』と外部から解釈される行為の表象」を「贈与」と呼ぶ(10ページ)。そのうえで、「近現代の日本におけるボランティア言説の展開をたどり、参加型市民社会のあり方を鋭く問いなおす」(「帯」)。サブタイトルにいう〈贈与のパラドックス〉(paradox:逆説、矛盾)とは、贈与は行為者の真の意図とは別に、交換や見返り、偽善や自己満足などとして外部観察されがちである、という意味である。平易に言えば、「贈与の偽善性」「贈与の疑わしさ・怪しさ」である。
〇「アナキズム」には、「無政府主義」「政治的極左」「革命思想」といったイメージがつきまとう。その実は互酬性や相互扶助に基づく「支配に抗する思想」である。[6]において山田は、モースの『贈与論』を手がかりに、多くの思想家の議論・言説について言及し、「来たるべき経済」(贈与経済)社会を模索する。そして山田は、「非中心性、自主的連合、そしてつねにダイレクトに否を表明できる直接民主主義、これらはアナキズムの変わることのない基底である」(228ページ)。アナキズムは「個人的自由の追求と連帯の追求とがけっして矛盾しないと考える思想」である。「個人の自由の確保こそが真の連帯の条件である」(195ページ)、という。なお、ここで筆者は、アナキズムに関して「地域主義」(「小さな政府」)の理念を基盤に、「市民」のつながりや集まりである「地域コミュニティ」における「共働」をイメージしている。誤解を恐れずに付記しておきたい。
アナキズムとは、個人の自由を抑圧・侵害するようなあらゆる支配権力(とくに国家権力)を否定し、上からの組織化や統制を拒否しながら、合意によって自由で調和的な社会を建設しようとする思想である。したがってその根本には、権力による支配や強制なしに、社会を運営していくことが可能だとする発想がある。方法は大別してふたつある。ひとつは直接政治の領域に入って、国家権力を打倒しようとするものであり、もうひとつは国家権力と直接対決するのではなく、権力支配とは無縁な空間を(多くの場合、小規模かつ分散的性格の自治的協同体を建設するなどの方法で)非政治領域のなかに作り上げることによって、国家による権力支配を骨抜きにしていこうとするものである。([6]、195、196ページ。中見真理(なかみ まり)著『柳宗悦――時代と思想―』東京大学出版会、2003年3月、59~60ページ。)
補遺
筆者の手もとにいま、在野の日本近代史家・渡辺京二(わたなべ きょうじ)の本『幻のえにし――渡辺京二 発言集』(弦書房、2020年10月)がある。少し長くなるが、次の一文を引いておきたい。なお、渡辺は、『苦海浄土――わが水俣病』(講談社、1969年1月)などで知られる作家・石牟礼道子(いしむれ みちこ)を「50年間一緒にやってきた戦友」(本書、119ページ)という。二人の「道行き」(歩み)については周知のことである(米本浩二『魂の邂逅――石牟礼道子と渡辺京二――』新潮社、2020年10月)。
自分というものがこの世に生まれてきて満足するような人間のあり方というのは、一人一人が独立するしかないんですよ。一人一人が独立してね、自分の主人公になってね、そういう本当に独立した人間がある地域を介してね、地域というのは土地、土地は自然ということでもあるけれども、そういうものを介して、お互いが結びついて、その土地の生活を守り抜いていくということしか無いんですよ。
要するに、僕らは自分自身をまず独立させることなんですよ。それはどういう意味かというと、自分の考えを持つことなんですね。自分の考えを持つ。(253~254ページ)
自分の頭で考えるということは、コモンセンスで考えることなんです。コモンセンス。つまり普通の良識です。生活する上での普通の理屈で考えればいいわけなんですよ。すべての事柄は。そうするとおかしい事は、いくら理論ぶって言ったっておかしいわけなんです。そういう健全な批判能力みたいなものをね、保持していこうというのが、自分が一人である事なんですよ。(255ページ)
つまり自分は一人である、自分は自分の考えで生きている、国からも支配されない、いわゆる世論からも妄想からも支配されないというあり方ができるのは、自分がある土地に仲間とともに結びついていると感じるからなんだ。ところがそういう基盤がなくなっているからね。自分が生きている土地に相当するのは、自分がともに生きてきた仲間なんだよ。自分がこの世の中で自分でありたい、妄想に支配されたくないという同じ思いの仲間がいる。それが小さな国である。自分が自分でありたいという自分と、同じく自分が自分でありたい人たちで作った仲間が、小さな国になっていく。そういうものをしっかり作るということが僕の思う革命なのさ。それ以外はない。(257~258ページ)
【初出】
<雑感>(134)阪野 貢/「贈与」再考メモ―コミュニズムとアナキズム―/2021年4月28日/本文
24 「共事者」の実践的態度
<文献>
(1)斎藤幸平『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』KADOKAWA、2022年11月、以下[1]。
〇『人新世の「資本論」』(集英社新書、2020年9月)で知られる斎藤幸平の新著に、『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』(KADOKAWA、2022年11月)がある。[1]は、2020年4月から2022年3月にわたって毎日新聞に連載された「斎藤幸平の分岐点ニッポン」を書籍化したものである。行き詰まっている資本主義の現場から、23のテーマについて言及する。第3章の「偏見を見直し公正な社会へ」では、声をあげることが難しい「沈黙する(日本)社会」にあって、「外国人労働者」をはじめ「釜ヶ崎の野宿者」「東日本大震災の復興」「水俣病問題」「部落差別」「アイヌ」などに関する実相が抉(えぐ)り出される。
〇斎藤は、[1]の「あとがき」で補足的に、マジョリティの特権集団に欠けている他者へのエンパシー(共感)や想像力について触れ、「一から学び直す」必要性を説く。また、誰もが加害者であり被害者でもある「事を共にする」ゆるい関りに根ざした「共事者(きょうじしゃ)」(いわき市在住の地域活動家、小松理虔の言葉)について言及する。
〇ここで、「共事者」とその類義語・関連語である「当事者」に関する斎藤の文章をメモっておくことにする(抜き書き)。
共事者は、一つの問題や正義に固執し、他の問題や自分の加害性に目を瞑(つぶ)るのではなく、さまざまな問題とのインターセクショナリティ(交差性)を見出し、さまざまな違いや矛盾を超えて、社会変革の大きな力として結集するための実践的態度である。/共事者になることは、これまでの「敵/味方」「被害者/加害者」というような単純な二元論的語りのなかで、排除・抑圧されてきた声を聞き取ることができるようになるための一歩である。(217ページ)
当事者とは誰か、本当の当事者探しをして、彼らの意見を絶対視して、尊重すべきことなのか? それは、当事者・非当事者という線引きのもとで分断を生むだけでない。結局、「真の当事者」として誰を優先するかを決定するにあたって、そこにもまた研究者や支援者の権力関係が入り込んでくる。自分にとっての都合のいい「真の当事者」の主張を探して、他の人々を黙らせることが一般化するだろう。それでは「当事者」も利用されているだけだ。それに、自らの正義に固執して、それに合致しないものを糾弾するような運動は、共感も生まない自己満足で終わる。/結果的に、「真の当事者」への語りを限定していくことが、多くの人にとって「自分には語る資格がない」と声どころか、考える能力さえも奪うことになる。その先に待っているのは、無関心と忘却である。それでは社会問題はまったく改善しない。「自分は当事者ではないから発言をするのを控えよう」というのは、一見するとマイノリティに配慮しているようで、単なるマジョリティの思考放棄である。それは、考えなくても済むマジョリティの甘えであり、特権なのだ。そのようなダイバーシティでは、差別もなくならない。(215~216ページ)
〇福祉教育ではしばしば、「当事者」や「当事者性」について議論される。その際の「当事者性」とは、「当事者」またはその問題との心理的・物理的な関係の深まりを示す度合いを意味する言葉である。その点において福祉教育は、その当事者性(すなわち当事者やその問題をどの程度 “ 我が事 ” として捉えるか)を高め深めることを支援することによって、問題意識や問題解決のための具体的な行動を得ようとする実践である、といえる(松岡廣路「福祉教育・ボランティア学習の新機軸―当事者性・エンパワメント―」『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報』 VOL.11、万葉舎、2006年11月、18、19ページ)。ただ、そこでは、「当事者」と「非当事者」を区分し、両者を二項対立的に位置づけて思考することは解消されない。留意したい。
<雑感>((170)阪野 貢/追補/「差別」再考―「共事者」と「当事者」に関するメモ―/2023年2月10日/本文
25 「思いやり」の暴力
<文献>
(1)長谷川眞理子・山岸俊男『きずなと思いやりが日本をダメにする―最新進化学が解き明かす「心と社会」―』集英社インターナショナル、2016年12月、以下[1]。
(2)中島義道『「思いやり」という暴力―哲学のない社会をつくるもの―』(PHP研究所、2016年2月、以下[2]。
(3)清水将一『ボランティアと福祉教育研究』風詠社、2021年6月、以下[3]。
〇長谷川眞理子・山岸俊男著『きずなと思いやりが日本をダメにする―最新進化学が解き明かす「心と社会」―』(集英社インターナショナル、2016年12月)が面白い。[1]は、進化生物学者の長谷川(総合研究大学院大学)と社会心理学者の山岸(一橋大学大学院)の対談本である。人間社会の問題を解決するに当たって人を過大評価してはならない。「心がけ」や「お説教」では社会は変わらない。革新をもたらす人は周りの「空気を読まない人」である。こういった指摘には、「まちづくり」や「市民福祉教育」について考えるヒントが示されている。
〇[1]のなかから、「プレディクタブルな人」と「思いやり」や「差別」に関する二人の知見や発想の要点を、我田引水と評されることを恐れずに、紹介することにする(見出しは筆者:阪野)。
相互協調性の質
「日本人は相互協調的である」。相互協調性(interdependence)は、質的には、ポジティブなものとネガティブなものの2種類に分けられる。前者は、何かの問題について、協力して一緒に解決しようというものである。後者は、集団の問題を解決するのではなく、集団内で波風を立てないように行動するというものである。その人たちは、いわゆる「空気を読む」人であり、いつも「びくびく」している。
相互協調性と対照的なものは独立性(independence)である。独立性にもポジティブとネガティブの二つがある。ポジティブ・インディペンデンスは、他者と積極的に関わり、自己主張することに躊躇しないというタイプである。ネガティブ・インディペンデンスは、「誰も私に構わないでくれ」という、他者との関わりに消極的なタイプである。
プレディクタブルな人
「人間は社会的動物である」。ヒトは、社会なくして生きられない存在であり、自分の独立を守り維持するためには、他者とコミュニケーションを取り、協力する必要がある。その際、相手の主張や反応を予測したうえで自己主張をしないと、摩擦や衝突が生じることになる。そこに求められるのは、プレディクタブル(predictable)、つまり「予測可能な」人間(「分かりやすい人」)になることである。
プレディクタブルになるということは、自分の旗幟(きし、立場や主張)を鮮明にし、首尾一貫した行動規範に基づいて行動すること(「言行一致」)を意味する。それはつまり、他者と自分との違い(個別性)を明確にすることであり、それはまた多様性を歓迎することでもある。そうすることによって、他者から信頼・評価される存在となり、フレンド(friend)=味方=仲間を増やすことになる。
思考力のトレーニング
「個性と多様性の尊重、共生社会の実現」。いまの日本では、これらの言葉や理念が心がけや説教、スローガンとして語られ、その際には「思いやり」「絆」などが強調される。多様性のある社会や共生社会の構築は、個々人の異質性や不明性について相互に認識し、理解することから始まる。即ち、自分とは違う他者が、どのような世界観や思想を持っているかを把握する。とともに、自分なりの価値観や原理原則の確立を図り、それに基づいて一貫性のある行動をとることが求められる。多様性や共生は、「違うこと」に耐えることであり、思いやりの心の育成を図れば済むようなものではない。「みんな違ってみんないい」は、それほど簡単ではない。
「ヒトは社会システムのなかで動いている」。即ち、自分はどういう種類の人間かということを鮮明にし、お互いにそれを理解し、他者と衝突しながら言及し議論し、一緒に何かに取り組んで行く。そういうヒトにとって必要かつ重要なのは、心がけを説く「心の教育」ではない。複雑な議論を展開し、社会づくりに関する制度設計を行う「思考力のトレーニング」である。
社会を変えるには、個人レベルの心がけや行動ではなく、社会科学の知見を踏まえて物事について思考・判断・表現する人たちが、ひとつのコアを形成し、社会変革の原動力になってくれるのを期待するしかない。(以上、第7章:243~288ページ)
差別の利得
「差別は偏見から生まれると思われている」。しかし、差別の原因は偏見ではない。差別と偏見は切り離して考えるべきである。
社会のなかで差別が行われるのは、そこに何らかのメリットがあるからである。少なくとも、当初の段階ではメリットがあり、それによって差別が構造化され、継続的に行われてきた。逆に言えば、差別することによってデメリットやコストが増えるのであれば、そうした差別は生まれない。従って、差別をなくすには、差別をすることによって得られるメリットよりも、差別をしないことで得られるメリットを大きくすることである。差別は感情ではなく、利得の問題である。そういう意味では、競争社会は「差別をなくす社会」であり、競争なき社会は「差別の社会」「差別を温存する社会」であると言える。
差別構造の追及
「差別問題を『心でっかち』で考えてはならない」。差別は、第一義的には、社会構造の要因によって起こるものであり、その結果である。社会に差別構造があると、それによって差別を正当化する現実が生まれ、その現実が差別構造をさらに補強していく。そしてますます、差別は正当化され、固定化されていく。
差別の解消は、個人の意識(「心がけ」)を変えたり、スローガンを叫ぶだけでは不可能である。差別の現実(「結果」)を直視し、それを生み出してきた(いる)社会構造(社会システム)を追及し、制度改革を進めることが肝要となる。(以上、第5章:181~203ページ)
〇以上に基づいて、「プレディクタブルな人=個性的であり、多様性を歓迎する人」(257ページ)すなわち「社会変革の原動力になる人」(288ページ)のあり方について考える際の視点や枠組みを、筆者なりに図式化(素案)しておくことにする。
「プレディクタブルな人」の検討枠組み
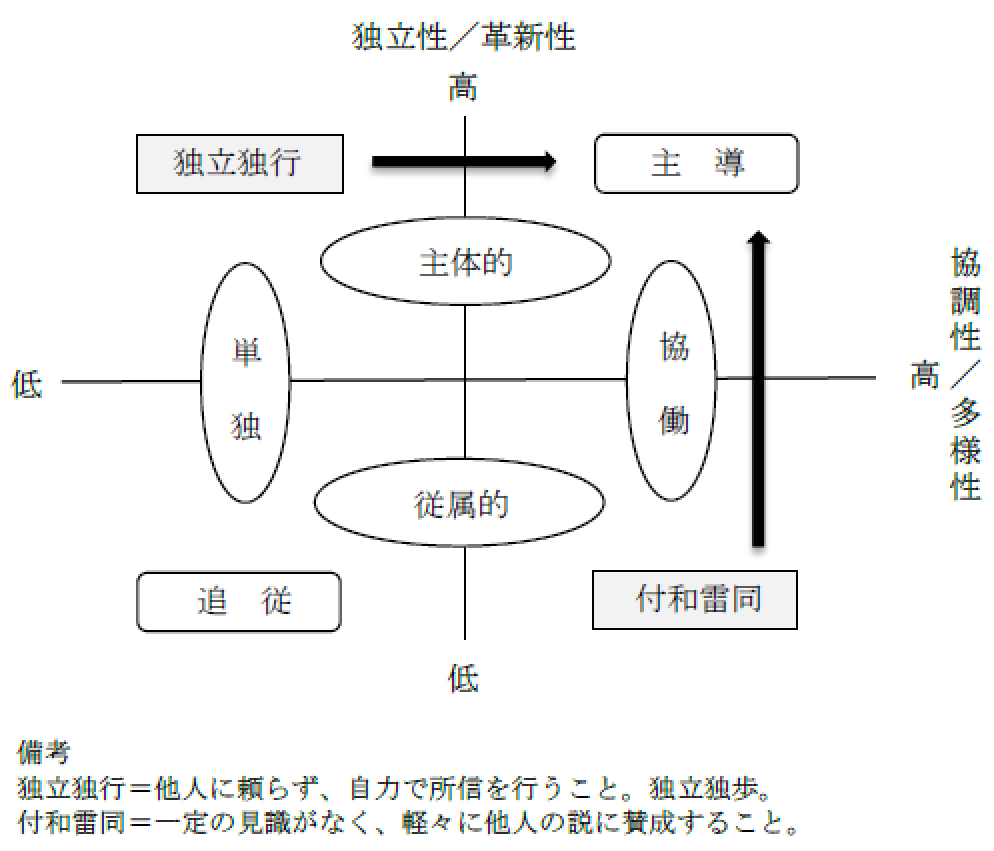
〇なお、プレディクタブルな人は、フレンド=味方だけではなく、エネミー(enemy)=敵をつくることにもなる。「出る杭(くい)は打たれる」。「和を以(も)って貴(とうと)しとなし、忤(さから)うこと無きを宗(むね)とせよ」である。それは、相互協調性を意味するが、他者からの承認欲求(独立性)の裏返しでもある。付記しておきたい。
補遺
中島義道『「思いやり」という暴力―哲学のない社会をつくるもの―』(PHP研究所、2016年2月)も、同意できない点もあるが、痛快で面白い。言説の一部を紹介(抜き書き)しておくことにする。なお、[2]は、中島著『<対話>のない社会―思いやりと優しさが圧殺するもの―』(PHP研究所、1997年11月)のタイトルを変えたものである。
わが国の人間関係において、最も重視されるのは、「他人を思いやる」ことであり、そのためには「本当のことを言わないこと」である。この国では、「お上」は「思いやり」や「優しさ」といった人間の根源的価値に関してまで個人のなかに踏み込もうとする。「思いやり」を持つことがなぜ必要なのかという問いを忘れて、「思いやりを持とう!」という掛け声だけが列島にこだまする。この国では、「思いやり」や「優しさ」を声高に唱え、人々から生き生きとした思考力を奪っている。「思いやり」や「優しさ」という名のもとに、とりわけ弱者の叫び声は完全につぶされつづける。風通しの悪い社会である。(4、11、13、76、165ページ)
この国では、「思いやり」はほとんどの場合「利己主義の変形」として機能してしまう。自分の身に危険がふりかからない範囲での「思いやり」など、気楽な「思いやり」である。この国では、みんな「思いやり」という名のもとに真実の言葉を殺している。「対話」を封じている。しかも、ほとんどの者はその暴力に気づいていない。(166~168ページ)
この国では「優しさ」は今やエスカレートして熱病にまでなっている。これほどまでに「優しさ」が叫ばれている空気のなかで、弱い人間は「優しさ」によって殺されてゆく。精神的に破綻してゆく。最新型の「優しさ」の特徴をなすものは、他者との対立や摩擦を徹底的に避けることであり、この目的を達成するために「言葉」を避ける。ひとことで言うと、自分に異質な者としての他者を徹底的に恐れるのである。(183~184ページ)
「対話」(「哲学的対話」)とは、各個人が自分固有の実感・体験・信条・価値観にもとづいて何ごとかを語ることである。正真正銘の「対話」とは、身分・地位・知識・年齢等々ありとあらゆる「服」を脱ぎ捨てて、全裸になって「言葉」という武器だけを手中にして戦うことである。「対話」とは全裸の格闘技である。(120、141~142ページ)
「対話」のある社会は、「思いやり」とか「優しさ」という美名のもとに相手を傷つけないように配慮して言葉をぐいと呑み込む社会ではなく、言葉を尽くして相手と対立し最終的には潔(いさぎよ)く責任を引き受ける社会である。それは、対立を避けるのではなく、何よりも対立を大切にしそこから新しい発展を求めてゆく社会である。それは他者を消し去るのではなく、他者の異質性を尊重する社会である。(228~229ページ)
この国で要求されるのは「和の精神」である。「和」とは、現状に不満をもつ者、現状に疑問を投げかける者、現状を変えてゆこうとする者にとっては最も重い足かせである。「和の精神」はつねに社会的勝者を擁護し社会的敗者を排除する機能をもつ。そして、新しい視点や革命的な見解をつぶしてゆく。かくして、「和の精神」がゆきわたっているところでは、いつまでも保守的かつ定型的かつ無難な見解が支配することになる。(61~62ページ)
【初出】
<雑感>(45)阪野 貢/プレディクタブルな人、その協調性と独立性:もう一つの考え方―長谷川眞理子・山岸俊男著『きずなと思いやりが日本をダメにする』の読後メモ―/2017年4月12日/本文
付記
「思いやり思いやり」と「思いうけ」:思いやり教育こそ福祉をダメにする
〇清水将一の『ボランティアと福祉教育研究』(風詠社、2021年6月)という本がある([3])。「福祉教育と思いやり」についての論考を紹介しておきたい(20~21ページ)。
福祉教育と思いやり
よく新聞などに小学校に障害児が進学して、健常児と一緒に学んでいる様子が載っている。いわゆる統合教育である。先日も大きな見出しで「思いやりの心が育った」という記事が目についた。私が引っかかるのは、思いやりの心が育ったのは健常児で障害児はどうなったのかいまいち分からない点である。
マスコミの取り上げ方が一方的なのかと思っていると学校でも似たところがある。福祉教育指定校などでも、「福祉とは思いやりの心である」なんて言っているようだ。障害児が福祉教育の教材であるかのような扱いである。果たして思いやりの心を育てることが福祉教育なのであろうか。
思いやりとは
思いやりの心が育つことは良いことであり今後も大いに続けるべきではあるが、思いやりの心は福祉教育の前提なのである。障害児を思いやるのは当たり前のこととならねばならない。思いやりとは自分の思いを相手にやることである。今度は相手(障害児)の思いを自分に受けとめることが大切である。これを「思いうけ」という。障害児の問題を自分のこととして受けとめることこそ福祉教育の起点である。
残念ながら現在は前提教育も十分に出来ておらず、この前提教育をあたかも福祉教育そのものと思い込んでいるようである。そろそろ福祉教育の起点に立った「思いうけ教育」実践が行われてもよさそうに思うのだが。
思いやり教育への反論
上記に続いて福祉教育を「思いやり教育」と捉えることに反対するもう一つの理由は、社会福祉の専門性との関わりからである。例えば一部の人が思っているように、社会福祉実践(ソーシャルワーク)はやさしい心、親切心があれば誰にでも出来るものと捉えられることがある。
今日社会福祉の専門性が言われているにもかかわらず、現場実践のない者や社会福祉学を学んでいない者が無責任にも福祉は思いやりの心だなどといい、その専門性に触れないことは我々ソーシャルワーカーにとっていらだたしく思えるのである。
思いやり教育こそ福祉をダメにする
そういう認識がある限りいつまで経っても福祉は聖域だと思われ(思わされ)、そのため低賃金や労働環境の悪い職場で働いている福祉従事者は多数いるのである。
思いやりの心、やさしい心は福祉に限ったことではない。医者や弁護士や教師、その他の専門職にも当然必要なはずである。それをことさら福祉に関してのみ、思いやりの心、やさしい心を強調するのは福祉に対する理解のなさの表れである。
福祉教育が思いやり教育である限り福祉の専門性は薄れていく。現在の福祉教育こそ、福祉の発展を阻害しているといえば言い過ぎであろうか。
26 「哲学対話」の方法
<文献>
(1)梶谷真司『考えるとはどういうことか―0歳から100歳までの哲学入門―』幻冬舎新書、2018年9月、以下[1]。
(2)河野哲也編『ゼロからはじめる哲学対話―哲学プラクティス・ハンドブック―』ひつじ書房、2020年10月、以下[2]。
意見とは、自分が考えてきた「問い」に対して、自分が出した「答え」である(山田ズーニー『伝わる・揺さぶる! 文章を書く 』(PHP新書、2001年11月、41ページ)。
〇筆者(阪野)の手もとに、哲学者の梶谷真司(かじたに・しんじ)の『考えるとはどういうことか―0歳から100歳までの哲学入門―』(幻冬舎新書、2018年9月。以下[1])という本がある。梶谷にあっては、哲学とは、「考える」営みそのものであり、「問い、考え、語ること」である(32ページ)。
〇梶谷はいう。「考える」という営為は本来、自分自身に問いかけ、自分なりの答えを出すことであり、自分自身との「対話」を意味する。しかし、ひとりで悶々(もんもん)と考えることには限界がある。また、現実の家庭や学校、社会(会社、地域等)における「考える」という営為は、既に決められている「正しいこと」「よいこと」「他者の意に沿うこと」の「正解」を探し求めるそれであり、そう考えさせられている。とりわけ学校では、生徒は教師や教科書によって提示された問いについて、強制的に考えさせられ、ひとつの正解を見出し、統制・画一化されている。また、特定の基準に即して選別され、序列化され、場合によっては周縁化され、排除される(12~13、52~53ページ)。
〇そこで、より広く、深く考えるためには、多様な立場の人が集まり、自由に「共に問い、考え、語り、聞くこと」が肝要になる。別言すれば、複数の人がいっしょに問い、その答えを探して考え、言葉にして語り、それを聞き、それを受け止める(「受け入れる」ではない)ことが、「共に考える」ということである。その際、とりわけ大事なのは、分からないことを「問う」ことである。それによって、はじめて「考える」ことができる。分からないことが増えれば、それだけ問うこと、考えることが増えるのである。そして、その過程を通して、自分を縛りつけるさまざまな制約(息苦しい世間の常識や慣習、人間関係、自分自身の思い込みや不安・恐怖、こだわり等)から解き放たれ、他の人といっしょに「自由になること」ができる。それは、人と人が「共に生きること」を意味する。こうした「共に問い、考え、語り、聞くこと」の具体的な方法(method)と方法論(methodology、方法の体系・システム)が、知識として学ぶ哲学(philosophy)ではなく、梶谷のいう「共に考える営み」としての哲学(philosophize)、すなわち「哲学対話」である(12~17ページ)。
〇「哲学対話」では、多様な立場の人が参加することが重要となる。適正な参加人数は10~15人前後とされる。また参加者は、対等であることを明確にするために、輪になって座る。そして、進行役(ファシリテーター)の支援のもとに、「共に考える体験」(共に問い、考え、語り、聞くこと)を通して個人的・主観的な感覚を覚え、それが「共感」を呼び起こし、思考を深化・拡大させる。こうした「哲学対話」について、[1]における梶谷の論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
哲学対話のルールと特徴―「他者へ」と「世界へ」と自らを開く
①何を言ってもいい
哲学対話においてもっとも大切なのは、「自由に考えること」であり、「問う」と「語る」からいかにして制約を取り払うかである。自由に問い、自由に語ることによって、はじめて自由に考えられるようになる。(47、48ページ)
②人の言うことに対して否定的な態度をとらない
自分の言うことが同意されなくても、決して否定されないと分かっていることが重要である。自分の言うことをそのまま受け止めてもらえると思えてはじめて、何でも言えるようになる。(55~56ページ)
③発言せず、ただ聞いているだけでもいい
話したくなければ黙っていていい。その自由がなければ、話したいことを話す自由もないことになる。「聞く」というのは、対話への立派な参加である。聞いていることじたいが、対話にとって決定的に重要である。(58ページ)
④お互いに問いかけるようにする
「問い」かけができなければ、対話で思考を深めたり広げたりすることはできない。問うことを学ばないところでは、考えることも学べるはずがない。考えるとは、「分からないことを増やすこと」であり、何を質問してもいい、ということである。(60、64、66ページ)
⑤知識でなく、自分の経験にそくして話す
知識に基づいて話したり、人の言葉や何かの用語を引き合いに出すのは、権威づけをし、それによって自分の優位を示そうとしていることが多い。「共に考える」ためには、
自分の言葉で、自分の経験や思いと結びつけたり、身近な例を出したりして話せばいいのである。(71ページ)
⑥話がまとまらなくてもいい
話し合いの答えを安易に先送りすることがあってはならないが、お互いに問い、考えた結果、結論が出るのであれば、それでいい。大切なのは、言いたいことを言い、問いたいことを問い、考えるべきことを考えたかどうかなのである。(75ページ)
⑦意見が変わってもいい
哲学対話では、みんなで考えているのだから、考えを深めたり広げたりするのであれば、個々人の意見は変わってもいい。意見が変わるということは、思考が深まった、広まった、違う角度から考えた、前提が問い直されたということであり、望ましいことである。(76ページ)
⑧分からなくなってもいい
分からなくなるというのは、問いが増える、考えることが増えることである。対話で分からなくなるのは、望ましいことであり、他者へと、世界へと自らを開いていくことである。(76、77ページ)
哲学対話の意義―「自由」と「責任」と「自分」のための哲学
哲学対話は「自由」を実感し理解する格好の機会である
哲学対話で自分とは違う考え方、ものの見方を他の人から聞いた時、自分自身から、そして自分の置かれた状況、自分のもっている知識やものの見方から距離をとる。その時私たちは、それまでの自分自身から解き放たれる。自分を縛っているもの――役割、立場、境遇、常識、固定観念など――がゆるみ、身動きがとりやすくなる。/また、哲学対話で今まで分かっていたことが分からなくなると、いわゆるモヤモヤした感覚、それこそ靄(もや)の中に迷い込んだ感じがする。/この自分を縛りつけていたものからの解放感と、自分を支えていたものを失う不安定感――この両義的感覚は、まさしく自由の感覚であろう。(93、94ページ)
哲学対話において感じるこの自由は、感覚じたいが個人的であり、主体的であるとしても、だからといって、他者と共有できないわけではない。そこで自分が感じる自由は、まさにその場で他の人と共に問い、考え、語り、聞くことではじめて得られるものである。だからそれは、他者と共に感じる自由なのだ。/こうして私たちは考えることで自由になり、また他の人といっしょに考えることで、お互いが自由になる――哲学対話は、このような固有の、そしておそらくは、より深いところにある自由を実感し理解する格好の機会なのである。(96~97ページ)
哲学対話を通して生まれる「責任」は他者と共に享受する権利である
哲学対話を通して自ら考え、決めた時に生じる責任の問題は、ポジティブな意味での責任である。それは、自由と引き換えにしぶしぶ負う義務ではなく、むしろ自由と共に手に入れるべき権利のようなものではないか。(98ページ)
私たちは、自ら考えて決めた時にだけ、自分のしたことに責任をとることができる。だから自ら考えていないということは、自分で決めていないということであり、そうであれば、やったことの責任は、本来とれないはずである。(100ページ)
哲学対話で選んだこと、決めたことは、結果がどうであれ、責任をとることができる。そうして私たちは、ただ自由だけを求めるのでも、責任だけを甘受するのでもなく、その間で妥協するのでもなく、自由と責任をいっしょに取り戻す。それは他でもない、自分自身の人生を生きることなのだ。/しかもそれは、対話を通して生まれた他者との共同的な関係に根差している。だからそこで引き受ける責任は、一人で負わなければならない責めでも、できれば避けたい負担でもない。他者と共に享受する権利となるのだ。(104ページ)
哲学対話は人生を「自分」のものにする営みである
哲学対話は、“恋愛”と同じである。/恋愛も人生も、自分で身をもってやってみるしかない。一から始めなければならない。うまくいかなくても、時に嫌気がさしても、臆病になっても、手放してしまうわけにはいかない。(110ページ)
哲学対話=「考えること」もそれと同じだ。レベルの高さ、厳密さ、深さ、一貫性を求める必要はかならずしもない。誰のためでもない。自分のために考えるのだ。どんなにつたなくても、自分でつまずいて自分で考えたことしか、その人のものにはならない。/だから、とにかくやってみればいい。そうして自由と思考を自分のものにし、人生を自分のものにするのだ。その時、いっしょに考えてくれる人がいたら続けられる。だから哲学は対話でするのがいいのだ。(110~111ページ)
哲学対話の核心―自分自身の「問い」をもつことと「考えること」の関連性
「問い、考え、語り、聞くこと」としての哲学(哲学対話)において、もっとも重要なのは「問うこと」である。「問い」こそが、思考を哲学的にする。/「考える」というのは、自発的で主体的な活動を指す。それは「問い」があってはじめて動き出す。問い、答え、さらに問い、答える――この繰り返し、積み重ねが思考である。それを複数の人で行えば、対話となる。(115ページ)
考えるには、考える動機と力がいる。自分自身が日ごろ、疑問に思っていることはつい考えたくなる。考えずにはいられない。こういう考える力をくれる問い、つい考えたくなる問い、考えずにはいられない問い、それが自分の問いであり、そうした問いを問うのが、自分を問うことである。/自ら問いたいことを問い、そこから考えることは、「問題を解くために考える」=「考えさせられる」のとは、まったく違うのである。(118~119、120ページ)
知識だけ学んで問うことがなければ、思考はどこにも行かず、育つこともない。知識もなしに問うばかりでは、思考は方向を見失う。知識はそこからさらに問うてこそ意味があり、問いは知識によってさらに発展する。だから哲学的に考えるためには、答えのある問いとない問い、閉じた問い(簡潔に答えられてそれ以上の説明を要しない問い)と開いた問い(答えに説明を要する問い)の両方が必要なのである。(141、144ページ)
〇およそ以上が、筆者の関心に基づいて捉えた、[1]が説く「哲学対話」や「考えること」の理念や意義、方法についての要点である(哲学対話の具体的な実践法については省略する)。そこには、「共に考える」ことを拡大・深化させるに際して、例えば、「論理的思考と批判的思考」、「具体的思考と抽象的思考」、「課題解決型思考と価値創造型思考」、「帰納的思考と演繹的思考」(複数の個別事例から一般原則・理論(結論)を導き出す思考と、一般原則・理論(一般論)を前提に個別の結論を導き出す思考)、あるいは他の人の考えの「容認と受容」などをめぐる疑問なしとしない。その点についての検討は別稿に譲ることにして、ここでは、再認識する意味で次の一文を引いておくことにする。それは、例によって唐突であるが、「まちづくりと市民福祉教育」の実践・研究に求められるひとつの理念や思想に通底するものでもある。地域コミュニティにおいて「共に考える」ことを通して自分の生きる現実を問い、考え、それを変え、自由と責任を取り戻してだれもが「よく生きる」、という理念や思想(地域共創のための自己責任と自己実現、相互責任と相互実現)である。
地域コミュニティにおいて、地元住民が当事者として地域をどうするかを考えなければならないはずなのに、それを国や自治体、もしくはどこかの企業が代わって考え、決めてきた。/何か問題が起きたら、住民は行政や企業を非難するが、彼らが責任をとることはない。当たり前である。それは彼らの人生ではないからだ。他方、当事者である住民は、自分たちで考えも決めもしなかったから、責任がとれない。それなのにその結果を引き受けるしかない。何とも理不尽なことではないか。(102~103ページ)
私たちは、自分の生き方に関わることを誰かに委ねるべきではない。また誰かに代わって考えて決めてあげることもやめなければならない。人間は自ら考えて決めたことにしか責任はとれないし、自分の人生には自分しか責任はとれないのだ。/しかもそのさい、一人で考えるのではなく、他者と共に考えることが重要なのだ。(103ページ)
哲学は夢を追いかけるユートピア思想ではないし、社会全体を変えようとする革命思想でもない。それは「考える」ということを通して、誰もが自分の生きる現実をほんの少しでも変え、自由と責任を取り戻して生きるための小さな挑戦である。そこで必要なのは、高邁(こうまい)な理想よりも徹底的なリアリズルなのだ。(259ページ)
〇筆者の手もとにもう1冊、「哲学対話」に関する本がある(2冊しかない)。哲学者の河野哲也(こうの・てつや)が編集する『ゼロからはじめる哲学対話―哲学プラクティス・ハンドブック―』(ひつじ書房、2020年10月。以下[2])がそれである。[2]は、哲学対話=哲学プラクティスに関する論点や言説が網羅的に記されているハンドブック(マニュアル)である。そこでは、「哲学対話とは、人が生きるなかで出会うさまざまな問いを、人々と言葉を交わしながら、ゆっくり、じっくり考えることによって、自己と世界の見方を深く豊かにしていくこと」(寺田俊郎:3ページ)をいう。
〇そして、哲学対話の特徴と実際的な意義・効用のポイントについて次の諸点を指摘する。[1]における説述と重複するが、参考に供しておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
哲学対話の特徴―「自由」によって自分と世界の見方を深く豊かにする
(1)哲学対話には問いがある
● 哲学的な問いは対話を必要とし、哲学的な問いを考える唯一の方法は対話である。
● 哲学的な問いの最終的な答えは誰も知らないのだから、対話に参加する人々の関係は平等・対等になる。
(2)哲学対話は答えを急がない
● 哲学対話は、速やかに答えを出さなければならないという圧力から自由である。
● 自分の意見を他の人々の意見に照らして吟味することによって、自分の意見の根底にある暗黙の前提に気づくことができる。
● その前提を明らかにすることは、自分の意見を明らかに、深く、豊かにしていくために必要であると同時に、互いに意見を理解するためにも必要なことである。
● 哲学対話が成功するということは、新たに問いが見出されるということであり、哲学対話を重ねれば重ねるほど問いが生まれ、さらに哲学対話が続いていく。
(3)哲学対話は自他の考えが変わっていくことを大切にする
● 自分で考え、他の人々と共に考えることによって、自他の考えが変わっていくことを自覚し認めあうことができる。
これらの特徴から、哲学対話を成立させるためにもっとも大切な条件は「自由」――問いを立てる自由、意見を表明する自由、意見に対する問いを立てる自由、答えを出す圧力からの自由、そして自分の考えを変える自由、である。(寺田俊郎:3~9ページ)
哲学対話の意義・効用―共生社会・成熟社会の構築と集団的意思決定に貢献する
(1)哲学対話は、多様な人々が、人が生きるうえで大切な問いを、互いの意見を尊重しあいつつ考えることによって対話の文化を醸成し、共生する社会を築くことに役立つ。
(2)哲学対話は、共生社会の別言であるが、風通しがよく、居心地がよく、生きやすい成熟した社会を築くことに貢献する。
(3)哲学対話は、重大な根本的な問題について問い、熟議し、まともな集団的意思決定を行うことに貢献する。それは民主主義に貢献するということである。(寺田俊郎:17~22ページ)。
自分の「考え」を持っていないということは、この考えを作りあげるための「考え方」を持っていないということである。(中略)何かの思想を持つことは、そうむつかしいことではない。それには出来合いのいろいろの思想があるからである。日本は今日まで、いつもそういう出来合いの西洋の思想を貰(もら)ってきて、サシ根して育てようとした。(中略)しかしほんとうに自分の考えを持つためには、それを持つ手段としての自分の「考え方」がなくてはならない。その考え方が我々にないならば、新たに学ぶほかはないのである(笠信太郎『ものの見方について』(改訂新版)角川ソフィア文庫、1966年7月、6ページ)。
追記
梶谷真司の次の文献も参照されたい。
・『人生を変える文章教室 書くとはどういうことか』飛鳥新社、2022年12月。
・『問うとはどういうことか―人間的に生きるための思考のレッスン―』大和書房、2023年8月。
【初出】
<雑感>(183)阪野 貢/「考えること」を考える:「哲学対話」をめぐって―梶谷真司著『考えるとはどういうことか』のワンポイントメモ―/2023年8月8日/本文
27 「地域共生社会」の模索
<文献>
(1)渡邉琢『介助者たちは、どう生きていくのか―障害者の地域自立生活と介助という営み』生活書院、2011年2月、以下[1]。
(2)渡邉琢『障害者の傷、介助者の痛み』青土社、2018年12月、以下[2]。
〇「相模原障害者施設殺傷事件」(2016年7月)の被告・植松聖は、「重度障害者は不幸を生む」「人生でやるべき事が見つかって、目の前が輝きだした」と嬉しそうに当時を思い出す。また、「(自分の考え方が)既に世の中に伝わっていると思う」と自信を見せる。そして、「事件を起こして良かったと思うのは、いろんな人が話を聞くために会いに来ること。ぼくもついに、ここまで来たんだ」と口元をゆがめて笑った、と報じられた(「虚栄/相模原事件面会記録(上)(下)」『岐阜新聞』2019年12月26日、27日朝刊)。
〇あの衝撃的な事件から3年半が経ったいま、障がい者や「障害(者)福祉」をめぐる社会的議論は深められず、社会の関心は薄れ、風化が確実に進んでいる。そんななかで、渡邉琢(わたなべ・たく)の『介助者たちは、どう生きていくのか―障害者の地域自立生活と介助という営み』(生活書院、2011年2月、以下[1])を再読し、新刊本の『障害者の傷、介助者の痛み』(青土社、2018年12月、以下[2])を読んだ。渡邉は、日本自立生活センター(JCIL、京都市)事務局員、NPO法人日本自立生活センター自立支援事業所介助コーディネーター、ピープルファースト京都(知的障害をもつ当事者の団体)支援者である([2]帯)。
〇[1]は、「障害者の地域生活に根ざした介助という営み、その歴史と現状をつぶさに見つめつつ、『介助で食っていくこと』をめざす問題群に当事者(介助者である渡邉)が正面から向き合った」([1]帯)本である。具体的には、「障害者介助に関わる介助者たちのこと、制度のこと、障害者介護保障運動の歴史のこと、労働運動との関係のこと、そして自立生活運動のさまざまなあり方のことなどを包括的に論じ、(中略)今でも色あせることのない充実した内容」([2]15ページ)である。「関東方面では『青本』と呼ばれ、運動や制度の歴史が簡潔にまとまったものとして、厚労省の役人も参考書にしている」([2]14ページ)とも言われる。
〇[2]は、「相模原障害者殺傷事件は社会に何を問いかけたのか。あらためて、いま障害のある人とない人がともに地域で生きていくために何ができるのか。障害者と介助者が互いに傷つきながらも手に手を取り合ってきた現場の歴史をたどりながら、介助と社会の未来に向けて」([2]帯)論考する。特筆すべきは、生々しいケア現場の視点から、介助者の障がい者に対する虐待・暴力だけでなく、障がい者の介助者に対する虐待・暴力があり、介助者も障がい害も加害者と被害者のどちらの立場にもなり得ると説く。そのなかで渡邉は、介助者と障がい者の信頼関係(相互理解と相互信頼)の回復と構築・深化を図ろうとする貪欲な姿勢と強い意志を示す。その際のキーワードは、「つながり」(他者とのつながり、社会とのつながり、自分自身とのつながり)であり、その「断絶からの回復」を強調する。そこでは、皮相浅薄な「地域共生社会」論はいとも簡単に打ち負かされる。
〇[1]と[2]のなかから、「市民福祉教育」に通底する、あるいはそれを論じる際に留意すべきであろう渡邉の論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
障がい者介助の運動と労働
「介助」は2000年代に入って成立した新しい職業形態である。雇用の非正規化、フリーターの増加などが社会的に認知されはじめた時期とだいたいかぶっている。介助者は、多くの非正規労働者と同様に、その将来も不確定だし、現状も不安定である。けれども、今、この障害者介助を生業として、生活を組み立てている人が少なくない規模で存在する。([1]20、25ページ)
障害者介助には、運動という側面と、労働という側面の二つがある。これまでの障害者運動においても、その両者は互いに拮抗しあっていたように思われる。それは無償で自立生活を支えていた時代からそうであったように思う。運動が盛り上がっている時期は、支援者、介護者も大勢集まってくる。けれど、いったん盛り上がりが鎮(しず)まると、あるいは時代の流れが悪くなると、支援者たちはさーっと潮のようにひいていってしまう。すると残された者たちに介護の重労働がのしかかってくる。運動というよりも、介護の重荷ばかりが強調されるようになる。(中略)運動の裏側にはそうした介護の「シンドサ」というのがコインの裏側としてあったと思う。([1]43ページ)
地域自立生活保障と介助者・介護者研修
介助者・介護者に何らかの研修が必要だとしたら、それは、障害者の地域自立生活の保障のための研修だろう。現在のところ介護福祉士の講師陣には地域自立生活の保障に関わっている人はほとんどいない。研修課程の中にも地域自立生活のことはほとんど含まれていない。
私たちに必要なのは、現在地域生活が難しいとされる重度の知的障害者、身体障害者、難病者、精神障害者などが、いかに地域生活を実現・継続していけるか、についての研修だろう。
あるいは、そのうち施設送りになりそうな障害者、高齢者がいかに地域で暮らし続けていけるか、それを学んでいくことが必要だろう。施設で研修して、施設でのケアを学び、そして施設を守るための研修だったら、それはいらない。([1]338ページ)
「つながり」をつくる
おそらく、自立生活運動は今分岐点に来ている。これまで自立生活、当事者主権ということで、運動が強く推進されてきたけど、現場では、むしろポスト自立の問題がテーマとなっている。施設や親元を出る、それは確かに自立である。けれど、その先に何が待っているのか、どのような人間関係、そして社会が待っているのか。現在、「無縁社会」、「孤立」が社会問題となっている時代である(さらに手のかかる患者などは病院から在宅への追い出しがはじまっている)。人とのつながりをいかにつくっていくかが新しい時代のテーマだろう。
自立は、「~出る」ということだけが至上の価値ではない。やはり「出てその先~」を求めて出るのである。その先の関係こそが自立の内実を決めていく。([1]414~415ページ)
支援とつながりの模索
入所施設にいる知的障害者たちとつながるということは、残念ながらぼくらもいまだにほとんどできていない。けれども、せめて入所施設に入らないための支援に尽力するということが、ぼくらにとっては目の前の課題である。施設関係者や施設入所者の家族は、ぜひ本人の地域生活の可能性を模索してほしい。地域が頼りないのなら、その地域を頼りあるものにする提言をしてほしい。そして地域生活支援に関わる人たちは、ぜひぎりぎりの状況にある当事者や家族が「入所施設しかない」と思うことがないよう、支援を模索していってほしい。それらはつながりを取り戻す模索であり、またつながりを断たないための模索でもある。([2]24ページ)
障がい者の被害と加害
「加害」とどう向き合い、どう対処していくかは、障害者の地域生活支援に取り組む上でとても重要なテーマだ。加害に及ぶから、あるいは加害に及びやすいから、自分たちの団体や地域から排除して、施設や精神病院にいってもらおうとするとすれば、それはあまりに安直だろう。少なくともそれは、インクルーシブ社会を目指す態度ではないと思う。そして、そういう拒絶的な態度こそが、さらにその人の攻撃性を強めることだって十分に考えられるのだ。
他者を排除しやすい社会は加害者を生みやすいし、当然同時に被害者を生みやすい。私たちがインクルーシブ社会、誰しも排除されない社会、誰しもが尊厳とつながりを奪われることのない社会というものを目指すのだとすれば、誰にも被害を被(こうむ)らせないことと、誰にも加害に及ばせないこととは同時に考えていかないといけないように思う。自分たちに危害を加えかねない人をも、インクルーシブ社会の包摂の対象と考えていく、一面で大変苦しく胆力(たんりょく。ものに恐れず臆せぬ気力)のいる作業でもある。([2]74~75ページ)
障がい者と介助者の痛み
街の中で、障害者が人から奇異な目で見られる、無視される、さまざまなところにアクセスできない、そういう環境に置かれて、毎日のように障害者自身が傷を負わざるをえないのがまだまだこの社会の現状だろう。その傷が、障害者の目の前にいる介助者にある程度転化していくのもある意味では受け止めざるをえない。この場合、障害者、介助者双方に傷を負わせているのは、この地域社会の責任だろう。長い目で見るならば、障害者に深い傷を負わせているこの社会の差別的なあり方こそ、改善されていかないといけないはずだ。だから、障害者としても目の前にいる介助者に都合よく痛みを転化し、留飲(りゅういん)を下げる(不平や不満を晴らして心を落ち着かせる)だけでは、決して深い傷の要因が取り除かれることはないだろうし、また介助者としても、単にキレやすいめんどくさい障害者と見るだけでも問題は解決されないだろう。([2]101ページ)
当事者同士による熟議
今もしそれぞれの生活が切り崩されており、それぞれなりのしんどさを抱えている時代状況なのだとしたら、そして、その中で相互のつながりを模索し、ともに生きていこうとするのだとしたら、「双方の関係のなかで詰めあっていく努力をして、それぞれの立場の違いを自覚した上で、双方がお互いの生活をみあっていくという関係が無いかぎり、お互いに認め合った関係」は成立しえないだろう。
当事者主体、当事者主権という主張が一方にあり、それによって自立生活運動等は進展してきた。その主張がある一定段階に達したとしたら、それぞれのニーズや立場の異なる当事者同士による相互の詰め合いの努力が今後不可欠となってくると思われる。それはおそらく「熟議デモクラシー」という言葉で指し示されている事態とも通底しているだろう。自立や自己決定は、当事者個人や当事者団体の主張に収斂(しゅうれん。一つに集約すること)されるものでもなく、次いで「熟議」を呼び起こしていくものだろう。([2]213ページ)
「共に生きる」可能性と希望
「殺すぞぉ!」「出てけぇ」は、障害のある人たちの生得的な攻撃性を示したものではなく、ある状況下におかれたら障害者、健常者関係なく、人間として普通の反応なのだ。([2]363ページ)
見えざる暴力の暴力性を認識しそれと対決しつつ、その暴力に苛(さいな)まれふりまわされている人々に手を差し伸べ、「共に生きる」姿勢を示し続けること、少なくともじっとそばに居続けること、あるいはその社会的暴力を察知しつつその暴力が発現しにくい環境をつくっていくこと、そのためにはきれいごとではすまされない人間のおぞましい側面とも向き合う忍耐や深い洞察が必要となるけれども、そうしたことが「共に生きる」社会をめざすうえで必要な態度なのであろう。
奪われた「つながり」を取り戻すことはもちろん安易なことではない。当事者、支援者双方ともに苦難の道を歩まないといけないだろう。その途上において深い断絶や絶望、激しい感情を感じることもしばしばあるだろう。(中略)私たちはひとりぼっちではない。つながりを取り戻す可能性は開かれているのだろう。([2]364ページ)
〇例によって唐突であるが、[1]と[2]から再確認・再認識したことについて、これまでとは異なる文体(文章のスタイル)で本稿を結ぶことにする。
「ふくし」の共働と共創
すべての住民が多様なかかわりのなかで/豊かに快適にそれぞれを生きる/その場が地域・社会であり/そのための労働や活動・運動が「ふくし」である。
福祉が福祉を閉じるとき/地域が福祉を拒むとき/「ふくし」は霧消する。
地域が地域を開くとき/地域が福祉を解するとき/「ふくし」を志向する。
福祉と地域が互いにつながるとき/地域と福祉が互いを包み込むとき/ひとつの土俵のうえで/相互理解に基づく相互支援と相互実現が図られ/「ふくし」が共創される。
「つながり」の熱意と誠意
障がい者に対する一方的な「思いやり」や「善意」の押し付けではなく/厳しい福祉現場で“働く”介助者の「つながり」への一途な願いや祈りに触れるとき/強い“熱意”と真の“誠意”があることを思い知らされる/そこには口当たりのよい言葉は不要である/そこに至難の「地域共生社会」への志向性を見る。
【初出】
<ディスカッションルーム>(81)阪野 貢/ケア現場の虐待や暴力が問う「地域共生社会」:福祉教育のもうひとつの視点―渡邉琢を読む―/2020年1月1日/本文
28 「まちづくりの哲学」の構築
<文献>
(1)アーク都市塾企画/戸沼幸市編著『まちづくりの哲学』彰国社、1991年12月、以下[1]。
(2)代官山ステキなまちづくり協議会企画・編集、蓑原敬・宮台真司『まちづくりの哲学―都市計画が語らなかった「場所」と「世界」―』ミネルヴァ書房、2016年6月、以下[2]。
近所に住むおじいちゃんが入院された。「にわか百姓」の私に、いつも優しくまた丁寧に、農作業を指南してくれた方である。早速お見舞いに伺ったが、一週間ほどたってご子息からお礼の連絡が入った。電話で、である。
我が家には2002年3月生まれの犬(柴犬)がいる。目が見えず、耳も聞こえず、認知症の症状が顕著にみられる。ある夜、大きな声で鳴き始めた。すぐに対応したが、近所からお叱りの連絡が入った。深夜23時30分、無言電話で、であ。
私は昨年、地元の老人クラブの役員を仰せつかった。ある役員との連絡は、時にはメールで行うことがあった。いま思えば、その時の話題は少々厄介なものばかりであった。メールは、お互いの「繋がり」を深化させない、「摩擦」を避けるためのツールとして活用されたのだろうか。
〇「まちづくり」について語るとき、「遠くの親戚より近くの他人」や「向こう三軒両隣り」の日頃の付き合いとそれによる見守り活動や支え合い活動の必要性が指摘される。また、近隣住民の日常の挨拶や立ち話から始まるが、住民相互の直接的な「対話」や対面的な「熟議」によるまちづくりの意義や重要性について述べられる。上記の話は、それらに関する、筆者(阪野)が暮らす田舎町でのひとつの現実である。
〇以前にも増して、住民の個人主義的傾向が強まるなかで、匿名性の高まりと人間関係の希薄化が進んでいる。また、無関心層やフリーライダー(対価を払わず便益を享受する人)が増えている。そういうなかで、新旧住民や世代間にさまざまな葛藤や軋轢が生じ、(地縁)共同体的紐帯の弱体化が深刻な問題になっている。「まちづくり」や「コミュニティ再生」の難しさを感じざるを得ない。
〇さて、筆者(阪野)の手もとにいま、『まちづくりの哲学』という本が2冊ある。アーク都市塾企画/戸沼幸市編著『まちづくりの哲学』彰国社、1991年12月(以下[1])と代官山ステキなまちづくり協議会企画・編集/蓑原敬・宮台真司著『まちづくりの哲学―都市計画が語らなかった「場所」と「世界」―』ミネルヴァ書房、2016年6月(以下[2])である。
〇「アーク都市塾」(現「アカデミーヒルズ」)は、1988年9月に設立された民間の成人向け教育施設である。[1]は、その「塾」で開催された「まちづくりの哲学ラボ」(アドバイザー・戸沼幸市早大教授)における議論の成果を纏めたものである。そこでは、「都市のユーザーとしての生活者の視点」から社会的事象の傾向や背景を把握・分析し、それを通して「まちづくり」について多角的かつ平易に論じている。その際の基本的な考え方のひとつは、「まちづくりは生活の作法づくり」(15~20ページ)である。以下では、「キキカンと生活者によるまちづくり」に関する言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「キキカン」からのまちづくり
「まちづくり」への強いきっかけづくりには、大ざっぱにみて「喜楽美」と「哀怒醜」のようなポジィティブとネガティブの感性の両面のベクトルが有効に思える。
この二つの感性ベクトルを一つにまとめた表現が、「キキカン」(嬉々感と危機感の同時表現)という概念である。
単純に「胸の躍るように楽しいこと、美しいこと」(嬉々感)なら、誰でも強く魅(ひ)かれるし、逆に「不当に醜いこと、怒りや不安をおぼえること」(危機感)なら早急に対策を練ろうとするのは、当然である。であれば、この「嬉々感と危機感」を生活環境の中から発見する活動が、「まちづくり」の第一歩であると言える。すなわちこうした一人一人の素朴な思い・感性・執着心の振向けの作法が、今後の都市環境の行方を握っている鍵とも考えられる。(216~217ページ)
生活者による現代版「まちづくり」
生活者による現代的(版)「まちづくり」とは、居住者の立場から一歩踏み出し、もっと幅広い生活範囲の環境に視野を広げたときに発見する様々なキキカン(嬉々感と危機感)をテコに、理性的なプロセスに基づく共同作業を経て、因果関係を明らかにし、建設的に問題解決を図る環境創造活動である。(231ページ)
〇「代官山ステキなまちづくり協議会」は、2006年5月に設置認定された、東京の渋谷区まちづくり条例に基づく「まちづくり協議会」のひとつである。[2]は、その協議会が2011年に開催したセミナー「まちづくりの哲学」の一環として企画・実施された対談を纏めたものである。対談者は、都市計画界の重鎮である蓑原敬(みのはら けい)と、稀代の社会学者と評される宮台真司(みやだい しんじ)である。
〇その対談は、「よいまちとは何か」「どうすればよいまちは作れるのか」「なぜよいまちを求めるのか」(ⅰページ)という三つの素朴な疑問や、「未来への渇望が“希望”と呼べるのなら、まちづくりとは“まち”に“希望”を刻印する営み」(ⅵページ)であるという理念(根本的な考え方)などをベースに展開される。そして、「まちづくり」をめぐる豊富で高尚な知識や見識に基づく対談を通して、人間の幸福や生きる意味を考える。とりわけ、宮台の読書体験(膨大な知識の量と質)には圧倒される。また、個人的体験の開陳や社会風俗や事件に対する鋭い分析も興味深い。以下では、「我田引水」的な「つまみ食い」と評されることを承知のうえで、論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「微熱感」と「生き物としての場所」
街とは、建物や街路などの空間的配置だけでなく、そこを行き交う人々の内面をも含んだ、生き物のようなもの(「生き物としての場所」)である。1990年代初めの渋谷には、街全体に「微熱感」があった。分かりやすい言葉で言えば、「この街にいれば、何かができる」という感覚(「魅力」)である。当時の渋谷は、女子高校生を中心とする若者たちにとって、普段緊張を強いられ“演技”をしている家や学校や地元とは違う、「素」の自分に戻れる「解放区」「居場所」であった。(宮台:15、17ページ)
まちづくりと「機能的に空白の場所」
まちが計画的に作られていくと、すべての場所に目的が割り振られてしまい、その目的に従って生活することが命じられ、まちに拘束されているという感じがする。(代官山ステキなまちづくり協議会 野口浩平:ⅲ、24ページ)
1990年代半ばに「屋上論」を展開した。なぜ学校の屋上には不良や今で言うひきこもりが滞留していたのか。「機能的に空白の場所」だからである。廊下は「歩く場所」。校庭は「運動する場所」。教室は「学ぶ場所」。でも屋上にはそうした機能が割り振られていない。だから「何かをする人」でいる必要がなくなって、解放されるのである。
機能を割り振られた場所を、機能的に空白の場所へと差し戻す「屋上化」は、<我有化>(固有化、自己化、自分のものとすること)の一種である。(宮台:24~25ページ)
IT化と「感情の劣化」
インターネット元年である1995年から2010年頃までは、ネットの良さは「誰にでも開かれていること」「誰とでも繋がれること」だとされた。そのお蔭で、「新しい政治参加」「新しいコミュニティ形成」に役立つのだと喧伝された。昨今は一転。ネットが「誰にでも開かれている」からこそ政治もコミュニティも<感情の劣化>に見舞われがちになった。また、ネットが「同じ穴の狢(ムジナ)」(同類の悪党)だけが集う<劣化空間>を提供したり、(ゲートを設けて出入りを制限する)<見えないゲーテッドコミュニティ化>つまり<見えない化>が進むようになった。ネットは、「見たいものだけ見て、見たくないものは見ない」という、さもしく浅ましき営みに帰結しがちである(宮台:51、54、57ページ)
「感情の劣化」とは、真理の獲得よりも、感情の発露が優先される態勢である。それは、「感情を制御できずに<表現>よりも<表出>に固着した状態」とも言える。ちなみに、<表現>の成否は相手を意図通りに動かせたか否かで決まり、<表出>の成否は気分がスッキリしたか否かで決まる。(宮台:58ページ)
コミュニティ再生とファシリテーター
対人ネットワークが空洞化してしまった現在、コミュニティ再生のための処方箋は、エリート論でもソーシャル・キャピタル論でもなく、「熟議論」である。ただしそれは、皆で話し合えばいいという議論ではなく、熟議論の半分はファシリテーター論である。ファシリテーターが従来のエリートと決定的に違うのは、人々が「自分たちで決めた」という感覚を失わない範囲で座まわしをすることである。(宮台:130~131ページ)
ファシリテーターは「依らしむべし、知らしむべからず」(「為政者は人民を施政に従わせることはできるが、その理由を理解させることは難しい」)の対極である。ファシリテーターには、知識や教養もさりながら、場の感情的配置やダイナミクスへの敏感さが必要である。なぜなら、これが正しいという内容的介入ではなく、「声のデカイ極端者」が場の空気を支配できないように、不完全情報を可能な限り完全化したり、発言機会をコントロールしたりする役目を果たす存在だからである。(宮台:131ページ)
「感情の教育」と「ななめの関係」
コミュニティ再生には、優秀な座回し役・呼び掛け役・巻き込み役を果たすことができるファシリテーターを養成することが必要である。そのためには、<感情の教育>が必須となる。しかしそれを国民全体のものとして構想すると、全体主義に陥ることになる。また、現在の教育人材を前提にすると、公的に制度化することは不可能である。そこで、顔が見えるコミュニティで、人格的信頼を基盤にした子どもの<感情の教育>に乗り出すしかない。(宮台:135ページ)
しかも、「何がいい人生なのか」「何がいい社会なのか」という価値への言及(価値教育)が不可欠となる。その価値を埋め込むのは、教育したがる大人を一部に含んだ子どもの「成育環境の全体」である。そのなかで例えば、親子という「縦の関係」よりは、井戸端や縁側の話とも関係するが、親戚や近所の大人との「ななめの関係」で「価値の伝承」を図ることが大切になる。(宮台:136、138~139ページ)
〇宮台がいう「感情の教育」は、道徳教育やそれを基盤とした「心の教育」などにかかわることから、慎重に取り組むことが求められる。それは、個人の主体性や自律性を軽視あるいは無視したり、現在の政治・経済・社会の状況や情勢を無批判的・肯定的に捉え、個人の社会への順応や適応を重視するもの(偏狭な「社会化」)であってはならない。「感情の教育」に求められるのは、「コミュニティの再生や創造」に向けた批判性や創造性、革新性である。
〇地域貢献活動と学習活動を通して市民性を育むサービス・ラーニング、学校・保護者・地域住民が連携・協働して進めるコミュニティ・スクール、地域課題の発見・解決に向けた能動的学修のアクティブ・ラーニング、そして「我が事・丸ごと」の「地域共生社会」の実現。いままさに、「体験学習」と「共生社会」の時代であり、「地域ファースト」と「一億総活躍社会」(皆が包摂され活躍できる全員参加型社会)の時代である。しかしそれは、政府・行政主導の、学校や地域に対する「強制」や「動員」あるいは「下請け」や「丸投げ」であってはならない。「まちづくりの哲学」の構築が求められるところである。外発的で他律的・依存的な、しかも哲学のない「まちづくり」は地域を亡ぼす。それは、「市民福祉教育」においても然りである。
〇なお、筆者は、「まちづくり」と言うと山崎亮と田村明を思い起こす。山崎は、全国各地で、「自立的共同体」づくりを支援する「コミュニティデザイナー」として活躍している。田村は、総合性や文化性のある都市計画づくりをめざして、平仮名の「まちづくり」を提唱した「都市プランナー」であった。[2]で、宮台は山崎について、蓑原は田村についてそれぞれ言及している。留意しておきたい(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
山崎亮と「コミュニティデザイン」
行政が山崎亮を呼ぶ目的は明白である。一口で言えば、地域住民にとって自治体行政が持つ意味を一変させること。「金を持ってこい」「予算を組んで何とかしろ」と政治家や行政に要求するかわりに、「邪魔しないでくれ」「自分たちの自立的活動をサポートする枠組みやインフラを整えろ」と要求するように、変える。とはいえ、霞が関エリートや自治体エリートには、山崎亮的なコミュニケーションをする能力も機会もない。
行政が「個人を」サポートして共同体を空洞化させるのでなく、行政が「(個人を包摂する)共同体を」サポートする。「弱者への再配分」から「(参加と包摂に向けた)動機づけへの再配分」へのシフトである。行政の山崎亮支援はこれである。(宮台:144ページ)
田村明と「まちづくり」
総合的な都市計画ではなく、法定外の協議型・参加型の都市計画が平仮名のまちづくりの代名詞になってしまっている。
平仮名のまちづくりが独立してしまうと、漢字の都市計画とは切れてしまい、補助金も使えないし、使えても微々たるものしか出してもらえない。国の縦割り組織との対立や国法の解釈をめぐる厳しい領域には立ち入らない、弥縫的なことになる。与えられた枠のなかで、自分たちが活動できる領域のみで行動して、それで「やれた。やれた。成果だ。成果だ」と言う。平仮名の共同体のスケールのまちづくりと、漢字の権力的なガバナンスが避けられない都市計画をトータルに考えるべきである。(蓑原:198~199ページ)
注
田村明に関する記事については、次の拙稿を参照されたい。
<雑感>(53)阪野 貢/改めて、田村明を読む―「まちづくり3部作」について―/2017年10月1日/本文
【初出】
<雑感>(55)阪野 貢/『まちづくりの哲学』という本:「キキカン」と「希望」―読後メモ―/2017年11月15日/本文
むすびにかえて―支配に抗する思想―
<文献>
(1)松村圭一郎『くらしのアナキズム』ミシマ社、2021年10月、以下[1]。
〇人は甚大な被害に見舞われた際、とりわけ新型コロナウイルス禍で、「国家」を意識する。国家はときに、無力で無能な制度と化し、人びとの平和な暮らしを脅かすことがある。国家は人びとにとって強くて大きい存在であり、国家を維持するために国民を犠牲にすることすらある。そもそも国家は、国民全員の生活を十全に支援し、保障する仕組みとして準備(形成)されているものではない。そういう国家のもとで暮らす人びと(弱い存在である生活者)は、国家から一定の距離をとり、ふだんの暮らしのなかで互いに助け合う意識を持ち、その論理を展開する(展開してきた)。そして、国家・社会によって「当たり前」とされているモノやコトを揺さぶり、問い直し、新たな知恵や技法を編み出す(編み出してきた)。そしてそこに、希望と可能性(力)を見出す(見出してきた)。
〇身の回りの出来事や社会的な問題に対処するのは、政治家や行政職員だけではない。その重要な役割を果たすのはむしろ、日々の暮らしを営んでいる一人ひとりの市民・生活者である。政治や行政は、人びとの現実の暮らしのなかにこそ見出される。その点において、現実生活から遊離した観念的で固定的な思考や知識に基づく、しかも「次の選挙を考える」政治家(政治屋)や「前例・横並び主義」に汲々とする行政職員は不要となる。
〇「アナキズム」というと、「無政府主義」「革命」「暴力」「無秩序」等々のイメージがつきまとう。[1]で松村圭一郎はいう。アナキズムの本来の意味は、普通の生活者がふだんの暮らしのなかで、国家や市場の支配権力に向き合いながら、自分たちの問題を自分たちで解決していく点にある。その解決のためには日頃から、「人と人が問題を共有し、手をさしのべられる関係や場」を「耕し」ておくことが肝要となる(176、177ページ)。またそこでは、「コンヴィヴィアリティ(共生的実践)の論理や「対話」と「同意」の技法などが必要かつ重要となる。
〇松村の「くらしのアナキズム」に関する論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
ふだんの・くらしの・アナキズム、その理念と思想
鶴見俊輔は、アナキズムを「権力による強制なしに人間がたがいに助けあって生きてゆくことを理想とする思想」と定義した。(24ページ)
人と人が問題を共有し、手をさしのべられる関係や場を準備しておく。それは政治家や経営者がやれる仕事ではない。むしろふつうの人こそがやっているし、できる仕事だ。(176ページ)
ぼくらはつねに匿名のシステムに依存して生きている。そのシステムが壊れたとき、たよりになるのは、それぞれがつながってきた顔のみえる社会関係だけだ。それが「くらしのアナキズム」である。(180ページ)
政治と暮らしが連続線上にあることを自覚する。政治を政治家まかせにしてもなにも変わらない。政治をぼくらの手の届かないものにしてしまった固定的な境界を揺さぶり、越境し、自分たちの日々の生活が政治そのものであると意識する。生活者が政治を暮らしのなかでみずからやること。それが「くらしのアナキズム」の核心にある。(61ページ)
だれかが決めた規則や理念に無批判に従うことと、大きな仕組みや制度に自分たちの生活をゆだねて他人まかせにしてしまうことはつながっている。アナキズムは、そこで立ち止まって考えることを求める。(227ページ)
くらしのアナキズムは、目のまえの苦しい現実をいかに改善していくか、その改善をうながす力が政治家や裁判官、専門家や企業幹部など選ばれた人たちだけでなく、生活者である自分たちのなかにあるという自覚にねざしている。よりよいルールに変えるには、ときにその既存のルールを破らないといけない。サボったり、怒りをぶつけたり、逸脱することも重要な手段になる。それなら、ぼくらにもできそうな気がする。自分の思いに素直になればいいのだから。(226ページ)
「国家なき社会」における普通の生活者による「公共」
21世紀のアナキストは政府の転覆を謀(はか)る必要はない。自助をかかげ、自粛にたよる政府のもとで、ぼくらは現にアナキストとして生きている。(12ページ)
「公(おおやけ)」とか「公共」といえば、お上(おかみ)のやることだと信じられてきた。今度はそれを企業など別のだれかにゆだねようとしている。ぼくらはどこかで自分たちには問題に対処する能力も責任もないと思っている。でも、ほんとうにそれはふつうの生活者には手の届かないものなのか。アナキズムには、国にたよらずとも、自分たちで「公共」をつくり、守ることができるという確信がある。
この無力で無能な国家のもとで、どのように自分たちの手で生活を立てなおし、下から「公共」をつくりなおしていくか。「くらし」と「アナキズム」を結びつけることは、その知恵を手にするための出発点だ。(13ページ)
「国家なき社会」とは国家と無縁の社会ではない。国家に包摂され、近接しながらもなお、それに抗(あらが)い、自律的な空間を保持しようとした(する)社会だ。(148ページ)
不完全性を肯定し異質性を包摂する「コンヴィヴィアリティ」
世界は流動的で、つねに変化しつづけている。そこでの「人間」は、いつも不完全な存在にすぎない、でも、不完全だからこそ、同じく不完全な他者との交わりのなかに無限の変化の可能性が生まれる。不完全な存在どうしが交わり、相互に依存しあい、折衝・交渉することのうち(裡)にある論理を「コンヴィヴィアリティ(conviviality:共生的実践、自立共生、自律共働)という。(198~199ページ)
コンヴィヴィアル(convivial)な世界(共に生きる世界)では、「改宗」を迫るのではなく、「対話」をすることが異なるものに対処する方法となる。異質なものをすべて包摂することが、その秩序の根幹をなす。自分とは異なる存在は、脅威ではなく、むしろ魅力的なものとして積極的に受け入れられる。(200ページ)
「コンヴィヴィアリティは、異なる人びとや空間、場所を架橋し互いに結びつける。また互いに思想を豊かにし合い、想像力を刺激し、あらゆる人びとが善き生活を求め確かなものとするための革新的な方法をもたらす」(現代のアフリカを代表する人類学者のフランシス・ニャムンジョの言)。(201ページ)
民主主義の根幹であり生活者がなすべき「対話」と「同意」
いまアナキズムを考えることは、どうしたら身のまわりの問題を自分たちで解決できるのか、そのためになにが必要かを考えることでもある。国や政治家よりも、むしろ自分たち生活者のほうが問題に対処する鍵を握っている。その自覚が民主主義を成り立たせる根幹にある。結局だれもが政治参加だと信じてきた多数決による投票は、政治とやらに参加している感をだす仕組みにすぎなかった。たぶんそこに「政治」はない。そうやって政治について誤解したまま、時間のかかる面倒なコンセンサス(同意)をとることを避け、みずから問題に対処することをやめてきた。それが結果として政治家たちをつけあがらせてきたのだ。(151~152ページ)
多数決には少数派に沈黙と妥協を強いる危険性がある。納得いくまで話しあい、異なる意見を調停し、妥協をうながしていく(地味で地道な)対話(コミュニケーション)の技法。それこそが民主的な自治の核心にある。(158ページ)
「自治」は、(自助を求める)国家(政府)を補完するような自治ではない。むしろ国の動きをけん制し、分け与えるよう求め、主導権をとりもどすためのものだ。国によりよき状態を要求し、その力への抵抗の足場をつくる。(222ページ)
〇アナキズムは、互酬性や相互扶助に基づく「支配に抗する思想」である。アナキズムは、「個人的自由の追求と連帯の追求とがけっして矛盾しないと考える思想」である。「個人の自由の確保こそが真の連帯の条件である」(山田広昭『可能なるアナキズム―マルセル・モースと贈与のモラル―』インスクリプト、2020年9月、195ページ)。
〇今日、資本主義社会の行き詰まりについて批判する文脈で、市民主導の地域社会の再生が求められ、「コモンズ」(共有資源)や「コミュニズム」(共同体主義)について論じられる。それは、資本主義(新自由主義)でも政治・行政主導でもない「社会像」(「脱成長コミュニズム」)であり、自然環境や福祉、医療、教育などのコモンズについて、市民による・市民のための自律的・民主的な運営管理がなされることをめざす。筆者はそこに、アナキズムの思想を見出す。すなわち、アナキズムに関して、「コミュニズム」や「地域主権社会」の理念を基盤に、「市民」のつながりや集まりである地域コミュニティにおける「共働」をイメージしている。
【初出】
<雑感>(147)阪野 貢/追記/「アナキズム」考―松村圭一郎著『くらしのアナキズム』のワンポイントメモ―/2021年12月5日/本文
備 考 ―<文献>一覧―
はじめに―哲学のある教育実践―
(1)高久清吉『哲学のある教育実践―「総合的な学習」は大丈夫か―』教育出版、2000年4月。
01 「ふくし」の哲学
(1)三谷尚澄『哲学しててもいいですか? ―文系学部不要論へのささやかな反論―』ナカニシヤ出版、2017年3月。
(2)広井良典『福祉の哲学とは何か―ポスト成長時代の幸福・価値・社会構想―』ミネルヴァ書房、2017年3月。
(3)糸賀一雄『福祉の思想』日本放送出版協会、1968年2月。
(4)阿部志郎『福祉の哲学』誠信書房、1997年4月。
(5)伊藤隆二『この子らは世の光なり』樹心社、1988年9月。
(6)仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉―<贈与のパラドックス>の知識社会学―』名古屋大学出版会、2011年2月。
(7)大橋謙策『社会福祉入門』放送大学教育振興会、2008年3月。
02 「正義感覚」の育成
(1)伊藤恭彦『さもしい人間―正義をさがす哲学―』新潮新書、2012年7月。
03 「人間的連帯」の言説
(1)馬淵浩二『連帯論―分かち合いの論理と倫理―』筑摩書房、2021年7月。
(2)齋藤純一『不平等を考える―政治理論入門―』ちくま新書、2017年3月。
04 「自己決定」の実相
(1)小松美彦『「自己決定権」という罠―ナチスから相模原障害者殺傷事件まで―』言視舎、2018年8月。
(2) 吉崎祥司『「自己責任論」をのりこえる―連帯と「社会的責任」の哲学―』学習の友社、2014年12月。
(3) 高橋隆雄・八幡英幸編『自己決定論のゆくえ―哲学・法学・医学の現場から―』九州大学出版会、2008年5月。
(4) 湯浅誠『どんとこい、貧困!』イースト・プレス、2011年7月。
05 「世間」からの解放
(1)阿部謹也『「世間」とは何か』講談社現代新書、1995年7月。
(2)阿部謹也『学問と「世間」』岩波新書、2001年6月。
(3)佐藤直樹『「世間」の現象学』青弓社、2001年12月。
(4)山本七平『「空気」の研究』文藝春秋、1983年10月。
(5)鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力―日本社会はなぜ息苦しいのか―』講談社現代新書、2020年8月。
(6)岡檀『生き心地の良い町―この自殺率の低さには理由がある―』講談社、2013年7月。
06 「しょうがい」という言葉
(1)荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』柏書房、2021年5月。
(2)荒井裕樹『車椅子の横に立つ人―障害から見つめる「生きにくさ」―』青土社、2020年8月。
(3)荒井裕樹『障害者差別を問いなおす』ちくま新書、2020年4月。
(4)荒井裕樹『障害と文学―「しののめ」から「青い芝の会」へ―』現代書館、2011年2月。
(5)荒井裕樹『差別されてる自覚はあるか―横田弘と青い芝の会「行動綱領」―』現代書館、2017年1月。
(6)佐藤貴宣・栗田季佳編『障害理解のリフレクション―行為と言葉が描く〈他者〉と共にある世界―』ちとせプレス、2023年3月。
07 「生」の倫理
(1)野崎泰伸『生を肯定する倫理へ―障害学の視点から―』白澤社、2011年6月。
(2)野崎泰伸『「共倒れ」社会を超えて―生の無条件の肯定へ!―』筑摩書房、2015年3月。
08 「しんがり」の姿勢
(1)鷲田清一『しんがりの思想―反リーダーシップ論―』角川新書、2015年4月。
(2)駒村康平編『社会のしんがり』新泉社、2020年3月。
09 「助けて」の表明
(1)奥田知志『もう、ひとりにさせない―わが父の家にはすみか多し―』いのちのことば社、2011年6月。
(2)奥田知志『「助けて」と言おう―3・11後を生きる―』日本キリスト教団出版局、2012年8月。
(3)奥田知志・茂木健一郎『「助けて」と言える国へ―人と社会をつなぐ―』集英社新書、2013年8月。
(4)佐藤彰・奥田知志・宋富子、明治学院150周年委員会編『灯を輝かし、闇を照らす―21世紀を生きる若い人たちへのメッセージ―』いのちのことば社、2014年3月。
(5)奥田知志・稲月正・垣田裕介・堤圭史郎『生活困窮者への伴走型支援―経済的困窮と社会的孤立に対応するトータルサポート―』明石書店、2014年3月。
(6)埋橋孝文、同志社大学社会福祉教育・研究支援センター編『貧困と生活困窮者支援―ソーシャルワークの新展開―』法律文化社、2018年9月。
10 「愛郷心」の相克
(1)将基面貴巳『反「暴君」の思想史』平凡社新書、2002年3月。
(2)将基面貴巳『日本国民のための愛国の教科書』百万年書房、2019年8月。
(3)将基面貴巳『愛国の構造』岩波書店、2019年7月。
(4)姜尚中『愛国の作法』(朝日新書)朝日新聞出版、2006年10月。
(5)佐伯啓思『日本の愛国心―序説的考察―』中公文庫、2015年6月。
(6)市川昭午『愛国心―国家・国民・教育をめぐって―』学術出版会、2011年9月。
(7)鈴木邦男『〈愛国心〉に気をつけろ!』岩波ブックレット、2016年6月。
11 「差別」の本質
(1)キム・ジへ、尹怡景訳『差別はたいてい悪意のない人がする―見えない排除に気づくための10章―』大月書店、2021年8月。
(2)神谷悠一『差別は思いやりでは解決しない―ジェンダーやLGBTQから考える―』集英社新書、2022年8月。
12 「共感」の功罪
(1)山竹伸二『共感の正体―つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか―』河出書房新社、2022年3月。
(2)ポール・ブルーム、高橋洋訳『反共感論―社会はいかに判断を誤るか―』白揚社、2018年2月。、
(3)永井陽右『共感という病―いきすぎた同調圧力とどう向き合うべきか?―』かんき出版、2021年7月。
13 「利他」の学問
(1)伊藤亜紗編、中島岳志・若松英輔・國分功一郎・磯崎憲一郎『「利他」とは何か』集英社新書、2021年3月。
(2)中島岳志『思いがけず利他』ミシマ社、2021年10月。
(3)若松英輔『はじめての利他学』NHK出版、2022年5月。
14 “Well-being ” の視点
(1)マーティン・セリグマン、宇野カオリ監訳『ポジティブ心理学の挑戦―“幸福”から“持続的幸福”へ―』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2014年10月。
(2)前野隆司『幸せのメカニズム―実践・幸福学入門―』講談社現代新書、2013年12月。
(3)前野隆司『実践・脳を活かす幸福学 無意識の力を伸ばす8つの講義』講談社、2017年9月。
(4)前野隆司・前野マドカ『ウェルビーイング』日経文庫、2022年3月。
(5)前野隆司『ディストピア禍の新・幸福論』プレジデント社、2022年5月。
(6)渡邊淳司・ドミニク=チェン監修・編著『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために―その思想、実践、技術』ビー・エヌ・エヌ、2020年3月。
(7)石川善樹・吉田尚記『むかしむかし あるところに ウェルビーイングがありました―日本文化から読み解く幸せのカタチ―』KADOKAWA、2022年1月。
(8)草郷孝好『ウェルビーイングな社会をつくる―循環型共生社会をめざす実践』明石書店、2022年7月。
(9)内田由紀子『これからの幸福について―文化的幸福観のすすめ―』新曜社、2020年5月。
15 「自前」の思想
(1)清水展・飯嶋秀治編『自前の思想―時代と社会に応答するフィールドワーク』京都大学学術出版会、2020年10月。
(2)佐高信・田中優子『池波正太郎「自前」の思想』集英社新書、2012年5月。
(3)伊藤幹治『柳田国男と梅棹忠夫―自前の学問を求めて』岩波書店、2011年5月。
16 「生きづらさ」の正体
(1) 中西新太郎『〈生きにくさ〉の根はどこにあるのか―格差社会と若者のいま―』(前夜セミナーBOOK)特定非営利活動法人 前夜、2007年3月。
(2) 湯浅誠・川添誠編『「生きづらさ」の臨界―“溜め”のある社会へ―』旬報社、2008年11月。
(3) 香山リカ・上野千鶴子・嶋根克己『「生きづらさ」の時代―香山リカ×上野千鶴子+専大生―』専修大学出版局、2010年11月。
(4) 岡田尊司『「生きづらさ」を超える哲学』(PHP新書)PHP研究所、2008年12月。
(5)小山真紀・相原征代・舩越高樹編『生きづらさへの処方箋』ナカニシヤ出版、2019年2月。
17 「相互支援」の人間学
(1)支援基礎論研究会編『支援学―管理社会をこえて―』東方出版、2000年7月。
(2)舘岡康雄『利他性の経済学―支援が必然となる時代へ―』新曜社、2006年4月。
(3)舘岡康雄『世界を変えるSHIEN学―力を引き出し合う働きかた―』フィルムアート社、2012年11月。
(4)森岡正博編著『「ささえあい」の人間学―私たちすべてが「老人」+「障害者」+「末期患者」となる時代の社会原理の探究―』法藏館、1994年1月。
18 「ふつう」の功罪
(1)深澤直人『ふつう』D&DEPARTMENT PROJECT、2020年7月。
(2)佐野洋子『ふつうがえらい』(新潮文庫)、新潮社、1995年3月。
(3)泉谷閑示『「普通がいい」という病』(講談社現代新書)、講談社、2006年10月。
(4)キリーロバ・ナージャ『6ヵ国転校生・ナージャの発見』集英社インターナショナル、2022年7月。
19 「批判的教育」の使命
(1)マイケル・W・アップル、ジェフ・ウィッティ、長尾彰夫編著『批判的教育学と公教育の再生―格差を広げる新自由主義改革を問い直す―』明石書店、2009年5月。
(2)ヘンリ―・A・ジルー、渡部竜也訳『変革的知識人としての教師―批判的教授法の学びに向けて―』春風社、2014年1月。
20 「対話」の技術
(1)山口裕之『コピペと言われないレポートの書き方教室―3つのステップ―』新曜社、2013年7月。
(2)山口裕之『「大学改革」という病―学問の自由・財産基盤・競争主義から検証する―』明石書店、2017年7月。
(3)山口裕之『人をつなぐ 対話の技術』日本実業出版社、2016年4月。
21 「 弱さ」のデザイン
(1)天畠大輔『<弱さ>を<強み>に―突然複数の障がいをもった僕ができること』岩波書店、2021年10月。
(2)澤田智洋『マイノリティデザイン―「弱さ」を生かせる社会をつくろう―』ライツ社、2021年1月。
(3)高橋源一郎・辻信一『弱さの思想―たそがれを抱きしめる―』大月書店、2014年2月。
(4)鷲田清一『<弱さ>のちから―ホスピタブルな光景―』講談社、2014年11月。
22 「 共同体」の教育的営為
(1)内田樹『サル化する世界』文藝春秋、2020年2月。
(2)内田樹・平川克己『沈黙する知性』夜間飛行、2019年11月。
23 「贈与」の意義
(1)白井聡『武器としての「資本論」』東洋経済新報社、2020年4月。
(2)斎藤幸平『人新世の「資本論」』集英社、2020年9月。
(3)内田樹『コモンの再生』文藝春秋、2020年11月。
(4)マルセル・モース、森山工訳『贈与論 他二篇』岩波文庫、2014年7月。
(5)仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉――〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』名古屋大学出版会、2011年2月。
(6)山田広昭『可能なるアナキズム――マルセル・モースと贈与のモラル』インスクリプト、2020年9月。
24 「共事者」の実践的態度
(1)斎藤幸平『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』KADOKAWA、2022年11月。
25 「思いやり」の暴力
(1)長谷川眞理子・山岸俊男『きずなと思いやりが日本をダメにする―最新進化学が解き明かす「心と社会」―』集英社インターナショナル、2016年12月。
(2)中島義道『「思いやり」という暴力―哲学のない社会をつくるもの―』(PHP研究所、2016年2月。
(3)清水将一『ボランティアと福祉教育研究』風詠社、2021年6月。
26 「哲学対話」の方法
(1)梶谷真司『考えるとはどういうことか―0歳から100歳までの哲学入門―』幻冬舎新書、2018年9月。
(2)河野哲也編『ゼロからはじめる哲学対話―哲学プラクティス・ハンドブック―』ひつじ書房、2020年10月。
27 「地域共生社会」の模索
(1)渡邉琢『介助者たちは、どう生きていくのか―障害者の地域自立生活と介助という営み』生活書院、2011年2月。
(2)渡邉琢『障害者の傷、介助者の痛み』青土社、2018年12月。
28 「まちづくりの哲学」の構築
(1)アーク都市塾企画/戸沼幸市編著『まちづくりの哲学』彰国社、1991年12月。
(2)代官山ステキなまちづくり協議会企画・編集、蓑原敬・宮台真司『まちづくりの哲学―都市計画が語らなかった「場所」と「世界」―』ミネルヴァ書房、2016年6月。
むすびにかえて―支配に抗する思想―
(1)松村圭一郎『くらしのアナキズム』ミシマ社、2021年10月。