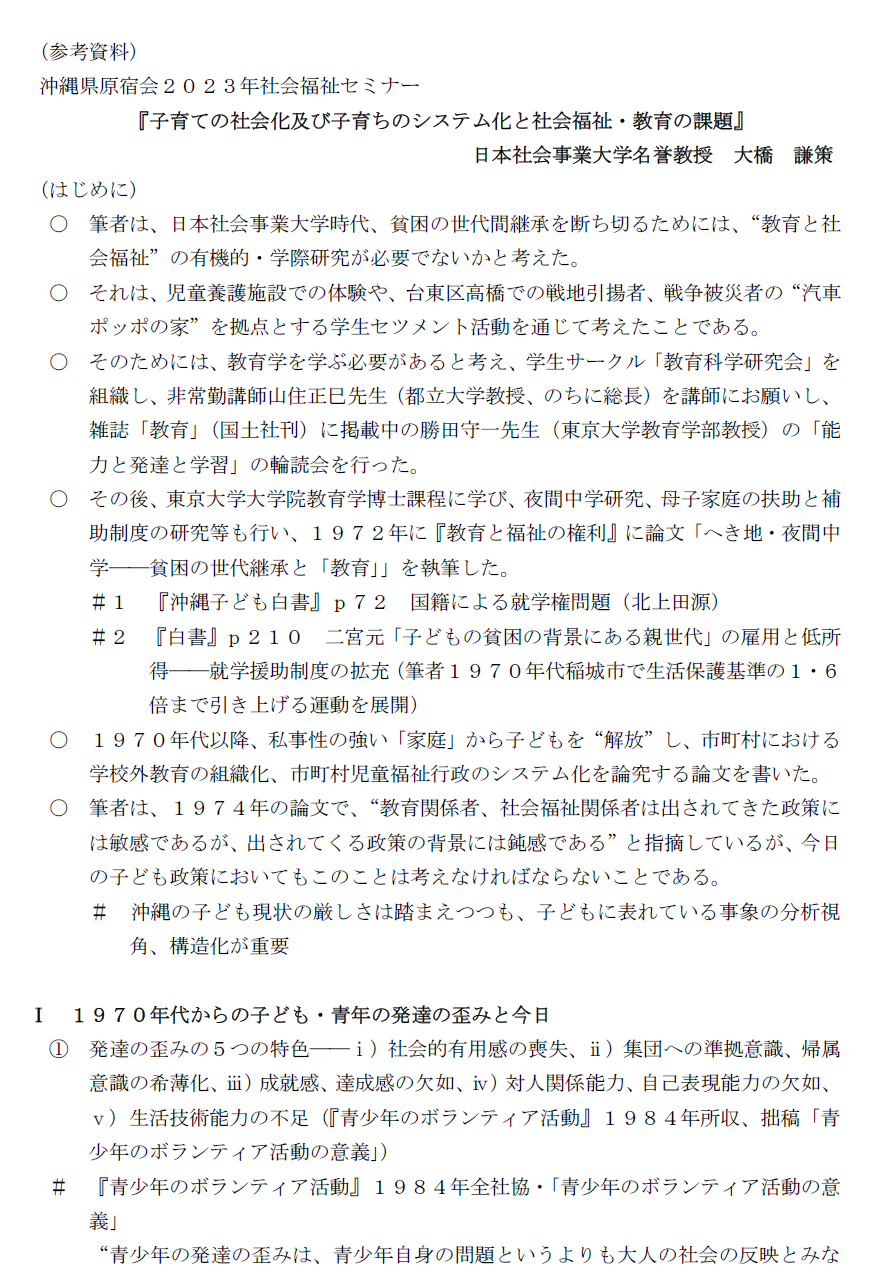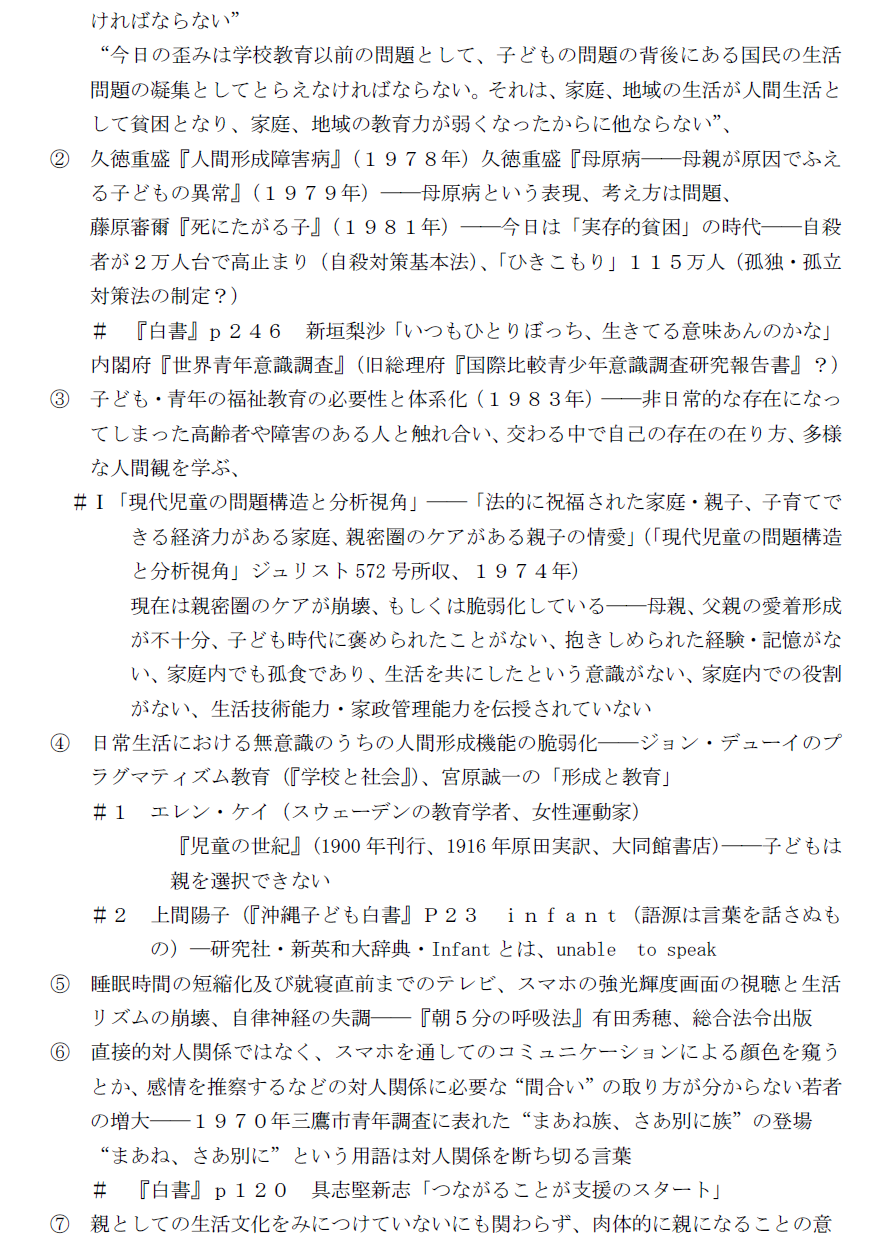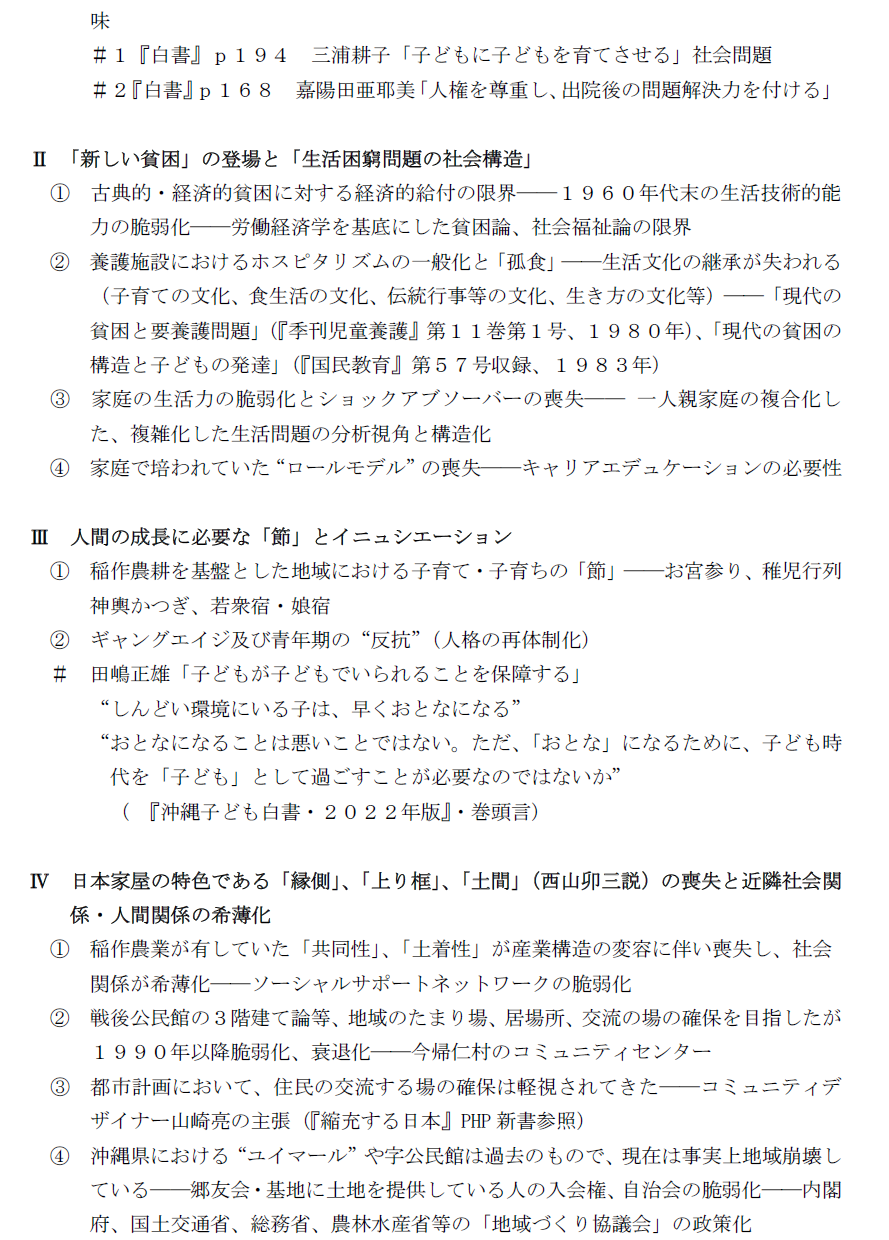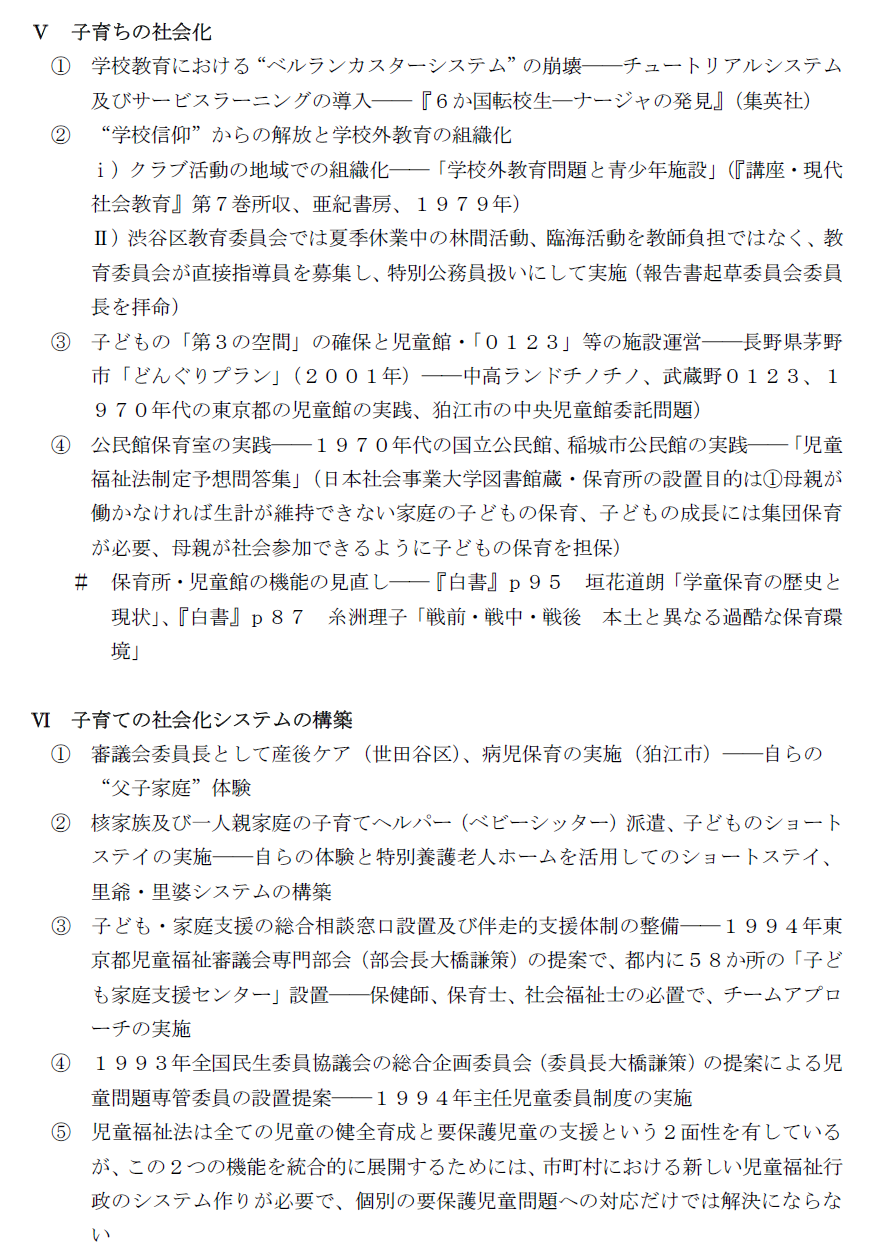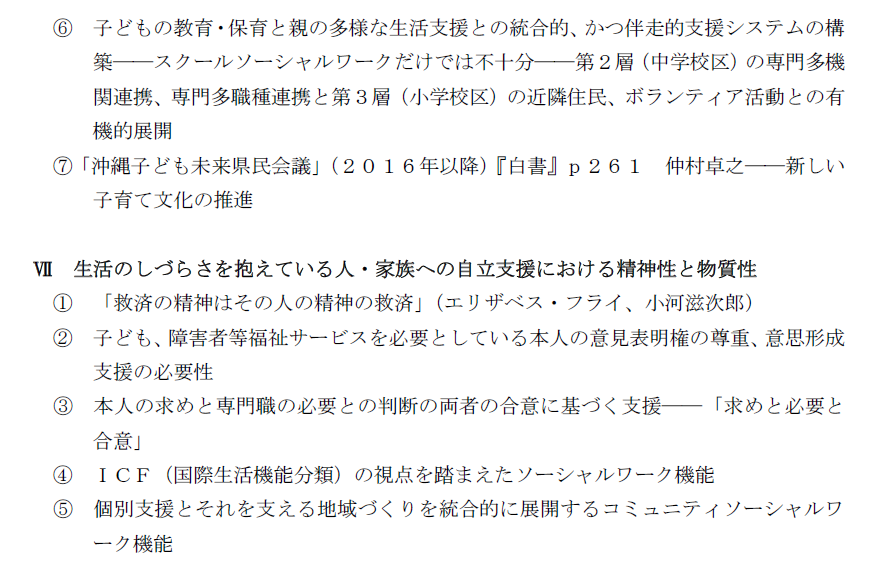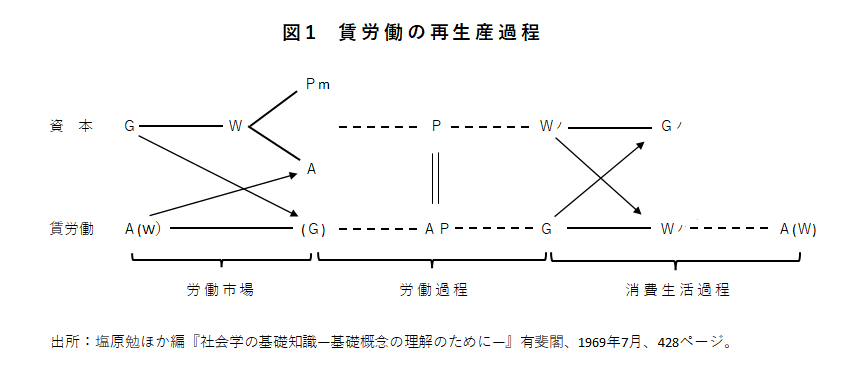〇吉田竜平(北星学園大学)によると、社会福祉研究領域において自己責任論を問いなおすための課題には次のようなものがある。①自己責任とそうでないとされる境界の設定、②自己責任でなく不運な状況にある人々がスティグマを感じることなく福祉サービスを利用するための方法の模索、③責任概念自体の捉えなおしと公的責任の拡大、④他者の共感の広がりと全ての「個」が他者から承認される社会についての議論の深化、がそれである(参考文献 ①)。
〇筆者(阪野)の手もとに、ヤシャ・モンク著、那須耕介・栗村亜寿香訳『自己責任の時代―その先に構想する、支えあう福祉国家―』(みすず書房、2019年11月。以下[1])という本がある。[1]においてモンクは「まず、政治における自己責任論の興隆を跡づけ、それが社会保障制度に弱者のあら探しを強いてきた過程を検討する。次に、被害者に鞭打つ行為をやめさせたい善意の責任否定論が、皮肉にも自己責任論と同じ論理を前提にしていると指摘する。そしてどちらの議論も的を外していることを明らかにし、責任とは懲罰的なものではなく、肯定的なものでありうる」(カバーそで)と説く。
〇別言すればこうである。かつて「責任」という言葉は、他者を助ける個人の義務を意味するものとして使われてきた。現在ではそれが変容し、「責任」という概念を議論する際、人びとの選択の結果(「自己選択」「自己決定」)に対して責任を負う「結果責任」(「懲罰的自己責任論」)が強調されている。それに対して、先天的あるいは構造的な要因などを除いて、純粋な結果責任のみを追求すべきであるという「責任否定論」がある。それらの主張は、結局のところ、自己選択の結果に関しては程度の差はあれ、責任を取らなければならないという前提から脱してはいない。そこで、責任の肯定的な部分を再発見し、肯定的な責任概念(「肯定的責任像」)を再興すること、すなわち「多くの人が責任を果たそうとしている理由を認め、かれらの引き受けた責任の達成を実際に援助するような責任観」(148ページ)が必要となる。それは、人びとに、「主体性」を取り戻すことでもある(参考文献 ②)。
〇上述の吉田の指摘に留意しながら、[1]におけるモンクの「自己責任論」の論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
責任像の変容―「他者への責任」から「自己責任」へ―
かつて責任という言葉は他者を助ける個人の義務のことを思い起こさせたものだが、今日では、自分で自分の面倒をみる責任――そしてそれを怠ったときにはその結果を引き受ける責任――のことが真っ先に思い浮かぶ。(中略)我々は「義務としての責任 responsibility-as-duty」〔他者への責任〕というとらえ方が優勢だった世界から、「結果責任としての責任 responsibility-as-accountability」〔自己責任〕という新たなとらえ方が舞台を支配する世界に移ったのである。責任そのものが人目を引くようになったことではなく、この変容した責任像が優位を占めていることこそが、責任の枠組みと責任の時代の両方をまとめて特徴づけているのである。(29~30ページ)
懲罰的責任論と責任否定論の論理
一見、懲罰的責任像と責任否定論とは正反対の立場のように思える。しかし、特定の問題について見解を対立させつつ、より深層の知的勢力図の分布を共有している者たちにはよくあることだが、その表面下にはおびただしい類似点が潜んでいる。適切な帰責条件については動かしがたい不一致が残るものの、責任の規範的重要性については、両者は驚くほど見方を一致させているのである。相違を声高に言いつのっておきながら、両派は次の点についてひそかに合意を交わしている。ある人の取り分が他の同胞市民よりも少ないこと、あるいは現に援助を要する状況にあることに関しては、当人がみずから招いたことかどうかによって、当人がどの程度補償を正当に要求できるのかが決まる、という点である(懲罰的責任論は、外的な環境や要因などによる、本人の責任ではないものについて懲罰的な責任を負わせることには反対するが、当人が制御することができたにもかかわらず自分が招いた結果については責任を負うべきであるとする。:筆者)。(18~19ページ)
肯定的な責任観の再興
責任の時代は、我々の政治的想像力を狭め、公共政策と現代哲学のどちらにも深刻な盲点を作ってきた。これへの主たる反発――筆者が責任否定論と呼んできたもの――も、ほぼ空振りに終わった。それは抗(あらが)うべき相手と同じ知的潮流に属しており、結局のところ理論的説得力も実践的効果もなかったのである。したがって、政治的にも哲学的にも、いまこそ肯定的な責任観を発展させるべき時だ。多くの人が責任を果たそうとしている理由を認め、かれらの引き受けた責任の達成を実際に援助するような責任観が必要なのである。(148ページ)/今日では、(中略)責任は結果責任の問題に置き換えられ、たえず懲罰的な仕打ちをちらつかせるようになった。/したがって、肯定的な責任観――個人が遂行し、社会が促進すべきものとしての責任のとらえ方――の再興をはかるには、我々の責任理解を広げる必要があるだろう。(149ページ)
肯定的な責任観の重要性
(肯定的な責任観が重要なのは)①自己への責任、自己志向的理由/自己への責任を負うことを通して、自分自身の生活に対して真の主体性の感覚をもつことができることによる(28、150ページ)。②他者への責任、他者志向的理由/他者への責任を果たすことを通して、一定の社会的役割や役目を引き受けることができ、その役割に伴う責任が自分にとってたいへん有意義だという思い(アイデンティティ)を形成することができることによる(28、159ページ)。③他者を責任ある存在と考えること、社会的理由/他者を、自分の行動への責任を負いうる存在とみなすことを通して、他者との有意義な関係を築くことができることによる(28、163ページ)。
自己志向的責任と主体性の獲得(上記①)
自分の生活を制御している感覚、すなわち主体性の感覚を求める願望は、少なくとも三つの形をとりうる。第一に、我々は一定の範囲で自分の生を実際に制御することを望んでいるはずである。第二に、我々は自分が自己への責任を果たしていると感じることを必要としているはずである。そして第三に、我々は自己への責任を果たしていると周囲からみなされることを必要としているはずである。(150~151ページ)/これと関連して、人が自己への責任を重んじる理由として、人は、自分の主体性を通じて最も基本的な欲求と欲望にかなう未来をわずかなりとも手にできる、という確信を必要としていることがあげられる。(157ページ)
他者志向的責任とアイデンティティの構成(上記②)
他者への責任を果たすことは、多くの人の生活のなかで役割を果たしていることである。他者への責任を果たすには多種多様なやり方がある。友人や家族に思いやりをもって接するという単純な行為から深い満足を得る人もいる。一定の社会的役割、配偶者や親、ペットの飼主としての役目を引き受けようとする決意する人もいるが、そこにはこれらの役割に伴う責任が自分にとってたいへん有意義だという思いがはたらいている。(159ページ)/個別の「企て project」に向けられた責任もまた、我々が他者に負う責任としては大切である。(162ページ)/(これらの)他者に対する責務、自分の家族への責務やみずから引き受けた企てへの責務は、人びとのアイデンティティを構成する。(172ページ)
社会的理由と関係性の構築(上記③)
他者を責任ある存在と考えることが重要である理由は、一つは、他者と有意義な関係を築くには、相手のことを自分の行動に責任を負える存在だと考える必要があるからである。第二の理由は、責任主体性の相互承認は、あらゆる平等主義的社会の成立条件でもあるからである。真に平等主義的な社会のねらいは、単に人びとに同程度の物質的資産を所有させることだけではなく、完全な市民としての対等な地位を互いに認めさせることでもある。この地位が致命的に損なわれるのは、一部の市民には完全な責任主体性が認められ、他方には認められない、という事態が生じた場合のことである。(164ページ)
肯定的責任像の概念
懲罰的責任像および責任否定論とは対照的に、肯定的責任像はこう主張する。(183ページ)/(1)一般に、特定の行動に責任が生じるのは、その行動が犯意mens reaという伝統的な要件を満たしている場合である。特定の行為について責任を負うには、自分自身の行動を一定範囲で制御できなければならず、たとえば条件反射的な行動であってはならない。(183ページ)/(2)特定の帰結の発生を促した行動に責任があるという事実があるからといって、その人にその帰結全体への責任があることにはならない。また、その帰結への責任の範囲は、どんなに単純化しても、その人の行動がその帰結の原因だったか否かに関する実証主義的説明に左右されることはない。(184ページ)/(3)誰かが特定の帰結について責任があるということを確定した後も、引き続き、そのことについてその人に結果責任をも負わせるべきかという問題が残る。特に、困窮状態にある人が自業自得でそのような状態に陥ったという事実があったからといって、即座にこの人への援助を否定すべきだということにはならない。(184ページ)
公共政策における肯定的責任像
責任像を懲罰的で前制度的なものから肯定的で制度的なものに切り替えると、公共政策の中心課題に関する理解を少なくとも次の三点で更新することになる。いくらか逆説的だが、そうすれば実際に意味ある仕方で責任を論じる方法を詳述できるようになるのである。非理想的な状況では、責任を負うことの意義を強調すること――そして各人の選んだ責任によって意味づけられた多くの生きがいをめぐる言説を流布させること――は、一般の市民の主体性を強化するプラグマテックな方法でありうる。同時にそれは、人に自分の責任遂行への誘因を与える鞭(むち)にばかり目を向ける傾向を克服し、人が望む責任を果たせるようになるための物質的、教育上の前提条件を整える政策設計を支える。そして最後に、それは福祉国家の官僚たちの努力を喚起して、かれらを、(片方が得点・利益するともう一方が失点・損失し、プラスマイナスゼロになる:阪野)ゼロサム・ゲームをとり仕切る懲罰的裁定者から協働的企てに関与する建設的パートナーへと変貌させうるのである。(202ページ)
「自己責任の時代」の克服
我々の選択次第で、我々は自己責任の時代を乗り越えることができる。(210ページ)/自己責任の時代の克服に必須の要素の一つは、責任の観念が求められている理由と、この概念にもっと前向きの色彩をもたせる方法とについて再考することである。(211ページ)/自己責任の時代を乗り越えるために必要なもう一つの作業は、我々の道徳的、政治的生活を別の長く忘れられてきた価値の言葉でとらえなおすことである。(211ページ)
〇限定的であるが、以上を要すると、①責任は懲罰的なものではなく、肯定的な意味を持つ(責任は、個人がそれを負い、それを社会が促進・支援すべきものである)。②懲罰的責任論と責任否定論は、結果責任について同じ論理(責任の規範的重要性)を前提にしている。③人は責任を負うことによって主体性を取り戻す(確保する)ことができ、自己責任の否定は個人の主体性を否定することに通じる。④他者への責任を果たすことは、一定の社会的役割や役目を果たすことになり、アイデンティティを育む。⑤他者を責任ある存在として認めること(責任主体の相互承認)は、他者と有意義な協働的な関係を築き、平等主義的社会の成立を促す。⑥責任を肯定的に展望するためには、責任を引き受けることを促すのではなく、責任を負う能力を養う物質的・教育的基盤を整備することが肝要となる。⑦こうした新しい責任について、その概念を社会的に周知させる方法について考えるとともに、新しい価値観に基づいて再考することが必要である、となろう。
〇価値観や社会課題が多様化・複雑化している現代社会にあって、ある結果の原因を一義的に個人に帰したり、本人の能力や努力の不足あるいは選択の失敗によって生じた結果を自業自得としてその責任を個人に押し付けることは、ほぼ不可能である。そこに求められるのは、自己責任の限界についての理解と認識である。とともに、自己責任ではなく、相互信頼と相互責任(社会的責任)を生み出す社会の構築であり、そのための物質的・教育的基盤の整備である。さらに付言すれば、自己責任を強いる自己決定ではなく、相互責任に繋がる相互決定の尊重であろう。しかもそれは、理性的・民主主義的な討議に依ることは言うまでもない。例によって唐突であるが、これらは「まちづくりと市民福祉教育」の実践・研究にも通底する。
参考文献
① 吉田竜平「自己責任論を問い直す―運の平等主義の視点から―」『北星学園大学社会福祉学部 北星論集』第59号、北星学園大学、2022年3月、61~73ページ。
② 有吉永介「ヤシャ・モンク『自己責任の時代』再考」『立教大学大学院教育学研究集録』第20号、立教大学大学院文学研究科教育学専攻、2023年3月、31~38ページ。