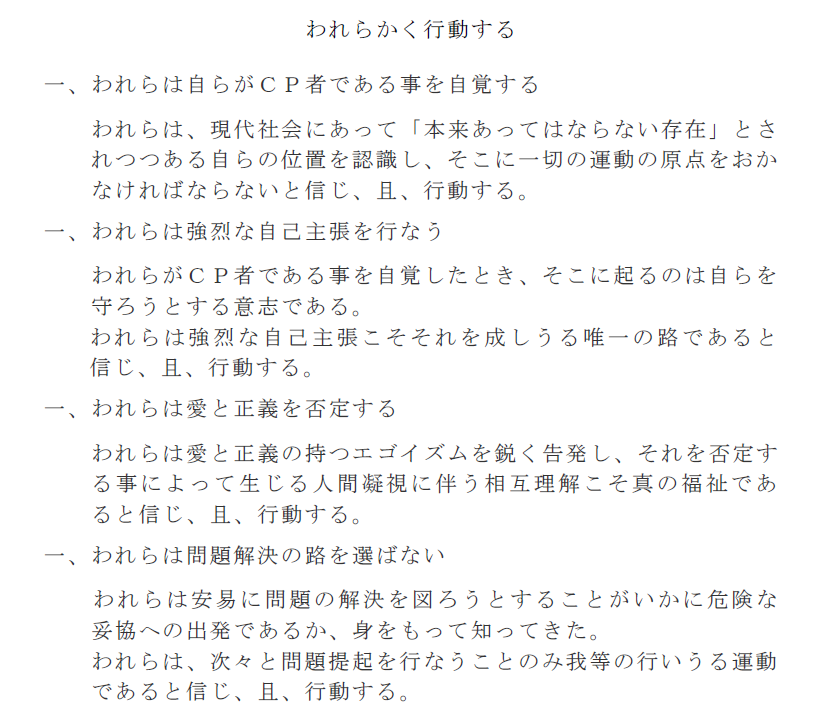〇1970年代から80年代にかけて、日本脳性マヒ者協会「青い芝の会」神奈川県連合会の横田弘(よこた・ひろし)や横塚晃一(よこづか・こういち) らは、「障害者は不幸」「障害者は施設で生きるしかない」「障害者は殺されてもやむを得ない」といった固定的な価値観(常識)と闘った(下記[3]134ページ。注①②)。その後、「完全参加と平等」(1981年の「国際障害者年」)をはじめ「バリアフリー社会」「自立生活」「地域生活支援」「地域共生社会」、あるいは「共生共育」(インクルーシブ教育)などの実現をめざした障がい者運動が展開された。2016年4月に「障害者差別解消法」(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が施行され、同年7月にはその対極に位置する「相模原障害者施設殺傷事件」が起きた。「差別を解消するための法律を作れば、そのうち差別は克服される」といってしまえるほど、この社会は単純な仕組みにはなっていない([3]13ページ)。元施設職員の犯人・植松聖(うえまつ・さとし)は「重度障害者は不幸をばらまく存在であり、絶対に安楽死させなければいけない」と断言した。そしていま、早くも事件の風化が進んでいる。ここに障がい者差別の「現在」があり、青い芝の会の「過去」の闘争やその思想が浮かび上がる。
〇筆者(阪野)の手もとに、荒井裕樹(あらい・ゆうき。専門は障害者文化論、日本近現代文学)の本が5冊ある(しかない)。(1)『まとまらない言葉を生きる』(柏書房、2021年5月。以下[1])、(2)『車椅子の横に立つ人―障害から見つめる「生きにくさ」―』(青土社、2020年8月。以下[2])、(3)『障害者差別を問いなおす』(筑摩書房、2020年4月。以下[3])、(4)『障害と文学―「しののめ」から「青い芝の会」へ―』(現代書館、2011年2月。以下[4])、(5)『差別されてる自覚はあるか―横田弘と青い芝の会「行動綱領」―』(現代書館、2017年1月。以下[5])、がそれである。
〇荒井は、「この社会に存在する数々の問題について『言葉という視点』から考えること」を仕事にする気鋭の「文学者」である。専門は、厳しい境遇に追いやられている「被抑圧者の自己表現活動」([1]20ページ)である。主な研究対象(テ―マ)は、障害や病気と共に生きる人たちの「言葉」であり、障がい者運動や患者運動に関わる(関わった)人たちの表現活動である。荒井はいう。1970年代に、障がい者の苦労をわかってもらうのではなく、世間の障がい者差別と闘った「青い芝の会」神奈川県連合会の横田は、「障害者は不幸」「障害は努力して克服すべき」という考えが常識だった時代に「なんで障害者のまま生きてちゃいけないんだ?!」と言った([1]151ページ)。障がい者運動家たちからもらった最大のものは、「『正しい』とか『立派』とか『役に立つ』といった価値観自体を疑う感覚」([1]244ページ)である。「ある人の『生きる気力』を削(そ)ぐ言葉が飛び交う社会は、誰にとっても『生きようとする意欲』が湧(わ)かない社会になる。そんな社会を次の世代には引き継ぎたくない」([1]29ページ)。荒井が依拠する基本的な視点や認識のひとつであり、ひとりの「学者」としての覚悟(姿勢)である。
〇[1]は、「言葉」に潜む暴力性を明らかにし、その息苦しさ(「言葉の壊れ」)に抗(あらが)うための18本のエッセイ集である。荒井は、「言葉の殺傷力」、特に2010年代以降に顕著になった「言葉が壊されている」現実に、猛烈な危機感を持つ。「言葉というものが、偉い人たちが責任を逃れるために、自分の虚像を膨らませるために、敵を作り上げて憂さを晴らすために、誰かを威圧して黙らせるために、そんなことのためばかりに使われ続けていったら、どうなるのだろう」([1]247ページ)。これが[1]の各エッセイに通底する問題意識である。空虚なスローガンやキャッチフレーズとともに、質疑や質問に向き合わず、討論やコミュニケーションを遮断した安倍政権の汚く卑劣な言葉やフレーズを思い出す。
〇[2]は、学術誌に掲載した論文と文芸誌やネットジャーナルに寄稿したエッセイの14本の論考から成っている。荒井の研究者人生「最初の10年間の総括」([2]222ページ)である。ほとんどの人が「車椅子の横に立つ人」を障がい者の「身内」か「介護者(福祉職)」と決めつけてしまう。障害や障がい者をめぐるある種の固定観念や思い込み(ステレオタイプ)にとらわれ、それを定型的・限定的に捉えてしまう狭い範囲での想像力は、何から生み出されるのか。障がい者が経験する現代社会における「生きにくさ(生きづらさ)」や、それをめぐる「語りにくさ(語られにくさ)」を言葉でどう捉えるのか。こうした「にくさ」が交錯(こうさく)する問題について考える端緒を開こうとするのが[2]である。そして荒井はいう。「いつか(その)正体を見極めて、ぶち壊したいと思う」([2]34ページ)。
〇[3]は、1970年代から80年代にかけてさまざまな抗議行動(闘争)を繰り広げた「青い芝の会」神奈川県連合会の問題提起を、その運動に参加した障がい者たちの言葉やフレーズ、思想や価値観などを通して丹念に振り返り、「障害者差別を問い直す」。例えば、青い芝の会が「障害者と対立関係にある健康な者」「障害者を差別する立場にいる健康な者」を「健全者」([3]73ページ)と呼んだ。あるいは、憲法第25条に規定された「生存権」を「生きる権利」「この世に存在する権利」([3]194ページ)という意味で使ったことなどに言及し、そこに青い芝の会の思想をみる。そして荒井はいう。「障害者本人たちが、障害者抜きに作られた『常識』に対して、異議申し立てを行なってきた経緯」([3]22ページ)について、その具体的な事例を一つひとつ調べていくことが重要である。障がい者差別についてあまりにも早急にあるいは短絡的に「解決」を求める発想は、「弱い立場の人に我慢や沈黙を強いたり、そうした『解決』に馴染(なじ)めない人たちを排除したりする方向へと進みかねない」([3]252ページ)。複雑に入り組んだ障がい者差別の問題について考える荒井のスタンス(立場)である。
〇本稿では、例によって我田引水的であるが、福祉教育(とりわけその実践)に関してしばしば見聞きする言葉やフレーズのいくつかを[1][2][3]から抜き出し、荒井のその論点や言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「障害」という言葉と定義
これまで「障害」は「不幸の代名詞」「生きにくさの象徴」のように考えられてきた側面がある。([2]192ページ)/「障害学」のなかでは、「障害」は二つに分類される。個人の身体的な欠陥や欠損、あるいは機能不全という意味の「インペアメント(impairment)」(医学モデル・個人モデル)と、社会的障壁という意味の「ディスアビリティ(disability)」(社会モデル)である。([2]187、188ページ)/「障害」は立場や見方によって定義がさまざまに変化し得る相対的なものである。([2]189ページ)
人は程度の差こそあれ、何らかの障害を抱えながら生きていると考えた方がよい。[2]190ページ)/自分には何ができて、何ができないのか。どこからが自分の手に負えない状況になってしまうのか。何かできないことに直面した際、誰に、どれだけのサポートを求めれば良いのか。自分のなかに「障害」を見出すというのは、こうした点について考えることでもある。([2]192ページ)
ここでいう「障害」とは、「ある特定の文脈や状況のなかで、他の多くの人がそれほど苦労せずにできることができず、そのことで日常生活に支障をきたすこと」という意味である。([2]194ページ)/人は誰しも「障害的要素」や「障害者的側面」をもっているはずであり、そうした内省(リフレクション(reflection))を通じて、社会を捉え返すことが大切である。([2]195ページ)
「障がい者」に対する紋切り型の表現
障害者に対する紋切り型の表現は、これまでも繰り返し批判されてきた。記憶に新しい例で言えば、Eテレの情報バラエティ番組「バリバラ(Barrierfee Variety Show)」が、日本テレビ系列の有名チャリティ番組「24時間テレビ」にぶつけて「障害者×感動の方程式」と題した番組を組み、障害者が感動や勇気を与える存在として描かれることを「感動ポルノ」(Inspiration porn)と批判したことが話題になった。([2]24ページ)
もともと「感動ポルノ」という言葉は、豪州(オーストラリア)のジャーナリスト、ステラ・ヤング(Stellar Young)のものとされている。Eテレの同企画を詳細に報じた『朝日新聞』(2016年9月3日)の記事は、当日の番組の様子を次のように伝えている。<番組では冒頭、豪州のジャーナリストで障害者の故ステラ・ヤングさんのスピーチ映像を流した。ステラさんは、感動や勇気をかき立てるための道具として障害者が使われ、描かれることを、「感動ポルノ」と表現。「障害者が乗り越えなければならないのは自分たちの体や病気ではなく、障害者を特別視し、モノとして扱う社会だ」と指摘した。([2]27ページ)
「不幸」や「悲劇」を健気(けなげ)な努力によって乗り越える障害者の姿が涙とともに「消費」されることは珍しくない。([2]113ページ)
障がい者の「役に立たない」という烙印
戦時中の障害者たちは、「お国の役に立たない」ということで、ものすごく迫害された。「国家の恥」「米食い虫」という言葉で罵(ののし)られた。/そうした迫害に苦しんだ人たちだからこそ、「障害者を苦しめる戦争反対!」とはならない。むしろ、なれないのだ。/迫害されている人は、これ以上迫害されないように、世間の空気を必死に感じ取ろうとする。どういった言動をとればいじめられずに済むか、自分をムチ打つ手をゆるめてもらえるかを必死になって考える。([1]104~105ページ)
誰かに対して「役に立たない」という烙印を押したがる人は、誰かに対して「役に立たないという烙印」を押すことによって、「自分は何かの役に立っている」という勘違いをしていることがある。/特に、その「何か」が、(「国家」「世界」「人類」などの)漠然とした大きなものの場合には注意が必要だ。/「誰かの役に立つこと」が、「役に立たない人を見つけて吊るし上げること」だとしたら、断然、何の役にも立ちたくない。([1]107ページ)
「障がい者はもっと遠慮するべきだ」という暴力
老若男女、障害や病気の有無にかかわらず、「遠慮」をまったく感じないでいられる人は現実的にはほとんどいない。だから、みんなが、どこかで、誰かに「遠慮」している。/それでも、障害や病気がある人の「遠慮」は、場合によっては命に関わる。([1]178ページ)
日本の障害者運動が最初に闘ったのは、「遠慮圧力」だった。/<生きるに遠慮が要るものか>というフレーズは、障害者運動の神髄だとさえ言える。/「みんな、それなりに遠慮しているのだから、障害者も弱者なんていう言葉にあぐらをかかず、もっと遠慮するべきだ」/いまでも、こうした意見を持つ人がいる。/でも、この世の「遠慮圧力」は、みんなに等しく均一にかかっているわけではない。やはり、どこかで、誰かに、重くのしかかっている。([1]183ページ)
自分たちが生きる社会のなかで、「生きること」そのものに「遠慮」を強いられている人がいることを想像してみてほしい。「遠慮圧力」が、ときには人を殺しかねないことを想像してみてほしい。/確かに、ある程度の「遠慮」は美徳かもしれないけれど、誰かに「命に関わる遠慮を強いる」のは暴力だ。([1]184ページ)
「障害は個性」「みんな違ってみんないい」という言葉
1990年代以降、「障害は個性」や「みんな違ってみんないい」といった言葉が、障害者との共生をめざす文脈でしばしば見かけられるようになった。しかし、これらの言葉は、どちらかというと「障害者と仲良くするための言葉」であり、障害者差別という人権侵害を抑止したり糾弾したりする「闘う言葉」ではないようである。([3]231~232ページ)
ある差別について語る言葉がない(少ない)ことは、その社会に差別が存在しないことを意味しない。むしろ、差別について語る言葉が少ないほど、その社会が差別に対して鈍感であることを意味している。([3]232ページ)
「障がい者も同じ人間である」というフレーズ
障害の有無にかかわらず、人は皆、等しくかけがえのない存在であり、等しい尊厳を有した存在であるという意味において、「障害者も同じ人間」というフレーズはまったく間違ってもいなければ、無力なきれいごとでもない。([3]235ページ)
「人間」とは極めて普遍的で抽象的な言葉だからこそ、ともすると、個々人の抱えた事情を一切無視して、少数者を多数者の論理に従わせたり、多数者の価値観を少数者に受け入れさせたりする抑圧的な言葉として、いかようにも転用できてしまう。/つまり、「障害者も同じ人間なのだから」という表現は、障害者に対して我慢や自制を強いる表現としても使われかねないのである。([3]236ページ)
障害者たちが障害者運動のなかで叫んできた「障害者も同じ人間」というフレーズは、「障害者も生物学上『人間』に分類される存在である」などといった意味ではない。運動の蓄積に鑑(かんが)みるならば、この言葉は「障害者も社会のなかで共に生活する者である」といったメッセージとして育て上げられてきたフレーズである。/「障害者も同じ人間」というフレーズは、「他の人々に認められている社会参加への機会や権利は、障害者にも等しく認められるべきである」といった意味内容で使われなければならない。([3]239ページ)
障がい者の「差別と区別は違う」という定型句
「差別と区別は違う」というのは、障害者差別が起きたときにも出てくる定型句である。/「差別」は不当に「されるもの」であり、「区別」は不利益が生じないように「してもらうもの」である。/「不利益の生じる区別」は「差別」だし、そもそも属性を理由に「不利益」を押しつけることは許されない。/「差別と区別は違う」というフレーズは、「それは差別だ!」と批判された側が思わず口走るというパターンが多かったように思う。([1]124、125ページ)
この社会は「権利」という概念に鈍(にぶ)いけど、それと対になって「差別」への感性も鈍い。「差別」への感性を鈍らせないためにも、「権利」に敏感でなければならない。([1]126ページ)
「隣近所」で生きる障がい者との「闘争(ふれあい)」
障害者が排除されるのは抽象的な「地域」ではなく、具体的な「隣近所」であることから、横田は「障害者は隣近所で生きなければならない」と言った。これは、「障害者は、目に見えて、声が聞こえる距離で生きなければならない」ということだ。障害者が身近にいない社会では、障害者はどんな人なのかといった想像力が希薄になる。([2]77ページ)
逆に、障害者にとっても、様々な人たちが混在している社会のなかで生きなければ、「自分とは何者か」「自分と社会はどのような関係にあるか」について考える機会を失う。「障害者が遠い社会」や「障害者にとって遠い社会」では、障害者について語る言葉も、障害者と語らう言葉も貧困になる。言葉が貧困なところに想像力は育まれない。([2]77、78ページ)
横田は、障害者は周囲の人々と軋轢を起こしながら・起こしてでも(「隣近所」で)生きなければならないと言った。小さな諍(いさか)いは、相手と言葉を交わし、相手が何者なのかを考える契機になる。横田が「闘争」という言葉に「ふれあい」というルビを振ったことは有名なエピソードだ。([2]78ページ)
「自己責任」という言葉とその不気味さ
「自己責任」という言葉に、おおむね次の三点において不気味さを覚えている。
一つ目は、2004年の「イラク邦人人質事件」で騒がれた時から、「自己責任の意味が拡大し過ぎている」という点だ。/これまでも、病気・貧困・育児・不安な雇用などで生活の困難を訴える人が、「甘え」「怠(なま)け」といった言葉でバッシングされることはあった。近年では、こうした場面にも「自己責任」が食い込んできた。([1]189、190ページ)
二つ目は、「自己責任」が「人を黙らせるための言葉」になりつつある、という点だ。/社会の歪みを痛感した人が、「ここに問題がある!」と声を上げようとした時、「それはあなたの努力や能力の問題だ」と、その声を封殺(ふうさつ)するようなかたちで「自己責任」が湧き出してくる。([1]190~191ページ)
三つ目は、この言葉が「他人の痛みへの想像力を削(そ)いでしまう」という点だ。/「自己責任」という言葉には「自らの行ないの結果そうなったのだから、起きた事柄については自力でなんとかするべき」「他人が心を痛めたり、思い悩んだりする必要はない」という意味が込められている。([1]191ページ)
「自己責任」というのは、声を上げる人を孤立させる言葉だ。/「従順でない国民の面倒など見たくない」という考えを持った権力者は、今後も「自己責任」という言葉を使い続けていくだろう。国民が分断されていることほど、権力者にとって好都合なことはないからだ。([1]195ページ)
人が「生きる意味」について議論すること
人が「生きる意味」について、軽々に議論などできない。障害があろうとなかろうと、人は誰しも「自分が生きている意味」を簡潔に説明することなどできない。「自分が生きる意味」も、「自分が生きてきたことの意味」も、簡潔な言葉でまとめられるような、浅薄なものではないからである。([3]234ページ)
私が「生きる意味」について、第三者から説明を求められる筋合いはない。また、社会に対して、それを論証しなければならない義務も負っていない。もしも私が第三者から「生きる意味」についての説明を求められ、それに対して説得力のある説明が展開できなかった場合、私には「生きる意味」がないことになるのか。/だとしたら、それはあまりにも理不尽な暴力だとしか言えない。([3]234ページ)
この社会のなかで、誰かに対し、「生きる意味」の証明作業を求めたり、そうした努力を課すこと自体、深刻な暴力であることを認識する必要がある。/重度障害者に対し「生きる意味」の証明作業を求めるような価値観は、必ず、重度障害者以外に対しても牙(きば)を剥(む)く。([3]235ページ)
〇上記の[4]は、「障害者によって描かれた文学」作品を研究対象に、それらの作品が生み出された文学活動の歴史と意義について考察する。具体的には、俳人で運動家の花田春兆(はなだ・しゅんちょう)と文芸同人団体「しののめ」、詩人で運動家の横田と「青い芝の会」神奈川県連合会をとり上げる。そして、「障害者自身がいかに自己の存在意義について悩み、いかに自己と社会との関係性について折り合いをつけてきたのか、その内省的な思索の変遷過程を、可能な限り同時代の障害者自身の文学表現から読み解いていく」([4]8ページ)作業を行う。それは、障がい者や障がい者運動の「内面史」を語ることでもある。荒井はいう。戦後日本の障がい者運動のなかでは、「文学は決して周縁的・副次的な存在ではなく、人脈を繋ぎ、思想を練磨していく上で、むしろ中心的な役割を果たしていたとさえ言える」([4]8ページ)。
〇上記の[5]は、横田が1970年5月に書き上げた「青い芝の会」の「行動綱領 われらかく行動する」(「補遺」参照)の解釈を通して、その歴史や思想、その意義について考察する。「行動綱領」は、「一人の重度脳性マヒ者が、この社会に厳然と存在する障害者差別に頽(くずお)れてしまわないために、自分を鼓舞し支えようとして綴った言葉」([5]299ページ)である。「青い芝の会」の活動には、「『自分たちの苦労と悲しみをわかってもらいたい』という迎合的な姿勢や、『障害のある人もない人も、共に手を取り合ってがんばろう』といった朗(ほが)らかな雰囲気は微塵もなかった」([5]14ページ)。彼らは、差別者を容赦なく徹底的に糾弾し、非妥協的で戦闘的な姿勢を貫き通した。荒井によると横田は、差別者と対峙して自覚的あるいは無自覚な差別を問いただし、その壁を乗り越えて明日を切り拓き、自分自身を解き放つためには「差別されてる側の自覚から湧き上がる怒りが必要だ」([5]299ページ)とした。障がい者(被差別者、被抑圧者)の「自覚」がキーワードである。ここに、『差別されている自覚はあるか』というタイトルの意味をみる。
社会のすべてが、障害者と共生する時が来るとは私には考えられない。/私たち障害者が生きるということは、それ自体、たえることのない優生思想との闘いであり、健全者との闘いなのである。(横田:[4]225ページ)
私達は生きたいのです。/人間として生きる事を認めて欲しいのです。/ただ、それだけなのです。(横田:[5]103ページ)
注
① 1970年5月に起きた実母による障がい児殺害事件に対する減刑嘆願反対運動をはじめ、優生保護法改悪反対運動および「胎児チェック」反対運動(1972年から1974年)、川崎バス闘争(1977年から1978年)、養護学校義務化阻止闘争(1975年から1979年)などがそれである。その概要と詳細は[3](41~47、128~145、150~176、188~220ページ)を参照されたい。
② 横田と横塚の言説(思想)については次の著作を参照されたい。
横田弘著『障害者殺しの思想』JCA出版、1979年1月
横田弘著、立岩真也解説『障害者殺しの思想(増補新装版)』現代書館、2015年6月
横塚晃一著『母よ!殺すな』すずさわ書店、1975年1月
横塚晃一著、立岩真也解説『母よ!殺すな(増補復刻版)』生活書院、2007年9月
補遺
横田の手になる「行動綱領 われらかく行動する」は、次の通りである([5]29~30ページ)。
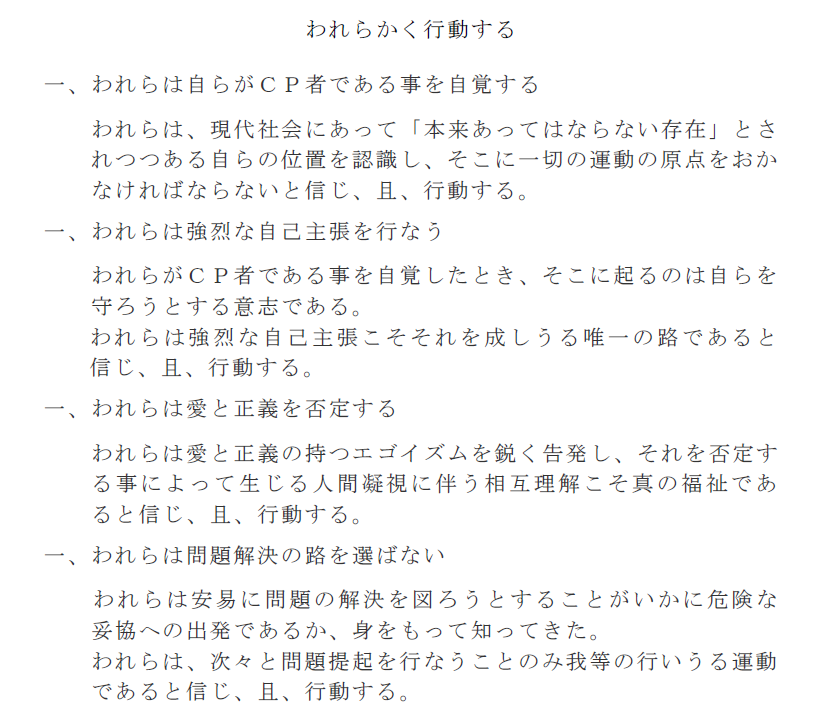
荒井による各項目の解説文(「注釈めいたもの」)をメモっておくことにする([5]121~142ページの抜き書きと要約)。
一、われらは自らがCP者である事を自覚する
障害者運動は障害者が主体となり、障害者の主体性が発揮されるかたちでなされなければならない。そのためには自分がCP者(脳性マヒ者)であることを自覚し、CP者としての思考や考え方がなければならない。それがすべての原点である。
一、われらは強烈な自己主張を行なう
障害者が障害者のまま生きていくために、障害者としてしか生きられない自分の存在を「自己主張」すべきである。この社会の常識自体が障害者の存在を否定的に捉えている。そんな常識を<健全者エゴイズム>として捉え直さない限り、障害者は<自己解放>の道を歩むことはできない。
一、われらは愛と正義を否定する
母親がわが子を愛するが故に障害児を殺した事件が起きた。その愛を圧倒的多数の人たちが支持すれば、それは正義になる。その「愛と正義」の名のもとに、障害児は殺され、あるいは施設へと送られた(送られている)。「障害者のためを思って」という健全者だけに都合のよい「愛と正義」について、人間の心を凝視しなければならない。「福祉は思いやり」という発想も怖い。非常時に真っ先に犠牲になるのは障害者である。
一、われらは問題解決の路を選ばない
障害者が成し得ることは、「不満があるなら何か具体的な対案や代替案を示せ」という発想に応えることではなく、次々と問題提起を起こす以外にない。安易な問題解決は<安易な妥協>を生む。安易な妥協は、「正義」として受け止められ、「誰」が「何」を考えなければならないのかという点を曖昧にしてしまう。妥協は、弱い立場の者がしぶしぶ折れる(折られる)ことになる。
付記
本稿を草することにしたきっかけのひとつは、次の記事にある(『岐阜新聞』2019年9月5日)。