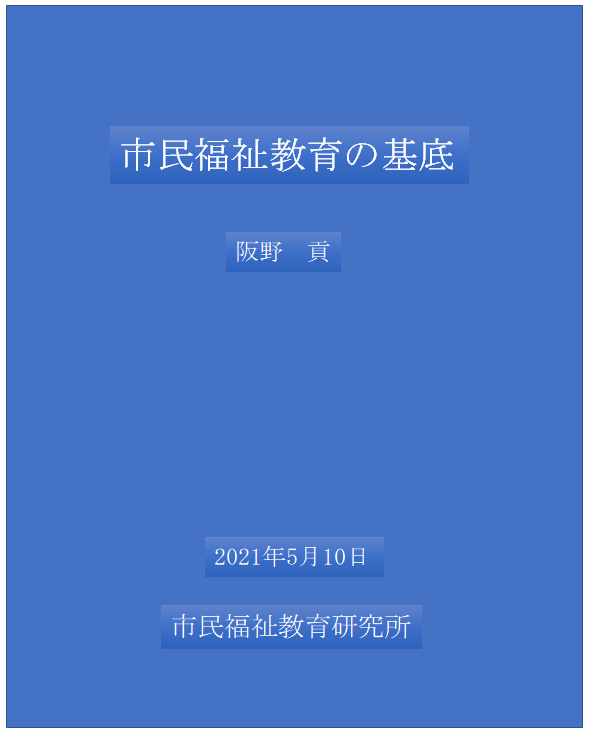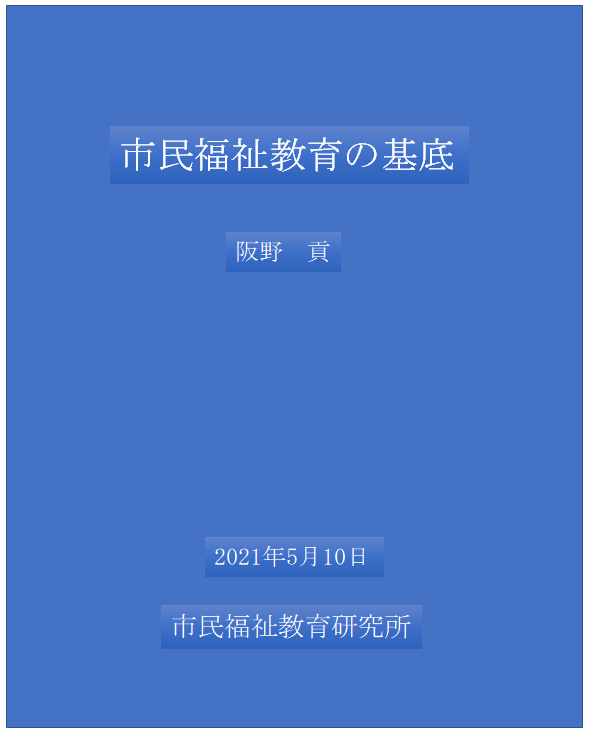
第1章
「人間は善であると同時に悪である」という言説
―リチャード・ランガム著『善と悪のパラドックス』のワンポイントメモ―
〇進化論や人類学などに関して全くの門外漢である筆者(阪野)が、興味深く読んだ本がある。リチャード・ランガム著・依田卓巳訳『善と悪のパラドックス―ヒトの進化と<自己家畜化>の歴史―』(NTT出版、2020年10月。以下[本書])がそれである。カバーの「そで」には次のような紹介文が記されている。「最も温厚で、最も残忍な種=ホモ・サピエンス。協力的で思いやりがありながら、同時に残忍で攻撃的な人間の特性は、いかにして育まれたのか? <自己家畜化>という人間の進化特性を手がかりに、(中略)人類進化の秘密に迫る」。この一文が目に留まったときなぜか、医療や介護の現場で献身的に働く職員の姿とともに、2016年7月の「相模原障がい者施設殺傷事件」のこと、2018年10月に20年ぶりに訪れた韓国の板門店(パンムンジョム)や非武装地帯(DMZ)の風景などが脳裏をかすめた(昨年12月に1週間の検査入院をしたこと、25年近く相模原市に居住していたこと、1989年前後の10年近くしばしば韓国・ソウルを訪ねていたこと、などによるのであろうか)。
〇「人間の本性(本質)は善か悪か」ではなく、「善良であると同時に邪悪である」(19ページ)。攻撃性の資質に関して人間は「どっちつかずであり、どちらでもある」(356ページ)。本書では、この矛盾を解明するために、「反応的攻撃性」(reactive aggression)と「能動的攻撃性」(proactive aggression)というキー概念を用い、「自己家畜化」(self-domestication)という仮説に基づいた進化論を展開する。その際、「専門的な論文と、その広範囲に及ぶ意味をわかりやすく(しかも丁寧に)紹介する」(5ページ)。筆者でも好奇心をもって通読できた要因のひとつである。
〇ランガムにあっては、「ほかの霊長類と比較して、人間が日々の生活で暴力的になることは例外的に少ないが、戦争時の暴力による死亡の割合は例外的に高い」という、この矛盾(paradox、背反)が「善と悪のパラドックス」(34ページ)である。それを解消するために用いる概念が、「反応的攻撃性」と「能動的攻撃性」である。反応的攻撃性は「恐怖や激情に駆られて衝動的に暴力をふるう性質」(「激情タイプ」)をいい、能動的攻撃性は「冷静に計画して相手を排除する性質」(「冷静沈着」タイプ)をいう(16、376ページ)。人間は、ほかの動物に比べて反応的攻撃性が低く、能動的攻撃性が高い。
〇その理由は「家畜化」にある。「ヒトは『家畜化された種』と呼んでさしつかえない特徴を充分に備えている」(16ページ)。その際の「家畜化」とは、生涯のあいだに飼い慣らされるというのではなく、「遺伝的適応の結果として従順になる」という意味である。ランガムは、「ほかの種にうながされることなく、反応的攻撃性が低下するプロセスを『自己家畜化』と呼ぶ」(116ページ)。「人間の(反応的攻撃性が弱く)従順な行動は、家畜化された種を思わせるが、われわれを家畜化しうる種がいない以上、自己家畜化したにちがいない」(82~83ページ)。
〇では、ヒトの自己家畜化はどうやって起きたのか。ランガムはいう。「ヒトは、おそらく比較的穏やかな社会的圧力に合わせて、とりわけ高い反応的攻撃性を示す個体をときおり排除しながら、ゆっくりと自己家畜化していったのだろう」(209ページ)。「言語能力の向上にともない、集団内で連携して支配的な攻撃者を排除、追放する個人の能力が発達した。その連合で、過度に攻撃的な人間を淘汰することが可能になり、結果として(中略)自己家畜化が進行した」(213ページ)。すなわち、横暴な支配者を連帯行動によって意図的・計画的に排除(「処刑」)する能動的攻撃性の発達が、(処刑の恐怖によって)反応的攻撃性を抑制し、ヒトの自己家畜化が進んだ、というのである。さらに自己家畜化の副産物として、有益な情報を意図的に共有する「協調的コミュニケーション」の能力(240ページ)が発達した、とランガムはいう。
〇およそ以上がランガムの議論・見識の要点である。一言でいえば、「人間は善であると同時に悪である」(12ページ)。「人類は『最高』で『最悪』の種になった」。すなわち、性善説か性悪説かの二者択一ではない。そのうえでランガムは、次のように述べて本書を締めくくる。
私たちはときに協調を価値ある目標と考えるが、道徳と同じく、それは善にも悪にもなりうる。/人類が探求すべき重要なことは、協調の促進ではない。その目標はむしろ単純で、家畜化と道徳感覚によってしっかりと基礎づけられている。それより困難な課題は、組織的な暴力が持つ力をいかに軽減させるかだ。/私たちはその道を歩きはじめたが、まだ先は長い。(366ページ)
〇筆者(阪野)は、市民福祉教育の思想や哲学、原理や価値についてどう考えるか、市民福祉教育の実践や研究の根底にはいかなる生命観や人間観、生活観を必要不可欠とするか、そんなことを考えている。本稿は、そのとてつもなく大きな課題にアプローチするためのひとつのメモにすぎない。
第2章
「人新世」における「変革への途」について考えるために
―斎藤幸平著『人新世の「資本論」』のワンポイントメモ―
〇あまりにも難解で、いまだに積読(つんどく)を続けている本にカール・マルクスの『資本論』がある。筆者(阪野)がそれを読もうと思ったきっかけは、当時、社会福祉(社会事業)を学ぶ学生の必読書であった孝橋正一の『全訂・社会事業の基本問題』(ミネルヴァ書房、1962年5月)に挑戦していたときであったと記憶している。孝橋の「社会事業とは、資本主義制度の構造的必然の所産である社会的問題」を対象にする、という一節である。(その後、筆者は、マルクス経済学者宇野弘蔵の「原理論」「段階論」「現状分析」のいわゆる三段階論にハマった時期があった。今は昔である。)
〇「資本論」という言葉が本のタイトルにあるだけで積読になっていた本がいま、筆者の手もとにある。斎藤幸平(さいとう・こうへい)の『人新世の「資本論」』(講談社新書、2020年9月。以下[本書])がそれである。今回は、「資本論」という言葉に対するアレルギー反応が起きる前に、一気に通読することができた。それは、現代に生きる者(ヒト)として、地球を破壊するほどに進んでいる「気候変動」やその影響に関心をもたざるを得ないことによる。とともに、「気候危機」とも言われるその原因の資本主義を丁寧に解き明かし、鋭く批判し、それゆえに刺激的である斎藤の議論・主張による。とりわけ、『資本論』第1巻の刊行後に「マルクスが取り組んでいたのはエコロジー研究と共同体研究」(179ページ)であった。晩年のマルクスは、「資本主義がもたらす近代化が、最終的には人類の解放をもたらす」という「進歩史観」(史的唯物論)と決別した(152ページ)。マルクスがめざした「コミュニズムとは、平等で持続可能な脱成長型経済(定常型経済)」(195ページ)であったという、斎藤による、マルクスの再解釈・再発見(「マルクスの復権」「マルクス理解の理論的大転換」)によるところが大きい。
〇本書のタイトルの「人新世」(ひとしんせい)とは、斎藤によると、「人類の経済活動が地球に与えた影響があまりに大きいため、ノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンは、地質学的に見て、地球は新たな年代に突入したと言い、それを『人新世』(Anthropocene)と名付けた。人間たちの活動の痕跡(こんせき)が、地球の表面を覆いつくした年代という意味である」(4ページ)。現在の地球の環境危機は、人(ヒト)の経済活動すなわち資本主義それ自体がもたらしたものであり、地球は新たな地質時代に突入した、というのである。
〇斎藤は本書で、環境危機を乗り越えようとする多様な主義・主張や運動に言及し、その問題点や限界を抉(えぐ)り出す。自然エネルギーや気候変動対策への公共投資によって、新たな雇用や経済成長を生み出そうとする「グリーン・ニューディール」(気候ケインズ主義)や、ロボットや人口知能(AI)の技術革新を加速させれば、持続可能な経済成長が可能になると主張する「加速主義」などについてである。それとともに、斎藤は、「マルクスが求めていたのは、無限の経済成長ではなく、大地=地球を<コモン>として持続可能に管理することであった」(190ページ)という。そして、気候変動問題の解決策として「脱成長コミュニズム」を提唱する。それは、資本主義の転換を迫る、資本主義でも社会主義でもない平等で持続可能な「社会像」である(コミュニズムは一般的には共産主義と訳される)。
〇本書から、<コモン>(共有資源)や「脱成長コミュニズム」に関する斎藤の言説について、筆者が留意したい一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
いま求められる脱成長型のポスト資本主義
資本主義は、利潤を増やすための経済成長をけっして止めることはない。/資本は、(経済成長のための)手段を選ばない。気候変動などの環境危機が深刻化することさえも、資本主義にとっては利潤獲得のチャンスになる。山火事が増えれば、火災保険が売れる。バッタが増えれば、農薬が売れる。ネガティブ・エミッション・テクノロジー(大気中の二酸化炭素を回収・除去する技術)は、その副作用が地球を蝕(むしば)むとしても、資本にとっての商機となる。いわゆる惨事便乗型資本主義だ。/このように危機が悪化して苦しむ人々が増えても、資本主義は、最後の最後まで、あわゆる状況に適応する強靭(きょうじん)性を発揮しながら、利潤獲得の機会を見出していくだろう。環境危機を前にしても、資本主義は自ら止まりはしない。/だから、このままいけば、資本主義が地球の表面を徹底的に変えてしまい、人類が生きられない環境になってしまう。それが、「人新世」という時代の終着点である。/それゆえ、無限の経済成長をめざす資本主義に、今、ここで本気で対峙しなくてはならない。私たちの手で資本主義を止めなければ、人類の歴史が終わる。(117~118ページ)
環境危機に立ち向かい、経済成長を抑制する唯一の方法は、私たちの手で資本主義を止めて、脱成長型のポスト資本主義(「脱成長コミュニズム」)に向けて大転換することである。(119ページ)
「脱成長コミュニズム」を実現する道としての<コモン>
マルクスは、人々が生産手段を<コモン>(common)として共同で管理・運営するだけでなく、地球をも<コモン>として管理する社会を、コミュニズム(communism)として構想していた。(142~143ページ)
<コモン>とは、社会的に人々に共有され、管理されるべき冨のことを指す。(中略)/<コモン>は、アメリカ型新自由主義とソ連型国有化の両方に対峙する「第3の道」を切り拓く鍵だといっていい。つまり、市場原理主義のように、あらゆるものを商品化するのでもなく、かといって、ソ連型社会主義のようにあらゆるものの国有化をめざすのでもない。第3の道としての<コモン>は、水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主義的に管理することをめざす。(141ページ)
(すなわち、マルクスがそう考えたように)<コモン>の思想は、貨幣や私有財産を増やすことをめざす個人主義的な生産から、将来社会においては「協同的富」を共同で管理する生産に代わることをめざすのである。(201ページ)
「脱成長コミュニズム」を実現するための具体的方策
「脱成長コミュニズム」をどのように実現させるのか、そのためになすべきことは大きく5点にまとめられる。
(1)使用価値経済への転換/生産の目的を商品としての「価値」(儲け)の増大すなわち利潤の獲得ではなく、「使用価値」(有用性。商品やサービスの質)に重きを置いた経済に転換して、大量生産・大量消費から脱却する。別言すれば、生産を社会的な計画のもとに置き、人々の基本的ニーズを満たすことを重視する。
(2)労働時間の短縮/労働時間を削減して、生活の質を向上させる。社会の再生産にとって本当に必要な生産に労働力を意識的に配分し、金儲けのためだけの、意味のない仕事を大幅に減らす。「使用価値」の経済に向けた転換には、労働時間の短縮が根本条件である。
(3)画一的な分業の廃止/画一的な労働をもたらす分業を廃止して、労働の創造性を回復させる。資本主義の分業体制のもとでは、労働は画一的で、単調な作業が多い。労働をより創造的な、自己実現の活動に変えていくためには、多種多様な労働に従事できる生産現場の設計が好ましい。
(4)生産過程の民主化/生産のプロセスの民主化を進めて、経済を減速させる。「使用価値」に重きを置きつつ、労働時間を短縮するために、開放的技術を導入していく。そのためには、一部の経営陣の意向に基づいて非民主的な決定が行われるのではなく、労働者たちが生産における意思決定権を握る必要がある。
(5)エッセンシャル・ワークの重視/使用価値経済に転換し、労働集約型のエッセンシャル・ワーク(生活維持に不可欠な仕事)を重視する。ロボットやAIでは対応しきれない、ケアやコミュニケーションを必要とする介護や看護、保育や教育などの労働がしっかりと評価される必要がある。(300~314ページ)
<コモン>と「社会的共通資本」(宇沢弘文)の違い
(<コモン>に関して、より一般的に馴染みがある概念として、宇沢弘文の「社会的共通資本」がある。)宇沢は、人々が「豊かな社会」で暮らし、繁栄するためには、一定の条件が満たされなくてはならない。そうした条件が、水や土壌のような自然環境、電力や交通機関といった社会的インフラ、教育や医療といった社会制度である。これらを、社会全体にとって共通の財産として、国家のルールや市場的基準に任せずに、社会的に管理・運営していこうと考えたのである。<コモン>の発想も同じだ。/ただし、「社会的共通資本」と比較すると、<コモン>は専門家任せではなく、市民が民主的・水平的に共同管理に参加することを重視する。そして、最終的には、この<コモン>の領域をどんどん拡張していくことで、資本主義の超克(ちょうこく。困難を乗り越えること)をめざすという決定的な違いがある。(141~142ページ)
〇経済成長は確かに、私たちの生活や社会を物質的に豊かにした。それは、資本主義のグローバル化が進むなかで、グローバル・ノース(北の先進国)によるグローバル・サウス(南の発展途上国)からの労働力の搾取や自然資源の収奪のうえに成り立っている。グローバル・ノースの「過剰発展」や大量生産・大量消費のライフスタイル(「帝国的生活様式」)は、グローバル・サウスの人々の劣悪な生活条件に依存している。そしてまた、グローバル・サウスはそのグローバル・ノースに依存せざるを得ない。ここに資本主義の「矛盾」と「悲劇」がある(27~30ページ)。いずれにしろ、資本主義社会は、絶えず「外部性」を作り出し、そこに負担や犠牲を強いる・転嫁することによって発展してきたのである。
〇現代の資本主義は、「不平等を一層拡大させながら、グローバルな環境危機を悪化させてしまう」。資本主義は、豊かさを生み出すシステムではなく、「私たちの生活に欠乏をもたらしている」。「持続可能で公正な社会」を実現するためには、資本主義によって解体させられた、人々が生産手段を自律的・水平的に「自治管理」「共同管理」する<コモン>を再建する必要がある。そのための唯一の選択肢が、マルクスにみる「脱成長コミュニズム」である(258、290、360ページ)。斎藤の、ラディカルな主張である。
〇それを換言すれば、生産手段を<コモン>として社会的に所有し、民主的に管理することによって、経済活動は減退するが、現代の環境危機を乗り越えることはできる。このコミュニズムの萌芽は、「21世紀の環境革命として花開く可能性を秘めている」(323ページ)、となる。ここに本書の核心があり、思考や概念の斬新さをみる。
〇そして、斎藤は、「資本の専制から、この地球という唯一の故郷を守る」ためには、「3.5%」(ハーヴァード大学の政治学者エリカ・チェノウェスらの研究による)の人々が非暴力的な方法で、本気で立ち上がることであるという(362、364ページ)。この点は非現実的な楽観論と評されるおそれなしとしないが、社会に大きなインパクトを与えた多くの抗議活動や社会運動は、最初は少人数で始まっている。本稿のタイトルにいう「変革への途」が含意するところでもある。
付記
〇論拠は不明であるが、斎藤の挑発的で小気味よい指摘やフレーズに次のようなものがある。あえて付記しておくことにする。
2015年9月に国連で開かれたサミットによって採択され、各国政府も大企業も推進する「SDGs」(エス・ディー・ジーズ、Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)は、「アリバイ作りのようなものであり、目下の危機から目を背(そむ)けさせる効果しかない。(中略)SDGsまさに現代版『大衆のアヘン』である」(4ページ)。
「高度経済成長の恩恵を受けてあとは逃げ切るだけの団塊世代の人々が、脱成長という『綺麗事(きれいごと)』を吹聴している。(中略)若いころに経済成長の果実を享受しておきながら、一線を退いたそのときから『このままゆっくり日本経済は衰退していけばいい』と言い始めたというわけである(120ページ)。(ちなみに、「平等に、緩(ゆる)やかに貧しくなっていけばいい」という上野千鶴子(うえの・ちずこ)は1948年生まれであり、「本当に豊かな生き方は『ローカル』と『定常経済』にある」という内田樹(うちだ・たつる)は1950年生まれである)。
(「定常型社会」論を展開する広井良典(ひろい・よしのり)や社会経済学者の佐伯啓思(さえき・けいし)によれば)「資本主義的市場経済を維持したまま、資本の成長を止めることができるという」(128~129ページ)。「利潤獲得に駆り立てられた経済成長という資本主義の本質的な特徴をなくそうとしながら、資本主義を維持したいと願うのは、丸い三角を描くようなものである。まさに、真の『空想主義』である。これが旧世代の脱成長論の限界なのだ」(133ページ)。
第3章
「脱成長」:人間の生き方の転換と生活基盤の再ローカル化を図る思想
―セルジュ・ラトゥーシュの「脱成長」論のワンポイントメモ―
〇本稿は、先の拙稿――<雑感>(132)「『人新世』における『変革への途』について考えるために―斎藤幸平著『人新世の「資本論」』のワンポイントメモ―」(2021年1月27日投稿)の「追記」「補遺」である。内容的には、フランスの経済哲学者セルジュ・ラトゥーシュ(Serge Latouche)の「脱成長」論の抜き書きである。そのひとつのねらいは、それによって斎藤の「脱成長コミュニズム」論についての理解や思考が促され、真に豊かな地域社会を再生・創造する視点や方向性、そのための枠組みなどを見出すことができれば、というところにある。
〇いま筆者の手もとにあるラトゥーシュの本は、次の4冊である。(1)中野佳裕訳『脱成長』(白水社、2020年11月。以下[1])、(2)同訳『経済成長なき社会発展は可能か? ―<脱成長>と<ポスト開発>の経済学―』(作品社、2010年7月。以下[2])、(3)同訳『<脱成長>は、世界を変えられるか? ―贈与・幸福・自律の新たな社会へ―』(作品社、2013年5月。以下[3])、(4)ディディエ・アルパジェス(Didier Harpagès)との共著、佐藤直樹・佐藤薫訳『脱成長(ダウンシフト)のとき―人間らしい時間をとりもどすために―』(未来社、2014年6月。以下[4])、がそれである。
〇[1]は、21世紀に入りフランスから世界へと普及した脱成長運動の歴史的背景や理論研究を整理・分析し、「簡素な生活と節度ある豊かな社会」を構築するための方策などについて解説する。ラトゥーシュの資本主義批判と脱成長論の集大成である。[2]は、「ポスト開発」の経済思想について論述する単著と、脱成長運動の骨子を整理する単著の2冊が収録されている。ラトゥーシュ思想の決定版である。[3]は、20世紀後半から世界で展開されている産業文明批判の思想を脱成長論の視点から議論し、経済成長なき社会発展の方法と実践を整理する。「脱成長の道」を描く思想書である。[4]は、生産至上主義による資本主義経済・社会の発展によって人間は、「時計」時間に隷属するようになったと、人間と時間との関係性について論じ、人間らしい時間の再征服(reconquête、レコンキスタ)を説く。若者向けの啓蒙書である。
〇ここでは[1][2][3]から、ラトゥーシュの「脱成長」(仏:décroissance、デクロワサンス。英:degrowth、デグロース)の言説について、その一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。例によって、我田引水の誹(そし)りは免れないであろうことを承知のうえで、である。
「脱成長」という言葉と「脱成長社会」
脱成長という語は、概念ではない。また、経済成長の対義語でもない。脱成長は何よりも論争的な政治スローガンである。その目的は、我々に省察を促して限度の感覚を再発見させることにある。特に留意すべきは、脱成長は景気後退やマイナス成長を意図していないという点だ。したがって、この語は文字通りの意味で受け取ってはならない。(中略)「脱成長派」(脱成長運動の賛同者)は、生活の質、空気や水の質、そして経済成長のための経済成長が破壊してきた多くの物の質を向上させることを望んでいる。(中略)脱成長という語を「経済成長を崇拝しない態度(acroissance)」を指す語として使用しなければならないだろう。まさしく、進歩・発展という信仰や宗教を捨て去ることなのだ。([1]8~9ページ)
脱成長は、別の形の経済成長を企図するものでも、(持続可能な開発、社会開発、連帯的な開発など)別の形の開発を企図するものでもない。それは、これまでとは異なる社会(「節度ある豊かな社会」「ポスト成長社会」「経済成長なき繁栄」)を構築する企てである。言い換えると、脱成長は経済学的な企てでも別の経済を構築する企てでもなく、現実としての経済および帝国主義的言説としての経済から抜け出すことを意味する社会的企てである。([1]12ページ)
<脱成長>というスローガンは、成長を際限なく追求することを徹底的に放棄することを至上命題とする。つまり、資本移動を規制緩和しながら利潤を追求し、自然環境と人類に壊滅的な結果をもたらすその目的を破棄することである。/<脱成長>はマイナス成長ではない。(中略)ただ単に成長の速度を緩めるだけでは社会が混乱に陥ることは周知の事実である。失業は増加し、必要不可欠な最低限の生活の質を保障するところの社会、保健、教育、文化、環境の各分野におけるプログラムを破綻させることになる。(中略)雇用のない労働社会ほど最悪なものはないことと同じように、成長を約束できない成長社会ほど危険な社会はない。(中略)<脱成長>は「<脱成長>社会」においてのみ、つまり〔成長想念(思想)とは〕別の論理に基づいた体制においてのみ思考可能であるといえる。/厳密に言うならば、理論レベルでは、(中略)成長の減少・緩慢化・衰退(dé-croissance)よりも「無成長」(a-croissance)について語るべきである。何よりも重要なことは、経済・進歩および発展といった信仰ないし宗教を破棄することである。([2]140ページ)
<脱成長>は、蓄積、資本主義、搾取、略奪の縮小のほかにはない。/<脱成長>は断固として反資本主義の立場をとる。/多かれ少なかれ自由主義的な資本主義と生産主義的な社会主義は、成長社会という同一のプロジェクトの2つの類型である。/(<脱成長>における)発展、経済、成長からの脱出は、経済と関わっている社会制度のすべてを放棄するのではなく、むしろそれら諸制度を別の論理に組み込むことを意味する。<脱成長>はおそらく「エコロジカル(生態学的)な社会主義」と見なすことができるだろう。([2]245、246、248ページ)
われわれが構想し求めなければならないのは、経済的価値を中心的な価値(あるいは唯一の価値)とはしない社会、つまり経済を増大させることを前提とするようなこの狂気じみたシナリオを放棄しなければならない。このことは、地球環境の決定的な破壊を回避するためだけではなく、現代に生きる人間の心理的かつ道徳的な貧困から脱出するためにも必要である。([2]123ページ)
愛他主義はエゴイズムよりも重視されるべきである。同様に、際限なき競争よりも協力が、労働への執着よりも余暇の快楽と遊びの精神(エトス)が、制約のない消費よりも社会生活の大切さが、グローバルなものよりローカルなものが、他律性よりも自律性が、生産主義的な効率性よりも素晴らしい手作りの作品を好むことが、科学的合理性(le rationnel)よりも思慮深さ〔実践倫理〕(le raisonnable)が、そして物質的なものよりも人間関係が重視されるべきである。真実への配慮、正義の感覚、責任、民主主義の尊重、差異の称賛、連帯の形成、既知に富んだ生活。これこそが何物に代えてもわれわれが取り戻さねばならない価値である。([2]172ページ)
〇以上のようにラトゥーシュは、開発・発展による地球環境の破壊や、資本による人間の支配・搾取などをもたらす資本主義から脱出し、そのためのオルタナティブな(それに代わるもうひとつの新しい)価値体系に基づく人間の生き方や社会像について議論し構想する。その際、脱成長を「『経済成長社会から抜け出す』」という否定の側面からだけでなく、『節度ある豊かさ(abondance frugale)』という創造すべきプランの価値の側面からも」([1]153ページ)説いている。留意すべき視点・視座である。
「脱成長社会」へ移行するための具体的なプログラム
経済成長社会との断絶、すなわち脱生産力至上主義社会の構想は、簡素な生活の「好循環」の形をとる。以下の8つの目標(「8つの再生プログラム」)は、生産力至上主義および消費主義の論理と対照を成す重要な点に触れており、相互に依存している。8つの目標は、穏やかで、自立共生的で、持続可能な簡素さから成る「自律社会」(脱成長社会)へ向かう推進力となる。([1]61~68ページ。[2]170~185ページ)
(1)再評価する(réévaluer)
経済成長社会におけるそれとは異なる価値観を再評価することである。例えば、エゴイズムよりも愛他主義が、競争よりも協力が、労働への執着よりも余暇の快楽と遊びの精神が、制約のない消費よりも社会生活の大切さが、グローバルなものよりもローカルなものが、物質的なものよりも人間関係が重視されるべきである。また、自然に対しては侵略者のような態度を改め、庭師(にわし)のような態度をとり、自然と人間との調和を図らなければならない。
(2)概念を再構築する(reconceputualiser)
諸価値を問い直すこと(価値観の変革)は、われわれの世界と実在を理解する諸概念を問い直すことにつながる。特に考慮しなければならないのは、豊かさはお金だけに還元されないということである。本当の豊かさは、何よりもまず、よく機能する社会関係の組織のなかから生まれる。豊かさを問い直すことは、貧しさについて考え直すことも意味する。貧しさもまた、経済的次元や物質的な極貧状態の次元にのみ還元されてはならない。
(3)社会構造を組立て直す〔再構造化〕(restructurer)
変革された価値観に応じて、生産の仕方が変わる。つまり、われわれが生産するものや生産関係(生産に関わる法的・制度的・慣習的な構造)が変わり、社会関係の調整が行われる。ここで重要なことは、<脱成長>社会へ向かうことである。こうすることで、資本主義から脱出するための具体的な問題提起が行われる。
(4)再分配を行う(redistribuer)
生産関係や社会関係の構造が変われば、再分配の仕組みも必然的に変わる。再分配は、階級間、世代間、諸個人の間といった各社会の内部にとどまらず、北側諸国と南側諸国との間における富および自然資産へのアクセス(利用する権利)の分配も含む。再分配は、直接的には「グローバルな消費階級」の権力と手段を削減する。間接的には、誇大妄想的な消費への勧誘を消滅する。
(5)再ローカリゼーションを行う(relocaliser)
地域のニーズ充足のために地域レベルでなされるあらゆる生産活動は、地元企業を通じて、地域単位で実現されなければならない。商品と資本の移動は必要不可欠な範囲に制限されなければならない。地域レベルで実行可能なあらゆる経済的、政治的、文化的な決断が、地域規模でなされなければならない。
(6)削減する(réduire)
われわれの生産様式と消費様式が生物圏に与える影響を縮小しなければならない。われわれの生活習慣となっている過剰消費を制限することをはじめ、ゴミの廃棄や保健衛生上のリスク、ツーリズム(観光旅行)などを削減する必要がある。とりわけ、仕事をしたいと望むすべての人々が雇用されるようにワークシェアリング(仕事の分かち合い)を実施したり、余暇、芸術・製作活動、遊び、会話、生の喜びなどのために、労働時間の削減は肝要である。「仕事」中毒を解毒することである。
(7)再利用する(réutiliser)/(8)リサイクルを行う(recycler)
抑制の効かない美食を制限し、設備の周期的な廃棄を止め、直接には再利用不可能なゴミをリサイクルすることが必要である。物や機械を廃棄せず再利用することは、資源浪費を削減するために必要なだけでなく、物の本当の価値を学び直し、寛大な自然が与える贈与に愛着をもつためにも必要である。最後に、再利用できないものはリサイクルするように努めるべきである。
「8つの再生プログラム」と「贈与」の精神
贈与の精神は脱成長社会構築の要石(かなめいし)である。贈与の精神は、自律社会(脱成長社会)という具体的なユートピアの建設のために提案された好循環を形成する8つの再生プログラム(8つの「R」)のそれぞれの中に顕在している。わけても最初の再生プログラムである「再評価」が特徴的だ。なぜなら市場社会の諸価値―悪化する経済競争、我利我利(がりがり。自分の利益だけを営むこと)の精神、富の際限なき蓄積―と自然に対する略奪的思考に代わり、利他主義、互酬性、コンヴィヴィアリテ(convivialité、楽しい生活を創造し分かち合う倫理)、自然環境の尊重などの諸価値を導入することが大切である。(中略)つましさの中でも分かち合いを行えば万人が満足し、さらには生きる楽しみも生まれるが、我利我利の精神と結びついて豊かさは不幸を生む。そこで2番目の再生プログラム「概念の再構築」は豊かさと貧しさを再考する必要性を重視す。「本当の」豊かさは人間関係からなる様々な財によってつくられる。例えば相互扶助、分かち合い、知識、愛情、友情に基づく財のことである。反対に不幸は何をおいても心理的なものであり、近代社会が連帯的共同体の代わりにもたらした「孤独な群衆」の中の孤独感からもたらされる。([3]88~89ページ)
〇ラトゥーシュにあっては、以上の「8つの再生プログラム」はどれも、ある種のユートピア(希望と夢の源泉)である。そして、その実現は、地域社会という具体的な場所において生起し、地域社会の基本的なニーズの充足をめざすことに収斂される。その点で、「再ローカリゼーション」は、「具体的なユートピアにおいて中心的な位置を占める」([2]186ページ)ものであり、「脱成長」の要諦(ようてい)である。
〇ラトゥーシュは、日本社会について、次のように評している。「日本は新興工業国が台頭する以前に西洋型経済成長を遂げた最後の偉大な社会である」([1]24ページ)。「日本は独自の<脱成長>社会を創造するに相応しい位置にいるように思われる。なぜなら日本には、古(いにしえ)から続く東洋の文化が凶暴な西洋化によって完全に根絶されることなく残っており、そのような伝統文化が現在の経済危機を契機に復活する可能性があるからである」([2]17ページ)。
〇自然環境の破壊や資源の枯渇が進行し、人間(人類)社会は存続の脅威にさらされている。貧困や格差・分断が深刻化し、民主主義が機能不全に陥り、しかもコロナ禍で社会全体が未曽有の危機的状況にある。そんななかで日本社会はいまだ、「経済成長」信仰の呪縛(じゅばく)から逃れられないでいる。オルタナティブな「脱成長」社会の創造は、人間と自然との関係性の再構築とともに、地域社会の政治・経済の自立性や歴史・文化の独自性を模索し再発見・再生することから始まる。それは、グローバルな経済成長や物質的な充足に価値をおく社会とは異なる論理の構築と展開を必要とし、住民自身の主体的・自律的で、連帯的・共働的な地道な実践(「生活基盤の再ローカル化」)に基づく。しかもその活動や運動は、日本の経済や社会に回収されてしまうのではなく、「節度ある豊かな地域社会」の創造に集約されなければならない。
〇本稿で取り上げたラトゥーシュの3冊の本の訳者である中野佳裕は、次のように述べている。「訳者として最も望むことは、ラトゥーシュ思想を通じてわれわれが戦後日本の社会発展の歴史を国際的な文脈で再検討し、その結果として、日本の(玉野井芳郎らの)地域主義や(宮本憲一らの)地方自治論等のオルタナティブな日本を求める思想潮流がより統合された形で急進化され、地域社会の自律自治を再生する実践が活性化されることである」([2]332ページ)。付記しておきたい。
第4章
「民俗としての福祉」×「福祉教育の目的」
―岡村重夫の「1976年論文」―
〇春が戻ってきた(内山節の「横軸の時間」)。筆者(阪野)は、定年を契機に、年金で生計を維持しながら、80坪ほどの農地で自家用野菜を育てる(「定年百姓」「年金百姓」になれるわけがない)家庭菜園者でもある。それが、「老人」(※)である自分の新たな生きがいやレクリエーションになっている。いまは、毎晩のように食卓に上がる“つみ菜”の春の香りを楽しんでいる。昨日(3月5日)は、春ジャガイモの植え付けをおこなった。
※民俗学者の宮田登(みやた・のぼる、1936年~2000年)は、『老人と子供の民俗学』(白水社、1996年3月)で、〈おい〉には「盛りを過ぎた」という語感がある〈老い〉と、「追加する」というイメージがある〈追い〉の二つがある。落ち目になっていくというマイナスの〈おい・老い〉を意味する前に、プラスイメージの〈おい・追い〉があった(5~6ページ)、という(5~6ページ)
※農(百姓仕事)は季節による単純な繰り返しの作業ではなく、自然を相手にした繊細で創造的な仕事である。アメリカの精神科医で老年学者のジーン・コーエンは、『いくつになっても脳は若返る』(野田一夫監訳、ダイヤモンド社、2006年10月)で、「創造性」は年をとるとより一層深まり、豊かになり得る。ガーデニングは「小さな創造性」が発揮しやすい分野である、という(225、227ページ)。
〇筆者の手もとに、安室知(やすむろ・さとる)の『都市と農の民俗―農の文化資源化をめぐって―』(慶友社、2020年2月)という本がある。この本では、「現代日本における農の存在意義について、生活者の目線に立ち、国の政治や経済とは別の角度から捉え直し」ている。その際の切り口は、都市や農村における「農の文化資源化」である。「文化資源化」とは、「人が遺伝的に獲得したもの以外のすべてを文化とし、それを何らかの目的をもって資源として利用すること、および利用可能な状態にすること」をいう。安室にあっては「現代民俗学においては、文化資源化は避けて通ることができない問題である。現代において民俗伝承とされるものは、程度の差こそあれ、商品化や観光化など何らかの形で資源化されているといってよい」(9ページ)ここで筆者は、都市における「市民農園」とともに、無農薬・有機栽培野菜の商品化やグリーン・ツーリズム(農山漁村地域における滞在型の交流・余暇活動)、棚田のオーナー制度や観光などを思い出す。
〇筆者が暮らす岐阜県S市は、700年以上の伝統をもつ“刃物のまち”として知られている。まちには何故か、喫茶店と寿司屋が多い(筆者にはそう思える)。住民には、労働に追われることから、また家事時間の削減を図るために喫茶店で「モーニング」の朝食をとり、夕食を外食ですませる習慣があるのであろうか。それは、S市の刃物産業は部品製造業者と工程加工業者による社会的分業体制が採られていることから、零細企業や家内工業が多いことによると思われる。また、喫茶店や寿司屋は、コミュケーションや接待・商談の場となっているのであろう。
〇喫茶店の「モーニング」といった“日常の実際の暮らし”“人間の生”を民俗学の視点で探り、それを「ヴァナキュラー(vernacular)」と称して、「現代民俗学」(「現代学」としての民俗学)の研究対象とする本がある。島村恭則(しまむら・たかのり)の『みんなの民俗学―ヴァナキュラーってなんだ?―』(平凡社、2020年11年)がそれである。この本で、島村は、「ヴァナキュラー(俗)」について次のように定義づけている。「民俗学とは、人間(人びと=〈民〉)について、〈俗〉の観点から研究する学問である」。その際の「〈俗〉とは、①支配的権力になじまないもの、②啓蒙主義的な合理性では必ずしも割り切れないもの、③「普遍」「主流」「中心」とされる立場にはなじまないもの、④(支配的権力、啓蒙主義的合理性、普遍主義、主流・中心意識を成立基盤として構築される)公式的な制度からは距離があるもの、のいずれか、もしくはその組み合わせのことをさす」(16、31ページ)。
〇別言すれば、〈俗〉とは、「対覇権主義的、対啓蒙主義的、対普遍主義的、対主流的、対中心的、対公式的な観点を集約的に表現したもの」(30、107ページ)である。それらの観点を持ち、それらの世界を研究対象とするのが「民俗学」である。島村によると、こうした観点や志向は、「日本の民俗学の基底部に確実に存在している」(29ページ)。なお、「覇権」とは「強大な支配的権力」(20ページ)を意味し、「啓蒙」とは「非合理的な世界にいる無知蒙昧な人を、明るい世界に導いて賢くすること」(17ページ)、「普遍」とは遍(あまね)く通用すること、を意味する。
〇周知の通り、「日本民俗学の創始者」と言われる人に柳田國男(やなぎた・くにお、1875年~1962年)がいる。その柳田民俗学に対して批判的な論陣を張る民俗学者に赤松啓介(あかまつ・けいすけ、1909年~2000年)がいる。筆者の手もとに、赤松の『差別の民俗学』(筑摩書房、2005年7月)という本がある。赤松は例えば、次のように批判する。「柳田系民俗学の最大の欠陥は、差別や階層の存在を認めようとしないことだ。いつの時代であろうと差別や階層があるかぎり、差別される側と差別する側、貧しい者と富める者とが、同じ風俗習慣をもっているはずがない。差別する側、富める者は、どうすれば自分の優位を示せるかを、いつの場合でも最大の関心にしている」(165ページ)。
〇赤松にあっては、民俗学は、伝承(「口頭伝承」「民間伝承」)や民俗に内在する階級性や差別論理と切り結び、それを読み解くことに意味があり、避けがたい必然がある。そして、日本社会の重層的な差別構造を見据えて、「解放の民俗学」を標榜し、「実践の民俗学」に執着する。赤松はいう。「一般の民俗学と、私たちの民俗学はどこが違うのか。権力や行政の民衆支配に協力するための調査、学術的研究のためという学閥的、また立身出世型のタネ探し、そうしたものがこれまでの民俗学であったといえる。(中略)解放の民俗学は、立身出世や金儲け、憐憫(れんびん。情けをかけること)などとは無縁のものである。あらゆる底辺、底層からの民俗の堀り上げ、掘り起こし、その人間性的価値の発見と、新しい論理、思考認識の道を開くということであろう。しかし、それは今後においても、とうてい平坦な道ではありえないのである」(116~117ページ)。
〇例によって唐突であるが、ここで想起されるものに、岡村重夫(おかむら・しげお、1906年~2001年)の論稿「福祉と風土―民俗としての福祉こそ基底―」がある。日本生命済生会社会事業局発行の雑誌『地域福祉』1976年3号(通巻121号)、1976年7月、4~9ページに掲載されている。岡村がそこで指摘することは、「われわれの社会生活や個人意識は、強く日本の風土によって規定される事実、従ってまたその共同生活を基盤とする社会福祉も、日本特有の風土性をもつという事実」(6ページ上段)である。
〇岡村はその論稿で、「民俗としての福祉」について概念規定はしない。ただ、福祉を「生活の次元」で捉えれば、福祉は風土によって規定され伝承された共同生活上の「生活の知恵」「生活の工夫」であり、「風土の産物」である、とする。次の一節を引いておく。
福祉とは、すぐれた人々の日常生活上の困窮に対する地域住民の共同的な援助に由来するものであると考えるならば、それは、人々の日常生活のいとなまれる環境、すなわち歴史的であると同時に空間的、自然的な風土との関連を無視することはできないであろう。社会福祉は政府の政策である以前に、すでに生活者が共同生活を守るために工夫した、いわば「生活の知恵」であった。(4ページ下段~5ページ上段)
主として輸入文化に支えられた官製社会福祉や専門家の社会福祉論と、民俗としての社会福祉も、また二重構造的に考えられるけれども、重要なことは、民俗としての福祉こそが基底となって、その上に社会福祉政策や社会福祉文化が消長するということである。福祉の風土とは、まさしくこの基底部分であると考えられる。そしてこの基底部分が掘りくずされ、分解しないためには、外来の上部構造に対して、生活者の見解を対置させ、近視眼的な専門家や法律を鋭く批判しなければならない。(9ページ下段)
〇古くは一番ケ瀬康子(いちばんがせ・やすこ、1927年~2012年)の指摘(「社会事業諸技術の文化的基盤」『社会事業』1958年2月号、全国社会福協議会)を引用するまでもなく、欧米の社会福祉やソーシャルワークの理論や思想、価値や倫理については、直輸入的に摂取し定着を図るのではなく、日本の文化や風土、日本人の国民性、社会構造や生活環境の特質などを十分に踏まえた日本的展開が求められる。ここで思い起こしておきたい。安易な輸入理論や思想(なかでも周回遅れのそれ)への依存には、十分注意すべきである。
〇ところで、「1976年」と言えば、岡村重夫の「福祉教育の目的」と題する論稿を思い出す。それは、伊藤隆二・上田薫・和田重正編著『福祉の思想・入門講座 ③福祉の教育』(柏樹社、1976年4月)の13~36ページに収められている。そこで岡村は、「福祉教育」は社会福祉の専門的知識や技術をもった福祉事業従事者を養成する「福祉専門教育」ではなく、一般市民の地域社会における福祉問題や社会福祉に対する関心を高めるものである(「福祉一般教育」)として、次のように述べている。
福祉教育の目的は、単に現行の社会福祉制度の普及・周知や「不幸な人びと」に対する同情をもとめることではなくして、社会福祉の原理ともいうべき人間像ないしは人間生活の原点についての省察を深めることであり、この省察にもとづく新しい社会観と人類文明の批判をも含まなくてはならないであろう。さらに言うならば、このような新しい社会観や生活観にもとづく具体的な対策行動の動機づけによって、福祉教育の目的は完結するものである。(19~20ページ)
〇そして、岡村にあっては、「真の福祉教育の目的」は具体的に以下の3点に集約される。そのなかで岡村は、次のように厳しく指摘する。福祉教育において「外在的な社会制度の欠陥を指摘する場合に、自分の内面的な偏見や人間観を自己批判することなしに、(あるいは)ひとの内面的文化を問うことなしに、単なる同情心や恩恵をよりどころとした『外面的福祉』の世論を造成することは、(それが)実現すればするほど福祉サービスの対象者は『気の毒なひと』として一般社会から疎外される結果になり終わり、福祉教育の目的は自己矛盾に陥らざるをえない」(34ページ抜き書き)。いまだに観念的な「福祉の心」や「思いやりの心」を育成する福祉教育が叫ばれ、その表層的な実践が展開されているなかで、改めて強く認識すべき指摘である。
(1)福祉的人間観の理解と体得
社会福祉は、その根底において独自の人間観に支えられねばならない。社会福祉の人間観は、社会的=全体的=主体的=現実的存在としての人間像である。この人間像の基礎にある仮説は、すべての個人が生活者であり、生活はいかなる場合にも、自己自身を貫徹してやまないということである。社会福祉の人間観は、抽象的に、あるいは観念的に「人格の尊厳」を主張するのではなく、具体的な生活者としての個人の重み、生活の重みを主張するものである。(31~32ページ抜き書き)
(2)現行社会制度の批判的評価
現在の社会制度によって福祉的人間性を無視せられ、そのような人間像による自己実現を妨げられている個人の生活実態を明らかにしなくてはならない。福祉教育の目的は、現行の社会制度から疎外され、「社会的・全体的・主体的・現実的な人間像」実現の機会を奪われている人が、どこに、またどれだけいるかを認識させることでなくてはならない。このことによって、福祉教育は、単なる人間観の教育よりすすんで具体的な教育目標をもつことができる。(33ページ)
(3)新しい社会福祉的援助方式の発見
福祉は本質的に社会福祉である。その「社会」とは、対等平等の個人によって形成される共同社会(コミュニティ)であり、社会福祉は、「慈善」や「施し」ではなくて、対等平等の個人が相互に援助し合う相互援助を本質とする。対等平等の個人が、全体的な自己実現の機会を提供されるように組織化された地域共同社会において、人びとはサービスの客体であると同時に主体にもなりうるような相互援助体系こそ、福祉的人間観から発展する新しい社会福祉体系である。その体系のなかで社会の果たすべき責任と個人の果たすべき責任とを明確にすることが福祉教育の第三の目的である。(35ページ抜き書き)
〇「民俗としての福祉」は、岡村の着想を手がかりに、今後洗練されるべき「形成途中の概念」(岡田哲郎)であると評される(福山清蔵・尾崎新編著『生のリアリティと福祉教育』誠信書房、2009年3月、180ページ)。また、「生活主体者の論理」を強調する岡村理論には、地域福祉の主体形成や福祉教育についての論究がほとんどみられないと言われる。そんななかで、「生活の知恵」「生活の工夫」としての「民俗としての福祉」という概念の明確化を図る。個人の社会生活の実態を生活者の目線に立ち、国の政治や経済とは別の角度や位相から捉え直す。そして、それを基底として地域住民の「相互援助の地域共同社会」に対する理解やそれに基づく行動のあり方を問う。それがいま、「福祉教育」実践や研究に改めて求められるひとつの歴史的・社会的視点や認識であろう。岡村の「民俗としての福祉」と「福祉教育の目的」の「1976年論文」は、その点においても注目すべき論稿(論考)である。「民俗としての福祉」と「(市民)福祉教育」の親和性・関連性に留意したい。
〇「人間(「民」)が遺伝的に獲得したもの以外はすべて文化」であり、「俗」である。それゆえに、民俗学はすべての学問の基底に位置づく。民俗学は非普遍や非主流、非中心などの民俗事象を研究対象とする。それゆえに、民俗学は「グラスルーツ(草の根)の学問」とも呼ばれる。また民俗学は、普遍や主流、中心などとされる側の基準によって形成された知識体系を相対化し、それを乗り越える知見を生み出そうとする学問である(島村恭規、30、256ページ)。「民俗としての福祉」の延長線上に「福祉民俗学」が構想されるとすれば、それは一面においてこうした民俗学に通底するものであろう。そしてそこに、生活主体者としての一般市民に対する福祉教育の新たな論理が見出される、あるいは見出すべきであろう。
〇なお、「福祉民俗学」を提唱するひとりに柴田周二(しばた・しゅうじ)がいる。柴田にあっては、「『福祉民俗学』を提唱する主たる理由は、福祉文化の基礎としての自立と協同の人間関係の根底に存在する、福祉をうけることを権利とする個人の協同を支える小集団をいかに形成するか、あるいはそれが形成されるための課題は何かを探究することである」(『福祉文化研究』Vol.24、日本福祉文化学会、2015年3月、63ページ)。別言すれば柴田は、「福祉社会を支える福祉文化の基礎を個人の自立と協同の人間関係とそれを支える小集団の形成に求め、福祉文化のあり方を、制度面だけでなく、人々の生活態度の面から考察する学問を『福祉民俗学』として位置付け、その方法と課題について」考察する(『人間福祉学研究』第10巻第1号、京都光華女子大学、2017年12月、8ページ)。
〇また、六車由実(むぐるま・ゆみ)は、「介護現場は民俗学にとってどのような意味をもつのか?」、「民俗学は介護の現場で何ができるのか?」という二つの方向性から問題提起をしようとして「介護民俗学」を掲げる。その際の問題意識のひとつは、「民俗研究者が地域で行っている聞き書きや調査が、地域の高齢者の介護予防につながる地域資源になりうるのではないか」ということにある(『驚きの介護民俗学』医学書院、2012年3月、6、227ページ)。本稿の最後に、六車の次の一節を引いておくことにしたい。
これまで民俗学は、地域の民俗の保存とそれを使った地域活性化という点で、地域づくり、まちづくりには積極的に関わってきた。高齢化がますます進み、在宅介護が地域における切実な問題となる今後は、このように高齢者が地域で暮らしていくことを支える介護予防事業に関わっていくことが、実践的な学問である民俗学に対して求められていくのではないだろうか。/だが、一方で私は、「介護予防」という言葉に少なからぬ違和感を覚えている。/介護予防という言葉には、介護は予防されるべきもの、という考え方が露骨に反映されている。/要介護状態になることは人間にとっては誰しもが迎える普遍的なことであり、(中略)介護を問題化するのではなく、介護を引き受けていく社会へと日本社会を成熟させていく(ことが必要である。)/そこで私は、「介護準備」という言葉を使ってみたい。(227~228ページ)
謝辞
本稿を草するに際しては、日本福祉大学の副学長・原田正樹先生と付属図書館にご高配を賜った。記して感謝申し上げます。
第5章
「贈与」再考メモ
―コミュニズムとアナキズム―
贈与概念を初めて体系的な社会分析のために用いた研究は、マルセル・モースの『贈与論』である。その主要な問いは、贈物の中に潜むいかなる力が、貰い手に返礼させるのかというものである。これに対するモースの答は神秘性を帯びている。つまり、マオリ族が用いる「ハウ」という観念それ自体に原因を求めた。「ハウ」とは、「物の霊、とくに森の霊や森の獲物の霊」とされ、返礼されずにいると――もち主を殺してでも――元の場所に戻りたがる「贈与の霊」である。贈与者は、贈物をハウと共に送ることで、貰い手に対して神秘的で危険な力を行使していることになる。この観念を媒介として、富、貢納、贈与の義務的循環と、それを通じた社会的結合関係の維持機能を説明するというのが、かの古典的名著の主旨であった。(下記[5]、28ページ)
〇筆者(阪野)の手もとにいま、3冊の本がある。白井聡(しらい さとし)著『武器としての「資本論」』(東洋経済新報社、2020年4月。以下[1])、斎藤幸平(さいとう こうへい)著『人新世の「資本論」』(集英社、2020年9月。以下[2])、内田樹(うちだ たつる)著『コモンの再生』(文藝春秋、2020年11月。以下[3])がそれである。現代の日本社会は、「格差」「分断」「貧困」、そして「コロナ禍」などの言葉で語られる。その現状は、「グローバル資本主義末期における、市民の原子化・砂粒化、血縁・地縁共同体の瓦解、相互扶助システムの不在という索漠(さくばく)たる」([3]6ページ)ものである。この3冊の本は、こうした行き詰まる資本主義社会の「いま」と、向こう側の新たな「社会像」について思考する際に役立つ。
〇[1]にあっては、自立が強制され、自己決定(自己責任)が追及される現代資本主義社会を生き延びるための「武器」になるのは、カール・マルクスの『資本論』である。1980年代以降の新自由主義(ネオリベラリズム)は、「小さな政府」「規制緩和」「市場原理主義」などをキーワードに、社会の仕組みだけではなく、人間の魂や感性、センスを変えてしまった。資本による生産・労働過程のそれのみならず、労働者の魂、人間の全存在(身体・心理・文化・社会的諸側面の全体。人間の「全体性」)の「包摂」である(66、67ページ)。[1]は、『資本論』のキモを平易に解説した画期的な入門書であるが、裏にあるテーマは「新自由主義の打倒」(222ページ)である。別言すれば、「資本主義を内面化した人生から脱却するための思考法」(「帯」)である。
〇[2]において斎藤は、「マルクスが求めていたのは、無限の経済成長ではなく、大地=地球を〈コモン〉として持続可能に管理することであった」(190ページ)として、「資本主義の転換」を迫る。その際の〈コモン〉とは、「社会的に人々に共有され、管理されるべき富のことを指す」。それは、資本主義(新自由主義)でも社会主義(国有化)でもない「社会像」(「脱成長コミュニズム」)であり、「水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主義的に管理する」(141ページ)ことをめざす。
〇[3]で内田はいう。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)によって、グローバル資本主義と新自由主義は大規模な修正を余儀なくされることになる。その先に取り得る選択肢のひとつが「コモンの再生」である。それは「いま」、世界各地で、共同・協働のネットワークの再評価が始まっていることからもうかがい知ることができる(270ページ)。内田にあっては、国民国家がより小さな政治単位に分割されてゆく「『地域主義』がこれからの流れ」(261ページ)になるなかで、「コモン(共有地)」とは(「私」ではなく)「私たち」による「ご近所」共同体(6ページ)である。
〇私事にわたるが、2020年9月、「PSA:4.43」が筆者のその後の生活を決することになった。同年12月、「グリソンスコア:9」によって奈落の底に突き落とされる。そして、コロナ禍のなかの2021年4月、手術のために12日間の入院生活を強いられた。入院中のある日、(本当に)何故かふと、40年以上も前のことであるが、他界した伯父の「献体」のことを思い出した。身体の「贈与」である。なお、伯父は晩年、百姓仕事などのすべてを娘婿に渡し、近くの寺院(真宗高田派本山 専修寺)で奉仕活動に没入している。
〇いま、資本主義社会の行き詰まりについて批判する文脈で、またコミュニティの再興が叫ばれ、「コモンズ」(共有資源)や「コミュニズム」(共同体主義)について論じられるなかで、「贈与」が注目されている。「贈与」は多義的で、多用あるいは乱用されている感があるが、その言葉で思い出すのはマルセル・モースの『贈与論』である。モース(1872年~1950年)は、フランスの社会学者・文化人類学者であり、協同組合運動を中心とする社会主義思想への共感・共鳴を示していた。1925年に出版された『贈与論』は、「バイブル的存在」(小林修一)、「現代贈与論の原点」(平尾昌宏)などと評される。周知の通りである。
〇以下では、モース著・森山工(もりやま たくみ)訳『贈与論 他二篇』(岩波文庫、2014年7月。以下[4])におけるモースの基本的な議論・主張のうちから、(1)「贈与の3つの義務」と(2)「全体的社会的事象」についてのみ再確認しておくことにする。それは例によって、「市民福祉教育」実践・研究に「使える」であろう理論や方法に関する筆者の個人的な関心による。
〇モースにあっては、伝統的な「贈与」は、「贈り物をおこなう義務」「贈り物を受け取る義務」、そして「受け取った贈り物に対してお返しをする義務」の3つの義務から成っている。この「贈与」「受領」「返礼」という義務のうち、その根幹に位置づけられるのは第3の義務すなわち「返礼」である。それは、「贈与」と「受領」の義務を前提としている(101ページ)。要するに、モースがいう「贈与」は、相互性(互酬性)に基づく義務的な「贈与交換」(「贈与と交換」「贈与=交換」「贈与という名の交換」)である。そして、モースによると、「贈与」「受領」「返礼」は「気前よく」(60ページ)なされねばならず、「借りを返さないままでいる」(395ページ)と劣位に置かれたり、対抗関係を生み出すことになる。この点は現代社会においても然りである。「ギフト(gift)という一つの単語が『贈り物』という意味と『毒』という意味」(37ページ)の両義性を持つといわれる所以でもある。物の贈与には悪意や敵対といった感情的要素(感情的価値)が備わっているのである。モースはいう。「物には依然として情緒的な価値(精神的価値:筆者)が備わっているのであって、貨幣価値に換算される価値(金銭的価値:筆者)だけが備わっているわけではない」(393ページ)。
〇「返礼」の義務の特徴は、「贈与の恩恵に浴した人には、もらったものと等価のものに、さらに何かを上乗せしてお返しすることが義務づけられるようになること」(15ページ)にある。そして、「贈与」「受領」「返礼」が果たす機能は、物の交換や流通それ自体ではなく、「贈り物を受け取るということ、さらには何であれ物を受け取るということは、呪術的にも宗教的にも、倫理的にも法的にも、物を贈る側と贈られる側とにある縛りを課し、両者を結びつける」(43ページ)ことにある。すなわち、「贈与」「受領」「返礼」の循環・体系は、個人や集団などの間に友好的な関係(紐帯)を生み出し、その維持・強化を促すのである。モースはいう。「社会が発展してきたのは、当のその社会が、そしてその社会に含まれる諸々の下位集団が、さらにその社会を構成している個々人が、さまざまな社会関係を安定化させることができたからである。すなわち、与え、受け取り、そしてお返しをすることができたからである」(450ページ)。
〇ところでモースは、「贈与」は、「社会生活をかたちづくるあらゆることが、ここで混ざり合っている」という。それは、「宗教的な制度であり、法的な制度であり、倫理的な制度である――この場合、それは同時に政治的な制度でもあり、家族関係にかかわる制度でもある。それはまた、経済的な制度である」。それゆえにモースは、これを「『全体的な』社会的現象」(「全体的社会的事象」)と呼ぶことを提唱する(59ページ)。これは、「『全体』への強い志向性にもとづいて学術的探究に臨む」(「訳者解説」476ページ)モースの社会学・文化人類学の特徴を示すものである。ここで、次の一文を引いておくことにする。「全体を丸ごと考察すること、これによって、本質的なことがら、全体の動き、生き生きとした様相を把捉(はそく)することができたのであり、(中略)社会生活を具体的に観察することのうちに、新しい諸事象を見いだす手段がある。(中略)全体的社会的事象を考究すること以上に差し迫ったものはないし、また実り多いものもない」(442ページ)。
〇上述したように、モースは[4]で、「贈与の3つの義務」に基づく贈り物が循環することによって、社会的連帯・紐帯が生み出されることを指摘した。その点に関して、私事ながら本稿の冒頭に記した伯父の「献体」の贈与行為についてはどう考えるのか。公益財団法人・日本篤志献体協会によると、「献体の最大の意義は、みずからの遺体を提供することによって医学教育に参加し、学識・人格ともに優れた医師・歯科医師を養成するための礎となり、医療を通じて次の世代の人達のために役立とうとすること」(同ホームページより)にある。現在、わが国には献体篤志家団体が62団体あり、献体登録者の総数はおよそ30万5000人を越え、そのうちすでに献体した人は約14万人に達している(2019年3月31日現在)。
〇伯父の献体行為は、宗教的な動機も考えられるが、見返りを求めない、利他主義に基づく不特定の匿名他者への自発的な贈与であった。また、伯父が普段所属していたアソシエーション(機能集団)やコミュニティ(共同体)に対する個人的な感情(正義、責任、義務、感謝、愛、自己実現など)の発露であったろう。しかもそれは、医学教育に参加し、医療を通じて次世代の人達に役立とうとする公的な贈与であったといってよい。さらに言えば、医学や医療技術、生命科学や生命倫理などの発展をもたらし、回りまわって伯父の家族の自己利益にもつながることが想定される。いずれにしろ、伯父の献体行為は何らかの個人的・社会的な連帯意識に基づくものであり、またその行為の結果として人々の個人的・社会(文化)的な連帯意識の形成が促される。あえて指摘するほどに目新しいものではないが、ひとつの論点として再確認しておきたい。
〇筆者の手もとにいま、2冊の本がある。仁平典宏(にへい のりひろ)著『「ボランティア」の誕生と終焉――〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』(名古屋大学出版会、2011年2月。以下[5])と山田広昭(やまだ ひろあき)著『可能なるアナキズム――マルセル・モースと贈与のモラル』(インスクリプト、2020年9月。以下[6])がそれである。そこに見いだされるひとつの論点([5]の〈贈与のパラドックス〉、[6]の「支配への抵抗」)について留意したい。
〇[5]において仁平は、「ボランティアをはじめとする参加型の市民社会の諸カテゴリーは、『善意』や『他者のため』と解釈される契機を不可避的に含むことになる。(中略)この『他者のため』と外部から解釈される行為の表象」を「贈与」と呼ぶ(10ページ)。そのうえで、「近現代の日本におけるボランティア言説の展開をたどり、参加型市民社会のあり方を鋭く問いなおす」(「帯」)。サブタイトルにいう〈贈与のパラドックス〉(paradox:逆説、矛盾)とは、贈与は行為者の真の意図とは別に、交換や見返り、偽善や自己満足などとして外部観察されがちである、という意味である。平易に言えば、「贈与の偽善性」「贈与の疑わしさ・怪しさ」である。
〇「アナキズム」には、「無政府主義」「政治的極左」「革命思想」といったイメージがつきまとう。その実は互酬性や相互扶助に基づく「支配に抗する思想」である。[6]において山田は、モースの『贈与論』を手がかりに、多くの思想家の議論・言説について言及し、「来たるべき経済」(贈与経済)社会を模索する。そして山田は、「非中心性、自主的連合、そしてつねにダイレクトに否を表明できる直接民主主義、これらはアナキズムの変わることのない基底である」(228ページ)。アナキズムは「個人的自由の追求と連帯の追求とがけっして矛盾しないと考える思想」である。「個人の自由の確保こそが真の連帯の条件である」(195ページ)、という。なお、ここで筆者は、アナキズムに関して「地域主義」(「小さな政府」)の理念を基盤に、「市民」のつながりや集まりである「地域コミュニティ」における「共働」をイメージしている。誤解を恐れずに付記しておきたい。
アナキズムとは、個人の自由を抑圧・侵害するようなあらゆる支配権力(とくに国家権力)を否定し、上からの組織化や統制を拒否しながら、合意によって自由で調和的な社会を建設しようとする思想である。したがってその根本には、権力による支配や強制なしに、社会を運営していくことが可能だとする発想がある。方法は大別してふたつある。ひとつは直接政治の領域に入って、国家権力を打倒しようとするものであり、もうひとつは国家権力と直接対決するのではなく、権力支配とは無縁な空間を(多くの場合、小規模かつ分散的性格の自治的協同体を建設するなどの方法で)非政治領域のなかに作り上げることによって、国家による権力支配を骨抜きにしていこうとするものである。(上記[6]、195、196ページ。中見真理(なかみ まり)著『柳宗悦――時代と思想―』東京大学出版会、2003年3月、59~60ページ。)
補遺
筆者の手もとにいま、在野の日本近代史家・渡辺京二(わたなべ きょうじ)の本『幻のえにし――渡辺京二 発言集』(弦書房、2020年10月)がある。少し長くなるが、次の一文を引いておきたい。なお、渡辺は、『苦海浄土――わが水俣病』(講談社、1969年1月)などで知られる作家・石牟礼道子(いしむれ みちこ)を「50年間一緒にやってきた戦友」(本書、119ページ)という。二人の「道行き」(歩み)については周知のことである(米本浩二『魂の邂逅――石牟礼道子と渡辺京二――』新潮社、2020年10月)。
自分というものがこの世に生まれてきて満足するような人間のあり方というのは、一人一人が独立するしかないんですよ。一人一人が独立してね、自分の主人公になってね、そういう本当に独立した人間がある地域を介してね、地域というのは土地、土地は自然ということでもあるけれども、そういうものを介して、お互いが結びついて、その土地の生活を守り抜いていくということしか無いんですよ。
要するに、僕らは自分自身をまず独立させることなんですよ。それはどういう意味かというと、自分の考えを持つことなんですね。自分の考えを持つ。(253~254ページ)
自分の頭で考えるということは、コモンセンスで考えることなんです。コモンセンス。つまり普通の良識です。生活する上での普通の理屈で考えればいいわけなんですよ。すべての事柄は。そうするとおかしい事は、いくら理論ぶって言ったっておかしいわけなんです。そういう健全な批判能力みたいなものをね、保持していこうというのが、自分が一人である事なんですよ。(255ページ)
つまり自分は一人である、自分は自分の考えで生きている、国からも支配されない、いわゆる世論からも妄想からも支配されないというあり方ができるのは、自分がある土地に仲間とともに結びついていると感じるからなんだ。ところがそういう基盤がなくなっているからね。自分が生きている土地に相当するのは、自分がともに生きてきた仲間なんだよ。自分がこの世の中で自分でありたい、妄想に支配されたくないという同じ思いの仲間がいる。それが小さな国である。自分が自分でありたいという自分と、同じく自分が自分でありたい人たちで作った仲間が、小さな国になっていく。そういうものをしっかり作るということが僕の思う革命なのさ。それ以外はない。(257~258ページ)