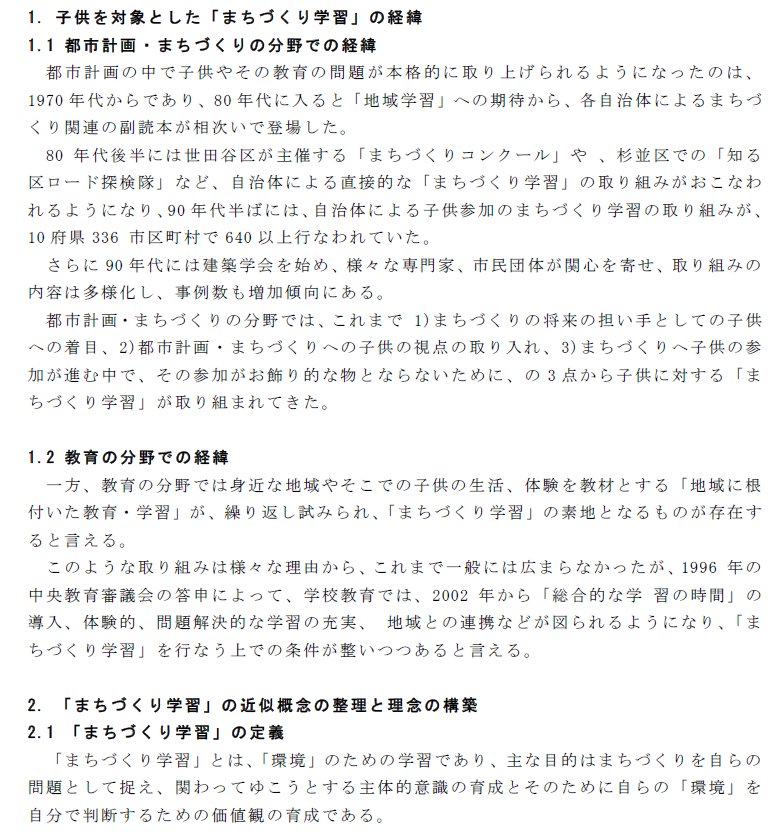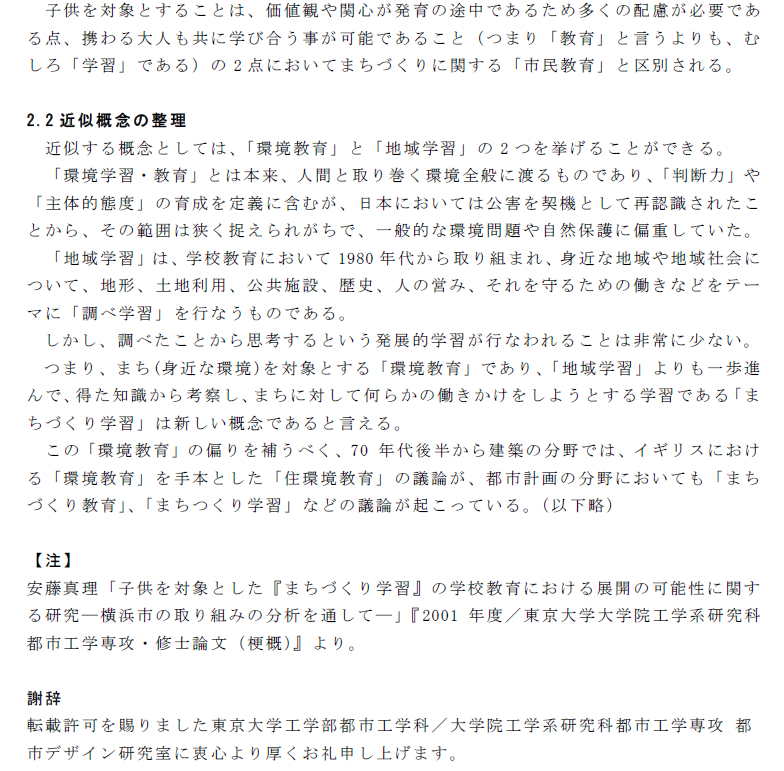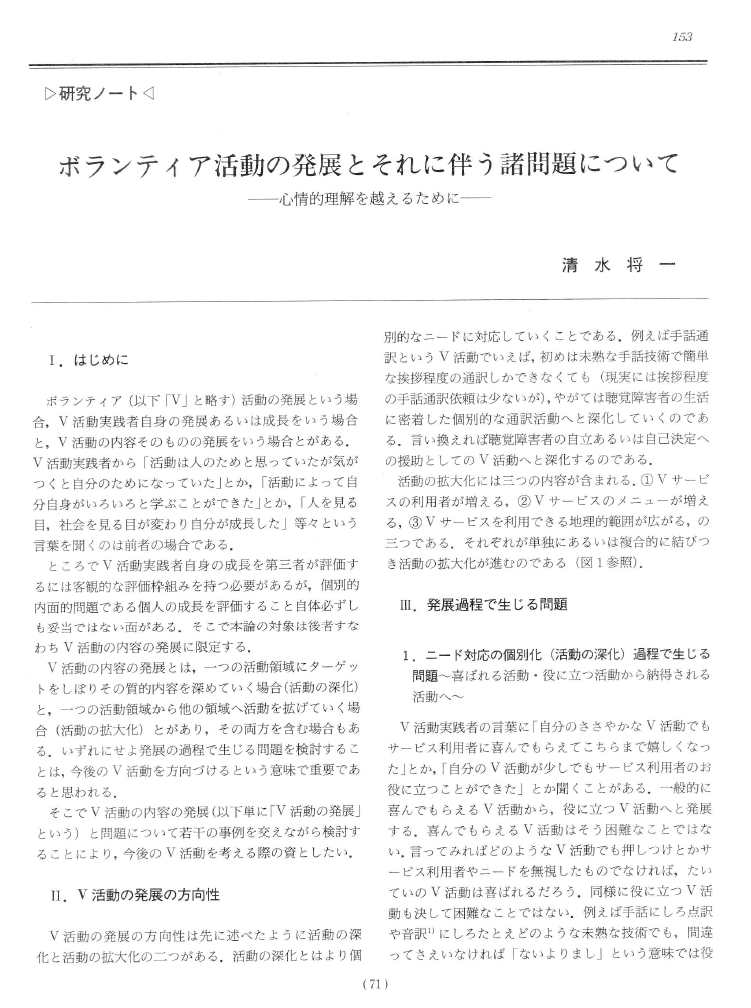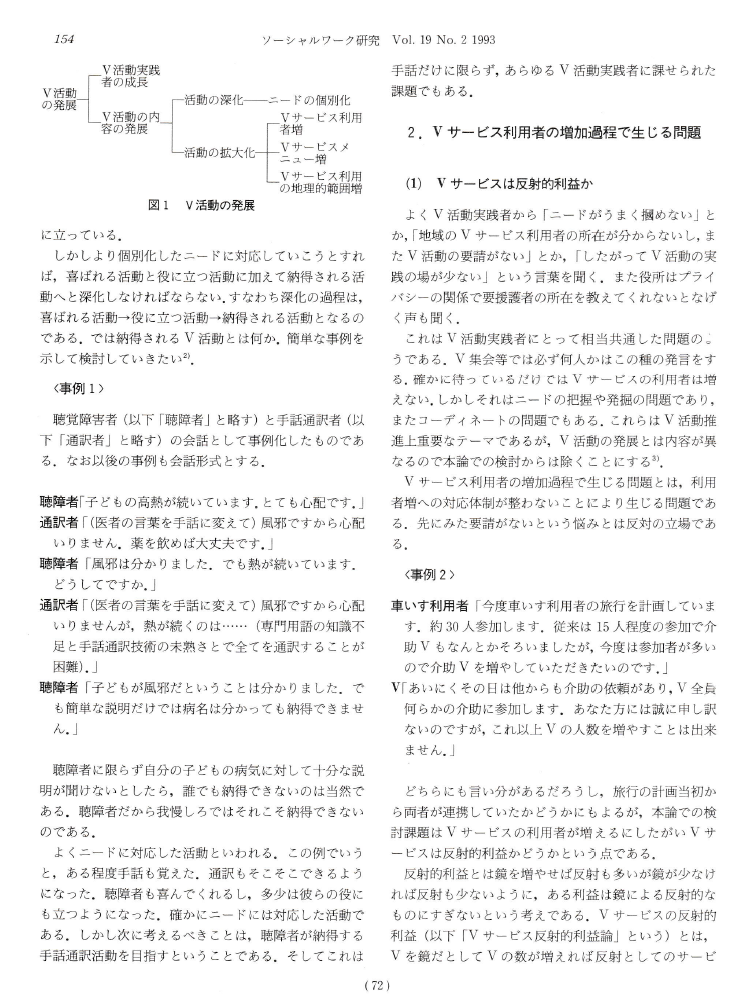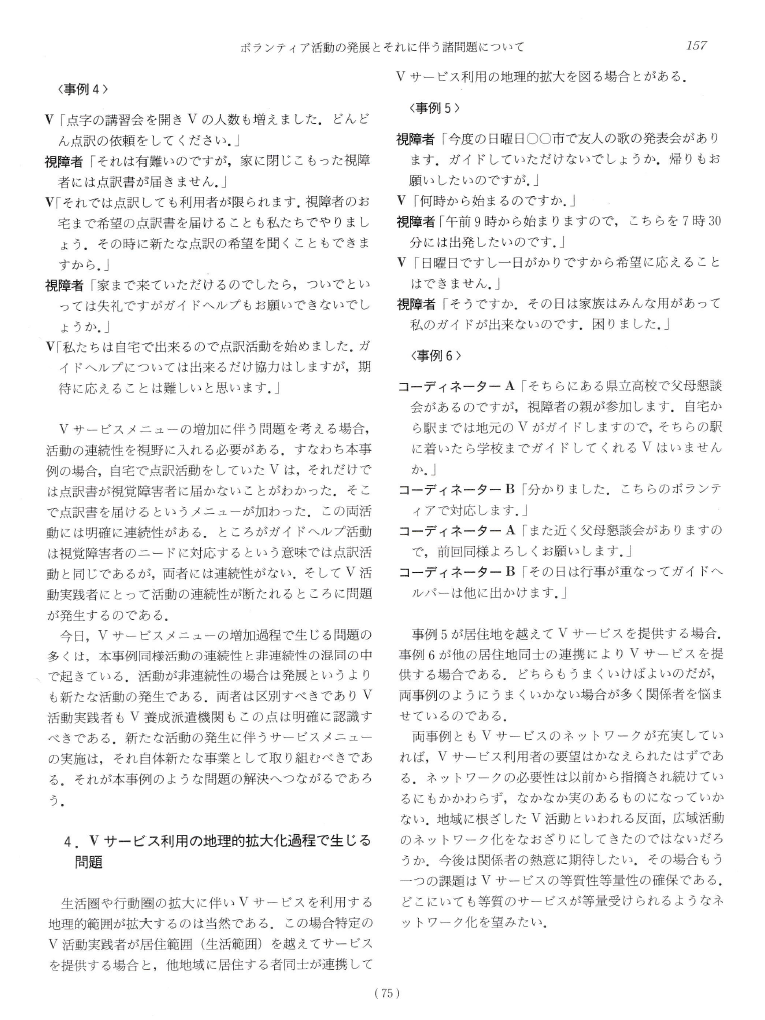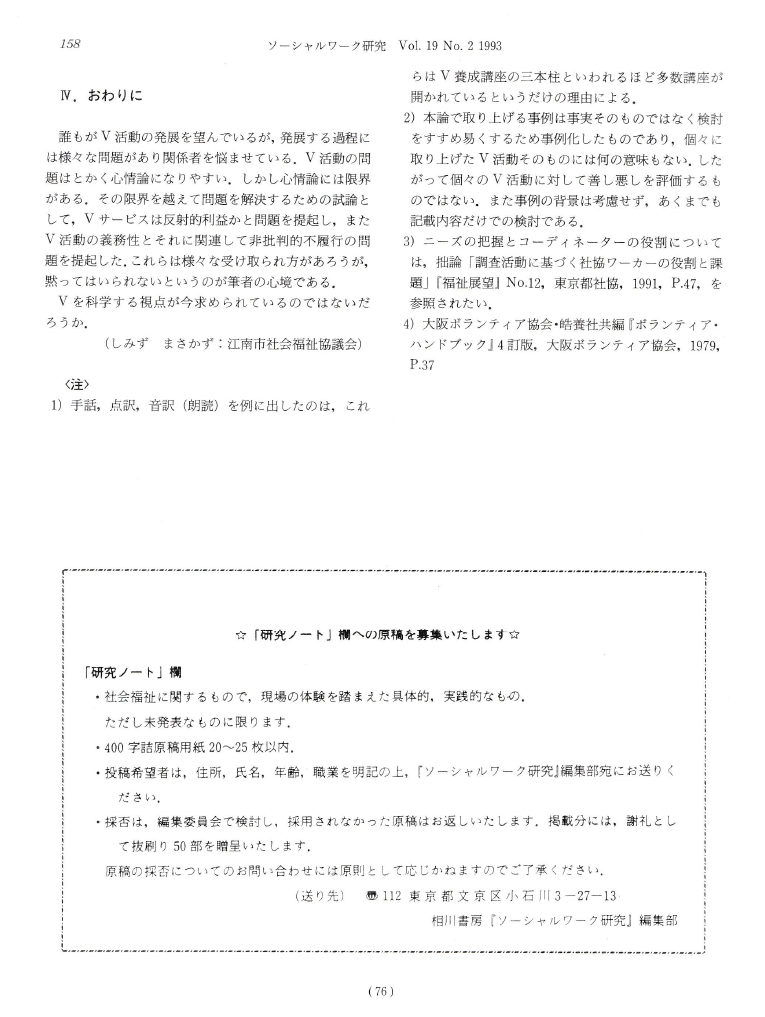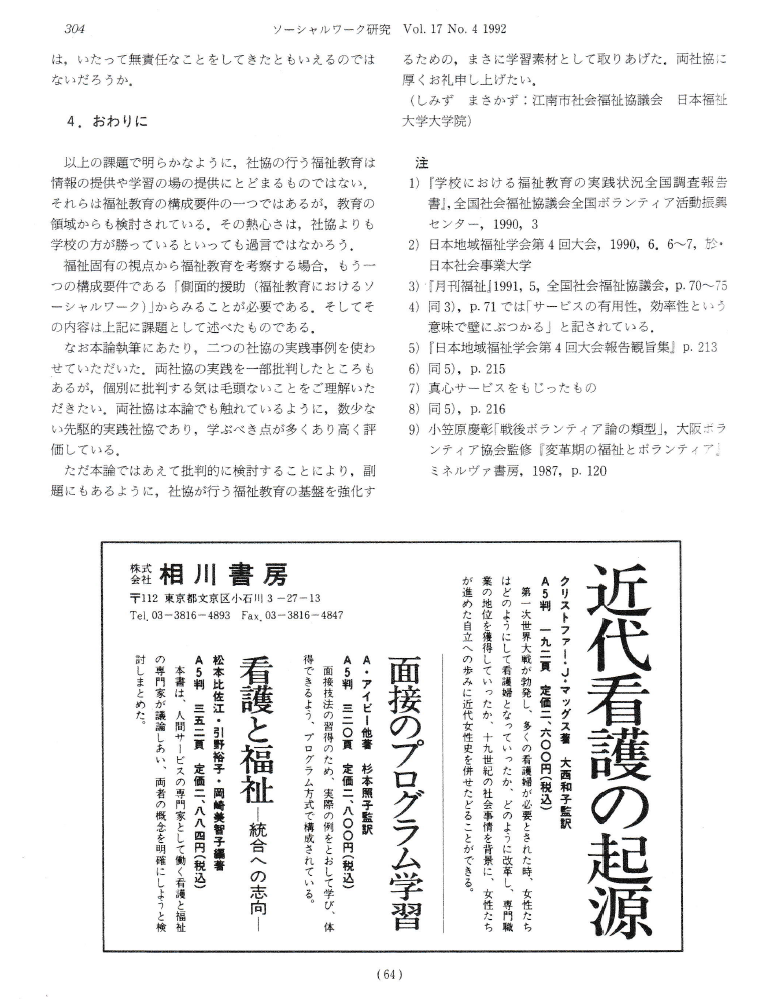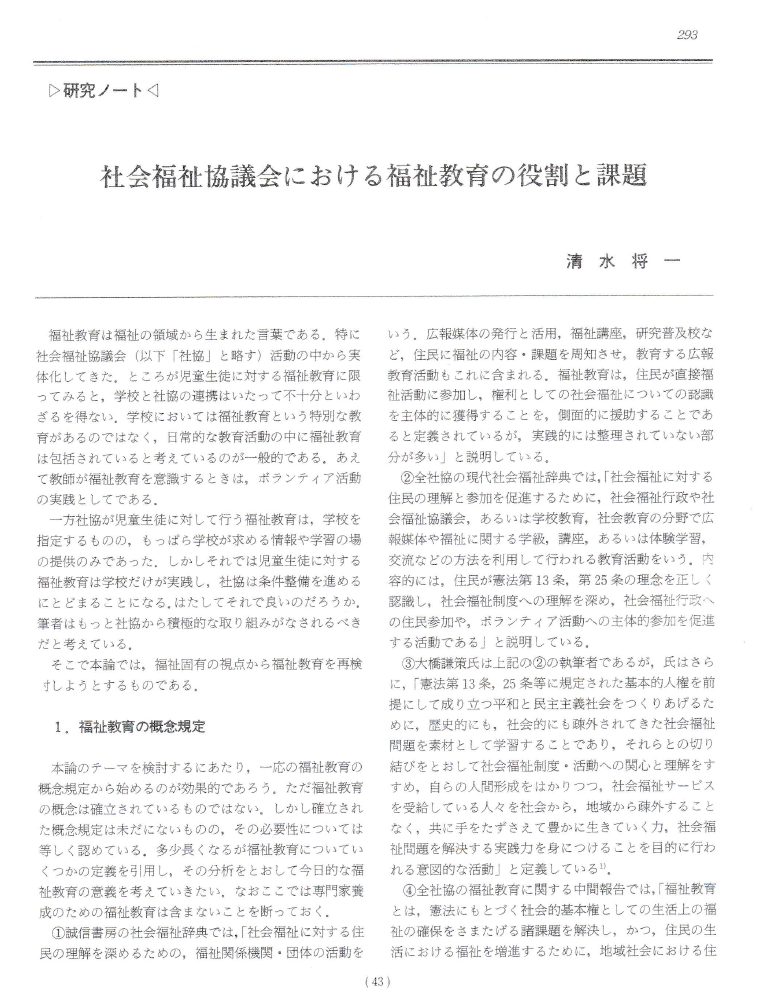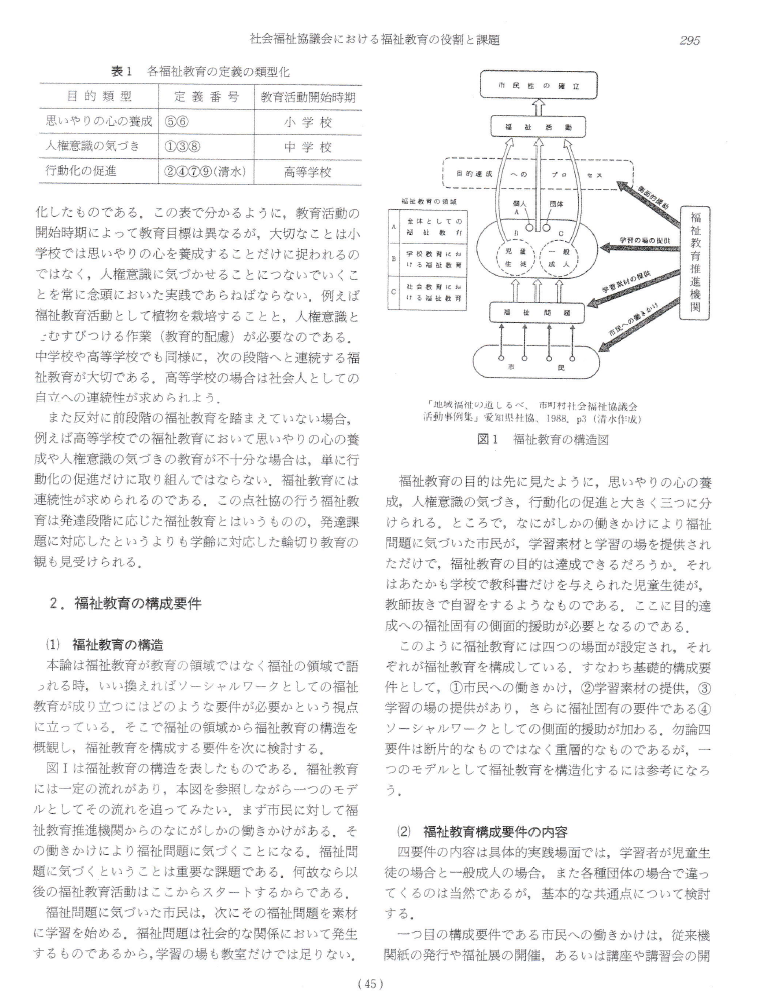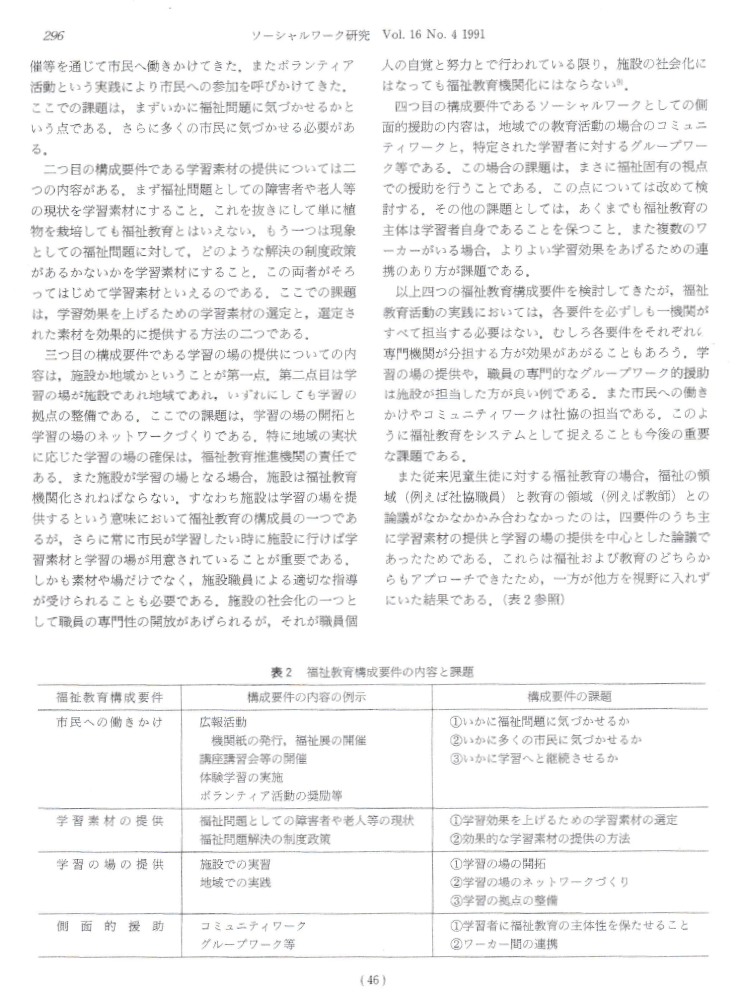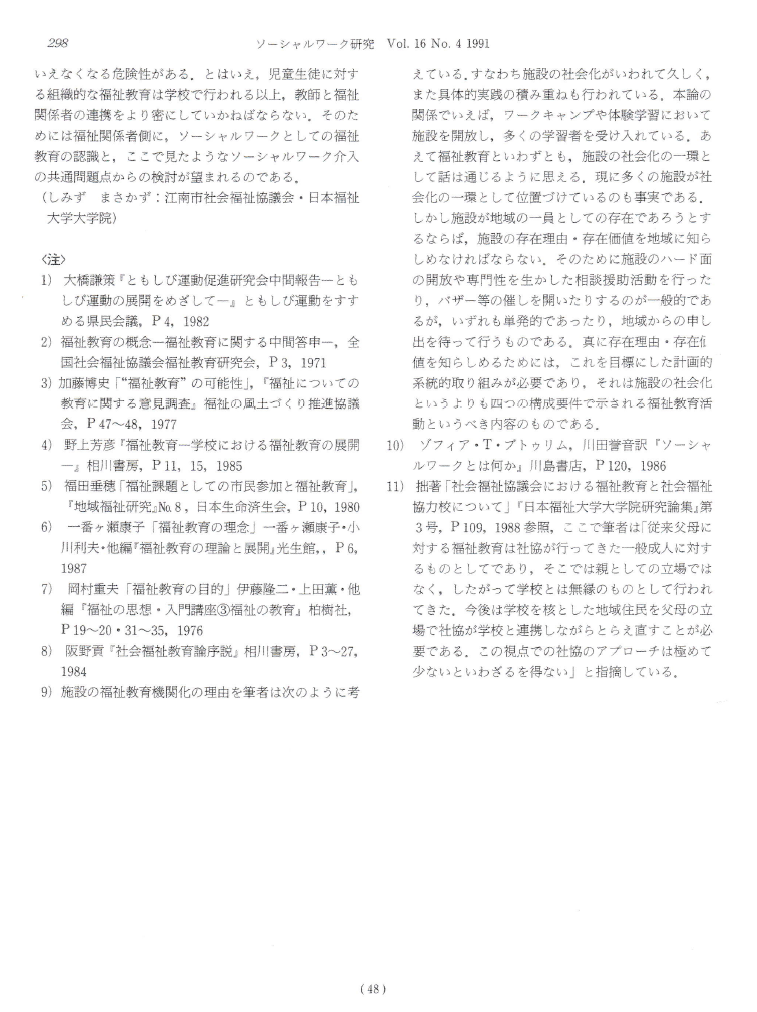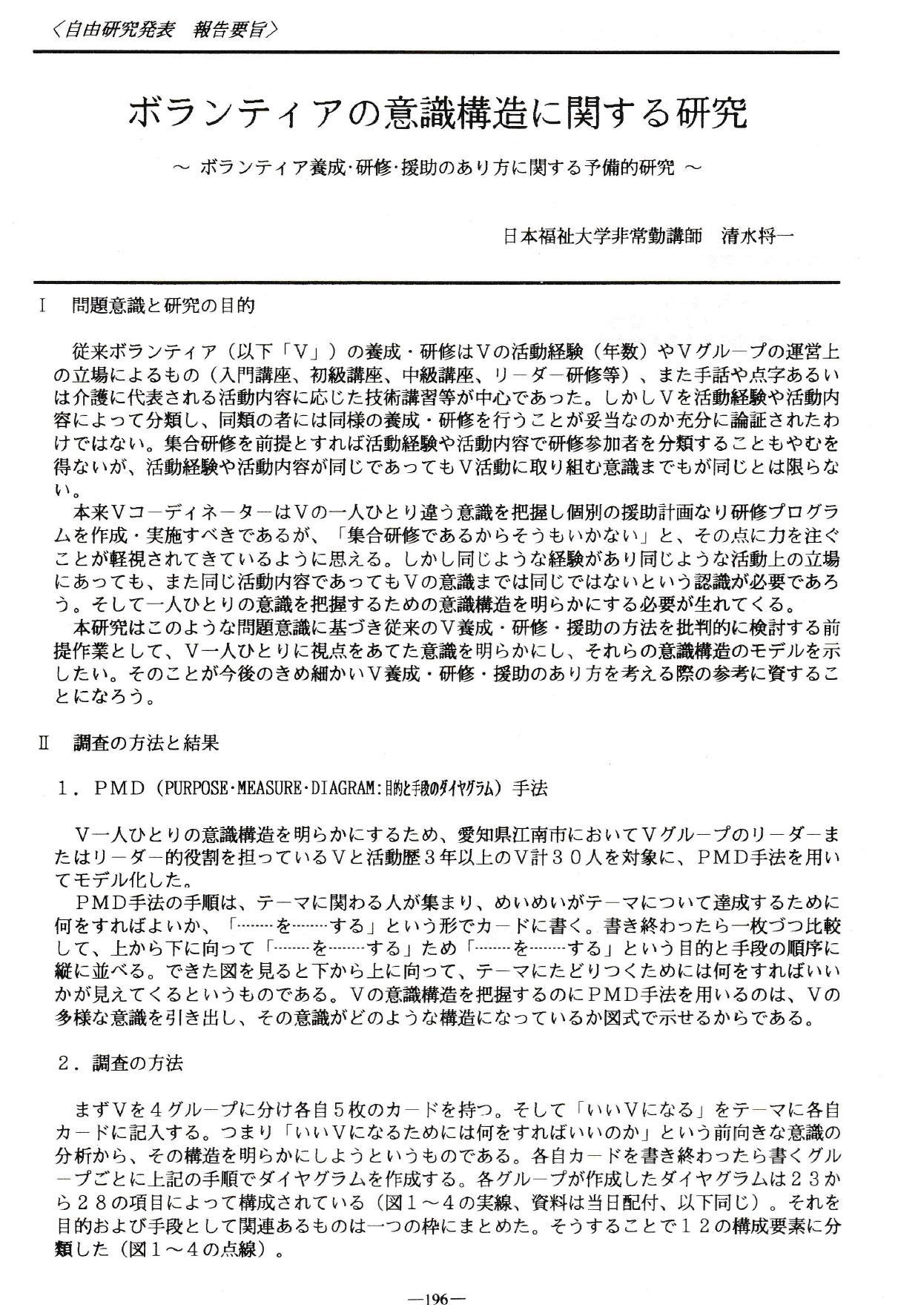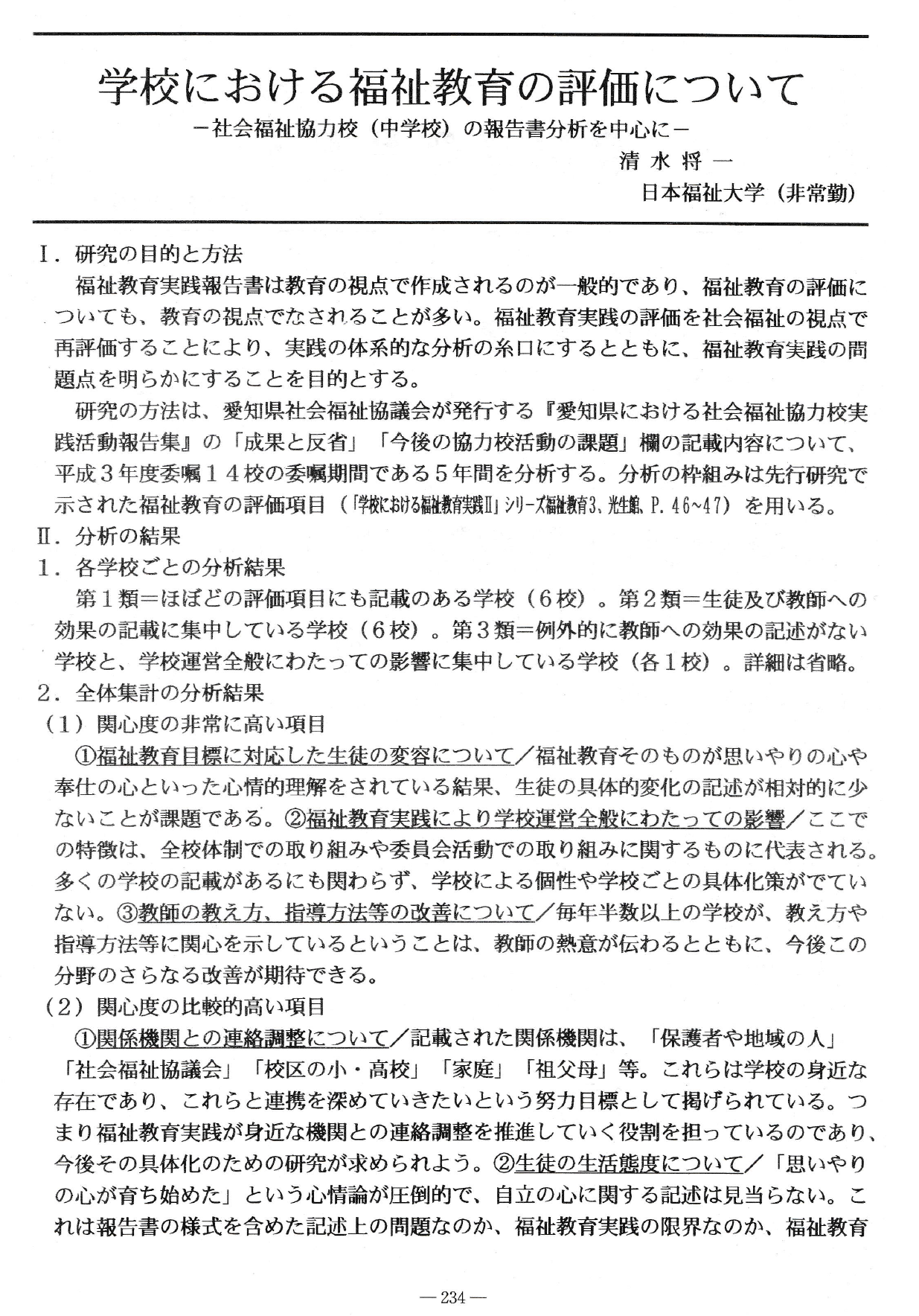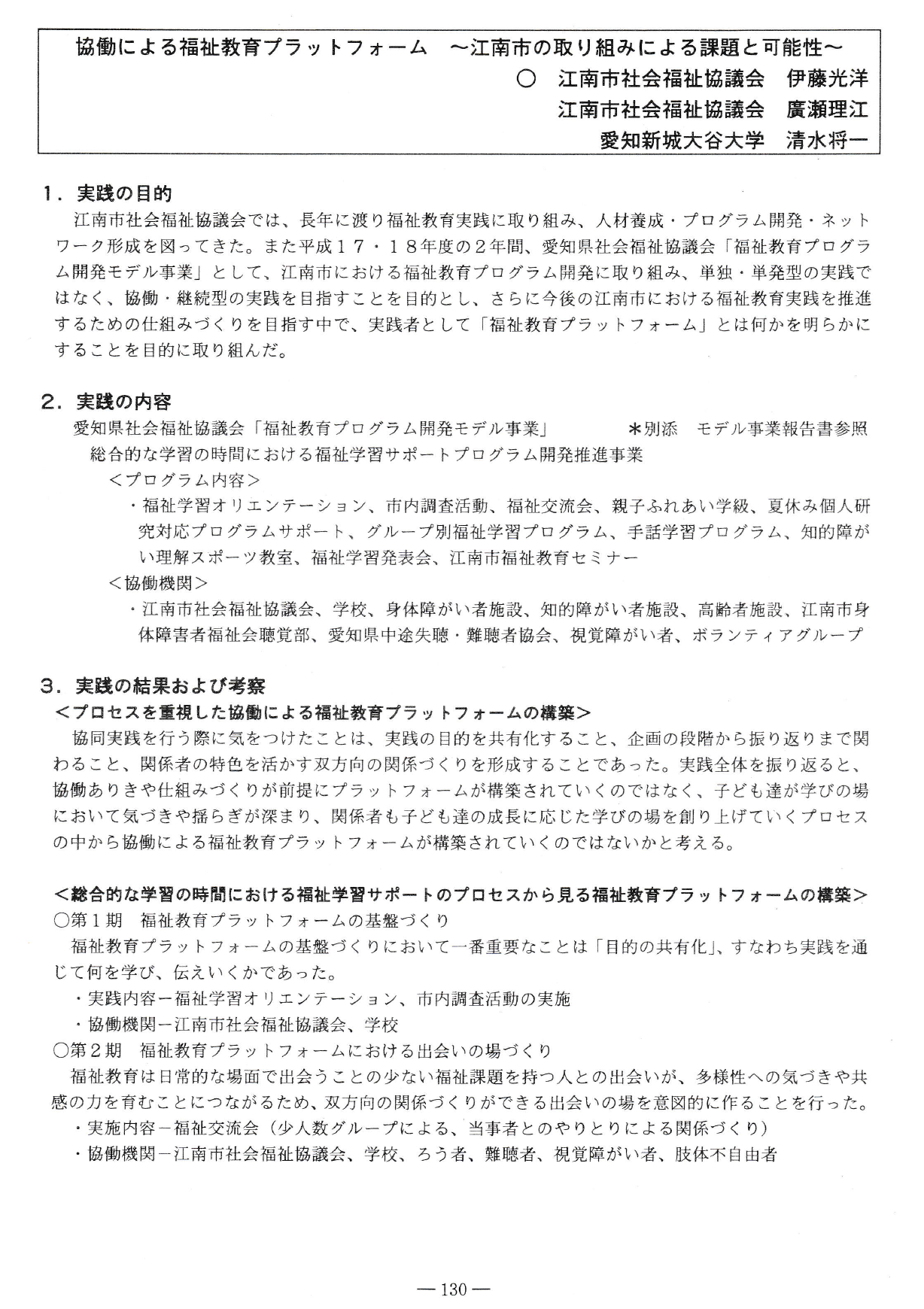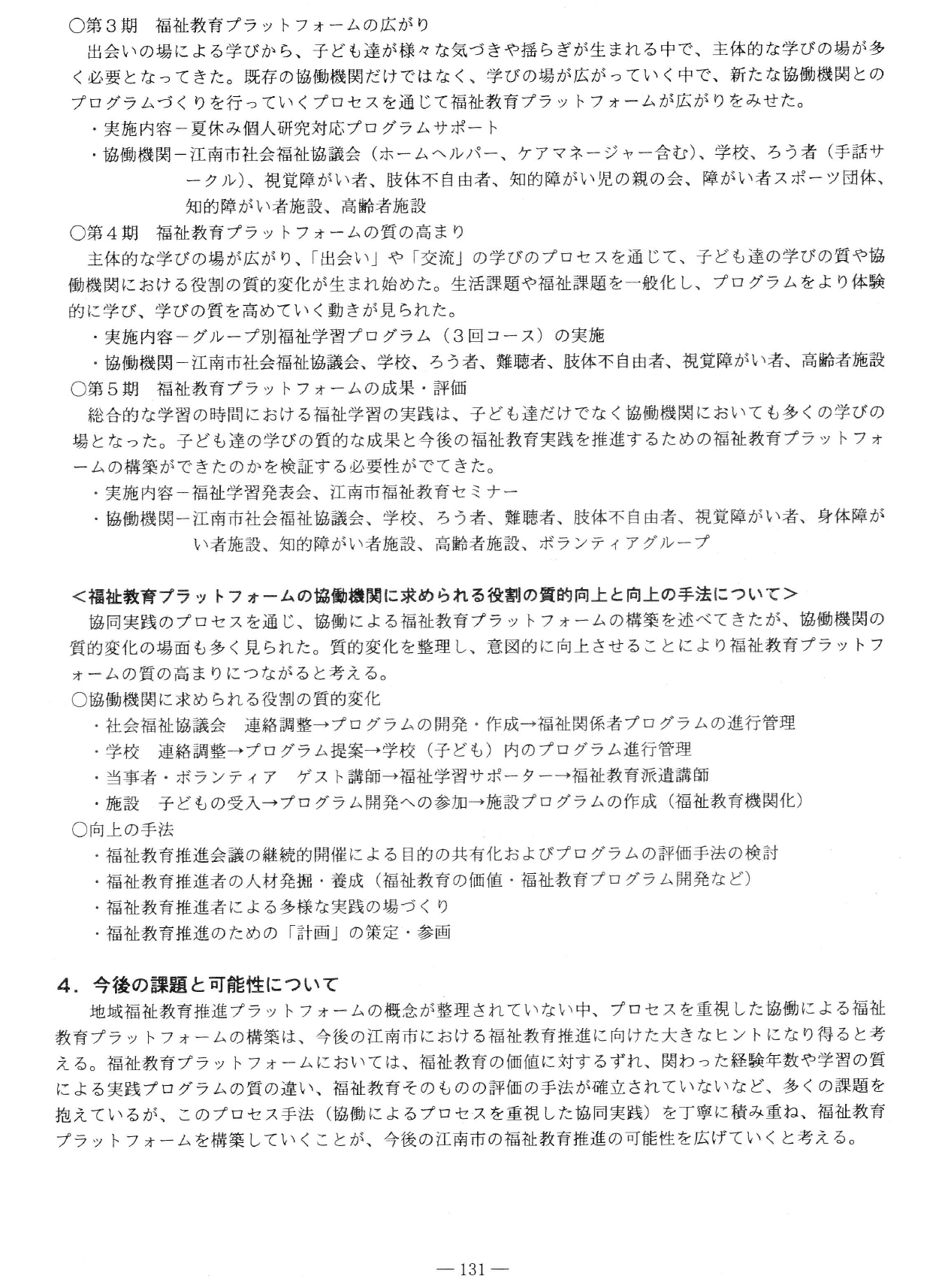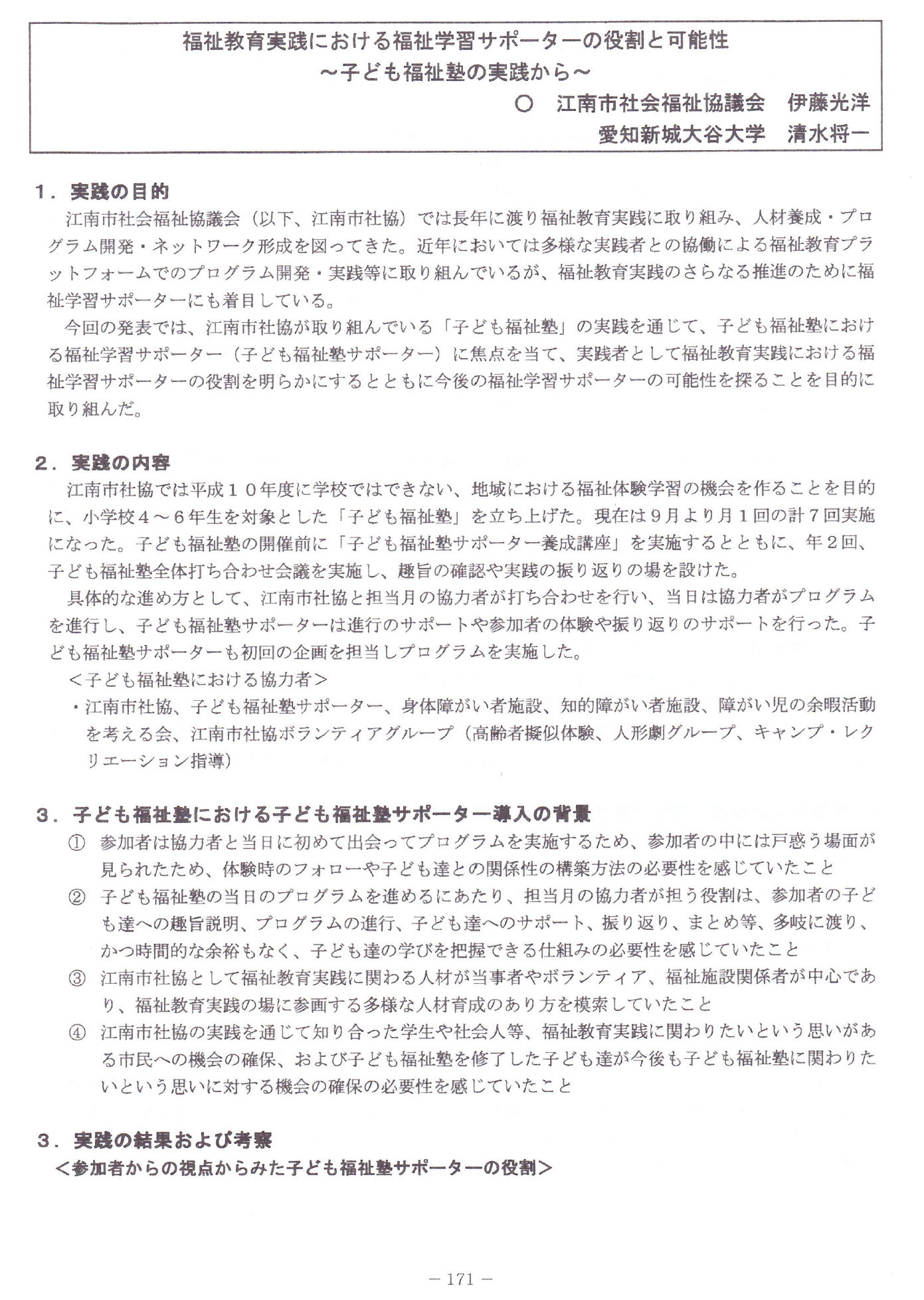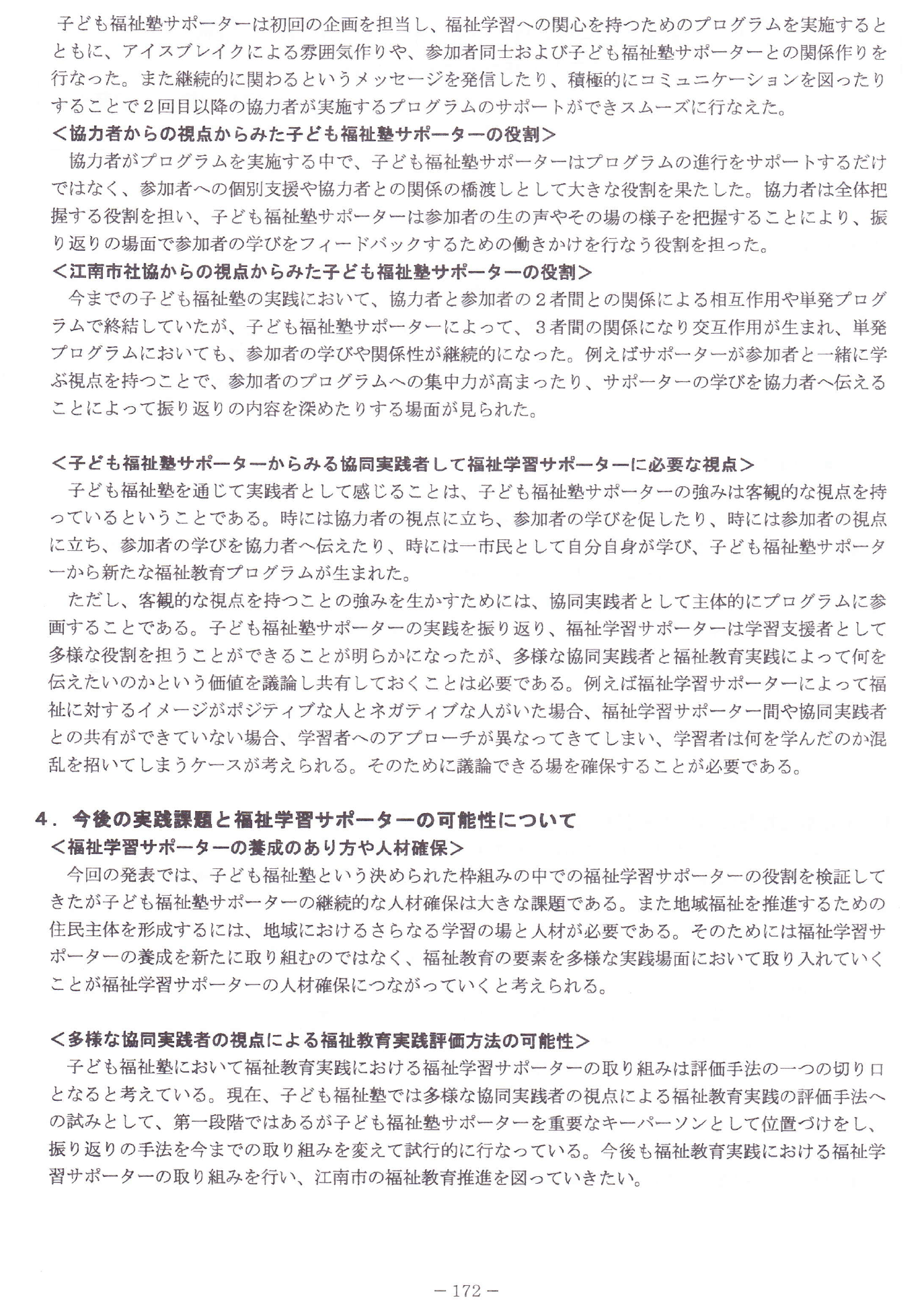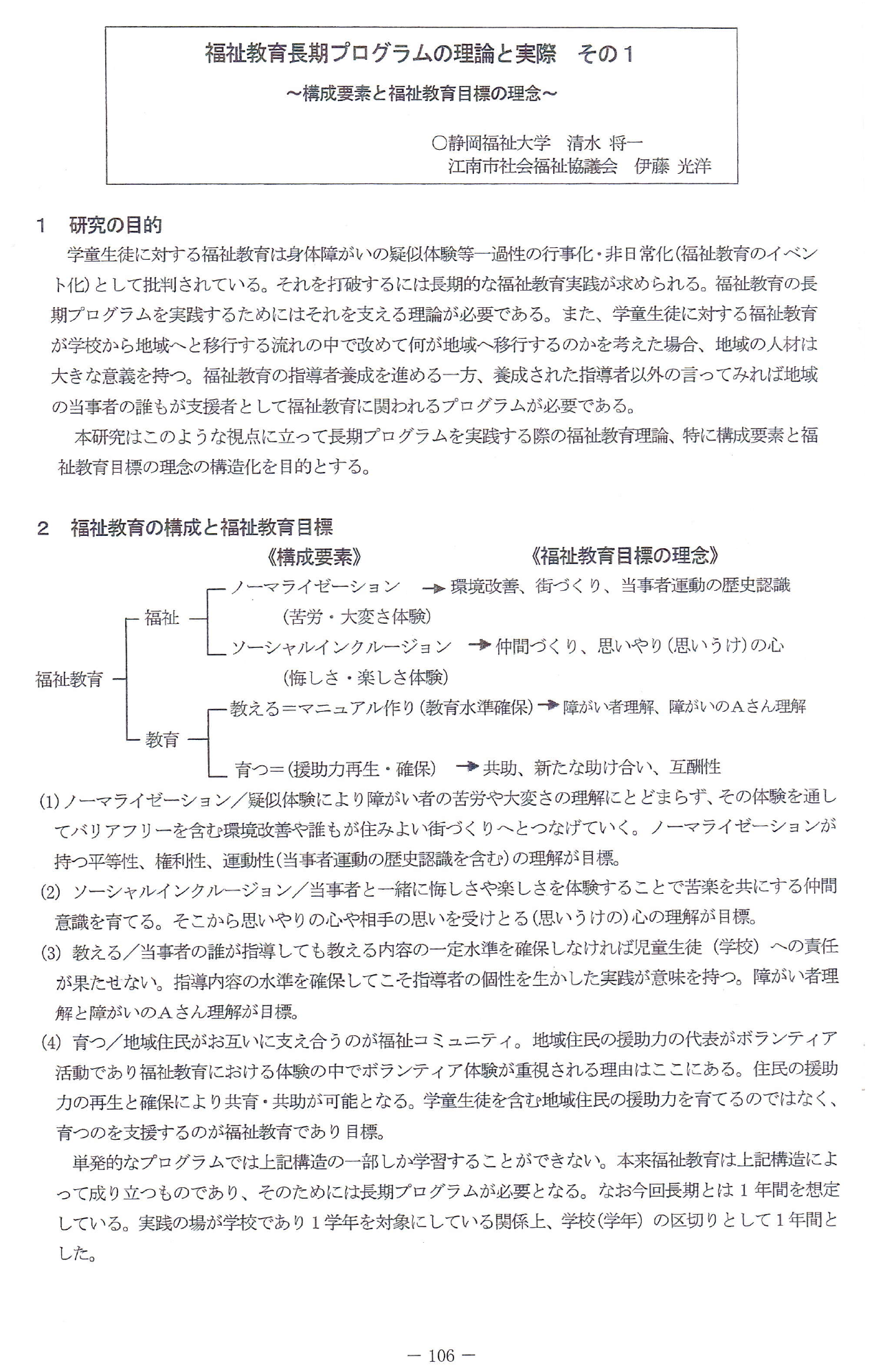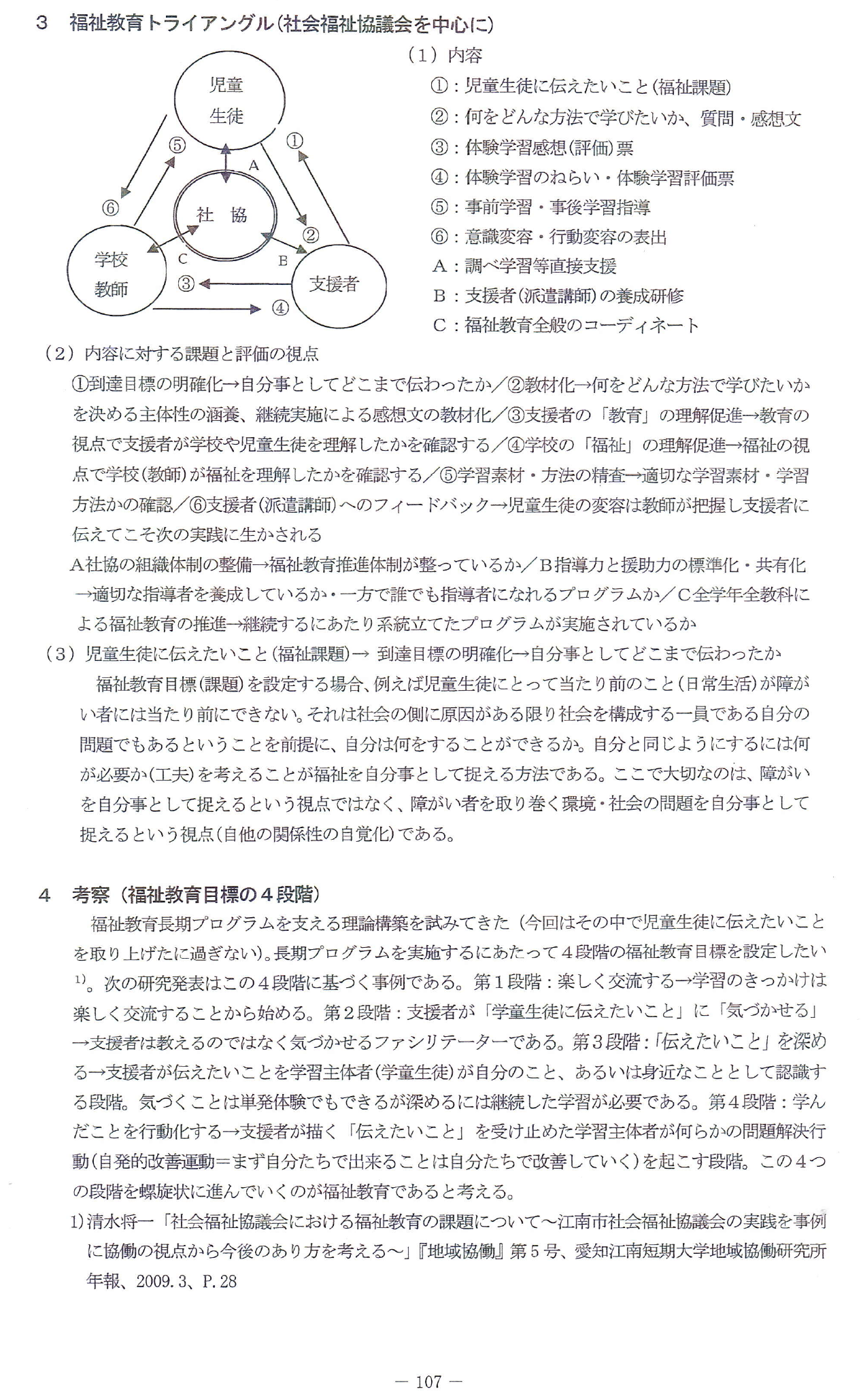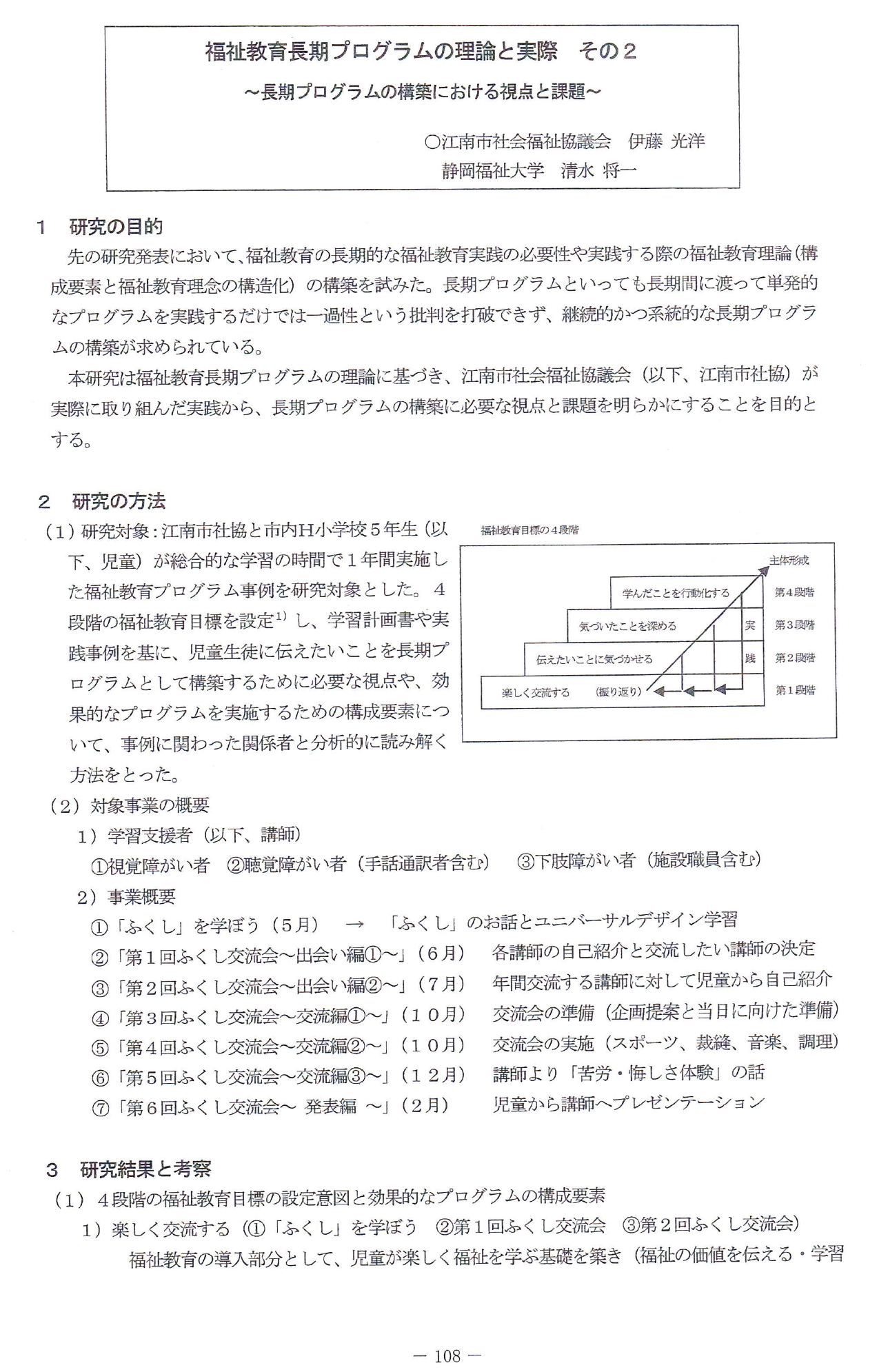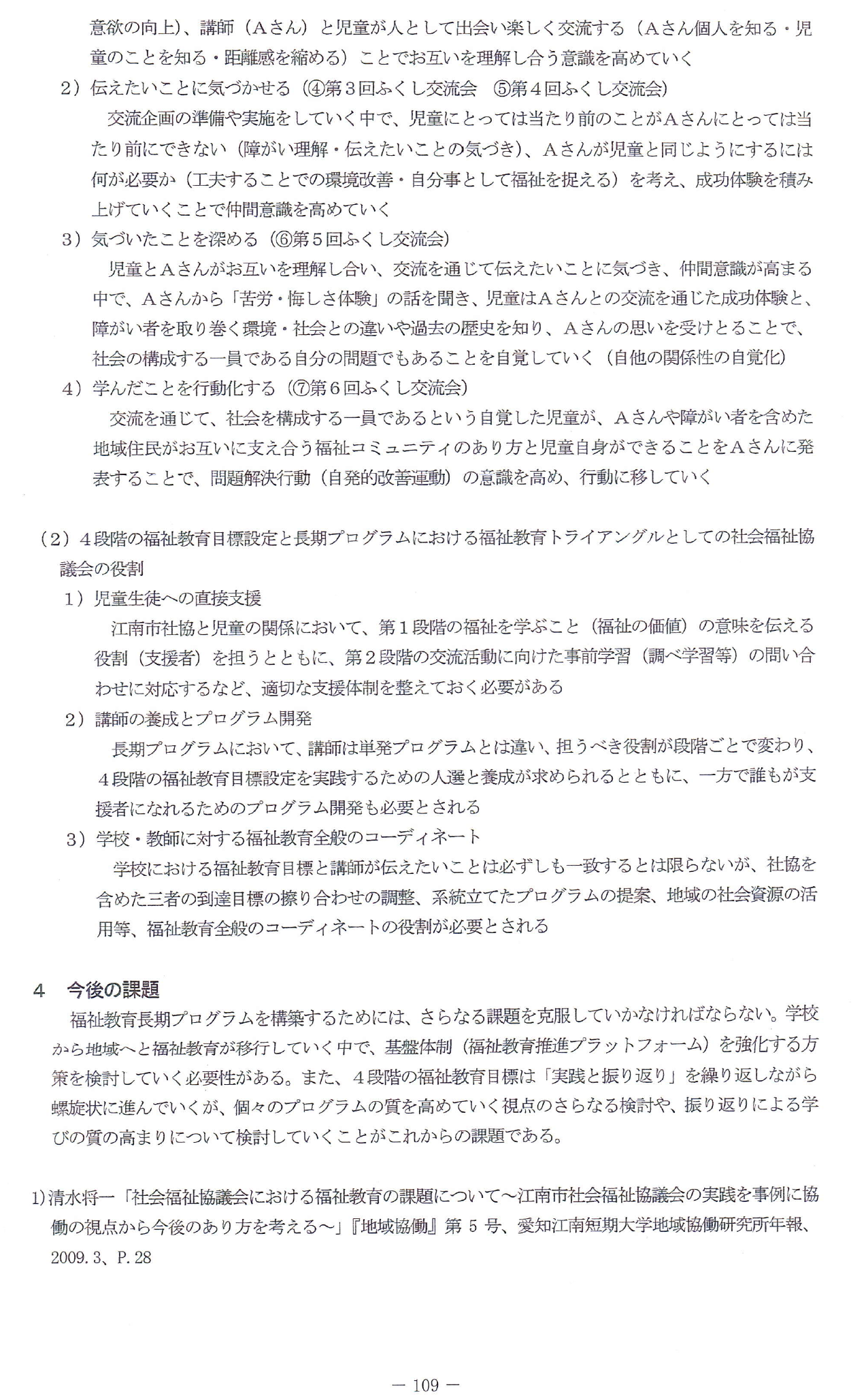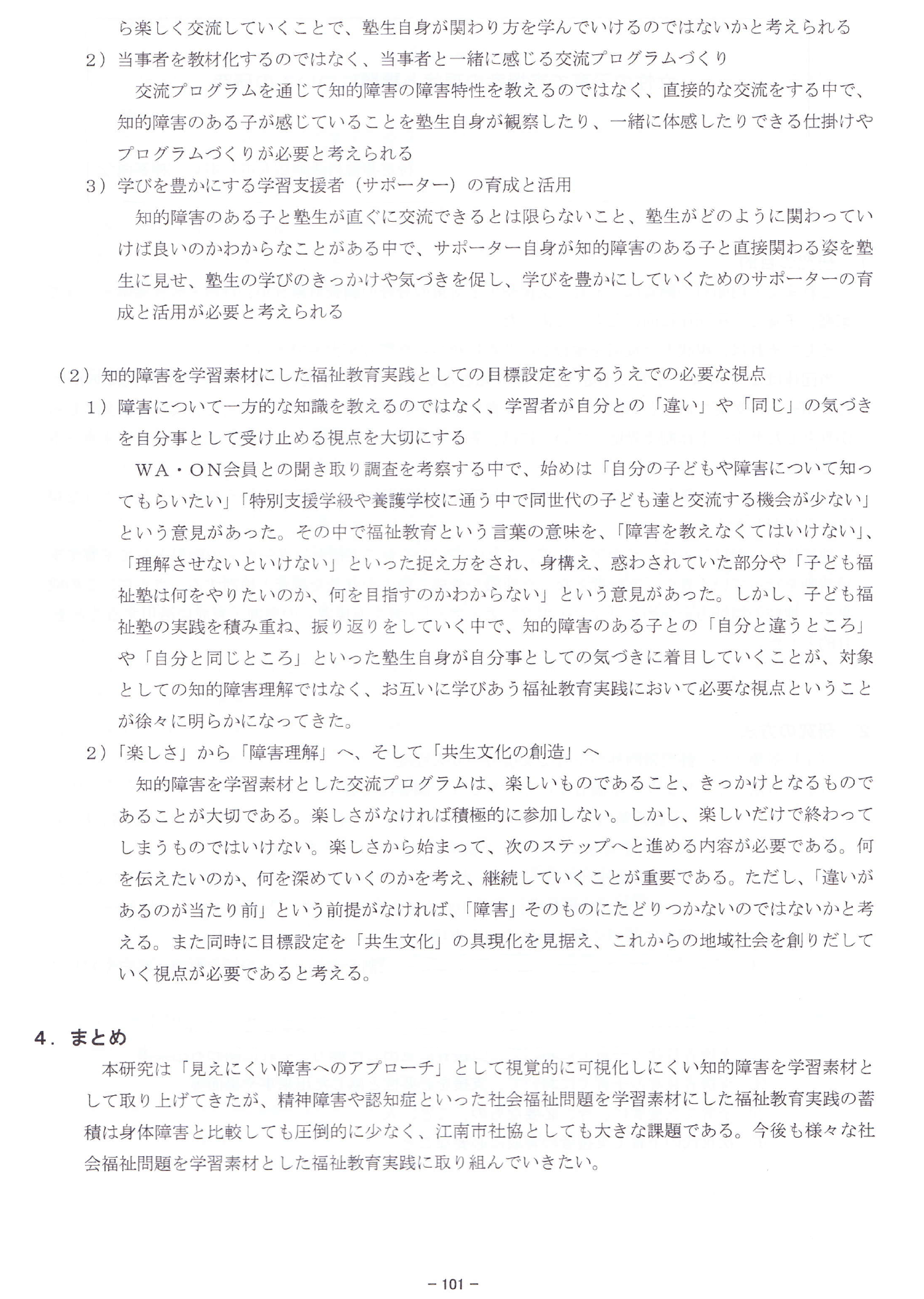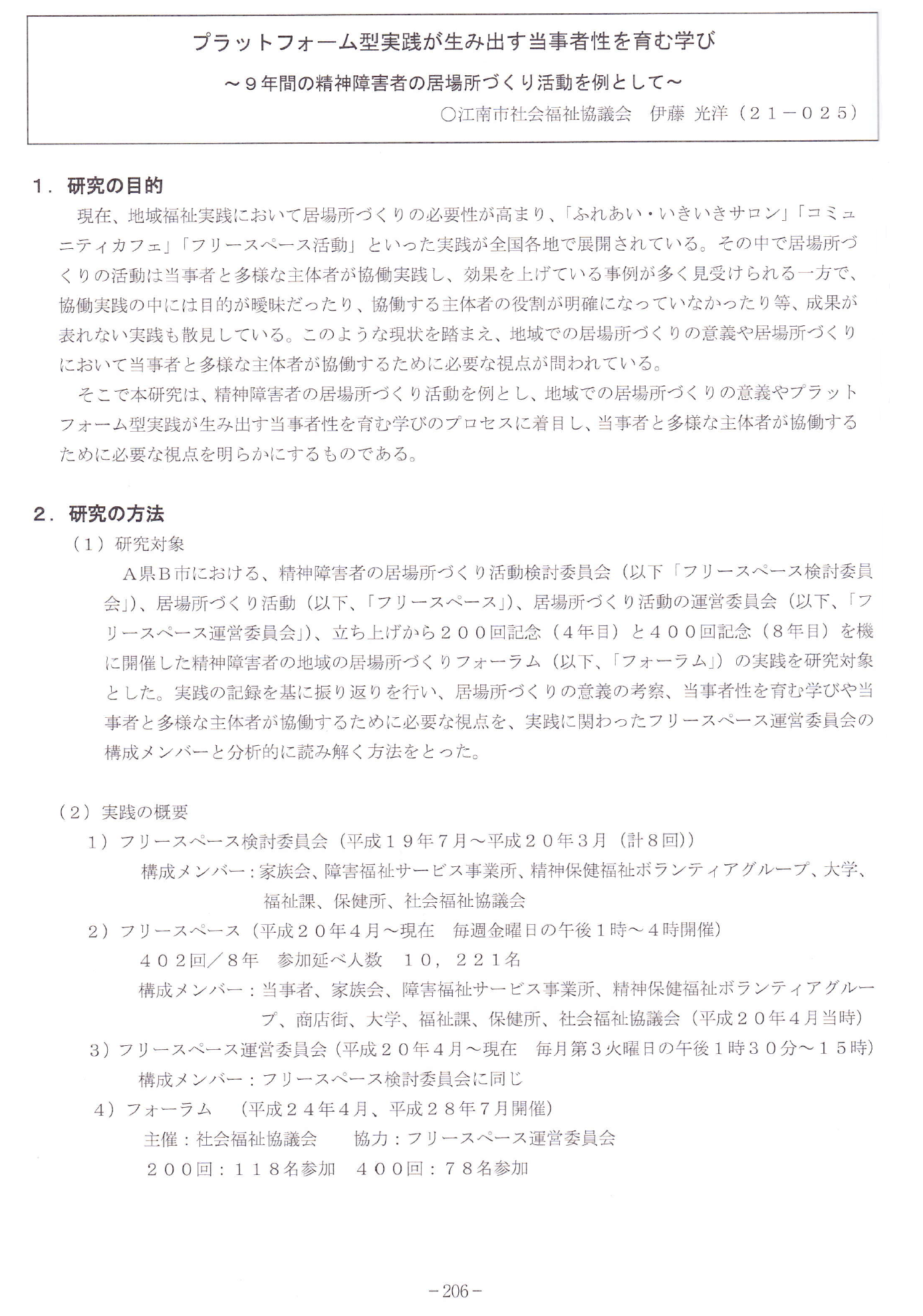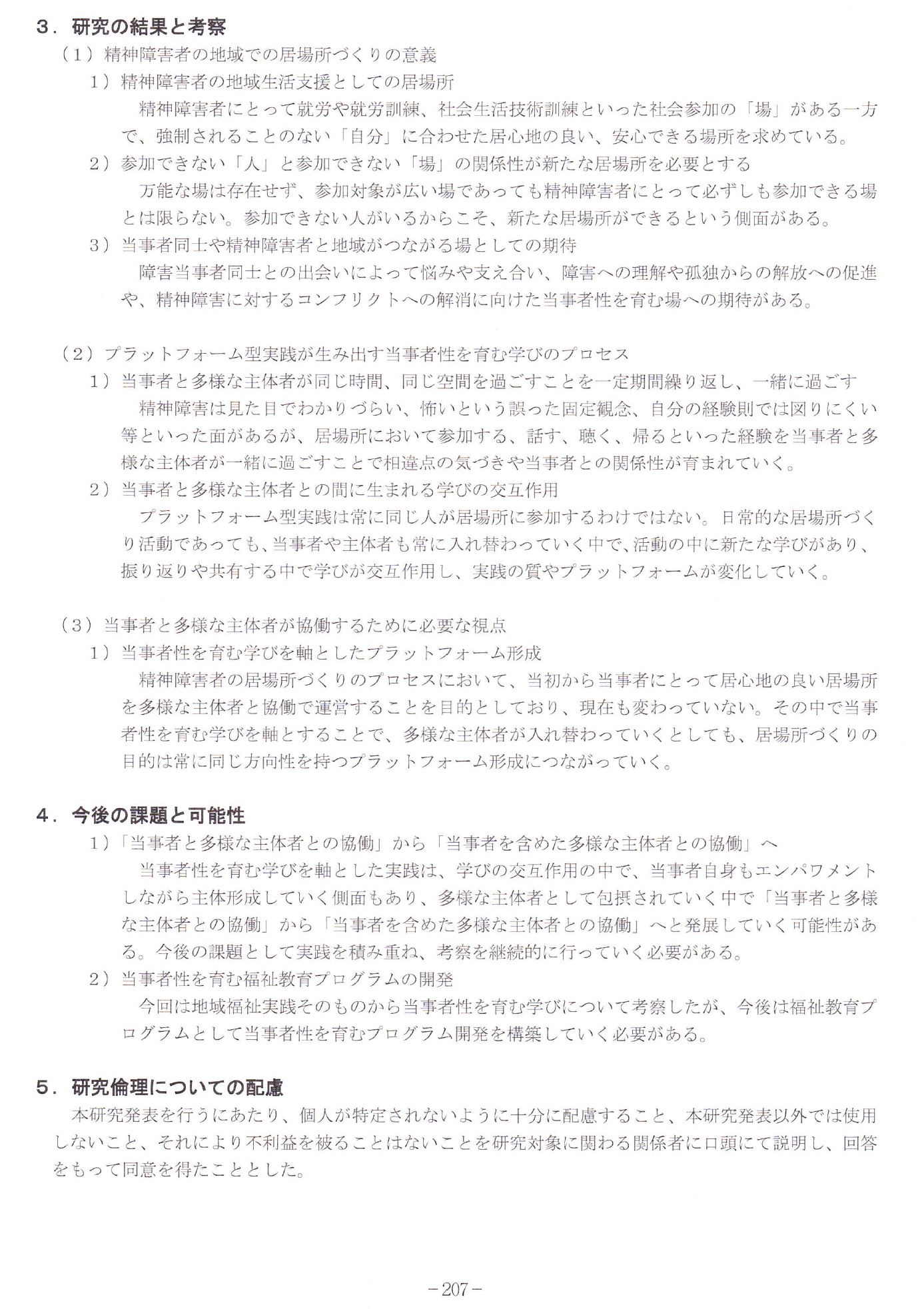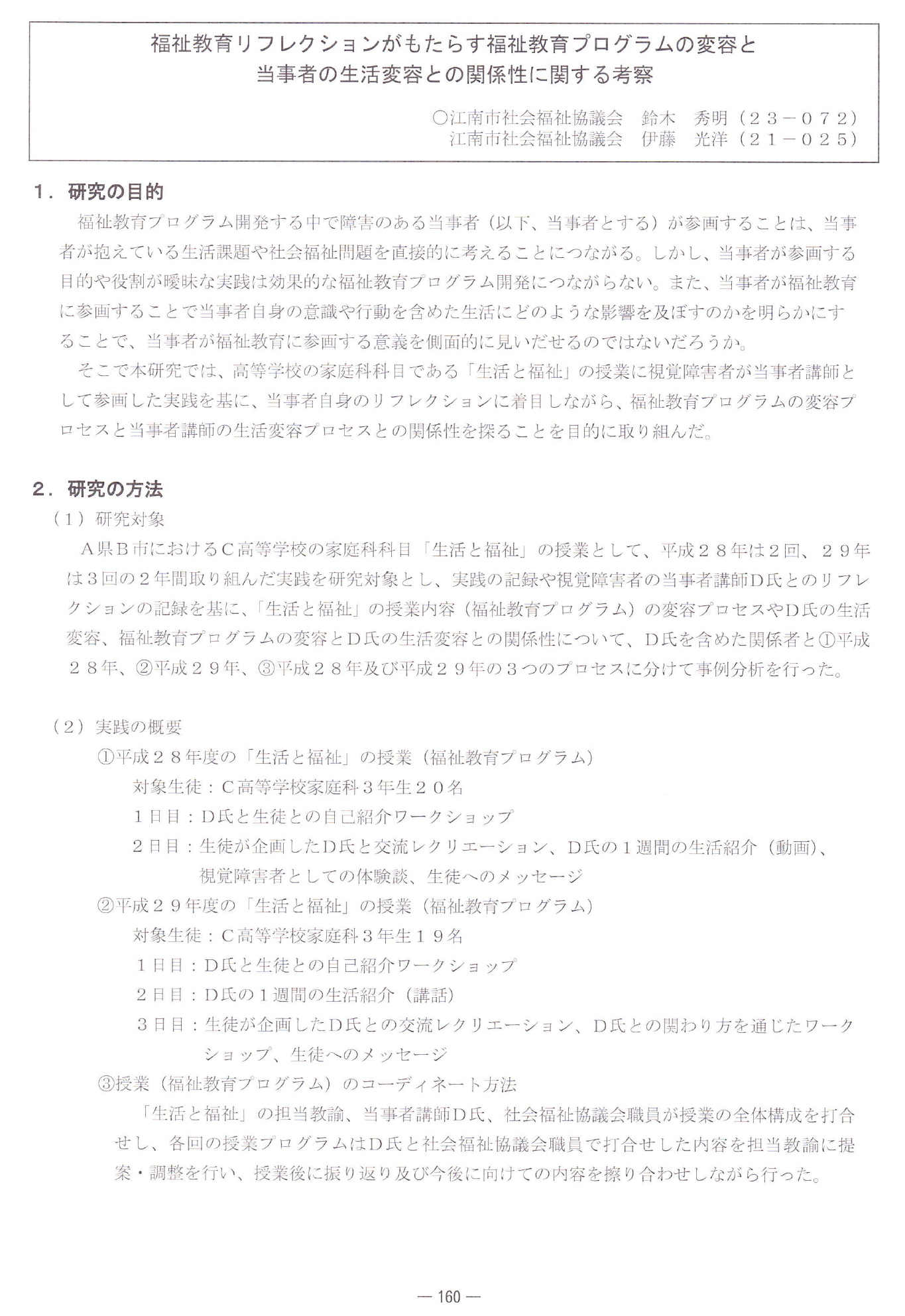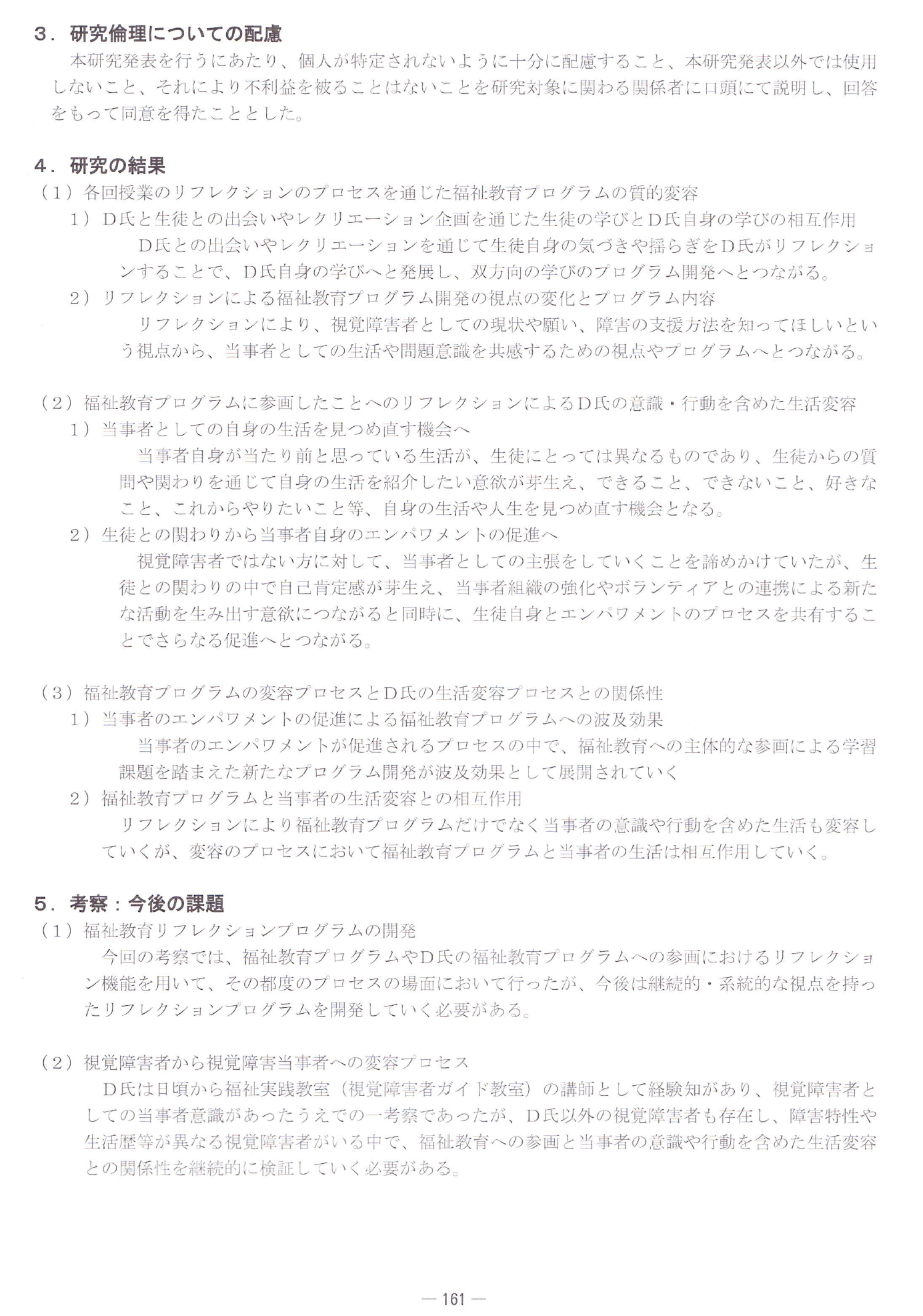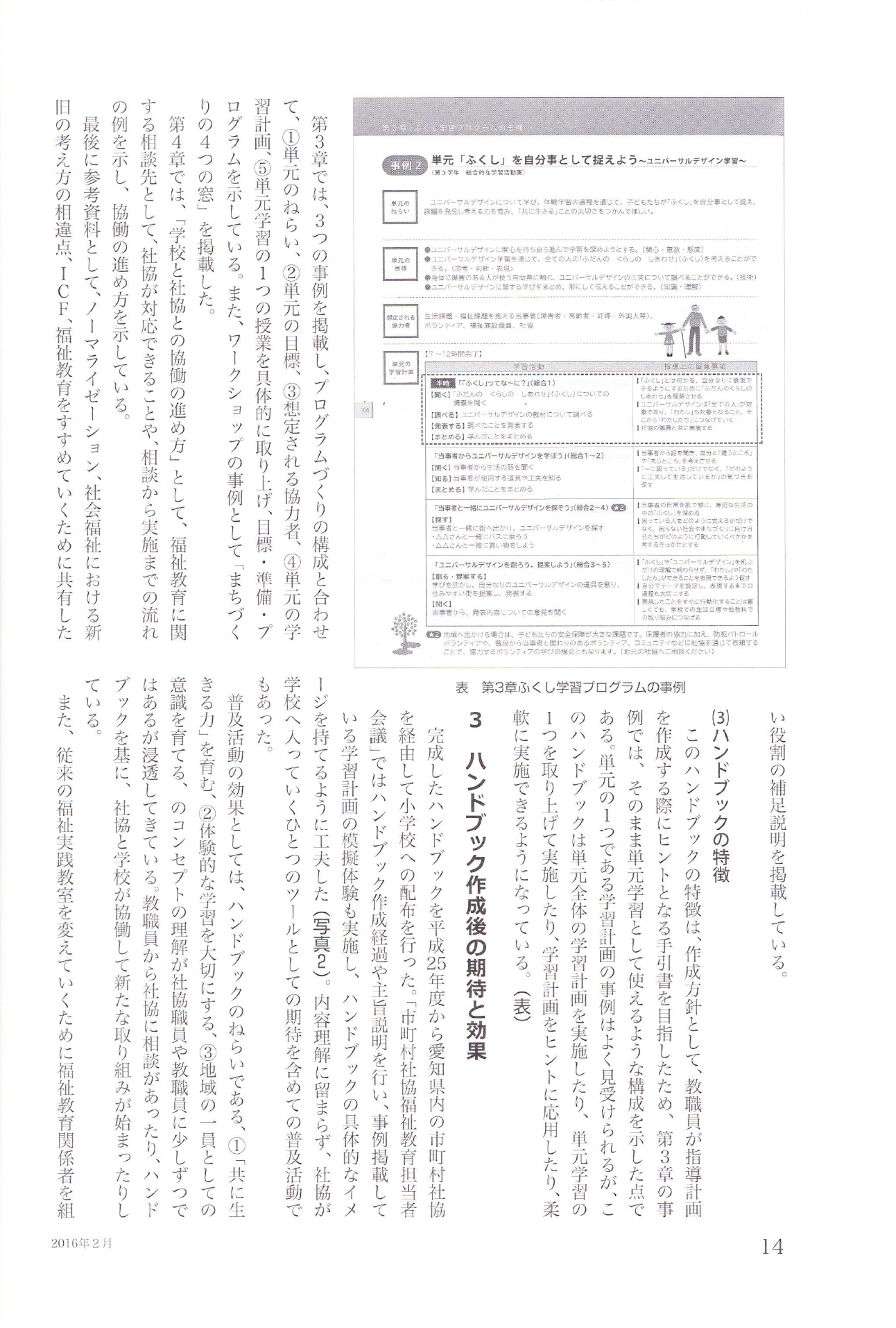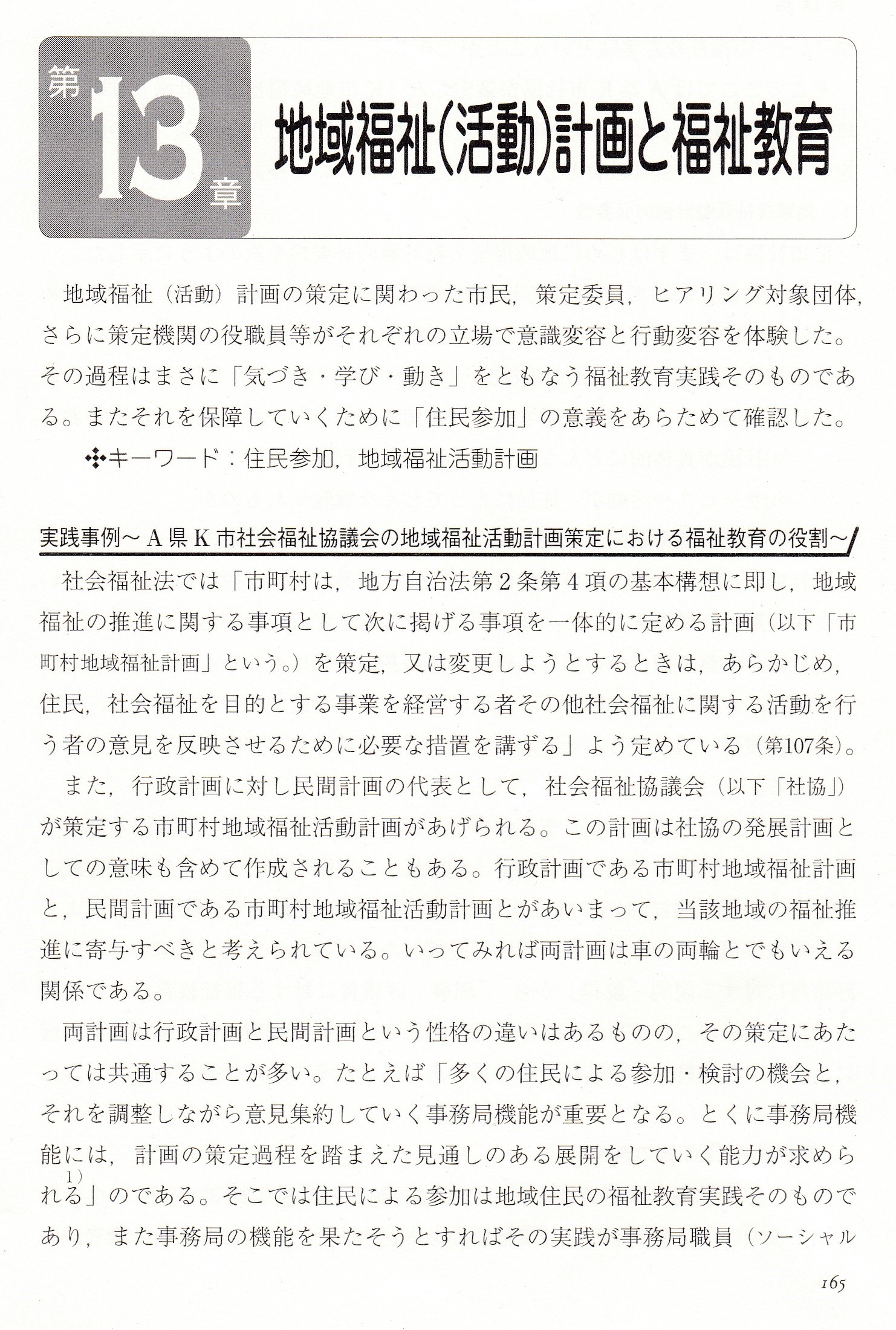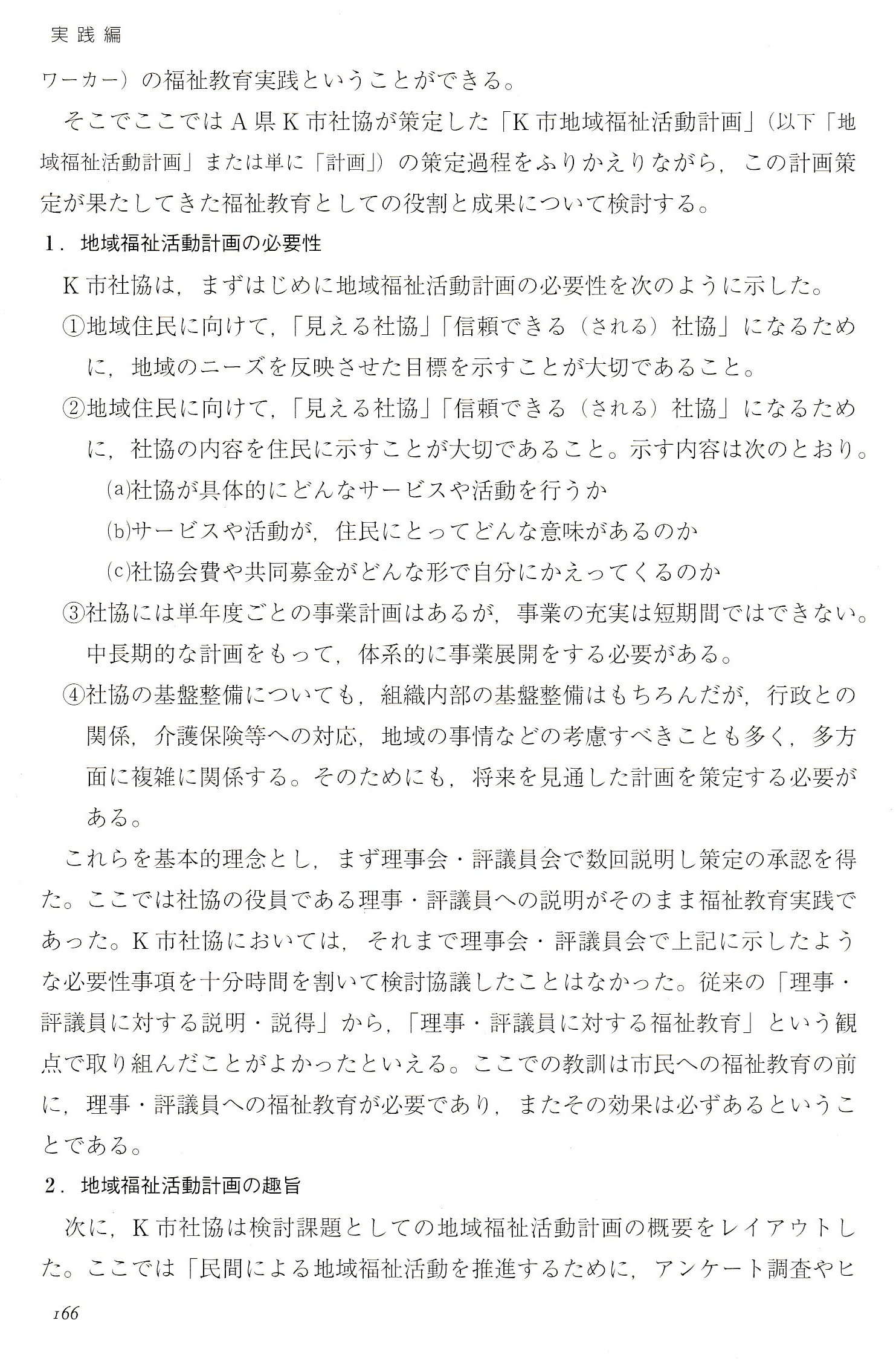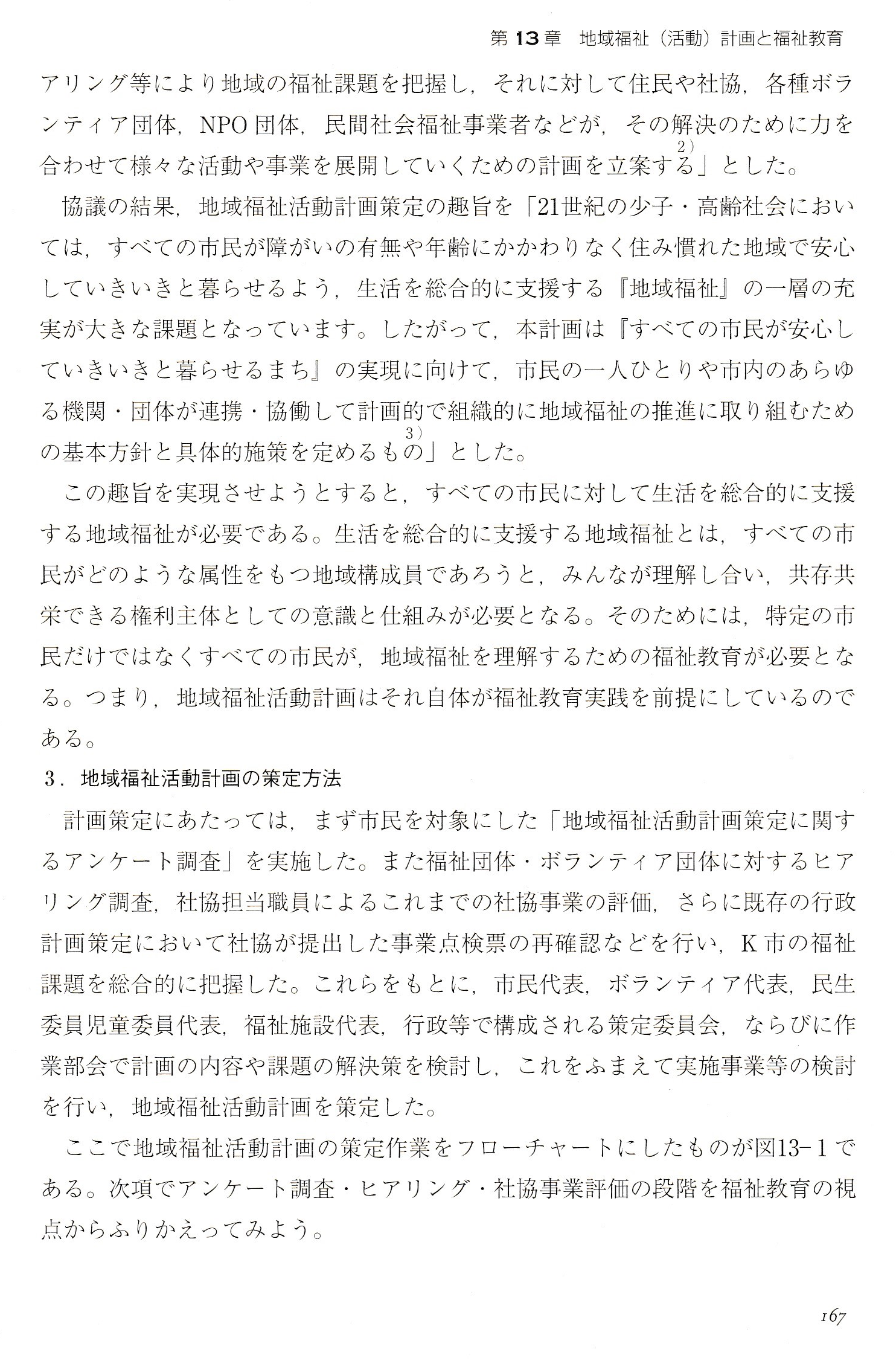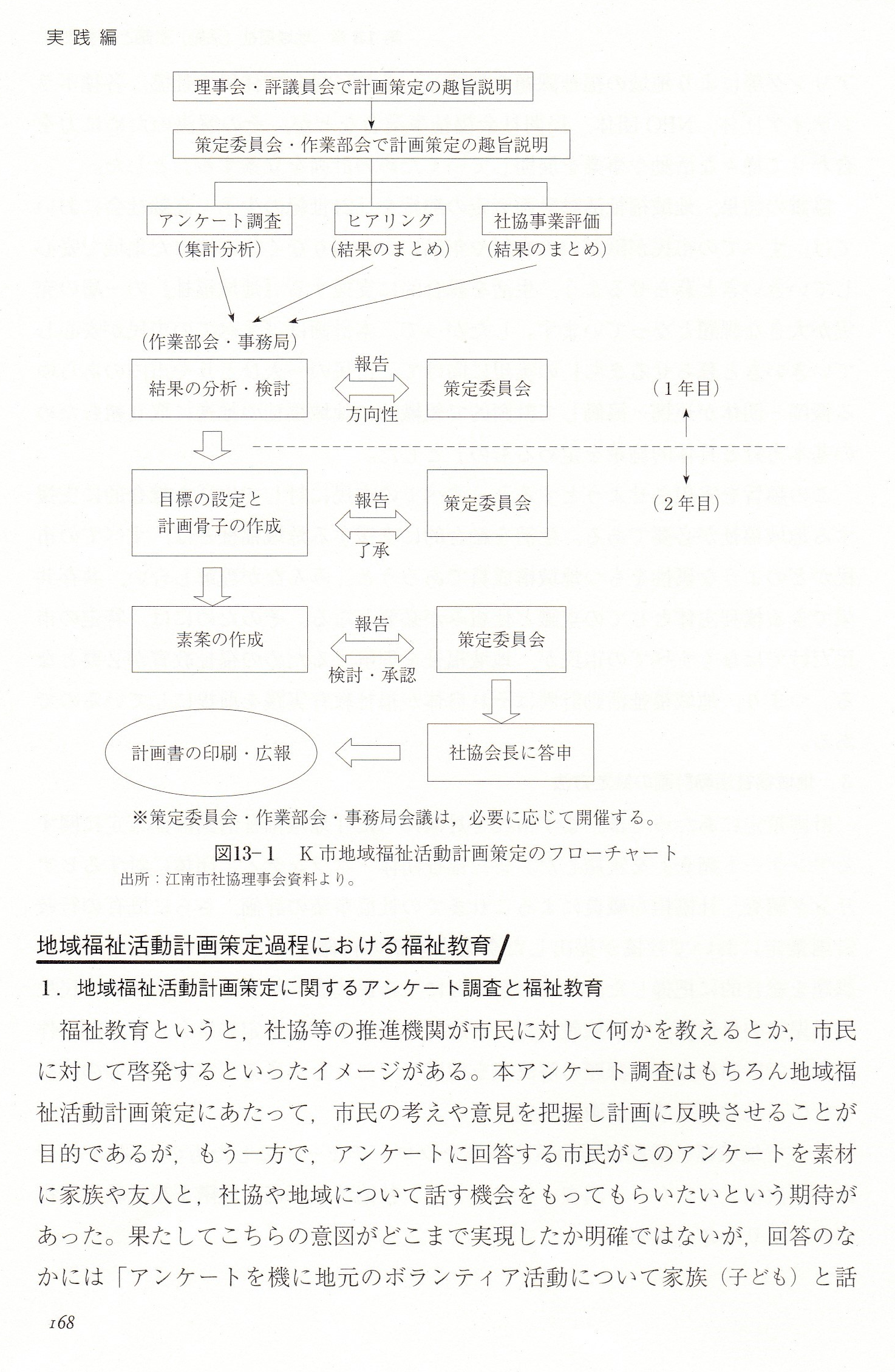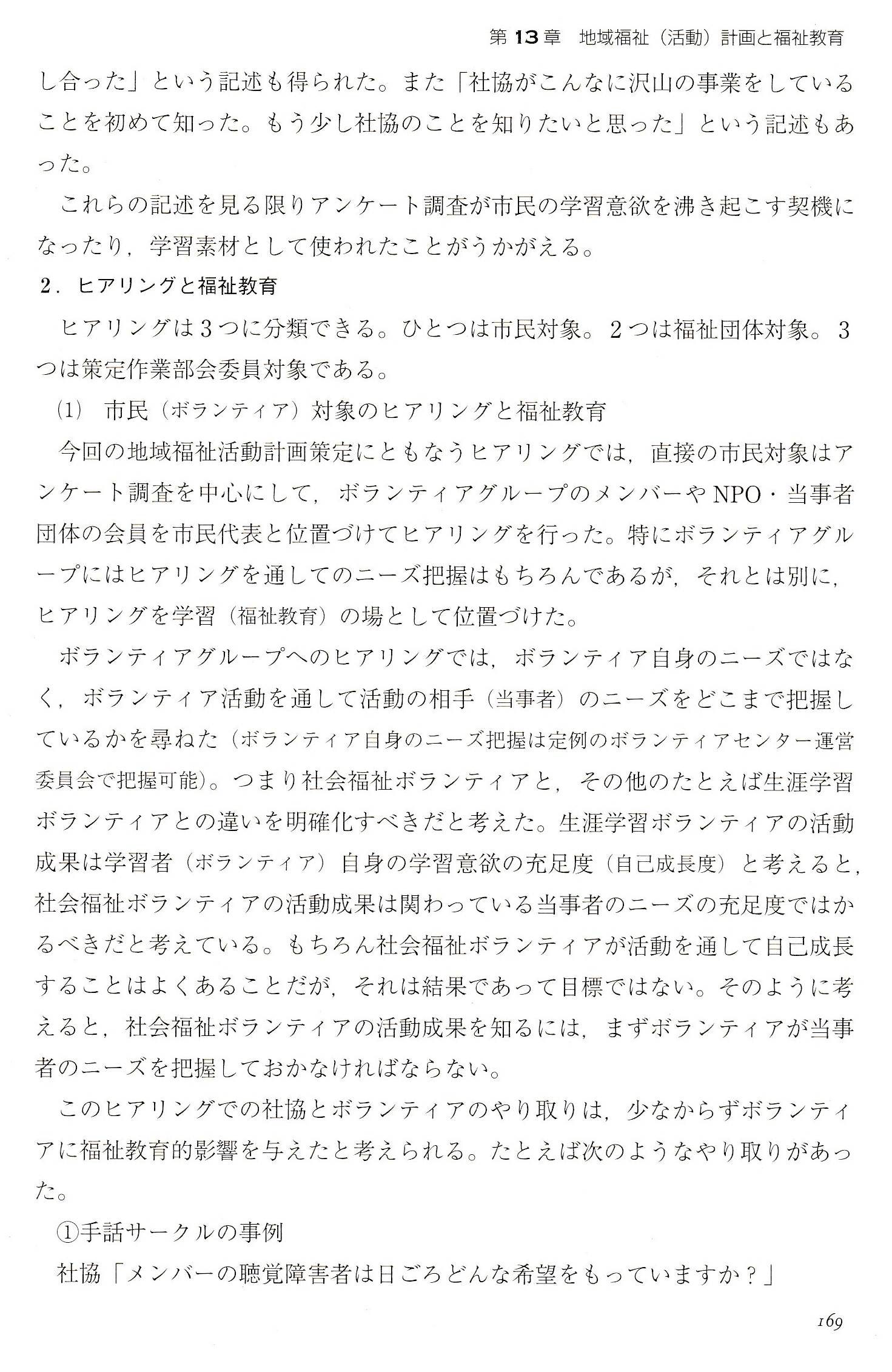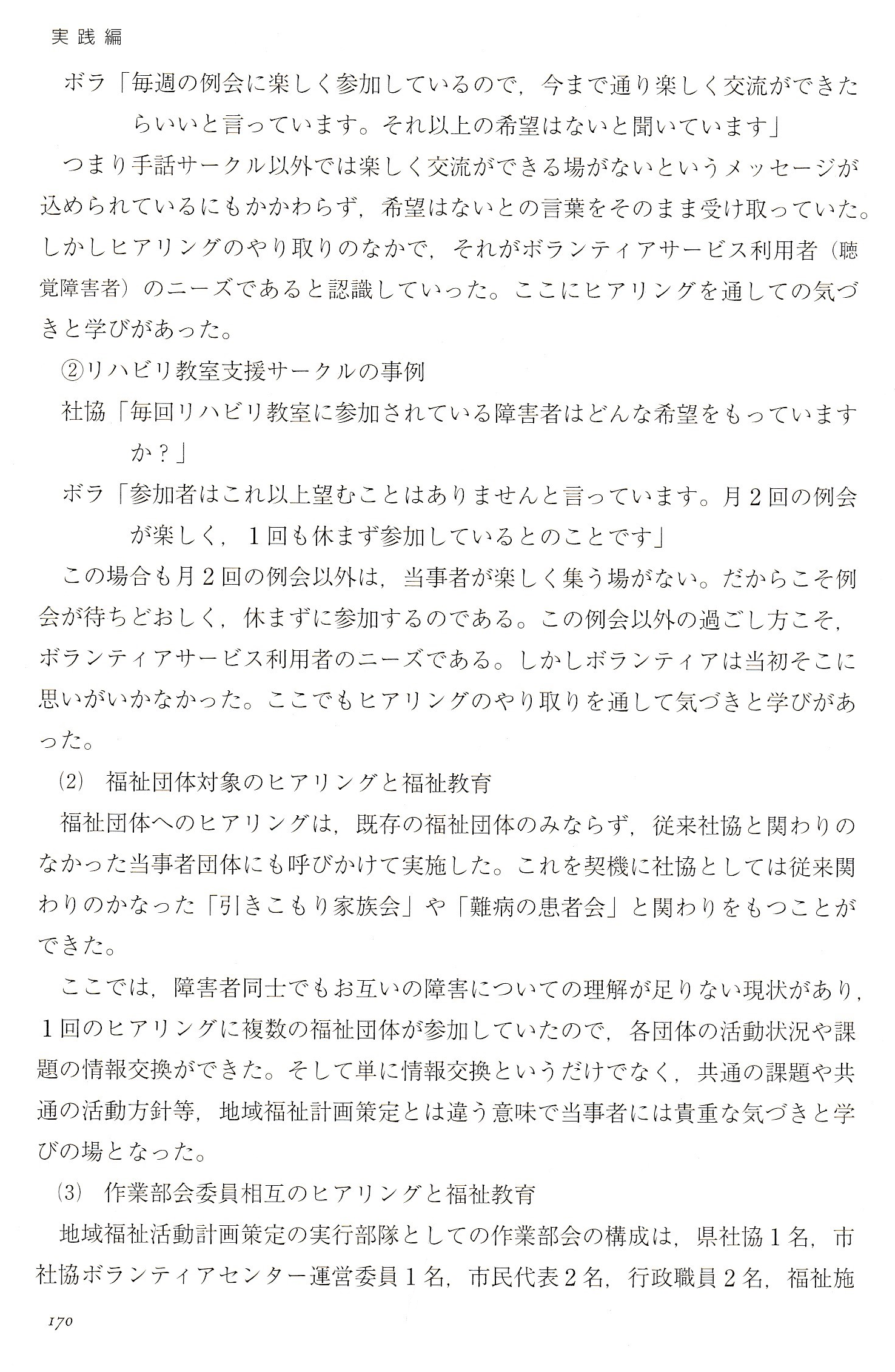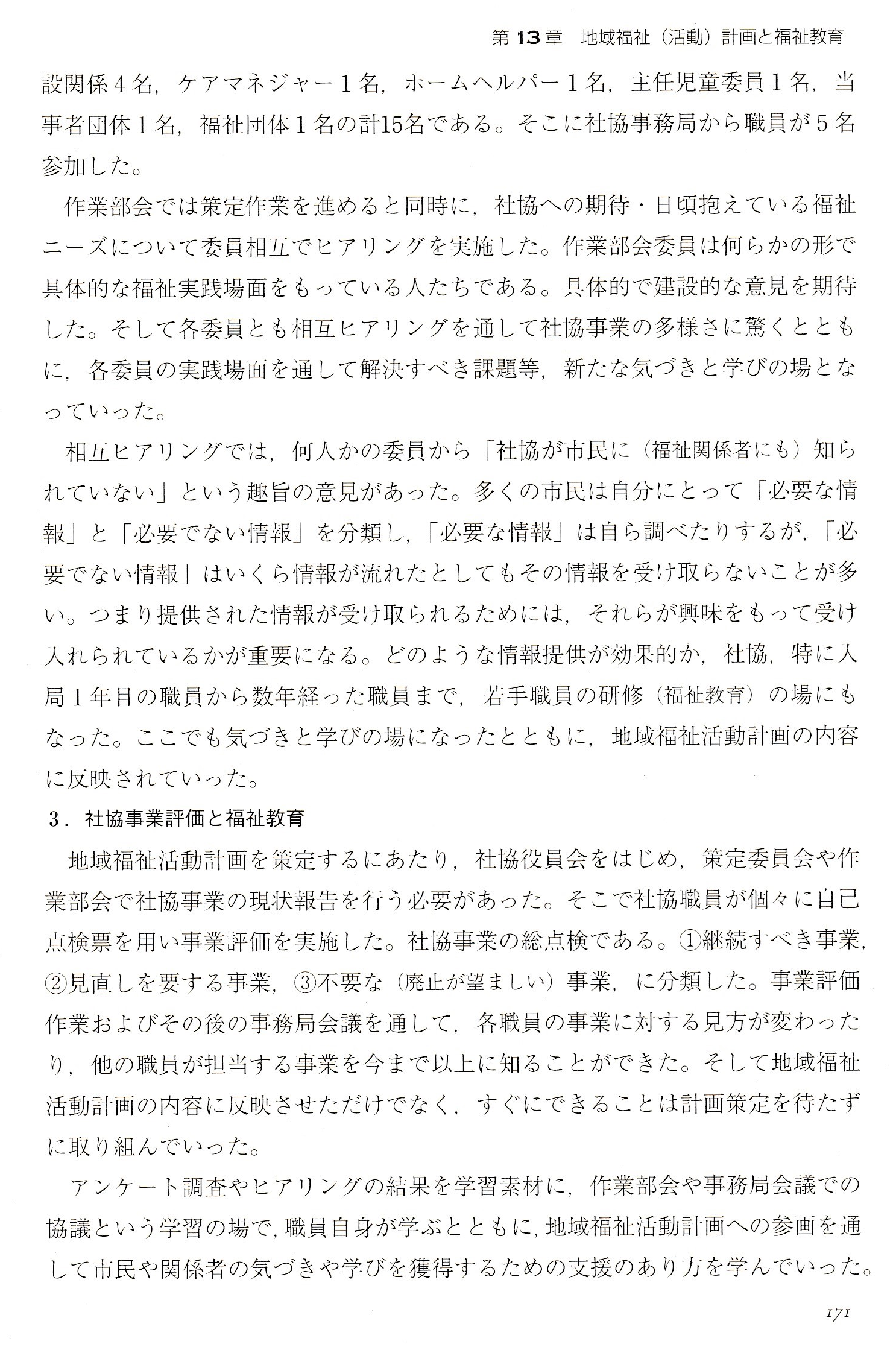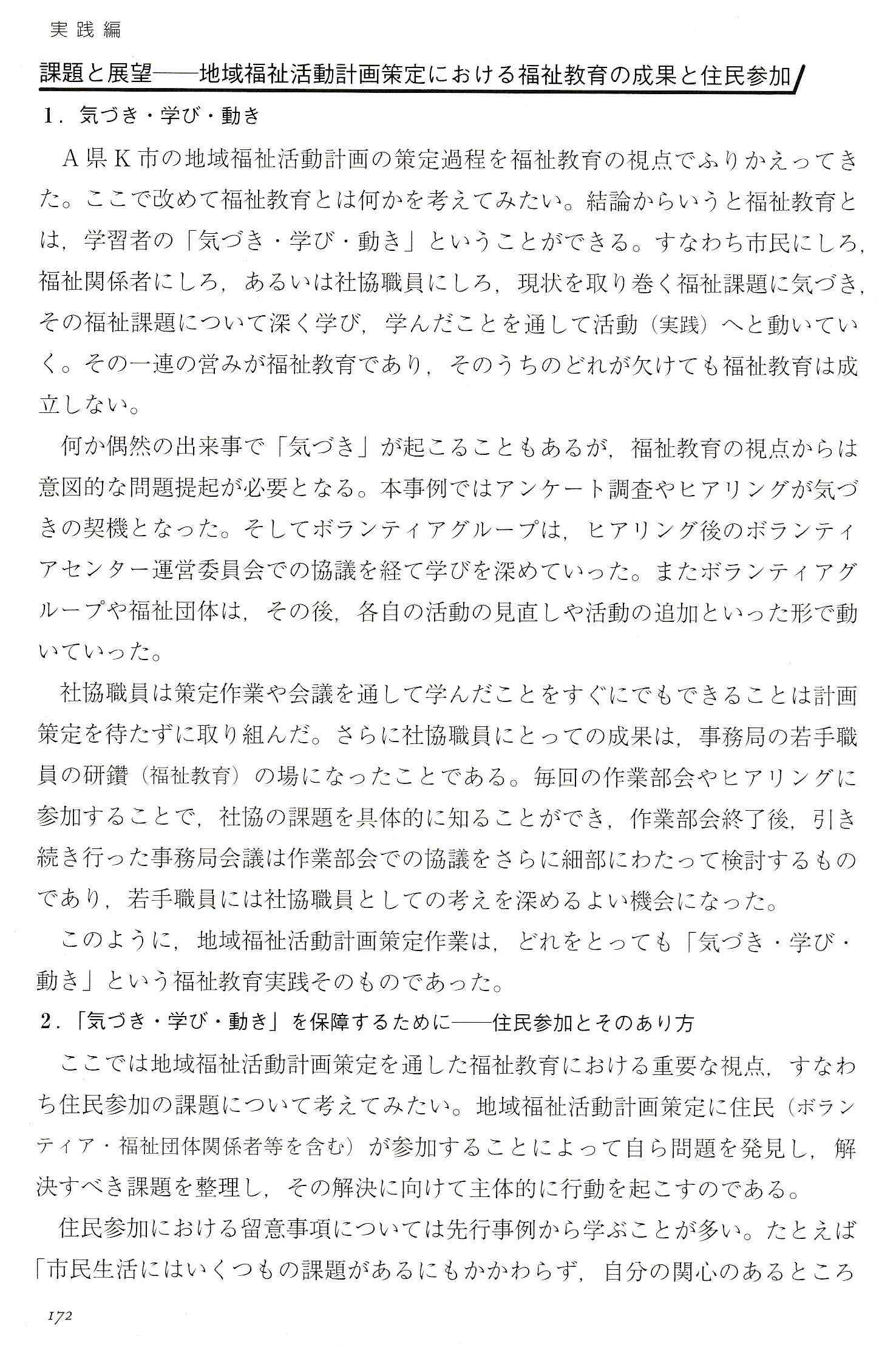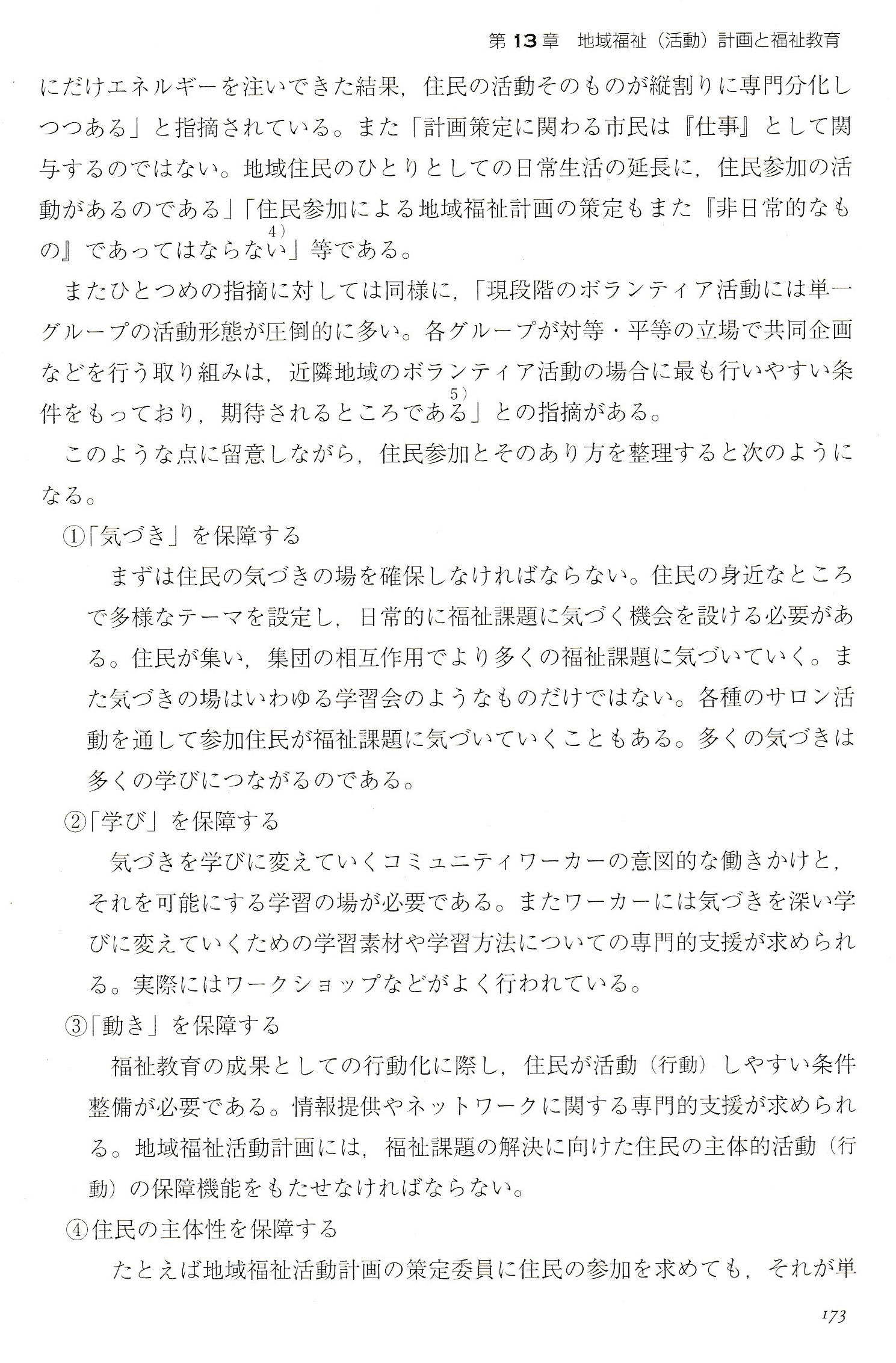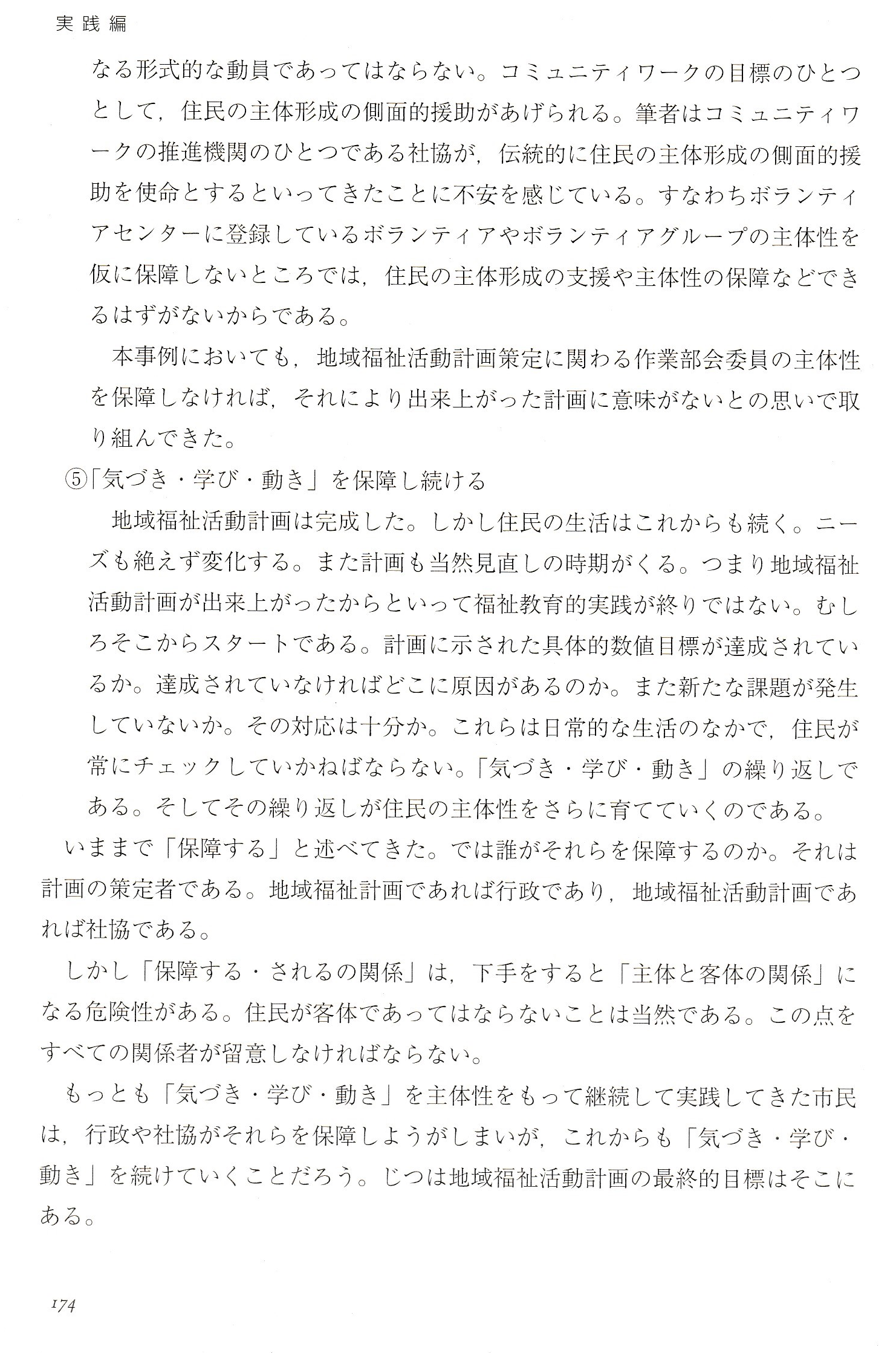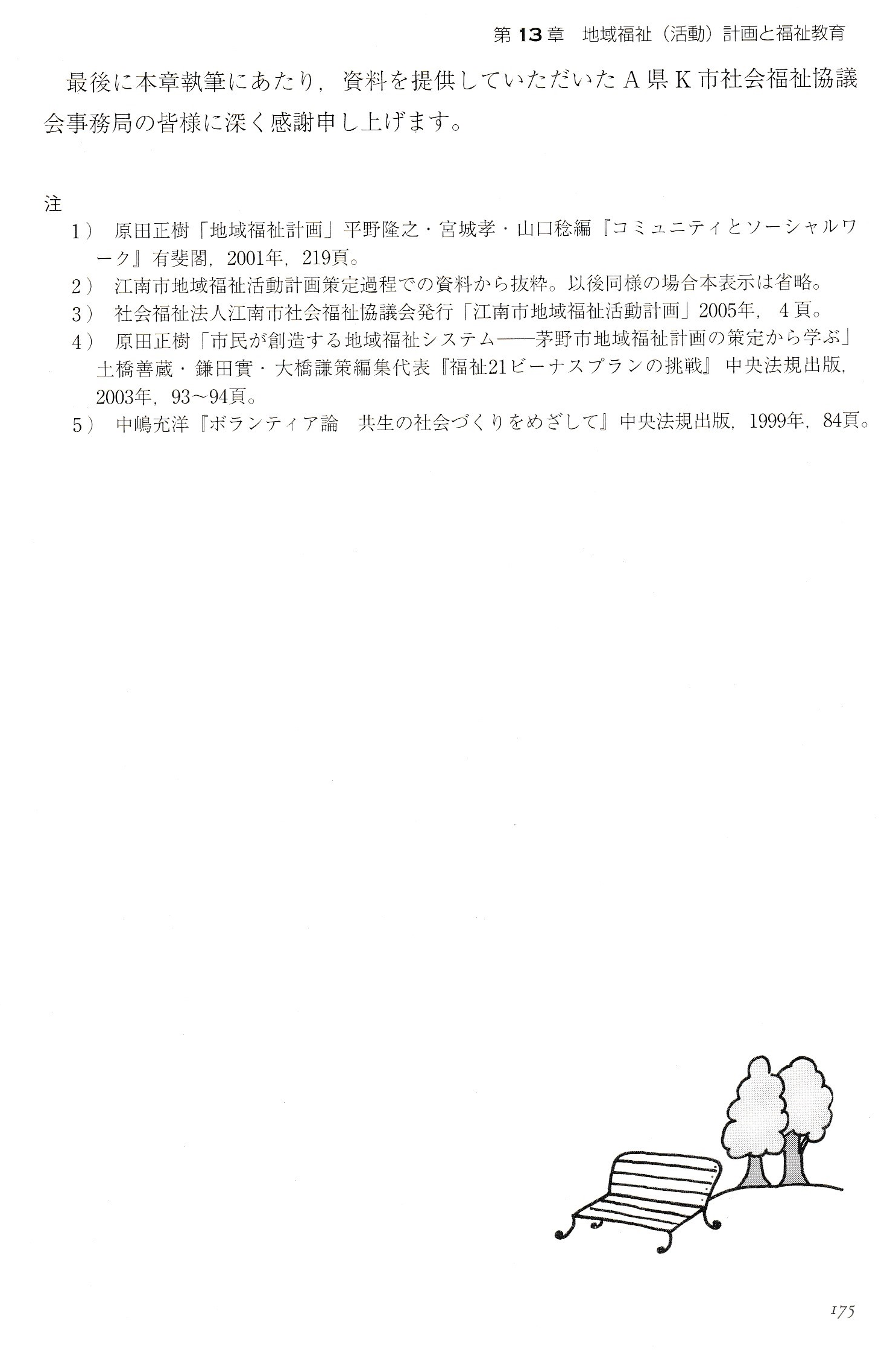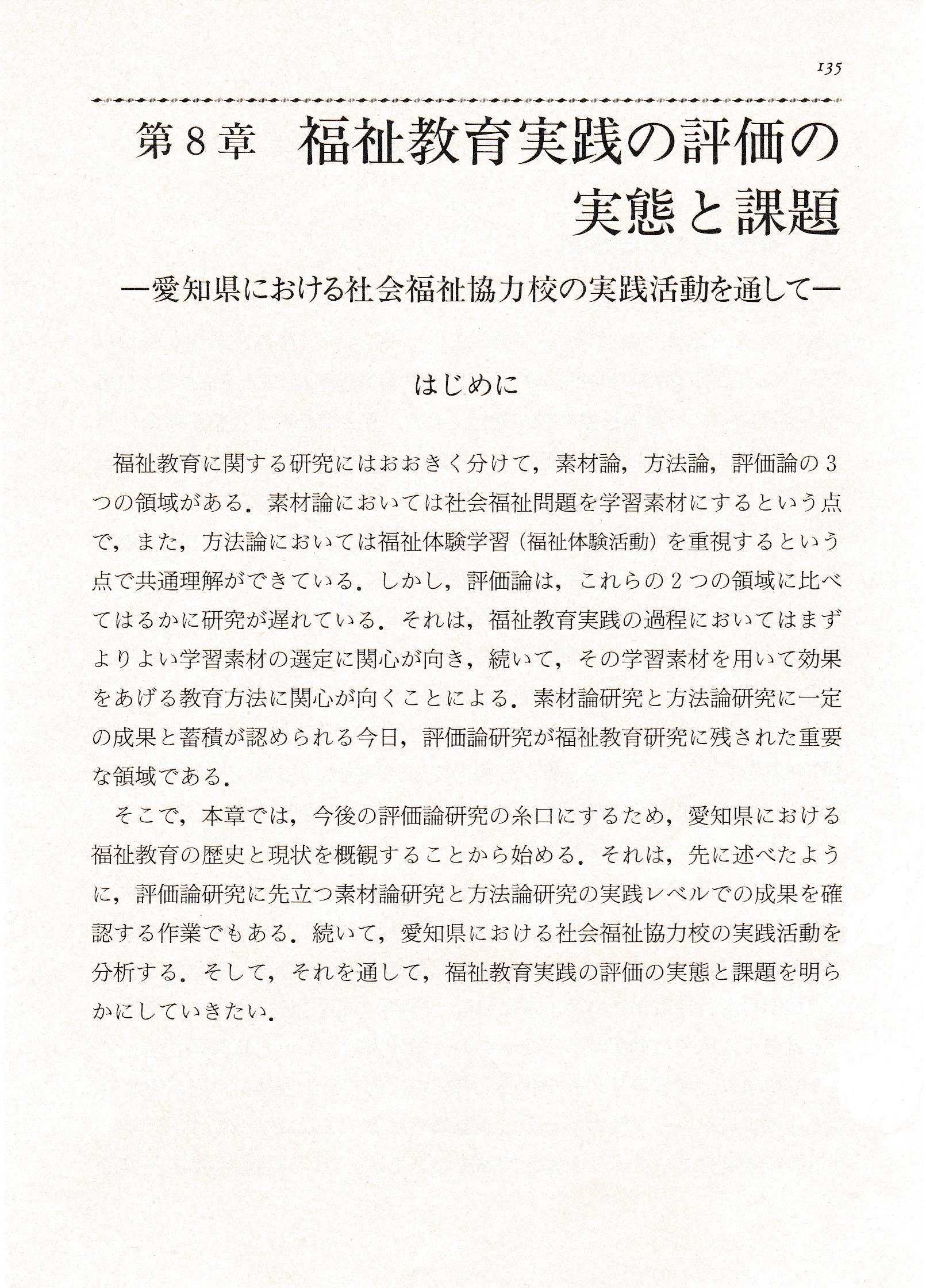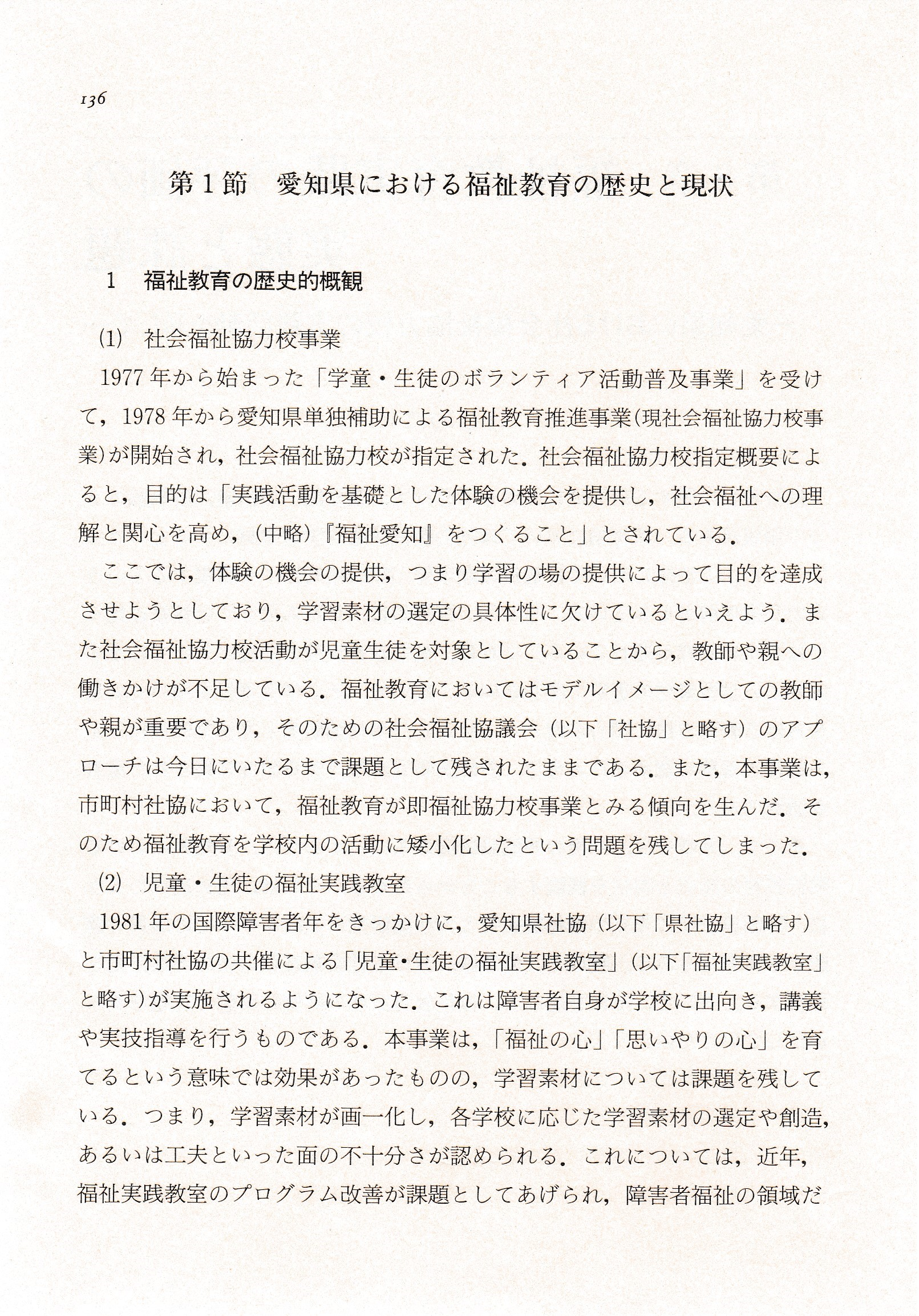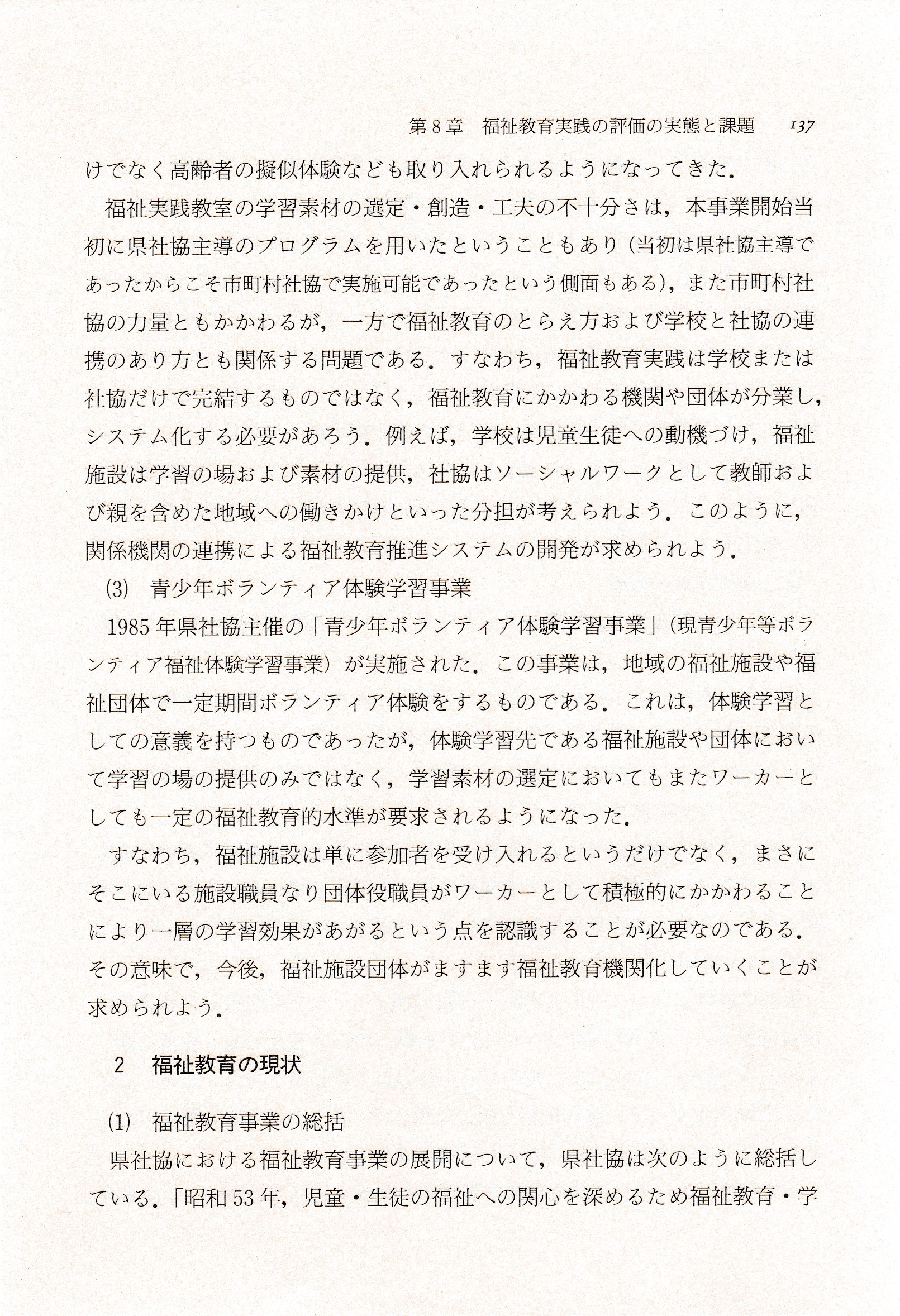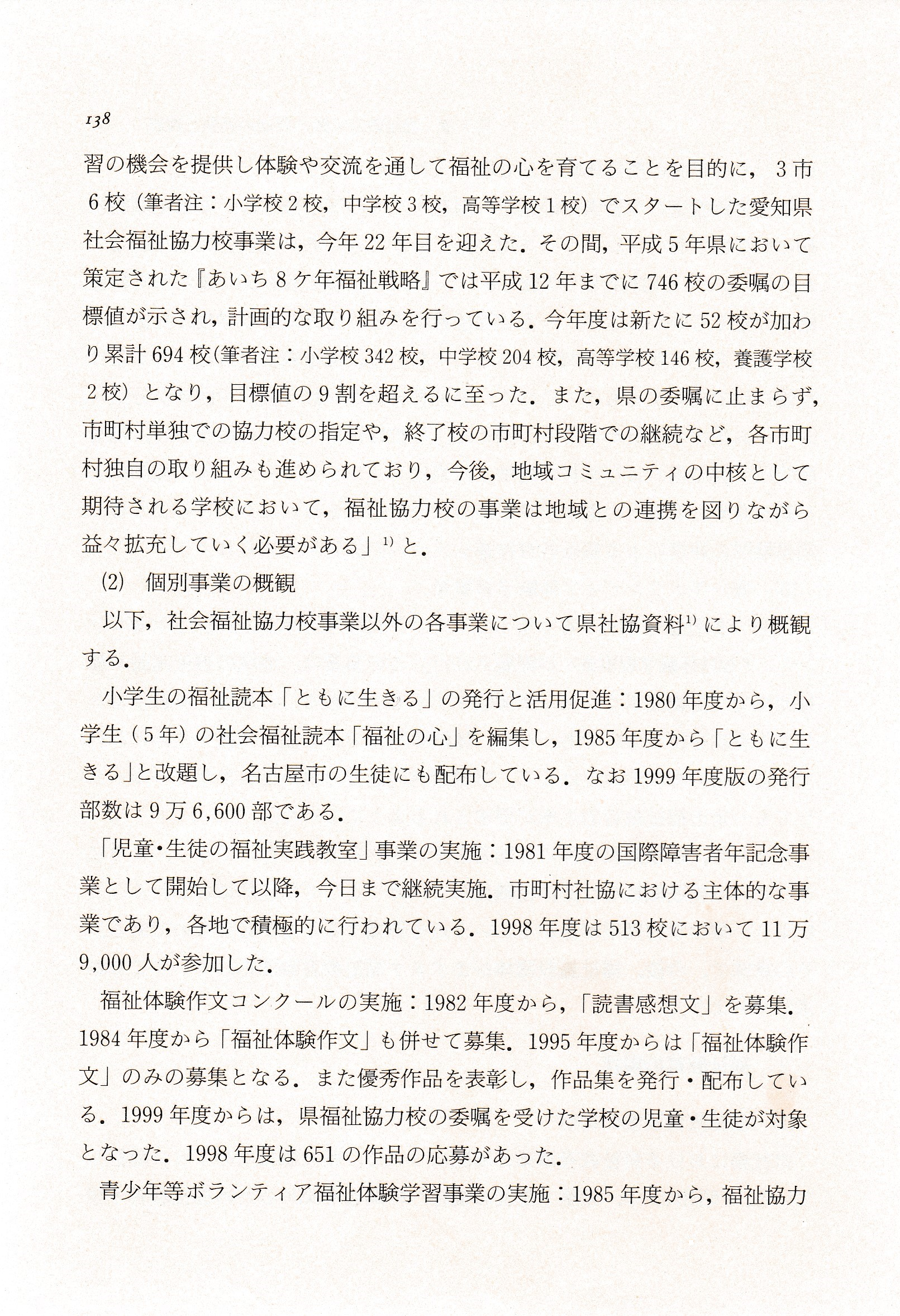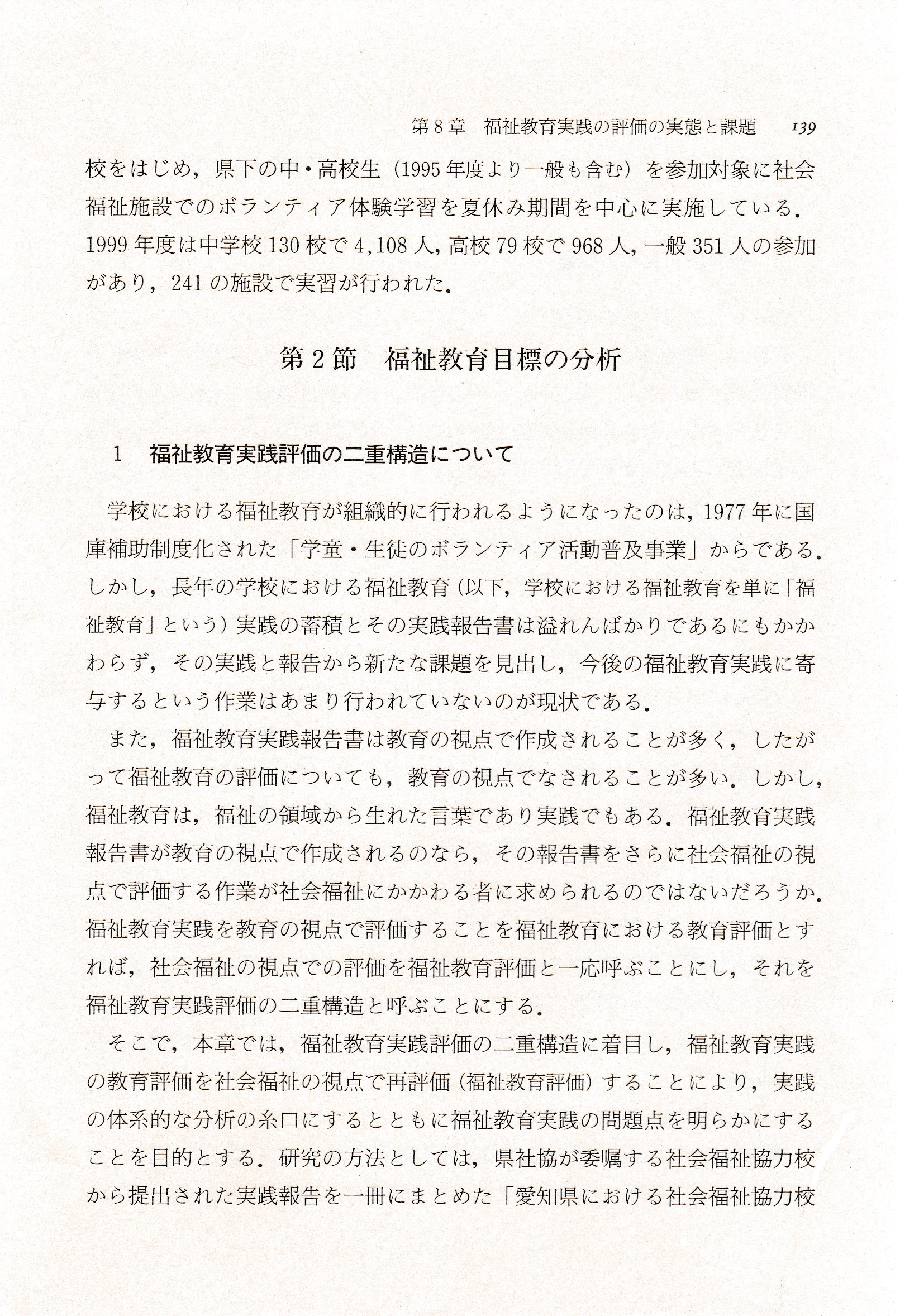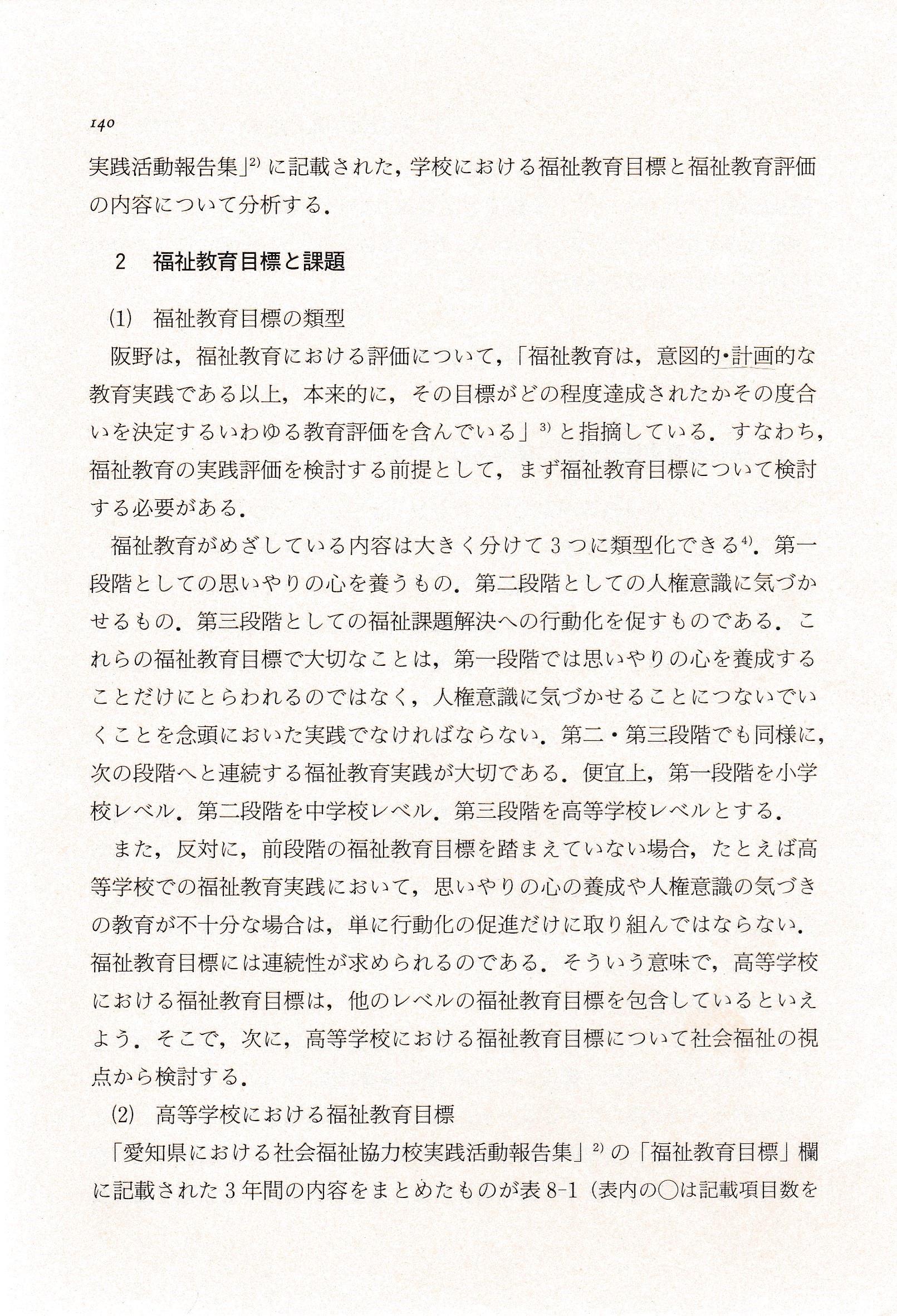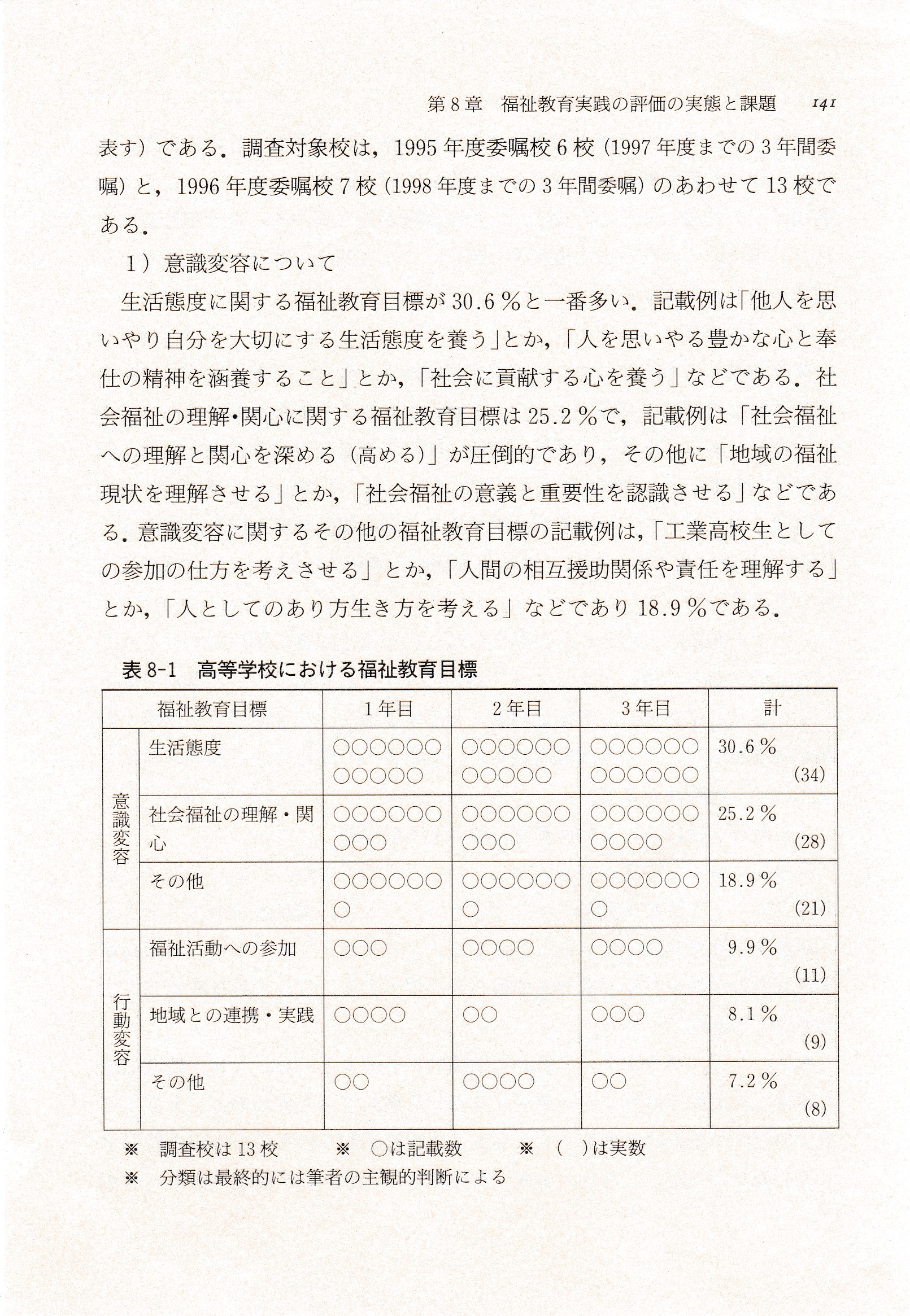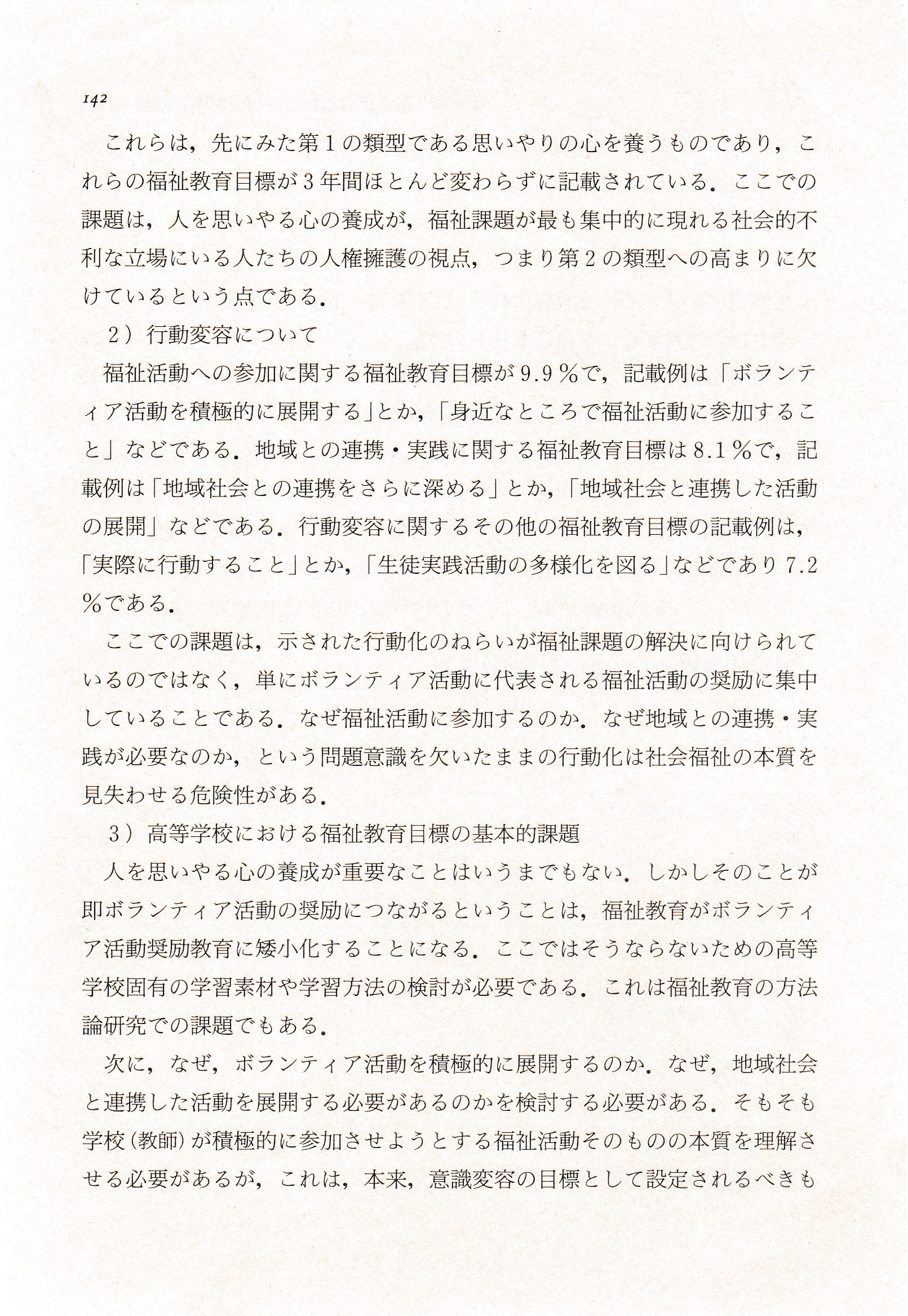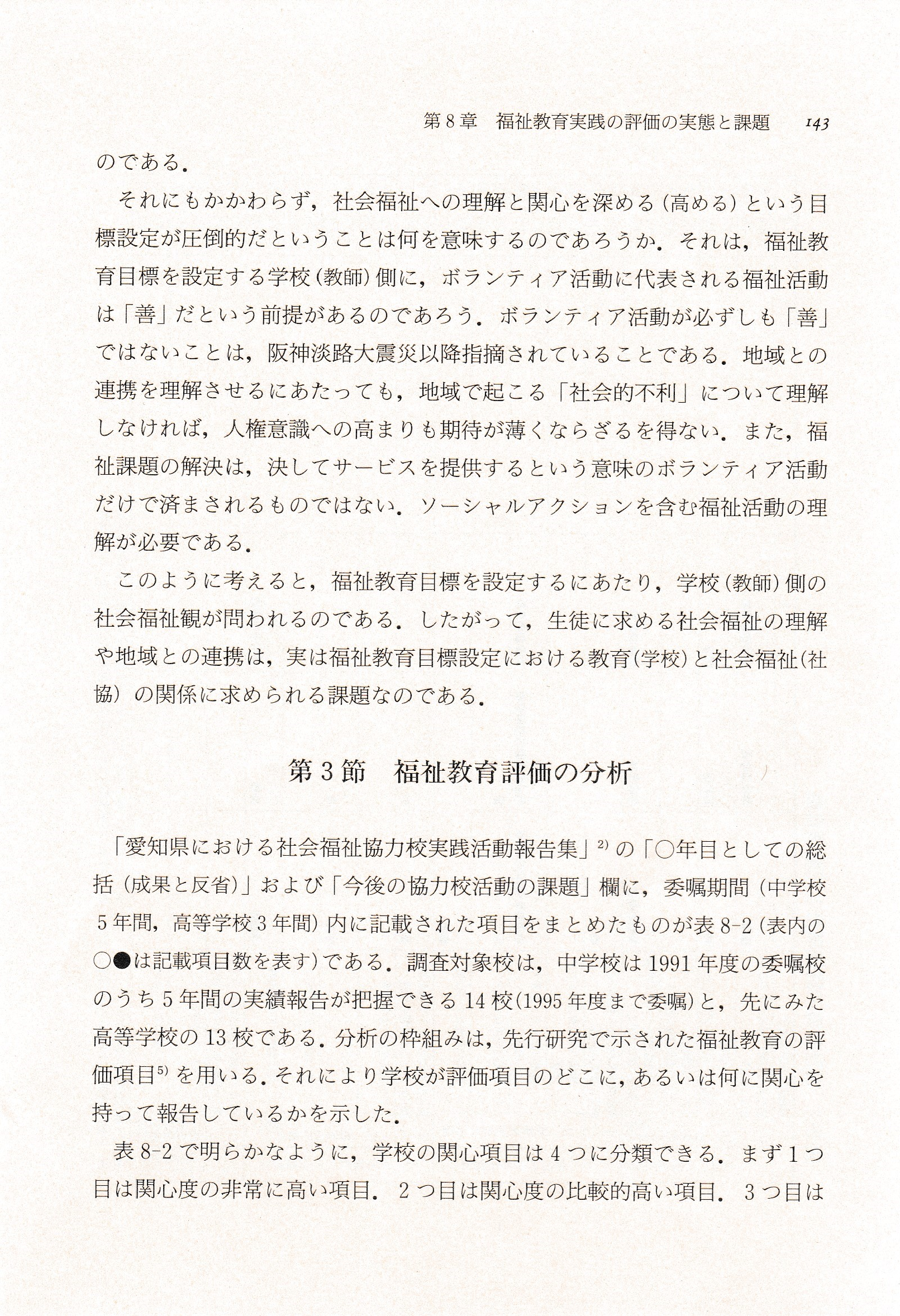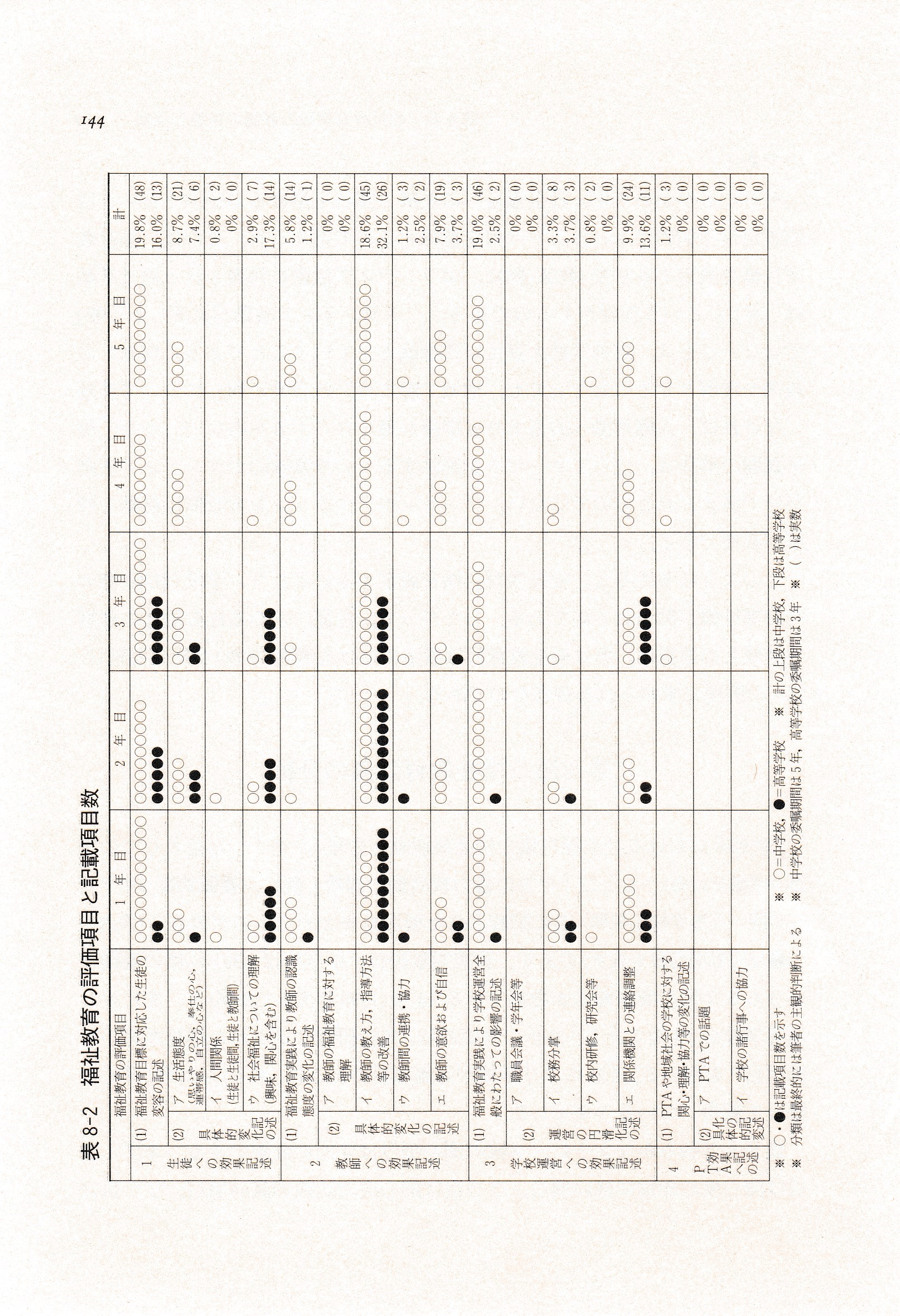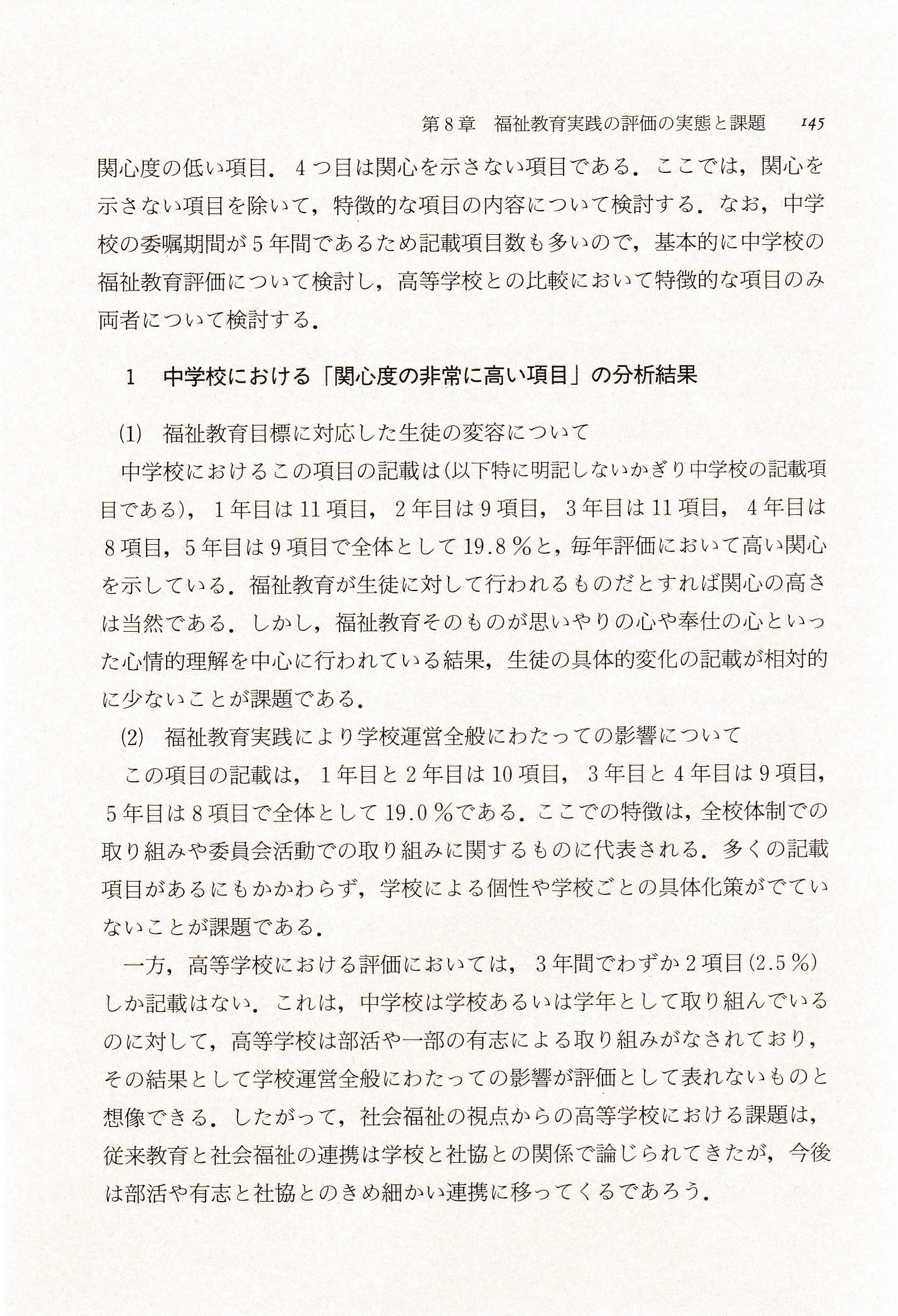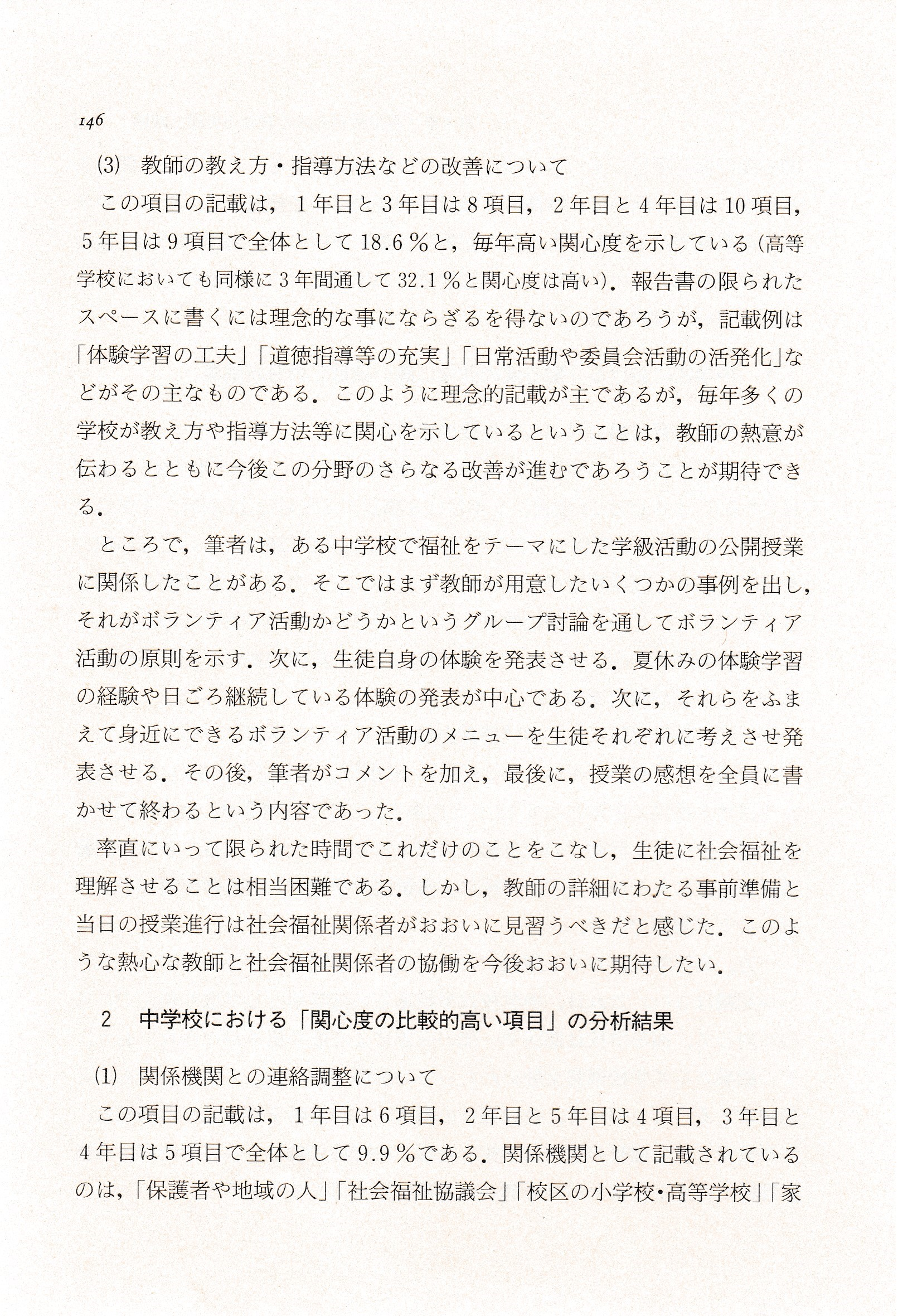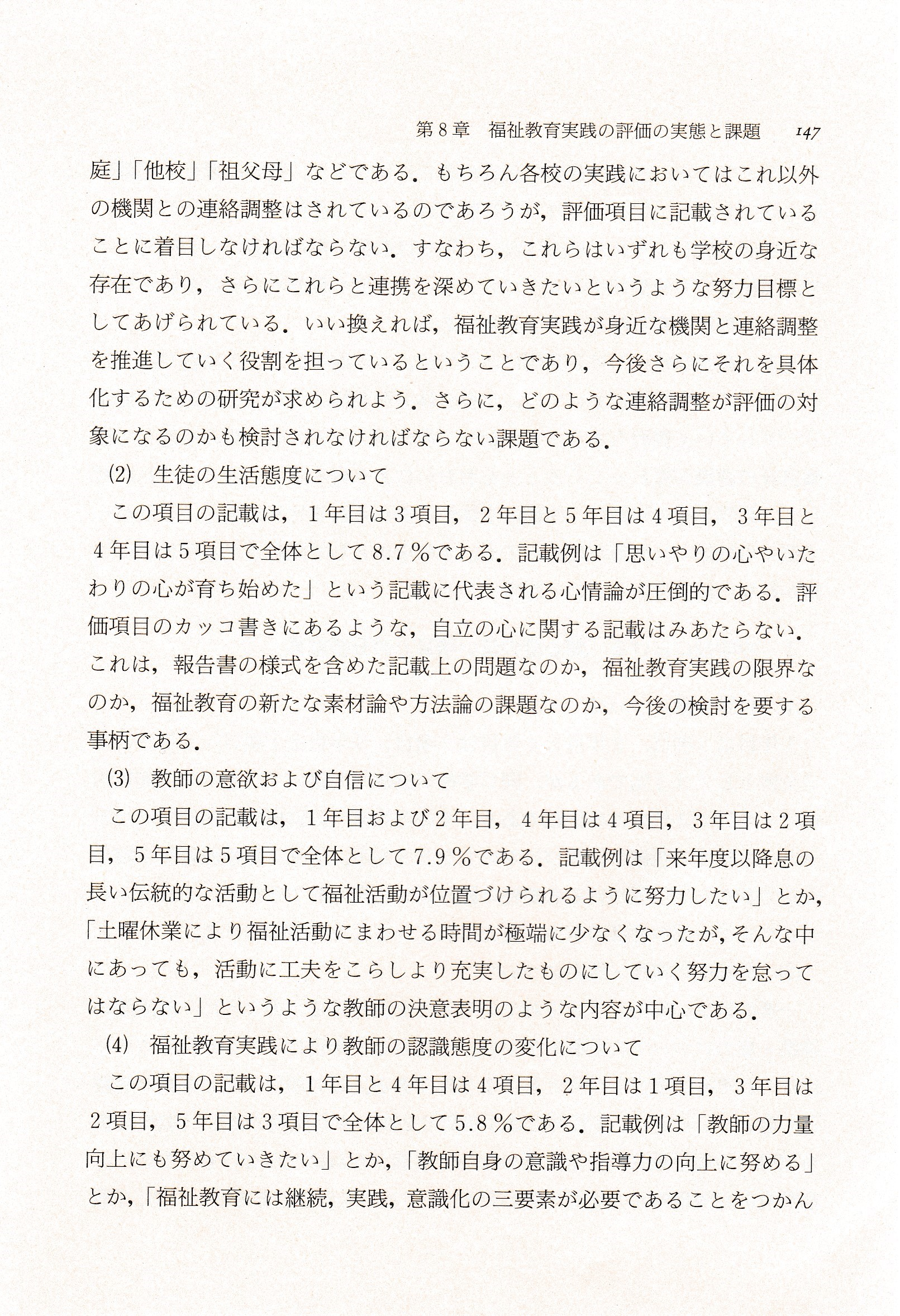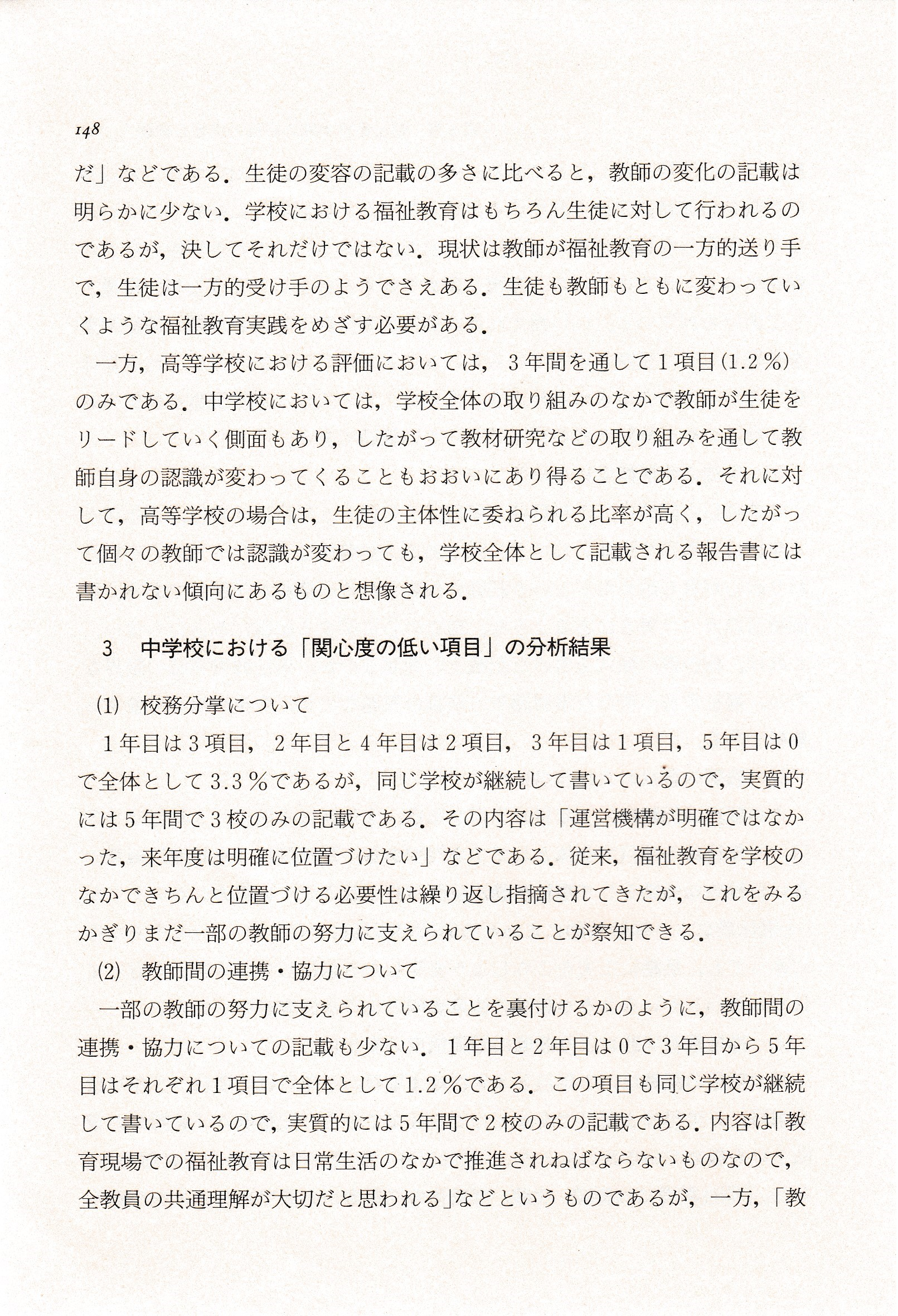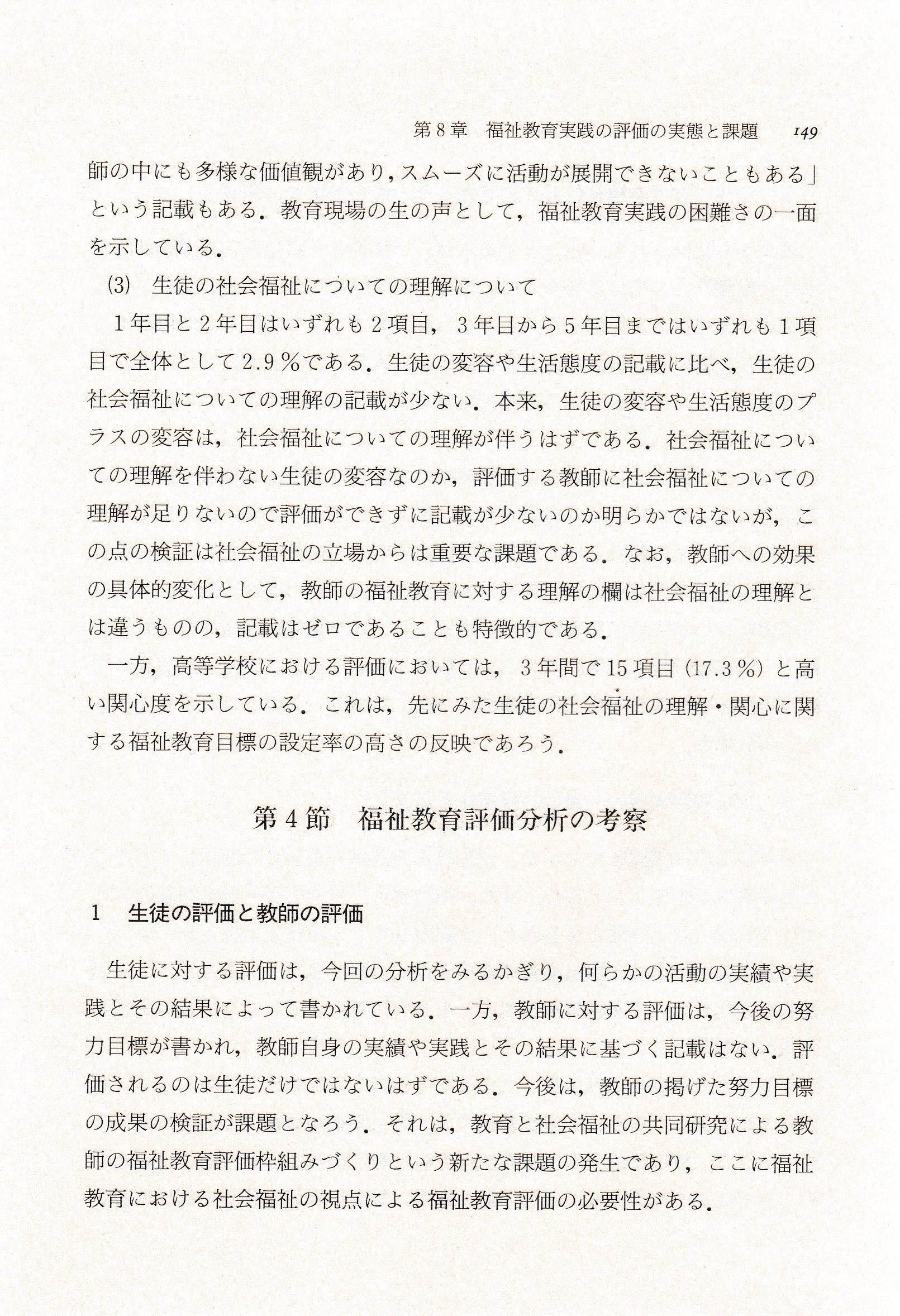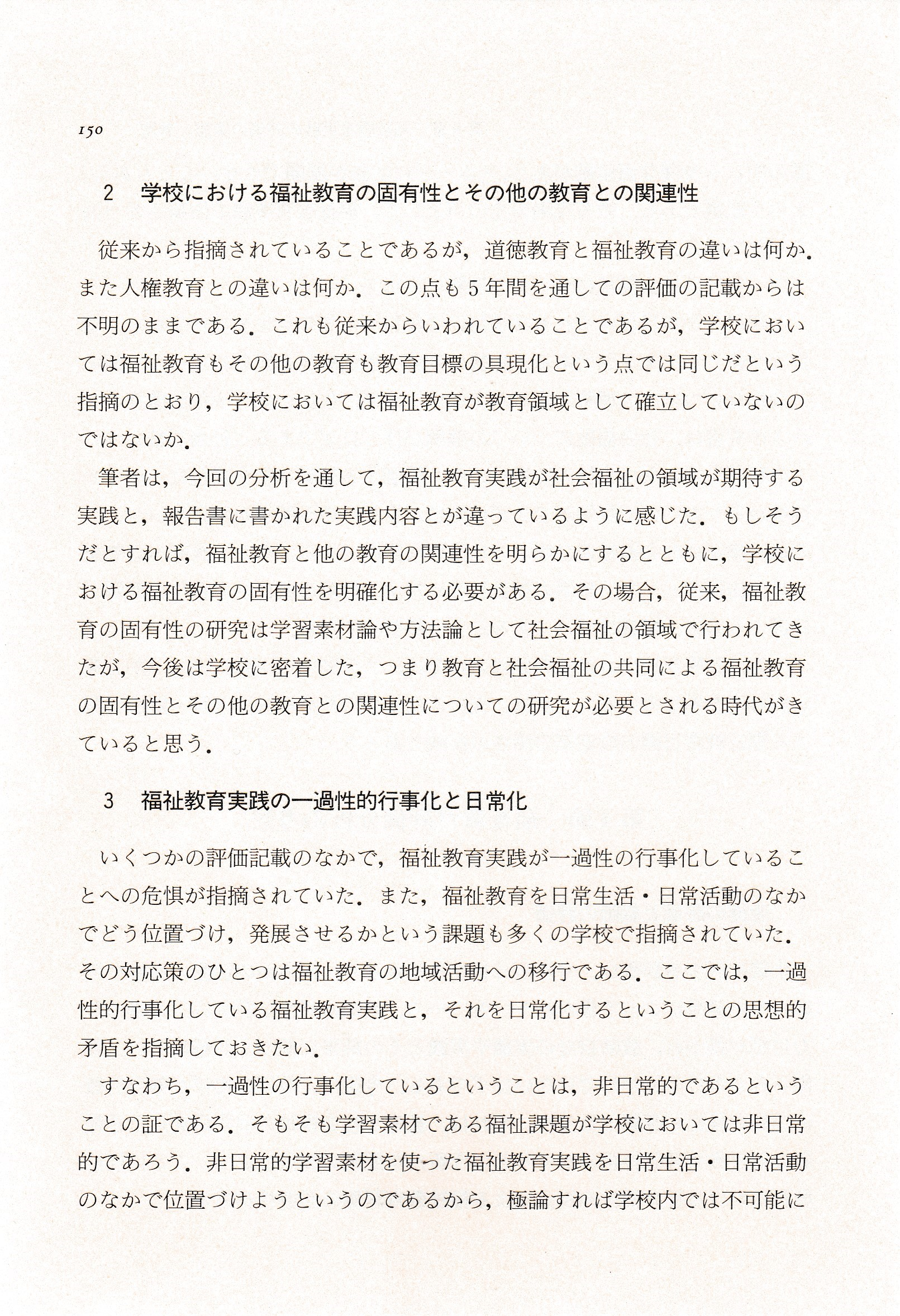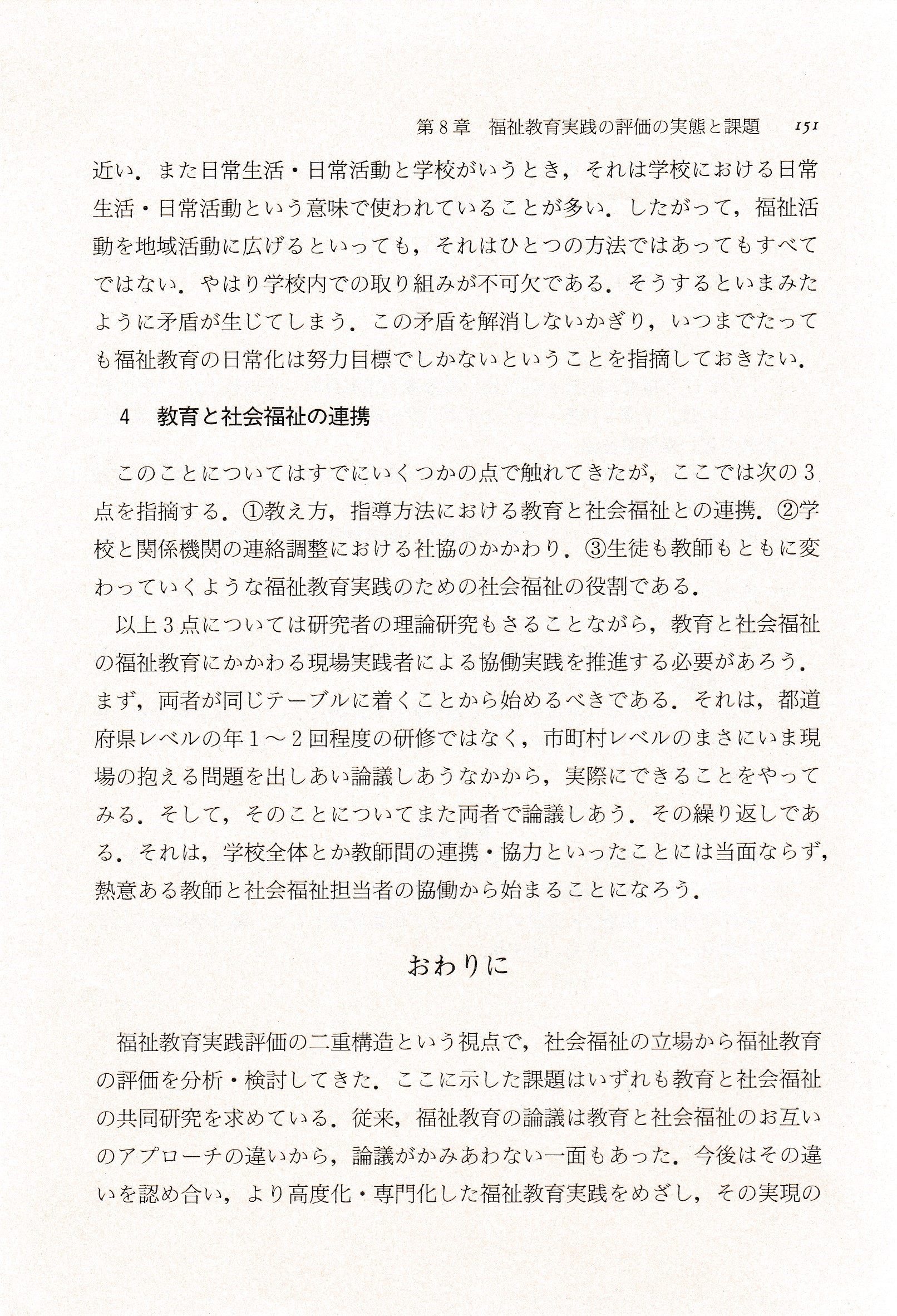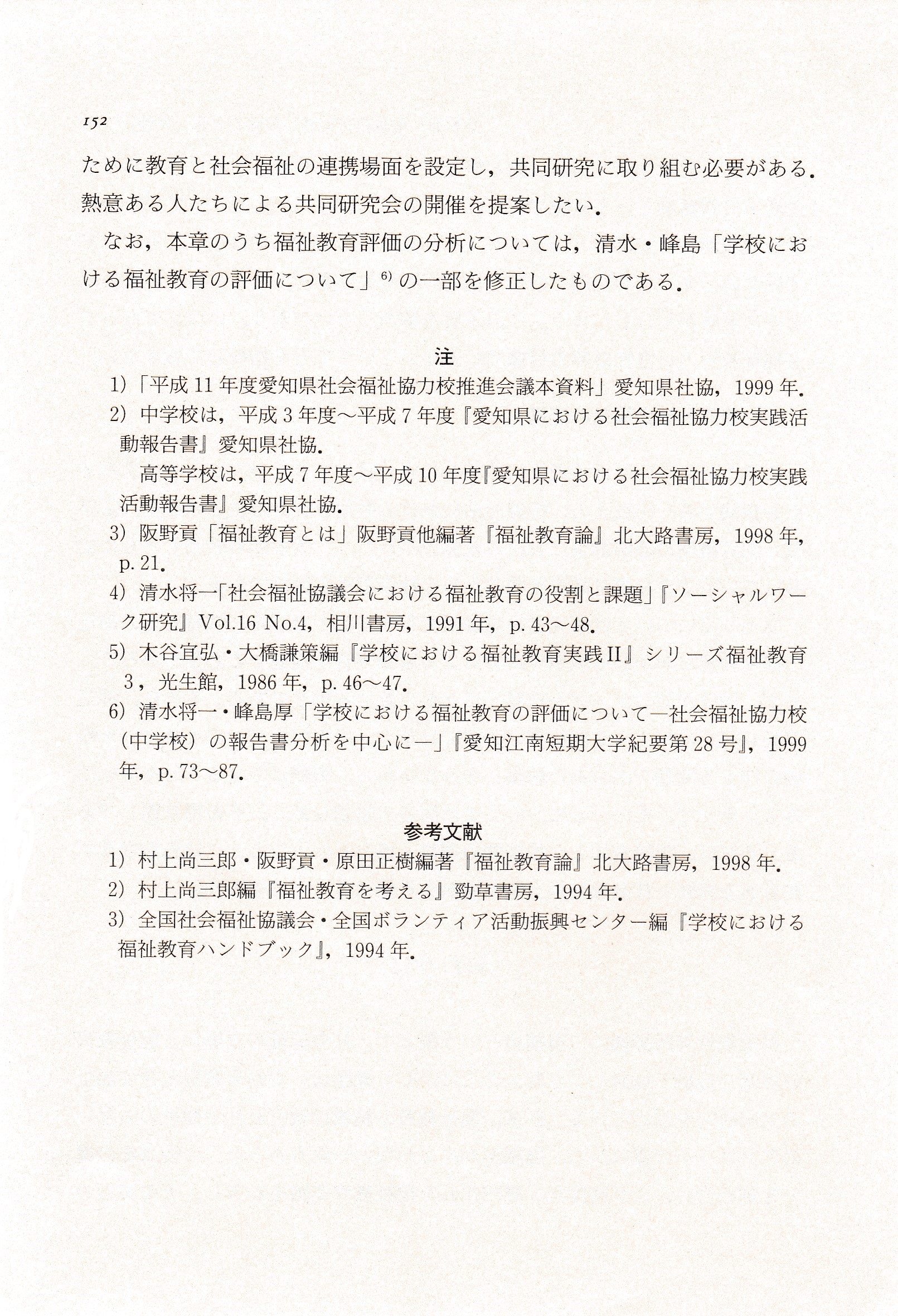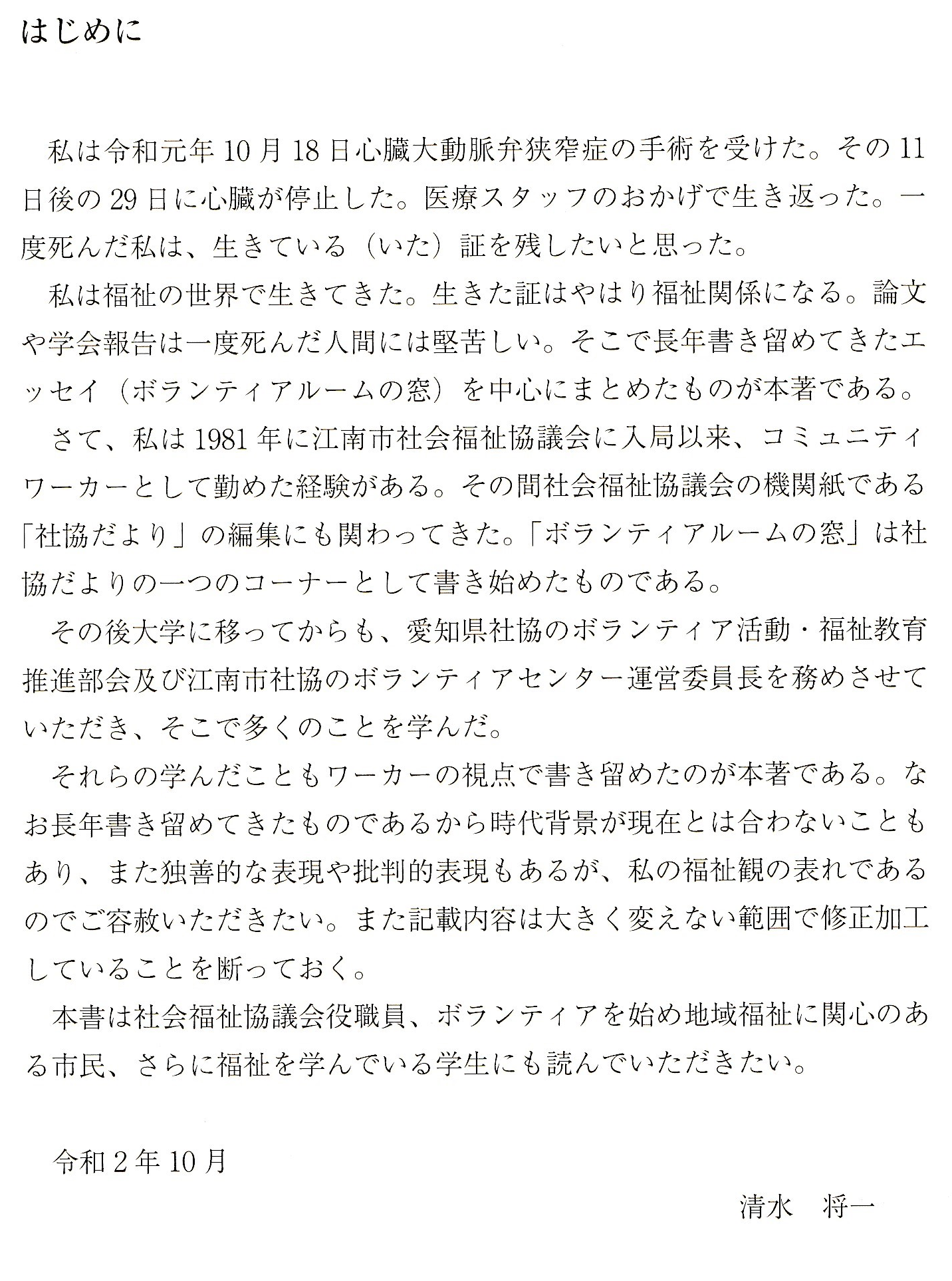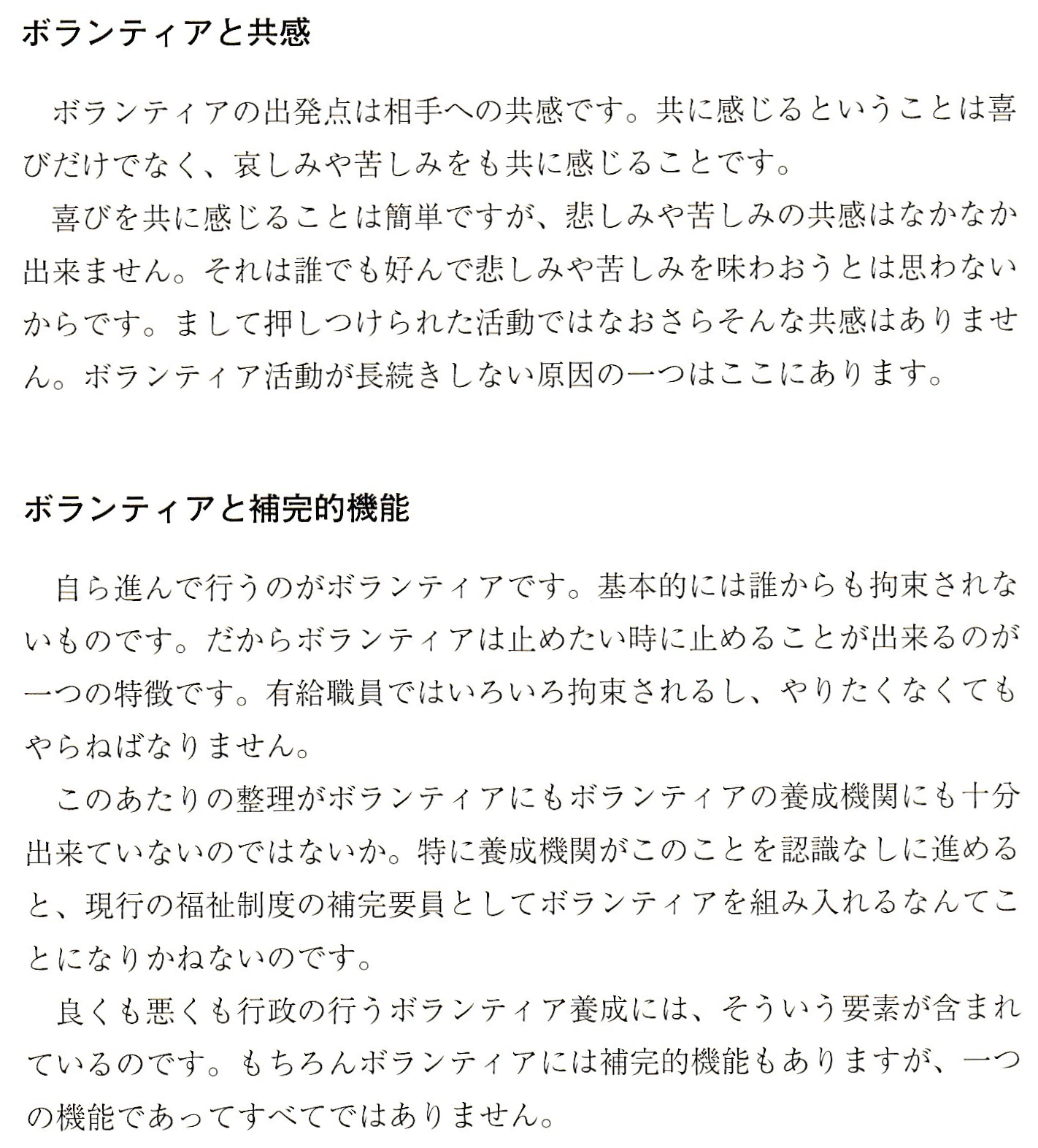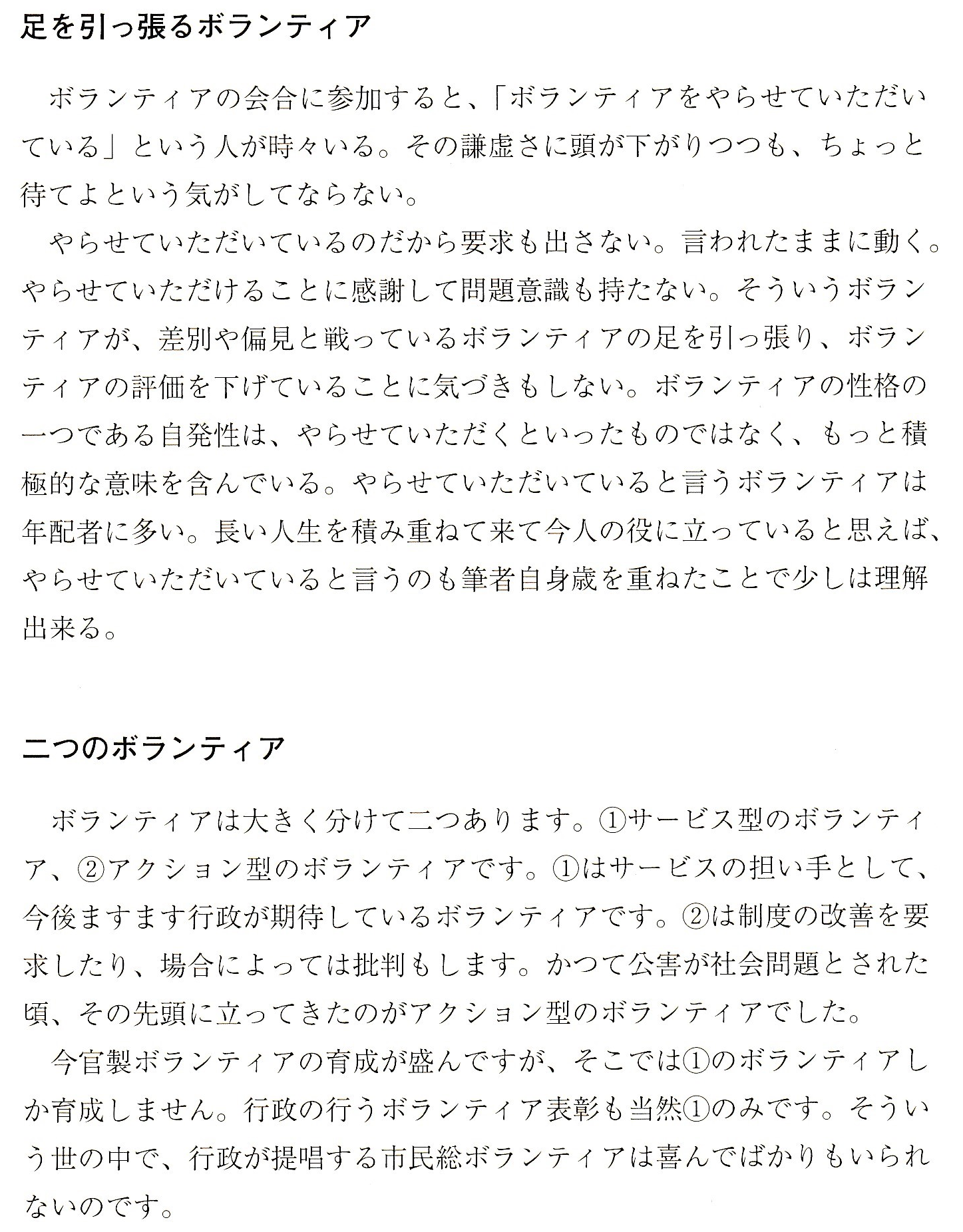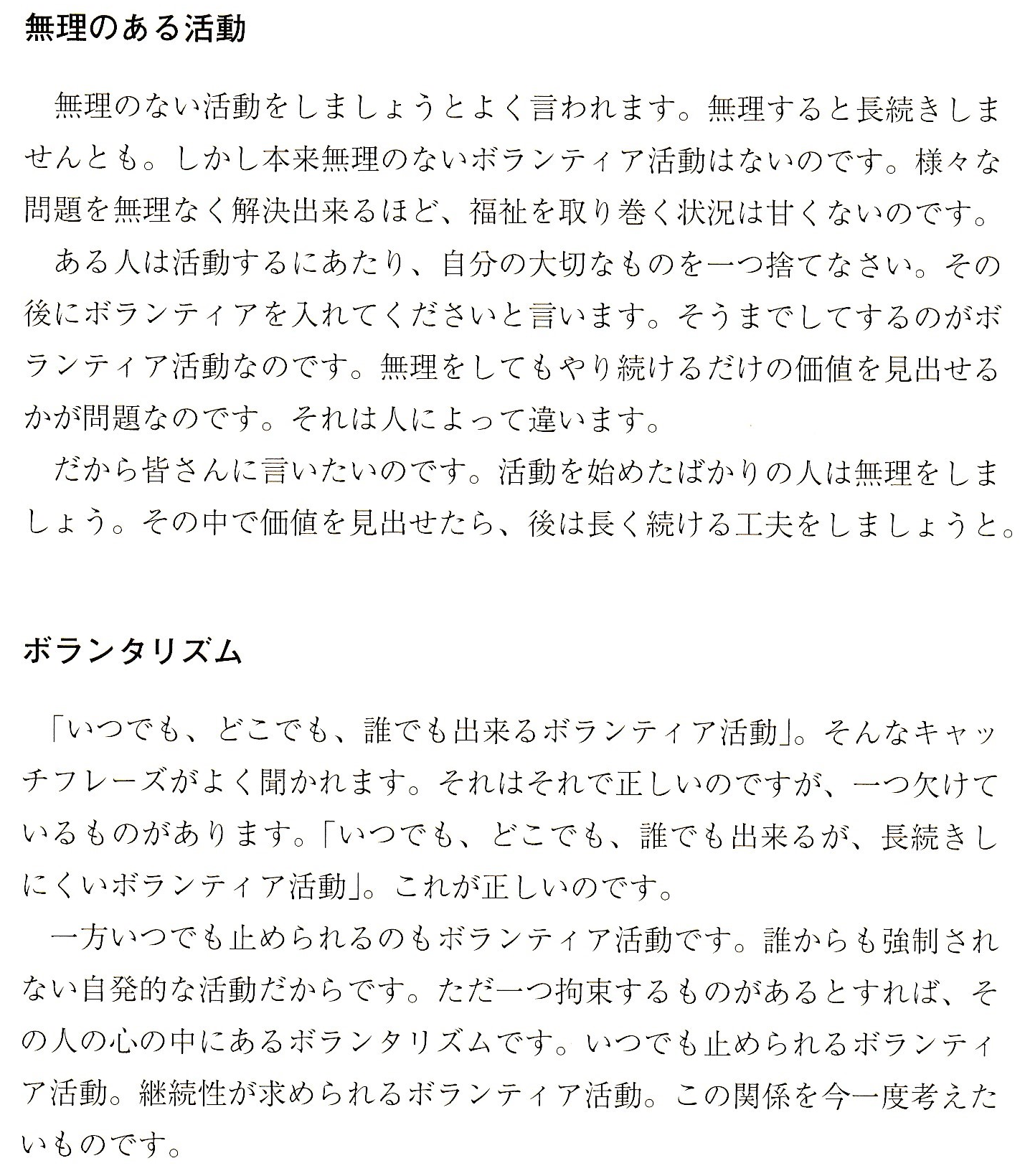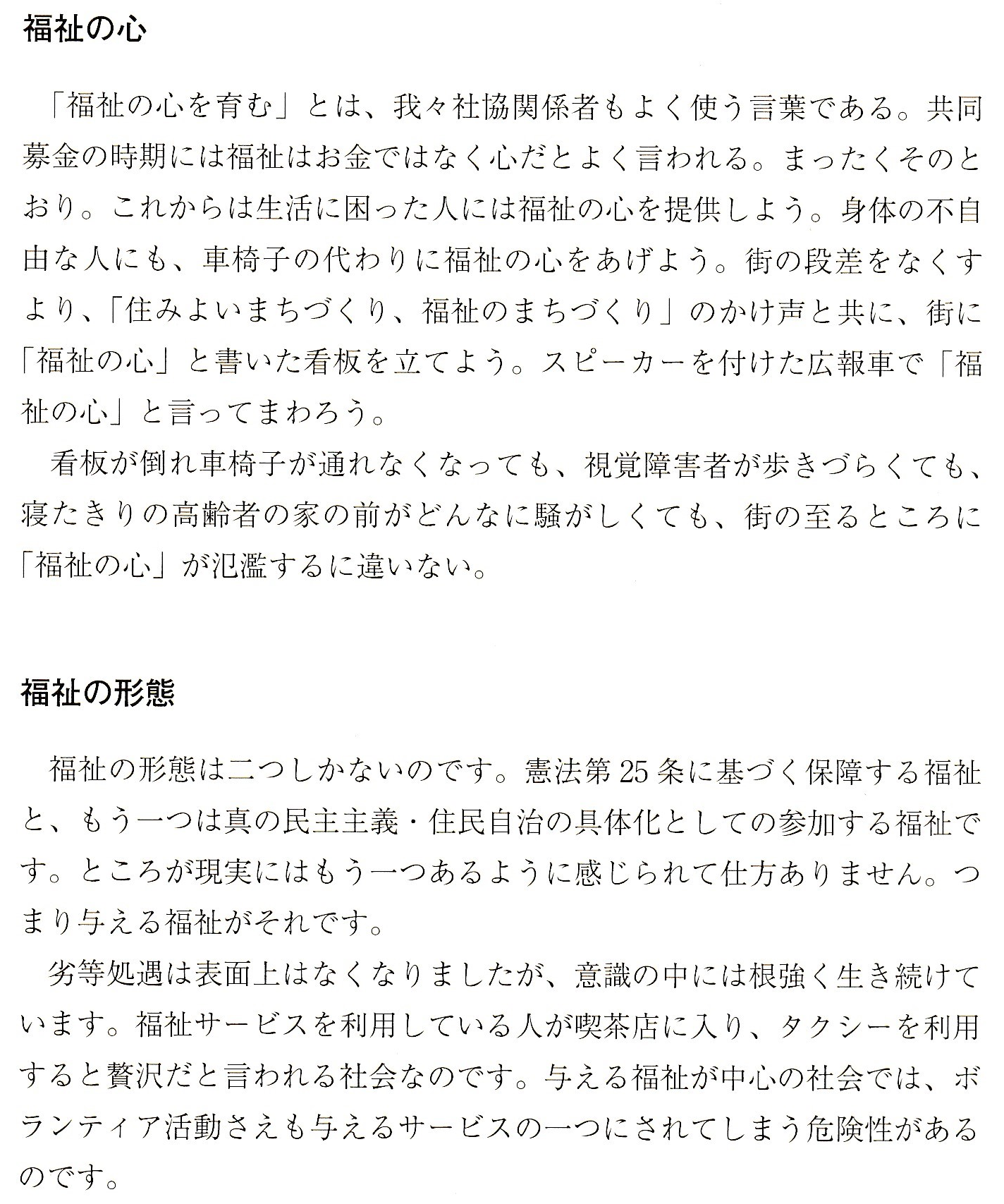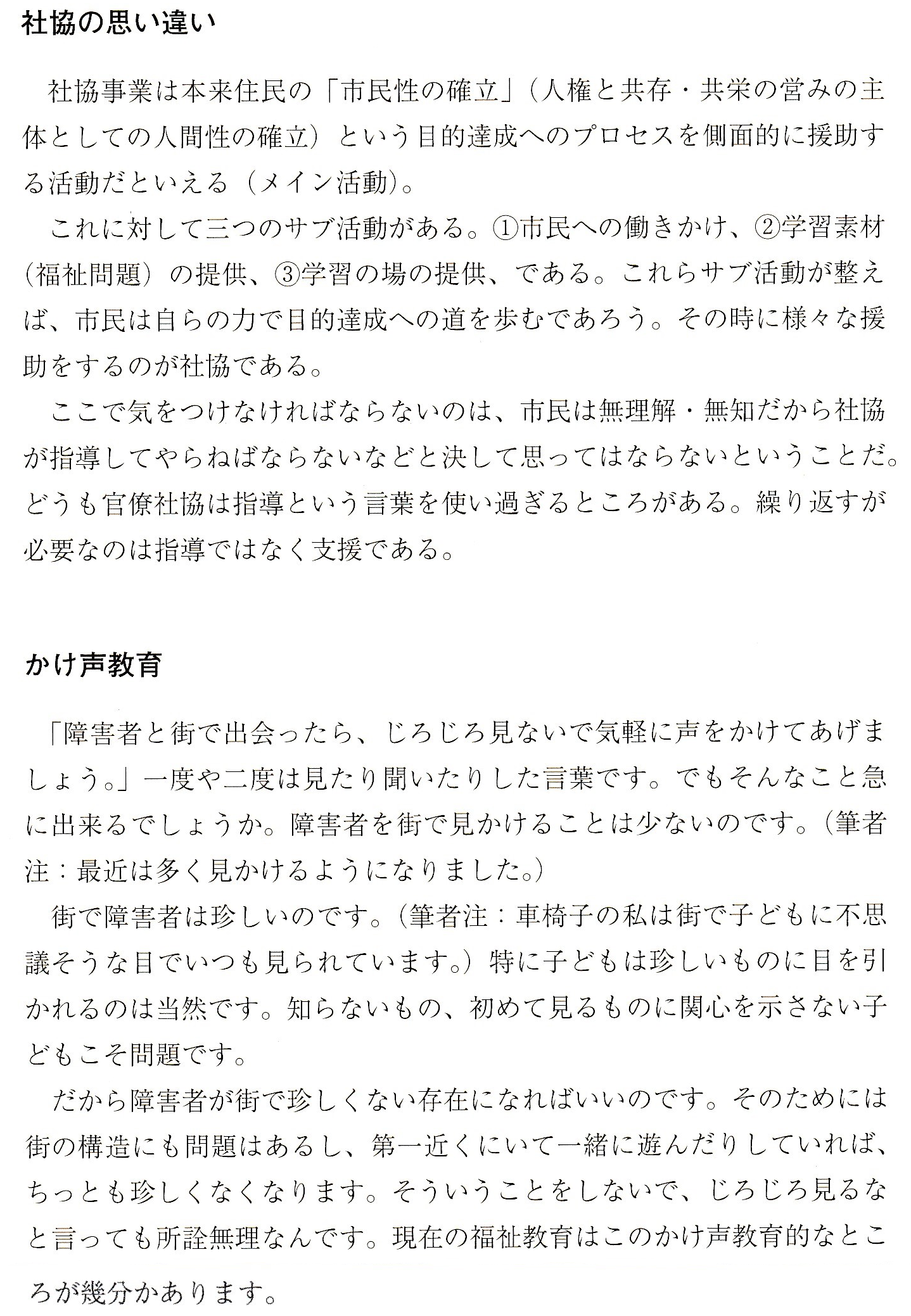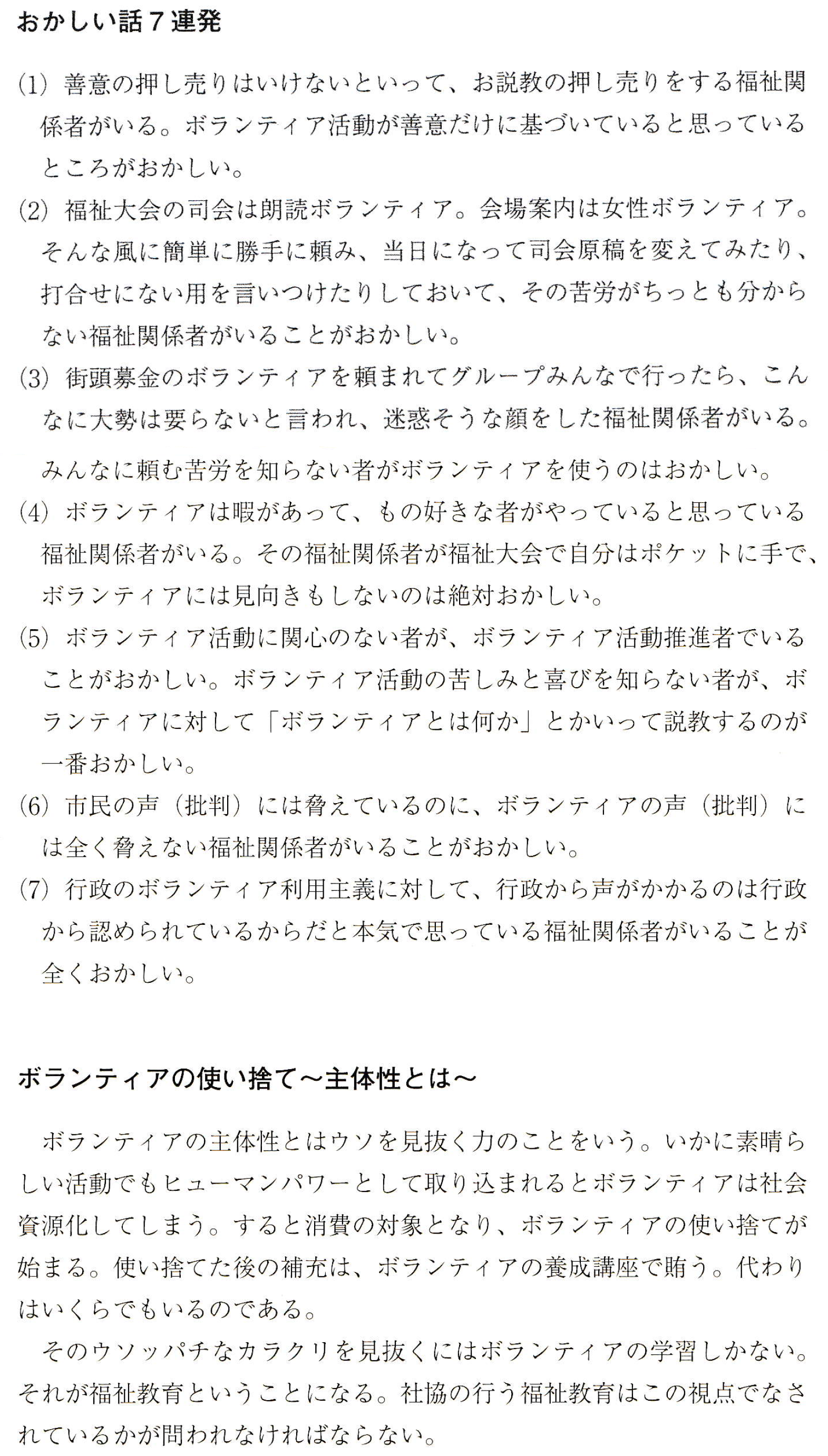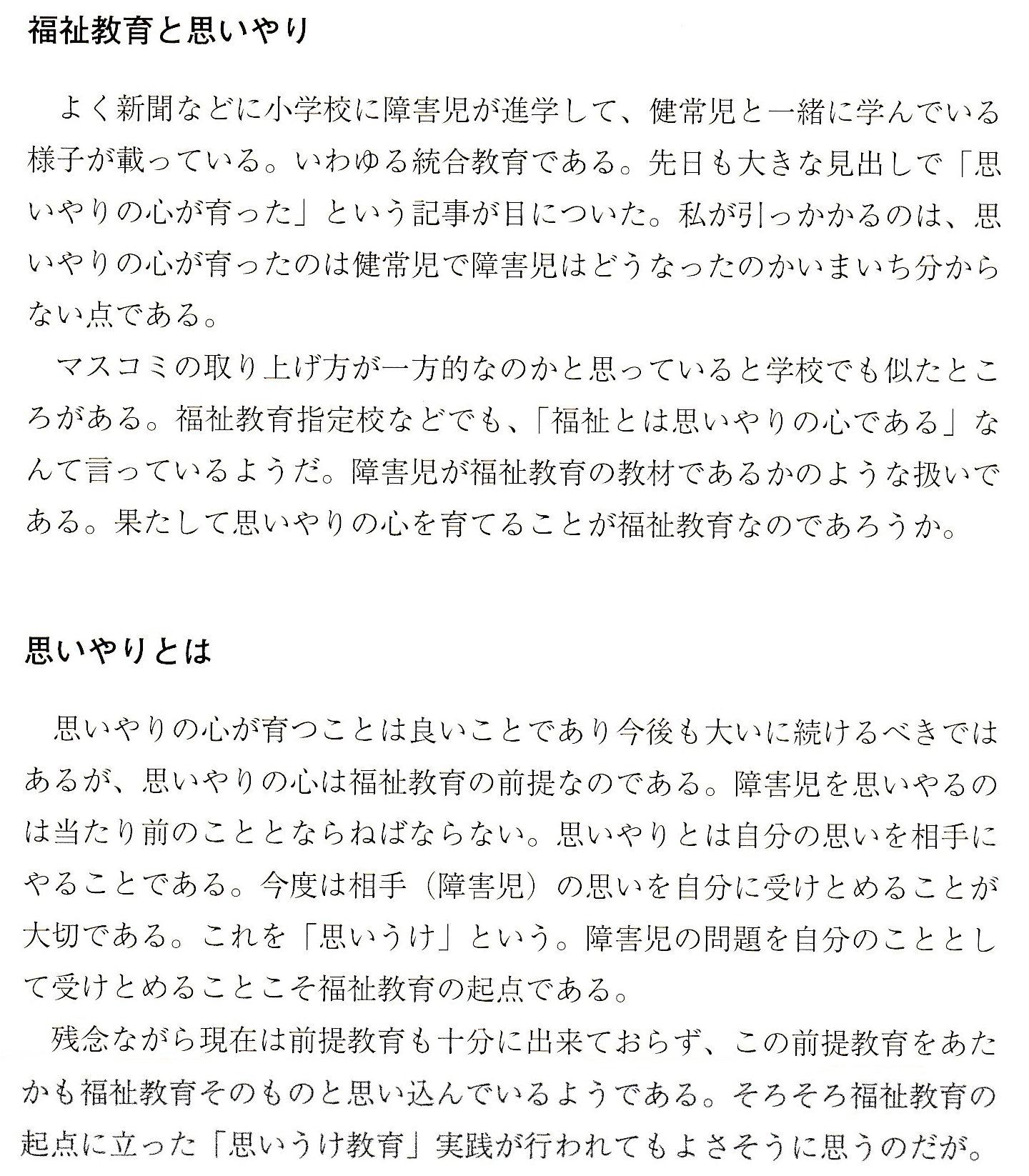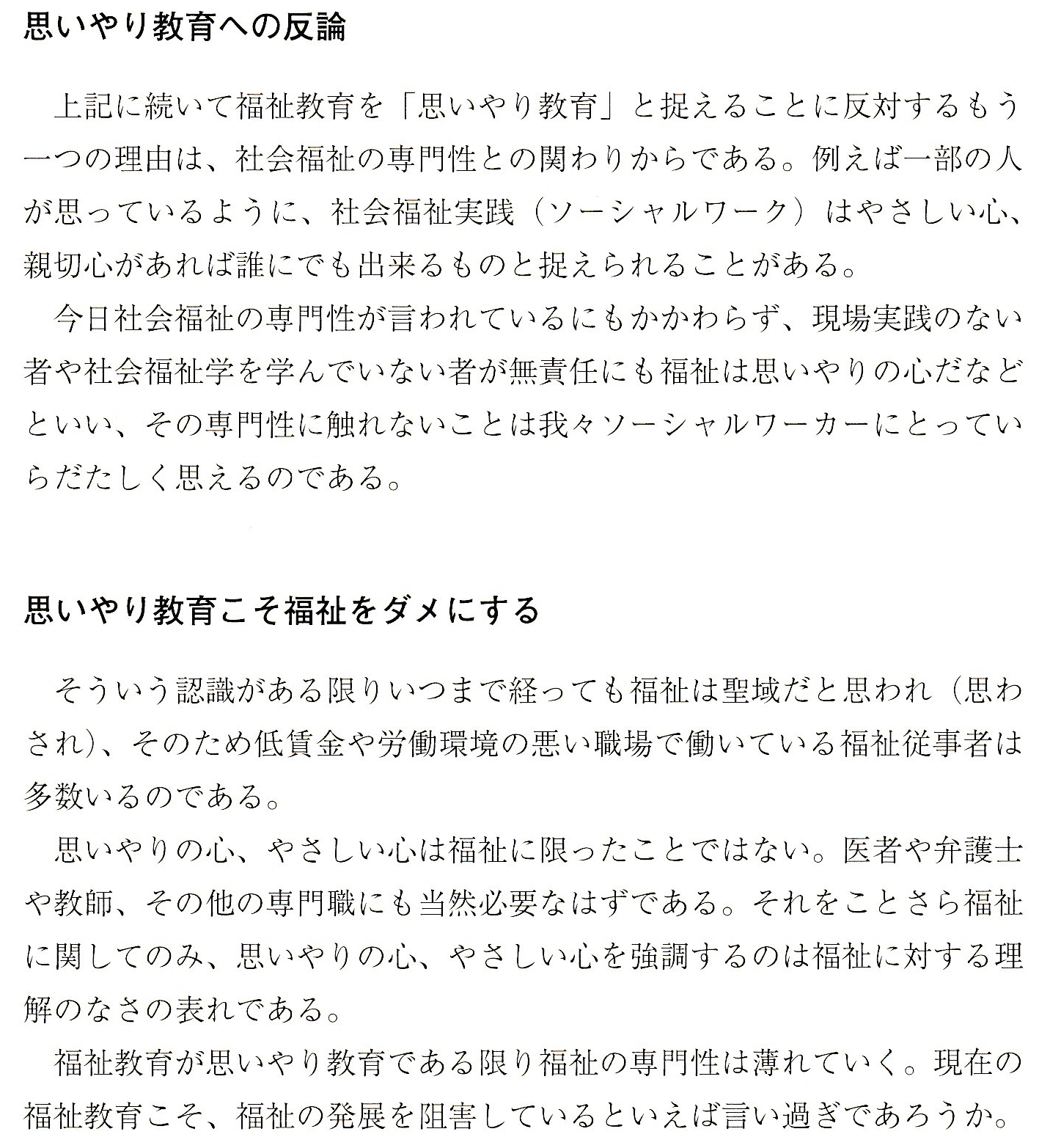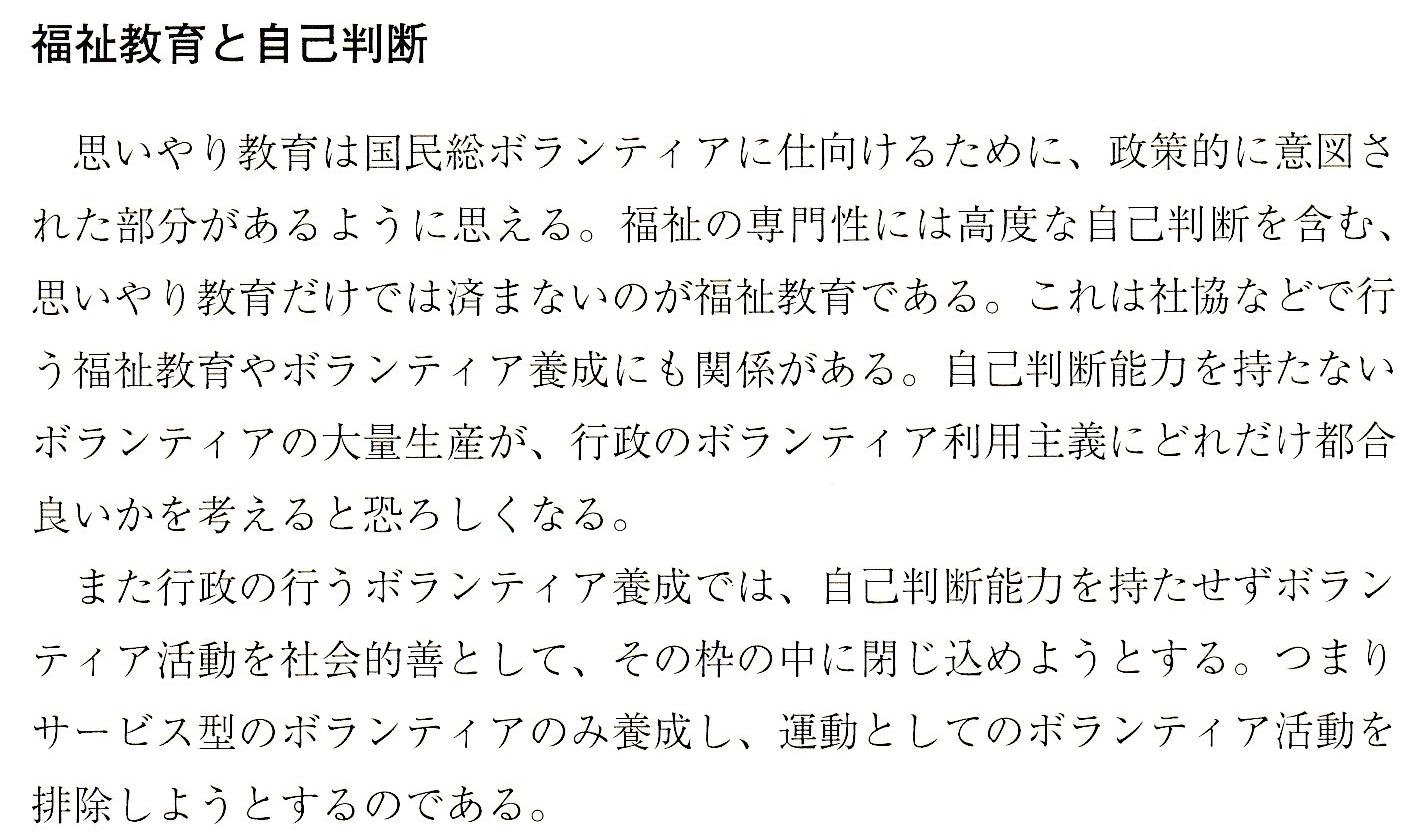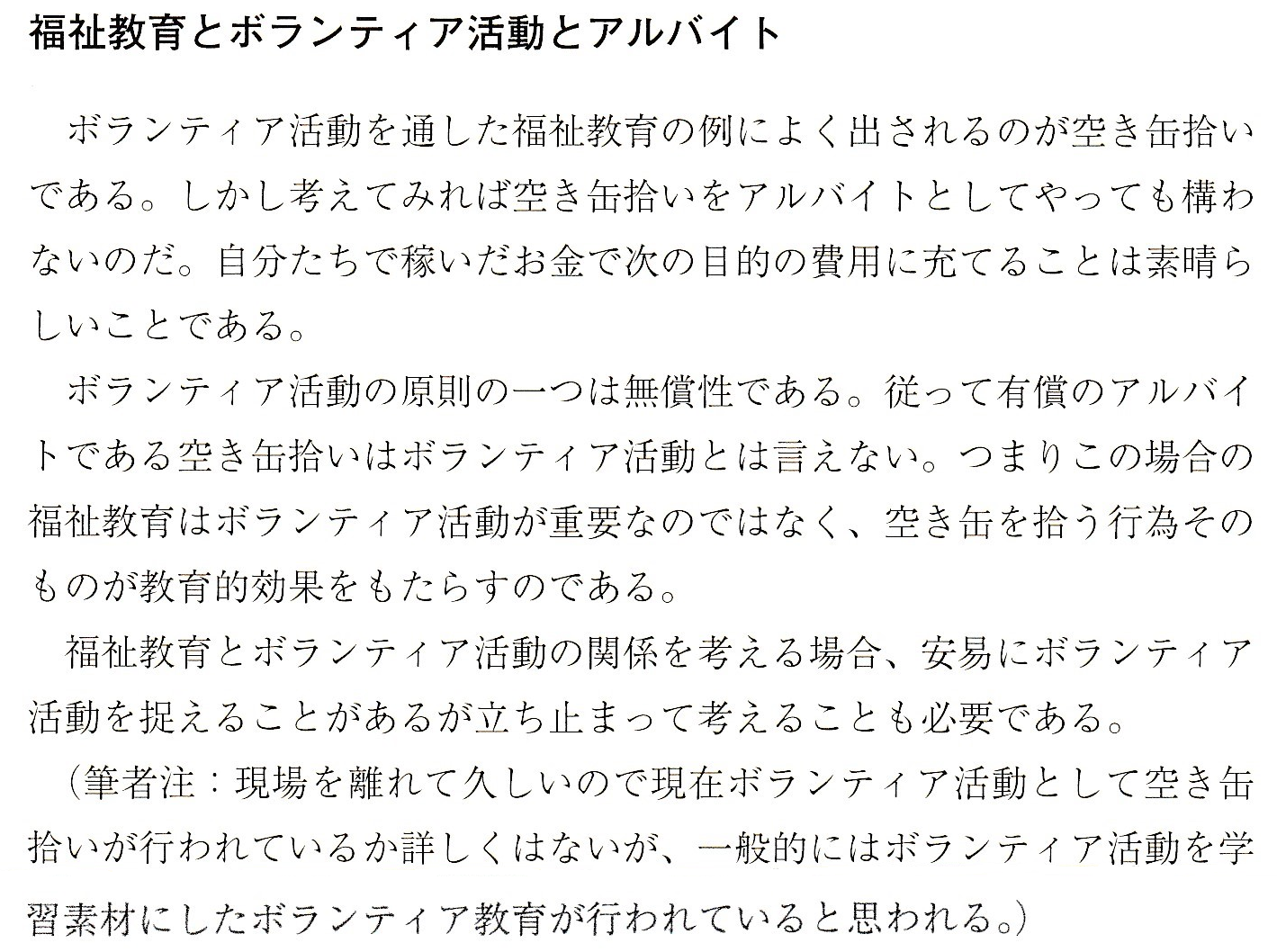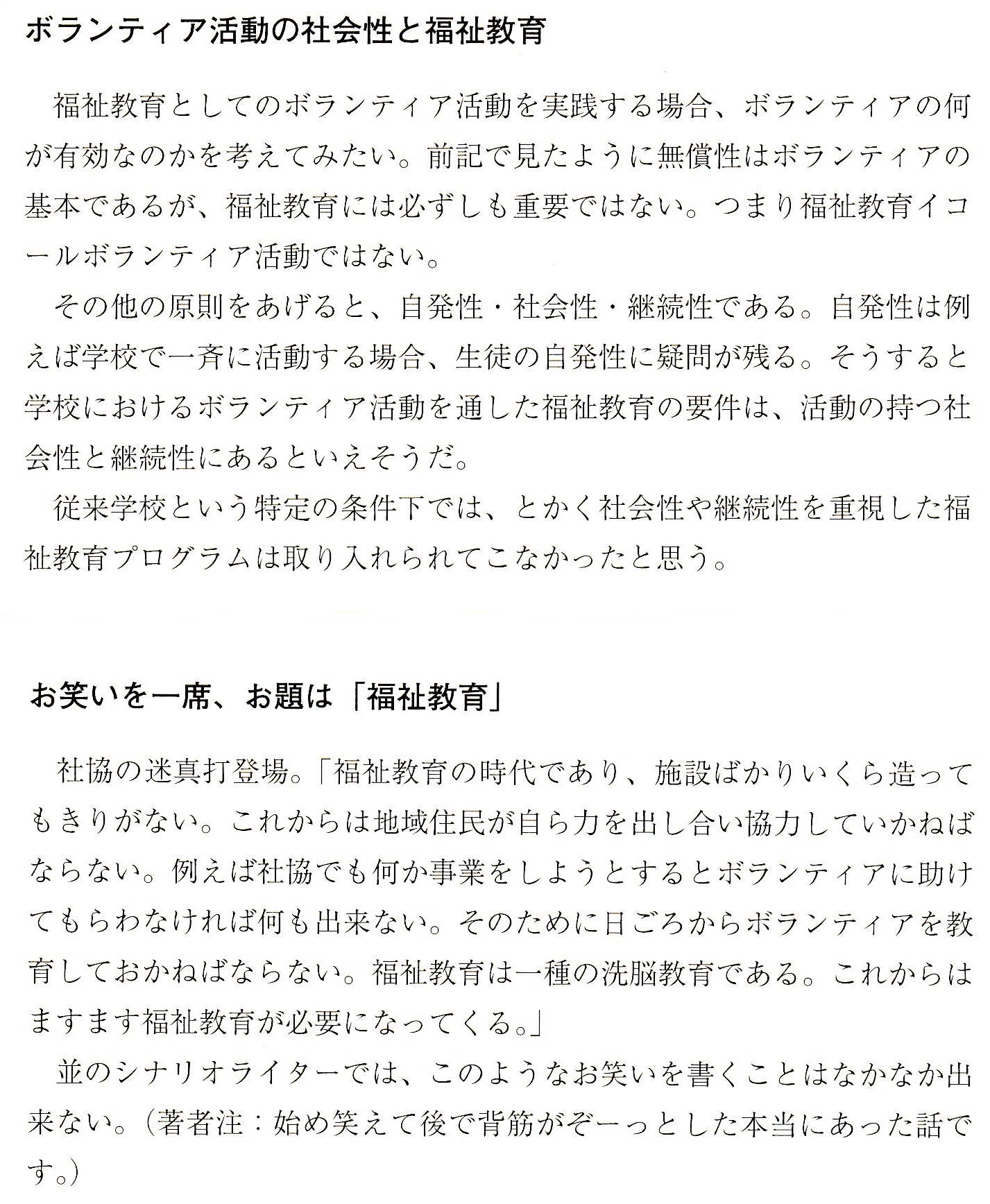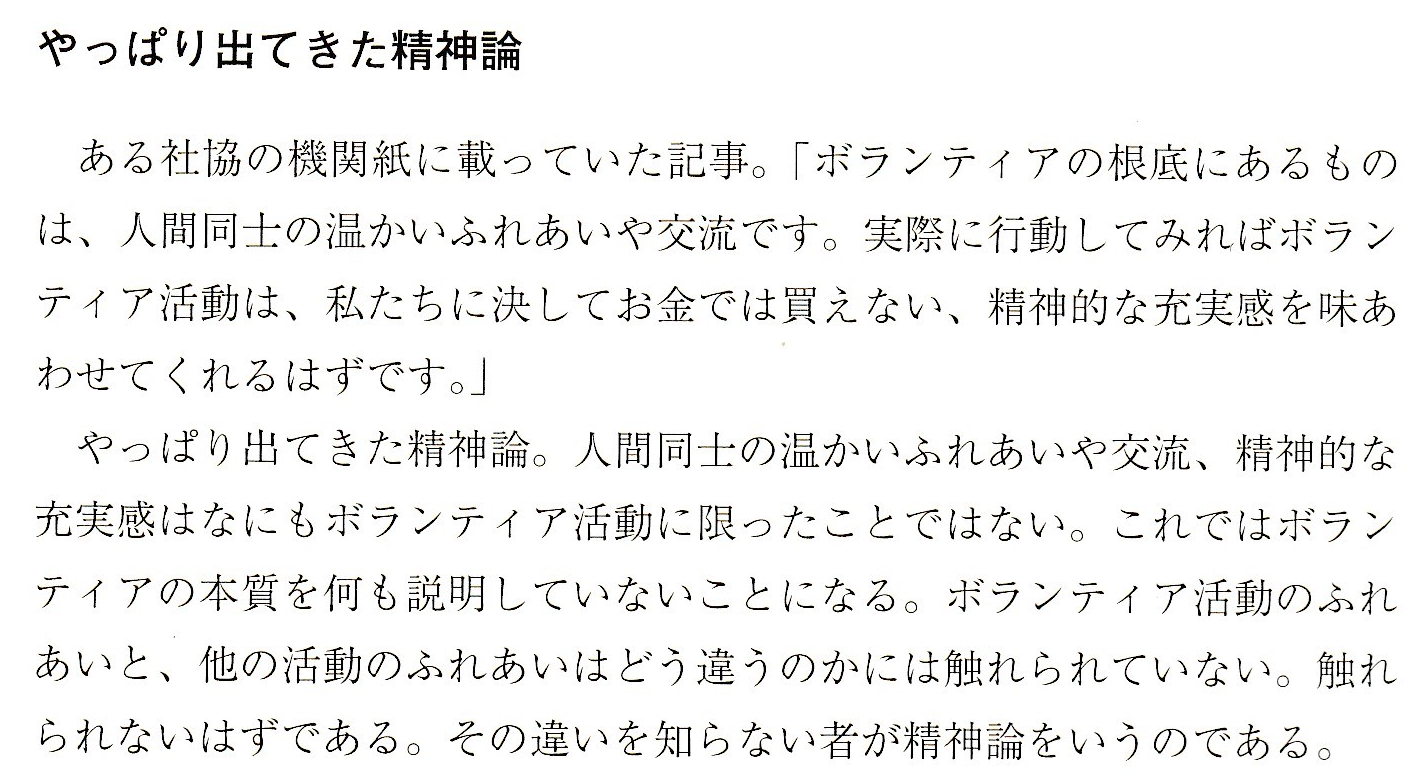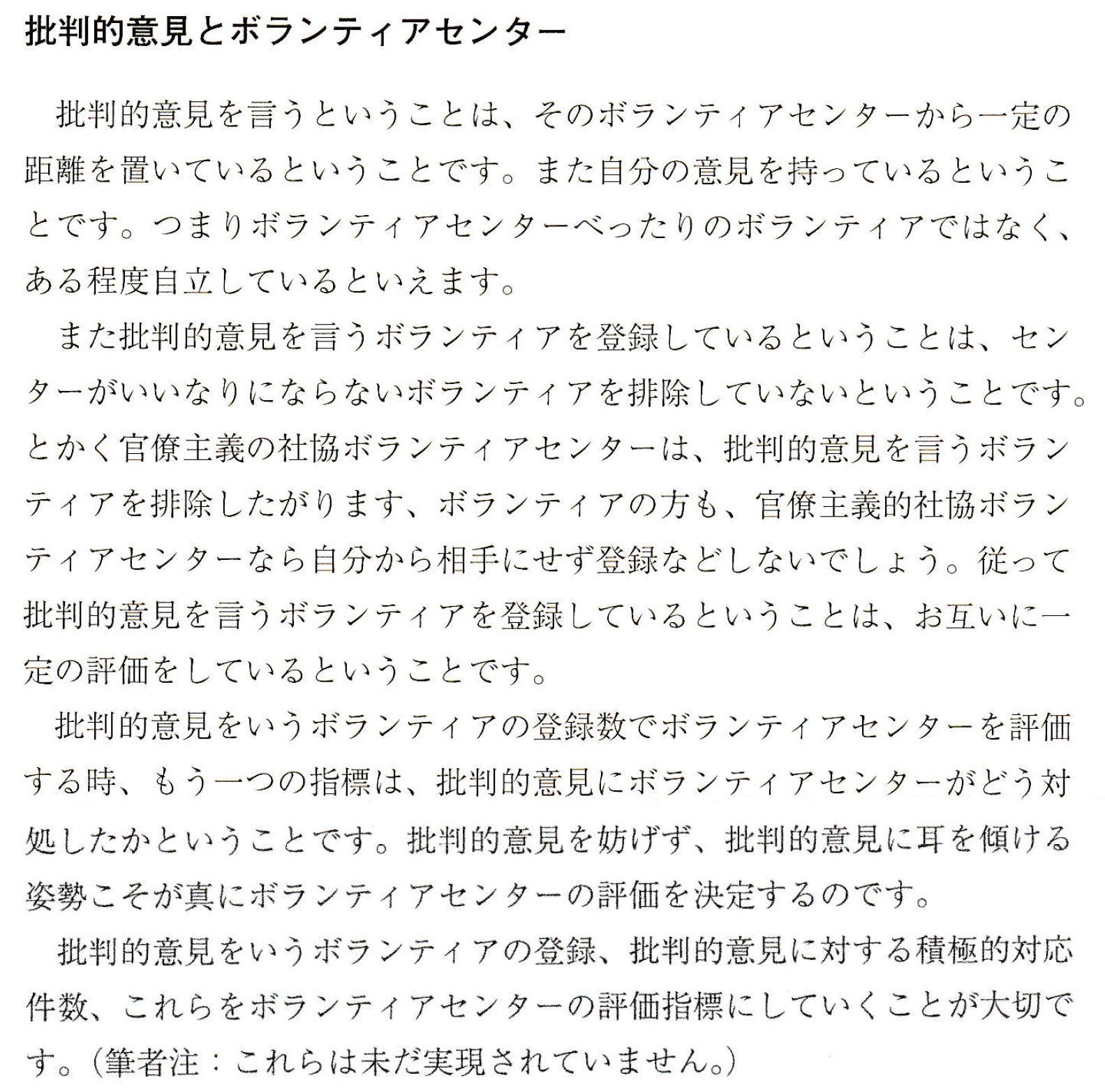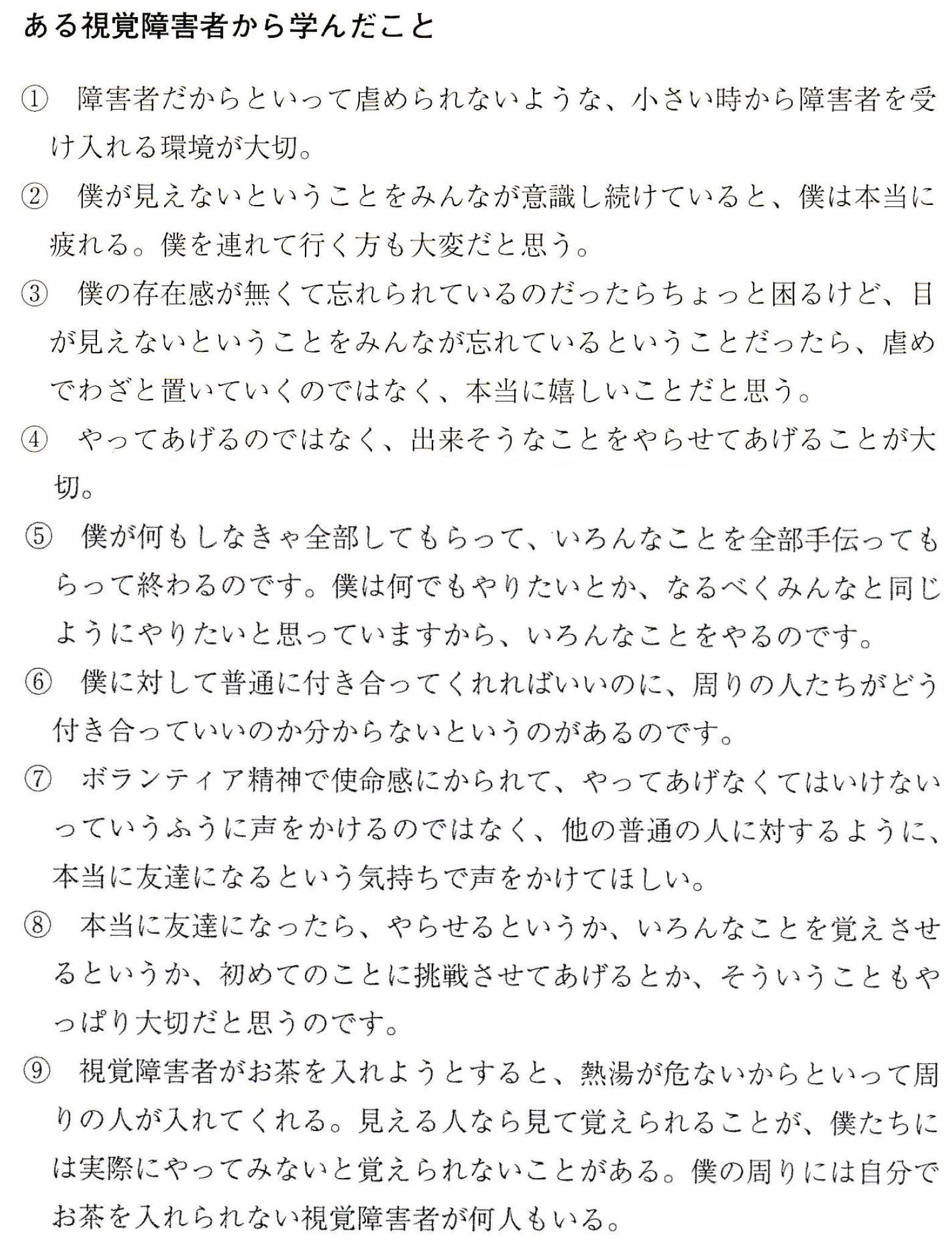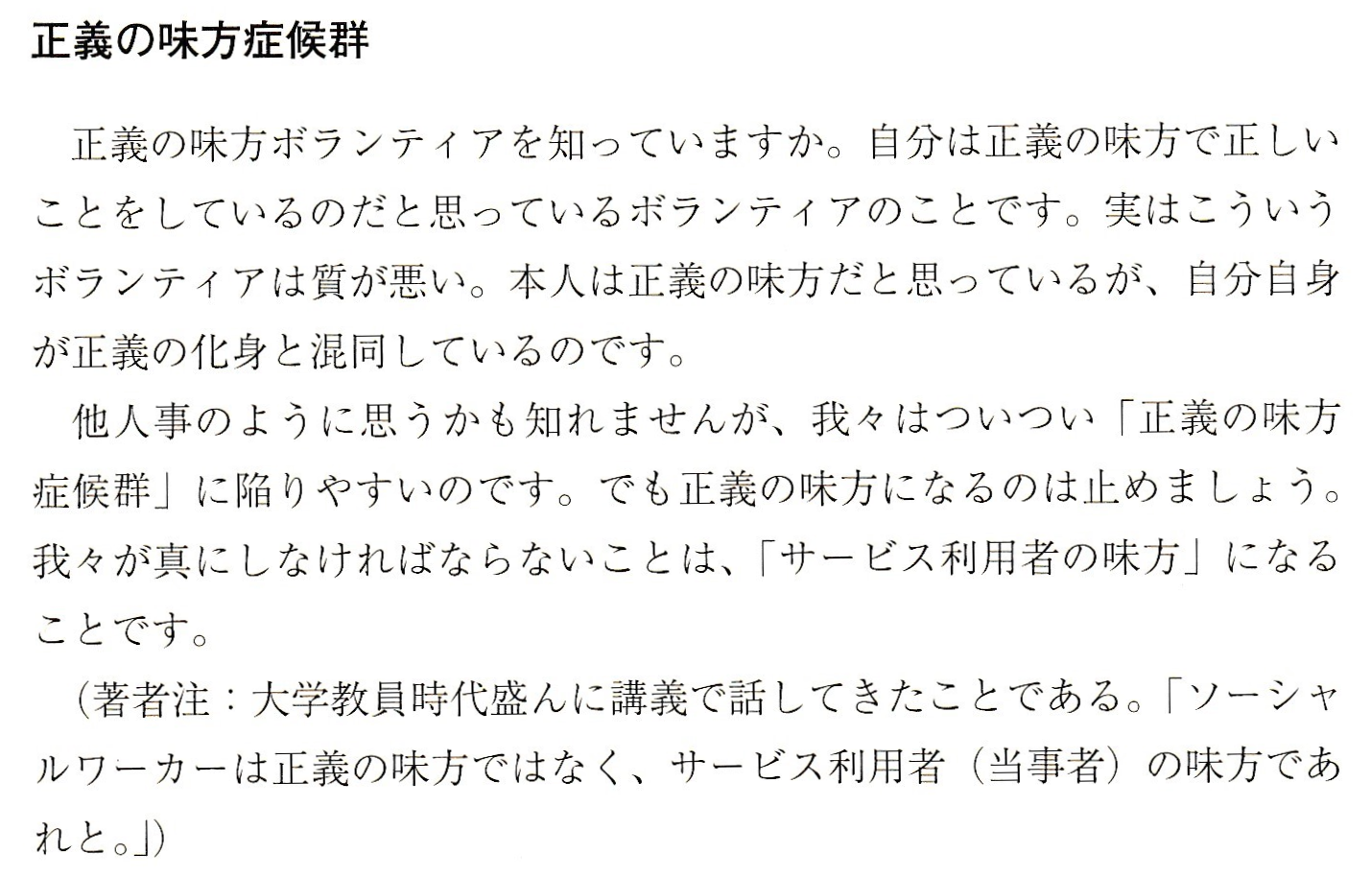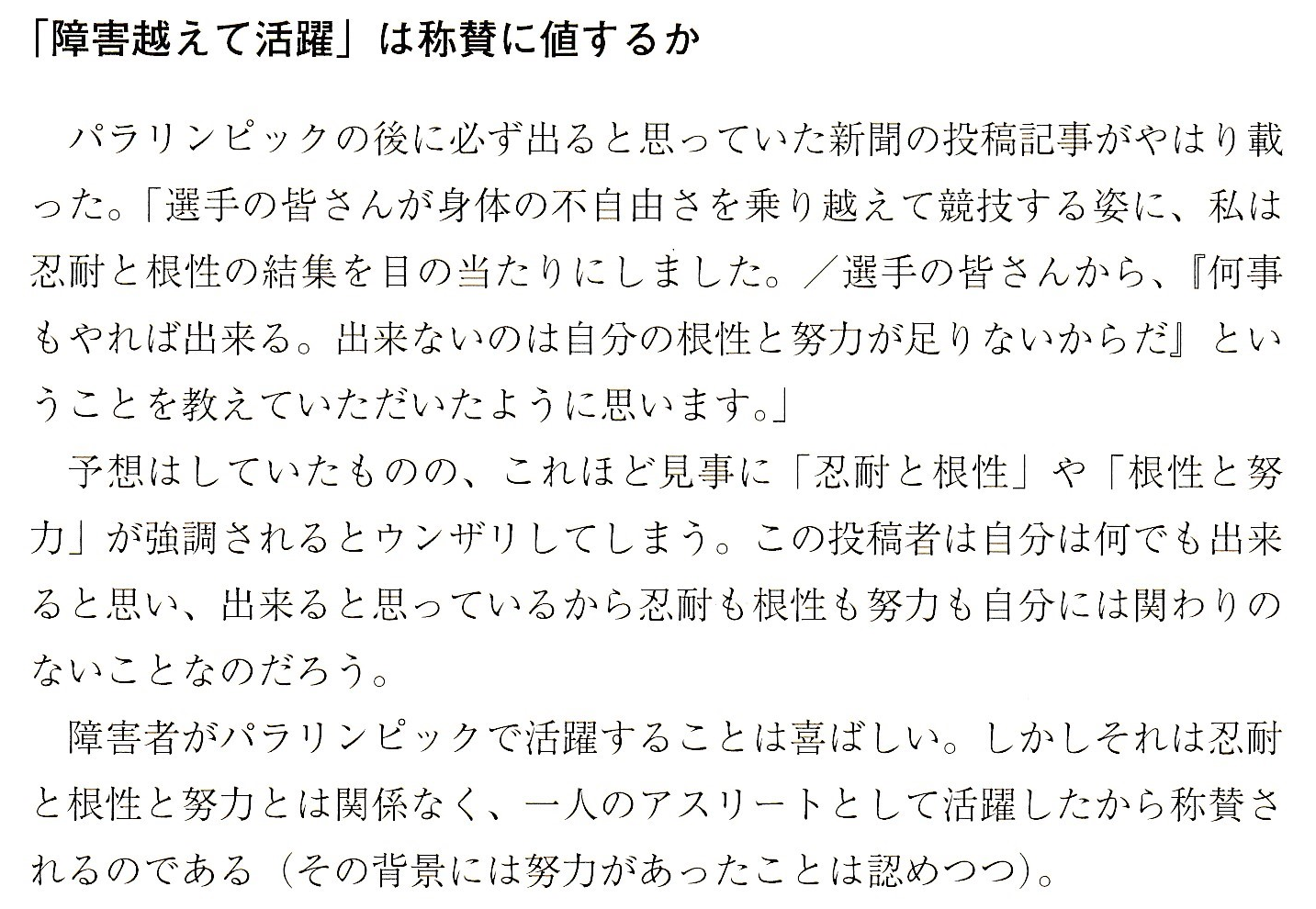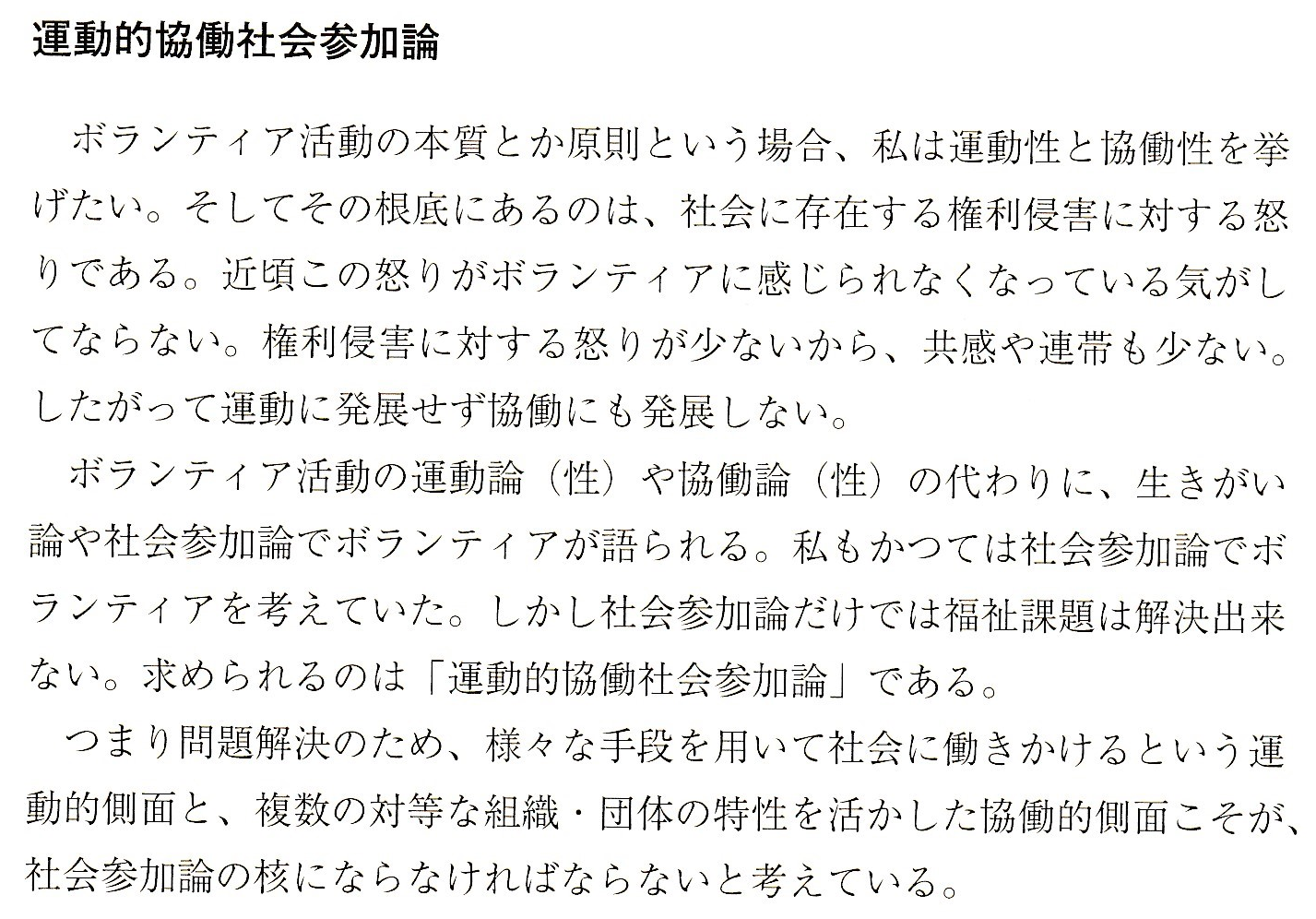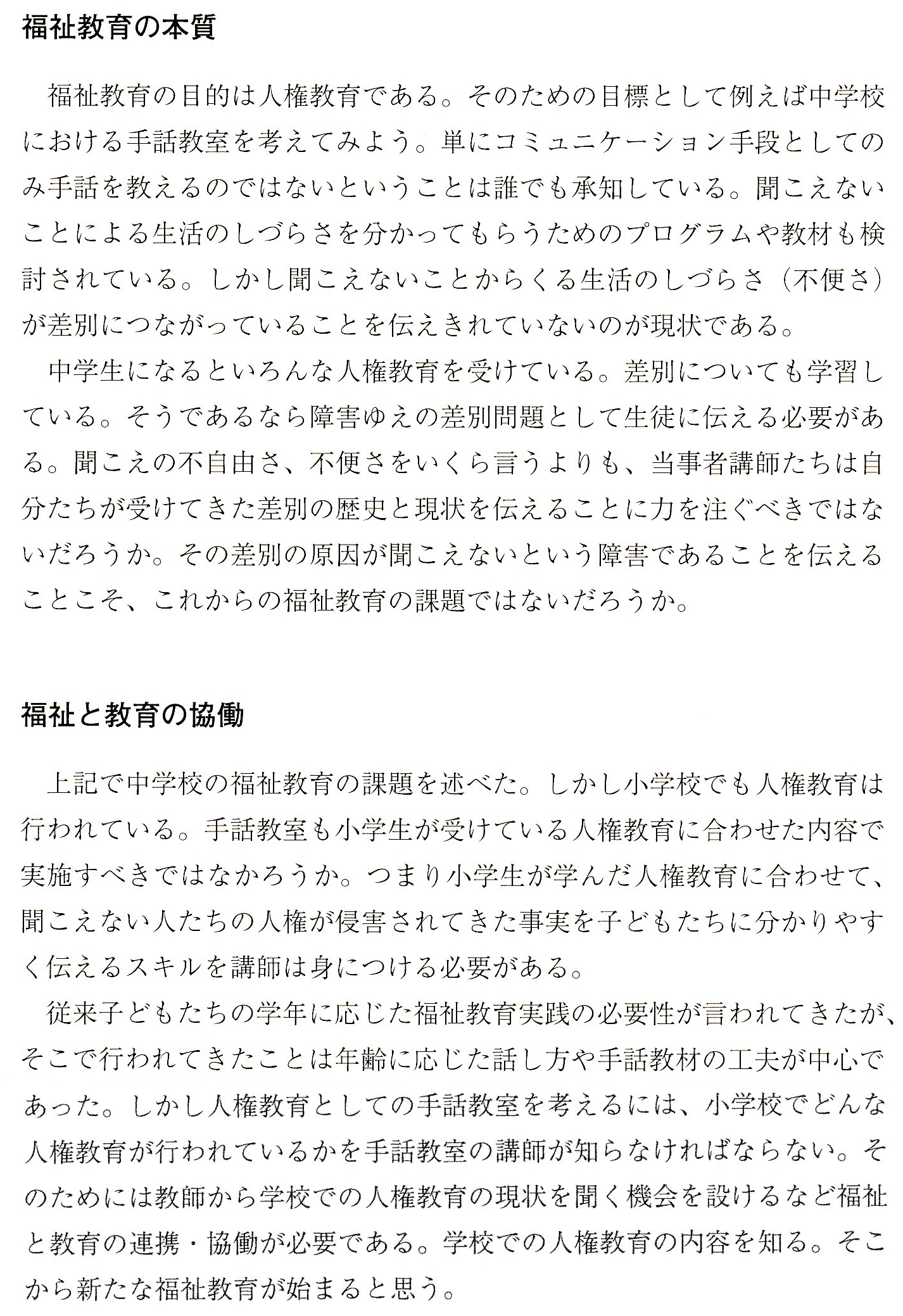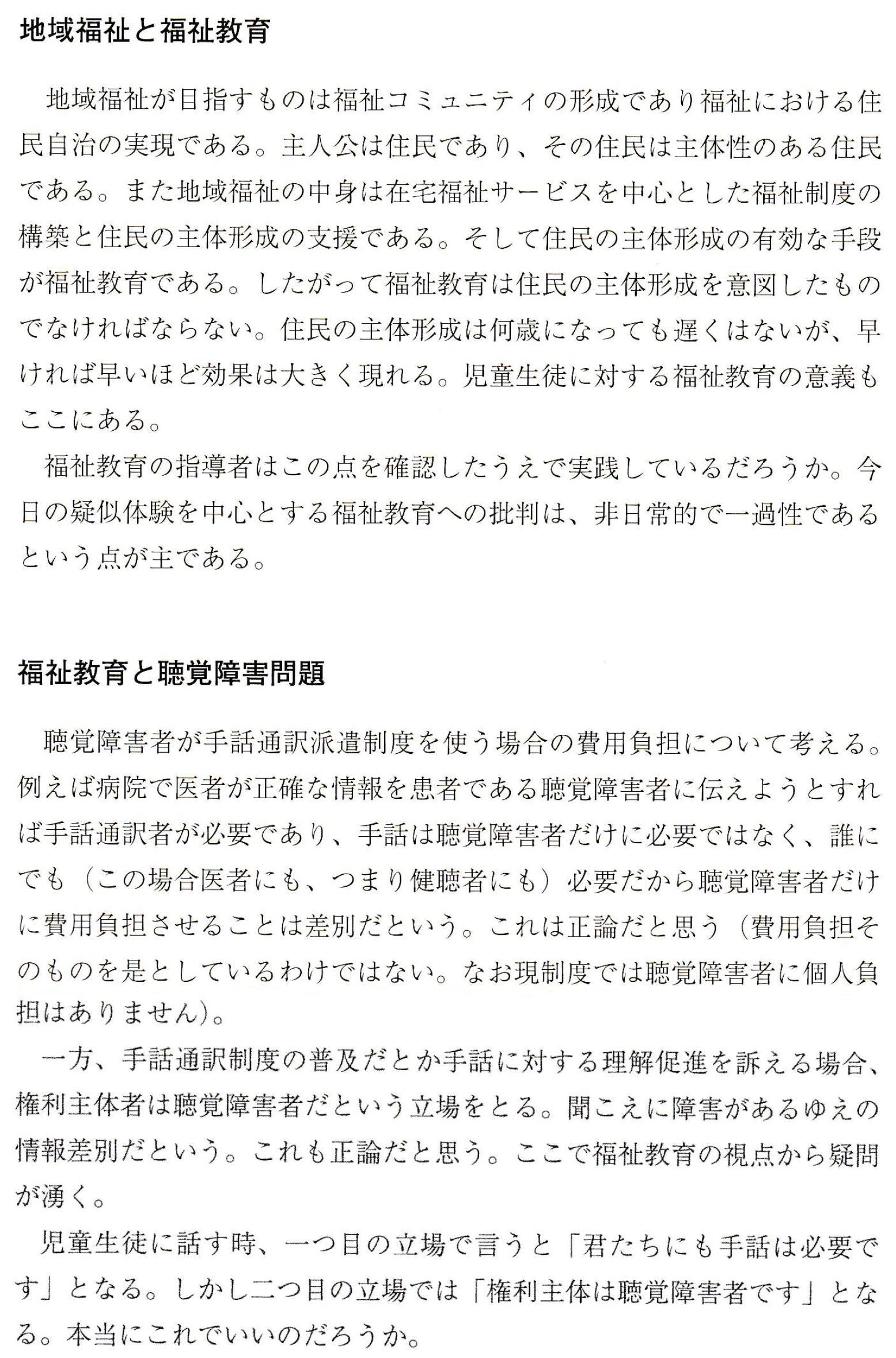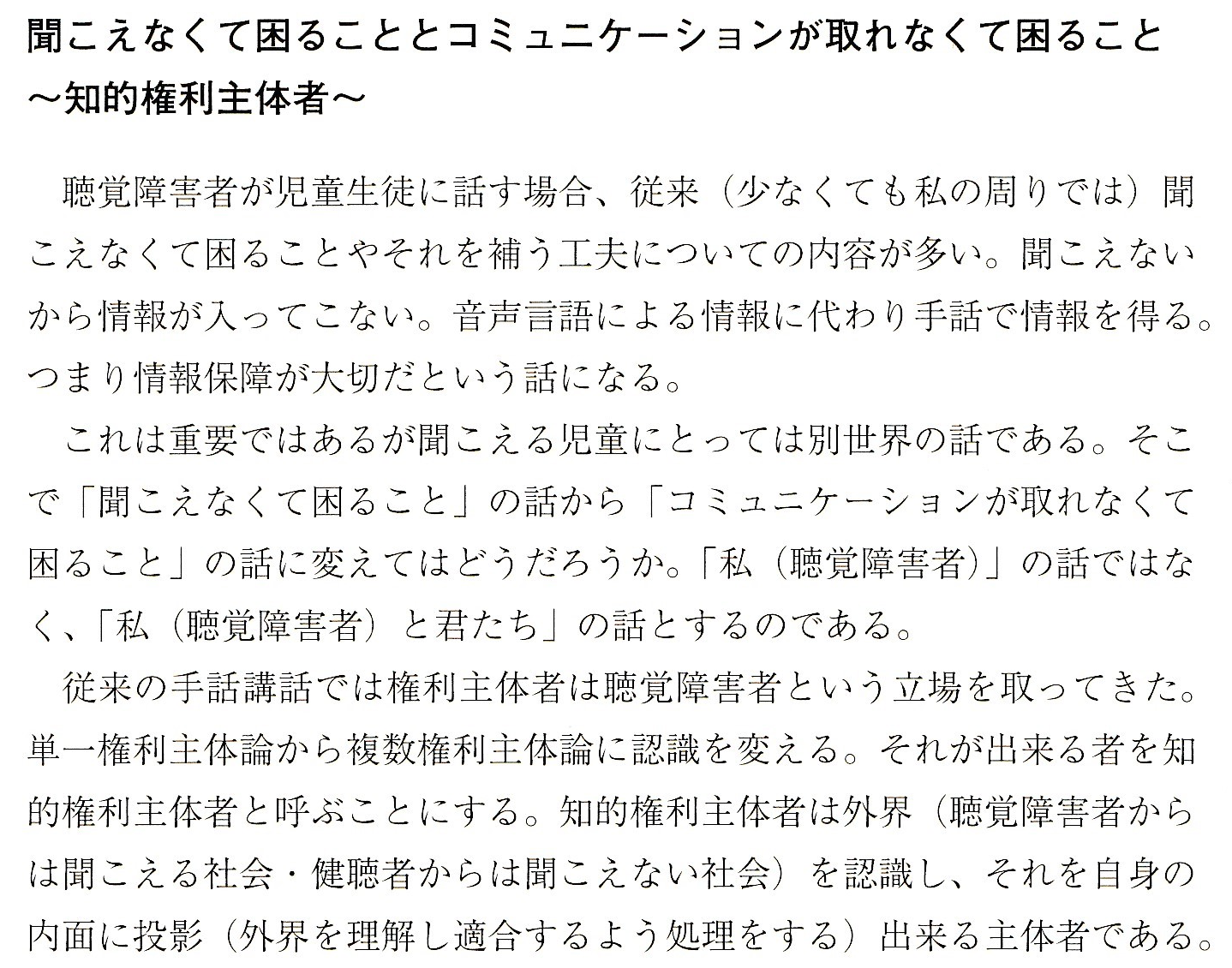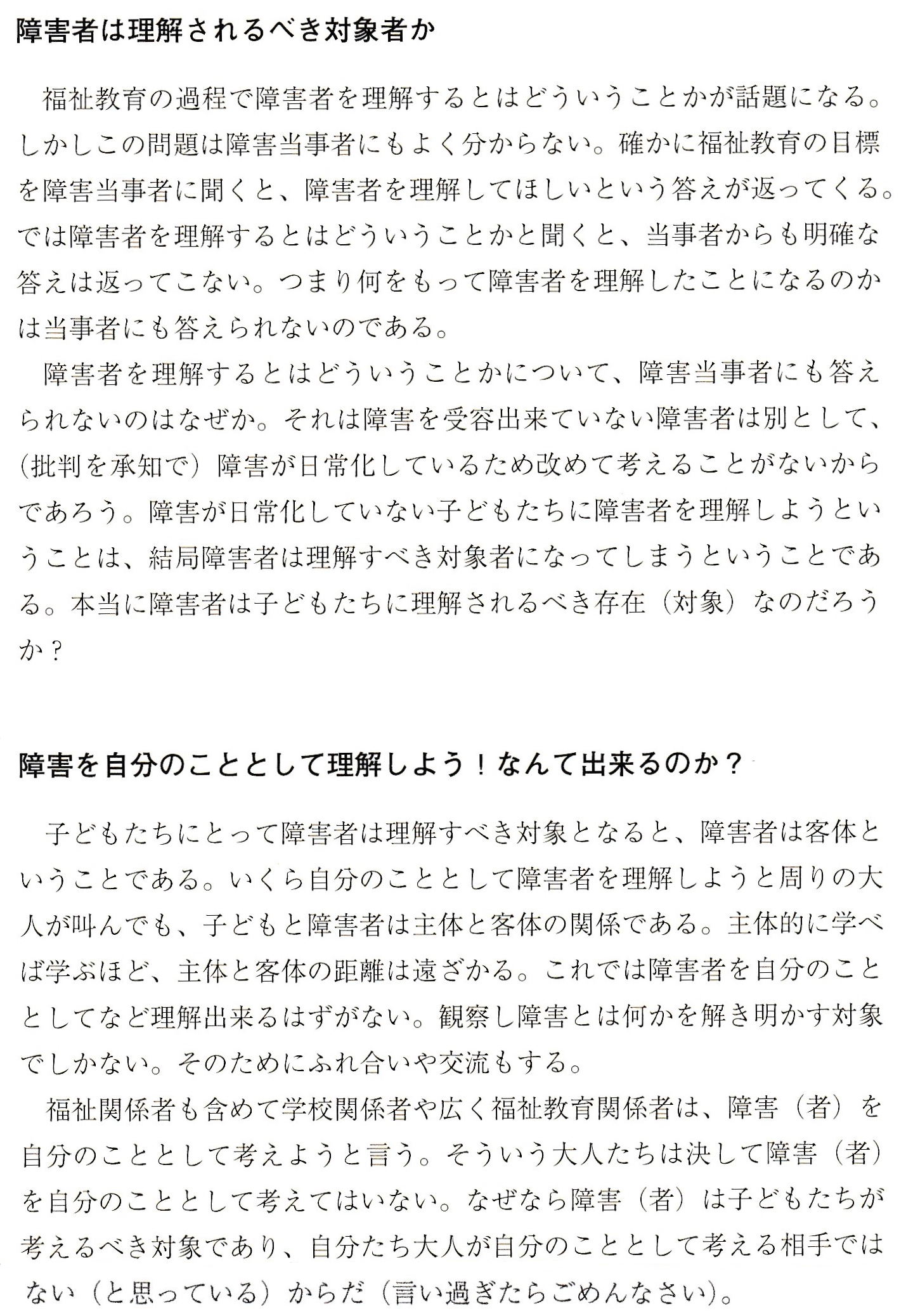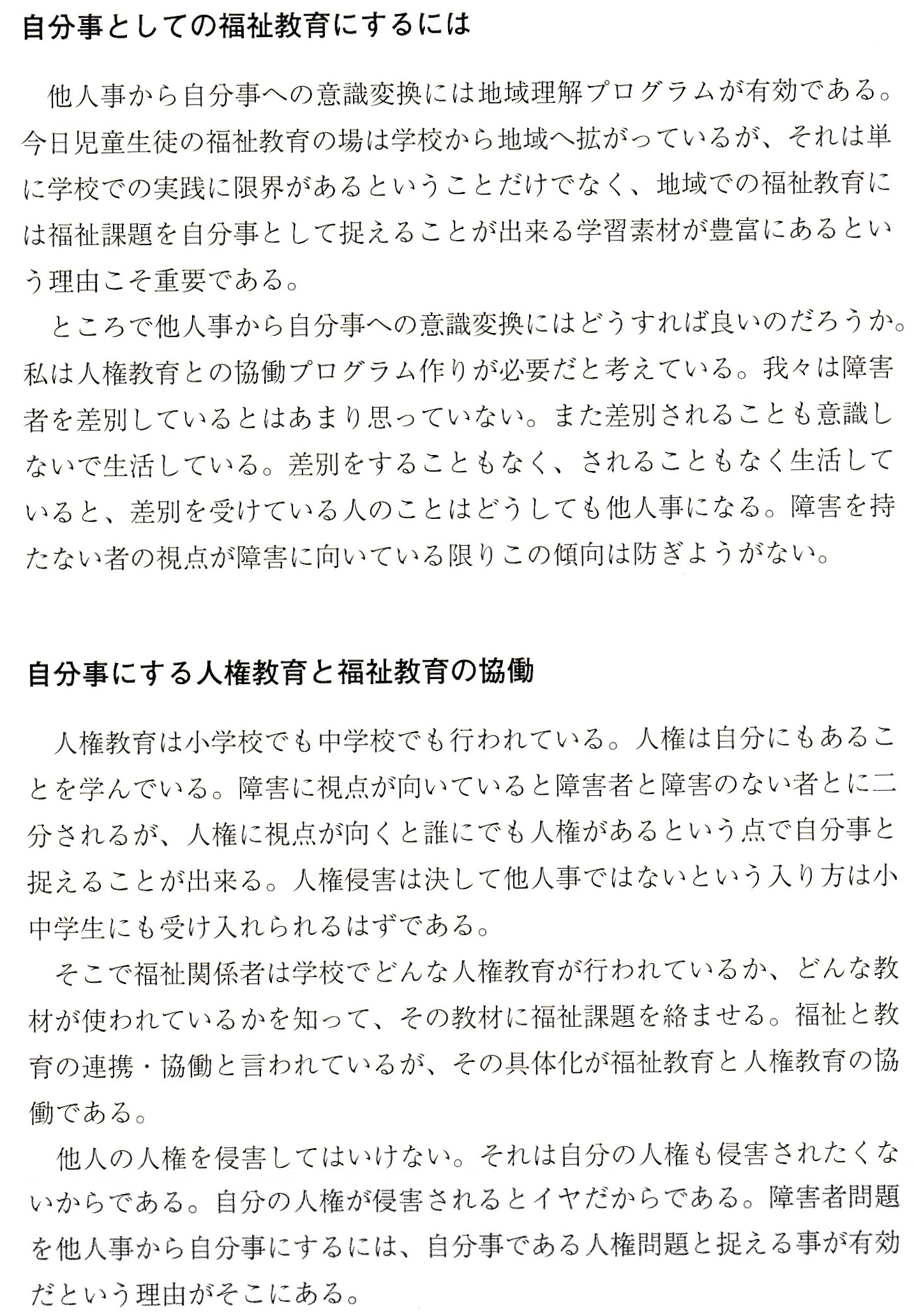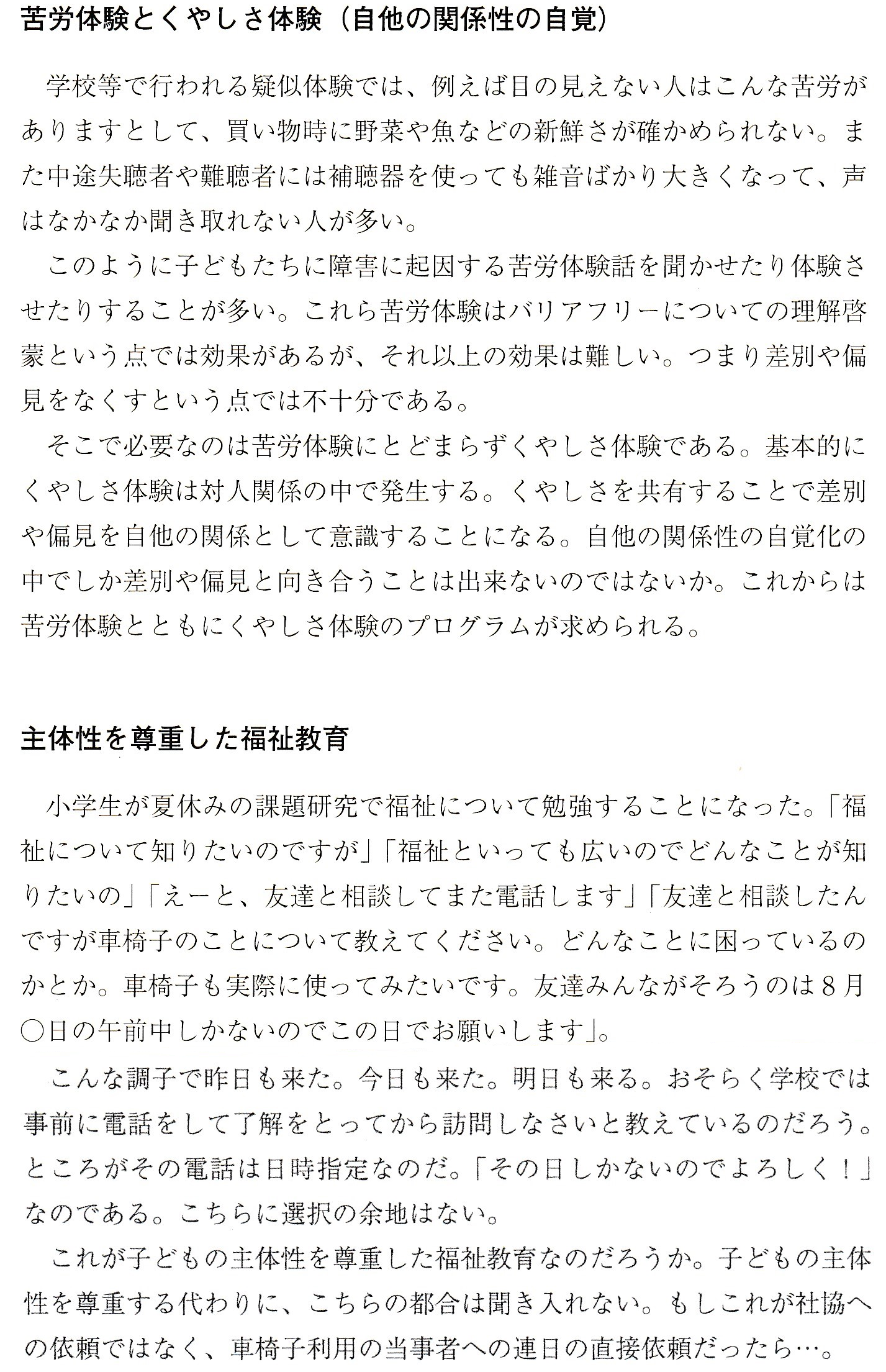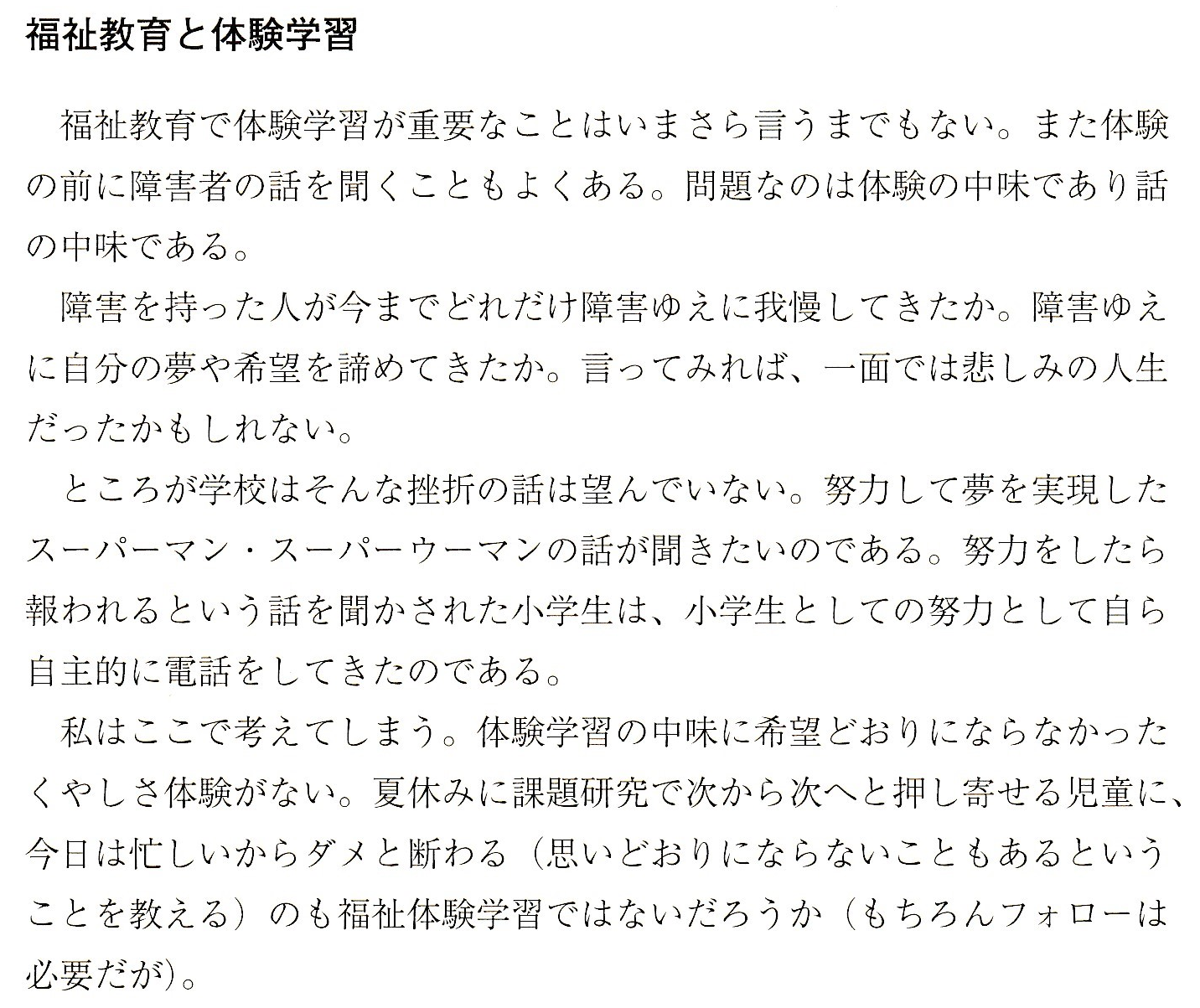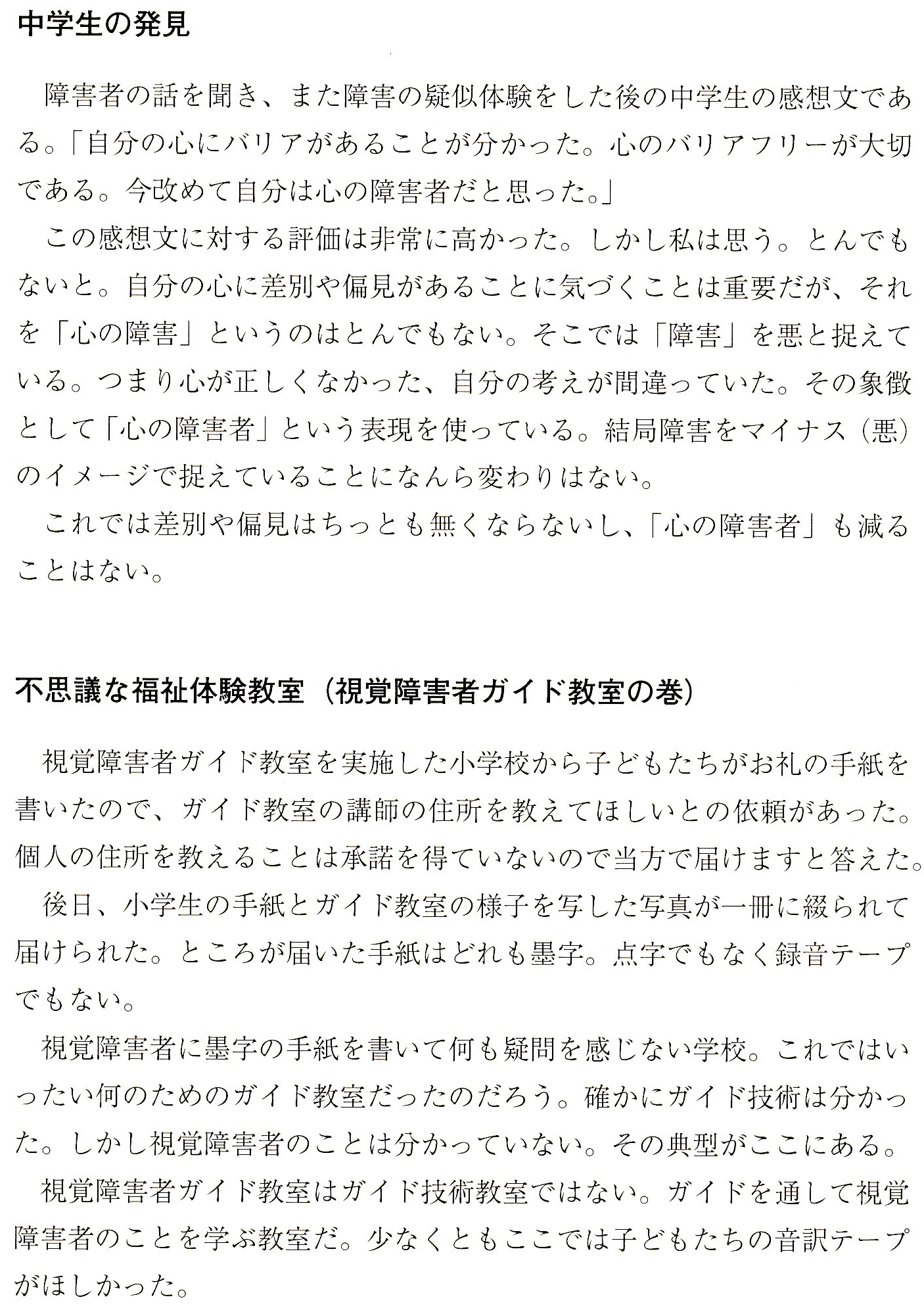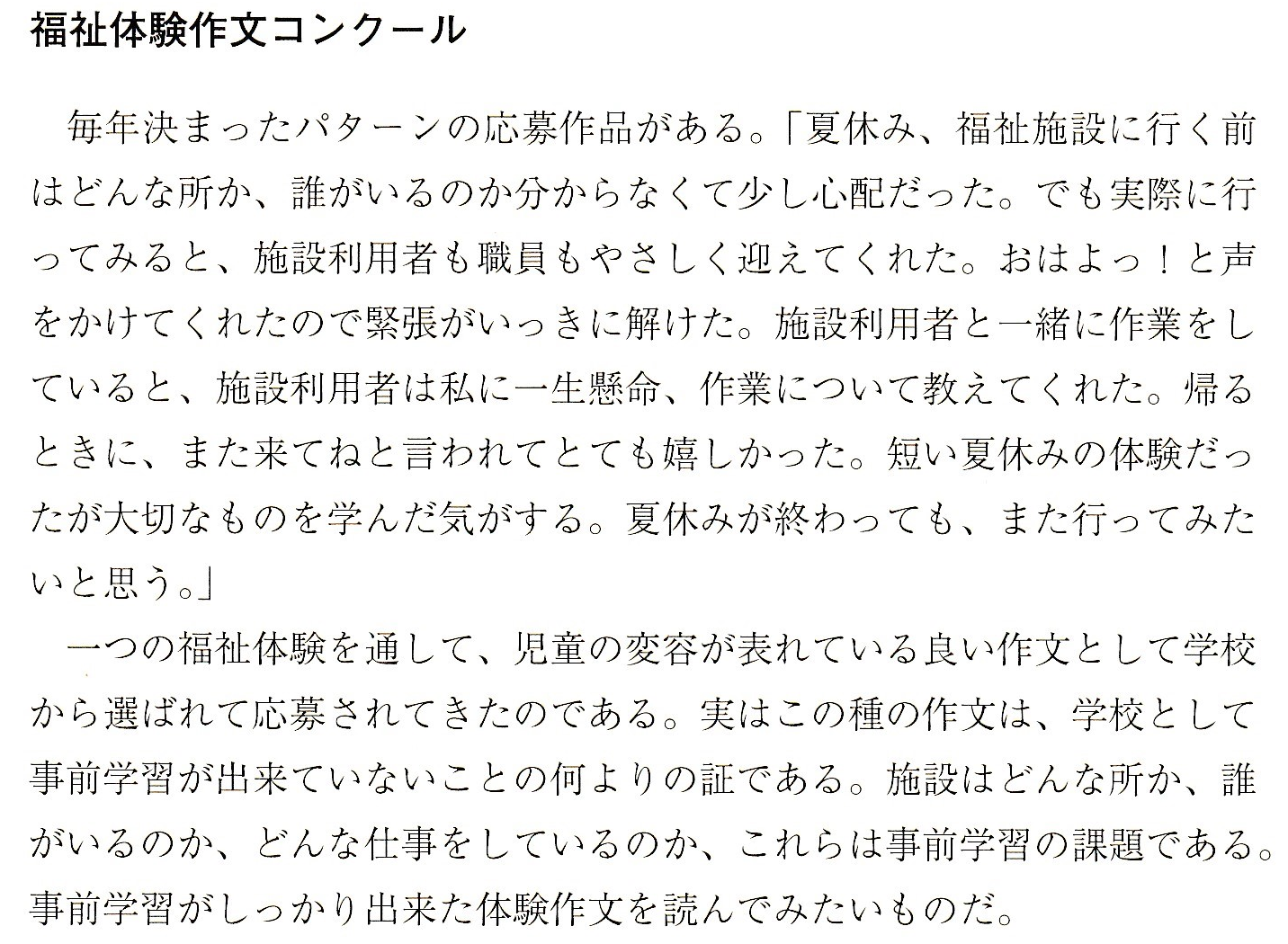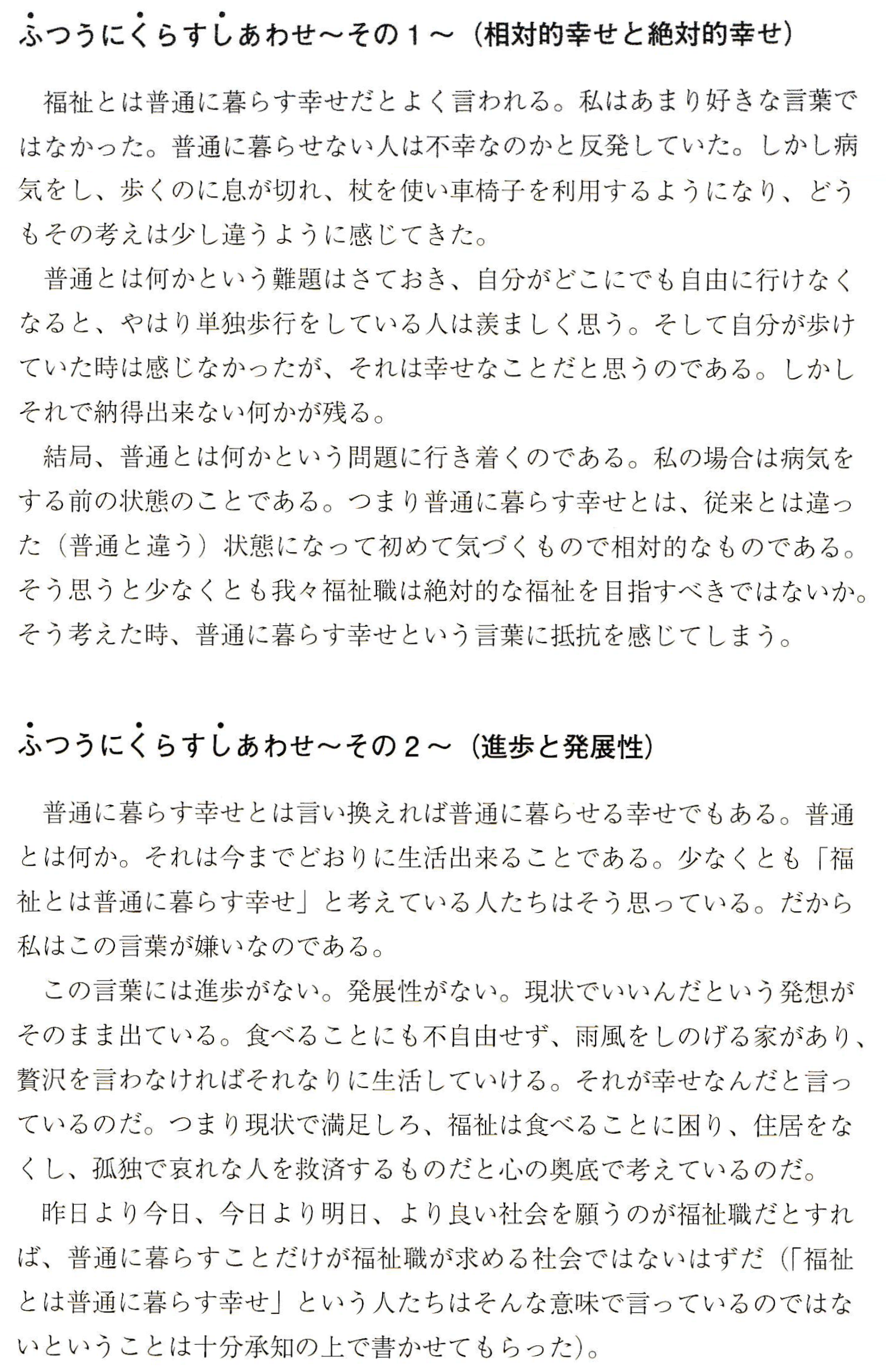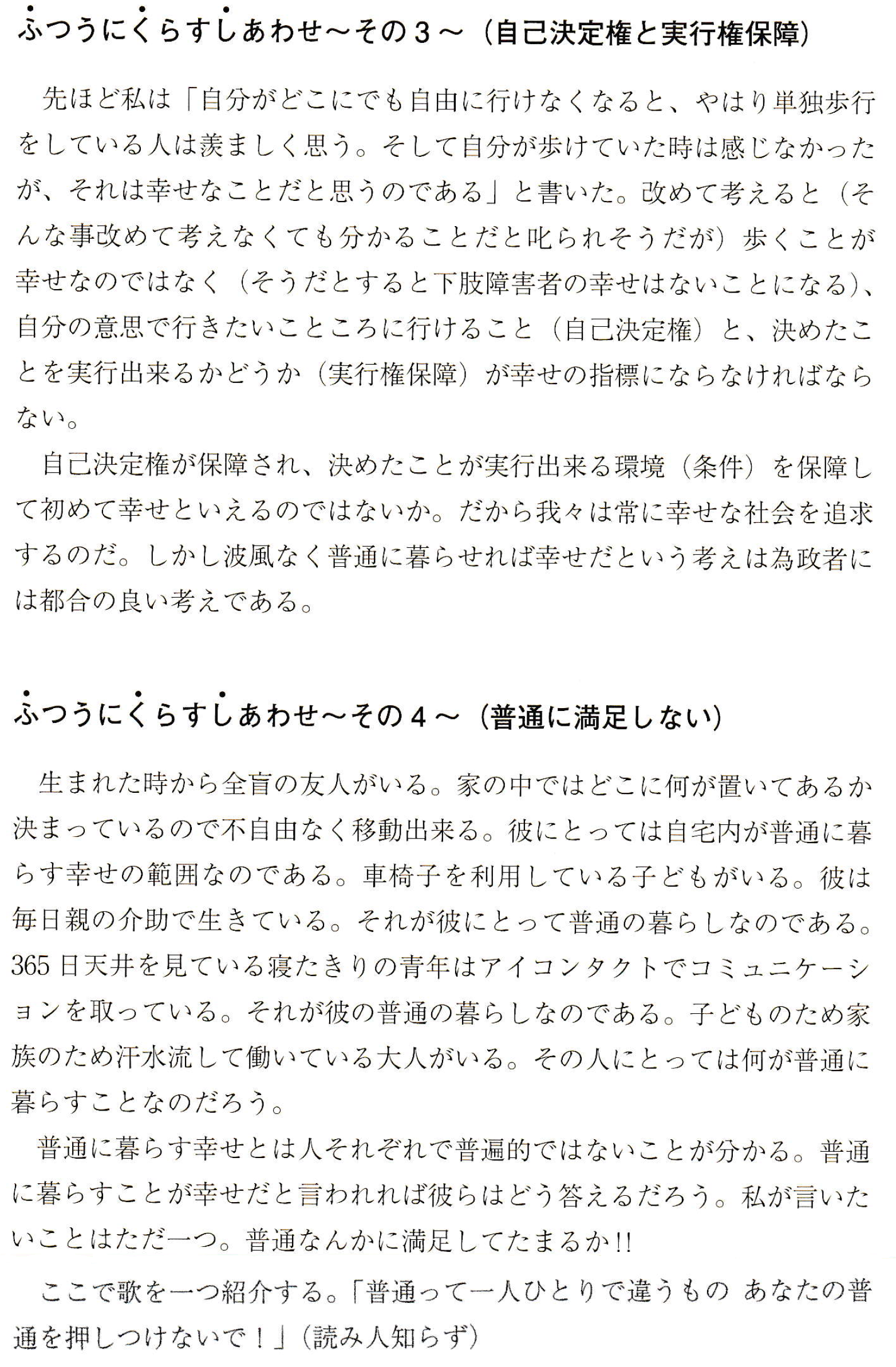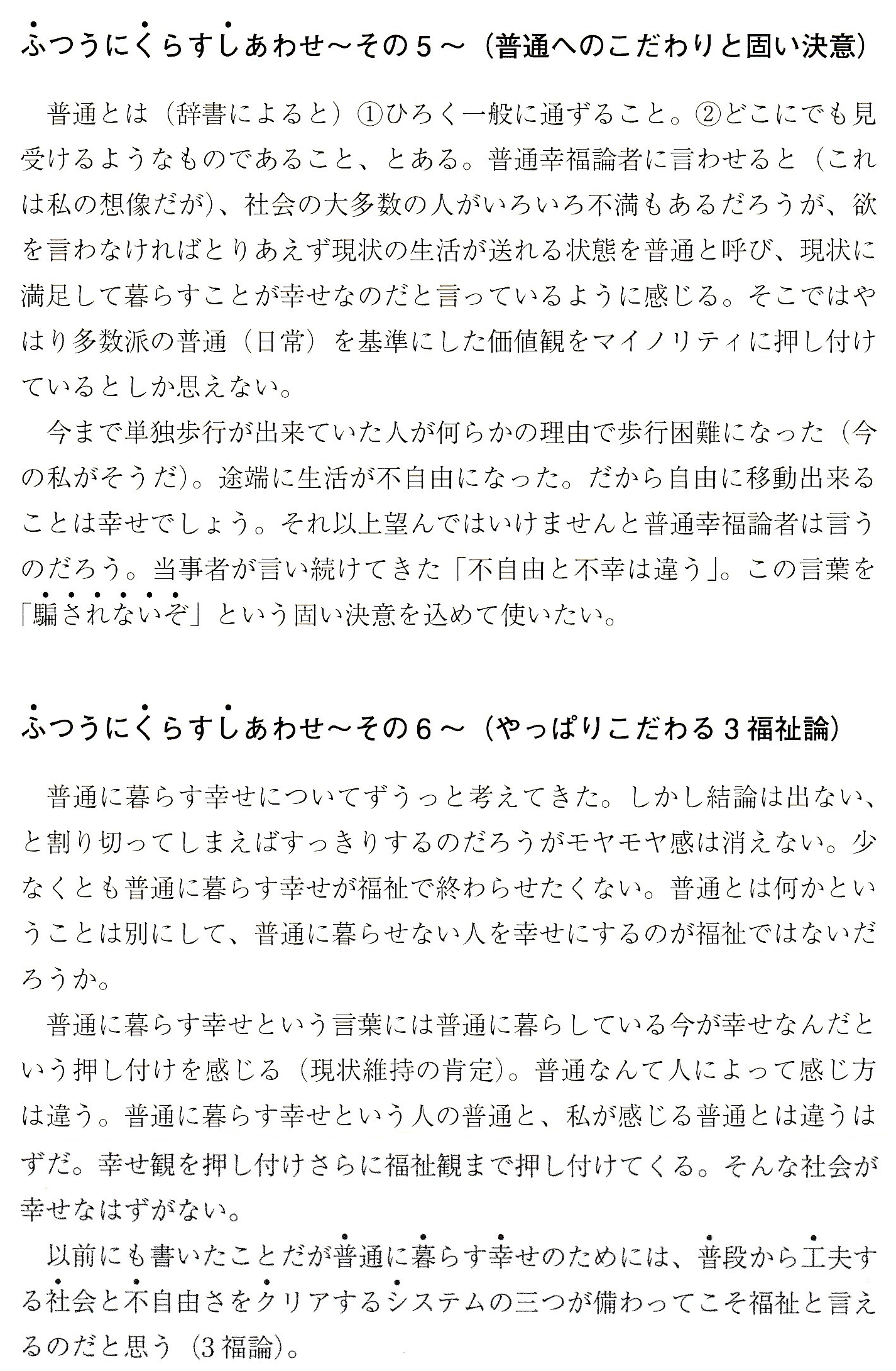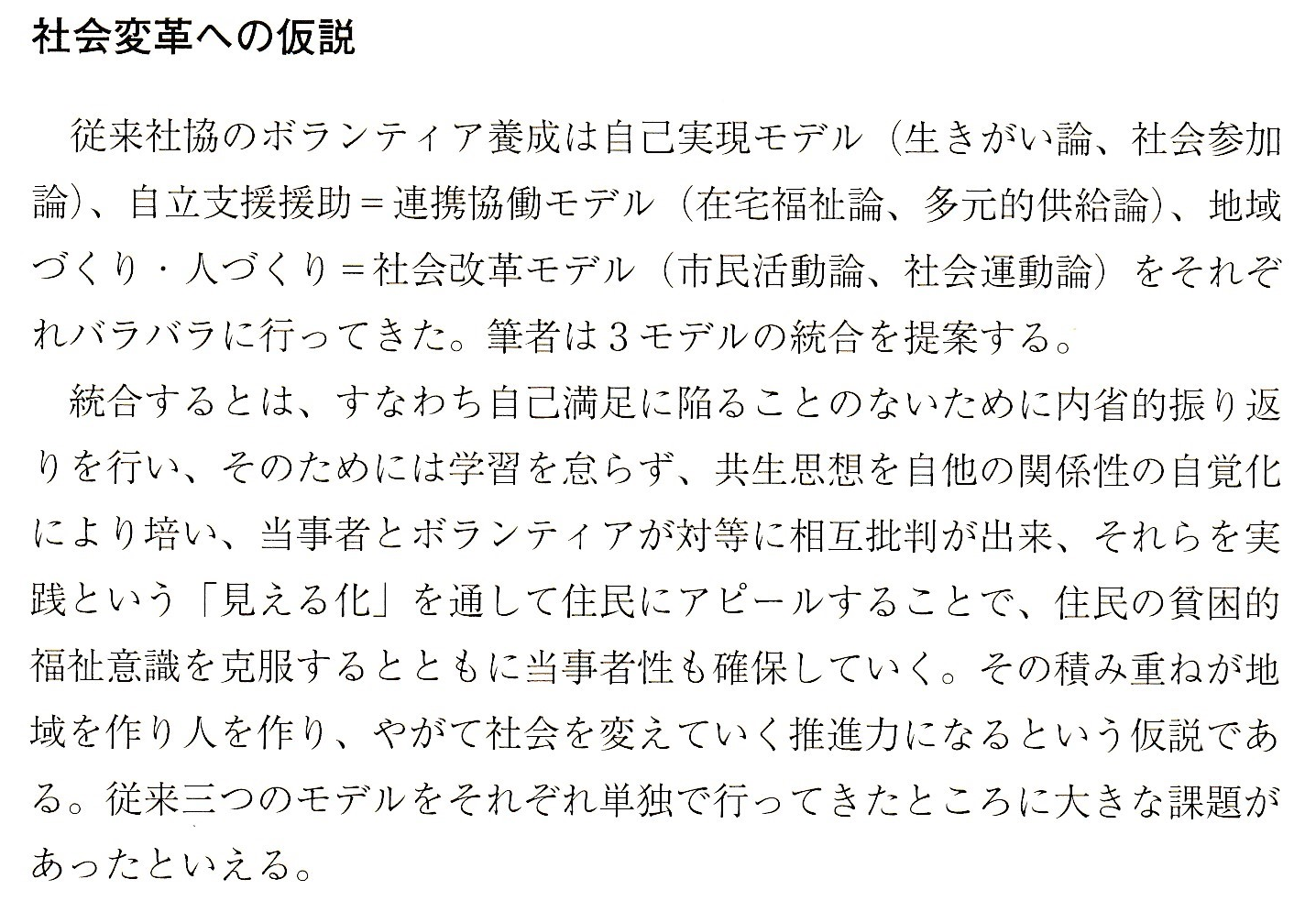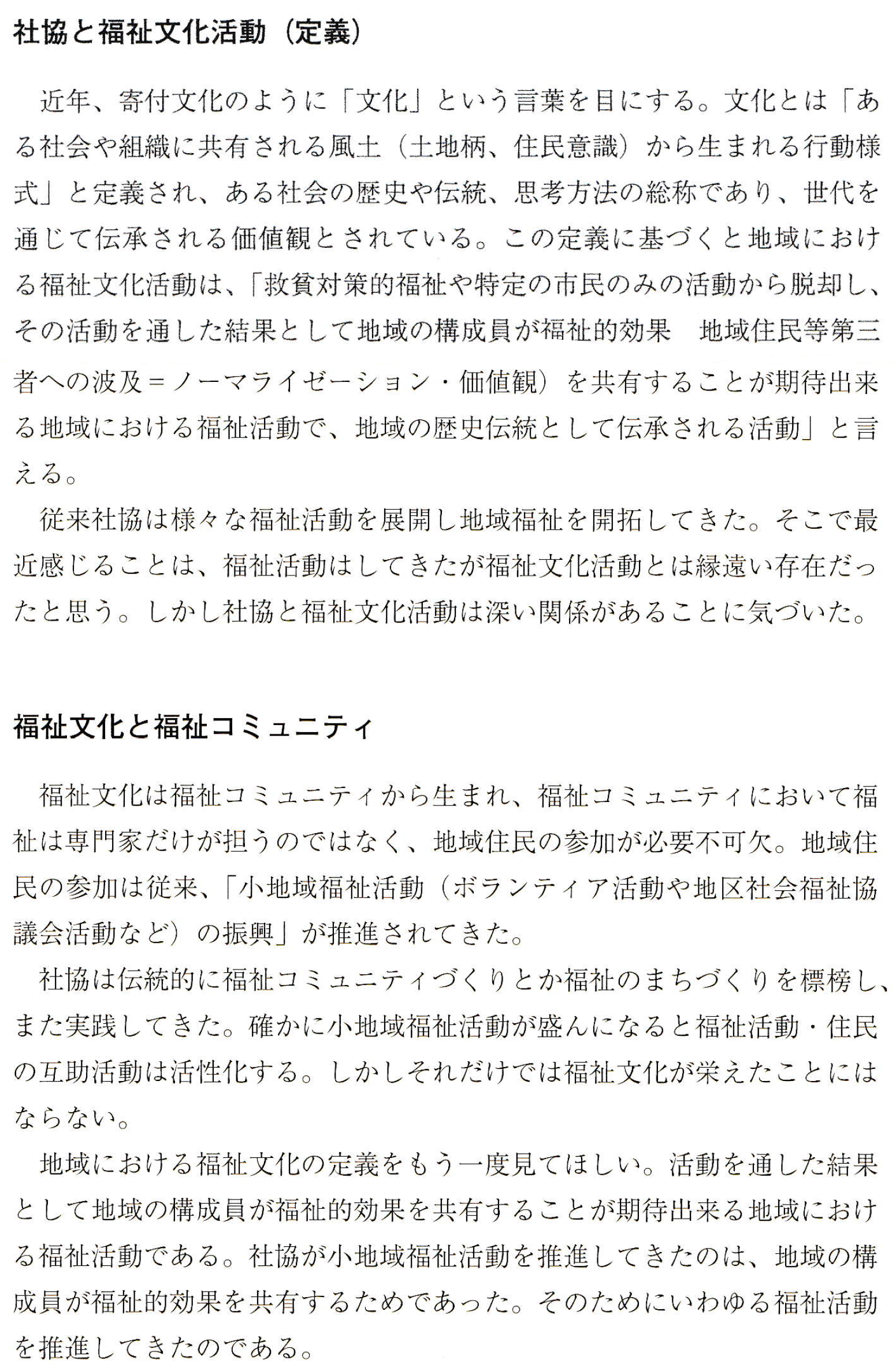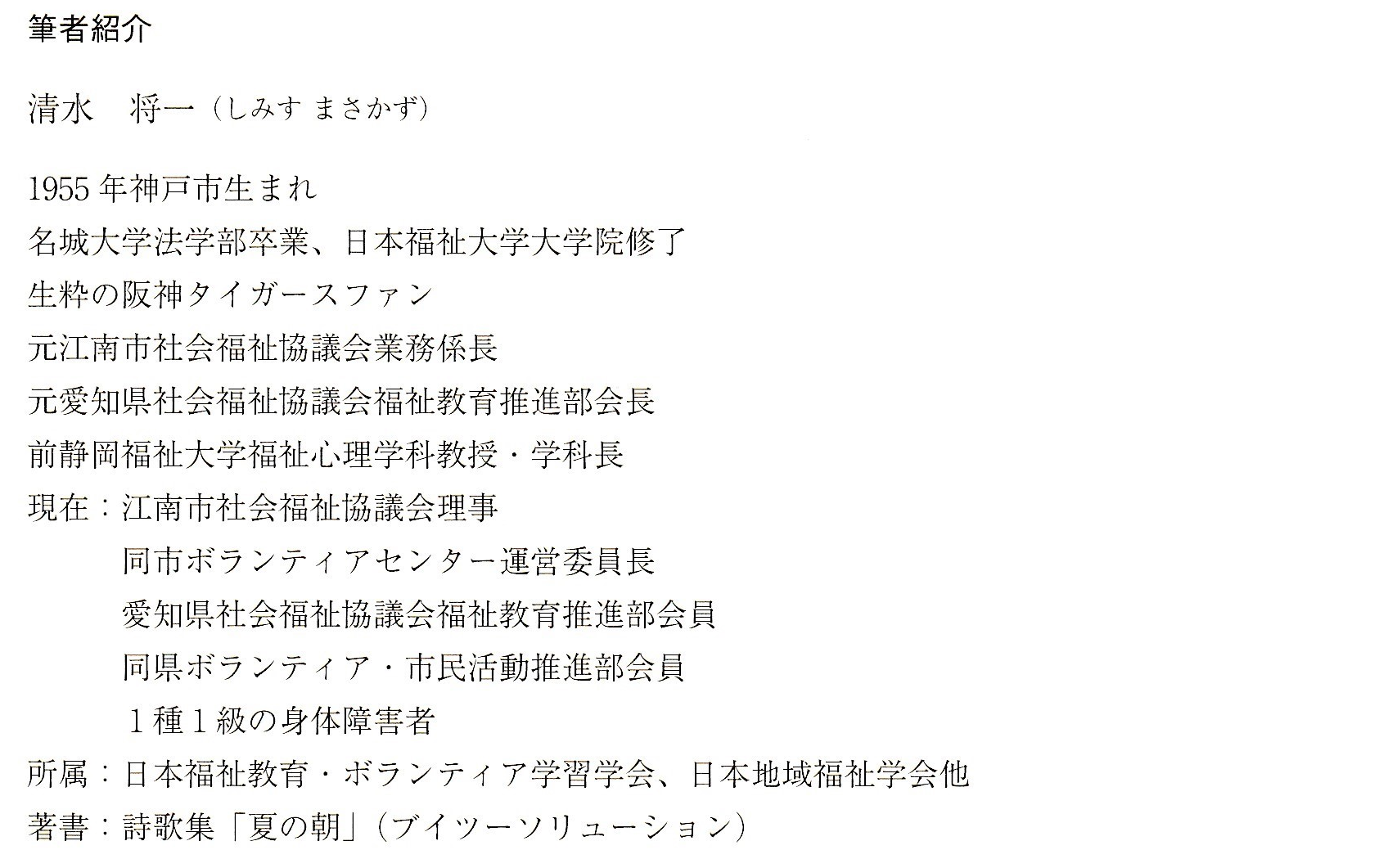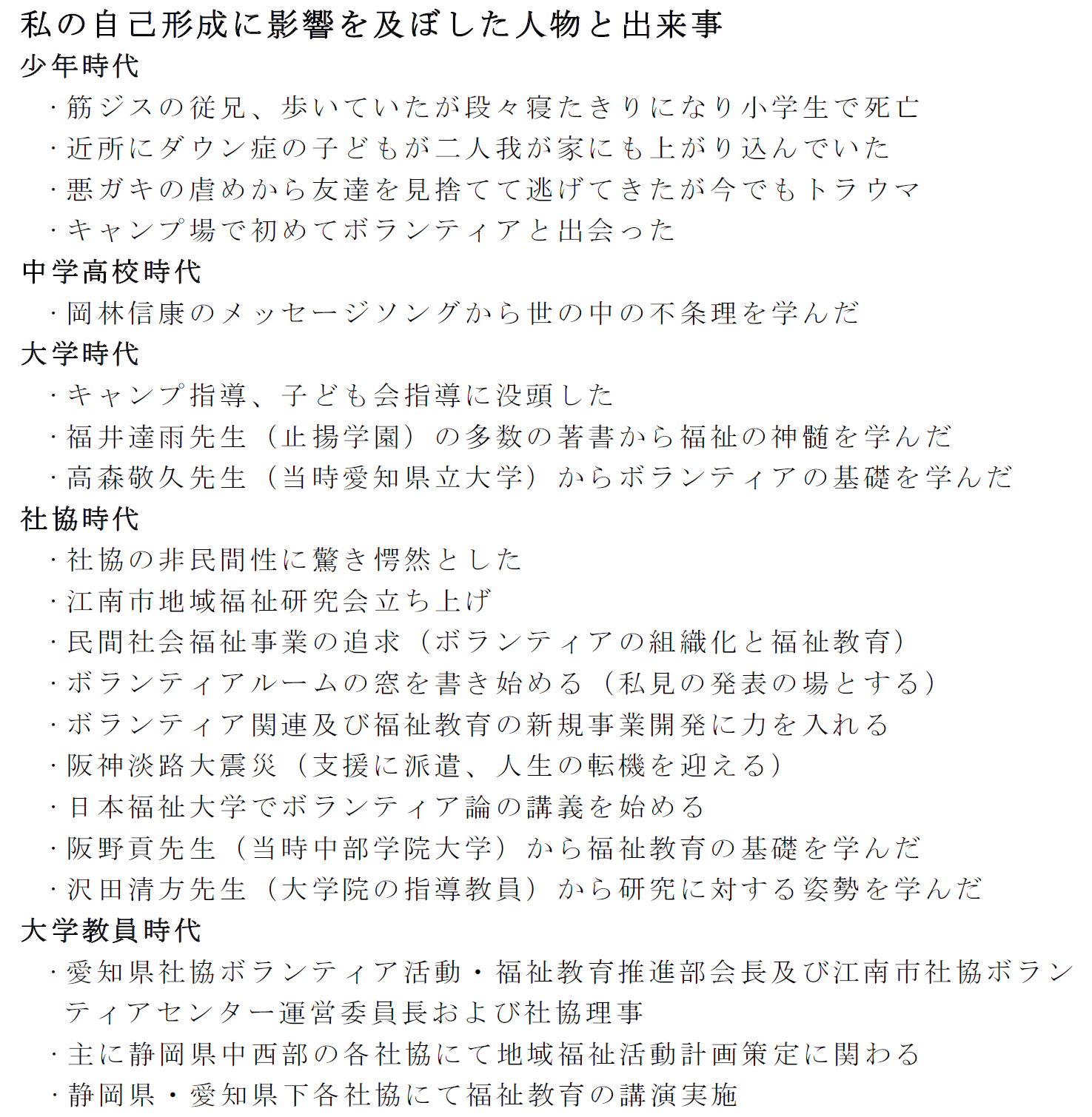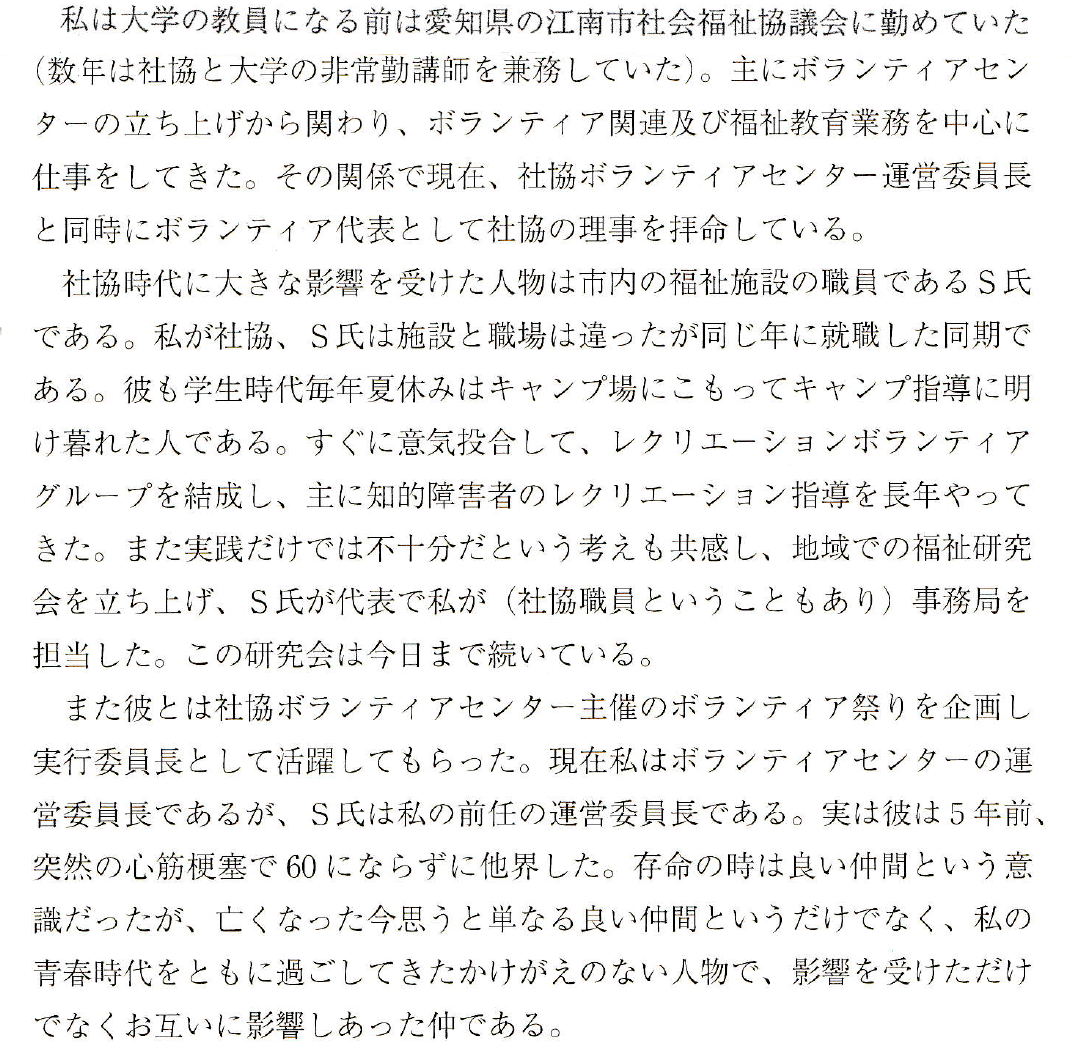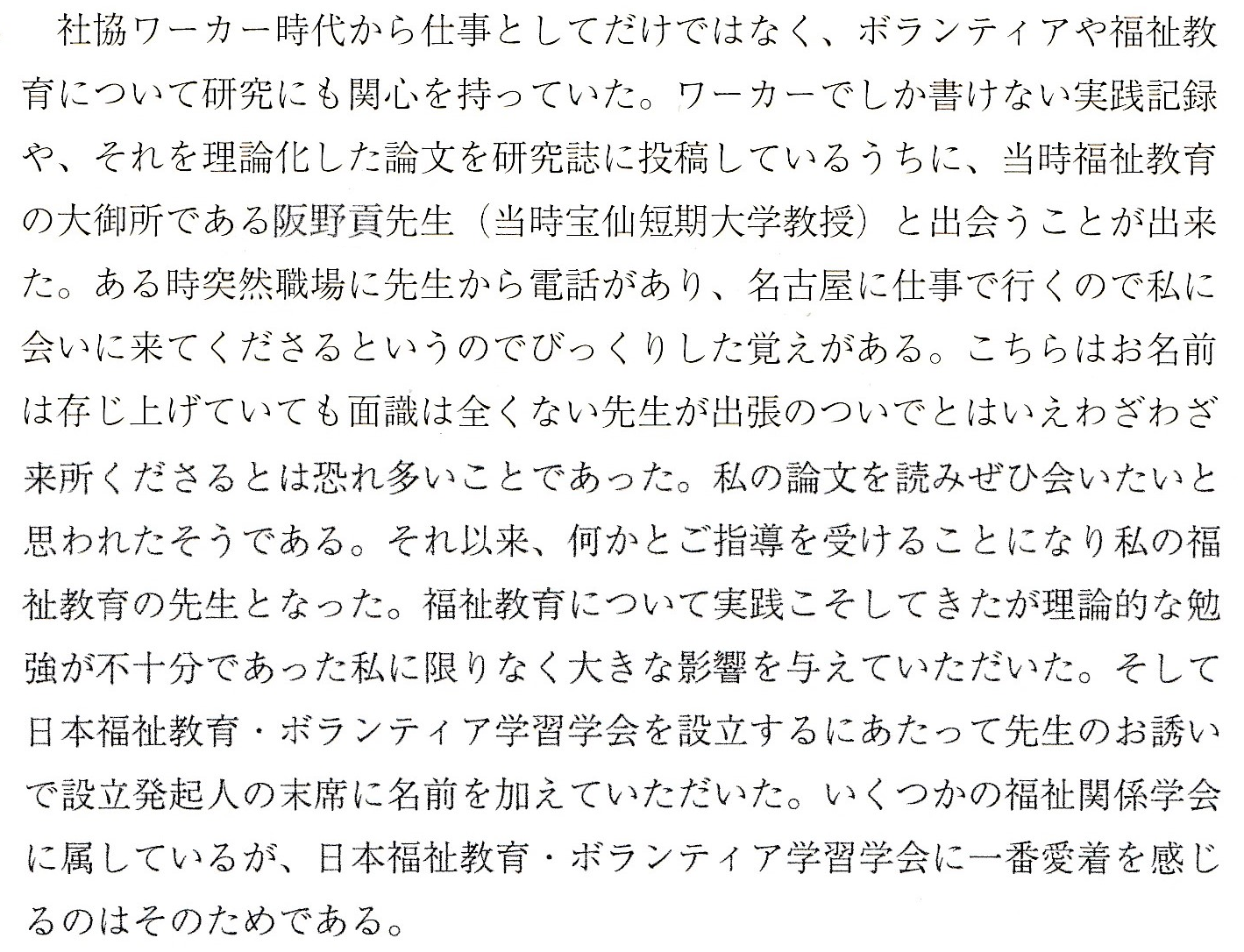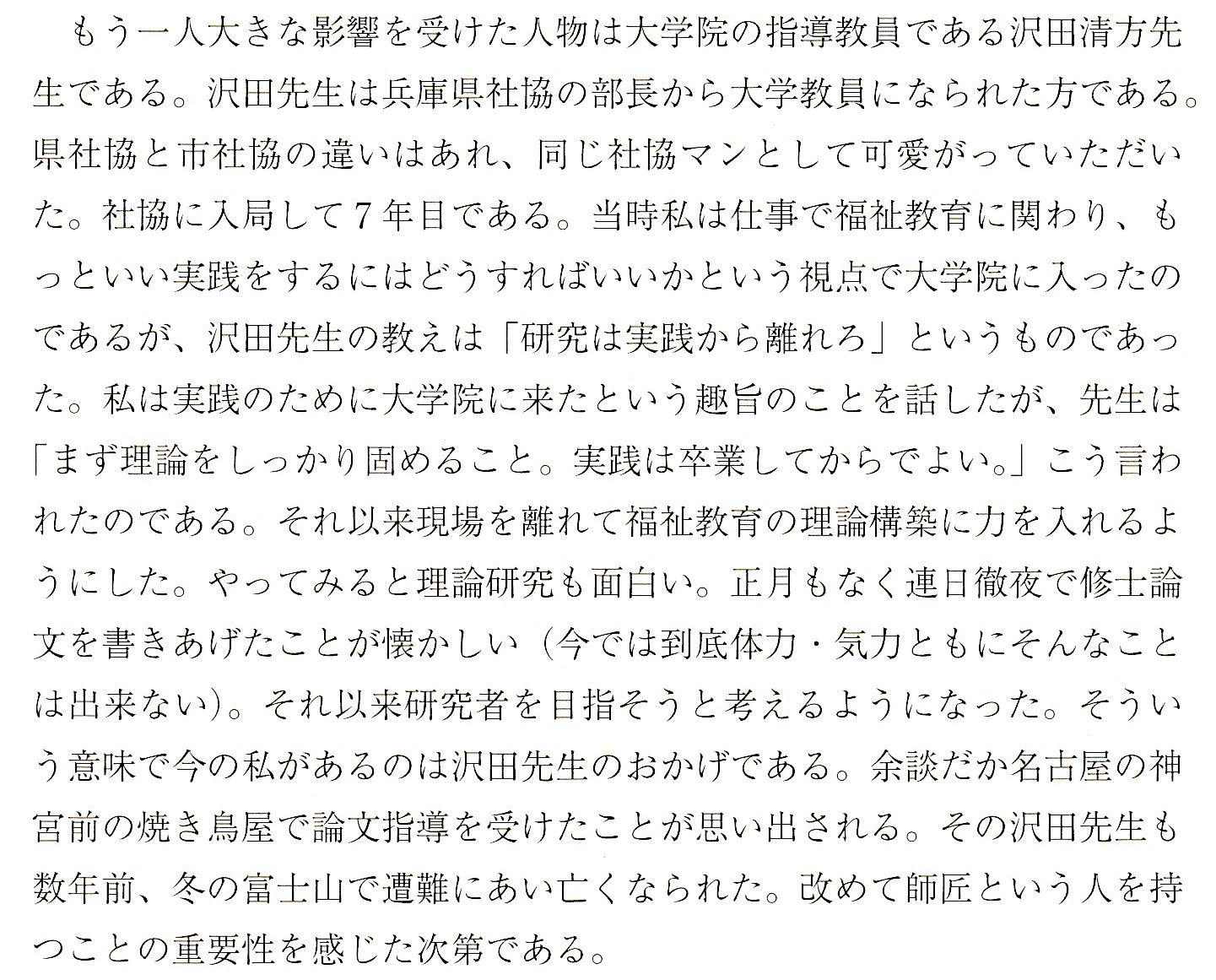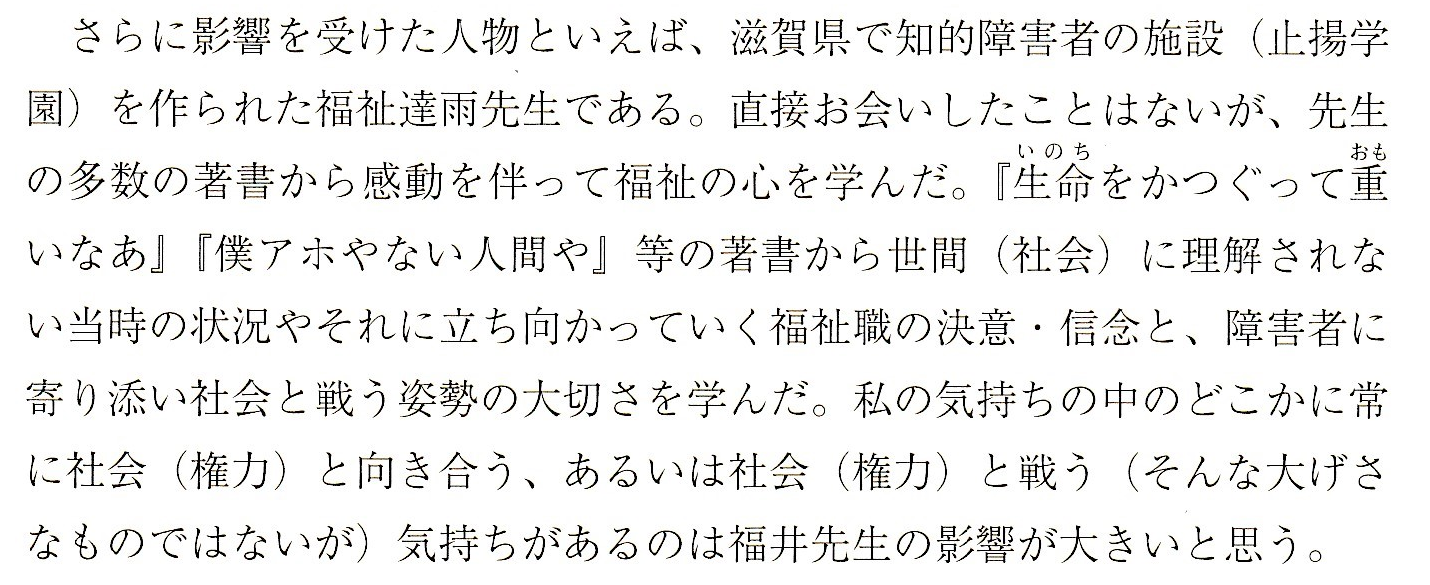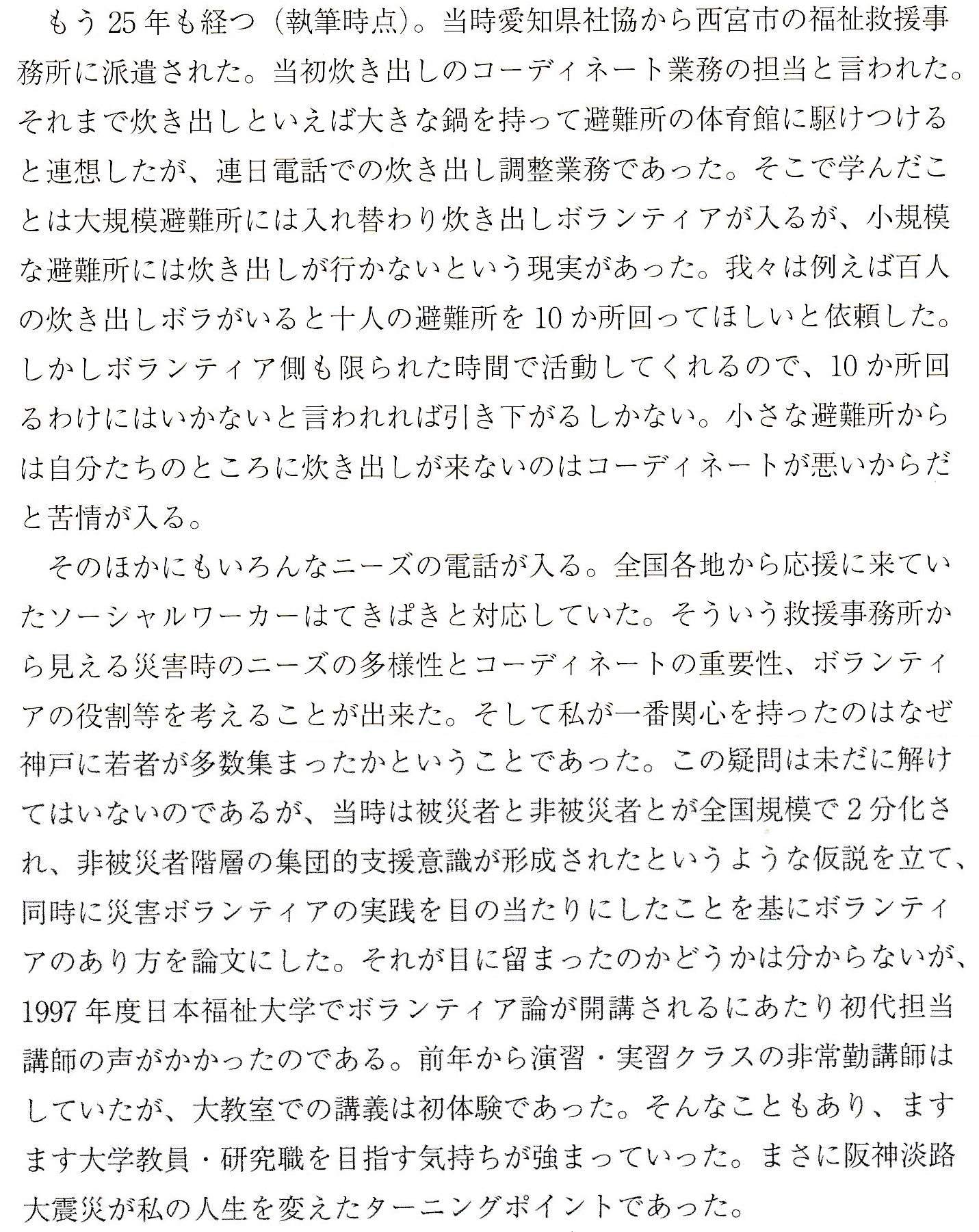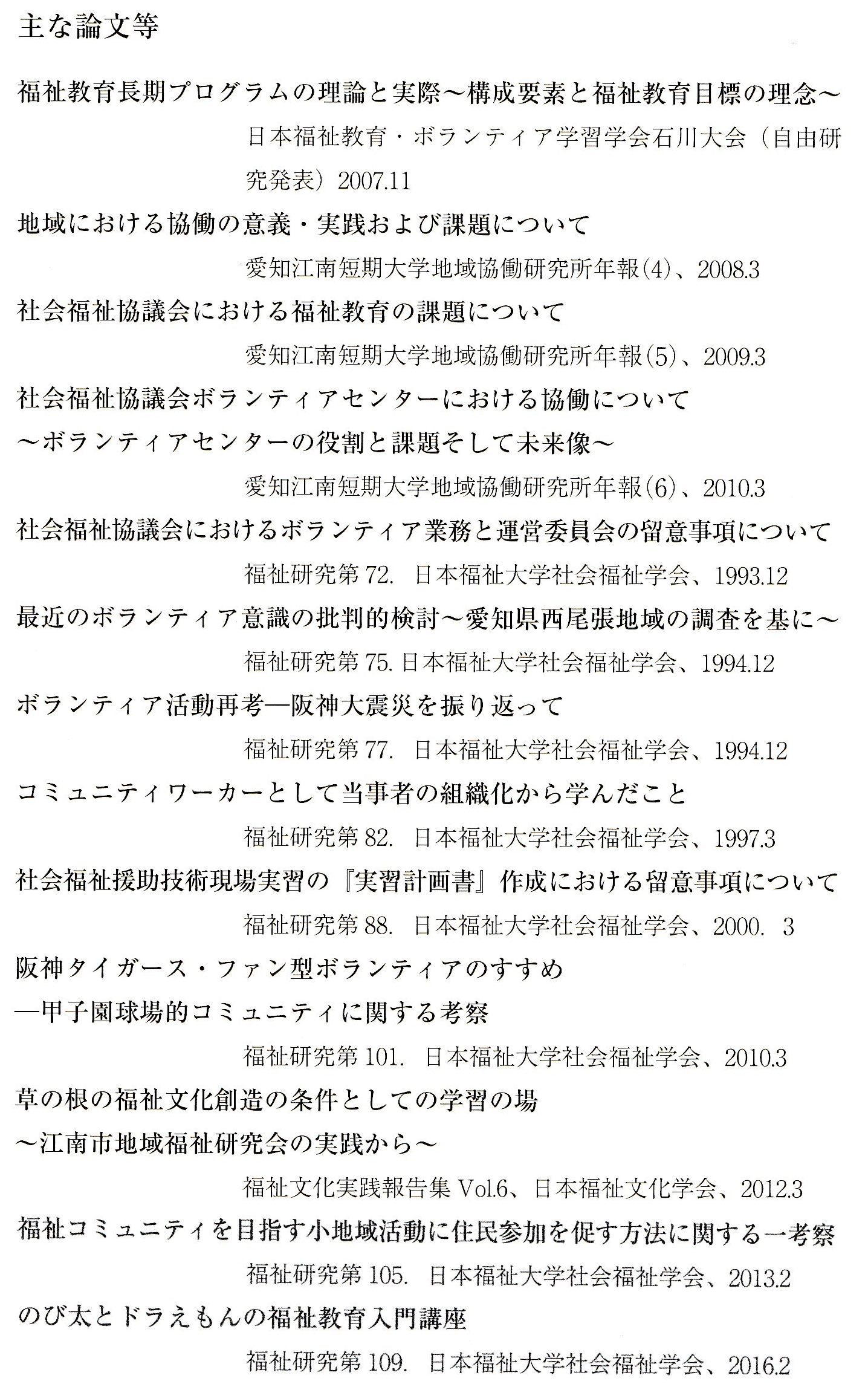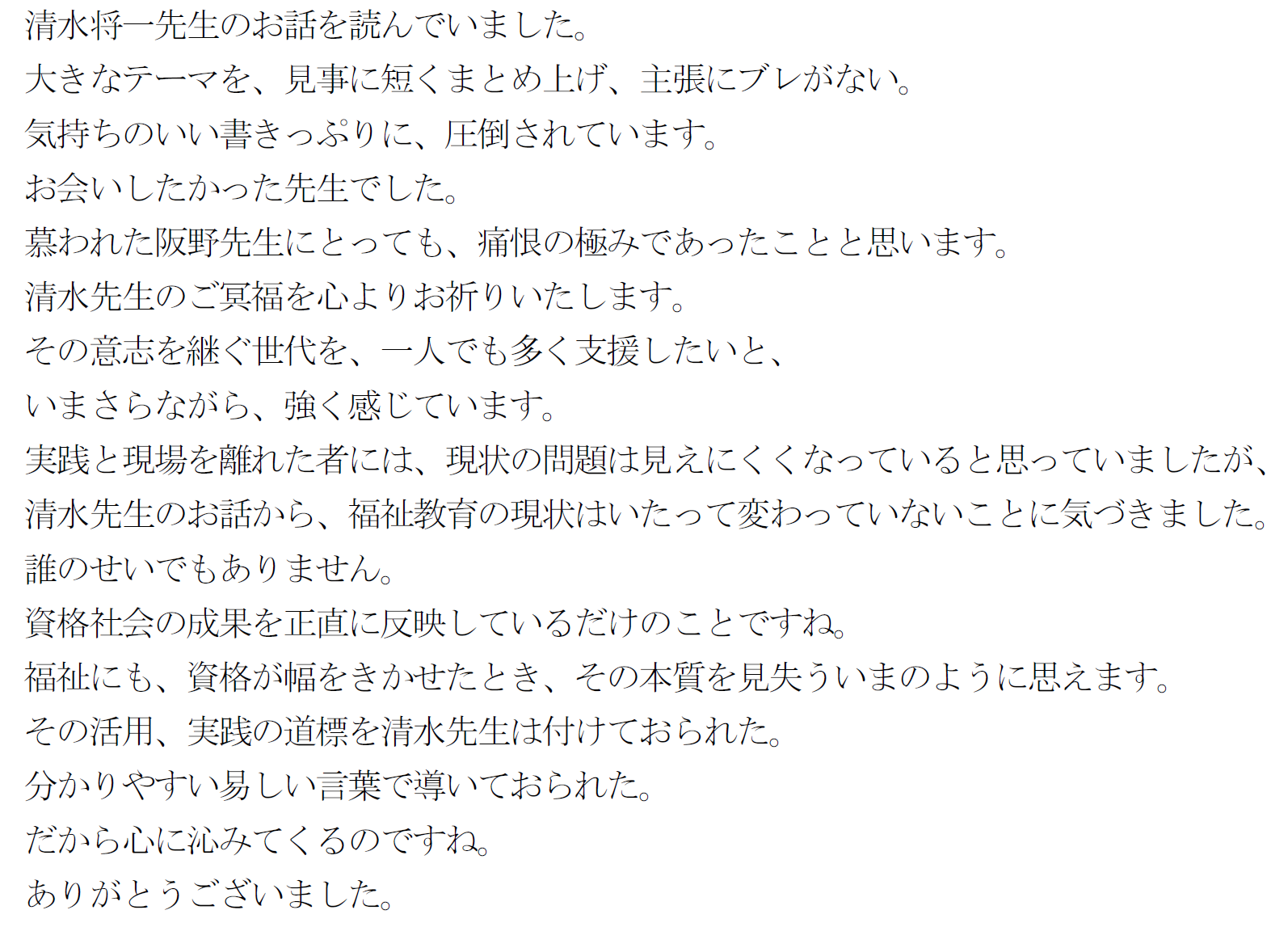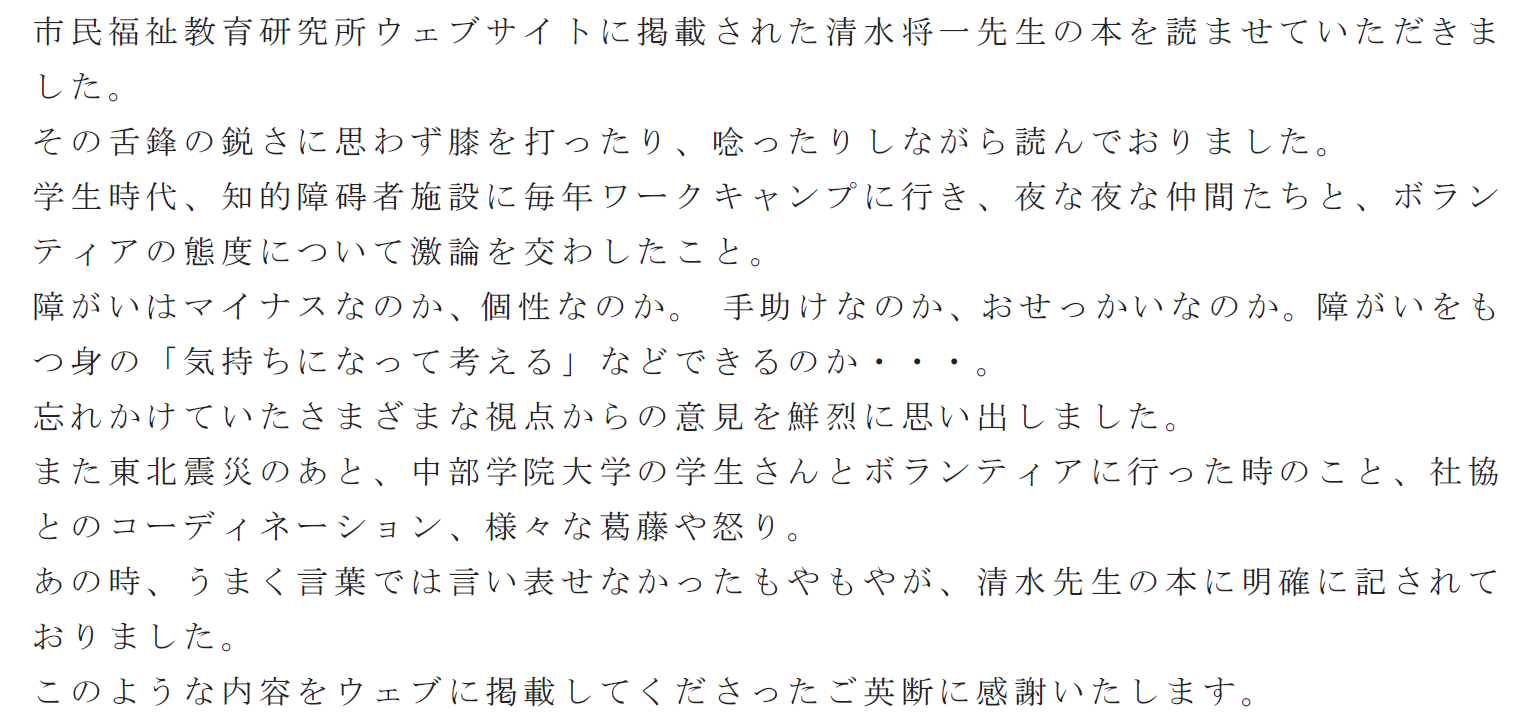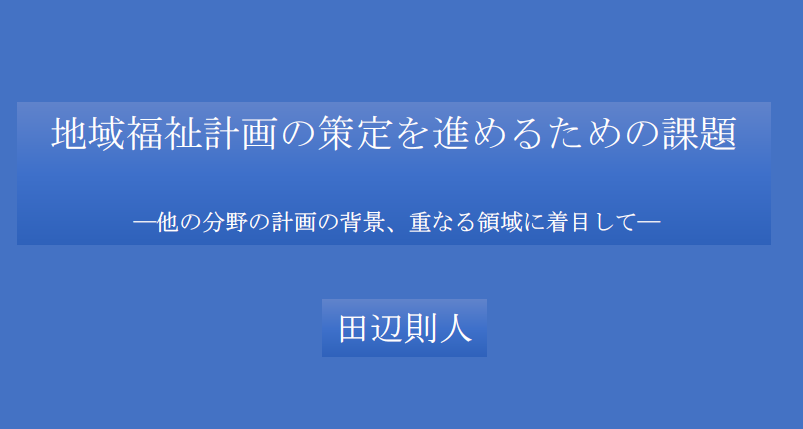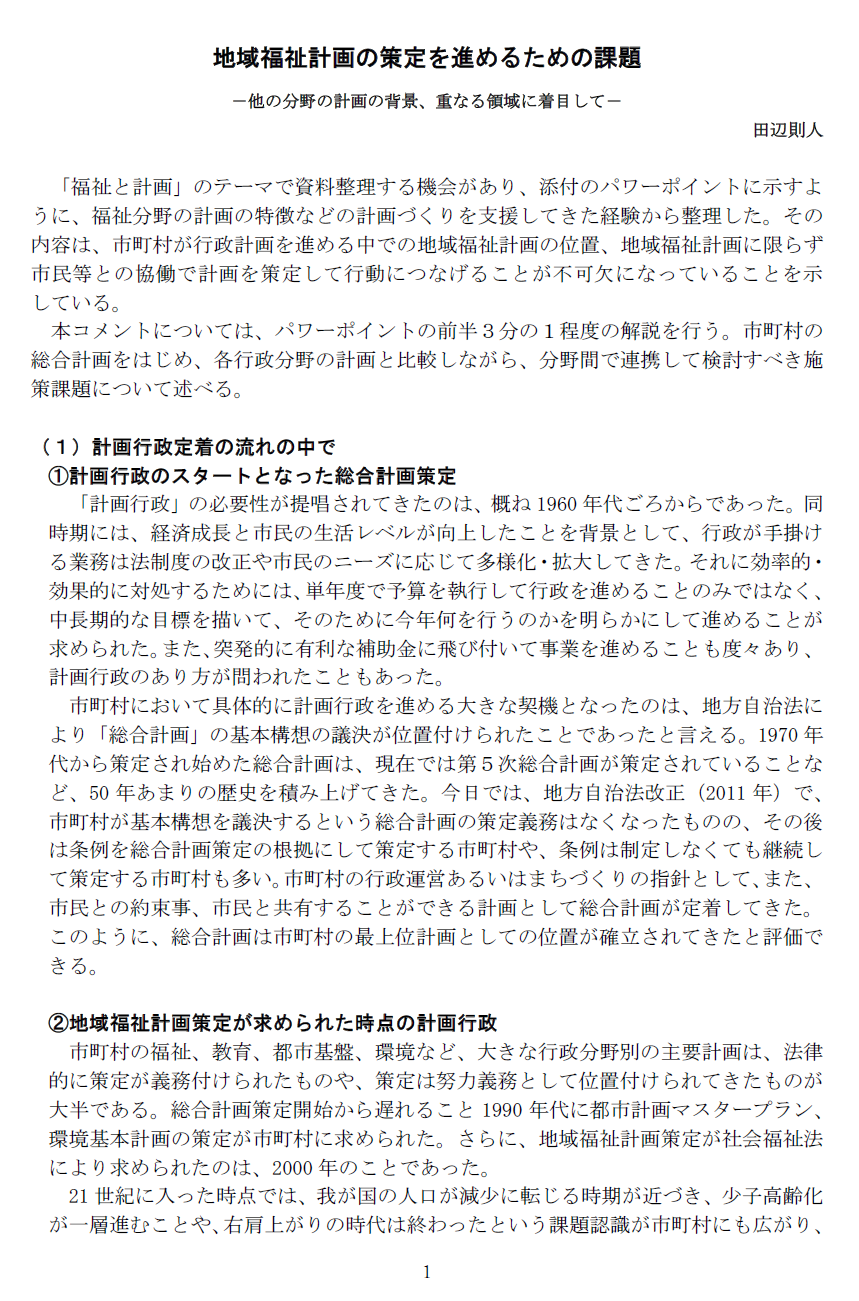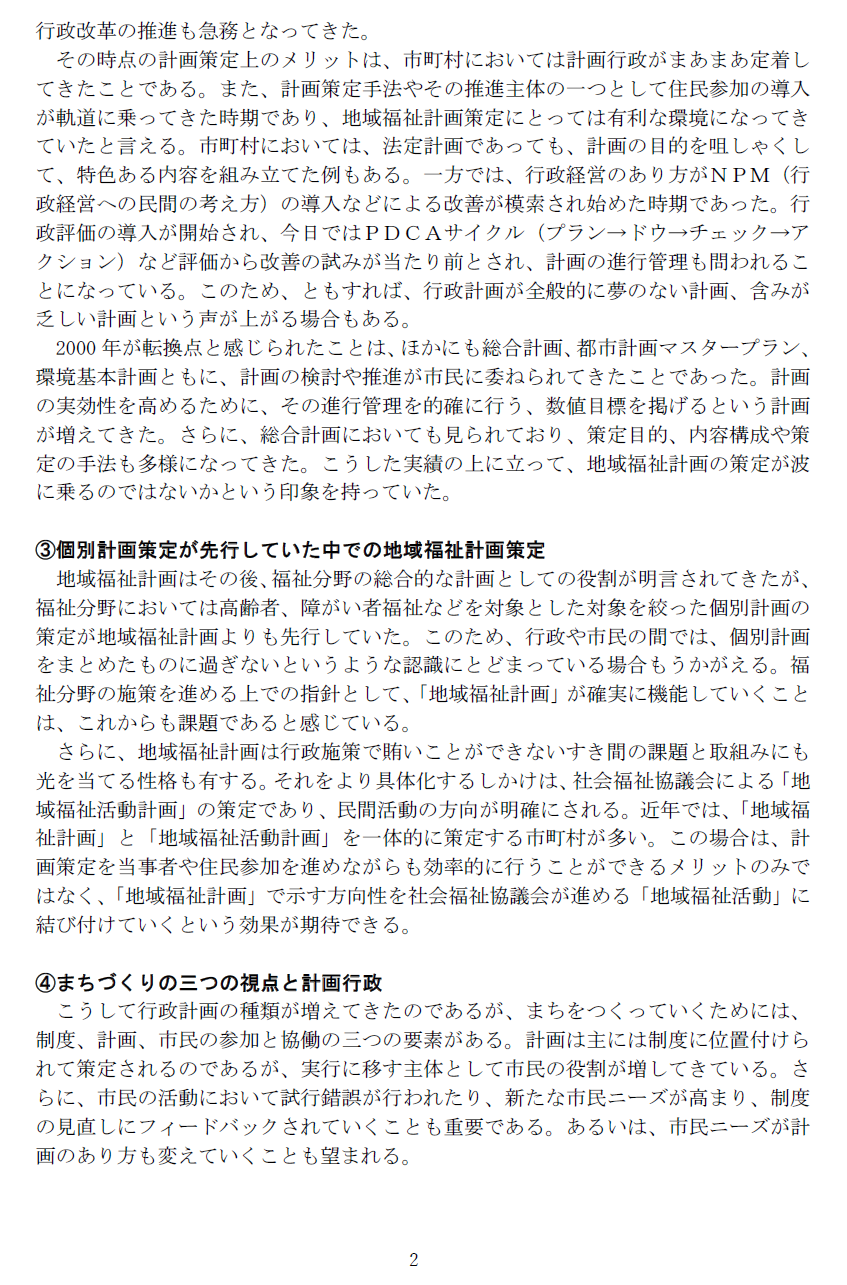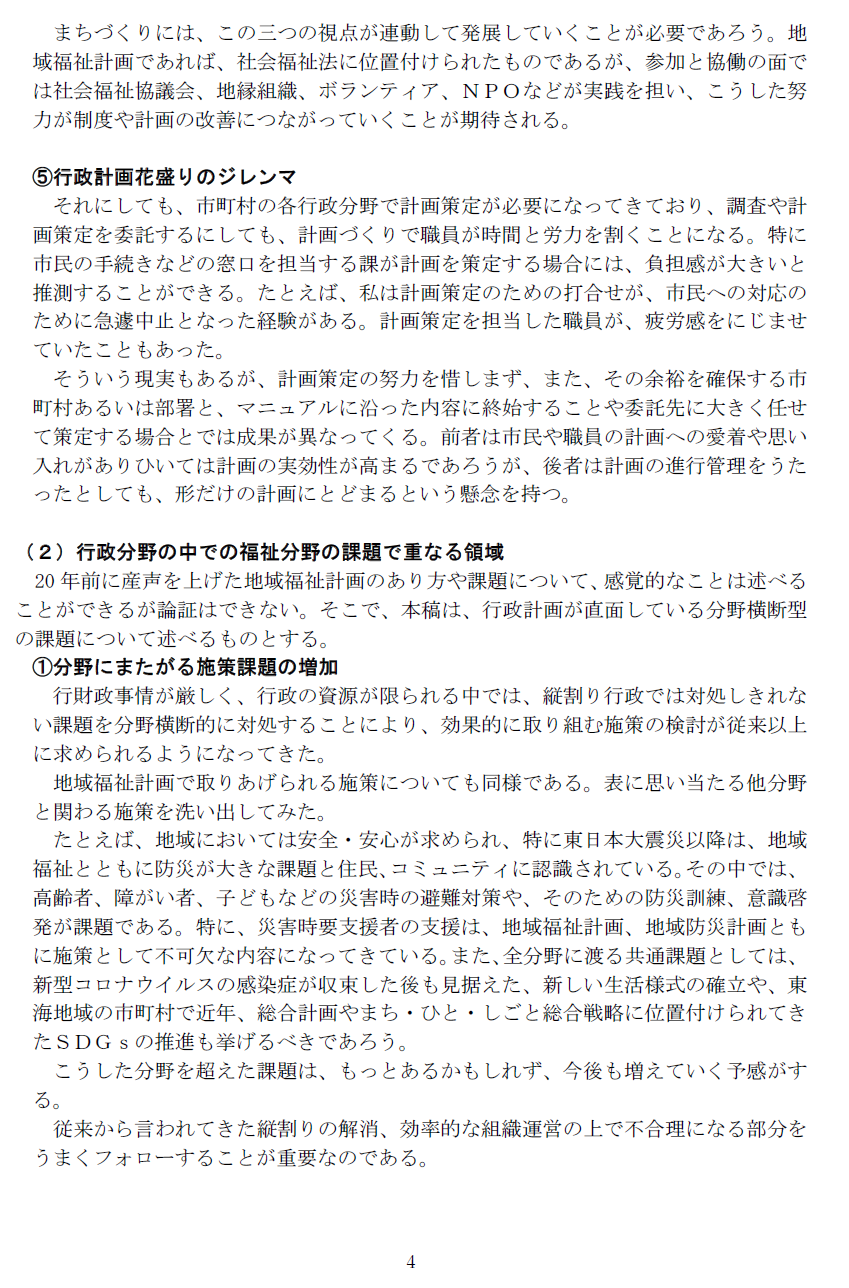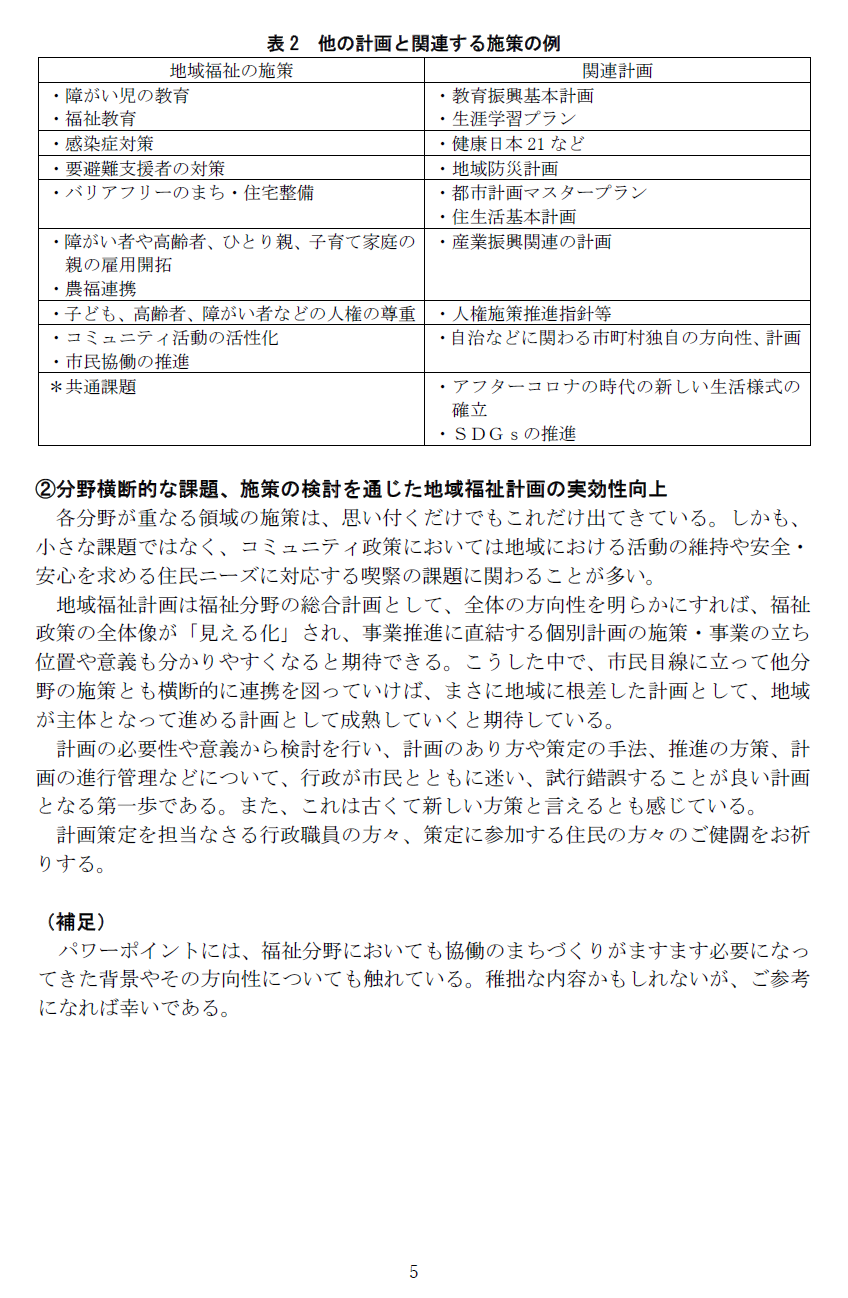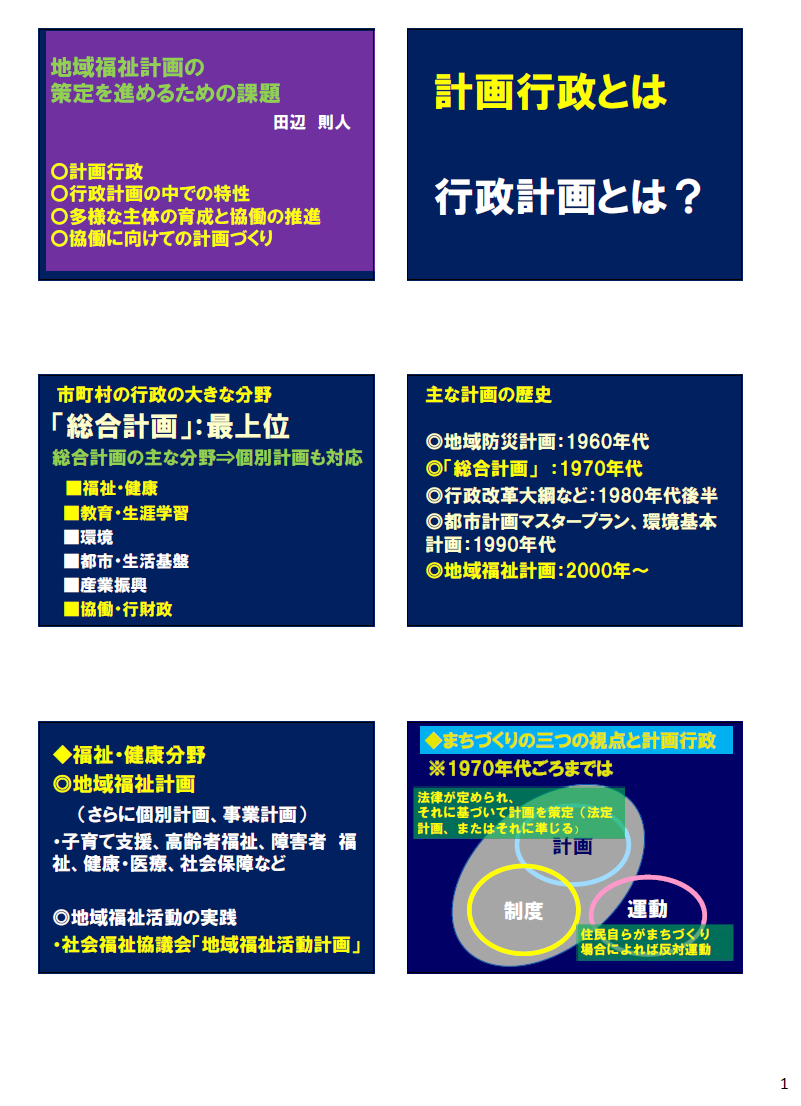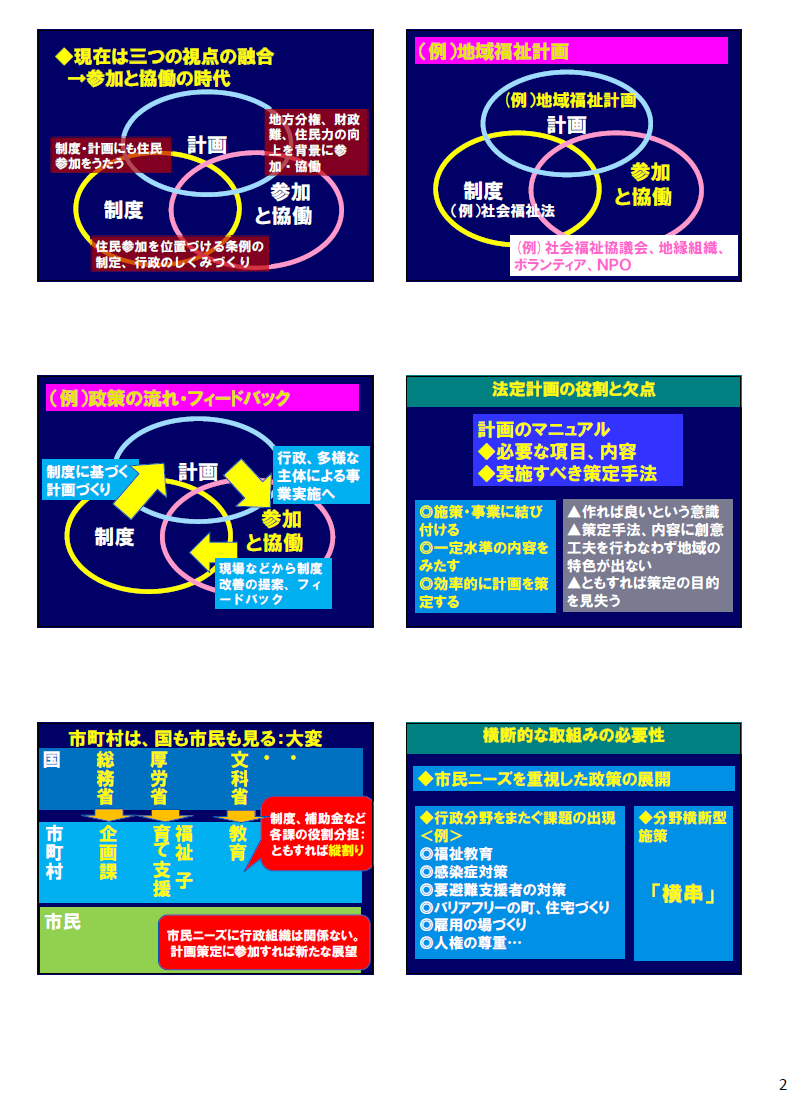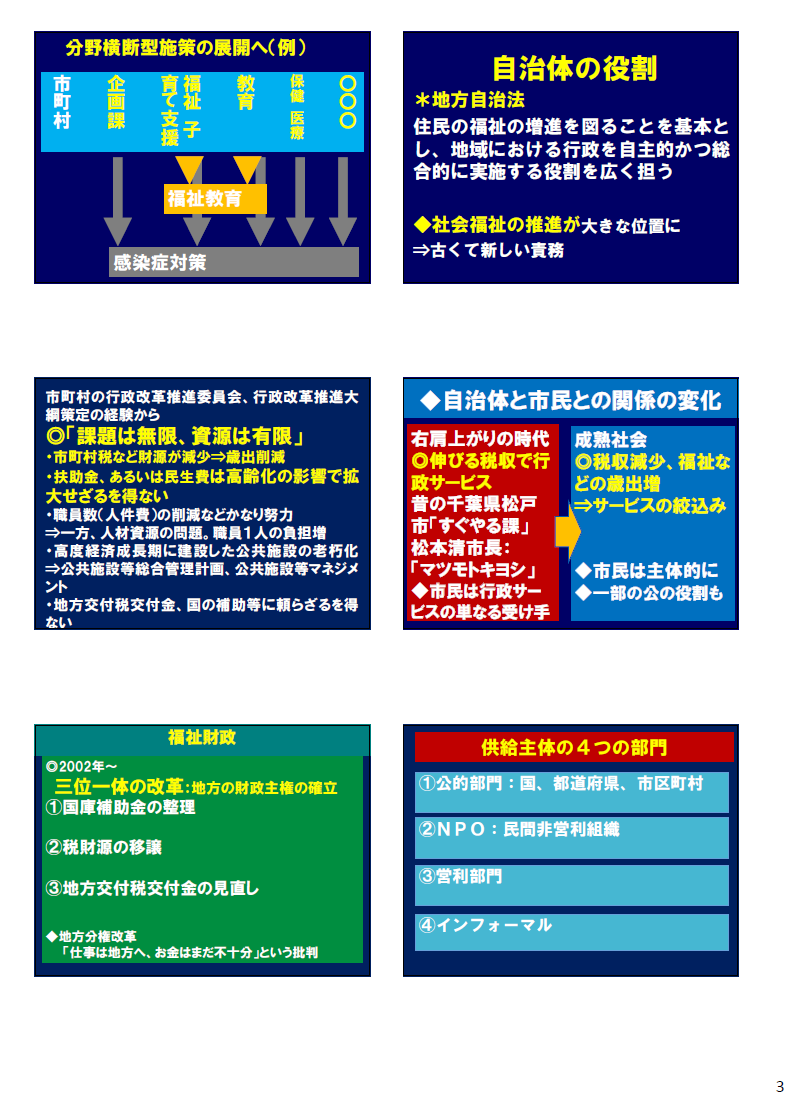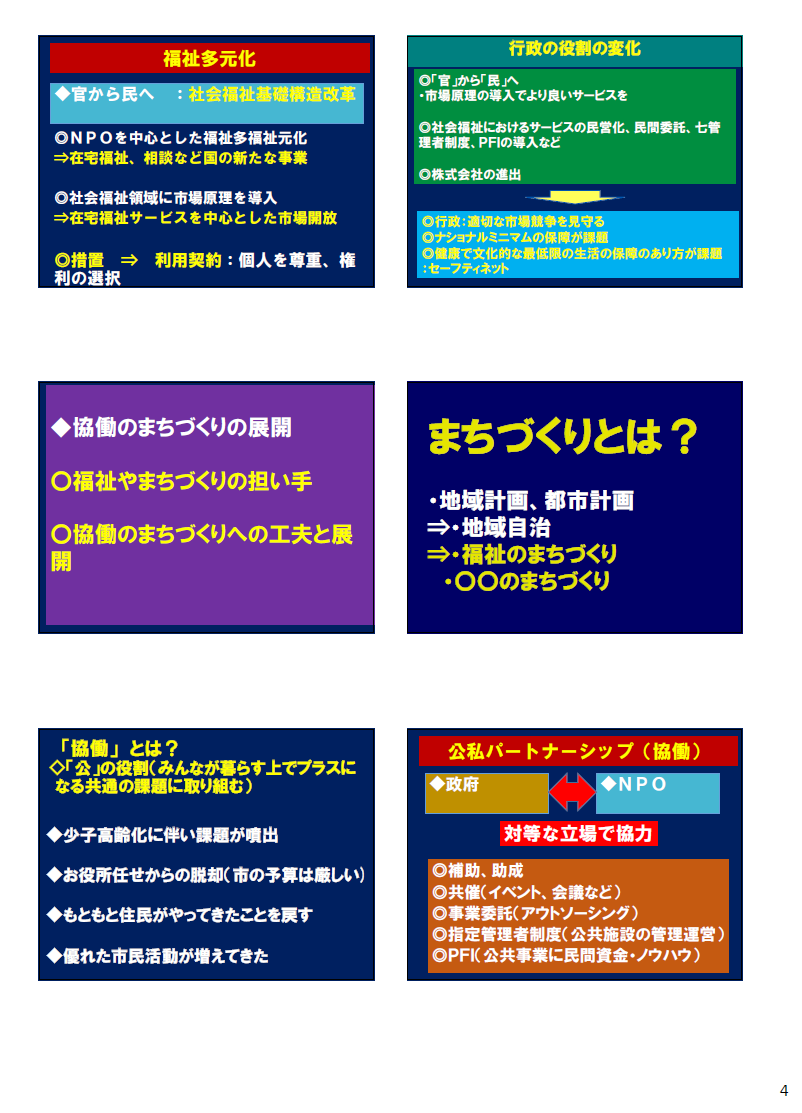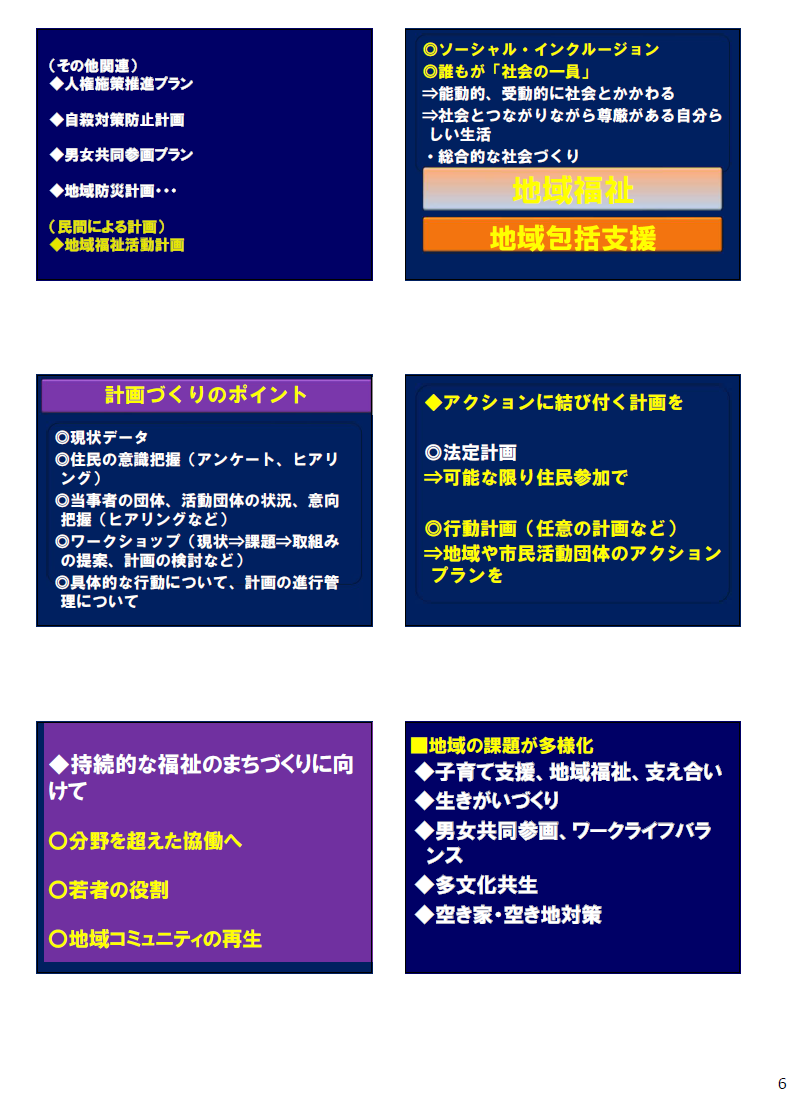〇筆者(阪野)の手もとにいま、山下祐介(やました・ゆうすけ。社会学専攻)の『地域学入門』(ちくま新書、2021年9月。以下[1])と『地域学をはじめよう』(岩波ジュニア新書、2020年12月。以下[2])という本がある。山下というと、『限界集落の真実―過疎の村は消えるか?』 (ちくま新書、2012年1月)や『地方消滅の罠―「増田レポート」と人口減少社会の正体』(ちくま新書、2014年12月)を思い出す。
〇人口の高齢化によって「限界集落」はいずれ消滅する(注①)、とその危機が声高に叫ばれるようになったのは2007年頃からである。そして、2014年5月、民間の政策提言組織である日本創成会議・人口減少問題検討分科会(座長・増田寛也)が、減少する若年女性人口の予測から、「2040年までに全国約1800の自治体のうち、そのほぼ半数の896の自治体が消滅する可能性がある」と発表した。いわゆる「増田レポート」である。とりわけ「消滅可能性都市」という言葉は衝撃的であり、大きな波紋を呼んだ。「消滅する」と名指しされた市町村やそこで暮らす人々の不安や恐怖、そして怒りは相当なものであった。
〇そうしたなかで山下は、「高齢化によって消滅した集落」はなく、「限界集落」問題はいわば「つくられた」ものである。増田レポートが説く「極点社会」(大都市圏に人々が凝集し、高密度のなかで生活している社会)におけるひとつの道筋である「選択と集中」は、国家の繁栄のために地方(地域)や農家の切り捨てに帰結する。地方消滅の“警鐘”にこそ地方消滅の“罠”がある、としてそのレポートの「うそ」を暴いた。以後、山下は、生身の人間の暮らしや個々の地域の歴史や現在の実像を明らかにし、そこからの学びの作業を通して「(山下)地域学」を描いてきた。[1] はその集大成である。
〇山下にあっては、地域は人間の生存の基盤であり、「足もとの地域を知ることが、自分を知ることにつながる」。自分の足下にある地域について学ぶこと、それが「地域学」である([1]11ページ)。そこで山下は、地域の実像を、「生命」「社会」「歴史と文化」の3つの切り口(側面)から捉える。「生命」では、環境社会学の視点(視座)から、地域を、一定の環境のなかで育まれる生命の営み(生態)として切り出す。「社会」では、農村社会学や都市社会学、家族社会学の視点から、地域を、そこで展開される人々の集団の営みとして描き出す。「歴史と文化」では、歴史社会学や文化社会学などの視点から、地域を、連綿と続く歴史と文化の蓄積の営みのなかに見出す([1]11ページ)。
〇そして、日本社会はいま、人々の暮らしや地域が「近代化」(「西欧化」)や「グローバル化」によって大きく変容し、「地域の殻が内側からも、外側からも、崩壊する間際にある」([1]300ページ)。そうした「地域を見直し、新たな国家とのハイブリッドとして再生させる」ための「認識運動」([1]301ページ)として山下は、「地域学」を構想する。それは、「地域の殻が破られはじめている」流れに抗(あらが)い、新しい未来を拓(ひら)く「抵抗としての地域学」([1]302ページ)であり、「生きる場の哲学」([1]308ページ)そのものである。
〇[2]は、「中高生、大学初級者向けのもので、『地域学入門』のさらなる導入編」([1]22ページ)である。そこでは、「どの地域にも固有の歴史や文化があり、人々の営みがある。それらを知っていくことで、地域の豊かさ、そして自分や自分が生きる社会、そして未来が見えてくる」(カバー紹介文)として、地域学の魅力を伝える。
〇「地域学」の類似用語に「地元学」がある。地元学を提唱する2人の言説を紹介しておきたい。まずは地元学を代表するひとりである結城登美雄(ゆうき・とみお。民族研究家)のそれである。結城は、「いたずらに格差を嘆き、都市にくらべて『ないものねだり』の愚痴をこぼすより、この土地を楽しく生きるための『あるもの探し』。それを私はひそかに『地元学』と呼んでいる。(中略)『地元学』は都市やグローバリズムへの否定の学ではない。自然とともに生きるローカルな暮らしの肯定の学でありたい」(結城登美雄『地元学からの出発―この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける』農山漁村文化協会、2009年11月、2ページ)と説く。結城にあっては、地元学は、「理念や抽象の学ではない。地元の暮らしに寄り添う具体の学」(14ページ)であり、その土地の人びとの声に耳を傾け、そこを生きる人びとの暮らし方や地域のありようを学ぶものである。「美しい村などはじめからあったわけではない。美しく生きようとする村人がいて、村は美しくなるのである」(柳田邦国男)。(下記[3]28ページ)
〇また、地元学のもうひとりの第一人者である吉本哲郎(よしもと・てつろう。地元学ネットワーク主宰)は、「地域のもつ人と自然の力、文化や産業の力に気づき、(それを)引き出していく手法が地域学である」(カバー紹介文)。「自分たちであるもの(モノ、コト、ヒト)を調べ、考え、あるものを新しく組み合わせる力を身につけて(人、地域の自然、経済の3つの)元気をつくることが地元学の目的である」(17、22、38ページ)という。吉本にあっては、暮らしを「つくることを楽しむ」ことが大事であり(32ページ)、地域やまちの衰退は「つくる力」の衰退に起因するものである。その「つくる力」の衰退は、「考える力」の衰退であり、「調べる力」の衰退である(22、23ページ)。
〇ここで、[1] から、また例によって我田引水の誹(そし)りを免(まぬが)れないであろうことを承知のうえで、山下の「地域学」に関する論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
「地域」は、固定化された空間ではなく、「私」の立場やものの見方・考え方によって認識される
「地域」はそもそも、誰かが世界の一部を切り取ることによって浮かび上がってくるものである。/何かを切り取らないと地域は出てこない(地域は境界性をもつ)。そして、その「切り取り方」にも色んなやり方があって、それは文脈にもよれば、時代によっても違う(地域は文化性・歴史性をもつ)。/そもそも世界のすべてはつながっている。どこかで切れ切れになっていて、「地域」がきれいに分かれているなどということはない。すべてはつながっているのだが、そのつながっているもののなかから、何らかの固まりを切り出してきたときに「地域」は立ち現れる。しかもそれが、全体の一部でありながら決して断片ではなく、それのみでなお一つの全体でありうるもの、それが地域である(地域は統一性・総合性をもつ)。(13ページ)/「地域」は、互いにつながりあっている世界の中から、何らかの固まりを見つけ、切り出してくる者がいるから「地域」になるのである。地域はだから、その「切り出してくる者」の立場やものの見方によって変わる。その者の見方がしっかりしていれば地域はしっかり示される。逆にその者の見方がぼんやりとしていれば、地域はぼんやりとしか見えないことになる。(13~14ページ)
「地域」という存在を欠き、国家と個人しかない認識は、危うい認識であり生き方である
いまや国民の多くは、空間的にも時間的にも、また暮らしにおいても仕事においても地域から切り離されて存立しており、地域を見出すどころか、地域とできるだけ無縁なまま暮らしている。/多くの人にとっては、日常の中に「地域」を認識しづらい状況にあり、宙ぶらりんな社会の中で、個人が国家やグローバル市場にだけ向き合って暮らしているかのような錯覚が、むしろ一般的な認識となってしまった。/実にちっぽけな一人一人の人間が、実に大きな装置の中で生きるようになっている。暮らしを成り立たせている環境が、広く際限のないものになっている。/こうした装置(や環境)を実際に保持し、また動かしているのは地域である。それは具体的には地方自治体であり、様々な事業体の集積であり、地域社会(村や町内社会)の形をとる。国はただ、これらが作動する条件を整えるのにすぎない。(286ページ)/いまを生きる私たちは、こうした地域のありようを想像力を働かせて再認識せれば、いったい自分がどんな基盤の上にいるのか、まったく気付かないような環境の中に暮らしている。それどころか、一部の人々の視野にはすでに地域は存在せず、国家と個人しかない認識さえ確立されているようだ。だがそれは、すべてを国家に委ね、依存するしかないという危うい認識である。自分がどのように生きているのかもわからぬままただ生きているとすれば、これほど危うい生き方はない。私たちは地域を知るきっかけを取り戻さなくてはならない。(286~287ページ)
専制主義国家であり、民主主義国家でない日本社会を変革するのは、「地域主義」(地域ナショナリズム)である
弱者批判や地方切り捨て、国家の高度武装化、トップの専横の容認や全体主義の礼賛といった言説が、政治学者でも政治家でもないふつうの人々の間で展開されている。そこではどうも、この国の挙国一致体制をさらに進めてより完全なものとし、海外との経済競争に打ち勝つべくしっかりとした体制を整えよという主張さえ広がっているようだ。/国家というものは、具体的には下から、国民や地域の現実の力によってはじめて作られていくものである。排除や分裂を伴う(自分の内部にあるものを否定し、その一部を排斥する)国家は危うい。(295ページ)/個人主義の中から立ち現れるナショナリズム(nationalism、国家主義)に対して、むしろ個人主義をさらに強く推し進めることで国家そのものを否定していこうという、コスモポリタニズム(cosmopolitanism、世界市民主義)の立場も表明されている。この超個人主義=脱国家主義的なコスモポリタニズムははたして、ナショナリズムを解消し、国家のない世の中をつくる適切な道筋になるのだろうか。(296ページ)/敵国と自国との差異だけを強調し、個人と国家の関係のみを際立たせる国民国家ナショナリズムの思考法には根本的な欠陥が潜んでいる。他方でそれをコスモポリタニズムによって解消しようとしても、それで問題が解決するものでもない。国家ナショナリズムにも、コスモポリタニズムにも、どちらにも大切なものが欠けている。(297ページ)/それは地域である。危険な一国ナショナリズムに対抗できるのは、コスモポリタニズムではなく、その内部に確立される地域主義――地域ナショナリズム――である。(297~298ページ)
地域の人材を育てること、「地域教育」は学校の持つ大切な役割である
学校はそもそも地域のためのものではなく、国家のために必要な人材をつくる機関として設立された。そしていま国家が必要としているのは、この国が苛烈な国際競争を勝ち抜くのに必要な経済力・生産力を実現する人材である。学校教育は、地域教育などのためではない。この国の国際競争力を、人材育成という場から高めるために、一丸となって敵(海外の企業群)に立ち向かうためである。子供たちには、地域の人間であるよりは国家人として、さらには国際人・コスモポリタン(世界主義者)として育つことが強く求められている。(287~288ページ)/学校は外向きにだけではなく内向きに、すなわち国内の運営バランスを実現するために、子供たちを適切に教育して各所に配置する装置でなければならない。そのためにも、一人一人が自分の人生の調整を自ら適切に実現できるよう、人としての成熟をうながすものであるべきだ。私たちの暮らしはいまも地域と国家の両方でできている。地域の人材を育てることは、学校の持つ大切な役割である。だが、現実には近年、国家だけが尊重され、地域が極度に軽視されてきた。(288ページ)/学校が今後とも地域を継承する人材を育てる場であるのか、それとも地域と子供たちのつながりを断ち、国家や国際社会対応の人材供給の場になるのか、私たちはその分岐点にいる。(249ページ)
〇山下にあっては、「地域学」は抽象的な言語や普遍的な理論を学ぶものではなく、具体的な時空にいる「私」を地域のうちに“生きているもの”として浮かび上がらせ、見定めていく、そんな学びの作業である([1]16ページ)。また、私たちの暮らしや、身近な地域と国家と世界が大きく変容するなかで、その変化に対応するための最低限の認識法が「地域学」である([1]309ページ)。その認識の視点や言説のひとつが、上記のメモである。
〇筆者(阪野)の手もとにもう一冊、柳原邦光(やなぎはら・くにみつ。フランス近代史専攻)ほか編著の『地域学入門―<つながり>をとりもどす』(ミネルヴァ書房、2011年4月。以下[3])という本がある。[3]は、「地域を考える」「地域をとらえる」「地域をとりもどす」という3部構成から成っている。柳原によるとそれは、「地域」をめぐる今日の困難や課題の現状を打開するための「希望の学」として「地域学」を構想するものである。すなわち、「地域学」は、地域課題をたちどころに解決するための処方箋を提示するものではなく、「現代の諸課題の根底にある問題性を探り出し、そこから諸課題をとらえ直して、未来を考えようとする」ものである([3]2ページ)。
〇いずれにしろ、「地域学」は、日本学術会議(地域学研究専門委員会)が2000年6月に報告した「地域学の推進の必要性についての提言」(注②)などにあるように、その研究や実践の必要性は認識されていよう。しかし、その理論化や体系化はまだ緒についたばかりであろうか。筆者としては、とりわけ「実践の学」としての「地域学」に注目したい。それは、「市民福祉教育(学)」と同様に、すでに地域で展開されているさまざまな実践や、そこから生まれる新たな知見に多くを学びたいからである。
〇ところで、「地域学」の必要性は、大学に設置されている学部名からも知ることができる。大学で「地域」を最も早く学部名に取り入れたのは1996年10月に設置された、岐阜大学の「地域科学部」(1997年度開設)である。その後、鳥取大学の「教育地域科学部」(1999年度開設。2004年度「地域学部」に改組)、金沢大学の「人間社会学域・地域創造学類」(2008年度開設)などが設置され、2015年度には高知大学に「地域協働学部」が開設されている。以後、国公立大学や私立大学でいわゆる「地域系学部・学科」の新設が続き、「地域学」が大学教育の場に普及する。
〇高知大学地域協働学部の目的は、「地域力を学生の学びと成長に活かし、学生力を地域の再生と発展に活かす教育研究を推進することで、『地域活性化の中核的拠点』としての役割を果たす」ことにある。そこでは、「地域協働教育」を通じて、地域資源を活かした6次産業化を推進してニュービジネスを創造できる「6次産業化人」や、「産業、行政、生活・文化の各分野における地域協働リーダー」の育成が図られている(高知大学地域協働学部ホームページ)。
〇高知大学地域協働学部では、「地域志向教育」あるいは「地域協働教育」を通して、「地域協働マネジメント力」の育成をめざしている。「地域協働マネジメント力」は3つの能力によって構成される。(1)「地域理解力」、(2)「企画立案力」、(3)「協働実践力」がそれである。(1)「地域理解力」は「地域の産業及び生活・文化に関する専門知識を活用して、多様な地域の特性を理解し、資源を発見できる力」と定義される。その能力を構成するのは、「状況把握力」「共感力」「情報収集・分析力」「関係性理解力」「論理的思考力」である。(2)「企画立案力」は「課題を発見・分析し、解決するための方策を立案し、その成果を客観的に評価する能力」と定義される。その能力を構成するのは、「地域課題探究力」「発想力」「商品開発力」「事業開発力」「事業計画力」「事業評価改善力」である。(3)「協働実践力」は「多様な人や組織を巻き込み、互いの価値観を尊重しながら、参加者や社会にとっての新しい価値を生み出す活動をリードする力」と定義される。その能力を構成するのは、「コミュニケーション力」「行動持続力」「リーダーシップ」「学習プロセス構築力」「ファシリテーション能力」である(注③)。これらの諸能力やその見方・考え方については、「まちづくりと市民福祉教育」に関するそれに通底するものでもあり、参考になろう。留意したい。
〇なお、高知大学地域協働学部がいう「地域志向教育」とは、「地域課題の解決や地域の再生、発展を目的とした教育」(下記注③、25ページ)である。[3]で取り上げられている「地域協働教育」は、「大学が教育面で地域に協力を仰ぐ地域連携教育から地域との関係を一歩進め、大学が地域と協働で学生の教育と学生参加の地域づくり活動を行うもの」。「生活に根ざして学問的知識や方法論を駆使することを会得した地域づくりの人材を大学と地域が一緒に養成していく」教育をいう(藤井正「地域に向き合う大学」[3]292、293ページ)。付記しておく。
注
① 周知の通り、「限界集落」という用語は、高知大学人文学部教授であった大野晃(おおの・あきら。社会学専攻)が1980年代後半から提唱してきた概念である。大野にあっては、「限界集落」は「65歳以上の高齢者が集落人口の半数を超え,冠婚葬祭をはじめ田役,道役などの社会的共同生活の維持が困難な状態に置かれている集落」をいう(大野晃『限界集落と地域再生』静岡新聞社、2008年11月、1ページ)。その点をめぐって山下は、「限界集落」問題はいわば「つくられた問題」としての色彩が強かったとして、次のように述べている。「『限界集落』の語をつくって注意喚起しようとした提唱者の意図に反し、その後の議論は、集落消滅を避けられない既定路線であるかのように取り扱っていった」。「『地方消滅』や『自治体消滅』は起きない」(山下祐介『地方消滅の罠』290~291ページ)。
② 日本学術会議の「提言」では、「地域学は、もっとも広義の『地域にかかわる研究』を指すものである。 現地研究(フィールド科学)に根ざして人文科学・社会科学・自然科学を統合的、俯瞰的に再編成しようとする学問的営為を、地域学と呼ぶ」。また、「提言」では、現地研究に根ざした基礎研究としての「地域学」の展開が必要とされている理由について、次の2点を指摘している。
1)わが国は明治以来、世界諸地域を相手どってそのおのおのを総合的にとらえようとする基礎研究としての地域学構築の地道な努力を十分にしないまま、いわば学理・学説としてのディシプリン(学術専門分野:阪野)だけを欧米から輸入してきた。そのために、わが国の学術専門分野は、とかく欧米の理論を追いかけるものとなってしまった面があることは否定できない。あらためて今日、もっとも基礎的な現地研究に立ち戻り、現地研究に立脚した学問を創り出す努力が必要になってきている。現地研究という「地を這う」ような地道な作業を経ないかぎり、しっかりした骨格をそなえる学問体系の構築は望めない。
2)従来の専門分化したディシプリンにしがみついているだけでは、あるいはまた、そのいくつかを寄せ集めてみる程度では、現在の世界の趨勢を的確に把握することができないばかりか、目前に危機的に発生している問題に対処し、それを解決することがむずかしくなっている。地球環境・生態系の破壊をいかにくい止めるか、世界的規模で公正をいかに実現するか、そして持続可能性・世代継承性に裏付けられた発展の道筋をいかに発見するか、など、人類的課題がつよく自覚されるなかで、水、食料、健康、人口、エネルギー、ライフスタイル、経済システム、価値観、教育、情報秩序、参加とパートナーシップ、民主主義、その他ありとあらゆる問題への取り組みが、何をとってみても、知識の統合を要求するとともに、これを具体的な場所に根ざした地域学として実現することを必須のものとしている。
③ 湊邦夫・玉里恵美子・辻田宏・中澤純治「地域協働教育への学生の意識~地域協働学部第1期生調査の結果から~」『高知大学教育研究論集』第20巻、2016年3月、25~33ページ。本稿では、高知大学地域協働学部第1期生(67名)を対象に、2015年4月に実施した調査の結果を事例として、「地域志向教育」を行う学部を選択した学生の学部教育に対する意識と将来像 について検討している。
補遺
高知大学地域協働学部第1期生調査にみる「地域協働マネジメント力」の(1)「地域理解力」、(2)「企画立案力」、(3)「協働実践力」の各構成能力について理解するために、各調査項目の質問文を紹介しておくことにする。その回答の選択肢は、「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」「どちらかといえばあてはまらない」「あてはまらない」の4つである。
(1)「地域理解力」
「状況把握力」
・身の回りの現状を客観的に理解して説明する方である
「共感力」
・人の話に興味を持ち、積極的に聴こうとする方である
「情報収集・分析力」
・起こった出来事や課題について理解するために、必要な情報を集めて整理しようとする方である
「関係性理解力」
・さまざまな出来事のつながりを理解しようとする方である
「論理的思考力」
・問題が起きたときに、すぐに結論を出すよりも、なぜそれが起きたのかを筋道を立てて考える方である
(2)「企画立案力」
「地域課題探究力」
・身近な地域の課題を発見し、その課題に取り組むことができる
「発想力」
・課題に対して取り組むための新しい方法を考えるのが好きである
「商品開発力」
・特産品を使って商品化することに関心がある
「事業開発力」
・自分でアイディアを思いつき、そのアイディアに基づいてイベントや事業を始めることに関心がある
「事業計画力」
・課題を解決するために必要な行動をリストアップして、その順序を決めることに関心がある
「事業評価改善力」
・自分の行動を振り返り、良い点と悪い点を見つけ出して次の行動に生かすことができる
(3)「協働実践力」
「コミュニケーション力」
・人の話を最後まで聞いてから、自分の話を始めることができる
・相手が自分の話を理解できるように話すことができる
「行動持続力」
・自分で決めたことは最後までやり通す
「リーダーシップ」
・グループにとって必要なことを自ら進んで実行することができる
・自分が提案した計画や企画を、他の人々に参加してもらいながら実現することができる
「学習プロセス構築力」
・授業時間以外にも、自分で計画を立てて学習することができる
「ファシリテーション能力」
・考えが違う相手と話し合いながら合意点を探ることができる