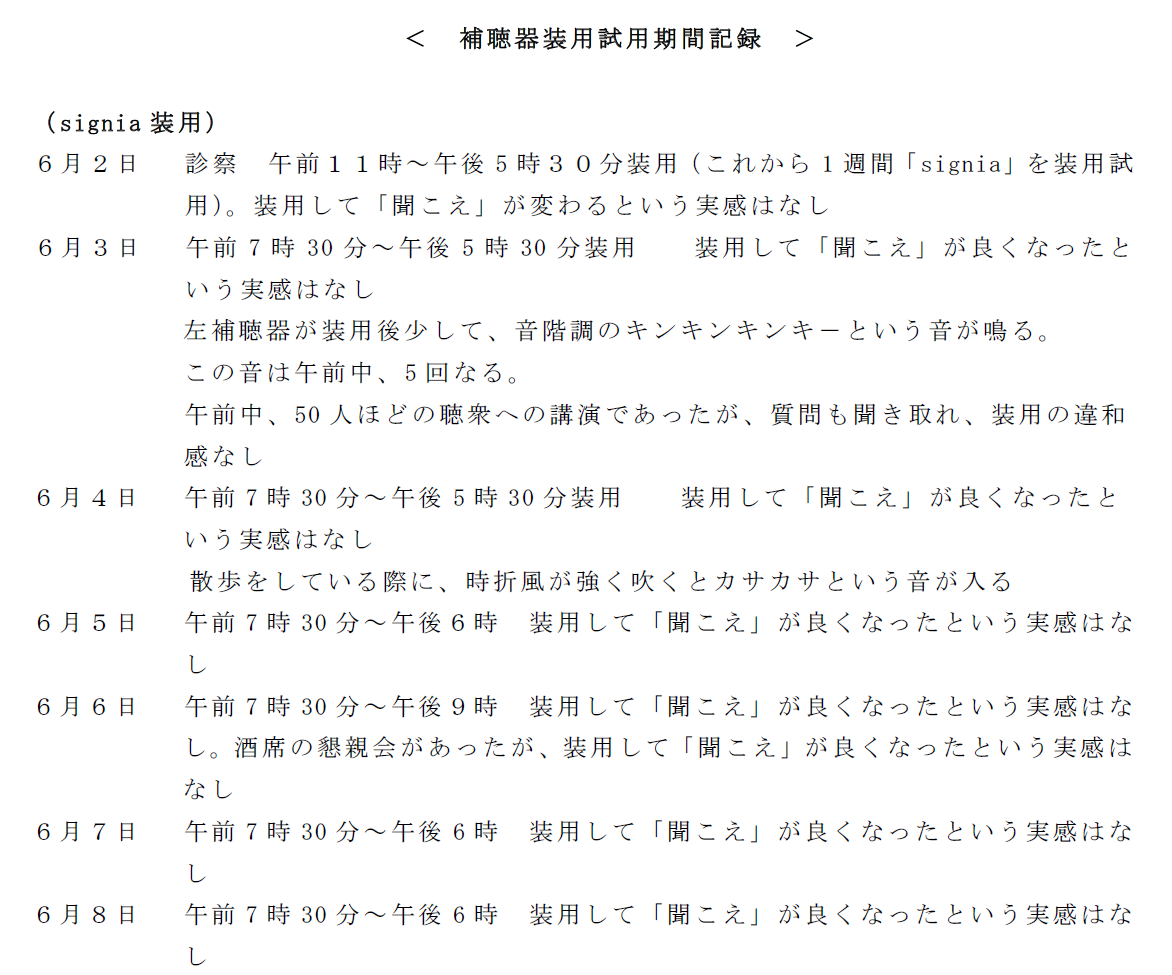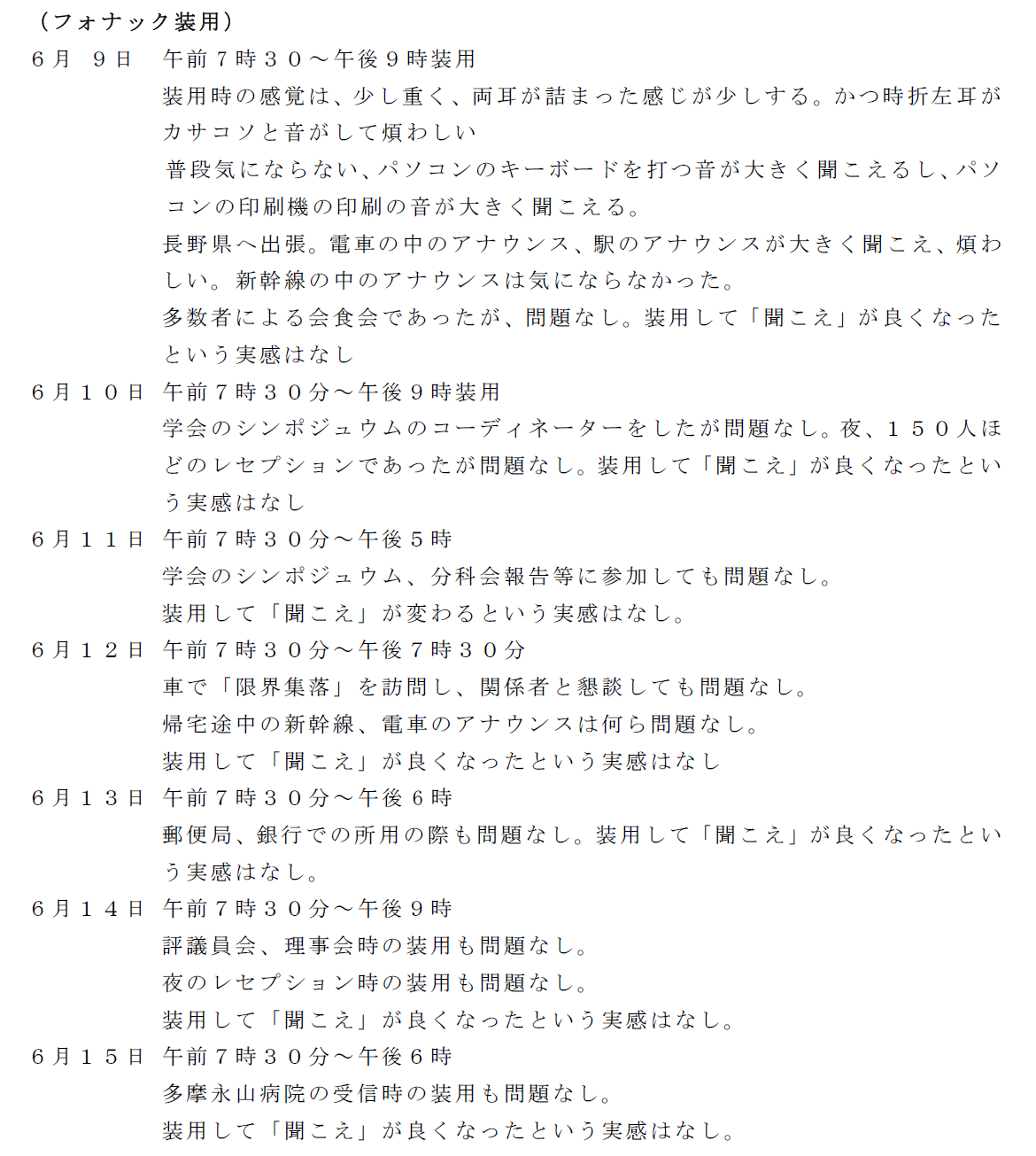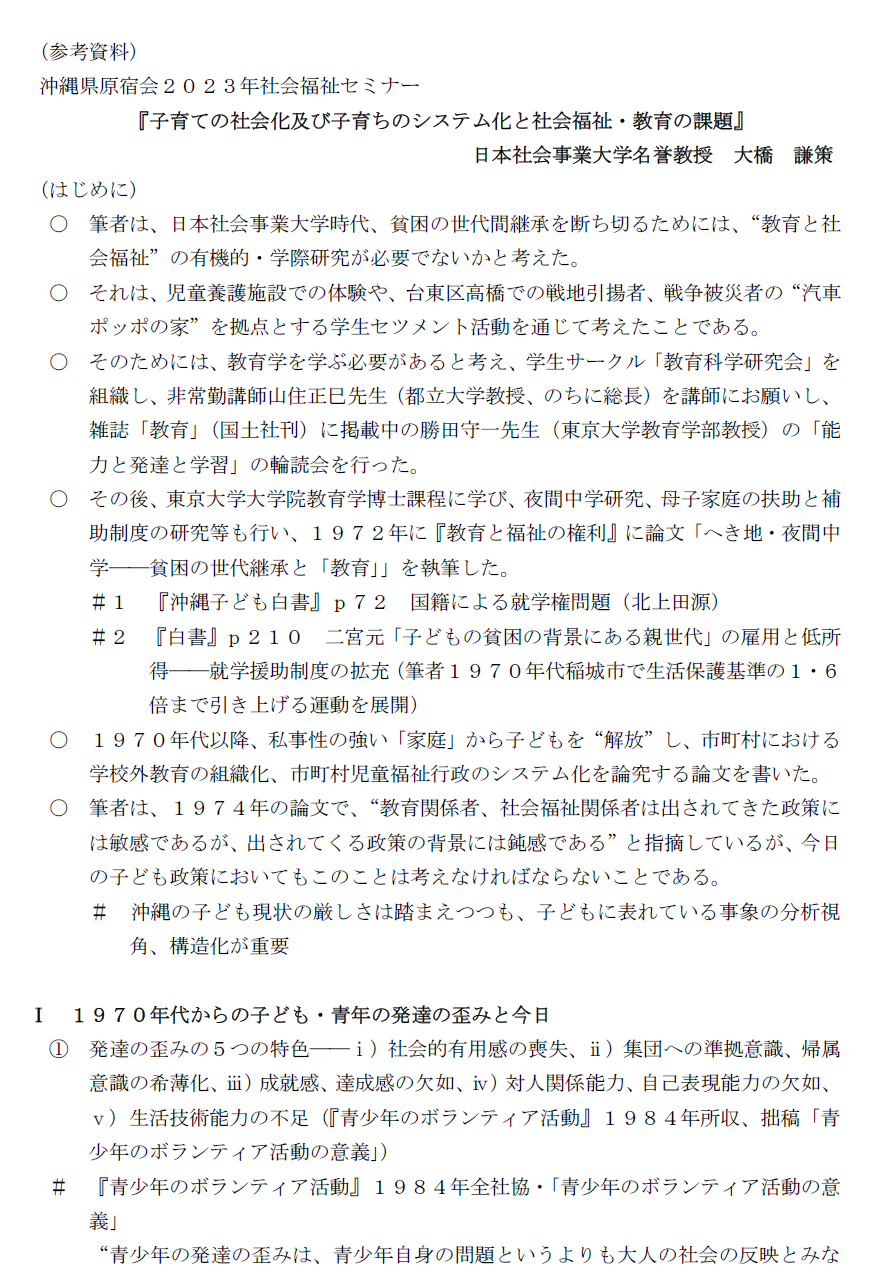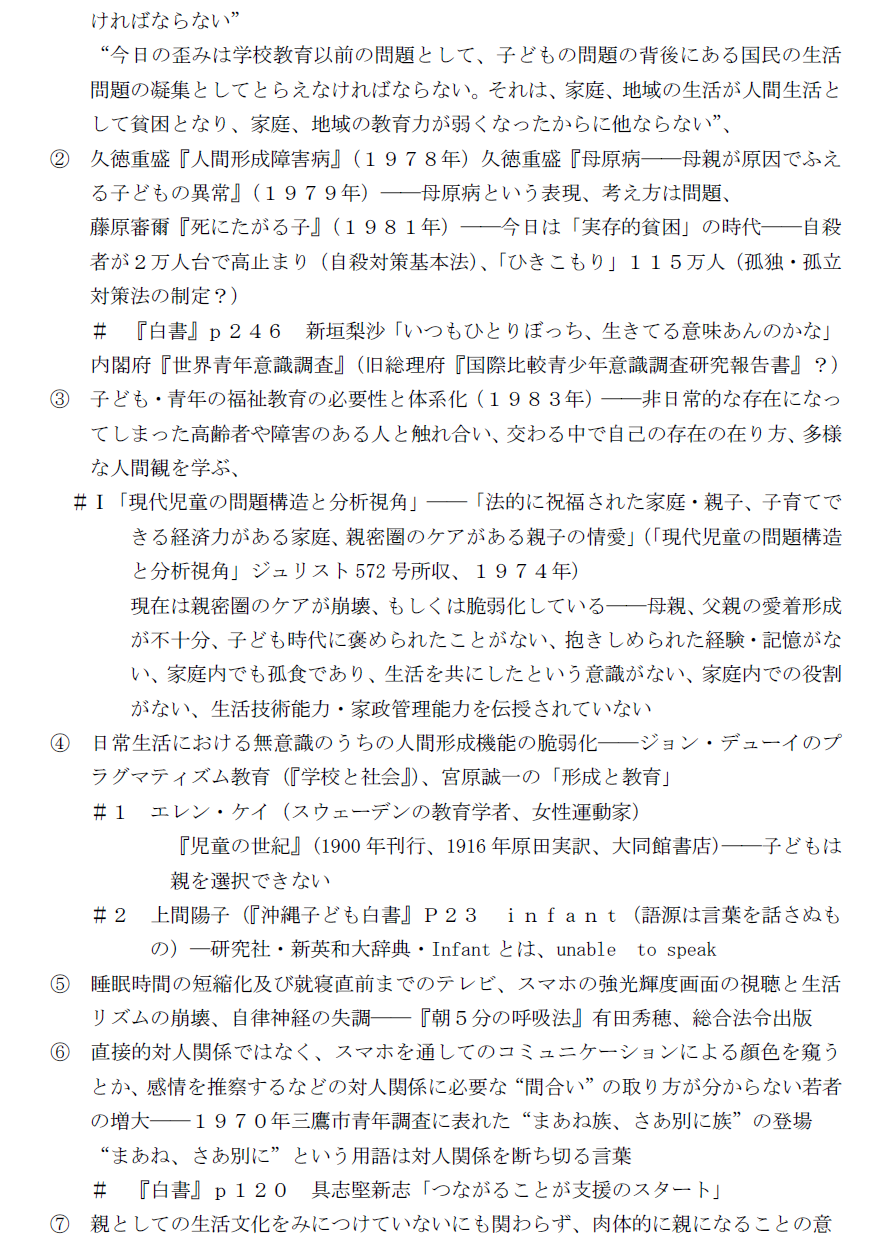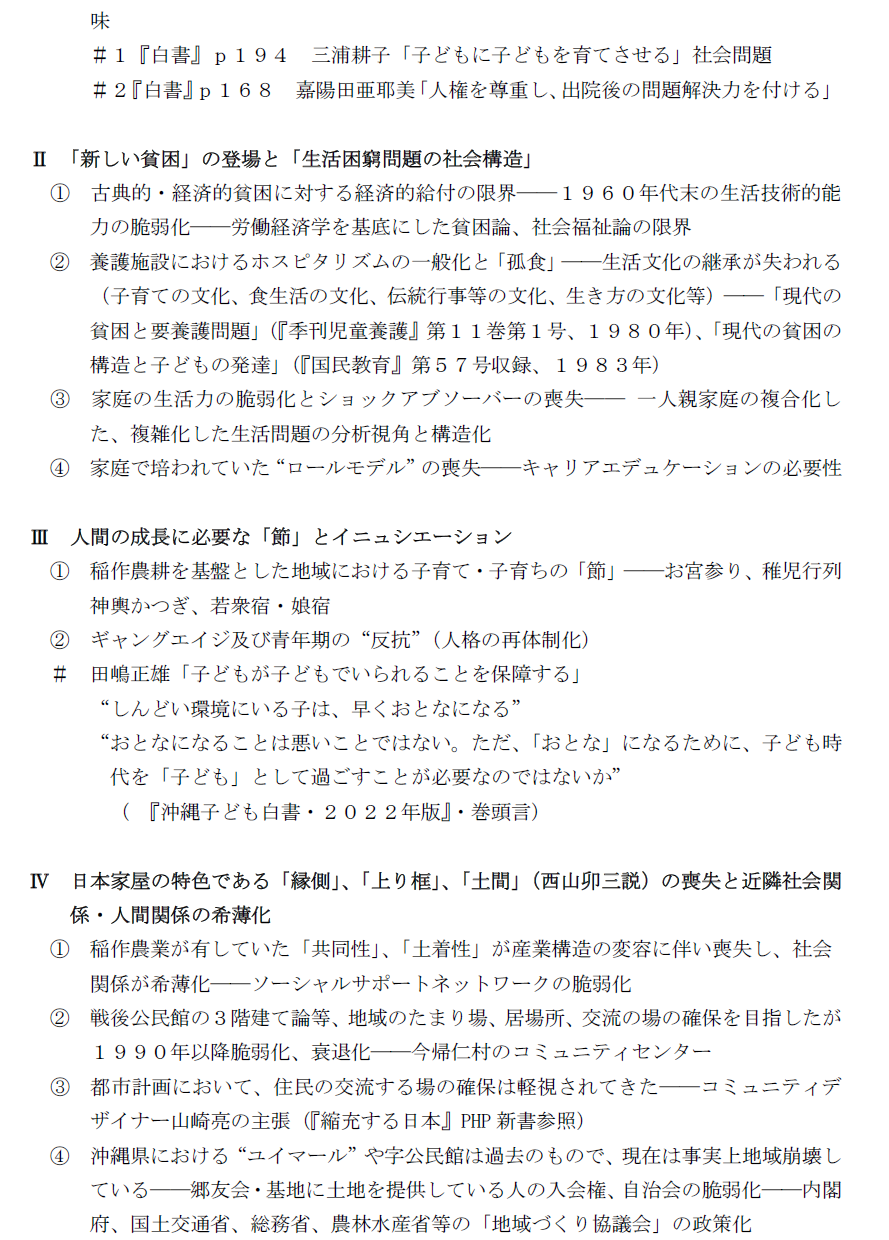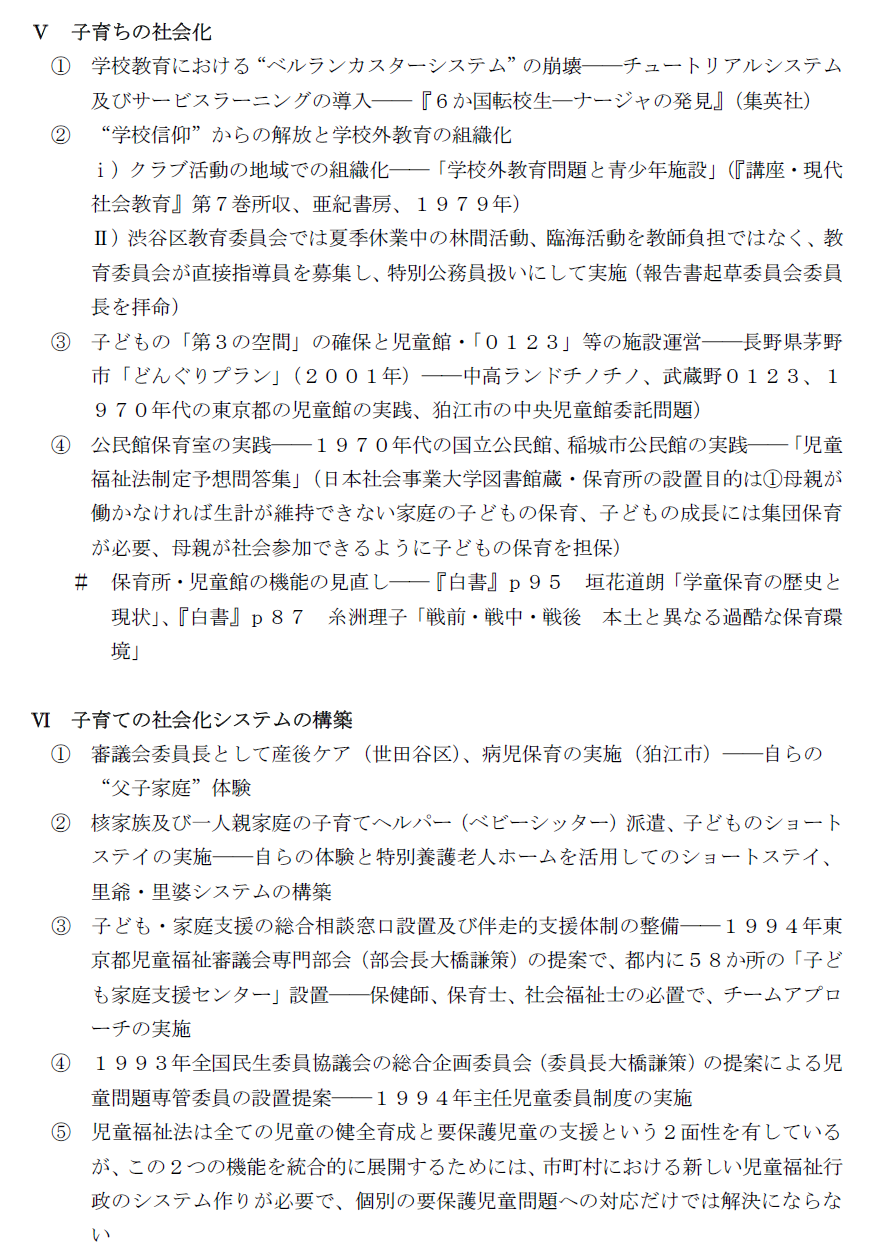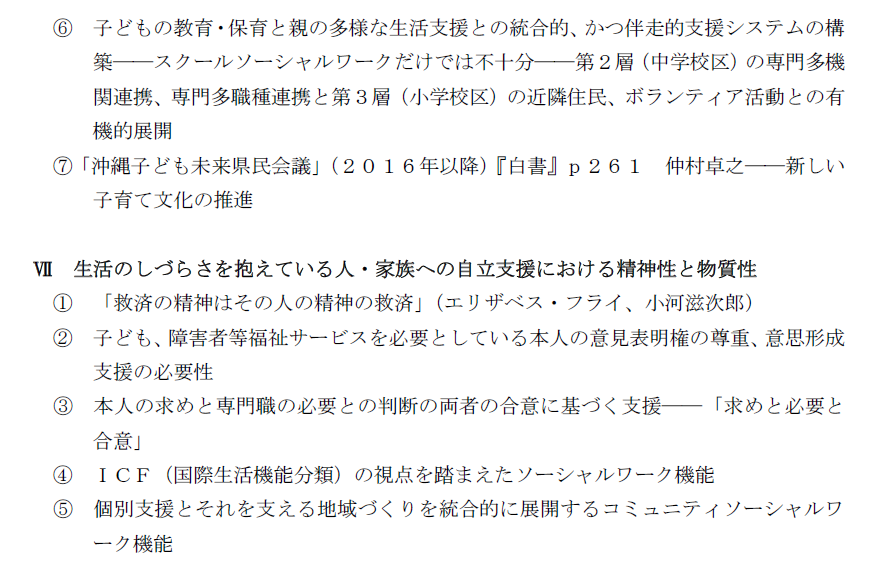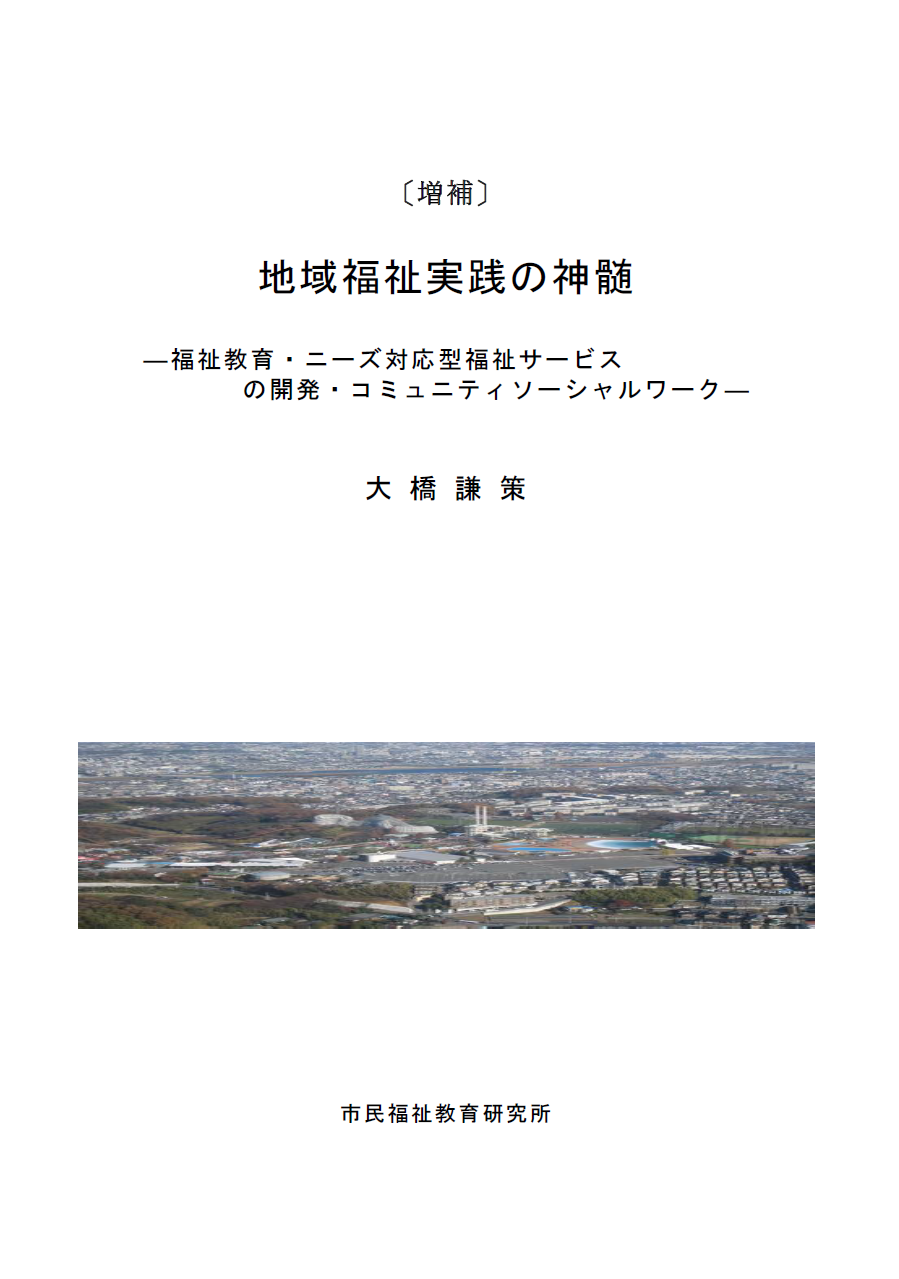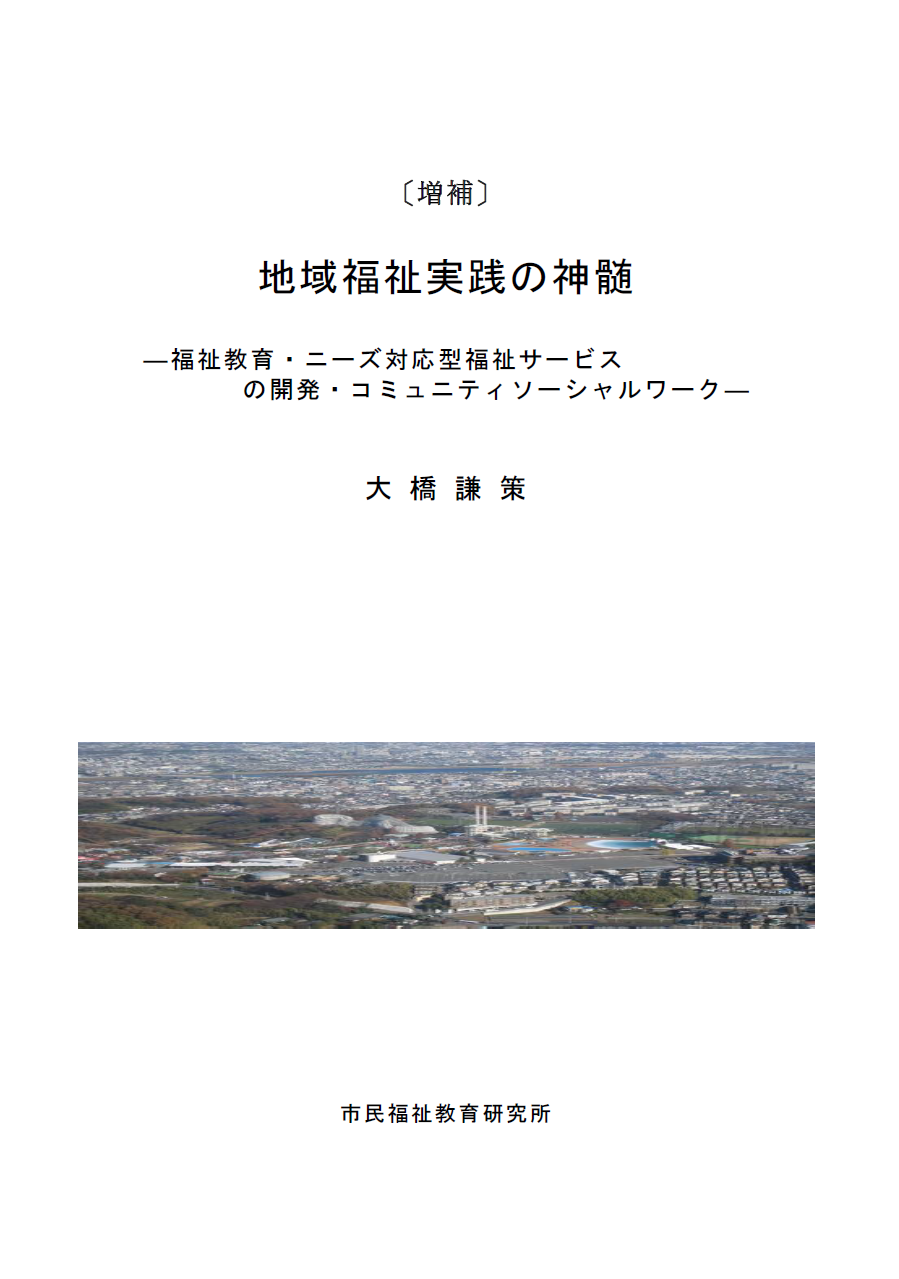
はじめに ―「我が事・丸ごと地域共生社会」の実現に向けての課題―
厚生労働省は、2016年7月に『「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部』を発足させ、2015年9月に発表した「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現―新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」(「以下「新しい福祉提供ビジョン」と略」)の具現化を推進させることになった。
それは、地域自立生活支援を展開する上で、①子ども、障害者、高齢者の全世代を一元的、一体的に受け止め、相談に応ずるワンストップサービスをシステム化すること、②福祉サービスを必要としながらサービス利用に繋がっていない人々をアウトリーチして発見し、支援することと、時には伴走型の継続的支援を行うこと、③福祉サービスを必要としている人々を地域から排除しない、新たな地域コミュニティづくりを進めること、④そのためにも子ども、障害者、高齢者の全世代が交流・利用できる地域における小さな拠点づくりが必要になること、⑤そして全世代支援、全世代交流を進めていくためには属性分野・機能別の縦割りの資格ではなく、各資格間の相互乗り入れが必要になること等を具体化、具現化させること、等が課題としてあることを指摘している。
しかしながら、これらのことは“言うは易く、行うは難し”である。それらの理念、考え方の具現化、具体化においては少なくとも福祉教育の推進、ニーズ対応型福祉サービスの開発とそれを企画できる力量のある職員の養成、住民と行政の協働を成り立たせる触媒、媒介の機能をもったコミュニティソーシャルワーク機能とそれを実施できるシステムを整備しない限り難しい。これ以外にも、専門多職種連携の在り方とシステム等の検討課題があるが、今回は触れない。
筆者は、それら「地域福祉実践の真髄」ともいえるそれら3つの機能の具現化とその理論化を求めて、50年間研究をしてきたといっても過言ではない。
その研究スタイルは「バッテリー型研究方法」ともいえるもので、実践家の実践を理論化、体系化するとともに、研究者の理論仮説を実践家に提起し、実践してもらい検証するという研究者と実践家とがあたかも投手、捕手のようにバッテリーを組んで行う方法であり、筆者の50年間の実践、研究はまさにその方法によるところが大きい。
四国・こんぴら地域福祉実践セミナーの20年間の実践もまさにそうで、筆者が関わった他のセミナーも含めて、それらのセミナー等において「バッテリー型研究方法」で実践され、論議され、システム化され、地方自治体の政策を産み出してきた多くの実践が先に述べた厚生労働省の報告書にそれなりの影響を与えたと自負している。
地域福祉実践の方法として検討しなければならないことは多々あるが、今回は「我が事・丸ごと地域共生社会」実現上特に考えなければならないことと、四国・こんぴら地域福祉実践セミナーの20年間の実践を通して考えてきたことに焦点化させることとし、本稿では、「地域福祉実践の真髄」ともいえるものの内、上記に挙げた3点を取り上げた。それを筆者がどのように考え、展開してきたのかを随想風に振り返りながら、四国・こんぴら地域福祉実践セミナーの実践に対し、若干のコメントをすることとしたい。
Ⅰ 地域福祉実践(社会福祉協議会活動)は “ 福祉教育に始まり、福祉教育に終わる ”
全国社会福祉協議会が1979年から始め、1991年(12期生)まで続けた「地域福祉活動指導員養成課程」は、筆者の研究者的成長に大きな影響を与えると同時に、そこでの相互の学びの過程を通じての実践者との交流が「バッテリー型研究方法」の推進とその後の実践者の組織化に非常に大きな役割を果たしてくれた。その養成課程では、設置された各教科目のテキストに基づき、レポートが課され、添削指導を受けた上で4泊5日の宿泊スクーリングがあり、修了論文の提出が課せられた。
筆者はその第1期から「社会福祉教育論」という科目を担当した。それは多分、筆者が「社会教育と地域福祉」の学際的研究を行い、既に「月刊福祉」等の雑誌や著作で「社会教育と地域福祉」に関わる論文を執筆していたからお呼びがかかったのであろうと推察している。
筆者の社会福祉学研究、地域福祉論研究において福祉教育は大きな柱である。後に筆者は、福祉教育を「憲法第13条、第25条などに規定された基本的人権を前提にして成り立つ平和と民主主義社会を作りあげるために、歴史的にも、社会的にも疎外されてきた社会福祉問題を素材として学習することであり、それらとの切り結びを通して社会福祉制度、社会福祉活動への関心と理解を進め、自らの人間形成を図りつつ、社会福祉サービスを利用している人々を社会から、地域から疎外することなく、ともに手をたずさえて豊かに生きていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身につけることを目的に行われる意図的な活動」(1982年)と定義した。
この定義は、戦前の社会問題対応策としての社会事業と社会教育との関係性、とりわけ内務省が推進した風化行政、地方改良運動、精神作興運動等の研究を踏まえたものである。
この福祉教育の考え方と実践は市町村社会福祉協議会が住民主体の活動を展開する上で必要不可欠な活動であると筆者は位置付け、先の「地域福祉活動指導員養成課程」において、“社会福祉協議会の活動は福祉教育に始まり、福祉教育に終わる”ほど重要な活動であることを強調してきた。
島根県瑞穂町(現邑南町)社会福祉協議会の事務局長になった日高政恵さん(「地域福祉活動指導員養成課程」の修了者であり、1997年の第1回こんぴらセミナーのシンポジュウムの登壇者でもある)は、住民の生活実態に関する様々な調査を行い、それを踏まえて68の集落福祉委員会を基盤に、13のブロックでの「地域福祉デザイン教室」を行い、徹底的に住民による問題発見・問題解決型の共同学習を通じて、住民の社会福祉意識の変容、向上を図る地域福祉実践を展開した(『未来家族ネットワークの創造――安らぎの田舎への道標』万葉舎、2000年参照)。
瑞穂町の実践は、子どもの福祉教育、住民の社会福祉学習、介護福祉人材の養成等町全体で文字通りトータル的に福祉教育を行っており、日高さん自身社会福祉協議会活動は“福祉教育に始まり、福祉教育に終わる”と述べてくれている。
福祉教育のより体系的実践としては、1988~89年に策定された東京都狛江市社会福祉協議会の「あいとぴあ推進計画」で位置付けられた「あいとぴあカレッジ」がある。
「あいとぴあ推進計画」は、狛江市社会福祉協議会の須崎武夫さん(「地域福祉活動指導員養成課程」の修了者であり、のちに事務局長)が東京都社会福祉協議会のモデル指定地区を受託し、社協中心の地域福祉計画づくりを行ったものである。筆者はこの策定委員会の委員長で、委員には狛江市福祉事務所の所長にも入ってもらい、行政との整合性を持たせることを意図した。その後、狛江市は「あいとぴあ推進計画」と連動させた「あいとぴあレインボープラン」を行政計画として策定。狛江市では「あいとぴあレインボープラン」に基づき狛江市条例による「市民福祉委員会」を設置し、重要な社会福祉政策課題については「市民福祉委員会」で協議することを明記。筆者はその「市民福祉委員会」の委員長を15年勤めた。
「あいとぴあ推進計画」に基づく「あいとぴあカレッジ」(1991年から実施)は、年間15回程度の本格的な市民福祉教育のカレッジとして実施された(『地域福祉計画策定の視点と実践――狛江市のあいとぴあへの挑戦』第一法規、1996年参照)。「あいとぴあカレッジ」を担当した阪野貢さん(当時宝仙学園短期大学、のちに中部学院大学教授)が「市民福祉教育研究所」を設立・主宰し、ブログも開設しているので参照されたい。
また、体系的な福祉教育実践としては狛江市の実践よりも早く、筆者は山口県宇部市において1977年より「宇部市婦人ボランティアセミナー」を企画・実施している。
このセミナーは、文部省(当時)の助成事業を活用しての実践であるが、社会福祉と社会教育との有機的連携を意識したもので、1年間に17回の座学(講義)と14回の体験、実習(朗読、点字、手話、配食サービス、老人の介護等)のプログラムが組まれた本格的な福祉教育の実践であった(『宇部市の生涯学習推進構想――いきがい発見のまち』東洋堂企画出版社、1999年参照)。筆者は17年間、毎年数回宇部市に通い、最後はセミナー(後に2年制のカレッジに改組)30周年記念までお付き合いをしてきた。
このような実践は、上記以外でも、岩手県沢内村(現西和賀町)社会福祉協議会で地域福祉計画の策定とそれに基づく「コーリム大学」を1990年代初頭に実施した。
筆者の問題発見・問題解決型共同学習的福祉教育は、1973年の東京都稲城市(筆者の居住地)における「住みよい稲城を創る会」(代表幹事・大橋謙策)が主催した「集い」が最初である。
そのプログラムは、初めに生活問題を抱えている人に実態報告をして頂き、その後分科会に分かれて討議をするというスタイルで行われた。第1回目の集いでは、「嫁」(息子の配偶者)の立場から同居している姑の介護問題の報告、父子家庭の単独世帯の子育ての困難さの報告、学校拒否児(当時の呼称)を抱える家族の悩みの3事例の話を頂いた。
東京都の「市」ではあっても、農村的風土が残っていた地域だっただけに、「集い」というオープンな場での発題者を探すのに大変苦労はしたが、発題者の問題提起は実に重要で、その実態の深刻さが浮き彫りになった。その当時、筆者は知らなかったが、既に市内(当時人口3万人)に多くの学校拒否児がいたようで、その親たち(15名)が学校拒否児の親の体験報告があるということで個々に「集い」に参加してきていた。当初、分科会としては設定していなかった学校拒否児に関する分科会を親たちの要望で急遽作ったことが昨日のように思い出される。いかに、“事実は小説よりも奇なり”で、我々がその実態をただ把握していないだけだということを痛感させられ、アウトリーチによる問題発見の重要性に気づかされた。
1997年に香川県琴平町で開催された第1回こんぴら地域福祉実践セミナーは、「ふれあいのまちづくり事業」の補助金による事業ということも考えて、単なる一過性の福祉講演会ではなく、福祉教育、住民の社会福祉学習の機会として、かつ継続することを意識して行われた。当時、人口約1万2,000人の町で、参加者が600人にのぼり、会場が立錐の余地がないほどの状況は驚きであった。考えてみれば、1986年に琴平町社会福祉協議会が受託した「ボラントピア事業」において、夏の暑い日に、冷房のない学校の体育館に並べた椅子と椅子の間の通路に氷柱を何本も立てて行われた講演会になんと1,000人が参加された歴史を持っていた(講演者・大橋謙策)。それらの仕掛けをした琴平町社会福祉協議会の越智和子さん(現琴平町社会福祉協議会常務理事)も20代末の若い時に、山口県笠戸島で「地域福祉活動指導員養成課程」を受講した一人である。
筆者は、このような地域福祉と社会教育の学際的研究と実践に関わるなかで、1979年、全国社会福祉協議会が設置した「ボランティア基本問題検討委員会」(委員長・阿部志郎、作業委員長・大橋謙策)において起草委員長として「ボランティア活動の性格と構造」をまとめさせて頂いた。それは①ボランティア活動と市民活動との関係性をどう整理するかという問題、②ボランティア活動の目的を“自立と連帯の社会・地域づくり”と考えること、③市民活動とボランティア活動を考える場合、その活動には3つの性格の活動があること。それは第1に近隣での日常的なふれあいのある地域づくりを行うこと、第2に地域内にある福祉サービスを必要としている人を発見し、その個別課題に対応する対人サービス活動を行うこと、第3に市町村における(地域)福祉計画づくりを行うことの3つの課題があり、それらを構造的に捉えて考え、実践することの重要性を提起した。
また、そのような市民活動とボランティア活動との関係を意識したのは、1970年前後のコミュニティ構想が“住民参加、住民の権利ということが担保されない、権限なきコミュニティにおいて、麗〈うるわ〉しき隣人愛に基づく活動、助け合い活動”を求めていたことへの反論であり、かつ地域住民の生活を守るためには国レベルの社会保険制度の整備と共に、居住する市町村自治体における福祉サービスの整備が必要であり、重要であると考えたからに他ならない。(全社協・ボランティア基本問題検討委員会報告書「ボランティアの基本理念とボランティアセンターの役割」全社協、1980年参照)。
また、その頃、福祉教育の実践が求める目標として「4つの地域福祉の主体形成」(地域福祉計画策定主体、地域福祉実践主体、社会福祉サービス利用主体、社会保険制度契約主体)の必要性をまとめ、提起している。
「我が事・丸ごと地域共生社会」の実現に向けて、市町村における行政と住民の協働のあり方や全世代支援を行えるワンストップサービスができるシステムの構築等を考え、実施できるようにするためにも、まずもって住民参画による市町村地域福祉計画づくりが重要になる。また、その計画策定主体の形成も含めて地域福祉の4つの主体形成がなされなければ実現は難しいことになる。
福祉教育を皮相的にとらえるのでなく、地域住民が社会福祉の学習を通じ、地域にある問題に目を開き、気づき、それを解決するためにどう行動するべきかを考える機会を提供する福祉教育こそ地域福祉実践の根幹であることを改めて認識して欲しい。
Ⅱ ニーズ対応型福祉サービスの開発と「福祉でまちづくり」
筆者は1990年まで、日本には事実上ソーシャルワーク実践はなかったということを日本社会事業学校連盟(現日本ソーシャルワーク教育学校連盟)の社会福祉教育セミナーの席上や日本社会福祉学会等の場において発言してきた。しかしながら、残念ながら反論はされなかった。それどころか、戦後日本のケースワーク研究を牽引し、国際社会事業学校連盟からも高く評価されていた仲村優一先生は、“まさに君(筆者)が言う通りである”とさえ言われ、逆に日本におけるソーシャルワーク実践の定着を図る研究をしっかり頼むと励まされる状況であった。
戦後日本では、アメリカの文化、社会福祉に関するシステムの中で育ったケースワーク、グループワーク、コミュニティオーガニゼーションといった方法論が紹介・解説され、社会福祉教育の場において教えられてきた。
そこでは、インテークという用語やクライエントという用語が使われ、福祉サービスを利用しようとして、あるいは生活上の様々な問題を抱えて相談機関に来談した人とのラポートづくりから実践が説き起こされてきた。
筆者のように、戦前の社会事業における精神性と物質性の関係性の研究、地域改良・居住者の生活改善・人格向上を目指すセツルメント運動等を研究してきたものにとって、それには非常な違和感があった。多くの“社会福祉研究者”は筆者(大橋謙策)に対し、社会福祉六法体制とケースワーク等の社会福祉方法論とを前提としている“社会福祉プロパーの研究者”として認めず、“社会福祉体系外の研究者”として位置付ける言動を投げかけていた。
1977年に上梓され、1980年に日本語に翻訳されたハリー・スペクト/アン・ヴィッケリー編『社会福祉実践方法の統合化』 (Integrating Social Work Methods編)において、アメリカのシステム理論やイギリスの地方自治体社会サービス法に基づく実践を通して、1930年代にアメリカで確立された社会福祉方法論の3分類法を「ソーシャルワーク」に止揚するべきであるという問題提起がなされ、それが日本語に翻訳されて紹介されているにも拘わらず、日本では実質的に2000年まで社会福祉士養成のカリキュラムの中で社会福祉方法論の3分類法を堅持しつづけた。しかも、いまでも多くの研究者がインテーク、クライエントという用語を無自覚的に論文上でも使用している。
筆者は、1973年に東京都稲城市立公民館の建設に際し、1947年に制定された児童福祉法の国会審議に向けて厚生省(当時)が作成した予想問答集の考え方(保育所設置の目的は①働かざるを得ない母親の就労支援、②子どもの成長には集団保育が必要、③文化国家、民主国家を建設するには女性の社会参加、社会活動を促進する必要があるので子どもを預ける保育所が必要)に基づき、公民館に市の専任職員である保母(当時)を常駐させた公民館保育室の設置を社会教育委員として提案し、建設した。その公民館の機能として住民のたまり場、交流の場としての機能・空間ももたせた。また、同じように1975年には、児童館、老人福祉センター、公民館を合築する地区公民館の建物の構想を示し、建設した。
更には、1973年、貧困児童の就学援助を増進させるために、当時、文部省の基準は生活保護基準の1.5倍が就学奨励費支給の基準であったものを市と交渉し、1.6倍にまで引き上げてもらった。
このような実践を若い時(20代)からしてきたものにとって、「申請主義」に囚〈とら〉われた社会福祉実践・研究やカウンセリング的ケースワーク論は何とも理解しがたいものであった。そのような発想は、社会福祉方法論の分野のみならず、施設経営をする社会福祉法人も陥っていた呪縛であり、市町村社会福祉行政自体も囚われていた呪縛であった。
日本の社会福祉実践、研究は、1990年まで中央集権的機関委任事務体制で展開されてきたこと、また福祉サービスも行政もしくは行政に委託された社会福祉法人が運営する施設において提供されてきたために、法人・施設運営の視点はあったものの、経営の視点は脆弱であったし、市町村における社会福祉行政のアドミニストレーションに関する研究は実質的になかったと言わざるを得なかった。
ある意味、国が設計する制度に基づく“制度ビジネス”に“安住”しており、そこでは、一般に経済界で必要とされている“市場調査”としての“サービスニーズの把握”の視点や方法、あるいは“商品開発”に該当する“ニーズ対応型サービス開発”の意識は希薄であったことは否めない。
筆者は、戦後の社会福祉実践・研究は中根千枝先生の研究の「鍵」概念を借りれば、「場」(枠組み)である制度としての枠(社会福祉六法体制、中央集権的機関委任事務体制)の中で社会福祉実践・研究を考え、行われてきたと指摘してきた。
しかしながら、21世紀においては「資格」(機能)として求められているソーシャルワーク機能に基づき、潜在化しがちな国民のニーズの発見・キャッチが重要であり、かつそれに対応したサービス開発とその起業化・経営が必要であることを頓〈とみ〉に1990年以降指摘してきた(「施設の社会化と福祉実践」『社会福祉学』第19号、日本社会福祉学会、1978年所収)。それ以降、ニーズ対応型のサービス開発のヒントは、入所型施設で提供しているサービスを細かく分節化させることや家庭機能を分節化させて、それをどういうシステムで提供するかを考えることにあると述べてきた。また、1990年以降「福祉でまちづくり」の必要性を提起してきた。
21世紀に入り、急速に進められている規制緩和の時代にあっては、社会福祉分野といえどもニーズの把握、ニーズ対応型サービスの開発とその起業化に関する研究が社会福祉研究上求められている。それは、ソーシャルワーク機能そのものが問われていることでもある。それはまた、ソーシャルワークの楽しさ、醍醐味を味わう機会でもある。
ソーシャルワークの使命(ミッション)は、ニーズキャッチ・発見を基盤に、それらの問題解決に向けてのサービスの提供、サービスの開発であり、それこそソーシャルワークの価値であることを忘れてはならない。
筆者は、今、①高齢者分野の介護保険制度外のサービス開発と供給の方法に関する研究(株式会社などが入所型施設で提供してきているサービスを細かく分節化させて、必要時に即応できるサービスシステムの開発をし、サービスを介護保険制度外のサービスとして提供している。従来の地域福祉実践はこれらの制度外のニーズに対応できているのであろうか)、②介護保険制度外の福祉機器、介護ロボットの購入・利活用に関する研究(障害者分野の補装具や介護保険の福祉用具の利活用と一般市販される福祉機器との利活用がボーダーレスになってきており、その相談、利活用システムのあり方が問われている。既に、福祉機器・介護ロボットの利活用・相談センターが制度外で動き始めている)、③障害者総合支援制度外のニーズキャッチとその商品開発、及びそれに関わっての新たな障害者の雇用形態、就労形態のあり方を考えた「起業化」が行われており、それにふさわしい経営形態はどういう組織がいいのかに関する研究、④「限界集落」、「消滅市町村」における「高齢者の、障害者のための福祉のまちづくり」ではなく、高齢者も障害者も参画した「福祉でまちづくり」という新たな第8次産業(第6次産業+障害者・高齢者・子育て中の親の参画+商店街を構成する生活衛生同業者組合も参画した地産地消・循環型地域経済)を創出することに関する研究に関心を寄せて実践に関わっている。「福祉でまちづくり」という用語は、1990年の岩手県遠野市の地域福祉計画策定において使用したのが最初である。それは特に市議会議員の研修会でその必要性と重要性を指摘した。
この④の研究、実践は、文字通り地域福祉実践そのものに関わる実践であり、これは地方創生や立地適正化計画(コンパクトシティ計画)、あるいは休耕田、空き家対策等とも関わるまちづくり、地域づくりそのものの課題であり、地域経済に関わる研究、実践でもある。
山形県鶴岡市の地域福祉計画策定において、新しく特別養護老人ホームを100床、ユニット型で建設する構想(社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会立特別養護老人ホームおおやま、2005年)に際し、地産地消型の視点を取り入れるべく、商工会に特別養護老人ホームへの食材等を納入する協同組合を新たしく設立頂き、地元の商工業者に参入頂いた。全国の約7,000ある介護老人福祉施設(特別養護老人福祉施設)及び全国に約4,000ある介護老人保健施設がこのような発想で「地産地消」の取り組みをすれば、地域経済に与えるえる影響は大きく、現在言われている社会福祉法人の地域貢献の実態よりもその影響は大きく、これこそ社会福祉法人の役割、責務ではないのだろうか。
先に述べた島根県瑞穂町の実践のスローガンは「未来家族ネットワークの創造」であったが、それはもう民法上の血縁家族に頼っていたのでは「中山間地域」という地域での地域自立生活が維持できなくなってきており、地域に居住している人々が血縁を超えて“地域の未来家族”として生活をしていこうとする願いでもあった。
一人暮らし高齢者のみならず、地域生活している単身の精神障害者や知的障害者、非婚の男性、女性が増えることを考えると、これからは「少子高齢社会」もさることながら、「単身生活者の時代」になり、単身生活者の生活支援が深刻な課題になる。そこでは、血縁家族機能へ期待することは幻想である。家族が居なくても、家族に頼ることもなく、人生を全うできるように、日常生活自立支援のシステム、成年後見制度のシステム、入退院支援のシステム、死後の対応としての葬儀・遺骨の取り扱いも含めての支援等、本人の意思の確認と尊重を踏まえた“自立生活支援”のシステムを地域ごとに構築していかなければならない。まさに、「未来家族ネットワークの創造」である。ここでも従来の地域福祉実践の枠組みを再検討しなければならない。
今や、社会福祉の制度の枠に縛られた実践、制度を改善することのみに行きがちな“制度ビジネス”的な実践、研究を脱皮し、新たな視点での実践と研究が求められている。
とすれば、地域福祉実践も従来の枠を超えて、「福祉でまちづくり」の視点を大胆に取り入れ、かつその実践組織も社会福祉協議会や施設経営の社会福祉法人だけでなく、NPO法人、株式会社も含めた多様な組織体による起業化が行われ、そのプラットホームの上に地域自立生活支援が成り立つという新たな地域福祉の展開の時代として、研究枠組みも実践の方法も考え直さなければならない。
四国・こんぴら地域福祉実践セミナーで取り上げられた徳島県のNPO法人どりーまぁサービスの山口浩志さんは在宅のALS患者や重症心身障害児者への24時間ケアサービスを提供しているが、その根源には住民からの相談を断らないという哲学がある。その相談こそが“ビジネスチャンス”であるという発想で、それに柔軟に対応するために、かつその実践の社会的評価を得るために、社会福祉法人という経営形態ではなく、かつ株式会社という経営形態でなく、NPO法人という経営形態を選択したと言っている。
同じく徳島県美馬市木屋平地区のNPO法人こやだいらの実践、高知県津野町の学校跡地を利用した「集落福祉としての『森の巣箱』」の実践、人口減に伴う利用者減による経営困難でJAさえも撤退した山間地域でのガソリンの供給から日常生活の買い物支援、全世代交流支援型のサービス提供等の多機能型の地域づくりを展開している地域の生活支援の中核的組織である「あったかふれあいセンター『いちいの郷』」の実践などは、従来の狭い地域福祉実践の枠を超えた地域づくりそのものであり、血縁家族を超えた、地域での住民の自立生活を支援する実践である。
徳島県美馬市木屋平地区(合併前の旧木屋平村)のNPO法人こやだいらの実践は、筆者が“ベッドサイドから診察室まで、スーパーから冷蔵庫までの実践”と勝手に命名したが、人口710人の集落(高齢化率58%)での、世帯単位ではなく、個人単位の加入による「集落福祉のNPO法人版」である。標高1,955メートルの剣山の中腹(標高800メートル、地区の集落は標高200~800メートルに散在)で、一面の雲海を下に見ながら、蝉しぐれの中で、住民座談会を開催し、木屋平地区の集落福祉をどう進めるかを論議し、NPO法人格を取得して行うしかないといった論議をしたことが昨日のように思い起こされる。
これからの地域福祉実践には「福祉でまちづくり」をスローガンに、基礎自治体を基盤にしつつも、共同性と土着性が強い稲作農耕によって作られた、自然発生的に形成された地域、自治会を超えて、一定の生活圏域ごとにより分権化(市町村からの地域組織への第3の分権化、東京都地方分権推進委員会及び東京都社会福祉審議会で、委員として筆者が提唱)させた新たな地域組織に再編成し、そこで地域の多様な生活課題を解決する多機能型地域組織を構築し、活動を推進していくことが求められる。
それはある意味、住民一人ひとりが「選択的土着民」(静岡県掛川市元市長の榛村純一氏が提唱)となって、地域づくりに関わることであり、それはある意味、住民総参加の直接的民主主義という、地域を“コミューン”にすることである。そこに「限界集落」、「消滅市町村」問題を乗り越える一つの鍵がある。NPO法人こやだいらや「ふれあいあったかセンター『いちいの郷』」の実践はその萌芽とも言える。
Ⅲ 行政と住民の協働を触媒・媒介するコミュニティソーシャルワーク
イギリスのミヒャエル・ベイリイが提唱(1973年)した考えを基に地域福祉の考え方に関わる発展段階を整理すると① Care Out The Communityの時代、② Care In The Communityの時代、③ Care By The Communityの3つの発展の時期・時代がある。
筆者は、日本では1971年~1990年が①の時代で、1990年~2000年までが②の時代であり、2000年以降は③の時代に入り、社会福祉法制も社会福祉法への改称・改正で理念的にそれを求め、明確化したと述べてきた。地域におけるヴァルネラビリティの人々とその人々を排除しない地域のあり方を指摘した2000年12月の「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」の報告書が出された意味は大きい。
ところで、コミュニティソーシャルワークという用語とその考え方は、1982年のイギリスでの「バークレイ報告」で提唱されたものであるが、イギリスではその考え方が実践的に必ずしも成功したとは言えない。
筆者は、日本的にコミュニティソーシャルワークがそれなりに定着できる状況になってきている要件として、(イ)まがりなりにも日常生活圏域における自治会等の地域組織機能があること、(ロ)全国の市町村に、地域を基盤として活動している社会福祉協議会が組織されていること、(ハ)全国の市町村に23万5千人の民生・児童委員と約5万人の保護司が設置されていることが大きいと考えている。
コミュニティソーシャルワークという考え方は、上記の③の時代には不可欠な考え方である。施設サービスから脱却し、地域での自立生活を支援していくためには、行政の力だけでは遂行できず、地域住民の参加、協働が欠かせない。そのためには先に述べた地域住民の4つの地域福祉の主体形成が求められる。
行政と住民との協働を促進し、住民の主体性を高め、住民自身が地域の問題を発見し、その問題に対し差別・偏見を持たず、地域から排除することなく、地域で問題解決を図る活動を推進するためには、住民の活動を活性化、促進させる触媒機能が重要であり、かつ行政と住民との協働を安定的に媒介させる機能が重要であり、それこそコミュニティソーシャルワーク機能である。
ところで、地域自立生活を支援するコミュニティソーシャルワーク機能の日本的発展段階には5つの段階があったと筆者は考えている。
第1の段階は、1979年にいち早く高齢化が進展していた秋田県が県単独事業として政策化させた在宅相談員制度である。一人暮らし高齢者を孤立させず、地域で見守ろうという実践で、社会福祉協議会と民生委員との協働の下に展開された。
筆者は、その初年度の在宅相談員の研修に招聘、参加させて頂いた。秋田県男鹿観光ホテルで行われた研修会では、従来の血縁的、地縁的見守りを昇華・発展させ、社会化させたシステムとして展開しようとする試みに社会福祉の新たな息吹と地域福祉実践の必要性を改めて認識させられた機会であった。そのもっとも優れた実践の一つは秋田県西仙北町社会福祉協議会の佐藤春子さん(「地域福祉活動指導員養成課程」修了者)の取り組みで、「一人ぼっちの不幸も見逃さない」という映画になり、その後“黄色いハンカチ運動”等に繋がっていく。社会福祉協議会と小地域とが協働して住民の孤立やゴミ出し等のちょっとしたお手伝いを行う事業は現在でも全国で行われており、富山県のケアネット事業等も県単で行われている。
第2の段階は、1990年に「生活支援地域福祉事業(仮称)の基本的考え方について」(平成2年8月、生活支援事業研究会中間報告、厚生省社会局保護課所管)と題する報告書がだされてからである。
筆者自身が、コミュニティソーシャルワークにより関心を寄せ、その政策化に関わるのは、この研究会の座長を仰せつかってからであり、日本におけるコミュニティソーシャルワーク機能が政策的に、実践的に意識された年である。
この報告書に基づき、1990年度にモデル事業として展開され、その成果を踏まえて政策化されたのが1991年度より始まる「ふれあいのまちづくり事業」という大型補助金事業である。モデル事業は福祉事務所、保健所、市町村社会福祉協議会で展開されたが、最も報告書の考え方を踏まえ実践してくれたのは富山県氷見市社会福祉協議会の中尾晶美さん(中尾さんも「地域福祉活動指導員養成課程」の修了者で、のちに事務局長を勤める)である。筆者は、氷見市社会福祉協議会へ約35年間通い、「バッテリー型研究方法」を展開した。最後の頃は、氷見市行政アドバイザーも勤めての実践だったこともあり、「ふれあいのまちづくり事業」は市町村社会福祉協議会で実施されることになった(このモデル事業の評価委員長は宮城孝現法政大学教授が担ってくれた)。
これが、実質的な意味での日本におけるコミュニティソーシャルワーク実践の始まりと言える。
この事業では、今日大きな問題となっている潜在的福祉サービスを必要としている人の発見、しっかりしたアセスメントによるケアマネジメントに基づく援助方針の立案、専門多職種によるチームアプローチ等が提唱された。また、制度の谷間の問題、多問題家族、多重債務者、在住外国人、核家族・単身者の入院時支援、家庭内暴力の問題等への対応の必要性と重要性を指摘している。
しかしながら、この「ふれあいのまちづくり事業」でコミュニティソーシャルワーク機能の具現化が図れたとはいいがたいと筆者は考えている。この補助事業が多くの市町村社会福祉協議会を活性化させる契機にはなったと思うが、コミュニティソーシャルワーク実践の具現化と先に述べた「生活支援地域福祉事業(仮称)」の具体化という点では筆者は必ずしも成功したとは考えていない。
第3の段階は、1993年から日本社会事業大学の社会福祉学部福祉計画学科の地域福祉コースの所属教員が研究会(研究代表・大橋謙策)を立ち上げ、厚生省(当時)の老人保健健康増進等事業の助成を受けて全国のいくつかの市町村をフィールドにして「在宅福祉サービスにおける自己実現サービスの位置とコミュニティソーシャルワークに関する実践的研究」を始めてからである。その研究成果は毎年報告書として出されているが、それを基に大橋謙策他編『コミュニティソーシャルワークと自己実現サービス』(万葉舎、2000年)が上梓されているので参照されたい。
そのフィールド市町村の一つである岩手県湯田町(当時、現西和賀町)社会福祉協議会において、主任ホームヘルパーの菊池多美子さん(「地域福祉活動指導員養成課程」の修了者で、全社協の「社会福祉主事養成課程」の修了者でもある。また、第1回こんぴら地域福祉実践セミナーのシンポジストとしても登壇)が実践していた事例に触れ、その実践こそがコミュニティソーシャルワーク機能を具現化させている実践であり、コミュニティソーシャルワーク機能の具現化を全国的に展開できると勇気づけられた実践であった(菊池多美子著『福祉の鐘を鳴らすまち―「うんだなーヘルパー」奮戦記』万葉舎、1998年参照)。
その実践には、①アウトリーチも含めた問題発見、②フォーマルケアとインフォーマルケアとを有機化させて提供、③個別対応型支援ネットワーク会議の開催、④伴走型のソーシャルワーク、⑤ニーズ対応型サービス開発、⑥社会福祉協議会独自の新しい財源創出等の機能を濃淡含めて実践していた。その考え方に学び、実践を体系化すると同時に、新たな理論仮説を提起し実践もして頂いた。この実践に関わることにより、筆者はコミュニティソーシャルワーク機能の実践ができると確信がもてた。
ただ、その実践は必ずしも意図的な、自らの仮説をもって、検証し、見直すというPDCAサイクルの実践でなかったこと、組織的には容認され、実践されていたが必ずしも社会福祉協議会の計画的、組織的位置づけの下に行われていなかったこと、かつその実践はすぐれて個人的であり、システムとして構築されていたわけでなかったこと等の課題があった。
その後、これら湯田町の実践における課題を解決するためにはコミュニティソーシャルワークを展開できるシステムづくりが必要であると考え、それには市町村地域福祉計画の策定との関わりが不可欠との認識をより強めさせることになった。
筆者は1970年代から市町村の地域福祉計画の必要性を論文で書いてきたし、先に述べた「ボランィア活動の性格と構造」のなかでも(地域)福祉計画の必要性を述べている。また、全社協が設置した「地域福祉計画研究委員会」にも委員として参加し、その委員会の報告書として1984年に上梓されている『地域福祉計画――理論と方法』(全社協)にも執筆している。筆者は、この研究会の論議を踏まえ、1985年に「地域福祉計画のパラダイム」という論文(『地域福祉研究』№.13所収、日本生命済生会福祉事業部刊)を書いているので参照されたい。
(註) 地域福祉計画策定委員長として1988年から取り組み、1990年に制定した東京都狛江市「あいとぴあ推進計画」(大橋謙策著『地域福祉計画策定の視点と実践』第一法規、1996年参照)や東京都目黒区が1990年から取り組んだ「目黒区地域福祉計画(福祉事務所と保健所を合体させ、人口26万人の区内を5地区に分け、その各々に保健福祉サービス事務所を設置)、あるいは同じく1990年から取り組んだ「遠野市ハートフルプラン」(大橋謙策他編『21世紀型トータルケアシステムの創造』万葉舎、2002年参照)等の計画策定の実践を行ってきた。
あるいは東京都児童福祉審議会(専門部会長・大橋謙策)において、筆者が委員長としてまとめた1990年の東京都東大和市の地域福祉計画で構想したものを、東京都児童福祉審議会専門部会に部会長である筆者が提案し、具現化して1994年から創設された「子ども家庭支援センター」(センターに保健師、社会福祉士、保育士を配置し、各区市町村に設置、現在58か所)等の政策提言及びその具現化の政策化及び実践がある。
これら一連の地域福祉計画において政策提言したことと、先のコミュニティソーシャルワークの実践課題の解決とを結び付けて提案し、システム化させたのが2000年4月から始まった長野県茅野市の保健福祉サービスセンターの実践である。
コミュニティソーシャルワークの発展の第4段階は、地域包括ケアシステムとコミュニティソーシャルワークとの連携がシステムとして確立できた長野県茅野市の保健福祉サービスセンターのシステムであり、実践である(筆者は1998年から15年間茅野市福祉行政アドバイザーを担当)。
この時期は、厚生労働省も未だ地域包括ケアとか、地域包括ケアシステムという用語は使っていないし、政策化させていない時期であった。筆者は、1990年の岩手県遠野市の地域福祉計画づくりから「地域トータルケアシステム」という用語を使用してきた。
長野県茅野市は、地域トータルケアシステムの拠点としての保健福祉サービスセンターを市内4か所に設置(当時人口5万7千人、中学校区9)し、市役所内にいた福祉事務所の職員、保健課の保健師を再編成して配属した。それに加えて市社会福祉協議会の職員も配属して、子ども、障害者、高齢者の全世代に対応するワンストップサービスを展開することにした。
基本的には、行政職員(ソーシャルワーカー)、保健師、社会福祉協議会職員(ソーシャルワーカー)が3人1組でチームアプローチをすることにした。それは、フォーマルサービスとインフォーマルサービスとを有機化させることとアウトリーチ型のニーズキャッチをやりやすくさせるためであった。ある年の社会福祉協議会の職員は年間280日も地域へ出張り、住民の相談とニーズキャッチに努めた。社会福祉協議会のソーシャルワーカーを配属したのは地域住民の福祉教育の促進や住民のインフォーマルケア力の向上と活用の促進を図るためでもあった。
その保健福祉サービスセンターでは、フォーマルな制度、サービスのコーディネート、家族、地域の支え合い及び新たな意図的なソーシャルサポートネットワークの構築とコーディネート、更には福祉サービスを必要としている人を発見、あるいは新たに必要な福祉サービスの開発等の機能を総合的、統合的に展開できるシステムとして構想された。
しかも、そのシステムは地域の各機関の機関長レベルの連絡調整ではなく、個別具体的な問題を個々に解決するためのチームアプローチを行う個別対応型支援ネットワーク会議を開催し、具体的支援をリードする拠点システムとしても構想された。
また、茅野市保健福祉サービスセンターには、内科クリニック、訪問看護、高齢者デイサービス、訪問介護、地域交流センターを併設し、更には、システムとして内科クリニックと諏訪中央病院との病診連携、「かかりつけ医」制度の促進を図ることなども組み込んだ(大橋謙策他編『福祉21ビーナスプランの挑戦』中央法規出版、2003年参照)。
長野県茅野市の計画、実践において、筆者は保健、医療、福祉の連携のみならず、社会教育との連携を意識して取り組んだ。地域福祉計画づくりに社会教育との連携を意識的に組み込むのは、1990年の遠野市の計画づくりからである。
なぜ、社会教育との連携を意識化したかというと、福祉サービスを必要としている人を発見し、支えていく上で、地域住民の力はプラスに働く場合もあれば、ややもするとそれらの人々への偏見、蔑視が働き、排除の動きにもなる恐れがあるので、地域住民のこれらの問題への関心の醸成と理解の深化を図ること及び住民自身が福祉サービスを必要としている人の支援者になることへの変容が求められるので、そのためにも筆者は一貫して地域福祉実践には福祉教育が不可欠であると述べてきたし、その一翼を社会教育が担うべきであると考えてきたからである。
更には、「福祉でまちづくり」の考え方を実現していくためには、住民の問題発見・問題解決型の共同学習が必要不可欠であると考えたからでもある。
まさに、地域包括ケアの構築には住民の学習を推進する社会教育行政との連携が必要と考えたからに他ならない。
この茅野市の実践事例は、その後、静岡県富士宮市、掛川市、千葉県鴨川市等へ波及していく。
茅野市のシステムと実践は、2006年に制度化された介護保険制度の地域包括支援センターのシステムとしてのモデルであり、かつコミュニティソーシャルワーク実践を展開できるシステムのモデルでもあった。
2016年7月からは、東京都世田谷区(人口91万人)の27地区に設置されている地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)で、子ども、障害者、高齢者の全世代支援型のワンストップサービスが始まっており、その地区ごとにコミュニティソーシャルワーク機能を担う社会福祉協議会の職員が1.5人ずつ配属されて活動している。
筆者が、この間、手がけてきた地域福祉実践の考え方が国の政策のあり方に最も反映されたものとして、2008年に発表された『地域における「新たな支え合い」を求めて――住民と行政の協働による新しい福祉』がある。この厚生労働省の研究会の座長を勤めさせて頂いたが、筆者が研究し、地方自治体で実践的に制度化、政策化させた考え方がほぼ反映されたと思っている。
しかも、その考え方は、2009年から始まる「安心生活創造事業」というモデル事業の創設により実証的に検証されることになる。そのモデル事業の市町村に指定された中に香川県琴平町があるし、筆者がアドバイザーとしてシステムづくりに関与している千葉県鴨川市も含まれている。
これらの地域福祉実践の積み重ねが、理論的にも、実践的にも可能性があるという判断がなされたのであろう、2015年9月に発表された厚生労働省の「新しい福祉提供ビジョン」にこれらの考え方が政策的に引き継がれていく。
コミュニティソーシャルワークの第5段階は、この「新しい福祉提供ビジョン」をどう具現化させるかという時代である。
その理念をより強固に具現化させるべく、2016年7月に「我が事・丸ごと地域共生社会」実現本部が設置された。
そこで求められる実践課題を筆者なりに改めて整理すると、①筆者のいう4つの地域福祉の主体形成と福祉教育の課題、②「福祉でまちづくり」を推進する上で必要なニーズ対応型サービスの開発というソーシャルワーク機能を発揮できる職員の養成とそれを展開できるシステムづくりの課題、③行政と住民の協働を触媒・媒介させるコミュニティソーシャルワーク機能とそれを展開できるシステムの課題がある。
ところで、これらのことを具体的に実施できるシステムの運営のあり方とその市町村毎のアドミニストレーションはどうあったらいいのか等は研究的にも、実践的にも未だ緒に就いたばかりであり、地域福祉研究的にはほとんど皆無の状況である。
ましてや、これらの活動の担い手をどう養成し、配属できるのか十分な展望を持てていない。筆者が理事長をしているNPO法人日本地域福祉研究所は、全国の県、市、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会等と協働して、多数のコミュニティソーシャルワークの研修の機会を担ってきているが、果たしてその研修内容や方法も今のままでいいのか、かつての「地域福祉活動指導員養成課程」のようなe-ラーニングも含めたより体系的養成課程を行う方がいいのか、かつ全国の市町村においてコミュニティソーシャルワークの養成・研修を実施することへの対応の展望は見えていない。
イギリスでは、大きな制度改革が行われるときには、必ずといっていいほどその制度改革を担う人材の養成のあり方を連動させて取り組んできた。日本では、制度は制度、人材養成は別か、あるいは制度に必要な人材を制度ごとの研修で養成するという立ち位置で行われてきた。そろそろ、ソーシャルワーク機能、とりわけコミュニティソーシャルワーク機能を発揮できる人材の養成を抜本的に考える必要があるのではないか。今の社会福祉士の養成課程がこれから求められるソーシャルワーク機能を発揮できる人材の養成として相応しいとは必ずしも筆者には思えない。
それらのことも含めて、「我が事・丸ごと地域共生社会」の実現にはいろいろ難しさがある、そうであればあるほど、改めて、今求められているコミュニティソーシャルワーク機能とはを整理、確認しておきたい。それが常に意識されていないと、福祉サービスを必要としている人を発見し、その人々が抱える問題を“我が事”のように理解、共感し、その問題を行政と住民が協働して地域を挙げて解決することはできない。
そして、それを推進しようとすればするほど、行政と住民の協働を触媒・媒介するコミュニティソーシャルワーク機能が求められることを意識化しなければならないからである。
改めて、今求められているコミュニティソーシャルワーク機能とは、を整理、確認すると、①地域に顕在的、潜在的に存在する生活上のニーズ(生活のしづらさ、困難)を把握(キャッチ)すること、②それら生活上の課題を抱えている人や家族との間にラポール(信頼関係)を築くこと、③時には、信頼、契約に基づき対面式(ファイス・ツー・フェイス)によるカウンセリング的対応も行う必要があること、④その人や家族の悩み、苦しみ、人生の見通し、希望等の個人的要因を大切にしつつ、それらの人々が抱えている問題がそれらの人々の生活環境、社会環境との関わりの中で、どこに問題があるのかという地域自立生活上必要な環境的要因に関しても分析、評価(アセスメント)すること、⑤その上で、それらの問題解決に関する方針と解決に必要な方策(ケアプラン)を本人の求め、希望と専門職が支援上必要と考える判断とを踏まえ、両者の合意の下で策定すること、⑥その際には、制度化されたフォーマルケアを有効に活用すること、⑦そのうえで、足りないサービスについてはインフォーマルケアを活用したり、新しくサービスを開発するなど創意工夫して問題解決を図ること、⑧問題解決には多様な関係者の個別対応型支援ネットワーク会議を開催したり、必要なサービスを統合的に提供するケアマネジメントの方法を手段とする個別援助過程を基本的に重視しなければならないこと、⑨と同時に、その個別援助を支える地域を構築するために、個別対応型の必要なインフォーマルケア、ソーシャルサポートネットワークの開発とコーディネートを行うこと、⑩地域での個別支援を可能ならしめる地域づくりに関する“ともに生きる”精神的環境醸成、ケアリングコミュニティづくりを行うこと、⑪個別生活支援の外在的要因である生活環境・住宅環境の整備等も行うことを同時並行的に、総合的に展開、推進していく活動、機能である。
これらのコミュニティソーシャルワーク機能が十分意識化されない皮相的な取り組みで「我が事・丸ごと地域共生社会」という政策が展開されることに、行政も社会福祉関係者も、住民も十分留意しなければならない。したがって、市町村においてコミュニティソーシャルワークを展開できるシステムがない中で、安易に、コミュニティソーシャルワーカーという名称だけが一人歩きすることには気を付けなければならない。
おわりに
四国・こんぴら地域福祉実践セミナーは20回続いているが、それは他の実践セミナー(日本地域福祉研究所主催の全国地域福祉実践研究セミナーが22回、房総地域福祉実践セミナーが14回、沖縄かりゆし地域福祉実践セミナーが8回等)と同様に、“継続こそが力なり”と思い、続けることを意識して、かつ参加してきた。この20回に亘る四国・こんぴら地域福祉実践セミナーのすべてに参加しているのは、筆者と越智和子さんだけであろうか。
ところで、このセミナーは原則的に県行政や県社協の力に頼らずに、開催地を中心に自分たちで実行委員会を作り運営してきた。また、このセミナーは県庁所在地ではなく、「限界集落」と呼ばれる中山間地で行うことを原則としてきた。それは、「草の根の地域福祉実践」を豊かにしたいという思いからであった。県庁所在地での開催は第17回セミナーの愛媛県松山市が初めてである。このような考え方も四国・こんぴら地域福祉実践セミナーの特色の一つである。
高知県の足摺岬のある土佐清水市でのセミナーに539名が四国4県から集まり、討議をした光景には、正直鳥肌が立つ程の感動と感銘を覚えた。この土佐清水市のセミナーに参加して、中央集権的機関委任事務体質、行政依存的体質が大きく変わりつつあることを確信できた。
しかも、この四国・こんぴら地域福祉実践セミナーは、「地域福祉俳句会」は固より、ジャズを聴きながらの交流、あるいは徳島の阿波踊り、高知の「よさこい」踊りの体験等地域文化の野趣〈やしゅ、素朴な味わい〉に富んでおり、参加していてとても楽しい「集い」である。
本稿は「地域福祉の真髄」と題して3つの点に絞って述べてきたが、これ以外でもニーズキャッチの方法、福祉教育を実践する上での資料の作り方、市町村の地域福祉計画づくりの方法、コミュニティソーシャルワークを展開できるアドミニストレーションのあり方等も検討しなければ地域福祉実践は推進できないであろう。しかしながら、それらについては紙幅の関係もあり、後日に委ねたい。
また、四国・こんぴら地域福祉実践セミナーの実践の中でも高知市の「こうちこどもファンド」の取り組みや香川県の「香川おもいやりネットワーク事業」(施設経営の社会福祉法人と市町村社会福祉協議会と民生・児童委員との3者がコラボレーションしての生活のしづらさ、生活の困窮者を地域で支える活動)、あるいは本資料には都合により収録できなかったが、愛媛県愛南町のNPO法人なんぐん市場が取り組んでいる、精神障害者の退院支援と地域定着、地域自立生活支援の取り組みの実践、更には想定される南海トラフ地震への対策も考えた災害時支援のソーシャルワーク実践のあり方等これからの地域福祉実践を考える上で大きな示唆を与えてくれる実践についても考察を深めなければならないし、かつそれに関わってこれからの地域福祉研究上の意義、あり方についても論述しなければならないが、これも後日に委ねたい。
最後になりましたが、20年間、四国・こんぴら地域福祉実践セミナーの開催にご尽力してくれた日開野博さん(「地域福祉活動指導員養成課程」修了者)、越智和子さん、白方雅博さん(「地域福祉活動指導員養成課程」修了者)、島崎義弘さん、佐和良佳さん、市川千香さん(「地域福祉活動指導員養成課程」修了者)、日下直和(「地域福祉活動指導員養成課程」修了者)さんをはじめ、お一人、お一人のお名前を挙げられないが、四国4県の市町村社会福祉協議会及び県社会福祉協議会の職員の方々、そして日夜、地域福祉実践に傾注されている方々、更には聖カタリナ大学、高知県立大学、松山大学、高知大学、四国学院大学の先生方等本当に多くの人々に支えられ、このセミナーが継続実施されてきたことにこの誌上を借りて改めて厚く御礼を申し上げるとともに、心より感謝を申し上げる次第である。
付記
本稿は2017年6月3~4日に、愛媛県松山市の松山大学で行われた日本地域福祉学会において、地元四国4県の地域福祉実践の発表の一環として編集刊行された『「地域福祉の遍路道」四国・こんぴら地域福祉セミナー資料集』に寄稿したものに一部加筆したものである。
謝辞
本稿は、一般財団法人社会福祉研究所『所報』第93号、2018年3月、1~17ページ所収の大橋謙策先生の玉稿です(一部削除・修正)。転載許可を賜りました大橋先生と社会福祉研究所に衷心より厚くお礼申し上げます。/市民福祉教育研究所

補遺
(1)社会福祉協議会は “ 自己満足 ”、“ 唯我独尊 ”、“ 視野狭窄 ” で生き残れるか?
新年に頂いた年賀状の中に、東京都の福祉局の職員として勤め、定年後に地区社会福祉協議会に関わり、草の根の地域福祉実践をしている方から、“社会福祉協議会は旧態依然で、改革する意欲がない”という嘆きの言葉が書かれた年賀状を頂きました。
私は厚生労働省が進めている地域共生社会政策の具現化には、社会福祉協議会が改革され、住民のニーズに対応する活動を展開できなければ、その具現化は難しいと思っていますし、かつ社会福祉協議会は生き残れないと思っています。
地域共生社会政策における重層的支援体制整備事業は、包括的相談と福祉サービスを必要としている人の社会参加支援とそれを可能ならしめる地域づくりの3つの事業を三位一体として展開して欲しいとしています。
これを行うためには、市町村における第2層の専門多機関、専門多職種の連携と第3層の小学校区レベルでの住民参加、住民のボランティア活動の活性化が不可欠ですし、とりわけ第2層の機能と第3層の機能をつなげ、コーディネートする力が必要です。この第2層と第3層との有機化ができないと、また“新たな縦割り”を産みかねません。
これらの事業・活動を展開する組織として、最もふさわしい組織は市町村社会福祉協議会ではないかと私は思っています。
私の地域福祉実践、研究、教育は全国の社会福祉協議会とバッテリーを組むことにより展開され、体系化できました。言わば、私は社会福祉協議会によって“地域福祉研究者”に育てられたと思っていますので、身びいきすぎるかも知れませんが、上記の機能を考えたたら社会福祉協議会しかないと思っています。
1980年代から社会福祉協議会は小学校区レベルで地区社会福祉協議会づくりを推進してきました。その過程で、自治会組織や民生委員・児童委員とも深い関係を築いてきました。
1990年代には、住民に信頼される組織になるためには、住民のニーズに応える具体的サービスを展開し、そのサービス提供過程において、新たな住民のニーズを把握しようという「事業型社協」の考え方を打ち出しました。
また、1991年からは潜在化しているニーズを発見し、専門多機関でのチームアプローチによる支援を行う「ふれあいのまちづくり事業」を展開してきました。
このような経緯を考えれば、地域共生社会政策の具現化、重層的支援体制整備事業は社会福祉協議会がその中軸になって活動して“当たり前”だと私は思うのです。
しかしながら、冒頭に述べたように、社会福祉協議会は未だ1980年代までの“旧態依然”の活動、組織になっています。これで、社会福祉協議会はいつまでも行政からの補助金を貰えるのでしょうか。
全国各地の地方自治体では、9月の決算議会で社会福祉協議会への補助金の費用対効果が問われ、補助金の見直しの論議が各地の自治体で論議されています。あるいは、行政の監査委員会から社会福祉協議会への補助金の見直しの勧告もされています。行政の保健福祉部局が社会福祉協議会への理解を示してくれても、財政部局が理解せず、補助金カットの厳しい査定が続いています。社会福祉協議会が有している「基金」を全て遣い切ってから、改めて補助金の支出の論議を余儀なくされているところもあります。地方自治体の「指定管理制度」に伴う入札において、従来使用していた事務所がある社会福祉センターの管理運営に関わる指定管理で、社会福祉協議会が落札できず、他の業者に事務所代の賃料を払って入居している社会福祉協議会もあります。その場合の事務所賃貸料の補助金は行政から出ません。
このような状況下で、社会福祉協議会の経営のあり方は現在とても厳しい状況にあり、早く“眼を覚ます”必要があると思っています。
私自身、昨年だけでも岩手県、秋田県、福島県、香川県等の社会福祉協議会の経営問題に関する会議・研修に招聘され、上記のような状況と課題を提起し、コンサルテーションを行ってきました。
社会福祉協議会を取り巻くこのような状況を改革するためには、地域共生社会政策における重層的支援体制整備事業を受託し、第2層の地域包括支援センターの運営を軸にした専門多機関協働と第3層の小学校区の地区社協における住民参加、ボランティア活動とを有機化させる活動に取り組むしか“生き残る道はない”と考えています。
そのためには、従来の社会福祉協議会の事務局体制を改編し、地区社会福祉協議会ごとの「地区担当制」を導入し、その地区において福祉サービスを必要としている人の“発見”と個別支援に関する包括的総合相談を行い、かつその福祉サービスを必要としている人の社会参加に関する問題解決プログラムを開発・提供すること、更にはそれらの活動を住民が支え、ボランティア活動として協力するとともに、福祉サービスを必要とする人々を地域から排除することなく、蔑視をすることなく、共に生きていける地域づくり、福祉教育の推進を統合的に展開できる事務局体制に再編するしか“生き残れる道はない”と思っています。
そのためには、社会福祉協議会職員、総務部門の職員も、生活福祉資金や権利擁護部門の職員も、施設・団体支援部門の職員も含めてコミュニティソーシャルワーク機能の研修を受講し、その資質向上を図るしかありません。
厚生労働省の2015年の「新たな福祉提供ビジョン」(この報告書が地域共生社会政策の起点になる)の中で述べているように、“個別支援を通じて地域を変えていく”過程が重要なのです。
その点、テーマ型NPO法人は、福祉サービスを必要としている人の個別課題分野ごとに特化した活動を展開していますので、“個別問題”に強い“印象”を創り出していますし、事実、個別課題分野ごとに大きな成果を挙げて評価されています。
また、それらのNPO法人は今日のインターネット社会の機能をよく活用し、全国的に組織化を図り、個別課題分野における“発言力”(政治的にも、行政の信頼度においても、行政からの補助金獲得においても、クラウドファンディングにおいても)を高めています。
正直なところ、この間の内閣府等の政府の福祉サービスを必要としている人の個別課題分野ごとに取り組むNPO法人への評価は高く、政府の審議会での発言力や報告書における位置づけも高いものがあります。
それに比して、社会福祉協議会への評価、位置づけは“相対的に地盤沈下”していると思います。福祉サービスを必要としている人の個別分野の取り組みが全体的に増加しているので、その個別課題に取り組む団体・組織が増えることはいいことであり、その結果、社会福祉協議会が“相対的に地盤沈下”するのも当然でやむを得ないと考えるべきなのでしょうか。
私は、社会福祉協議会の位置は“相対的に地盤沈下”しているのではなく、“絶対的に地盤沈下”していると考えています。つまり、住民のニーズに対応しないで、相変わらず“旧態依然”の活動に終始し、“自己満足”、“唯我独尊”、“視野狭窄”に陥っているのではないでしょうか。
これらの課題は一朝一夕には解決できないと思いますが、せめてNPO法人と社会福祉協議会との“彼我の位置関係”を確認するためにも、各都道府県、各市町村で取り組み始めて貰っている「社会福祉関係資料集」の中に、これら「福祉サービスを必要としている人の個別支援をしているNPO法人」と「福祉サービスを必要としている当事者組織・団体」の把握を行い、収録することが必要ではないかと思っています。
私は、富山県社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーク研修において、『社会福祉関係資料集』の作成の必要性を説き、富山県福祉カレッジと協働して立派なものを作成してもらいました。この実践の取り組みは、現在では千葉県、岩手県、香川県、佐賀県の社会福祉協議会に普及しています。
地域共生社会政策では、社会福祉法の改正で地域福祉計画等を作成する際に、「地域生活課題」を明確に把握することを求めています。私は、この改正が行われる前から、住民のニーズに関わる「地域福祉・地域包括ケアに関わる基本情報」を市町村ごとに、かつ地域包括支援センター圏域毎に作ることの必要性と重要性を指摘してきました。
上記の『社会福祉関係資料集』は、これらの国の動向を踏まえても必要な取り組みです。富山県では、コミュニティソーシャルワークの研修の時のみならず、いろいろな研修の機会に活用しています。
せめて、これらの『社会福祉関係資料集』の中で、全国の、各都道府県の、各市町村で活動している「福祉サービスを必要としている人への個別支援をしているNPO法人」と「福祉サービスを必要としている人々の当事者団体・組織」の一覧を収録することにより、“彼我の位置関係”を認識し、社会福祉協議会が陥っている“自己満足”、“唯我独尊”、“視野狭窄”に気付き、改革する契機になればと思っています。
そして、社会福祉協議会がそれらの組織、団体の参加の基にプラットホームを創り、その“中核的組織”として社会福祉協議会が活動を行い、社会的評価を高められればと祈念しています。
――「老爺心お節介情報」第38号/2023年1月2日(一部削除・修正)
(2)「バッテリー型研究」と「関係人口」
私は地域福祉研究の「研究方法」について長らく悩んできました。とりわけ、外部の人間として地域に入るのですから、“地域”との関わり方については悩んできました。
研究者として、“上から目線”で地域に入り、“教えてあげる”という“臭い”をさせながら、“地域を引っ搔き回し”、その成果をあたかも自分の“手柄”のように披歴する研究者に1970年代から辟易してきました
私自身はそれについては相当気を付けてきたつもりではありますが、住民の皆さんからみたら、同じような指摘を受けるのかも知れません。
また、住民の意識、関係等の大量的リサーチを行うのが地域福祉研究なのかとも思ってきました。
その地域福祉の「研究方法」については『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク』で述べたつもりです。一言で言えば、実践家と研究者が野球の投手、捕手のようにバッテリーを組んで、協働実践を行う「バッテリー型研究」が重要だと考えてきました。
そのことに関し、阪野貢先生が「関係人口」に関わらせて説明しているので参照して頂きたい。その一部を以下に抜粋しておきます。是非、阪野貢先生のブログ(「市民福祉教育研究所」<まちづくりと市民福祉教育>(63)2022年1月21日)を読んで下さい。
阪野 貢/追補:「関係人口」と「よそ者」―田中輝美の論考と大橋謙策の実践研究―
〇筆者(阪野)の手もとに、田中輝美(ローカルジャーナリスト、島根県立大学)の『関係人口の社会学―人口減少時代の地域再生―』(大阪大学出版会、2021年4月。以下[1])がある。
〇「関係人口」という用語は、高橋博之と指出一正の二人のメディア関係者が2016年に初めて言及したものである。「関係人口」とは、高橋にあっては「交流人口と定住人口の間に眠るもの」、指出にあっては「地域に関わってくれる人口」をいう。その後、田中輝美は「地域に多様に関わる人々=仲間」(2017年)、総務省は「長期的な『定住人口』でも短期的な『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に関わる者」(2018年)、農業経済学者である小田切徳美(明治大学)は「地方部に関心を持ち、関与する都市部に住む人々」(2018年)、河井孝仁(東海大学)は「地域に関わろうとする、ある一定以上の意欲を持ち、地域に生きる人々の持続的な幸せに資する存在」(2020年)としてそれぞれ、「関係人口論」を展開する(73~75ページ)。
〇田中は[1]で、こうした抽象的・多義的で、農村論や過疎地域論に偏りがちな(都市部における関係人口を切り捨ててしまう)関係人口論に問題を投げかけ、関係人口について社会学的な視点から学術的な概念規定を試みる。関係人口とは「特定の地域に継続的に関心を持ち、関わるよそ者」(77ページ)である、というのがその定義である。この定義づけで田中は、関係人口を、移住した「定住人口」でも観光に来た「交流人口」でもなく、新たな地域外の主体、別言すれば「一方通行ではなく、自身の関心と地域課題の解決が両立する関係を目指す『新しいよそ者』」(69ページ)として捉える。その際、地域とどのように関わるかについて、関係人口の空間(「よそ者」)とともに、時間(「継続的」)と態度(「関心」)に注目する。(中略)
〇ここで筆者は、「福祉でまちづくり」の「スーパースター」(田中輝美の言葉)的な「関係人口」や地域づくりの専門家(「実践的研究者」)といえる大橋謙策(日本地域福祉研究所)の「バッテリー型研究方法」を思い出す。大橋のそれについては、本ブログの<まちづくりと市民福祉教育>(27)大橋謙策「地域福祉実践の神髄―福祉教育・ニーズ対応型福祉サービスの開発・コミュニティソーシャルワーク―」(2018年4月4日投稿)を参照されたい。
〇大橋は、全国各地の地域福祉(活動)計画の策定や地域福祉の研修会・セミナーなどに関わるが、その際の視点や姿勢はおよそ次のようなものである。
(1) 地域による実践の理論化・体系化と関係人口としての理論仮説の提起と検証(バッテリー型研究方法)を行う。
(2) 地域と長期間にわたって関わり、特定あるいは総合的・統合的な事業・活動への支援を継続的に行う。
(3) 地域による実践活動の活性化と、地域と行政や関係機関との協働を成立させるコミュニティソーシャルワーク機能(触媒・媒介機能)の展開、そのためのシステムの整備を支援する。
(4) 多種多様な、あるいは潜在的な地域課題の解決に向けた専門多職種によるチームアプローチの必要性や重要性を提唱し、その実現を図る。
(5) 地域との相互作用や相互学習の過程を通して、地域内外との交流や福祉等関係者(実践者)の組織化を促す。
(6) 地域による実践のプロセスとその結果の客観化・一般化や実践仮説の検証を図るために、著作物の刊行や地域によるそれを支援する。
(7) 地域による問題発見・問題解決型の共同学習(福祉教育)を徹底的に行い、地域(地域住民や専門家等)の社会福祉意識の変容・向上を図る。
(8) 地域との共同実践を通して地元自治体における福祉サービスの整備や、全国の地方自治体や国への政策提言を行い、その具現化の制度化・政策化を促す、
などがそれである。これらを総じていえば、地域による「草の根の地域福祉実践」を豊かなものにするために「継続は力なり」の意志を体して、理論と実践を往還・融合する探究的な「実践的研究」に取り組み、「福祉教育・ニーズ対応型福祉サービスの開発・コミュニティソーシャルワーク」を追究する、ここに大橋の「関係人口」としての具体的・実践的な視点や姿勢を見出すことができる。しかもそれらは、地域づくりや地域再生に「関係人口」が果たすべき役割や機能のひとつのモデルとして整理されよう。
〇なお、上記の(6)に関する文献に例えば次のようなものがある。紹介しておきたい。表記した地名は大橋が関わった地域である(それはそのほんの一部に過ぎない)。
・東京都狛江市/大橋謙策編著『地域福祉計画策定の視点と実践―狛江市・あいとぴあへの挑戦―』第一法規出版、1996年9月。
・富山県氷見市/大橋謙策監修、日本地域福祉研究所編『地域福祉実践の課題と展開』東洋堂企画出版社、1997年9月。
・岩手県湯田町(現・西和賀町)/菊池多美子著/『福祉の鐘を鳴らすまち―「うんだなーヘルパー」奮戦記―』東洋堂企画出版社、1998年9月。
・富山県富山市/大橋謙策・林渓子共著『福祉のこころが輝く日―学校教育の変革と21世紀を担う子どもの発達―』東洋堂企画出版社、1999年1月。
・山口県宇部市/宇部市教育委員会編『いきがい発見のまち―宇部市の生涯学習推進構想―』東洋堂企画出版、1999年6月。
・島根県瑞穂町(現・邑南町)/大橋謙策監修、澤田隆之・日高政恵共著『安らぎの田舎(さと)への道標(みちしるべ)―島根県瑞穂町 未来家族ネットワークの創造―』万葉舎、2000年8月。
・岩手県遠野市/日本地域福祉研究所監修、大橋謙策・ほか編『21世紀型トータルケアシステムの創造 ―遠野ハートフルプランの展開―』万葉舎、 2002年9月。
・長野県茅野市/土橋善蔵・鎌田實・大橋謙策編集代表『福祉21ビーナスプランの挑戦―パートナーシップのまちづくりと茅野市地域福祉計画―』中央法規出版、2003年2月。
・香川県琴平町/越智和子著『地域で「最期」まで支える―琴平社協の覚悟―』全国社会福祉協議会、2019年7月。
――「老爺心お節介情報」第33号/2022年2月22日(一部削除・修正)
(3)地域福祉研究者の「バッテリー型研究」
私は、1960年代、東京都三鷹市で中卒青年等を対象とした青年学級の講師を約10年間担当した。その際に、青年たちから投げかけられた言葉はいまでも忘れられないし、忘れてはいけないと“自虐”的と思えるほど意識して研究者生活をしてきた。
その言葉は“あなたたちが大学院に進み、研究できているのは我々の税金があるからではないのか。我々は、勉強したくても家が貧困で高校へも行けなかったし、大学へも行けなかった。だから、この青年学級で学んでいる。あなた方の奨学金も我々の税金で賄われているのではないのか。そいうことを考えてあなたは生活し、研究しているのかという”問い掛けであった。
当時は、東大紛争もあったりして、このような言葉がだされたのだと思うが、この言葉は自分にとって大変身に堪えた。そうでなくても、日本社会事業大学を進路として選択する際に、そのような考えを自分でしていたものの、直接、面と向かって、このような言葉を投げ掛けられると身に堪えた。それ以来、ディレッタンティズム(もの好き)で研究するのではなく、社会に貢献できる研究者になろうと誓った研究生活であった。
そんなこともあり、私は講演や研修を依頼されると、常に参加者にどのような“お土産”を持って帰ってもらうのか、参加してよかったと思える“成果”をどう提供できるのかを考えてきた。
また、講演や研修等の頂いた機会にその地域、その組織、その自治体から何を自分が学ぶかということを常に考えてきた。それは自分自身の学びであると同時に、参加者への“お土産”の素材を掴むことにもつながっていた。
その際の私の姿勢として、自分が学んだことや自分が知っている情報を“分かち与える”という、ややもすると“上から目線”になりがちな“教える”ということではなく、参加者がこれから考える糸口、課題を整理し、学びへの関心、興味を引き出せるような契機になればということを常に意識してきた。それは、言葉で優しく言うとか、言葉で励ますとかいうことではなく、参加者が主体的に考え、行動に移したいと思えるような問題の整理と課題の提起を志すことであった。
一方、私は1985年1月に『高齢化社会と教育』を室俊二先生と共編著で上梓した。それに収録された論文の中で、生涯教育、リカレント教育、有給教育制度等に触れながら、これからは高学歴社会と高度情報化社会が到来し、従来のような知識“分与”的、情報伝達的教育や研修は変わらざるをえないことを指摘した。
今、文部科学省はアクティブラーニングの必要性をしきりに強調しているが、それはかつて社会教育が青年団を中心に提唱してきた「問題発見・問題解決型協働学習」で言われてきたことと同じである。
このような状況のなかで、地域福祉研究者は、気軽に“地域づくり”、“地域共生社会”づくりというが、どのような立ち位置で研究し、どのような立ち位置で講演や研修に臨んでいるのであろうか。
他方、私は地域福祉実践をしている現場の方々と“バッテリーを組んで”、その地域、その自治体、その社会福祉協議会をフィールドにして研を行ってきた。そして、その研究は一時的なものではなく、長期に亘り、継続的に関わることによって行われるべきものだと考えてきた。
地域に住んでいる住民は、移転、移住しようにも、先祖伝来の土地、「家」のしがらみの中で生きており、気軽に移動できない状況を十分理解しないままに、外部から入り、外部の目線で“気軽に”地域づくりを言い、短期で関わりを切ってしまう研究方法は、あたかも住民の方々を弄ぶかのように思えていたからである。
私は、1970年に現在の東京都稲城市に移住し、地域活動を始めたが、それ以降、よほどのことが無い限り、この稲城市を離れることをしまいと決意を固めた。“地域づくり”を言うということは、それだけの重みのある取組であるべきだし、そうでないと住民の方々は納得してくれないと思ったからである。現に、そのような指摘は各地で幾度も聞いたし、聞かされてきた。
そんなこともあり、“バッテリーを組めた地域”には、長い地域では40年間のお付き合いをさせて頂いている地域もある。
ところで、このような文章を書いたのは、まさに「老爺心お節介」の最たるものかもしれないが、最近目にする論文等を読んでいて、研究者自身の立ち位置を明確にしないままに、取り組まれている実践を評価、紹介しているものが多く、地域福祉研究者として“一種の研究倫理”に抵触しているのではないかと思う論文を散見するからである。全国のいい実践は、大いに紹介し、情報共有化がおこなわれてほしいが、その場合でも紹介なのか、評論なのか、自分の学説の論証に使うのか等その位置づけは明確にしてほしいものである。しかも、その実践のアイディアは誰が出したのか、参与観察をするならばどういう立ち位置で行うのかを明確にする必要がある。最近、政治学の分野で「オーラルヒストリー研究法」が活用されているが、ある政策、ある実践がどういう形で企画され、政策化されていくのかを、その過程の力学も踏まえて研究が進められている。地域福祉研究においても、同じような研究の枠組みを作る必要があるのではないかと考え、この拙稿を書いてみた。
――「老爺心お節介情報」第23号/2021年3月25日(一部削除・修正)
(4)社会福祉実践における「実践仮説」と実践者の “ ゆらぎ ”
筆者は、ここ数年千葉県、富山県、香川県、佐賀県、大阪府、岩手県の社会福祉協議会において、CSW研修を体系化させようと取り組んできました。その際、感じることは、社会福祉関係者の活動には「実践仮説」をもって意識的に取り組むという姿勢が弱いと感じている。
筆者が、東京都三鷹市の勤労青年学級の講師として取り組み始めたのは1966年度からですが、その際、小川正美社会教育主事から強く求められたのは、①勤労青年という教育実践の対象になる「学習者理解」を深めること、②これらの青年に対し、どのような教育目標を設定し、どのような教材や教育方法を駆使して実践するのか、1年間の、あるいは中期の「実践仮説」をもって取り組むこと、③年度がおわったら、「実践仮説」に基づいた実践がどうであったかを総括、評価し、文章化することであった。当時、日本社会事業大学の学部4年生であった私にとっては、それはとても厳しい“注文”であったが、それを意識化して取り組んだことが筆者を育ててくれたと今では感謝している。
三鷹市の勤労青年学級だけではなく、教育学分野では、教師が「実践仮説」をもって、実践に取り組むということが必要だと教えられてきたが、1970年代、社会福祉分野において「実践仮説」という言葉を使うと、関係者はその用語は初めて聞いたとか、「実践仮説」とはどういうことですかとか、用語の使用が共有化できないことに驚いた記憶がある。ある意味、社会福祉分野は“制度の枠”の中で、“制度に基づくサービスを提供”していたので、「実践仮説」という考え方を持たなくても通用してきたのかなと思ったことがある。
しかしながら、これからは制度が十分でなければ、ニーズに対応する新しいサービスを開発する必要があるし、生活のしづらさを抱えている人への伴走的支援によるソーシャルワーク実践が求められてきている。そこでは、実践者の「実践仮説」が大いに問われるはずである。
――「老爺心お節介情報」第21号/2021年1月18日(一部削除・修正)
(5)実践・研究における問題構造の把握と分析視角
私は、恩師の小川利夫先生から研究指導を受ける際、“おまえの分析視角は何か、そのナイフは先行研究を踏まえた理論課題を明らかにできる研ぎ澄まされているナイフなのか、それともなまくらなのかどうか?”、“事象に流されて、紹介するだけのものは論文とは言わない”等と常に戒められてきた。
そんなこともあり、私は論文を書くときに、あるいは講演をする際にとても十分とはいえないにしても、常に以下のようなことを考えて研究生活を送ってきた。
➀ 何故、その社会問題、事象を取り上げるのか、それを取り上げる意義は何か?
② 取り上げた社会問題、事象をどう分析するのか、その分析の視角は何か?
③ 分析したここの要因間の関係の構造を考え、何が幹で、何が枝で、何が葉なのか、枝葉末節を考えて、構造的に分析を行い、考えているか?
④ 分析をした社会問題、事象を通して、社会福祉学界に対してどのような理論課題を提起し、論述しようとしているのか、その理論課題に即した先行研究も十分ふまえて論述しているのか?
上記のことを私が意識して問題構造、分析視角という用語を使って書いた最初の論文が「現代児童の問題構造と分析視角」(『ジュリスト』572号、有斐閣、1974年10月)である。
自分のことを棚に上げておこがましいことを言うようであるが、最近の実践や研究において、上記のことがほとんど触れられずに、“犬が歩けば棒に当たる”類の研究姿勢が多いことはなぜなのだろうか?それは私達の世代の“大学院”での研究指導が不十分であったからであろうか。
――「老爺心お節介情報」第36号/2022年6月13日(一部削除・修正)