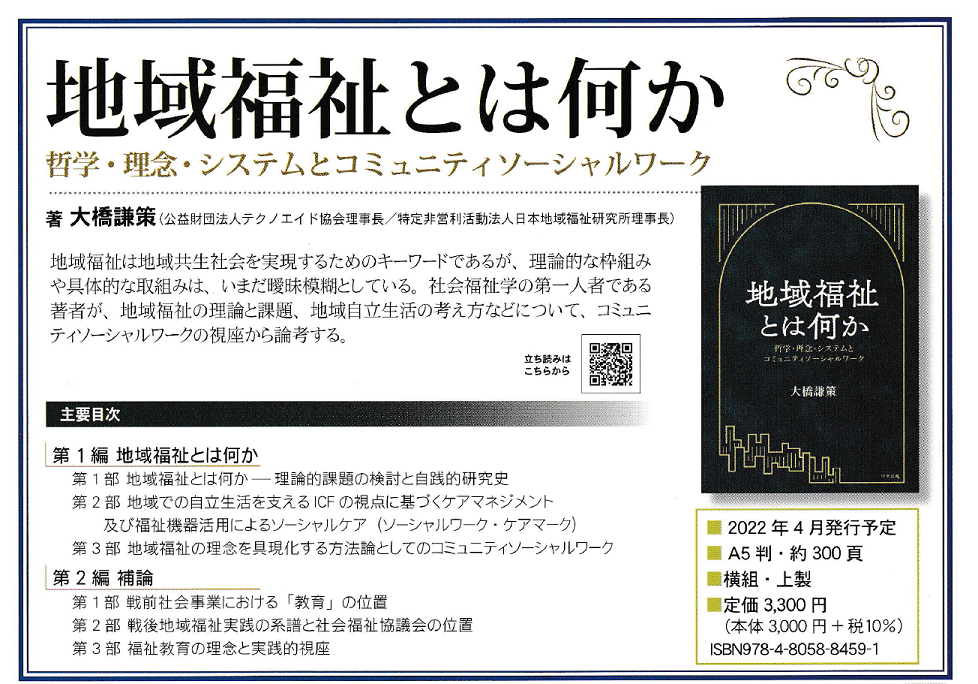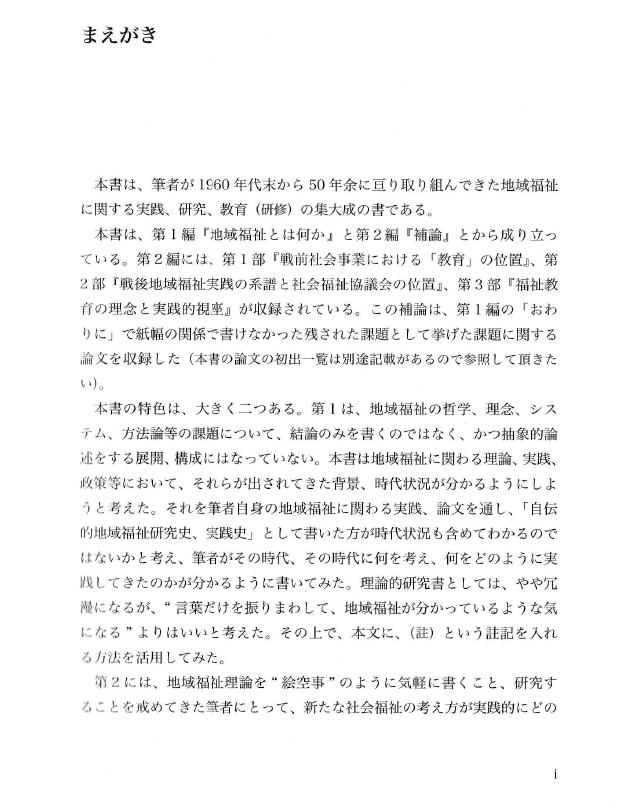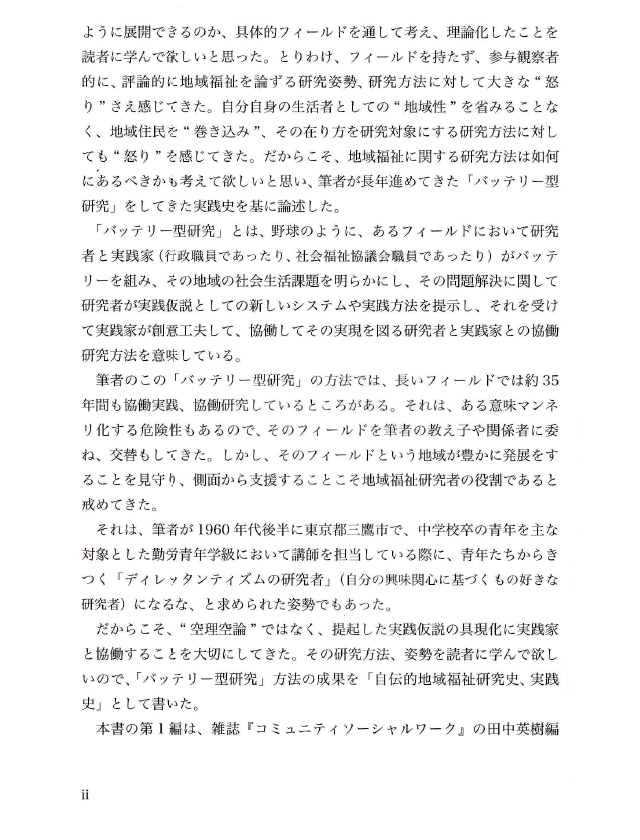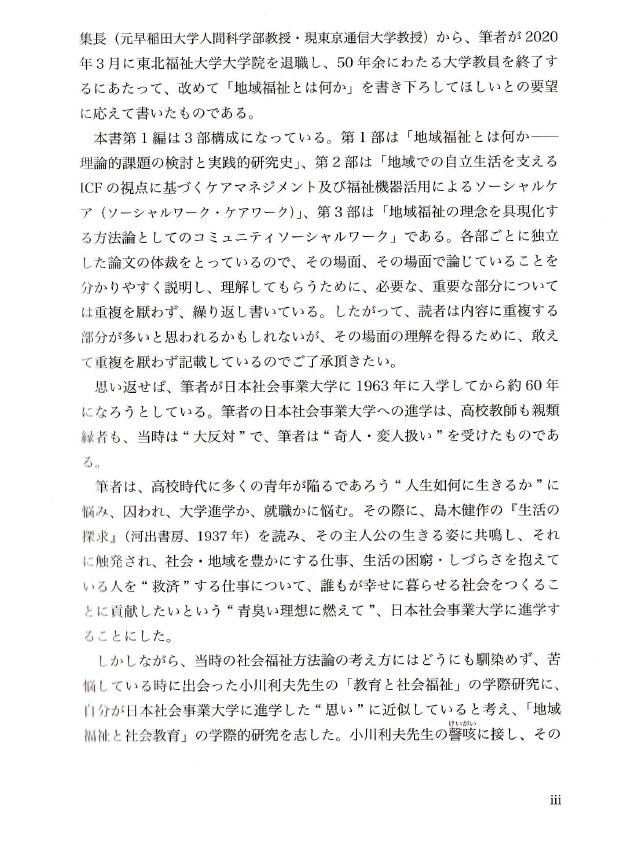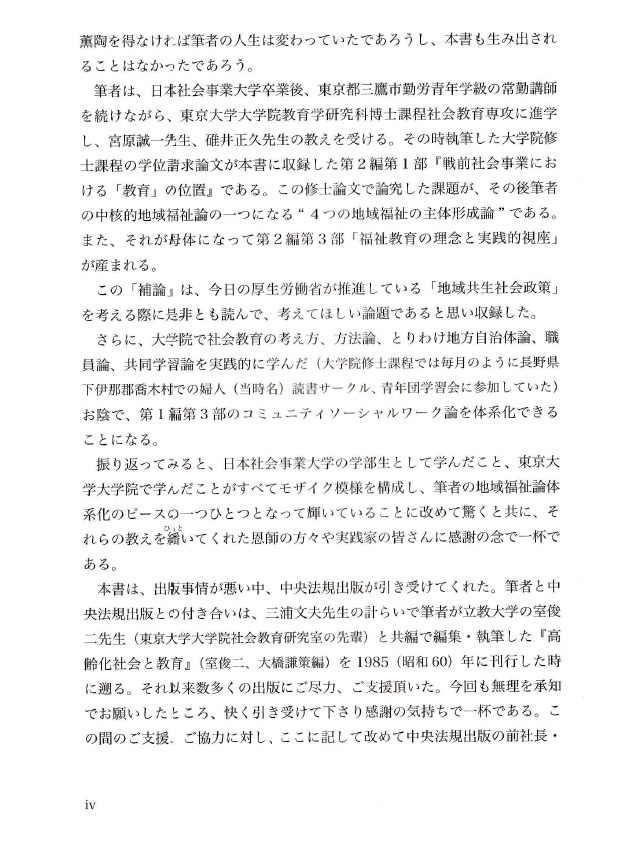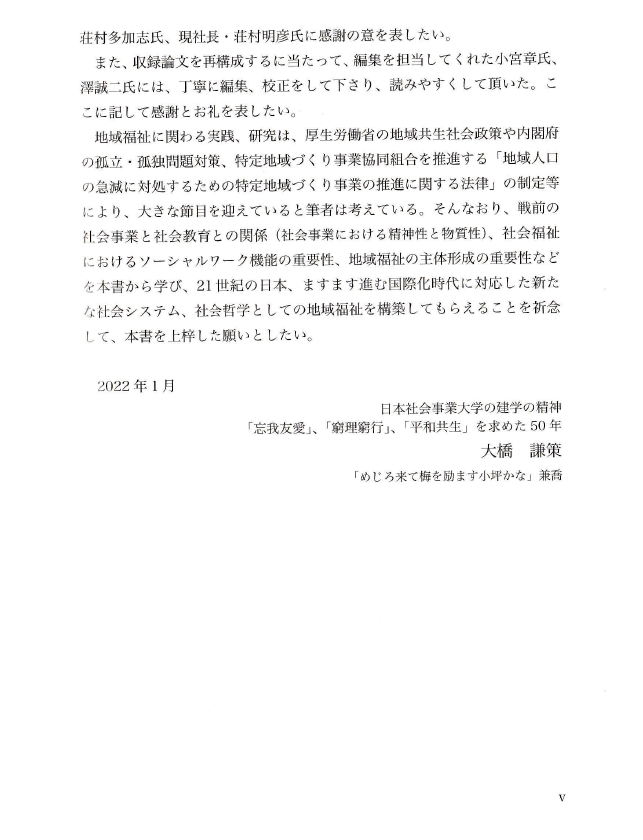「老爺心お節介情報」第39号
「老爺心お節介情報」第39号を送ります。
関係する方々への配信は自由ですので、大いにご活用下さい。
なお、阪野貢先生が主宰する「市民福祉教育研究所」のブログには第1号からすべて掲載されていますので、必要な方はアクセスしてください。
ご自愛の上、ご活躍下さい。
2023年1月9日 大橋 謙策
寒中お見舞い申し上げます!
〇皆様お変わりありませんでしょうか。暦の上では小寒になり、これから寒さ本番の大寒を迎えます。
〇新型コロナウイルス感染症と共に、インフルエンザも流行してきているようです。くれぐれもご自愛の上、ご活躍下さい。
〇今回の「老爺心お節介情報」では2つの事項の情報提供と提案です。
〇今年も、これから研修等忙しくなります。次回の「老爺心お節介情報」を発信できるのは、多分3月になってからではないでしょうか。第36号から37号までの期間が約6か月も空き、多くの方に“大橋は生きているのか、病気したのではないか”とご心配を頂きましたが、今回は斯様なご心配はご放念下さい。
Ⅰ 地域共生社会政策における必読書
『差別はたいてい悪意のない人がする――見えない排除に気づくための10章』キム・ジヘ著、尹怡景訳、大月書店、2021年7月初版、1600円
〇本書は、韓国で2019年に『善良な差別主義者』というタイトルで出版され、1年もしないで10万部を超えるベストセラーになった本の日本語訳版である。
〇日本でも、2021年に翻訳刊行されてから今まで7刷りされている。
〇私はこの本を読んで、自分の従来の差別論や人権感覚を多面的に問い直す必要性を感じた。本書で述べられている論理を全て首肯できてはいないが、少なくとも何気なく使ってきた差別、特権、平等、多文化、共生という用語、言葉を、改めて自らが置かれている“立ち位置”を意識して使わなければならないということを意識させられた。
〇“発せられた言葉”は同じものでも、それを発した人の“立ち位置”によって“意味”が大きく異なり、時にはその“言葉”が差別にもなることも意識させられた。
〇本書で改題をしている大東文化大学の金美珍准教授が、「本書が注目されたのは、差別に関する既存の考え方に新たな問を投げかけたからと考えられる。一般に、差別に対する認識は、差別する加害者とそれをうける被害者という構造の中で議論される。本書でも指摘されているように、だれもが差別は悪いことだと思う一方、自分が持つ特権には気づかないので、みずからが加害者となる可能性は考えない傾向が強い。本書は『善良な』という表現を用いて、「私も差別に加担している」、「私も加害者になりうる」という可能性に気づかせる。つまり、平凡な私たちは知らず知らず差別意識に染まっていて、いつでも意図せずに差別行為を犯しうるという、挑発的なメッセージを著者は投げかけている。」と述べているが、私が気づかされた点もまさにその通りである。
〇本書を読みながら、多くのページに蛍光ペンでマークをし、かつ付箋も付けた。その一つ一つに関わる私のコメントを書きたい思いがあるが、それはある意味一冊の本を書くようなものである。皆さんは、是非この本を読んで欲しい。とりわけ、地域共生社会政策に関わる人、福祉教育に携わる人、差別、人権に興味関心を寄せ、差別を無くし、平等の社会を創ろうと思っている人には是非読んで欲しい本である。
〇本書は、アメリカの事例、判例、韓国の社会状況をふんだんに取り上げながら論述されていると同時に、政治学、民主主義に関わる歴史的論者の考えも引用しており、その文献の渉猟の広さ、凄さ、博学さにも圧倒される本である。
Ⅱ 市町村に「ソーシャルケア連絡協議会」を創ろう
〇国は今、地域共生社会政策を推進しています。その中で、市町村の第2層レベルでの専門多機関、専門多職種の連携を求めています。
〇筆者は、2000年5月に、日本学術会議の幹事を仰せつかっている時に、当時の日本学術会議会員であった仲村優一先生と、私と同じ幹事であった田端光美先生に相談し「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」を設立しました。
〇それは、ソーシャルワークとケアワークとを統合的に考え、両者の社会的評価、社会的発言力を高める試みとして設立しました。その協議会には、社会福祉士会、精神保健福祉士会などのソーシャルワーク専門職団体、介護福祉士会のケアワーク専門職団体、それらの養成を担う大学、養成校の団体並びにそれらの研究を行う日本社会福祉学会などの17団体に参加してもらい結成されました。
〇このソーシャルワークとケアワークとを連動させる考え方は、1987年の「社会福祉士及び介護福祉士法」制定の際にも、その必要性を説きましたが却下され、社会福祉士及び介護福祉士は別々の国家資格として法制化され、各々が専門職団体を設立し、成長してきました。
〇しかしながら、1980年代の入所型社会福祉施設中心の時代ならいざ知らず、1990年代に入り、在宅福祉サービスが法定化され、住民の在宅福祉サービス利用が増えてきている状況では、1980年代までの施設福祉サービス提供とは大きく異なり、ソーシャルワークとケアワークとを統合的に捉えるケアマネジメントが必要とされてきます。
〇この状況はイギリスでも同じで、イギリスは1998年にソーシャルワークとケアワークとを連動させた教育研修体系に切り替えるために、「ソーシャルケア統合協議会」を設立しました。
〇この点については、拙著『地域福祉とは何かーー哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク』第2部第1章(P73)に書いていますので参照してください。
〇私は全国的な「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」を創ると同時に、各都道府県レベルでも「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」を創り、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の地位向上、社会的発信を強めるべきであると考え、関係者にお願いしてきました。そのためにも、毎年7月の「海の日」をソーシャルワーカーデーに定め、各都道府県レベルでの活動の強化をお願いしてきました。私の知る限り、最も典型的な組織を創ってくれたのは栃木県です。大友崇義先生を中心の「栃木県ソーシャルケアサービス研究協議会」が設立され、2022年に20周年大会が行われました。
〇と同時に、私は「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」の市町村版を創るべきだと考え、いろいろ働き掛けをしてきました。その一環として、市町村で設置される審議会や地域福祉計画策定委員会に社会福祉士や介護福祉士等の専門職団体の支部長を参加させるべく行政に働き掛けてきました。
〇一例をあげると山形県鶴岡市の地域福祉計画策定委員会に、社会福祉士会の支部長に入ってもらいました。また、東京都豊島区の地域保健福祉審議会の委員に豊島区社会福祉士会支部長に入ってもらいました。
〇行政は、当初、そのような支部があるかどうかも分からない等という理由で拒否反応を示しましたが、支部はあるはずであると説得して委員に入れてもらうことにしました。
〇鶴岡市の社会福祉士は地域福祉計画策定委員会の副委員長として、現場の状況を踏まえた適切な情報提供、発言をしてくれました。豊島区の場合は、支部長は社会福祉士養成の専門学校の先生でしたが、全く“現場感覚”がなく、発言もできず、私は社会福祉士の代表を入れて欲しいと行政に頼み込んだ経緯もあり、行政の関係者に幾度か謝りました。
〇市町村レベルでは、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の国家資格を有している人がいると言っても数は多くないでしょうし、その力量、資質も“千差万別”であり、その時点(2000年代)ではやむを得ないと思っています。医師のレベルは100年以上かけて、そのレベルが確立してきていますが、社会福祉士等の資格は国家資格になってから高々20年にも満たない状況での取り組みだったので、その旨行政に話し、育てて欲しいと行政にお願いしました。
〇しかしながら、現在推進されている地域共生社会政策における包括的・重層的支援体制における第2層の専門多機関、専門多職種連携が求められている状況の中では、“待ったなし”の状況で、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の力量が問われます。
〇この機会に、市町村レベルにおいて「ソーシャルケア連絡協議会」を創り、切磋琢磨してお互いの力量を高めると同時に、社会福祉士等のソーシャルワーク、ケアワークの国家資格の認知度を高め、社会的評価と信頼を高める活動を展開する必要があるのではないでしょうか。
〇市町村レベルの状況を考えると、この「ソーシャルケア連絡協議会」には、介護支援専門員、障害者相談支援員、あるいは保育士の方々にも参加して欲しいものです。
〇是非、市町村社会福祉協議会の方はこの取り組みを進めて欲しいですし、県レベルの方々にはその支援をお願いしたいと思います。
(2023年1月9日記)