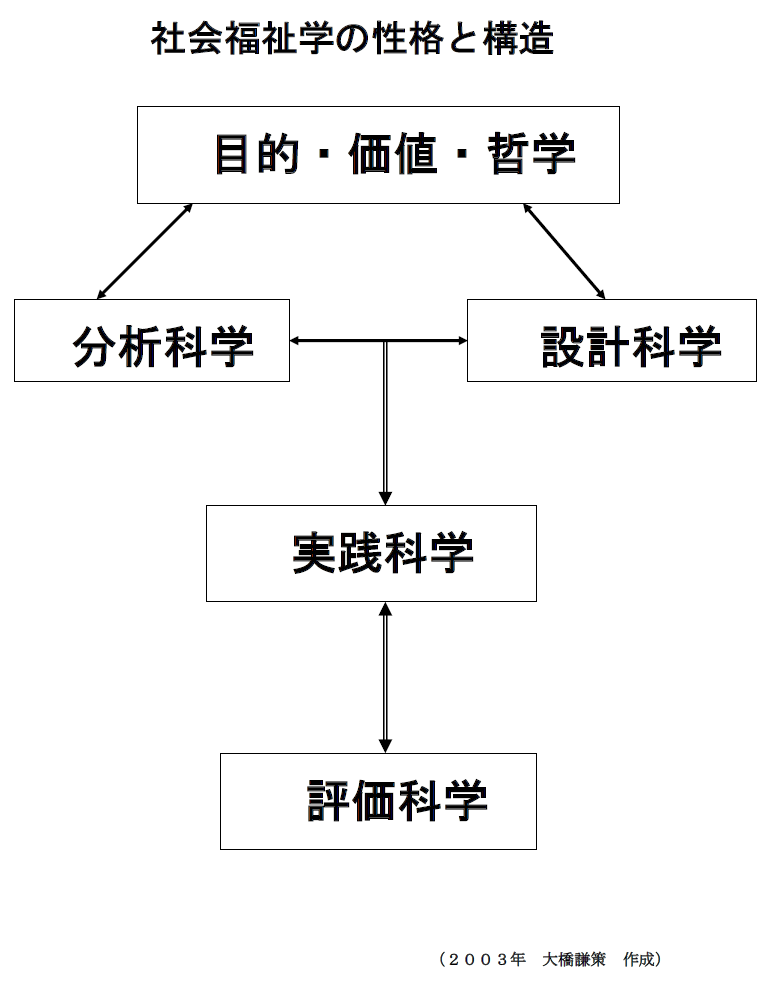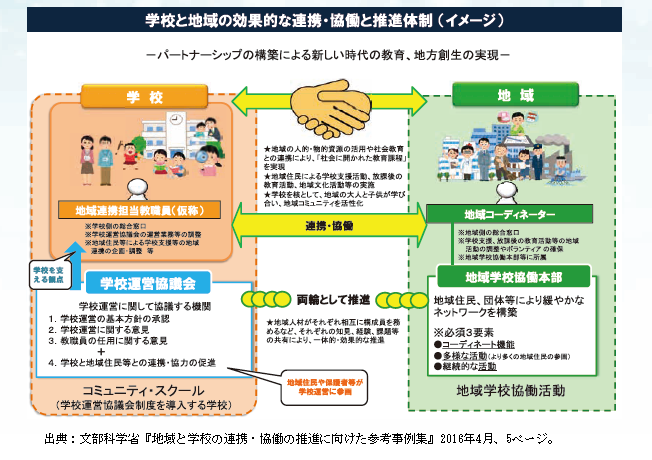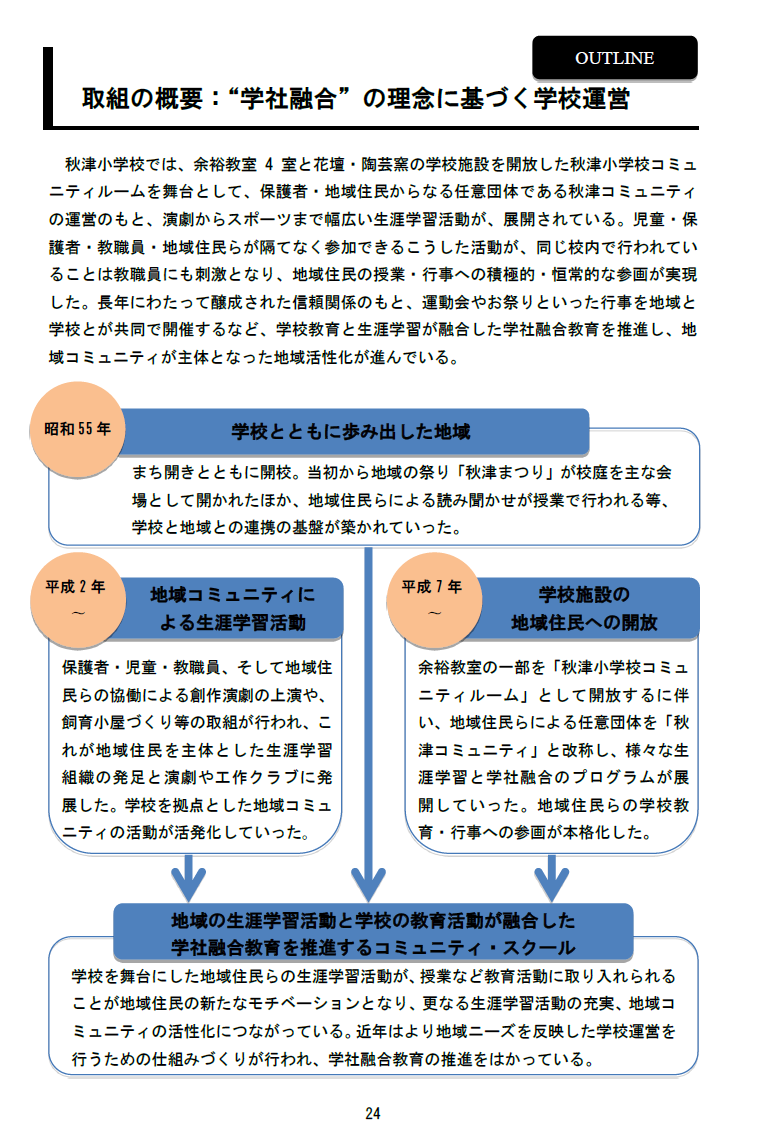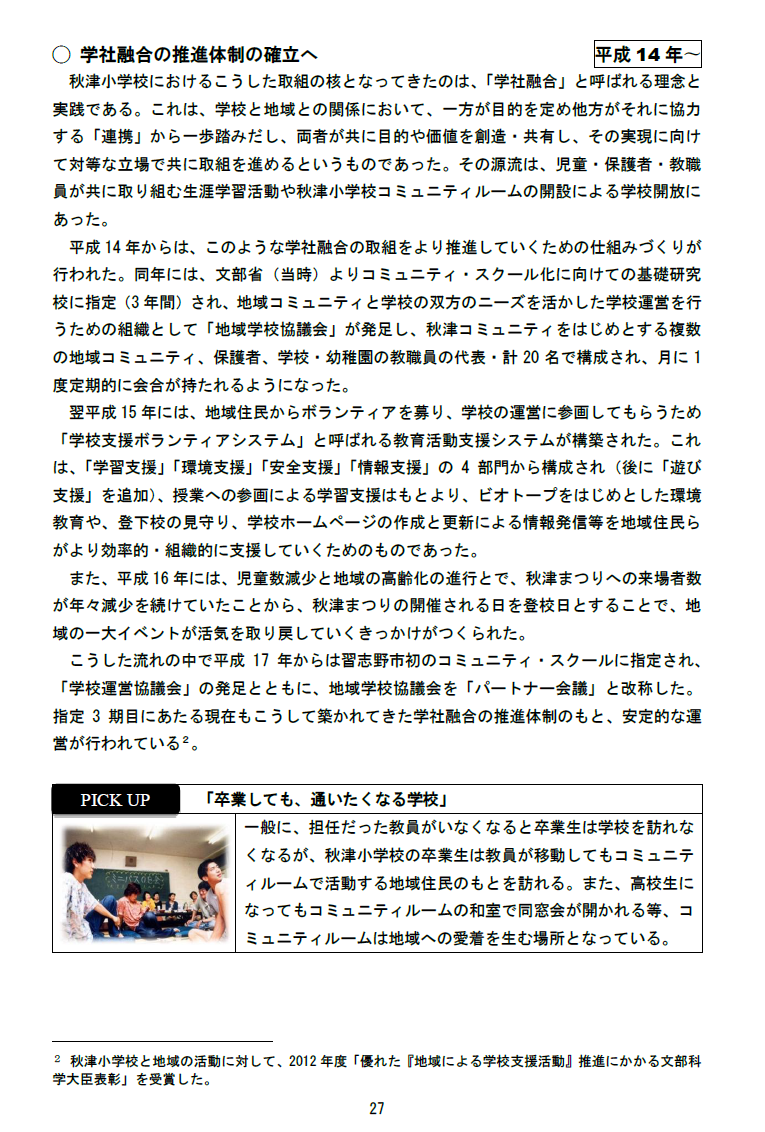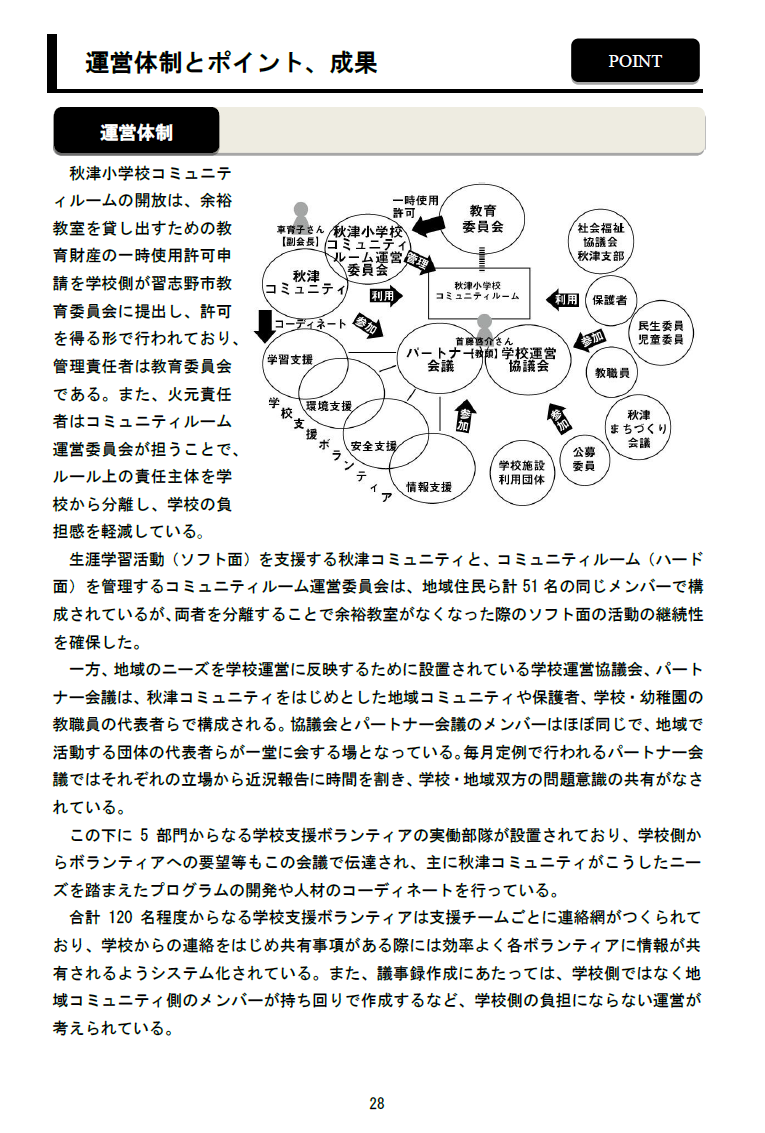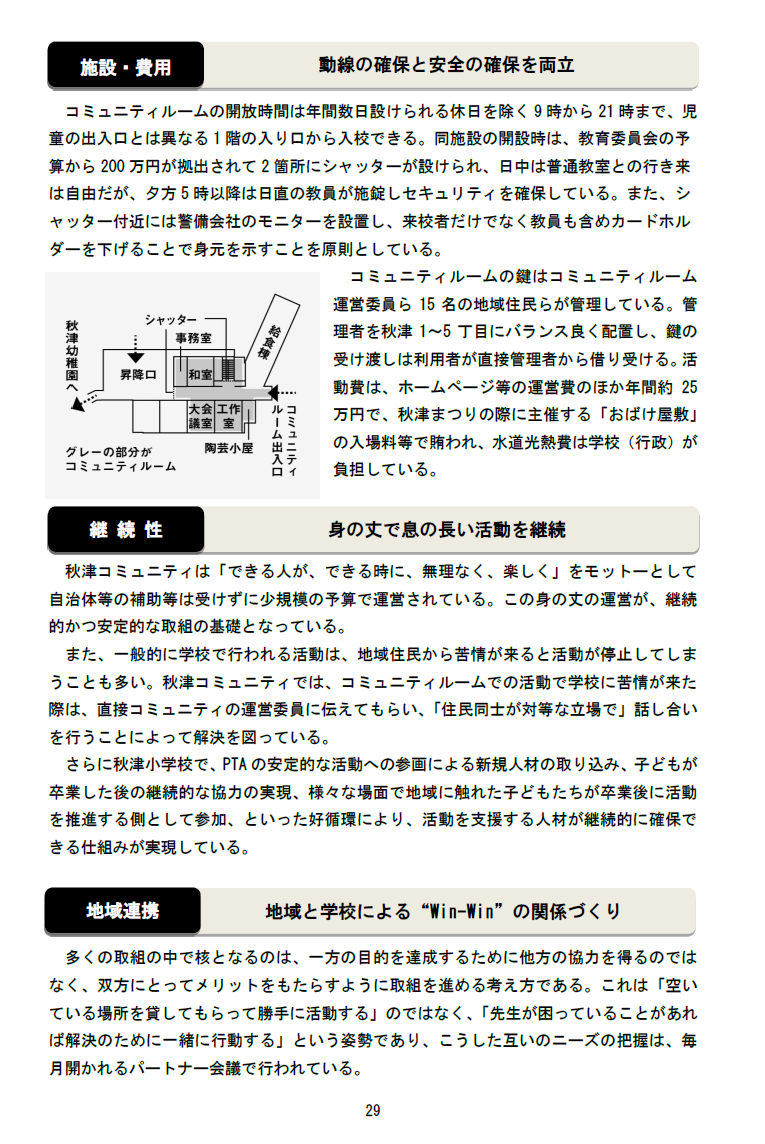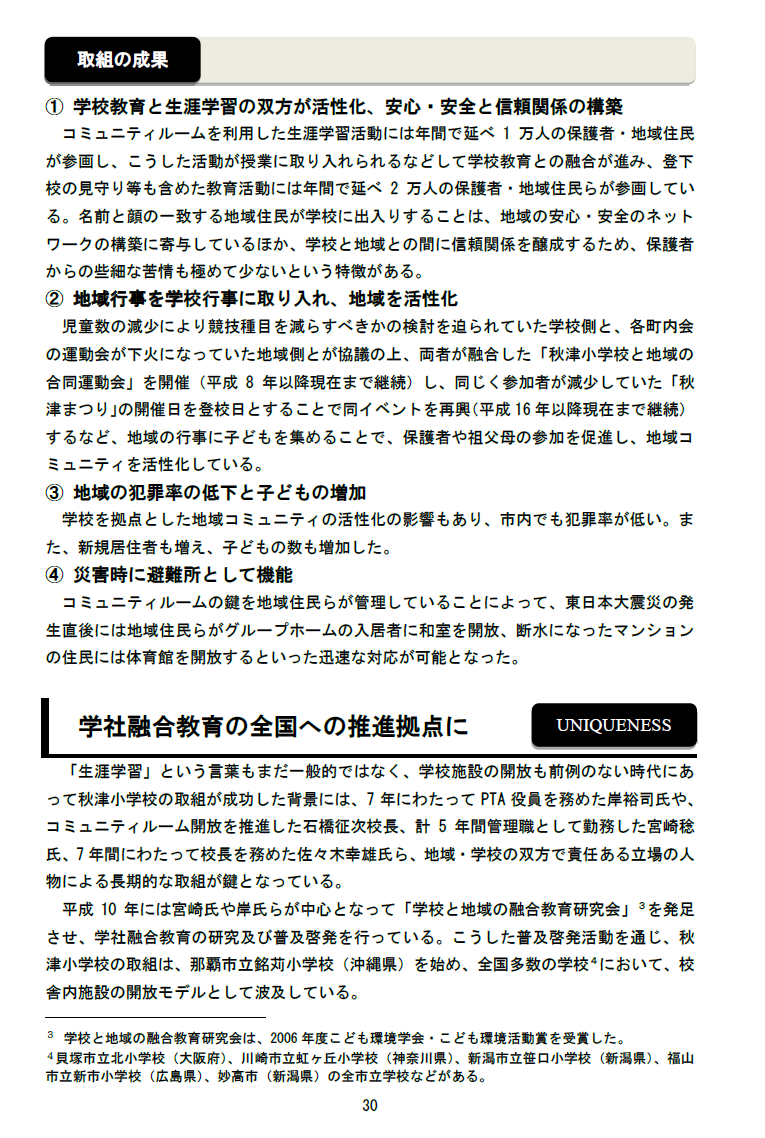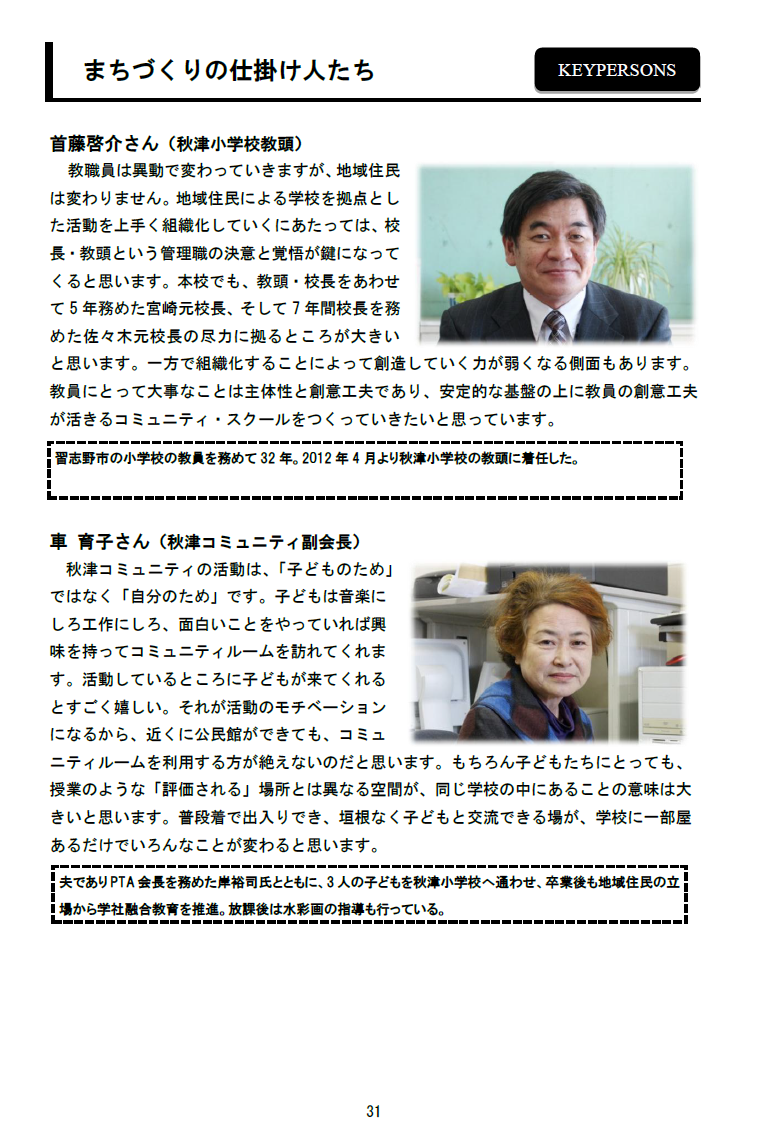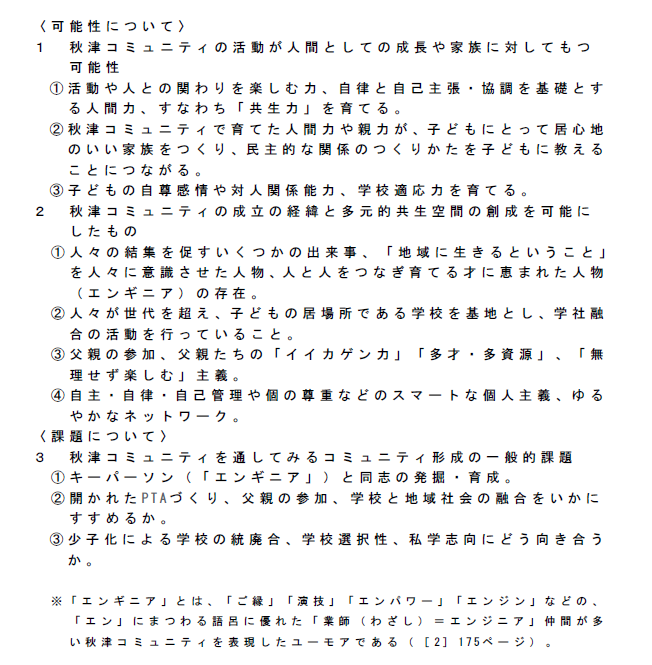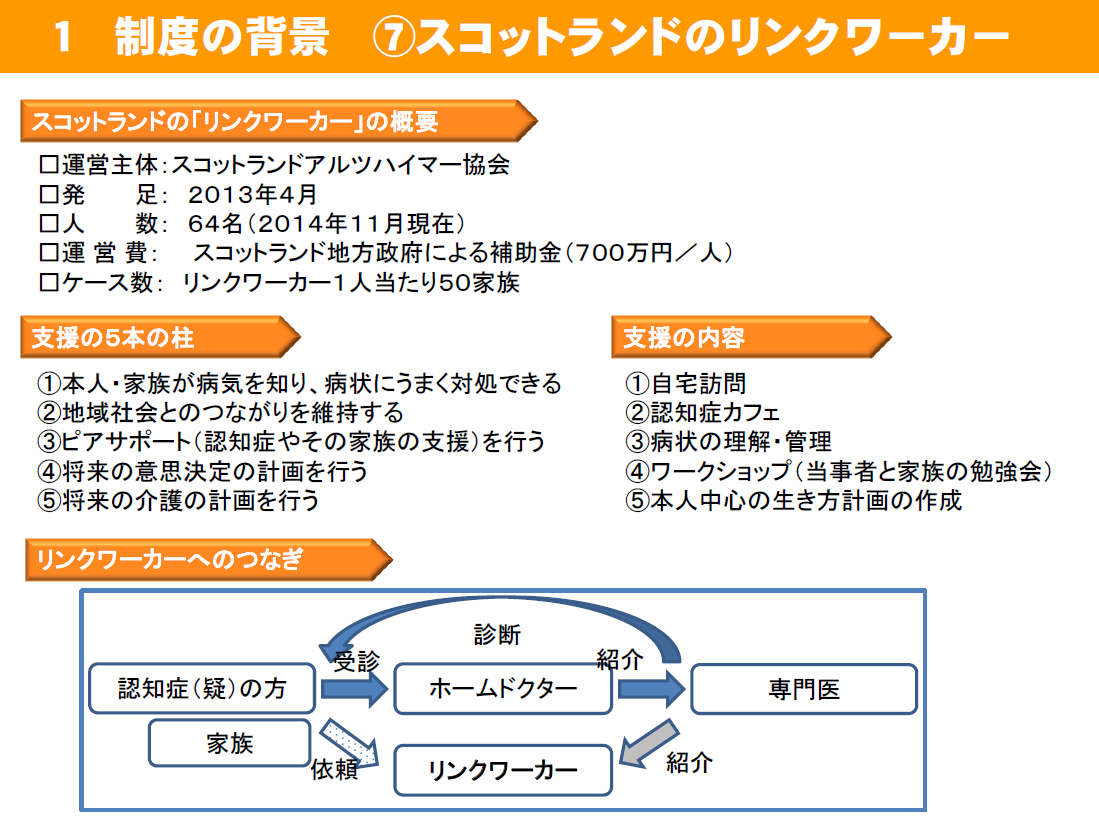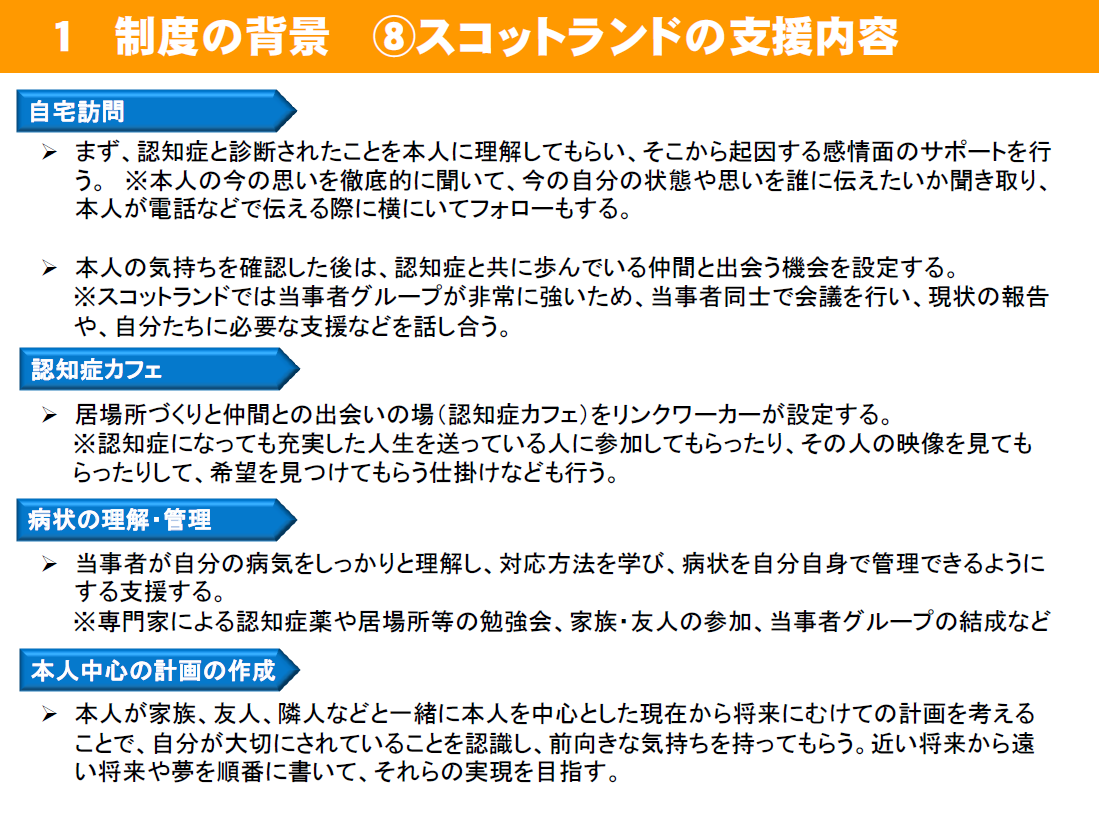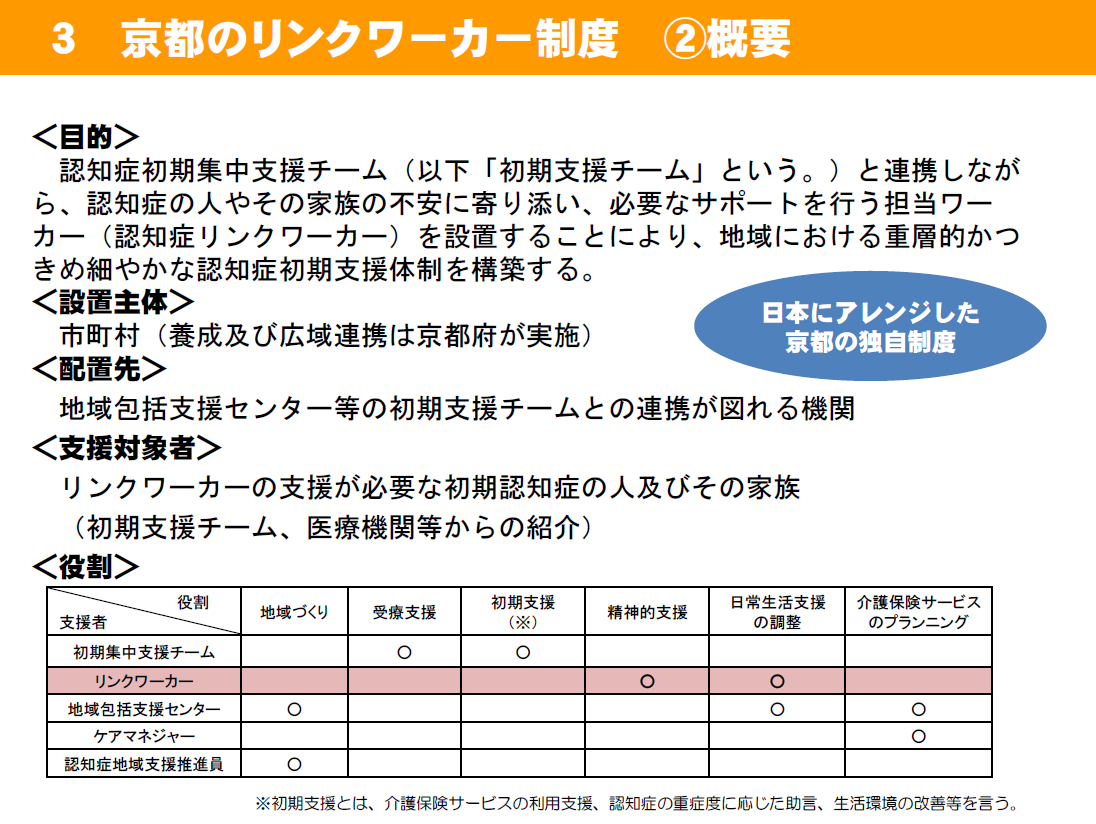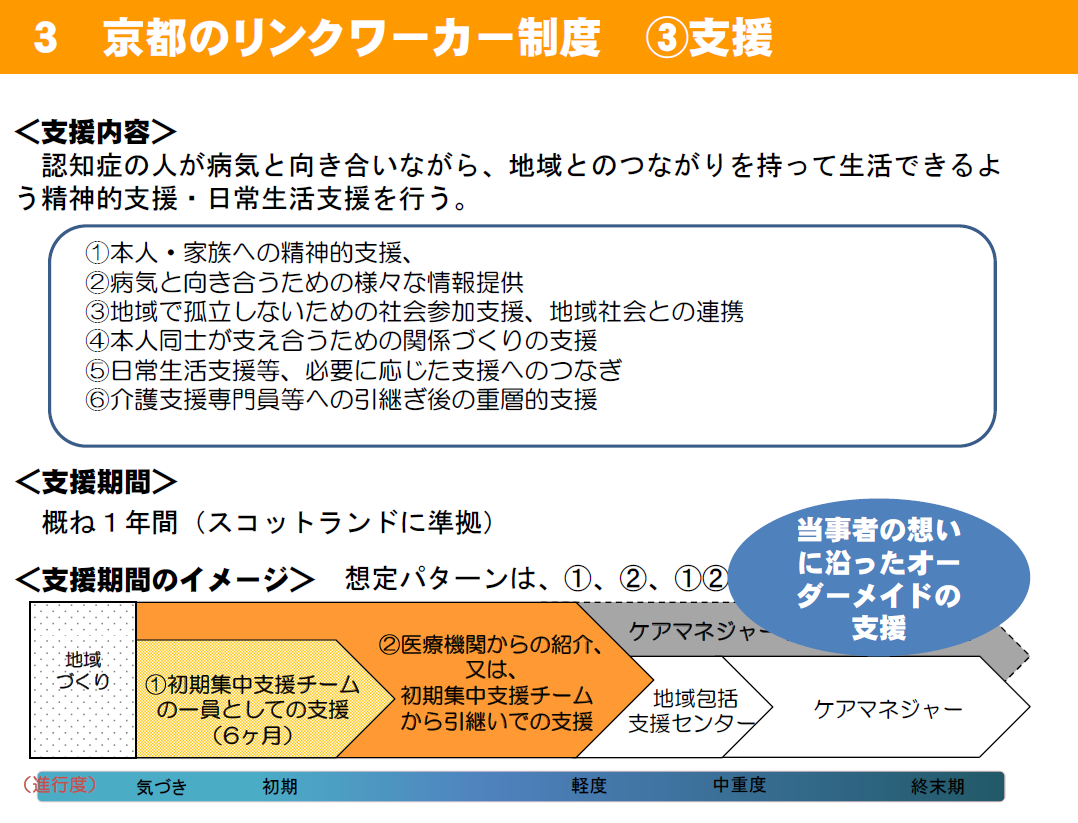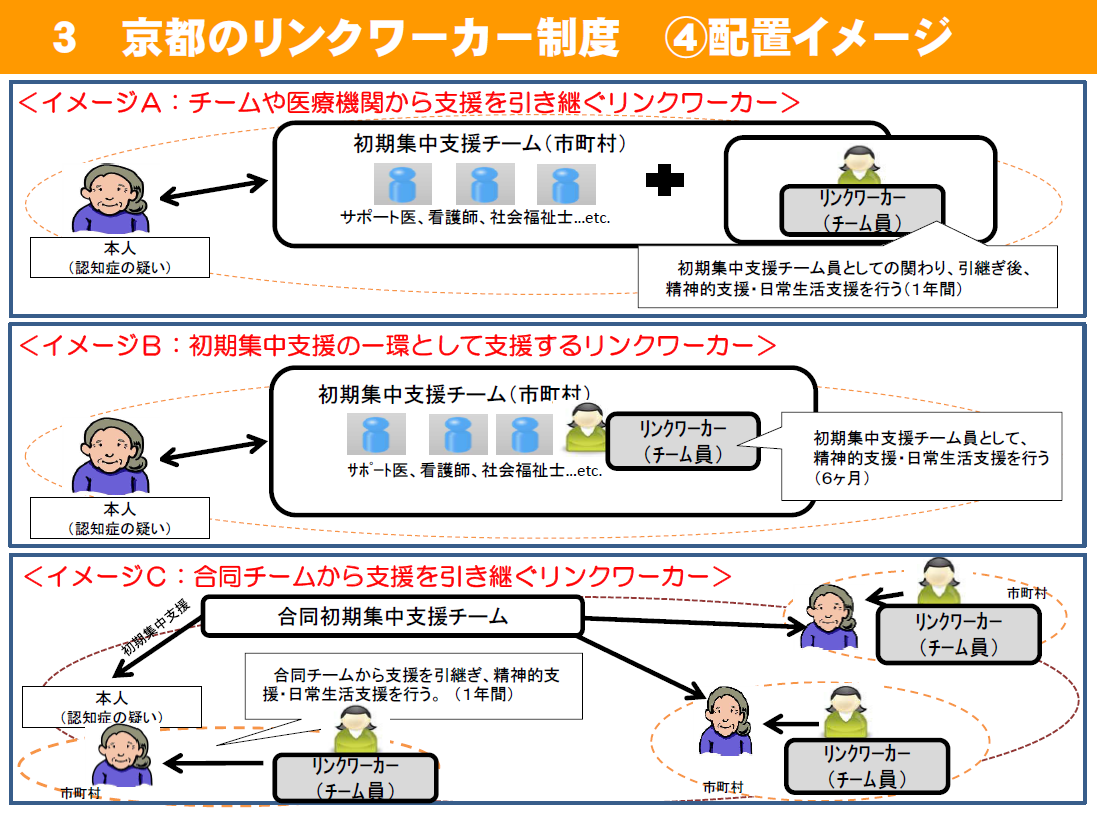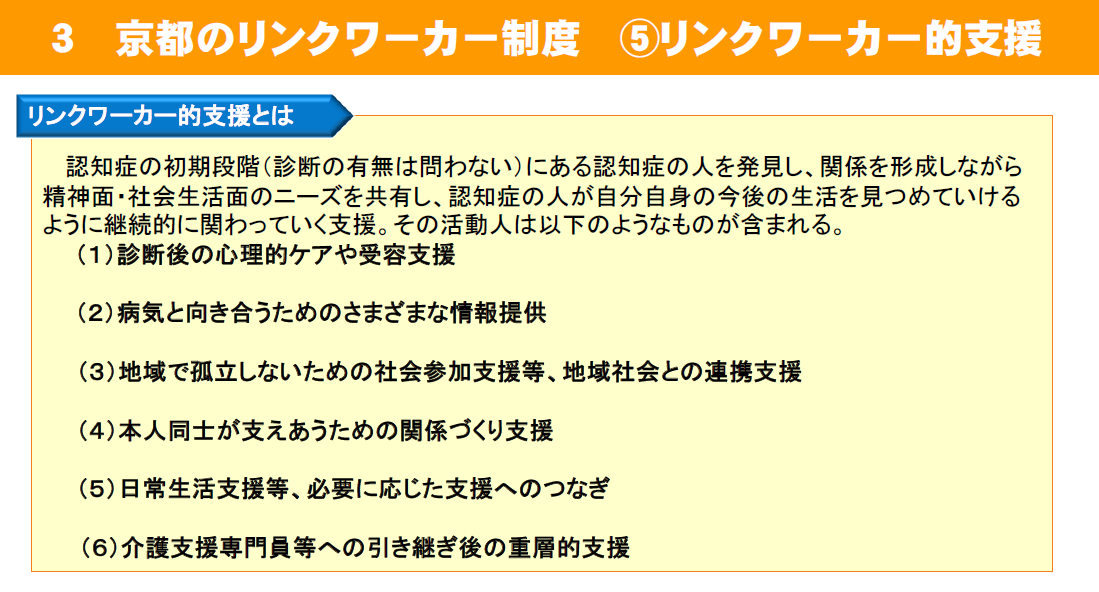〇あまりにも難解で、いまだに積読(つんどく)を続けている本にカール・マルクスの『資本論』がある。筆者(阪野)がそれを読もうと思ったきっかけは、当時、社会福祉(社会事業)を学ぶ学生の必読書であった孝橋正一の『全訂・社会事業の基本問題』(ミネルヴァ書房、1962年5月)に挑戦していたときであったと記憶している。孝橋の「社会事業とは、資本主義制度の構造的必然の所産である社会的問題」を対象にする、という一節である。(その後、筆者は、マルクス経済学者宇野弘蔵の「原理論」「段階論」「現状分析」のいわゆる三段階論にハマった時期があった。今は昔である。)
〇「資本論」という言葉が本のタイトルにあるだけで積読になっていた本がいま、筆者の手もとにある。斎藤幸平(さいとう・こうへい)の『人新世の「資本論」』(講談社新書、2020年9月。以下[本書])がそれである。今回は、「資本論」という言葉に対するアレルギー反応が起きる前に、一気に通読することができた。それは、現代に生きる者(ヒト)として、地球を破壊するほどに進んでいる「気候変動」やその影響に関心をもたざるを得ないことによる。とともに、「気候危機」とも言われるその原因の資本主義を丁寧に解き明かし、鋭く批判し、それゆえに刺激的である斎藤の議論・主張による。とりわけ、『資本論』第1巻の刊行後に「マルクスが取り組んでいたのはエコロジー研究と共同体研究」(179ページ)であった。晩年のマルクスは、「資本主義がもたらす近代化が、最終的には人類の解放をもたらす」という「進歩史観」(史的唯物論)と決別した(152ページ)。マルクスがめざした「コミュニズムとは、平等で持続可能な脱成長型経済(定常型経済)」(195ページ)であったという、斎藤による、マルクスの再解釈・再発見(「マルクスの復権」「マルクス理解の理論的大転換」)によるところが大きい。
〇本書のタイトルの「人新世」(ひとしんせい)とは、斎藤によると、「人類の経済活動が地球に与えた影響があまりに大きいため、ノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンは、地質学的に見て、地球は新たな年代に突入したと言い、それを『人新世』(Anthropocene)と名付けた。人間たちの活動の痕跡(こんせき)が、地球の表面を覆いつくした年代という意味である」(4ページ)。現在の地球の環境危機は、人(ヒト)の経済活動すなわち資本主義それ自体がもたらしたものであり、地球は新たな地質時代に突入した、というのである。
〇斎藤は本書で、環境危機を乗り越えようとする多様な主義・主張や運動に言及し、その問題点や限界を抉(えぐ)り出す。自然エネルギーや気候変動対策への公共投資によって、新たな雇用や経済成長を生み出そうとする「グリーン・ニューディール」(気候ケインズ主義)や、ロボットや人口知能(AI)の技術革新を加速させれば、持続可能な経済成長が可能になると主張する「加速主義」などについてである。それとともに、斎藤は、「マルクスが求めていたのは、無限の経済成長ではなく、大地=地球を<コモン>として持続可能に管理することであった」(190ページ)という。そして、気候変動問題の解決策として「脱成長コミュニズム」を提唱する。それは、資本主義の転換を迫る、資本主義でも社会主義でもない平等で持続可能な「社会像」である(コミュニズムは一般的には共産主義と訳される)。
〇本書から、<コモン>(共有資源)や「脱成長コミュニズム」に関する斎藤の言説について、筆者が留意したい一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
いま求められる脱成長型のポスト資本主義
資本主義は、利潤を増やすための経済成長をけっして止めることはない。/資本は、(経済成長のための)手段を選ばない。気候変動などの環境危機が深刻化することさえも、資本主義にとっては利潤獲得のチャンスになる。山火事が増えれば、火災保険が売れる。バッタが増えれば、農薬が売れる。ネガティブ・エミッション・テクノロジー(大気中の二酸化炭素を回収・除去する技術)は、その副作用が地球を蝕(むしば)むとしても、資本にとっての商機となる。いわゆる惨事便乗型資本主義だ。/このように危機が悪化して苦しむ人々が増えても、資本主義は、最後の最後まで、あわゆる状況に適応する強靭(きょうじん)性を発揮しながら、利潤獲得の機会を見出していくだろう。環境危機を前にしても、資本主義は自ら止まりはしない。/だから、このままいけば、資本主義が地球の表面を徹底的に変えてしまい、人類が生きられない環境になってしまう。それが、「人新世」という時代の終着点である。/それゆえ、無限の経済成長をめざす資本主義に、今、ここで本気で対峙しなくてはならない。私たちの手で資本主義を止めなければ、人類の歴史が終わる。(117~118ページ)
環境危機に立ち向かい、経済成長を抑制する唯一の方法は、私たちの手で資本主義を止めて、脱成長型のポスト資本主義(「脱成長コミュニズム」)に向けて大転換することである。(119ページ)
「脱成長コミュニズム」を実現する道としての<コモン>
マルクスは、人々が生産手段を<コモン>(common)として共同で管理・運営するだけでなく、地球をも<コモン>として管理する社会を、コミュニズム(communism)として構想していた。(142~143ページ)
<コモン>とは、社会的に人々に共有され、管理されるべき冨のことを指す。(中略)/<コモン>は、アメリカ型新自由主義とソ連型国有化の両方に対峙する「第3の道」を切り拓く鍵だといっていい。つまり、市場原理主義のように、あらゆるものを商品化するのでもなく、かといって、ソ連型社会主義のようにあらゆるものの国有化をめざすのでもない。第3の道としての<コモン>は、水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主義的に管理することをめざす。(141ページ)
(すなわち、マルクスがそう考えたように)<コモン>の思想は、貨幣や私有財産を増やすことをめざす個人主義的な生産から、将来社会においては「協同的富」を共同で管理する生産に代わることをめざすのである。(201ページ)
「脱成長コミュニズム」を実現するための具体的方策
「脱成長コミュニズム」をどのように実現させるのか、そのためになすべきことは大きく5点にまとめられる。
(1)使用価値経済への転換/生産の目的を商品としての「価値」(儲け)の増大すなわち利潤の獲得ではなく、「使用価値」(有用性。商品やサービスの質)に重きを置いた経済に転換して、大量生産・大量消費から脱却する。別言すれば、生産を社会的な計画のもとに置き、人々の基本的ニーズを満たすことを重視する。
(2)労働時間の短縮/労働時間を削減して、生活の質を向上させる。社会の再生産にとって本当に必要な生産に労働力を意識的に配分し、金儲けのためだけの、意味のない仕事を大幅に減らす。「使用価値」の経済に向けた転換には、労働時間の短縮が根本条件である。
(3)画一的な分業の廃止/画一的な労働をもたらす分業を廃止して、労働の創造性を回復させる。資本主義の分業体制のもとでは、労働は画一的で、単調な作業が多い。労働をより創造的な、自己実現の活動に変えていくためには、多種多様な労働に従事できる生産現場の設計が好ましい。
(4)生産過程の民主化/生産のプロセスの民主化を進めて、経済を減速させる。「使用価値」に重きを置きつつ、労働時間を短縮するために、開放的技術を導入していく。そのためには、一部の経営陣の意向に基づいて非民主的な決定が行われるのではなく、労働者たちが生産における意思決定権を握る必要がある。
(5)エッセンシャル・ワークの重視/使用価値経済に転換し、労働集約型のエッセンシャル・ワーク(生活維持に不可欠な仕事)を重視する。ロボットやAIでは対応しきれない、ケアやコミュニケーションを必要とする介護や看護、保育や教育などの労働がしっかりと評価される必要がある。(300~314ページ)
<コモン>と「社会的共通資本」(宇沢弘文)の違い
(<コモン>に関して、より一般的に馴染みがある概念として、宇沢弘文の「社会的共通資本」がある。)宇沢は、人々が「豊かな社会」で暮らし、繁栄するためには、一定の条件が満たされなくてはならない。そうした条件が、水や土壌のような自然環境、電力や交通機関といった社会的インフラ、教育や医療といった社会制度である。これらを、社会全体にとって共通の財産として、国家のルールや市場的基準に任せずに、社会的に管理・運営していこうと考えたのである。<コモン>の発想も同じだ。/ただし、「社会的共通資本」と比較すると、<コモン>は専門家任せではなく、市民が民主的・水平的に共同管理に参加することを重視する。そして、最終的には、この<コモン>の領域をどんどん拡張していくことで、資本主義の超克(ちょうこく。困難を乗り越えること)をめざすという決定的な違いがある。(141~142ページ)
〇経済成長は確かに、私たちの生活や社会を物質的に豊かにした。それは、資本主義のグローバル化が進むなかで、グローバル・ノース(北の先進国)によるグローバル・サウス(南の発展途上国)からの労働力の搾取や自然資源の収奪のうえに成り立っている。グローバル・ノースの「過剰発展」や大量生産・大量消費のライフスタイル(「帝国的生活様式」)は、グローバル・サウスの人々の劣悪な生活条件に依存している。そしてまた、グローバル・サウスはそのグローバル・ノースに依存せざるを得ない。ここに資本主義の「矛盾」と「悲劇」がある(27~30ページ)。いずれにしろ、資本主義社会は、絶えず「外部性」を作り出し、そこに負担や犠牲を強いる・転嫁することによって発展してきたのである。
〇現代の資本主義は、「不平等を一層拡大させながら、グローバルな環境危機を悪化させてしまう」。資本主義は、豊かさを生み出すシステムではなく、「私たちの生活に欠乏をもたらしている」。「持続可能で公正な社会」を実現するためには、資本主義によって解体させられた、人々が生産手段を自律的・水平的に「自治管理」「共同管理」する<コモン>を再建する必要がある。そのための唯一の選択肢が、マルクスにみる「脱成長コミュニズム」である(258、290、360ページ)。斎藤の、ラディカルな主張である。
〇それを換言すれば、生産手段を<コモン>として社会的に所有し、民主的に管理することによって、経済活動は減退するが、現代の環境危機を乗り越えることはできる。このコミュニズムの萌芽は、「21世紀の環境革命として花開く可能性を秘めている」(323ページ)、となる。ここに本書の核心があり、思考や概念の斬新さをみる。
〇そして、斎藤は、「資本の専制から、この地球という唯一の故郷を守る」ためには、「3.5%」(ハーヴァード大学の政治学者エリカ・チェノウェスらの研究による)の人々が非暴力的な方法で、本気で立ち上がることであるという(362、364ページ)。この点は非現実的な楽観論と評されるおそれなしとしないが、社会に大きなインパクトを与えた多くの抗議活動や社会運動は、最初は少人数で始まっている。本稿のタイトルにいう「変革への途」が含意するところでもある。
付記
〇論拠は不明であるが、斎藤の挑発的で小気味よい指摘やフレーズに次のようなものがある。あえて付記しておくことにする。
2015年9月に国連で開かれたサミットによって採択され、各国政府も大企業も推進する「SDGs」(エス・ディー・ジーズ、Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)は、「アリバイ作りのようなものであり、目下の危機から目を背(そむ)けさせる効果しかない。(中略)SDGsまさに現代版『大衆のアヘン』である」(4ページ)。
「高度経済成長の恩恵を受けてあとは逃げ切るだけの団塊世代の人々が、脱成長という『綺麗事(きれいごと)』を吹聴している。(中略)若いころに経済成長の果実を享受しておきながら、一線を退いたそのときから『このままゆっくり日本経済は衰退していけばいい』と言い始めたというわけである(120ページ)。(ちなみに、「平等に、緩(ゆる)やかに貧しくなっていけばいい」という上野千鶴子(うえの・ちずこ)は1948年生まれであり、「本当に豊かな生き方は『ローカル』と『定常経済』にある」という内田樹(うちだ・たつる)は1950年生まれである)。
(「定常型社会」論を展開する広井良典(ひろい・よしのり)や社会経済学者の佐伯啓思(さえき・けいし)によれば)「資本主義的市場経済を維持したまま、資本の成長を止めることができるという」(128~129ページ)。「利潤獲得に駆り立てられた経済成長という資本主義の本質的な特徴をなくそうとしながら、資本主義を維持したいと願うのは、丸い三角を描くようなものである。まさに、真の『空想主義』である。これが旧世代の脱成長論の限界なのだ」(133ページ)。