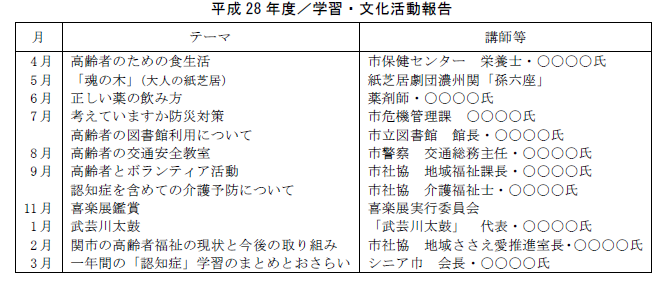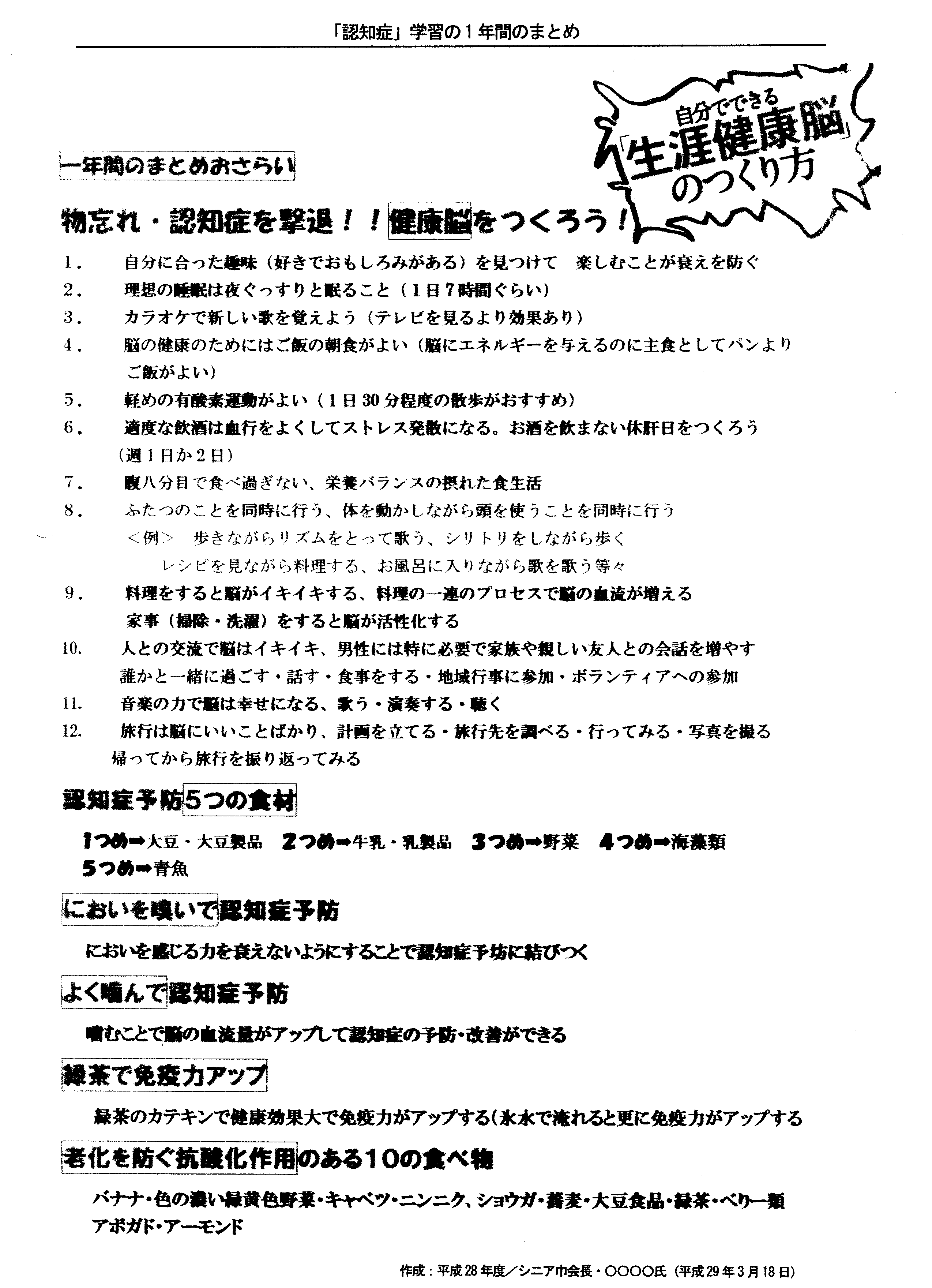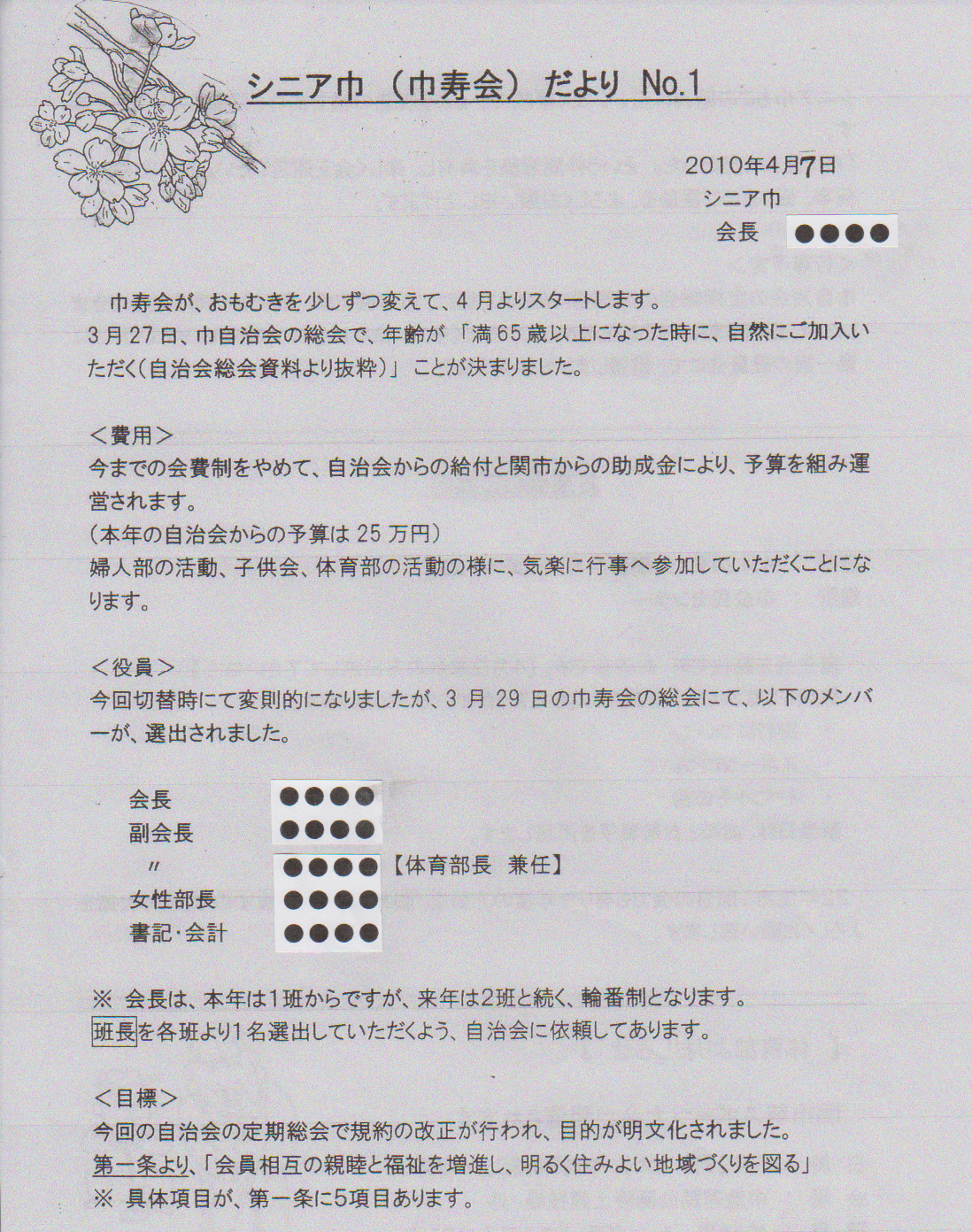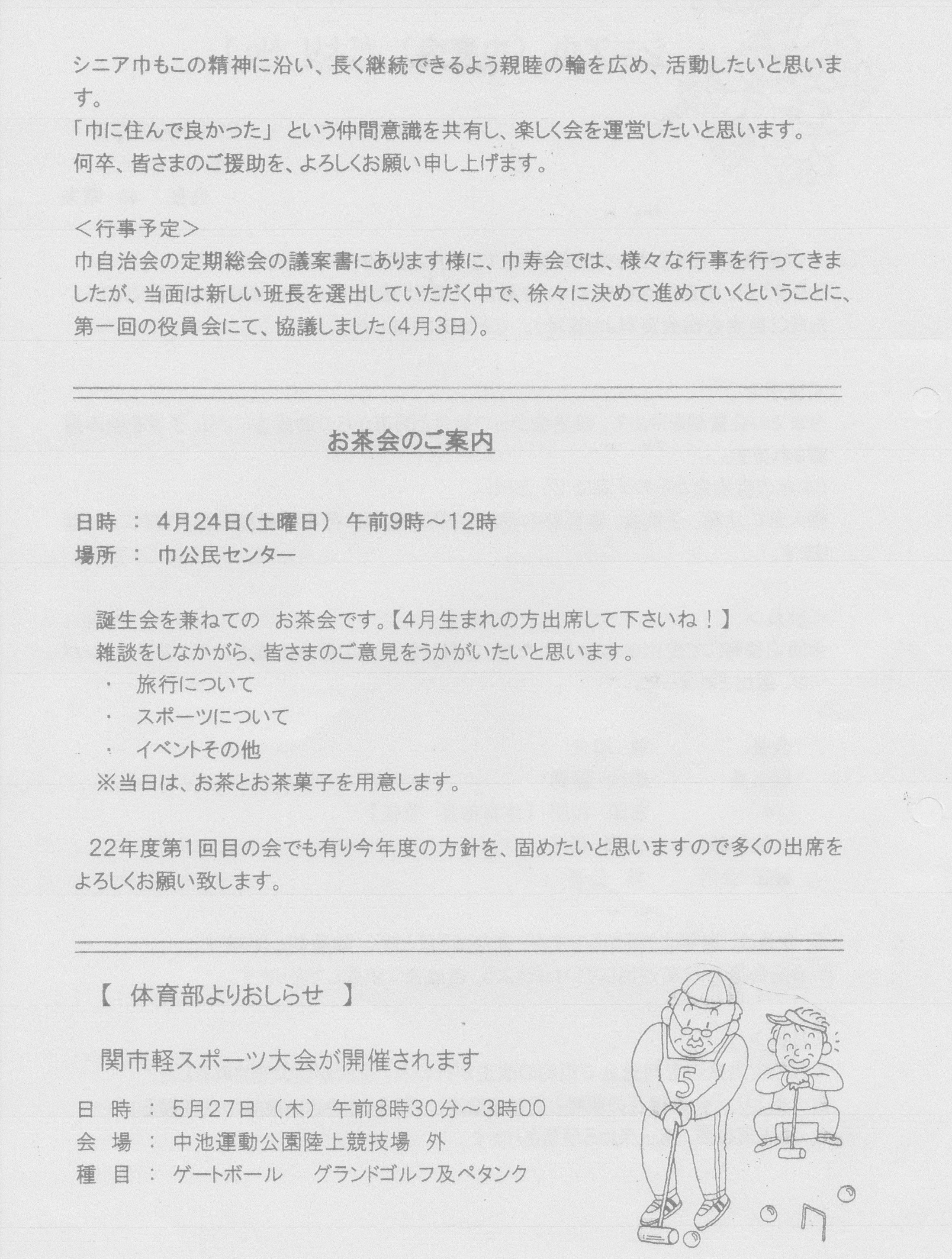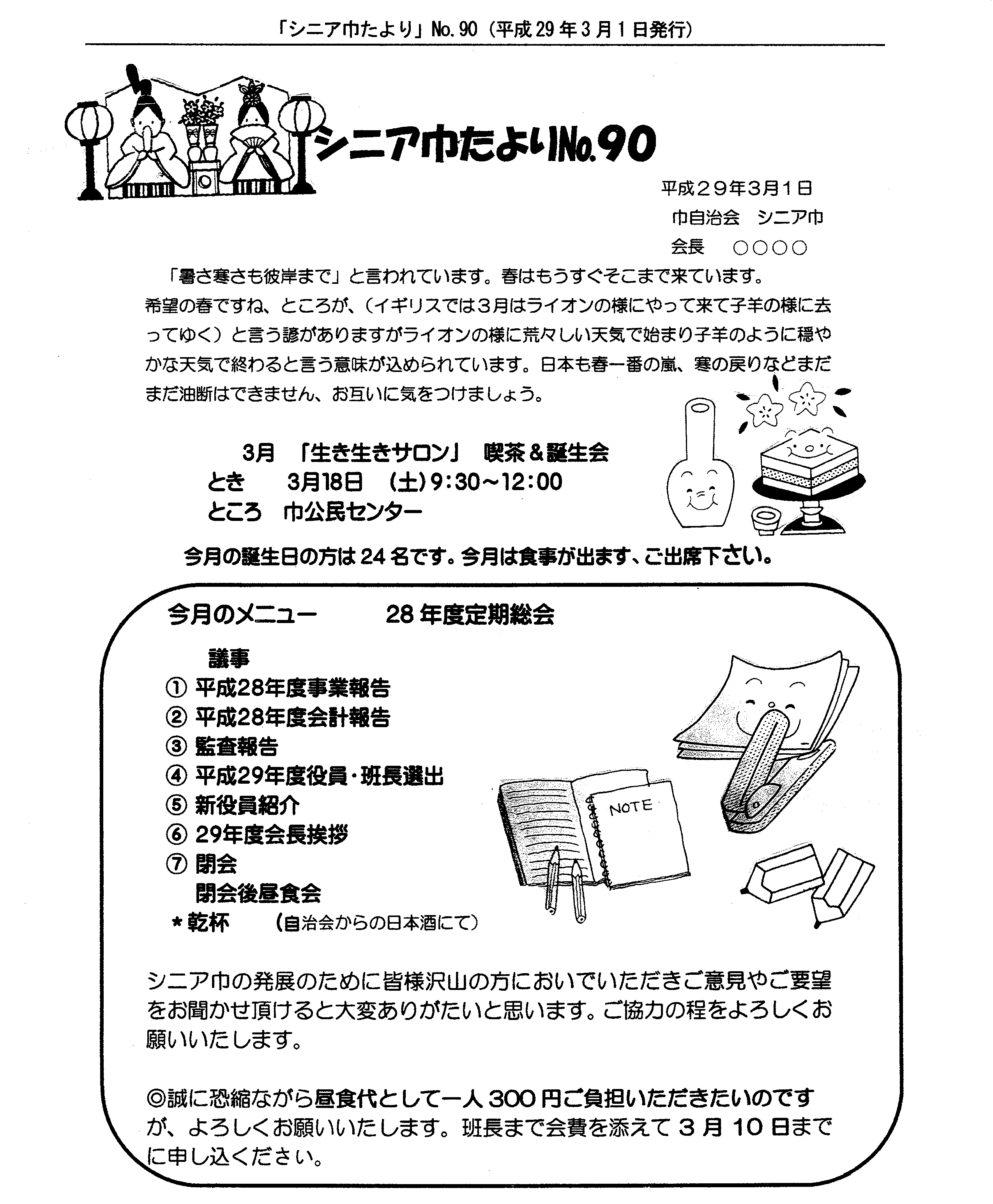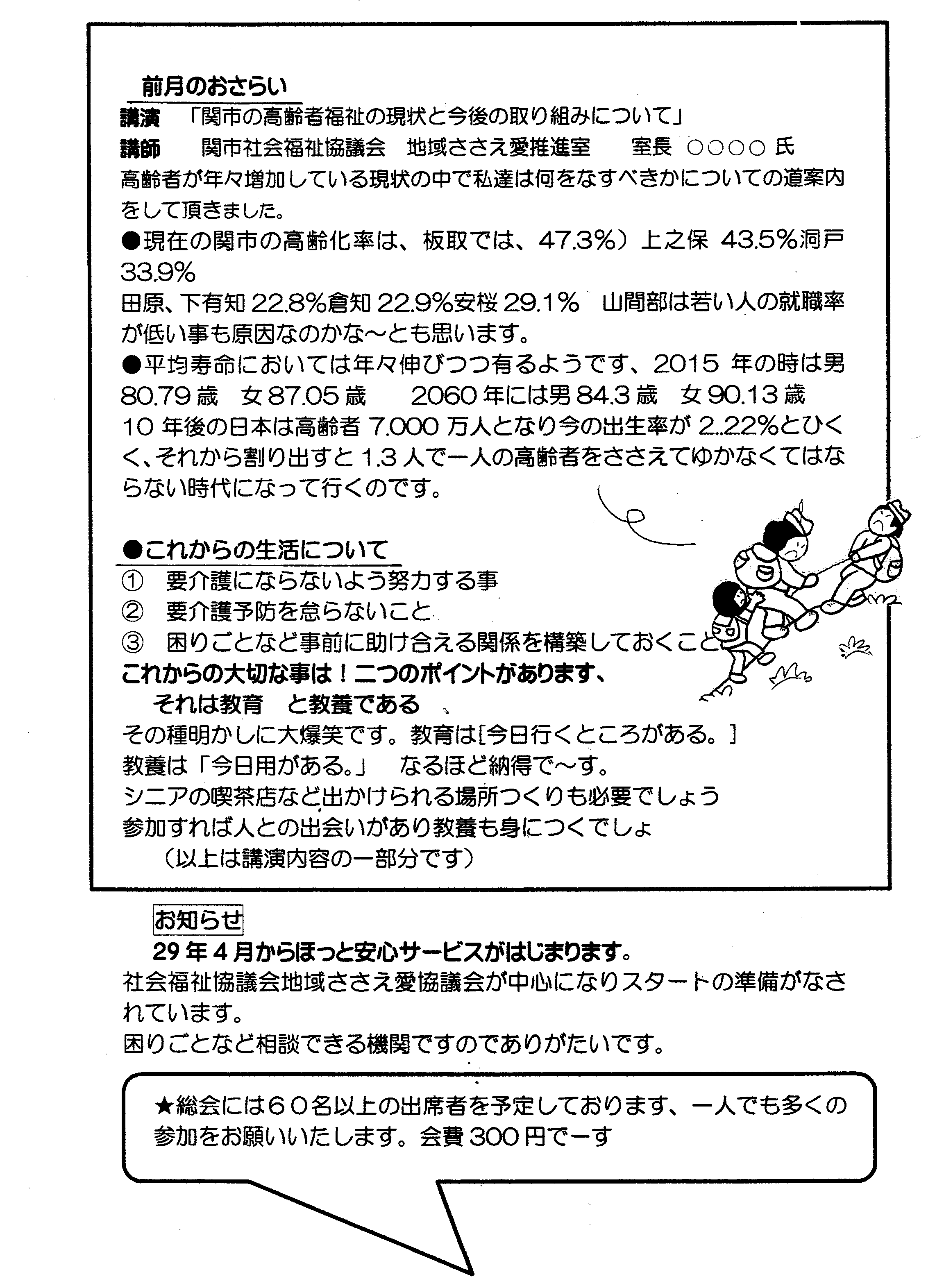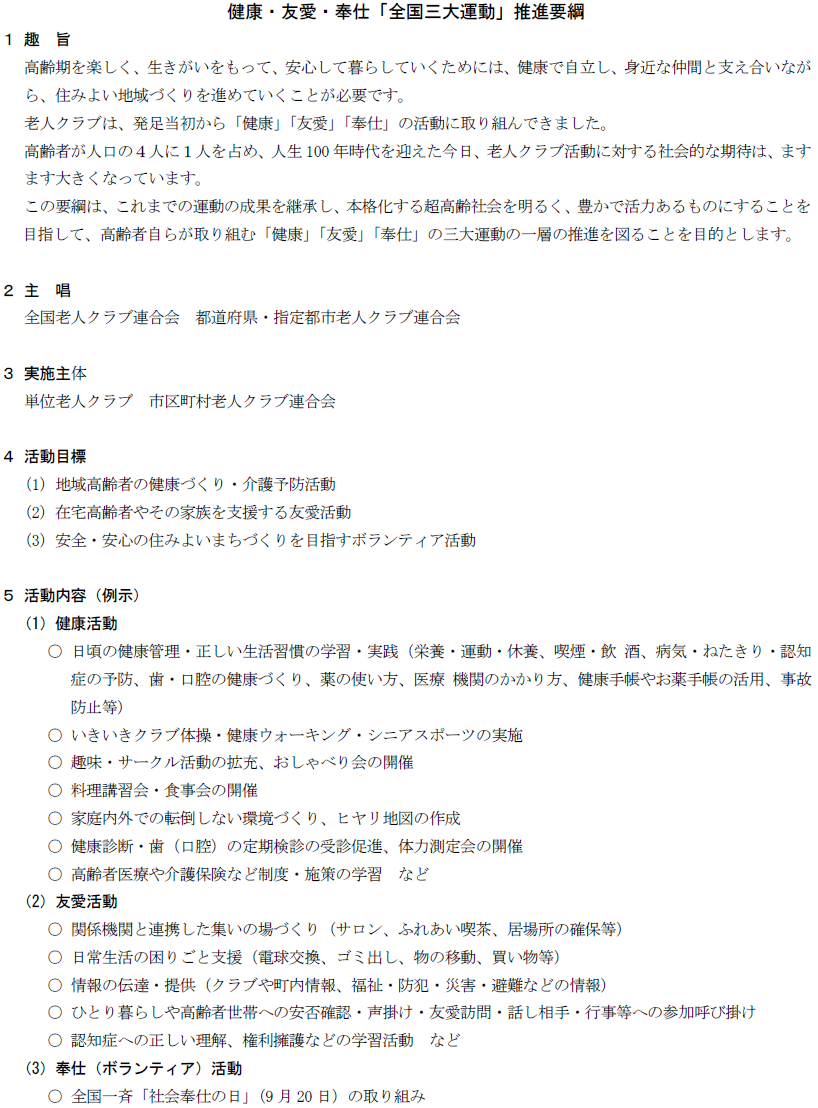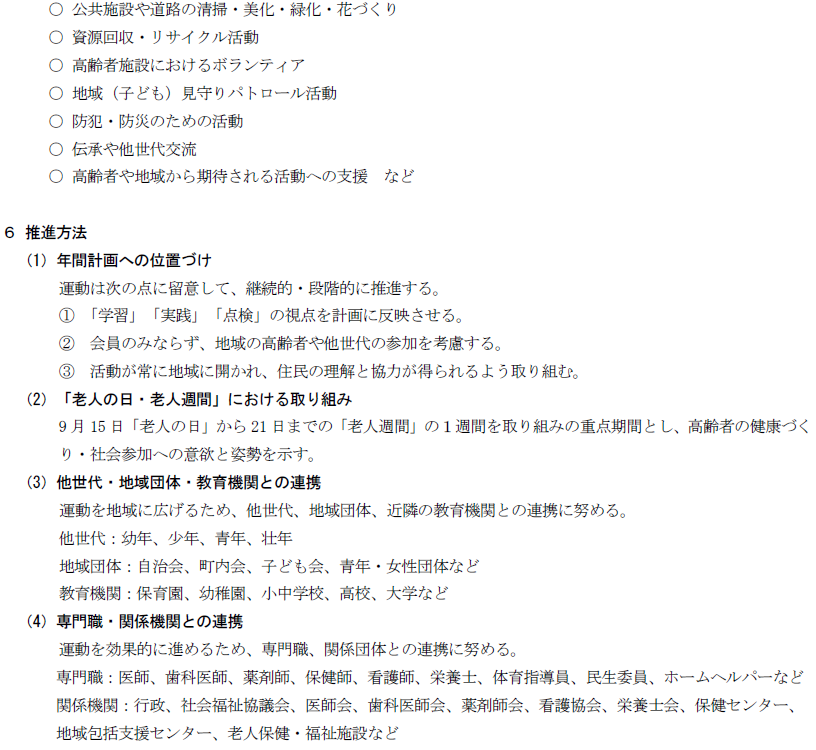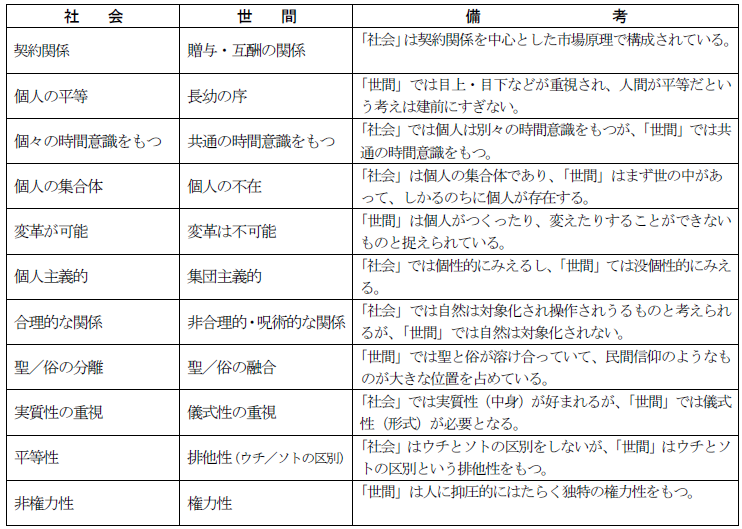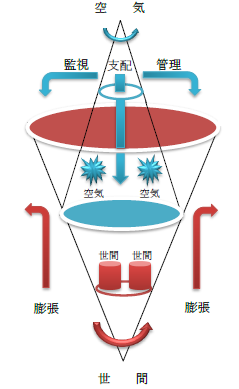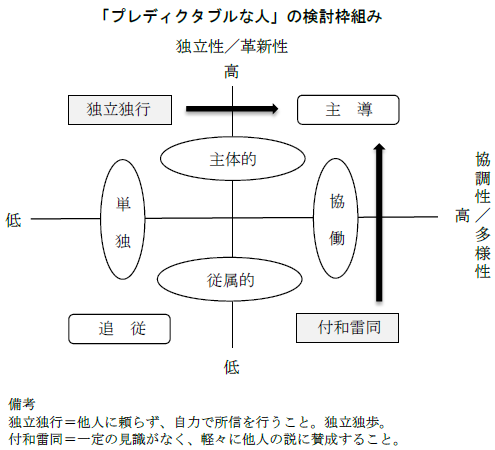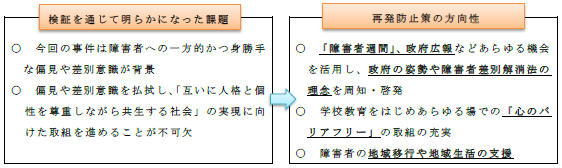〇「知的生産」という言葉は、梅棹忠夫(うめさおただお、専攻は民族学)の造語である。梅棹は、「京大型カード」の発案者であり、情報管理の「古典」と評される『知的生産の技術』(岩波書店、1969年7月。以下[1])を著わしている。[1]で梅棹は、エッセイふうに次のように述べている。
知的生産とは、知的情報の生産である。既存の、あるいは新規の、さまざまな情報をもとにして、それに、それぞれの人間の知的情報処理能力を作用させて、そこにあたらしい情報をつくりだす作業なのである。それは、単に一定の知識をもとでにしたルーティン・ワーク以上のものである。そこには、多少ともつねにあらたなる創造の要素がある。知的生産とは、かんがえることによる生産である。(11ページ)
人間の知的活動を、教養としてではなく、積極的な社会参加のしかたとしてとらえようというところに、この「知的生産の技術」というかんがえかたの意味もあるのではないだろうか。このような意味での知的生産であるならば、それは、現代にいきる人間すべての問題ではないか。(中略)すべての人間が、その日常生活において、知的生産活動を、たえずおこなわないではいられないような社会に、われわれの社会はなりつつあるのである。(12ページ)
〇異例のロングセラーやヒットとなっている「思考」や「勉強」に関する2冊の本がある。外山滋比古(とやましげひこ、専攻は英文学)の『思考の整理学』(筑摩書房、1983年3月。以下[2])と千葉雅也(ちばまさや、専攻は哲学)の『勉強の哲学―来たるべきバカのために―』(文藝春秋、2017年4月。以下[3])である。筆者(阪野)の手もとにある[2]は、1986年4月発行の文庫本であるが、その帯(おび)には「東大・京大で1番読まれた本」「“もっと若い時に読んでいれば…”」というキャッチコピーがある。[3]のそれには、「東大・京大でいま1番読まれている本!」「勉強とは、これまでの自分を失って、変身することである」とある。ともに読者の、「学歴」(「東大・京大」)や「人生」(「過去・現在・未来」)への思いを刺激し、その感情(「後悔や希望」)を巧みに煽(あお)る。不安や不満が渦巻く現代社会(格差社会、管理社会、閉塞社会)の時流やニーズを反映した本でもある。
〇[2]で外山は、「思考」の本質と方法(具体的な“秘伝”であり、単なるハウツーではない)についてエッセイ的に解説する。その基本には、「知識よりも思考の方が重要である」という主張がある。筆者が再認識しておきたい言説には、次のようなものがある(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
グライダー能力と飛行機能力
人間には、グライダー能力と飛行機能力とがある。受動的に知識を得るのが前者、自分でものごとを発明、発見するのが後者である。両者はひとりの人間の中に同居している。グライダー能力をまったく欠いていては、基本的知識すら習得できない。何も知らないで、独力で飛ぼうとすれば、どんな事故になるかわからない。
指導者がいて、目標がはっきりしているところではグライダー能力が高く評価されるけれども、新しい文化の創造には飛行機能力が不可欠である。(「グライダー」13、15ページ)
思考を寝させる
アイデアと素材さえあれば、思考は進むか、というと、そうではない。これをしばらくそっとしておく必要がある。“寝させる”のである。思考の整理法としては、寝させるほど大切なことはない。思考を生み出すのにも、寝させるのが必須である。
努力をすれば、どんなことでも成就するように考えるのは思い上がりである。努力しても、できないことがある。それには、時間をかけるしか手がない。(「醗酵」32ページ。「寝させる」40、41ページ)
テーマの設定
「テーマはひとつでは多すぎる。すくなくとも、二つ、できれば、三つもって、スタートしてほしい」。ひとつだけだと、これがうまく行かないと、あとがない。こだわりができる。妙に力(りき)む。頭の働きものびのびしない。ところが、もし、これがいけなくとも、代りがあるさ、と思っていると、気が楽だ。テーマ同士を競争させる。いちばん伸びそうなものにする。さて、どれがいいか、そんな風に考えると、テーマの方から近づいてくる。
“熟したテーマは、向うからやってくる”(「カクテル」43ページ。「醗酵」35ページ)
知識の組み合わせと順序
思考における思いつき、着想は、第一次的なものである。単独ではさほど力をもっていないようないくつかの着想があるとする。そのままにしておけば、たんなる思いつきがいくつか散乱しているに過ぎない。それに対して、自分の着想でなくてもよい。おもしろいと思って注意して集めた知識、考えがいくつかあるとする。これをそのままノートに眠らせておくならば、いくら多くのことを知っていても、その人はただのもの知りでしかない。“知のエディターシップ”(既存の知識を編集によって、新しい、それまでとはまったく違った価値のあるものにすること)、言いかえると、頭の中のカクテルを作るには、自分自身がどれくらい独創的であるかはさして問題ではない。もっている知識をいかなる組み合わせで、どういう順序に並べるかが緊要事となるのである。
本当のカクテル論文(すぐれた学術論文)は、諸説を照合・参照して調和折衷(「新しい結合」「自由な化合」)させ、人を酔わせながら、独断におちいらない手堅さをもっている。(「エディターシップ」51ページ。「カクテル」47ページ)
知識の蓄積と忘却
頭の優秀さは、記憶力の優秀さとしばしば同じ意味をもっている。これまでの教育では、知識をどんどん蓄積することが重視されてきた。しかし、これからは、新しいことを考え出し、作り出す「創造的人間」が問題になる。頭に、勉強し習得した知識を保存保管するだけでなく、不要になったものを、処分し、整理し、広々としたスペースをとる必要がある。頭をよく働かせるには、この“忘れる”ことが、きわめて大切である。
思考の整理には、忘却がもっとも有効である。不易(不変)の知識のみが残るようになれば、そのときの知識は、それ自体が力になりうるはずである。(「整理」110~112、115ページ。「時の試練」127ページ。「すてる」133ページ)
〇[3]で千葉は、「勉強」の原理論と実践論(「勉強を進めるための基礎的なテクニック」)について哲学的に論述する。その最初に提示する基本的なテーゼは、「勉強とは、これまでの自分の自己破壊である」。筆者がメモっておきたい言説には、次のようなものがある(要約と抜き書き。見出しは筆者)。
勉強とは「自己破壊」であり、「変身」することである
人は基本的には、家族や学校、会社、地域・社会など周りの環境の「ノリ」に合わせて生きている(環境への「同調」「適応」「順応」)。
勉強するのは、環境や同調圧力(「みんな同じようにしなさい」「出る杭は打たれる」)によって狭められた人生の「可能性」を切り開き、これまでのノリから「自由」になるためである。その意味で、勉強とは、かつての「ノっていた自分」を破壊し、わざと「ノリが悪い」人になることである。具体的には、勉強によって身につけるのは「批判的になる」ことであり、ノリの悪い「言語」を使用すること(「言語偏重」の人になること)である。それは、環境から「浮く」ことであり、周りから見て「キモい人」になることでもある。
要するに、勉強とは「自己破壊」であり、「新しいノリ」に引っ越すこと、新しい生き方に「変身」することである。(第1章「勉強と言語―言語偏重の人になる」)
勉強は情報の比較を「中断」し、「有限化」することが必要である
勉強は、いま気になっていること、「問題意識をもつ」ことから始まる。ただ、勉強にはきりがなく、「深追い」しすぎると「目移り」してしまうことがある。「深追い」(「アイロニー」「ツッコミ」)とは根拠を疑うこと、「追究」であり、「目移り」(「ユーモア」「ボケ」)とは見方を変えること、「連想」である。この二つは、「深い勉強」(「ラディカル・ラーニング」)のための思考スキルである。
勉強とは、何らかの専門分野に参加することである。専門分野の勉強は、「深追い」方向と「目移り」方向にきりがなくなる。そこで、勉強する際には、「まずこれだけ」「ここまで」「ひとまずこれを勉強した」というように勉強を「有限化」する(きりをつける)。そして、継続すること、が肝要となる。そのためには、「信頼」できる著者による「まとも」な本を読むことが基本となる。その読書から得た信頼できる情報を自分なりに考えて比較し、ある結論、しかし絶対的なものではなく仮の結論を出す。それは、自分の「こだわり」(「享楽」)によるが、この「比較の中断」「結論の仮固定」を比較の継続のなかで進めることが勉強を継続し、深めることである。
なお、「このくらいでいい」という勉強の「有限化」をしてくれる存在(「有限化の装置」)が教師である。また、勉強するにあたって「信頼」すべき他者は、「粘り強く比較を続けている人」「たえず勉強を続けている他者」である。(第2章「アイロニー、ユーモア、ナンセンス」、第3章「決断ではなく中断」、第4章「勉強を有限化する技術」)
〇「知る」ことと「考える」こと(「知識」と「思考」)は、例えば、「一次資料と二次資料」「量的データと質的データ」「既知のことと未知のこと」「伝達の言語と思考の言語」などの取り扱いや、「インプットとアウトプット」「概念くずしと概念づくり」「具体的思考と抽象的思考」「拡散的思考と収束的思考」などの取り組みが問われることになる。また、管見ながら、勉強とは、関心と疑問から始まり、ゆとりと自由のなかで知識の習得と思考の推進を図り、それを一所懸命に行い、未来(あす)の地域・社会を創るために繰り返すこと(活動と過程)である。改めて梅棹と外山、そして新たに千葉の「勉強論」を通じて再認識し、学んだことのひとつである。なお、[1][2]が長い時間を超えた「古典」と言われ、[3]が「いま」注目されるのは、その是非は別にして、単なるハウツー本ではなく、現代社会が求める「知的生産」の思想書(哲学書)であるからでもある。
〇筆者はかつて、学生たちに「住民の生活の匂(にお)いがする場に自分の身を置く」「フィールドの地べたを這(は)う」「一人ひとりの高齢者や障がい者などの人生に思いを致す」勉強や研究の重要性を説いてきた。そして、次のように言ってきた。(1)すべてを疑い、問題意識の明確化を図ること。(2)微視的かつ俯瞰的、複眼的視点をもつこと。(3)第一次的現実とともに、歴史から学ぶこと。(4)先行研究や、使える理論や方法について熟考すること。(5)量的研究と質的研究を組み合わせ、多面的・多層的に考察すること。(6)関連および周辺領域の知見を広範に参照すること。(7)協働的活動によって思考を拡散・焦点化、深化させること。(8)既存のものに偏重せず、新たな仮説の探索や設定・検証に基づくこと。(9)グラフや概念図を作成することによって、思考を視覚化すること。(10)信頼性や独創性・先駆性、そして倫理性を重視すること、などがそれである。付記しておく。