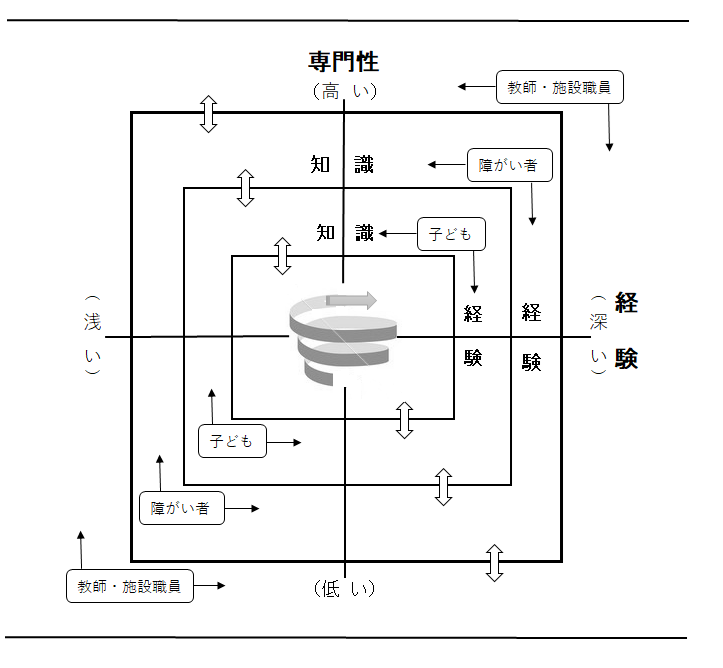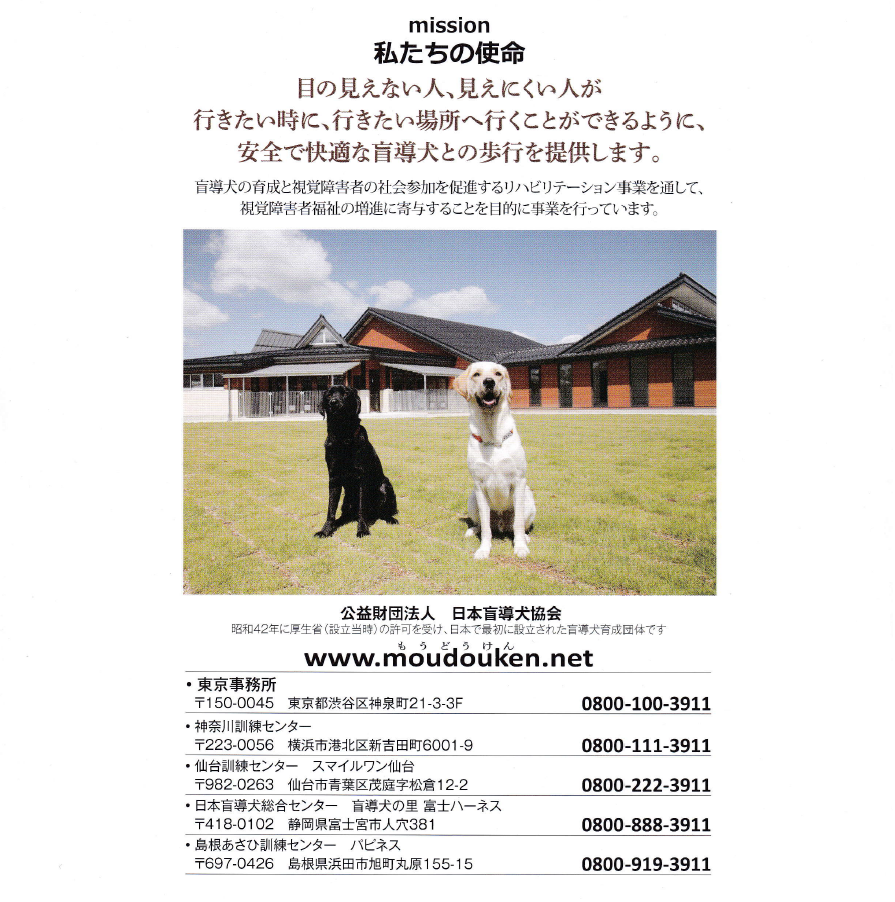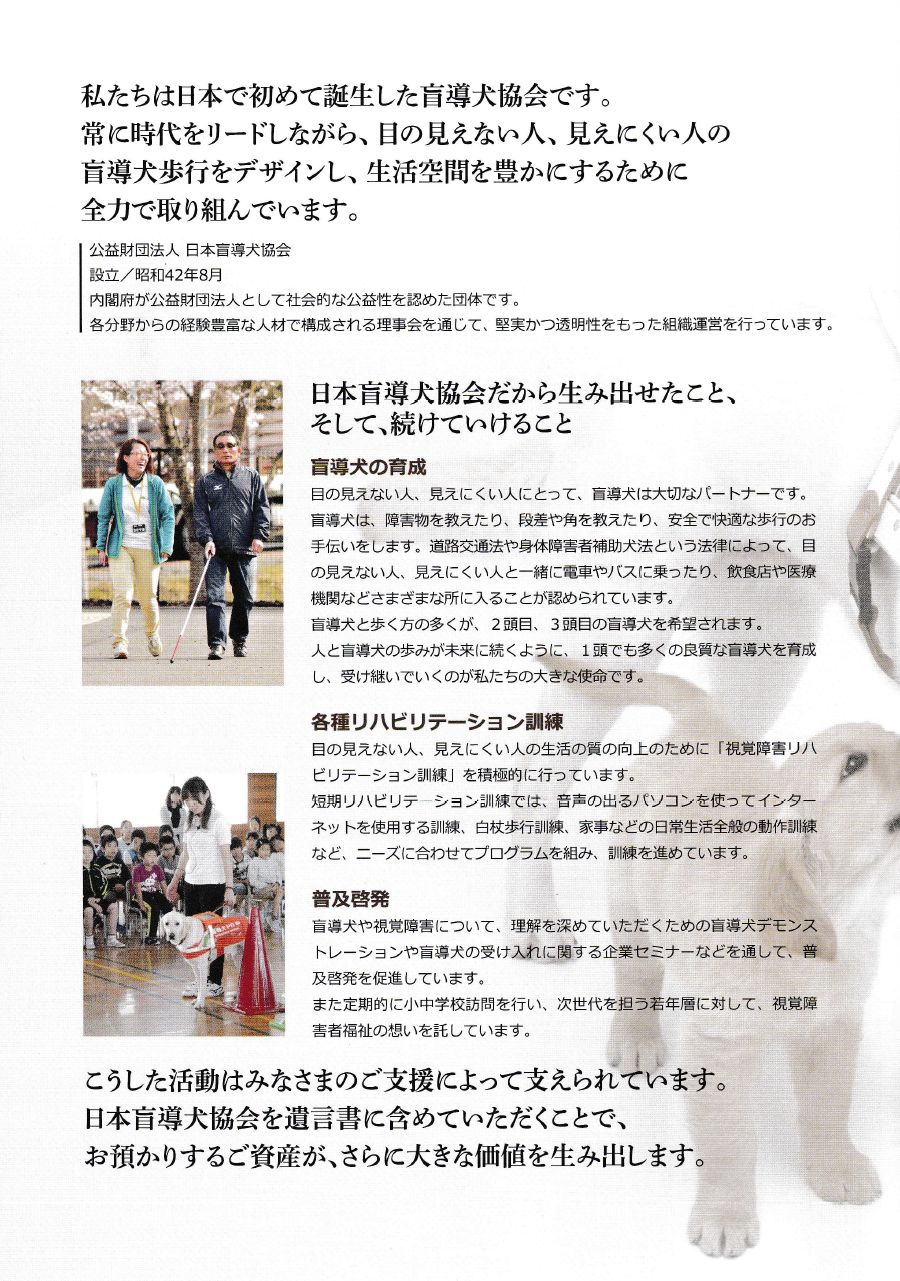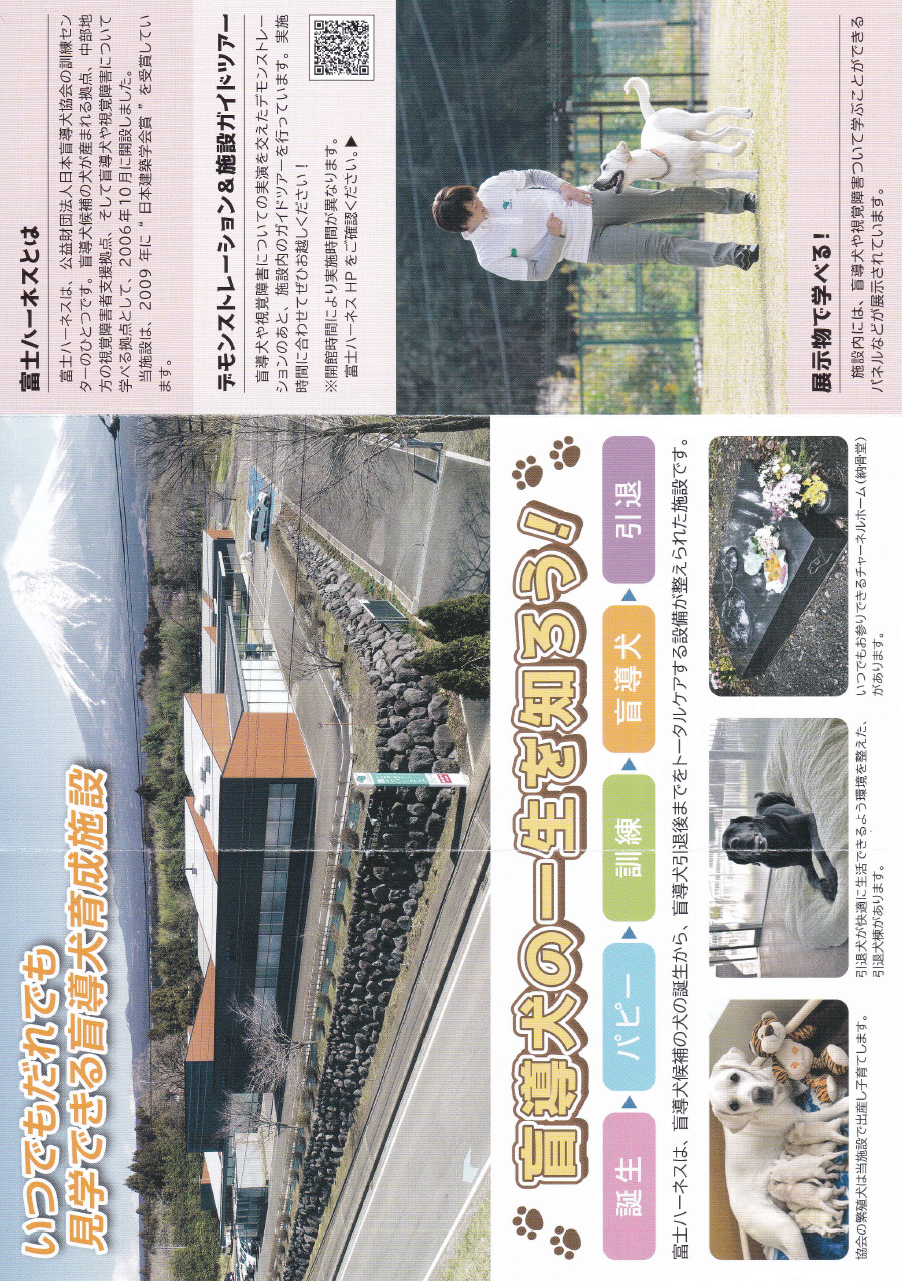〇筆者(阪野)の手もとに、エーリッヒ・フロム著、日高六郎(ひだか・ろくろう)訳『自由からの逃走』(Erich Fromm,Escape from Freedom,1941. 132版(新版)、東京創元社、2024年4月。以下[1])がある。訳者である日高は、その「訳者あとがき」で次のようにいう。「フロムによれば、現代における自由の問題は、たんに巨大な機械主義社会や政治的全体主義の圧力などによって、個人の自由がおびやかされているということだけではなくて、いっぽうではひとびとが求めてやまないはずの、価値としての自由が、他方では、ひとびとがそこから逃れでたいとのぞむような呪咀(じゅそ)となりうるところにあるという」(329ページ)。[1]におけるフロムの主要なメッセージである。そして、日高によると、[1]は「専門書であるばかりでなく、むしろそれ以上に、一般の知識人全体にうったえる文明批評の書である」(333ページ)。超ロングセラーの所以でもある。
〇もう一冊、筆者の手もとに、仲正昌樹(なかまさ・まさき)著『人はなぜ「自由」から逃走するのか―エーリヒ・フロムとともに考える―』(KKベストセラーズ、2020年9月。以下[2])がある。[2]は、[1]の「純粋な解説書」ではない。それは、[1]の「議論の流れに即して、全体主義を可能にした歴史的・社会的条件を確認し」、「大衆社会の住人が『自由』から逃走し始め、その一部が全体主義を支持するに至ったプロセスを再構成したうえで、どうして『自由』は重荷になるのか」(17ページ)を、仲正の視点・視座から広く・深く論究する専門書である。仲正は、フロムと[1]について、こう説述する。
エーリヒ・フロム(1900~1980)は、ドイツ系ユダヤ人で、フロイトに始まる精神分析の理論を社会的性格の分析に応用する研究に従事していたが、ナチス政権成立後、アメリカに亡命し、戦後はアメリカやメキシコで研究活動を続けた。「愛」「悪」「神」「自由」「ヒューマニズム」「社会主義」「革命」など、人間の生き方の根本に関わる重要なテーマに関する多くの著作を残し、政治的・宗派的な立場の違いを超えて様々な立場の人に影響を与えてきたが、最も大きなインパクトがあったのは、彼が大戦中に執筆した『自由からの逃走』(1941)である。/この著作は、そのタイトルが示しているとおり、近代世界において「自由」を与えられた諸個人が、自由に生きることに伴う重圧、不安に耐えかねて、自らが自由を放棄するに至った過程を社会心理学・社会史的に描き出している。(15~16ページ)
〇この最後の一節に関して仲正は、フロムがいう「‥‥‥への自由」という「積極的な自由」と、「‥‥‥からの自由」という「消極的な自由」について、次のように要約する。「安定感を与えてくれていた第一次的な絆が断ち切られ、世界と対峙することを強いられ、無力感と孤独感に囚われた個人には、二つの選択肢がある。/一つは「積極的自由」への道、愛情と仕事を通して、自発的に世界と結び付く道である。この道を歩めば、彼は、独立と個人的自己の統合性を失うことなく、人間らしく、自然と調和して生きることができる。/もう一つは退行し、自らの自由と独立、自己の統合性を放棄する道である(「消極的自由」:阪野)。耐えがたく思われる心理状態を取りあえず回避するための『逃走』である」(116ページ)。
〇フロムの言によると、「積極的な自由」は、「自我の実現」すなわち自分の独自性と個性の成長や実現をめざした「全的統一的なパースナリティの自発的な行為のうちに存する」(284ページ)。「消極的な自由」は、母子関係や封建的・伝統的な束縛・強制などの「個人が完全に解放される以前に存在する第一次的絆」(35ページ)からの解放である。そして次のようにいう。ひとは「『‥‥‥からの自由』の重荷にたえていくことはできない。かれらは消極的な自由から積極的な自由へと進むことができないかぎり、けっきょく自由から逃れようとするほかない」(150~151ページ)のである。
近代人にとって自由は二重の意味をもっている。(中略)すなわち、近代人は伝統的権威から解放されて、「個人」となったが、しかし同時に、かれは孤独な無力なものになり、自分自身や他人から引きはなされた、外在的な目的の道具となったということ、さらにこの状態は、かれの自我を根底から危くし、かれを弱め、おびやかし、かれに新しい束縛にすすんで服従するようにするということである。それにたいし積極的な自由は、能動的自発的な生きる能力をふくめて、個人の諸能力の十分な実現と一致する。(296ページ)
〇こうしてフロムは、「人間存在と自由とは、その発端から(切り)離すことはできない」(42ページ)。こんにち人間は「貧困よりも、むしろ大きな機械の歯車、自動人形になってしまった」(302ページ)なかにあって、自由は単に外的な束縛から個人を解放するだけでなく、自己を認識し、自発的・創造的な行為・活動を生み出すとして、「積極的な自由」の重要性を主張するのである。
〇なお、フロムにあっては、「自由からの逃走」は、「権威主義」(服従)、「破壊性」(破壊)「機械的画一性」(同調)という3つの行動パターンとなって表れる。それぞれについてその要点をメモっておく(抜き書きと要約)。
権威主義
権威主義的性格の人間は、権威をたたえ、それに服従しようとする。しかし同時にかれはみずから権威であろうと願い、他のものを服従させたいと願っている。(182ページ)
権威はつねに、汝はこのことをなせ、あのことをなすべからずと命令するような個人や制度であるとはかぎらない。この種の権威は、外的権威と名づけることができるであろうが、権威は、義務、良心あるいは超自我の名のもとに、内的権威としてあらわれることもある。(184ページ)
権威主義的性格の問題で注意すべきもっとも重要な特徴は、力にたいする態度である。権威主義的性格にとっては、すべての存在は二つにわかれる。力をもつものと、もたないものと。それが人物の力によろうと、制度の力によろうと、服従への愛、賞賛、準備は、力によって自動的にひきおこされる。力は、その力が守ろうとする価値のゆえにではなく、それが力であるという理由によって、かれを夢中にする。かれの「愛」が力によって自動的にひきおこされるように、無力な人間や制度は自動的にかれの軽蔑をよびおこす。無力な人間をみると、かれを攻撃し、支配し、絶滅したくなる。ことなった性格のものは、無力なものを攻撃するという考えにぞっとするが、権威主義的人間は相手が無力になればなるほどいきりたってくる。(186ページ)
破壊性
破壊性は、対象との共棲(きょうせい)を目指すものではなく、対象を除去しようとするところにある。破壊性は、たえがたい個人の無力感や孤独感にもとづいている。外界にたいする自己の無力感は、その外界を破壊することによって逃れることができる。たしかに首尾よくそれを除去することができても、私は依然として孤独である。しかし、そのときの孤独はすばらしいもので、私はもはや外界の事物の圧倒的な力によって、おしつぶされるようなことはない。外界を破壊することは、外界の圧迫から自己を救う、ほとんど自暴自棄的な最後の試みである。(197ページ)
われわれの社会生活における人間関係を観察すると、破壊性がいたるところに、非常に多く存在していることに気づかないものはあるまい。その大部分は破壊性として意識されず、さまざまな方法で合理化されている。(中略)愛、義務、良心、愛国心などが、これまで他人や自己を破壊するためのカムフラージュとして利用されてきたし、現在も利用されている。(197~198ページ)
破壊性の源泉は、孤独と無力、不安、生命の障害(孤独になった無力な人間は、その感覚的、感情的、また知的なさまざまの能力を十分に実現することができない。かれは内的な安定性と自発性とをかいている)の3つである。(199~200ページ)
機械的画一性
機械的画一性とは、個人が自分自身であることをやめるのである。すなわち、かれは文化的な鋳型によってあたえられるパースナリティを、完全に受けいれる。そして他のすべてのひとびととまったく同じような、また他のひとびとがかれに期待するような状態になりきってしまう。「私」と外界との矛盾は消失し、それと同時に、孤独や無力を恐れる意識も消える。このメカニズムは、ある種の動物にみられる保護色と比較することができる。かれらはその周囲の状態にまったくにてしまうので、周囲からほとんどみきわめがつかない。個人的な自己をすてて自動人形となり、周囲の何百万というほかの自動人形と同一となった人間は、もはや孤独や不安を感ずる必要はない。しかし、かれの払う代価は高価である。すなわち自己の喪失である。(203~204ページ)
〇地縁・血縁などの社会的紐帯の希薄化・弱体化が進み、「社会的孤立」や「無縁社会」などが叫ばれるようになって久しい。そのひとつのきっかけは、2010年1月に放映された
NHKスペシャル「無縁社会―“無縁死” 3万2千人の衝撃―」であったと言われる。そして、とりわけ最近のSNS(Social Networking Service)の進展は、ネットワーキングとは裏腹に、新たな社会的孤立や無縁状態を生み出している。そうした日本社会の現状を抉り出し、現代に生きる人間の「存在」(実存)について考えるにあたって、求められる新たな視点・視座をどこにおき、新たな哲学思想をどう構築するかが問われなければならない。その際、「自由」はひとつのディープな概念であろう。そんな認識のもとに、本稿ではフロイトの『自由からの逃走』を取りあげることにした。
〇仲正は、「『自由からの逃走』はかつて、少なくとも私が学生だった30数年前には、現状批判的な社会科学を学ぶ者が当然読んでおくべき基本図書だった」(16ページ)という。筆者はそのさらに前の世代であるが、もうひとつの必読書に、デイヴィッド・リースマンの『孤独な群衆』(David Riesman,THE LONELY CROWD,1950. みすず書房、1964年2月)があった。人間の「社会的性格」は、伝統や慣習に従う伝統指向型 → 自分の価値観や良心に基づく内部指向型 → 他人からの承認を求める他人指向型へと変化するという言説である。そして、高度産業社会において人は、他人指向型になり、内面的には孤独感に囚われ、それをやわらげるために群衆のなかに紛れ込む(「孤独な群衆」)のである。
〇余談であるが、当時筆者は、「自由」と「疎外」について、また「社会心理学」に興味・関心をもち、大冊のセオドア・ミード・ニューカムの『社会心理学』(Theodore Mead Newcomb,Social Psychology,1950. 培風館、1956年)や南博の『体系社会心理学』(光文社、1957年)などに “ 挑戦 ” したことが懐かしく思い出される。
〇フロムの疎外論については、観念論的なそれであるとも評されるが、マルクス主義的な言説を併せもつものでもある。例えば[1]には、次のような一文がある。
資本主義においては、人間は巨大な経済的機械の歯車となった。(127ページ)
人間は利益を求めて働く。しかし獲得した利益は消費するためのものではなく、新しい資本として投資するためのものである。(128ページ)
資本の蓄積のために働くという原理は、(中略)主観的には、人間が人間をこえた目的のために働き、人間が作ったその機械の召使いとなり、ひいては個人の無意味と無力の感情を生みだすこととなった。(129ページ)
〇私事に渡るこんなことを思い出しながら、フロムがその重要性を説く「積極的な自由」の核心は、人間が自発的・創造的な活動を展開することにある、ということを再確認しておきたい。
付記
「積極的自由」と「消極的自由」については周知の通り、イギリスの政治哲学者のアイザイア・バーリン(Isaiah Berlin)もその著――『自由論』(Four Essays on Liberty,1969. 小川晃一ほか訳、新装版、みすず書房、2025年5月)で明示的に定義している。積極的自由は自己実現や自立としての自由、消極的自由は他人の干渉からの自由を意味し、前者を「への自由」(freedom to)、後者を「からの自由」(freedom from)と表現する。バーリンにあっては、この2つの概念は両立するものではなく、衝突するものである。