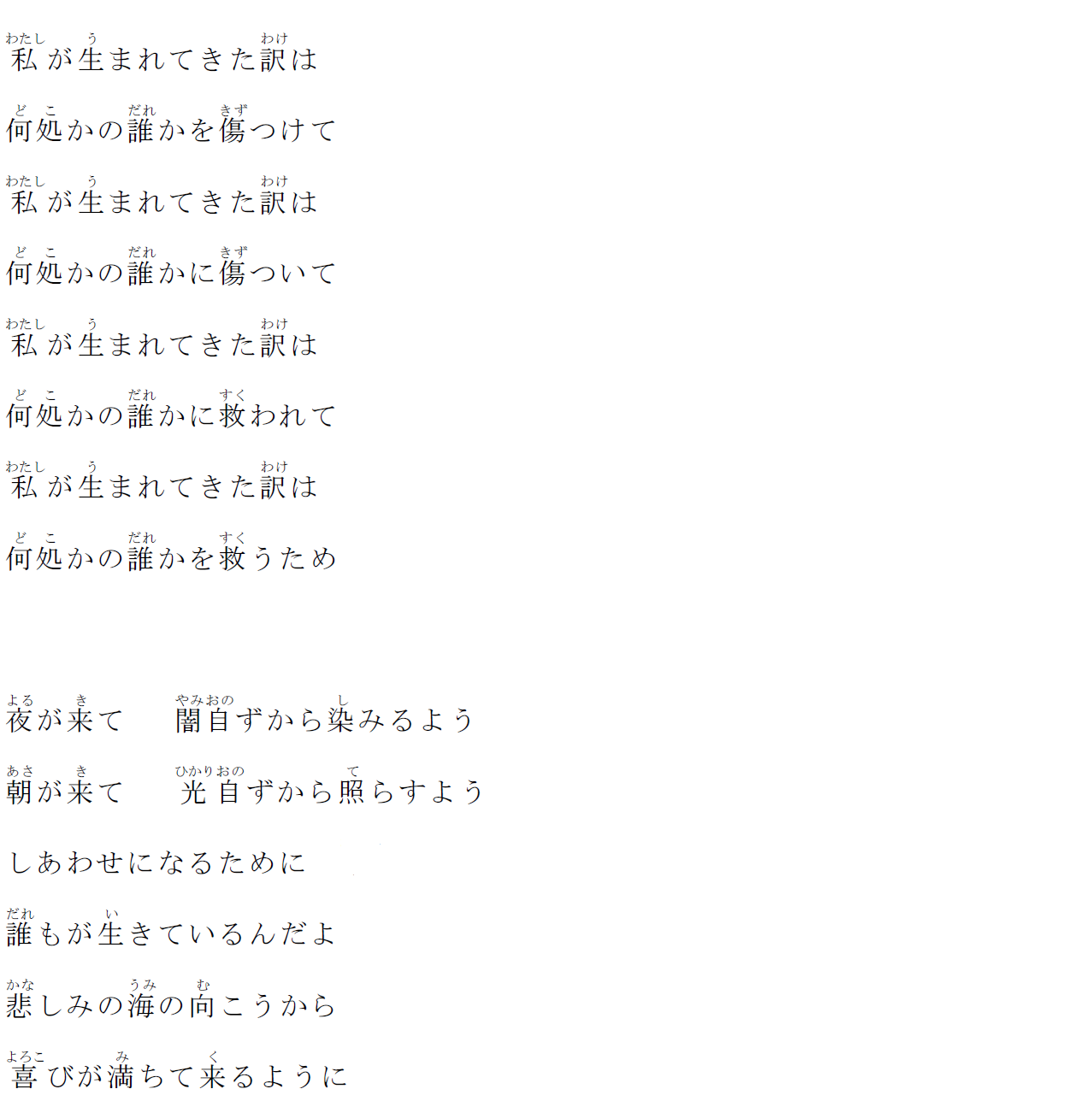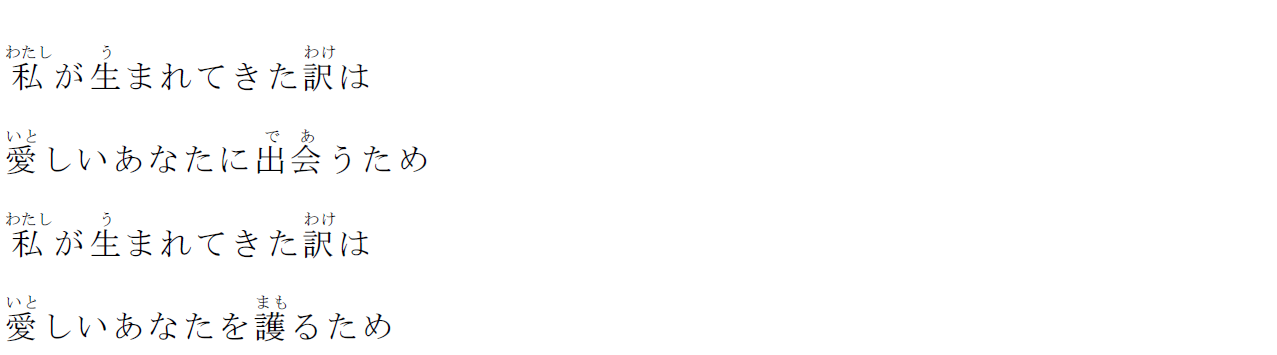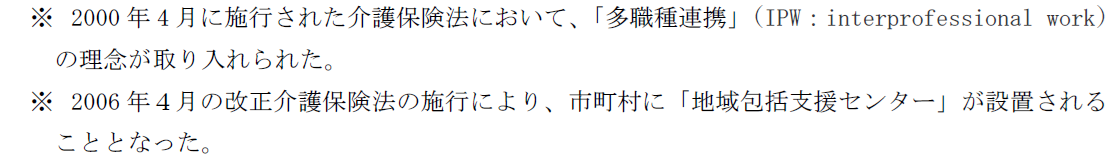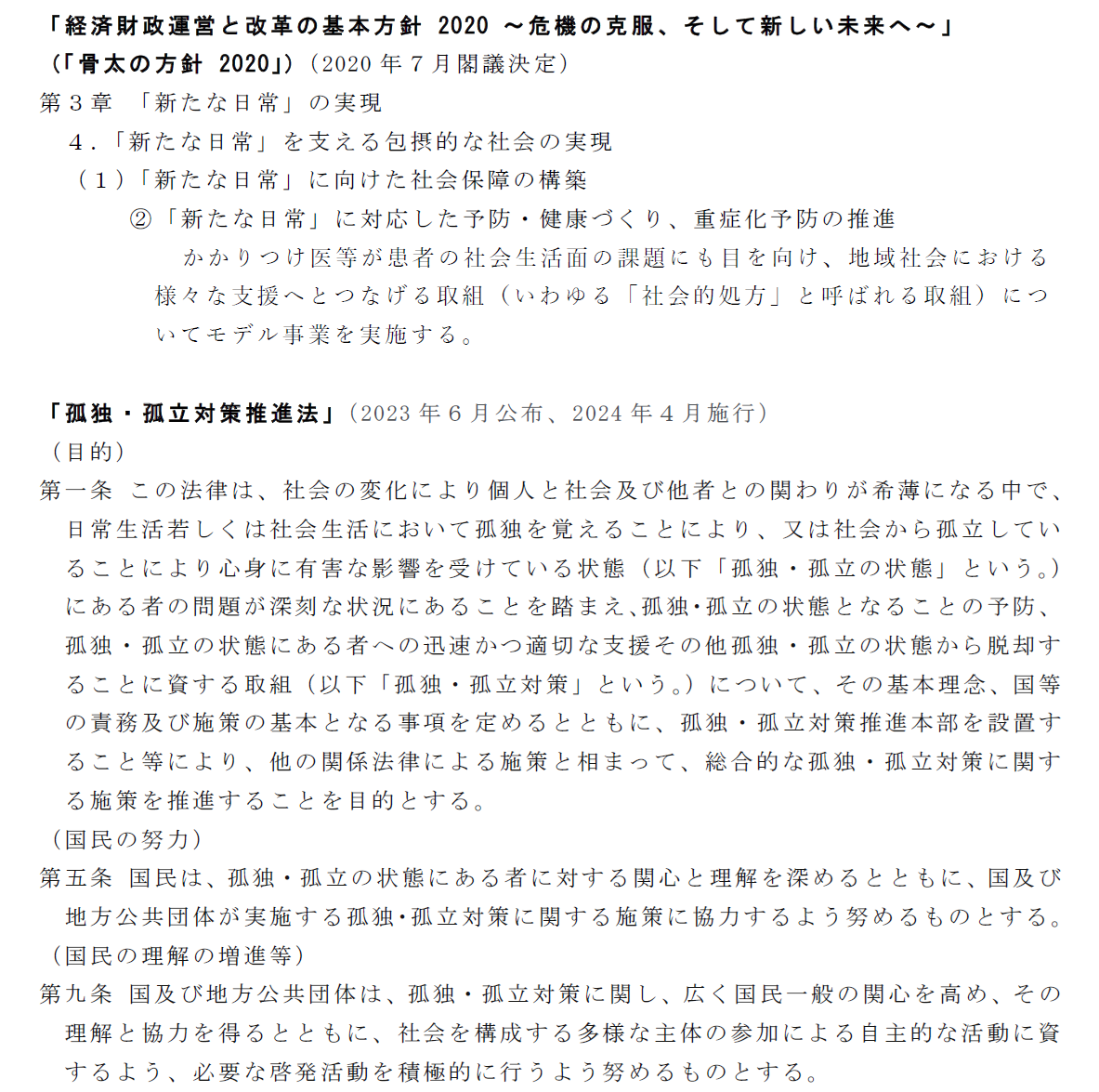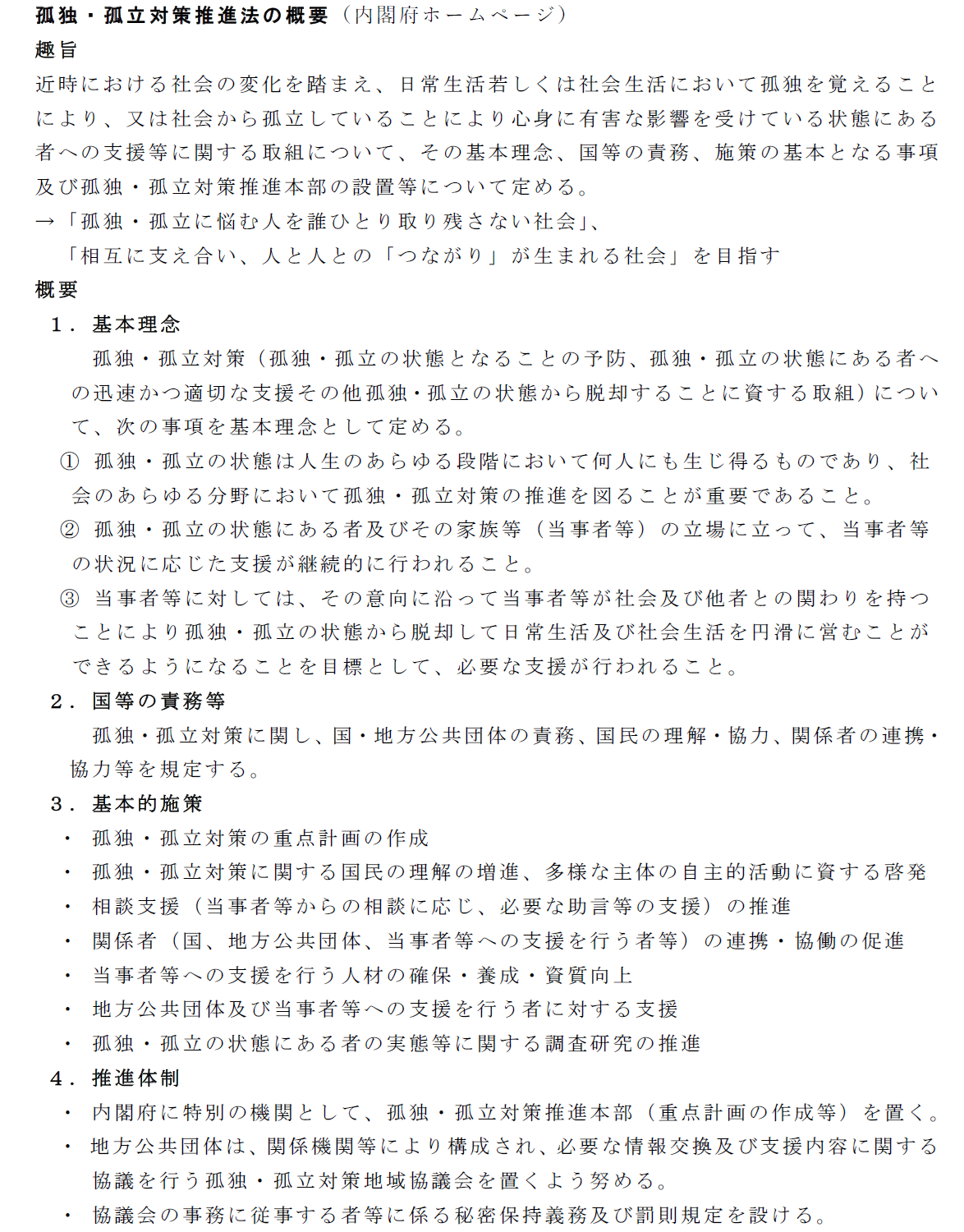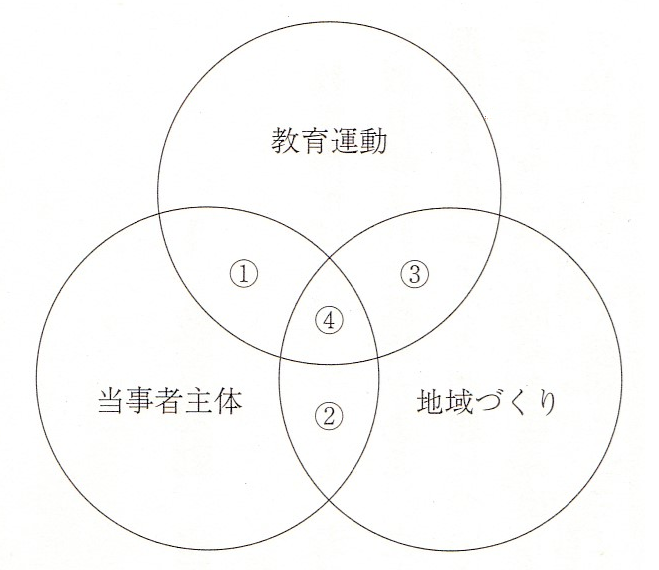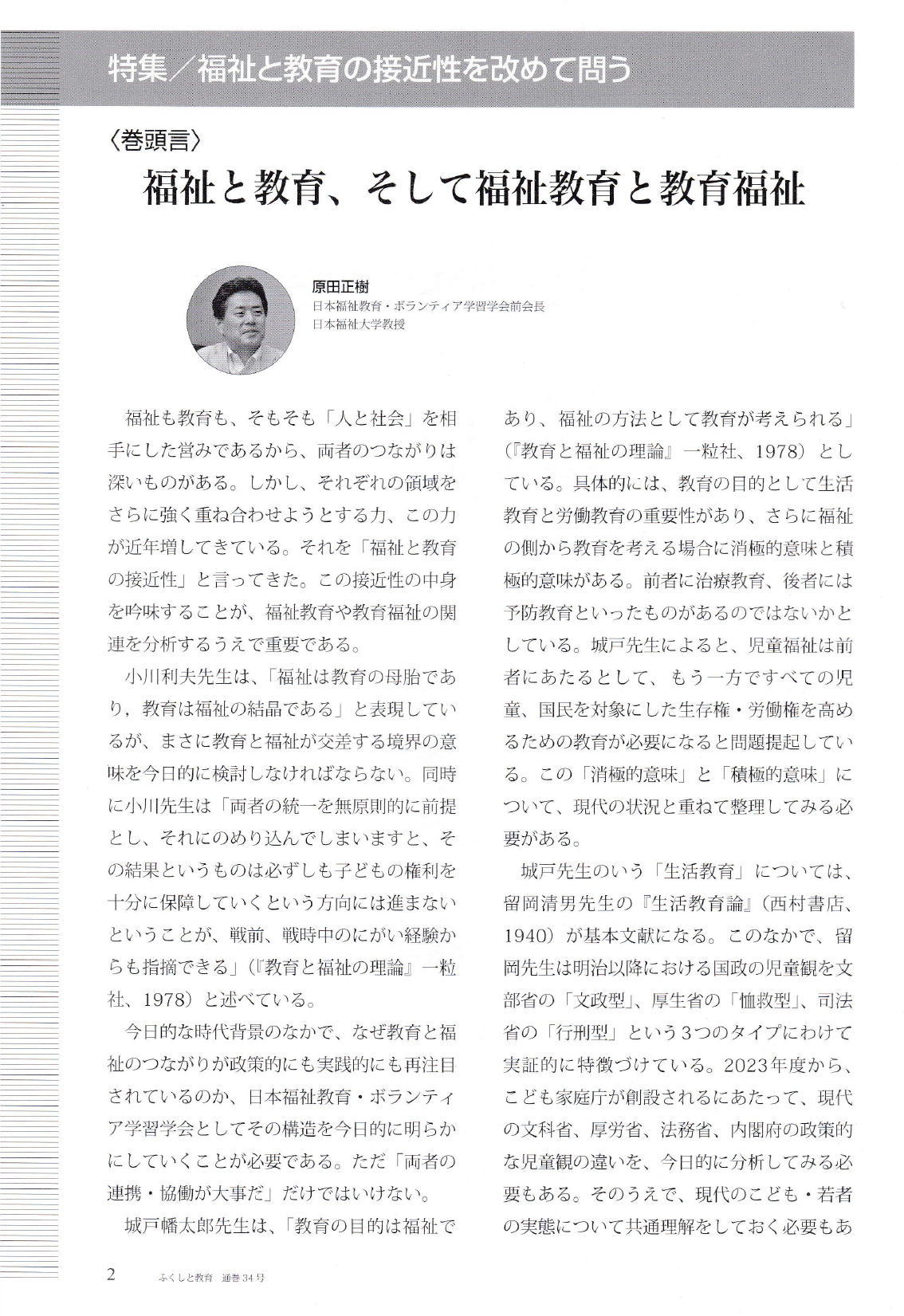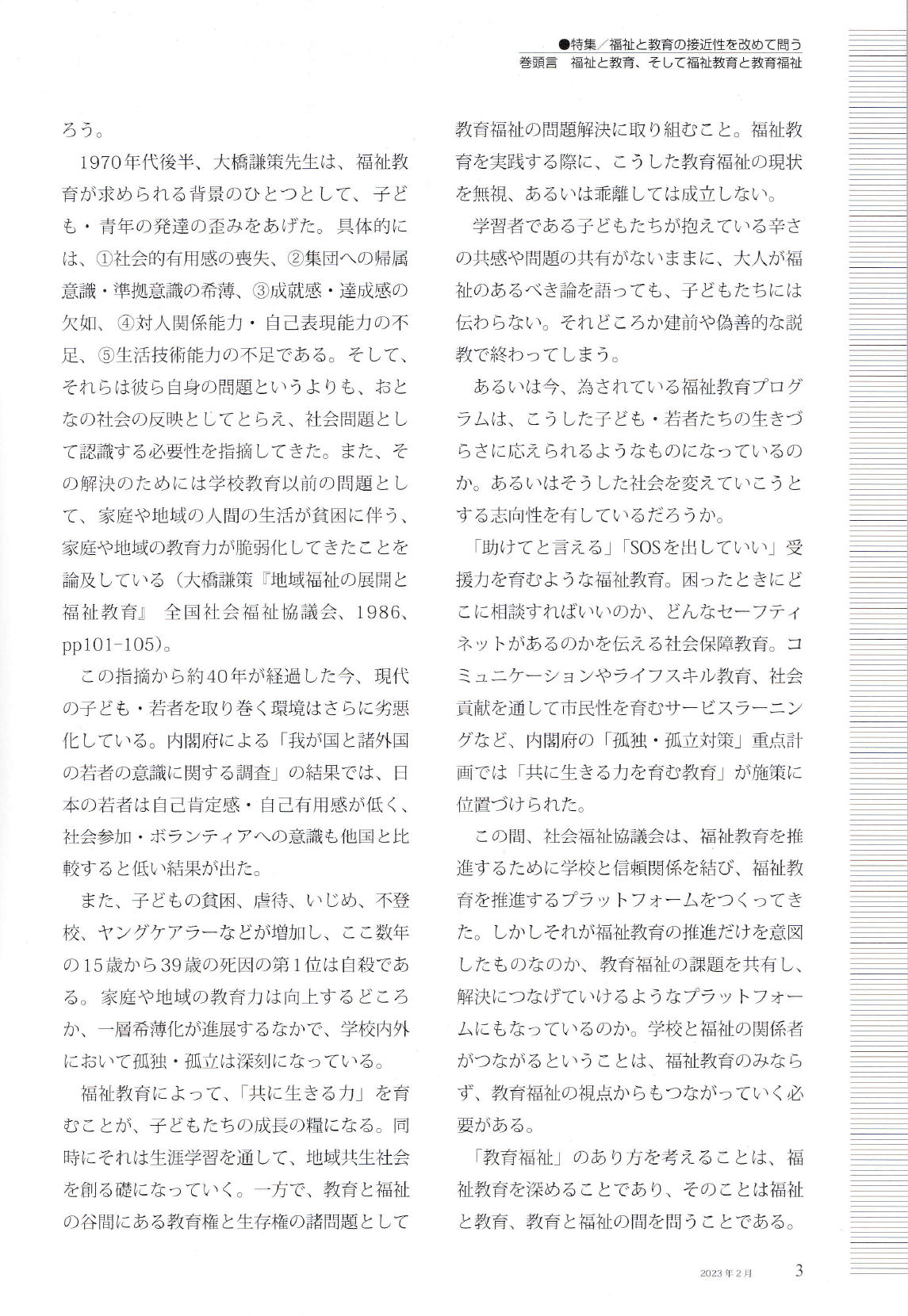〇筆者(阪野)の手もとに、小澤デシルバ慈子著、吉川純子訳『孤独社会―現代日本の<つながり>と<孤立>の人類学―』(青土社、2024年9月。以下[1])という本がある。
〇小澤(アメリカ在住の医療人類学・心理人類学者)にあっては、「孤独」(Loneliness)とは、「一人で『いる』ことではなく、独りぼっちだと『感じる』こと」(39ページ)である。また、孤独は、個人の問題ではなく、社会の問題であり、現代の日本社会は「孤独な社会先進国」(10ページ)である。その「孤独な社会」(Lonely Society)とは、①その社会にいるたくさんの人が孤独を感じている社会、②その社会にいる人々が自分は重要でなく価値がない存在だと思わせられてしまう社会、③その社会またはコミュニティ自体が孤立していて、他の社会とのつながりがない、もしくは見捨てられている、無視されている、過小評価されている、権利をはく奪されているなどと感じてしまう社会、をいう(9~10、23ページ)。
〇こうした認識や理解に基づいて小澤は、[1]で、自殺サイトや大学生のインタビュー、東日本大震災の被災者の声などを通して、社会的な問題である孤独すなわち日本の孤独社会について分析し、個人的・社会的レベルでのいくつかの「対処法」を提案する。
〇そこで小澤は、手始めに、「孤独についての誤解」を指摘する。①孤独は、社会の新しい(心理的な)問題である。②孤独はうつ病の一種、または隠れうつ病の一症状である。③孤独とは、一人でいることである。④孤独は、主に高齢者の問題である、がそれである。
〇これらの誤解に対して小澤は、次のように説述する。①に対して、孤独は社会的な現実の一面というだけでなく、生物学的、進化論的な現実の一面でもあり、人間のなかにかなり古くからある真に生物心理社会的(bio-psychosocial)なものが関係している。②に対して、うつ病は漠然とした悲しみや絶望、落胆という感情であるのに対し、孤独は、親密な、あるいは意味のある関係やつながりのなさ、居場所のなさを感じたり認識したりすることから来る社会的苦痛の感情を伴う。③に対して、孤独とは、社会的に孤立していることを認識し、実感する感情的、主観的な現実(経験)である。孤立は一人でいることだが、孤独とはひとりぼっちだと感じることである。④に対して、高齢者にとって社会的孤立が深刻な問題であることはよく知られている事実だが、孤独が主に高齢者だけの問題であることを示すエビデンスはほとんどない、という(28~33ページ)。
〇そのうえで小澤は、孤独に関する研究文献からいくつかの定義を紹介し、そこから着想を得て、孤独を「他者や環境との関係において生じるさまざまな不満を感じること」(35ページ)と定義する。この定義では、孤独は、相互の “ 関わり合い ” や “ 絆 ”、そしてある “ 世界の共有 ” という「関係」性(つながり)において、自分が帰属していると感じられる、自分の居場所だと感じられる社会的かつ物理的な場所がないことをいう。また、孤独は、永続的ではなく、常に変化している状態であり、その形態や現れ方は「さまざま」に存在する。しかも、孤独は、一個人の心理的な作用で形成されるだけでなく、社会的・文化的・政治的な「不満」を「感じる」ことによっても形成されるのである(35~37ページ)。
〇すなわち、この定義によると、孤独は実際に社会的・物理的に孤立していることだけではなく、社会的・物理的に孤立しているという認知の仕方や感じ方にもよるのである。それは、個人やコミュニティ、あるいは社会全体の客観的な状況が変わらなくても、孤独についての認識や受け止め方、感じ方を変えることによって孤独に対処することができることを意味する(294ページ)。
〇そこで、小澤は[1]の “ 結び ” として、「個人のレベルと社会のレベルで孤独に対処するために役立つと思われる5つの提案」を行う。それをメモっておく(296~300ページ)。
(1) 孤独を受け入れる
孤独は人生においてたびたび起こる一時的な状態である。そう考えれば、それが過ぎ去るまで辛抱強く待つことができるようになる。孤独を受け入れるという実践は、むしろ自分の孤独を和らげる重要なステップになるかもしれないし、孤独に対するレジリエンス(回復力、しなやかさ)を身につけるにあたって重要なポイントなる。
(2)他者を受け入れる
孤独な人たちは、拒絶されることを恐れるあまり他者と進んで関わろうとする意欲が削(そ)がれるかもしれない。しかし、孤独は人生において誰もが共通に持つ人間らしさの一部であり、現実の人間生活において身体のサバイバル(生き延びること)を脅かす(生死に関わる)ものとはならない。その点をじっくりと考えるなかで他者を受け入れることによって、社会的拒絶に対する恐怖を和らげることができる。
(3)自分自身を受け入れる
自尊心や自己肯定感は、他者との関係に大きく左右される。一人ひとりが自分自身の内在的な価値を確信し、いかなる失敗も、実績の無さも、生産性の無さも自分の価値を無に帰してしまうことはありえないという事実を確信し、自尊心や自己肯定感を育むことが重要である。
(4)自分の居場所を見つける
孤独を体験しているとき、多くの人は自分にははっきりした生きがいがないと感じている。そういう人に生きがいを見出すよう提案するよりは、まず居場所を見つける方が容易である。人は孤独を感じていても、同じような感情や体験を持つ他者を見つけることができれば、居場所を見つけたり、創り始めることができる。
(5) 受容するシステムの構築
上記の4つの対処法は、すべて個人もコミュニティも行うことができるものではあるが、それらが最も効果的に機能するためには、社会的、文化的な制度によって支援されることが必要である。その制度は、①から④について認識し、それに基づいて対処し、支援しているかが問われる。
〇そして、小澤はいう。
ここで述べた5つの提案は教育制度に組み込まれることで最も効果的なものになるかもしれない。孤独が普遍的に存在すること、その孤独にどう対処するか、違いがあっても他者を受け入れることや烙印を押して蔑視しないことの大切さ、絆の形成と共感を培うことの大切さ、そして、子どもたち一人ひとりに内在的な価値があるということは、小学生にも教えることができる。実際、ますます多くの社会的、感情的学習プログラムが、まさにこういうことを行おうとしている。長期的には、これらのプログラムが日本における孤独の蔓延に対処するに当たって非常に有意義な役割を果たすことができるものと考えている。(300ページ)
〇小澤のこの主張を別言すればこうであろう。「孤独を直に癒す薬」は、「お互いを尊重すること、共感すること、思いやりを持つこと」によって「人と人とのつながりを育み、それを価値あるものとして認めることである」(25ページ)。「孤独に対処するために最も適切なのは、関係の中での生きる意味、そして生きがいである」(26ページ)。「生きがいを感じ、それによって生きる意味を持つことの重要な源泉は、自分の存在価値を認め、自分が他者にとって意味のある人間だと感じ、必要不可欠な存在である」と認識することである(173、274ページ)。そこに求められるのが、人との関係性によって形成される「居場所」(「要(い)場所」)であり、社会的・制度的な営みである「教育」である。そしてそれは、「市民権」(市民性)を国家との関係だけでなく社会の仲間との関係として位置づけ(300ページ)、その意識の育成を図ることによって、人間関係の希薄化が進む地域社会においてその課題解決を促すことになる。
〇筆者の手もとには、「孤独」について解明する本がもう一冊ある。ヴィヴェック・H・マーシー著、樋口武志訳『孤独の本質 つながりの力―見過ごされてきた「健康課題」を解き明かす―』(英治出版、2023年11月。以下[2])がそれである。
〇マーシー(医師、第19代アメリカ公衆衛生局長官)は[2]で、「人と人のつながりの大切さ、孤独が健康に与える隠れた影響、そしてコミュニティが持つ力」(3ページ)について説く。そして、「孤独と社会的つながり」についていう。「依存症や暴力、職場や学校での意欲の低下、政治的分極化など、私たちが社会で直面している問題の実に多くが、孤独やつながりの欠如によって悪化する。よりつながり合った世界にすることは、こうした問題や、現在私たちが個人または社会として抱えている他の多くの問題を解決するためのガキとなる」(27ページ)。「人間同士のつながりが強まると、私たちはより健康になり、レジリエンス(回復力)が高まり、生産性が向上し、より活き活きとした創造が可能になり、充実感も高まっていく」(30ページ)。その際、マーシーにあっては、「孤独」(loneliness)とは、「自分が欲する社会とのつながりが欠けている」という「主観的な感情」(40ページ)をいう。それに対して「孤立」(isolation)とは、「客観的・物理的にひとりきりで周りとの交信がない状態」(41ページ)を指す。一方で「単独」(solitude)とは、「心穏やかにひとりでいる状態や、みずから進んで周りから離れている状態」(42ページ)を指す。
〇[1]において注目したい論点や言説に、「孤独に対する4つの戦略」、「孤独の3つの領域」、「交友関係の3つのサークル」などがある。本稿では、その要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部見出しは筆者)。
孤独に対する4つの戦略
孤独に対処し、社会的なつながりを強化することによって、コミュニティを強固なものにし、社会を癒やしていくことができる。(6~7ページ)
(1)毎日、愛する人と時間を過ごそう。
自分にとって不可欠な人たちと毎日、少なくとも15分は、声を聞いたり顔を見たりして、つながり(交流)の時間を割こう。
(2)お互い、目の前の相手に集中しよう。
人と接するときは、気が散るものを排除するようにして、相手に全神経を注ぎ、可能であれば心から耳を傾けよう。
(3)ひとりの状態を受け入れよう。
他者とのより強いつながりを築くための第一歩として、自己認識や理解を深め、自分自身とのつながりを強めよう。
(4)助け、助けられる相互扶助を図ろう。
奉仕(サービス、支援)は人のつながりの一形態であり、与えること、受け取ることの相互扶助によって社会的な絆を強めよう。
孤独の3つの領域
研究者たちは、孤独を感じる場合にどのようなタイプの関係が欠けているのか分析する過程で、孤独には「3つの領域」があることを明らかにしてきた。これら3つの領域が満たされることで、活き活きと生きるために必要な質の高い社会的なつながりが生じる。どれかが欠けると孤独を感じる可能性がある。(40~41ページ)
(1)親密圏の孤独(感情的孤独)
愛と信頼の絆で深く結ばれた親友や親しいパートナーを欲している状態を指す。
(2)関係圏の孤独(社会的孤独)
良質な交友関係や社会的なつながりとサポートを求めている状態を指す。
(3)集団圏の孤独
目的意識や関心を分かち合える人的ネットワークやコミュニティに飢えている状態を指す。
交友関係の3つのサークル
ロビン・ダンバー(イギリスの進化心理学者)によると、人間の交友関係(つながり)は、「インナーサークル(内円)」「ミドルサークル(中間円)」「アウターサークル(外円)」の3つのレベルに分類される。これは、孤独の3つのレベル(親密圏、関係圏、集団圏)と大まかに対応している。これらのサークル(への帰属や帰属意識)は、互いに関連し合い、補完し合い、人生の質や人間としての経験を豊かにしてくれる。(323~335ページ)
(1)インナーサークル(内円)
人は誰しも、互いへの愛と信頼を持って深くつながった親しい友人や相談相手を必要としている。このサークルの人間関係は相互の絆が最も強く、親密であり、最も時間とエネルギーを必要とするものである。
(2)ミドルサークル(中間円)
人はときどき会う人で、支援やつながりをともにするカジュアルな(気楽で堅苦しくない)人間関係や社会関係も必要としている。このサークルに属する人たちは、深い秘密まで分かち合うことはないかもしれないが、関係圏における孤独を防ぐクッションとなる。
(3)アウターサークル(外円)
人は職場の仲間や知人など、集団的な目的やアイデンティティを体感する場所(コミュニティ)に属する必要がある。こうしたサークルに属する人々と目的意識や関心を分かち合っているという感覚は、集団圏における孤独を回避する助けになる。
〇[2]におけるマーシーからのひとつのメッセージはこうである。「孤独を乗り越え、よりつながりのある未来を築くことは、私たちがともに取り組むことができ、ともに取り組まねばならない喫緊の任務である」(31ページ)。「強い人間関係は私たちの健康を向上させ、パフォーマンスを高め、意見や主義の違いを乗り越え、力を合わせて大きな難題に社会として取り組んでいくことを可能にする。人とのつながりこそが基盤であり、その他すべてのものはその上に築かれる」(413ページ)。「人とのつながりが強ければ強いほど、私たちの文化は豊かになり、社会もより強固になる」(71ページ)。そしてマーシーは私たちに問いかける。「人のための時間を作ろうとしているか? 本当の自分を見せているか? 人をつなぐ奉仕の力を認識し、思いやりを持って人と接しようとしているだろうか?」(413ページ)。これは上記の孤独に対する「戦略」に通底する。例によって唐突ではあるが、“ 結び ” にかえておくことにする。