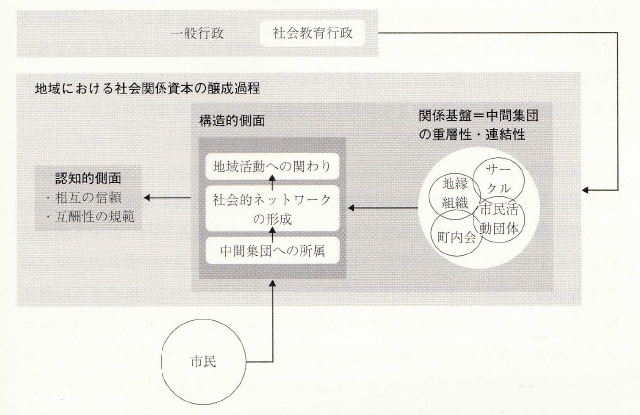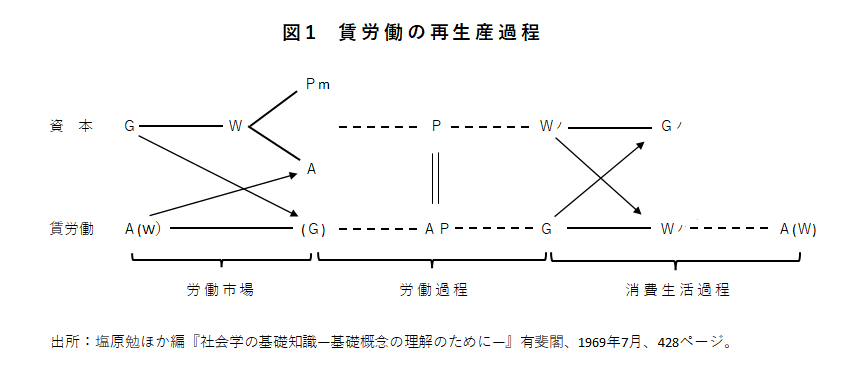〇筆者(阪野)の手もとに、伊藤亜紗(編)・中島岳志・若松英輔・國分功一郎・磯崎憲一郎著『「利他」とは何か』(集英社新書、2021年3月。以下[1])という本がある。伊藤は美学者、中島は政治学者、若松は批評家・随筆家、國分は哲学者、そして磯崎は小説家である。分野も背景も異なるこの5名の研究者が、東京工業大学の「未来の人類研究センター」(2020年2月設立)のメンバーとして取り組んでいるのが、「利他」をめぐる問題である。[1]は、「全員ではぐくんできた利他をめぐる思考の、5通りの変奏」であり、いまだその「出発点であり、思考の『種』にすぎない」という(8ページ)。
〇[1]におけるひとつのキーワードは、「うつわ」――「うつわになること」「『うつわ』的利他」である。伊藤は次のようにいう。
利他とは「うつわ」のようなものではないか。相手のために何かをしているときであっても、自分で立てた計画に固執せず、常に相手が入り込めるような余白を持っていること。それは同時に、自分が変わる可能性としての余白でもある。この何もない余白が利他であるとするならば、それはまさにさまざまな料理や品物をうけとめ、その可能性を引き出すうつわのようである。(58ページ。語尾変換)
〇人間は「うつわ」のような存在として生きることによって、「利他」が宿る。こうした人間観を生み出す伊藤の言説は、こうである。利他的な行動には本質的に、「これをしてあげたら相手にとって利になるだろう」という、「私の思い」が含まれている。その「私の思い」は私の思い込みでしかなく、「自分の(利他的な)行為の結果はコントロールできない」、すなわち見返りは期待できない(「利他の不確実性」)。自分の利他的な行為は、相手は「喜ぶはずだ」「喜ぶべきだ」という押しつけが始まるとき、人は利他を自己犠牲と捉えており、その見返りを相手に求めていることになる。その点において、利他的な「思い」や「行為」は、相手をコントロールしたり、支配することにつながる危険をはらんでいる。そうならないためには、相手を「信頼」してその自律性を尊重し、相手の言葉や反応を「聞く」ことを通じて相手の潜在的な可能性を引き出すこと、すなわち相手の力を信じることが必要不可欠となる。それは、「こちらには見えていない部分がこの人にはあるんだ」という距離と敬意を持って、相手を気づかうこと(「ケア」)である。この他者への気づかい、すなわち「ケアとしての利他」は、相手の隠れた可能性を引き出すこと(「他者の発見」)になり、それは同時に自分が変わること(「自分の変化」)になる。そのためには、こちらから善意を押しつけるのではなく、相手を信頼し、利他の結果の可能性や意外性を受け入れる、うつわのような「余白」を持つことが必要となる。この自由な余白、スペースは、とくに複数の人が「ともにいる」ことをかなえる場面で重要な意味を持つ(50~56、59ページ)。
〇筆者の手もとに、中島岳志著『思いがけず利他』(ミシマ社、2021年10月。以下[2])という本がある。中島は[1]の著者のひとりである。[2]において中島は、「利他の本質に『思いがけなさ』ということがある。利他は人間の意思を超えたものとして存在している」(6ページ)と説く。具体的にはこうである。「利他は自己を超えた力の働きによって動き出す(「縁起による業」:私はさまざまな縁によって(縁起的現象として)存在している)。利他はオートマティカルなもの(意思を超えたもの)。利他はやって来るもの(利他の与格性)。利他は受け手によって起動する(利他は事後的)。そして、利他の根底には偶然性の問題がある(利他の偶然性)」(174ページ。括弧内は筆者)。
〇[2]のうちから、中島の言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
「共感」が利他的行為の条件となったとき、「別の規範」が起動し「共感される人間」になることが求められる
通常、利他的行為の源泉は、「共感」にあると思われている。/他者への共感、そして贈与(利他)。この両者のつながりは非常に重要である。(21ページ)/しかし、共感が利他的行為の条件となったとき、例えば重い障害のある人たちのような日常的に他者からの援助・ケアが必要な人は、「共感されるような人間でなければ、助けてもらえない」といった思いに駆(か)られる。/他者に自分の苦境を伝えることが苦手な人、笑顔を作ることが苦手な人、人付き合いが苦手な人。人間は多様で、複雑である。だから「共感」を得るための言動を強(し)いられると、そのことがプレッシャーとなり、精神的に苦しくなる人は大勢いる。/そもそも「共感される人間」にならなければならないとしたら、自分の思いや感情、個性を抑制しなければならない場面が多く出てくる。(22ページ)/「共感」されるために我慢を続ける。自分の思いを押し殺し続ける。むりやり笑顔を作る。そうしないと助けてもらえない。そんな状況に追い込むことが「利他」の影で起きているとすれば、問題は深刻である。(23ページ)/さらに、「より深い共感」を利他の条件にしてしまうと、今度は自分の思っていることや感情を露わにしなければならないという「別の規範」が起動してしまう。そうすると、「自分をさらけ出さないと助けてもらえない」という新たな恐怖が湧き起こってくる。(24ページ)
利他の主体はどこまでも受け手側にあり、その意味において私たちは利他的なことを行うことはできないのである
特定の行為が利他的になるか否かは、事後的にしかわからない。いくら相手のことを思ってやったことでも、それが相手にとって「利他的」であるかはわからない。与え手が「利他」だと思った行為であっても、受け手にとってネガティブな行為であれば、それは「利他」とは言えない。むしろ、暴力的なことになる可能性もある。いわゆる「ありがた迷惑」というものである。/つまり、「利他」は与えられたときに発生するのではなく、それが受け取られたときにこそ発生するのである。自分の行為の結果は、所有できない。あらゆる未来は不確実である。そのため、「与え手」の側は、その行為が利他的であるか否かを決定することができない。あくまでも、その行為が「利他的なもの」として受け取られたときにこそ、「利他」が生まれるのである。(122ページ)/受け手が相手の行為を「利他」として認識するのは、その言葉(や行為など)のありがたさに気づいたときであり、発信と受信の間には長いタイムラグがある。(128ページ)/つまり、発信者にとって、利他は未来からやって来るものである。また、発信者を利他の主体にするのは、どこまでも、受け手の側であるということである。この意味において、私たちは利他的なことを行うことができないのである。/発信者にとって、利他は未来からやって来るものであり、受信者にとっては、「あのときの一言」(や「あのときの行為」)のように、過去からやって来るもの。これが利他の時制である。(132ページ)
利他的になるためには「偶然の自覚」に基づいて器(うつわ)のような存在になり、与格的主体を取り戻すことが必要である
私という存在は、突然、根拠なく与えられたものである。あらゆる存在は、自己の意志によって誕生したのではなく、意志の外部の力によってもたらされたものである(与格的な存在)。ここに存在の被贈与性という原理がある。/そして、誕生以降も私という存在の奇跡は続く。今の私は、様々な偶然性の奇跡的な組み合わせによって成立している。私という個性は、単純な因果関係では説明できない天文学的な縁起によって構成されている。(150ページ)/この「私が私であることの偶然性」についての自覚が、「自分が現在の自分ではなかった可能性」「私がその人であった可能性」へと自己を開くことになる。(143ページ)/この「偶然の自覚」が他者への共感や寛容へとつながり、連帯意識を醸成し、「利他」が共有される土台を築くことになる。(143、145ページ)/ここで重要なのは、私たちが偶然を呼び込む器(うつわ)になることである。偶然そのものをコントロールすることはできない。しかし、偶然が宿る器になることは可能である。(176ページ)/そして、この器にやって来るものが「利他」である。器に盛られた不定形の「利他」は、いずれ誰かの手に取られる。その受け手の潜在的な力が引き出されたとき、「利他」は姿を現し、起動し始める。/このような世界観のなかに生きることが、「利他」なのである。/だから、利他的であろうとして、特別のことを行う必要はない。毎日を精一杯生きることである。私に与えられた時間を丁寧に生き、自分が自分の場所で為(な)すべきことを為す。能力の過信を諫(いさ)め、自己を超えた力に謙虚になる。その静かな繰り返しが、自分という器を形成し、利他の種を呼び込むことになるのである。(177ページ)
〇筆者の手もとに、若松英輔著『はじめての利他学』(NHK出版、2022年5月。以下[3])という本がある。若松も[1]の著者のひとりである。若松はいう。人と人との「つながり」が問われている今日、「私たちがもう一度、他者とともに生きるために『つながり』を持続的に深めるには何が必要か。この問題を解く鍵語(キーワード)として考えてみたいのが『利他』である」(6ページ)。そして若松は、[3]において、日本仏教の視座から最澄や空海、儒教のそれから孔子や孟子、西洋哲学からフランスのオーギュスト・コント(1798年~1857年)やアラン(本名:エミール=オーギュスト・シャルティエ、1868年~1951年)らの「利他」の思想を取りあげる。とともに、「利他を生きた人たち」として吉田松陰や西郷隆盛、二宮尊徳、中江藤樹らの「利他」の哲学を紹介し、論述する。そのうえで若松は、ドイツの心理学者・哲学者であったエーリッヒ・フロム(1900年~1980年)の『愛するということ』(1956年)を読み解き、「自分を愛すること」、すなわち「自分を深く信頼すること」が「利他」につながる、と主張する。次の一節が若松の結論である。
自分で自分のことを愛することができれば、その人は自分を固有なものにできる。そして、そのうえで誰かのことを愛することができれば、その人は他人のことを固有な存在として認めることができる。自分自身が固有であると知ることは、他者が固有であると知ることである。それはすなわち自他ともに等しい存在であることを経験するということでもある。/愛を通して利他を考えるとき、私たちは愛の前で等しくなければならない。Aさんのことは愛せて、Bさんのことは愛せないのであれば、それは利他がうまく働いている状態とはいえないのである。/利他には等しさが必要である。そして、そのためにはまず、他者を愛するように、自分を愛し、信じることが大切なのである。/(人は唯一無二の存在であることを認め、自他を愛するという)真の意味の「愛」があるとき、そこに在るものはすべて等しくなる。ただ人間であるというそのことにおいて、等しく貴い存在になる、のである。(118~119ページ。語尾変換)
〇前述の[1]で伊藤は、障がい者へのインタビューを通じて、こう語る。晴眼者が視覚障がい者に先回りしてことこまかに道案内をするとき、それはしばしば「善意の押しつけ」になってしまう。それは、視覚障がい者にとっては、「障がい者を演じること」が求められることになり、自分の聴覚や触覚を使って自分なりに世界を感じることができなくなってしまう。それはまた、障がい者が「健常者の思う『正義』を実行するための道具にさせられてしまう」(47ページ)ことになる。さらに伊藤は、認知症当事者の言として、こういう。認知症の当事者がイライラし怒りっぽいのは、支援や援助を求めていないのに周りの人が助けすぎるからではないか(46~48ページ)。福祉教育の実践・研究において、深く留意したい点である。
〇なお、筆者はしばしば、とりわけ福祉教育実践をめぐって「思いやり」と「思い違い」「思い上がり」はときとして紙一重(かみひとえ)であり表裏一体である、と語ってきた。ここで改めて強く認識したい。
〇加えて、次のことを付言しておきたい。人間は日常生活や社会生活を営むうえで何らかの支援や援助を受けるに際して、「たすけられ上手・たすけ上手に生きる」ことが問われることがある。その際の「たすけられ上手」とは、 甘え上手や集(たか)り上手ではないのは当然のことながら、社会(世間、財界)や支援者・援助者が期待し求める「たすけられ上手を演じる(あるいは演じさせられる)こと」(演じるさまや人)であってもならない。