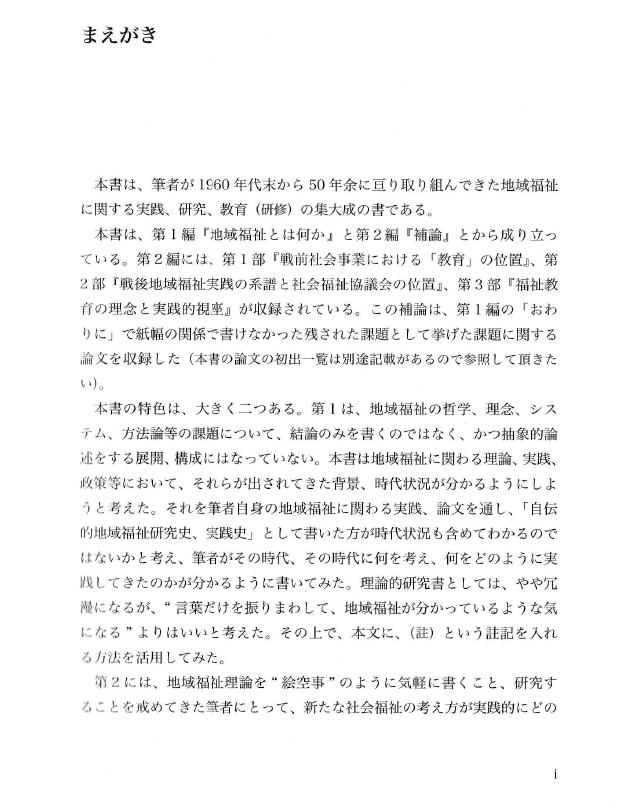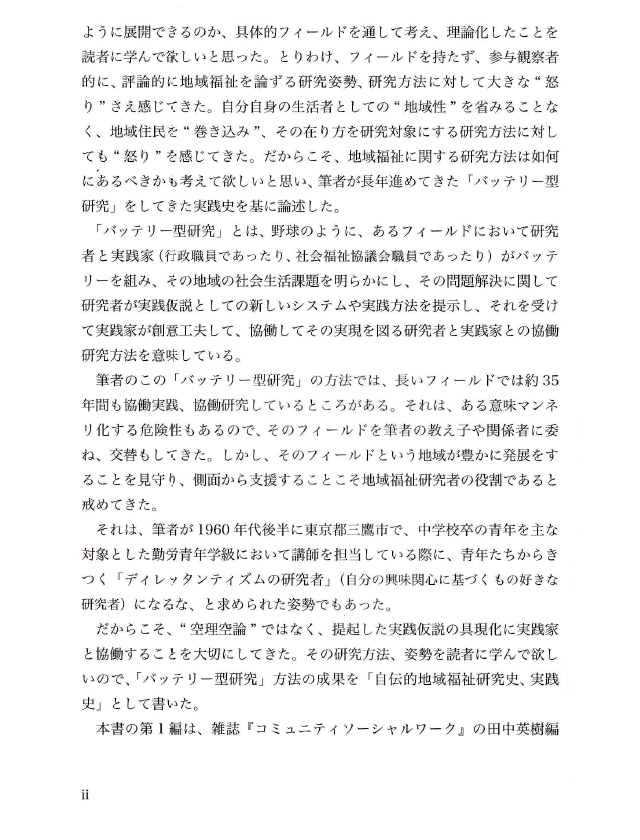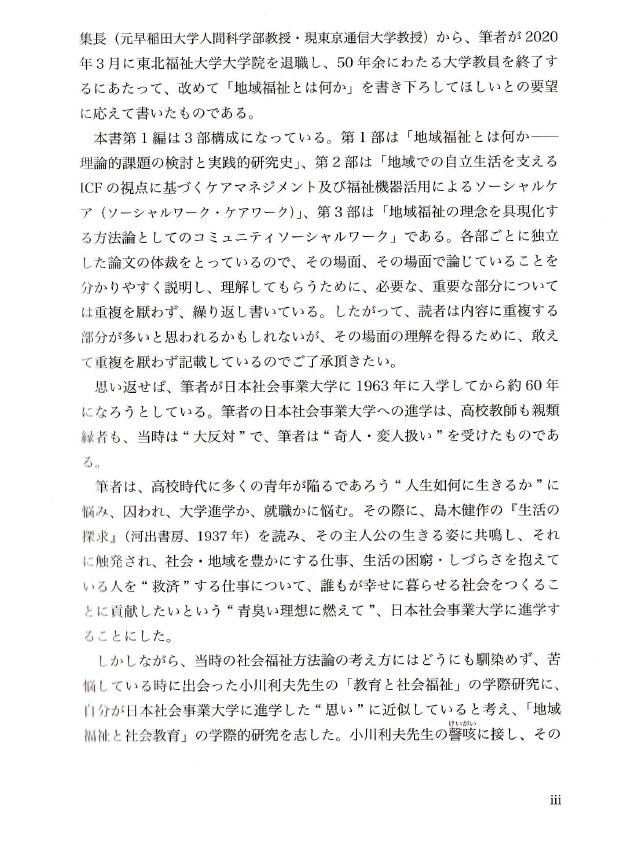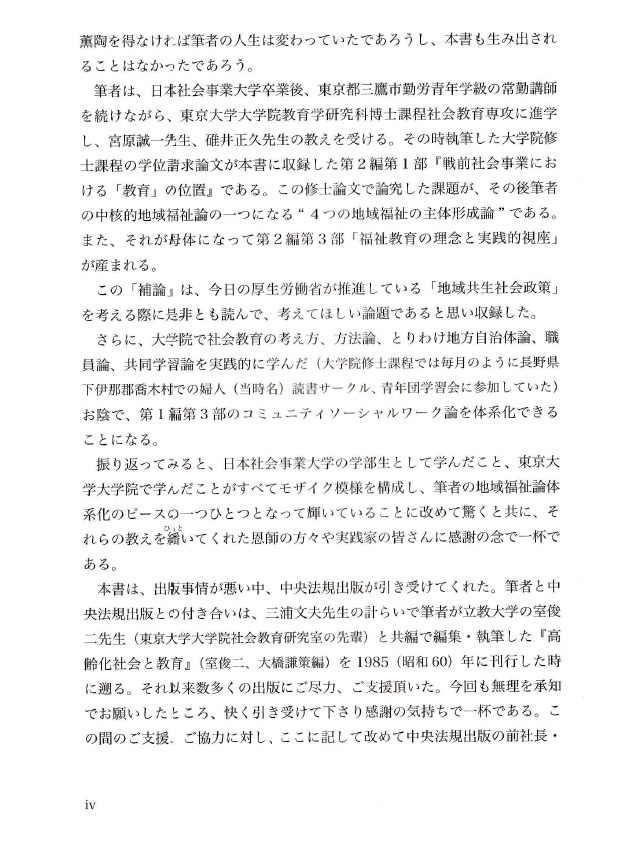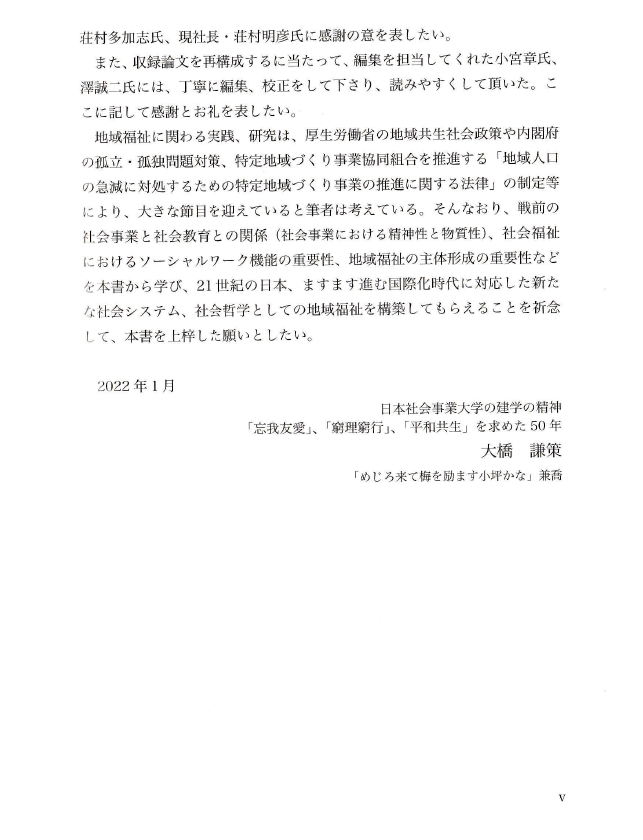「老爺心お節介情報」第40号
皆さんお変わりありませんか。
「老爺心お節介情報」第40号を送ります。
今号はやや私的な事情の述懐が含まれていますがお許し下さい。
2023年2月3日 大橋 謙策
< 立 春 >
< メジロ来て梅を励ます小坪かな >
〇この句は、季語が実質的に2つあり、俳句の関係者には受け入れられない句かも知れないが、私が好きな句の一つである。
〇毎年、我が家の小坪に、メジロが来て、庭の梅の木にとまり、蕾をくちばしで突いている情景を謳ったものである。私の書斎から見えるメジロの愛くるしい姿はまさに“絵になる”情景で何とも心が洗われる思いがする。春の到来を予感させる情景である。
〇私の大学教員50周年を記念した『地域福祉とは何か』に、この句を入れたのも、俳句の出来悪しはしょうがないとして、私の心にぴったりする句で気に入っている。
Ⅰ 異なる国の文化・生活慣習と多文化理解――『6ヶ国転校生・ナージャの発見』
〇私が、国によって文化や言語が違い、その結果として「ものの見方、考え方」が違うことに関心を持つようになったのは、何歳の頃か定かでない。ただし、笠信太郎の『ものの見方・考え方』を読んで、非常に興味をそそられたことは覚えている。
〇そんなこともあり、以前の「老爺心お節介情報」にも書いたが、私は1960年代に社会福祉方法論としてのケースワークを習ったが、その内容が基底になる文化、言語の違いがあるにも関わらず、アメリカの“直輸入”的で、どうにも馴染めず、学習が進まなかった。
〇当時、“社会福祉と文化”との関係を極める必要があると考え、社会人類学や民俗学、文化論等の書物を読んだが、奥が深く、幅が広くとても自分には研究できないと考え、“文化・民俗学・社会人類学の視点からの社会福祉研究”を断念した思い出がある。しかしながら、その命題は、いつも私の心に、私の思考に引っかかる命題であった。
〇1990年代半ばに「村山談話」がだされ、日本が侵略した韓国、中国への私の贖罪感、こだわりも少し解消され、韓国への調査研究に出掛けられるようになった。その折に、韓国と日本の食文化、食事作法の違いに、改めて驚かされた。1970年代から、アメリカ、ヨーロッパに出掛けていたにも関わらず、その当時は食事マナーに気がとられていたのか、あまり注目していなかったが、韓国への旅行では食文化、食事作法をはじめとして様々な文化の違い、生活習慣の違いがあるにも関わらず、日本は“侵略”し、日本語を強制し、創氏改名まで強制した蛮行になんとも心が痛んだ。この“蛮行”をすべての日本人に理解してもらわないと、真の交流にはならないと思っている。
〇朝日新聞の1月9日の「天声人語」で紹介されていた『6ヵ国転校生・ナージャの発見』(集英社、2022年)を読んだ。学校の給食、テスト、体操での整列の仕方等、国々によってこんなにも違うのかと改めて驚いた。それは、現象、制度が違うだけでなく、そのことを通して何を獲得するのか、なにを学ぶのかまで左右する大きな違いがあることに驚かされた。国の違う学校の試験でも、「正答」を求めない試験もあるという。つまり、社会生活の中で、常に「正答」は一つではないことを考えさせる取組でもある。一つの価値基準が全てという画一的な思考法とは異なる取り組みである。
〇この本を読んで、多文化理解とは、その国の、その民族の生活様式、文化を理解するだけでなく、それらがもたらす思考方法の違いにも目を向けなければ、その理解は皮相的なものになることを教えられた。まさに“ものの見方、考え方”の違いを理解することが多文化理解なのではないかと教えられた。そこでは自分にとって“「ふつう」こそ個性だ”という記述はとても考えさせられる記述であった。、
〇以前悩んだ文化、社会人類学あるいは民俗学をきちんと学ばないと“生活に関わるソーシャルワーク”の理解は深まらないのではないかと改めて考えている。研究者生活を50年間もやってきて、いまさらながら、何をしてきたのだろうかという“自虐的自戒”に囚われる。
〇私は2005年に書いた「わが国におけるソーシャルワークの理論化を求めて」(相川書房『ソーシャルワーク研究』Vol31No1、2005年所収)において、中根千枝の社会構造研究において、日本をタテ社会と論じた枠組みを援用して、日本の社会福祉、ソーシャルワークの問題について論究した。そこでは、日本には実質的にソーシャルワーク実践、研究が1990年までなかったと主張している。
〇我々は、多文化理解、多様性等について、“分かっている気になっている”が、本当に分かっているのであろうか。『6ヵ国転校生・ナージャの発見』を読んで、改めて福祉教育の奥の深さ、難しさを思い知らされた。
〇この『6ヵ国転校生・ナージャの発見』は、福祉教育関係者、地域福祉関係者の必読文献と言っていい本である。
Ⅱ 健康診断とがん告知――“説明同意書”へのサインと3人の身元保証人の必要性?
〇現在、がんは国民の2人に1人がり患する病気であり、生存率も格段に良くなり、完治する病気にもなってきている。しかしながら、生活習慣病とは異なり、体のどこの部位に発症するのかも予測できないし、がん予防の対策も今一つはっきりしない。
〇私は、1987年3月の島根県邑南郡瑞穂町(現邑南町)への出張中、咳が酷く、風邪だろうと思い帰宅後の3月13日(金)に稲城市民病院珉を受診した。診療に当たった医師は、私の胸部レントゲン写真の他に3葉のレントゲン写真を並べ、私に私のレントゲン写真が示された3葉のレントゲン写真のどれと似ているかを質問した。3葉のレントゲン写真は肺がんのもの、肺結核のもの、肺炎のものの3葉であった。私は、自分の肺の写真の中に白い、丸い画像があったので、同じような写真を同じだと挙げた。医師は、その写真は肺がん患者の写真だと説明し、あなたは“肺がんである”と宣告し、慶應大学病院か国立がんセンターに行って、詳しい検査を受けるようにと言って、肺がんの診断書と共に紹介状をくれた。
〇風邪と思って受診した私に取って、肺がんの宣告は“晴天の霹靂”で、当時日本社会事業大学の移転業務を担っていた関係もあり、その足で、大学へ行き、相談して国立がんセンターへ検査入院することになった。
〇国立ガンセンターでの検査でも主治医は98%、肺がんだと思うが、国立ガンセンターは病理検査の結果がでないと確定診断はしないということで、セカンドオピニオンを求められ、肺結核専門の複十字病院と北里病院を紹介された。2つの病院とも肺がんの診断であった。
〇国立がんセンターの治療方針は,肺生検を行い、病理検査で確定させてから手術を行うという。病巣が右肺の上葉にあるが、内視鏡を使えないので、肺生検で病理検査を行うという。手術は右肺の肋骨3本を切除し、右肺上葉を切除するというものであった。
〇肺生検は肺の部分の局部麻酔なので、私自身の意識はあり、検査の際にモニターのブラウン管に映し出される自分の肺に針が刺され、血が滲んでいくのが見える。咳が続く中での肺生検は辛いものであった。2回行われた肺生検では病巣から組織をとることができなかった。にも拘わらず、4月17日に手術を行うということになり、術後の呼吸法の訓練が始まった。この呼吸法の訓練は辛く、いつも涙を流していた。
〇4月17日の前日、最後の検査としてレントゲンでの確認がおこなわれた。この時、レントゲンに映っていた肺の丸い、がんと思われる病巣の画像が少し変形したことに医師が気が付いてくれ、少し様子をみるということで、17日の手術は延期になった。その後、咳も止まり、退院したが、再度12月に同じような病巣の画像があらわれ、医師は手術をさせてほしいといったが、私は拒否した。その後のレントゲンではその病巣の画像は出ず、今日に至っている。
〇当時、がんは不治の病であり、生存率も低く、私はがん告知を扱った井上靖の本を始め、多くのガンについての本を読み、どう死に対応するのか、残す子どもたちの将来はどうなるのか、煩悶する日々であった。
〇他方、この“肺がん騒ぎ”の時は、丁度1987年に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法」の国会審議の最中で、私は日本社会事業学校連盟(現日本ソーシャルワーク学校連盟)の事務局長を仰せつかっていたこともあり、築地の国立がんセンターから永田町の自民党の本部などに駆け付け、請願活動をしたことも懐かしい思い出である。
〇このような経験もあり、私は健康診断や人間ドックにやや懐疑的になっていく。日本社会事業大学の専任教員の際は、法定の健康診断が求めれるが、私学共済事業団の人間ドックは受診しないようになっていく。“肺がん騒ぎ”の頃は、未だ子どもが小さいこともあり、人間ドックを利用していたが、子どもが成長してからは人間ドックを利用しなくなった。そんな折に読んだ近藤誠医師(昨年2022年に急逝、医学界の常識を覆すような論説をいくつもの本で提起)の影響もあったかもしれない。
〇日本社会事業大学退任後は、法定の健康診断も受けず、かつ自治体から送られてくる高齢者の健康診断も受けず、かかりつけ医で6か月に1回受ける血液検査で、自分自身の体調の変化を確認することにした。ヘモグロビン(Hb)A1c、γ―GTP、血糖値、コレステロール、クレアチニン等の検査項目をチェックしている。
〇2022年3月の定期血液検査の際、S先生の強い奨めもあり、20年ぶり位に前立腺がんの腫瘍マーカーであるPSAの検査項目を入れておこなった。その結果、普段の血液検査では、検査結果票を渡してくれるだけなのに、その時はかかりつけ医が診察室に私を呼び、PSAの数値が15.4なので、前立腺がんが疑われる(正常値はPSA数値が4以下)ので、紹介状を書くのですぐに受診してほしいとのことであった。稲城市立病院と日本医科大学多摩永山病院が提示され、どちらにするかという選択をせまるので、日本医科大学多摩永山病院をお願いし、紹介状を書いてもらった。
〇多摩永山病院では、ⅯRI検査、CTスキャナー、骨シンチ等の検査を行い、前立腺以外への転移がないことが確認された。前立腺への生検が1泊2日の入院でおこなわれ、グリソンスコアが8,がんのステージ(臨床病期)はT2aで、ステージ2と診断された。
〇これに基づき、医師は選択肢が4つあると提示。第1は、このまま治療せず、放置しても余命が10年間はあるので治療しない。第2は手術ロボット・ダビンチによる全摘手術、第3はホルモン療法と放射線治療を行う。この場合には、がんは完治できないかもしれない。第4は重粒子線治療とホルモン療法を行う。ただし、東京都内には重粒子線治療ができる病院がないので、神奈川県立がんセンター(自宅から小田急線、相鉄線を乗り継いで、二俣川駅で下車、片道約2時間かかる)に行かなければならない。重粒子線とは放射線よりも重い粒子で、炭素イオンを高速で回転させ、がん細胞に照射するという。この重粒子線治療ならばがん細胞を完治できるという。夫婦で呼び出されていたので、相談して、その選択は第4の重粒子線治療にすることを決めた。
〇この一連の過程で、常に医師、看護師に問われたのは本人の意思確認であり、そのための丁寧な説明であった。インフォームドコンセントが徹底しており、そのために、必ず、“了承した旨の同意書”へのサインが求められた。またセカンドオピニオンも奨められ、その際には検査結果は提供するという姿勢であった。35年前とは雲泥の差で、医療界が大きく患者目線に変わってきていることを実感した。
〇他方、これだけの丁寧な説明をし、同意書にサインをさせておきながら、本人を信頼しないのか、時には配偶者もしくはそれに代わる人の臨席を求められることには違和感を感じた。私の子どもは勤務しているわけだし、同居ではないので、配偶者だけの身元保証人でいいのではないかといっても、身元保証人は3人必要だといって譲らない。
〇今後、一人暮らし高齢者や一人暮らし障害者等その意思確認や説明を理解できない人への対応の在り方が医療界でも社会福祉界でも大きな問題になると思われた。
〇単身高齢者が増え、身元保証人(それも3人も必要?)もいない人が増えてきている状況、一人暮らしの障害者も増加してきている状況の中で、医師、看護師からの説明を理解し、同意書にサインを求められても対応できない人が多くなることがこれからは考えられる。これは、社会福祉界において重要な、かつ喫緊の課題であると、改めて自分自身の体験から痛感した。
〇このように、配偶者、身元保証人の臨席を求めるものだから、病院内は付き添いの人も含めて大混雑であった。
〇神奈川県立がんセンターは、築50年以上の日本医科大学多摩永山病院とは異なり、近代的な建物であり、空間も広く、かつ診察システムもICTを活用した近代化された病院であった。
〇神奈川がんセンターでも日本医科大学多摩永山病院と同じような診断が下され、グリソンスコアが8、がんのステージはT2aかつ2ということであった。ホルモン療法は2年間、重粒子線治療はホルモン治療開始後6か月以降に行うという治療方針が示された。
〇ホルモン治療の効果をチェックする3か月ごとの検査では、PSAの数値が10月3日には0・217になり、1月10日は0・04迄下がっている。この数値なら、重粒子治療は必要ないのではないかと尋ねると、ホルモン治療の結果、数値が下がっているが、ホルモン治療だけではいずれ効果がなくなり、また数値が上がるので、重粒子線治療が必要との回答であった。
〇重粒子線治療がいよいよ2月末から始まる。重粒子線治療が始まるとお酒が飲めないという。それだけならまだしも、治療終了後3か月間もお酒は飲めないという。6月20日まで禁酒である。
〇前立腺がんと診断されて以降も、何の自覚症状もなく、毎日お酒を楽しんできたものにとって、3か月半の禁酒は“人生最大の危機”である。
〇3回行った「四国歩きお遍路」でも、第2回目を禁酒しただけである。その時は約40日間お酒を飲まず、結願したあと、徳島での打ち上げ式にお酒を飲んだら、まずくて早々に引き上げた記憶があるが、今度は100日間の禁酒である。どのような体質になるのか、今から楽しみである。
〇1月30日の再診で、重粒子治療に向けた準備が始まった。整腸剤を始め、4種類の服薬が毎食後必要になったが、外出している時にはついつい服薬を忘れてします。4種類の薬をコミュニティ袋に分けて持ち歩いていても、昼食等外食する際にはついつい忘れてしまう。頭では分かっていたつもりでも、いざ自分がその身になってみると、一つ一つが新たな体験で、社会福祉分野での話し方、考え方をもっと実情に合わせて考えなければならないことの反省と実感の日々である。
〇現時点では、何の自覚症状もなく、自分が前立腺がんに罹患していることが全く自覚できない、不思議な状況である。治療しなくても10年間の余命というなら、その選択肢もあったのかなという思いと、他方これからどんな体験ができるのかという楽しみと不思議な感情がなり混ざった心境のこの頃である。
(2023年2月3日記)