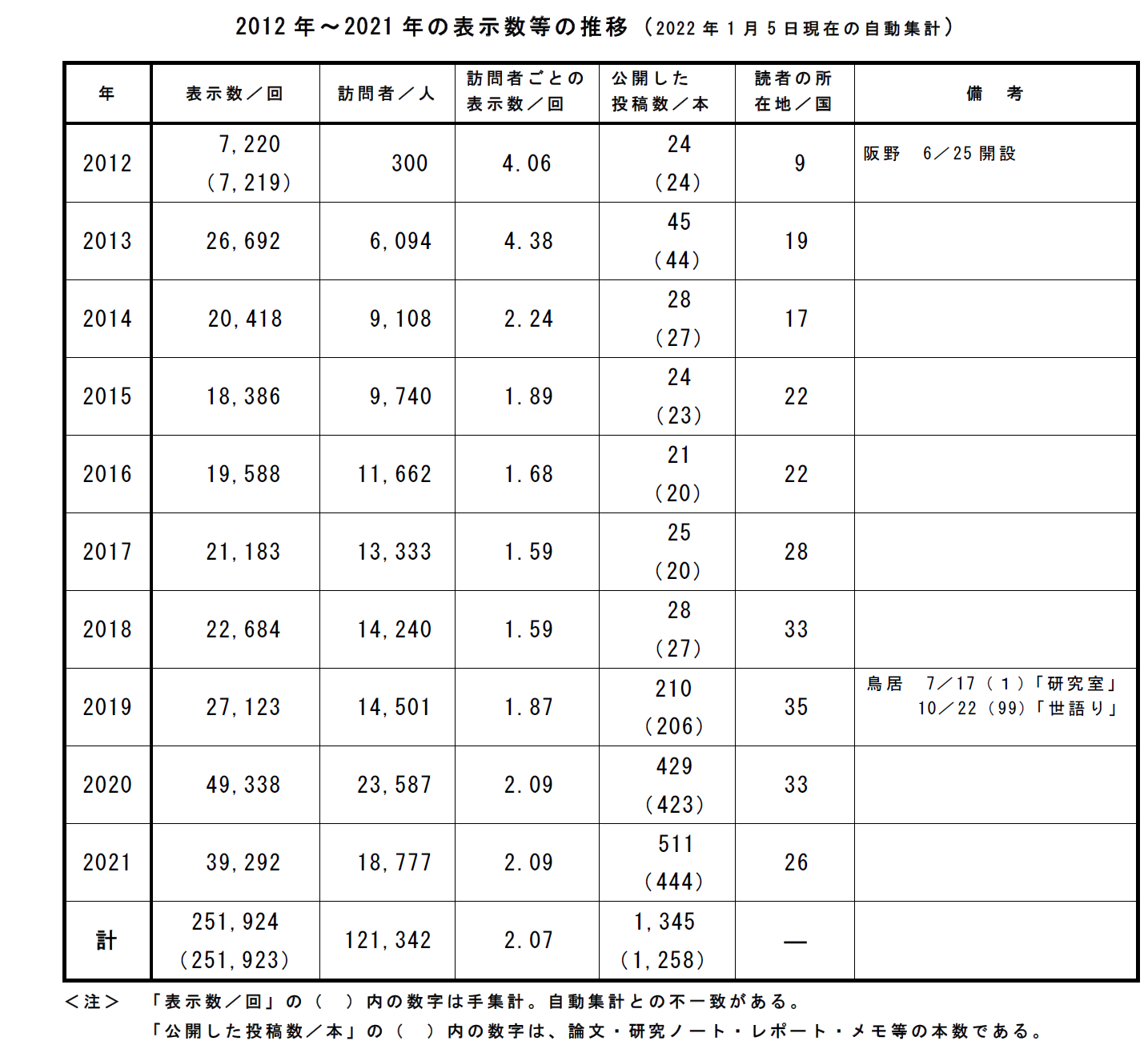社協の認知度は低かった
何をしているのか知らなかった
市民と福祉をつなぐ道は険しかった
社協は市福祉部局の出先機関と思われていた
市に人件費も人事権も握られていた
社会福祉法人として苦渋の年月を重ねていた
2005年一大改革に打って出た
市民と協働して策定する地域福祉実践計画
道内では事例はなかった
道外も五万人規模の事例は皆無だった
市民主導の計画づくりそのものが挑戦となった
50余名の委員が各校区から選出された
会議は定刻に始まり2時間で終わる
時間厳守で集中審議を促した
市民参画の揺るぎない態度形成をもたらした
市民アンケート調査は連合町内会の支援を得て実施した
全世帯に配布し回収率6割弱は前代未聞の快挙であった
社協の存在と社会福祉をアピールする手法でもあった
地域座談会も全地区で開催して民意を聴き集めた
手探りの拙い計画づくりではあったが
市民と協働するスタート地点となった
あれから17年の歳月が流れた
コロナ禍で第4期の策定委員会が開けず
第3期計画を1年延ばさざるを得なかった
去年の6月からようやく委員会が動き出した
この17年で求めたものは何か
何を得ようとしたのか
何を得たのか
何が得られなかったのか
この17年で変わったのは何か
何が変わったのか
何を変えようとしたのか
なぜ変わったのか
この17年で変わらなかったのは何か
何が変わらなかったのか
何を変えようとしなかったのか
なぜ変わらなかったのか
その解を第4期計画に求めてきた
これからの5年は予断を許さぬ時代が始まる
変わるべきものを変える
変わらなければならぬものを変える
変えてはならないものを確かめる
いま新たな「きずな計画」が立ち上がる
変えてはならぬことだけは明らかだった
市民一人ひとりの暮らし方を問う「きずな計画」
市民と福祉をつなぐ「きずな計画」
市民が福祉を実践する「きずな計画」
変えた事実も明らかだった
17年の実績は市民も社協もその福祉力を逞しく育てた
社協は市民の民意をきずなに束ねる福祉でまちづくり
社協を市民が民意で支えて築く福祉でまちづくり
社協が市民と民意で創る明日に福祉でまちづくり
わたしがこのマチ登別で
幸せに暮らし続ける理由を添えて
市民の信頼と希望を注いだきずな計画は
新たな役割と展望を持って
市民が躍動する計画となる
〔2022年1月3日書き下ろし。登別市民の願いと希望を第4期きずな計画に託す〕