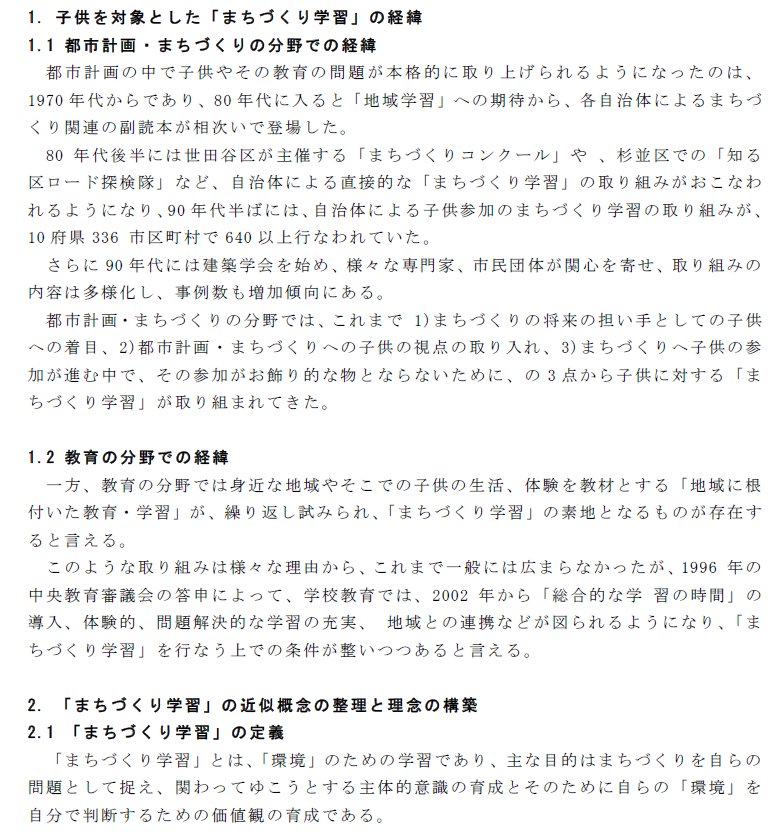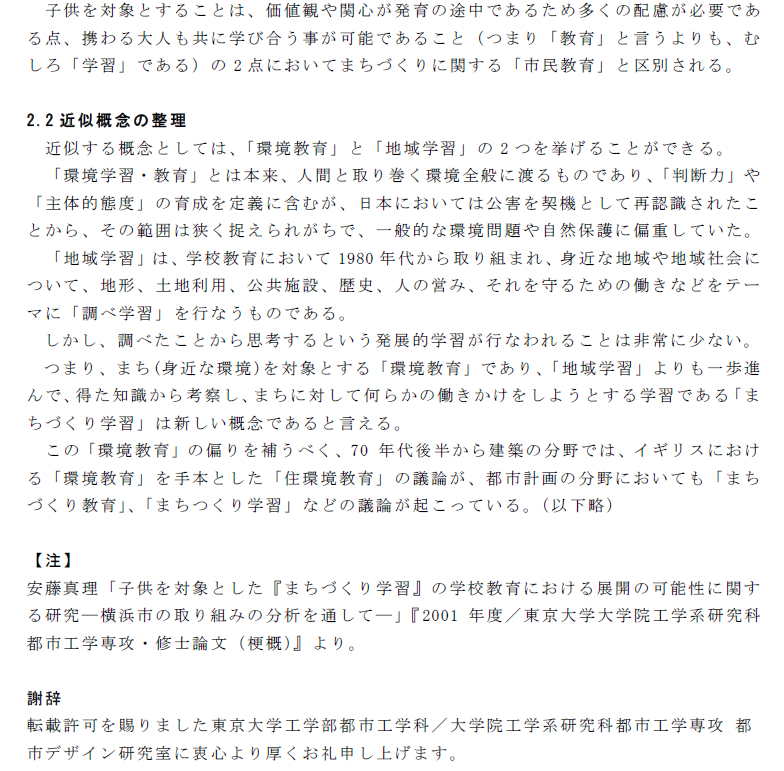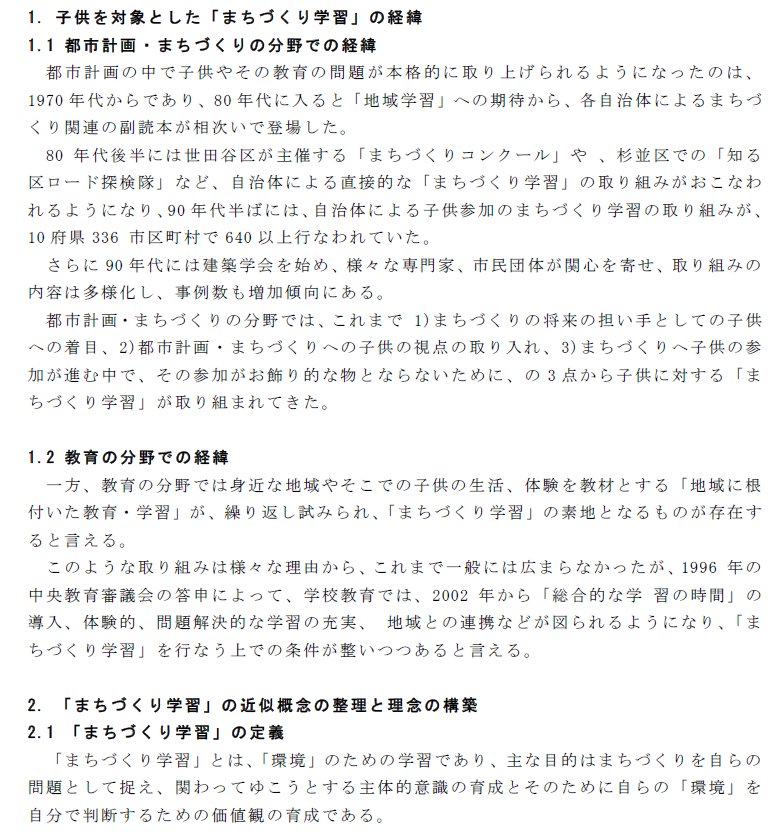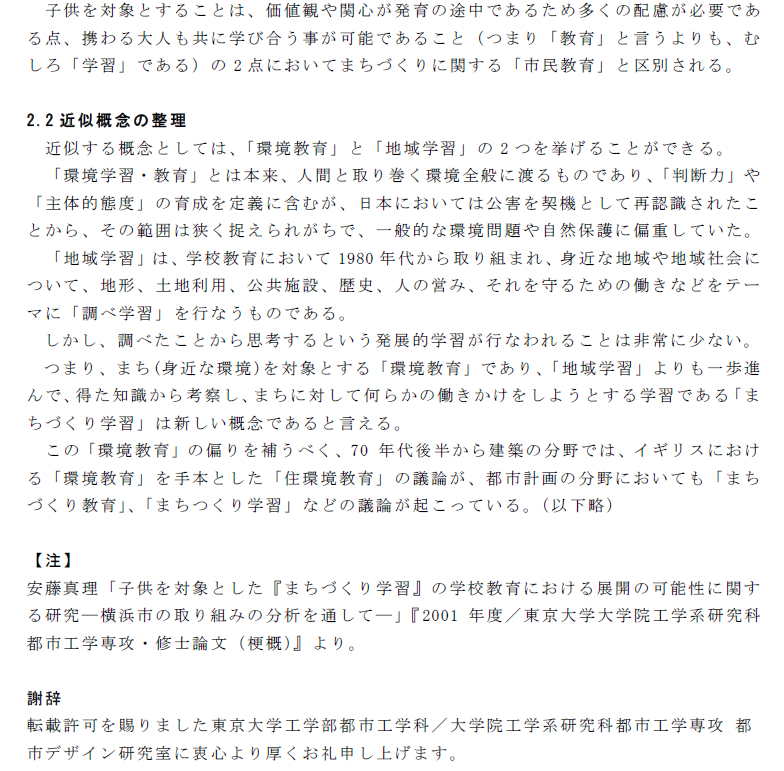〇筆者の手もとにいま、宮本太郎(みやもと・たろう。政治学・福祉政策論専攻)の本が2冊ある。『生活保障―排除しない社会へ―』(岩波新書、2009年11月。以下[1])と『共生保障―<支え合い>の戦略―』(岩波新書、2017年1月。以下[2])がそれである。[1]は、人々の生活は雇用と社会保障がうまくかみあってこそ成立するという前提に立つ。そして、雇用と社会保障を包括する「生活保障」という視点から、日本と各国の雇用と社会保障の連携を比較分析し、ベーシックインカムやアクティベーション(活性化)などの諸議論にも触れながら、日本で生活保障システムがどのように再構築されるべきかを論じる。その際、所得保障だけではなく、大多数の人が就労でき、あるいは社会に参加できる「排除しない社会」のかたちを問う。とともに、そうした社会を実現するために必要な「生きる場」(人々が誰かにその存在が「承認」されていることで、生きる意味と張り合いを見出すことができる場)が確保される生活保障のあり方について考える。なお、ベーシックインカムとは、就労や所得を考慮せずにすべての国民に一律に一定水準の現金給付を行なう考え方である。アクティベーションとは、雇用と社会保障の連携強化を図り、社会保障給付の条件として就労や積極的な求職活動を求める考え方である。
〇[2]は、[1]の延長に位置づけられ、生活保障の新しいビジョンとして「共生保障」を提示する。本稿は[2]の(限定的な)再読メモである。宮本はいう。旧来の日本型生活保障は、現役世代の「支える側」(「強い個人」)と高齢者・障がい者・困窮者などの「支えられる側」(「弱い個人」)を過度に峻別してきた。そして、双方の生活様式を固定化し、「支えられる側」を一定の基準によって絞り込みながら、 社会保障・社会福祉の支出を医療や介護などの人生後半に集中させてきた(「人生後半の社会保障」)。ところがいま、高齢世代や子育て世代、非正規や単身の現役世代を中心に、生活困窮・孤立・健康などの様々な問題を、しかもそれらを複合的に抱える事態・状況が拡大・深刻化している。そこで、「支える側」と「支えられる側」という二分法から脱却し、生活保障の新しいビジョンとして、(すべての人の福祉ニーズに応える)普遍主義的な「共生保障」の制度や政策を構築する必要がある(「補遺」参照)。これが[2]における宮本の問題意識であり、議論(提唱)である。その際宮本は、「共生保障」は、地域における人々の「支え合い」を可能にするよう、「地域からの問題提起を受けとめつつ、社会保障改革の新たな方向付けにつなげる枠組みである」(48ページ)という。
〇宮本は、「共生」について次のように述べる(抜き書きと要約)。
(日本社会では)人々が支え合いに加わる力そのものが損なわれ、共生それ自体が困難になっている。こうした現実に分け入ることなく、規範として共生を掲げ続けるならば、それは現実を覆い隠すばかりか、困難になった支え合いに責任をまる投げしてしまうことにもなりかねない。(ⅳページ)。
共生という言葉は、その意味がいささか漠然としているゆえに、誰も反論しがたく、だからこそ都合良く使われてしまうところがある。今、社会の紐帯が根本から揺らいでいることから、「共生社会」が盛んに提起されるが、人々がどのように関わり合い、誰が何に対して責任をもつ構想なのか、はっきりしないことが多い。(223ページ)
共生や支え合いは規範として押し付けられる筋合いのものではない。一見したところ利他的な行為であっても、共生は長期的に見ると自己に利益をもたらす(「手段としての共生」)。また、人々が互いに認め認められる相互承認の関係を取り結ぶことができれば、共生はそれ自体が価値となる(「目的としての共生」)。共生や支え合いは、人々にとって手段でもあり目的でもあり、したがって本来は自発的な営みなのである。(194ページ)。
〇こうした指摘は、国(厚生労働省)がその実現を図る「我が事・丸ごと」の「地域共生社会」について考える際の重要なポイントとなる。「我が事・丸ごと」の政策は、社会保障や社会福祉の国家責任が地域社会に転嫁され、社会保障・社会福祉費の削減と自助・互助による支援体制の推進が図られている。それを一言で言えば、「他人事(ひとごと)・丸投げ」である。確かな「共生」には、政府主導による「上から」の規範としてではなく、地域・住民の、地域・住民による、地域・住民のための「下から」の支え合いの戦略と、それを踏まえた事業化や制度化が強く求められる。なお、国が説く「地域共生社会」は、「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、 人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」(厚生労働省「『地域共生社会』の実現に向けて 」2017年2月)をいう。耳ざわりの良い(口当たりの良い)言葉が連なる、“美しく”まとめられた一文である。ここで筆者は、中身がスカスカ(浅薄皮相)な、「活力とチャンスと優しさに満ちあふれ、自律の精神を大事にする」(なんと白々しいことか)という「美しい国、日本」(2006年9月に召集された第165回国会における安倍内閣総理大臣の所信表明演説)という言葉を思い出す。
〇宮本は、「共生保障」について次のように述べる(抜き書きと要約)。
共生や自立というテーマが政府から打ち出されるとき、そこには行政と政治の責任が曖昧にされ、人々の助け合いや自助にすりかえられる危険もある。共生保障とは、そのようなすりかえを回避し、人々の支え合いのために行政と政治が果たすべき条件を示す政策基準でもある。(219~220ページ)
共生保障は、年金や医療などを含めた生活保障のすべてに関わるものではない。それは、次のような制度や政策を指す。
第一に、「支える側」を支え直す制度や政策を指す。これまで男性稼ぎ主を中心とした「支える側」は、支援を受ける必要のない自立した存在とされてきたが、「支える側」と目される多くの人々は経済的に弱体化し孤立化し、力を発揮できなくなっている。
第二に、「支えられる側」に括(くく)られてきた人々の参加機会を広げ、社会につなげる制度と政策である。そのためにも、人々の就労や地域社会への参加を妨げてきた複合的困難を解決できる包括的サービスの実現が目指される。
第三に、就労や居住に関して、より多様な人々が参入できる新しい共生の場をつくりだす施策である。所得保障については、限定された働き方でもその勤労所得を補完したり、家賃や子育てコストの一部を給付する補完型所得保障を広げる。(47ページ)
人々を共生の場につなげ、共生の場自体を拡充していく共生保障の戦略は、それ自体が生成途上のものである。このような考え方をより具体化していくためにも、地域におけるさらなる創造的な取り組み、社会保障改革の新展開、そして両者をつなぐ共生保障の政治が必要である。生活保障の新しい理念は、そのような地域、行政、政治の連関のなかで活かされ、練磨されていくべきものであろう。(221~222ページ)
〇「支える側」を子育て支援や介護サービス、リカレント教育などによって支え直し、「支えられる側」に就労支援や地域包括ケア、生活支援サービス(見守り・外出支援・家事支援)などを通して社会への参加機会を提供する。それは、より多くの人々が共生や支え合いの「場」(居住・就労・活動の場や領域)に参入することを意味する。その「場」は、地域における居住(高齢者や現役世代などが支え合いながら一緒に暮らす、あるいは一人暮らしの高齢者が地域の生活支援を受けながら暮らす「地域型居住」)の場をはじめ、コミュニティ(共同体)や就労の場、共生型ケアの場など、人々が直接、間接に相互の必要を満たし合う場(フィールド)を指す(51、52、94ページ)。
〇宮本は、「共生保障」型の地域福祉や地域組織づくりについて、その実践事例を紹介する。「ひきこもりで町おこし」を進めた秋田県藤里町社会福祉協議会の取り組みや、「このゆびとーまれの共生型ケア」を進めた富山市の民間デイサービス事業所「このゆびとーまれ」の取り組み、「小規模多機能自治」と呼ばれる島根県雲南市の市民と行政による協働のまちづくりの取り組みなどがそれである。
〇藤里町社協の取り組みは、ひきこもりの若者の居場所や交流拠点、働き場所として、2010年に地域福祉の拠点「こみっと」を開設し、それを特産品づくりによる町おこしへとつなげた実践である。それは、「障害や生活困窮など、働きがたさを抱えていた人々が、支援を受けつつも多様なかたちで働くことができる新しい職場環境」(82ページ)を指す「ユニバーサル就労」の考え方による。「このゆびとーまれ」のそれは、高齢者だけでなく子どもや障がい者などの誰もが利用できるデイケアハウスを1993年に開所し、それを「地域密着・小規模・多機能」をコンセプトとした共生型福祉施設、そしてその後の「富山型デイサービス」へと発展させた実践である。それは、「福祉のなかから当事者同士の支え合いをつくりだし、部分的には支援付き就労にもつなげていく試み」(106ページ)である「共生型ケア」の考え方による。それらの詳細については次の文献を参照されたい。
・菊池まゆみ『「藤里方式」が止まらない― 弱小社協が始めたひきこもり支援が日本を変える可能性?』萌書房、2015年4月
・菊池まゆみ『地域福祉の弱みと強み―「藤里方式」が強みに変える―』全国社会福祉協議会、2016年10月
・惣万佳代子『笑顔の大家族このゆびとーまれ―「富山型」デイサービスの日々―』水書坊、2002年11月
〇雲南市では、「まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主体的に関わることです」(雲南市まちづくり基本条例前文)という基本理念のもとに、2010年に公民館を地域づくり・生涯学習・地域福祉を担う交流センター(公設民営・指定管理)に改組する。そして、そこに自治会(地縁型組織)や消防団(目的型組織)、PTA(属性型組織)などがつながり、地域の総力を結集して地域課題を自ら解決し、住民主体のまちづくりを進める地域自主組織(小規模多機能自治)を概ね小学校区に立ち上げた。そこでは、要援護者の安心生活見守り事業や高齢者の買い物支援事業などが展開されている。地域自主組織は、市の財政支援や人的支援などを受けながら、地域間の連携や行政との協議・協働を図り(「地域自主組織取組発表会」「地域円卓会議」「地域経営カレッジ」等)、さらには2015年に「小規模多機能自治推進ネットワーク会議」を設立して全国の他地域とのネットワークを構築している。特筆されるところである。
〇なお、こうした「好事例」について、宮本は次のようにもいう。「『好事例』は、既存制度を超える『技』(『裏技』『荒業』を含めて)を備えた突出したリーダーシップによる例外的事例に留まっている」(ⅴページ)。「新聞やメディアは、地域で広がるひとり親世帯や高齢世帯の困窮、孤立をクローズアップし、時に警鐘を乱打する。その一方で、地域における困窮者支援やまちづくりの『好事例』を積極的に取り上げ、これを持ち上げる。さらに、国の社会保障改革の停滞について伝える。だが、深刻な地域の現実と一部の『好事例』と停滞する社会保障改革が、時々のトピックスに伴って代わる代わる前面に出て、相互につながらない」(ⅵページ)。「地域では、人々の支え合いを支え、共生を可能にしようとする多様な試みが広がっている。しかし、こうした動きは、『好事例』に留まり大きな制度転換にはつながっていない」(218ページ)。留意しておきたい。
〇「共生保障」の観点から「まちづくりと市民福祉教育」について一言しておきたい。(「支えられる側」とされがちな)高齢者や障がい者、子どもなどが自律的・能動的な地域生活を営むためには、「支える側」による個別具体的な支援とともに、安全・安心な生活環境が整備され豊かな社会関係が構築されなければならない。しかも、生活上の困難や社会的課題を抱える高齢者や障がい者、子どもにはそれゆえに、地域社会を構成する一員であるとともにまちづくりの主体であることを認識し、その役割を果たすことが期待される。その際、(まちづくりの主体である)その地域に暮らす多様な人々との相互理解や相互承認、共働や支え合い、それを保障するための仕組みが必要かつ重要となる。それが、「まちづくりと市民福祉教育」の内容や方法を決める。
〇周知の通り、(1)1970年代以降の高齢化社会の進展を背景に、高齢者の学習活動の奨励や社会参加活動の促進が図られるなかで、高齢者の学習・教育プログラムが開発、提示されてきた。(2)1960年代にアメリカで生まれた身体障がい者の自立生活運動を契機に、日本では1980年代以降、障がい者が自律的に地域生活を営むための自立生活プログラムが組織化され、その普及が図られてきた。(3)学校教育においては1980年代から「地域学習」が取り組まれ、1980年代後半には「環境教育」が注目される。2002年度から小・中学校で(高等学校では2003年度から)全面実施された「総合的な学習の時間」では、「まちづくり学習」の取り組みが行なわれるようになった。こうしたなかでまちづくり学習プログラムの開発が進むことになる(「付記」参照)。(4)1990年代以降、社会の階層化・ 分裂化が指摘され、政治や社会に積極的・主体的に参加する「能動的市民」(民主主義社会の形成者)の育成が求められた。イギリスでは 2002 年に、公教育の中等教育段階でシティズンシップ教育が必修化された。日本では2006 年に、経済産業省によって「シティズンシップ教育宣言」が出された。それをきっかけに、東京都品川区の小中一貫教育のなかでの「市民科」の設置(2006年)、お茶の水女子大学附属小学校における「市民」科の授業の取り組み(2007年)などがクローズアップされた。以後、学校教育のみならず、生涯学習の一環としてシティズンシップ教育プログラムの開発と実践が展開されることになる。
〇これらは、「まちづくりと市民福祉教育」に含まれるべき学習・教育活動であるが、市民福祉教育実践として十分に取り上げられてこなかった。共生保障としての「まちづくりと市民福祉教育」の重要な要素であり、積極的な議論の展開が求められる。
補遺
普遍主義的改革の「三重のジレンマ」
1990年代からの社会保障改革の基調は普遍主義的改革であったが、その改革は空転し、掲げた目標のように進んでいない。それは、3つの深刻なジレンマあるいは矛盾――(1)国と自治体の財政的困難、(2)自治体の縦割り行政の制度構造と機能不全、(3)「支える側」の中間層の解体と雇用の劣化のなかで進行してきたからである、と宮本はいう。留意しておきたい(抜き書きと要約)。
第一に、本来は大きな財源を必要とする普遍主義的改革が、(経済)成長が鈍化し財政的困難が広がるなかで(その打開のための消費税増税の理由づけとして)着手されたということである。高齢社会が到来するなかで、高齢者介護については社会保険化(介護保険)が可能だったが、障がい者福祉や保育のニーズは、介護に比べて誰しも不可避とはいえない面があり、社会保険化は困難であった。したがって、財政的困難のなかで税財源へ依拠するというジレンマがいっそう深まった。
第二に、自治体の制度構造は「支える側」「支えられる側」の二分法に依然として拘束されている面がある。にもかかわらず、普遍主義的改革においては、その自治体にサービスの実施責任が課された。
第三に、救貧的福祉からの脱却を掲げた普遍主義が、中間層の解体が始まり困窮への対処が不可避になるなかですすめられた、という逆説である。日本社会で救貧という課題が現実味を増すなかで、救貧的施策からの転換が模索されるという皮肉な展開となったのである。そして新たな目標であった自立支援は、雇用が劣化して多くの人々の就労自立が困難になるなかで取り組まれた。
すなわち、共生保障とも重なる普遍主義的改革は、財政危機、自治体制度の未対応、雇用の劣化による中間層の解体という三重のジレンマのなかで、進行したのである。この三重のジレンマこそが、普遍主義的改革の展開とその結果を方向づけた。(153~154ページ)
付記
子どもを対象とした「まちづくり学習」の経緯―素描―