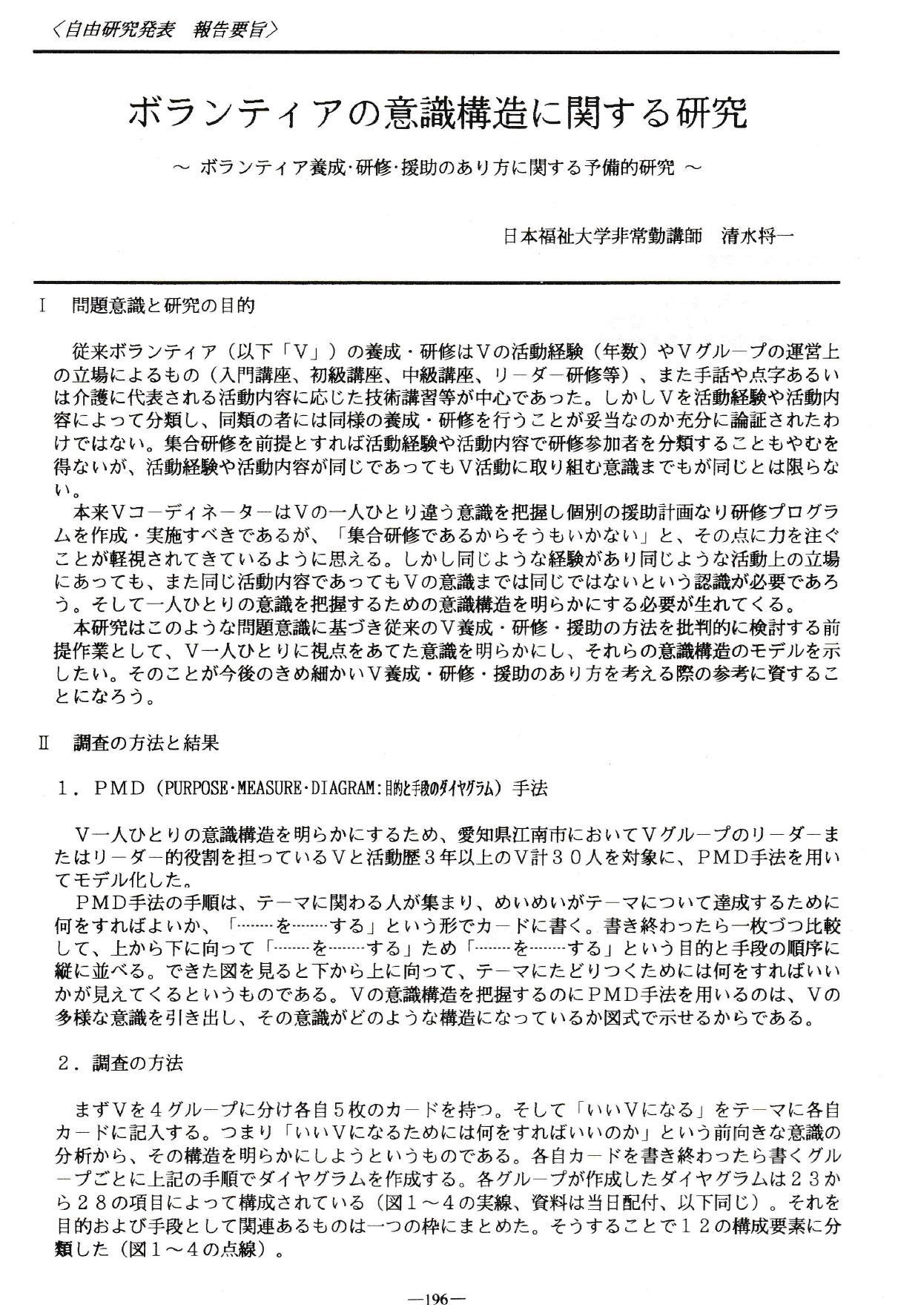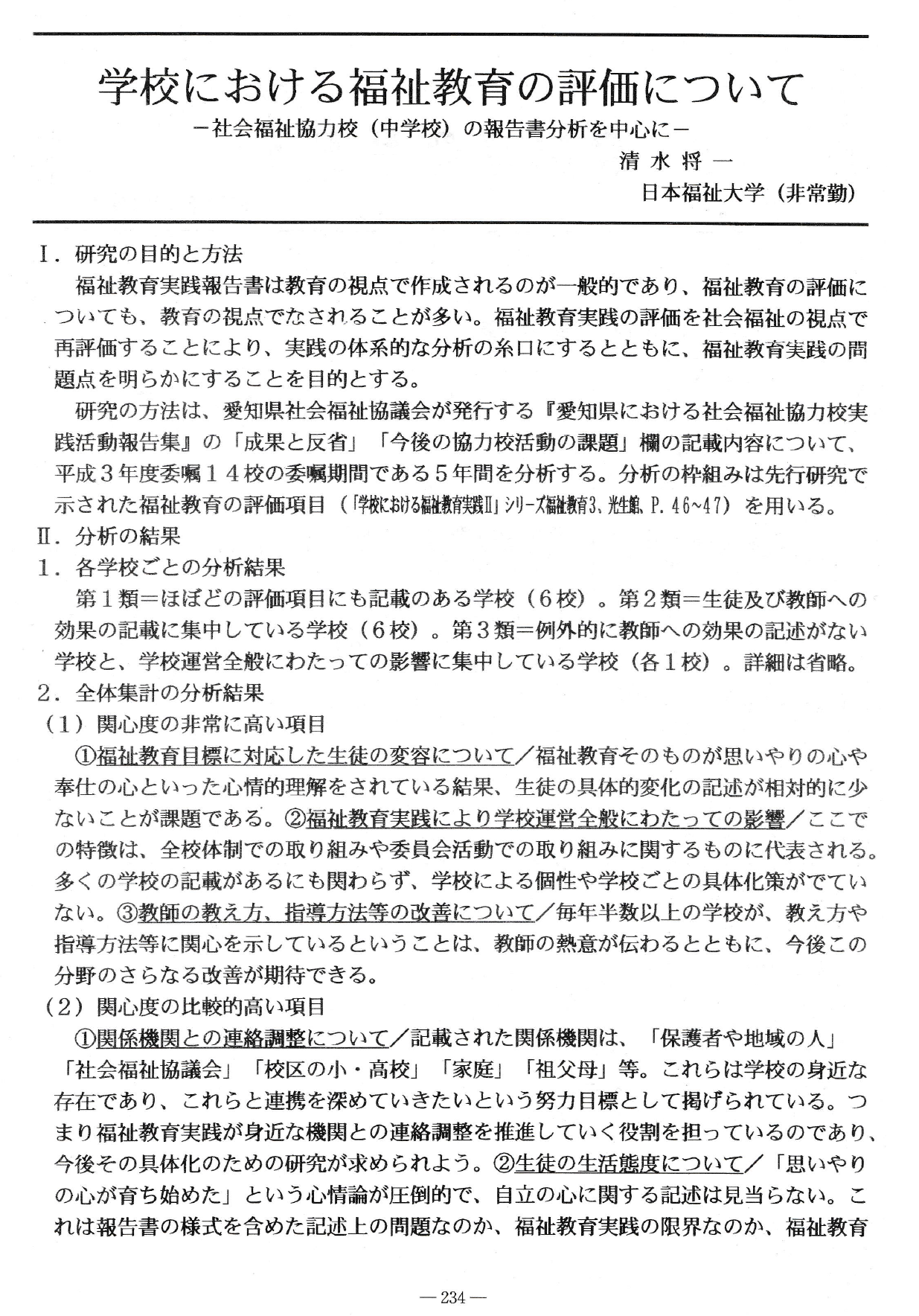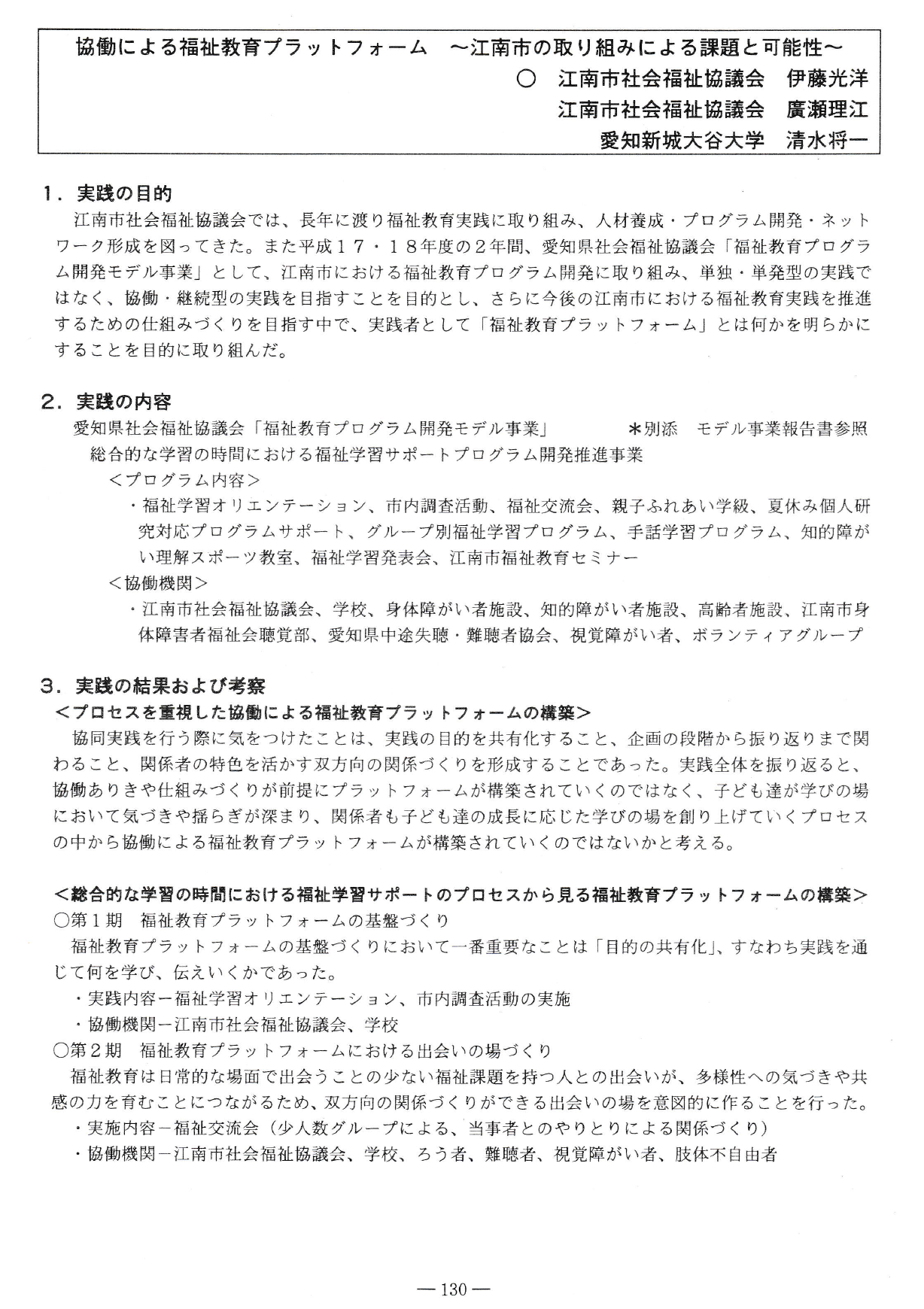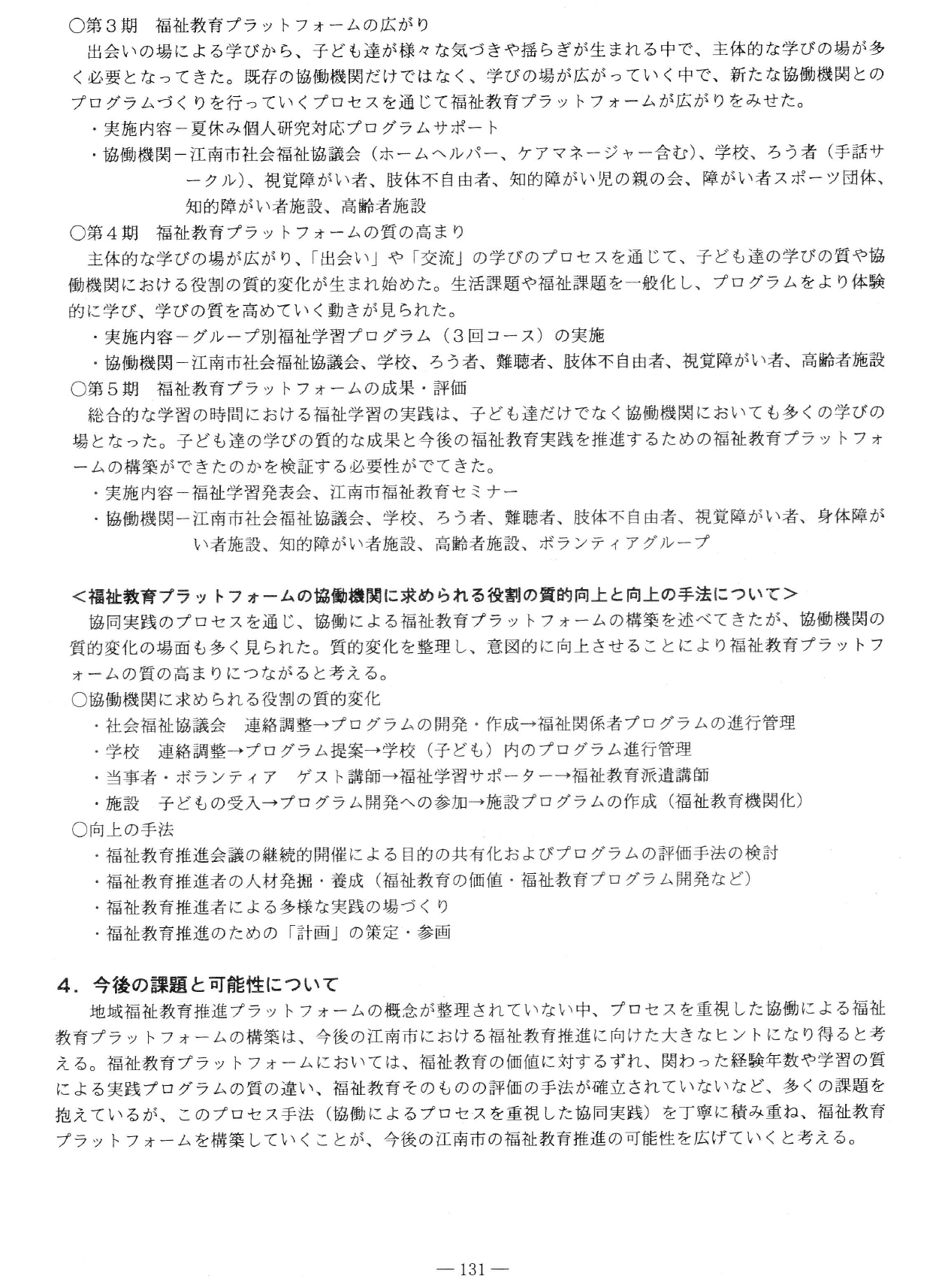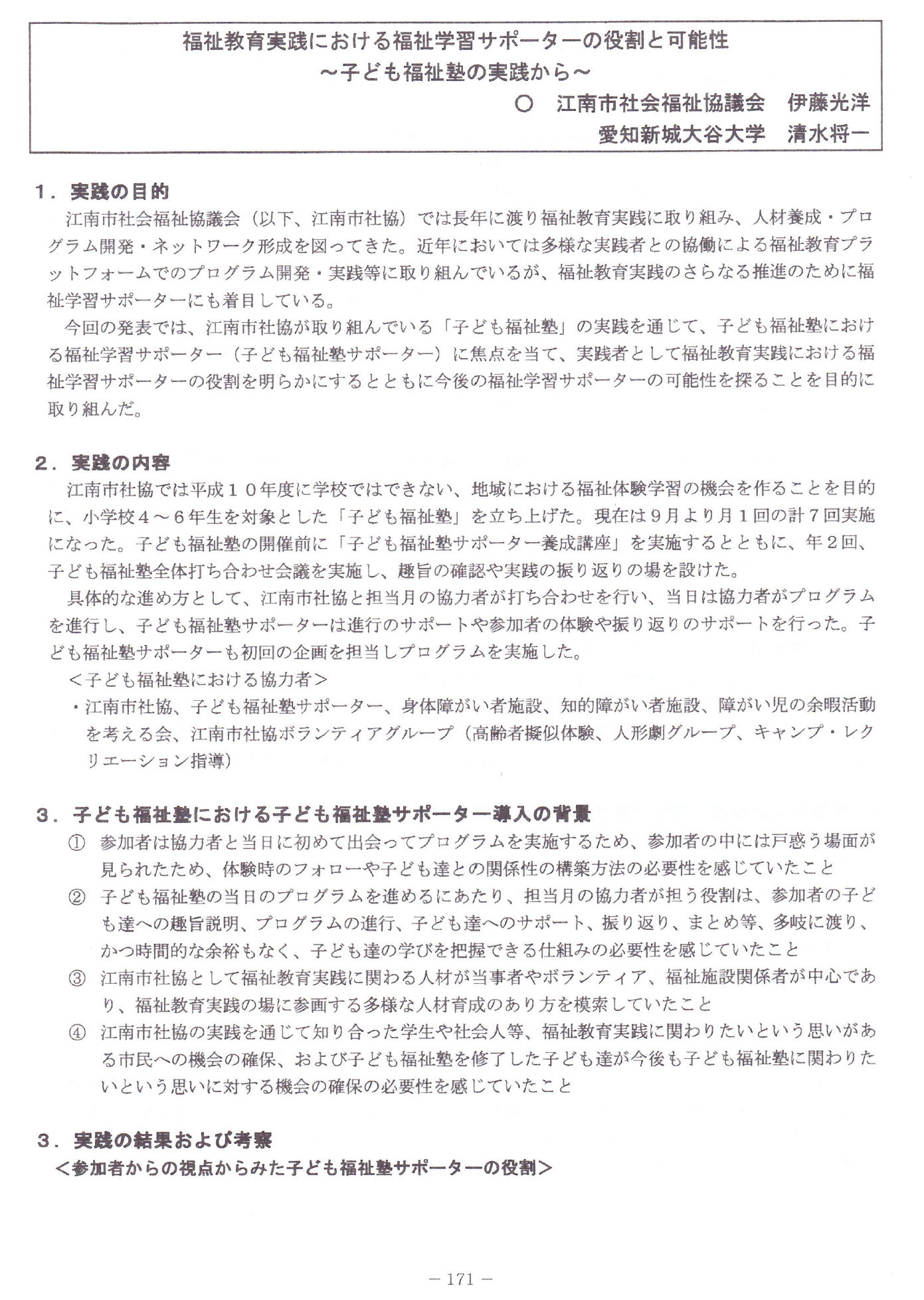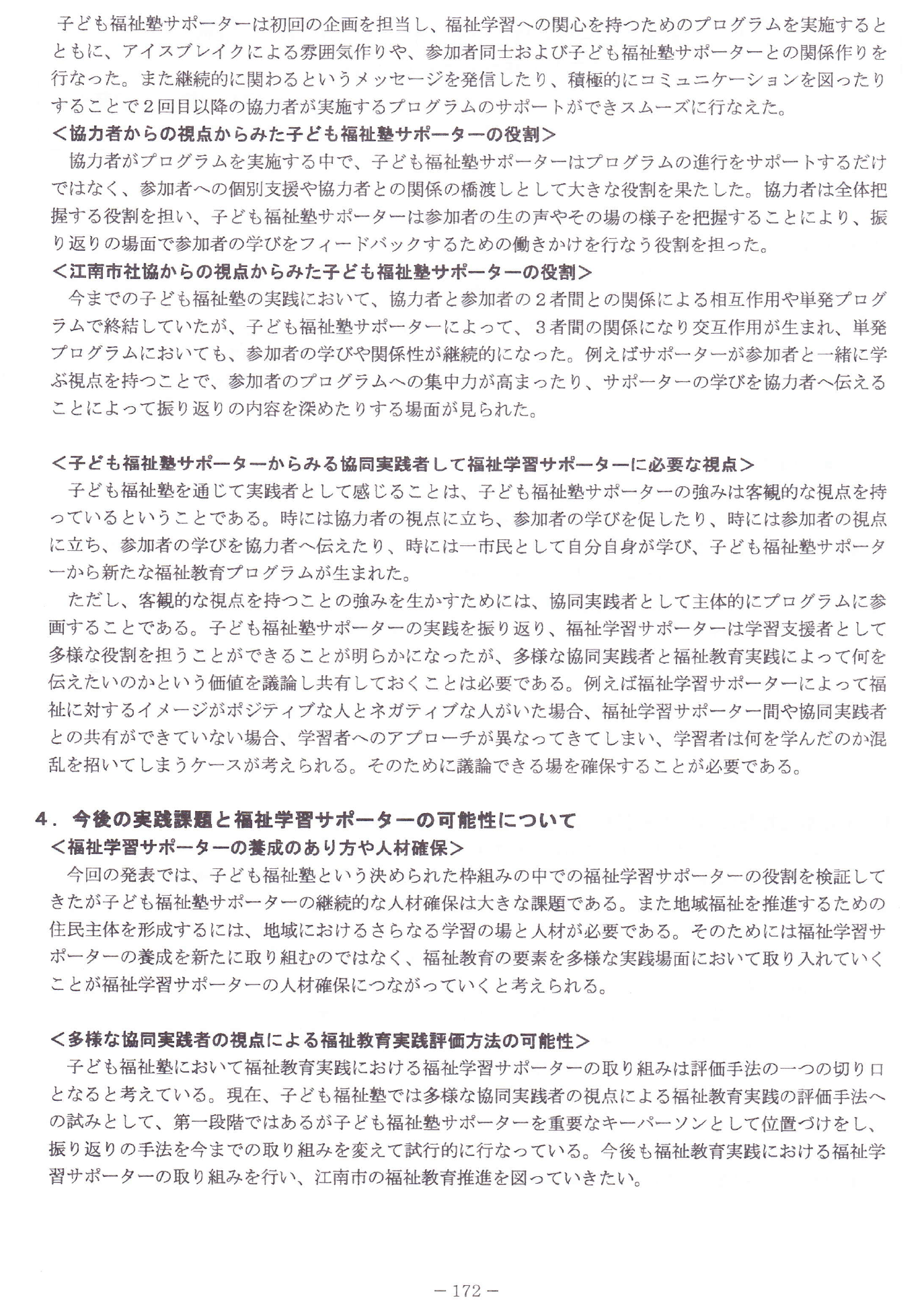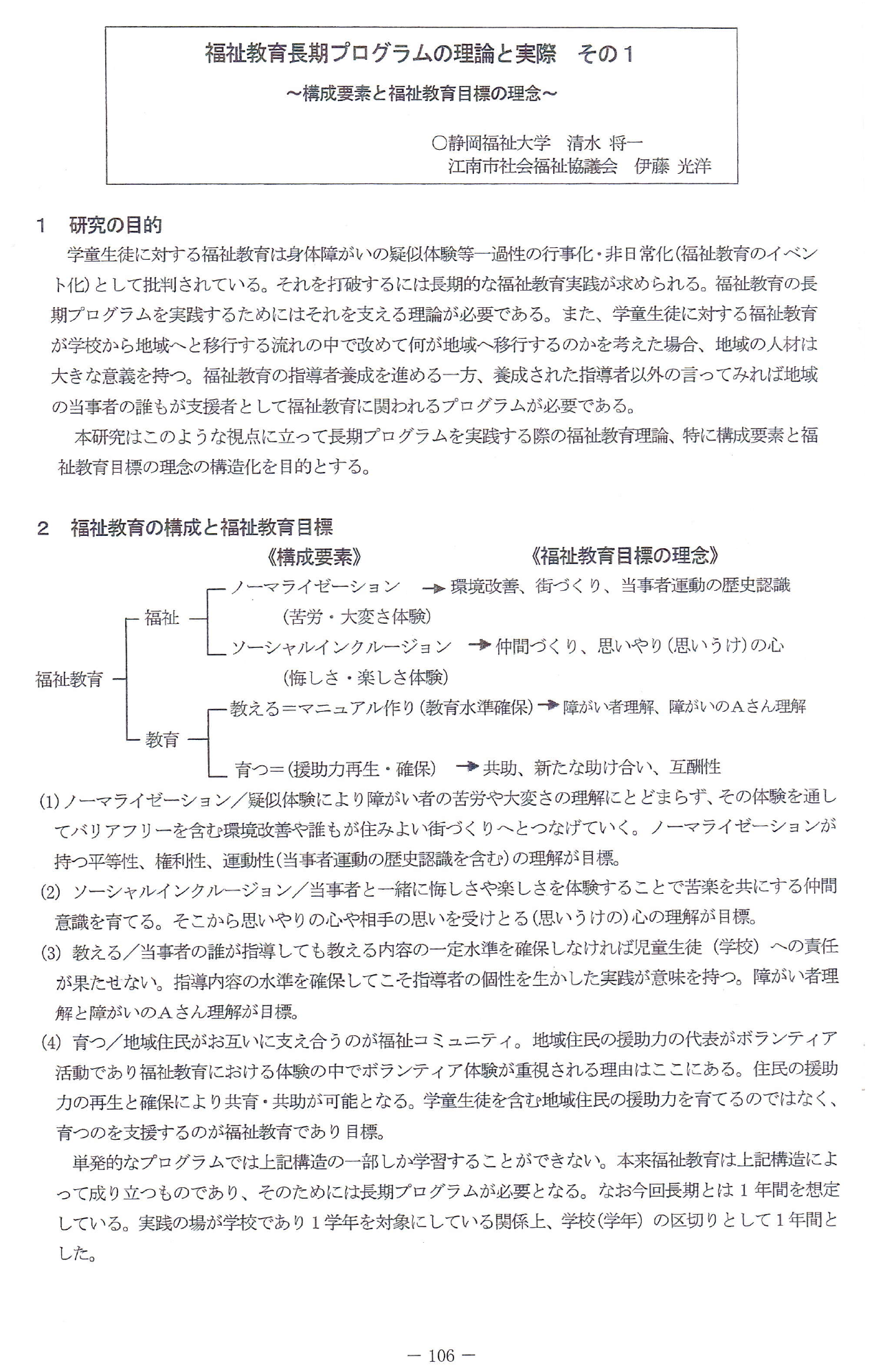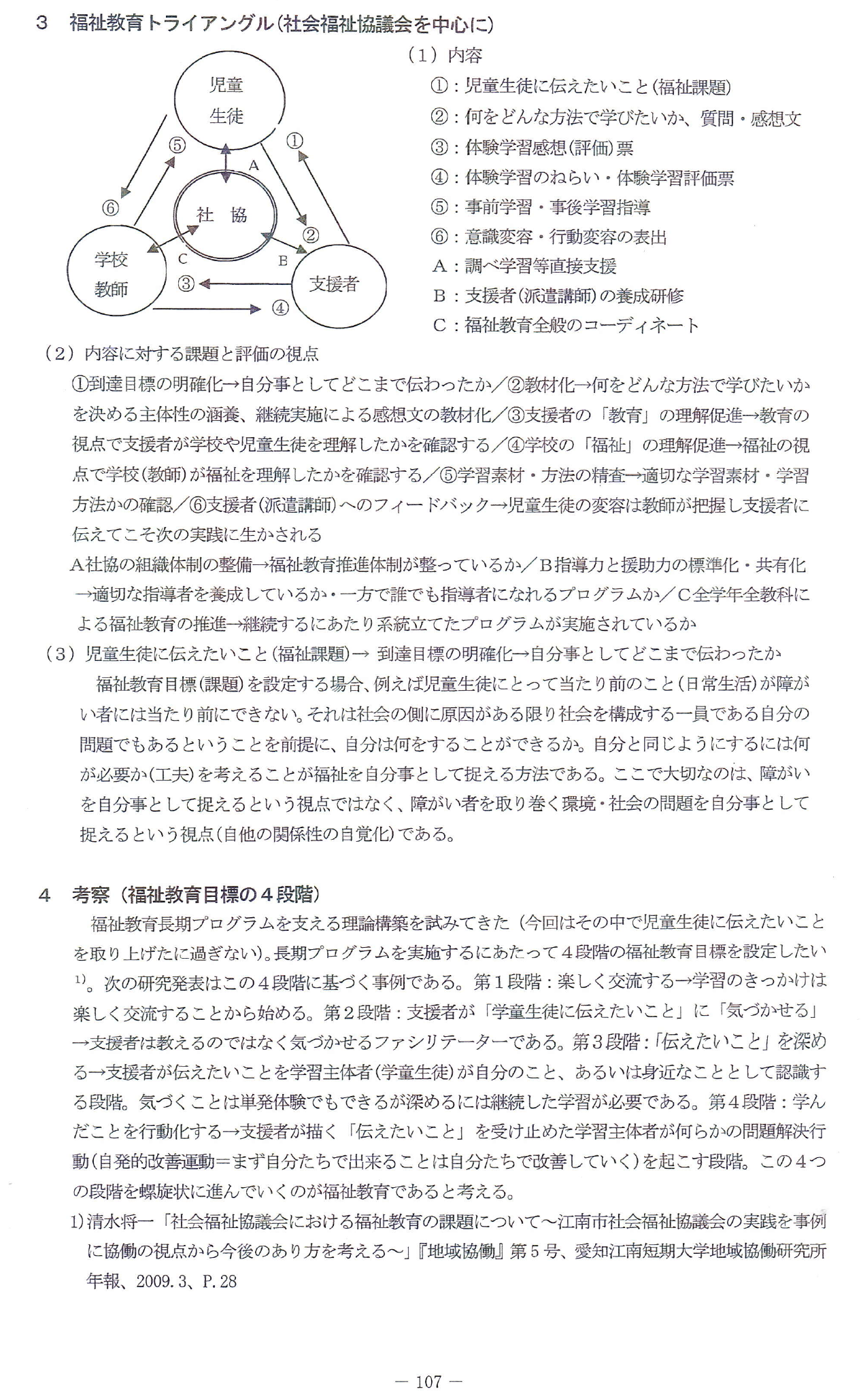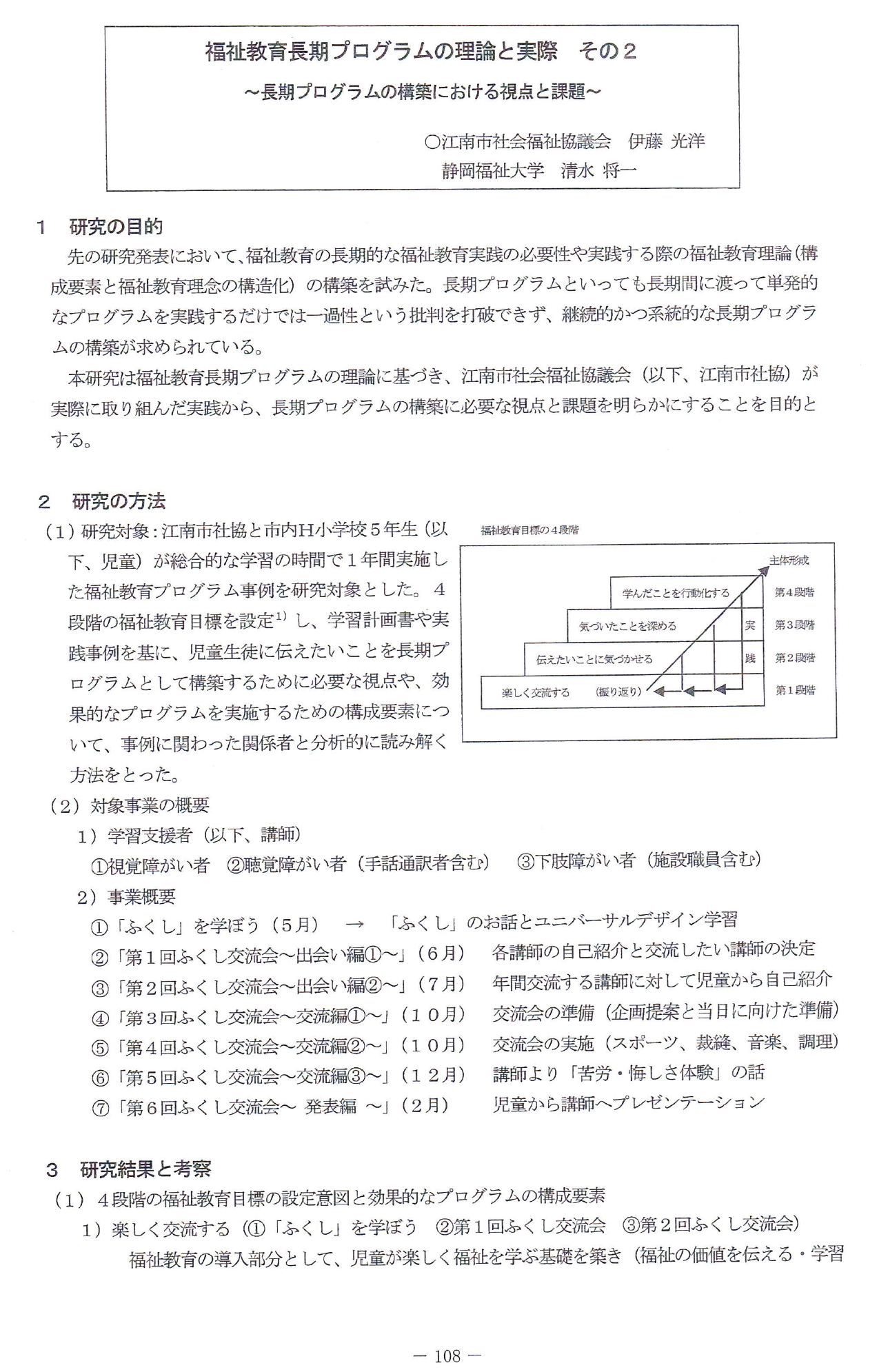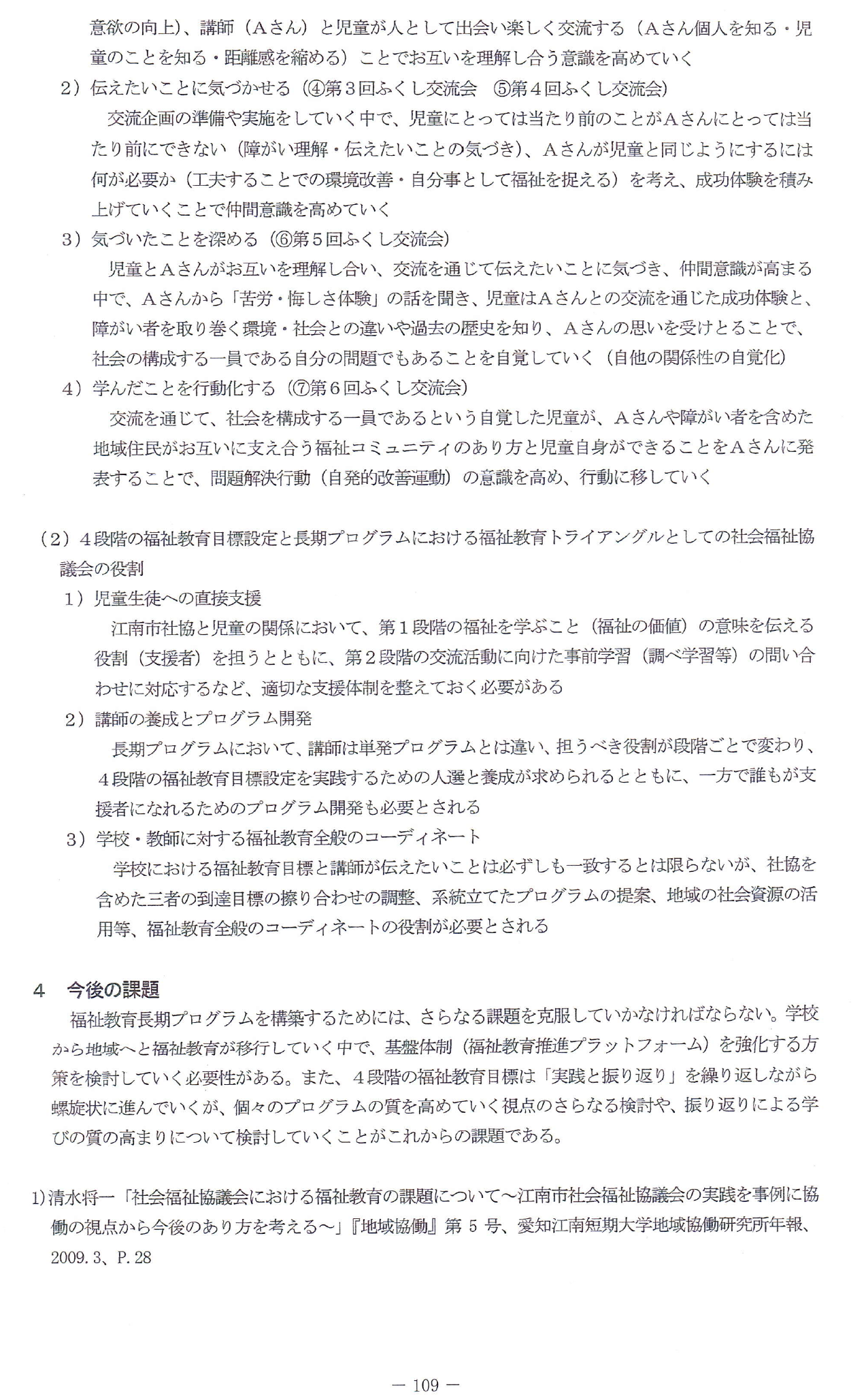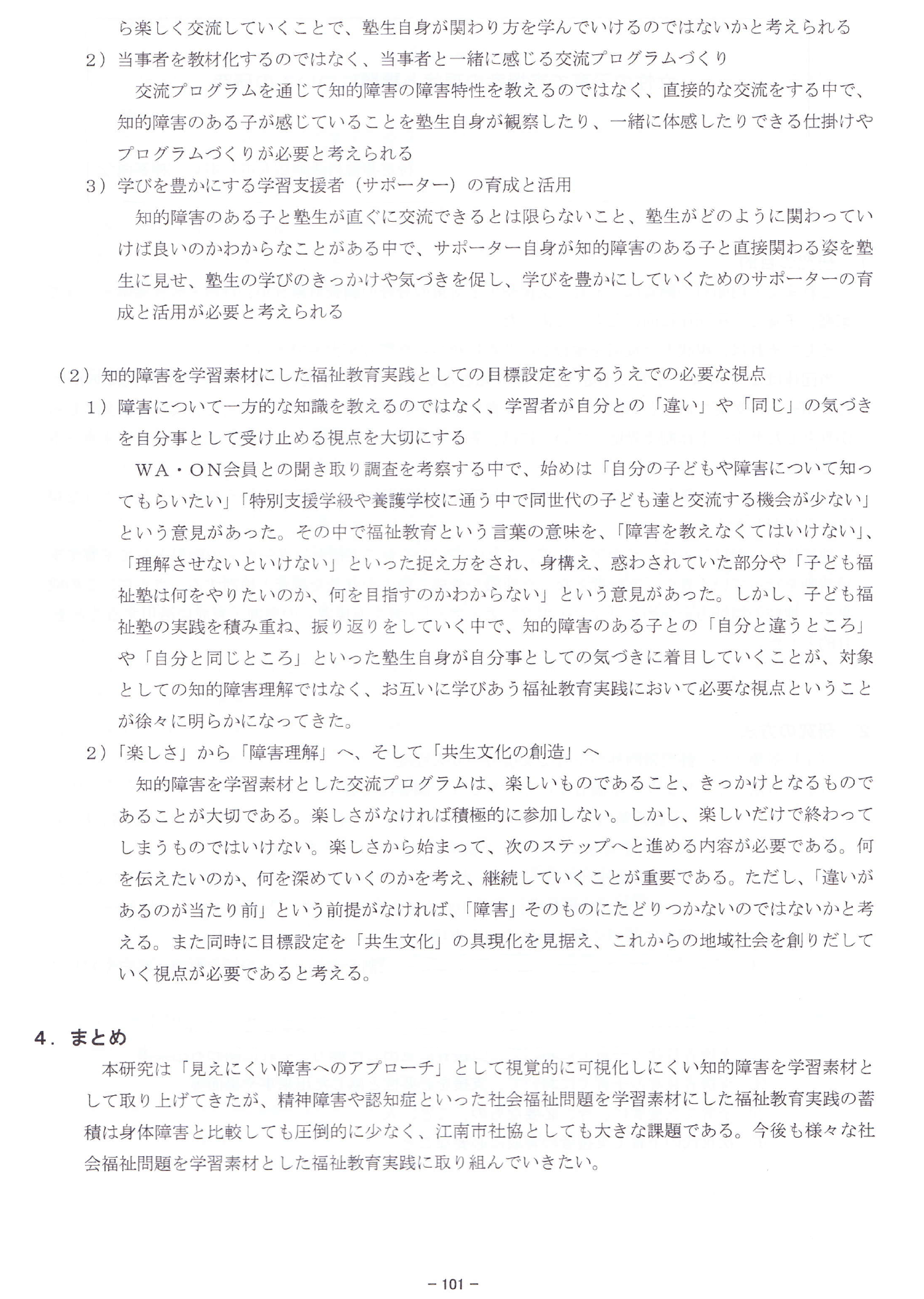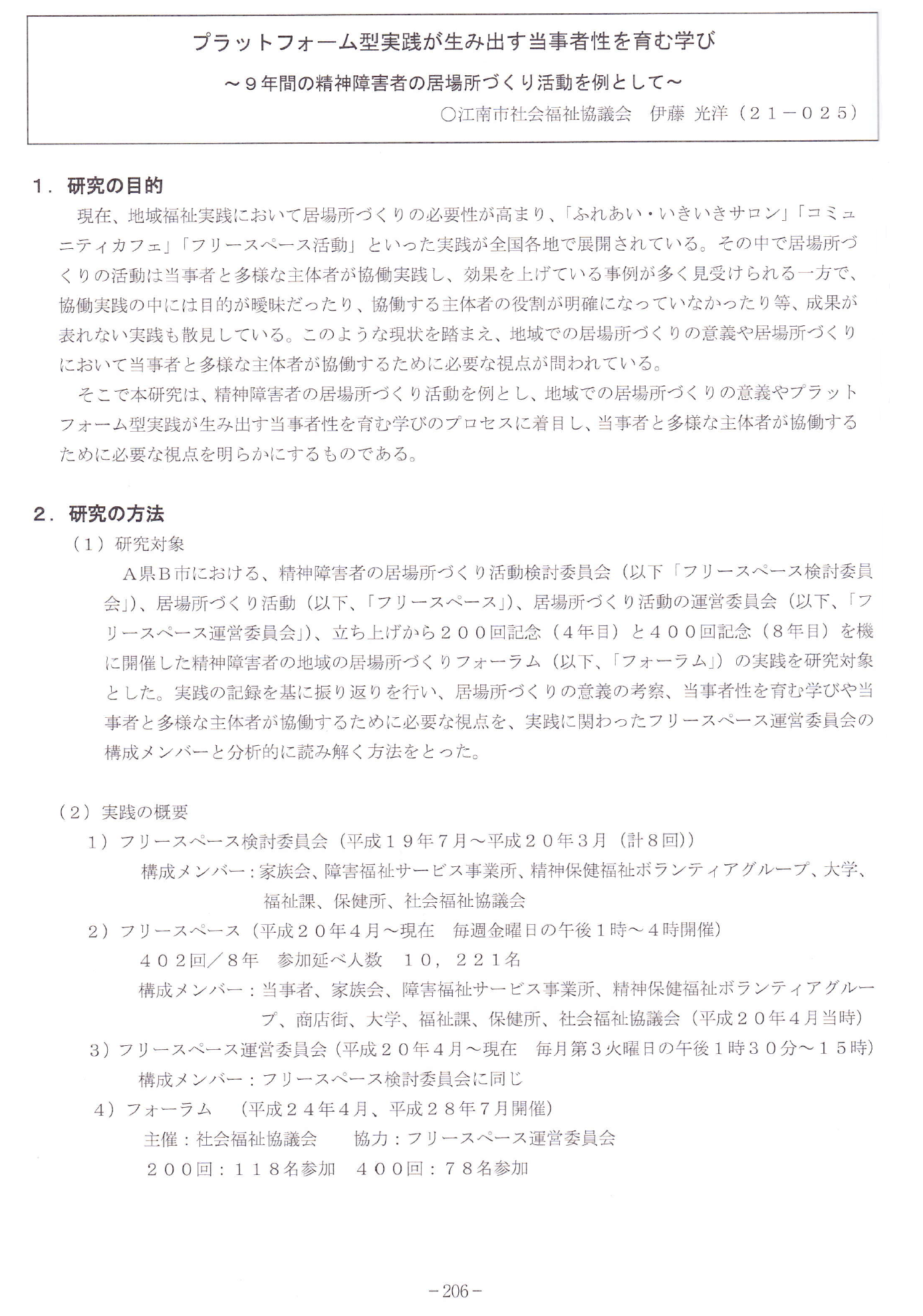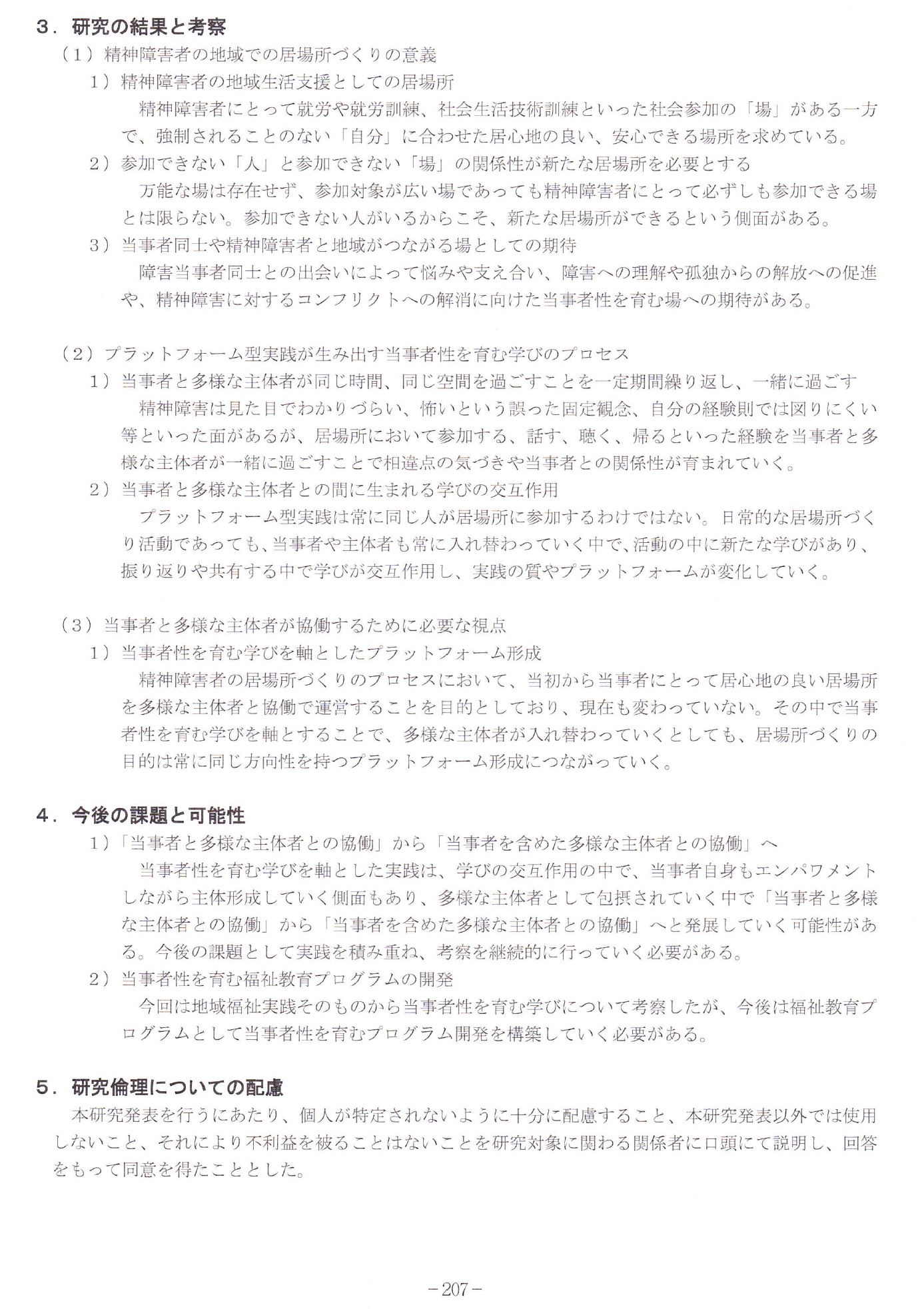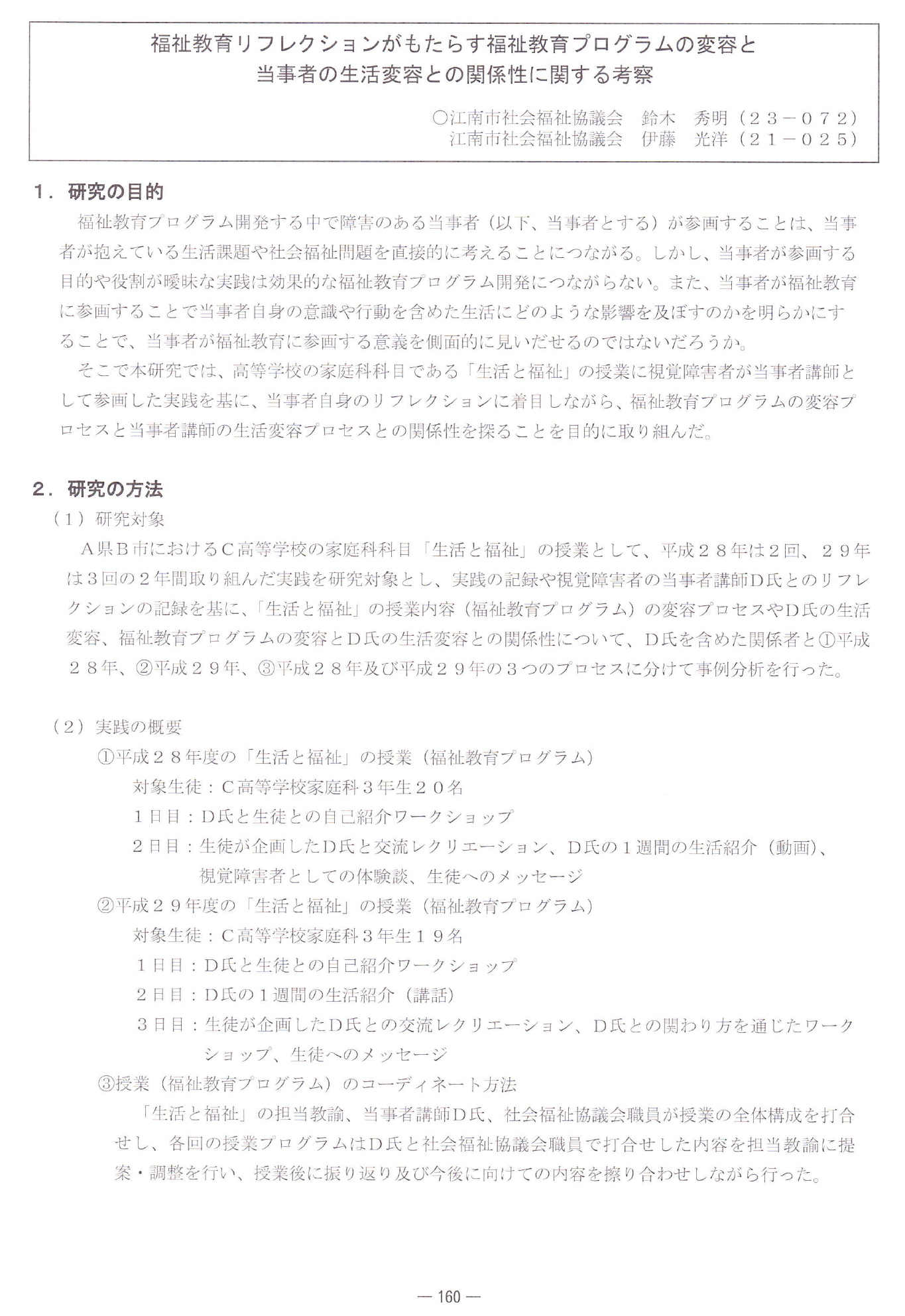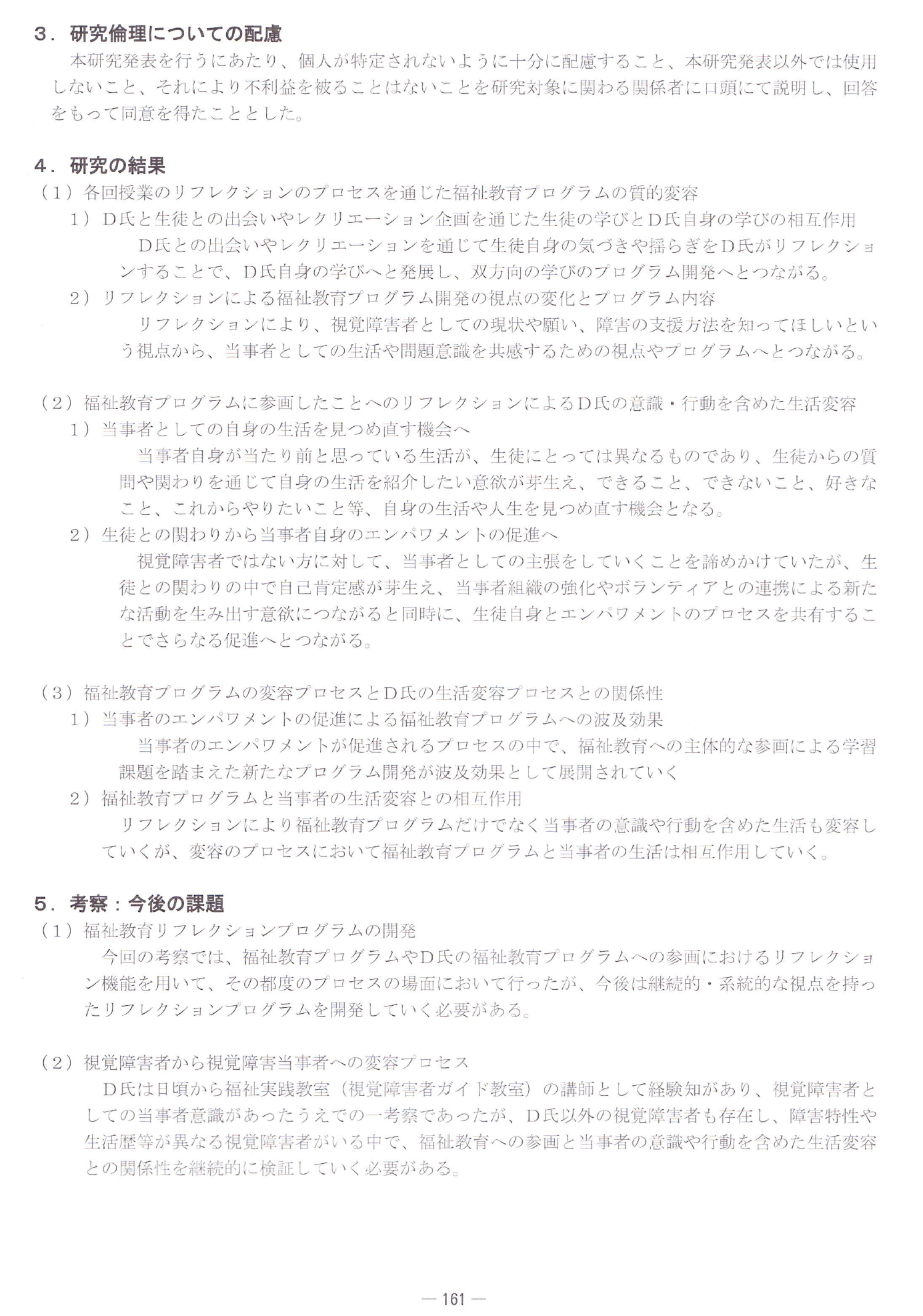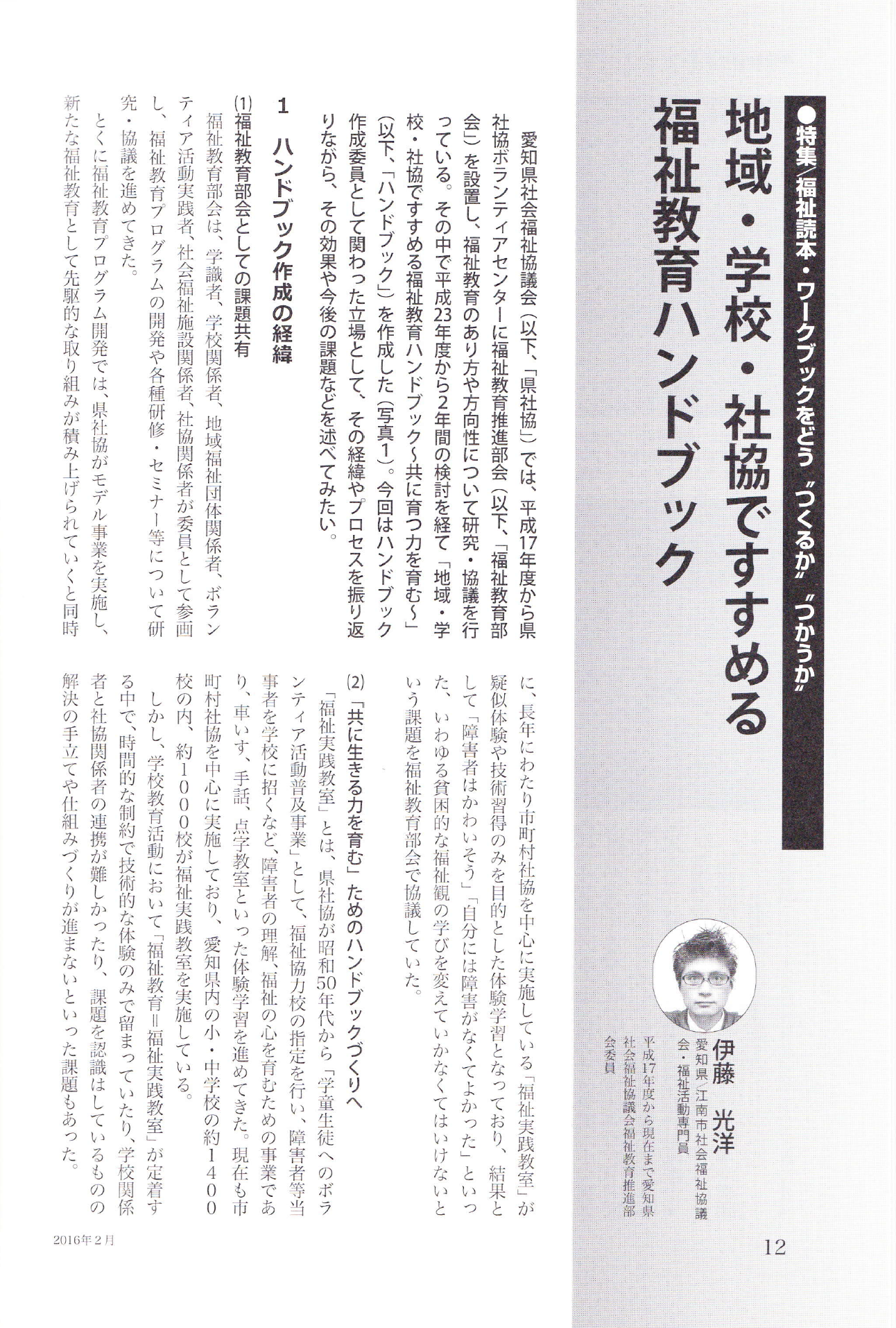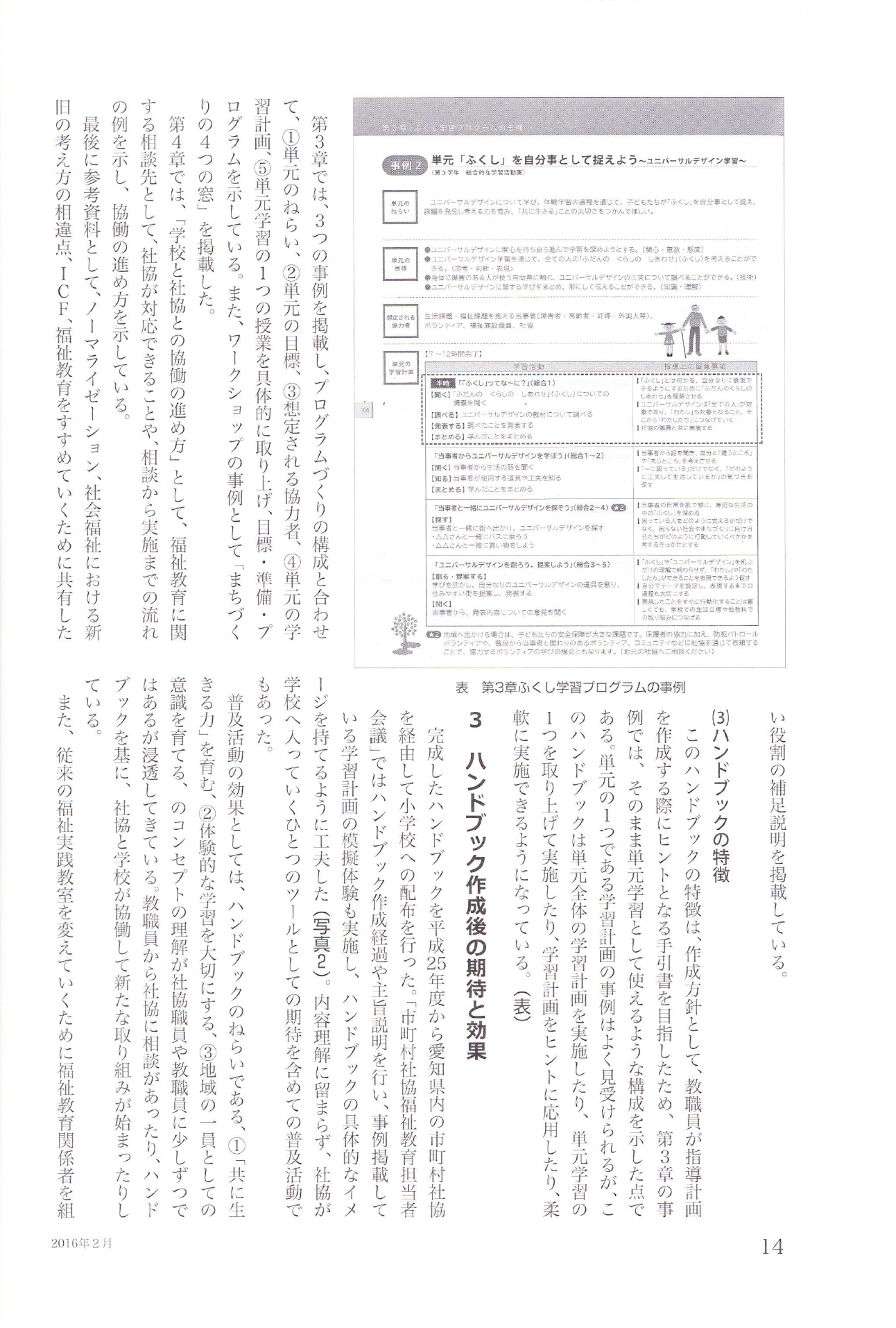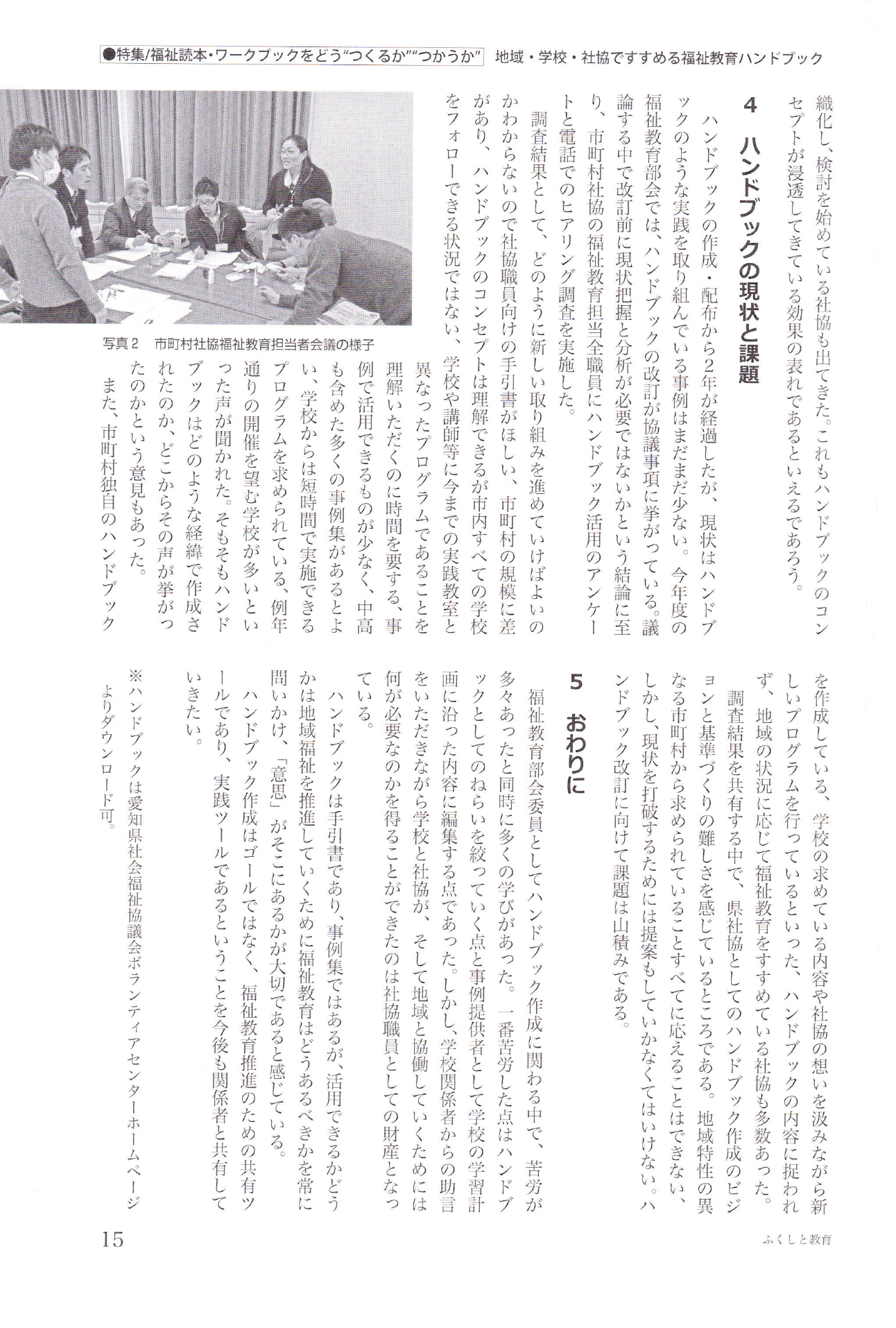〇机の上には、最近買い換えたばかりのパソコンがある。手もとにはノートパソコンとアイパッド、それにスマホがある。それらは常時接続されており、容赦なく多様な情報が大量に入ってくる。必要に応じて、あるいは惰性的にそれらのディスプレイを見つめる日々が続いている。それは、情報量が増大・巨大化するなかで、大容量のデータを収集し活用することが前提となる社会、すなわち「ビッグデータ社会」を有意義に生きたい(生きている)というものではない。情報過多の大海原(おおうなばら)を溺れそうになりながら漂流している、といった姿である。そして、それが何よりも問題なのは、情報を整理・分析することなく、“答”についていろいろと思考することを停止あるいは放棄し、ひたすらひとつの“答”を探し回ることである。人はいま、思考のない探索の時代を生きている。「探しものは何ですか?」「まだまだ探す気ですか?」。井上陽水の「夢の中へ」の歌詞を思い出す。この文章の主語は、筆者(阪野)でもある。
〇情報は大雑把には、①それに対するニーズを認識し、必要な情報の性質や範囲を決定することから始まる。次いで、②多様な情報源や多量の情報量から利用可能なものを確定し、アクセスする。③選択・収集した情報を整理し、分析・評価し、それを新しい情報として編集・組織化して既存の知識体系に統合する。そして、④それによって批判的思考や新たな客観的・論理的思考を促し、ニーズの充足や問題の解決を図る。その際の新しい情報については、新奇性(目新しいこと)をはじめ、具体性や普遍性、社会性や文化性、現場性や歴史性などが重視されることになる。情報についてのこうした常識的な理解でとりわけ重視されるべきは、情報の「編集力」と「新奇性」であろうか。それによってその情報は情報力を高めることになる。
〇筆者の手もとにいま、柴田邦臣(しはだ・くにおみ。社会学専攻)の『<情弱>の社会学』(青土社、2019年10月。以下[本書])という本がある。「情弱」=情報弱者について、おそらく日本ではじめて論じた本である。
〇「情弱」といえば、ネガティブな言葉として、障がい者や高齢者、外国籍住民などを想起しがちである。彼らはその環境や状況のもとで、情報弱者の典型となる。しかしときに、最先端の情報処理技術を活用し、あるいは大仰(おおぎょう)な装置ではなく本人の工夫などによって多様な情報を効率よく、正確かつ迅速に活用することができる(活用している)。それよりも、多くの人は、「『情弱』であったりそう呼ばれたりすることを、徹底的に嫌悪し強迫的に回避すべく、必死にスマホを叩きディスプレイを見つめ続ける」(19ページ)、「情報強迫性障害」とでも呼ぶべき過度の「情報」至上主義にある(35ページ)。本書は、情報に関する脅迫的な恐怖を生み出しているビックデータ社会において、人はどのような存在になるのか、すなわち人間の存在と「生きる」意味を問う。そして、生きることを情報システムによって管理・調整したり、排除あるいは統制したりする「生きることの情報化」や、自らが自立し現代社会を生き抜くためのリテラシー、すなわちツールの利用法=「生の技法」を探る。
〇本書では、「生きる」ことそのものをめぐって、特定健康診査やマイナンバー、介護保険などのビックデータ化の成否や功罪について議論する。本書の核心のひとつである。ここでは、断片的であるという誹(そし)りを免れないであろうが、それらの議論に通底するいくつかの言説や論点をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
テクノロジーの発展が人間の「生きる意味」の追究を求めている
私たちは、テクノロジーが明確な一線を越えつつあることを、より強く認識すべきである。私たちが生きているのは、テクノロジーが有史以来はじめて、人間の存在とその「生きる」意味に隣接し越境しようとしている時代なのである。私たちの身体や生活の逐一(ちくいち)が、情報技術によってログ(記録)され、ないしはサジェスト(提案)されるようになるのは、長い時を待つまでもないかもしれない。研究者や教育者が真面目に「生きる意味」を考えるべきなのは、この潮流をふまえてのことであろう。(181ページ)
ポスト・ビックデータ社会は「生きづらさ」「情報弱者」を生み出す
ポスト・ビックデータ社会(生活世界の情報化が完了する社会。「生きることの情報化」の最終局面)では、どんなに巧みに設計され、どんなに安全に実装され、どんなに善良に運営されたとしても、それは私たちの生を<擬制>し(あまりにも多様すぎる私たちの生を同一のものとみなし)、その<自粛>を強(しい)い、私たちを<適正化>するように機能する。その中で生きる主体を<弱者>とせずにはいられないということについては、他の論点にまして、考察しておくべきである。(193ページ)
情報弱者/強者に関する議論は「情報格差」の問題である
<情弱>という表現は、ある情報を正確に把握したり、情報の背後に隠された意図を見抜けないといった判断力などを揶揄したりしている面は少なくない。しかしそういった力そのものが養われたり発揮されたりするためには、ディバイス(パソコンやスマホ本体とその周辺機器・ハードウェア)やメディアを使ったり学んだりできる環境や条件が揃っていることが大前提になることは疑いもない。本質的には、情報にかんする「強者/弱者」については、個人の生まれながらの資質や、何らかの努力の結果だけではなく、社会環境の方がむしろ重要になる。情報弱者/強者にかんする議論は、情報にかんする社会的な格差(「情報格差」)の問題として、先ず考えられるべきである。(35、36ページ)
「自立」に必要な自己決定には「自己の主体」化が肝要となる
自立のために必要なのは、「自分についての情報を自分で所有したり、自分のこと(情報)を、自分に納得いくかたちで決める」という<力>である。つまり「自分についての真理」を自らの理性で判断し語る<力>が、自らが生きるための<技>として必要である。(141、142ページ)
主体なき自己がありうるか、理性なき市民が存在しうるか、他者理解なき共存や共生が到来するのか。自己を配慮する用意のないものが他者や世界に配慮できるとは思えない。(145ページ)
「生の技法」には徹底した理屈・論理・考察を必要とする
<生の技法>において重要なのは、すでに情報社会に蔓延し、今後さらに増殖していくような、安易な同情や共感といった感覚的だったり本能的だったりするものではなく、むしろ徹底した理屈、論理、考察である。今、社会的な弱者とされてしまう人も、現在、将来の<情報弱者>も、直面しているのは社会的に構築された問題である。だから、その社会的な問題に感性的に反応するのではなく、冷徹に問題構造を把握し、限られた中でも論理的に回避したり克服したりする意識の中にこそ、生き抜く技――<生きる技法>――が生まれるのである。(198、199ページ)
〇ビックデータ社会で多くの人は、自らを情報の活用主体と位置づけ、情報強者をめざしている。しかし、その社会では、社会的・経済的・文化的発展が実現する反面、情報や生活の管理による人間疎外の促進や社会統制の強化が進んでいる。例えば、個人情報保護法(「個人情報の保護に関する法律」、2003年5月施行)やマイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、2015年10月施行)は、公権力が単なる行政手続きとしてのそれをはるかに越えて、すべての個人情報を丸裸にし、プライバシーを侵害する「残酷な使命」(102ページ)をもっている。めざすところは計画通りの、巧みな方法によるビッグデータ社会の構築である。
〇そのような認識のもとで、柴田はいう。障がい者や高齢者は必ずしも情報弱者に直結するものでもないが、社会的弱者であるとされている人たちのなかにこそ、情報弱者と化す多くの人たちを開放する手がかりがあるかもしれない(29ページ)。ビックデータ社会を生き残る「技法」は、はるか昔から深刻な社会問題に直面し、それゆえ自らの存在をかけて「自立」と「共生」のリテラシー=「生の技法」を鍛え上げてきたとりわけ障がい者のリアリティのなかにあるのではないか(184ページ)。そうしたことについて探究する際の基本的なもののひとつは、人間はその「価値」の有無ではなくただ「存在」することに「固有の意味」がある、という考え方である。。
〇続けて柴田はいう。命がかけがえがないのは自明であり、他者との相互理解が必要なのは不変であり、社会が多様であることは公理である(202ページ)。多様性とは、私たちが自らの価値観では想像も想定もできない存在の連鎖である。異質の現前(現に存在すること)こそが、その本質である(204ページ)。そもそも人間は、それ同士を比較するにはあまりにも多様すぎる、比較し選別することのできない存在である(160ページ)。人間の生は「多様で、予想外で、それゆえ自由にあふれる」(181ページ)ものである。それ故に、障がい者や高齢者などの態度や行動の「価値」が共有できなくても、理解できなくても、いや「わからない」からこそ、そこにはただ存在する「固有の意味」がある。私たちが共存し共生するために必要なのは、尊重と忍耐だけである(205、206ページ)。
〇筆者(阪野)はいま、共存や共生についての「尊重」と「忍耐」に加えて、望んでいる事柄が実現するという証拠に基づく「確信」(すなわち、別言すれば「信仰」)をもつことの必要性と重要性を感じている。そして、その証拠の科学的探究と思考が続くことになる。付記しておきたい。