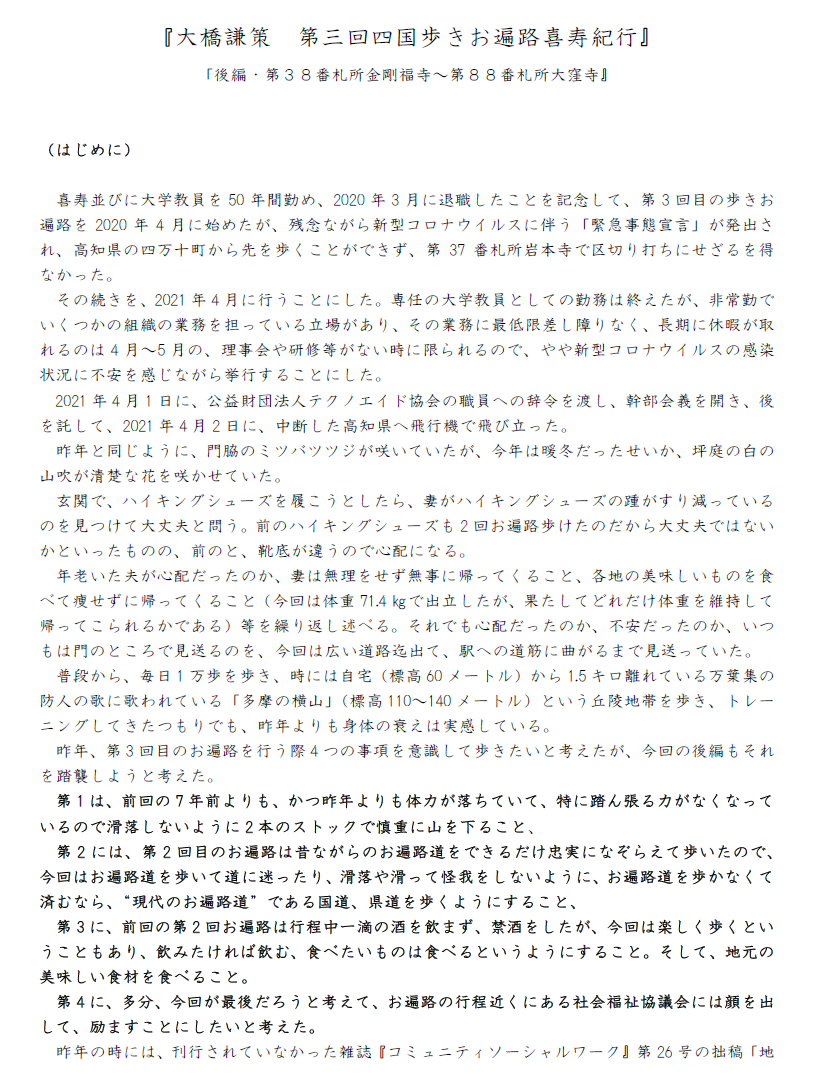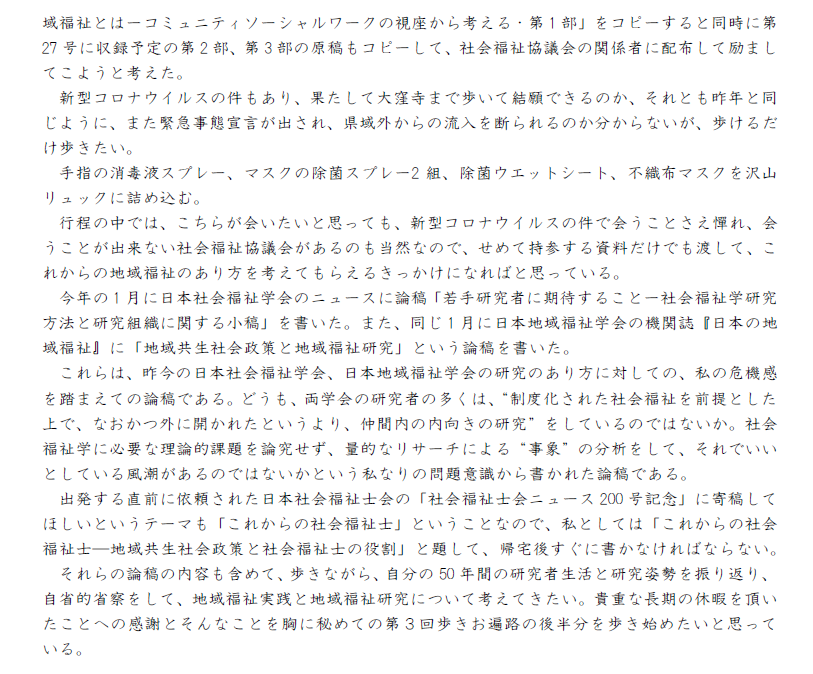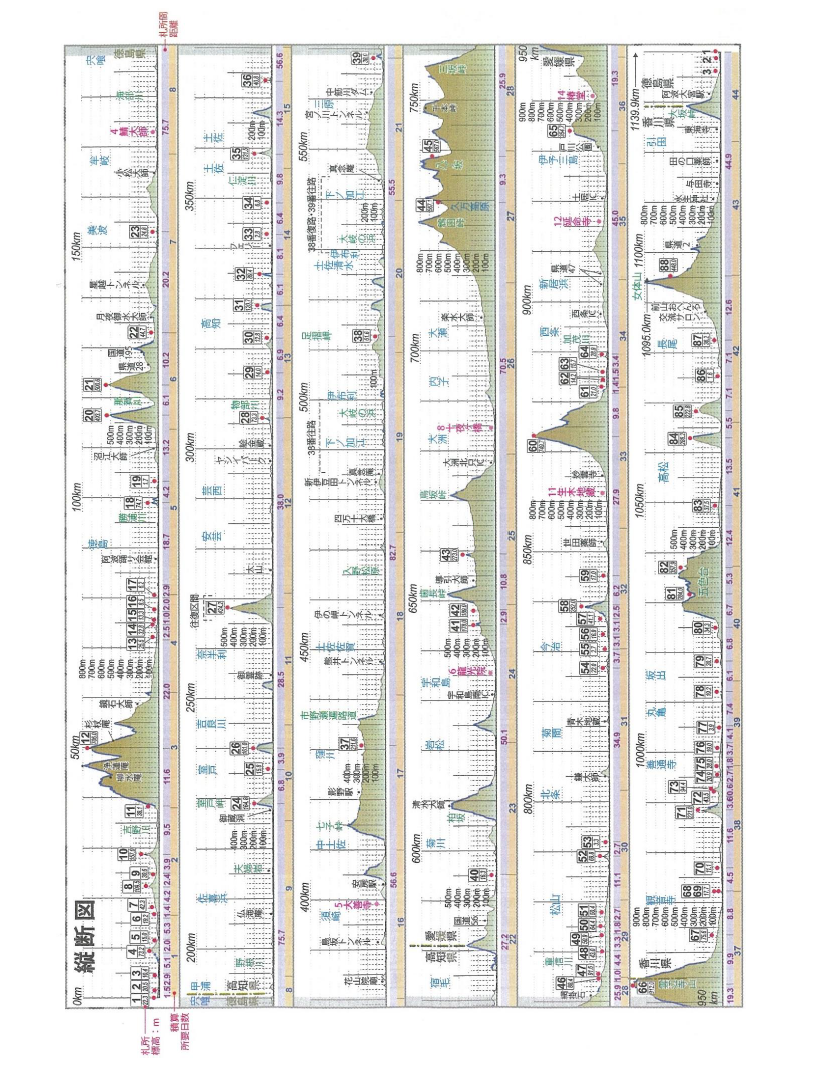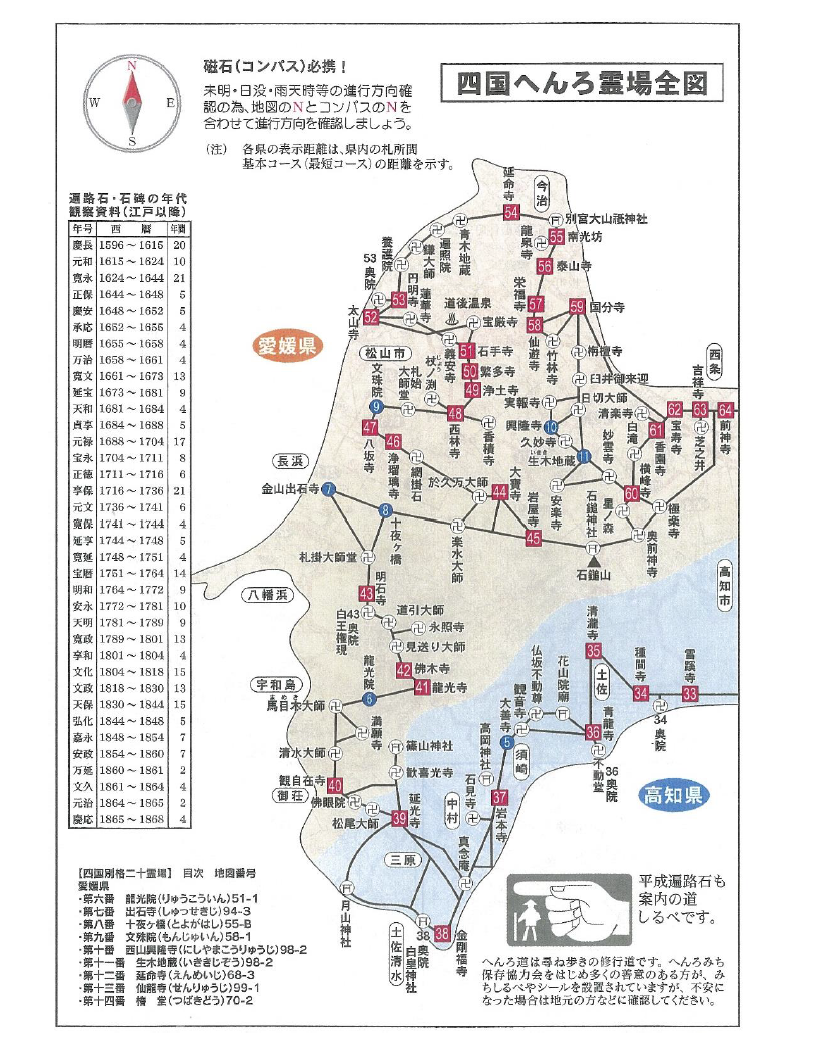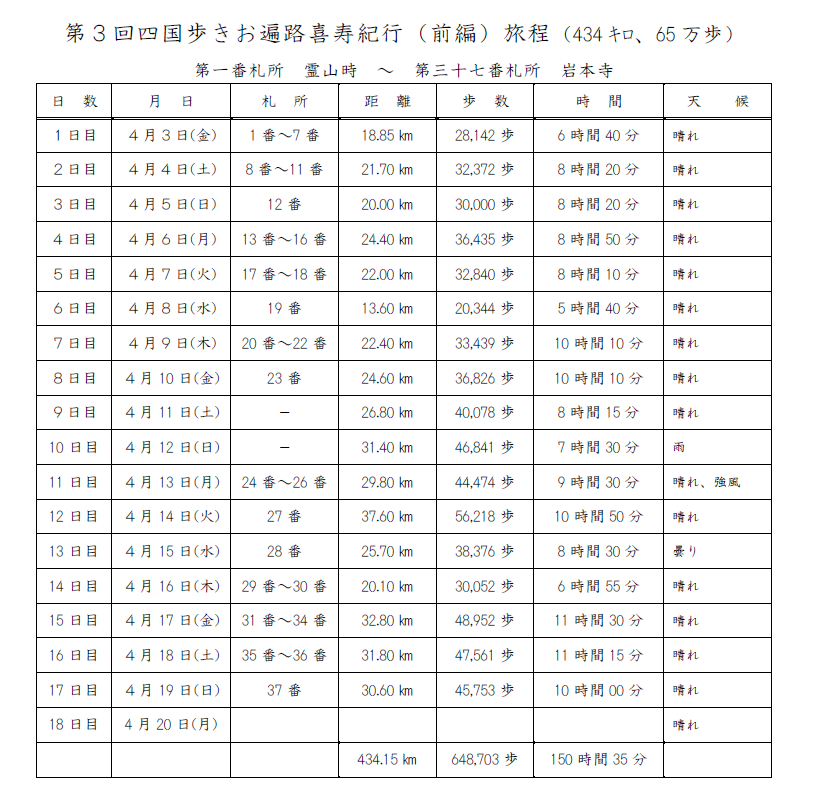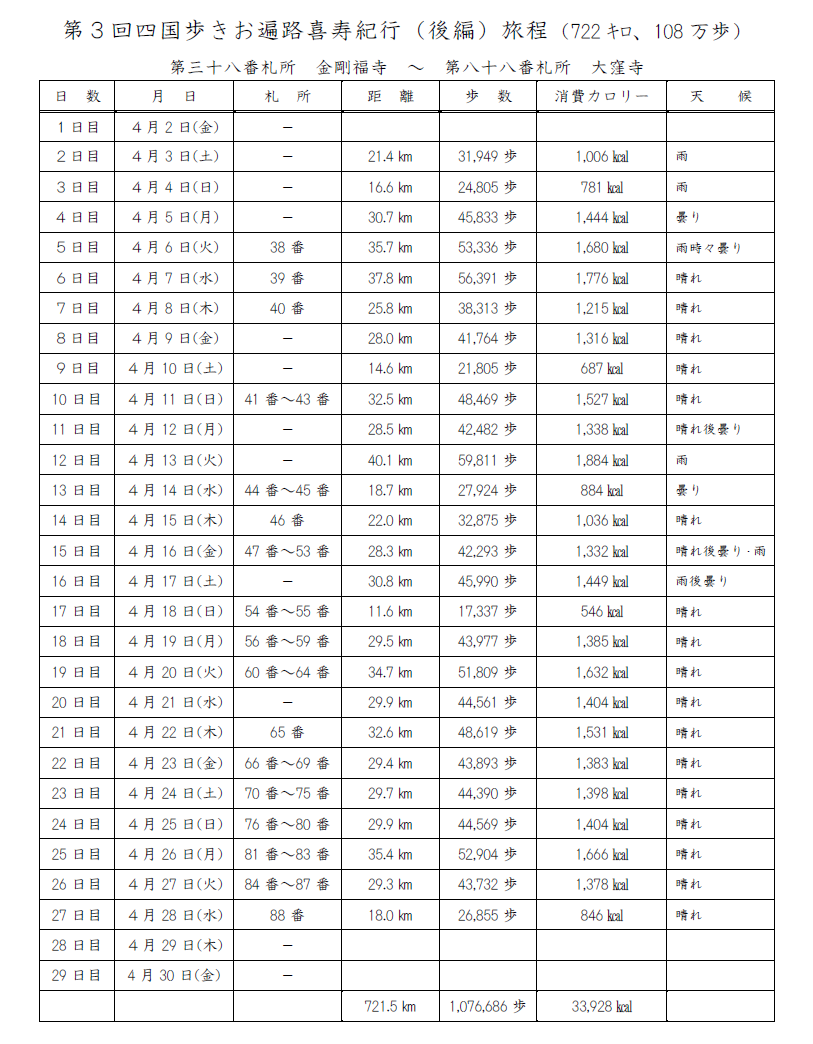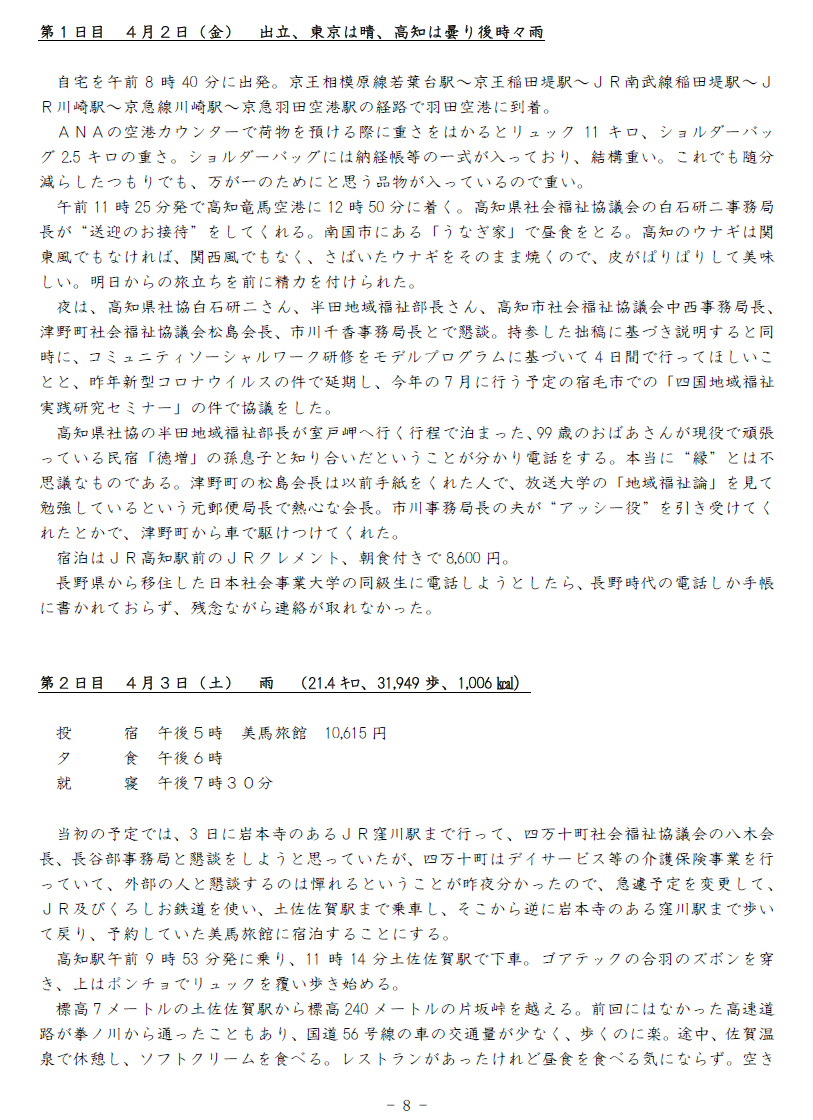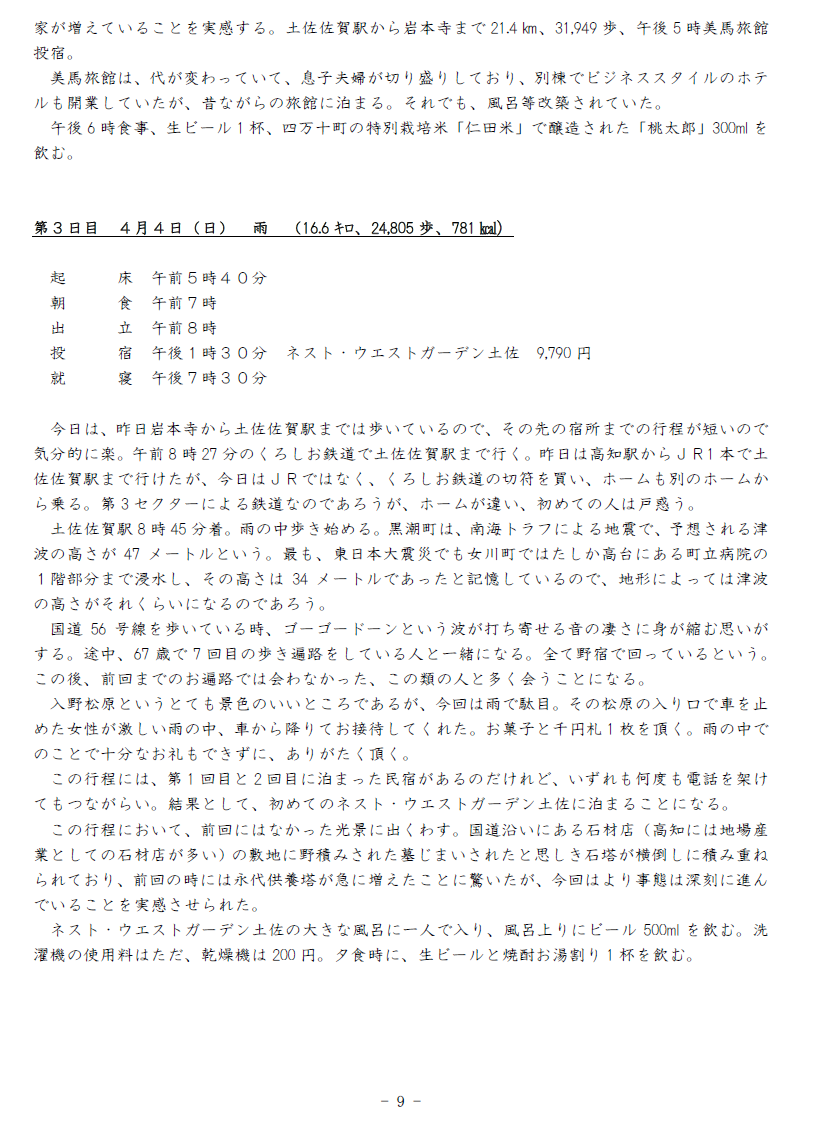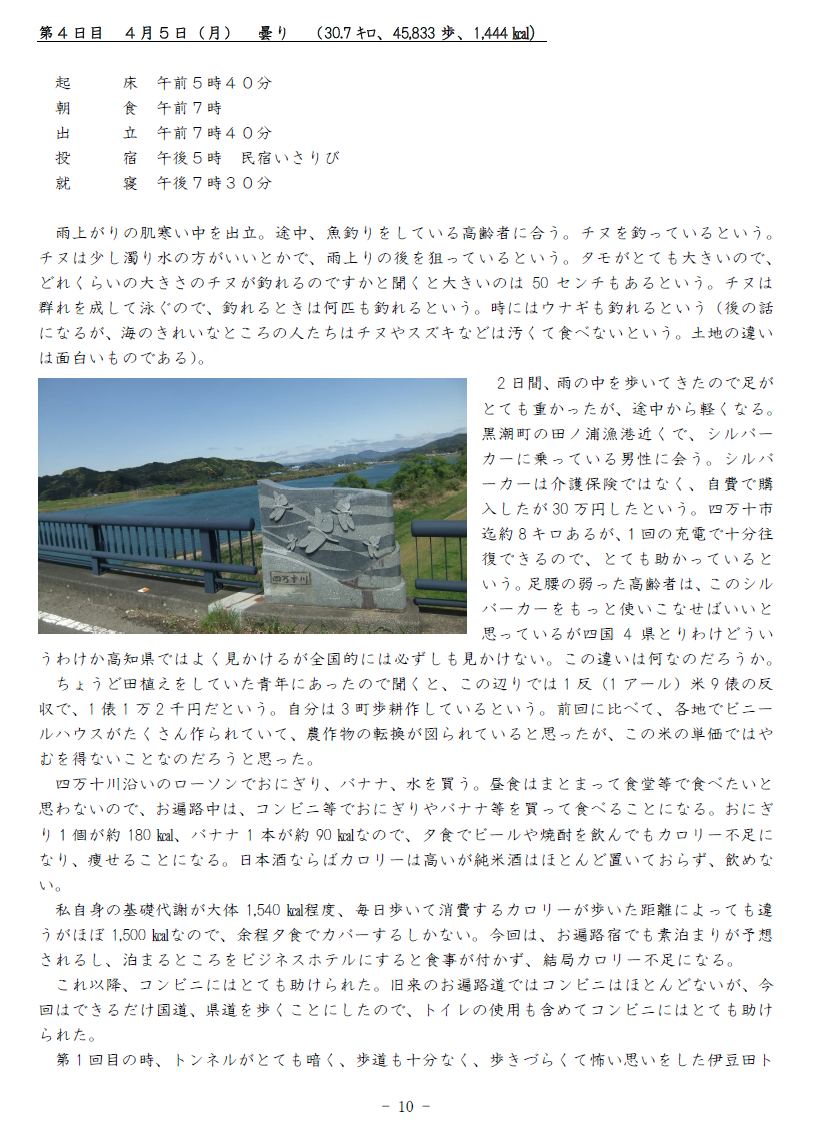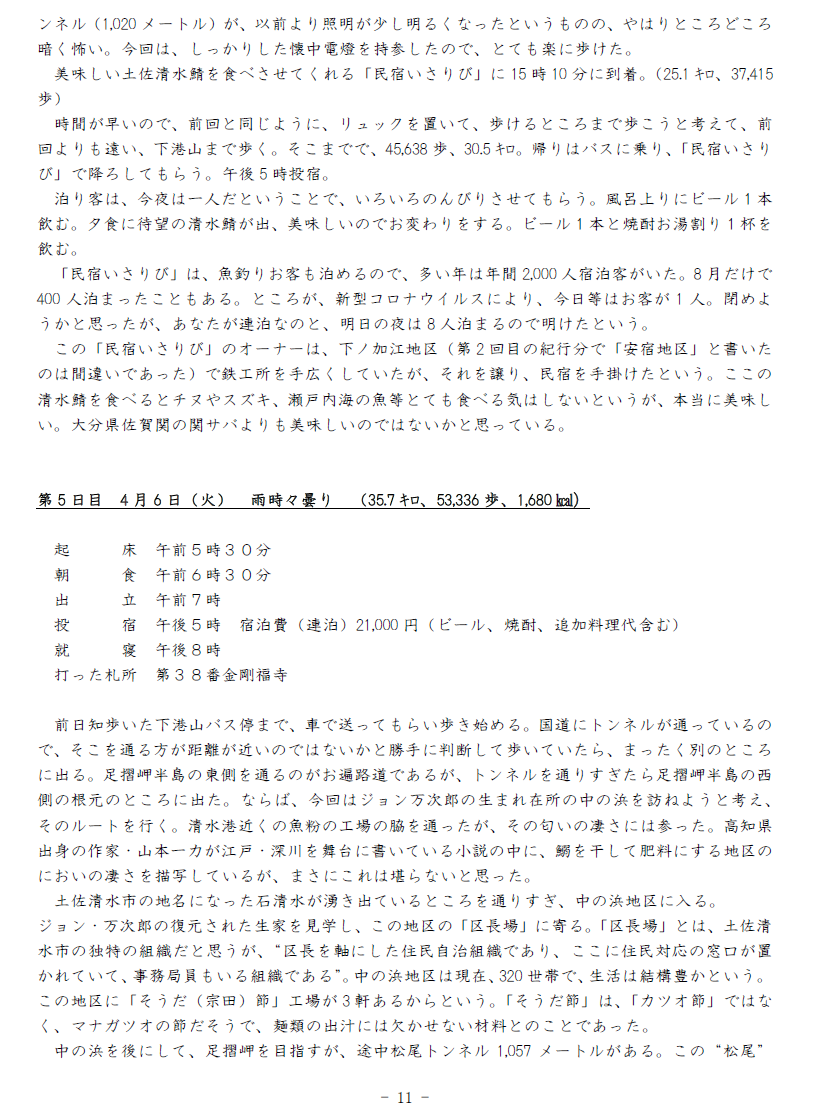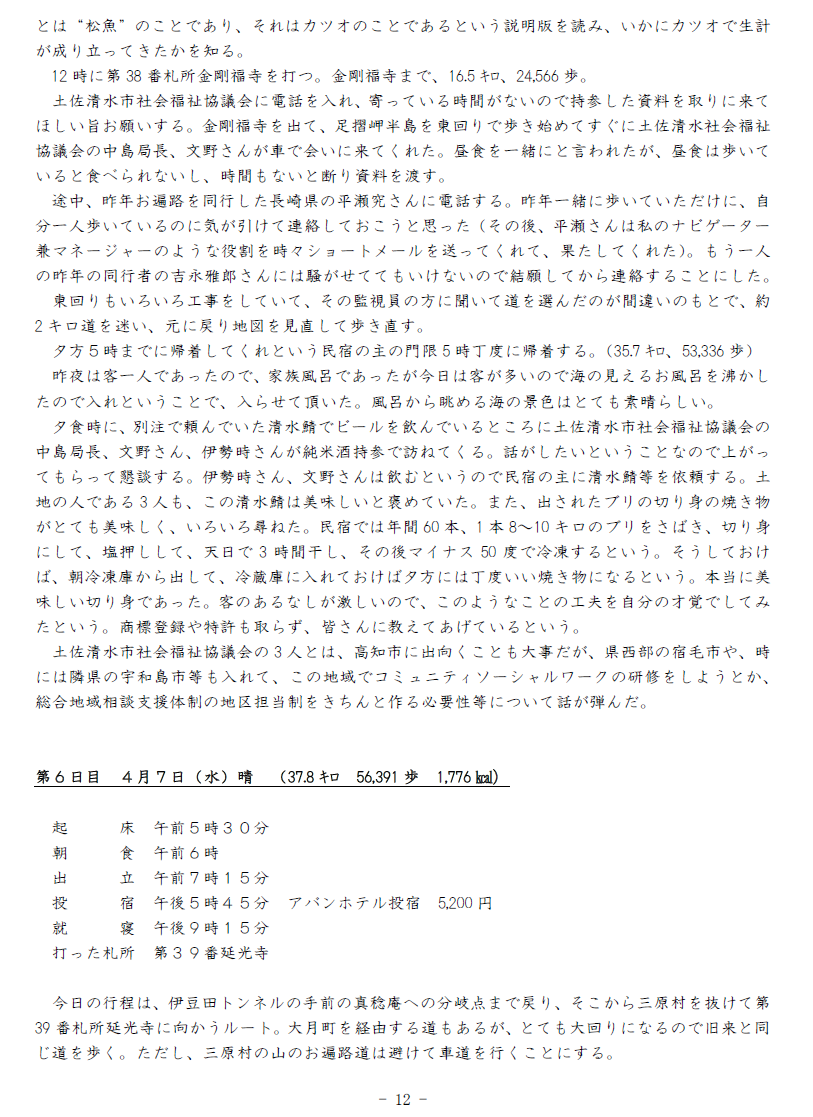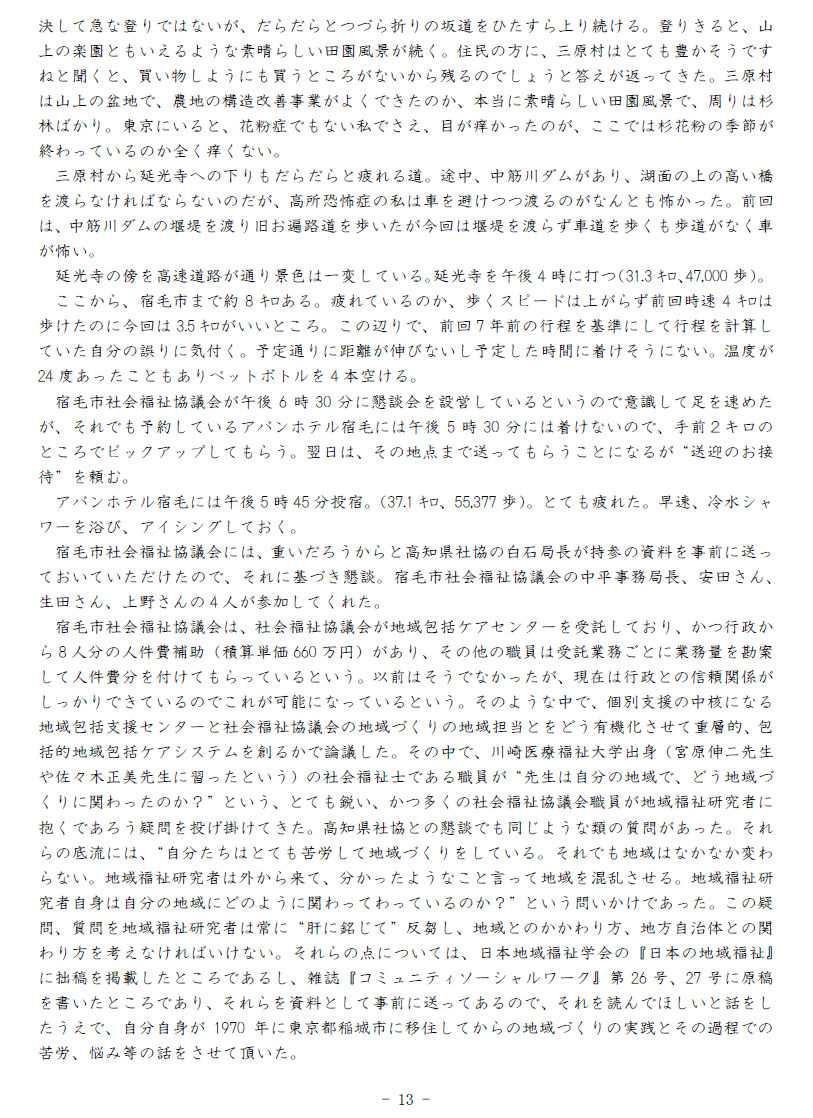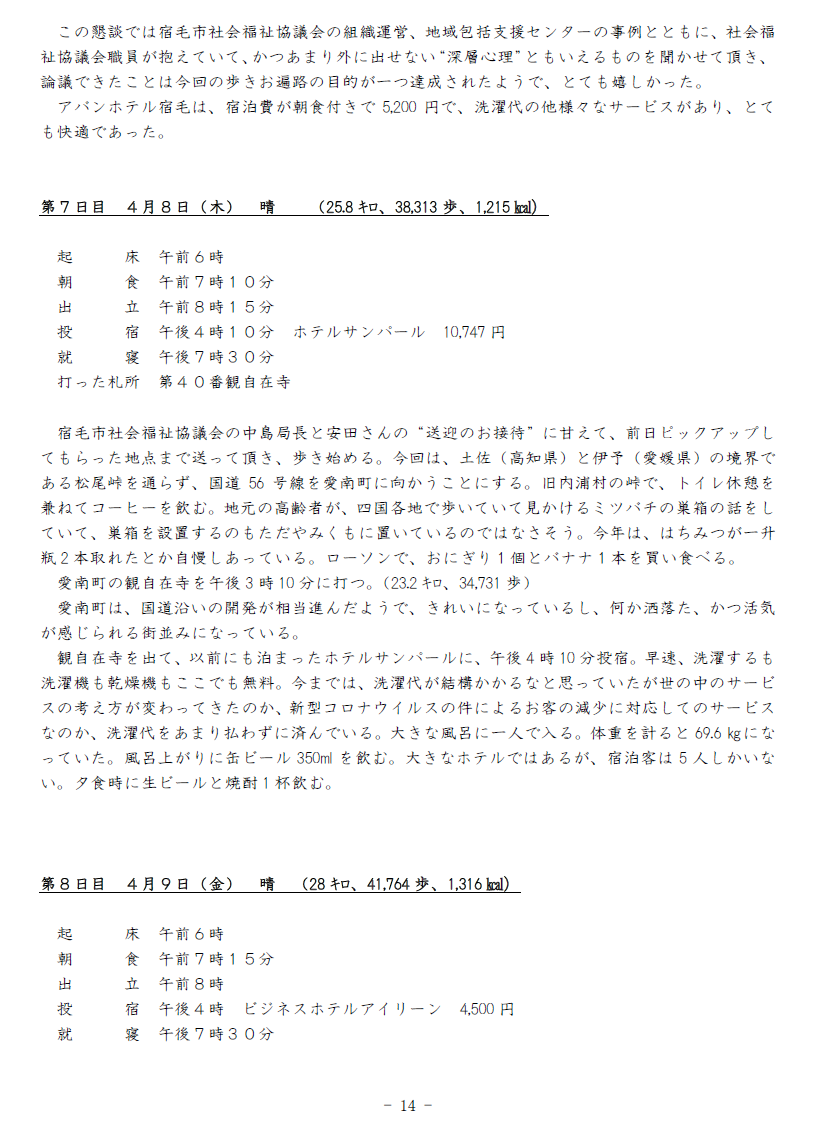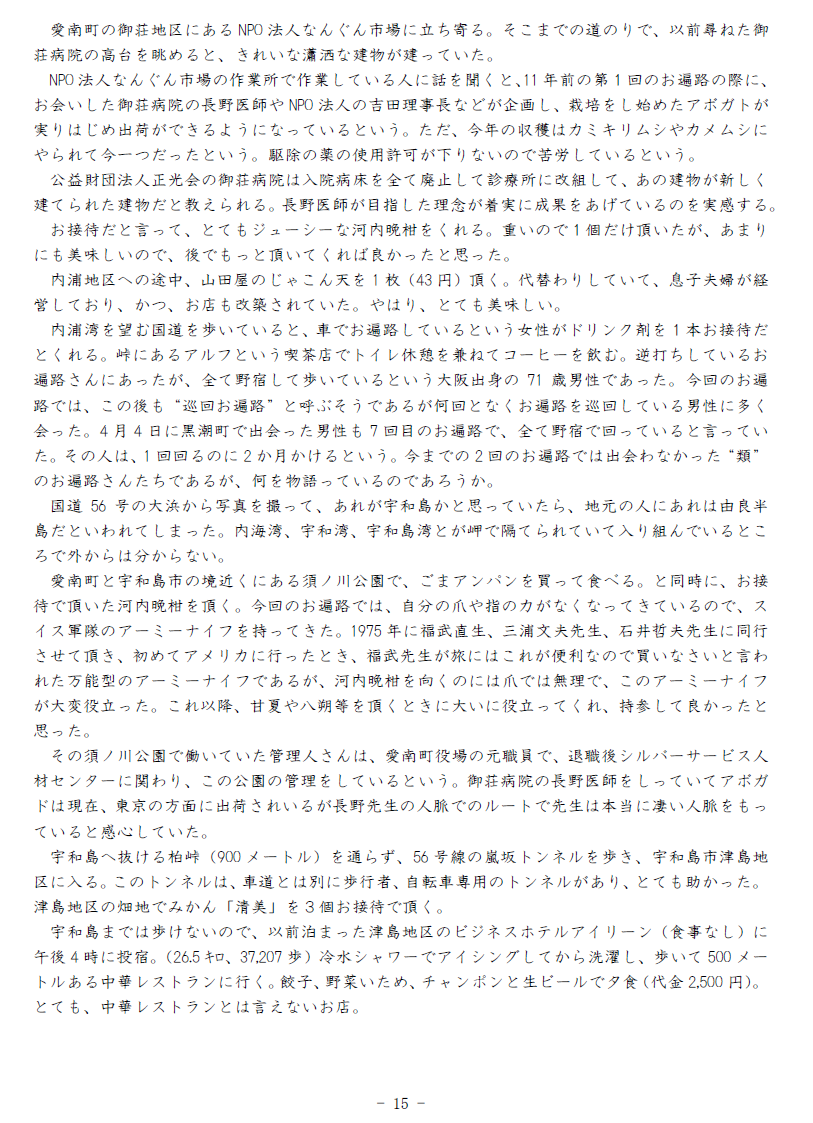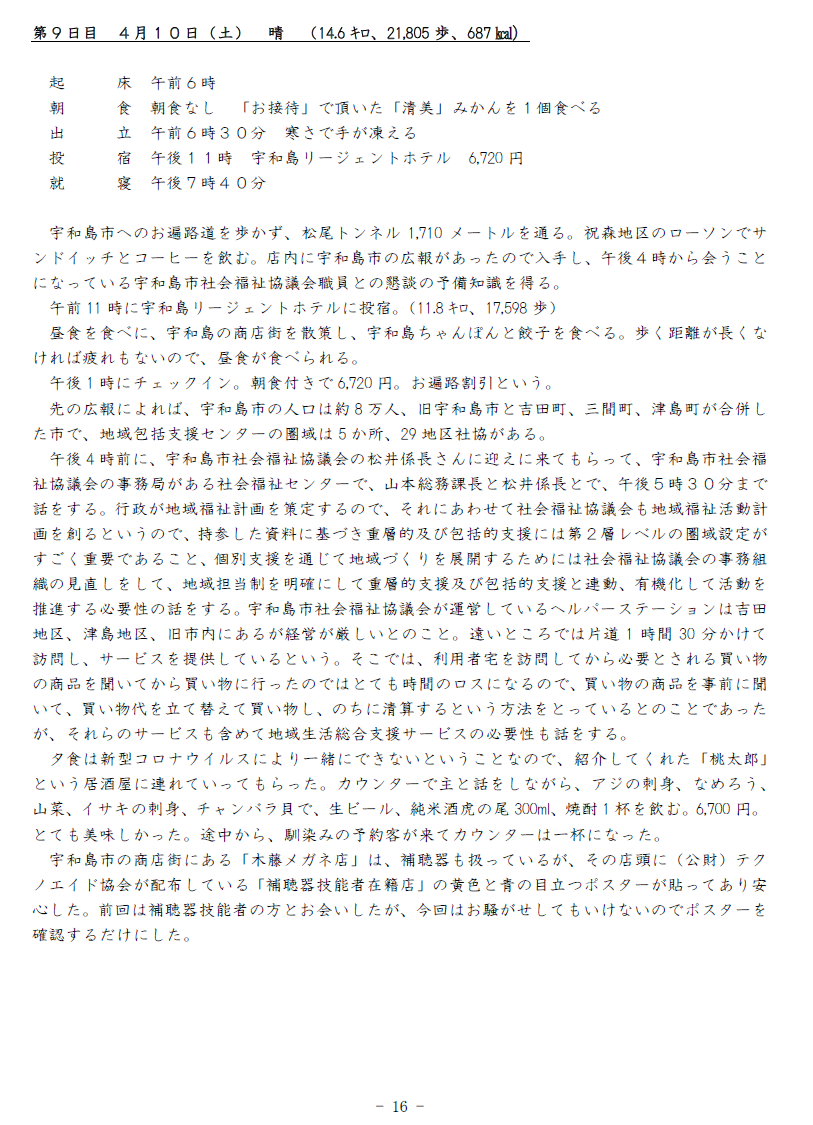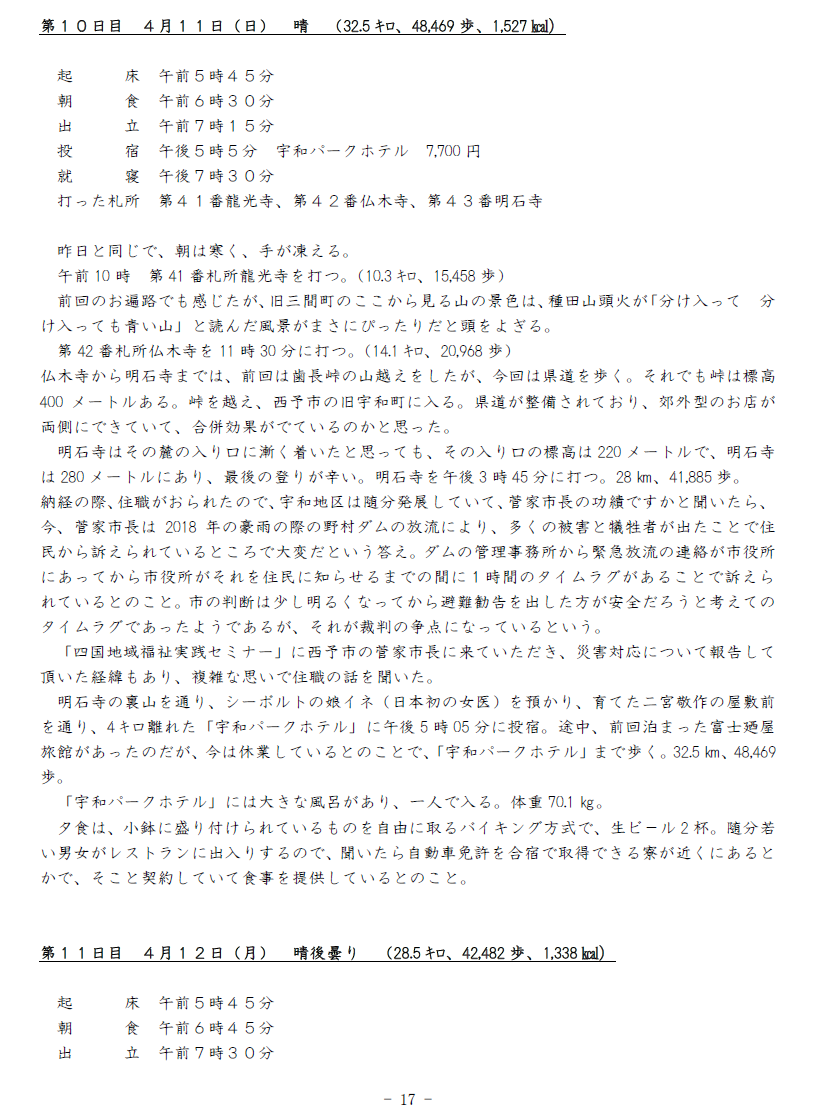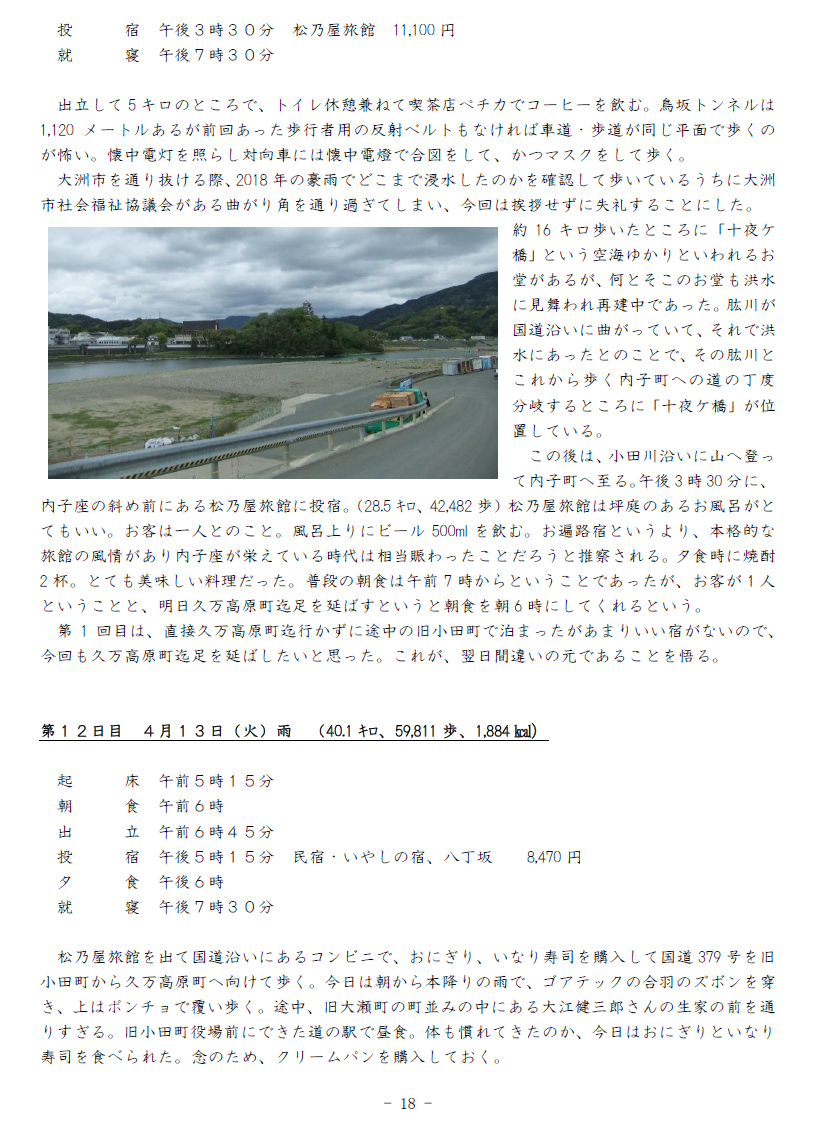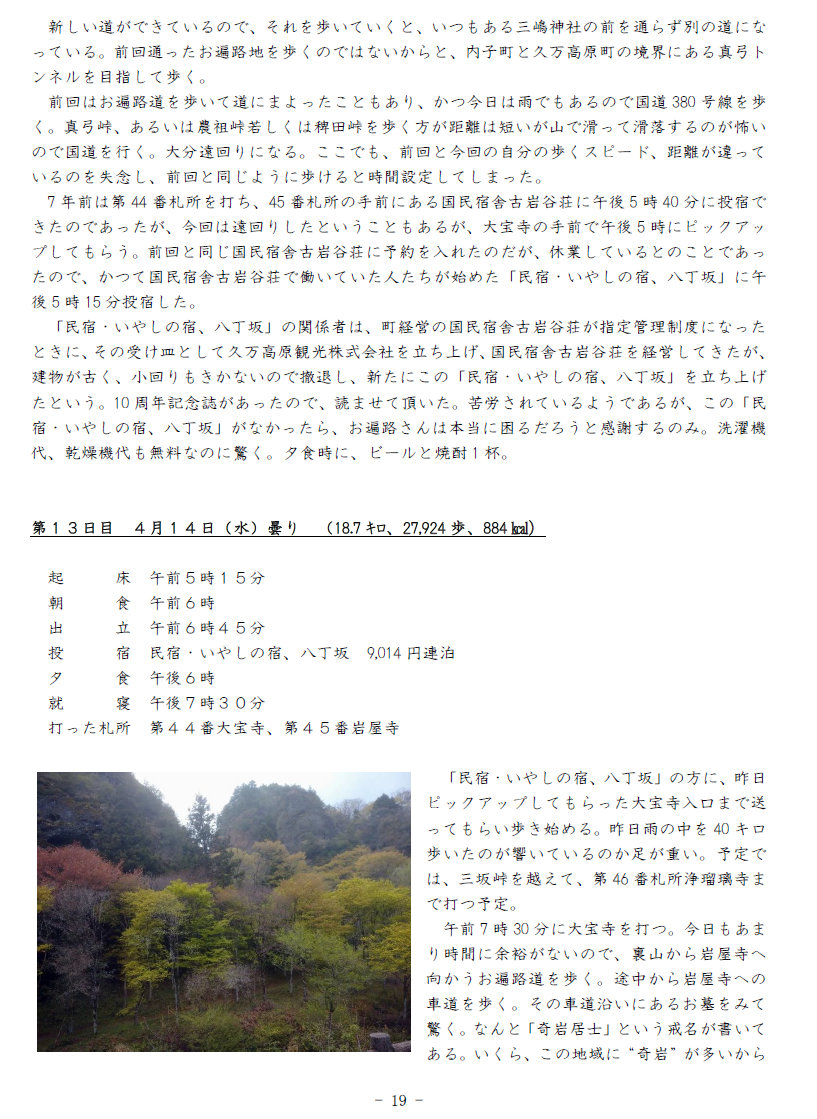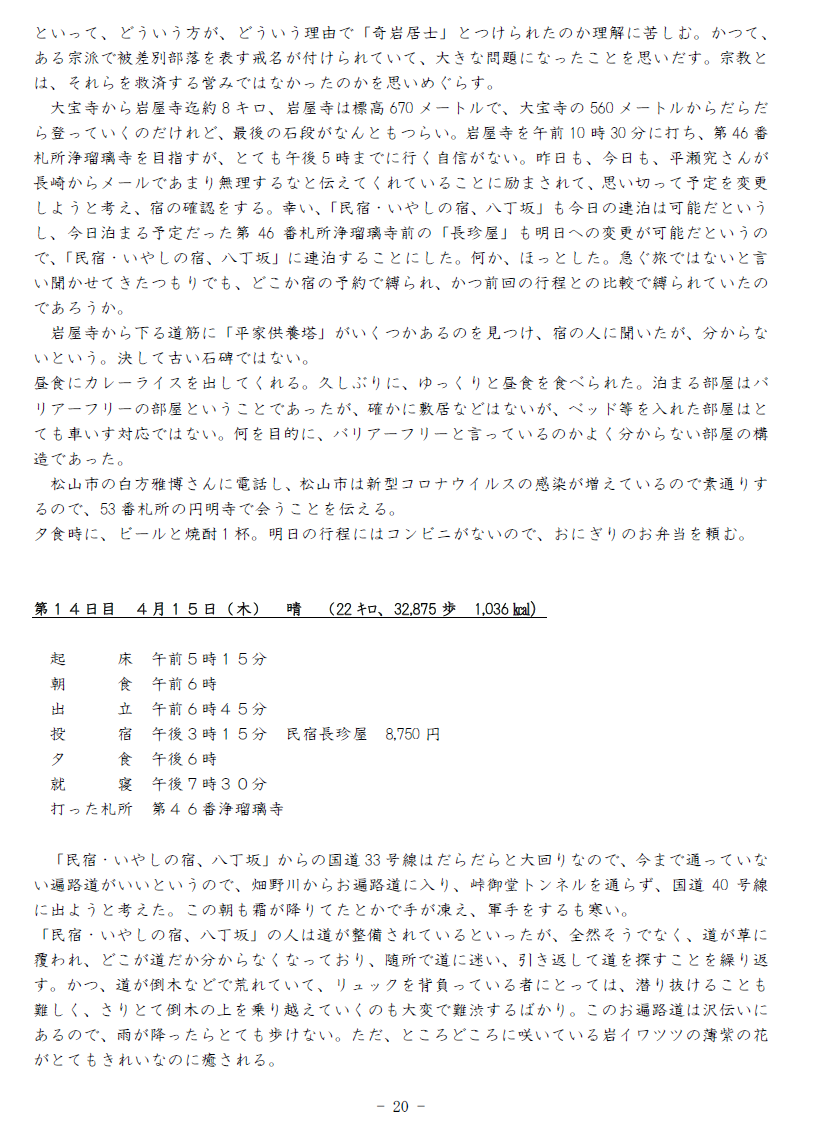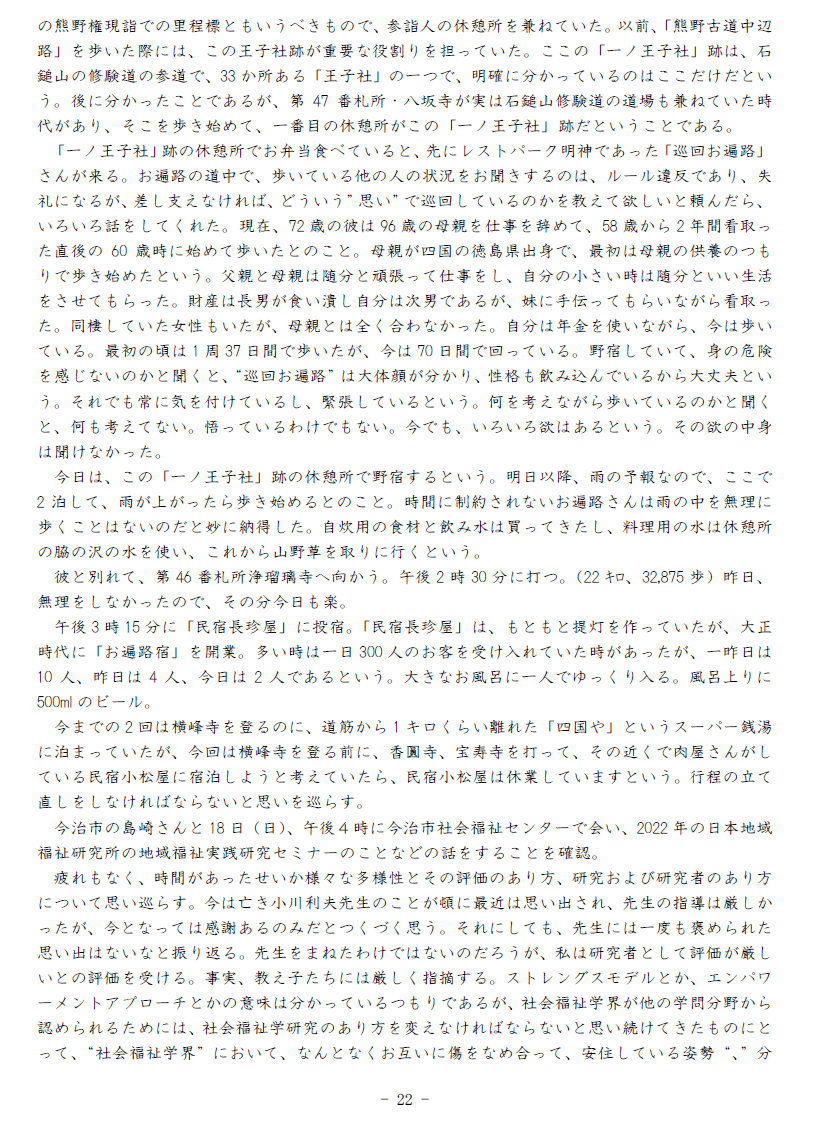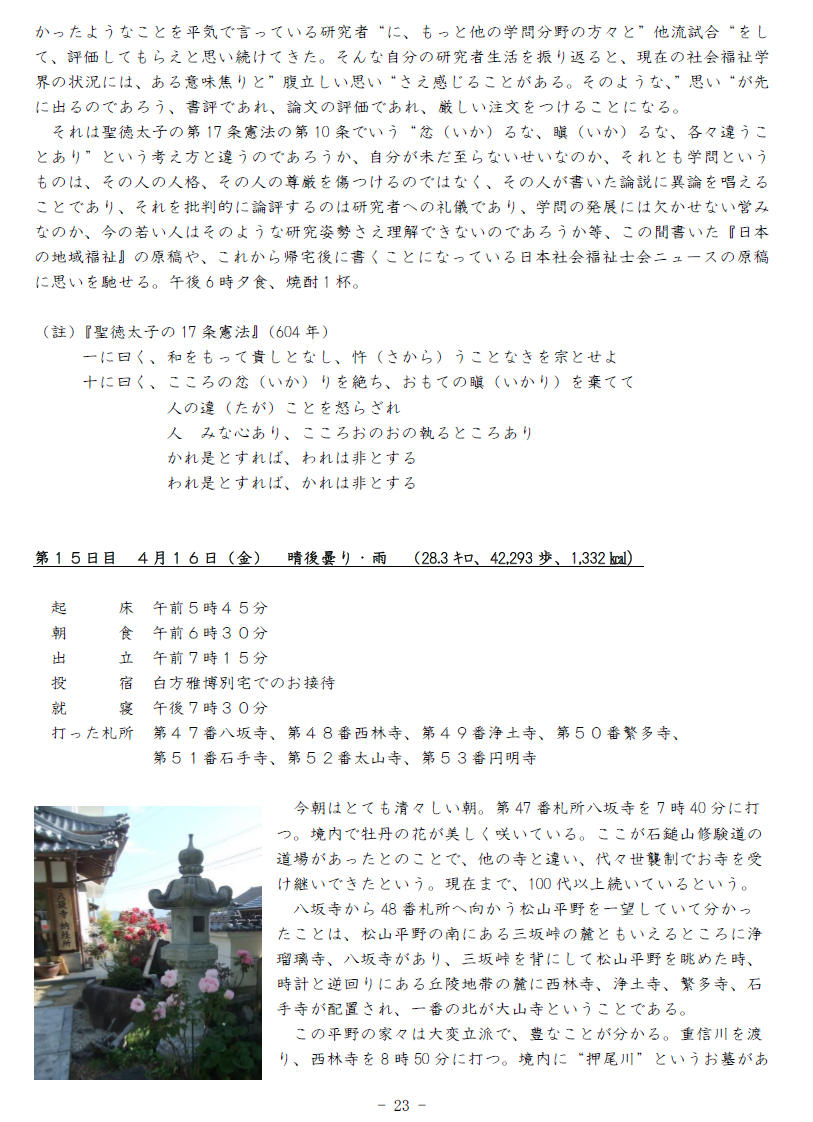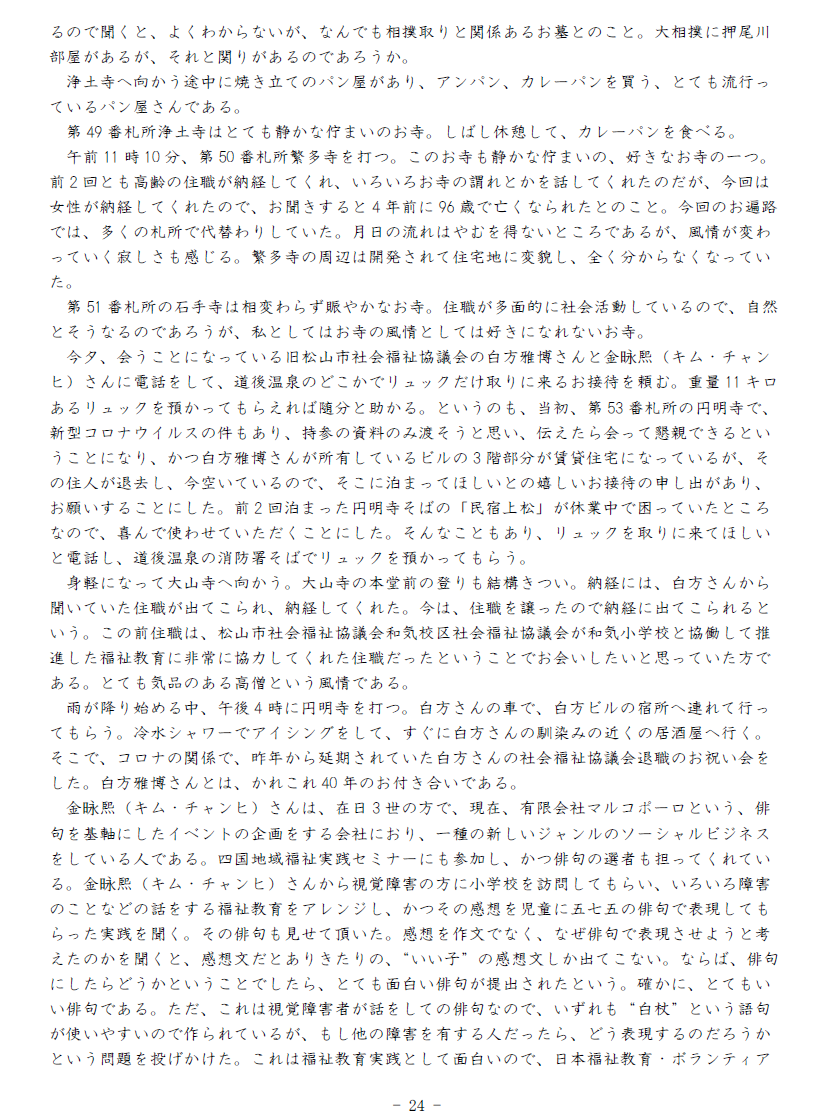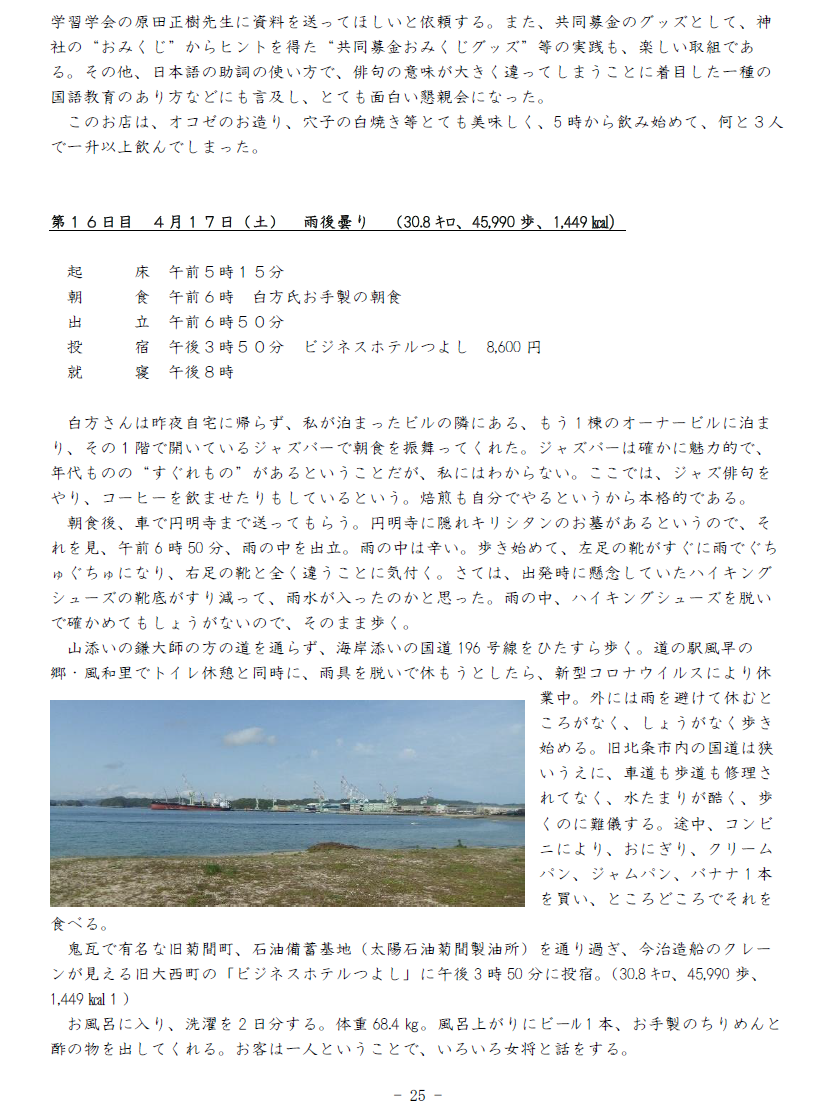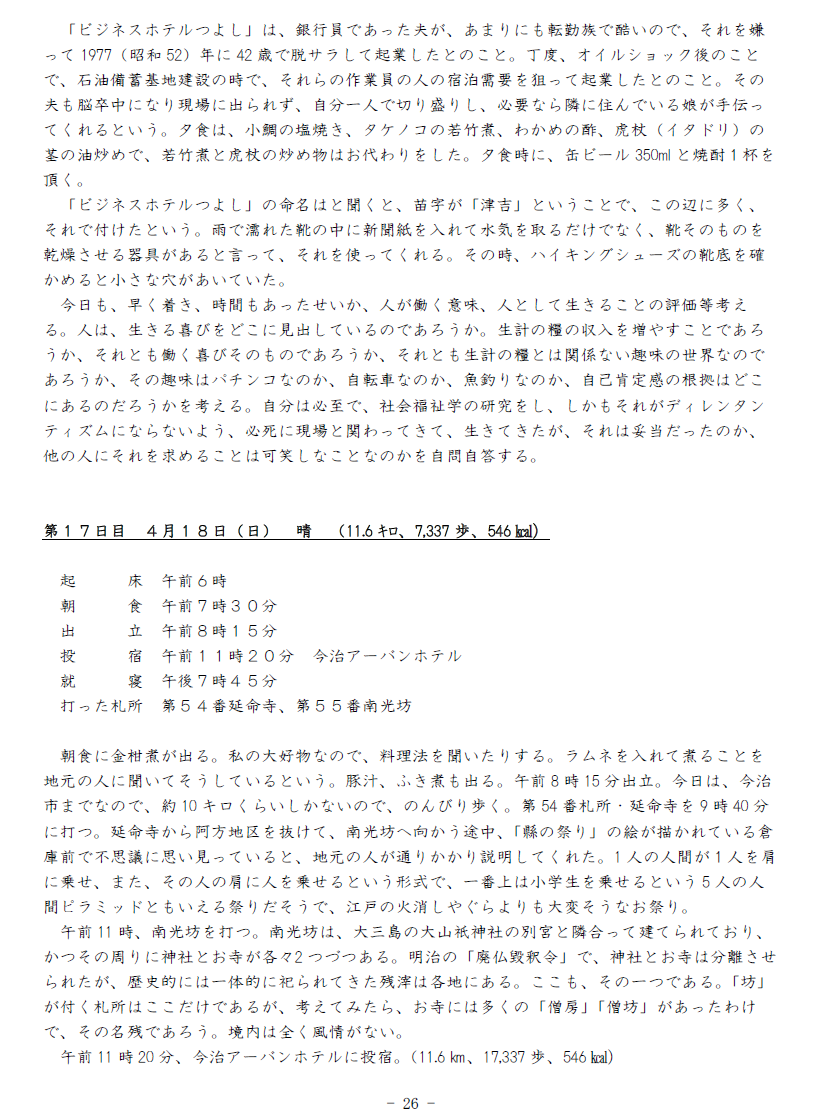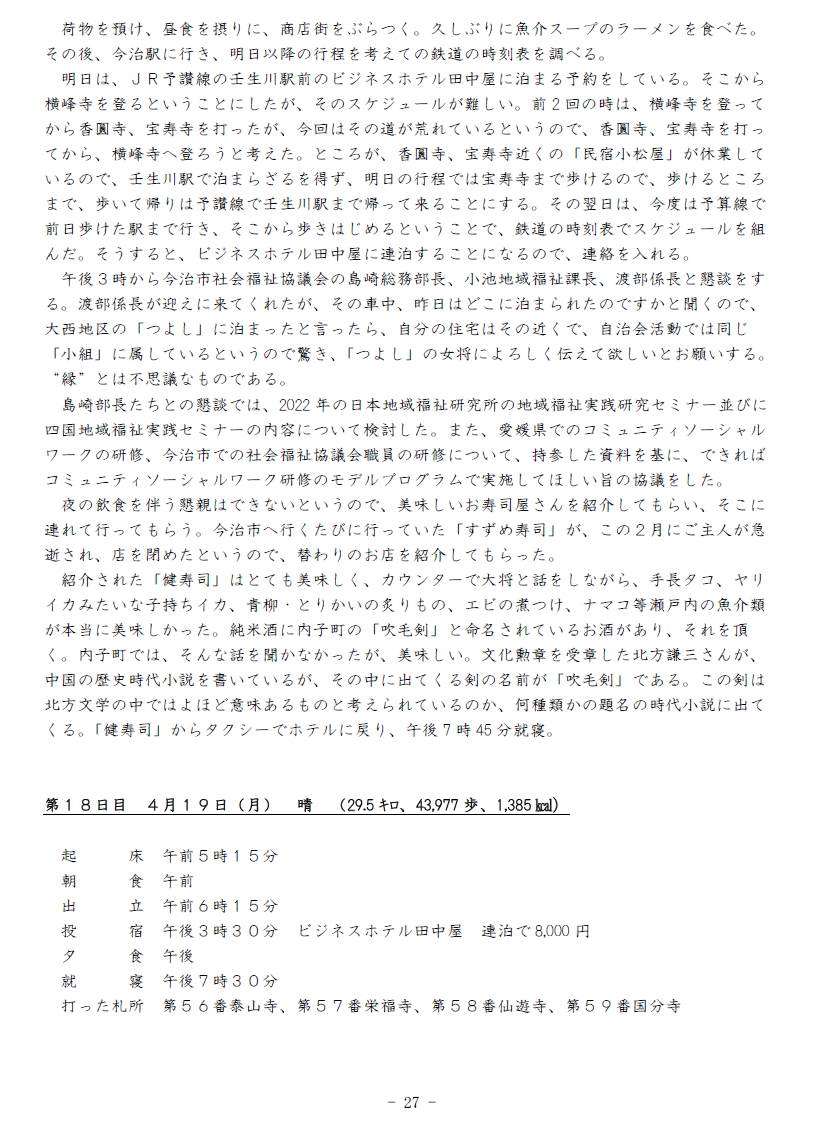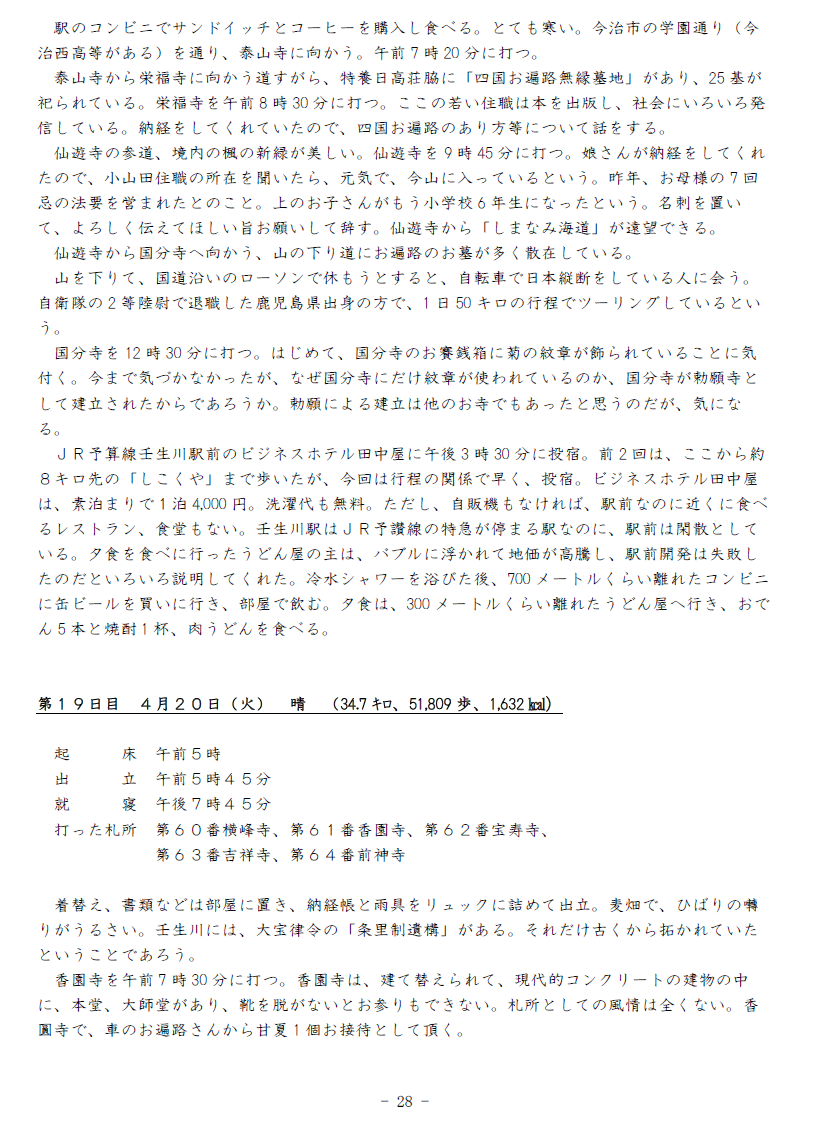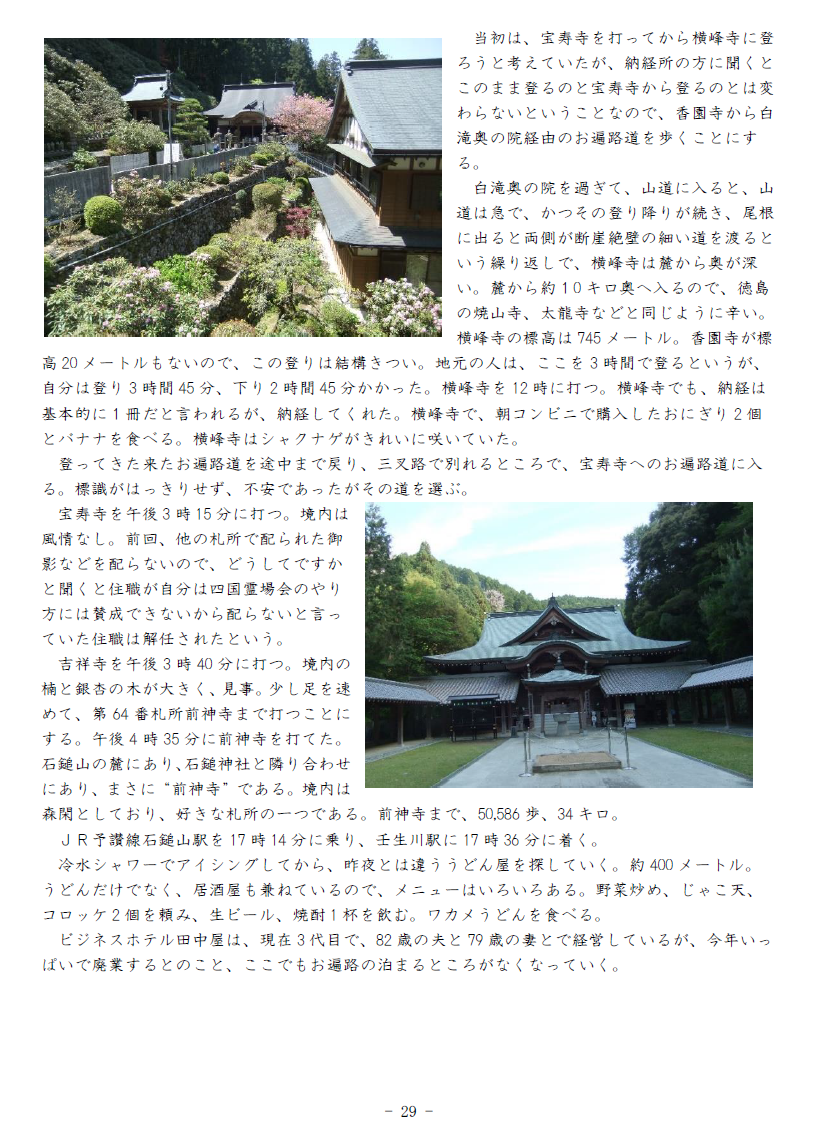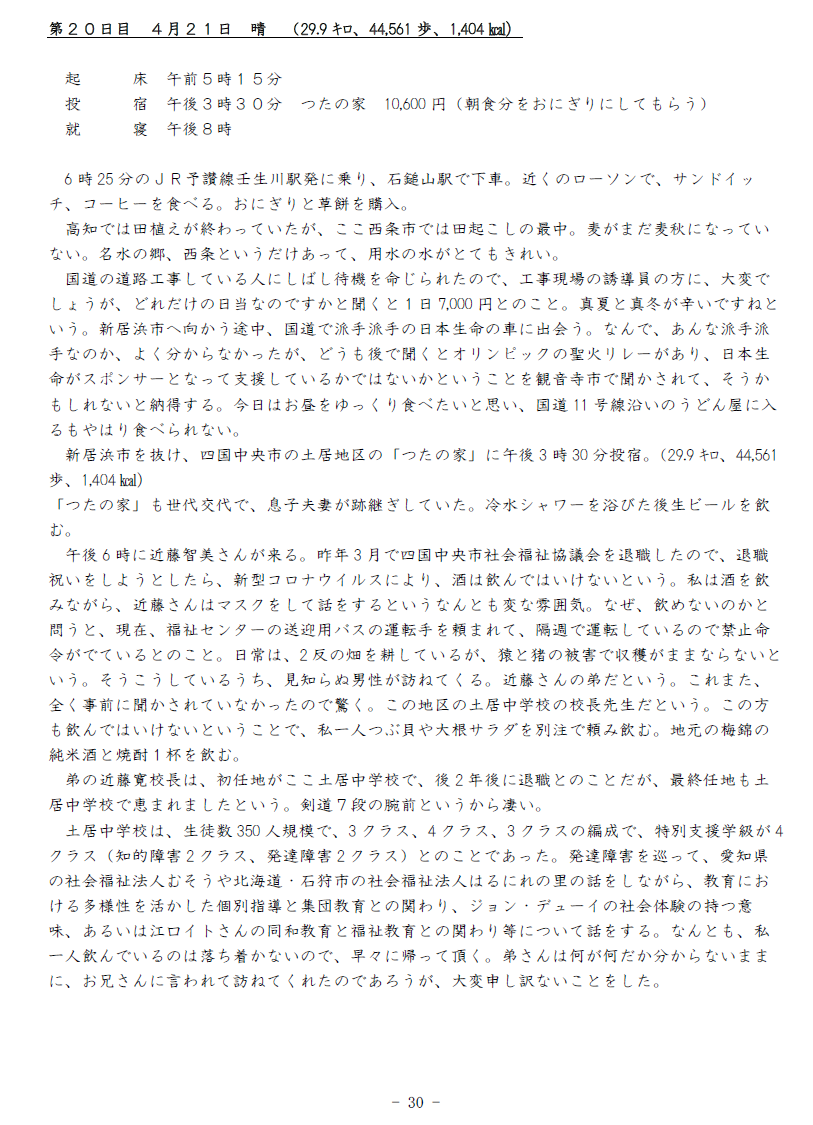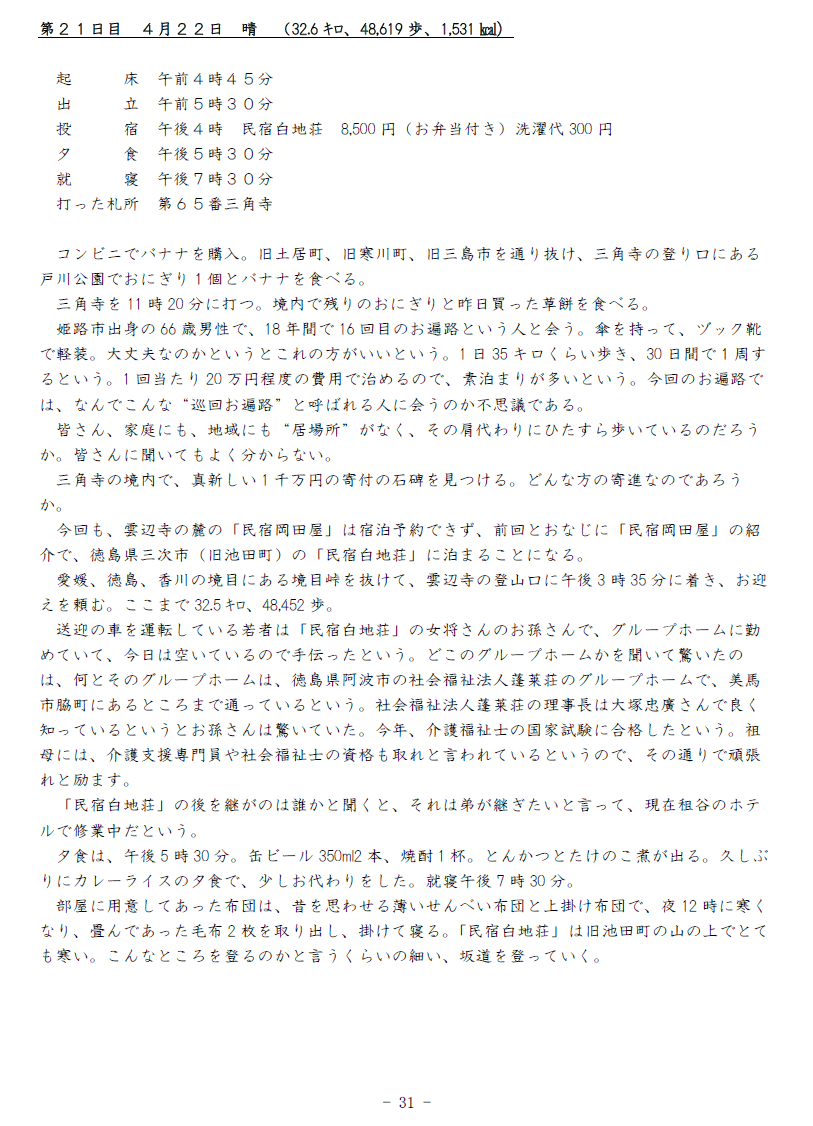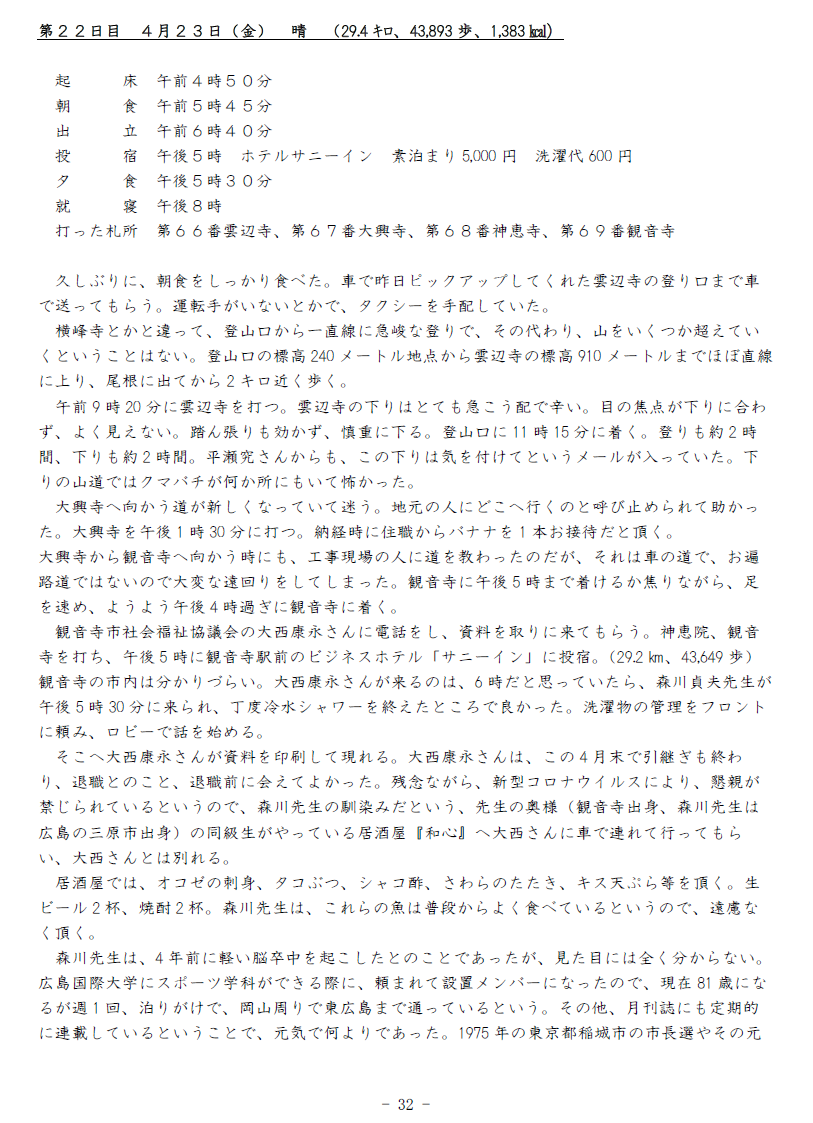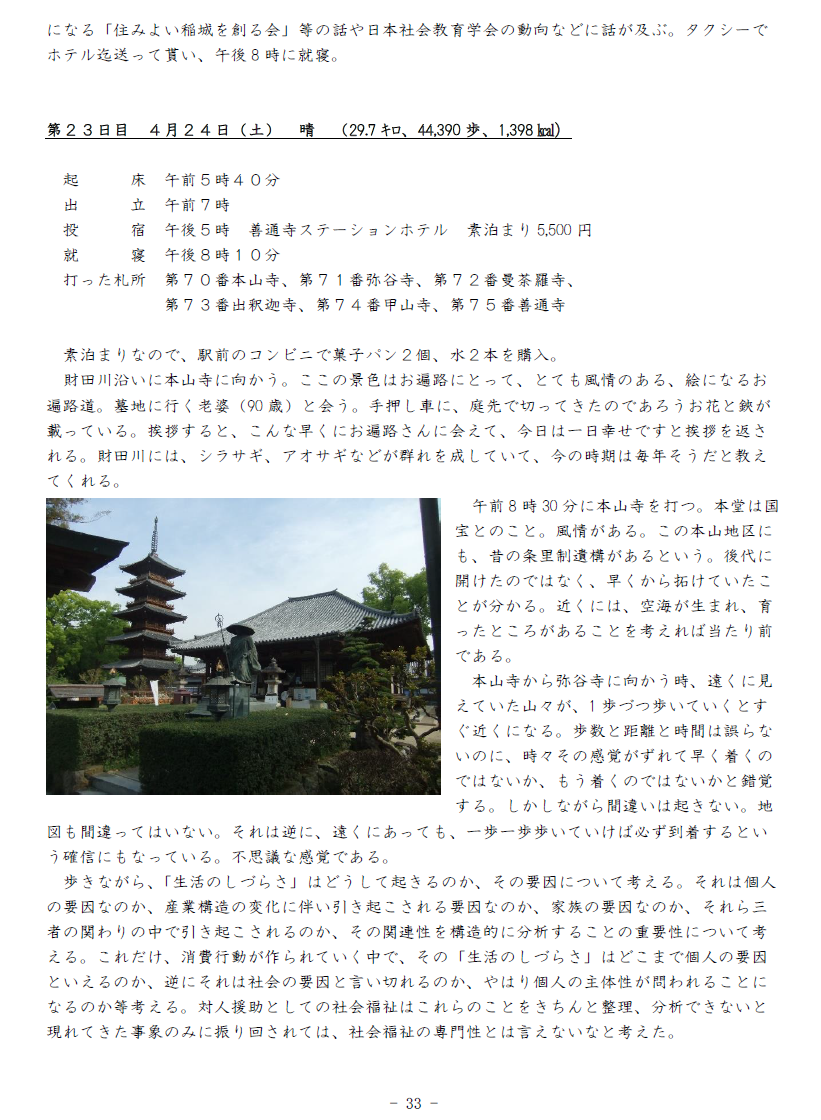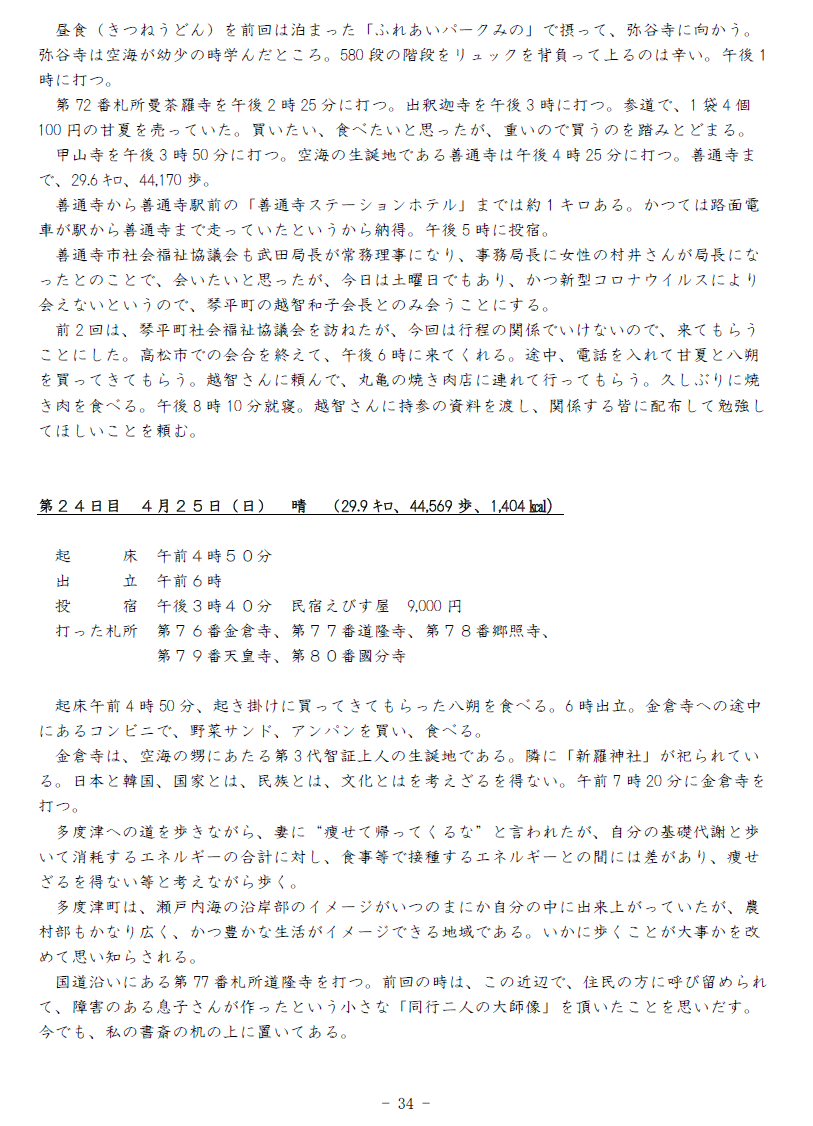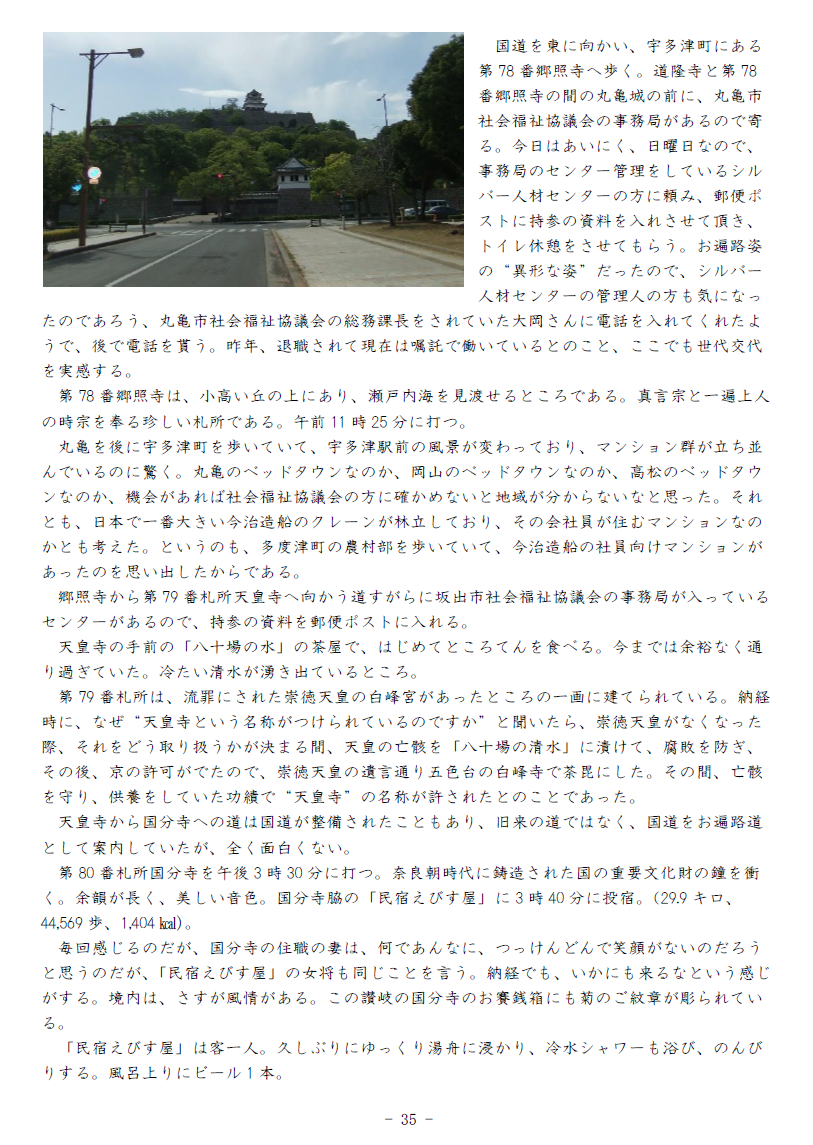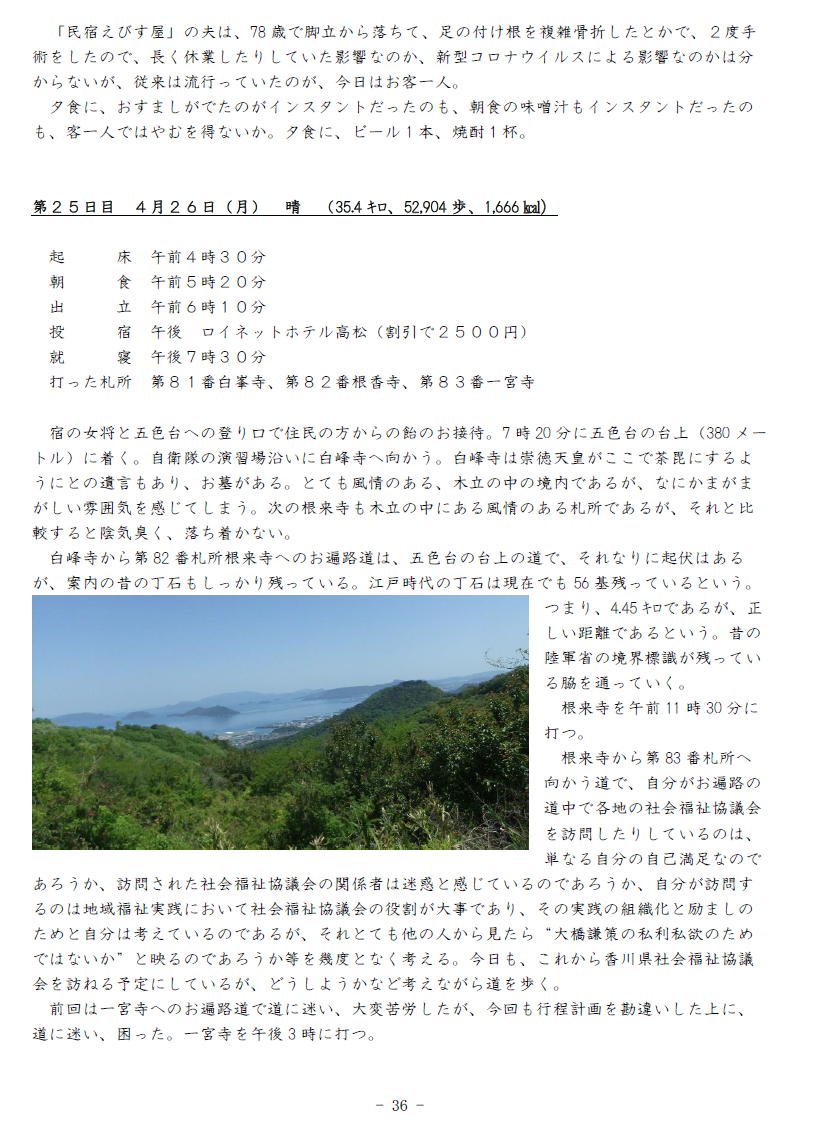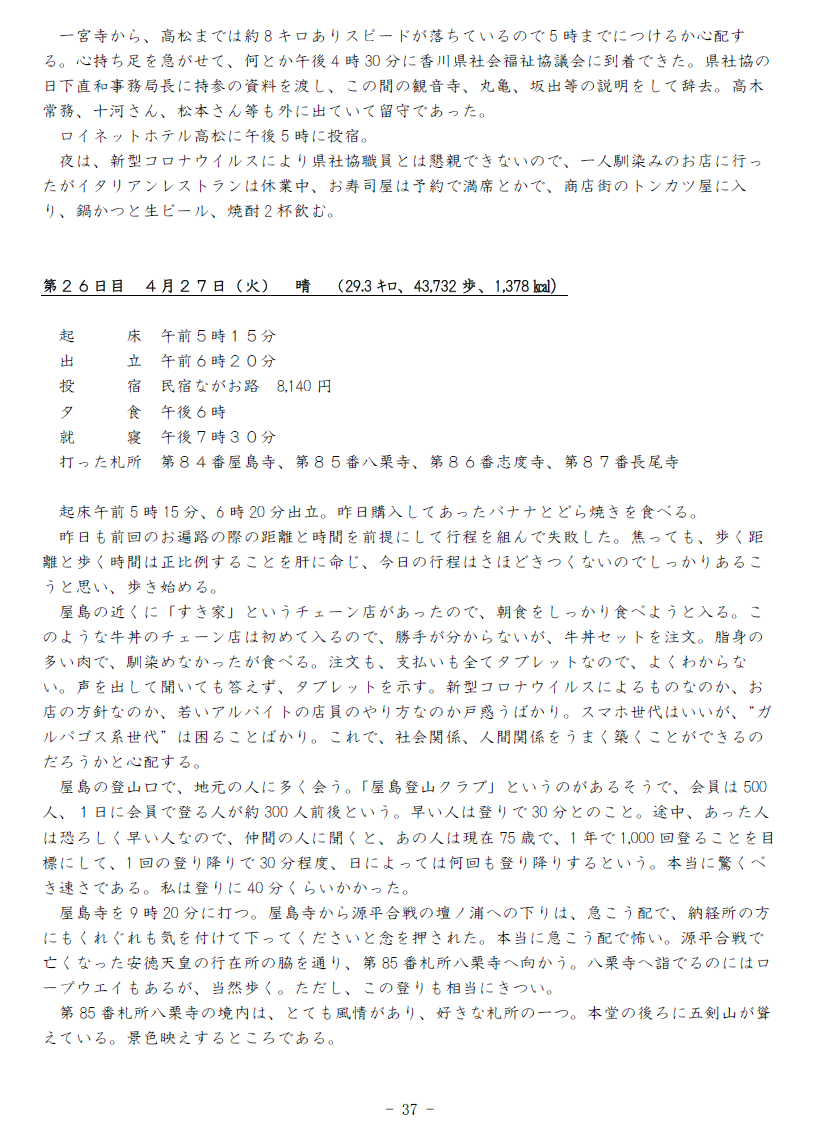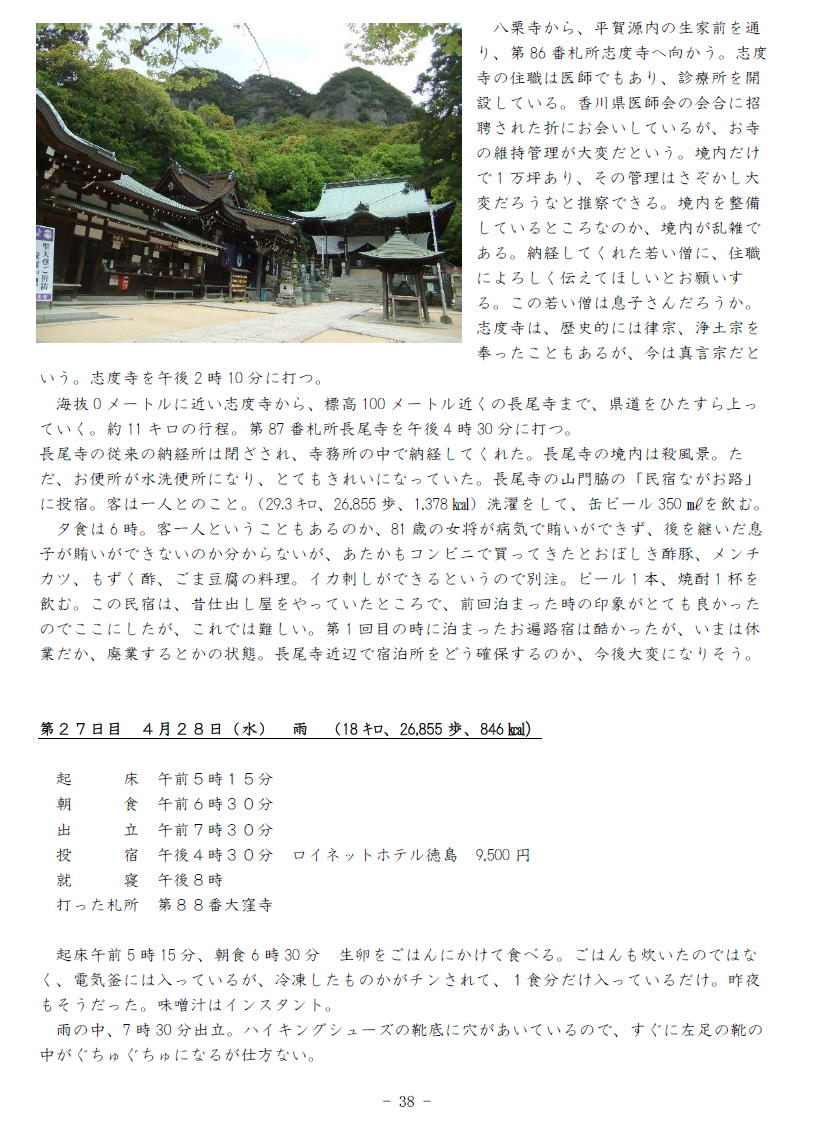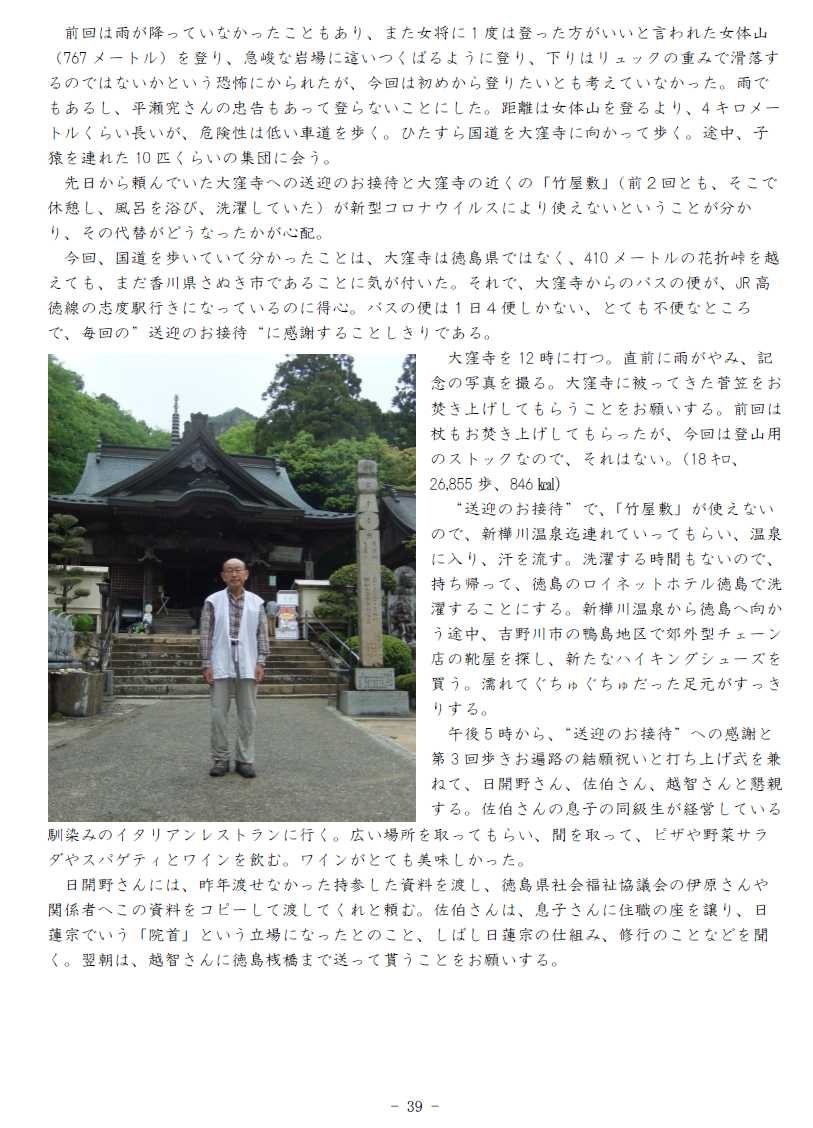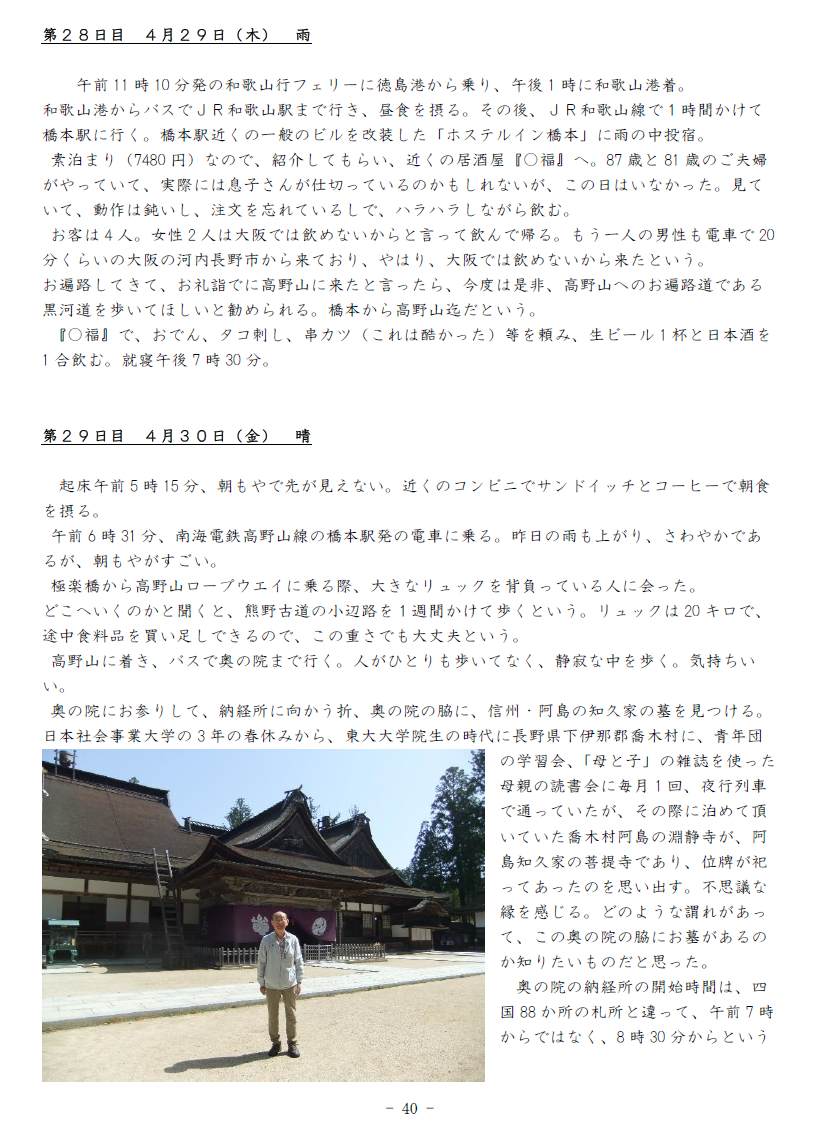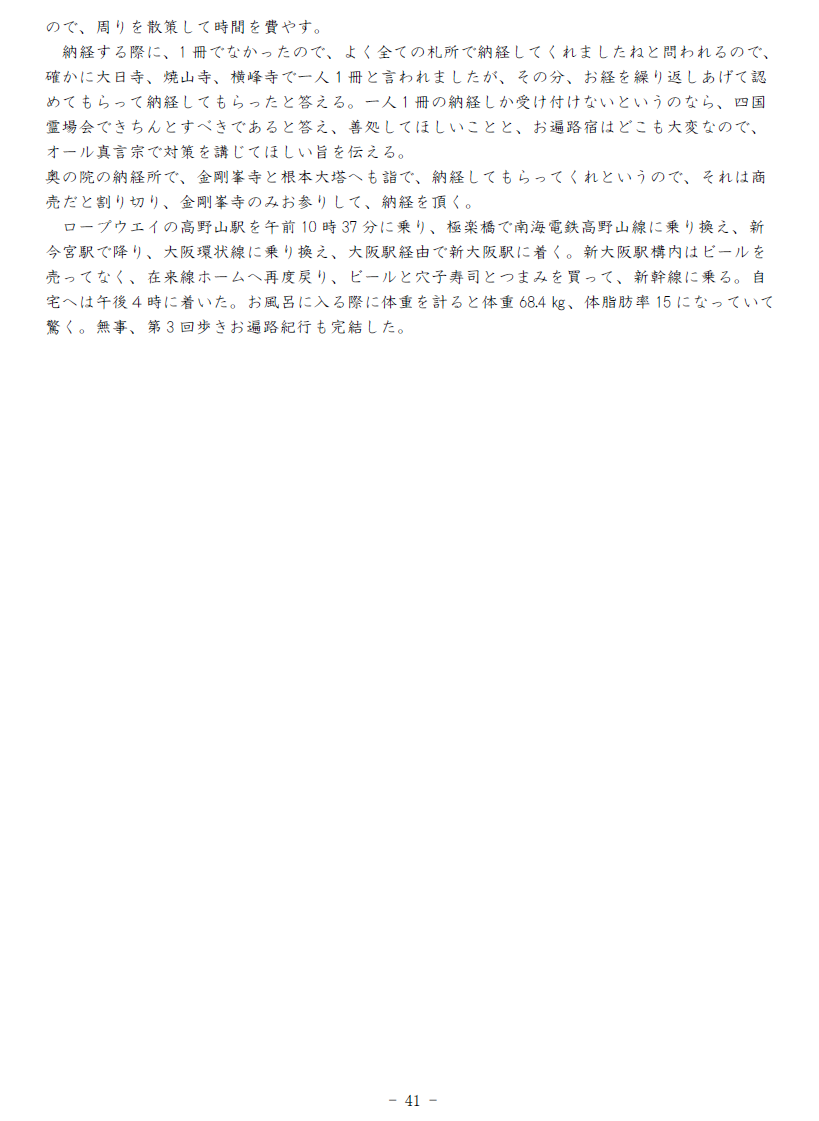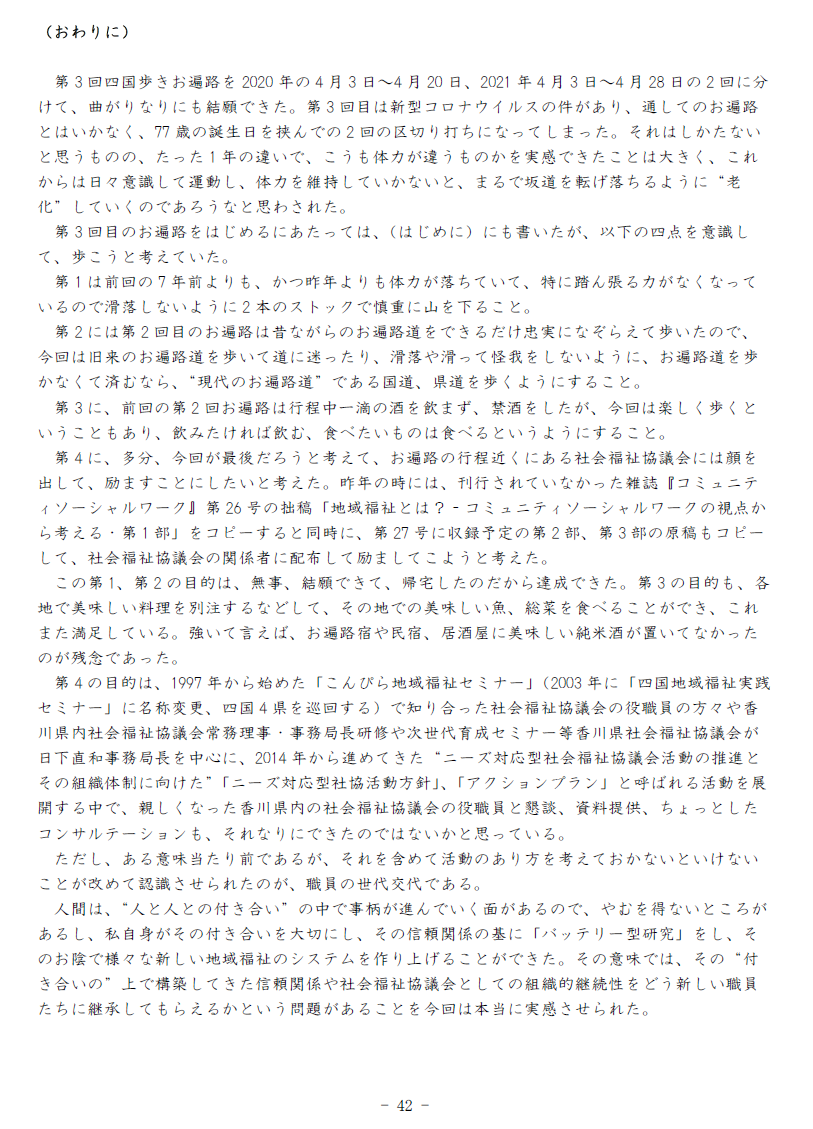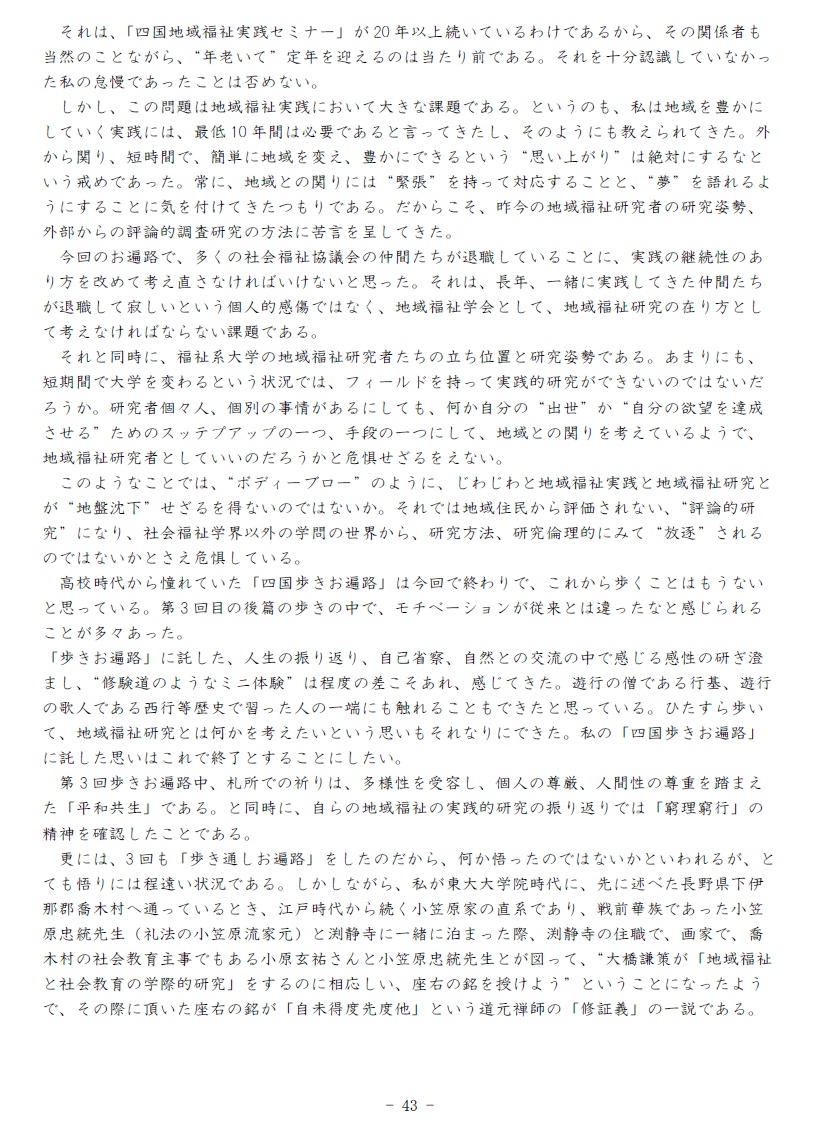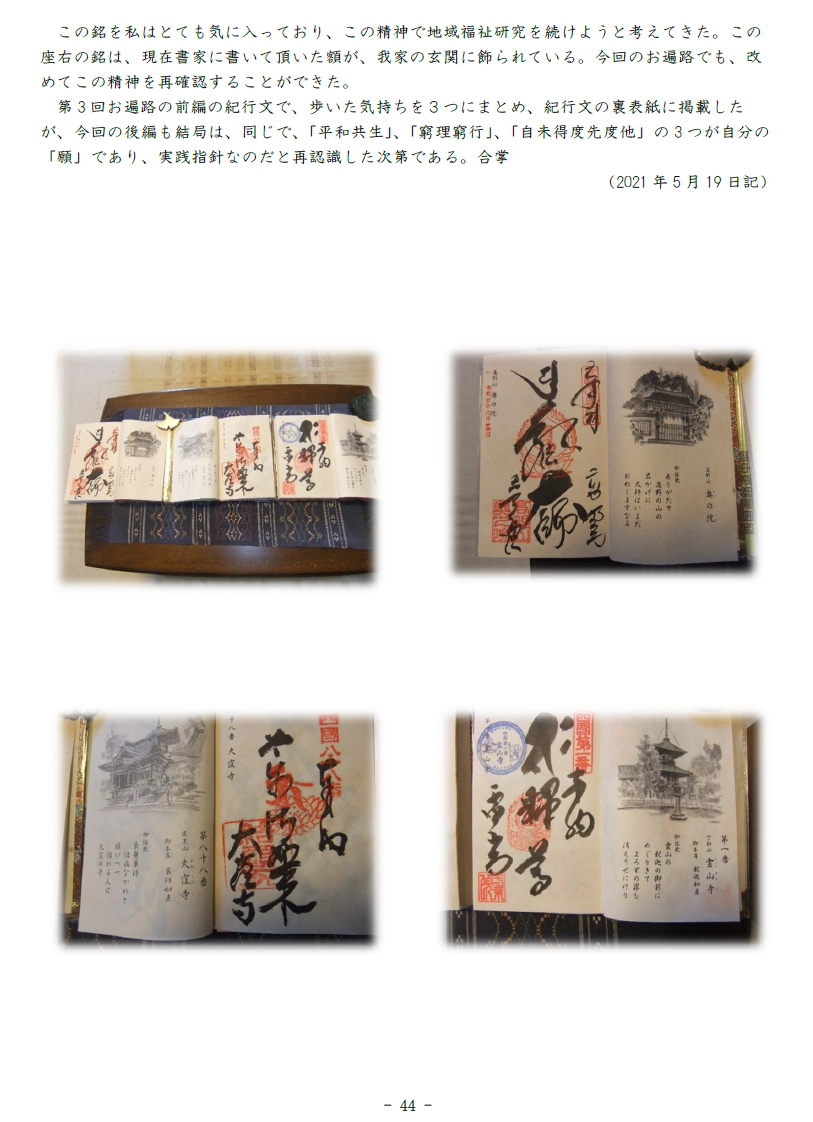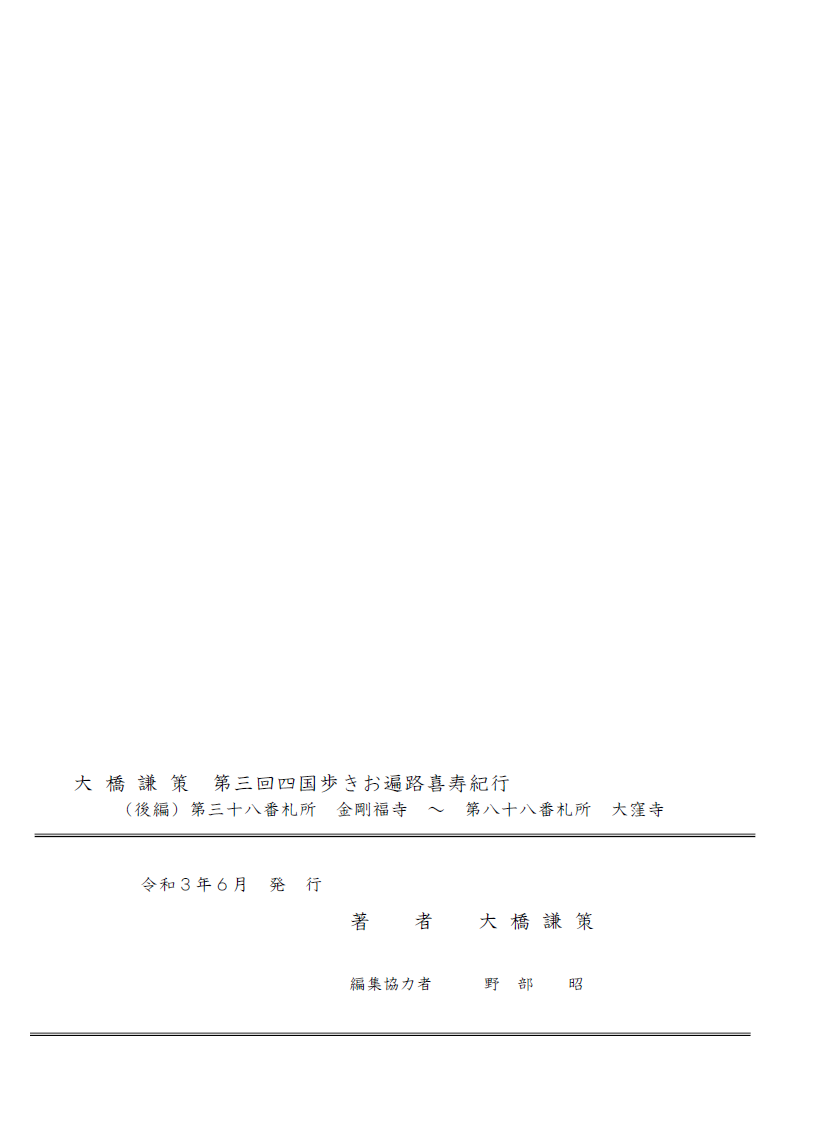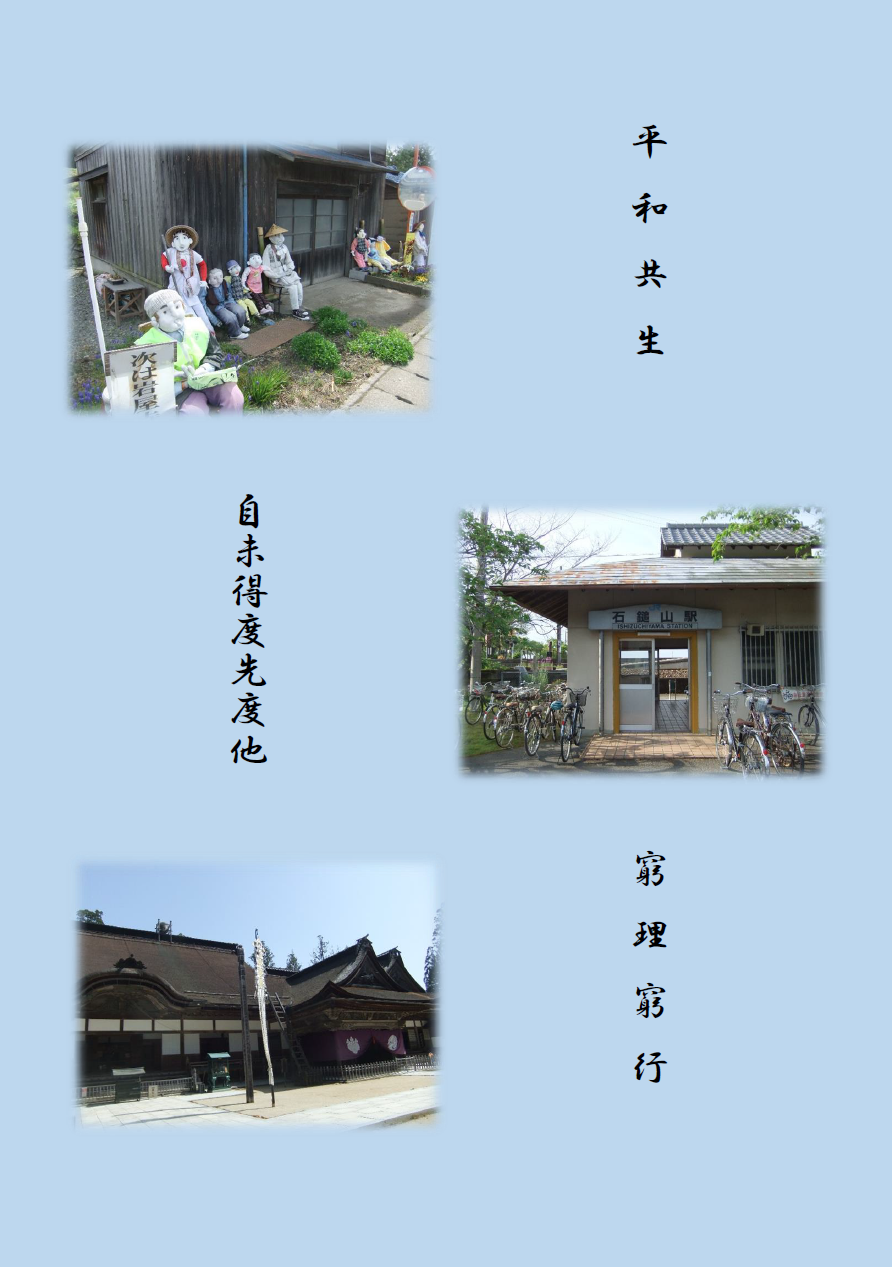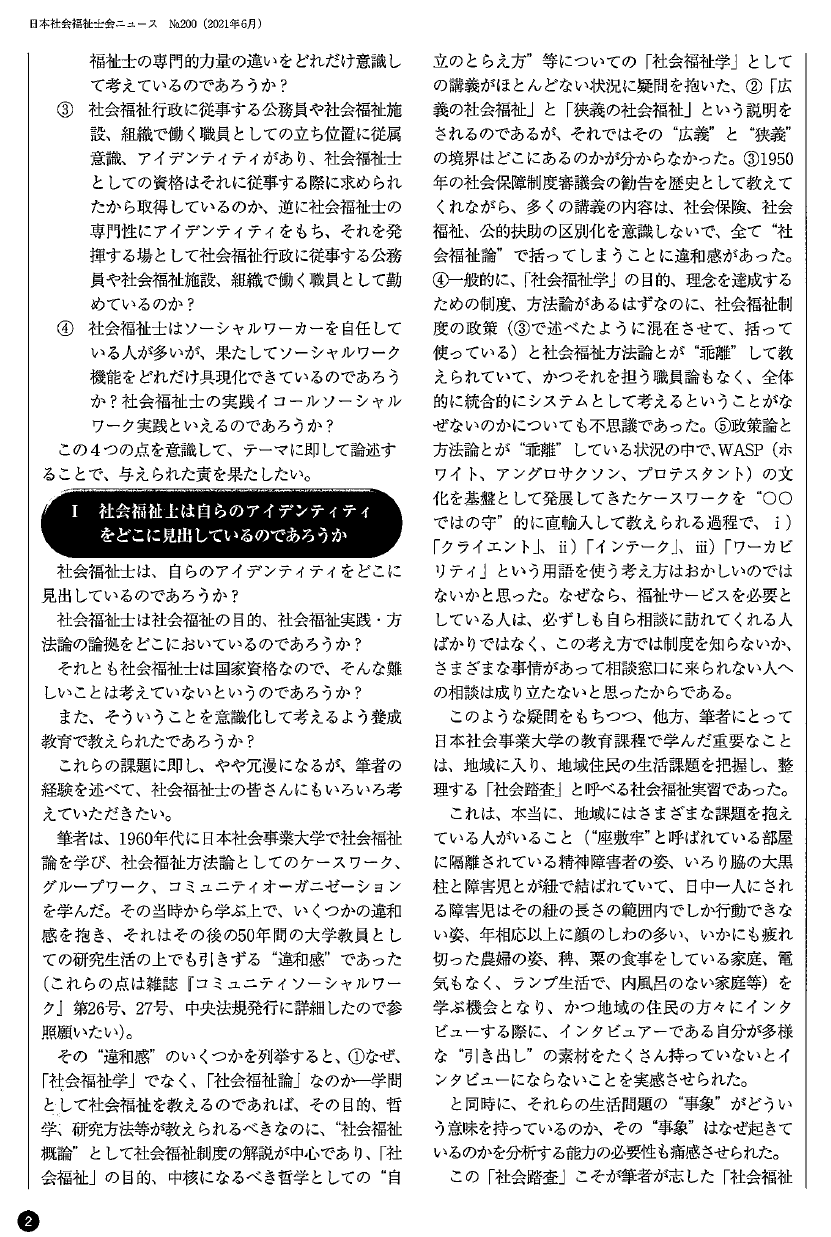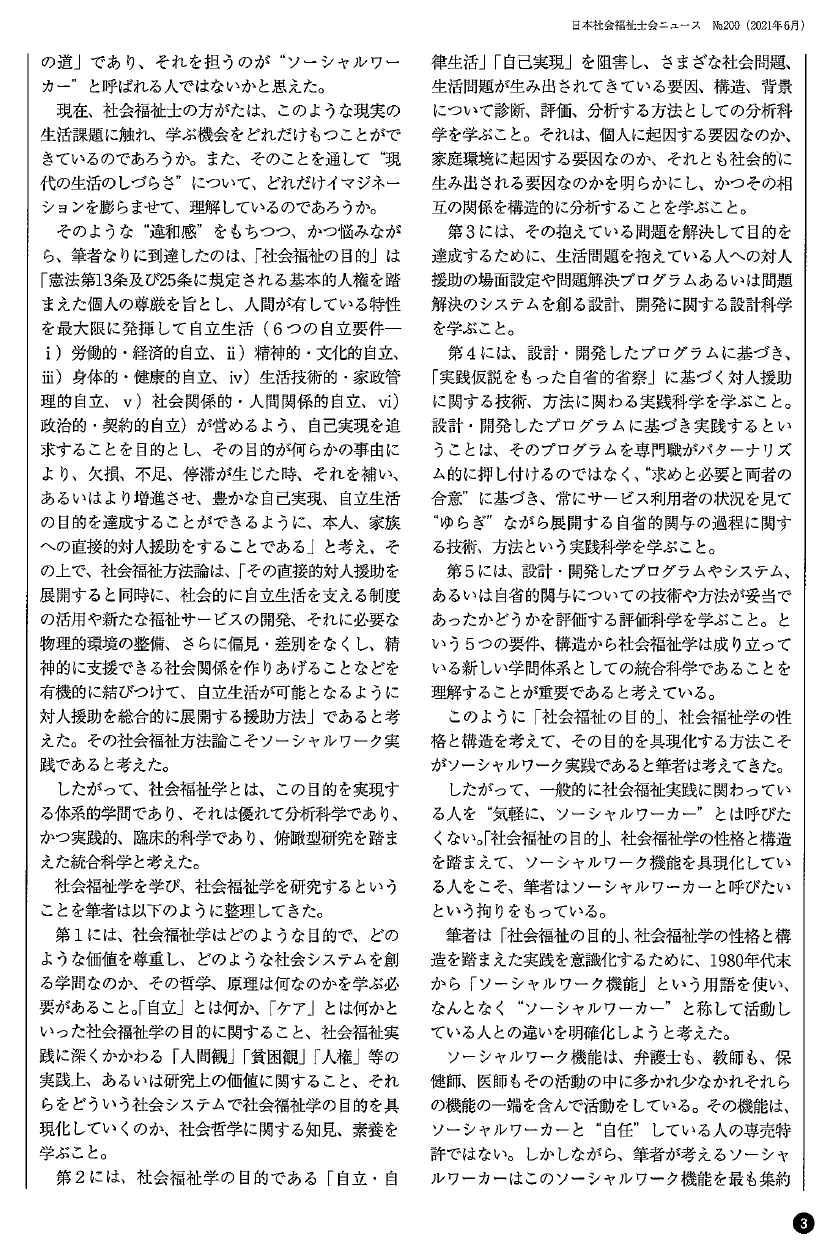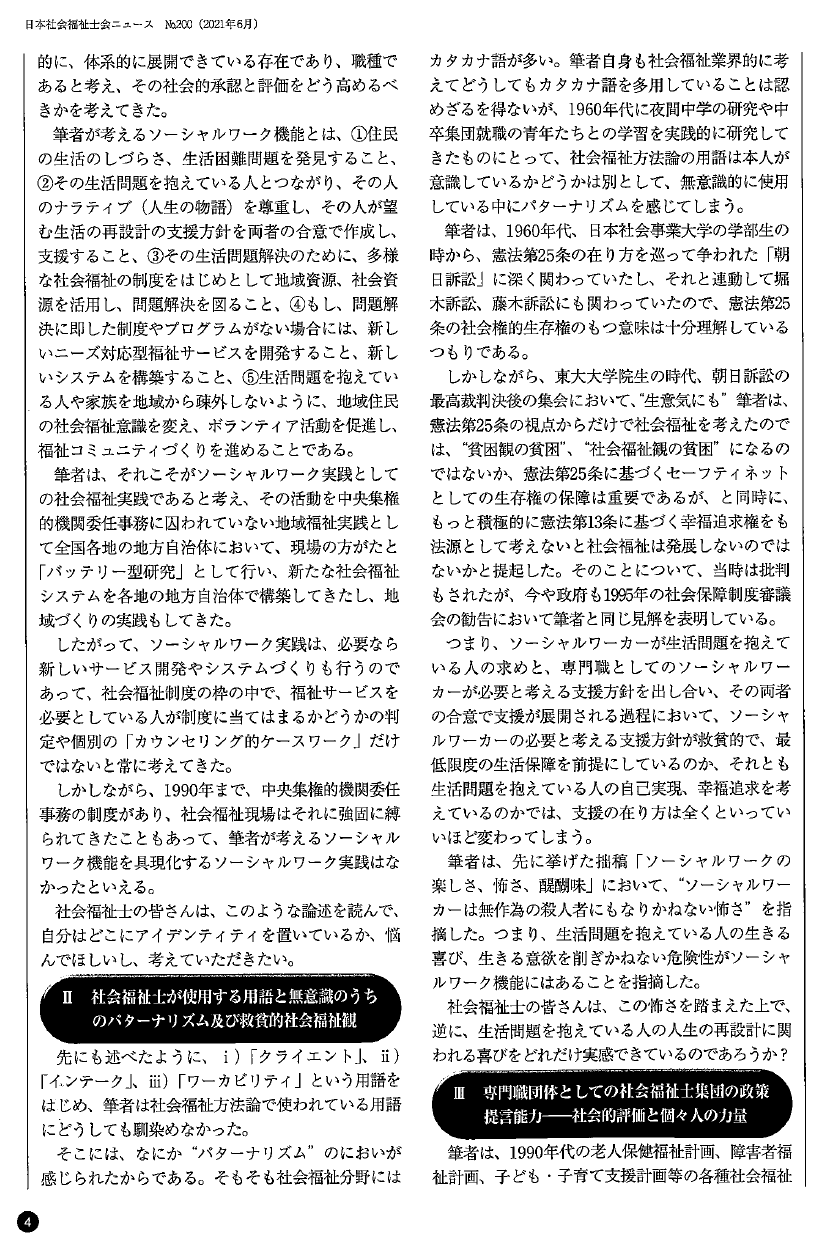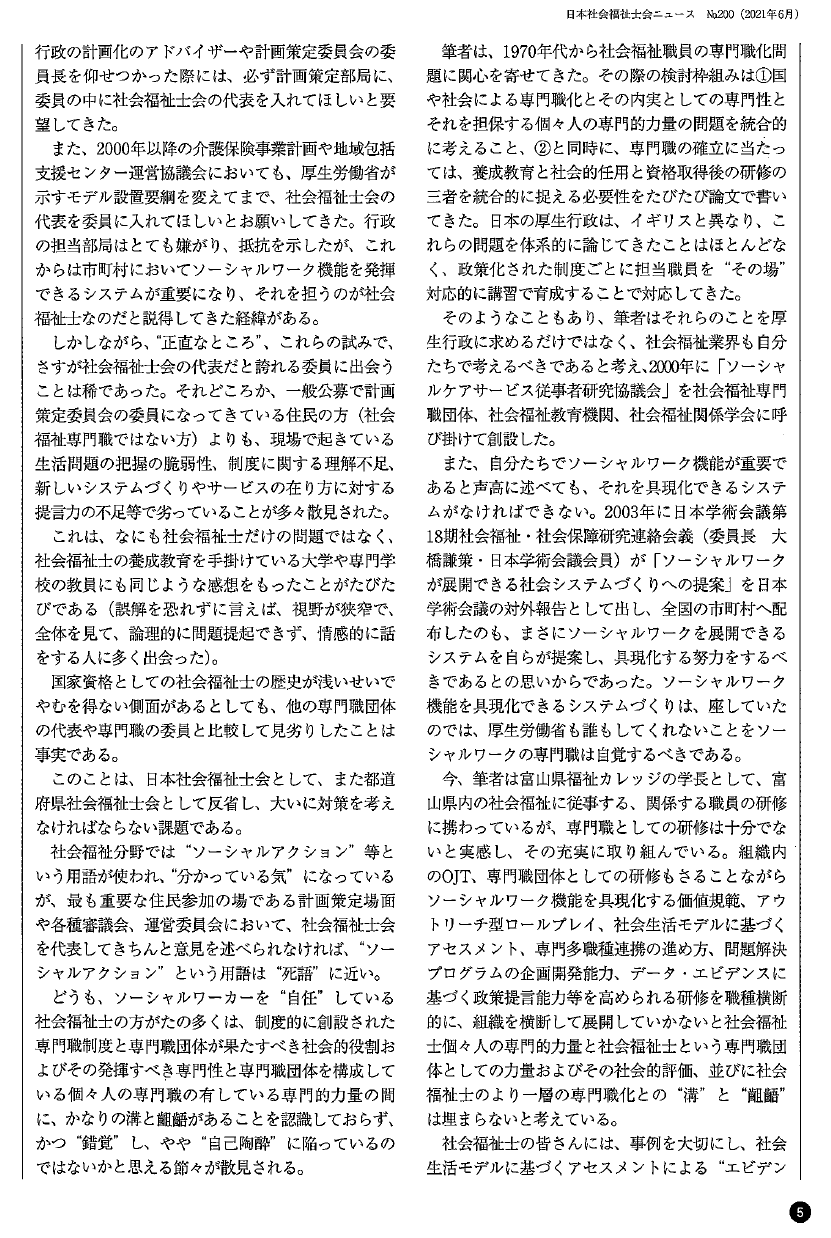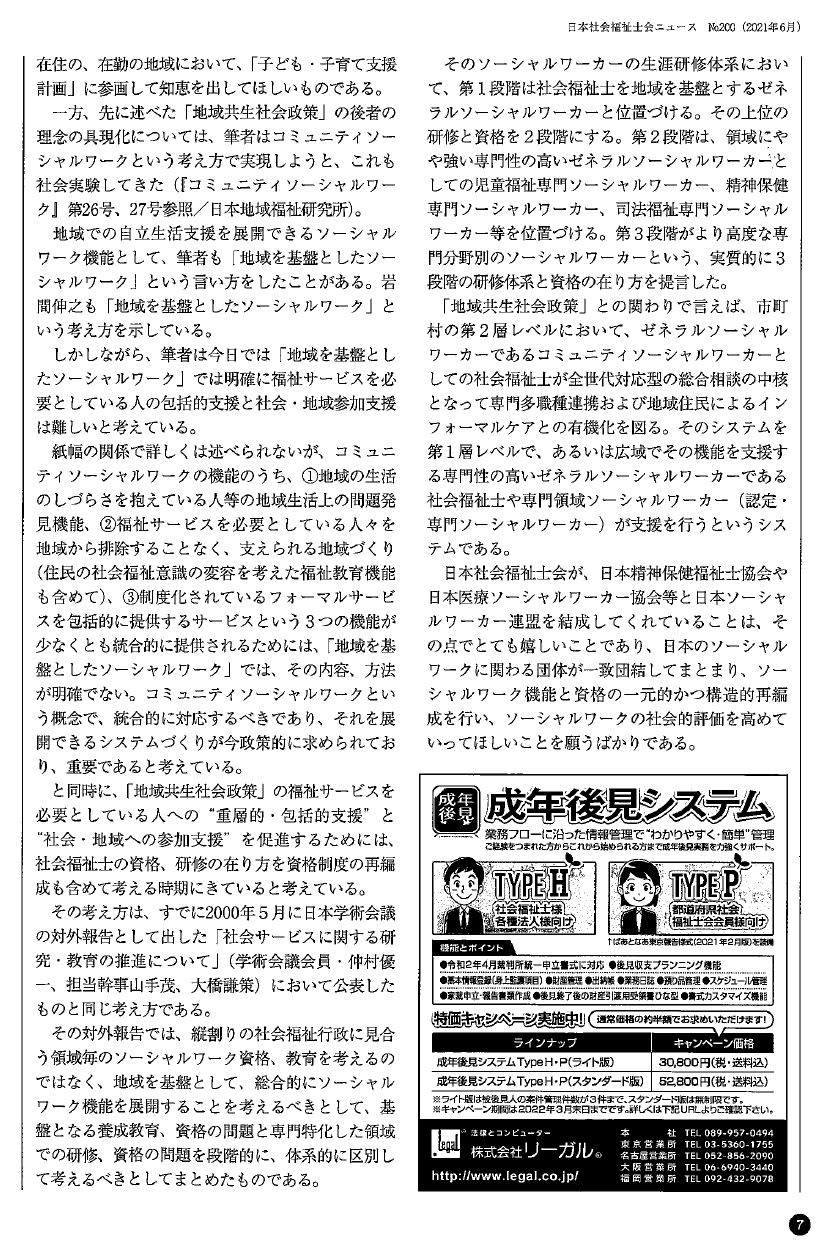〇稚拙で荒っぽい思考であるが、筆者(阪野)は過日、「時間」と「空間」の座標や尺度のなかに我が身が存在しない、というような体験をした。全身麻酔(一時的な昏睡)による手術である。麻酔が切れたその時、眠りから覚めた(覚醒)という感覚は一切なかった。そこに存在したのは「死」であったのであろうか。それ故に、我が身の「生」(あえて言えば「生き抜く力」)の「時間」と「空間」について考えることが求められる。本稿を草することにしたひとつのきっかけであり、思い(想い)である。
〇筆者の手もとにいま、「文章を書く建築家」のひとりである内藤廣(ないとう・ひろし)の本が3冊ある(しかない)。(1)『建築のちから』(王国社、2009年7月。以下[1])、(2)『場のちから』(王国社、2016年7月。以下[2])、(3)『空間のちから』(王国社、2021年1月。以下[3])、がそれである。編集者の思いによる3部作であるが、そこにはその時々の信条や心象を言葉にした、哲学的で、専門的知識に裏打ちされた玉稿が収められている。それ故に、洞察の深い文章は筆者にとって難解である。
〇内藤は、[1]で「建築の本懐(本意)は、その誕生にあるのではなく、その後、時代と共に生きていく時間の中にこそある」(18~19ページ)。「大衆が心から望むものと建築家が実現しようとするもの、そのベクトルが一致する時、建築は街を変え、人びとを変えていく力となる」(20ページ)、と説く。[2]で「建築の依って立つところ、それは大地だ。大地とその場所に生きる人間だ」(12ページ)。いま、建築という価値が大きく毀損(きそん)され、本質的な意味で「建築の冬の時代」(12ページ)が到来しつつある。そんななかで必要とされるのは、「場所の持っている内在的な力、人を生かしめる内発的な力」(20ページ)である「場のちから」であり、それを全身で受け止めるような体験である(12ページ)、という。 [3]で「空間の本性は、『和解の場』のことなのかもしれない」。「建築や環境が内包する空間とは、(「人と自然」、「生と死」、「過去と未来」、「復興と街造り」など)全てのものが流れ込み、もつれあい、そしてその和解を用意する場のことなのではないか」(34ページ)、と問う。そして、建物の空間や街の空間を豊かなものにするのは、可能な限り「時間が生まれ育っていくような空間」をつくることだけである(236ページ)、と言い切る。
〇3冊の本に通底する基本的な言説のひとつは、次のようなものである。すなわち、「建築」(architecture)は「人間」の「身の置き所」([3]206ページ)を「構築する意志」であり、「建物」(building)はそのための道具、具体的なモノである([3]232~233ページ)。大切なのは(守るべきは)、「空間」と「時間」によって織りなされている「建築」という名の意志である。本来の建築の価値は、「人の生きる長さを越えて何事かを伝える」([3]5ページ)ところにあり、メッセージを伝えることによって建築は生命を与えられる。その際の(本当の)価値は、「生み出すものではなく、生まれてくるものであり、なおかつきわめて個人的なもの」([3]89ページ)である。
〇そして、内藤にあっては、建築について自分の思考を磨き、建物が生み出された内実について(技術や経済や制度の側から)説明すめためには、言葉の助けが必要となる。「文章を書く」ひとつの所以でもある。内藤はいう。「建物を建てる際の現実的な体験は、建築に対する思い込みに修正を迫る。現実と思考、そのやりとりの試行錯誤が言葉になり文章になる」。「建築と文章とは切っても切れない関係にある」([1]82ページ)。
〇本稿では、[1][2][3]における論点や言説から、例によって我田引水的であるが、「まちづくりと市民福祉教育」に関して「使える」であろう・留意したい一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。
『建築のちから』
「建築の力」は空間や時間と人びととの開放的な共感のなかに現れる
われわれは、建物の完成にこだわり、品質にこだわり、意図したものができ上がる作品性に神経質になり、その結果、いちばん大切なことを見失ってはいまいか。社会制度の命ずるところ、資本主義経済が望むところ、そうしたものに対する律儀さが建物の質に無意識のうちに現れているのなら、人びとは建物から距離を置くだろう。なぜなら、建物が社会や資本に顔を向けて、人びとに背を向けているからだ。
「建築の力」(建築のなかに生まれてくる価値:阪野)はそういうところには現れない。「建築の力」は人びととの共感の中に現れる。それは、発注者、建設関係者、設計者、住民、不特定多数の人びと、よりよい社会を目指すそうした人たちの運動体、そうしたものの中で初めて兆(きざ)すはずだ。そのためには建築という価値は「完結的」であってはならない。開かれていなければならない。空間的に開かれている、あるいは時間的に開かれている必要がある。いちばん望ましいのは「空間にも時間にも開かれている」ということだ。そう誰もが感じられるような状況となった時、「建築の力」は熱湯がいきなり泡立つように内側から湧き上がってくる。([1]19ページ)
建築には空間に身を置き時間のなかに生きる人間に対する洞察が不可欠である
おそらく建築の中には、「わかりやすい価値」と「わかりにくい価値」が存在する。「わかりやすい価値」はわかりやすいのだから容易に広まる。([1]233ページ)
一方、「わかりにくい価値」は伝わりにくいから、いくら声を大にしてもなかなか広まらない。建築に時代を超えていく本質的な生命力というようなものが存在するとしたら、それはこの中にしかない。多くの場合、「わかりにくい価値」は空間の中にある。空気の肌触り、陰影の深さ、音、匂い、そうした目に見えない空間の質に価値の重点が置かれた場合、そこに表現されたもの、建築家が精魂込めて託したもの、それはきわめて高度でわかりにくいものになる。その空間に身を置き、時を過ごし、体験しなければわからない。メディアも写真家もこうした価値には不親切であり続けた。
しかし、このあり方は、誰にでも開かれているわけではない。これを現実のものとするには、才能が要る。たくさんの要素を同時に想像し、それを空間の中に結び合わせなければならないからだ。経験と直観が必要なことはいうまでもないが、それが一級のものになるためには、何より、その空間に身を置く人間というものにたいする深い洞察が不可欠で、それだけのものを身につけた建築家はめったにいない。([1]233~234ページ)
『場のちから』
建築は空間の「湿り気」・人の感情の総体と向き合わなければならない
モダニティ(近代性、近代的なもの:阪野)は、わたしたちの身の回りを覆い尽くしつつある。それは、世界的な経済構造や社会構造と連動して、いまだに生活の隅々にまで浸潤し続けている。便利さ、明るさ、速さ、安さ、そしてなによりわかりやすさ、この力には抵抗し難いものがある。しかし、人という存在は、それだけでは遥(はる)かに足りない。人の感情を受け止め、人が尊厳を保持しうる空間とは、そんなものに支配された空間ではないはずだ。
モダニティがもたらす空間は何故か乾いている。現代建築も乾いている。雑誌で目にする様々な作品には、明らかに「湿り気」が欠落している。([2]123~124ページ)
空間に「湿り気」を求めたい。ここで言う「湿り気」とは、感情の襞(ひだ)や心の陰影を受け止める空間の質のことだ。([2]124ページ)
建築という価値も、本来はそうした人の感情に生起する様々な質に内包すべきである。そのためには設計は、喜び、夢、希望、愛着、悲しみ、打算、矛盾、裏切り、葛藤、追憶、といった人の感情の総体と向き合わねばならないだろう。この態度は設計者に多大の忍耐を強いるが、結果として、出来上がる空間に「湿り気」をもたらすはずだ。この困難さに耐えることは、それ自体が「建築に感情を取り戻すための戦い」なのだ。([2]124ページ)
都市計画は終わりも完成もない物語(物語ること)のプロセスである
誰であれ志のある都市計画家を思うとき、その職業の難しさと悲しさを思わずにはいられない。彼らは100年を夢想し、理想を思い描き、今日の日常的な無理難題を扱う。それでいて、都市の時間に終わりのないこともよく知っている。華々しくテープを切るようなゴールなどない。すなわち、すべてはプロセスであって、目の前の現実は過ぎ去る一側面でしかない。そのことを誰よりも熟知している。また同時に、自らが夢想する未来もまた過ぎ去る一側面でしかないことも知っている。人間のそして人間社会の性(さが)を嫌というほど見ながら、それでも社会の改良を諦めない。都市計画家とはそういう存在なのだ。難しさと悲しさが浮かぶのはそれ故だ。([2]183ページ)
終わりのない都市の物語は、たとえそれがプロセスであったにせよ、そして、それがたとえ見果てぬ夢であったとしても、空間デザインを旋律(メロディー)に、そして社会システムを通奏低音に、より美しい韻律(リズム)を奏でることが出来るはずだ。ソフトウェアとはその韻律のこと。その韻律にこそ人間社会の希望がある。([2]186ページ)
『空間のちから』
建築は「つまらなくて価値のあるもの」「生き生きと生きる」を価値の中心に据える
建築が本来担わなければならない長い時間からすれば、「面白さ」は初期に求められる付加的な要素に過ぎない。([3]83~84ページ)
建築に「面白さ」を求めることは危険だ。一発芸と同じで、「面白さ」は一時もとはやされるが、すぐに「時代遅れ」になる。「面白さ」があったにしても、それはやはり建築の原理原則に適ったものでなくてはならないはずだ。しかし、それはそうたやすく手に入る類のものではない。昨日目新しく話題になった建物が、見る間に日常風景の中に飲み込まれ、忘れ去られていく様をいくつも見てきた。だから、「面白さ」を建築という価値の中心に据えていいはずがない。
世の中の公共建築を見渡してみると、「面白くて価値のないもの」ばかりが目立つようになってきている。そこで、逆説的なようだが、あえて「面白さ」を捨てて、「価値のあるもの」を目指してはどうか、また、多くの人が「生きること」、「生き生きと生きること」を価値の中心に据えてはどうか。
「面白さ」はわかりやすく、それ故伝わりやすいから流布しやすく、それ故に容易に消費されていく。とかく人の心は飽きやすい。それに対して、建築的体験の中に留まるような「わかりにくさ」は言葉になりにくい。それ故、伝わりにくい。この矛盾を乗り越える必要がある。([3]84~85ページ)
〇ここで、評論家・加藤周一(1919年~2008年)の『日本文化における時間と空間』(岩波書店、2007年3月。以下[4])を思い出す。加藤はいう。日本文化のなかには3つの異なる「時間」が共存している。①(『古事記』にみられる時間のような)始めなく終りない直線=歴史的時間、②(四季を中心とした)始めなく終りない円周上の循環=日常的時間、③(人生の)始めがあり終りがある普遍的時間、である。そして3つの時間のどれもが、「今」に生きることを強調する([4]28~36ページ)。日本における(閉鎖的な)「空間」の特徴は3つある。①(神社の建築的空間がそうであるように)空間の秘密性と聖性が増大する(人に見せず、大事にする)「オク」(奥)の概念、②(神社には塔がないように)建築は平屋または二階建てで、地表に沿って広がり、天に向かって伸びていくことはない「水平」面の強調、③(武家屋敷や都会の地下的のように)時とともに変わる必要に応じて家屋などを増やしていく「建増し」思想、である([4]164~174ページ)。これらによって「私の居る場所」、すなわち「ここ」を重視する。要するに、日本文化に内在する時間と空間の概念は、自分がいる「今=ここ」に集約され・強調される。それは「全体から部分へ」ではなく、「部分から全体へ」という思考過程をたどるものであり、日本文化の基本的な特徴(「今=ここ」の文化)である。その時間における典型的な表象・表現が現在主義であり、空間におけるそれが共同体集団主義である([4]233~238ページ)。
〇このような加藤の言説に対して内藤は、[2]において次のように要約して持論を展開する(抜き書きと要約。見出しは筆者)。留意しておきたい。
建築の本質は「今・ここ」を確かなものにするために「待つ」ことにある
加藤周一の「今・ここ」論を要約すると、「今・ここ」という時空の中の一点から世界の認識を広げていくという癖のようなものが(日本)文化の基層に根強くあるのではないか、という提示だ。西欧の時間と空間とは、個人という存在の外部に普遍的な尺度を設定し、自分と世界を定位しようとするが、この国の文化はそれとは違って、「今・ここ」という内部化された座標のもとに育まれてきたのだが、これがかつて戦争へと向かう精神を生み出した、というのである。([2]112~113ページ)
建築や都市に課せられた大きなテーマは、「今・ここ」の確かさではなかったか。しかし、情報化社会の出現と共にこれが急速に希薄になりつつある。今問題にすべきは、失われつつある「今・ここ」が生命を持つためにはどのようにすれば良いのかということだ。つまり、現在を起点に、時間と空間の幅を広く捉えること、それが建築や都市に課せられた大きなテーマなのではないか。([2]113ページ)
近年、建築が育んできた文化は、あまりにも一足飛びに未来を志向しすぎてはいまいか。そこには、その未来に至る持続的な時間が消去されている。どこかの時点で、建築は「待つ」ことを辞めたのである。([2]114ページ)
「待つ」という行為を通して、人は広がりのある「今・ここ」を引き出すことが出来る。([2]113ページ)
「待つ」ためには、未来を想起し、そこから現在を逆照射する逆立ちしたような意識が必要だ。「待つ」ことは建築にふたたび持続的な時間概念を導き入れることである。おそらく、「待つ」ことを想起することは、建築に新たな質をもたらすはずだ。([2]115ページ)