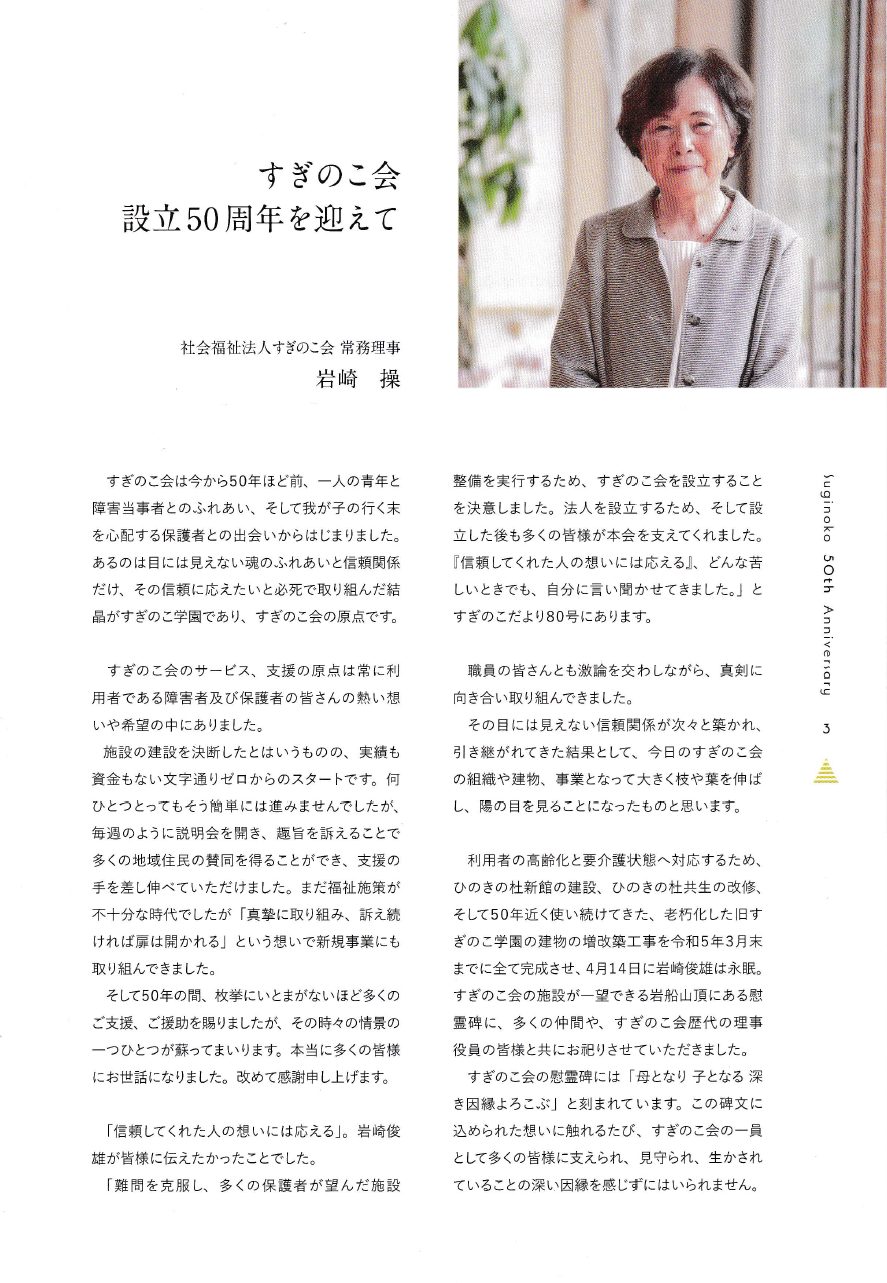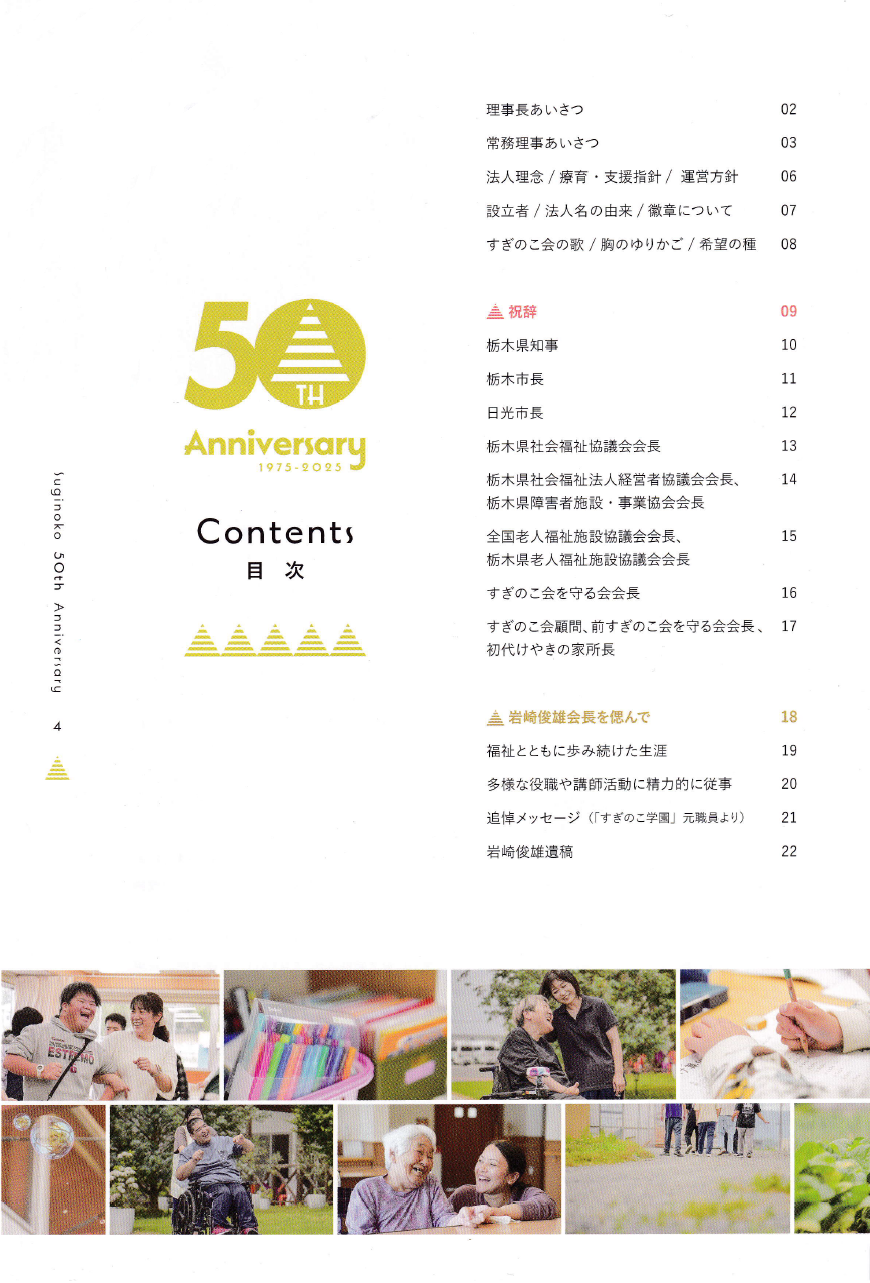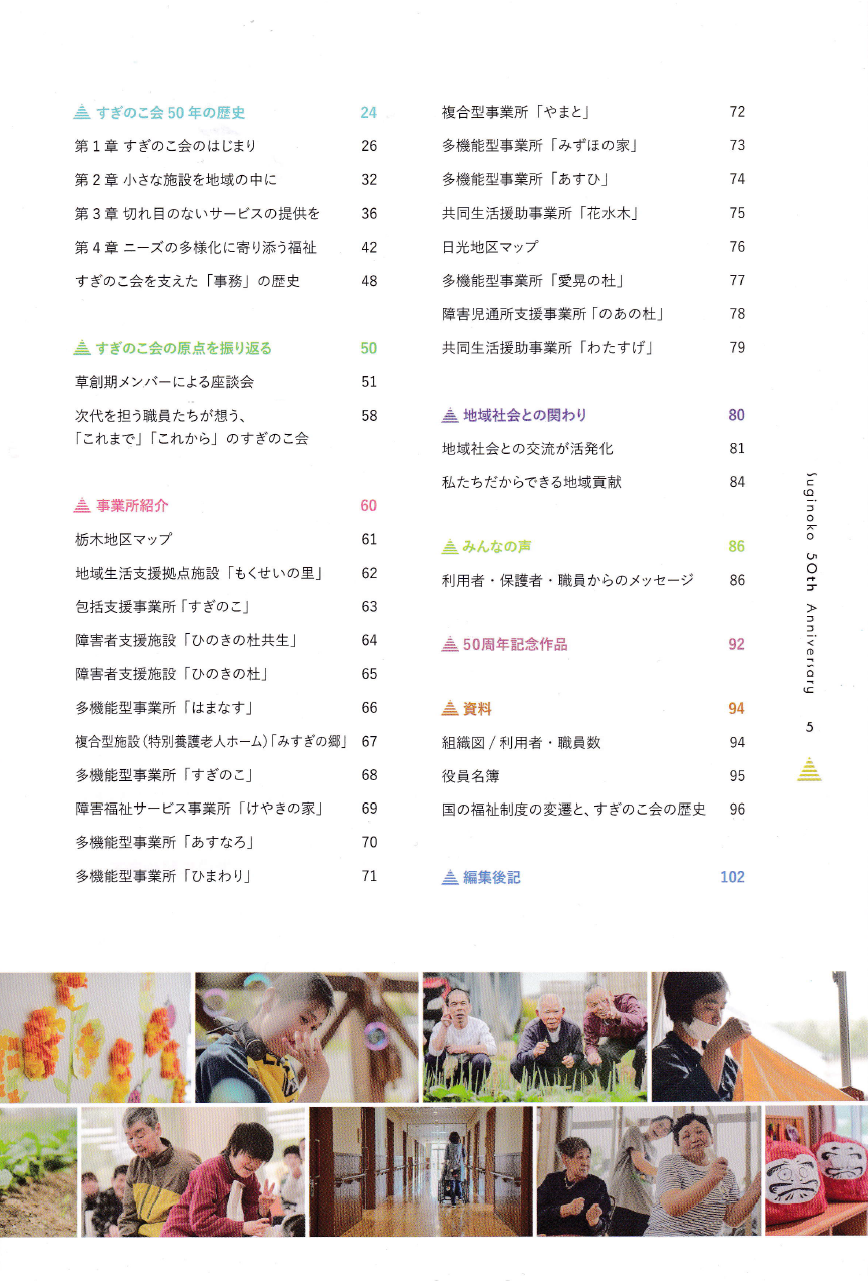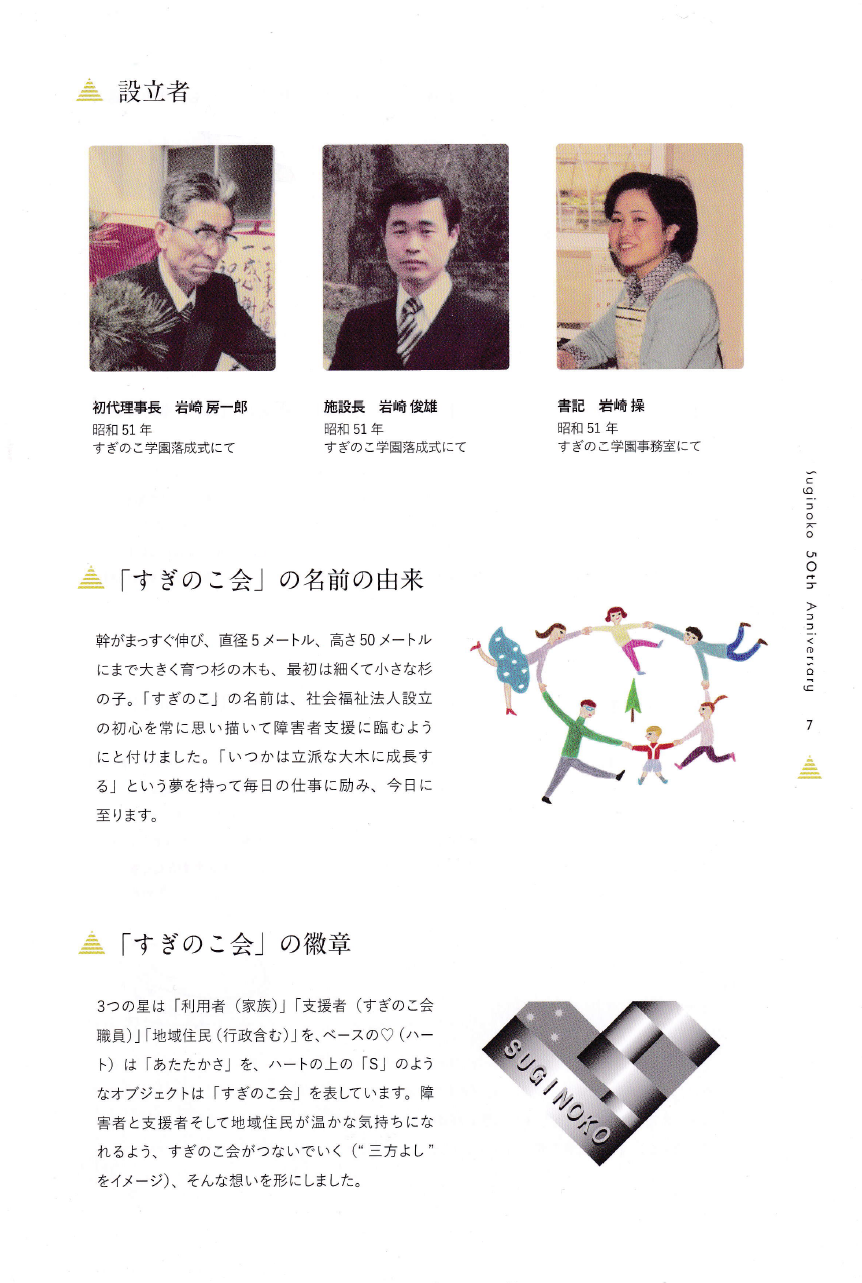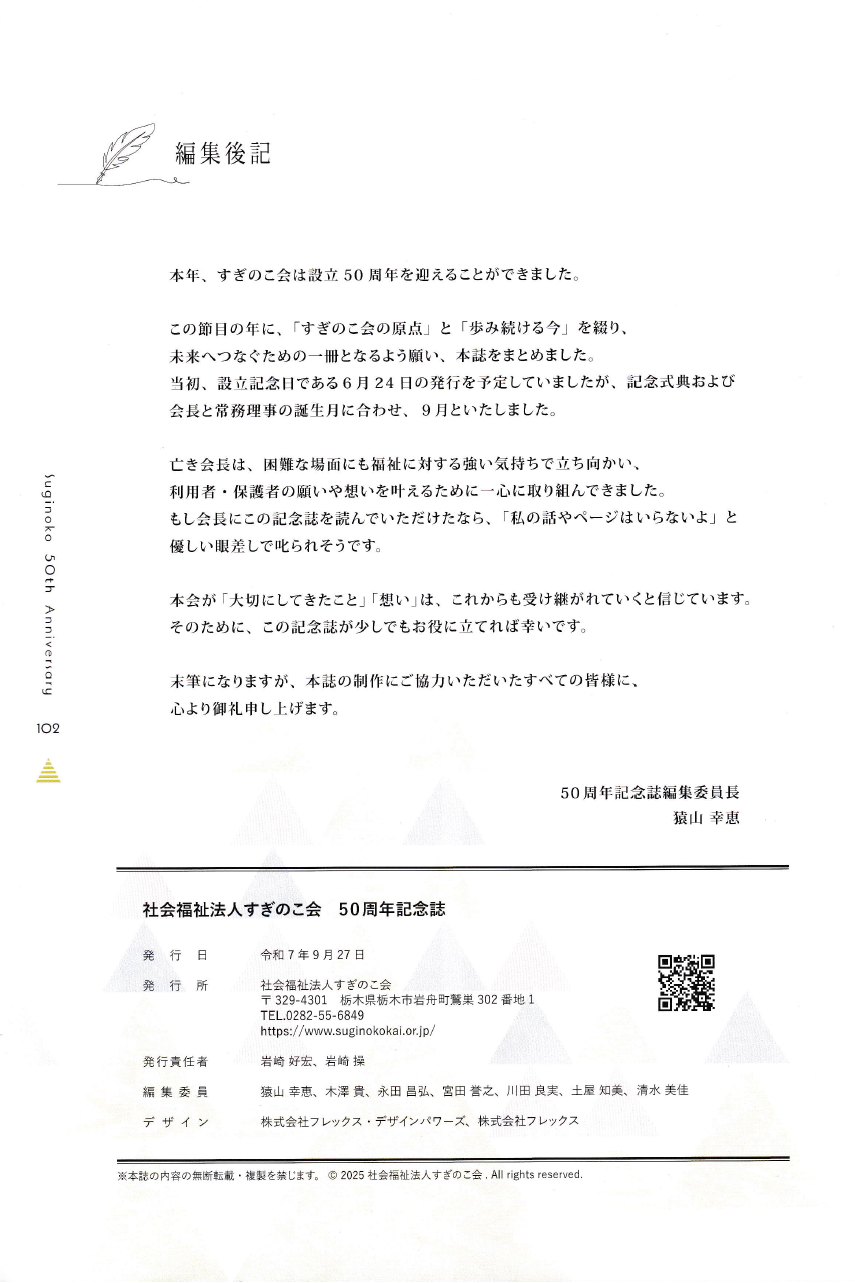国家として政策・法整備をしっかり進めて、差別や不平等を解消するための施策、法的地位の改正、差異の承認と多文化社会の構想を育むための市民教育などに国レベルで取り組むことは喫緊の課題である。(下記[1]71ページ)
〇筆者(阪野)の手もとに、岩渕功一著『多様性とどう向き合うか―違和感から考える―』(岩波新書、2025年12月。以下[1])がある。「多様性」という言葉やそれを尊重し奨励する言説や態度に、耳ざわりのいい・居心地のよい「共生」「共存」の物語を感じるが、どこか違和感を覚える。[1]は、「多様性」が既存の差別や不平等を隠すための免罪符になっていないかを問い、その言葉の欺瞞を暴きながら、他者との真の共生のための思考の枠組みを提示する。その際、岩渕の立論は、「多様性の尊重と奨励は、社会の中心に位置するマジョリティによって価値判断され管理される対象として存在している。多様性の語りは、マジョリティの/による/のためのものである」(14、15ページ)という認識を基点に置く。こうした状況が社会に組み込まれた(構造化・制度化された)差別や不平等を再生産し、マジョリティによる包摂と管理をもたらしている、と説くのである。
〇あえて先に結論を引くならば、岩渕のメッセージはこうである。「多様性を奨励する語りが問題なのは、あたかも多様性をめぐる問題が解決したかのように、あるいは多様性の奨励によって問題が解決するかのように語られることにある。(中略)多様性の奨励をめぐるさまざまな経験や違和感に目を向けて、耳を傾けて、構造化・制度化された差別・不平等の複雑な作用に向き合いながら、それを乗り越えていく方途をモヤモヤ感やしんどさと付き合いながら、さまざまな人たちと共に考えて話し合うことで、少しずつ自分を、周りの人との関係を、そして社会を共に変えていくことを目指すべきではないか。」(174ページ)。
〇本稿では、例によって恣意的であるが、次の4点についてメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。
封じ込めと後景化:多様性の尊重と奨励は、社会に組み込まれている差別や不平等に向き合って解消する取り組みを封じ込め、後景化・後退させるような作用をもたらしている
多様性は文化的にも経済的にも有益で、生産的で、調和的で、豊かさをもたらすと肯定的なものとして語られるようになり、差異をめぐる差別と不平等の問題は挑戦的で、分断的で、否定的なものとみなされてしまいがちである。/多様性をめぐる問題を真剣に考えるのなら、差異をめぐるあらゆる差別、不平等、周縁化、生きづらさの問題に正面から向き合い、その解消に取り組むことは急務である。(中略)さまざまな企業、政府、自治体、教育機関、国際機関、NGO/NPOが多様性を尊重して受け入れ、活かすことが組織・社会のパフォーマンスの向上にとって重要だとしてその奨励・推進を謳っているが、制度化・構造化された不平等、格差、差別といった根源的な現実の問題が後景に追いやられてしまい、その問題の解消に継続して取り組んでいく必要を見失わせてはいないのか注視して検証することが求められる。(47ページ)
構造化の理解:多様性とは単なる個性の尊重ではなく、構造化された差別や不平等を直視し、それを自分ごととして捉え、その解消に向けて取り組む実践である
差別や不平等が社会の仕組みに組み込まれたものであることを理解すれば、多様性を奨励する取り組みに抱いていた自らの違和感に対して、これまでとは異なる見方ができるようになるのではないか。(118ページ)/多様性の尊重と受け入れの根幹にあるのは、差異をめぐる差別と不平等の解消であること。同じ社会に生きている人たちが何らかの差別や不平等を被っているとすれば、それは自分とは切り離されたものではあり得ないこと。それに疑問を呈して解消することは誰もが関わる社会全体の問題であること。それは個人の思いやりや優しさだけでは解消できないこと。そして、その解消は誰をもより生きやすくすること。/こうした発想の転換をすることで、社会における多様性をめぐる差別や不平等の問題を自分とは関係のない他人ごとであると認識するのではなく、それに関与したり対話しようとしたりする姿勢が育まれていく。構造化の理解は、他の人たちが経験している問題を自分ごととして捉えて、より能動的に関わっていくことを促してくれるのである。(118~119ページ)
共感から共関へ:社会変革にとって重要なのは、単に他者に対する共感力を持つことだけでなく、他者の苦難や生きづらさに自分自身も関与していることを認めることである
差別や生きづらさが社会で構造化されているとすれば、少なくとも同じ社会で生を営んでいる自分もそれに関わっており、不公正に対して異議を唱えて是正する務めがあると自覚することである。他者の苦難や生きづらさを自分ごととして考えるには、それをもたらしている社会のあり方とその変革には、その社会で生きる自分自身も意識する、しないにかかわらず、関わっていることを認識することが欠かせないのである。それは共感力を、誰もが共に関わっているという「共関」意識に結びつけることを意味する。(130ページ)/自分と異なる他者の感情や経験を理解し想像しようとする共感力は大切であるが、それに加えて、歴史的・社会的な文脈の中で構築されてきた他者が被る差別・不平等に対しての、同じ社会の一員である自分の関わりという軸を入れ込むことで、社会で構造化された問題に対する当事者意識とその是正に向けて、自分ごととして継続的に考えていくことを促す共関意識が芽生えてくるのではないか。(131ページ)
連帯から協繋へ:自分の経験とは異なる他者の差別や生きづらさに向き合い、同じではない当事者として支え合うためには、「学びひらき」と緩やかな「協繋」が求められる
社会において知らぬ間に布置されてきた自己と他者の不均衡で分断された関係性に気づき、批判的に向き合い、他者との関係性を自覚的に編み直し、より包含的で対話的な自己と他者の共生のあり方を模索する学びのあり方(プロセス)を「学びひらき」という。この学びひらきは、社会横断的な連帯につながる(136ページ)/(差別や不平等によって)分断化された状況に抗うには、多様な差別や生きづらさの経験をつないで互いの生きやすさを保証し合う在り方を模索する必要がある。(137ページ)/(それは連帯につながるが)連帯というと強い政治的あるいは苦難や利害を共有する集団の団結・結束を思い浮かべるかもしれない。しかし、今より求められているのは多様な生のあり方を肯定して、誰もが=自分も生きやすいように社会のあり方を共に変えていくことに向けた、差異を横断するしなやかな連帯である。(138ページ)/その意味ではむしろ「協繋(きょうけい)」という言い方が適切かもしれない。(中略)協繋は異なる価値観を持つ人々が、社会における不公正や不正義にともに抗うために対等な関係で関わり合うことである。(中略)少なくとも、いかなる差別に対しても理不尽でおかしいと向き合おうとすることである。(138~139ページ)
〇最後に、例によって、以上の言説を「まちづくりと市民福祉教育」に引き寄せて一言しておきたい。ひとつは、「まちづくりと市民福祉教育」の根幹にある「共感」の本質的転換についてである。「まちづくりと市民福祉教育」において、高齢者や障がい者が直面する差別や生きづらさに単に情緒的な「共感」を寄せ、抽象的に「共生」を語るだけでは不十分である。その困難を生み出している社会構造や慣習に対し、無意識のうちに自分自身も加担しているという「当事者性」の自覚こそが不可欠である。こうした「共関(共に、関わり、関心を持つ)」意識を促す教育的営為こそが、岩渕の提唱する「学びひらき」の実践に他ならない。社会構造のなかに自分自身を位置づけ直すことで、高齢者や障がい者と共に社会を変革しようとする能動的な姿勢が初めて立ち現れるのである。
〇いまひとつは、「連帯」の質的転換についてである。「まちづくりと市民福祉教育」において、これまでの連帯は往々にして等質な集団による「同質性の連帯」に留まり、排他的な側面を持っていた(同質性による排除)。また、具体的な実践を伴わないまま、抽象的・理念的に「自立と連帯」のまちづくりについて説くこと(手垢のついたスローガン)に終始してきた感は否めない。今後は、異なる背景を持つ人々が共生する「異質性の連帯」へと、その質的転換を図る必要がある。岩渕が説く「協繋」こそが、異なる価値観を持つ人々が対等に関わり合い、共に社会の不公正に抗う「まちづくり」のための基盤となるのである。