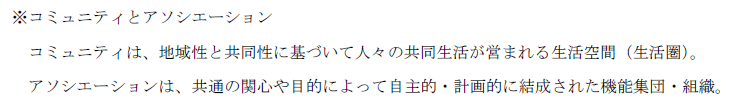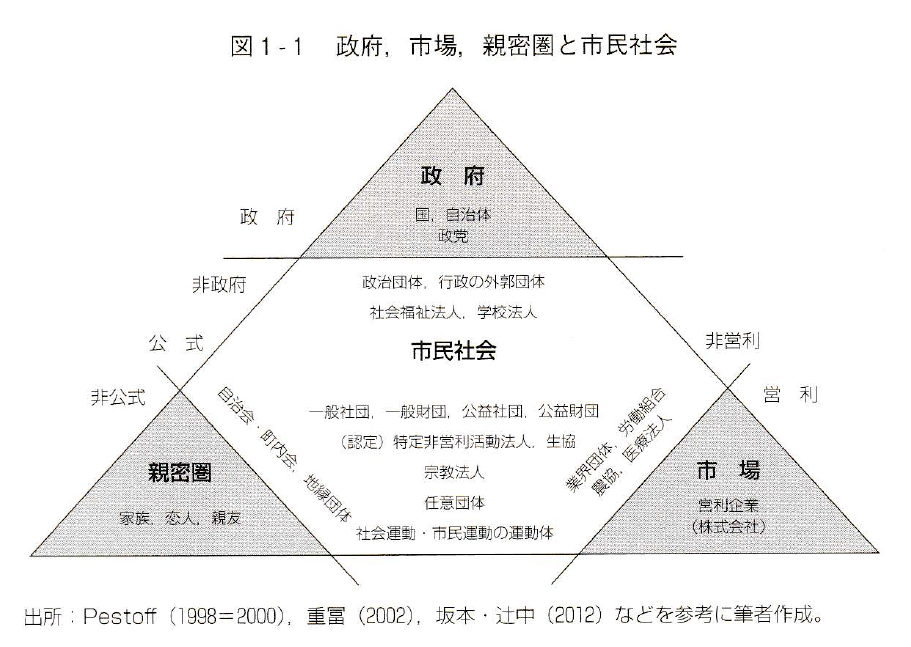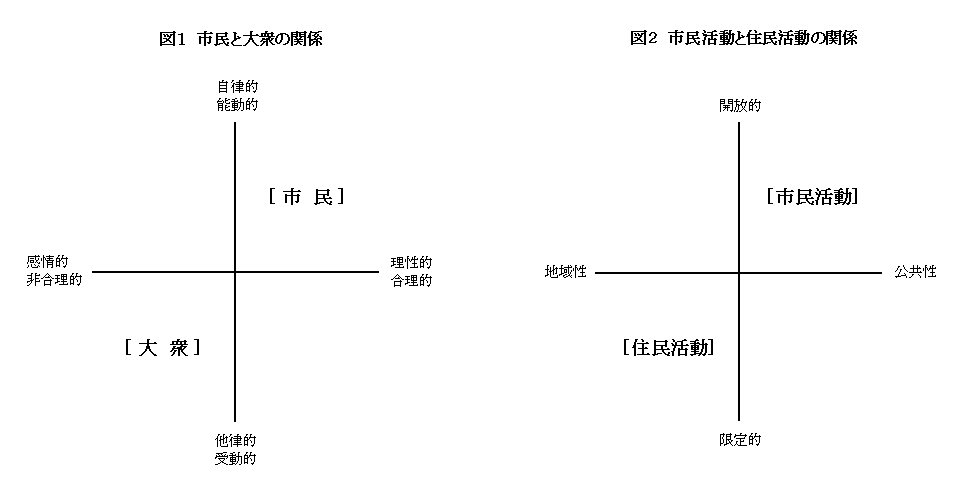『めんこいしょ』(原詩)
ぐずって 泣きそう
泣き顔がはじけ 泣き声が発せられるこの一瞬
顔を崩して こぼれる涙顔
めんこいしょ
つぶらな瞳と にらめっこ
ジッと顔を見てて 泣くかなと思ったこの一瞬
ニコッと まさかのほほえみ返し
めんこいしょ
おいでをすると ためらいがちに
ゆっくり両手を伸ばして からだを預けたこの一瞬
やわらかな 匂い立つ顔
めんこいしょ
スプーンを自分で持つと 強情(ごうじょう)はって
口のまわりに たくさん散らかすこの一瞬
してやったりと にたり顔
めんこいしょ
ことばにならない 声を出し
指さす方に 目を向かせ
おぼしきおもちゃを 差し出すこの一瞬
いやいやと かぶりをふる不満顔
めんこいしょ
素っ裸 湯船で
お湯と戯れて おいたをするこの一瞬
満面の笑みをうかべる 赤ら顔
めんこいしょ
めんこくて めんこくて
ただただ めんこくて
包み込まれる いのちのぬくもり
めんこくて めんこくて
ただただ ありがとう
包み込む 二人の深い慈しみ
いのちの限り 共に歩まん

保坂美保子『めんけなぁ』
ぐずめで べっちょかいで
なぎべっちょかいで はちけるときのこの一瞬
つらっこくずして こぼれてくる涙のつらっこ
めんけなぁ
まんまるっこい目ど にらめっこ
ジッとつらっこ見てて あや なぐべがと思ったこの一瞬
ニコッと まさがのほほえみ返し
めんこいすべ
「こ」ってへば どしたもんだべがって
ゆ~っくり両方の手っこ伸ばして 抱がさってきたこの一瞬
やわらけえ かまりっこのするつらっこ
めんけなぁ
匙(しゃじ)自分でたなぐどって じょっぱって
口のまわりさ いっぺちらがすこの一瞬
おらもでぎるんでと にったり
めんこいすべ
ことばではねんども 声っこだして
指さすほうを みれってしゃべる
これだが?って おもちゃっこやるこの一瞬
んでねんでねって 首っこふってふぐれっつら
めんけなぁ
はだがっこで 湯船さはいって
湯のながで遊んで いたずらっこするこの一瞬
ほれがおもしぇどってわらって 赤(あげ)ぇつらっこして
めんこいすべ
めんけくて めんけくて
たんだたんだ めんけくて
包み込まれる いのちのぬぐもり
めんこいすべ めんこいすべ
ただたんだ ありがでぇ
包み込む 二人の深い慈しみ
いのちのあるかぎり 共に歩いていぐべし
〔秋田県大館市比内町在住の共同研究者保坂美保子さん(一般財団法人大館市文教振興事業団大館市立栗盛記念図書館館長)〕
金澤昌子『めんけべしゃ』
ぐずって 泣ぐどご
泣き顔っこはじけで 泣き声出でくるこの一瞬
顔っこ崩れで こぼれだ涙っこ
めんけべしゃ
大きなま(・)な(・)ぐ(・)ど にらめっこ
ジッと顔見で 泣くべがと思ったこの一瞬
ニコッと まさがのほほえみ返し
めんけべしゃ
おいでってへば どだべがど
ゆっくり手っこ伸ばして 抱がさってきた この一瞬
ぽわぽわど あまいかまりの顔っこ
めんけべしゃ
匙(しゃんじ)たなぐどって 強順(ごんじょ)ぱって
顔っこ カマネゴになるこの一瞬
得意満足で にったり笑う
めんけべしゃ
ことばにならねばって 声だして
あっち見れって 手っこのべて
これがっておもちゃを とってやれば
いやいや ほれでねって頭っこふって ふくれがお
めんけべしゃ
裸っこになって 湯さ入れで
ちゃぽちゃぽ イタズラこの一瞬
にっこにこの 赤(あげ)え顔っこ
めんけべしゃ
めごくて めごくて
ただただ めごくて
包み込まれる いのちのぬくもり
めごくて めごくて
ただただ ありがとう
包み込む 二人の慈しみ
命の限り 共に行くべし
※カマネゴ:顔に食べ物をいっぱい付けた状態。地域でもほとんど使われていない様子。
※「めんこいしょ」を「めんけべしゃ」「めごいごどだなぁ」「めんこいすべ」と地域でのバリエーションも多彩。替えるとニュアンスも変わるかと(金澤)
〔秋田県大館市在住の金澤昌子(かねざわしょうこ)さん(一般財団法人大館市文教振興事業団大館市立栗盛記念図書館館司書)〕
棟方梢『めごいべぇ』
ぐずって 泣ぐべが
泣ぎそうなつらっこがら 泣ぎ声ででくるこの一瞬
つらっこくずいでまって 涙っここぼれでくる涙顔
めごいべぇ
でったらなまなぐど にらめっこ
じたっとつらばみでで 泣くべがど思ったこの一瞬
ニコッと まさがのほほえみ返し
めごいべぇ
おいでってへば どんだべがって
ゆったらど両手ば伸ばして 抱がさってきた この一瞬
やわらけぇ かまりっこするつらっこ
めごいべぇ
しゃんじばじぶんでもずって じょっぱりはって
つらっこのまわりさ いっぺつけでまるこの一瞬
すげえべぇって にたっとしたつらっこ
めごいべぇ
こどばさなねばって 声さだして
あじだって むがへで
こいだべがって思うおもちゃば とってやるこの一瞬
ちがうって あだまばふって不満だつらっこ
めごいべぇ
裸さなって 風呂っこで
湯っこで遊んで いだずらするこの一瞬
にたらっと笑っう あげえつらっこ
めごいべぇ
めごくて めごくて
たんだたんだ めごくて
包み込まいる いのちのあったかさ
めごくて めごくて
たんだたんだ ありがでな
包み込まいる 二人の深ゖ慈しみ
命の限り 一緒に行くべし
(共同研究者の青森明の星短期大学棟方梢先生。ちなみに、先生の出身地は青森県五所川原金木町、太宰治の故郷です〕
野間晴美『かいらしおすやろ?』
ぐずぐずゆうて 泣かはりまっせ
顔がはじけて 泣き声ではる とおもたとたん
顔を崩して こぼれる涙
かいらしおすやろ
つぶらなお目めと にらめっこ
じーっと顔見て 泣くやろか とおもたとたん
ニコッと まさかのほほえみ返し
かいらしぃなあ
おいないすると ちょっとためろうて
ゆっくり両のてえのばして からだをあずけはった とおもたとたん
やらかい におい立つお顔
かいらしおすやろ
スプーンをもつんやて ごんたゆうて
口のまわりに ぎょうさん散らかさはるわ とおもたとたん
ほれやったったと にたり顔
かいらしぃなあ
ことばにならへん 声だして
指さす方に 目を向かせ
おぼしきおもちゃを さしだそう とおもたとたん
ちゃうちゃうと かぶりをふって ふくれっつら
かいらしおすやろ
素っ裸 湯船で
お湯とほたえて てんごしゃはるとおもたとたん
満面の笑みをうかべる 赤ら顔
かいらしぃなあ
かいらしぃて かいらしぃて
ただただ かいらしぃて
包み込まれる いのちのぬくもり
かいらしぃて かいらしぃて
ただただ おおきにどす
包み込む 二人の深い慈しみ
いのちの限り 共に歩まん
〔共同研究者京都華頂短期大学名賀亨先生が依頼した、華頂短期大学附属幼稚園教頭野間晴美先生の作品〕
『や~らしかやろー』(佐賀弁)
ぐずー ぐずーいうて 泣くとやろうか
泣き面(つら)のうっかんげて 泣きじゃーた そん時
つらば よんごひんぐになゃーて こぼらかす涙のつらは
や~らしかやろー
こまーか めんこんたんと にらめっこ
ジーとつらば 見よっぎんた 泣くかにゃーと思うた そん時
ニコって ほほえみばかえすこんなんてん
や~らしかやろー
きんしゃい きんしゃいばすっぎ ちゃーがつかごとして
ゆっくらーと両手ばのばゃーて ごちゃあば なんかけた その時
やわらかか においのしてくっつら
や~らしかやろー
スプーンば自分で持っぎんた 強かふいして
くちんまわりい どっさい散らきゃーて そん時
どうじゃって ニタッてすっつら
や~らしかやろー
ことばにならん 声ばじゃーて
指ばさすとこば 見んしゃいて
こいかにゃーて思うごたっおもちゃば さい出す そん時
いんにゃ いんにゃ かんぶいかんぶいすっ ぶっちょうずら
や~らしかやろー
すっぱだきゃーで ふろんなかで
お湯とぞうぐいして いたずらばすっ そん時
つら中笑うたごとなって まっきゃきゃのつら
や~らしかやろー。
や~らしゅうして や~らしゅうして
ほんなごて や~らしゅうして
ひっこまるっごと いのちのぬっかった
や~らしゅうして や~らしゅうして
ほんなごってー ありがとうない!
だっこだっこすっ ふちゃあのふかーか やさしさ
いのちのあっかぎい いっしょに歩こうない!
〔友人の佐賀市社協桑原直子さんが依頼した、佐賀弁で演劇をしている方の作品〕
須々田秀美『めごいなぁ』
えへで 泣ぐんたな
泣き顔(つら)くぁして 泣ぎ声(ごえ)ば出すこのいっとぎ
顔(つら)こひしゃげで 流す涙顔(つら)こ
めごいなぁ
ちっちぇーまなごど にらめあい
じへっど顔(つら)こ見でれば 泣ぐべがど思(おも)たこのいっとぎ
にまらっと わいはのほほえみけし
めごいなぁ
こちゃこいってへば どすべがど
ゆったど両手ば伸ばし 抱(だが)さってきたこのいっとぎ
やっこして 香(かま)りっこえー顔(つら)っこ
めごいなぁ
さじば自分(ふとり)で持づど ごんぼほって
口(くぢ)のまわりば のったど散(ち)らがすこのいっとぎ
どだばど にったどして
めごいなぁ
何(なだ)がさわがね 声っこ出して
指(ゆび)っこさす方(ほ)さ 目っこ向かせ
こいだなっておもちゃば 取(と)てやたこのいっとぎ
んでねんでねって 頭(あだま)っこふるふぐれっ顔(つら)っこ
めごいなぁ
裸(はだが)っこで 湯(ゆ)こさ入って
湯(ゆ)こかまして 悪(わる)さばするこのいっとぎ
にまにまど笑う 赤(あげ)ぇ顔(つら)っこ
めごいなぁ
めごくて めごくて
たんだたんだ めごくて
包(つづ)みこまれる 命このぬぐだまり
めごくて めごくて
たんだたんだ ありがてなぁ
包(つづ)みこむ 二人(ふだり)の深(ふけ)ぇ慈しみ
命こあるうじ 一緒(いしょ)じに行くべ
〔白神山地ブナ林再生事業に取り組む日本山岳会青森支部の須々田秀美氏は、青森県平川市に在し弘前弁で表現する〕
宮城葉子『肝愛(チムガナ)さぬ』(ウチナーグチ)
肝(チム)ぬままならん 泣ちがーたー
泣顔(ナチガウ)ぬ にじら らん
泣(ナ)ち声(グィー)ーぬ出(ン)じたる
くぬ はっとぅま
顔(カウ) わじゃまち
涙(ナダ)落(ウ)とぅちゃる 顔(カウ)
肝愛(チムガナ)さぬ
目(ミ)ーまってん 目(ミ)ーぐゎーとぅ
みぃーくぅーめぇー
みぃーちきてぃ 顔(チラ)ぐゎー見(ン)ーちょうてぃ
くぬ はっとぅま
ニコッんでぃち まさかぬ
見(ミ)ーぐゎー笑(ワレェ)ー返(ゲェ)ーし
肝愛(チムガナ)さぬ
くぅーわっ! んでぃち さくとぅ
ちゃーすがやーんでぃち思(ウム)やがなー
ようーんなー たーちぬ手(ティー)
伸(ヌ)ばち 身体(ドゥー) あじきたる
くぬ はっとぅま
やふぁってん ぐゎーとぅ
かばさ だちゅる顔(カウ)
肝愛(チムガナ)さぬ
サジ 自分(ドゥー)し 持(ム)っちゃくとぅ
がーはてぃ くちぬまんまーるや
いっぺー 散(チ)らかちゃる
くぬ はっとぅま
しーやんてぃ 目(ミ)ー笑(ワレェ)ー顔(ガウ)
肝愛(チムガナ)さぬ
くぅとぅばにならん 声(クィ)ー出(ン)じゃち
指(イービ)さする とぅくるんかい
目(ミ)ー向(ン)けぇーらしみてぃ
くりやんでぃ 思(ウ)まーりーる イーリムン
取(トゥ)らちゃる くぬはっま
ンパーンパーんでぃち
頭(チブル)ふる 肝(チム)ふがん顔(ガウ)
肝愛(チムガナ)さぬ
まる裸(ハラカ) 風呂(ユフル)桶(ウゥーキ)んじ
湯(ユー)とぅ がんまり遊(アシ)びし
痛(ヤマ)ちゃる
くぬ はっとぅま
肝愛(チムガナ)さぬ
肝(チム)がなさぬ 肝(チム)がなさぬ
どぅく どぅく 肝(チム)がなさぬ
抱(だ)ちくだる
命(イヌチ)ぬ 温(ヌク)むい
肝(チム)がなさぬ 肝(チム)がなさぬ
いっぺー いっぺー ニフェードォー
抱(だ)ち込(ク)みたる 二人(タイ)ぬ母子(ファファクッ)ぬ
志情(シナサキ)ぬ深(フカ)さ 肝愛(チムガナ)さぬ
命(ヌチ)ぬあるかじり
いちまでぃん 共(トゥム)に 歩(アユ)まな
〔沖縄市在住の友人木下義宣氏の紹介で、童唄研究家の宮城葉子先生のウチナーグチ(沖縄語)での訳詩をいただいた。過去に「方言札」という「日本語の標準語激励の強硬手段としての罰札」により、貴重な言葉と文化を失った歴史があることを知った。先生は幼児教育の指導者教育に長年携わりながら、うるま市田場の古民家「沖縄のわらべ唄 民謡の里・田場ぬてぃーだぬ家-」を拠点に、現在も文化継承活動をされておられる〕
『かわえげな』(出雲弁)
ぐじって ほえそ
ほえがおがはじけ ほえごえがでてくー
このえっしゅん
かおをめぐほど ぼろけるなんだがお
かわえげな
ちぶらな瞳と にらめっこ
じっと顔をみちょって ほえーかなと思った
このえっしゅん
ねこっと まさかのほほえんがえし
かわえげな
おいでをすーと こまったげに
ゆっくー両手をのばいて からだをあじけた
このえっしゅん
やおい ねおいたつ顔
かわえげな
さじをわでもつと えじはって
口のまわーね よーけちらかす
このえっしゅん
まいことやったと おれしげに
かわえげな
ことばねならん 声だいて
指さす方に めーみかしぇ
おもったおもちゃを 差し出す
このえっしゅん
やだやだと あたまをふてぶー不満顔
かわえげな
まっぱだか いぶねで
おいとつばえて えけずすー
このえっしゅん
かおじーの笑みをうかべー まっかな顔
かわえげな
かわえげで かわえげで
ただただ かわえげで
つつんこまれー えのちのぬくもー
かわえげで かわえげで
ただただ だんだん
つつんこむ ふたーの深いえつくしん
えのちのかぎー えっしょにえかこい
〔共同研究者山本寿子先生が友人の出雲市在住の堀内クミさんに依頼し、さらに出雲弁の研究をされている方にお願いして訳していただいた〕